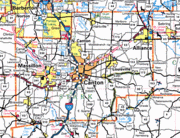|
|
|
|
コメント(217)
>しーめいさん
ウィキペディアによれば、「市内には池が数多く見られるが、これはため池や金魚の養殖池として用いられていたものである」とのことで、「金魚の養殖池」と「干ばつ防止用のため池」の両方があるようです。
金魚養殖といえば、愛知県弥富市も有名ですが、ここは大和郡山の金魚商人が東海道熱田宿へ向かう途中に金魚を休ませたことが始まりとのことで、つながりがあります。
弥富もまた、大和郡山と似たような状況です。
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35.10964212020653&lon=136.7388685090083&z=16&mode=map&pointer=on&datum=wgs&fa=ks&home=on&hlat=35.073754845085&hlon=136.75427511759&layout=&ei=utf-8&type=static&v=2
あと、観賞魚の養殖といえば、新潟県小千谷市、長岡市の錦鯉養殖が有名で、2004年の新潟県中越地震では大きな被害を受けましたが、ここもあちこちに養殖池があることが地図で分かります。
(小千谷市)
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=37.315728265378915&lon=138.8293621476003&z=16&mode=map&pointer=on&datum=wgs&fa=ks&home=on&hlat=37.29545179&hlon=138.81781792&layout=&ei=utf-8&type=static&v=2
(長岡市)
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=37.356708271694764&lon=138.84798740699966&z=16&mode=map&pointer=on&datum=wgs&fa=ks&home=on&hlat=37.3157282653789&hlon=138.8293621476003&layout=&ei=utf-8&type=static&v=2
ウィキペディアによれば、「市内には池が数多く見られるが、これはため池や金魚の養殖池として用いられていたものである」とのことで、「金魚の養殖池」と「干ばつ防止用のため池」の両方があるようです。
金魚養殖といえば、愛知県弥富市も有名ですが、ここは大和郡山の金魚商人が東海道熱田宿へ向かう途中に金魚を休ませたことが始まりとのことで、つながりがあります。
弥富もまた、大和郡山と似たような状況です。
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35.10964212020653&lon=136.7388685090083&z=16&mode=map&pointer=on&datum=wgs&fa=ks&home=on&hlat=35.073754845085&hlon=136.75427511759&layout=&ei=utf-8&type=static&v=2
あと、観賞魚の養殖といえば、新潟県小千谷市、長岡市の錦鯉養殖が有名で、2004年の新潟県中越地震では大きな被害を受けましたが、ここもあちこちに養殖池があることが地図で分かります。
(小千谷市)
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=37.315728265378915&lon=138.8293621476003&z=16&mode=map&pointer=on&datum=wgs&fa=ks&home=on&hlat=37.29545179&hlon=138.81781792&layout=&ei=utf-8&type=static&v=2
(長岡市)
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=37.356708271694764&lon=138.84798740699966&z=16&mode=map&pointer=on&datum=wgs&fa=ks&home=on&hlat=37.3157282653789&hlon=138.8293621476003&layout=&ei=utf-8&type=static&v=2
農業用のため池と言えば、香川県にも多数ありますね。
例えば、この辺り↓。
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=34.256365,134.021873&spn=0.067394,0.063515&z=13&brcurrent=3,0x3553c1c5548d47df:0x72f429d49c1ef71b,1&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=34.256365,134.021873&spn=0.067394,0.063515&z=13&brcurrent=3,0x3553c1c5548d47df:0x72f429d49c1ef71b,1&source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small>
今から20ン年前の学生時代、オートバイでツーリングに行った時に、地図を見て「なんだこりゃ?」と思いました。
降雨量が少なく、大きな川もないため、昔よりため池が多数作られて今も残っている、というのが理由だそうです。
例えば、この辺り↓。
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=34.256365,134.021873&spn=0.067394,0.063515&z=13&brcurrent=3,0x3553c1c5548d47df:0x72f429d49c1ef71b,1&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=34.256365,134.021873&spn=0.067394,0.063515&z=13&brcurrent=3,0x3553c1c5548d47df:0x72f429d49c1ef71b,1&source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small>
今から20ン年前の学生時代、オートバイでツーリングに行った時に、地図を見て「なんだこりゃ?」と思いました。
降雨量が少なく、大きな川もないため、昔よりため池が多数作られて今も残っている、というのが理由だそうです。
帰宅後に地図を見て「なんだこりゃ」と思ったルートだったのですが。
東急田園都市沿線(神奈川県)から府中(東京都)へ出かけるときのルート。
ほぼ10km真北の場所に行くのに、東急、JR、京王の乗り継ぎ、
東京都と神奈川県の県境を縫うようなルートなので、
なんと県境を越えること7回!! (長津田、橋本乗り換え)
1.JR横浜線 青葉区(神奈川)→ 町田市(東京)
2.JR横浜線 町田市 → 相模原市(神奈川)
3.京王線 相模原市 → 町田市
4.京王線 町田市 → 麻生区(神奈川)
5.京王線 麻生区 → 稲城市(東京)
6.京王線 稲城市 → 多摩区(神奈川)
7.京王線 多摩区 → 調布市(東京)
狛江や成城などへJRを使わずに遠回りして旅費を節約できますが、
これも県境を7回こえます!(中央林間、相模大野乗り換え)
1.東急線 青葉区 → 町田市
2.東急線 町田市 → 大和市(神奈川)
3.小田急線 相模原市 → 町田市
4.小田急線 町田市 → 青葉区
5.小田急線 青葉区 → 町田市
6.小田急線 町田市 → 麻生区
7.小田急線 多摩区 → 狛江市(東京)
県境を何度も横切らないといけないのは、東京都の形を魚に例えると
「腹ヒレ」に当たる町田市が出っ張っていて、しかも複雑な形の境界を
持っているためでした。
こんなところ国内の他の地域にありますか?
南北に行き来するのが面倒臭い地域ですけど、実は東急、小田急、京王、
相鉄の乗り換えって、休日の外出時だけに限れば、とても楽しんでます。
東急田園都市沿線(神奈川県)から府中(東京都)へ出かけるときのルート。
ほぼ10km真北の場所に行くのに、東急、JR、京王の乗り継ぎ、
東京都と神奈川県の県境を縫うようなルートなので、
なんと県境を越えること7回!! (長津田、橋本乗り換え)
1.JR横浜線 青葉区(神奈川)→ 町田市(東京)
2.JR横浜線 町田市 → 相模原市(神奈川)
3.京王線 相模原市 → 町田市
4.京王線 町田市 → 麻生区(神奈川)
5.京王線 麻生区 → 稲城市(東京)
6.京王線 稲城市 → 多摩区(神奈川)
7.京王線 多摩区 → 調布市(東京)
狛江や成城などへJRを使わずに遠回りして旅費を節約できますが、
これも県境を7回こえます!(中央林間、相模大野乗り換え)
1.東急線 青葉区 → 町田市
2.東急線 町田市 → 大和市(神奈川)
3.小田急線 相模原市 → 町田市
4.小田急線 町田市 → 青葉区
5.小田急線 青葉区 → 町田市
6.小田急線 町田市 → 麻生区
7.小田急線 多摩区 → 狛江市(東京)
県境を何度も横切らないといけないのは、東京都の形を魚に例えると
「腹ヒレ」に当たる町田市が出っ張っていて、しかも複雑な形の境界を
持っているためでした。
こんなところ国内の他の地域にありますか?
南北に行き来するのが面倒臭い地域ですけど、実は東急、小田急、京王、
相鉄の乗り換えって、休日の外出時だけに限れば、とても楽しんでます。
>186 碧泉さん
一旦分離して,再合併(再吸収)の例は幾つか今までにもあるようです。
たとえば
1943年・・・騎西町・種足村・高柳村・田ヶ谷村・鴻茎村が合併して騎西町に。
1946年・・・騎西町・種足村・高柳村・田ヶ谷村・鴻茎村に分離。
1954年・・・騎西町・種足村・田ヶ谷村・鴻茎村が再合併して騎西町に。
1955年・・・高柳村が騎西町に編入。
なんて例があるようです。戦時合併したものが終戦後に分離して,一息ついてから再合併,というケースが結構あるみたいですね。
鳩ヶ谷市も,前回川口市に編入されたのが1940年,分離したのが1950年なので,これに似たケースだったのかも(その割には,再合併までにだいぶ時間が掛かりましたが)。
ちょっと前に別トピックスで話題に上った小郡町なんかも,1944年に山口市編入,1949年再分離,2005年に阿知須町・秋穂町・徳地町とともに山口市に新設合併,ということなので,今回の川口市に似たパターンなのかもしれません。
合併対象の自治体にほとんど囲まれているという意味でも,鳩ヶ谷と小郡は似てますね(違うのは,小郡は交通の要所だったのに対し,鳩ヶ谷は鉄道過疎地だった事か・・・)。
一旦分離して,再合併(再吸収)の例は幾つか今までにもあるようです。
たとえば
1943年・・・騎西町・種足村・高柳村・田ヶ谷村・鴻茎村が合併して騎西町に。
1946年・・・騎西町・種足村・高柳村・田ヶ谷村・鴻茎村に分離。
1954年・・・騎西町・種足村・田ヶ谷村・鴻茎村が再合併して騎西町に。
1955年・・・高柳村が騎西町に編入。
なんて例があるようです。戦時合併したものが終戦後に分離して,一息ついてから再合併,というケースが結構あるみたいですね。
鳩ヶ谷市も,前回川口市に編入されたのが1940年,分離したのが1950年なので,これに似たケースだったのかも(その割には,再合併までにだいぶ時間が掛かりましたが)。
ちょっと前に別トピックスで話題に上った小郡町なんかも,1944年に山口市編入,1949年再分離,2005年に阿知須町・秋穂町・徳地町とともに山口市に新設合併,ということなので,今回の川口市に似たパターンなのかもしれません。
合併対象の自治体にほとんど囲まれているという意味でも,鳩ヶ谷と小郡は似てますね(違うのは,小郡は交通の要所だったのに対し,鳩ヶ谷は鉄道過疎地だった事か・・・)。
新しい話題で失礼します。
静岡県の地図を見て文字通りの「なんだこりゃなとこ」を見つけました。
静岡県の大きな川の形が「なんだこりゃ」です。
(昭文社「ニューエスト静岡県都市地図」を見ています。)
特に安部川です。
普通、川と言うのは地図上に青くて太い線が上流から河口まで
力強い一本の線で描かれるものですが、安部川の描かれ方は「異常」です。
まるで肝臓か腎臓の血管の解剖図のよう、またはしゃぶしゃぶに好都合な
霜降り肉みたいな網目状の模様が流域に広がっています。特に上流に向かって
行き止まりになっている「支流」ってどうなっているんだろう?
どこか砂地の地底から水が湧きだしたりしているのだろうか?
静岡県を五か月くらい掛けて徒歩で横断する旅行を済ませたのは半年前。
地図を見て気になっていた安部川、橋の上から見ても異常。砂地の上に
網目状に流れを形作っていて、所によっては自然に任せるわけには
行かないらしくて発電機つきのポンプで水をくみ上げては下流に流している
箇所もありました。
「自然を守る」とはどういうことか考えさせられる風景でしたが、
こんな例は他にどこにあるのでしょうか?
静岡県の地図を見て文字通りの「なんだこりゃなとこ」を見つけました。
静岡県の大きな川の形が「なんだこりゃ」です。
(昭文社「ニューエスト静岡県都市地図」を見ています。)
特に安部川です。
普通、川と言うのは地図上に青くて太い線が上流から河口まで
力強い一本の線で描かれるものですが、安部川の描かれ方は「異常」です。
まるで肝臓か腎臓の血管の解剖図のよう、またはしゃぶしゃぶに好都合な
霜降り肉みたいな網目状の模様が流域に広がっています。特に上流に向かって
行き止まりになっている「支流」ってどうなっているんだろう?
どこか砂地の地底から水が湧きだしたりしているのだろうか?
静岡県を五か月くらい掛けて徒歩で横断する旅行を済ませたのは半年前。
地図を見て気になっていた安部川、橋の上から見ても異常。砂地の上に
網目状に流れを形作っていて、所によっては自然に任せるわけには
行かないらしくて発電機つきのポンプで水をくみ上げては下流に流している
箇所もありました。
「自然を守る」とはどういうことか考えさせられる風景でしたが、
こんな例は他にどこにあるのでしょうか?
>さとし@青葉区さん
>普通、川と言うのは地図上に青くて太い線が上流から河口まで
>力強い一本の線で描かれるものですが、安部川の描かれ方は「異常」です。
>霜降り肉みたいな網目状の模様が流域に広がっています。特に上流に向かって
>行き止まりになっている「支流」ってどうなっているんだろう?
多分農業用の用水路だと思います。
グーグルの地図でも、
地図で見る限り、河川は結構川幅の広い所でも1本線で描かれているところも多数あります。
100mくらいの砂州になっている所は「胃袋」みたいになっている所もありますが、
川幅30mくらいの所も2mくらいの用水路も地図上では1本線で描かれてます。
鈴鹿市でもホンダの工場の近くの鈴鹿川から白子漁港近くまで用水路が敷かれていますが、ほとんど気づかないような見かけは溝の様な用水路も地図上では1本線です。
地図上で用水路が途切れていて、その延長戦上に再び描かれているところは地下に埋設されている場合もあります。
鈴鹿でも本田技研鈴鹿製作所=ホンダの鈴鹿工場の地下にもこの用水路が通っているそうです。
用水路があった土地に後から工場や団地などが出来た場合に埋設することもあるそうです。
このような用水路は戦前からのもので、公共工事ではなく、地元の水利組合や鈴鹿の場合は個人の方が私財を投じて建設したそうです。
その土地で稲作をしている者としては、
用水路が地上から見えないことの方が普通じゃないと感じます。
グーグルマップで
鈴市庄野郵便局
(鈴鹿市)立明生小学校
付近を見て頂くと途切れ途切れの用水路(青い線)が見ることが出来ます。
>普通、川と言うのは地図上に青くて太い線が上流から河口まで
>力強い一本の線で描かれるものですが、安部川の描かれ方は「異常」です。
>霜降り肉みたいな網目状の模様が流域に広がっています。特に上流に向かって
>行き止まりになっている「支流」ってどうなっているんだろう?
多分農業用の用水路だと思います。
グーグルの地図でも、
地図で見る限り、河川は結構川幅の広い所でも1本線で描かれているところも多数あります。
100mくらいの砂州になっている所は「胃袋」みたいになっている所もありますが、
川幅30mくらいの所も2mくらいの用水路も地図上では1本線で描かれてます。
鈴鹿市でもホンダの工場の近くの鈴鹿川から白子漁港近くまで用水路が敷かれていますが、ほとんど気づかないような見かけは溝の様な用水路も地図上では1本線です。
地図上で用水路が途切れていて、その延長戦上に再び描かれているところは地下に埋設されている場合もあります。
鈴鹿でも本田技研鈴鹿製作所=ホンダの鈴鹿工場の地下にもこの用水路が通っているそうです。
用水路があった土地に後から工場や団地などが出来た場合に埋設することもあるそうです。
このような用水路は戦前からのもので、公共工事ではなく、地元の水利組合や鈴鹿の場合は個人の方が私財を投じて建設したそうです。
その土地で稲作をしている者としては、
用水路が地上から見えないことの方が普通じゃないと感じます。
グーグルマップで
鈴市庄野郵便局
(鈴鹿市)立明生小学校
付近を見て頂くと途切れ途切れの用水路(青い線)が見ることが出来ます。
>206 森の熊さん
>201 zakaさん
コメントありがとうございます。
こちらからのお礼のコメントをせずに失礼しました。
リンクされたサイト、持っている神奈川県都市地図と東京都都市地図、
すべてチェックしました。青葉区民なのに小田急線が青葉区を通っていると
勘違いしたのは不覚です。
それにしても小田急線の線路に三回(五回?)貫通されながら駅がない
(鶴川は町田市)川崎区麻生区岡上のみなさんはどんな気持ちなんだろう?
飛び地になった経緯について検索していい記事を見つけたんだけど、
今もういちど検索したら見つかりませんでした。田園風景の残るとても
素敵な所らしいです。飛び地になった経緯は青葉区や町田市より川崎市に
親近感を持つ事情があったらしいのですが、社会科が本来苦手な私には
十分に理解できず、ここで思いだして適当なことを書くわけにもいきません。
>「京王線 町田市→麻生区(神奈川)」は、「多摩市→麻生区(神奈川)」
これもたった今、確認しました。地図を見るのも、地図を持参して外出するのも
大好きで、知ったかぶりでカキコミをするのも好きだけど、社会科のセンスが
足りないからぼろが出る、いい加減に地図を見ていること反省して出直します。
>201 zakaさん
コメントありがとうございます。
こちらからのお礼のコメントをせずに失礼しました。
リンクされたサイト、持っている神奈川県都市地図と東京都都市地図、
すべてチェックしました。青葉区民なのに小田急線が青葉区を通っていると
勘違いしたのは不覚です。
それにしても小田急線の線路に三回(五回?)貫通されながら駅がない
(鶴川は町田市)川崎区麻生区岡上のみなさんはどんな気持ちなんだろう?
飛び地になった経緯について検索していい記事を見つけたんだけど、
今もういちど検索したら見つかりませんでした。田園風景の残るとても
素敵な所らしいです。飛び地になった経緯は青葉区や町田市より川崎市に
親近感を持つ事情があったらしいのですが、社会科が本来苦手な私には
十分に理解できず、ここで思いだして適当なことを書くわけにもいきません。
>「京王線 町田市→麻生区(神奈川)」は、「多摩市→麻生区(神奈川)」
これもたった今、確認しました。地図を見るのも、地図を持参して外出するのも
大好きで、知ったかぶりでカキコミをするのも好きだけど、社会科のセンスが
足りないからぼろが出る、いい加減に地図を見ていること反省して出直します。
>205 harvestさん
地図上の用水路の描かれ方についての詳しい解説ありがとうございます。
私が地図を見て「なんだこりゃ」と思った箇所の写真をアップしました。
安部川の流れの様子、流域がほとんど砂州になっていて、川の本体は
網目のようにほぐれて砂州のあちこちに顔をだす異様な形になっています。
>204
>特に上流に向かって行き止まりになっている
これはたぶん見間違いで、砂の下を流れていた水が再び表面に流れ出して
いるのかもしれません。
静岡県では大井川、天竜川にも同じ構造の流れがあります。
「日本アルプス」からの土砂をはるばる運んできたのが堆積して
あの様な流れの形状となったのでしょうか?
台風などで増水したらどうなるのだろう?
毛細血管の様な細かい流れを描いた地図を初めから
書き直す羽目になるんじゃないかと気になります。
地図上の用水路の描かれ方についての詳しい解説ありがとうございます。
私が地図を見て「なんだこりゃ」と思った箇所の写真をアップしました。
安部川の流れの様子、流域がほとんど砂州になっていて、川の本体は
網目のようにほぐれて砂州のあちこちに顔をだす異様な形になっています。
>204
>特に上流に向かって行き止まりになっている
これはたぶん見間違いで、砂の下を流れていた水が再び表面に流れ出して
いるのかもしれません。
静岡県では大井川、天竜川にも同じ構造の流れがあります。
「日本アルプス」からの土砂をはるばる運んできたのが堆積して
あの様な流れの形状となったのでしょうか?
台風などで増水したらどうなるのだろう?
毛細血管の様な細かい流れを描いた地図を初めから
書き直す羽目になるんじゃないかと気になります。
>210 さとし@青葉区 さん
安倍川ですが,大井川・天竜川と同様,日本アルプスからの土砂に起因するものである可能性が高いかと思います。
安倍川を遡って貰えば解りますが,源流には「大谷崩れ」という有名な崩壊地形があります。
大井川・天竜川の場合は,それに加えて上流のダムで取水される水の量が多いため,本流の水量が著しく少ないという事情もあるかと思いますが。
尚,昔の安倍川の流れ方について,下記のサイトに記述があります。
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/01_kasen/01_abe/history.html
今と昔ではだいぶ流れ方が違うようです。今の安倍川は,あくまでも堤防があるからあの位置を流れているのであって,堤防がなければもっと好き勝手に流れていたと見るべきでしょうね。
それから,増水したり,川の流れが(河川敷内で)少しくらい変わったとしても,その都度地図を書き直すようなことは無いでしょうね(生活にはほとんど影響しないでしょうから)。
安倍川ですが,大井川・天竜川と同様,日本アルプスからの土砂に起因するものである可能性が高いかと思います。
安倍川を遡って貰えば解りますが,源流には「大谷崩れ」という有名な崩壊地形があります。
大井川・天竜川の場合は,それに加えて上流のダムで取水される水の量が多いため,本流の水量が著しく少ないという事情もあるかと思いますが。
尚,昔の安倍川の流れ方について,下記のサイトに記述があります。
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/01_kasen/01_abe/history.html
今と昔ではだいぶ流れ方が違うようです。今の安倍川は,あくまでも堤防があるからあの位置を流れているのであって,堤防がなければもっと好き勝手に流れていたと見るべきでしょうね。
それから,増水したり,川の流れが(河川敷内で)少しくらい変わったとしても,その都度地図を書き直すようなことは無いでしょうね(生活にはほとんど影響しないでしょうから)。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
地図が好きな人の会 更新情報
地図が好きな人の会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 89995人
- 3位
- 酒好き
- 170659人