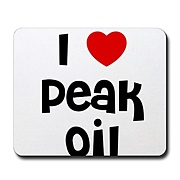2007年は、石炭ピークに関する情報が多数出現しました。
最新のレポートによると、2025年〜2030年頃がピークだろうということです。
主な原因は、
・データの更新により埋蔵量が激減した地域が出てきた
・今後採掘される石炭の熱量としての質は落ちる一方である
・最大の生産国である中国の生産量が今後急激に落ち込む可能性がある
ということのようです。
▼石炭需要は増え続けている
石炭は過去の燃料と思っている日本人は多いかもしれませんが、未だ石炭は世界のエネルギー需要の大きな部分(約27%)を占め、特に電力分野でのシェアは大きいです。発展著しい中国では約7割、インドでも半分以上のエネルギーが石炭によってまかなわれており、今後も消費量は増加し続けると考えられていて、価格もぐんぐん上昇しています。
日本では、ここ10年脱石油戦略として、火力発電用燃料の石油の割合を減らし(現在は約1割)、その分石炭や天然ガスの割合を増やして来ました。また、相次いだ原発停止をまかなう為にも石炭火力が増やされています。そのことが、京都議定書の取り決めを守れなくしている大きな原因の一つにもなっているわけですが・・・。
▼石炭はまだまだあるか
石炭は、一般にふんだんにあると考えられており、可採年数は150年とも200年とも言われています。しかし、ここ2年程で、その常識に疑問を投げかけるレポートが相次いで発表されました。(まとめ参照)
▼埋蔵量9割減
石炭の埋蔵量調査は、主に1960年代に行われて来ましたが、その後本格的な調査やデータの更新はなされて来ませんでした。
ここ数年で、一部の地域で埋蔵量の見直しが行われた結果、ドイツ、ボツワナ、イギリスでは実に埋蔵量の9割が既に無くなっていた事が明らかになりました。ポーランドなども20年で50%減少しています。同様の類推で、世界の他の炭田もまた、埋蔵量評価の下方修正の可能性が考えられます。アメリカでも、2007年に再調査の為の予算が組まれました。
▼キーは中国
一方で、最大の石炭生産国である中国では、毎年莫大な量の石炭を採掘しているのにもかかわらず、公表されている埋蔵量は1992年からまったく同じで、信用出来るデータとはとても言えません。中国の生産力のこれからが、今後の世界の石炭供給のカギを握ると考えられています。
▼熱量の質の低下
石炭と一口に言っても、その質の幅は広いです。これまで石炭と言えば比較的質のよい瀝青炭(れきせいたん、コークス、bituminous)が殆どでしたが、それらはとりやすい所から採られ、今後はより質の悪い亜瀝青炭(あれきせいたん、subbituminous coal)やリグニンの生産比率がさらに増加していくと考えられます。
熱量の評価は幅がありますが、
瀝青炭 18.8–29.3 MJ/kg
亜瀝青炭 8.3–25 MJ/kg
と言われています。
この質の低下により、重さ当たりの平均の熱量が今後ますます下がる事となり、この事が熱量で見た場合の石炭ピークを早める原因になっています。特に、中国の石炭の質については様々な予想があり、その不確定性の大きさが問題になっています。
▼ピークが来るとわかるとどのような影響があるか
これまで、石炭は際限なくあると考えていた人たちにとって、石炭供給の限界を認識することは、ある意味では大きな影響があるかもしれません。
また、ポストピークオイル時代に向けて、ふんだんにあるであろう石炭の有効利用を押し進めようとしている人たちもたくさんいます。いわゆる石炭液化技術(CTL coal-to-liquid)や石炭ガス化複合発電(IGCC)などです。彼等の未来ビジョンにも影響を与えるかも知れません。
(液化やガス化は、古くから行われていた技術であり、なぜ廃れてしまったのかという事も知らなければいけません。つまり、効率が落ちるのです。)
また、温暖化問題にも影響を与えると考える人もいます。石炭ピーク論者の主張が正しいとすると、IPCCが示す温暖化シナリオの殆どは石炭ピークやピークオイルを無視した荒唐無稽なものであって、特に今対策などしなくても供給側の制約により温暖化問題は自然に抑制されるだろうといいます。
参照)環境問題、温暖化問題とピークオイル
http://
▼資源は有限です
石炭ピーク論は、まだ出現して日が浅い事もあって、その賛否や正当性に関する議論も十分になされていない段階であると思います。世界の主な機関は、石炭生産に関する予測は2030年頃までしかしていないものが殆どで、見解の差は読み取りづらいです。
しかし、「石炭は無限のようにあるから大丈夫」とか、「石油がなくなったら次は石炭」というような、安直な考えをし続ける限り、人類は資源制約という破滅的宿命から逃れる事は出来ないでしょう。
■これまでの動き■
▼Gregson Vaux氏(エンジニア)
2004年5月25日
アメリカの石炭ピークを2032年と予測。
http://
▼Werner Zittel(LBSTの人間として)
2005年10月29日
この会合での発表によると、石炭ピークは2050年から2080年と言っている(後に変わる)。
http://
▼Jean Laherrère氏(元トタル社)
2006年10月9日
世界の石炭ピークは2050年頃と発表。彼が先鋒者か。
http://
▼J. David Hughes氏(Geological Survey of Canada)
2006年11月25日
この日に収録されたインタビュー
http://
で、"peak coal looks like it's occurred in the Lower 48 (US states)"(アメリカ南部の州では石炭ピークが来たようだ)という発言があった。詳しくはEWGの報告書を見ろと言っている。これをもって、Hughes氏を石炭ピークを最初に訴えた人物とする動きも多い。2007年10月のヒューストンで行われたASPO-USA会議では、北米の石炭ピークは1998年であったと発表している。
http://
▼Energy Watch Group (独シンクタンク)
2007年3月28日(最新版は07/7/10update)
EWGのレポートによると、石炭ピークは2025年。このレポートの中心的な人物の一人が上のZittel氏である。このレポートが多くの議論の中心的な存在。
http://
▼Dave Rutledge氏(カルフォルニア工科大)
2007年5月〜10月
独自の分析により、埋蔵量の中で実際に使える石炭の割合を計算。およそ2025年頃がピークという予想。
http://
▼Mikael Höök氏
2007年末発表
基本的な内容はEWGのレポートとかなり被っている。2030年ピークの予測。
EWGのZittel氏やSchindler氏も参加。Aleklett氏は現在のASPO(ピークオイル協会)の会長。
他にも、Institute for Energy (IFE)の二つの石炭レポート
http://
http://
や、
US National Academy of Sciencesのレポート(要約は無料で手に入る。全レポートは私が所有してますので、欲しい人はあげます。)
http://
が、埋蔵量評価に疑問を投げかけたものとして知られています。
また、これらのレポートに対し、ハインバーグ(Heinberg)氏
http://
http://
など、多くの人が記事を書いています。
最近では、
David Strahan氏の2008年1月17日
http://
の記事や、Luis de Sousa氏の2008年2月28日の記事
http://
があります。
New!!
Scienceにも乗りました。
「How Much Coal Remains」 Richard A. Kerr
Science 1420, Vol323, 13 March 2009
http://
▼主なまとめサイト
COAL - The Roundup
http://
Coal (Hubbert peak of oil production)
http://
▼写真
[写真1]
EWGレポートの石炭生産予測の上に、Laherrère、Rutledge、WEO2006(World Energy Outlook 2006 IEA国際エネルギー機関発行)の生産予測を重ねたもの。Sousa氏の記事より。
[写真2]
Höök氏のレポートより。
[写真3]
EWGのレポートより、アメリカの瀝青炭と亜瀝青炭の生産量推移。
ここまで、文責はぬりです。
◆元々のおぐおぐさんのトピ頭文◆
まずはこのトピックは作る必要はないんじゃないかと思っていましたが・・・。
●石炭戦線異常なし?
Coal prices triple as supply crisis deepens
http://
豪州産コークス用石炭のスポット価格が数日で3倍にまでなっているとのこと。石炭について、少なくともスループットの限界が起こっていることは疑う余地がありません。
最新のレポートによると、2025年〜2030年頃がピークだろうということです。
主な原因は、
・データの更新により埋蔵量が激減した地域が出てきた
・今後採掘される石炭の熱量としての質は落ちる一方である
・最大の生産国である中国の生産量が今後急激に落ち込む可能性がある
ということのようです。
▼石炭需要は増え続けている
石炭は過去の燃料と思っている日本人は多いかもしれませんが、未だ石炭は世界のエネルギー需要の大きな部分(約27%)を占め、特に電力分野でのシェアは大きいです。発展著しい中国では約7割、インドでも半分以上のエネルギーが石炭によってまかなわれており、今後も消費量は増加し続けると考えられていて、価格もぐんぐん上昇しています。
日本では、ここ10年脱石油戦略として、火力発電用燃料の石油の割合を減らし(現在は約1割)、その分石炭や天然ガスの割合を増やして来ました。また、相次いだ原発停止をまかなう為にも石炭火力が増やされています。そのことが、京都議定書の取り決めを守れなくしている大きな原因の一つにもなっているわけですが・・・。
▼石炭はまだまだあるか
石炭は、一般にふんだんにあると考えられており、可採年数は150年とも200年とも言われています。しかし、ここ2年程で、その常識に疑問を投げかけるレポートが相次いで発表されました。(まとめ参照)
▼埋蔵量9割減
石炭の埋蔵量調査は、主に1960年代に行われて来ましたが、その後本格的な調査やデータの更新はなされて来ませんでした。
ここ数年で、一部の地域で埋蔵量の見直しが行われた結果、ドイツ、ボツワナ、イギリスでは実に埋蔵量の9割が既に無くなっていた事が明らかになりました。ポーランドなども20年で50%減少しています。同様の類推で、世界の他の炭田もまた、埋蔵量評価の下方修正の可能性が考えられます。アメリカでも、2007年に再調査の為の予算が組まれました。
▼キーは中国
一方で、最大の石炭生産国である中国では、毎年莫大な量の石炭を採掘しているのにもかかわらず、公表されている埋蔵量は1992年からまったく同じで、信用出来るデータとはとても言えません。中国の生産力のこれからが、今後の世界の石炭供給のカギを握ると考えられています。
▼熱量の質の低下
石炭と一口に言っても、その質の幅は広いです。これまで石炭と言えば比較的質のよい瀝青炭(れきせいたん、コークス、bituminous)が殆どでしたが、それらはとりやすい所から採られ、今後はより質の悪い亜瀝青炭(あれきせいたん、subbituminous coal)やリグニンの生産比率がさらに増加していくと考えられます。
熱量の評価は幅がありますが、
瀝青炭 18.8–29.3 MJ/kg
亜瀝青炭 8.3–25 MJ/kg
と言われています。
この質の低下により、重さ当たりの平均の熱量が今後ますます下がる事となり、この事が熱量で見た場合の石炭ピークを早める原因になっています。特に、中国の石炭の質については様々な予想があり、その不確定性の大きさが問題になっています。
▼ピークが来るとわかるとどのような影響があるか
これまで、石炭は際限なくあると考えていた人たちにとって、石炭供給の限界を認識することは、ある意味では大きな影響があるかもしれません。
また、ポストピークオイル時代に向けて、ふんだんにあるであろう石炭の有効利用を押し進めようとしている人たちもたくさんいます。いわゆる石炭液化技術(CTL coal-to-liquid)や石炭ガス化複合発電(IGCC)などです。彼等の未来ビジョンにも影響を与えるかも知れません。
(液化やガス化は、古くから行われていた技術であり、なぜ廃れてしまったのかという事も知らなければいけません。つまり、効率が落ちるのです。)
また、温暖化問題にも影響を与えると考える人もいます。石炭ピーク論者の主張が正しいとすると、IPCCが示す温暖化シナリオの殆どは石炭ピークやピークオイルを無視した荒唐無稽なものであって、特に今対策などしなくても供給側の制約により温暖化問題は自然に抑制されるだろうといいます。
参照)環境問題、温暖化問題とピークオイル
http://
▼資源は有限です
石炭ピーク論は、まだ出現して日が浅い事もあって、その賛否や正当性に関する議論も十分になされていない段階であると思います。世界の主な機関は、石炭生産に関する予測は2030年頃までしかしていないものが殆どで、見解の差は読み取りづらいです。
しかし、「石炭は無限のようにあるから大丈夫」とか、「石油がなくなったら次は石炭」というような、安直な考えをし続ける限り、人類は資源制約という破滅的宿命から逃れる事は出来ないでしょう。
■これまでの動き■
▼Gregson Vaux氏(エンジニア)
2004年5月25日
アメリカの石炭ピークを2032年と予測。
http://
▼Werner Zittel(LBSTの人間として)
2005年10月29日
この会合での発表によると、石炭ピークは2050年から2080年と言っている(後に変わる)。
http://
▼Jean Laherrère氏(元トタル社)
2006年10月9日
世界の石炭ピークは2050年頃と発表。彼が先鋒者か。
http://
▼J. David Hughes氏(Geological Survey of Canada)
2006年11月25日
この日に収録されたインタビュー
http://
で、"peak coal looks like it's occurred in the Lower 48 (US states)"(アメリカ南部の州では石炭ピークが来たようだ)という発言があった。詳しくはEWGの報告書を見ろと言っている。これをもって、Hughes氏を石炭ピークを最初に訴えた人物とする動きも多い。2007年10月のヒューストンで行われたASPO-USA会議では、北米の石炭ピークは1998年であったと発表している。
http://
▼Energy Watch Group (独シンクタンク)
2007年3月28日(最新版は07/7/10update)
EWGのレポートによると、石炭ピークは2025年。このレポートの中心的な人物の一人が上のZittel氏である。このレポートが多くの議論の中心的な存在。
http://
▼Dave Rutledge氏(カルフォルニア工科大)
2007年5月〜10月
独自の分析により、埋蔵量の中で実際に使える石炭の割合を計算。およそ2025年頃がピークという予想。
http://
▼Mikael Höök氏
2007年末発表
基本的な内容はEWGのレポートとかなり被っている。2030年ピークの予測。
EWGのZittel氏やSchindler氏も参加。Aleklett氏は現在のASPO(ピークオイル協会)の会長。
他にも、Institute for Energy (IFE)の二つの石炭レポート
http://
http://
や、
US National Academy of Sciencesのレポート(要約は無料で手に入る。全レポートは私が所有してますので、欲しい人はあげます。)
http://
が、埋蔵量評価に疑問を投げかけたものとして知られています。
また、これらのレポートに対し、ハインバーグ(Heinberg)氏
http://
http://
など、多くの人が記事を書いています。
最近では、
David Strahan氏の2008年1月17日
http://
の記事や、Luis de Sousa氏の2008年2月28日の記事
http://
があります。
New!!
Scienceにも乗りました。
「How Much Coal Remains」 Richard A. Kerr
Science 1420, Vol323, 13 March 2009
http://
▼主なまとめサイト
COAL - The Roundup
http://
Coal (Hubbert peak of oil production)
http://
▼写真
[写真1]
EWGレポートの石炭生産予測の上に、Laherrère、Rutledge、WEO2006(World Energy Outlook 2006 IEA国際エネルギー機関発行)の生産予測を重ねたもの。Sousa氏の記事より。
[写真2]
Höök氏のレポートより。
[写真3]
EWGのレポートより、アメリカの瀝青炭と亜瀝青炭の生産量推移。
ここまで、文責はぬりです。
◆元々のおぐおぐさんのトピ頭文◆
まずはこのトピックは作る必要はないんじゃないかと思っていましたが・・・。
●石炭戦線異常なし?
Coal prices triple as supply crisis deepens
http://
豪州産コークス用石炭のスポット価格が数日で3倍にまでなっているとのこと。石炭について、少なくともスループットの限界が起こっていることは疑う余地がありません。
|
|
|
|
コメント(91)
突然ですが、ここ数年豪州からでしょう。中国は世界中の資源を買いあさってますが、豪州の石炭鉱山の買収も激しいですね。
いよいよ石炭売買の長期契約交渉時期が始まりました。一般炭は、エクストラータの妥結は80US$/t代といわれてますね。
石炭価格はリーマンショックの影響はあまり受けませんでした。リーマン直後は70US$/t弱でしたので80US$/t代は安くないです。豪州銀行アナリストによると100US$/t代も決してありえなくないといってます。これからも石炭価格は上がっていくでしょう。
ところで、石炭資源なんですが、石油・天然ガスよりは寿命的にやや有望かもしれませんが、ご多分に漏れず質は低下していますね。質、量とも維持するためにはアンダーグランドなどコストをかけていかなくてはなりません。
ご存知のように石炭採掘は大きく2つあります。オープンカット(露天掘り)とアンダーグランド(坑内堀)です。アープンカットのほうがアンダーグランドより採掘コストは安いです。アンダーグランドの重要評価指標としてストリップレシオというものがあります。これは採掘される石炭にたいして、その上部の土砂をどれくらい剥土するかというインデックスです。このストリップレシオがたかいと単位採掘石炭量あたり剥土量が高いということで、コストがかかり、メリットとしては低くなるということです。
オープンカットの鉱山は採掘していくとストリップレシオが高くなります。つまりコスト高になる。あるストリップレシオを超えるとだいたいアンダーグランドに切り替わります。
最盛期の鉱山でも昨今ストリップレシオが高くなりアンダーグランドを検討しているところも多いでしょう。
お邪魔しました。
いよいよ石炭売買の長期契約交渉時期が始まりました。一般炭は、エクストラータの妥結は80US$/t代といわれてますね。
石炭価格はリーマンショックの影響はあまり受けませんでした。リーマン直後は70US$/t弱でしたので80US$/t代は安くないです。豪州銀行アナリストによると100US$/t代も決してありえなくないといってます。これからも石炭価格は上がっていくでしょう。
ところで、石炭資源なんですが、石油・天然ガスよりは寿命的にやや有望かもしれませんが、ご多分に漏れず質は低下していますね。質、量とも維持するためにはアンダーグランドなどコストをかけていかなくてはなりません。
ご存知のように石炭採掘は大きく2つあります。オープンカット(露天掘り)とアンダーグランド(坑内堀)です。アープンカットのほうがアンダーグランドより採掘コストは安いです。アンダーグランドの重要評価指標としてストリップレシオというものがあります。これは採掘される石炭にたいして、その上部の土砂をどれくらい剥土するかというインデックスです。このストリップレシオがたかいと単位採掘石炭量あたり剥土量が高いということで、コストがかかり、メリットとしては低くなるということです。
オープンカットの鉱山は採掘していくとストリップレシオが高くなります。つまりコスト高になる。あるストリップレシオを超えるとだいたいアンダーグランドに切り替わります。
最盛期の鉱山でも昨今ストリップレシオが高くなりアンダーグランドを検討しているところも多いでしょう。
お邪魔しました。
↑ Kimチョワンさん、貴重な情報をありがとうございます!!
3月始めのニュースではございますが、、
□□□
鉄鋼原料用石炭:55%値上げで合意 製品価格に影響も 【毎日jp】
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100306k0000m020082000c.html
新日本製鉄やJFEスチールなど日本の鉄鋼大手各社と、英豪系資源大手のBHPビリトンは5日、10年4〜6月に購入する鉄鋼原料用石炭(原料炭)の価格について、09年度より55%高い1トン当たり200ドルとすることで合意した。原料炭の値上げは2年ぶり。新興国需要の増加などを反映したと見られ、自動車やデジタル家電向けなどの鋼材価格にも影響を及ぼしそうだ。
鉄鋼各社は今後、自動車や電機など大口需要先と鋼材の価格交渉に入るが、需要先は「デフレ進行で原材料の値上げを最終価格に転嫁できる状況にはない」(自動車業界幹部)と話している。
□□□
需要増を反映しての値上げということですが、質の低下も影響しているのでしょうか?気になります。
3月始めのニュースではございますが、、
□□□
鉄鋼原料用石炭:55%値上げで合意 製品価格に影響も 【毎日jp】
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100306k0000m020082000c.html
新日本製鉄やJFEスチールなど日本の鉄鋼大手各社と、英豪系資源大手のBHPビリトンは5日、10年4〜6月に購入する鉄鋼原料用石炭(原料炭)の価格について、09年度より55%高い1トン当たり200ドルとすることで合意した。原料炭の値上げは2年ぶり。新興国需要の増加などを反映したと見られ、自動車やデジタル家電向けなどの鋼材価格にも影響を及ぼしそうだ。
鉄鋼各社は今後、自動車や電機など大口需要先と鋼材の価格交渉に入るが、需要先は「デフレ進行で原材料の値上げを最終価格に転嫁できる状況にはない」(自動車業界幹部)と話している。
□□□
需要増を反映しての値上げということですが、質の低下も影響しているのでしょうか?気になります。
発電用石炭価格、98ドルで合意=エクストラータが日本の電力大手と
2010/04/02 10:19[エネルギー][時事通信社]
http://members.kankyomedia.jp/news/20100402_10274.html
【ロンドン・ロイターES=時事】スイス資源大手エクストラータは1日、日本の大手電力会社との間で、今年度の発電用石炭価格をトン当たり98ドルとすることで合意したと発表した。ロイター通信が集計した事前予想の89ドルを上回る価格となった。
同社は今回合意した電力会社名について明らかにしていないが、日本の他の顧客との交渉は続いているという。
日本の電力各社と合意した前年度の価格は70〜72ドル。
関係筋によると、エクストラータは当初100ドルかそれ以上を要求。一方、日本の電力会社は90ドル付近で確定することに期待していた。
Content above is subject to our fair use notice.
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=32531704&comment_count=0&comm_id=1322211
2010/04/02 10:19[エネルギー][時事通信社]
http://members.kankyomedia.jp/news/20100402_10274.html
【ロンドン・ロイターES=時事】スイス資源大手エクストラータは1日、日本の大手電力会社との間で、今年度の発電用石炭価格をトン当たり98ドルとすることで合意したと発表した。ロイター通信が集計した事前予想の89ドルを上回る価格となった。
同社は今回合意した電力会社名について明らかにしていないが、日本の他の顧客との交渉は続いているという。
日本の電力各社と合意した前年度の価格は70〜72ドル。
関係筋によると、エクストラータは当初100ドルかそれ以上を要求。一方、日本の電力会社は90ドル付近で確定することに期待していた。
Content above is subject to our fair use notice.
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=32531704&comment_count=0&comm_id=1322211
お邪魔します。
うるおぼえで本当に申し訳ないのですが、先週末のNEWC(豪州にある恐らく世界最大規模の石炭積出港ベースのスッポト市場)スポット価格が90USDだったですね。今年度初頭より丼で10ドルほど上がってます。
加えて、BHPとJFEの今年度契約が、なんと4半期ごととなり、石炭メジャーの思うツボになってきてますね。
強気でいられるのは、中国、インドなどの石炭需要を見込んでのことでしょう。実際、豪州でもインド向け出荷が増えております。ここ数年前はほぼありませんでしたが。
石炭価格の上昇は需要が堅調なのが主だと思いますが、コスト・品質の問題もあるかもしれませんね。
BHPやリオ、Xstrataのざっくりした戦略としては、コストがかかるが品質がよいアンダーグランドを掘って、高値で売ろうという魂胆みたいですね。逆に言うと、高くないと採算が合わなくなる。オープンカットは、徐々にいいところが減っていますし。
景気に関しては、大需要家の中国、インドがこけない限り、石炭を含む資源価格は上昇することがあっても下降は、しばらくないと思います。石炭メジャーの強気発言もしばらく止らないと思います。
お邪魔しました。
うるおぼえで本当に申し訳ないのですが、先週末のNEWC(豪州にある恐らく世界最大規模の石炭積出港ベースのスッポト市場)スポット価格が90USDだったですね。今年度初頭より丼で10ドルほど上がってます。
加えて、BHPとJFEの今年度契約が、なんと4半期ごととなり、石炭メジャーの思うツボになってきてますね。
強気でいられるのは、中国、インドなどの石炭需要を見込んでのことでしょう。実際、豪州でもインド向け出荷が増えております。ここ数年前はほぼありませんでしたが。
石炭価格の上昇は需要が堅調なのが主だと思いますが、コスト・品質の問題もあるかもしれませんね。
BHPやリオ、Xstrataのざっくりした戦略としては、コストがかかるが品質がよいアンダーグランドを掘って、高値で売ろうという魂胆みたいですね。逆に言うと、高くないと採算が合わなくなる。オープンカットは、徐々にいいところが減っていますし。
景気に関しては、大需要家の中国、インドがこけない限り、石炭を含む資源価格は上昇することがあっても下降は、しばらくないと思います。石炭メジャーの強気発言もしばらく止らないと思います。
お邪魔しました。
ぬりさん
いえいえ、です。
ストリップレシオは各鉱山の、ほぼ企業秘密です。普通個々には出ててきませんが、ざっくりいいますと、豪州だと、トラック&ショベルで5:1〜7:1、ドラッグラインだと10:1〜12:1くらいでしょうか。トラック&ショベル(T&S)とは、10〜20m3のバケットのエクスカベーターで掘削し、土塊を100t〜200t積みのダンプカーで運び出す方法。ドラッグライン(DL)とは、100m3前後のバケットがついた、巨大なクレーン−ブームが100m長さ、本体5〜6階立てのビル−です。T&Sは、小規模、炭層が複数で地質構造が複雑なところ、DLは大規模、炭層や地質構造が比較的単調なところに使われる傾向にあります。T&Sはきめが細かいのですが、ちょこまかするぶんランニングコストが高いです。一方、DLは初期投資が莫大ですが、1m3掘削あたりのランニングコストがT&Sの10分の1以下ですね。ところで、ストリップレシオ(SR)をおさらいすると、SR=石炭層上部の土塊の量(m3)÷取り出した石炭量(t)で表す、無地現数値です。ディメンションが合いませんが、なぜかこうです。石炭層が深くなるほど、上部の土塊が増えますから、SRは上昇します。ですので、大雑把に言うと、ドラッグラインで土塊除去しているところは、露天掘りでは結構限界に近づいているということがいえます。
豪州の石炭鉱山も、いいところから掘られていますから、今後開発は条件が悪いところに着手せざるを得なくなるでしょう。品質が悪くなるとか、港から遠くなるとか、環境的に厳しいところなど。一鉱山の品質低下を見るなら、もともと露天掘りやっているところがアンダーグランドに移行したことをチェックするのが一つの方法でしょうか。あと条件の悪い内陸とかに展開していることなどを着目するとか。あと、瀝青炭(Low ash)から褐炭(High ash)に手を出すことでしょうか。実際そういう傾向です。蛇足しますと、石炭の品質は、まず第一は、灰分(Ash)含有量です。石炭に含まれる生物起源ではない燃えないものです。ボイラーで燃やすと燃え残りとなるやつです。原料炭だと5-7%くらい、一般炭だと8-15%くらいですね。褐炭は20%以上でしょうか、経験的に(JIS規格ではないということです)。
石炭メジャーの戦略としては、価格を限りなくスポットに近づけたいのが本音でしょう。つまり現在は石炭価格の著しい下降はないと踏んでいて、上昇基調だから長期契約だと損する。契約タームを小刻みにして、儲けを多くしたいという作戦です。石炭メジャーのみならず石炭会社は、中国やインドの大需要を見込んでいるのと、これは私の推測ですが、将来の石油の供給不安を肌で感じていると思います。です強気発言ができるのではと思います。
長々と読みにくくてすみません。
いえいえ、です。
ストリップレシオは各鉱山の、ほぼ企業秘密です。普通個々には出ててきませんが、ざっくりいいますと、豪州だと、トラック&ショベルで5:1〜7:1、ドラッグラインだと10:1〜12:1くらいでしょうか。トラック&ショベル(T&S)とは、10〜20m3のバケットのエクスカベーターで掘削し、土塊を100t〜200t積みのダンプカーで運び出す方法。ドラッグライン(DL)とは、100m3前後のバケットがついた、巨大なクレーン−ブームが100m長さ、本体5〜6階立てのビル−です。T&Sは、小規模、炭層が複数で地質構造が複雑なところ、DLは大規模、炭層や地質構造が比較的単調なところに使われる傾向にあります。T&Sはきめが細かいのですが、ちょこまかするぶんランニングコストが高いです。一方、DLは初期投資が莫大ですが、1m3掘削あたりのランニングコストがT&Sの10分の1以下ですね。ところで、ストリップレシオ(SR)をおさらいすると、SR=石炭層上部の土塊の量(m3)÷取り出した石炭量(t)で表す、無地現数値です。ディメンションが合いませんが、なぜかこうです。石炭層が深くなるほど、上部の土塊が増えますから、SRは上昇します。ですので、大雑把に言うと、ドラッグラインで土塊除去しているところは、露天掘りでは結構限界に近づいているということがいえます。
豪州の石炭鉱山も、いいところから掘られていますから、今後開発は条件が悪いところに着手せざるを得なくなるでしょう。品質が悪くなるとか、港から遠くなるとか、環境的に厳しいところなど。一鉱山の品質低下を見るなら、もともと露天掘りやっているところがアンダーグランドに移行したことをチェックするのが一つの方法でしょうか。あと条件の悪い内陸とかに展開していることなどを着目するとか。あと、瀝青炭(Low ash)から褐炭(High ash)に手を出すことでしょうか。実際そういう傾向です。蛇足しますと、石炭の品質は、まず第一は、灰分(Ash)含有量です。石炭に含まれる生物起源ではない燃えないものです。ボイラーで燃やすと燃え残りとなるやつです。原料炭だと5-7%くらい、一般炭だと8-15%くらいですね。褐炭は20%以上でしょうか、経験的に(JIS規格ではないということです)。
石炭メジャーの戦略としては、価格を限りなくスポットに近づけたいのが本音でしょう。つまり現在は石炭価格の著しい下降はないと踏んでいて、上昇基調だから長期契約だと損する。契約タームを小刻みにして、儲けを多くしたいという作戦です。石炭メジャーのみならず石炭会社は、中国やインドの大需要を見込んでいるのと、これは私の推測ですが、将来の石油の供給不安を肌で感じていると思います。です強気発言ができるのではと思います。
長々と読みにくくてすみません。
もしかして舌足らずだったかもしれませんが、露天掘り→アンダーグランドというのは、実は昔からあります。たいていの場合、露天掘りで石炭層が深くなり取れなくなったら、つまりSRが上昇しコストが高くなったら、アンダーグランドに移行というのがいわば定石的なところがあります。ただしすべてではないです。豪州の例にとると、だいたいどこでも、あちこちで新規鉱山が立ち上がってきました。ところが最近いい場所が段々と限られてきて、また環境的な側面も厳しくなってきていますので、新規鉱山の開発スピードが徐々に小さくなってきています。一方で、需要は急激に増えていますので、品質を保ちながら、具体的に言うとLow ashなCoalを充分供給していくには、アンダーグランド(UG)突入ということになります。この流れから言って、品質の低下のバロメーターとして全鉱山におけるアンダーグランドの割合の増加というのが、品質低下を端的に表すのではと考えられます。
実は手元に資料がないので、記憶でいうと、NSW州では、いまやっているところで、UGに移行しているところは、XstrataのRavensworth、考慮中というかトライアル実施しているところは、BHPのMt.Athurその他、小規模鉱山で数箇所。QLDだと、UG移行しているのはXstrataのOaky Creek、RioのKestrelです。その他考慮中もいくつかあったと思います。
ちょっとわかりにくかったかもしれません。
また何かわかれば、思いつけば、報告します。
実は手元に資料がないので、記憶でいうと、NSW州では、いまやっているところで、UGに移行しているところは、XstrataのRavensworth、考慮中というかトライアル実施しているところは、BHPのMt.Athurその他、小規模鉱山で数箇所。QLDだと、UG移行しているのはXstrataのOaky Creek、RioのKestrelです。その他考慮中もいくつかあったと思います。
ちょっとわかりにくかったかもしれません。
また何かわかれば、思いつけば、報告します。
すいません、鉄鉱石ネタなのでトピ違いなんですが、↑の一連のトピと共通項がいくつかあるのでこちらにコメを。。
鉄鉱石価格、2倍で合意=4〜6月、今後も四半期ごと改定−鉄鋼大手 [時事通信社]
http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2010052000938
国内鉄鋼大手とブラジル、英豪の資源大手は20日までに、4〜6月期の鉄鉱石価格について、2009年度比約2倍の1トン当たり120ドル前後に値上げすることで正式合意した。また、価格改定も年度ごとの現行方式から四半期ごとに移行することで一致した。原料市況は上昇局面にあり、7〜9月期は一層の価格アップが不可避の情勢だ。
これだけ大幅な値上げは、中国の需要増や資源大手の寡占化が背景で、過去最高の水準となった。
四半期ごとの価格改定について鉄鋼側は、頻繁に鋼材価格などが動きかねないとして、3月末に4〜6月の暫定価格で合意した後も反発してきたが、最終的に資源側に押し切られた。
石炭に続き、鉄鉱石も値が上がってきました。
しかもこちらも四半期契約ということです。
鉄鉱石価格、2倍で合意=4〜6月、今後も四半期ごと改定−鉄鋼大手 [時事通信社]
http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2010052000938
国内鉄鋼大手とブラジル、英豪の資源大手は20日までに、4〜6月期の鉄鉱石価格について、2009年度比約2倍の1トン当たり120ドル前後に値上げすることで正式合意した。また、価格改定も年度ごとの現行方式から四半期ごとに移行することで一致した。原料市況は上昇局面にあり、7〜9月期は一層の価格アップが不可避の情勢だ。
これだけ大幅な値上げは、中国の需要増や資源大手の寡占化が背景で、過去最高の水準となった。
四半期ごとの価格改定について鉄鋼側は、頻繁に鋼材価格などが動きかねないとして、3月末に4〜6月の暫定価格で合意した後も反発してきたが、最終的に資源側に押し切られた。
石炭に続き、鉄鉱石も値が上がってきました。
しかもこちらも四半期契約ということです。
豪政府、資源新税の妥協案で主要鉱山会社と合意
2010年 07月 2日 09:53 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-16109520100702
[キャンベラ 2日 ロイター] オーストラリア政府は、前政権が提案し、資源業界が反発していた資源新税をめぐり、主要鉱山会社と妥協案で合意した。ギラード首相が2日、キャンベラで新しい資源税制について説明した。
前政権が提案していた「資源超過利潤税(RSPT)」を撤回し、鉄鉱石および石炭事業のみに適用する「鉱物資源利用税(MRRT)」を導入する。
また、現在はオフショアの石油・天然ガス事業に適用されている「石油資源利用税」が国内の石油・天然ガス事業に適用されることになる。
新しい鉱物資源利用税の税率は30%で、資源超過利潤税で提案されていた40%から引き下げられた。
石油資源利用税の税率は40%で変わらず。
新税制の導入日は当初提案通りの2012年7月1日になった。
豪政府が業界に譲歩した資源新税を発表したことを受けて投資家の間で安心感が広がり、豪ドルの対米ドル相場は一時0.5米セント近く急伸し、0.8579米ドルをつけた。
IGマーケッツのディーラー、クリス・ウェストン氏は資源新税について「不透明感がなくなったことで信頼感が醸成される。豪経済にとって大きな好材料だ」と語った。
英豪系資源大手のBHPビリトン(BHP.AX: 株価, 企業情報, レポート)(BLT.L: 株価, 企業情報, レポート)やリオ・ティント(RIO.L: 株価, 企業情報, レポート)(RIO.L: 株価, 企業情報, レポート)、スイス系鉱山大手エクストラータ(XTA.L: 株価, 企業情報, レポート)も共同声明を発表し、新税制に歓迎の意を表明した。
2010年 07月 2日 09:53 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-16109520100702
[キャンベラ 2日 ロイター] オーストラリア政府は、前政権が提案し、資源業界が反発していた資源新税をめぐり、主要鉱山会社と妥協案で合意した。ギラード首相が2日、キャンベラで新しい資源税制について説明した。
前政権が提案していた「資源超過利潤税(RSPT)」を撤回し、鉄鉱石および石炭事業のみに適用する「鉱物資源利用税(MRRT)」を導入する。
また、現在はオフショアの石油・天然ガス事業に適用されている「石油資源利用税」が国内の石油・天然ガス事業に適用されることになる。
新しい鉱物資源利用税の税率は30%で、資源超過利潤税で提案されていた40%から引き下げられた。
石油資源利用税の税率は40%で変わらず。
新税制の導入日は当初提案通りの2012年7月1日になった。
豪政府が業界に譲歩した資源新税を発表したことを受けて投資家の間で安心感が広がり、豪ドルの対米ドル相場は一時0.5米セント近く急伸し、0.8579米ドルをつけた。
IGマーケッツのディーラー、クリス・ウェストン氏は資源新税について「不透明感がなくなったことで信頼感が醸成される。豪経済にとって大きな好材料だ」と語った。
英豪系資源大手のBHPビリトン(BHP.AX: 株価, 企業情報, レポート)(BLT.L: 株価, 企業情報, レポート)やリオ・ティント(RIO.L: 株価, 企業情報, レポート)(RIO.L: 株価, 企業情報, レポート)、スイス系鉱山大手エクストラータ(XTA.L: 株価, 企業情報, レポート)も共同声明を発表し、新税制に歓迎の意を表明した。
国営電力、来年に異例の石炭輸入=豪から900万トン、国内調達困難に−政府も同意・インドネシア
2010/08/27 10:15[エネルギー][時事通信社]
【ジャカルタ時事】インドネシア国営電力PLNのダーラン社長は26日、2011年に同社が石炭輸入を行う計画を明らかにした。年間3000万トン規模に上る同社の石炭需要をすべて国内で確保することが困難となったため。輸入元はオーストラリア、輸入量は900万トンを想定している。国営アンタラ通信などが報じた。
インドネシアは現在、世界6位の規模となる年間約2億5000万トンの石炭を生産しているが、うち約2億トンは中国、日本、インドなどに輸出している。政府は国内向け供給を確保するため、今年から石炭生産の30%の国内供給義務(DMO)を生産者に適用する見込みとなっているが、PLNは依然として石炭確保のめどが立っておらず、異例の輸入計画が浮上した。
ダーラン社長は「われわれは電力を供給し続けなくてはならないため、国内で解決できない場合は近日中に輸入の協議を開始する」と言明。PLNは既に石炭の確保が困難に陥っており、国内の石炭生産者との交渉も不調が続いていると窮状を訴えた。
同社長はまた、「政府は石炭へのDMO導入を既に決定済みだが、解決の道がないのであれば、われわれは(石炭供給を)強要しない」と強調。輸入を通じて独自に石炭問題を解決することは十分可能との見方を示した。
同社長によれば、PLNが保有する全発電所の石炭需要は年3000万トン程度となっており、今年分の需要については既に問題ないという。
PLNは最近、天候不順を受けて各発電所の石炭備蓄を積み増すなど、石炭確保の取り組みを強めていた。今後は第1弾の発電所1万メガワット分建設プログラムで建設した石炭火力発電所が続々と稼働するため、石炭需要は急増が予想されている。
ムスタファ国務相(国営企業担当)は26日、PLNの石炭輸入計画について「悪いことではない」と容認を表明。「石炭は砂糖やコメと同じく、輸入を禁止しているわけではない」とも語った。
同相によると、政府は石炭生産者に国内供給を優先させる方針は変えておらず、DMOのコンセプトは今後も推進するものの、仮に石炭生産者のDMO順守が困難な場合は、需要家に輸入の実施を認める意向という。
◇電気料上げ、石油価格下落なら回避も
ダーラン社長はまた、国会や産業界から反対が続出している2011年の電気基本料金(TDL)15%引き上げに関し、石油燃料価格が下がり、ルピア高が進めばまだ回避できる可能性があると語った。
同社長によれば、このほかPLN発電所のガス需要がすべて満たされれば、石油燃料消費が減り、政府の補助金負担も減るため、同様にTDL引き上げを回避できる。同社長は「仮に日量3億立方フィートのガスが追加されれば、コストを12兆ルピア節減できるはずだ」と語った。
政府は11年度予算案で、PLNに供与する電力向け補助金を41兆ルピアと、10年度補正予算の55兆1000億ルピアよりも14兆1000億ルピア削減している。
2010/08/27 10:15[エネルギー][時事通信社]
【ジャカルタ時事】インドネシア国営電力PLNのダーラン社長は26日、2011年に同社が石炭輸入を行う計画を明らかにした。年間3000万トン規模に上る同社の石炭需要をすべて国内で確保することが困難となったため。輸入元はオーストラリア、輸入量は900万トンを想定している。国営アンタラ通信などが報じた。
インドネシアは現在、世界6位の規模となる年間約2億5000万トンの石炭を生産しているが、うち約2億トンは中国、日本、インドなどに輸出している。政府は国内向け供給を確保するため、今年から石炭生産の30%の国内供給義務(DMO)を生産者に適用する見込みとなっているが、PLNは依然として石炭確保のめどが立っておらず、異例の輸入計画が浮上した。
ダーラン社長は「われわれは電力を供給し続けなくてはならないため、国内で解決できない場合は近日中に輸入の協議を開始する」と言明。PLNは既に石炭の確保が困難に陥っており、国内の石炭生産者との交渉も不調が続いていると窮状を訴えた。
同社長はまた、「政府は石炭へのDMO導入を既に決定済みだが、解決の道がないのであれば、われわれは(石炭供給を)強要しない」と強調。輸入を通じて独自に石炭問題を解決することは十分可能との見方を示した。
同社長によれば、PLNが保有する全発電所の石炭需要は年3000万トン程度となっており、今年分の需要については既に問題ないという。
PLNは最近、天候不順を受けて各発電所の石炭備蓄を積み増すなど、石炭確保の取り組みを強めていた。今後は第1弾の発電所1万メガワット分建設プログラムで建設した石炭火力発電所が続々と稼働するため、石炭需要は急増が予想されている。
ムスタファ国務相(国営企業担当)は26日、PLNの石炭輸入計画について「悪いことではない」と容認を表明。「石炭は砂糖やコメと同じく、輸入を禁止しているわけではない」とも語った。
同相によると、政府は石炭生産者に国内供給を優先させる方針は変えておらず、DMOのコンセプトは今後も推進するものの、仮に石炭生産者のDMO順守が困難な場合は、需要家に輸入の実施を認める意向という。
◇電気料上げ、石油価格下落なら回避も
ダーラン社長はまた、国会や産業界から反対が続出している2011年の電気基本料金(TDL)15%引き上げに関し、石油燃料価格が下がり、ルピア高が進めばまだ回避できる可能性があると語った。
同社長によれば、このほかPLN発電所のガス需要がすべて満たされれば、石油燃料消費が減り、政府の補助金負担も減るため、同様にTDL引き上げを回避できる。同社長は「仮に日量3億立方フィートのガスが追加されれば、コストを12兆ルピア節減できるはずだ」と語った。
政府は11年度予算案で、PLNに供与する電力向け補助金を41兆ルピアと、10年度補正予算の55兆1000億ルピアよりも14兆1000億ルピア削減している。
インドの石炭埋蔵量に疑問
Doubts on Coal India’s coal reserves
By Joe Leahy in Mumbai and Amy Kazmin in New Delhi
Published: September 12 2010 18:59 | Last updated: September 12 2010 18:59
Coal India is set to begin a roadshow to promote what is expected to be India’s biggest stock listing, even as tightened environmental regulations and a Maoist insurgency threaten to render much of the state-owned miner’s reserves inaccessible.
The company’s biggest coal fields are located in remote regions dominated by Maoist rebels who often target business activities for extortion, disrupt roads and railway lines used to transport coal and are suspected of involvement in coal theft.
Moreover, the coal ministry has yet to persuade Manmohan Singh, the prime minister, to roll back an order by the environment ministry that this year designated areas covering about 40 per cent of Coal India’s reserves as “no-go areas” for mining to stop the wholesale felling of eastern forests.
“Although India has large reserves, actual production of coal has only been growing at 6-7 per cent per year,” said Arvind Mahajan, head of natural resources at KPMG.
Coal India hopes to raise up to Rs150bn ($3.2bn) from the sale of a 10 per cent stake. That would make its initial public offering bigger than India’s largest completed listing, the $3bn offering of domestic electricity producer Reliance Power in early 2008.
Coal India claims to be the world’s largest coal producer and accounts for 85 per cent of production in India, which has the fourth-largest reserves on the globe. But it recently revised down its annual production target from 520m tonnes to 486m tonnes, citing delays in environmental clearance for mine expansion. Meanwhile, Indian coal imports are surging, with KPMG estimating a domestic shortfall of 189m tonnes a year by 2015.
India’s coal ministry has urged Mr Singh to pare back the environment ministry’s designated “no-go” order to regions accounting for just 10 per cent of coal reserves. Coal India’s prospectus said the issue should be resolved in a few months through “mutual consultation”. But it said: “If we are unable to produce coal from such designated areas, estimates of our reserves could be adversely affected.” In its prospectus, Coal India admits to problems with insurgency and theft from its mines by illegal miners and others, especially in eastern regions with a heavy Maoist presence.
In spite of the problems, bankers expect a strong reception for the offering given its near monopoly status and demand from the power sector. “It just depends on the price,” said one person familiar with the deal.
Citigroup, Morgan Stanley, Kotak Mahindra Capital, Enam Securities, Deutsche Bank, and Bank of America-Merrill Lynch are managing the IPO. The offering is part of government plans to raise $8.6bn through stake sales in the fiscal year to March 2011.
Copyright The Financial Times Limited 2010. You may share using our article tools. Please don't cut articles from FT.com and redistribute by email or post to the web.
http://www.ft.com/cms/s/0/2c2f8e84-be92-11df-a755-00144feab49a.html?ftcamp=crm/email/2010913/nbe/EnergyMining/product
Doubts on Coal India’s coal reserves
By Joe Leahy in Mumbai and Amy Kazmin in New Delhi
Published: September 12 2010 18:59 | Last updated: September 12 2010 18:59
Coal India is set to begin a roadshow to promote what is expected to be India’s biggest stock listing, even as tightened environmental regulations and a Maoist insurgency threaten to render much of the state-owned miner’s reserves inaccessible.
The company’s biggest coal fields are located in remote regions dominated by Maoist rebels who often target business activities for extortion, disrupt roads and railway lines used to transport coal and are suspected of involvement in coal theft.
Moreover, the coal ministry has yet to persuade Manmohan Singh, the prime minister, to roll back an order by the environment ministry that this year designated areas covering about 40 per cent of Coal India’s reserves as “no-go areas” for mining to stop the wholesale felling of eastern forests.
“Although India has large reserves, actual production of coal has only been growing at 6-7 per cent per year,” said Arvind Mahajan, head of natural resources at KPMG.
Coal India hopes to raise up to Rs150bn ($3.2bn) from the sale of a 10 per cent stake. That would make its initial public offering bigger than India’s largest completed listing, the $3bn offering of domestic electricity producer Reliance Power in early 2008.
Coal India claims to be the world’s largest coal producer and accounts for 85 per cent of production in India, which has the fourth-largest reserves on the globe. But it recently revised down its annual production target from 520m tonnes to 486m tonnes, citing delays in environmental clearance for mine expansion. Meanwhile, Indian coal imports are surging, with KPMG estimating a domestic shortfall of 189m tonnes a year by 2015.
India’s coal ministry has urged Mr Singh to pare back the environment ministry’s designated “no-go” order to regions accounting for just 10 per cent of coal reserves. Coal India’s prospectus said the issue should be resolved in a few months through “mutual consultation”. But it said: “If we are unable to produce coal from such designated areas, estimates of our reserves could be adversely affected.” In its prospectus, Coal India admits to problems with insurgency and theft from its mines by illegal miners and others, especially in eastern regions with a heavy Maoist presence.
In spite of the problems, bankers expect a strong reception for the offering given its near monopoly status and demand from the power sector. “It just depends on the price,” said one person familiar with the deal.
Citigroup, Morgan Stanley, Kotak Mahindra Capital, Enam Securities, Deutsche Bank, and Bank of America-Merrill Lynch are managing the IPO. The offering is part of government plans to raise $8.6bn through stake sales in the fiscal year to March 2011.
Copyright The Financial Times Limited 2010. You may share using our article tools. Please don't cut articles from FT.com and redistribute by email or post to the web.
http://www.ft.com/cms/s/0/2c2f8e84-be92-11df-a755-00144feab49a.html?ftcamp=crm/email/2010913/nbe/EnergyMining/product
ついでに
中国とインドの石炭輸入が増えているという記事(ちょっとちがうけど)
Scramble for coal reaches Indonesia
By Anthony Deutsch, Amy Kazmin and Leslie Hook
Published: September 8 2010 16:52 | Last updated: September 8 2010 16:52
http://www.ft.com/cms/s/0/986dbd40-bb5f-11df-a136-00144feab49a.html
The battle for resources between India and China has arrived in Indonesia, where Asia’s emerging giants are scrambling to secure the vast supplies of thermal coal needed to fire their electricity plants and power economic expansion.
But a shortage of attractive, large-scale producers for sale and restrictive business conditions are driving fierce competition for assets in the world’s leading exporter of the commodity.
Often unable to buy mines outright, Indian and Chinese companies have secured a series of billion-dollar deals in recent months, agreeing to invest heavily in the construction of railways, power plants and ports, in exchange for coal.
Such long-term commitments show just how eager they are to buy into Indonesia.
Analysts say the model is likely to become more common as India and China aggressively try to make up a shortage of hundreds of millions of tonnes of coal in coming years. It is also a logical fit for their southern neighbour, which is trying to attract $160bn in foreign investment to revamp crumbling roads, power plants, ports and bridges.
Indonesia’s vast reserves of thermal coal are a cheap and relatively close source for Asian buyers, but government red tape, corruption and a lack of buying opportunities are hampering possible mergers and acquisitions.
Still, there has been no shortage of activity in the sector this year, as India has made strong inroads.
Adani Group, the Indian conglomerate, said in August it was investing $1.6bn to build a railway line and coal terminal in remote Sumatra. That deal, which trumped an earlier Chinese bid, will increase Adani’s Indonesian supplies, although it did not say by how much.
India’s state-controlled power generator, NTPC, the country’s largest power producer, also said it aimed to acquire stakes in two, as yet unnamed, Indonesian coal mines.
Tom Aaker, Standard Chartered’s chief executive in Indonesia, expects the “huge appetite from overseas” to drive a wave of buying in the sector in the near future.
“They are trying to build their economy ... so they are looking for a source of raw material and if they can own that source, it’s even more secure,” Mr Aaker told the Financial Times. “So, they are coming here all the time saying: ‘Do you know anyone who has a coal concession for sale, because we want to buy it’.”
中国とインドの石炭輸入が増えているという記事(ちょっとちがうけど)
Scramble for coal reaches Indonesia
By Anthony Deutsch, Amy Kazmin and Leslie Hook
Published: September 8 2010 16:52 | Last updated: September 8 2010 16:52
http://www.ft.com/cms/s/0/986dbd40-bb5f-11df-a136-00144feab49a.html
The battle for resources between India and China has arrived in Indonesia, where Asia’s emerging giants are scrambling to secure the vast supplies of thermal coal needed to fire their electricity plants and power economic expansion.
But a shortage of attractive, large-scale producers for sale and restrictive business conditions are driving fierce competition for assets in the world’s leading exporter of the commodity.
Often unable to buy mines outright, Indian and Chinese companies have secured a series of billion-dollar deals in recent months, agreeing to invest heavily in the construction of railways, power plants and ports, in exchange for coal.
Such long-term commitments show just how eager they are to buy into Indonesia.
Analysts say the model is likely to become more common as India and China aggressively try to make up a shortage of hundreds of millions of tonnes of coal in coming years. It is also a logical fit for their southern neighbour, which is trying to attract $160bn in foreign investment to revamp crumbling roads, power plants, ports and bridges.
Indonesia’s vast reserves of thermal coal are a cheap and relatively close source for Asian buyers, but government red tape, corruption and a lack of buying opportunities are hampering possible mergers and acquisitions.
Still, there has been no shortage of activity in the sector this year, as India has made strong inroads.
Adani Group, the Indian conglomerate, said in August it was investing $1.6bn to build a railway line and coal terminal in remote Sumatra. That deal, which trumped an earlier Chinese bid, will increase Adani’s Indonesian supplies, although it did not say by how much.
India’s state-controlled power generator, NTPC, the country’s largest power producer, also said it aimed to acquire stakes in two, as yet unnamed, Indonesian coal mines.
Tom Aaker, Standard Chartered’s chief executive in Indonesia, expects the “huge appetite from overseas” to drive a wave of buying in the sector in the near future.
“They are trying to build their economy ... so they are looking for a source of raw material and if they can own that source, it’s even more secure,” Mr Aaker told the Financial Times. “So, they are coming here all the time saying: ‘Do you know anyone who has a coal concession for sale, because we want to buy it’.”
And while China and India are leading the charge, Thai, Korean, Italian and Japanese companies are also on the lookout for acquisitions or coal-sourcing deals.
Churchill Mining, listed in London, is looking to sell a $1bn coal asset on Borneo and says it has received strong interest from the Indian coal majors, including Coal India, that have yet to complete any deals in Indonesia.
China became a net importer of coal in 2007 and a shift towards Indonesia followed soon thereafter. In July Shenhua, China’s largest coal producer, announced a $331m coal project in Sumatra, and last October China’s sovereign wealth fund injected $1.9bn into Bumi Resources, Indonesia’s largest coal producer.
Rather than just mine resources, China is building two 150MW power generators, which will supply the local grid. “It’s a win-win, since Shenhua gets the coal and the local economy gets the power,” says Bai Zhongyi, an analyst at UBS.
Shenhua operates power stations and railways in China, and is expanding coal production abroad with the goal of producing 15m tonnes overseas by 2015, up from none last year.
The tie-up between Bumi and China Investment Corp, the sovereign fund, was seen as a further sign of China’s interest in the sector. Bumi said it expected to sell 13m tonnes of coal to China this year. China’s coal consumption was almost half of the global total last year, according to the BP statistical review.
It is poised to overtake Japan as the largest importer of thermal coal. India, meanwhile, consumes about 7.5 per cent of global exports, but that number is set to grow. “If India ramps up and starts competing with China for resources [abroad], things could get quite heated up in terms of the price,” Mr Bai said.
Indonesia recently overtook Australia as the world’s largest supplier of thermal coal. Exports jumped fourfold between 2000 and 2010. Production was projected to rise 7 per cent to 280m tonnes in 2010, led by purchases from China, India, South Korea, Japan and Taiwan, said the Indonesian Coal Mining Association.
“The industry as a whole is gearing up for exports,” said Rudi Vann, a regional coal analyst for Wood Mackenzie, an energy consultancy, citing the recent investments in Indonesia. “We are talking about quite a lot of activity. A major chunk of it is to China and India.”
Churchill Mining, listed in London, is looking to sell a $1bn coal asset on Borneo and says it has received strong interest from the Indian coal majors, including Coal India, that have yet to complete any deals in Indonesia.
China became a net importer of coal in 2007 and a shift towards Indonesia followed soon thereafter. In July Shenhua, China’s largest coal producer, announced a $331m coal project in Sumatra, and last October China’s sovereign wealth fund injected $1.9bn into Bumi Resources, Indonesia’s largest coal producer.
Rather than just mine resources, China is building two 150MW power generators, which will supply the local grid. “It’s a win-win, since Shenhua gets the coal and the local economy gets the power,” says Bai Zhongyi, an analyst at UBS.
Shenhua operates power stations and railways in China, and is expanding coal production abroad with the goal of producing 15m tonnes overseas by 2015, up from none last year.
The tie-up between Bumi and China Investment Corp, the sovereign fund, was seen as a further sign of China’s interest in the sector. Bumi said it expected to sell 13m tonnes of coal to China this year. China’s coal consumption was almost half of the global total last year, according to the BP statistical review.
It is poised to overtake Japan as the largest importer of thermal coal. India, meanwhile, consumes about 7.5 per cent of global exports, but that number is set to grow. “If India ramps up and starts competing with China for resources [abroad], things could get quite heated up in terms of the price,” Mr Bai said.
Indonesia recently overtook Australia as the world’s largest supplier of thermal coal. Exports jumped fourfold between 2000 and 2010. Production was projected to rise 7 per cent to 280m tonnes in 2010, led by purchases from China, India, South Korea, Japan and Taiwan, said the Indonesian Coal Mining Association.
“The industry as a whole is gearing up for exports,” said Rudi Vann, a regional coal analyst for Wood Mackenzie, an energy consultancy, citing the recent investments in Indonesia. “We are talking about quite a lot of activity. A major chunk of it is to China and India.”
ナショナルジオグラフィックに、ピークコールの記事が出て、Kjell Aleklettウプサラ大教授もコメントされています。
Mining the Truth on Coal Supplies
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/09/100908-energy-peak-coal/
ウプサラ大の石炭論文
Global coal production outlooks based on a logistic model
http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/Coal_Fuel.pdf
試しに、コメントにあった、可採年数の推移をプロットし、線形近似したところ、2019年に可採年数がゼロになることがわかりました。
驚愕
Mining the Truth on Coal Supplies
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/09/100908-energy-peak-coal/
ウプサラ大の石炭論文
Global coal production outlooks based on a logistic model
http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/Coal_Fuel.pdf
試しに、コメントにあった、可採年数の推移をプロットし、線形近似したところ、2019年に可採年数がゼロになることがわかりました。
驚愕
daiさん
ツイッターは難しいです。
さて。
実は、上記サイトのコメントにあった、BP統計のR/Pという数値なんですが、最近の10年のデータは正しいのですが、90年代後半頃のデータがいまいち一致しなかたりして、よくわかりません。
BP統計上は、90年代のR/Pは180年ぐらいを推移しているように見えます。
daiさんが仰っていることが正しいとすれば、R/Pは採掘コストに逆相関するということになるのですが、なぜそのように考えられるのか、私にはすぐに理解できませんでした。
単純に考えれば、採掘コストが上がる(つまりその価格でも需要が有る)ことになれば、掘れるエリアは広がり、埋蔵量は増える方向に働くという効果もあるため、単純には言えない気がするからです。
石炭の場合、多くの国でその埋蔵量はあまりアップデートされていません。毎年採掘しているのにも関わらずです。真面目な再評価は最近ようやく行われるようになったばかりだと思います。
肝心の中国については、中間評価はでましたが、最終的な更新値はまだ発表されていません。
石油と異なり、埋蔵量データの更新がないまま、世界経済の成長で消費量がどんどん増えていった結果、単純にR/Pが減少したと考えるのが、私は順当ではないかと考えています。
グラフは、EWG(Energy Watch Group)のレポートにあった、過去の世界の石炭埋蔵量の推移です。
ツイッターは難しいです。
さて。
実は、上記サイトのコメントにあった、BP統計のR/Pという数値なんですが、最近の10年のデータは正しいのですが、90年代後半頃のデータがいまいち一致しなかたりして、よくわかりません。
BP統計上は、90年代のR/Pは180年ぐらいを推移しているように見えます。
daiさんが仰っていることが正しいとすれば、R/Pは採掘コストに逆相関するということになるのですが、なぜそのように考えられるのか、私にはすぐに理解できませんでした。
単純に考えれば、採掘コストが上がる(つまりその価格でも需要が有る)ことになれば、掘れるエリアは広がり、埋蔵量は増える方向に働くという効果もあるため、単純には言えない気がするからです。
石炭の場合、多くの国でその埋蔵量はあまりアップデートされていません。毎年採掘しているのにも関わらずです。真面目な再評価は最近ようやく行われるようになったばかりだと思います。
肝心の中国については、中間評価はでましたが、最終的な更新値はまだ発表されていません。
石油と異なり、埋蔵量データの更新がないまま、世界経済の成長で消費量がどんどん増えていった結果、単純にR/Pが減少したと考えるのが、私は順当ではないかと考えています。
グラフは、EWG(Energy Watch Group)のレポートにあった、過去の世界の石炭埋蔵量の推移です。
ぬりさん
私が言いたいのは、採掘コストではなく、探鉱コストというのかな、採掘開始(最初の1ドルの売上げが入る)までにかかるコストで、無駄足リスク含みます。かつての、石油のR/Pが40年という話については、40年分くらいの資源在庫を持つのが合理的という意味だと理解しています。R/Pの議論は適正在庫の議論と似ていると。
もっとも、関岡正弘さんにその話をしたら、探鉱はもっと山師の世界であって、そのような計画的な探鉱はできないと否定されましたが。
R/Pが180年にせよ200年以上にせよ、それは探鉱というコストをかけた結果というより、表土のすぐ下に埋まっていて以前から知られていた炭田について、深さと広さを調べて埋蔵量を推計した(たいした費用はかからないと思います)結果ではないでしょうか。
ところが坑道堀の炭田を新たに探そうとすると、油田ほど深くはないとしても、当たりをつけ、ボーリングをするのに相応のコストがかかると思います。
「埋蔵量データの更新がないまま」ということ自体、この分野で石油のような探鉱や埋蔵量推計が行われてこなかった結果ではないでしょうか。
> 石油と異なり、埋蔵量データの更新がないまま、世界経済の成長で消費量が
> どんどん増えていった結果、単純にR/Pが減少したと考えるのが、私は順当
> ではないかと考えています。
多分、ぬりさんの主張と私の主張に大きな隔たりはないだろうと思います。
「在庫」切れだとすると、ぬりさんのグラフからいえば7-8年以内にコールショックが起きて、その後探鉱コストをかけた高くて少ない石炭の時代へと相転移するかもしれません。あるいは犬谷先生さんが怖れているような、もっと激烈な変化になるかもしれません。
もし、「在庫」切れではなく、探鉱はしているけど数字をアップデートしていないだけなら、まだしばらくマイルドな変化が続くかもしれません。
ピークオイルは、それなりにその姿が見えてきているのに対して、コールショックは全く姿が見えていないショックなので、もしかすると身も凍るショック(、、、ごめん)になるのかもしれません。
私が言いたいのは、採掘コストではなく、探鉱コストというのかな、採掘開始(最初の1ドルの売上げが入る)までにかかるコストで、無駄足リスク含みます。かつての、石油のR/Pが40年という話については、40年分くらいの資源在庫を持つのが合理的という意味だと理解しています。R/Pの議論は適正在庫の議論と似ていると。
もっとも、関岡正弘さんにその話をしたら、探鉱はもっと山師の世界であって、そのような計画的な探鉱はできないと否定されましたが。
R/Pが180年にせよ200年以上にせよ、それは探鉱というコストをかけた結果というより、表土のすぐ下に埋まっていて以前から知られていた炭田について、深さと広さを調べて埋蔵量を推計した(たいした費用はかからないと思います)結果ではないでしょうか。
ところが坑道堀の炭田を新たに探そうとすると、油田ほど深くはないとしても、当たりをつけ、ボーリングをするのに相応のコストがかかると思います。
「埋蔵量データの更新がないまま」ということ自体、この分野で石油のような探鉱や埋蔵量推計が行われてこなかった結果ではないでしょうか。
> 石油と異なり、埋蔵量データの更新がないまま、世界経済の成長で消費量が
> どんどん増えていった結果、単純にR/Pが減少したと考えるのが、私は順当
> ではないかと考えています。
多分、ぬりさんの主張と私の主張に大きな隔たりはないだろうと思います。
「在庫」切れだとすると、ぬりさんのグラフからいえば7-8年以内にコールショックが起きて、その後探鉱コストをかけた高くて少ない石炭の時代へと相転移するかもしれません。あるいは犬谷先生さんが怖れているような、もっと激烈な変化になるかもしれません。
もし、「在庫」切れではなく、探鉱はしているけど数字をアップデートしていないだけなら、まだしばらくマイルドな変化が続くかもしれません。
ピークオイルは、それなりにその姿が見えてきているのに対して、コールショックは全く姿が見えていないショックなので、もしかすると身も凍るショック(、、、ごめん)になるのかもしれません。
スレ分けして、RとPについての分析を書きます。
わかりやすいように、時間次元は「年」、資源量の次元は「トン」、貨幣価値の次元は「ドル」で表記します。
[Reservation のテーゼ]
・R は、探鉱費用と強い正の相関を持つ。
・既知の露天掘り炭田に投じられた過去の探鉱費用は、資本費が問題にならないくらい小さい。
・未知の坑道堀り炭田の探鉱費用は、既知の露天掘り炭田とは桁違いに大きい。人類は、これまで無視できた石炭の探鉱にともなう資本費を議論に組み入れなければならないフェーズに遷移しつつある。
[Production のテーゼ]
・P にともなう利益は、販売量(トン/年)×{販売単価−採掘・輸送単価}(ドル/トン)−資本費(ドル/年) で概ね表記できる。
・既知の露天掘り炭田の資本コストは、上記のとおり無視できた。
・露天掘り炭田の採掘コストと比べて、坑道堀り炭田の採掘コストは桁違いに大きい。
・また探鉱堀りの場合、既知の炭田で生産量を増加させようとすると資本費の増加を招く(投資金額の増加面だけでなく、生産年数の短縮を資本費の増加で近似するという形で整理したい)。これも後述の議論でRの圧縮要因となる。
これまでは資本費が無視できたので、石炭会社は採掘・輸送コスト以上の値段で売れば利益を上げられた。
しかし、坑道堀りの時代になると、x軸を生産=販売量、y軸を利益としたときに、資本費がマイナスのy切片となり、また採掘・輸送コストの分だけグラフの傾きが小さくなる。
したがって、これまでは深く考えなくても利益を出せたが、これからは深く考えないと利益が出ない。
販売単価は、石油・天然ガスとの競争関係で上限が決まる。
その販売単価で利益が出ない場合、あるいはより多くの利益を求める場合、資本費を減らす、つまりRを減らす必要がある。
以上の考察の結果。
ガス要因はよく分からないので、さしあたりないものと仮定して。
先行して石油価格が上昇したので、それと比べて競争上不利にならないところまで石炭価格も追随して上昇する可能性が高い。
その上で、R/Pは新たな(坑道堀りを前提とした)安定点まで低下する。ただしあらかじめ安定点が決まっているわけではないので、コールショックを起こした上で、安定点が決まる。
石油も不安定要因を抱えており、ガスも安定というほどでもないので、犬谷先生さんがおそれているカタストロフが起きる可能性がゼロとは考えない。
R/Pの安定点が小さすぎる場合、それは強い不安定要因になる。
まあ、こんなことを考えた次第です。
そして、ピークオイルが問題を引き起こす前にコールショックが起きるかもしれない、という考えに至りました。
わかりやすいように、時間次元は「年」、資源量の次元は「トン」、貨幣価値の次元は「ドル」で表記します。
[Reservation のテーゼ]
・R は、探鉱費用と強い正の相関を持つ。
・既知の露天掘り炭田に投じられた過去の探鉱費用は、資本費が問題にならないくらい小さい。
・未知の坑道堀り炭田の探鉱費用は、既知の露天掘り炭田とは桁違いに大きい。人類は、これまで無視できた石炭の探鉱にともなう資本費を議論に組み入れなければならないフェーズに遷移しつつある。
[Production のテーゼ]
・P にともなう利益は、販売量(トン/年)×{販売単価−採掘・輸送単価}(ドル/トン)−資本費(ドル/年) で概ね表記できる。
・既知の露天掘り炭田の資本コストは、上記のとおり無視できた。
・露天掘り炭田の採掘コストと比べて、坑道堀り炭田の採掘コストは桁違いに大きい。
・また探鉱堀りの場合、既知の炭田で生産量を増加させようとすると資本費の増加を招く(投資金額の増加面だけでなく、生産年数の短縮を資本費の増加で近似するという形で整理したい)。これも後述の議論でRの圧縮要因となる。
これまでは資本費が無視できたので、石炭会社は採掘・輸送コスト以上の値段で売れば利益を上げられた。
しかし、坑道堀りの時代になると、x軸を生産=販売量、y軸を利益としたときに、資本費がマイナスのy切片となり、また採掘・輸送コストの分だけグラフの傾きが小さくなる。
したがって、これまでは深く考えなくても利益を出せたが、これからは深く考えないと利益が出ない。
販売単価は、石油・天然ガスとの競争関係で上限が決まる。
その販売単価で利益が出ない場合、あるいはより多くの利益を求める場合、資本費を減らす、つまりRを減らす必要がある。
以上の考察の結果。
ガス要因はよく分からないので、さしあたりないものと仮定して。
先行して石油価格が上昇したので、それと比べて競争上不利にならないところまで石炭価格も追随して上昇する可能性が高い。
その上で、R/Pは新たな(坑道堀りを前提とした)安定点まで低下する。ただしあらかじめ安定点が決まっているわけではないので、コールショックを起こした上で、安定点が決まる。
石油も不安定要因を抱えており、ガスも安定というほどでもないので、犬谷先生さんがおそれているカタストロフが起きる可能性がゼロとは考えない。
R/Pの安定点が小さすぎる場合、それは強い不安定要因になる。
まあ、こんなことを考えた次第です。
そして、ピークオイルが問題を引き起こす前にコールショックが起きるかもしれない、という考えに至りました。
daiさん
なんだか、こうしてmixiで議論するのは久しぶりで、懐かしい感じすらします。
twitterはあわただしいです。
なるほど、確かに探鉱コストは大きく違うようにも思います。
>かつての、石油のR/Pが40年という話については、40年分くらいの資源在庫を持つのが合理的という意味だと理解しています。R/Pの議論は適正在庫の議論と似ていると。
>もっとも、関岡正弘さんにその話をしたら、探鉱はもっと山師の世界であって、そのような計画的な探鉱はできないと否定されましたが。
R/Pを適正在庫の観点から議論するには、時代によっても、また石油と石炭によっても大きく事情が異なると思います。
確かに、「かつて」の石油産業にとって適正在庫としてのR/Pの維持ということは行われており、その結果平均40年が続くという現象が起きました。実際は「合理的」と考えるR/Pの数値は国毎に大きく水準は異なります(図)
関岡さんの山師という表現は、昔よりも今の方があたってますよね。現在石油探鉱は千三つと言われていますから。それでも、地下構造からある程度の発見確立は統計上わかるので、いまのところ埋蔵量をキープできるわけです。
また、逆に発見しても埋蔵量のちゃんとした見積もりをするまではその会社の保有埋蔵量にカウントしませんので、ある程度大きなものを発見した場合でも、小出しにして温存し、企業のR/Pが一定になるようなインセンティブが働いていると思います。
探鉱コストの件など、いろいろ私なりの細かい見解もあるのですが、煩雑になりそうなのでやめます。
一番言いたいのは、エネルギーとしての意味合いの石油と石炭のギャップです。
石炭はそのほとんどが産炭国内で消費されており、流通に回っているのはオーストラリアやカナダ、インドネシア等の一部の国においてのみです。
そのような事情と、基幹エネルギーとしての位置づけから、米、中国、インド等の大石炭消費国では、石炭資源の管理は歴史的に他のエネルギーと切り離されて、国の強い管理の元にあり、かなり特殊です。埋蔵量の情報も、対外的に公開する意味合いは、単純に政治的なものにすぎなくなります。海外からの投資をはじめから期待していませんので。
ま、そんなところです。
相変わらずのヤーギン。WSJ有料記事です。
○「石炭には未来がある」3つの理由
http://bit.ly/cZZcuD
「石炭は未来の燃料でもある」。エネルギー専門家のダニエル・ヤーギン氏は石炭がこの先20年間は世界の発電所における燃料の第一位
の座を守るとみている。太陽光などによる発電量も割合としては増加しているが、絶対量としては依然極めて少ない。
なんだか、こうしてmixiで議論するのは久しぶりで、懐かしい感じすらします。
twitterはあわただしいです。
なるほど、確かに探鉱コストは大きく違うようにも思います。
>かつての、石油のR/Pが40年という話については、40年分くらいの資源在庫を持つのが合理的という意味だと理解しています。R/Pの議論は適正在庫の議論と似ていると。
>もっとも、関岡正弘さんにその話をしたら、探鉱はもっと山師の世界であって、そのような計画的な探鉱はできないと否定されましたが。
R/Pを適正在庫の観点から議論するには、時代によっても、また石油と石炭によっても大きく事情が異なると思います。
確かに、「かつて」の石油産業にとって適正在庫としてのR/Pの維持ということは行われており、その結果平均40年が続くという現象が起きました。実際は「合理的」と考えるR/Pの数値は国毎に大きく水準は異なります(図)
関岡さんの山師という表現は、昔よりも今の方があたってますよね。現在石油探鉱は千三つと言われていますから。それでも、地下構造からある程度の発見確立は統計上わかるので、いまのところ埋蔵量をキープできるわけです。
また、逆に発見しても埋蔵量のちゃんとした見積もりをするまではその会社の保有埋蔵量にカウントしませんので、ある程度大きなものを発見した場合でも、小出しにして温存し、企業のR/Pが一定になるようなインセンティブが働いていると思います。
探鉱コストの件など、いろいろ私なりの細かい見解もあるのですが、煩雑になりそうなのでやめます。
一番言いたいのは、エネルギーとしての意味合いの石油と石炭のギャップです。
石炭はそのほとんどが産炭国内で消費されており、流通に回っているのはオーストラリアやカナダ、インドネシア等の一部の国においてのみです。
そのような事情と、基幹エネルギーとしての位置づけから、米、中国、インド等の大石炭消費国では、石炭資源の管理は歴史的に他のエネルギーと切り離されて、国の強い管理の元にあり、かなり特殊です。埋蔵量の情報も、対外的に公開する意味合いは、単純に政治的なものにすぎなくなります。海外からの投資をはじめから期待していませんので。
ま、そんなところです。
相変わらずのヤーギン。WSJ有料記事です。
○「石炭には未来がある」3つの理由
http://bit.ly/cZZcuD
「石炭は未来の燃料でもある」。エネルギー専門家のダニエル・ヤーギン氏は石炭がこの先20年間は世界の発電所における燃料の第一位
の座を守るとみている。太陽光などによる発電量も割合としては増加しているが、絶対量としては依然極めて少ない。
中国政府、ピーク・コールを懸念して石炭生産の制限を検討
2010年 11月 17日 16:14 JST
http://jp.wsj.com/World/China/node_149623
China's Coal Crisis
By DAVID WINNING
SYDNEY―The idea of peak oil―the point at which global production reaches its maximum―has fixated the energy industry for years. Now, China is grappling with a new worry: peak coal.
State-run media reported that Beijing is considering capping domestic coal output in the 2011-2015 period, partly because officials worry miners are running down reserves too quickly to meet the needs of a rapidly expanding economy.
"China accounts for around 14% of global coal reserves but its share of global coal consumption is already over triple that at 47%, which is unsustainable," Hong Kong-based brokerage CLSA Asia-Pacific Markets said in a report last month.
Imposing a cap would be significant as China's mining sector is already finding it hard to keep up with domestic coal demand, which has grown around 10% annually over the past decade.
Its net coal imports exceeded 106 million metric tons in the first nine months of the year―higher than the level for 2009 as a whole―and state companies have been aggressively acquiring overseas coal assets to secure long-term supply.
In the three years to September 2010, Chinese companies spent $20.96 billion on overseas coal-sector acquisitions, according to Dealogic.
An output ceiling would also underpin regional coal prices, which are near six-month highs on expectations that China will import record volumes of coal this month and in December.
While China hasn't declared publicly it will impose a coal production cap, the idea is gathering momentum.
Zhang Guobao, head of China's National Energy Administration, said in a speech on Oct. 27 that he doesn't favor the country's coal output expanding above four billion tons a year.
Policy makers are mulling an annual cap of between 3.6 billion tons and 3.8 billion tons in the next five-year plan, running from 2011 to 2015, the state-run Xinhua news agency reported earlier.
This would be unlikely to hurt large state-owned miners, such as China Shenhua Energy Co., as they have invested in modern equipment and can generate economies of scale. Shenhua aims to double its annual coal output capacity to 400 million tons in the 2009-2014 period.
2010年 11月 17日 16:14 JST
http://jp.wsj.com/World/China/node_149623
China's Coal Crisis
By DAVID WINNING
SYDNEY―The idea of peak oil―the point at which global production reaches its maximum―has fixated the energy industry for years. Now, China is grappling with a new worry: peak coal.
State-run media reported that Beijing is considering capping domestic coal output in the 2011-2015 period, partly because officials worry miners are running down reserves too quickly to meet the needs of a rapidly expanding economy.
"China accounts for around 14% of global coal reserves but its share of global coal consumption is already over triple that at 47%, which is unsustainable," Hong Kong-based brokerage CLSA Asia-Pacific Markets said in a report last month.
Imposing a cap would be significant as China's mining sector is already finding it hard to keep up with domestic coal demand, which has grown around 10% annually over the past decade.
Its net coal imports exceeded 106 million metric tons in the first nine months of the year―higher than the level for 2009 as a whole―and state companies have been aggressively acquiring overseas coal assets to secure long-term supply.
In the three years to September 2010, Chinese companies spent $20.96 billion on overseas coal-sector acquisitions, according to Dealogic.
An output ceiling would also underpin regional coal prices, which are near six-month highs on expectations that China will import record volumes of coal this month and in December.
While China hasn't declared publicly it will impose a coal production cap, the idea is gathering momentum.
Zhang Guobao, head of China's National Energy Administration, said in a speech on Oct. 27 that he doesn't favor the country's coal output expanding above four billion tons a year.
Policy makers are mulling an annual cap of between 3.6 billion tons and 3.8 billion tons in the next five-year plan, running from 2011 to 2015, the state-run Xinhua news agency reported earlier.
This would be unlikely to hurt large state-owned miners, such as China Shenhua Energy Co., as they have invested in modern equipment and can generate economies of scale. Shenhua aims to double its annual coal output capacity to 400 million tons in the 2009-2014 period.
However, small mines and township operations will be under increasing pressure. Shanxi province has closed scores of small mines in a bid to improve safety and efficiency, and Inner Mongolia region and Henan province are taking similar steps.
Even if no official limits are introduced, China can't keep growing coal output much beyond another decade, analysts say. The mining sector is constrained by chronic infrastructure bottlenecks, especially road and rail, and those coal deposits that are easiest to mine have already been tapped.
Experts are starting to predict when China's coal reserves will run out―a nightmare scenario in a country where 70% of its energy is derived from coal.
According to BP PLC, China can only continue at current rates of production for 38 years before its coal reserves are exhausted. That compares with 245 years in the U.S., and 105 years in India.
BP estimates that China had 114.5 billion tons of proven coal reserves at the end of 2009, ranking it third behind the U.S. and Russia. The International Energy Agency says China could have as much as 189 billion tons of coal that it hasn't tapped yet.
Calculating the size of China's coal reserves isn't easy. The government doesn't publish data on discoveries or how much coal can still be recovered from existing mines. Complicating matters further, China's National Bureau of Statistics recently stopped issuing monthly output figures.
In addition, not all coal has the same energy content. That's significant as many new discoveries in Inner Mongolia are of poorer quality than the coal reserves being depleted in Shanxi.
But the strength of China's coal demand, and moves by miners to raise output in step, is worrying the market as well as Beijing.
Even if China's annual coal demand growth halved to 5% then the country would run out of coal in 21 years unless it finds material new deposits, CLSA says, using 114.5 billion tons of reserves as a benchmark.
The picture isn't much brighter when calculations use IEA estimates of China's proven reserves. Annual consumption growth of 5% would see China run out of coal in 28 years, it forecasts.
"With either estimate, it is clear that the rapid increase of coal production puts China's energy security at risk," CLSA says.
Write to David Winning at david.winning@dowjones.com
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704312504575617810380509880.html
Even if no official limits are introduced, China can't keep growing coal output much beyond another decade, analysts say. The mining sector is constrained by chronic infrastructure bottlenecks, especially road and rail, and those coal deposits that are easiest to mine have already been tapped.
Experts are starting to predict when China's coal reserves will run out―a nightmare scenario in a country where 70% of its energy is derived from coal.
According to BP PLC, China can only continue at current rates of production for 38 years before its coal reserves are exhausted. That compares with 245 years in the U.S., and 105 years in India.
BP estimates that China had 114.5 billion tons of proven coal reserves at the end of 2009, ranking it third behind the U.S. and Russia. The International Energy Agency says China could have as much as 189 billion tons of coal that it hasn't tapped yet.
Calculating the size of China's coal reserves isn't easy. The government doesn't publish data on discoveries or how much coal can still be recovered from existing mines. Complicating matters further, China's National Bureau of Statistics recently stopped issuing monthly output figures.
In addition, not all coal has the same energy content. That's significant as many new discoveries in Inner Mongolia are of poorer quality than the coal reserves being depleted in Shanxi.
But the strength of China's coal demand, and moves by miners to raise output in step, is worrying the market as well as Beijing.
Even if China's annual coal demand growth halved to 5% then the country would run out of coal in 21 years unless it finds material new deposits, CLSA says, using 114.5 billion tons of reserves as a benchmark.
The picture isn't much brighter when calculations use IEA estimates of China's proven reserves. Annual consumption growth of 5% would see China run out of coal in 28 years, it forecasts.
"With either estimate, it is clear that the rapid increase of coal production puts China's energy security at risk," CLSA says.
Write to David Winning at david.winning@dowjones.com
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704312504575617810380509880.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ピークオイル 更新情報
ピークオイルのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 89995人
- 3位
- 酒好き
- 170658人