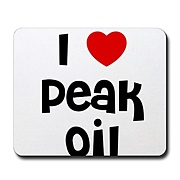|
|
|
|
コメント(201)
NERAが珍しく原子力の話を書いている。
「原子力発電プロジェクトのリスク評価」
3月12日、地球温暖化対策基本法案が閣議決定されました。地球環境の保全と、雇用機会の拡大を見込んだ新産業の創出を両立し、地球効果ガス(GHG)の排出を削減しながら持続可能な経済社会を実現することを目的としています。この手段として「原子力発電の推進」が盛り込まれたのが特徴のひとつです。
国際原子力機関(IAEA)は2030年の原子力発電能力見通しを上方修正し、現在の370ギガワットから810ギガワットに急増するとの見解を示しています。二酸化炭素を排出しないエネルギーとして原子力発電が再評価されており、日本国内の電力需要が今後大きな伸びが見込めない現在、海外市場におけるプロジェクト開拓の必要性が高まっています。
日本は原子力発電実績(基数、出力容量)の面でも安全技術水準の面でも国際的に高い水準にありながら、近年の海外プロジェクトの受注ではフランスや韓国などの攻勢に苦戦が続いています。経済産業省は3月29日に海外原子力案件の受注獲得に向けた新会社設立の方針を示しており、今後官民一体での日本の原子力分野での国際競争力の強化が期待されています。
巨額な投資を伴い、受注から建設、稼動まで長期に渡る原子力プラントプロジェクトにおいては、プロジェクトの成否に影響を及ぼす多様なリスクが内在しています。具体的には、(1)規制:国及び地方の原子力安全規制や二酸化炭素・環境関連の規制等に係るリスク、(2)市場:長期的に変動する需給バランスや競合するエネルギー価格の動向に影響される採算性リスク、(3)調達:資材や建設労働力等を提供する関連企業の対応能力やプロジェクトとしてそれら生産要素を確保できる調達リスク(例えば、労働に係るリスクは建設の直接費用だけでなく、工程管理にも影響し追加コストの発生にもつながります)、そして(4)価格:構造用鋼や鉄筋等の資材の価格高騰リスク等があげられます。
原子力プラント建設プロジェクトに参画する企業、投資家及び政府機関は、これら多様なリスク要因を事前に特定、包括的かつ定量的に分析し、リスク回避・低減策を策定することが必要となります。また工程の要所では適切かつ迅速に意思決定を行い、リスクを管理することが重要です。
中野 八英
http://www.nera.jp/Update/update_1004.html#energy
「原子力発電プロジェクトのリスク評価」
3月12日、地球温暖化対策基本法案が閣議決定されました。地球環境の保全と、雇用機会の拡大を見込んだ新産業の創出を両立し、地球効果ガス(GHG)の排出を削減しながら持続可能な経済社会を実現することを目的としています。この手段として「原子力発電の推進」が盛り込まれたのが特徴のひとつです。
国際原子力機関(IAEA)は2030年の原子力発電能力見通しを上方修正し、現在の370ギガワットから810ギガワットに急増するとの見解を示しています。二酸化炭素を排出しないエネルギーとして原子力発電が再評価されており、日本国内の電力需要が今後大きな伸びが見込めない現在、海外市場におけるプロジェクト開拓の必要性が高まっています。
日本は原子力発電実績(基数、出力容量)の面でも安全技術水準の面でも国際的に高い水準にありながら、近年の海外プロジェクトの受注ではフランスや韓国などの攻勢に苦戦が続いています。経済産業省は3月29日に海外原子力案件の受注獲得に向けた新会社設立の方針を示しており、今後官民一体での日本の原子力分野での国際競争力の強化が期待されています。
巨額な投資を伴い、受注から建設、稼動まで長期に渡る原子力プラントプロジェクトにおいては、プロジェクトの成否に影響を及ぼす多様なリスクが内在しています。具体的には、(1)規制:国及び地方の原子力安全規制や二酸化炭素・環境関連の規制等に係るリスク、(2)市場:長期的に変動する需給バランスや競合するエネルギー価格の動向に影響される採算性リスク、(3)調達:資材や建設労働力等を提供する関連企業の対応能力やプロジェクトとしてそれら生産要素を確保できる調達リスク(例えば、労働に係るリスクは建設の直接費用だけでなく、工程管理にも影響し追加コストの発生にもつながります)、そして(4)価格:構造用鋼や鉄筋等の資材の価格高騰リスク等があげられます。
原子力プラント建設プロジェクトに参画する企業、投資家及び政府機関は、これら多様なリスク要因を事前に特定、包括的かつ定量的に分析し、リスク回避・低減策を策定することが必要となります。また工程の要所では適切かつ迅速に意思決定を行い、リスクを管理することが重要です。
中野 八英
http://www.nera.jp/Update/update_1004.html#energy
北朝鮮、核融合反応技術に成功と主張(笑) 労働新聞 http://bit.ly/cYwcss
北朝鮮、核融合反応技術に成功と主張 労働新聞
ソウル(CNN) 北朝鮮の朝鮮中央通信は12日、北朝鮮の科学者が核融合反応の技術に成功したと報じた。朝鮮労働党機関紙、労働新聞の記事を引用して伝えた。同紙は核融合反応について「人工太陽の技術」と形容、人類が望んでいた新たなエネルギーの開発であるとも報じた。
故金日成(キム・イルソン)主席の誕生日に当たる今年4月15日に成功したとしている。どのような施設で成功したのかは不明。
太陽や星のエネルギー源といわれる核融合反応は核開発技術の究極的な目標とされ、長期的に安価なエネルギー源となるため、世界でも研究が進められている。ただ、この技術開発で安定した成果を獲得した国はないのが実情となっている。核融合は水爆のエネルギー源にもなる。
核融合反応の成功が事実なら、北朝鮮にとっては極めて大きな成功ともなるが、韓国の安全保障問題の専門家は成功を伝えたのが労働新聞である点に注目し、北朝鮮の現体制強化を狙った報道の可能性があると指摘。技術的な成果に関する報道は割り引いて受け止めた方が良いとの見方を示した。
また、世界の紛争解決策を研究、提言する非政府組織「国際危機グループ」(ICG)の韓国代表は、北朝鮮が核融合反応技術で世界の核大国に先駆けて成果を挙げるとは考えられないとも述べている。
北朝鮮は現在、核開発問題で米国などと厳しく対立、事態打開を目指す6者協議も停滞している。
北朝鮮、核融合反応技術に成功と主張 労働新聞
ソウル(CNN) 北朝鮮の朝鮮中央通信は12日、北朝鮮の科学者が核融合反応の技術に成功したと報じた。朝鮮労働党機関紙、労働新聞の記事を引用して伝えた。同紙は核融合反応について「人工太陽の技術」と形容、人類が望んでいた新たなエネルギーの開発であるとも報じた。
故金日成(キム・イルソン)主席の誕生日に当たる今年4月15日に成功したとしている。どのような施設で成功したのかは不明。
太陽や星のエネルギー源といわれる核融合反応は核開発技術の究極的な目標とされ、長期的に安価なエネルギー源となるため、世界でも研究が進められている。ただ、この技術開発で安定した成果を獲得した国はないのが実情となっている。核融合は水爆のエネルギー源にもなる。
核融合反応の成功が事実なら、北朝鮮にとっては極めて大きな成功ともなるが、韓国の安全保障問題の専門家は成功を伝えたのが労働新聞である点に注目し、北朝鮮の現体制強化を狙った報道の可能性があると指摘。技術的な成果に関する報道は割り引いて受け止めた方が良いとの見方を示した。
また、世界の紛争解決策を研究、提言する非政府組織「国際危機グループ」(ICG)の韓国代表は、北朝鮮が核融合反応技術で世界の核大国に先駆けて成果を挙げるとは考えられないとも述べている。
北朝鮮は現在、核開発問題で米国などと厳しく対立、事態打開を目指す6者協議も停滞している。
daiさん
「そこそこの密度」の程度によりますね。電子レンジでもプラズマはカンタンに作れますし。
技術的にはその程度ですが、これは極めて政治的なニュースだったと思います。
さて、
脱原発、30年ぶりに転換 スウェーデン、建設法案可決
http://www.asahi.com/eco/TKY201006180562.html
2010年6月18日23時24分
【ロンドン=土佐茂生】スウェーデン議会は17日、脱原発を目指す政策を30年ぶりに転換し、古くなった原発を建て直すことを認める法案を賛成174票、反対172票のわずかな差で可決した。
スウェーデンは1980年の国民投票の結果を受け、原発を2010年までに全廃する方針を決めた。これまで2基を閉鎖し、現在は10基が残るが、昨年2月に政府は脱原発方針の転換を表明。国会で同じ場所での建て替えを認める法案を審議していた。
ロイター通信によると、中道右派政権のカールグレン環境相は「地球温暖化問題に加え、メキシコ湾の原油流出事故が起きた。石油への依存度を減らさなければならない」と語った。
ただ、9月に総選挙を控えており、中道左派の社会民主労働党は「選挙に勝利すれば同法は廃止する」と主張。選挙戦の争点になるのは必至の情勢だ。
欧州では1986年にチェルノブイリ原発事故が起きて以来、脱原発の流れができてきたが、地球温暖化問題が持ち上がったことで英国、イタリア、フィンランドなどが温室効果ガスを出さない原発の建設推進を強めている。
☆
スウェーデン、フィンランドは既に処分場を決めてますから、その分気が楽ですな。
「そこそこの密度」の程度によりますね。電子レンジでもプラズマはカンタンに作れますし。
技術的にはその程度ですが、これは極めて政治的なニュースだったと思います。
さて、
脱原発、30年ぶりに転換 スウェーデン、建設法案可決
http://www.asahi.com/eco/TKY201006180562.html
2010年6月18日23時24分
【ロンドン=土佐茂生】スウェーデン議会は17日、脱原発を目指す政策を30年ぶりに転換し、古くなった原発を建て直すことを認める法案を賛成174票、反対172票のわずかな差で可決した。
スウェーデンは1980年の国民投票の結果を受け、原発を2010年までに全廃する方針を決めた。これまで2基を閉鎖し、現在は10基が残るが、昨年2月に政府は脱原発方針の転換を表明。国会で同じ場所での建て替えを認める法案を審議していた。
ロイター通信によると、中道右派政権のカールグレン環境相は「地球温暖化問題に加え、メキシコ湾の原油流出事故が起きた。石油への依存度を減らさなければならない」と語った。
ただ、9月に総選挙を控えており、中道左派の社会民主労働党は「選挙に勝利すれば同法は廃止する」と主張。選挙戦の争点になるのは必至の情勢だ。
欧州では1986年にチェルノブイリ原発事故が起きて以来、脱原発の流れができてきたが、地球温暖化問題が持ち上がったことで英国、イタリア、フィンランドなどが温室効果ガスを出さない原発の建設推進を強めている。
☆
スウェーデン、フィンランドは既に処分場を決めてますから、その分気が楽ですな。
ぬりさん
私個人の考えは原子力の全廃にあることは何度も書いていますが、それとは別に、政治的リアリティーという点で日本の政策決定に大きな問題があると考えています。
スウェーデンの場合、原発をゼロに向って減少させるという方針を打ち出した後、それを可能にするエネルギー需給構造を作ろうとしたけれど、思ったより時間がかかっているので、まずは廃炉のペースを落とす決定をし、次に今回の決定になったのだと思います。とはいえ各論はこれからでしょうから、今後の計画に何を盛り込むかをウオッチする必要があります。
日本の場合、現実問題として新設がなく、増設にも計画から竣工まで相当な年数がかかっていること、現在計画決定している炉が数炉にすぎないこと、設計耐用年数が過ぎた炉が今後続々と出てくることを考えると、大きな社会的転換がなければ原子力の年間発電量を大きく増やすことができないのがリアリティーではないでしょうか。
にもかかわらず、10年後のエネルギー供給量の中にさえ、原子力の年間発電量を現状の延長線より上に振らそうとする人たちがエネルギー政策の中心部にいる。無責任なフィクションのように見えます。
私個人の考えは原子力の全廃にあることは何度も書いていますが、それとは別に、政治的リアリティーという点で日本の政策決定に大きな問題があると考えています。
スウェーデンの場合、原発をゼロに向って減少させるという方針を打ち出した後、それを可能にするエネルギー需給構造を作ろうとしたけれど、思ったより時間がかかっているので、まずは廃炉のペースを落とす決定をし、次に今回の決定になったのだと思います。とはいえ各論はこれからでしょうから、今後の計画に何を盛り込むかをウオッチする必要があります。
日本の場合、現実問題として新設がなく、増設にも計画から竣工まで相当な年数がかかっていること、現在計画決定している炉が数炉にすぎないこと、設計耐用年数が過ぎた炉が今後続々と出てくることを考えると、大きな社会的転換がなければ原子力の年間発電量を大きく増やすことができないのがリアリティーではないでしょうか。
にもかかわらず、10年後のエネルギー供給量の中にさえ、原子力の年間発電量を現状の延長線より上に振らそうとする人たちがエネルギー政策の中心部にいる。無責任なフィクションのように見えます。
daiさん
増やすにせよ減らすにせよ、既に作ってしまった廃棄物の処分を決めたのは評価できるかと思います。
確かに日本は2020年までの新設計画は8基ほどです。元々電力需要がジリ貧なだけに、電力会社にしてみれば、よほどの火力に対する規制(英国は2020年までに老朽火力を廃止することが決まっているため、電力の30%分の穴埋めに原発を検討中)でもないかぎり、わざわざ新設する計画が生まれないのでしょう。
日本は、長年の運用実績にも関わらず、スウェーデンや韓国など他国とは違い、原発の設備利用率が下がり続けている唯一の国です。特に、東京電力の柏崎の影響も大きいです。現在、やっと2基が稼動しましたが、すべて動くだけでかなり違いますし、無用かつむしろ危険性を増大させてしまっている可能性すらある、やたら多い計画外点検を少しでも増やすと、発電電力量はかなり変わります。
東京電力が発表した10年計画で、原発の新設は3基(設備容量比率は23%→27%に)であるのに対し、発電電力量比率は29%→48%と計算されています。
新設の効果よりも、稼働率向上の効果の方が大きいという証拠ですね。
一方、2020年までに9基新設することがベースに計算されているGHG削減のロードマップは、新設がなくなれば完全に破綻します。削減のほとんどは実は原発による効果なわけですから。
増やすにせよ減らすにせよ、既に作ってしまった廃棄物の処分を決めたのは評価できるかと思います。
確かに日本は2020年までの新設計画は8基ほどです。元々電力需要がジリ貧なだけに、電力会社にしてみれば、よほどの火力に対する規制(英国は2020年までに老朽火力を廃止することが決まっているため、電力の30%分の穴埋めに原発を検討中)でもないかぎり、わざわざ新設する計画が生まれないのでしょう。
日本は、長年の運用実績にも関わらず、スウェーデンや韓国など他国とは違い、原発の設備利用率が下がり続けている唯一の国です。特に、東京電力の柏崎の影響も大きいです。現在、やっと2基が稼動しましたが、すべて動くだけでかなり違いますし、無用かつむしろ危険性を増大させてしまっている可能性すらある、やたら多い計画外点検を少しでも増やすと、発電電力量はかなり変わります。
東京電力が発表した10年計画で、原発の新設は3基(設備容量比率は23%→27%に)であるのに対し、発電電力量比率は29%→48%と計算されています。
新設の効果よりも、稼働率向上の効果の方が大きいという証拠ですね。
一方、2020年までに9基新設することがベースに計算されているGHG削減のロードマップは、新設がなくなれば完全に破綻します。削減のほとんどは実は原発による効果なわけですから。
ぬりさん
ここから先は、私自身はその分析チームに入っていないので、つっこまれるときちんとした回答ができない内容ですが、まあ、問題意識として書いておきます。
COP3を受けて90年代末に作られたエネルギー計画では、原子力発電の新増設を過大に見込んでおり、それは実現できず、できなかった分を電力会社は石炭火力で埋めた(同じベース電源なので)。そのため、2000年以降、日本の排出量が増加した。最初から原子力でなく再生エネで計画していれば(そしてそのための努力をしていれば)排出削減目標は達成できたはずである。
原発は(計画期間内にそれほど多くは)建たない、石炭火力は建てない、という前提で次の計画を作らなければいけないのに、相変わらず過大に原発を見込んでおり、結局それが石炭火力に化けるのではないか。
そういう問題意識です。(作業仮説と考えていただいてもいいです)
ここから先は、私自身はその分析チームに入っていないので、つっこまれるときちんとした回答ができない内容ですが、まあ、問題意識として書いておきます。
COP3を受けて90年代末に作られたエネルギー計画では、原子力発電の新増設を過大に見込んでおり、それは実現できず、できなかった分を電力会社は石炭火力で埋めた(同じベース電源なので)。そのため、2000年以降、日本の排出量が増加した。最初から原子力でなく再生エネで計画していれば(そしてそのための努力をしていれば)排出削減目標は達成できたはずである。
原発は(計画期間内にそれほど多くは)建たない、石炭火力は建てない、という前提で次の計画を作らなければいけないのに、相変わらず過大に原発を見込んでおり、結局それが石炭火力に化けるのではないか。
そういう問題意識です。(作業仮説と考えていただいてもいいです)
daiさん
原発がたくさん増設出来るという前提でものを考えるのは確かに危険ですね。
日本の排出量が増加したのは、2002年の東電の点検記録に改竄で原発稼働率が26%まで落ち込んだのと、2002年、2004年に浜岡1・2号の停止、2007年の中越沖地震の影響等が最も大きいという認識でした。
特に東京電力に関しては、元々石炭火力の割合が極端に少ないですし、ほとんど増えていません。
原子力の停止に対応したのは、石油火力がほとんどでした。
90年代の時点で、再生可能エネルギーを国の基幹エネルギーに据えるという考えに至るには、当時の石油価格は安すぎたのではないでしょうか。
再生可能エネルギーというか、風力をもっと増やせないもんですかね。
原発がたくさん増設出来るという前提でものを考えるのは確かに危険ですね。
日本の排出量が増加したのは、2002年の東電の点検記録に改竄で原発稼働率が26%まで落ち込んだのと、2002年、2004年に浜岡1・2号の停止、2007年の中越沖地震の影響等が最も大きいという認識でした。
特に東京電力に関しては、元々石炭火力の割合が極端に少ないですし、ほとんど増えていません。
原子力の停止に対応したのは、石油火力がほとんどでした。
90年代の時点で、再生可能エネルギーを国の基幹エネルギーに据えるという考えに至るには、当時の石油価格は安すぎたのではないでしょうか。
再生可能エネルギーというか、風力をもっと増やせないもんですかね。
北朝鮮、核融合の実験を実施か
5月12日の北朝鮮発表の二日後、放射性物質「キセノン」8倍を検出
韓国政府、知りながらも公開せず
北朝鮮が先月12日、水素爆弾の基礎技術となる核融合の開発に成功したと発表した直後、韓国原子力安全技術院(KINS)が管理している最北端の測定所で、通常の8倍ほどの放射能物質「キセノン」が検出されていたことが、20日までに確認された。これによって、北朝鮮が当時、核融合技術の開発のため、小規模の核実験を行っていた可能性が取りざたされている。
韓国政府の関係者は20日、「北朝鮮による発表の二日後(先月14日)、江原道高城郡の巨津測定所で採集された大気を検査した結果、キセノン分析器が通常の数値を8倍ほど上回るキセノンを検出した。関係機関と当局がこれについて集中的に分析している」と話した。キセノンはクリプトンと共に核分裂によって発生する気体状態の放射能物質で、ほかの物質と科学反応を起こさないため、核実験の最も確実な証拠とみられている。北朝鮮が2006年、咸鏡北道吉州郡風渓里で核実験を実施した際も、数日後に韓国政府がキセノンを検出した、と発表した。
原子力専門家のA博士は、「核融合技術は通常、三重水素を強く圧縮させるために磁場やレーザービームを利用するが、兵器(水素爆弾)をつくるためには原子爆弾を利用し、三重水素を圧縮させる必要がある。もしキセノンが検出されたのならば、北朝鮮が実験用の原子爆弾を爆発させる過程で発生した可能性がある」と話した。水素爆弾は製造過程で必要な1次エネルギーの相当量を原子爆弾から得るというわけだ。
しかし韓国政府は、北朝鮮が先月核融合技術の開発を発表した際、「信じられない」ような懐疑的な反応を見せた。その後、政府は、キセノンが検出された事実および原子力安全技術院による分析結果を公開しなかった。政府関係者は「キセノンは核実験でも検出できるが、発電所の稼動でも発生するケースがある」と語った。
北朝鮮は先月12日、労働新聞を通じて「北朝鮮の科学者はついに核融合反応に成功した。核融合の成功は飛躍的な発展を遂げる朝鮮の先端科学技術の姿を誇示する一大事件だ」と発表した。ファン・ジャンヨプ元労働党書記は当時、「北朝鮮は長年にわたり水素爆弾を研究してきた。北朝鮮による核融合の成功は十分に可能なこと」と話した。核融合から発生する水素爆弾は核分裂による原子爆弾の数十−数千倍の威力がある。
朱庸中(チュ・ヨンジュン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
核問題:韓国政府、キセノンの8倍検出を認める
「核融合実験の可能性は低い」
韓国と北朝鮮の軍事境界線付近で先月中旬に、放射性物質「キセノン」が通常の8倍も検出されたことから、北朝鮮が水素爆弾の製造に利用できる核融合の実験を行った可能性がある、と報じられたことについて、韓国政府は21日、キセノンが検出されたことは認めたものの、実際に核融合実験を行ったと見なすのは困難だ、と発表した。
教育科学技術部(教科部)は、北朝鮮が先月12日に「核融合実験に成功した」と発表した直後の同15日、江原道高城郡の巨津測定所で、キセノンの濃度が通常(0.55)の8倍程度(4.09)に達した、と発表した。キセノンは核分裂反応によって発生する気体状の放射性物質で、ほかの物質と化学反応を起こすことがないため、最も確実な核実験の証拠と考えられている。だが、教科部は「当時、核爆弾の爆発実験によって生じる人工地震波は検知されなかった。当時、人工地震波は計3回検知されたが、すべてマグニチュード3以下であり、地下核実験によるものではない」と説明した。
キセノンは、核爆弾の爆発実験以外では、原子力発電の過程や使用済み核燃料などでも発生することがある。だが、北朝鮮で稼働中の原子力発電所はなく、また使用済み核燃料からキセノンが漏れた場合、北朝鮮が自ら、事故が起こったかのように対外的に発表すると考えられるため、つじつまが合わなくなる、と指摘されている。
専門家らは、「北朝鮮が水素爆弾を開発する過程でキセノンが漏れ出し、実験そのものには失敗したため、人工地震の規模がマグニチュード3未満になった可能性もある」との見方を示した。一方、金泰栄(キム・テヨン)国防部長官はこの日、国会で「地震波が確認されないなど、核爆弾の爆発と考えられる兆候が見られないため、引き続き検討している。より科学的な手段による確認作業が必要だ」と語った。
朱庸中(チュ・ヨンジュン)記者
チョ・ホジン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
北朝鮮、核融合の実験を実施か
http://www.chosunonline.com/news/20100621000013
核問題:韓国政府、キセノンの8倍検出を認める
http://www.chosunonline.com/news/20100622000014
5月12日の北朝鮮発表の二日後、放射性物質「キセノン」8倍を検出
韓国政府、知りながらも公開せず
北朝鮮が先月12日、水素爆弾の基礎技術となる核融合の開発に成功したと発表した直後、韓国原子力安全技術院(KINS)が管理している最北端の測定所で、通常の8倍ほどの放射能物質「キセノン」が検出されていたことが、20日までに確認された。これによって、北朝鮮が当時、核融合技術の開発のため、小規模の核実験を行っていた可能性が取りざたされている。
韓国政府の関係者は20日、「北朝鮮による発表の二日後(先月14日)、江原道高城郡の巨津測定所で採集された大気を検査した結果、キセノン分析器が通常の数値を8倍ほど上回るキセノンを検出した。関係機関と当局がこれについて集中的に分析している」と話した。キセノンはクリプトンと共に核分裂によって発生する気体状態の放射能物質で、ほかの物質と科学反応を起こさないため、核実験の最も確実な証拠とみられている。北朝鮮が2006年、咸鏡北道吉州郡風渓里で核実験を実施した際も、数日後に韓国政府がキセノンを検出した、と発表した。
原子力専門家のA博士は、「核融合技術は通常、三重水素を強く圧縮させるために磁場やレーザービームを利用するが、兵器(水素爆弾)をつくるためには原子爆弾を利用し、三重水素を圧縮させる必要がある。もしキセノンが検出されたのならば、北朝鮮が実験用の原子爆弾を爆発させる過程で発生した可能性がある」と話した。水素爆弾は製造過程で必要な1次エネルギーの相当量を原子爆弾から得るというわけだ。
しかし韓国政府は、北朝鮮が先月核融合技術の開発を発表した際、「信じられない」ような懐疑的な反応を見せた。その後、政府は、キセノンが検出された事実および原子力安全技術院による分析結果を公開しなかった。政府関係者は「キセノンは核実験でも検出できるが、発電所の稼動でも発生するケースがある」と語った。
北朝鮮は先月12日、労働新聞を通じて「北朝鮮の科学者はついに核融合反応に成功した。核融合の成功は飛躍的な発展を遂げる朝鮮の先端科学技術の姿を誇示する一大事件だ」と発表した。ファン・ジャンヨプ元労働党書記は当時、「北朝鮮は長年にわたり水素爆弾を研究してきた。北朝鮮による核融合の成功は十分に可能なこと」と話した。核融合から発生する水素爆弾は核分裂による原子爆弾の数十−数千倍の威力がある。
朱庸中(チュ・ヨンジュン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
核問題:韓国政府、キセノンの8倍検出を認める
「核融合実験の可能性は低い」
韓国と北朝鮮の軍事境界線付近で先月中旬に、放射性物質「キセノン」が通常の8倍も検出されたことから、北朝鮮が水素爆弾の製造に利用できる核融合の実験を行った可能性がある、と報じられたことについて、韓国政府は21日、キセノンが検出されたことは認めたものの、実際に核融合実験を行ったと見なすのは困難だ、と発表した。
教育科学技術部(教科部)は、北朝鮮が先月12日に「核融合実験に成功した」と発表した直後の同15日、江原道高城郡の巨津測定所で、キセノンの濃度が通常(0.55)の8倍程度(4.09)に達した、と発表した。キセノンは核分裂反応によって発生する気体状の放射性物質で、ほかの物質と化学反応を起こすことがないため、最も確実な核実験の証拠と考えられている。だが、教科部は「当時、核爆弾の爆発実験によって生じる人工地震波は検知されなかった。当時、人工地震波は計3回検知されたが、すべてマグニチュード3以下であり、地下核実験によるものではない」と説明した。
キセノンは、核爆弾の爆発実験以外では、原子力発電の過程や使用済み核燃料などでも発生することがある。だが、北朝鮮で稼働中の原子力発電所はなく、また使用済み核燃料からキセノンが漏れた場合、北朝鮮が自ら、事故が起こったかのように対外的に発表すると考えられるため、つじつまが合わなくなる、と指摘されている。
専門家らは、「北朝鮮が水素爆弾を開発する過程でキセノンが漏れ出し、実験そのものには失敗したため、人工地震の規模がマグニチュード3未満になった可能性もある」との見方を示した。一方、金泰栄(キム・テヨン)国防部長官はこの日、国会で「地震波が確認されないなど、核爆弾の爆発と考えられる兆候が見られないため、引き続き検討している。より科学的な手段による確認作業が必要だ」と語った。
朱庸中(チュ・ヨンジュン)記者
チョ・ホジン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
北朝鮮、核融合の実験を実施か
http://www.chosunonline.com/news/20100621000013
核問題:韓国政府、キセノンの8倍検出を認める
http://www.chosunonline.com/news/20100622000014
− インド:第4回日印エネルギー対話共同声明の発出
【日程】 2010年4月
【内容】 直嶋経済産業大臣とアルワリア計画委員会副委員長は、4月30日に第4回日印エネルギー対話をデリーで開催。省エネ、再生可能エネルギー、石炭、電力等に加え、今回新たに原子力WGを設置し、エネルギー・経済産業の観点から、情報・意見交換を行うことを決定しました。両大臣は今回議論の結果を踏まえ共同声明を発出しました。
【資料】
○ 第4回日印エネルギー対話に係る日本国経済産業省とインド計画委員会との間の共同声明
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-affairs/data/20100507seimei.pdf
○ 第4回日印エネルギー対話に係る日本国経済産業省とインド計画委員会との間の共同声明(骨子)
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-affairs/data/20100507kosshi.pdf
○ Joint Statement between the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan and the Planning Commission of India on the Occasion of the Forth Meeting of the Japan-India Energy Dialogue
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-affairs/data/20100507en.pdf
【日程】 2010年4月
【内容】 直嶋経済産業大臣とアルワリア計画委員会副委員長は、4月30日に第4回日印エネルギー対話をデリーで開催。省エネ、再生可能エネルギー、石炭、電力等に加え、今回新たに原子力WGを設置し、エネルギー・経済産業の観点から、情報・意見交換を行うことを決定しました。両大臣は今回議論の結果を踏まえ共同声明を発出しました。
【資料】
○ 第4回日印エネルギー対話に係る日本国経済産業省とインド計画委員会との間の共同声明
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-affairs/data/20100507seimei.pdf
○ 第4回日印エネルギー対話に係る日本国経済産業省とインド計画委員会との間の共同声明(骨子)
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-affairs/data/20100507kosshi.pdf
○ Joint Statement between the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan and the Planning Commission of India on the Occasion of the Forth Meeting of the Japan-India Energy Dialogue
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-affairs/data/20100507en.pdf
原発輸出会社設立へ準備室=電力3社と東芝、日立、三菱重 [環境メディア] http://kankyomedia.jp/news/20100707_12679.html
東京、中部、関西の電力3社と東芝、日立製作所、三菱重工業は6日、日本製の原発やその運転技術をベトナムなど海外に売り込むための新会社設立に向けた準備室を、同日設置したと発表した。今秋をめどに、新会社「国際原子力開発」(仮称)を共同で設立する。
新会社は電力3社が中心となる。当面は原発の建設計画を持つベトナムでの受注を目指し、同国政府が求める具体的なニーズの調査や、プラント建設・人材育成計画の提案などを行う。
原子力発電は、二酸化炭素(CO2)削減の観点からも見直され、新興国などで導入計画が増加。プラント技術を持つフランス、日本、韓国などによる受注競争が激しさを増している。
東京、中部、関西の電力3社と東芝、日立製作所、三菱重工業は6日、日本製の原発やその運転技術をベトナムなど海外に売り込むための新会社設立に向けた準備室を、同日設置したと発表した。今秋をめどに、新会社「国際原子力開発」(仮称)を共同で設立する。
新会社は電力3社が中心となる。当面は原発の建設計画を持つベトナムでの受注を目指し、同国政府が求める具体的なニーズの調査や、プラント建設・人材育成計画の提案などを行う。
原子力発電は、二酸化炭素(CO2)削減の観点からも見直され、新興国などで導入計画が増加。プラント技術を持つフランス、日本、韓国などによる受注競争が激しさを増している。
世界のウラン資源、今後100年分は十分 (NEA・IAEA共同研究)
http://blogs.yahoo.co.jp/yada7215/61179006.html
今回のNEAとIAEAの研究報告は、かなり楽観的な見方ですが、これまで、ウランの探鉱活動や調査に充分な投資が行われていなかったために、実は、このような結果も予想されてきました。
石油資源のピークアウトが近づいているので、再生可能エネルギーとともに、今後の現実的な対応として原子力発電が、欠かせないオプションになってきたようです。
今後は、高速増殖炉や、新興国向けの小型原子炉の開発競争が激しくなると思います。
☆
ただ、もうすぐロシアの核兵器解体から出るウランが減るので、短期的には需給はタイトになる気がします。
http://blogs.yahoo.co.jp/yada7215/61179006.html
今回のNEAとIAEAの研究報告は、かなり楽観的な見方ですが、これまで、ウランの探鉱活動や調査に充分な投資が行われていなかったために、実は、このような結果も予想されてきました。
石油資源のピークアウトが近づいているので、再生可能エネルギーとともに、今後の現実的な対応として原子力発電が、欠かせないオプションになってきたようです。
今後は、高速増殖炉や、新興国向けの小型原子炉の開発競争が激しくなると思います。
☆
ただ、もうすぐロシアの核兵器解体から出るウランが減るので、短期的には需給はタイトになる気がします。
EU、核種変換炉の建設決定
EUは、2010年11月にベルギーのモル(Mol)に世界初の研究用の核種変換炉を建設することを決めた。この「ミラ・プロジェクト」の費用は1036億円相当で、操業開始は2024年の予定。
高レベル放射性廃棄物に含まれる半減期の長いマイナーアクチニドなどに加速器駆動未臨界炉において中性子を当てて核分裂させて、短半減期の同位体に核種変換する技術。
Energy question of the week: Can nuclear waste be made safe?
15. November 2010, 08.55, Jan Oliver Löfken, 2 Comment/s
http://www.dlr.de/blogs/en/DesktopDefault.aspx/tabid-6192/10184_read-302/
DLR エネルギー・ブログ(DLR:ドイツ航空宇宙センターは国立の
研究所、英語名 German Aerospace Center)
より
いわゆるADSR(Accelerator Driven Subcritical Reactor)ですね。熊取の原子炉が老朽化で使えないので、京大の原子力関係者が起死回生で構想しているようですが、話を聞く限り・・・実用化への本気度が感じられませんでした。
EUは、2010年11月にベルギーのモル(Mol)に世界初の研究用の核種変換炉を建設することを決めた。この「ミラ・プロジェクト」の費用は1036億円相当で、操業開始は2024年の予定。
高レベル放射性廃棄物に含まれる半減期の長いマイナーアクチニドなどに加速器駆動未臨界炉において中性子を当てて核分裂させて、短半減期の同位体に核種変換する技術。
Energy question of the week: Can nuclear waste be made safe?
15. November 2010, 08.55, Jan Oliver Löfken, 2 Comment/s
http://www.dlr.de/blogs/en/DesktopDefault.aspx/tabid-6192/10184_read-302/
DLR エネルギー・ブログ(DLR:ドイツ航空宇宙センターは国立の
研究所、英語名 German Aerospace Center)
より
いわゆるADSR(Accelerator Driven Subcritical Reactor)ですね。熊取の原子炉が老朽化で使えないので、京大の原子力関係者が起死回生で構想しているようですが、話を聞く限り・・・実用化への本気度が感じられませんでした。
需要が伸びないので、リプレースや新規立地が出来ないとうい実態。
でも、今後化石燃料が十分に供給されなかったらどうするのだろう。
分散型エネルギー新聞2011.2.15 6面
「ちょっと一言」より
中国電力・上関原子力は、新規立地地点の内でも数多くの問題を抱えている。地元の強い反対運動や、希少な生態系の破壊につながるといった懸念が強いほか、中国電力そのものが抱える課題も浮き彫りにしている。
この上関原子力をめぐる資源エネルギー庁の対応のお粗末さが、話題になっている。
発端は、与党民主党の「原子力政策・立地政策PT」の1月28日の議事録だ。これがネットに流出し、自民党の河野太郎衆議院議員のメールマガジンなどで瞬く間に広がった。
そこでは、PTの座長の「(上関原子力について、地元漁協は)協定を結んでいるのに、補償金を受け取らないなど経緯がわからない」という質問に対し、エネ庁長官らは質問に答えることができず、ひたすら、少数の反対派が障害になっていると答弁。また環境影響評価についても、十分な説明なしに、問題ないと答えている。
正確には、共同漁業権について、地元8漁協のうち7漁協の賛成で協定を結んだが、祝島漁協だけが反対を示し補償金を受け取っていない。
また環境影響評価については、日本生態学会や日本鳥学会などが調査のやり直しなどを求めている。瀬戸内海という閉鎖性水域での温排水の影響が適切に評価されていないということだ。
こうしたことに加え、中国電力・島根原子力の点検漏れなどの失態などもあり、エネ庁自身、上関原子力が進まないことをきちんと説明できない。
一方、上関原子力のユーザーとみられている関西電力では、地元からの要望があったにも関わらず、美浜原子力3号機のリプレースは、まだ検討しないことを表明した。需要が伸びない以上、リプレースにお金をかけられないということだ。こうした状況では、上関原子力の必要性はますます希薄になる。
原子力がいけないというのではない。ただ「エネルギー基本計画」の数字合わせのための立地は、自然環境の面でも、経済的な面でも禍根を残す。エネ庁のお粗末な対応は、無理な立地計画ゆえのことなのだろう。
上関が登場するドキュメンタリー映画「ミツバチの羽音と地球の回転」は、2月19日から都内でロードショー公開される。
でも、今後化石燃料が十分に供給されなかったらどうするのだろう。
分散型エネルギー新聞2011.2.15 6面
「ちょっと一言」より
中国電力・上関原子力は、新規立地地点の内でも数多くの問題を抱えている。地元の強い反対運動や、希少な生態系の破壊につながるといった懸念が強いほか、中国電力そのものが抱える課題も浮き彫りにしている。
この上関原子力をめぐる資源エネルギー庁の対応のお粗末さが、話題になっている。
発端は、与党民主党の「原子力政策・立地政策PT」の1月28日の議事録だ。これがネットに流出し、自民党の河野太郎衆議院議員のメールマガジンなどで瞬く間に広がった。
そこでは、PTの座長の「(上関原子力について、地元漁協は)協定を結んでいるのに、補償金を受け取らないなど経緯がわからない」という質問に対し、エネ庁長官らは質問に答えることができず、ひたすら、少数の反対派が障害になっていると答弁。また環境影響評価についても、十分な説明なしに、問題ないと答えている。
正確には、共同漁業権について、地元8漁協のうち7漁協の賛成で協定を結んだが、祝島漁協だけが反対を示し補償金を受け取っていない。
また環境影響評価については、日本生態学会や日本鳥学会などが調査のやり直しなどを求めている。瀬戸内海という閉鎖性水域での温排水の影響が適切に評価されていないということだ。
こうしたことに加え、中国電力・島根原子力の点検漏れなどの失態などもあり、エネ庁自身、上関原子力が進まないことをきちんと説明できない。
一方、上関原子力のユーザーとみられている関西電力では、地元からの要望があったにも関わらず、美浜原子力3号機のリプレースは、まだ検討しないことを表明した。需要が伸びない以上、リプレースにお金をかけられないということだ。こうした状況では、上関原子力の必要性はますます希薄になる。
原子力がいけないというのではない。ただ「エネルギー基本計画」の数字合わせのための立地は、自然環境の面でも、経済的な面でも禍根を残す。エネ庁のお粗末な対応は、無理な立地計画ゆえのことなのだろう。
上関が登場するドキュメンタリー映画「ミツバチの羽音と地球の回転」は、2月19日から都内でロードショー公開される。
智山さん
> 放射線量は生命に危険が及ぶレベルの1000分の1以下だそうです
この種の数字がテレビを含めて本日飛び交っており、とても多くの人が誤解している危険性が大きいと感じています。充分理解せずに人前で書かない方がいいと思いますよ。
たとえば、一般人に関する国の規制値は、この間の報道によると年間 1,000μSv です。つまり 1,000μSv/年。これを単純に毎秒に換算すると、1年間は 31,536,000 秒ですから、0.0000317μSv/s ということになります。このところの福島原発正門の放射線量が 50μSv/s 程度だとすると、何と規制値の157万倍ということになってしまいます。
なぜこんな計算になってしまうのか、おわかりになりますか?
> 放射線量は生命に危険が及ぶレベルの1000分の1以下だそうです
この種の数字がテレビを含めて本日飛び交っており、とても多くの人が誤解している危険性が大きいと感じています。充分理解せずに人前で書かない方がいいと思いますよ。
たとえば、一般人に関する国の規制値は、この間の報道によると年間 1,000μSv です。つまり 1,000μSv/年。これを単純に毎秒に換算すると、1年間は 31,536,000 秒ですから、0.0000317μSv/s ということになります。このところの福島原発正門の放射線量が 50μSv/s 程度だとすると、何と規制値の157万倍ということになってしまいます。
なぜこんな計算になってしまうのか、おわかりになりますか?
>>180
ようやく繋がりました。
出典元はここです。
http://takedanet.com/2011/03/post_deb3.html
以下引用
人間が放射線によって障害を受ける最低の放射線は200ミリシーベルト付近ですから。現在の200倍ぐらいに相当しますので、人間に直接的に影響が及ぶということはありません。
さらに放射線で死ぬということを考えますと、1シーベルとぐらいですから、その点ではまだ1000倍程度の余裕があります。ちなみに、4シーベルトぐらいになると半分ぐらいの人が放射線で死にます
.引用終わり
ところで50μsV/sという数字はどこから来たのでしょうか。
東電の出しているデータを見る限りそんな大きな数値は見当たりませんよ。
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110314e.pdf
ようやく繋がりました。
出典元はここです。
http://takedanet.com/2011/03/post_deb3.html
以下引用
人間が放射線によって障害を受ける最低の放射線は200ミリシーベルト付近ですから。現在の200倍ぐらいに相当しますので、人間に直接的に影響が及ぶということはありません。
さらに放射線で死ぬということを考えますと、1シーベルとぐらいですから、その点ではまだ1000倍程度の余裕があります。ちなみに、4シーベルトぐらいになると半分ぐらいの人が放射線で死にます
.引用終わり
ところで50μsV/sという数字はどこから来たのでしょうか。
東電の出しているデータを見る限りそんな大きな数値は見当たりませんよ。
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110314e.pdf
智山さん
ありがとうございます。モニタリングポストと正門を読み間違えました。すみません、、、(^^;)
何にせよ、短時間の被爆の危険を言うのか、長時間滞在したときの危険を言うのかでも異なります。
さらに言うと、引用された数値は10分間間隔ですが、公表するときには計測方法も書くべきですよね。累積データからの換算なのか、サンプリングデータなのかによっても評価が異なりますし。
引用された文章で言うと「障害を受ける最低の放射線は200ミリシーベルト付近ですから。現在の200倍ぐらい」は単位(ディメンション)が間違っていますよね。
生体が受けるダメージは累積線量におおむね比例するけれど、回復力もあるので、年間の累積線量を規制値にしていると私は理解しています。したがって智山さん引用の200ミリシーベルト(mSv)は、そのまま200ミリシーベルトを指していると思います。
一方、報道されている正門付近でのピーク値は、約1ミリシーベルト毎時(mSv/h)、です。
物理の試験で、「200ミリシーベルトは1ミリシーベルト毎時の200倍」と答案に書いたら、落第します。ディメンションが違うから比較できません。
比較したければ「200ミリシーベルトの線量は、1ミリシーベルト毎時の場所に200時間滞在したときに浴びる線量」であり、上記引用の他の数字で言うと、1ミリシーベルト毎時の場所に1,000時間(約42日間)滞在すると死亡する危険が高まり、4,000時間(約167日間)滞在すると半数が死ぬことになりますよね。
もちろん、実際には放射線量は大きく変動しますので、このような単純計算にはなりません。
私も素人なのであまり人前で書くことではありませんが、放射線データの評価には相応のトレーニングが必要ですよね。
ありがとうございます。モニタリングポストと正門を読み間違えました。すみません、、、(^^;)
何にせよ、短時間の被爆の危険を言うのか、長時間滞在したときの危険を言うのかでも異なります。
さらに言うと、引用された数値は10分間間隔ですが、公表するときには計測方法も書くべきですよね。累積データからの換算なのか、サンプリングデータなのかによっても評価が異なりますし。
引用された文章で言うと「障害を受ける最低の放射線は200ミリシーベルト付近ですから。現在の200倍ぐらい」は単位(ディメンション)が間違っていますよね。
生体が受けるダメージは累積線量におおむね比例するけれど、回復力もあるので、年間の累積線量を規制値にしていると私は理解しています。したがって智山さん引用の200ミリシーベルト(mSv)は、そのまま200ミリシーベルトを指していると思います。
一方、報道されている正門付近でのピーク値は、約1ミリシーベルト毎時(mSv/h)、です。
物理の試験で、「200ミリシーベルトは1ミリシーベルト毎時の200倍」と答案に書いたら、落第します。ディメンションが違うから比較できません。
比較したければ「200ミリシーベルトの線量は、1ミリシーベルト毎時の場所に200時間滞在したときに浴びる線量」であり、上記引用の他の数字で言うと、1ミリシーベルト毎時の場所に1,000時間(約42日間)滞在すると死亡する危険が高まり、4,000時間(約167日間)滞在すると半数が死ぬことになりますよね。
もちろん、実際には放射線量は大きく変動しますので、このような単純計算にはなりません。
私も素人なのであまり人前で書くことではありませんが、放射線データの評価には相応のトレーニングが必要ですよね。
補足
前の書き込みは体外被曝を前提に書きましたが、体内被爆問題になると全く局面が変わります。
体外被曝の場合ガンマ線がメインで、ベータ線が少し、アルファ線はほぼ遮断。時間的にも平均的。体重60kgなら60kgが平均的に吸収。
体内被曝になると、吸収されなくても消化管に12−24時間とどまり、アルファ線は全量、ベータ線もほぼ全量吸収され、しかも局所的に吸収されるので、体重の10分の1くらいの細胞が吸収=その時点で10倍の効果。さらに体内吸収されると、平均退社時間の間被爆が継続し、数十グラム、数百グラムの体細胞が集中的に被爆。
医学は素人なのでこれくらいしか書けませんが、局面が変わることは間違いないです。
前の書き込みは体外被曝を前提に書きましたが、体内被爆問題になると全く局面が変わります。
体外被曝の場合ガンマ線がメインで、ベータ線が少し、アルファ線はほぼ遮断。時間的にも平均的。体重60kgなら60kgが平均的に吸収。
体内被曝になると、吸収されなくても消化管に12−24時間とどまり、アルファ線は全量、ベータ線もほぼ全量吸収され、しかも局所的に吸収されるので、体重の10分の1くらいの細胞が吸収=その時点で10倍の効果。さらに体内吸収されると、平均退社時間の間被爆が継続し、数十グラム、数百グラムの体細胞が集中的に被爆。
医学は素人なのでこれくらいしか書けませんが、局面が変わることは間違いないです。
「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」
平成23年(2011)3月18日(金曜日)貳
通巻第3268号
より
(読者の声1)「原発施設の改善を妨害してきたマスコミの罪と今後の対応」
今回の福島原発の大事故について、マスコミに東電の施設改善の遅れという批判がある。
しかし原発の改善にいつもブレーキをかけてきたのはマスコミではなかったか。それが設備の改良を送らせて今回の大事故につながったといえる。
マスコミはわずかな放射線漏れも大騒ぎである。
このためマスコミの反政府煽動をおそれた政治家は原子力問題の論議を凍結し、電力会社も原発問題については常に隠蔽してきた。このため原発会社の現場でも自由な設備改善論議が封じられていたのではないか。
このマスコミの反原発の背後には日本の核自衛を妨害しようとする反日国家の対日政策が見え隠れする。
その証拠にあれほど騒ぐ日本のマスコミは反日国家の核開発にはいっさい沈黙だ。それどころか「社会主義国家の原爆はきれいな原爆」とまで言いだす始末だ。
反日国家は日本が戦後スパイ防止法を奪われたことを良いことに、政治家、政党、マスコミ、大学、文化、出版界に浸透し、日本の原子力利用能力を奪うように、たえず撹乱工作を続けてきた。
そして今や健康に害のないわずかな放射線の漏洩でさえヒステリックに騒ぐ日本人をみてほくそ笑んでいるのである。
日本はエネルギー資源がないので原子力発電を利用しなければ生き残ることはできない。
したがってエネルギーの安定供給を確保するために、原発の設置地域としてはツナミ銀座の三陸地方は避け、歴史的に地震や津波の少ない中国地方などに設置すべきである。
これもマスコミがセンセーショナルに騒ぐために、政治家が無知な住民に金をばらまいて設置にOKを言わせるような、国家的見地を欠いた立地選択が行われてきた。
原発の技術については今回の事故でギブアップしてはならない。
戦前、潜水艦事故で殉職した佐久間艇長は、その遺書で事故によって日本の潜水艦開発を遅らせてはならないと述べている。人間の歴史をみると大きな技術はほとんどと言ってよいほど犠牲を伴ってきた。しかし重要なのは事故であきらめずに改良を進めることである。それが尊い犠牲を無駄にしないことになる。止めてしまえば全部無駄になってしまう。
その意味で日本人はこの大事故を機会に、原子力発電をより安全で安定したエネルギー技術にするため、一層の技術改良を進めなければならない。
そのためにも国民は無責任なマスコミの報道に騙されないようにこれまで以上に原子力発電の知識深め、またマスコミの原発報道を厳しく監視する必要がある。
(東海子)
(宮崎正弘のコメント)ネバー・ギブアップ。
平成23年(2011)3月18日(金曜日)貳
通巻第3268号
より
(読者の声1)「原発施設の改善を妨害してきたマスコミの罪と今後の対応」
今回の福島原発の大事故について、マスコミに東電の施設改善の遅れという批判がある。
しかし原発の改善にいつもブレーキをかけてきたのはマスコミではなかったか。それが設備の改良を送らせて今回の大事故につながったといえる。
マスコミはわずかな放射線漏れも大騒ぎである。
このためマスコミの反政府煽動をおそれた政治家は原子力問題の論議を凍結し、電力会社も原発問題については常に隠蔽してきた。このため原発会社の現場でも自由な設備改善論議が封じられていたのではないか。
このマスコミの反原発の背後には日本の核自衛を妨害しようとする反日国家の対日政策が見え隠れする。
その証拠にあれほど騒ぐ日本のマスコミは反日国家の核開発にはいっさい沈黙だ。それどころか「社会主義国家の原爆はきれいな原爆」とまで言いだす始末だ。
反日国家は日本が戦後スパイ防止法を奪われたことを良いことに、政治家、政党、マスコミ、大学、文化、出版界に浸透し、日本の原子力利用能力を奪うように、たえず撹乱工作を続けてきた。
そして今や健康に害のないわずかな放射線の漏洩でさえヒステリックに騒ぐ日本人をみてほくそ笑んでいるのである。
日本はエネルギー資源がないので原子力発電を利用しなければ生き残ることはできない。
したがってエネルギーの安定供給を確保するために、原発の設置地域としてはツナミ銀座の三陸地方は避け、歴史的に地震や津波の少ない中国地方などに設置すべきである。
これもマスコミがセンセーショナルに騒ぐために、政治家が無知な住民に金をばらまいて設置にOKを言わせるような、国家的見地を欠いた立地選択が行われてきた。
原発の技術については今回の事故でギブアップしてはならない。
戦前、潜水艦事故で殉職した佐久間艇長は、その遺書で事故によって日本の潜水艦開発を遅らせてはならないと述べている。人間の歴史をみると大きな技術はほとんどと言ってよいほど犠牲を伴ってきた。しかし重要なのは事故であきらめずに改良を進めることである。それが尊い犠牲を無駄にしないことになる。止めてしまえば全部無駄になってしまう。
その意味で日本人はこの大事故を機会に、原子力発電をより安全で安定したエネルギー技術にするため、一層の技術改良を進めなければならない。
そのためにも国民は無責任なマスコミの報道に騙されないようにこれまで以上に原子力発電の知識深め、またマスコミの原発報道を厳しく監視する必要がある。
(東海子)
(宮崎正弘のコメント)ネバー・ギブアップ。
daiさん
当時はコミンテルンなど共産主義勢力が跋扈していて、それを米国はかなり気にしていたようですし、未だにそうですが、当時は今にもまして米国の許可がないと何もできないという雰囲気はあったと思います。
ましてや、戦後、原子力関係の研究は全て実験装置を破壊没収され、研究はストップしていたわけで、米国がまさか手のひらを返すとはおもってなかったでしょうし、米国も日本に原子力を許可するつもりはなかったでしょう。
それが、予想をはるかにこえてソ連などの原子力技術開発が進み、米国の優位性を保つことか事情上困難になったので、そうならばと先手を売って寧ろ米国主導で原子力の平和利用を推進し、IAEAを設立して日本を監視、原爆を作れないようにコントロールをするのが得策と考えたのでしょう。原子力導入時期は、日本が英国やソ連に関心を持たないように気を遣い始めた頃。それを示唆する資料があったはずです。
当時はコミンテルンなど共産主義勢力が跋扈していて、それを米国はかなり気にしていたようですし、未だにそうですが、当時は今にもまして米国の許可がないと何もできないという雰囲気はあったと思います。
ましてや、戦後、原子力関係の研究は全て実験装置を破壊没収され、研究はストップしていたわけで、米国がまさか手のひらを返すとはおもってなかったでしょうし、米国も日本に原子力を許可するつもりはなかったでしょう。
それが、予想をはるかにこえてソ連などの原子力技術開発が進み、米国の優位性を保つことか事情上困難になったので、そうならばと先手を売って寧ろ米国主導で原子力の平和利用を推進し、IAEAを設立して日本を監視、原爆を作れないようにコントロールをするのが得策と考えたのでしょう。原子力導入時期は、日本が英国やソ連に関心を持たないように気を遣い始めた頃。それを示唆する資料があったはずです。
↑よく思い出してみると石油と電気と食料の間には絶対的な序列があったんだった。
確かkJあたりの価格はいつの時代も石油<電気<食料になっているという記述をネットで見かけたことがある。
この序列が崩れて初めて電気で合成石油を作ることが成り立つわけか…。
ただし食料の方は電気より高いから電気→炭水化物はいけそうな気がする。
水
↓←電気←原子力、風力、水力、太陽光
水素
↓←C、CO、CO2、カーバイト等
メタン、メタノール、炭化水素→合成石油
↓
---------微生物細胞膜---------
↓
ホルムアルデヒド
↓(ペントースリン酸経路)
グルコース
↓ ↓(解糖系)
↓ α-ケト酸
↓ ↓←アンモニア
↓ アミノ酸
↓ ↓↓
↓ ↓タンパク質
---------微生物細胞膜---------
↓ ↓
糖 アミノ酸
エネルギー面の評価:
このプロセスに使われる全ての電気が原発で作られると仮定すると、原発の効率は30%で水の電気分解も30%。
よって水素にした時点で原子力エネルギーの9%しか残っていない。
フィッシャートロプッシュ合成は発熱反応だし、この段階でもだいぶロスするだろうね。
微生物細胞に入ってしまえば酵素反応なので効率よく進むが、細胞自身がピンハネするから良くて8割ぐらいになるだろう。
完成品を細胞の外へ放り出すか、さもなくば細胞を潰して分離するにもエネルギーが必要。
効率はざっと5%程度か…。(電気からだと15%)
コスト面での評価:
標準的な米は1kgが400円で4kWhのエネルギーが内包されている。
つまり100円/kWhと計算できる。
原発の電気は6円/kWh(資源エネルギー庁より)
電気から炭水化物への変換効率が15%とすると価格差は6.67倍(+α)となる。分かりやすく7倍とすると42円/kWh。
なんと!
原発の電気で炭水化物を合成しても既存の米と十分に渡り合えるではないか。
もちろん合成に必要な炭素源やアンモニアの調達は除外してあるが、それでも100円/kWhには届かないだろうし届いたとしても米が高騰すればすぐに逆転する。
確かkJあたりの価格はいつの時代も石油<電気<食料になっているという記述をネットで見かけたことがある。
この序列が崩れて初めて電気で合成石油を作ることが成り立つわけか…。
ただし食料の方は電気より高いから電気→炭水化物はいけそうな気がする。
水
↓←電気←原子力、風力、水力、太陽光
水素
↓←C、CO、CO2、カーバイト等
メタン、メタノール、炭化水素→合成石油
↓
---------微生物細胞膜---------
↓
ホルムアルデヒド
↓(ペントースリン酸経路)
グルコース
↓ ↓(解糖系)
↓ α-ケト酸
↓ ↓←アンモニア
↓ アミノ酸
↓ ↓↓
↓ ↓タンパク質
---------微生物細胞膜---------
↓ ↓
糖 アミノ酸
エネルギー面の評価:
このプロセスに使われる全ての電気が原発で作られると仮定すると、原発の効率は30%で水の電気分解も30%。
よって水素にした時点で原子力エネルギーの9%しか残っていない。
フィッシャートロプッシュ合成は発熱反応だし、この段階でもだいぶロスするだろうね。
微生物細胞に入ってしまえば酵素反応なので効率よく進むが、細胞自身がピンハネするから良くて8割ぐらいになるだろう。
完成品を細胞の外へ放り出すか、さもなくば細胞を潰して分離するにもエネルギーが必要。
効率はざっと5%程度か…。(電気からだと15%)
コスト面での評価:
標準的な米は1kgが400円で4kWhのエネルギーが内包されている。
つまり100円/kWhと計算できる。
原発の電気は6円/kWh(資源エネルギー庁より)
電気から炭水化物への変換効率が15%とすると価格差は6.67倍(+α)となる。分かりやすく7倍とすると42円/kWh。
なんと!
原発の電気で炭水化物を合成しても既存の米と十分に渡り合えるではないか。
もちろん合成に必要な炭素源やアンモニアの調達は除外してあるが、それでも100円/kWhには届かないだろうし届いたとしても米が高騰すればすぐに逆転する。
14基の原発新増設、見直し…太陽光など重視へ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1551787&media_id=20
引用
” 政府は29日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、2030年までに少なくとも14基の原発の新増設を目標に掲げた「エネルギー基本計画」を見直す方針を固めた。”
おいおい…。
太陽光や風力の積極的開発はもちろん急ピッチで進めるべきだが、今のペースじゃ石油の減耗分を埋め合わせられるかどうかも怪しいのに脱原発した分まで埋め合わせるのは当分無理だろう。
物理学的には太陽エネルギーは有り余っているがそれを人類の利用出来る形に変換する施設はまだまだ足りていないし、それを作るには莫大なエネルギー投資が不可欠だ。
石油はもうあてにできないとなると原子力しかない。しばらくは原子力をあてにしなければ太陽光パネルも風車も作れない。
太陽光や風力が十分に利用できるようになれば原子力はいらなくなる。なぜなら太陽電池で太陽電池を再生産できるからだ。
しかしそれを2030年までに行うのは難しい。
ましてや石油が減耗する上に原発も減るとなれば太陽光パネル製造に回せるエネルギーも大幅に制約されることだろう。
半導体工業は安定した電力供給が無ければ成り立たない。
まずは輪番停電なんていう馬鹿なことを早くやめるべきだろう。
そのためには電力の不足分を補えるだけの発電所を新設しなければならないが、石油火力なんか作ったら10年もすれば燃料が不足して使い物にならなくなる。
今は非効率だがインスタントに作れるガスタービン発電所を急ピッチで建設しているようだが、ガスタービンはあくまでつなぎにしておいて再び原発の建て替えと新設に重点を置くべきだろう。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1551787&media_id=20
引用
” 政府は29日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、2030年までに少なくとも14基の原発の新増設を目標に掲げた「エネルギー基本計画」を見直す方針を固めた。”
おいおい…。
太陽光や風力の積極的開発はもちろん急ピッチで進めるべきだが、今のペースじゃ石油の減耗分を埋め合わせられるかどうかも怪しいのに脱原発した分まで埋め合わせるのは当分無理だろう。
物理学的には太陽エネルギーは有り余っているがそれを人類の利用出来る形に変換する施設はまだまだ足りていないし、それを作るには莫大なエネルギー投資が不可欠だ。
石油はもうあてにできないとなると原子力しかない。しばらくは原子力をあてにしなければ太陽光パネルも風車も作れない。
太陽光や風力が十分に利用できるようになれば原子力はいらなくなる。なぜなら太陽電池で太陽電池を再生産できるからだ。
しかしそれを2030年までに行うのは難しい。
ましてや石油が減耗する上に原発も減るとなれば太陽光パネル製造に回せるエネルギーも大幅に制約されることだろう。
半導体工業は安定した電力供給が無ければ成り立たない。
まずは輪番停電なんていう馬鹿なことを早くやめるべきだろう。
そのためには電力の不足分を補えるだけの発電所を新設しなければならないが、石油火力なんか作ったら10年もすれば燃料が不足して使い物にならなくなる。
今は非効率だがインスタントに作れるガスタービン発電所を急ピッチで建設しているようだが、ガスタービンはあくまでつなぎにしておいて再び原発の建て替えと新設に重点を置くべきだろう。
智山さん
197より
>kJあたりの価格はいつの時代も石油<電気<食料
エネルギー形態としてのエクセルギーやエントロピーが違いますからね。
>この序列が崩れて初めて電気で合成石油を作ることが成り立つわけか…。
ただし食料の方は電気より高いから電気→炭水化物はいけそうな気がする。
電気<石油
となった時には、既に石油で発電は行われていないと考えられます(既に殆ど行われていませんが)。
なにから電気を作るかによりますが、一般論として、電気の様に低エントロピー形態のエネルギーを、わざわざ液体燃料に変換するのはあまり効率がよくなさそうな気がします。
>このプロセスに使われる全ての電気が原発で作られると仮定すると、原発の効率は30%で水の電気分解も30%。
よって水素にした時点で原子力エネルギーの9%しか残っていない。
フィッシャートロプッシュ合成は発熱反応だし、この段階でもだいぶロスするだろうね。
原発から合成液体燃料を作るのであれば、電気を経由せず、核反応熱によって水性ガスシフト反応を起こし、合成ガスから水素をとりだすか、メタン、メタノール、DME等を合成するのが合理的だと思います。エネ総工研等が、そのあたりのスタディはかなりやっていますが、コストパフォーマンス的に、天然ガスと石炭に勝てないのが現状です。
微生物は大規模かつ長期のシーケンスコントロールが難しいですよね。不安定なので維持管理コスト。
理論上は、食用に耐えうる炭水化物(やタンパク質)を安価な核反応熱から合成できれば、食糧問題は一気に解決するわけですが・・・。
197より
>kJあたりの価格はいつの時代も石油<電気<食料
エネルギー形態としてのエクセルギーやエントロピーが違いますからね。
>この序列が崩れて初めて電気で合成石油を作ることが成り立つわけか…。
ただし食料の方は電気より高いから電気→炭水化物はいけそうな気がする。
電気<石油
となった時には、既に石油で発電は行われていないと考えられます(既に殆ど行われていませんが)。
なにから電気を作るかによりますが、一般論として、電気の様に低エントロピー形態のエネルギーを、わざわざ液体燃料に変換するのはあまり効率がよくなさそうな気がします。
>このプロセスに使われる全ての電気が原発で作られると仮定すると、原発の効率は30%で水の電気分解も30%。
よって水素にした時点で原子力エネルギーの9%しか残っていない。
フィッシャートロプッシュ合成は発熱反応だし、この段階でもだいぶロスするだろうね。
原発から合成液体燃料を作るのであれば、電気を経由せず、核反応熱によって水性ガスシフト反応を起こし、合成ガスから水素をとりだすか、メタン、メタノール、DME等を合成するのが合理的だと思います。エネ総工研等が、そのあたりのスタディはかなりやっていますが、コストパフォーマンス的に、天然ガスと石炭に勝てないのが現状です。
微生物は大規模かつ長期のシーケンスコントロールが難しいですよね。不安定なので維持管理コスト。
理論上は、食用に耐えうる炭水化物(やタンパク質)を安価な核反応熱から合成できれば、食糧問題は一気に解決するわけですが・・・。
智山さん
198のご意見、概ね同意します。
太陽光なんかよりも、効率よくて安定な小水力や地熱、風力などまだマシなエネルギーを先に長期的に入れていくことは良いとしても、とても原発の代わりにはなりません。
原発の新設を民主的プロセスで国民同意が得られないのであれば、電力需要を下げるほかありません。
できるだけ民主的なプロセスで、電力需要を抑えるには、電力料金を上げるのが最も効率的な意思決定メカニズムかと思いますが、日本にはまだまだ工業産業がありますので、いきなり高額にしては国内の産業が干上がってしまいます。
例えば、今回の事故が起きるまで、福島原発の恩恵に授かっていて、まずは、現在計画停電を受けていない特権地域の23区内の電力料金を値上げ(災害援助増税)して、自主的な省エネ努力に任せるのが最も効率が良いかなと思います。
そして、23区内の冷暖房はガス化優遇補助をすればいい。GHPなど、良い製品があります。
198のご意見、概ね同意します。
太陽光なんかよりも、効率よくて安定な小水力や地熱、風力などまだマシなエネルギーを先に長期的に入れていくことは良いとしても、とても原発の代わりにはなりません。
原発の新設を民主的プロセスで国民同意が得られないのであれば、電力需要を下げるほかありません。
できるだけ民主的なプロセスで、電力需要を抑えるには、電力料金を上げるのが最も効率的な意思決定メカニズムかと思いますが、日本にはまだまだ工業産業がありますので、いきなり高額にしては国内の産業が干上がってしまいます。
例えば、今回の事故が起きるまで、福島原発の恩恵に授かっていて、まずは、現在計画停電を受けていない特権地域の23区内の電力料金を値上げ(災害援助増税)して、自主的な省エネ努力に任せるのが最も効率が良いかなと思います。
そして、23区内の冷暖房はガス化優遇補助をすればいい。GHPなど、良い製品があります。
原発導入のシナリオ
冷戦下の対日原子力戦略
http://bit.ly/gl8aSO
これはわかりやすいです。
核開発で予想以上にイニシアチブがとれない事を理解したアメリカは、寧ろ平和利用を推進する事で核開発を管理し、優位性を維持しようとした。
そんなさなか第五福竜丸事件が発生し、日本では反原発・反米ムードが高まり、共産主義勢力がその動きを利用しようとしていた。
日本テレビ幹部の柴田は、これに歯止めをかけるには、毒をもって毒を制す、原子力の平和利用しかないと考える。読売新聞社主の正力は、自らのマイクロ波放送網構想の夢の実現の為、総理になるためにCIAに恩を売りつつ実績を上げるのに、原発が格好の題材と判断。電力不足に悩む産業界や、職のない原子力科学者の賛同を得られると・・・
こうした米国の国際政治上の思惑の上で導入された原発は、必ずしも電力として絶対の選択肢ではなかった。
原発導入の判断は、敗戦が根にある。仕方が無い。
では、今後は?
私は今までは必要なかったかも知れないが、寧ろこれから必要なんだと思ってます。
冷戦下の対日原子力戦略
http://bit.ly/gl8aSO
これはわかりやすいです。
核開発で予想以上にイニシアチブがとれない事を理解したアメリカは、寧ろ平和利用を推進する事で核開発を管理し、優位性を維持しようとした。
そんなさなか第五福竜丸事件が発生し、日本では反原発・反米ムードが高まり、共産主義勢力がその動きを利用しようとしていた。
日本テレビ幹部の柴田は、これに歯止めをかけるには、毒をもって毒を制す、原子力の平和利用しかないと考える。読売新聞社主の正力は、自らのマイクロ波放送網構想の夢の実現の為、総理になるためにCIAに恩を売りつつ実績を上げるのに、原発が格好の題材と判断。電力不足に悩む産業界や、職のない原子力科学者の賛同を得られると・・・
こうした米国の国際政治上の思惑の上で導入された原発は、必ずしも電力として絶対の選択肢ではなかった。
原発導入の判断は、敗戦が根にある。仕方が無い。
では、今後は?
私は今までは必要なかったかも知れないが、寧ろこれから必要なんだと思ってます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ピークオイル 更新情報
ピークオイルのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 89995人
- 3位
- 酒好き
- 170658人