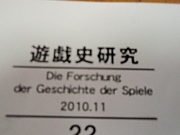開催終了第二回遊戯史ミニ研究会 10/3
詳細
2010年09月29日 15:32 更新
正規の遊戯史学会のような講義→論文形式でなく、リポーターに紙一枚程度のレジュメで20分以内の発表をしてもらい、みんなで質疑応答→討議をしながらゲームの歴史を考えようという、ミニ研究会を開催します。ゲームの歴史に興味のある方なら、どなたでも歓迎です。
どちらかと言えば硬い発表より自由な討議に時間と重点を置き、場合によっては実技を加え、楽しくかつ真摯な研究会にしようという計画です。
このミニ研究会については既に会長に了承を戴き、事後に理事会にも簡単な報告を提出する約束です。理事会の要請があれば、総会への報告もいたします。
場所は、第二回も上石神井の草場宅(03-3929-5558)です。第三回以降も同所で、第三回は二月六日日午後一時からを考えています。
参加費は、遊戯史学会員は無料で、非会員は一人二百円戴きます。これは茶菓代と通信費に充てるものです。
第二回研究会の内容
?挨拶・新聞記事等提供
?参加者の自己紹介と近況報告(一人1〜5分)
?リポート? 熊谷さん「象棋の起源について」
質疑・討議
―休憩―
?リポート? 溝口さん「『普通唱導集』の大将棋について」
質疑・討議
?情報交換・意見交換
?第三回研究会について
?歓談
なお、「前回のリポート三つは多すぎた」という意見が寄せられましたので、今回は二本にしてみました。様子を見ながら今後の方向を決めて行きたいと思います。
また、今回はたまたま二本とも広い意味の将棋系ですが、できたらバラエティに富んだリポートを目指したいと考えています。会長からも「カードゲームの研究も欲しい」というお話も戴いています。皆さんのご協力を期待します。
今回は越智さんの提案を戴きまして、可能な方には新聞記事・週刊誌・新刊本等々から遊戯史関係・ゲーム関係と思われる記事を切り抜いたりコピーしたりして持ってきていただき、できたら?の挨拶の前に戴いて?の後の休憩時間にコピーし、?の最初に皆さんに配布しようと考えています。ご提供をお願いします。(無理にとは申しません。)
また、最初の自己紹介の時間に一人五分以内で、自分の興味のある対象や近況などを全員に一言ずつ言っていただく予定です。遊戯史学会員は一分以上の発言をお願いします。(会員以外は本当に一言でも構いません。)
なお、時刻については前回は午後二時開始でしたが、今回は午後一時開始ですのでお間違いなきよう。時間通り正確に始めたいので、ご協力を宜しくお願いします。なお開場は正午です。
?の終了は午後四時を予定しています。その後はお帰りになっても構いませんし、自由に意見交換・歓談などをしていただいても構いません。午後五時に閉場の予定ですが、若干の余裕はあります。
ご質問についてはコメント戴ければ回答します。
なお会場は、西武新宿線上石神井駅北口下車徒歩8分、新青梅街道沿いの上石神井ビューハイツの五階の一番奥です。上石神井は高田馬場から急行か準急で二駅目、13分二百円です。
どちらかと言えば硬い発表より自由な討議に時間と重点を置き、場合によっては実技を加え、楽しくかつ真摯な研究会にしようという計画です。
このミニ研究会については既に会長に了承を戴き、事後に理事会にも簡単な報告を提出する約束です。理事会の要請があれば、総会への報告もいたします。
場所は、第二回も上石神井の草場宅(03-3929-5558)です。第三回以降も同所で、第三回は二月六日日午後一時からを考えています。
参加費は、遊戯史学会員は無料で、非会員は一人二百円戴きます。これは茶菓代と通信費に充てるものです。
第二回研究会の内容
?挨拶・新聞記事等提供
?参加者の自己紹介と近況報告(一人1〜5分)
?リポート? 熊谷さん「象棋の起源について」
質疑・討議
―休憩―
?リポート? 溝口さん「『普通唱導集』の大将棋について」
質疑・討議
?情報交換・意見交換
?第三回研究会について
?歓談
なお、「前回のリポート三つは多すぎた」という意見が寄せられましたので、今回は二本にしてみました。様子を見ながら今後の方向を決めて行きたいと思います。
また、今回はたまたま二本とも広い意味の将棋系ですが、できたらバラエティに富んだリポートを目指したいと考えています。会長からも「カードゲームの研究も欲しい」というお話も戴いています。皆さんのご協力を期待します。
今回は越智さんの提案を戴きまして、可能な方には新聞記事・週刊誌・新刊本等々から遊戯史関係・ゲーム関係と思われる記事を切り抜いたりコピーしたりして持ってきていただき、できたら?の挨拶の前に戴いて?の後の休憩時間にコピーし、?の最初に皆さんに配布しようと考えています。ご提供をお願いします。(無理にとは申しません。)
また、最初の自己紹介の時間に一人五分以内で、自分の興味のある対象や近況などを全員に一言ずつ言っていただく予定です。遊戯史学会員は一分以上の発言をお願いします。(会員以外は本当に一言でも構いません。)
なお、時刻については前回は午後二時開始でしたが、今回は午後一時開始ですのでお間違いなきよう。時間通り正確に始めたいので、ご協力を宜しくお願いします。なお開場は正午です。
?の終了は午後四時を予定しています。その後はお帰りになっても構いませんし、自由に意見交換・歓談などをしていただいても構いません。午後五時に閉場の予定ですが、若干の余裕はあります。
ご質問についてはコメント戴ければ回答します。
なお会場は、西武新宿線上石神井駅北口下車徒歩8分、新青梅街道沿いの上石神井ビューハイツの五階の一番奥です。上石神井は高田馬場から急行か準急で二駅目、13分二百円です。
コメント(14)
2010年10月03日 23:20
第二回研究会の記録
参加:草、本、溝、田、熊、岸、越、小、岡、熊。10名
進行
?挨拶・新聞記事等提供
?参加者の自己紹介と近況報告(一人1〜5分)
詳細は省きますが、一人一人自己紹介と近況報告を行いました。
?リポート? 熊谷さん「象棋の起源について」/質疑・討議
熱心な議論が行われました。
―休憩―
?リポート? 溝口さん「『普通唱導集』の大将棋について」/質疑・討議
熱心な議論が行われました。
?情報交換・意見交換
新聞記事の解説、11月27日大阪で開かれる遊戯史学会について(参加5名!)
?第三回研究会について
2011年2月6日日曜日午後一時から五時、上石神井。
?歓談
反省
・大変議論が盛り上がってよかった。
・実際の大将棋の駒を使っての説明は分かりやすかった。→盤駒の提供、多謝。
・リポートは二本で丁度よい。 →次回も二本で。
・次回はカードゲームの発表を。 →その方向で。
・参加者全員が名札をつけるとよい。 →次回から準備します。
・越智さんから事前に郵送して貰っていた新聞記事を、複写・配布し忘れた。→参加者に郵送します。
2010年10月11日 08:42
先日の遊戯史ミニ研究会には突然の参加にも関わらず、暖かく迎えていただきありがとうございました。
その席で話題になったことの一つに「なぜ、将棋は大型化したか?」ということがあります。
研究会の席では
? 庶民は覚えやすく道具が少なくてすむ小将棋、金と時間がある僧侶や貴族は、手間暇のかかる大将棋を好んだ。
? 思いつきで大型の将棋を考え出すこともある。
という2つの考え方を教えていただきました。
家に帰ってからふと思いついたことがありますので、皆さんからのご意見をいただきたいと思います。
「簡単なゲームほど奥が深い」
と。言います。囲碁がそうですし、現行将棋もそうでしょう。
小将棋では、簡単に技量の差がついてしまい、強い人はいつも勝ち、弱い人はいつも負け。そこで、強い人でも覚えるのが大変な大型の将棋(例えば、二中歴大将棋)が考案された。ところが、強い人はそれでもすぐ強くなってしまう。
そこでさらに複雑な将棋、もっと覚えるのが大変な将棋、と次々に考案されて、多様な大型の将棋が生み出されたのではないでしょうか?
大型の将棋を考えてみると、最初のうちこそ、強い弱いに関係なく遊べましたが、大型になればなるほど覚えるのも大変なため、指せる人がいなくなってしまいます。(研究会でも、「泰将棋などは実際に指されたことはないのではないか。」と言われていましたね。)
それで、結局、誰でも指せる小将棋系の現行将棋に落ち着き、技量の差は駒落ちなどで調整するようになったと思います。
実際、西洋のクーリエ(西洋大将棋)もあまり普及しなかったようです。モンゴルのヒアシャタルはおそらく事情が違う(ヒアのあるシャタルの方が面白い?)でしょうから、すべてそうとは言い切れませんが、世界的にも大型の将棋が考案されても、残ったのが8〜9マス、6〜8種類のコマの将棋というのには、やはり「覚えやすく奥が深い」のはこの辺りという共通認識があるためではないかと思いますが、いかがでしょうか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
困ったときには