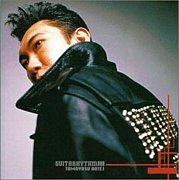開催終了聖書講座「聖書と現代社会――共同幻想の諸相――」第1回
詳細
2012年04月18日 16:13 更新
講師 上村 静
と き:第3土曜日3時〜5時
ところ:寿地区センター
参加費:一般¥1,000/回 学生\500/回
【講座の概要】
現代社会では、<いのち>を生かすためのさまざまな働きがなされている一方で、<いのち>を暴力的に奪う試みが繰り返されている。さまざまな社会問題は認識されているけれども、その解決への兆しは見られず、むしろときに隠蔽され、あるいは露骨な形で正当化されている。
地震と津波による大きな被災に対しては、多くの善意が寄せられた。そこには被災者の苦しみへの共感・思いがあったことはたしかであろう。けれども、その善意は必ずしもすべてがよい結果につながったとは言えない。「善意」はときに自己満足に終わってしまう。他方、原発事故は二重の意味で人災であった。政官財学マスコミが「安全神話」を勝手に捏造し、原発を建設したこと自体がすでに人災であったし、事故の後になお「安全」を繰り返し喧伝し、被爆者を増やし続けている。この「神話」はすでに崩壊したはずなのに、「がんばろうニッポン!」という掛け声のもとに、再構築されようとしている。
「被災者」という言葉自体がひとつのレッテルである。たしかに多くの人が被災したが、しかしそれぞれにはそれぞれの人生がある。「被災者」とひとくくりにして「善意」を押しつけることは、「差別」と同じ構造を有している。被災した人たちは、たまたま「日本」にいて被害にあったが、だからといって「ニッポン」の復興と関連づけられるいわれはない(そもそも「被災者」のすべてが「日本人」なわけではないはずだが、「在日外国人」については、「美談」は語られても「被害」は伝えられない)。彼らにはそれぞれの人生を再構築する権利がある。「ニッポン」なるものに彼らの人生が回収させられねばならないわけではない。それにもかかわらず、「がんばろうニッポン」、「がんばろう東北」、「がんばろう福島」などの空虚な標語が国家・マスコミによって喧伝され、「ニッポン」や「東北」や「福島」などという実体のないたんなる行政区分のために、いわれなき忍耐を強要されている。それとともに、自分の人生を生きたいと思うごくあたり前の感覚にしたがおうとする人たちを白眼視する風潮が生まれている。「被災者」は、お上にとって聞き分けのいい「被害者」と、お上にしたがわない「困った者」に二分されている。そして後者は切り棄てられる(この棄民国家においてはやがて前者も棄てられるし、今はまだ「被災者」と認定されていない無数の被爆者たちも切り棄てられるだろう)。
こうした<いのち>の切り棄ては、「ニッポン」なるものが個々の生身の<いのち>よりも優先されることに起因する。だが、その「ニッポン」とはなんなのか?
国家や民族は、抽象概念であって、実体として存在するものではない。それは「想像の共同体」(アンダーソン)であり、「共同幻想」(吉本隆明)に過ぎない。「想像」や「幻想」は、まさに虚構でしかないはずなのに、その虚構上のイメージのために、現実の生身の<いのち>は実に頻繁に虐殺され続けている。この虐殺がもっともあからさまに正当化されるのが「戦争」である。今回の原発人災がしばしば戦争と対比的に論じられるのは、両者に同根の問題が内包されているからである。
共同幻想は虚構である。そのことはすでに多くの人が認識している。しかし、それにもかかわらず、共同幻想は解体されないし、仮に既存の共同幻想が解体されたとしても、新たな共同幻想が生み出されるであろう。なぜなら、人は他者との幻想の共有を欲するからである。人は独りでは生きられないし、裸の自分、剥き出しの一人だけの自分で生きることに耐えられない。人間存在は、自分でも認識しきれないほどの多様性をもっているが、まさにそれゆえに自分自身のアイデンティティを確立することができない。それゆえ他者と共有できる属性に自らのアイデンティティを委ねたいのである。こうして自らの持つ多様性を犠牲にした上で、ごくわずかの属性をもってなんらかの集団アイデンティティに自らを固着させ、安心したいと願う。すなわち、共同幻想は、自分が自分であるという認識を集団に帰属させることで確認しようとする自我の欲求に由来する。「わたしたち」の一人であることで、独りではないことを確認し、安心したいのである。それゆえこの幻想を揺さぶる存在は「敵」とされる。<いのち>の抹殺が正当化されるのはこのときである。
こうしてわれわれは袋小路につきあたる。共同幻想は虚構に過ぎないのだから解体してしまえばそれでよさそうなものであるが、おそらく一切の共同幻想から解き放たれた個として生きられる人間、自我の存在確認への欲求を抑制できる人間はそう多くはないだろう。ではどうしたらよいのか。<いのち>の尊厳を守り、<いのち>の抹殺を許さない共同幻想はないだろうか?
本講座ではこうした問題を考える。その切り口として、<いのち>のあり方と共同幻想のもたらす諸問題に焦点を当てる。その際、聖書のいくつかの記事を参照する。聖書は古代人の書いたものではあるけれども、その<いのち>のあり方についての洞察には、現代を生きるわれわれにも学ぶべきところがあるからである。<いのち>を生かしまた殺す社会のあり様は、古代も現代もさして変わるところはない。
本講座はこれまでの講義形式ではなく、受講者の発題と受講者同士の対論を中心に据えたセミナー形式で展開したい。本講であつかう諸問題に「正解」はない。各人が各人なりに相対的な正解を見出してもらえればそれでよいし、またそれが相対的なものに過ぎないことを知るためにも、受講者同士の対論が必須である。受講者には積極的な議論への参加が望まれる。
具体的な講座の進め方は、初回に次回以降の発題者と発題テーマを割り当てる。発題者には、下記「講座スケジュール」に挙げた現代社会の諸問題のなかから興味のあるテーマを一つ選び、そのテーマにおいて「何が問題とされているか」について発題してもらう(論じたいテーマがあれば自由に設定することも可能)。一つのテーマであっても、それが内包する課題は多様であるから、発題者はあくまでも自分の問題意識に応じて可能な範囲で調べられたことを発題してもらえれば十分である。その他の受講者には時間の許す範囲で下調べをしてきてもらえればありがたい。自分の体験や見聞を紹介していただくだけでも十分である。
毎回の講座は、前半が発題にもとづく議論、後半が聖書にもとづく議論から構成される。こうして現代社会の諸問題が聖書をとおして考察されるとともに、聖書の記述が現代の視点から解釈される。
古代の叡智から学び、それによって古典たる聖書を現代においてなお有意義なものとして再活性化させること、古代と現代の交錯がこの「聖書講座」の狙いである。
【講座スケジュール】 全10回
第1回(4/21) ガイダンス――人間の尊厳と共同幻想の暴力(「天地創造」)
第2回(5/19) 差別問題1――共同幻想の現実(「癒しの奇跡物語」)
少数者差別――同性愛者差別、性同一性障害者差別
弱者差別――ハンセン病者差別、障碍者差別
第3回(6/16) 差別問題2――共同幻想の再生産(「徴税人との会食物語」「見失われた羊のたとえ」)
社会差別――部落差別、「フクシマ」差別
第4回(7/21) 「生命」の終わりと<いのち>――「私の生命」という共同幻想(「安息日問答」)
生命倫理1――終末期医療問題
第5回(10/20) 「生命」のはじまりと<いのち>――「私のいのち」という共同幻想(「失楽園」、「永遠の生命」)
生命倫理2――中絶問題、自傷・自殺問題
第6回(11/17) 人間存在の価値――功績主義の共同幻想(「ぶどう園の労働者」、「放蕩息子」)
序列化への志向1――ホームレス問題、いじめ問題
第7回(12/15) 人間存在の意味――人生の「意味」という共同幻想(「コヘレトの言葉」)
序列化への志向2――格差社会の問題、国際間格差の問題
第8回(1/19) 民族主義と国家主義――「国民」という共同幻想(「善きサマリア人の譬え」)
パレスチナ問題、在日外国人問題、外国人労働者問題、難民申請者問題、日の丸・君が代問題
第9回(2/16) 虚構なる集団アイデンティティ――共同幻想の克服(「自ずから育つ種」、「思い煩うな」)
原発人災、「がんばろうニッポン!」、「公同の教会」
第10回(3/16) まとめ――共同幻想の脱構築(「モーセ五書」)
天皇制と憲法9条
【テキスト】
聖書(旧約・新約)
【参考文献】
上村静『宗教の倒錯――ユダヤ教・イエス・キリスト教』岩波書店、2008
上村静『旧約聖書と新約聖書――「聖書」とはなにか』新教出版社、2011
(これらの参考文献は講座で直接的にあつかうことはしない。各人で読了していただきたい。質問はいつでも歓迎する。)
コメントを書く(全角2000文字以内)
と き:第3土曜日3時〜5時
ところ:寿地区センター
参加費:一般¥1,000/回 学生\500/回
【講座の概要】
現代社会では、<いのち>を生かすためのさまざまな働きがなされている一方で、<いのち>を暴力的に奪う試みが繰り返されている。さまざまな社会問題は認識されているけれども、その解決への兆しは見られず、むしろときに隠蔽され、あるいは露骨な形で正当化されている。
地震と津波による大きな被災に対しては、多くの善意が寄せられた。そこには被災者の苦しみへの共感・思いがあったことはたしかであろう。けれども、その善意は必ずしもすべてがよい結果につながったとは言えない。「善意」はときに自己満足に終わってしまう。他方、原発事故は二重の意味で人災であった。政官財学マスコミが「安全神話」を勝手に捏造し、原発を建設したこと自体がすでに人災であったし、事故の後になお「安全」を繰り返し喧伝し、被爆者を増やし続けている。この「神話」はすでに崩壊したはずなのに、「がんばろうニッポン!」という掛け声のもとに、再構築されようとしている。
「被災者」という言葉自体がひとつのレッテルである。たしかに多くの人が被災したが、しかしそれぞれにはそれぞれの人生がある。「被災者」とひとくくりにして「善意」を押しつけることは、「差別」と同じ構造を有している。被災した人たちは、たまたま「日本」にいて被害にあったが、だからといって「ニッポン」の復興と関連づけられるいわれはない(そもそも「被災者」のすべてが「日本人」なわけではないはずだが、「在日外国人」については、「美談」は語られても「被害」は伝えられない)。彼らにはそれぞれの人生を再構築する権利がある。「ニッポン」なるものに彼らの人生が回収させられねばならないわけではない。それにもかかわらず、「がんばろうニッポン」、「がんばろう東北」、「がんばろう福島」などの空虚な標語が国家・マスコミによって喧伝され、「ニッポン」や「東北」や「福島」などという実体のないたんなる行政区分のために、いわれなき忍耐を強要されている。それとともに、自分の人生を生きたいと思うごくあたり前の感覚にしたがおうとする人たちを白眼視する風潮が生まれている。「被災者」は、お上にとって聞き分けのいい「被害者」と、お上にしたがわない「困った者」に二分されている。そして後者は切り棄てられる(この棄民国家においてはやがて前者も棄てられるし、今はまだ「被災者」と認定されていない無数の被爆者たちも切り棄てられるだろう)。
こうした<いのち>の切り棄ては、「ニッポン」なるものが個々の生身の<いのち>よりも優先されることに起因する。だが、その「ニッポン」とはなんなのか?
国家や民族は、抽象概念であって、実体として存在するものではない。それは「想像の共同体」(アンダーソン)であり、「共同幻想」(吉本隆明)に過ぎない。「想像」や「幻想」は、まさに虚構でしかないはずなのに、その虚構上のイメージのために、現実の生身の<いのち>は実に頻繁に虐殺され続けている。この虐殺がもっともあからさまに正当化されるのが「戦争」である。今回の原発人災がしばしば戦争と対比的に論じられるのは、両者に同根の問題が内包されているからである。
共同幻想は虚構である。そのことはすでに多くの人が認識している。しかし、それにもかかわらず、共同幻想は解体されないし、仮に既存の共同幻想が解体されたとしても、新たな共同幻想が生み出されるであろう。なぜなら、人は他者との幻想の共有を欲するからである。人は独りでは生きられないし、裸の自分、剥き出しの一人だけの自分で生きることに耐えられない。人間存在は、自分でも認識しきれないほどの多様性をもっているが、まさにそれゆえに自分自身のアイデンティティを確立することができない。それゆえ他者と共有できる属性に自らのアイデンティティを委ねたいのである。こうして自らの持つ多様性を犠牲にした上で、ごくわずかの属性をもってなんらかの集団アイデンティティに自らを固着させ、安心したいと願う。すなわち、共同幻想は、自分が自分であるという認識を集団に帰属させることで確認しようとする自我の欲求に由来する。「わたしたち」の一人であることで、独りではないことを確認し、安心したいのである。それゆえこの幻想を揺さぶる存在は「敵」とされる。<いのち>の抹殺が正当化されるのはこのときである。
こうしてわれわれは袋小路につきあたる。共同幻想は虚構に過ぎないのだから解体してしまえばそれでよさそうなものであるが、おそらく一切の共同幻想から解き放たれた個として生きられる人間、自我の存在確認への欲求を抑制できる人間はそう多くはないだろう。ではどうしたらよいのか。<いのち>の尊厳を守り、<いのち>の抹殺を許さない共同幻想はないだろうか?
本講座ではこうした問題を考える。その切り口として、<いのち>のあり方と共同幻想のもたらす諸問題に焦点を当てる。その際、聖書のいくつかの記事を参照する。聖書は古代人の書いたものではあるけれども、その<いのち>のあり方についての洞察には、現代を生きるわれわれにも学ぶべきところがあるからである。<いのち>を生かしまた殺す社会のあり様は、古代も現代もさして変わるところはない。
本講座はこれまでの講義形式ではなく、受講者の発題と受講者同士の対論を中心に据えたセミナー形式で展開したい。本講であつかう諸問題に「正解」はない。各人が各人なりに相対的な正解を見出してもらえればそれでよいし、またそれが相対的なものに過ぎないことを知るためにも、受講者同士の対論が必須である。受講者には積極的な議論への参加が望まれる。
具体的な講座の進め方は、初回に次回以降の発題者と発題テーマを割り当てる。発題者には、下記「講座スケジュール」に挙げた現代社会の諸問題のなかから興味のあるテーマを一つ選び、そのテーマにおいて「何が問題とされているか」について発題してもらう(論じたいテーマがあれば自由に設定することも可能)。一つのテーマであっても、それが内包する課題は多様であるから、発題者はあくまでも自分の問題意識に応じて可能な範囲で調べられたことを発題してもらえれば十分である。その他の受講者には時間の許す範囲で下調べをしてきてもらえればありがたい。自分の体験や見聞を紹介していただくだけでも十分である。
毎回の講座は、前半が発題にもとづく議論、後半が聖書にもとづく議論から構成される。こうして現代社会の諸問題が聖書をとおして考察されるとともに、聖書の記述が現代の視点から解釈される。
古代の叡智から学び、それによって古典たる聖書を現代においてなお有意義なものとして再活性化させること、古代と現代の交錯がこの「聖書講座」の狙いである。
【講座スケジュール】 全10回
第1回(4/21) ガイダンス――人間の尊厳と共同幻想の暴力(「天地創造」)
第2回(5/19) 差別問題1――共同幻想の現実(「癒しの奇跡物語」)
少数者差別――同性愛者差別、性同一性障害者差別
弱者差別――ハンセン病者差別、障碍者差別
第3回(6/16) 差別問題2――共同幻想の再生産(「徴税人との会食物語」「見失われた羊のたとえ」)
社会差別――部落差別、「フクシマ」差別
第4回(7/21) 「生命」の終わりと<いのち>――「私の生命」という共同幻想(「安息日問答」)
生命倫理1――終末期医療問題
第5回(10/20) 「生命」のはじまりと<いのち>――「私のいのち」という共同幻想(「失楽園」、「永遠の生命」)
生命倫理2――中絶問題、自傷・自殺問題
第6回(11/17) 人間存在の価値――功績主義の共同幻想(「ぶどう園の労働者」、「放蕩息子」)
序列化への志向1――ホームレス問題、いじめ問題
第7回(12/15) 人間存在の意味――人生の「意味」という共同幻想(「コヘレトの言葉」)
序列化への志向2――格差社会の問題、国際間格差の問題
第8回(1/19) 民族主義と国家主義――「国民」という共同幻想(「善きサマリア人の譬え」)
パレスチナ問題、在日外国人問題、外国人労働者問題、難民申請者問題、日の丸・君が代問題
第9回(2/16) 虚構なる集団アイデンティティ――共同幻想の克服(「自ずから育つ種」、「思い煩うな」)
原発人災、「がんばろうニッポン!」、「公同の教会」
第10回(3/16) まとめ――共同幻想の脱構築(「モーセ五書」)
天皇制と憲法9条
【テキスト】
聖書(旧約・新約)
【参考文献】
上村静『宗教の倒錯――ユダヤ教・イエス・キリスト教』岩波書店、2008
上村静『旧約聖書と新約聖書――「聖書」とはなにか』新教出版社、2011
(これらの参考文献は講座で直接的にあつかうことはしない。各人で読了していただきたい。質問はいつでも歓迎する。)
コメントを書く(全角2000文字以内)
- 2012年04月21日 (土) 土曜 午後3時〜5時
- 神奈川県 寿地区センター 横浜市寿町3-10-13 金岡ビル305 JR関内駅・石川町駅から徒歩7分
- 2012年04月21日 (土) 締切
- 参加者
- 1人
困ったときには