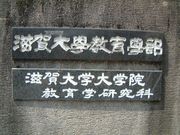滋賀大学教育学部コミュのAIで昭和のロボット「パロ、AIBOLOVOT」復活か? 人を癒やすコミュニケーションロボット再ブームの“真相” アメリカでは《医療ロボ》として活用。 ■ロボットが実現する新たな医療福祉 ギネス記録を持つロボットといわれたら、何を想像するでしょうか。 実用的に活躍するロボットとしては「世界一癒し効果のあるロボット」という記録があります。 実は、日本生まれのアザラシ型ロボット「パロ」がその称号を持っています。 1993年から研究が始まったパロは、2002年にギネス世界記録で「最もセラピー効果のあるロボット」として認定されました。 パロのギネス認定は、決して偶然ではありません。 アメリカでは「神経学的セラピー用医療機器」の承認を得た初めての医療ロボットとなっており、認知症、発達障害、精神障害、PTSD、脳機能障害、がん患者などを対象として、1台42万円で売り出され、いまや30カ国以上で約5000体が利用されているのです。 パロの導入効果は目覚ましいものがあります。パロとの触れ合いにより、ストレスも低減され、不安、うつ、痛み、孤独感を改善することが示されています。 特に認知症者の場合には、徘徊、暴力、暴言といった問題行動や昼夜逆転の生活スタイルを抑制・緩和することも確認されているのです。 患者本人への効果はもちろんのこと、これらの効果は介護者の負担を軽減することにもつながります。ロボットを用いた治療は、副作用がない「非薬物療法」としてまったく新しい医療福祉サービスのかたちなのです。 少し想像してみてください。 オフィスの一角で、小さなロボットが社員たちと和やかに会話を交わしています。また別の机では、仕事に疲れた社員がロボットに話しかけています。このロボット、実は社員のメンタルヘルスケアを担当しているのです。 こんなシーンがすでに一部の会社では日常になりつつあります。 高度なAIを搭載したロボットは「AIロボット(Embodied AI/ Physical AI)」とも呼ばれています。 このような進歩によって、人間とロボットのより自然なコミュニケーションが可能になり、コミュニケーションロボットは再び脚光を浴びているのです。 興味深いのは、これらのロボットの開発に携わる企業の顔ぶれです。 従来の家電メーカーやロボットメーカーに加え、ミクシィやサイバーエージェントといったIT企業やモバイルゲーム企業も参入し、業界に新たな風を吹き込んでいます。 現在のコミュニケーションロボットは、2つのタイプに大別されます。 ひとつは「言語コミュニケーション型」で、人間との会話を主な機能とするロボット。もうひとつは表情や動作で感情を表現する「非言語コミュニケーション型」です。 たとえば、ソフトバンクの「Pepper」は言語コミュニケーション型の代表格です。 一方、ソニーの新型「AIBO」やGROOVE Xの「LOVOT(らぼっと)」は、愛らしい仕草や表情で人間の心を癒す非言語コミュニケーション型に分類されます。 使い方も多様化しています。家庭での利用(B2C)だけでなく、企業での活用(B2B)も急速に広がっているのです。オフィスで活用することによる社内コミュニケーションの促進、新入社員教育支援、店舗での顧客対応サポートなどです。 コクヨなどが行った調査では、約4割の人が「コミュニケーションロボットがいるから出社しよう」と出社の動機になるといいます。実際に87.6%の従業員がロボットのおかげでコミュニケーションが活性化したと感じています。 このような背景から、会社の福利厚生の一環としてロボットの導入が進められる事例も出てきています。 ■AIロボットとの共存時代の幕開け もちろん、課題がないわけではありません。 ロボットが収集する個人情報の管理といったプライバシーの問題や、より複雑な環境下でのロボットの音声認識、画像認識、データ分析などの能力は、今後さらなる対応が必要になってくるでしょう。 特にプライバシーの問題は、欧州で制定された「一般データ保護規則(GDPR)」など個人データの保護とも関連し、人の身近な場所で使われるロボットならではのアプローチも必要になってくるかもしれません。 これらの課題を克服しつつ、人間とロボットが共生する社会の実現に向けて、着実に技術開発と社会実装が進められています。 コミュニケーションロボットの再ブームは、単なるガジェットの流行ではありません。 AIロボットとの共存時代の幕開けを告げる重要な現象なのです。今後、私たちの生活や仕事がどのように変わっていくのかに影響するひとつの要素であることは間違いなさそうです。
困ったときには