- 詳細 2017年12月2日 11:31更新
-
運営期間2128日にして、22人。
97日に1人のペースでの人口増加です。
これは日本の出生率より厳しい事になっているのではないでしょうか。
さて、再度仕切り直し。
おれは一人で生きて生ける。ふふ。冗談はやめて下さい。
わたしは一人で生きてきた!ふふ。冗談は顔だけにして下さい。
『人生の意義』
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
人生の意義(じんせいのいぎ、The meaning of life)は、人間の発する究極の問いのひとつ。
自然な日本語では「人生の意義」などとは表現せず、むしろ「生きがい」という表現のほうが定着している[1]。
目次 [非表示]
1 概要
2 ヴィクトール・フランクルの思想
3 神谷美恵子による研究
3.1 生存目標の喪失と喪失した人の心の世界
3.2 新しい生存目標
3.3 生きがいと宗教
4 参考文献
5 関連書
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
[編集]概要
この問いは、数ある哲学的な問いの中でも、おそらく最も古くから存在し、普遍的に存在する問いであり、多くの人間が想い抱く問いであるといえよう。「意義」という語が多くの解釈を持ち得ることもあって、この問いは漠然としている。「生きる事・人生の意義とは何か?」というこの問いに対する直接的な回答よりも、それを考えること自体に比重が置かれている場合もあり、人により様々な意味あいを持っている。
人が生きていく時間は長く、また、様々な思いが生まれ出てから果てるまで交錯する中で、自分自身の生を意識することが、また、他人の生を意識することが、人の常であるためである。この命題を問い掛けるもの、思い悩むものは、古今東西を問わず、様々な場所で見出される。
この問いは、経済的に豊かな国でほど切実な問題となってくる傾向がある。経済的・物質的に豊かな国の人々ほど、ひどい「空虚感」や「心のむなしさ」にさいなまれている人の数が増える傾向がある。アブラハム・マズローは人間は基本的欲求のすべてを満たして、ようやく「自己実現の欲求」といった高次欲求にかられ始める、と言っているが、「豊かな社会」は基本的欲求を満たしやすい社会なので、高次の欲求が発現しやすく、それが満たされない苦しみにさいなまれやすい、という面がある。[2]
この問いは、そもそも自身の価値観の決定あるいは態度決定に関する問いであって、普遍的な事実に関する問いというわけではないので、学問や科学は、この問いに対する解答を与えてくれはしない[3]。
人が感銘を受ける模範解答の多くは、宗教や哲学に存在している。あるいは文学や音楽などの芸術作品にも数多く存在する。ただしそのいずれも、やはり万人に有効な普遍的回答、というわけではなく、人の一生は各個人に固有のものであるため、ひとりひとりが自分で回答を見出してゆく努力が必要とされる。
同様の問いとしては「幸福とは?」「人生において貴重なこととは?」などがある。同様の理由で、これらの命題についても万人に当てはまる結論が見出されているわけではなく、各人が自力で見出してゆく必要がある。
このような命題が人の心を捉える時期は3つある、とも言われる。ひとつは思春期であり、この期間を経た者の多くは、その段階なりの解答を持つ。中年期にもこのような問いが心を捉えることがある。これは「中年期の危機(en:Mid-life crisis)」などとも呼ばれる。深層心理学者のユングがこのような中年期の危機の問題に早くから関心を抱いた。 傍から見ると特に何の問題もない人で、むしろ財産・地位・家族などについては恵まれた状態の人に、このような問いで悩む人が多くいる。若いころに、「財産・地位・家族などを手に入れれば幸福になれるに違いない」と思い込み、ひたすら頑張ってきたのに、いざそれらを手に入れてみると、まったく幸福という実感が無く、自分の人生に「大切な何か」が欠けている、という気がして仕方なくなり、「人生のむなしさ」を痛感する人が多いのである。 この段階で、あらためて「残された人生で、私は何をすることを求められているのだろう?」「自分の人生を意味あるものにするためには、今後どう生きてゆけばいいのだろう?」という問いに真正面から向き合うことになるのである[4]。
そして老年期にも、このような問いが心をとらえることがある[5]。神谷美恵子は以下のことを指摘する。 「自分の存在は何かのため、またはだれかのために必要であるか」という問いに肯定的に答えられれば、それだけでも充分生きがいをみとめる、という人は多い。老年期の悲哀の大きな部分はこの問いに充分確信をもって答えられなくなることにあろう。よって老人に生きがい感を与えるには、老人にできる何らかの役割を分担してもらうほうがよい。また、愛情の関係としても老人の存在がこちらにとって必要なのだ、と感じてもらうことが大切である。[6]。
[編集]ヴィクトール・フランクルの思想
ヴィクトール・フランクルは以下のように述べた。
「人間が人生の意味は何かと問う前に、人生のほうが人間に対し問いを発してきている。だから人間は、本当は、生きる意味を問い求める必要などないのである。人間は、人生から問われている存在である。人間は、生きる意味を求めて問いを発するのではなく、人生からの問いに答えなくてはならない。そしてその答えは、それぞれの人生からの具体的な問いかけに対する具体的な答えでなくてはならない」
– ヴィクトール・フランクル 『死と愛』 みすず書房、1961年。(原題『医師による魂の癒し』)
多くの人は人生を「自分がしたいことをしてゆく場」と捉えてしまっている。このような「私のやりたいことをするのが人生だ」という人生観(欲望中心の価値観)に対し、フランクルは「私がなすべきこと、使命を実現してゆくのが人生だ」という価値観へと転換しているのである。
欲望中心の価値観では、例えば病気や人間関係等のトラブルはただの邪魔なものとしか眼に映らないが、「意味と使命中心の生き方」「なすべきことをなす生き方」では、それらのトラブルは何らかの意味がある、と受け止められるようになる。「これらの出来事を通して、人生が私に何かを問いかけてきている」「私に何を学ばせようとしているのだろう?」と受け止めることができるようになる、といったことをヴィクトール・フランクルは言っている。
そして「人生が自分に求めていること」を見つけるための手がかりとして、"三つの価値"を提示する。「創造価値」「体験価値」「態度価値」である。
創造価値
自分の仕事を通して実現される価値。これは大それたものである必要はなく、例えば、調理、コピーとり、清掃などでも。これによって助かる人、快適になる人がいる何かを提供している、ということ。
体験価値
人や自然と触れ合う体験によって何かを受け取ることができ、また何かが実現できる価値のこと。
態度価値
自分に与えられた運命に対してどういう態度をとるか。それによって実現されてゆく価値のこと。人生には、生まれつき決まってしまっている一種の「宿命」のようなものもあり、「運命」とも言えるものもあり、また生きている最中にはさまざまなことが起きる。このような「与えられたもの」に対してどういう態度をとりながら生きるかによって、その人の人生の真価がわかる、とフランクルは述べる。そして、この態度価値だけは、(前述の二つの価値とは異なり)人がいかなる苦境に追い込まれ、さまざまな能力や可能性が奪われても、実現の可能性がたたれることはない、と述べる。つまり、この価値をもってすれば、人は息を引き取るその瞬間まで、人生から意味が無くなることは無く、「人生の意味」は絶えず送り届けられ、発見され、実現されるのを待っている、ということになるのである[7]。
[編集]神谷美恵子による研究
日本語で「生きがい」と言うと、対象を指す場合と、感情を指す場合がある。生きがいを感じさせる対象を「生きがい」と呼び、それを感じる人の感覚・感情を「生きがい感」と呼び分けることもできる。人は長い一生の間にはふと立ち止まって自分の生きがいは何であろうか、と考えてみたりすることがあり、このようなときは、大まかにいって次のような問いが発せられるわけだろう、と神谷は述べる。
自分の生存は何かのため、またはだれかのために必要であるか。
自分固有の生きて行く目標は何か。あるとすれば、それに忠実に生きているか。[8]
人間が最も生きがいを感じるのは、自分がしたいと思うことと義務とが一致したときだと思われ、それは上記の問いの第一と第二が一致した場合であろう、と述べる。だが、これらは必ずしも一致しない。生活のための職業とは別に、ほんとうにやりたい仕事を持っている人も多い。それらの両立が困難になると、うっかりすると神経症になる人もあり、中には反応性うつ病や自殺にいたる人さえいる[9]。
「生きがい感」を一番感じている人種というのは、使命感に生きている人(自己の生存目標をはっきりと自覚し、自分の生きている必要を確信し、その目標にむかって全力で歩いている人)、ではないか、と述べる[10]。このような使命感の持ち主は、立派な肩書や地位を持って目立っているというわけではなく、むしろ人目につかないところに多くひそんでいて、例えば小、中学校の先生、特殊教育に従事する人、僻地の看護婦など、いたるところにいる、と述べる。
社会的にどんなに「立派」とされることをやっている人でも、自己に対してあわせる顔のない人は次第に自己と対面することを避けるようになる。心の日記もつけられなくなる。ひとりで静かにしていることも耐えられなくなり、自分の心の深いところからの声に耳をかすのも苦しくなる。すると、生活を忙しくして、この自分の心の深いところからの声が聞こえぬふりをするようになる。この、「自己に対するごまかし」こそが、生きがい感を何よりも損うものである、と指摘する[11]。
使命感に生きる人にとっては、たとえ使命半ばで倒れたとしても、事の本質は少しもちがわない。自己に忠実な方向に歩いているかどうかが問題なのであって、その目標さえが、正しいと信じるところに置かれているならば、使命の途上のどこで死んでも本望であろう、と述べる。これに対して、使命にもとっていた人(使命に背いていた人)は、安らかに死ぬことすらできない[12]。
[編集]生存目標の喪失と喪失した人の心の世界
難病にかかったり、恋人を失ったり、子供を失ったりするなどして生存目標を失うと、人は「前途が真っ暗な世界に閉ざされた」「世の中が真っ暗になった」「深い谷底につき落とされた」などといった感覚を味わうのであり[13]、ヤスパースやクーレンカンプが「足場」とか「立場」などと表現しているのは、決して抽象概念などではなく、人間の根源的な感覚に根ざした表現である[14]。 それまで生存目標としていたものが失われると、人はもはや何のために生きてゆくのか、何が大切なのか、判断の基準すら分からなくなる。つまり価値観が崩壊し、これは概念レベルにとどまらず、もっと根本的な生体験(感情や欲求や知覚)にも影響を及ぼす[15][16]。
[編集]新しい生存目標
新しい生存目標の発見は、自分自身の本質的なものの線に沿ったものではなくてはならない、と神谷は言う[17]。自分自身の本質に沿ったもので、これ以外に自分の生きる道はないのだ、とわかったら思い切ってそれを選びとるほかはない、この決断と選択と賭けの前にしり込みしたときには、いわゆる実存的欲求不満の種をまくことになり、後日に神経症や「にせの生き方」や自殺をひきおこす、と述べる[18]。
新しい生存目標は、かつてのものと比較して類似のものに変形したり、すっかり置き換えられたりする。人間への愛が生きがいという状態から、神への愛こそが生きがい、と変わる場合もある。神秘家などにこの例は多く、失恋を契機として修道院での人生を選ぶ人などもこの例にあたる[19]。生きがいの置き換えのことを、リボーは「情熱の置き換え」と呼んだ。例えばゴーギャンにおいては、株の仲買人で生きていたが、35歳の時その職を捨て、絵画に走り、現世的な幸福はすべて捨てさってしまった、という[20]。
結局、自分の内にさまざまの可能性を持っている人は、ひとつの生きがいを失っても、ほかの生存目標をみいだし、強く生きてゆけるのではないか、と言い、内在的傾向の複雑なひとほど生きがいの置き換え現象が起きやすいのだろう、とする[21]。また、ある事例を挙げて、全てのできごとを「天の摂理」として受け入れる素朴な宗教心をもっている人だと、新しい境遇に置かれればまたそこで新たな生きがいを見出すものだ、とも述べる[22]。
[編集]生きがいと宗教
宗教というものは現世において満たされない欲求を埋め合わすもので、代償と自己防衛の役割を果たしているものに過ぎない、などと考えてしまう人が多くいるが、もし仮にそのようなものだとしたら、現実の苦悩の原因がとりのぞかれれば宗教は必要でなくなってしまう、ということになるが、実際はそうではない[23]。
ゴードン・オールポートの著書に明快に書かれているように、宗教とは、人格に統一的な原理を与えるものであり、宗教とは、自我の成長の各段階において存在全体を意味づける前進的意図を用意するものである。宗教が積極的な生きがいを人に与えうるとしたら、まさにこのような意味での宗教でなくてはならない、と神谷は述べる。このような宗教は、単なる思想や理想の意味をこえて、人間の心の世界を内部から作りかえ、価値基準を変革し、もののみかたのみならず、見えかたまで変え、世界に対する意味づけまで変える、とする[24]。また、多くの思想家や心理学者の言うように、宗教の果たしうるもっとも本質的な役割は、人格に新しい統合を与え、意味感、すなわち生きがい感を与えることであろう、とも述べる[25]。
ということは。総括すると、陳腐な言葉しか思いつかないですが、最後は人は人の為に生きるということでしょうか。例えばスポーツ一つとっても、いくら素晴らしい選手、チームがあったとしても観客がいなくては何も成り立たない。一人一人が自分という物を形成したところで、それが周りに影響を及ぼさなければそれは恐らく生きているとは言わない。
で、結局 〝人と人〝 これに尽きる。
やはり、人間は一人では生きていけないのであります。
こういう哲学的なものっていうものは考え始めると無限ループにハマってしまいますね。
それはともかく。
『家族』 『小学校』 『中学校』 『高校』 『大
学』 『会社』などなどいろんな人間関係があると思い
ますが『mixi』 という人間関係を作るというのもあり
という方、コミュニティーに参加というところをポチっと
な。
徹子の部屋のごとく、テキトーに好きなトピックを立てるのもよし。
哲学的な話を朝日が出るまで語り明かすもよし。
さて、無限ループの世界にいざ行かん。
とりあえず、よろしく哀愁から始めましょう!
目指すはミクシー最大のコミュニティー。
最終目標は、やはり〝人間は一人では生きていけない″ 事を証明する事であります。
気合い空回り。元気いっぱい。面舵いっぱい。
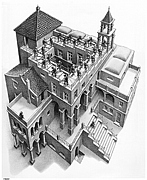







![[修造公認] Shijimixi](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/97/17/5179717_193s.gif)



