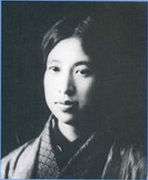- 詳細 2023年7月10日 15:36更新
-
近代婦人労働史に刻んだ女性というニ文字。
その夜、石塀に囲まれた広い屋敷うちには、もの音もなく、円窓のある別棟のみ明け放たれて、ガス灯の蒼白い光が、庭の築山や植え込みをおぼろに浮き上がらせていた。
”元始,女性は実に太陽であった”(「青鞜」創刊に刻まれた一文)
1911年八月下旬の、そのとき、女たちの行く手に高々と解放の旗帳を掲げる『青鞜』が、まさに創刊されようとしていた。
平塚らいてうについて:
大正-昭和時代の婦人運動家。
明治19年2月10日生まれ。44年婦人文芸誌「青鞜(せいとう)」を創刊,女性の解放を主張し,新しい女の生き方を実践。大正9年市川房枝らと新婦人協会をつくり,婦人参政権運動をすすめる。戦後は反戦・平和運動に力をそそいだ。昭和46年5月24日死去。85歳。東京出身。日本女子大卒。本名は奥村明(はる)。著作に「円窓(まるまど)より」「わたくしの歩いた道」など。
略歴:東京生まれ。本名は明(はる)。1906年(明治39)日本女子大学家政科卒業。在学中より人生観を模索し続けるうちに禅に出会い、禅の修行が彼女の自我の確立に大きな影響を及ぼした。大学卒業後、生田長江主宰の閨秀文学会に参加、そこで知り合った作家の森田草平と08年に心中未遂事件、いわゆる「塩原事件」を起こし、センセーションを巻き起こした。11年には生田長江の勧めで、保持研子、中野初子、木内錠子、物集和子とともに女性文芸誌『青鞜』を発刊、らいてうが書いた創刊の辞「元始、女性は太陽であった」は、女性自身による解放宣言として、大正デモクラシーの風潮のなかで大きな反響をよんだ。『青鞜』はしだいに「婦人問題誌」の色彩を増し16年(大正5)2月まで続いたが、しばしば発売禁止処分にあった。青鞜社員の言動は「新しい女」の出現としてジャーナリズムの脚光を浴びたが、非難中傷されることが多かった。この間、らいてうは年下の画家奥村博史と恋愛、同棲するが、あえて家族制度の下での婚姻手続を踏まない共同生活を実行し、これも話題となった。18、19年の母性保護論争では、「女権主義」の立場にたつ与謝野晶子らと対立し、「母性主義」を唱えた。20年には市川房枝、奥むめおの協力を得て新婦人協会を結成、女性の政治活動を禁止した治安警察法第5条の改正や花柳病男子の結婚制限法制定の請願運動をおこし、前者の一部修正を実現させた。しかし、らいてうと市川の対立などから新婦人協会は22年12月解散され、以後らいてうは執筆活動中心の生活に入った。昭和初期には高群逸枝らの『婦人戦線』の同人となり、また消費組合運動にも参加した。第二次世界大戦後は反戦・平和運動に力を注ぎ、日本婦人団体連合会会長、国際民主婦人連盟副会長などを務めた。