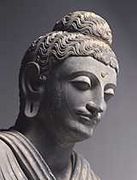アナータピンディカ居士への得難い四法・得難いものを得る四法・適切業四法の教えの続きです。
(『南伝大蔵経18 増支部経典2』大蔵出版 P119−121 に相当)
増支部経典四集>第二 適切業品
「 第二 無債
62.ときにアナータピンディカ居士は先生を訪ねた。訪ねて先生に敬礼して一方に座った。一方に座ってアナータピンディカ居士に先生はこう言った。
居士よ、これら四つの楽は欲を享受する在家が時に応じ機会に応じ取って得るべきものである。何が四か。
所有の楽、使用の楽、無債の楽、無罪の楽である。
では居士よ、何が所有の楽か。
居士よ、ここに良家の子は発起し精進して、腕の力で集め汗を流し、法にかない法によって財産を得る。
彼は「私は発起し精進して、腕の力で集め汗を流し、法にかない法によって得た財産を所有している」と楽を得て喜びを得る。
居士よ、これが所有の楽と言われる。
では居士よ、何が使用の楽か。
居士よ、ここに良家の子は発起し精進して、腕の力で集め汗を流し、法にかない法によって得た財産を享受し、また福も為す。
彼は「私は発起し精進して、腕の力で集め汗を流し、法にかない法によって得た財産を享受し、また福も為す」と楽を得て喜びを得る。
居士よ、これが使用の楽と言われる。
では居士よ、何が無債の楽か。
居士よ、ここに良家の子にはいかなる者にも少なくも多くも何も負うところがない。
彼は「私はいかなる者にも少なくも多くも何も負うところがない」と楽を得て喜びを得る。
居士よ、これが無債の楽と言われる。
では居士よ、何が無罪の楽か。
居士よ、ここに聖なる弟子は無罪の身業を成就し、無罪の語業を成就し、無罪の意業を成就する。
彼は「私は無罪の身業を成就し、無罪の語業を成就し、無罪の意業を成就している」と楽を得て喜びを得る。
居士よ、これが無罪の楽と言われる。
居士よ、これら四つの楽は欲を享受する在家が時に応じ機会に応じ取って得るべきものである。
無債の楽を知り それとは別に所有の楽を得て
財産を使用することを楽しむ人は 智慧によって観察する
そして賢い者は観察して知る これら両方とも
この無罪の楽の 十六分の一にも値しないと(終)」
『南伝大蔵経18 増支部経典2』大蔵出版 P119−121 に相当
註 所有の楽 Atthisukhaṃ (財産が)存在する楽
使用の楽 bhogasukhaṃ 受用の楽
無債の楽 ānaṇyasukhaṃ 借金・負債がない楽
無罪の楽 anavajjasukhaṃ 罪が無い楽
この記述では主に財産に着目して楽が語られていますが、これを「五欲全般」として理解しても得るところがあると思います。
たとえば所有の楽を財だけでなく五欲全般の所有楽として見れば、「自分には財産が有る」というのも喜びですが他にも「自分には良い容姿がある」「自分には良い経歴がある」「自分は良い仕事に就いている」「自分には友人がいる」「自分には異性がいる」「自分には家族がいる」「自分には毎日楽しむ趣味がある」「自分はまだ若い」「自分は健康だ」「自分はまだ生きている」「自分には五感の快楽となるものをある程度所有している」なども所有楽となります。
金銭は五欲を得させるものとして設定されるがゆえに、出家者たちにとって金銭は汚れであり触れてはならないものとしてゴータマによって設定されています。金銭と代替交換ができる財産全般は「所有する」ことによってはじめて五感の快楽として享受できるものとなります。外界に存在しても所有し利用し楽を生じる接触を得ることができなければ、その財産も人間関係も意味がありません。財産は所有することによって五感による接触が可能となり、あるいは接触回数の増大と接触密度の向上が計れるからです。所有は動産や不動産はもとより、人間関係における見えない信頼や評価もまた接触への影響力を根本から規定する原因です。言い換えれば、財産も人間関係も使用されず享受されず五感によって接触されないならば、所有していても意味がないということです。
所有の楽は「自分はいつでもある程度五感の快楽対象との接触に使用できる。あるいは五感の苦痛の原因を生じさせないために使用できる」ということを見て、その状況把握と自覚を原因として安心感として楽を生じるところにあります。
使用の楽は実際に外界において自分が所有しているものを五感の快楽の増大と苦痛の減少のために用いることです。貯金するばかりで使用しないのは良くないと原始仏典に書いてあります。逆に使用してばかりで残らないのも良くないとも書いてあります。収入と支出のバランスが大事という教えが原始仏典にあります。また機会があれば訳したいと思います。
無債の楽は財産で言えば借金になりますが、それ以外の外界の状況について語れば「何らかの義務的なもの全て」と見ても得るところがあると思います。学業や仕事や扶養はもとより人間関係における義務的なこと、やらなければならないと思っていること、これらの減少は楽を生じます。原始仏教の出家には暇がありますが、その代わりに無職のため自主的に財産を得ることができないため五感の快楽が少ないです。だから「貧乏暇なし」ではなくて「貪欲暇なし」が正解です。
五欲への意欲は五蓋の第一ですが、これは借金にたとえられます。貪りは内的な借金状態を作り出し、自らそれを支払って満たすために外界における多くの活動に従事させます。欲貪を断つことによって自らに課している多くの仕事や外出が実際になくなります。仕事の選択や人間関係の選択は多く欲貪と五欲を失う不快と恐怖、引いては身体と命を惜しむ執着が絡んでいます。もし義務や責務を放棄したい場合は、無害を行動範囲として義務の放棄を為すことが推奨されます。
無罪の楽は三悪行を断ち三善行を修することです。十悪を断ち十善を修する、あるいは八邪を断ち八正道を修するでもよいと思います。罪を犯さない力は四力のうち無罪力として設定されており、無限に鍛えることができます。無罪楽は出家の戒学においても味わうべき楽として長部経典に繰り返し出て来ます。無罪性、特に他者を害さないことは在家出家に共通です。出家は特に厳しいです。
無罪楽が四楽のうち最上であるとこの経典の偈に書いてあります。原始仏教は悪がないことを尊びます。またその苦を原因として悪が減少し絶無となるならばその苦も厭うべきではないとしています。泣きながら修行してもその正しい修行のゆえに称賛されると増支部経典五集に書いてあります。ただその苦を原因として悪が増大するようなものは無意義な苦行、一つの極端として排除しています。利益ある苦行は為すべきであり、不利益となる苦行は為すべきではないとしています。最終的に楽を結果する正しい苦行と最終的に苦を結果する間違った苦行との区別が重要です。
無罪楽は外界において悪がないこと、悪業を為さないこと、悪業の報いがないことを見ることによって生じる楽であると思います。一方で内界において悪がないこと、三悪根の絶無と一切執着の放棄、渇愛を尽くすこと、貪りを離れること、再度生まれる原因の滅、これが無害の境地としての完成であると思います。
涅槃の別名の一つに「無悩害」があります。無害は「ア・ヴィヒンサー」で無悩害は「ア・ビャーパッジャ」で別語ですが、大体において同義で使用されています。外界に悪を為さずして無罪楽を得て、内界に悪を為さずして愛尽楽を得て、後は死ねば身体を原因とする外界との嫌な接触もなくなって、また生まれて身体をまとうこともないので安楽ということだと思います。
四つの楽を外界全般の五欲として理解すると
1.五欲を所有する楽
2.五欲を享受する楽
3.義務がない楽
4.無罪楽
のような感じになると思います。ただ三番については無債楽のままでいいとも思います。無理矢理当てはめた感じです。しかし実際に「お気楽なご身分という楽」は誰もが感じたことはあると思います。たとえば休暇などです。その代わりそういう身分の人には財産も五欲楽も将来の安定も少ないものです。僕は「気楽が一番」と思っています。そして一切執着の放棄が一番気楽であり、原始仏典でも「重荷とは五取蘊である」と書いてあり、また解脱の境地の定型句として「重荷をおろし」とも書いてあります。一番気楽な状態を得るために正精進を気楽でなくともやらなければならないという点では気楽ではないと言えます。しかし気楽に達すれば正精進も気楽となるのでそれまでの辛抱なのだと思います。
誰かが『世界で一番お気楽な人たち』とか『一切は萌えている』とか適当なタイトルで原始仏教の作品を作ってくれると面白いと思います。色々な人に興味を持ってもらうのは大事だと思います。ただ現実に対応していない見解を流布して自らも意図せずして邪語を行なっていても自他世間に善くないので、検証の重要性を繰り返し随時訴えて行くことも大切だと思っています。
久しぶりにゴータマのガヤーシーサ山(象頭山)における大説法である「一切は燃えている」から始まる一切熾燃の教えを読んでみてください。トピック本文の下部のほうです。
・律蔵 ゴータマ伝 5
http://
まだゴータマ伝を読んでない方は以下で。
・2 犍度部 〔サンガの規律〕
大品 第1 「ゴータマ伝」 (南伝3 P1–82)
1 http://
2 http://
3 http://
4 http://
5 http://
6 http://
[パーリ語原文]
2. Ānaṇyasuttaṃ
62. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca –
‘‘Cattārimāni, gahapati, sukhāni adhigamanīyāni gihinā kāmabhoginā kālena kālaṃ samayena samayaṃ upādāya. Katamāni cattāri? Atthisukhaṃ, bhogasukhaṃ, ānaṇyasukhaṃ [aṇaṇasukhaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)], anavajjasukhaṃ.
‘‘Katamañca, gahapati, atthisukhaṃ? Idha, gahapati, kulaputtassa bhogā honti uṭṭhānavīriyādhigatā bāhābalaparicitā sedāvakkhittā dhammikā dhammaladdhā . So ‘bhogā me atthi uṭṭhānavīriyādhigatā bāhābalaparicitā sedāvakkhittā dhammikā dhammaladdhā’ti adhigacchati sukhaṃ, adhigacchati somanassaṃ. Idaṃ vuccati, gahapati, atthisukhaṃ.
‘‘Katamañca, gahapati, bhogasukhaṃ? Idha, gahapati, kulaputto uṭṭhānavīriyādhigatehi bhogehi bāhābalaparicitehi sedāvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi paribhuñjati puññāni ca karoti. So ‘uṭṭhānavīriyādhigatehi bhogehi bāhābalaparicitehi sedāvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi paribhuñjāmi puññāni ca karomī’ti adhigacchati sukhaṃ, adhigacchati somanassaṃ. Idaṃ vuccati, gahapati, bhogasukhaṃ .
‘‘Katamañca, gahapati, ānaṇyasukhaṃ? Idha, gahapati, kulaputto na kassaci kiñci dhāreti appaṃ vā bahuṃ vā. So ‘na kassaci kiñci dhāremi [kiñci vā deti (ka.)] appaṃ vā bahuṃ vā’ti adhigacchati sukhaṃ, adhigacchati somanassaṃ. Idaṃ vuccati, gahapati, ānaṇyasukhaṃ.
‘‘Katamañca, gahapati, anavajjasukhaṃ? Idha, gahapati, ariyasāvako anavajjena kāyakammena samannāgato hoti, anavajjena vacīkammena samannāgato hoti, anavajjena manokammena samannāgato hoti. So ‘anavajjenamhi kāyakammena samannāgato, anavajjena vacīkammena samannāgato, anavajjena manokammena samannāgato’ti adhigacchati sukhaṃ, adhigacchati somanassaṃ. Idaṃ vuccati, gahapati, anavajjasukhaṃ. Imāni kho, gahapati, cattāri sukhāni adhigamanīyāni gihinā kāmabhoginā kālena kālaṃ samayena samayaṃ upādāyā’’ti.
‘‘Ānaṇyasukhaṃ ñatvāna, atho atthisukhaṃ paraṃ;
Bhuñjaṃ bhogasukhaṃ macco, tato paññā vipassati.
‘‘Vipassamāno jānāti, ubho bhoge sumedhaso;
Anavajjasukhassetaṃ, kalaṃ nāgghati soḷasi’’nti. dutiyaṃ;
(『南伝大蔵経18 増支部経典2』大蔵出版 P119−121 に相当)
増支部経典四集>第二 適切業品
「 第二 無債
62.ときにアナータピンディカ居士は先生を訪ねた。訪ねて先生に敬礼して一方に座った。一方に座ってアナータピンディカ居士に先生はこう言った。
居士よ、これら四つの楽は欲を享受する在家が時に応じ機会に応じ取って得るべきものである。何が四か。
所有の楽、使用の楽、無債の楽、無罪の楽である。
では居士よ、何が所有の楽か。
居士よ、ここに良家の子は発起し精進して、腕の力で集め汗を流し、法にかない法によって財産を得る。
彼は「私は発起し精進して、腕の力で集め汗を流し、法にかない法によって得た財産を所有している」と楽を得て喜びを得る。
居士よ、これが所有の楽と言われる。
では居士よ、何が使用の楽か。
居士よ、ここに良家の子は発起し精進して、腕の力で集め汗を流し、法にかない法によって得た財産を享受し、また福も為す。
彼は「私は発起し精進して、腕の力で集め汗を流し、法にかない法によって得た財産を享受し、また福も為す」と楽を得て喜びを得る。
居士よ、これが使用の楽と言われる。
では居士よ、何が無債の楽か。
居士よ、ここに良家の子にはいかなる者にも少なくも多くも何も負うところがない。
彼は「私はいかなる者にも少なくも多くも何も負うところがない」と楽を得て喜びを得る。
居士よ、これが無債の楽と言われる。
では居士よ、何が無罪の楽か。
居士よ、ここに聖なる弟子は無罪の身業を成就し、無罪の語業を成就し、無罪の意業を成就する。
彼は「私は無罪の身業を成就し、無罪の語業を成就し、無罪の意業を成就している」と楽を得て喜びを得る。
居士よ、これが無罪の楽と言われる。
居士よ、これら四つの楽は欲を享受する在家が時に応じ機会に応じ取って得るべきものである。
無債の楽を知り それとは別に所有の楽を得て
財産を使用することを楽しむ人は 智慧によって観察する
そして賢い者は観察して知る これら両方とも
この無罪の楽の 十六分の一にも値しないと(終)」
『南伝大蔵経18 増支部経典2』大蔵出版 P119−121 に相当
註 所有の楽 Atthisukhaṃ (財産が)存在する楽
使用の楽 bhogasukhaṃ 受用の楽
無債の楽 ānaṇyasukhaṃ 借金・負債がない楽
無罪の楽 anavajjasukhaṃ 罪が無い楽
この記述では主に財産に着目して楽が語られていますが、これを「五欲全般」として理解しても得るところがあると思います。
たとえば所有の楽を財だけでなく五欲全般の所有楽として見れば、「自分には財産が有る」というのも喜びですが他にも「自分には良い容姿がある」「自分には良い経歴がある」「自分は良い仕事に就いている」「自分には友人がいる」「自分には異性がいる」「自分には家族がいる」「自分には毎日楽しむ趣味がある」「自分はまだ若い」「自分は健康だ」「自分はまだ生きている」「自分には五感の快楽となるものをある程度所有している」なども所有楽となります。
金銭は五欲を得させるものとして設定されるがゆえに、出家者たちにとって金銭は汚れであり触れてはならないものとしてゴータマによって設定されています。金銭と代替交換ができる財産全般は「所有する」ことによってはじめて五感の快楽として享受できるものとなります。外界に存在しても所有し利用し楽を生じる接触を得ることができなければ、その財産も人間関係も意味がありません。財産は所有することによって五感による接触が可能となり、あるいは接触回数の増大と接触密度の向上が計れるからです。所有は動産や不動産はもとより、人間関係における見えない信頼や評価もまた接触への影響力を根本から規定する原因です。言い換えれば、財産も人間関係も使用されず享受されず五感によって接触されないならば、所有していても意味がないということです。
所有の楽は「自分はいつでもある程度五感の快楽対象との接触に使用できる。あるいは五感の苦痛の原因を生じさせないために使用できる」ということを見て、その状況把握と自覚を原因として安心感として楽を生じるところにあります。
使用の楽は実際に外界において自分が所有しているものを五感の快楽の増大と苦痛の減少のために用いることです。貯金するばかりで使用しないのは良くないと原始仏典に書いてあります。逆に使用してばかりで残らないのも良くないとも書いてあります。収入と支出のバランスが大事という教えが原始仏典にあります。また機会があれば訳したいと思います。
無債の楽は財産で言えば借金になりますが、それ以外の外界の状況について語れば「何らかの義務的なもの全て」と見ても得るところがあると思います。学業や仕事や扶養はもとより人間関係における義務的なこと、やらなければならないと思っていること、これらの減少は楽を生じます。原始仏教の出家には暇がありますが、その代わりに無職のため自主的に財産を得ることができないため五感の快楽が少ないです。だから「貧乏暇なし」ではなくて「貪欲暇なし」が正解です。
五欲への意欲は五蓋の第一ですが、これは借金にたとえられます。貪りは内的な借金状態を作り出し、自らそれを支払って満たすために外界における多くの活動に従事させます。欲貪を断つことによって自らに課している多くの仕事や外出が実際になくなります。仕事の選択や人間関係の選択は多く欲貪と五欲を失う不快と恐怖、引いては身体と命を惜しむ執着が絡んでいます。もし義務や責務を放棄したい場合は、無害を行動範囲として義務の放棄を為すことが推奨されます。
無罪の楽は三悪行を断ち三善行を修することです。十悪を断ち十善を修する、あるいは八邪を断ち八正道を修するでもよいと思います。罪を犯さない力は四力のうち無罪力として設定されており、無限に鍛えることができます。無罪楽は出家の戒学においても味わうべき楽として長部経典に繰り返し出て来ます。無罪性、特に他者を害さないことは在家出家に共通です。出家は特に厳しいです。
無罪楽が四楽のうち最上であるとこの経典の偈に書いてあります。原始仏教は悪がないことを尊びます。またその苦を原因として悪が減少し絶無となるならばその苦も厭うべきではないとしています。泣きながら修行してもその正しい修行のゆえに称賛されると増支部経典五集に書いてあります。ただその苦を原因として悪が増大するようなものは無意義な苦行、一つの極端として排除しています。利益ある苦行は為すべきであり、不利益となる苦行は為すべきではないとしています。最終的に楽を結果する正しい苦行と最終的に苦を結果する間違った苦行との区別が重要です。
無罪楽は外界において悪がないこと、悪業を為さないこと、悪業の報いがないことを見ることによって生じる楽であると思います。一方で内界において悪がないこと、三悪根の絶無と一切執着の放棄、渇愛を尽くすこと、貪りを離れること、再度生まれる原因の滅、これが無害の境地としての完成であると思います。
涅槃の別名の一つに「無悩害」があります。無害は「ア・ヴィヒンサー」で無悩害は「ア・ビャーパッジャ」で別語ですが、大体において同義で使用されています。外界に悪を為さずして無罪楽を得て、内界に悪を為さずして愛尽楽を得て、後は死ねば身体を原因とする外界との嫌な接触もなくなって、また生まれて身体をまとうこともないので安楽ということだと思います。
四つの楽を外界全般の五欲として理解すると
1.五欲を所有する楽
2.五欲を享受する楽
3.義務がない楽
4.無罪楽
のような感じになると思います。ただ三番については無債楽のままでいいとも思います。無理矢理当てはめた感じです。しかし実際に「お気楽なご身分という楽」は誰もが感じたことはあると思います。たとえば休暇などです。その代わりそういう身分の人には財産も五欲楽も将来の安定も少ないものです。僕は「気楽が一番」と思っています。そして一切執着の放棄が一番気楽であり、原始仏典でも「重荷とは五取蘊である」と書いてあり、また解脱の境地の定型句として「重荷をおろし」とも書いてあります。一番気楽な状態を得るために正精進を気楽でなくともやらなければならないという点では気楽ではないと言えます。しかし気楽に達すれば正精進も気楽となるのでそれまでの辛抱なのだと思います。
誰かが『世界で一番お気楽な人たち』とか『一切は萌えている』とか適当なタイトルで原始仏教の作品を作ってくれると面白いと思います。色々な人に興味を持ってもらうのは大事だと思います。ただ現実に対応していない見解を流布して自らも意図せずして邪語を行なっていても自他世間に善くないので、検証の重要性を繰り返し随時訴えて行くことも大切だと思っています。
久しぶりにゴータマのガヤーシーサ山(象頭山)における大説法である「一切は燃えている」から始まる一切熾燃の教えを読んでみてください。トピック本文の下部のほうです。
・律蔵 ゴータマ伝 5
http://
まだゴータマ伝を読んでない方は以下で。
・2 犍度部 〔サンガの規律〕
大品 第1 「ゴータマ伝」 (南伝3 P1–82)
1 http://
2 http://
3 http://
4 http://
5 http://
6 http://
[パーリ語原文]
2. Ānaṇyasuttaṃ
62. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca –
‘‘Cattārimāni, gahapati, sukhāni adhigamanīyāni gihinā kāmabhoginā kālena kālaṃ samayena samayaṃ upādāya. Katamāni cattāri? Atthisukhaṃ, bhogasukhaṃ, ānaṇyasukhaṃ [aṇaṇasukhaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)], anavajjasukhaṃ.
‘‘Katamañca, gahapati, atthisukhaṃ? Idha, gahapati, kulaputtassa bhogā honti uṭṭhānavīriyādhigatā bāhābalaparicitā sedāvakkhittā dhammikā dhammaladdhā . So ‘bhogā me atthi uṭṭhānavīriyādhigatā bāhābalaparicitā sedāvakkhittā dhammikā dhammaladdhā’ti adhigacchati sukhaṃ, adhigacchati somanassaṃ. Idaṃ vuccati, gahapati, atthisukhaṃ.
‘‘Katamañca, gahapati, bhogasukhaṃ? Idha, gahapati, kulaputto uṭṭhānavīriyādhigatehi bhogehi bāhābalaparicitehi sedāvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi paribhuñjati puññāni ca karoti. So ‘uṭṭhānavīriyādhigatehi bhogehi bāhābalaparicitehi sedāvakkhittehi dhammikehi dhammaladdhehi paribhuñjāmi puññāni ca karomī’ti adhigacchati sukhaṃ, adhigacchati somanassaṃ. Idaṃ vuccati, gahapati, bhogasukhaṃ .
‘‘Katamañca, gahapati, ānaṇyasukhaṃ? Idha, gahapati, kulaputto na kassaci kiñci dhāreti appaṃ vā bahuṃ vā. So ‘na kassaci kiñci dhāremi [kiñci vā deti (ka.)] appaṃ vā bahuṃ vā’ti adhigacchati sukhaṃ, adhigacchati somanassaṃ. Idaṃ vuccati, gahapati, ānaṇyasukhaṃ.
‘‘Katamañca, gahapati, anavajjasukhaṃ? Idha, gahapati, ariyasāvako anavajjena kāyakammena samannāgato hoti, anavajjena vacīkammena samannāgato hoti, anavajjena manokammena samannāgato hoti. So ‘anavajjenamhi kāyakammena samannāgato, anavajjena vacīkammena samannāgato, anavajjena manokammena samannāgato’ti adhigacchati sukhaṃ, adhigacchati somanassaṃ. Idaṃ vuccati, gahapati, anavajjasukhaṃ. Imāni kho, gahapati, cattāri sukhāni adhigamanīyāni gihinā kāmabhoginā kālena kālaṃ samayena samayaṃ upādāyā’’ti.
‘‘Ānaṇyasukhaṃ ñatvāna, atho atthisukhaṃ paraṃ;
Bhuñjaṃ bhogasukhaṃ macco, tato paññā vipassati.
‘‘Vipassamāno jānāti, ubho bhoge sumedhaso;
Anavajjasukhassetaṃ, kalaṃ nāgghati soḷasi’’nti. dutiyaṃ;
|
|
|
|
|
|
|
|
原始仏典 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
原始仏典のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90042人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6423人
- 3位
- 独り言
- 9045人