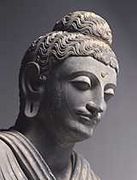増支部経典>四集>第四 戦士品
「 百八十六
一 あるとき、一比丘がいて世尊のところに詣り、詣り終わって世尊に問訊して一方に座った。一方に座ったその比丘は世尊に言った。
大徳、世間は何に導かれるのですか。世間は何に牽かれるのですか。すでに生じたいかなるものの力に従うのですか。
比丘よ、善いかな善いかな。比丘よ、汝の智慧の発言は賢い。弁才は賢い。問いは善い。
比丘よ、汝はこのように問うのか。即ち、「大徳、世間は何に導かれるのですか。世間は何に牽かれるのですか。すでに生じたいかなるものの力に従うのですか」と。
大徳、そうです。
比丘よ、世間は心に導かれる。心に牽かれる。すでに生じた心の力に従う。
二 大徳、善いかな。
と言ってその比丘は世尊の所説に歓喜し随喜し終わって、さらに世尊に質問した。
大徳、多聞持法者、多聞持法者と言います。大徳、何を限って多聞持法者であるのですか。
比丘よ、善いかな善いかな。比丘よ、汝の智慧の発言は賢い。弁才は賢い。問いは善い。
比丘よ、汝はこのように問うのか。即ち、「大徳、多聞持法者、多聞持法者と言います。大徳、何を限って多聞持法者であるのですか」と。
大徳、そうです。
比丘よ、私は多くの法を説いた。経・応頌・記説・諷頌・無問自説・如是説・本生・未曾有法・知解である。
比丘よ、十四句のガーター(偈)であっても、義を知り、法を知り、法随法を行なえば多聞持法者と名付けられるに足る。
三 大徳、善いかな。
と言ってその比丘は世尊の所説に歓喜し随喜し終わって、さらに世尊に質問した。
大徳、具聞の決択慧者、具聞の決択慧者と言います。大徳、何を限って具聞の決択慧者であるのですか。
比丘よ、善いかな善いかな。比丘よ、汝の智慧の発言は賢い。弁才は賢い。問いは善い。
比丘よ、汝はこのように問うのか。即ち、「大徳、具聞の決択慧者、具聞の決択慧者と言います。大徳、何を限って具聞の決択慧者であるのですか」と。
大徳、そうです。
比丘よ、世に比丘がいて、これは苦であると聞いて、慧によってその義を分析して見て、これは苦集であると聞いて、慧によってその義を分析して見て、これは苦滅であると聞いて、慧によってその義を分析して見て、これは苦滅道であると聞いて、慧によってその義を分析して見る。
比丘よ、これが具聞の決択慧者である。
四 大徳、善いかな。
と言ってその比丘は世尊の所説に歓喜し随喜し終わって、さらに世尊に質問した。
大徳、賢人大慧者、賢人大慧者と言います。大徳、何を限って賢人大慧者であるのですか。
比丘よ、善いかな善いかな。比丘よ、汝の智慧の発言は賢い。弁才は賢い。問いは善い。
比丘よ、汝はこのように問うのか。即ち、「大徳、賢人大慧者、賢人大慧者と言います。大徳、何を限って賢人大慧者であるのですか」と。
大徳、そうです。
比丘よ、世に賢人大慧者がいて、自己の悩害のためを思わず、他者の悩害のためを思わず、両者の悩害のためを思わず、自利と他利と倶利と一切世間の利と心に思い考える。
比丘よ、これが賢人大慧者である」
『南伝大蔵経18 増支部経典2』大蔵出版 P311–313
1 世間は心に導かれ、心に牽かれ、生じた心の力に従う。心→名
2 多聞の持法者 義知法知法随法行の者。多聞でも義知法知法随法行でなければ多聞持法者ではない。
3 具聞の決択慧者 四諦を分析して見る者。四諦を分析して見なければ具聞の決択慧者ではない。
4 賢人大慧者 自害他害倶害を思わず、自利他利倶利一切世間利を思う。
1 世間と心
名は一切に勝つというのが相応部経典にあったと思います。それと同じだと思います。世は心に従うがゆえに心を修します。五根五力の信勤念定慧の心の力です。信は四預流支なのでその四番目の戒からこれを増上戒学と解釈し、勤念定を八正道と同様の分類で増上心学と見て、最上の心の力である慧力を増上慧学としても暗記するのもいいと思います。
2 多聞持法者
「私は多くの法を説いた」と言って、九分経を出しています。ゴータマは自分は長部・中部・相応部・増支部を説いたのではなく、九を説いたと自覚していることがわかります。
聞く目的、多聞の目的、記憶する目的、思い出す目的は全て義知法知法随法行のためです。義知法知法随法行は苦滅のためです。苦滅は何のためかというにゴータマは問いの究極を得ることはできない、全ては涅槃に究竟し涅槃に終わると説きます。知識は実生活で生かし、実行するためのものですが、聞いただけで実行しない人は多いです。僕も一部実行、一部放置なので、非常に反省させられます。
3 具聞決択慧者
ゴータマの全説法は四諦に包括され、四諦の中に無限の言葉、無限の文句、無限の意義があると書いてあります。最高の利益の原因となる知識が即ち、四諦です。それゆえに智慧者は自己の最高の利益の原因となる四諦を考察します。最高の自利の原因となる四諦を考察することこそが、「最高の自利を聞いた者」であり「解明する智慧がある者」の証です。四諦を考察しない人は四諦の重要性と四諦了知の利益を知りません。それゆえに聞くことのない人であり、物事を解明する智慧のない人です。八正道において正見が最初に来る所以です。つまり、如来が世界に現れて、説法を聞いて、はじめて四諦を知って、流れに入るという順序においても。だから、聞くことが有るということ、決択慧がセットになるのだと思います。
4 賢人大慧者
ゴータマは独坐のとき自利・他利・倶利・一切世間利を考えて坐すと別の箇所に書いてあります。モッガーラナがかつて魔ドゥーシンとして地獄に落ちたとき獄卒は「賢者よ(パンディタ)」と呼びかけ、ゴータマがバカ梵天を訪れたときもまた「賢者よ(パンディタ)、よく来た」と呼びかけています。大慧の者の第一はサーリプッタであるというのは有名で、マハーカッチャーナやアーナンダもたまにそのように言われます。大慧は念身によって得られ、また四預流向支である善人親近・正法聴聞・如理作意・法随法行によっても得られます。大慧への道はこの念身と四預流向支の二つがメインになりますので、余力があれば覚えていると便利です。
自利は他利となります。これは原始仏典には書いてないですが僕はそう考えています。ですから単独仏陀が出現するだけでもその地方や国家が受ける功徳は大きいと思っています。また自分が阿羅漢になれば家族や友人にも利益が多いでしょう。他利もまた自利となります。四無量心や四摂事を修めれば、善い功徳が積めるし自己の内にある瞋も断ち、害意も断ち、法施によって智慧も増します。説法する者も説法を聞く者もその両者も法を理解するという三つの利益をよく観じる者は説法するに足るということが書いてあります。こうして自利は他利、他利は自利、よって自利は倶利、他利は倶利となり、倶利を大きく広げ利益を与える対象を限定せず無量に倶利を考えることが一切世間利だと思います。
しかし、ここでは賢人大慧者です。賢者たらんと欲する者は自利は他利倶利一切世間利になるだろうと考えて、他利を思惟せず、倶利を思惟せず、一切世間利を思惟しないというのは相応しくありません。むしろ、自利を完全に全うし最高の沙門である柔軟沙門にならんと欲するがゆえに他利をも思惟し、倶利をも思惟し、一切世間利を思惟するのが称賛されます。自害他害倶害を思惟しないのも非常に重要な修行です。そのために悩害することの不利益と過患を考察することが有用だと思います。
世間は心に従うという教え。
法随法行をしなければ教えを聞いても意味がないという教え。
四諦を考察しなければ教えを聞いたとは言えないという教え。
自利他利倶利一切世間利を思惟する者が賢者大慧者であるという教えです。
もし余力があれば「自利他利倶利一切世間利を考えるのを自分の基本タイプにしよう」という戒、ポリシーを持つことをおすすめします。
多聞持法者:bahussuto dhammadharo、バフ(多)スッタ(聞)ダンマダラ(持法者)、
多くの法 :Bahū dhammā
suttaṃ, geyyaṃ, veyyākaraṇaṃ, スッタ・ゲッヤ・ベッヤーカラナ
gāthā, udānaṃ, itivuttakaṃ, ガーター・ウダーナ・イティヴッタカ
jātakaṃ, abbhutadhammaṃ, vedallaṃ. ジャータカ・アッブタダンマ・ヴェーダッラ
義知、法知、法随法行:atthamaññāya dhammamaññāya dhammānudhammappaṭipanno
具聞の決択慧者:sutavā nibbedhikapañño、聞くことのある決択慧のある者
賢人大慧者 :paṇḍito mahāpañño、賢者であり大慧者
パーリ語原文
6. Ummaggasuttaṃ
186. Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘kena nu kho, bhante, loko nīyati, kena loko parikassati, kassa ca uppannassa vasaṃ gacchatī’’ti?
‘‘Sādhu sādhu, bhikkhu! Bhaddako kho te, bhikkhu, ummaggo [ummaṅgo (syā. ka.)], bhaddakaṃ paṭibhānaṃ, kalyāṇī [kalyāṇā (ka.)] paripucchā. Evañhi tvaṃ, bhikkhu, pucchasi – ‘kena nu kho, bhante, loko nīyati, kena loko parikassati, kassa ca uppannassa vasaṃ gacchatī’’’ti? ‘‘Evaṃ, bhante’’. ‘‘Cittena kho, bhikkhu, loko nīyati, cittena parikassati, cittassa uppannassa vasaṃ gacchatī’’ti.
‘‘Sādhu , bhante’’ti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā bhagavantaṃ uttari pañhaṃ apucchi – ‘‘‘bahussuto dhammadharo, bahussuto dhammadharo’ti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, bahussuto dhammadharo hotī’’ti?
‘‘Sādhu sādhu, bhikkhu! Bhaddako kho te, bhikkhu ummaggo, bhaddakaṃ paṭibhānaṃ, kalyāṇī paripucchā. Evañhi tvaṃ, bhikkhu, pucchasi – ‘bahussuto dhammadharo, bahussuto dhammadharoti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, bahussuto dhammadharo hotī’’’ti? ‘‘Evaṃ, bhante’’. ‘‘Bahū kho, bhikkhu, mayā dhammā desitā [bahu kho bhikkhu mayā dhammo desito (ka.)] – suttaṃ, geyyaṃ, veyyākaraṇaṃ, gāthā, udānaṃ, itivuttakaṃ, jātakaṃ, abbhutadhammaṃ, vedallaṃ. Catuppadāya cepi, bhikkhu, gāthāya atthamaññāya dhammamaññāya dhammānudhammappaṭipanno hoti bahussuto dhammadharoti alaṃ vacanāyā’’ti.
‘‘Sādhu, bhante’’ti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā bhagavantaṃ uttari pañhaṃ apucchi – ‘‘‘sutavā nibbedhikapañño, sutavā nibbedhikapañño’ti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, sutavā nibbedhikapañño hotī’’ti?
‘‘Sādhu sādhu, bhikkhu! Bhaddako kho te, bhikkhu, ummaggo, bhaddakaṃ paṭibhānaṃ, kalyāṇī paripucchā. Evañhi tvaṃ, bhikkhu, pucchasi – ‘sutavā nibbedhikapañño, sutavā nibbedhikapaññoti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, sutavā nibbedhikapañño hotī’’’ti? ‘‘Evaṃ, bhante’’. ‘‘Idha, bhikkhu, bhikkhuno ‘idaṃ dukkha’nti sutaṃ hoti, paññāya cassa atthaṃ ativijjha passati; ‘ayaṃ dukkhasamudayo’ti sutaṃ hoti, paññāya cassa atthaṃ ativijjha passati; ‘ayaṃ dukkhanirodho’ti sutaṃ hoti, paññāya cassa atthaṃ ativijjha passati; ‘ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ti sutaṃ hoti, paññāya cassa atthaṃ ativijjha passati. Evaṃ kho, bhikkhu, sutavā nibbedhikapañño hotī’’ti.
‘‘Sādhu, bhante’’ti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā bhagavantaṃ uttari pañhaṃ apucchi – ‘‘‘paṇḍito mahāpañño, paṇḍito mahāpañño’ti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, paṇḍito mahāpañño hotī’’ti?
‘‘Sādhu sādhu bhikkhu! Bhaddako kho te, bhikkhu, ummaggo, bhaddakaṃ paṭibhānaṃ, kalyāṇī paripucchā. Evañhi tvaṃ bhikkhu pucchasi – ‘paṇḍito mahāpañño, paṇḍito mahāpaññoti , bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, paṇḍito mahāpañño hotī’’’ti? ‘‘Evaṃ, bhante’’. ‘‘Idha, bhikkhu, paṇḍito mahāpañño nevattabyābādhāya ceteti na parabyābādhāya ceteti na ubhayabyābādhāya ceteti attahitaparahitaubhayahitasabbalokahitameva cintayamāno cinteti. Evaṃ kho, bhikkhu, paṇḍito mahāpañño hotī’’ti. Chaṭṭhaṃ.
「 百八十六
一 あるとき、一比丘がいて世尊のところに詣り、詣り終わって世尊に問訊して一方に座った。一方に座ったその比丘は世尊に言った。
大徳、世間は何に導かれるのですか。世間は何に牽かれるのですか。すでに生じたいかなるものの力に従うのですか。
比丘よ、善いかな善いかな。比丘よ、汝の智慧の発言は賢い。弁才は賢い。問いは善い。
比丘よ、汝はこのように問うのか。即ち、「大徳、世間は何に導かれるのですか。世間は何に牽かれるのですか。すでに生じたいかなるものの力に従うのですか」と。
大徳、そうです。
比丘よ、世間は心に導かれる。心に牽かれる。すでに生じた心の力に従う。
二 大徳、善いかな。
と言ってその比丘は世尊の所説に歓喜し随喜し終わって、さらに世尊に質問した。
大徳、多聞持法者、多聞持法者と言います。大徳、何を限って多聞持法者であるのですか。
比丘よ、善いかな善いかな。比丘よ、汝の智慧の発言は賢い。弁才は賢い。問いは善い。
比丘よ、汝はこのように問うのか。即ち、「大徳、多聞持法者、多聞持法者と言います。大徳、何を限って多聞持法者であるのですか」と。
大徳、そうです。
比丘よ、私は多くの法を説いた。経・応頌・記説・諷頌・無問自説・如是説・本生・未曾有法・知解である。
比丘よ、十四句のガーター(偈)であっても、義を知り、法を知り、法随法を行なえば多聞持法者と名付けられるに足る。
三 大徳、善いかな。
と言ってその比丘は世尊の所説に歓喜し随喜し終わって、さらに世尊に質問した。
大徳、具聞の決択慧者、具聞の決択慧者と言います。大徳、何を限って具聞の決択慧者であるのですか。
比丘よ、善いかな善いかな。比丘よ、汝の智慧の発言は賢い。弁才は賢い。問いは善い。
比丘よ、汝はこのように問うのか。即ち、「大徳、具聞の決択慧者、具聞の決択慧者と言います。大徳、何を限って具聞の決択慧者であるのですか」と。
大徳、そうです。
比丘よ、世に比丘がいて、これは苦であると聞いて、慧によってその義を分析して見て、これは苦集であると聞いて、慧によってその義を分析して見て、これは苦滅であると聞いて、慧によってその義を分析して見て、これは苦滅道であると聞いて、慧によってその義を分析して見る。
比丘よ、これが具聞の決択慧者である。
四 大徳、善いかな。
と言ってその比丘は世尊の所説に歓喜し随喜し終わって、さらに世尊に質問した。
大徳、賢人大慧者、賢人大慧者と言います。大徳、何を限って賢人大慧者であるのですか。
比丘よ、善いかな善いかな。比丘よ、汝の智慧の発言は賢い。弁才は賢い。問いは善い。
比丘よ、汝はこのように問うのか。即ち、「大徳、賢人大慧者、賢人大慧者と言います。大徳、何を限って賢人大慧者であるのですか」と。
大徳、そうです。
比丘よ、世に賢人大慧者がいて、自己の悩害のためを思わず、他者の悩害のためを思わず、両者の悩害のためを思わず、自利と他利と倶利と一切世間の利と心に思い考える。
比丘よ、これが賢人大慧者である」
『南伝大蔵経18 増支部経典2』大蔵出版 P311–313
1 世間は心に導かれ、心に牽かれ、生じた心の力に従う。心→名
2 多聞の持法者 義知法知法随法行の者。多聞でも義知法知法随法行でなければ多聞持法者ではない。
3 具聞の決択慧者 四諦を分析して見る者。四諦を分析して見なければ具聞の決択慧者ではない。
4 賢人大慧者 自害他害倶害を思わず、自利他利倶利一切世間利を思う。
1 世間と心
名は一切に勝つというのが相応部経典にあったと思います。それと同じだと思います。世は心に従うがゆえに心を修します。五根五力の信勤念定慧の心の力です。信は四預流支なのでその四番目の戒からこれを増上戒学と解釈し、勤念定を八正道と同様の分類で増上心学と見て、最上の心の力である慧力を増上慧学としても暗記するのもいいと思います。
2 多聞持法者
「私は多くの法を説いた」と言って、九分経を出しています。ゴータマは自分は長部・中部・相応部・増支部を説いたのではなく、九を説いたと自覚していることがわかります。
聞く目的、多聞の目的、記憶する目的、思い出す目的は全て義知法知法随法行のためです。義知法知法随法行は苦滅のためです。苦滅は何のためかというにゴータマは問いの究極を得ることはできない、全ては涅槃に究竟し涅槃に終わると説きます。知識は実生活で生かし、実行するためのものですが、聞いただけで実行しない人は多いです。僕も一部実行、一部放置なので、非常に反省させられます。
3 具聞決択慧者
ゴータマの全説法は四諦に包括され、四諦の中に無限の言葉、無限の文句、無限の意義があると書いてあります。最高の利益の原因となる知識が即ち、四諦です。それゆえに智慧者は自己の最高の利益の原因となる四諦を考察します。最高の自利の原因となる四諦を考察することこそが、「最高の自利を聞いた者」であり「解明する智慧がある者」の証です。四諦を考察しない人は四諦の重要性と四諦了知の利益を知りません。それゆえに聞くことのない人であり、物事を解明する智慧のない人です。八正道において正見が最初に来る所以です。つまり、如来が世界に現れて、説法を聞いて、はじめて四諦を知って、流れに入るという順序においても。だから、聞くことが有るということ、決択慧がセットになるのだと思います。
4 賢人大慧者
ゴータマは独坐のとき自利・他利・倶利・一切世間利を考えて坐すと別の箇所に書いてあります。モッガーラナがかつて魔ドゥーシンとして地獄に落ちたとき獄卒は「賢者よ(パンディタ)」と呼びかけ、ゴータマがバカ梵天を訪れたときもまた「賢者よ(パンディタ)、よく来た」と呼びかけています。大慧の者の第一はサーリプッタであるというのは有名で、マハーカッチャーナやアーナンダもたまにそのように言われます。大慧は念身によって得られ、また四預流向支である善人親近・正法聴聞・如理作意・法随法行によっても得られます。大慧への道はこの念身と四預流向支の二つがメインになりますので、余力があれば覚えていると便利です。
自利は他利となります。これは原始仏典には書いてないですが僕はそう考えています。ですから単独仏陀が出現するだけでもその地方や国家が受ける功徳は大きいと思っています。また自分が阿羅漢になれば家族や友人にも利益が多いでしょう。他利もまた自利となります。四無量心や四摂事を修めれば、善い功徳が積めるし自己の内にある瞋も断ち、害意も断ち、法施によって智慧も増します。説法する者も説法を聞く者もその両者も法を理解するという三つの利益をよく観じる者は説法するに足るということが書いてあります。こうして自利は他利、他利は自利、よって自利は倶利、他利は倶利となり、倶利を大きく広げ利益を与える対象を限定せず無量に倶利を考えることが一切世間利だと思います。
しかし、ここでは賢人大慧者です。賢者たらんと欲する者は自利は他利倶利一切世間利になるだろうと考えて、他利を思惟せず、倶利を思惟せず、一切世間利を思惟しないというのは相応しくありません。むしろ、自利を完全に全うし最高の沙門である柔軟沙門にならんと欲するがゆえに他利をも思惟し、倶利をも思惟し、一切世間利を思惟するのが称賛されます。自害他害倶害を思惟しないのも非常に重要な修行です。そのために悩害することの不利益と過患を考察することが有用だと思います。
世間は心に従うという教え。
法随法行をしなければ教えを聞いても意味がないという教え。
四諦を考察しなければ教えを聞いたとは言えないという教え。
自利他利倶利一切世間利を思惟する者が賢者大慧者であるという教えです。
もし余力があれば「自利他利倶利一切世間利を考えるのを自分の基本タイプにしよう」という戒、ポリシーを持つことをおすすめします。
多聞持法者:bahussuto dhammadharo、バフ(多)スッタ(聞)ダンマダラ(持法者)、
多くの法 :Bahū dhammā
suttaṃ, geyyaṃ, veyyākaraṇaṃ, スッタ・ゲッヤ・ベッヤーカラナ
gāthā, udānaṃ, itivuttakaṃ, ガーター・ウダーナ・イティヴッタカ
jātakaṃ, abbhutadhammaṃ, vedallaṃ. ジャータカ・アッブタダンマ・ヴェーダッラ
義知、法知、法随法行:atthamaññāya dhammamaññāya dhammānudhammappaṭipanno
具聞の決択慧者:sutavā nibbedhikapañño、聞くことのある決択慧のある者
賢人大慧者 :paṇḍito mahāpañño、賢者であり大慧者
パーリ語原文
6. Ummaggasuttaṃ
186. Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘kena nu kho, bhante, loko nīyati, kena loko parikassati, kassa ca uppannassa vasaṃ gacchatī’’ti?
‘‘Sādhu sādhu, bhikkhu! Bhaddako kho te, bhikkhu, ummaggo [ummaṅgo (syā. ka.)], bhaddakaṃ paṭibhānaṃ, kalyāṇī [kalyāṇā (ka.)] paripucchā. Evañhi tvaṃ, bhikkhu, pucchasi – ‘kena nu kho, bhante, loko nīyati, kena loko parikassati, kassa ca uppannassa vasaṃ gacchatī’’’ti? ‘‘Evaṃ, bhante’’. ‘‘Cittena kho, bhikkhu, loko nīyati, cittena parikassati, cittassa uppannassa vasaṃ gacchatī’’ti.
‘‘Sādhu , bhante’’ti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā bhagavantaṃ uttari pañhaṃ apucchi – ‘‘‘bahussuto dhammadharo, bahussuto dhammadharo’ti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, bahussuto dhammadharo hotī’’ti?
‘‘Sādhu sādhu, bhikkhu! Bhaddako kho te, bhikkhu ummaggo, bhaddakaṃ paṭibhānaṃ, kalyāṇī paripucchā. Evañhi tvaṃ, bhikkhu, pucchasi – ‘bahussuto dhammadharo, bahussuto dhammadharoti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, bahussuto dhammadharo hotī’’’ti? ‘‘Evaṃ, bhante’’. ‘‘Bahū kho, bhikkhu, mayā dhammā desitā [bahu kho bhikkhu mayā dhammo desito (ka.)] – suttaṃ, geyyaṃ, veyyākaraṇaṃ, gāthā, udānaṃ, itivuttakaṃ, jātakaṃ, abbhutadhammaṃ, vedallaṃ. Catuppadāya cepi, bhikkhu, gāthāya atthamaññāya dhammamaññāya dhammānudhammappaṭipanno hoti bahussuto dhammadharoti alaṃ vacanāyā’’ti.
‘‘Sādhu, bhante’’ti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā bhagavantaṃ uttari pañhaṃ apucchi – ‘‘‘sutavā nibbedhikapañño, sutavā nibbedhikapañño’ti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, sutavā nibbedhikapañño hotī’’ti?
‘‘Sādhu sādhu, bhikkhu! Bhaddako kho te, bhikkhu, ummaggo, bhaddakaṃ paṭibhānaṃ, kalyāṇī paripucchā. Evañhi tvaṃ, bhikkhu, pucchasi – ‘sutavā nibbedhikapañño, sutavā nibbedhikapaññoti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, sutavā nibbedhikapañño hotī’’’ti? ‘‘Evaṃ, bhante’’. ‘‘Idha, bhikkhu, bhikkhuno ‘idaṃ dukkha’nti sutaṃ hoti, paññāya cassa atthaṃ ativijjha passati; ‘ayaṃ dukkhasamudayo’ti sutaṃ hoti, paññāya cassa atthaṃ ativijjha passati; ‘ayaṃ dukkhanirodho’ti sutaṃ hoti, paññāya cassa atthaṃ ativijjha passati; ‘ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ti sutaṃ hoti, paññāya cassa atthaṃ ativijjha passati. Evaṃ kho, bhikkhu, sutavā nibbedhikapañño hotī’’ti.
‘‘Sādhu, bhante’’ti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā bhagavantaṃ uttari pañhaṃ apucchi – ‘‘‘paṇḍito mahāpañño, paṇḍito mahāpañño’ti, bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, paṇḍito mahāpañño hotī’’ti?
‘‘Sādhu sādhu bhikkhu! Bhaddako kho te, bhikkhu, ummaggo, bhaddakaṃ paṭibhānaṃ, kalyāṇī paripucchā. Evañhi tvaṃ bhikkhu pucchasi – ‘paṇḍito mahāpañño, paṇḍito mahāpaññoti , bhante, vuccati. Kittāvatā nu kho, bhante, paṇḍito mahāpañño hotī’’’ti? ‘‘Evaṃ, bhante’’. ‘‘Idha, bhikkhu, paṇḍito mahāpañño nevattabyābādhāya ceteti na parabyābādhāya ceteti na ubhayabyābādhāya ceteti attahitaparahitaubhayahitasabbalokahitameva cintayamāno cinteti. Evaṃ kho, bhikkhu, paṇḍito mahāpañño hotī’’ti. Chaṭṭhaṃ.
|
|
|
|
|
|
|
|
原始仏典 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-