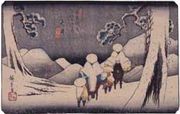みなさんに勧められて、旅日記を立ち上げることにしました。
まずは、2009.4.2.に中山道に旅立つまでについて書きます。
2009年3月26日(木)に東海道五十三次制覇、全行程495.5km歩き終えて、京都三条大橋にたどり着き、1週間目の4月2日(木)。
アル中(歩き中毒)にかかってしまった私は、新しい旅に飛び出しました。
数日前にアマゾンに注文しておいた中山道を歩くガイド本が届き、朝読み始めたら、矢も盾もたまらず、家を飛び出して電車に乗っていました。
旅立ちは、ちょっとの勇気と計画と、たくさんの思いきりと、あとはやっぱり浪漫かなあ。
文芸社「誰でも歩ける中山道六十九次 上巻」(日殿言成著)
上中下、三巻に分かれている上巻を持って出ましたが…バックに入りきらないので、本用に小さな手提げを持っていきました。
この本、地図が詳細で説明も分かりやすく、この上中下の三巻があれば、誰でも京都まで(事情があって、草津宿の手前の守山宿までしか案内がありませんが)行けそうな、素晴らしいガイド本です。
表紙をめくると、「はじめに」の文は、著者の日殿言成さんではなく、彼のお姉さんが書いていました。
著者プロフィールを見たら…
日殿言成(ひとのいいなり)はペンネーム。昭和26年に東京麻布に生まれ、大学卒業後、某ファミリーレストランの店長などを務め、その後、腎臓病で入院。平成2年から人工透析を始め、15年間病気と闘いながら、一日一歩の思いで歩き続け、自分の足で調べながら、少しずつ記録したものの集大成が、このガイド本。
平成17年5月永眠。計算すると53歳で亡くなっているんですね。
「はじめに」の最後の方に、「ふと、『青空が見たい』『おいしい空気が吸いたい』と思った時に、この本を片手に歩いてみたら、著者『日殿言成』の思いと感性にふれ、彼が一緒に道案内してくれるのではないかと期待してしまうのです…」
泣けました。電車の中で、涙、出ちゃいました。
これを読んだから、今日、旅立ちたくなったのです。
著者によると、中山道は東海道に比べて、すごく遠いイメージがあるけれど、実は東海道より39〜41kmしか長くなく、さらに、川止めされると何日かかるかわからない東海道に比べて安定していたため、女性の旅人が意外に多かったのだそうです。
字数制限になってしまったので、旅立ちまで、について、次に続けて書かせていただきます。
まずは、2009.4.2.に中山道に旅立つまでについて書きます。
2009年3月26日(木)に東海道五十三次制覇、全行程495.5km歩き終えて、京都三条大橋にたどり着き、1週間目の4月2日(木)。
アル中(歩き中毒)にかかってしまった私は、新しい旅に飛び出しました。
数日前にアマゾンに注文しておいた中山道を歩くガイド本が届き、朝読み始めたら、矢も盾もたまらず、家を飛び出して電車に乗っていました。
旅立ちは、ちょっとの勇気と計画と、たくさんの思いきりと、あとはやっぱり浪漫かなあ。
文芸社「誰でも歩ける中山道六十九次 上巻」(日殿言成著)
上中下、三巻に分かれている上巻を持って出ましたが…バックに入りきらないので、本用に小さな手提げを持っていきました。
この本、地図が詳細で説明も分かりやすく、この上中下の三巻があれば、誰でも京都まで(事情があって、草津宿の手前の守山宿までしか案内がありませんが)行けそうな、素晴らしいガイド本です。
表紙をめくると、「はじめに」の文は、著者の日殿言成さんではなく、彼のお姉さんが書いていました。
著者プロフィールを見たら…
日殿言成(ひとのいいなり)はペンネーム。昭和26年に東京麻布に生まれ、大学卒業後、某ファミリーレストランの店長などを務め、その後、腎臓病で入院。平成2年から人工透析を始め、15年間病気と闘いながら、一日一歩の思いで歩き続け、自分の足で調べながら、少しずつ記録したものの集大成が、このガイド本。
平成17年5月永眠。計算すると53歳で亡くなっているんですね。
「はじめに」の最後の方に、「ふと、『青空が見たい』『おいしい空気が吸いたい』と思った時に、この本を片手に歩いてみたら、著者『日殿言成』の思いと感性にふれ、彼が一緒に道案内してくれるのではないかと期待してしまうのです…」
泣けました。電車の中で、涙、出ちゃいました。
これを読んだから、今日、旅立ちたくなったのです。
著者によると、中山道は東海道に比べて、すごく遠いイメージがあるけれど、実は東海道より39〜41kmしか長くなく、さらに、川止めされると何日かかるかわからない東海道に比べて安定していたため、女性の旅人が意外に多かったのだそうです。
字数制限になってしまったので、旅立ちまで、について、次に続けて書かせていただきます。
|
|
|
|
コメント(67)
> ビアヘーロさん
東海道を歩いた時は、出来るだけ昔の人が歩いた道、にこだわりましたが、実際には、昔の道は既に失われたり、橋がなかったりで、近似値を歩くしかありません。
今回、中山道は、あまり拘らず、行けたらいいなあ、と思いつつ、案外拘ってたりしますが(笑)
ガイド本を忘れた時、ブログを幾つか見て参考にしましたが、何を参考にするかによって、土手道を歩いたり歩かなかったり、の差も出てきて、さらに碓氷峠では、旧中山道は熊が出たり、雨が降ると通れない、とあったので、敢えて皇女和宮の道を行ったりもしました。
特に女性一人旅なので、危険なら違う道をとることも必要と思っています。
いずれにすよ、旅を楽しみたいですからね。
東海道を歩いた時は、出来るだけ昔の人が歩いた道、にこだわりましたが、実際には、昔の道は既に失われたり、橋がなかったりで、近似値を歩くしかありません。
今回、中山道は、あまり拘らず、行けたらいいなあ、と思いつつ、案外拘ってたりしますが(笑)
ガイド本を忘れた時、ブログを幾つか見て参考にしましたが、何を参考にするかによって、土手道を歩いたり歩かなかったり、の差も出てきて、さらに碓氷峠では、旧中山道は熊が出たり、雨が降ると通れない、とあったので、敢えて皇女和宮の道を行ったりもしました。
特に女性一人旅なので、危険なら違う道をとることも必要と思っています。
いずれにすよ、旅を楽しみたいですからね。
2009.4.15. 中山道ウォーキング第7日目 高崎〜板鼻〜安中〜松井田〜横川駅 前半
私の旅にとって、命、お金、ガイド本、スニーカー、そしてその次に大事な携帯電話を忘れて旅立ってしまった私。
時計代わりにしていたので…大丈夫、万歩計に時計が付いている。
カメラは…仕方ない、簡易カメラ(レンズ付きフィルム)を買おう。今日の写真は、レンズ付きフィルムで撮ったプリントを、また携帯電話で撮ったシロモノ。
一番困るのは、今夜の宿探しと、帰りの電車の時間を調べられないこと…
朝、5時に家を出て、電車に乗ってから、やっちまった!携帯がない!と心の中で絶叫し、それでも先日のガイド本忘れより何倍もまし、と気を取り直しました。
高崎に着いたのは、午前8時半頃。
駅に降り立ち、まずはコンビニでレンズ付きフィルムを2個買いました。
高崎宿本町三丁目の黒い土蔵の家などをウォッチングしながらぐんぐん歩きます。
道は赤坂通りと呼ばれる細い坂道へと入ります。高崎は昔は赤坂と呼ばれ、その後、和田と改名され、慶長三年、井伊直政が築城の際に高崎と改名したそうです。
赤坂をずっと進んだ先に古い造りの醤油店があり、その向かいのやはり古い建物を山田文庫として公開していますが、今日は休館日でした。
道は右に折れ、ずっと行った先に、君が代橋碑がありました。
200メートルほどサイクリングロードを歩き、新しい君が代橋で国道18号線と合流すると、左奥に高崎観音が小さく見え、前には妙義山が見えました。今日はずっと妙義山を見ながら歩きました。
また、近くの低い山々は、新緑と山桜が柔らかな色合いを見せて、気持ちよく歩けました。
国道から離れた静かな道の豊岡という所では、ダルマを作っている家の前に、「高崎だるまあります」という幟が何本も立っていました。
豊岡の茶屋本陣は無料で見学できました。
茶屋本陣は泊まれないので狭いのですが、大名が休憩する上段の間は、東海道で見た本陣より装飾が立派でした。
再びR15と合流し、国道脇の碓氷川の土手の下の歩道を歩くと、藤塚一里塚がありました。(写真1)
板鼻下町の交差点で、右斜め方向に旧道に入り、板鼻川橋を渡った先に、双体道祖神がありました。(写真2)
信越線踏切を渡り、暫く行くと板鼻宿。
公民館が本陣跡で、奥の資料館にここに宿泊した皇女和宮についての展示がありました。資料館は無料で見られますが、声をかけて鍵を開けてもらいます。昔の書院を資料館として使っています。
和宮の下向ルートはほぼ中山道でしたが、花嫁道具の輸送ルートは東海道だったことが、資料で分かりました。
板鼻宿を抜け、碓氷の渡し場跡を左折して高之巣橋を渡り、その先、右折して小さい橋を渡ると、遠くにハウルの動く城みたいな要塞のような物が見えました。安中の亜鉛精錬工場だそうです。
Y字の右側の静かな道を行くと、道祖神が点在する辺りを左へ右へと曲がり、国道に合流するとやがて久芳橋で、ちょうど正午の時報がウ〜ウ〜と鳴り響きました。
下野尻で国道と分かれ、暫く行くと、100円ショップがあったので、黒い細いゴム紐を買いました。風が強くて帽子が飛ぶので、ゴム紐で飛ばないように工夫してみました。
その先、郵便局脇に安中宿本陣跡がありました。
東海道ウォーキングの時は、なるべく旧東海道を歩くことにこだわりましたが、今度の中山道ウォーキングは、かなり柔軟に行こう、と決めているので、伝馬町交差点で曲がって一本脇の大名小路を歩きました。
旧碓氷郡役所、垂れ桜がきれいな安中教会、そして有料公開されている郡奉行役宅と武家長屋を見学。郡奉行役宅の管理人さんから、「男部屋」の説明と、この近所に、この家で生まれ育ったお嬢さんが90何歳で元気でおられて、当時の暮らしについて話してくれたことを二、三、聞きました。
まず、男部屋と言うのは、当時まだ暗い早朝に出勤してきて、薪割りをして竈に火を起こしたり、井戸水を汲んで湯を沸かし、夜遅くまで働いては家に帰る通いの男の人がいて、その人は、土間より上には上がってはいけない決まりになっていたため、疲れて休みたいときに、ちょっと腰掛けるだけの板の間のスペースをもらっていて、それを男部屋と言います。覗いてみると、横になるほどの長さはなく、本当に腰掛けるだけ。
また、この家のお嬢さんは、自分で足袋を履いたことがないそうです。朝、起きれば、使用人の女性が足袋を履かせてくれる。しかし、そんなお嬢様がとにかく辛かったのは、寒い時期の湯殿。当時は湯船はなく、沸かしたお湯をかけてもらうだけだったそうですが、実際見学してみてなるほど、と思いましたが、板の壁は隙間だらけ。特に上下に隙間がある。昔のシャワーは命がけだったんですね。
(後半へ続く)
私の旅にとって、命、お金、ガイド本、スニーカー、そしてその次に大事な携帯電話を忘れて旅立ってしまった私。
時計代わりにしていたので…大丈夫、万歩計に時計が付いている。
カメラは…仕方ない、簡易カメラ(レンズ付きフィルム)を買おう。今日の写真は、レンズ付きフィルムで撮ったプリントを、また携帯電話で撮ったシロモノ。
一番困るのは、今夜の宿探しと、帰りの電車の時間を調べられないこと…
朝、5時に家を出て、電車に乗ってから、やっちまった!携帯がない!と心の中で絶叫し、それでも先日のガイド本忘れより何倍もまし、と気を取り直しました。
高崎に着いたのは、午前8時半頃。
駅に降り立ち、まずはコンビニでレンズ付きフィルムを2個買いました。
高崎宿本町三丁目の黒い土蔵の家などをウォッチングしながらぐんぐん歩きます。
道は赤坂通りと呼ばれる細い坂道へと入ります。高崎は昔は赤坂と呼ばれ、その後、和田と改名され、慶長三年、井伊直政が築城の際に高崎と改名したそうです。
赤坂をずっと進んだ先に古い造りの醤油店があり、その向かいのやはり古い建物を山田文庫として公開していますが、今日は休館日でした。
道は右に折れ、ずっと行った先に、君が代橋碑がありました。
200メートルほどサイクリングロードを歩き、新しい君が代橋で国道18号線と合流すると、左奥に高崎観音が小さく見え、前には妙義山が見えました。今日はずっと妙義山を見ながら歩きました。
また、近くの低い山々は、新緑と山桜が柔らかな色合いを見せて、気持ちよく歩けました。
国道から離れた静かな道の豊岡という所では、ダルマを作っている家の前に、「高崎だるまあります」という幟が何本も立っていました。
豊岡の茶屋本陣は無料で見学できました。
茶屋本陣は泊まれないので狭いのですが、大名が休憩する上段の間は、東海道で見た本陣より装飾が立派でした。
再びR15と合流し、国道脇の碓氷川の土手の下の歩道を歩くと、藤塚一里塚がありました。(写真1)
板鼻下町の交差点で、右斜め方向に旧道に入り、板鼻川橋を渡った先に、双体道祖神がありました。(写真2)
信越線踏切を渡り、暫く行くと板鼻宿。
公民館が本陣跡で、奥の資料館にここに宿泊した皇女和宮についての展示がありました。資料館は無料で見られますが、声をかけて鍵を開けてもらいます。昔の書院を資料館として使っています。
和宮の下向ルートはほぼ中山道でしたが、花嫁道具の輸送ルートは東海道だったことが、資料で分かりました。
板鼻宿を抜け、碓氷の渡し場跡を左折して高之巣橋を渡り、その先、右折して小さい橋を渡ると、遠くにハウルの動く城みたいな要塞のような物が見えました。安中の亜鉛精錬工場だそうです。
Y字の右側の静かな道を行くと、道祖神が点在する辺りを左へ右へと曲がり、国道に合流するとやがて久芳橋で、ちょうど正午の時報がウ〜ウ〜と鳴り響きました。
下野尻で国道と分かれ、暫く行くと、100円ショップがあったので、黒い細いゴム紐を買いました。風が強くて帽子が飛ぶので、ゴム紐で飛ばないように工夫してみました。
その先、郵便局脇に安中宿本陣跡がありました。
東海道ウォーキングの時は、なるべく旧東海道を歩くことにこだわりましたが、今度の中山道ウォーキングは、かなり柔軟に行こう、と決めているので、伝馬町交差点で曲がって一本脇の大名小路を歩きました。
旧碓氷郡役所、垂れ桜がきれいな安中教会、そして有料公開されている郡奉行役宅と武家長屋を見学。郡奉行役宅の管理人さんから、「男部屋」の説明と、この近所に、この家で生まれ育ったお嬢さんが90何歳で元気でおられて、当時の暮らしについて話してくれたことを二、三、聞きました。
まず、男部屋と言うのは、当時まだ暗い早朝に出勤してきて、薪割りをして竈に火を起こしたり、井戸水を汲んで湯を沸かし、夜遅くまで働いては家に帰る通いの男の人がいて、その人は、土間より上には上がってはいけない決まりになっていたため、疲れて休みたいときに、ちょっと腰掛けるだけの板の間のスペースをもらっていて、それを男部屋と言います。覗いてみると、横になるほどの長さはなく、本当に腰掛けるだけ。
また、この家のお嬢さんは、自分で足袋を履いたことがないそうです。朝、起きれば、使用人の女性が足袋を履かせてくれる。しかし、そんなお嬢様がとにかく辛かったのは、寒い時期の湯殿。当時は湯船はなく、沸かしたお湯をかけてもらうだけだったそうですが、実際見学してみてなるほど、と思いましたが、板の壁は隙間だらけ。特に上下に隙間がある。昔のシャワーは命がけだったんですね。
(後半へ続く)
2009.4.15. 中山道ウォーキング7日目後半 安中〜松井田〜横川駅
武家長屋から中山道へ戻る途中にあった食事処で山菜うどんを食べました。
旧中山道に戻ると、あちこちに倉がありました。
その先、昔は杉並木だったそうですが、杉は残っていません。
18号線をまたぐと、その先に杉並木がありました。
原市、郷原と進み…
やがて国道とぶつかる左側にセブンイレブン。トイレ休憩後、国道に入りましたが、道の左側に渡りたいのに渡れない。車は頻繁に通るから無理矢理には渡れないし、渡っても反対側には歩道もなくて危険…と様子を見ながら歩いていたら、結局かなり行きすぎて、戻るのもバカらしい上、歩道がなくて危険なので、旧道は諦めて松井田方面への県道を行きました。
さっきは、敢えて旧中山道ではなく大名小路を歩いたけれど…分かっていて違う道を歩くのと、不本意に違う道を歩くことを余儀なくされるのでは全然違います。なんだか悔しい。
暫く行くと、さっき入りそびれて別れ別れになっていた、旧中山道と涙の再会。
松井田脇本陣があった所辺りで、小学校低学年のジャージの女の子に挨拶されました。こんな小さな子から、向こうから挨拶されてドギマギ。嬉しい!
松井田城址の石垣と、補陀寺の門の写真を撮り…
その先で、道祖神の写真を撮っていたら、地元の方に、「一里塚はここですよ」と声をかけられました。
「立て札はここにあるけど、あの奥にちょっとだけこんもり見えているのが一里塚。昔の4分の1になっちゃったらしいけど」
「家の脇(庭)を通っていっても構いませんよ」と言うということは、ここの家の方なのね。
「そちらの道からも回っていけますよ」
お礼を言って、遠回りの道から回ってみましたが…
裏から見ると、さっきは小さいながらも小高く塚らしく見えたのに、反対側からだと、草ぼうぼうの中に木があるようにしか見えませんでした…
気づくともう16時半。最近夕方も明るいから、うっかりしてました。やばい!ペースを上げろ!
時間がないからパスしようと思っていた、五料村の茶屋本陣のお西、お東。急いで線路を渡って見に行くと、門だけでも立派で、外から立派な建物が見えましたが、夕方だからか、休館日なのか、閉まっていました。
暫くグングン歩き、左側に双体道祖神があったので、しゃがみこんで妙義山をバックに道祖神を撮りました。(写真1)
その先、右折して線路を渡ると、上り坂の細い道。夕方に山に入っていく雰囲気の道は、ちょっと不安になりますが、行ってみると陽当たりのいい気持ちのいい道で、草に半分埋もれた道祖神を見つけて写真を撮り、気分がハイになりました。
中学生の頃、道祖神を訪ねて写真を撮る旅をしてみたい、と思っていましたが、その夢が、今、実現している!
道は急な上りになり、それが空にぶつかる右側に、青面金剛塔。
その先、坂の頂点に、夜泣き地蔵と茶釜石。茶釜石を、上に置いてある石で叩いてみると、確かに鉄製の茶釜みたいに響きます。
下り坂となり、草の中に地蔵が2つ点在。(写真2)
果樹園の中を、ゆるやなか上りとなり、下りとなり…
馬頭観音があり、川を渡り、線路沿いの道に出ました。17時のチャイムはイエスタデイ。夕暮れにピッタリ。
碓氷神社を右に見て、左の踏切を渡り、国道をまたいだ正面は、妙義山を背負った臼井小学校。
道は再び国道に合流。右に山、左下に川。川の向こうも山。
川から霧(靄?)が上がってきて、夕陽に照らされてキラキラ光っていました。
左に、釜飯発祥地、横川のおぎのやがあり、そのすぐ左奥が横川駅。
横川で泊まれるところを探そうと思っていたけれど、案内所もないし、無理そうなので、バスで軽井沢まで行こうと思い、時間を調べたら、現在17:34で、バスは18:10。
飲み物を買って、上着を着て、うろうろしていたら、「宿泊」と書いてある建物発見。
ダメ元で聞いてみたところ、泊まれることになりました。
横川には泊まれるところがここだけ、という東京屋。
今日の宿泊客は私だけ。
2階の鉄線の間に通され、みすず飴とお茶で一服しました。
本日の宿までの歩数は47,916歩。距離は34.31km。平均時速4.85km。
風呂の準備が出来、汗を流して、大きな湯船に浸かった時、幸せだなあ、と思いました。
急に来たのに、すばらしい御馳走でした。
自家製合鴨燻製サラダ、田芹お浸し、こんにゃく田楽、ヤマメ唐揚げトマトソース、おきりこみ(群馬の郷土料理。うどんと野菜の汁物で、甲州のほうとうを思い出しました)、天婦羅(山椒、タラの芽、しめじ、ふなっぷえんどう、海老)、煮物(高野豆腐、里芋、椎茸)、香の物、ご飯。
生ビールを2杯飲みました。
今日採ってきたばかりという山椒、タラの芽、芹が美味しかった。
23時に寝ました。
武家長屋から中山道へ戻る途中にあった食事処で山菜うどんを食べました。
旧中山道に戻ると、あちこちに倉がありました。
その先、昔は杉並木だったそうですが、杉は残っていません。
18号線をまたぐと、その先に杉並木がありました。
原市、郷原と進み…
やがて国道とぶつかる左側にセブンイレブン。トイレ休憩後、国道に入りましたが、道の左側に渡りたいのに渡れない。車は頻繁に通るから無理矢理には渡れないし、渡っても反対側には歩道もなくて危険…と様子を見ながら歩いていたら、結局かなり行きすぎて、戻るのもバカらしい上、歩道がなくて危険なので、旧道は諦めて松井田方面への県道を行きました。
さっきは、敢えて旧中山道ではなく大名小路を歩いたけれど…分かっていて違う道を歩くのと、不本意に違う道を歩くことを余儀なくされるのでは全然違います。なんだか悔しい。
暫く行くと、さっき入りそびれて別れ別れになっていた、旧中山道と涙の再会。
松井田脇本陣があった所辺りで、小学校低学年のジャージの女の子に挨拶されました。こんな小さな子から、向こうから挨拶されてドギマギ。嬉しい!
松井田城址の石垣と、補陀寺の門の写真を撮り…
その先で、道祖神の写真を撮っていたら、地元の方に、「一里塚はここですよ」と声をかけられました。
「立て札はここにあるけど、あの奥にちょっとだけこんもり見えているのが一里塚。昔の4分の1になっちゃったらしいけど」
「家の脇(庭)を通っていっても構いませんよ」と言うということは、ここの家の方なのね。
「そちらの道からも回っていけますよ」
お礼を言って、遠回りの道から回ってみましたが…
裏から見ると、さっきは小さいながらも小高く塚らしく見えたのに、反対側からだと、草ぼうぼうの中に木があるようにしか見えませんでした…
気づくともう16時半。最近夕方も明るいから、うっかりしてました。やばい!ペースを上げろ!
時間がないからパスしようと思っていた、五料村の茶屋本陣のお西、お東。急いで線路を渡って見に行くと、門だけでも立派で、外から立派な建物が見えましたが、夕方だからか、休館日なのか、閉まっていました。
暫くグングン歩き、左側に双体道祖神があったので、しゃがみこんで妙義山をバックに道祖神を撮りました。(写真1)
その先、右折して線路を渡ると、上り坂の細い道。夕方に山に入っていく雰囲気の道は、ちょっと不安になりますが、行ってみると陽当たりのいい気持ちのいい道で、草に半分埋もれた道祖神を見つけて写真を撮り、気分がハイになりました。
中学生の頃、道祖神を訪ねて写真を撮る旅をしてみたい、と思っていましたが、その夢が、今、実現している!
道は急な上りになり、それが空にぶつかる右側に、青面金剛塔。
その先、坂の頂点に、夜泣き地蔵と茶釜石。茶釜石を、上に置いてある石で叩いてみると、確かに鉄製の茶釜みたいに響きます。
下り坂となり、草の中に地蔵が2つ点在。(写真2)
果樹園の中を、ゆるやなか上りとなり、下りとなり…
馬頭観音があり、川を渡り、線路沿いの道に出ました。17時のチャイムはイエスタデイ。夕暮れにピッタリ。
碓氷神社を右に見て、左の踏切を渡り、国道をまたいだ正面は、妙義山を背負った臼井小学校。
道は再び国道に合流。右に山、左下に川。川の向こうも山。
川から霧(靄?)が上がってきて、夕陽に照らされてキラキラ光っていました。
左に、釜飯発祥地、横川のおぎのやがあり、そのすぐ左奥が横川駅。
横川で泊まれるところを探そうと思っていたけれど、案内所もないし、無理そうなので、バスで軽井沢まで行こうと思い、時間を調べたら、現在17:34で、バスは18:10。
飲み物を買って、上着を着て、うろうろしていたら、「宿泊」と書いてある建物発見。
ダメ元で聞いてみたところ、泊まれることになりました。
横川には泊まれるところがここだけ、という東京屋。
今日の宿泊客は私だけ。
2階の鉄線の間に通され、みすず飴とお茶で一服しました。
本日の宿までの歩数は47,916歩。距離は34.31km。平均時速4.85km。
風呂の準備が出来、汗を流して、大きな湯船に浸かった時、幸せだなあ、と思いました。
急に来たのに、すばらしい御馳走でした。
自家製合鴨燻製サラダ、田芹お浸し、こんにゃく田楽、ヤマメ唐揚げトマトソース、おきりこみ(群馬の郷土料理。うどんと野菜の汁物で、甲州のほうとうを思い出しました)、天婦羅(山椒、タラの芽、しめじ、ふなっぷえんどう、海老)、煮物(高野豆腐、里芋、椎茸)、香の物、ご飯。
生ビールを2杯飲みました。
今日採ってきたばかりという山椒、タラの芽、芹が美味しかった。
23時に寝ました。
2009.4.16. 中山道ウォーキング8日目 横川〜坂本〜碓氷峠〜軽井沢〜沓掛 前半
美味しい朝食をいただき、東京屋のご夫妻に見送られて8時に出発。
碓氷関所跡の門には、花びらが舞っていました。
暫く行くと、国道と少しだけ合流。国道は大きく左へカーブ、旧中山道はまっすぐ進みます。
左に薬師堂、そこから薬師坂。焦らずゆっくり坂を上っていくと、国道に出て、右へ。
高速道路の下辺りに、「みんなのトイレ」があって、助かりました。
横川から2.5kmで坂本宿。
脇本陣だった永井家、昔の坂本宿の面影を残す「かぎや」などを写真に撮りました。
昨日買ったフィルム付きレンズの2本目の残り枚数が少なくなっていて、横川でも、坂本宿のデイリーヤマザキでも買えなかったので、フィルムの残り枚数を考えながら、撮るものを限定しました。
右に宿外れの木戸跡があり、そのすぐ先に、刎石(はねいし)の芭蕉句碑。「ひとつ脱いでうしろにおひぬ衣がえ」
建物が切れて寂しくなってきた辺り、国道が右にカーブする手前に、左に入っていく林道赤松線が旧中山道。
ガイド本には、草ぼうぼうの道とありましたが、草はきれいに刈られていました。
左に溜め池があり、坂を上っていくと道はキュッと左に曲がります。
草ぼうぼうで、右手の階段入り口が分かりづらい、とありましたが、すぐに階段は分かりました。
倒れた電柱が、土砂を塞き止めて、道の一部と化していました。
急な坂を上ると、ガードレールの切れたところから国道に出ます。
斜め正面に旧バス停跡の小屋。旧バス停左脇から、山道に入り、いよいよ碓氷峠越え。
碓氷峠越えは、過去2回やったことがあり、今回が一番道が整備されて歩きやすく感じました。
山道に入ってすぐの急坂は松ノ木坂。
急坂がいったん落ち着いた辺りが、堂峰番所跡。「安政遠足ゴールまで8.0km」という立て札。安中市が毎年5月第2日曜日に行っている、安政遠足の案内板です。昔の行事に倣い、鎧甲冑を着けて、安中市内から碓氷峠の熊野神社まで走るそうです。歩くだけでもきつい山道を、よく走れるなあ、とびっくりします。
上りが続き、ところどころにロープが張られ、「危険注意」の札。
上り道が左に曲がっている正面に、ケルンが積んであり、その奥に縦すじの結晶の集合体みたいな岩肌が見えます。(写真)
「柱状節理」というもので、説明によると、「火成岩が冷却、固結するとき、き裂を生じ、自然に四角または六角の柱状に割れたものである」
刎石(はねいし)坂には、馬頭観音と大日尊がありました。坂本宿で見た芭蕉句碑も、昔はここにあったらしい。
上りがずっと続き、上り地蔵下り地蔵と書かれた岩壁のところを巻き込んでいき、覗(のぞき)と呼ばれる、眼下に坂本宿を見下ろせる場所。その先に風穴がありました。
右奥に弘法の井戸。
もう少し先、右に四軒茶屋跡。
道がわりと平坦になり、杉木立の気持ちいい道になりました。
左にあずまや。
下り道になり、堀切りと呼ばれる、道の両脇が切れて、馬の背のように細くなっている所がありました。
その先、左に大きくカーブしていてロープが張られている場所は左が谷で、気を付けなければいけません。
南向馬頭観音は小さいので見逃しやすい、とガイド本にありましたが、立て札の回りを随分探したけれど、見つけられませんでした。私が見つけられなかっただけなのか、実際、なかったのか。風化して崩れてしまったり、嵐などで流されてしまったり、時には、誰かに持ち去られてしまうこともあるそうです。
北向馬頭観音は、小高いところに立っていました。
左に一里塚跡の看板。
緩い坂を上っていると、上から落ち葉の絨毯がそこだけ膨らんだような茶色のかたまりが下りてきました。
なんだろう、と見ていたら、オコジョでした。
オコジョは鈍いのか、人間に脅かされたことがないからか、私に向かって下りてきました。
1メートルぐらいまで接近すると、オコジョもさすがに私に気がつき、慌てて右手に逃げていきました。
急な坂を上りきると、「座頭ころがし」の立て札。赤土で滑りやすいらしい坂ですが、落ち葉の絨毯のおかげで、滑らず、膝にもやさしい。
朴葉と思われる大きな葉が沢山落ちていて、裏が白っぽく、まるで紙屑を散らしたみたいに見えました。
座頭ころがしの先で休憩しようと、座りやすい岩か木の根を求めて少し先まで進んだら廃車が見えて、なんだか怖いので、それ以上近づくのはやめて休憩しました。
廃車は窓ガラスが全部なくなって、ボロボロのシートが見えていましたが、何かが潜んでいるような気がしました。
後半へ続く
美味しい朝食をいただき、東京屋のご夫妻に見送られて8時に出発。
碓氷関所跡の門には、花びらが舞っていました。
暫く行くと、国道と少しだけ合流。国道は大きく左へカーブ、旧中山道はまっすぐ進みます。
左に薬師堂、そこから薬師坂。焦らずゆっくり坂を上っていくと、国道に出て、右へ。
高速道路の下辺りに、「みんなのトイレ」があって、助かりました。
横川から2.5kmで坂本宿。
脇本陣だった永井家、昔の坂本宿の面影を残す「かぎや」などを写真に撮りました。
昨日買ったフィルム付きレンズの2本目の残り枚数が少なくなっていて、横川でも、坂本宿のデイリーヤマザキでも買えなかったので、フィルムの残り枚数を考えながら、撮るものを限定しました。
右に宿外れの木戸跡があり、そのすぐ先に、刎石(はねいし)の芭蕉句碑。「ひとつ脱いでうしろにおひぬ衣がえ」
建物が切れて寂しくなってきた辺り、国道が右にカーブする手前に、左に入っていく林道赤松線が旧中山道。
ガイド本には、草ぼうぼうの道とありましたが、草はきれいに刈られていました。
左に溜め池があり、坂を上っていくと道はキュッと左に曲がります。
草ぼうぼうで、右手の階段入り口が分かりづらい、とありましたが、すぐに階段は分かりました。
倒れた電柱が、土砂を塞き止めて、道の一部と化していました。
急な坂を上ると、ガードレールの切れたところから国道に出ます。
斜め正面に旧バス停跡の小屋。旧バス停左脇から、山道に入り、いよいよ碓氷峠越え。
碓氷峠越えは、過去2回やったことがあり、今回が一番道が整備されて歩きやすく感じました。
山道に入ってすぐの急坂は松ノ木坂。
急坂がいったん落ち着いた辺りが、堂峰番所跡。「安政遠足ゴールまで8.0km」という立て札。安中市が毎年5月第2日曜日に行っている、安政遠足の案内板です。昔の行事に倣い、鎧甲冑を着けて、安中市内から碓氷峠の熊野神社まで走るそうです。歩くだけでもきつい山道を、よく走れるなあ、とびっくりします。
上りが続き、ところどころにロープが張られ、「危険注意」の札。
上り道が左に曲がっている正面に、ケルンが積んであり、その奥に縦すじの結晶の集合体みたいな岩肌が見えます。(写真)
「柱状節理」というもので、説明によると、「火成岩が冷却、固結するとき、き裂を生じ、自然に四角または六角の柱状に割れたものである」
刎石(はねいし)坂には、馬頭観音と大日尊がありました。坂本宿で見た芭蕉句碑も、昔はここにあったらしい。
上りがずっと続き、上り地蔵下り地蔵と書かれた岩壁のところを巻き込んでいき、覗(のぞき)と呼ばれる、眼下に坂本宿を見下ろせる場所。その先に風穴がありました。
右奥に弘法の井戸。
もう少し先、右に四軒茶屋跡。
道がわりと平坦になり、杉木立の気持ちいい道になりました。
左にあずまや。
下り道になり、堀切りと呼ばれる、道の両脇が切れて、馬の背のように細くなっている所がありました。
その先、左に大きくカーブしていてロープが張られている場所は左が谷で、気を付けなければいけません。
南向馬頭観音は小さいので見逃しやすい、とガイド本にありましたが、立て札の回りを随分探したけれど、見つけられませんでした。私が見つけられなかっただけなのか、実際、なかったのか。風化して崩れてしまったり、嵐などで流されてしまったり、時には、誰かに持ち去られてしまうこともあるそうです。
北向馬頭観音は、小高いところに立っていました。
左に一里塚跡の看板。
緩い坂を上っていると、上から落ち葉の絨毯がそこだけ膨らんだような茶色のかたまりが下りてきました。
なんだろう、と見ていたら、オコジョでした。
オコジョは鈍いのか、人間に脅かされたことがないからか、私に向かって下りてきました。
1メートルぐらいまで接近すると、オコジョもさすがに私に気がつき、慌てて右手に逃げていきました。
急な坂を上りきると、「座頭ころがし」の立て札。赤土で滑りやすいらしい坂ですが、落ち葉の絨毯のおかげで、滑らず、膝にもやさしい。
朴葉と思われる大きな葉が沢山落ちていて、裏が白っぽく、まるで紙屑を散らしたみたいに見えました。
座頭ころがしの先で休憩しようと、座りやすい岩か木の根を求めて少し先まで進んだら廃車が見えて、なんだか怖いので、それ以上近づくのはやめて休憩しました。
廃車は窓ガラスが全部なくなって、ボロボロのシートが見えていましたが、何かが潜んでいるような気がしました。
後半へ続く
2009.4.16. 中山道ウォーキング8日目 後半 碓氷峠〜軽井沢〜沓掛
小休憩を終えて廃車の脇を通り抜けましたが、その先、今までよりは平坦になったとはいえ、木があったり、道幅的にも車は通れそうにありません。
楳図かずおの「漂流教室」や、時空を越えたSFを思い出し、この車はこの山道を走ってきたわけではなく、タイムマシンみたいに突然ここに現れて捨てられたのではないか、と思いたくなるぐらい、走ってくるには無理のある場所でした。
栗が原付近、とても気持ちがいい。
その先、ガイド本には、熊笹の道、笹で道が塞がれている、とありましたが、よく整備されていました。
その先に、また杉木立があり、とても気持ちがいい道。
過去に碓氷峠越えをした時の、今まで忘れていたいろいろなことが思い出され、人間の記憶の襞はおもしろいと思います。
暫く行くと、山中茶屋跡、山中小学校跡。比較的新しい廃屋がありました。
その付近から先は道が広くなり、その先にまた、廃車がありました。
左側に、「一ッ家跡」の立て札。昔、この辺りに一人の老婆がいて、旅人を苦しめたという、と説明がされていましたが、山姥?鬼婆?
以前は家族で茶屋をしていて、みんな亡くなって一人残され、本人は旅人と話がしたかったのに、旅人が怖がって逃げた、というのが真実ではないか、と、想像…。
やがて、子持山の立てと、陣馬が原の立て札。ここが分岐で、旧中山道は左に入ります。右の林道は、皇女和宮の道&安政遠足の道。
ガイド本によると、旧中山道は熊が出たり、雨で増水すると通れないところがあり、東京屋の方も、旧中山道は通れないかもしれない、と言っていたので、私は皇女和宮の道を通ることにしました。一人旅だから、回避できる危険は回避して、安全な旅を心がけるべきだと思います。
林道歩きは変化には乏しいけれど、一定に歩けるので、ぐんぐん距離を伸ばしました。
昔、何らかの施設があった跡地の廃屋、廃バスがあり、その少し先には、また廃車がありました。
暫くすると、旧中山道と合流。ちょうど合流地点付近に、仁王門跡、思婦石などがありました。思婦石は、ヤマトタケルが亡き妻、オトタチバナヒメを思って嘆いた、という故事に因んだもの。
ヤマトタケルが走水で入水したオトタチバナヒメを思って「あづまはや」と言ったのが、ここの碓氷峠という説が一番の定説になっていますが、実は碓氷峠は3カ所あって、私は学生時代に、ヤマトタケルが「あづまはや」と嘆いた碓氷峠は、箱根の碓氷坂ではないか、という説を書いたことがあります。
暫く林道へと進むと、霧積温泉への道との分岐に出ました。
西条八十の帽子の詩を思い出しました。
「母さん、僕のあの帽子、どうしたんでせうね?
ええ、夏、碓氷から霧積へゆくみちで、
谷底へ落としたあの麦わら帽子ですよ。(後略)」
松田優作主演、ジョー山中の主題歌で話題となった映画「人間の証明」の1シーンで、吊り橋から麦わら帽子が落ちていく、あのシーンが目に浮かんできました。
暫く行くと、道はアスファルトになり、右に熊野神社。11:31。ずっと一緒に歩んできた安政遠足のゴールです。
見晴らし亭などの何軒かの茶屋は、みんな休業でした。公衆トイレがありました。坂本宿手前の、みんなのトイレ以来のトイレでした。
見晴らし台は、何度も来たことがあるので今回はパスして、旧軽井沢へのハイキングコースに進みました。
このハイキングコースは、軽井沢に遊びに来たファミリーも利用する、歩きやすく、小さな橋や吊り橋などの変化に富んだハイキング道です。
坂本宿を出てから見晴らし茶屋まで、全く誰にも会わなかったのですが、このハイキング道で何人かの人に会い、挨拶を交わし合いました。
車道を渡る歩道橋があり、渡りきった鉄階段の踊り場が、バンッと音がして、足元がベコッと2回もなったので、鉄階段の強度が心配になりました。
吊り橋は、昔に比べて立派になった気がします。
旧軽井沢の別荘地に下りてきて、自転車置き場のトイレに着いたのは、12:34。
軽井沢の父、ショー記念碑を通りすぎ、芭蕉句碑「馬をさへながむる雪の朝(あした)かな」も通りすぎ、本陣跡はどこかな、と見ながら軽井沢銀座をどんどん下っていきました。
今日の軽井沢銀座は人が少なく、静かでした。(写真)
ロータリーに着いたのは、12:50。ロータリー脇の店でランチを食べました。
さらに旧中山道の雑木林の道を歩いて沓掛まで。
最初は離山を見て歩き、最後は浅間山を見て歩きました。
中軽井沢着が14:33。夜、用事があるため、今日の中山道ウォーキングはここまで。しなの鉄道に乗り、軽井沢から長野新幹線に乗って帰りました。
中軽井沢までの今日の歩数は、34,789歩。距離は24.72km。平均時速は4.50km。
小休憩を終えて廃車の脇を通り抜けましたが、その先、今までよりは平坦になったとはいえ、木があったり、道幅的にも車は通れそうにありません。
楳図かずおの「漂流教室」や、時空を越えたSFを思い出し、この車はこの山道を走ってきたわけではなく、タイムマシンみたいに突然ここに現れて捨てられたのではないか、と思いたくなるぐらい、走ってくるには無理のある場所でした。
栗が原付近、とても気持ちがいい。
その先、ガイド本には、熊笹の道、笹で道が塞がれている、とありましたが、よく整備されていました。
その先に、また杉木立があり、とても気持ちがいい道。
過去に碓氷峠越えをした時の、今まで忘れていたいろいろなことが思い出され、人間の記憶の襞はおもしろいと思います。
暫く行くと、山中茶屋跡、山中小学校跡。比較的新しい廃屋がありました。
その付近から先は道が広くなり、その先にまた、廃車がありました。
左側に、「一ッ家跡」の立て札。昔、この辺りに一人の老婆がいて、旅人を苦しめたという、と説明がされていましたが、山姥?鬼婆?
以前は家族で茶屋をしていて、みんな亡くなって一人残され、本人は旅人と話がしたかったのに、旅人が怖がって逃げた、というのが真実ではないか、と、想像…。
やがて、子持山の立てと、陣馬が原の立て札。ここが分岐で、旧中山道は左に入ります。右の林道は、皇女和宮の道&安政遠足の道。
ガイド本によると、旧中山道は熊が出たり、雨で増水すると通れないところがあり、東京屋の方も、旧中山道は通れないかもしれない、と言っていたので、私は皇女和宮の道を通ることにしました。一人旅だから、回避できる危険は回避して、安全な旅を心がけるべきだと思います。
林道歩きは変化には乏しいけれど、一定に歩けるので、ぐんぐん距離を伸ばしました。
昔、何らかの施設があった跡地の廃屋、廃バスがあり、その少し先には、また廃車がありました。
暫くすると、旧中山道と合流。ちょうど合流地点付近に、仁王門跡、思婦石などがありました。思婦石は、ヤマトタケルが亡き妻、オトタチバナヒメを思って嘆いた、という故事に因んだもの。
ヤマトタケルが走水で入水したオトタチバナヒメを思って「あづまはや」と言ったのが、ここの碓氷峠という説が一番の定説になっていますが、実は碓氷峠は3カ所あって、私は学生時代に、ヤマトタケルが「あづまはや」と嘆いた碓氷峠は、箱根の碓氷坂ではないか、という説を書いたことがあります。
暫く林道へと進むと、霧積温泉への道との分岐に出ました。
西条八十の帽子の詩を思い出しました。
「母さん、僕のあの帽子、どうしたんでせうね?
ええ、夏、碓氷から霧積へゆくみちで、
谷底へ落としたあの麦わら帽子ですよ。(後略)」
松田優作主演、ジョー山中の主題歌で話題となった映画「人間の証明」の1シーンで、吊り橋から麦わら帽子が落ちていく、あのシーンが目に浮かんできました。
暫く行くと、道はアスファルトになり、右に熊野神社。11:31。ずっと一緒に歩んできた安政遠足のゴールです。
見晴らし亭などの何軒かの茶屋は、みんな休業でした。公衆トイレがありました。坂本宿手前の、みんなのトイレ以来のトイレでした。
見晴らし台は、何度も来たことがあるので今回はパスして、旧軽井沢へのハイキングコースに進みました。
このハイキングコースは、軽井沢に遊びに来たファミリーも利用する、歩きやすく、小さな橋や吊り橋などの変化に富んだハイキング道です。
坂本宿を出てから見晴らし茶屋まで、全く誰にも会わなかったのですが、このハイキング道で何人かの人に会い、挨拶を交わし合いました。
車道を渡る歩道橋があり、渡りきった鉄階段の踊り場が、バンッと音がして、足元がベコッと2回もなったので、鉄階段の強度が心配になりました。
吊り橋は、昔に比べて立派になった気がします。
旧軽井沢の別荘地に下りてきて、自転車置き場のトイレに着いたのは、12:34。
軽井沢の父、ショー記念碑を通りすぎ、芭蕉句碑「馬をさへながむる雪の朝(あした)かな」も通りすぎ、本陣跡はどこかな、と見ながら軽井沢銀座をどんどん下っていきました。
今日の軽井沢銀座は人が少なく、静かでした。(写真)
ロータリーに着いたのは、12:50。ロータリー脇の店でランチを食べました。
さらに旧中山道の雑木林の道を歩いて沓掛まで。
最初は離山を見て歩き、最後は浅間山を見て歩きました。
中軽井沢着が14:33。夜、用事があるため、今日の中山道ウォーキングはここまで。しなの鉄道に乗り、軽井沢から長野新幹線に乗って帰りました。
中軽井沢までの今日の歩数は、34,789歩。距離は24.72km。平均時速は4.50km。
おかピョンさん、こんにちは。
私はおかピョンさんが歩いた5日前に碓氷を横川に向けて下りていたことになります。ですから「ああ、そうだった」と思う描写が随所にあり、おもしろかったです。例えば、花の舞う碓氷関所門とか、座頭ころがしのあたりの枯れ葉の絨毯とか(ただ、下りる身としては、ぶあつい枯れ葉の絨毯たぶんまちがいないとはどこに足をおろせばよいのか、慎重になりましたが。)
ところで、南向馬頭観音ですが、表示板と少し離れた上方にあったように思います。写真1が先日下りる途中で撮った南向馬頭観音ですが、私自身表示板と観音を別々の写真に納めているので、たぶん間違いないと思います。ちなみに写真2は去年の夏撮った北向馬頭観音です。
これからもお気をつけて、よい旅を。
私はおかピョンさんが歩いた5日前に碓氷を横川に向けて下りていたことになります。ですから「ああ、そうだった」と思う描写が随所にあり、おもしろかったです。例えば、花の舞う碓氷関所門とか、座頭ころがしのあたりの枯れ葉の絨毯とか(ただ、下りる身としては、ぶあつい枯れ葉の絨毯たぶんまちがいないとはどこに足をおろせばよいのか、慎重になりましたが。)
ところで、南向馬頭観音ですが、表示板と少し離れた上方にあったように思います。写真1が先日下りる途中で撮った南向馬頭観音ですが、私自身表示板と観音を別々の写真に納めているので、たぶん間違いないと思います。ちなみに写真2は去年の夏撮った北向馬頭観音です。
これからもお気をつけて、よい旅を。
2009.4.19. 中山道ウォーキング9日目 沓掛〜追分〜小田井〜岩村田〜塩名田〜八幡〜望月 前半
4時半にパンを食べ、5時に家を出て、東京から長野新幹線に乗りました。
車内では弁当を売りに来ていて、皆さんむしゃむしゃ召し上がってましたが、私はパンを食べてきたのでおなかがすかない。
軽井沢でしなの鉄道に乗り換え、中軽井沢駅に降り立ったのは、7:44。中軽井沢駅は昔は沓掛駅という名前だったそうです。中山道では沓掛宿です。
中軽井沢に着いてからお腹がすき、コンビニでおにぎりを2個買って食べました。次回、こういうことがあったら、家では食べないで新幹線で弁当を食べよう。
日曜なので混んでいるかと思いましたが、中軽井沢まで来るとひっそりしています。
空気は冷たいのですが、朝は斜めに日がさしてきて暑く感じます。
国道18号を離れて旧道を行くと、やや上りではあるけれど、静かで気持ちがいい道。
R18と合流したり離れたりを何回か繰り返します。
右手には浅間山。ほんの少し雪が残っていて、左側はいったん下がった稜線がまたクイッと上がって、三角の尖ったピークが見えます。
道には馬頭観音や石仏が点在していますが、この辺り一帯、石や岩が多く、あっ、石仏かな?と思うと庭石だったり…
旧道に遠近宮(おちこちのみや)という伊勢物語所縁の神社がありました。伊勢物語八段の業平の歌「信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ」
国道沿いに、軽井沢でパン屋と言えば「あさのや」があったので、思わず入って、フォッカッチオとデニッシュを買いました。お十時に食べよう。
もうすぐ追分。歩道橋で右側に渡り、一里塚を探しながら行きました。コブシの花と思われる、白い花が咲いている木が一里塚でした。
旧道に入り、郷土館を通りすぎ、せせらぎにかかった橋を渡る、素敵な浅間神社へ。芭蕉の句碑がありました。「吹き飛ばす石も浅間の野分かな」
道に「夢のはこ」というものが何ヵ所か設置されていました。ガラス戸の棚に本が20冊ほど入れてあり、自由に借りては返す、小さな図書館でした。
その近くに堀辰雄記念館がありました。
その斜め前の油屋旅館は、昔の脇本陣だったそうです。
現金屋という趣深い古い家、表札に「旧本陣」と出している、本陣の経営者の末裔の家、蔦屋という古い家などがありました。
泉洞寺には、堀辰雄が愛した半伽思惟像があるというので探しに行ったのですが見当たらず、入り口の石仏群のひとつの半伽思惟像の石仏があったので、これだろう、と思って写真を撮ったのですが、後で調べたらこれじゃなかった。残念。
旧道が国道に合流する辺りに、つがるやという立派な古い家がありました。
少し国道を行くと、追分の地名の語源となった、分去れ(わかされ)があります。北国街道と中山道の分岐点。(写真1)別れる股のところには、たくさんの道標や歌碑や、こどもを抱いた地蔵などがあります。
「右は越後へ行く北の道、左は木曽まで行く中山道…」
兄弟デュオ、狩人の「コスモス街道」が浮かんできます。
今日は旧道を歩きながら、「コスモス街道」を歌っていました。感傷的に歌いながら歩くのも、ひとり旅の特権!
旧道に入り、赤松林の下り道を、浅間山を見ながらぐんぐん歩きます。
御代田の一里塚は、垂れ桜(写真2)。花の時期に訪れてラッキー!
御代田駅近くの線路は、地下道で向こう側に渡ります。
渡って左側に、龍神の杜公園があり、ベンチでパンを食べて休憩。立派なきれいな公園です。
中山道に戻り、振り返ると浅間山から白い噴煙が…
小田井宿。飯盛り女(実質的一夜妻)を置く宿場が多い中、小田井は飯盛り女を置かなかったため、家族連れや女性に好まれ、「姫の宿」と呼ばれたそうです。
そう言えば、東海道に姫街道という別ルートがありましたが…あれは、新居の関の厳しい女改めを避けるためでしたが…東海道より中山道の方が女性に好まれた理由は幾つかありました。
1、渡しなどの増水で何日も足止めをくいたくない。
2、東海道には、「今切れの渡し」「さった峠」など縁起の悪い地名がある。
3、渡し場には、舟の渡しもありましたが、徒歩(かち)渡しは、人足に肩車されて渡るわけで…着物の裾をまくらねばならないし、当時の女性の下着は西洋式のブルマ型ではなく、腰巻きという布で巻いていただけなので…どう考えても、嫌ですよねえ。なるほど、私が当時の女性なら、中山道を歩くか、少年の格好をするでしょう。
小田井の本陣跡、問屋場跡の立派な門を見て、町外れにある、飴屋さんの古い建物を見て、やがて道は国道9号線に合流。
右に皎月原という広い原があるはずでしたが、今は一部だけ残されていました。
後半に続く
4時半にパンを食べ、5時に家を出て、東京から長野新幹線に乗りました。
車内では弁当を売りに来ていて、皆さんむしゃむしゃ召し上がってましたが、私はパンを食べてきたのでおなかがすかない。
軽井沢でしなの鉄道に乗り換え、中軽井沢駅に降り立ったのは、7:44。中軽井沢駅は昔は沓掛駅という名前だったそうです。中山道では沓掛宿です。
中軽井沢に着いてからお腹がすき、コンビニでおにぎりを2個買って食べました。次回、こういうことがあったら、家では食べないで新幹線で弁当を食べよう。
日曜なので混んでいるかと思いましたが、中軽井沢まで来るとひっそりしています。
空気は冷たいのですが、朝は斜めに日がさしてきて暑く感じます。
国道18号を離れて旧道を行くと、やや上りではあるけれど、静かで気持ちがいい道。
R18と合流したり離れたりを何回か繰り返します。
右手には浅間山。ほんの少し雪が残っていて、左側はいったん下がった稜線がまたクイッと上がって、三角の尖ったピークが見えます。
道には馬頭観音や石仏が点在していますが、この辺り一帯、石や岩が多く、あっ、石仏かな?と思うと庭石だったり…
旧道に遠近宮(おちこちのみや)という伊勢物語所縁の神社がありました。伊勢物語八段の業平の歌「信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ」
国道沿いに、軽井沢でパン屋と言えば「あさのや」があったので、思わず入って、フォッカッチオとデニッシュを買いました。お十時に食べよう。
もうすぐ追分。歩道橋で右側に渡り、一里塚を探しながら行きました。コブシの花と思われる、白い花が咲いている木が一里塚でした。
旧道に入り、郷土館を通りすぎ、せせらぎにかかった橋を渡る、素敵な浅間神社へ。芭蕉の句碑がありました。「吹き飛ばす石も浅間の野分かな」
道に「夢のはこ」というものが何ヵ所か設置されていました。ガラス戸の棚に本が20冊ほど入れてあり、自由に借りては返す、小さな図書館でした。
その近くに堀辰雄記念館がありました。
その斜め前の油屋旅館は、昔の脇本陣だったそうです。
現金屋という趣深い古い家、表札に「旧本陣」と出している、本陣の経営者の末裔の家、蔦屋という古い家などがありました。
泉洞寺には、堀辰雄が愛した半伽思惟像があるというので探しに行ったのですが見当たらず、入り口の石仏群のひとつの半伽思惟像の石仏があったので、これだろう、と思って写真を撮ったのですが、後で調べたらこれじゃなかった。残念。
旧道が国道に合流する辺りに、つがるやという立派な古い家がありました。
少し国道を行くと、追分の地名の語源となった、分去れ(わかされ)があります。北国街道と中山道の分岐点。(写真1)別れる股のところには、たくさんの道標や歌碑や、こどもを抱いた地蔵などがあります。
「右は越後へ行く北の道、左は木曽まで行く中山道…」
兄弟デュオ、狩人の「コスモス街道」が浮かんできます。
今日は旧道を歩きながら、「コスモス街道」を歌っていました。感傷的に歌いながら歩くのも、ひとり旅の特権!
旧道に入り、赤松林の下り道を、浅間山を見ながらぐんぐん歩きます。
御代田の一里塚は、垂れ桜(写真2)。花の時期に訪れてラッキー!
御代田駅近くの線路は、地下道で向こう側に渡ります。
渡って左側に、龍神の杜公園があり、ベンチでパンを食べて休憩。立派なきれいな公園です。
中山道に戻り、振り返ると浅間山から白い噴煙が…
小田井宿。飯盛り女(実質的一夜妻)を置く宿場が多い中、小田井は飯盛り女を置かなかったため、家族連れや女性に好まれ、「姫の宿」と呼ばれたそうです。
そう言えば、東海道に姫街道という別ルートがありましたが…あれは、新居の関の厳しい女改めを避けるためでしたが…東海道より中山道の方が女性に好まれた理由は幾つかありました。
1、渡しなどの増水で何日も足止めをくいたくない。
2、東海道には、「今切れの渡し」「さった峠」など縁起の悪い地名がある。
3、渡し場には、舟の渡しもありましたが、徒歩(かち)渡しは、人足に肩車されて渡るわけで…着物の裾をまくらねばならないし、当時の女性の下着は西洋式のブルマ型ではなく、腰巻きという布で巻いていただけなので…どう考えても、嫌ですよねえ。なるほど、私が当時の女性なら、中山道を歩くか、少年の格好をするでしょう。
小田井の本陣跡、問屋場跡の立派な門を見て、町外れにある、飴屋さんの古い建物を見て、やがて道は国道9号線に合流。
右に皎月原という広い原があるはずでしたが、今は一部だけ残されていました。
後半に続く
2009.4.19. 中山道ウォーキング9日目 後半 皎月原〜岩村田〜塩名田〜八幡〜望月
皎月原跡の一部には桜がきれいに咲いていました。そして、皎月原のほとんどが、中古車センターになっていました。
その先にショッピングセンターがありました。実は先日、万歩計をなくしてしまい、ショッピングセンター内に売ってないかと探しましたが、売っていませんでした。
暫く行くと、マックと、その奥に電器店があったので行ってみると、万歩計がありました。
昼時でしたが、私はさっきパンを食べたので、マックのSシェイクで休憩しました。
国道沿いを暫く行き、大きなタブの木の古木と、溶岩で出来た常夜灯がある住吉神社に寄りました。
タブの木は立派なコブコブがあり(写真1)、私はタブの木の写真を何枚か撮りましたが、タブの木の奥にちょうど見頃の大きな桜の木があり、他に境内にいた人たちは、みんな桜の写真を撮っていました。
南関東は10日ほど前に桜が満開で、もうすっかり葉桜になってしまいましたが、私は佐久に来たおかげで、2回目の桜のピークに出会えました。
佐久市は今日が市長と市議会議員の選挙の投票日だそうで、あちこちに大きなポスターのベニヤの壁が立っていました。
岩村田付近で小海線の線路を渡る手前に、銀に光るドームのような物が見えたので、なんだろう、と思って見に行ったら、佐久市こども未来館でした。
線路を渡り、岩村田高校や大きな病院を過ぎた先に、相生の松がありました。皇女和宮は、相生の松は縁起がいいからと、この木の下で茶会を開いたそうです。
当時の松は枯れてしまい、今ある松は2代目か3代目か分かりませんが…私は相生の松は∞無限大マークみたいに絡み合っているのかと思ったら、主なる幹の下の方の脇から、新しい幹が出ていて、二本の松の根本が一緒、というものでした。
この後、「むぎの里」という店で昼食。
旧道に入り、桃畑の中を進みます。向こうに浅間山も見え、ちょっとした桃源郷。
林檎畑もあちこちあり、林檎は既に葉が出ていました。
濁川という川を渡りましたが、川の水が黄色っぽく、なんの成分なんだろう。
下り坂が続き、やがて塩名田宿へ。
本陣跡、問屋場跡を見て、歩いていたら、白い大きな布を被ったおばあさんが、私にお辞儀して…私にはその人が、修道女に見えました…その人に、「一人?男の人はいないの?」と聞かれました。「はい、一人です」と答えると、「気をつけてね」と言われました。
旧道に入り、坂を上っていくと、白い腹かけと白い帽子(給食当番みたいな)の大日如来像がありました。(写真2)
大日如来像は二ヶ所にあったらしいのですが、私は二つ目の大日如来像しか気付きませんでした。隣には、芭蕉句碑がありました。
その先、一里塚跡。
川を渡ると八幡神社。八幡宿の名の由来となった神社です。本陣跡などを見て、やがて宿外れ。
急な上り坂は瓜生坂。旧道は山の中のくねくね道へ入っていきます。
夕方になってきたので、山の中の道は不安になってきます。
道祖神や一里塚がありました。
急な下り坂は、鴬がずっと鳴いていて、癒されました。
細い急な下り坂を下りていくと長坂の石仏群がありました。
望月宿に入り、山城屋や井出野屋旅館などの写真を撮り、脇本陣鷹野家、この宿場最古の建物である大和屋(昔の旅籠)、下駄の看板の家(軒先に大きな下駄がぶら下がっています)などの写真を撮り、17時20分頃、井出野屋旅館(写真3)に入りました。
風呂は大きくて気持ちよく、夕飯は馬刺し、鯉の煮付け、鯉のあらい、きのこおろし、山菜天ぷら、ヤマメ塩焼き、信州そば、香の物、ご飯。
部屋で一人で食べたので、「おっ、この馬刺しはとろけるねえ。鯉の煮付けは身がしまって、味は濃いめで…でも骨が多いから気をつけないと。おっ、大根おろしが緑色だ。木の芽じゃないし…馬刺しのツマの大根も緑ってことは、大根そのものが緑なんだ。珍しいねえ。鯉のあらいも酢味噌との相性がいい。鯉の玉子は固くて味が濃くてしっかりしていて…鱈の子がたらこなら、鯉の卵はこいこ?味が濃いから泥臭くない。濃い鯉子…こいこいこ、ですねえ」…と、ひとり食いしん坊万才!をしていました。
隣のお客様、19時には大いびき。熟睡すればいびきは消えるかと期待しましたが、夜中までいびきは続きました。
それでも、23時過ぎに布団に入った私は、たぶん瞬間に眠りに落ちました。
今日の行程は、ガイド本によると、25.3km。12kmちょっとのあたりで万歩計を買いまして、その後の歩数は、23,503歩、マクドナルドでSシェイクを飲んだ後から望月の宿までの平均時速は、5.06km。
皎月原跡の一部には桜がきれいに咲いていました。そして、皎月原のほとんどが、中古車センターになっていました。
その先にショッピングセンターがありました。実は先日、万歩計をなくしてしまい、ショッピングセンター内に売ってないかと探しましたが、売っていませんでした。
暫く行くと、マックと、その奥に電器店があったので行ってみると、万歩計がありました。
昼時でしたが、私はさっきパンを食べたので、マックのSシェイクで休憩しました。
国道沿いを暫く行き、大きなタブの木の古木と、溶岩で出来た常夜灯がある住吉神社に寄りました。
タブの木は立派なコブコブがあり(写真1)、私はタブの木の写真を何枚か撮りましたが、タブの木の奥にちょうど見頃の大きな桜の木があり、他に境内にいた人たちは、みんな桜の写真を撮っていました。
南関東は10日ほど前に桜が満開で、もうすっかり葉桜になってしまいましたが、私は佐久に来たおかげで、2回目の桜のピークに出会えました。
佐久市は今日が市長と市議会議員の選挙の投票日だそうで、あちこちに大きなポスターのベニヤの壁が立っていました。
岩村田付近で小海線の線路を渡る手前に、銀に光るドームのような物が見えたので、なんだろう、と思って見に行ったら、佐久市こども未来館でした。
線路を渡り、岩村田高校や大きな病院を過ぎた先に、相生の松がありました。皇女和宮は、相生の松は縁起がいいからと、この木の下で茶会を開いたそうです。
当時の松は枯れてしまい、今ある松は2代目か3代目か分かりませんが…私は相生の松は∞無限大マークみたいに絡み合っているのかと思ったら、主なる幹の下の方の脇から、新しい幹が出ていて、二本の松の根本が一緒、というものでした。
この後、「むぎの里」という店で昼食。
旧道に入り、桃畑の中を進みます。向こうに浅間山も見え、ちょっとした桃源郷。
林檎畑もあちこちあり、林檎は既に葉が出ていました。
濁川という川を渡りましたが、川の水が黄色っぽく、なんの成分なんだろう。
下り坂が続き、やがて塩名田宿へ。
本陣跡、問屋場跡を見て、歩いていたら、白い大きな布を被ったおばあさんが、私にお辞儀して…私にはその人が、修道女に見えました…その人に、「一人?男の人はいないの?」と聞かれました。「はい、一人です」と答えると、「気をつけてね」と言われました。
旧道に入り、坂を上っていくと、白い腹かけと白い帽子(給食当番みたいな)の大日如来像がありました。(写真2)
大日如来像は二ヶ所にあったらしいのですが、私は二つ目の大日如来像しか気付きませんでした。隣には、芭蕉句碑がありました。
その先、一里塚跡。
川を渡ると八幡神社。八幡宿の名の由来となった神社です。本陣跡などを見て、やがて宿外れ。
急な上り坂は瓜生坂。旧道は山の中のくねくね道へ入っていきます。
夕方になってきたので、山の中の道は不安になってきます。
道祖神や一里塚がありました。
急な下り坂は、鴬がずっと鳴いていて、癒されました。
細い急な下り坂を下りていくと長坂の石仏群がありました。
望月宿に入り、山城屋や井出野屋旅館などの写真を撮り、脇本陣鷹野家、この宿場最古の建物である大和屋(昔の旅籠)、下駄の看板の家(軒先に大きな下駄がぶら下がっています)などの写真を撮り、17時20分頃、井出野屋旅館(写真3)に入りました。
風呂は大きくて気持ちよく、夕飯は馬刺し、鯉の煮付け、鯉のあらい、きのこおろし、山菜天ぷら、ヤマメ塩焼き、信州そば、香の物、ご飯。
部屋で一人で食べたので、「おっ、この馬刺しはとろけるねえ。鯉の煮付けは身がしまって、味は濃いめで…でも骨が多いから気をつけないと。おっ、大根おろしが緑色だ。木の芽じゃないし…馬刺しのツマの大根も緑ってことは、大根そのものが緑なんだ。珍しいねえ。鯉のあらいも酢味噌との相性がいい。鯉の玉子は固くて味が濃くてしっかりしていて…鱈の子がたらこなら、鯉の卵はこいこ?味が濃いから泥臭くない。濃い鯉子…こいこいこ、ですねえ」…と、ひとり食いしん坊万才!をしていました。
隣のお客様、19時には大いびき。熟睡すればいびきは消えるかと期待しましたが、夜中までいびきは続きました。
それでも、23時過ぎに布団に入った私は、たぶん瞬間に眠りに落ちました。
今日の行程は、ガイド本によると、25.3km。12kmちょっとのあたりで万歩計を買いまして、その後の歩数は、23,503歩、マクドナルドでSシェイクを飲んだ後から望月の宿までの平均時速は、5.06km。
2009.4.20. 中山道ウォーキング10日目 望月〜芦田〜長久保〜和田
夕べの宿、井出野屋旅館は大正5年築で3階建て。旅籠の面影を残す旅館です。
今朝は6:50に朝食を食べ、宿を7:20に出発。
まず、望月宿外れの大伴神社へ。景行天皇が開いた古い神社とのこと。先を急ぐから、60段の階段は上らないつもりでいたら、境内の石仏群には面白いものもある、というので、結局60段上って石仏を見にいきました。(写真1)
車道を桜を見ながら上ります。今朝、空になったペットボトルに宿で水を入れてきてよかった。コンビニはないし、自動販売機もたまにしかない。宿で入れてきた水が美味い!
御桐谷という交差点は、「おとや」と読みます。
道を歩いていたら、お食事処の名が、「しいらんぼ」という店があり、椎の実の絵が描いてあったので…椎とさくらんぼからの連想の造語なのか、この地方では、椎の実をしいらんぼと言うのか…
間の宿茂田井は、昔から美味しい酒を作っていた町。坂道に用水路が流れ、建ち並ぶ家々の佇まいに、一瞬タイムスリップの気分。昔の町並みがここまで残っているとは!
造り酒屋の立派な門には、杉玉が下げられていました。(写真2)近くには、若山牧水の歌碑がありました。
江戸時代の一角を通りすぎ、町並みは新しい家になってきますが、それでもそこかしこに昔の面影を残していました。
急な坂を上り、左下に田畑が見えてくると、蛙の鳴き声が聞こえてきました。
宿外れで大きな車道に突き当たると、その付近、桜が満開で、花の向こうに鯉のぼりが泳いでいました。
車道を右折すると、一陣の風に花が舞い落ち、鼻に花びらがぶつかると、案外強く感じるんだな、と思いました。
芦田宿は立科町の中心地だそうで、中山道と交差する商店街に、結構いろいろな店がありそうでした。
芦田から笠取峠へ向かう途中、新しい道を敷く工事が行われていました。
しかし、工事現場に歩行者への対策がなされていなくて、一番近くにいた人に「どうやって行ったらいいですか」と聞いたら、「あそこに監督さんがいるから、許可をもらって」…なんで歩行者が許可をもらわなくちゃいけないんだろう。
で、「あそこ」が私からは視角だったため、別の人に声をかけても無視されるし…。最初の人が、「ちゃんと聞いたの?」…どの人が監督?…「みんなそうなんだから。昨日通った人も」…なんだか不愉快です。歩行者向け案内が何も出されていなくて、どうして私がヘコヘコしなきゃいけないんだろう。
やっと監督さんが事態に気づき、「どうぞお通りください。お好きなところをどうぞ」
この道が完成したら、中山道を歩く人達、間違えやすくなるんじゃないかなあ。明らかに地図にない道が新設されつつあるのです。
やっと笠取峠への旧道に入りました。
車の来ない、すばらしい松並木の道を歩きます。(写真3)
杉並木の合間に、保科五無斎歌碑、若山牧水歌碑、桜広場などがありました。
公園のような場所には、金明水が湧いていて、飲めるとのことで、ペットボトルに水を入れました。望月の水も美味しかったけど、金明水はもっと美味しい。
国道に合流して、杉並木も終わり。上りの傾斜が急になりました。
ウグイスが鳴いていました。
登坂斜線が終わる辺りに一里塚があるはずで、探したのですが分からない。
もしかしたら、さっき、目を引く垂れ桜に看板みたいなものがあったから、あれが一里塚だったのかなあ。
笠取峠で長和町に入りました。暫くして旧道に入り、気持ちのいい新緑の道を下っていくと、行く先に大きな桜の木があり、花の上辺りに向こう側の高い位置の道が走っていて、私の位置からみると、花の上をトラックが走っているように見えました。花びらハラハラ…の道。ウグイスの声が、谷にこだまし、ずっと下の方からは、せせらぎの音も聞こえてきます。
長久保宿に入り、二人のおばあさんと「こんにちは」と挨拶を交わし合いました。一福処という休憩所で休もうと思っていたら、開いてなさそうなので通過しようとしたら、さっきの二人のおばあさんが、「どうぞ中に入って休んでいってください。トイレもあるし、お茶も飲めますよ」と言ってくれたので、戸が開くのかとやってみたけれど…
「あっ、今日は月曜日か。ごめんなさい。お休みだ」「かえって悪かったねえ。ごめんなさい」と二人に代わる代わる言われ、「いえ、大丈夫です」と笑顔で答え…でも、ここのトイレを当てにしていたんです…
もしかしたら、バスの営業所にあるかも、と行ってみたら、トイレがありました。自動販売機でお茶も買えました。
後半へ続く
夕べの宿、井出野屋旅館は大正5年築で3階建て。旅籠の面影を残す旅館です。
今朝は6:50に朝食を食べ、宿を7:20に出発。
まず、望月宿外れの大伴神社へ。景行天皇が開いた古い神社とのこと。先を急ぐから、60段の階段は上らないつもりでいたら、境内の石仏群には面白いものもある、というので、結局60段上って石仏を見にいきました。(写真1)
車道を桜を見ながら上ります。今朝、空になったペットボトルに宿で水を入れてきてよかった。コンビニはないし、自動販売機もたまにしかない。宿で入れてきた水が美味い!
御桐谷という交差点は、「おとや」と読みます。
道を歩いていたら、お食事処の名が、「しいらんぼ」という店があり、椎の実の絵が描いてあったので…椎とさくらんぼからの連想の造語なのか、この地方では、椎の実をしいらんぼと言うのか…
間の宿茂田井は、昔から美味しい酒を作っていた町。坂道に用水路が流れ、建ち並ぶ家々の佇まいに、一瞬タイムスリップの気分。昔の町並みがここまで残っているとは!
造り酒屋の立派な門には、杉玉が下げられていました。(写真2)近くには、若山牧水の歌碑がありました。
江戸時代の一角を通りすぎ、町並みは新しい家になってきますが、それでもそこかしこに昔の面影を残していました。
急な坂を上り、左下に田畑が見えてくると、蛙の鳴き声が聞こえてきました。
宿外れで大きな車道に突き当たると、その付近、桜が満開で、花の向こうに鯉のぼりが泳いでいました。
車道を右折すると、一陣の風に花が舞い落ち、鼻に花びらがぶつかると、案外強く感じるんだな、と思いました。
芦田宿は立科町の中心地だそうで、中山道と交差する商店街に、結構いろいろな店がありそうでした。
芦田から笠取峠へ向かう途中、新しい道を敷く工事が行われていました。
しかし、工事現場に歩行者への対策がなされていなくて、一番近くにいた人に「どうやって行ったらいいですか」と聞いたら、「あそこに監督さんがいるから、許可をもらって」…なんで歩行者が許可をもらわなくちゃいけないんだろう。
で、「あそこ」が私からは視角だったため、別の人に声をかけても無視されるし…。最初の人が、「ちゃんと聞いたの?」…どの人が監督?…「みんなそうなんだから。昨日通った人も」…なんだか不愉快です。歩行者向け案内が何も出されていなくて、どうして私がヘコヘコしなきゃいけないんだろう。
やっと監督さんが事態に気づき、「どうぞお通りください。お好きなところをどうぞ」
この道が完成したら、中山道を歩く人達、間違えやすくなるんじゃないかなあ。明らかに地図にない道が新設されつつあるのです。
やっと笠取峠への旧道に入りました。
車の来ない、すばらしい松並木の道を歩きます。(写真3)
杉並木の合間に、保科五無斎歌碑、若山牧水歌碑、桜広場などがありました。
公園のような場所には、金明水が湧いていて、飲めるとのことで、ペットボトルに水を入れました。望月の水も美味しかったけど、金明水はもっと美味しい。
国道に合流して、杉並木も終わり。上りの傾斜が急になりました。
ウグイスが鳴いていました。
登坂斜線が終わる辺りに一里塚があるはずで、探したのですが分からない。
もしかしたら、さっき、目を引く垂れ桜に看板みたいなものがあったから、あれが一里塚だったのかなあ。
笠取峠で長和町に入りました。暫くして旧道に入り、気持ちのいい新緑の道を下っていくと、行く先に大きな桜の木があり、花の上辺りに向こう側の高い位置の道が走っていて、私の位置からみると、花の上をトラックが走っているように見えました。花びらハラハラ…の道。ウグイスの声が、谷にこだまし、ずっと下の方からは、せせらぎの音も聞こえてきます。
長久保宿に入り、二人のおばあさんと「こんにちは」と挨拶を交わし合いました。一福処という休憩所で休もうと思っていたら、開いてなさそうなので通過しようとしたら、さっきの二人のおばあさんが、「どうぞ中に入って休んでいってください。トイレもあるし、お茶も飲めますよ」と言ってくれたので、戸が開くのかとやってみたけれど…
「あっ、今日は月曜日か。ごめんなさい。お休みだ」「かえって悪かったねえ。ごめんなさい」と二人に代わる代わる言われ、「いえ、大丈夫です」と笑顔で答え…でも、ここのトイレを当てにしていたんです…
もしかしたら、バスの営業所にあるかも、と行ってみたら、トイレがありました。自動販売機でお茶も買えました。
後半へ続く
2009.4.20. 中山道ウォーキング10日目 後半 長久保〜和田
濱田屋旅館の前を左に曲がり、ところどころ残る古い家を見ながら進むと、国道に出ます。
暫く左側を歩くと、国道と並行している畦道風の道があり、そこを歩きました。
畦道風の道は、右に国道を見下ろし、左には用水路が流れ、土の道には草やたんぽぽが生え、のどかな道です。
家型の道祖神?(写真1)のところで右に入って国道に戻ると、ちょっと先に「四泊落合 650M」と書いた標識。その先から右の、旧道に入ります。
旧道には一里塚があるはずでしたが、どこかわかりませんでした。
また国道に出て、左折すると、二つの川が合流していて、岩にぶつかった水がきれいに盛り上がって、山奥の渓流みたいだ、と思ったら、この上流で渓流釣りができるそうです。(写真2)
小さな橋を二つ渡り、また大きな道に出て、川沿いの旧道へ。
藁葺き屋根のバス停がありました。(写真3)
石仏があちこちにある静かな道を歩きましたが、暑くなってきて、単調な道だし、ちょっとつらくなってきました。
キノコの種菌を育てる研究所があり、ちょっと興味があったけれど、一般公開はしていないみたいでした。
藁葺き屋根の神社があり、境内には芭蕉の句碑もありました。
和田小学校、和田中学校と隣り合って広い敷地の学校がありました。小学校は新しそうな建物で、塔があったり、夢堂みたいな何角形かの建物が両翼についていました。
中学は、桜の花の中に、昔ながらの木造校舎がありました。
12時40分に和田宿のバス停に着きました。
しかし、鉄道の駅まで出るバスがない。朝には上田行きバスがあるのですが。
国道まで出ると和田宿ステーションというところがある、と書いてあるので、そこまで出れば、別のバス便があるのかも、と思い、行ってみましたが、ない。ここは道の駅で、食堂は定休日。聞く人もいない。
再びさっきのバス停に戻り、よくよく調べたら、14:36の長久保行きバスが長久保で上田行きに接続しているとのこと。
汗で濡れた服を着替え、待ち時間に他の方法はないか調べてみました。
タクシーもいないし。
14:36のバスで長久保→上田と行けば、今夜家に帰れることは確実ですが、夜、ミュージカルの練習があるのには間に合わない。
14:36の前のバスは、11時台だったので、望月から歩いてきたのでは、かなり健脚でも無理だと思います。
どうせ、ミュージカルの稽古に間に合わないのなら、いっそ今夜は和田宿に泊まって、明日、和田峠越えをして下諏訪まで行こうか、とも思いました。
今日一旦帰宅したら、次回また和田宿まで来るのは大変なので、下諏訪まで行っておけば楽だよね。
で、バス停の目の前にある、本亭旅館に電話してみましたが、御用意が出来ない、とのこと。…これは、神様が、今日のところは帰りなさい、と言っているんだ。
私自身も疲れてるし、明日は天気が悪いみたいだし。
次回来るなら、ちゃんと本亭旅館に予約を入れた上で、1日目は余裕をもって、上田からバスを乗り継いで、その日は泊まるだけにして…
2日目に和田峠越えをして下諏訪まで行く、という計画を立てよう。
東海道は、結構行き当たりばったりでも宿はとれたけど、中山道はこれから先、ちゃんと予約をとらなきゃだめだし、昼食のこと、飲み物の調達も考えておかなきゃだめだな。
上田までのバス代、950円でした。
上田駅16:02初のあさま号で帰宅しました。
ここまでの歩数は、33,708歩。歩いた距離、24.07km。平均時速、4.82km。
今朝は朝食が早かったのに、間食いっさいなしで、昼食は新幹線に乗って軽井沢を過ぎてからなので、16時半頃でした。買ったお弁当は、「信州夢回廊」膳という名前がつけられていました。
濱田屋旅館の前を左に曲がり、ところどころ残る古い家を見ながら進むと、国道に出ます。
暫く左側を歩くと、国道と並行している畦道風の道があり、そこを歩きました。
畦道風の道は、右に国道を見下ろし、左には用水路が流れ、土の道には草やたんぽぽが生え、のどかな道です。
家型の道祖神?(写真1)のところで右に入って国道に戻ると、ちょっと先に「四泊落合 650M」と書いた標識。その先から右の、旧道に入ります。
旧道には一里塚があるはずでしたが、どこかわかりませんでした。
また国道に出て、左折すると、二つの川が合流していて、岩にぶつかった水がきれいに盛り上がって、山奥の渓流みたいだ、と思ったら、この上流で渓流釣りができるそうです。(写真2)
小さな橋を二つ渡り、また大きな道に出て、川沿いの旧道へ。
藁葺き屋根のバス停がありました。(写真3)
石仏があちこちにある静かな道を歩きましたが、暑くなってきて、単調な道だし、ちょっとつらくなってきました。
キノコの種菌を育てる研究所があり、ちょっと興味があったけれど、一般公開はしていないみたいでした。
藁葺き屋根の神社があり、境内には芭蕉の句碑もありました。
和田小学校、和田中学校と隣り合って広い敷地の学校がありました。小学校は新しそうな建物で、塔があったり、夢堂みたいな何角形かの建物が両翼についていました。
中学は、桜の花の中に、昔ながらの木造校舎がありました。
12時40分に和田宿のバス停に着きました。
しかし、鉄道の駅まで出るバスがない。朝には上田行きバスがあるのですが。
国道まで出ると和田宿ステーションというところがある、と書いてあるので、そこまで出れば、別のバス便があるのかも、と思い、行ってみましたが、ない。ここは道の駅で、食堂は定休日。聞く人もいない。
再びさっきのバス停に戻り、よくよく調べたら、14:36の長久保行きバスが長久保で上田行きに接続しているとのこと。
汗で濡れた服を着替え、待ち時間に他の方法はないか調べてみました。
タクシーもいないし。
14:36のバスで長久保→上田と行けば、今夜家に帰れることは確実ですが、夜、ミュージカルの練習があるのには間に合わない。
14:36の前のバスは、11時台だったので、望月から歩いてきたのでは、かなり健脚でも無理だと思います。
どうせ、ミュージカルの稽古に間に合わないのなら、いっそ今夜は和田宿に泊まって、明日、和田峠越えをして下諏訪まで行こうか、とも思いました。
今日一旦帰宅したら、次回また和田宿まで来るのは大変なので、下諏訪まで行っておけば楽だよね。
で、バス停の目の前にある、本亭旅館に電話してみましたが、御用意が出来ない、とのこと。…これは、神様が、今日のところは帰りなさい、と言っているんだ。
私自身も疲れてるし、明日は天気が悪いみたいだし。
次回来るなら、ちゃんと本亭旅館に予約を入れた上で、1日目は余裕をもって、上田からバスを乗り継いで、その日は泊まるだけにして…
2日目に和田峠越えをして下諏訪まで行く、という計画を立てよう。
東海道は、結構行き当たりばったりでも宿はとれたけど、中山道はこれから先、ちゃんと予約をとらなきゃだめだし、昼食のこと、飲み物の調達も考えておかなきゃだめだな。
上田までのバス代、950円でした。
上田駅16:02初のあさま号で帰宅しました。
ここまでの歩数は、33,708歩。歩いた距離、24.07km。平均時速、4.82km。
今朝は朝食が早かったのに、間食いっさいなしで、昼食は新幹線に乗って軽井沢を過ぎてからなので、16時半頃でした。買ったお弁当は、「信州夢回廊」膳という名前がつけられていました。
2009.4.30. 中山道ウォーキング 11日目 長久保宿散策と和田宿散策
朝、5時50分に家を出て、東京から長野新幹線で上田へ。
東京駅で買った地鶏弁当を車内で食べました。
上田に降り立ち、長久保行き、9:05発JRバスに乗りました。
長久保に着いて、乗り換えのバス待ちの間、長久保宿を見学しました。
長久保宿一福処濱屋は、明治時代初期に旅籠として建てられましたが、中山道の交通量が減ったため、開業には至らなかったそうです。
山間部の旅籠建築に多く見られる、一階部より二階部を突出させた「出梁造り」が特徴的な総二階建て。
住居として使われてきましたが、長久保宿を訪れる旅人の休み処として、また、宿場に関する歴史、民俗資料の展示公開の場として使われています。
庭側の縁側に、地元の年輩の方達5〜6人が集まってお茶を飲んでいて、「お嬢さんもどうぞ」と誘われました。ずいぶん若く見られたものです。
今日はみんなで庭整備に来て、お茶タイムをしているところでした。
瓜の漬け物、蕪の漬け物、柿を甘く漬けたものをお裾分けしていただきました。特に柿が美味しかった。
「取材ですか」と聞かれたので、「旅です」と答えたら、「歩いていて感じたことはありますか」と聞かれました。
「東海道も歩いてから中山道に来たのですが、東海道よりも中山道の方が、自然も古い家なども残っていて面白いです」と答えると、「そうでしょう、そうでしょう」と満足げ。
石合家という本陣には、四代目のところに真田幸村の娘が嫁いできたそうで、お墓が近くの寺にあるそうです。
その娘さんは、おすへさんといって、この資料館の案内役のマスコットになっていました。
「そうだ、あそこの家を見せてもらうといい」
「あそこの方が、ここより古いものが沢山ある」
皆さんに勧められ、案内までしていただいて、古い家を見学させてもらいました。
その古い家にはお子さんがいなくて、年老いた主人が趣味で集めた古い道具類を展示しています。
旅人に見てもらうために展示しているのですが、地元の人たちで管理しているそうで、旅人が勝手に見ることはできないようでした。
機織り機、糸車、石臼、櫛や簪、etc.
案内してくれたおばさまが、嫁入りしてきた時に履いてきた、畳のような表面の草履も展示されていました。
「あっちよりも、古いものが沢山あるでしょ」と言われましたが、実は一福処濱家の二階の展示は、まだ見ていなかったのです。でも、どうやらこちらに比べてたいしたことはないらしいので、濱家の二階にはもう行かないことにしました。
おばさまにお礼を言って別れてから、濱家でもらってきたパンフを見ながら、問屋の小林家、旅籠古久屋、酒造業の釜鳴屋(写真1)、横町の辰埜屋の写真を撮って回りました。
一般に開放されているのは、一福処濱家だけです。
11:19のバスで上和田まで移動。
前回来た時は閉まっていた、「和田宿農家レストランかあちゃんや」が営業していたので、山菜そばを食べました。煮物と自家製そば羊羮が付いていました。
バスから見えた、学生服の看板が出ていた店…Yシャツや上履きを売る店…にボールペンを買いに行きました。忘れてきてしまい、不便だったので。ボールペンは置いてはいたけれど、かなり昔に仕入れたきり、売れなくてほったらかしにされているので、書けないと思う、と言われましたが、粘り強く試し書きをさせてもらい、7本目で書けるものと巡り会い、買ってきました。100円でした。
前回来た時、やはり休館だった、歴史の道資料館かわちや、に行き、入館料300円を支払ったら、共通券で見られるものが何軒かありました。
かわちやは旅籠ですが、文久元年(1861)年の大火で和田宿117軒中107軒が焼失した中にかわちやも含まれていて、その後すぐに再建されたのですが、旅籠なのに上段の間がある珍しい造り。本来は、本陣、脇本陣以外の庶民の建物に、上段の間はいけなかったはずなのになぜ?
ちょうど、皇女和宮がお通りになるとのことで、大火からの再建が急を要され、本陣脇本陣だけでは間に合わないとの判断から、かわちやにも上段の間を作ったと考えられるそうです。
急な階段を上った二階(写真2)は、真ん中辺りの天井と、街道沿い側の天井の高さが違っています。街道側が天井が低いのですが、これは、大名行列が通った時、二階から矢を射れないように(二階の窓際で、腕を大きく振り被れないように)幕府からこのようにするよう決められていたのだそうです。
階段部分は二階の床は大きく切り取られ、手摺も柵もない。酔った旅人が何人か、絶対落ちたよなあ…
後半に続く
朝、5時50分に家を出て、東京から長野新幹線で上田へ。
東京駅で買った地鶏弁当を車内で食べました。
上田に降り立ち、長久保行き、9:05発JRバスに乗りました。
長久保に着いて、乗り換えのバス待ちの間、長久保宿を見学しました。
長久保宿一福処濱屋は、明治時代初期に旅籠として建てられましたが、中山道の交通量が減ったため、開業には至らなかったそうです。
山間部の旅籠建築に多く見られる、一階部より二階部を突出させた「出梁造り」が特徴的な総二階建て。
住居として使われてきましたが、長久保宿を訪れる旅人の休み処として、また、宿場に関する歴史、民俗資料の展示公開の場として使われています。
庭側の縁側に、地元の年輩の方達5〜6人が集まってお茶を飲んでいて、「お嬢さんもどうぞ」と誘われました。ずいぶん若く見られたものです。
今日はみんなで庭整備に来て、お茶タイムをしているところでした。
瓜の漬け物、蕪の漬け物、柿を甘く漬けたものをお裾分けしていただきました。特に柿が美味しかった。
「取材ですか」と聞かれたので、「旅です」と答えたら、「歩いていて感じたことはありますか」と聞かれました。
「東海道も歩いてから中山道に来たのですが、東海道よりも中山道の方が、自然も古い家なども残っていて面白いです」と答えると、「そうでしょう、そうでしょう」と満足げ。
石合家という本陣には、四代目のところに真田幸村の娘が嫁いできたそうで、お墓が近くの寺にあるそうです。
その娘さんは、おすへさんといって、この資料館の案内役のマスコットになっていました。
「そうだ、あそこの家を見せてもらうといい」
「あそこの方が、ここより古いものが沢山ある」
皆さんに勧められ、案内までしていただいて、古い家を見学させてもらいました。
その古い家にはお子さんがいなくて、年老いた主人が趣味で集めた古い道具類を展示しています。
旅人に見てもらうために展示しているのですが、地元の人たちで管理しているそうで、旅人が勝手に見ることはできないようでした。
機織り機、糸車、石臼、櫛や簪、etc.
案内してくれたおばさまが、嫁入りしてきた時に履いてきた、畳のような表面の草履も展示されていました。
「あっちよりも、古いものが沢山あるでしょ」と言われましたが、実は一福処濱家の二階の展示は、まだ見ていなかったのです。でも、どうやらこちらに比べてたいしたことはないらしいので、濱家の二階にはもう行かないことにしました。
おばさまにお礼を言って別れてから、濱家でもらってきたパンフを見ながら、問屋の小林家、旅籠古久屋、酒造業の釜鳴屋(写真1)、横町の辰埜屋の写真を撮って回りました。
一般に開放されているのは、一福処濱家だけです。
11:19のバスで上和田まで移動。
前回来た時は閉まっていた、「和田宿農家レストランかあちゃんや」が営業していたので、山菜そばを食べました。煮物と自家製そば羊羮が付いていました。
バスから見えた、学生服の看板が出ていた店…Yシャツや上履きを売る店…にボールペンを買いに行きました。忘れてきてしまい、不便だったので。ボールペンは置いてはいたけれど、かなり昔に仕入れたきり、売れなくてほったらかしにされているので、書けないと思う、と言われましたが、粘り強く試し書きをさせてもらい、7本目で書けるものと巡り会い、買ってきました。100円でした。
前回来た時、やはり休館だった、歴史の道資料館かわちや、に行き、入館料300円を支払ったら、共通券で見られるものが何軒かありました。
かわちやは旅籠ですが、文久元年(1861)年の大火で和田宿117軒中107軒が焼失した中にかわちやも含まれていて、その後すぐに再建されたのですが、旅籠なのに上段の間がある珍しい造り。本来は、本陣、脇本陣以外の庶民の建物に、上段の間はいけなかったはずなのになぜ?
ちょうど、皇女和宮がお通りになるとのことで、大火からの再建が急を要され、本陣脇本陣だけでは間に合わないとの判断から、かわちやにも上段の間を作ったと考えられるそうです。
急な階段を上った二階(写真2)は、真ん中辺りの天井と、街道沿い側の天井の高さが違っています。街道側が天井が低いのですが、これは、大名行列が通った時、二階から矢を射れないように(二階の窓際で、腕を大きく振り被れないように)幕府からこのようにするよう決められていたのだそうです。
階段部分は二階の床は大きく切り取られ、手摺も柵もない。酔った旅人が何人か、絶対落ちたよなあ…
後半に続く
2009.4.30. 中山道ウォーキング 11日目 長久保宿散策と和田宿散策 後半
共通券で見られる、黒曜石石器資料館と、旅籠大黒屋と、本陣を見学。
本陣に上段の間がないなあ、変だなあ、と思っていたら、本陣建物は、大名などの宿泊に当てられる「座敷棟」と、本陣の所有者が生活する「居室棟」に分かれており、この建物は「居室棟」に当たるのだそうです。
上段の間がないから、そうかあ、とは思うものの、居室棟と考えると、すごく広い!(写真1)
でも、湯殿は、安中の奉行役宅に似ていて、冬は寒かったろうなあ、と思いました。
本陣の前の、もうひとつ共通券で見学できる羽田野は、さっき山菜そばを食べた農家レストランかあちゃんやではありませんか。
もう一回入るのは、なんだか入りにくい。でも、表から裏への9間半の通り抜け土間を見たい。
よし、通り抜け土間だけ見よう、と、突撃。
ちょうどご夫婦連れがお蕎麦を食べていました。
とにかく9間半の通り抜け土間の写真だけ撮って退散。
さて、長久保に戻るバスまで約2時間あるので、明日の朝のバスで出来るだけ先まで行けるように、大出バス停まで歩いておくことにしました。
酒屋のよろづやは、前回来た時も写真をとりましたが、雰囲気あるお店です。出梁造り、瓦屋根のどっしりした軒先に吊るされている麦わら帽子が似合っている。(写真2)
公民館にしめ縄や、神社みたいな杉の枝が飾られているのは何故か、と思ったら、お神輿を保管しているため、神社風に祀られているみたいです。
その先に、立派な松が2本あり家があり、よく見ると、2本の松は根本がくっついている。つまり、相生の松なんだ。
やがて和田鍛治足交差点。車道を渡ると、一里塚や分岐の道標。
その先、左に材木屋。建物に印象的なキツツキの絵が描いてありました。
大出バス停は藁葺き屋根。(写真3)
ここで引き返しました。
この辺り、側溝にマンマンと水が流れ、たっぷんどっぷん音高らかに流れていました。
上和田のバス停に戻り、時間までバス停の小屋で待ち、14:36の巡回バスで長久保に戻り、今夜の宿、濱田屋に入りました。
私の部屋は3階。後から男性がたくさん来るというので、先に風呂に入りました。
夕食は1階に行きました。複数連れのお客様は隣の部屋で、私はやはり一人旅のおじさんと同室で食べました。
コシアブラやタラの芽などの天ぷら、筍ご飯が美味しかった。
もう一人の方も、明日、バスで和田へ行って和田峠越えをするそうです。
部屋に戻り、テレビを見ながら日記をつけ、22時に寝ました。
今日のブラブラ散歩の歩数は、13,915歩、距離は、9.79km。平均時速4.37km。
共通券で見られる、黒曜石石器資料館と、旅籠大黒屋と、本陣を見学。
本陣に上段の間がないなあ、変だなあ、と思っていたら、本陣建物は、大名などの宿泊に当てられる「座敷棟」と、本陣の所有者が生活する「居室棟」に分かれており、この建物は「居室棟」に当たるのだそうです。
上段の間がないから、そうかあ、とは思うものの、居室棟と考えると、すごく広い!(写真1)
でも、湯殿は、安中の奉行役宅に似ていて、冬は寒かったろうなあ、と思いました。
本陣の前の、もうひとつ共通券で見学できる羽田野は、さっき山菜そばを食べた農家レストランかあちゃんやではありませんか。
もう一回入るのは、なんだか入りにくい。でも、表から裏への9間半の通り抜け土間を見たい。
よし、通り抜け土間だけ見よう、と、突撃。
ちょうどご夫婦連れがお蕎麦を食べていました。
とにかく9間半の通り抜け土間の写真だけ撮って退散。
さて、長久保に戻るバスまで約2時間あるので、明日の朝のバスで出来るだけ先まで行けるように、大出バス停まで歩いておくことにしました。
酒屋のよろづやは、前回来た時も写真をとりましたが、雰囲気あるお店です。出梁造り、瓦屋根のどっしりした軒先に吊るされている麦わら帽子が似合っている。(写真2)
公民館にしめ縄や、神社みたいな杉の枝が飾られているのは何故か、と思ったら、お神輿を保管しているため、神社風に祀られているみたいです。
その先に、立派な松が2本あり家があり、よく見ると、2本の松は根本がくっついている。つまり、相生の松なんだ。
やがて和田鍛治足交差点。車道を渡ると、一里塚や分岐の道標。
その先、左に材木屋。建物に印象的なキツツキの絵が描いてありました。
大出バス停は藁葺き屋根。(写真3)
ここで引き返しました。
この辺り、側溝にマンマンと水が流れ、たっぷんどっぷん音高らかに流れていました。
上和田のバス停に戻り、時間までバス停の小屋で待ち、14:36の巡回バスで長久保に戻り、今夜の宿、濱田屋に入りました。
私の部屋は3階。後から男性がたくさん来るというので、先に風呂に入りました。
夕食は1階に行きました。複数連れのお客様は隣の部屋で、私はやはり一人旅のおじさんと同室で食べました。
コシアブラやタラの芽などの天ぷら、筍ご飯が美味しかった。
もう一人の方も、明日、バスで和田へ行って和田峠越えをするそうです。
部屋に戻り、テレビを見ながら日記をつけ、22時に寝ました。
今日のブラブラ散歩の歩数は、13,915歩、距離は、9.79km。平均時速4.37km。
西から歩いて、現在「中津川宿」まで到達しました。
紀行記、拝見して「長久保宿」や「和田宿」等、旧街道の雰囲気が残っていて早く行きたいと思った次第です。
その時は、紀行記を参考に歩きたいと思っています。
No40.で「熊野神社」の話題がありました。
小生「熊野古道」を歩いた時、お世話になったサイト「みくまのねっと」(http://www.mikumano.net/)で、
「全国熊野神社参詣記」のコーナーがあり、全国に3000社あると云われている「熊野神社」情報を参拝者が投稿しています。
西から歩いていて、今まで2社の存在に出会いました。
これからの行程についても、参拝して行きたいと思いますので、情報提供よろしくお願いします。
紀行記、拝見して「長久保宿」や「和田宿」等、旧街道の雰囲気が残っていて早く行きたいと思った次第です。
その時は、紀行記を参考に歩きたいと思っています。
No40.で「熊野神社」の話題がありました。
小生「熊野古道」を歩いた時、お世話になったサイト「みくまのねっと」(http://www.mikumano.net/)で、
「全国熊野神社参詣記」のコーナーがあり、全国に3000社あると云われている「熊野神社」情報を参拝者が投稿しています。
西から歩いていて、今まで2社の存在に出会いました。
これからの行程についても、参拝して行きたいと思いますので、情報提供よろしくお願いします。
> もと中年ケニヤさん
私が先週佐久平を歩いた時、林檎の花が咲いていなかったので、もう終わってしまったのかと思ったら、これからだったのですね。
私はこれからアップしますが、1日に和田峠を越えて下諏訪まで、2日は夜用事があったため、塩尻までしか行けませんでした。
和田峠を越えてすぐのザレ場は、地質の関係かと思われます。あれでもかなり整備されたのではないかと思うのですが。
西餅屋跡を出て国道に出た後、私の持っているガイド本では、旧道は荒れていて5センチぐらいしか足場のないところもあるから国道を歩くことを推奨していましたが、その後整備されたらしく、案内板に、西餅屋跡から先、直進せよ、との指示があり、旧道を行くと、一里塚の先、道が補修されていて、普通にあるけました。
ただし、皆さんのブログによると、雨の日はやはり危険だそうで、国道歩きを推奨していました。
以前も書きましたが、碓氷峠では、過去2回の方が道が荒れていて、今回が一番整備されて歩きやすかったです。
昨日は塩尻峠付近で、市の職員さんなのか、ボランティアさんなのか、道を整備している方を見掛けました。
道は、どんどん変化していきます。
雨が降れば道がえぐれ、夏には草ぼうぼうになったり。
道は日々変化しているので、道の変化を調べるのもおもしろいかも。
私は結構、道の写真を録るのもすきてます。
私が先週佐久平を歩いた時、林檎の花が咲いていなかったので、もう終わってしまったのかと思ったら、これからだったのですね。
私はこれからアップしますが、1日に和田峠を越えて下諏訪まで、2日は夜用事があったため、塩尻までしか行けませんでした。
和田峠を越えてすぐのザレ場は、地質の関係かと思われます。あれでもかなり整備されたのではないかと思うのですが。
西餅屋跡を出て国道に出た後、私の持っているガイド本では、旧道は荒れていて5センチぐらいしか足場のないところもあるから国道を歩くことを推奨していましたが、その後整備されたらしく、案内板に、西餅屋跡から先、直進せよ、との指示があり、旧道を行くと、一里塚の先、道が補修されていて、普通にあるけました。
ただし、皆さんのブログによると、雨の日はやはり危険だそうで、国道歩きを推奨していました。
以前も書きましたが、碓氷峠では、過去2回の方が道が荒れていて、今回が一番整備されて歩きやすかったです。
昨日は塩尻峠付近で、市の職員さんなのか、ボランティアさんなのか、道を整備している方を見掛けました。
道は、どんどん変化していきます。
雨が降れば道がえぐれ、夏には草ぼうぼうになったり。
道は日々変化しているので、道の変化を調べるのもおもしろいかも。
私は結構、道の写真を録るのもすきてます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
東海道より中山道 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
東海道より中山道のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6473人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19244人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208299人