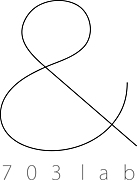卒業論文の提出が迫ってきましたね。メーリングリストにも書いた「論文の書き方(注意事項)」をこちらにも書いてみます。
■卒業論文には形式がある。形式を守ること。形式のチェック項目は以下の通り。
( 1) 製本状態
( 2) 表紙および背表紙における表題・氏名の明記
( 3) 適切な目次の記述
( 4) ページ数のナンバリング
( 5) 研究の目的,方法の記述
( 6) 既往研究への言及,研究の位置づけに関する記述
( 7) 結論,考察
( 8) 図版のナンバリング
( 9) 文章および図版の正しい引用(著者,書名,出版社,出版年,引用ページ)
(10) 参考文献の列挙
(11) 謝辞
などなど。
■(2)の「背表紙における表題・氏名の明記」は忘れがちである。必ず背表紙に表題・氏名を貼り付けること。
■(8)図版のナンバリングにも気をつけること。図版は,図と表と写真に分けて,図○○,表○○,写真○○,というナンバリングを行うと同時に, すべての図版にタイトルを付ける。ナンバリングは,通し番号でもいいし, 章ごとに,「○−○」ということでもかまわないが,僕は,章ごとのナンバリングを勧める。2章で10個の図があれば,「図2−1〜図2−10」というナンバリングとなる。
図と表と写真は,明確に分けなければならない。撮影した写真以外のCGなどはすべて図とする。
本文には,「〜を図○−○に示した」とか「図○−○に示したように〜」という風に,必ず,対応する図版の説明を記述がなければならない。研究の図版は雑誌のイラストではないから,対応する説明が必須である。
■(9)に関して,文章,図版,ホームページ等を引用した場合は,必ず(絶対!),引用元を書くこと。引用元は,「著者,書名,出版社,出版年,引用ページ」の順番に書く。引用ページを忘れがちなので,注意すること。ホームページの場合は,「作者,ホームページ名,URL」を書く。ホームページの作者,ホームページ名は,正式な名称がわからない場合も,わかる範囲で書くこと。URLは該当ページだけではなく,トップページを書くことが重要である。該当ページよりもトップページの方が,将来にわたって存続し続ける確率は高いからである。
研究論文に関しては,他の論文, 市販の文献,写真,ホームページなどの引用についての制限はないと考えればよい(著作権を細かく気にする必要はない)。商業的な出版物に関しては,引用の際に許諾(著作権者の許可)が必要になるが,論文では許諾は不要と考えてよい。そのかわり,引用元の正確な明記は絶対条件である。引用元の明記を忘れると,盗作として処分されると心得よ。
■既往の研究については,第1章=序論の中で言及すること。建築学会大会の梗概集などで関連する研究をピックアップし,その論文がどういう研究なのかについてコメントすること。関連する本についてもコメントすること。
■実際に参考にした文献,ホームページなどを,(10)参考文献としてリスト化すること。既往の研究ではコメントが必要だが,参考文献リストではコメントは不要。
■(11)の「謝辞」は,非常に重要である。「謝辞」は感謝するためのものというよりは,映画のエンドタイトルのような関係者リストだと考えるべきだ。謝辞には,純粋に感謝とという意味もないわけではないが,「共犯者」(関係者)を列挙するという意味もある。もし,論文の内容に嘘があれば,それは本人だけではなく,「共犯者」の責でもあるということだ。
謝辞には,まずは,指導教員の名前を書いてくれなければならない。指導教員は,自分から感謝を強要したいとはまったく思っていないだろうが,謝辞という形式を使って,指導教員が関係者であることを明記する必要がある。次に,アドバイスをしてくれた先生,資料を提供してくれた個人,組織,会社がある場合は,その名前も挙げなければならない。また,手伝ってくれた仲間,大学院生,友人がいる場合は,彼ら(彼女ら)の名前も挙げる。
■「法政大学懸賞論文」募集要項の「論文の書き方についての技術的注意」から関連する部分を抜粋する。
1.論文の冒頭部分で問題設定を明確に行うこと。(1)論文である以上,通常のスタイルとしては,その冒頭部分(序,はじめに, 第1章,序論,プロローグ等)において,例えば疑問文の形で問題設定があるはずである。同時に,なぜこういう問題を設定するのかについて,その理由あるいは自分の動機を書くことが望ましい。(2)論文全体がその問いに支えられ,全編を通して,その問いに答えを与えて行くという形で論述が展開されるべきである。問題設定が不明確なままに,いきなり書き始めても良い論文にはならない。
2.論文の末尾部分(結論,結び,終わりに,終章,まとめ,エピローグ等)において,冒頭の「問題」に対応する「まとめ」を書くべきである。「序」と「結論」とは, 呼吸がピッタリ合っていなければならない。
3.調査に基づく論文は,必ず調査の概要を明記すること。(1)個人として行った調査か,ゼミ等で行った調査に参加したのか。(2)調査の年月日,場所,対象者数,回収率,方法(面接法,郵送法等)。(3)調査票を必ず添えること。
4.目次,注および参考文献のリストをていねいにつけること。(1)論文には目次をつけ,頁付けをすること。(2)注には番号をふり,章末あるいは全体の末尾にまとめて記入するか,各ページ毎に脚注として記入すること。(3)参考文献は少数の場合,それぞれの注の中で記入すればよいが,多数に上る場合には,注とは別に,全体の末尾に参考文献リストを添えるとよい。いずれの方法にせよ著者名,編者者名,翻訳者名,書店あるいは論文名,掲載誌名,発行年,出版社名等を,明記すること。
以下,省略
補足(安藤):3の(3)の調査票には,データシート/野帳/スケッチブック/アンケート用紙が含まれると考えていい。
■建築学会のホームページにも,論文の執筆要領がある。参考にするとよい(これはちょいと高度であるが…)。
http://
■卒業論文には形式がある。形式を守ること。形式のチェック項目は以下の通り。
( 1) 製本状態
( 2) 表紙および背表紙における表題・氏名の明記
( 3) 適切な目次の記述
( 4) ページ数のナンバリング
( 5) 研究の目的,方法の記述
( 6) 既往研究への言及,研究の位置づけに関する記述
( 7) 結論,考察
( 8) 図版のナンバリング
( 9) 文章および図版の正しい引用(著者,書名,出版社,出版年,引用ページ)
(10) 参考文献の列挙
(11) 謝辞
などなど。
■(2)の「背表紙における表題・氏名の明記」は忘れがちである。必ず背表紙に表題・氏名を貼り付けること。
■(8)図版のナンバリングにも気をつけること。図版は,図と表と写真に分けて,図○○,表○○,写真○○,というナンバリングを行うと同時に, すべての図版にタイトルを付ける。ナンバリングは,通し番号でもいいし, 章ごとに,「○−○」ということでもかまわないが,僕は,章ごとのナンバリングを勧める。2章で10個の図があれば,「図2−1〜図2−10」というナンバリングとなる。
図と表と写真は,明確に分けなければならない。撮影した写真以外のCGなどはすべて図とする。
本文には,「〜を図○−○に示した」とか「図○−○に示したように〜」という風に,必ず,対応する図版の説明を記述がなければならない。研究の図版は雑誌のイラストではないから,対応する説明が必須である。
■(9)に関して,文章,図版,ホームページ等を引用した場合は,必ず(絶対!),引用元を書くこと。引用元は,「著者,書名,出版社,出版年,引用ページ」の順番に書く。引用ページを忘れがちなので,注意すること。ホームページの場合は,「作者,ホームページ名,URL」を書く。ホームページの作者,ホームページ名は,正式な名称がわからない場合も,わかる範囲で書くこと。URLは該当ページだけではなく,トップページを書くことが重要である。該当ページよりもトップページの方が,将来にわたって存続し続ける確率は高いからである。
研究論文に関しては,他の論文, 市販の文献,写真,ホームページなどの引用についての制限はないと考えればよい(著作権を細かく気にする必要はない)。商業的な出版物に関しては,引用の際に許諾(著作権者の許可)が必要になるが,論文では許諾は不要と考えてよい。そのかわり,引用元の正確な明記は絶対条件である。引用元の明記を忘れると,盗作として処分されると心得よ。
■既往の研究については,第1章=序論の中で言及すること。建築学会大会の梗概集などで関連する研究をピックアップし,その論文がどういう研究なのかについてコメントすること。関連する本についてもコメントすること。
■実際に参考にした文献,ホームページなどを,(10)参考文献としてリスト化すること。既往の研究ではコメントが必要だが,参考文献リストではコメントは不要。
■(11)の「謝辞」は,非常に重要である。「謝辞」は感謝するためのものというよりは,映画のエンドタイトルのような関係者リストだと考えるべきだ。謝辞には,純粋に感謝とという意味もないわけではないが,「共犯者」(関係者)を列挙するという意味もある。もし,論文の内容に嘘があれば,それは本人だけではなく,「共犯者」の責でもあるということだ。
謝辞には,まずは,指導教員の名前を書いてくれなければならない。指導教員は,自分から感謝を強要したいとはまったく思っていないだろうが,謝辞という形式を使って,指導教員が関係者であることを明記する必要がある。次に,アドバイスをしてくれた先生,資料を提供してくれた個人,組織,会社がある場合は,その名前も挙げなければならない。また,手伝ってくれた仲間,大学院生,友人がいる場合は,彼ら(彼女ら)の名前も挙げる。
■「法政大学懸賞論文」募集要項の「論文の書き方についての技術的注意」から関連する部分を抜粋する。
1.論文の冒頭部分で問題設定を明確に行うこと。(1)論文である以上,通常のスタイルとしては,その冒頭部分(序,はじめに, 第1章,序論,プロローグ等)において,例えば疑問文の形で問題設定があるはずである。同時に,なぜこういう問題を設定するのかについて,その理由あるいは自分の動機を書くことが望ましい。(2)論文全体がその問いに支えられ,全編を通して,その問いに答えを与えて行くという形で論述が展開されるべきである。問題設定が不明確なままに,いきなり書き始めても良い論文にはならない。
2.論文の末尾部分(結論,結び,終わりに,終章,まとめ,エピローグ等)において,冒頭の「問題」に対応する「まとめ」を書くべきである。「序」と「結論」とは, 呼吸がピッタリ合っていなければならない。
3.調査に基づく論文は,必ず調査の概要を明記すること。(1)個人として行った調査か,ゼミ等で行った調査に参加したのか。(2)調査の年月日,場所,対象者数,回収率,方法(面接法,郵送法等)。(3)調査票を必ず添えること。
4.目次,注および参考文献のリストをていねいにつけること。(1)論文には目次をつけ,頁付けをすること。(2)注には番号をふり,章末あるいは全体の末尾にまとめて記入するか,各ページ毎に脚注として記入すること。(3)参考文献は少数の場合,それぞれの注の中で記入すればよいが,多数に上る場合には,注とは別に,全体の末尾に参考文献リストを添えるとよい。いずれの方法にせよ著者名,編者者名,翻訳者名,書店あるいは論文名,掲載誌名,発行年,出版社名等を,明記すること。
以下,省略
補足(安藤):3の(3)の調査票には,データシート/野帳/スケッチブック/アンケート用紙が含まれると考えていい。
■建築学会のホームページにも,論文の執筆要領がある。参考にするとよい(これはちょいと高度であるが…)。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
安藤直見研究室 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
安藤直見研究室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 2位
- 酒好き
- 170690人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人