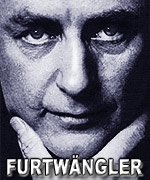カール・シューリヒト(Carl Schuricht。1880〜1967年。独)
通好みの辛口で端正な表現、遅めでゆったりと思いきや疾走感あふれるテンポに早変わり、重厚なドイツ音楽の伝統を頑固に守った巨匠です。
戦前からヨーロッパのオケの客演指揮が多く、戦後でもウィーンフィルを中心に、パリオペラ座、パリ音楽院、バイエルン放送響などさまざまなオケで名演を残しています。
レパートリーはドイツ音楽中心で、交響曲では、ハイドン104番・シューベルト未完成(フランス国立放送。エラート)、モーツァルト35番「ハフナー」(VPO。デッカ)、ベートーヴェン全集(パリ音楽院管。EMI)、シューマン2・3番(パリ音楽院管。デッカ)、ブラームス4番(バイエルン放送。デンオン)、ブルックナー3・5・8・9番(VPO。EMI・DG)などが名演で知られています。
コミュはhttp://
あなたのお好きなシューリヒトの名演・名盤をお教え下さい。
通好みの辛口で端正な表現、遅めでゆったりと思いきや疾走感あふれるテンポに早変わり、重厚なドイツ音楽の伝統を頑固に守った巨匠です。
戦前からヨーロッパのオケの客演指揮が多く、戦後でもウィーンフィルを中心に、パリオペラ座、パリ音楽院、バイエルン放送響などさまざまなオケで名演を残しています。
レパートリーはドイツ音楽中心で、交響曲では、ハイドン104番・シューベルト未完成(フランス国立放送。エラート)、モーツァルト35番「ハフナー」(VPO。デッカ)、ベートーヴェン全集(パリ音楽院管。EMI)、シューマン2・3番(パリ音楽院管。デッカ)、ブラームス4番(バイエルン放送。デンオン)、ブルックナー3・5・8・9番(VPO。EMI・DG)などが名演で知られています。
コミュはhttp://
あなたのお好きなシューリヒトの名演・名盤をお教え下さい。
|
|
|
|
コメント(19)
お得意だったブルックナーの交響曲演奏をもう少し詳しく(Lはライヴ盤)。
(1)3番(1965年。ウィーンPO。EMI)
(2)4番(1955年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(3)5番(1962年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(4)5番(1963年。ウィーンPO。L。DG)→他レーヴェルで復刻。
(5)7番(1938年。ベルリンPO。フィリップス)
(6)7番(1953年。北ドイツ放送O。L。ターラ)
(7)7番(1953年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(8)7番(1962年。ベルリンPO。L。伊輸入)
(9)7番(1964年。ハーグPO。デンオン)
(10)8番(1954年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(11)8番(1961年。北ドイツ放送SO。ライブ)
(12)8番(1963年。ウィーンPO。L。Altus)
(13)8番(1963年。ウィーンPO。EMI)
(14)9番(1951年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(15)9番(1955年。ウィーンPO。L。L。Altus)
(16)9番(1961年。ウィーンPO。EMI)
(17)9番(1963年。バイエルン放送O。L。オルフェオ)
以上の中で正規盤が(1)(9)(13)(16)で、(16)の9番が不滅の名演として有名です。またライブで素晴らしい出来なのは(4)と(11)でどちらもおすすめです。
(1)3番(1965年。ウィーンPO。EMI)
(2)4番(1955年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(3)5番(1962年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(4)5番(1963年。ウィーンPO。L。DG)→他レーヴェルで復刻。
(5)7番(1938年。ベルリンPO。フィリップス)
(6)7番(1953年。北ドイツ放送O。L。ターラ)
(7)7番(1953年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(8)7番(1962年。ベルリンPO。L。伊輸入)
(9)7番(1964年。ハーグPO。デンオン)
(10)8番(1954年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(11)8番(1961年。北ドイツ放送SO。ライブ)
(12)8番(1963年。ウィーンPO。L。Altus)
(13)8番(1963年。ウィーンPO。EMI)
(14)9番(1951年。シュトゥットガルト放送O。L。ハンスラー盤)
(15)9番(1955年。ウィーンPO。L。L。Altus)
(16)9番(1961年。ウィーンPO。EMI)
(17)9番(1963年。バイエルン放送O。L。オルフェオ)
以上の中で正規盤が(1)(9)(13)(16)で、(16)の9番が不滅の名演として有名です。またライブで素晴らしい出来なのは(4)と(11)でどちらもおすすめです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
巨匠指揮者讃 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
巨匠指揮者讃のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75486人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6445人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208288人