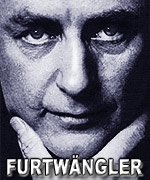ヘルベルト・フォン・カラヤン(Herbert von Karajan 1908〜1989年。オーストリア)
戦後のクラシック界で「帝王」として君臨し、その一挙手一投足は常に世を騒がし、BPO・VPOを駆使して名録音を次から次に世に出した巨匠指揮者ですが、その生涯は苦渋と悲劇に満ちていました。
ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院、ウィーン音楽アカデミーに学び、ウルム市立歌劇場で指揮デビュー、ドイツ各地のオケを歴任して、1938年に初めてベルリンフィルを指揮しました。しかしアーヘン市立歌劇場の音楽総監督になるためナチス党員になったため、戦後彼はオーストリアに送還され不名誉なレッテルが生涯つきまとうことになりましたが、EMIの名プロデュサー・レッグによって1946年から録音をはじめ、1956年にフルトヴェングラーの後任としてベルリンフィルの終身指揮者となりました。テンポをはっきりとらず時には目をつぶったりして顔の表情だけで表現したり、クライマックスでは両手を横に広げるなど、指揮の表現にこだわり、従来の巨匠の音楽性にアンチテーゼを投げかけ、耽美面とオケの精妙さを求めたことが現役時代に過小評価されていたことは残念です。DGとの契約後は膨大な録音活動を生涯つづけ、音楽界の帝王の名をほしいままにしました。
レパートリーはきわめて広く、ウィーン古典派からロマン派、国民楽派、近代音楽などお得意だった作曲家は十指に余り、また歌劇にも名演が多くあります。映像も多く残され、DVD化されていることは嬉しい限りです。
コミュはhttp://
あなたのお好きなカラヤンの名演・名盤をお教え下さい。
戦後のクラシック界で「帝王」として君臨し、その一挙手一投足は常に世を騒がし、BPO・VPOを駆使して名録音を次から次に世に出した巨匠指揮者ですが、その生涯は苦渋と悲劇に満ちていました。
ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院、ウィーン音楽アカデミーに学び、ウルム市立歌劇場で指揮デビュー、ドイツ各地のオケを歴任して、1938年に初めてベルリンフィルを指揮しました。しかしアーヘン市立歌劇場の音楽総監督になるためナチス党員になったため、戦後彼はオーストリアに送還され不名誉なレッテルが生涯つきまとうことになりましたが、EMIの名プロデュサー・レッグによって1946年から録音をはじめ、1956年にフルトヴェングラーの後任としてベルリンフィルの終身指揮者となりました。テンポをはっきりとらず時には目をつぶったりして顔の表情だけで表現したり、クライマックスでは両手を横に広げるなど、指揮の表現にこだわり、従来の巨匠の音楽性にアンチテーゼを投げかけ、耽美面とオケの精妙さを求めたことが現役時代に過小評価されていたことは残念です。DGとの契約後は膨大な録音活動を生涯つづけ、音楽界の帝王の名をほしいままにしました。
レパートリーはきわめて広く、ウィーン古典派からロマン派、国民楽派、近代音楽などお得意だった作曲家は十指に余り、また歌劇にも名演が多くあります。映像も多く残され、DVD化されていることは嬉しい限りです。
コミュはhttp://
あなたのお好きなカラヤンの名演・名盤をお教え下さい。
|
|
|
|
コメント(54)
カラヤンほど名盤と呼ばれる盤を出している指揮者も
珍しいですが、個人的に好きなCDを下記に列記してみ
たいと思います。
01位:ブルックナー交響曲第七番 VPO
ただひたすら感動するだけです。特に第二楽章は白眉
02位:マーラー交響曲第九番(1980年代録音)BPO
バーンスタインの演奏に危機感を覚えたカラヤンが
焦って録音しなおした一品。バーンスタインの演奏
と比較すると面白いです。ついでにバルビローリの
盤も比較すると三者三様に楽しめます。
03位:スメタナ モルダウ(1980年代)BPO
ウィーンフィル盤(1984年頃?)よりベルリンフィル
盤の方が好きです。
04位:モーツァルト ホルン協奏曲 デニス・ブレイン(hr)PO
未だに色あせない名演。どちらかというとブレイン
あっての名盤と言えるかもしれません。
05位:R.シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき VPO
ウィーンフィル盤が好きですね。コンサートマスターは
記憶が確かならボスコフスキー。そして映画のサントラ
でも使われております。
06位:R.シュトラウス アルプス交響曲 BPO
個人的ですみませんが、アルプスにのめりこんだのは、
ほかならぬカラヤン盤でした。未だに愛聴盤になって
おります。
07位:チャイコフスキー ピアノ協奏曲 リヒテル VSO
何気に名演だと思うのは私だけでしょうか。
08位:ベートーヴェン トリプルコンチェルト BPO
今思えば豪華すぎます。カラヤン・ベルリンフィルで
ソリストがオイストラフ(Vn)、ロストロポーヴィッチ(Vc)
リヒテル(Pf)
共産圏ソリストを全員かき集めた一期一会な演奏会は
想像するだけでも考えられない光景です。
09位:R.シュトラウス バラの騎士
カラヤンはシュトラウス指揮者だなと思うところです。
DVD も勿論素晴らしい仕上がり。
10位:モーツァルト交響曲29番 BPO (1980年代)
最後の日本公演でも取り上げた曲。彼が頻繁に取り上げた
ためか晩年29番と39番のみCDで残しています。
当時のジャケットもお気に入りの一つだったりします。
番外:
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」 VPO
ブルックナー交響曲第九番 VPO(1970年頃Live)
ブルックナー交響曲第八番 VPO(1980年頃)
チャイコフスキー交響曲第五番VPO(1980年代)
シュミット ノートルダム間奏曲
ベルリオーズ 鬼火の踊り・妖精の踊りBPO
ビゼー 歌劇「カルメン」
ビゼー 管弦楽曲集 BPO
プロコフィエフ 交響曲第五番 BPO
チャイコフスキー 三大バレー
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロストロポーヴィッチ
ドヴォルザーク 交響曲第九番「新世界」
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」
ワグナー 管弦楽集 VPO(ザルツブルグ音楽祭)
珍しいですが、個人的に好きなCDを下記に列記してみ
たいと思います。
01位:ブルックナー交響曲第七番 VPO
ただひたすら感動するだけです。特に第二楽章は白眉
02位:マーラー交響曲第九番(1980年代録音)BPO
バーンスタインの演奏に危機感を覚えたカラヤンが
焦って録音しなおした一品。バーンスタインの演奏
と比較すると面白いです。ついでにバルビローリの
盤も比較すると三者三様に楽しめます。
03位:スメタナ モルダウ(1980年代)BPO
ウィーンフィル盤(1984年頃?)よりベルリンフィル
盤の方が好きです。
04位:モーツァルト ホルン協奏曲 デニス・ブレイン(hr)PO
未だに色あせない名演。どちらかというとブレイン
あっての名盤と言えるかもしれません。
05位:R.シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき VPO
ウィーンフィル盤が好きですね。コンサートマスターは
記憶が確かならボスコフスキー。そして映画のサントラ
でも使われております。
06位:R.シュトラウス アルプス交響曲 BPO
個人的ですみませんが、アルプスにのめりこんだのは、
ほかならぬカラヤン盤でした。未だに愛聴盤になって
おります。
07位:チャイコフスキー ピアノ協奏曲 リヒテル VSO
何気に名演だと思うのは私だけでしょうか。
08位:ベートーヴェン トリプルコンチェルト BPO
今思えば豪華すぎます。カラヤン・ベルリンフィルで
ソリストがオイストラフ(Vn)、ロストロポーヴィッチ(Vc)
リヒテル(Pf)
共産圏ソリストを全員かき集めた一期一会な演奏会は
想像するだけでも考えられない光景です。
09位:R.シュトラウス バラの騎士
カラヤンはシュトラウス指揮者だなと思うところです。
DVD も勿論素晴らしい仕上がり。
10位:モーツァルト交響曲29番 BPO (1980年代)
最後の日本公演でも取り上げた曲。彼が頻繁に取り上げた
ためか晩年29番と39番のみCDで残しています。
当時のジャケットもお気に入りの一つだったりします。
番外:
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」 VPO
ブルックナー交響曲第九番 VPO(1970年頃Live)
ブルックナー交響曲第八番 VPO(1980年頃)
チャイコフスキー交響曲第五番VPO(1980年代)
シュミット ノートルダム間奏曲
ベルリオーズ 鬼火の踊り・妖精の踊りBPO
ビゼー 歌劇「カルメン」
ビゼー 管弦楽曲集 BPO
プロコフィエフ 交響曲第五番 BPO
チャイコフスキー 三大バレー
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロストロポーヴィッチ
ドヴォルザーク 交響曲第九番「新世界」
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」
ワグナー 管弦楽集 VPO(ザルツブルグ音楽祭)
はじめまして
カラヤンはこの人の演奏が無かったらクラシックなんか聞き続けなかったと言えるほどに好きなアーティストです
完璧主義と言われつつも、楽団員が音を外してもそのまま続けてしまうあたりに本当に良い意味での「音楽バカ」だったんだろうなあ、と想い出します
生前は「死後は忘れ去られる」とか言われてましたが、今の音楽状況を見るにつけ、むしろ存在感が増して来てる感じがしますね
カラヤンには大好きな録音が多いのですが、特に他の巨匠が残さなかったような小品集に素敵なものが多いと思います
個人的にはリストの前奏曲が好きです
磨き抜かれた美しさ、透明感、そしてフィナーレにおける豪快なファンファーレとまさにこの曲のベスト演奏ではないでしょうか
カラヤンはこの人の演奏が無かったらクラシックなんか聞き続けなかったと言えるほどに好きなアーティストです
完璧主義と言われつつも、楽団員が音を外してもそのまま続けてしまうあたりに本当に良い意味での「音楽バカ」だったんだろうなあ、と想い出します
生前は「死後は忘れ去られる」とか言われてましたが、今の音楽状況を見るにつけ、むしろ存在感が増して来てる感じがしますね
カラヤンには大好きな録音が多いのですが、特に他の巨匠が残さなかったような小品集に素敵なものが多いと思います
個人的にはリストの前奏曲が好きです
磨き抜かれた美しさ、透明感、そしてフィナーレにおける豪快なファンファーレとまさにこの曲のベスト演奏ではないでしょうか
私は、やはり写真に上げたR.シュトラウスの
『英雄の生涯』でしょう。コレに尽きますね。(^_^;)
写真のモノは、59年録音のBPOとの作品ですが、
後年に録音したモノと比較しても、やはり59年の
録音が最高です。
カラヤンと完全無欠の集団『BPO』が織りなす、
完全版と言って も良いぐらいの出来だと、
私は思います。(^_^;)
それと『アルプス交響曲』もイイですね。
カラヤンの演奏では、R.シュトラウスや、ワーグナーの
様な、感情がハッキリと出ていて、少々派手な曲の方が
合っている様な気がします。
ベートーヴェンやモーツァルトも悪くは無いですが
その演奏の余りの美しさが、却って重厚感を抑えて
しまい、軽くなって聞こえて来る感じがして、今一つ
と感じます。
その点、ベーム辺りのベートーヴェン・モーツァルト
の演奏の方が、実直感があり、良く聞こえてしまうのは
私だけでしょうか? (^_^;)
そう言った意味で、私はカラヤンの派手な曲の演奏を
支持します。
『英雄の生涯』でしょう。コレに尽きますね。(^_^;)
写真のモノは、59年録音のBPOとの作品ですが、
後年に録音したモノと比較しても、やはり59年の
録音が最高です。
カラヤンと完全無欠の集団『BPO』が織りなす、
完全版と言って も良いぐらいの出来だと、
私は思います。(^_^;)
それと『アルプス交響曲』もイイですね。
カラヤンの演奏では、R.シュトラウスや、ワーグナーの
様な、感情がハッキリと出ていて、少々派手な曲の方が
合っている様な気がします。
ベートーヴェンやモーツァルトも悪くは無いですが
その演奏の余りの美しさが、却って重厚感を抑えて
しまい、軽くなって聞こえて来る感じがして、今一つ
と感じます。
その点、ベーム辺りのベートーヴェン・モーツァルト
の演奏の方が、実直感があり、良く聞こえてしまうのは
私だけでしょうか? (^_^;)
そう言った意味で、私はカラヤンの派手な曲の演奏を
支持します。
カラヤン指揮ベルリンフィル70年代のベートーヴェン交響曲第6番「田園」を聞いたマイミクさんが、とても美しいと書いていたのを思い出し、私はその録音の直後に来日した際のライブを聞きました。p(^_^)q
1977年11月16日、普門館でエフエム東京が音声を収録し、テレビ放映もされた日の演奏ということで、オケの団員は一軍メンバーが舞台に乗っていたとのことです。
ライブなのにオケが上手い巧い!
18型の弦楽器群が滝のような音の洪水をこれでもかという美しい音で浴びせてきます。
こういうサウンドを聞かせる指揮者とオケは少なくとも録音で聞いた限りではこのコンビ以外では聞いたことがありません。*\(^o^)/*
私はそういうところが好きなのに、元マイミクの一人からは全く理解してもらえず、カラヤンのベートーヴェンやブラームスなんてどこがいいのかさっぱりわからないと言われて不満でした。~_~;
カラヤンの田園はテンポが早くてゆったりとした音の味わいに欠けるせいか、
田舎をスポーツカーで走り抜けるような演奏と揶揄する評論家もいましたが、
逆に遅すぎるおどろおどろしいテンポのフルトヴェングラーの田園は、
第一楽章の副題が「田舎に着いたときの憂鬱な気分」だと皮肉った評論家もいるので、
受け止め方は人それぞれだということですね。
ベートーヴェン存命中の昔の演奏はテンポが早かったことが予想されるので、カラヤンのテンポは決して早すぎるとは言えないと思います。
指揮者自身の独創的な解釈や感情を排し、純粋に楽しく美しい音楽を提供してくれる田園です。
カップリングの運命は、特定の管楽器奏者の細かいミスがありますが、気になるレベルではありません。
かの、カルロス・クライバーも尊敬していたというカラヤンの運命は確かに彼の演奏ともそっくりです。カルロスのがやや音楽に弾力が感じられるかな。
先日聞いたティーレマンのゆったりしたテンポの堂々たる運命も感銘を受けましたが、早めのテンポでキビキビと、しかもゴージャスな音で迫り来るタイプのこういう演奏はもはや現代では聞かれない貴重な遺産だと思いました。
録音や映像を残すことに執念を燃やしたカラヤン
は、こうして私の心の中でずーっと生き続けてくれてます。(^◇^)
1977年11月16日、普門館でエフエム東京が音声を収録し、テレビ放映もされた日の演奏ということで、オケの団員は一軍メンバーが舞台に乗っていたとのことです。
ライブなのにオケが上手い巧い!
18型の弦楽器群が滝のような音の洪水をこれでもかという美しい音で浴びせてきます。
こういうサウンドを聞かせる指揮者とオケは少なくとも録音で聞いた限りではこのコンビ以外では聞いたことがありません。*\(^o^)/*
私はそういうところが好きなのに、元マイミクの一人からは全く理解してもらえず、カラヤンのベートーヴェンやブラームスなんてどこがいいのかさっぱりわからないと言われて不満でした。~_~;
カラヤンの田園はテンポが早くてゆったりとした音の味わいに欠けるせいか、
田舎をスポーツカーで走り抜けるような演奏と揶揄する評論家もいましたが、
逆に遅すぎるおどろおどろしいテンポのフルトヴェングラーの田園は、
第一楽章の副題が「田舎に着いたときの憂鬱な気分」だと皮肉った評論家もいるので、
受け止め方は人それぞれだということですね。
ベートーヴェン存命中の昔の演奏はテンポが早かったことが予想されるので、カラヤンのテンポは決して早すぎるとは言えないと思います。
指揮者自身の独創的な解釈や感情を排し、純粋に楽しく美しい音楽を提供してくれる田園です。
カップリングの運命は、特定の管楽器奏者の細かいミスがありますが、気になるレベルではありません。
かの、カルロス・クライバーも尊敬していたというカラヤンの運命は確かに彼の演奏ともそっくりです。カルロスのがやや音楽に弾力が感じられるかな。
先日聞いたティーレマンのゆったりしたテンポの堂々たる運命も感銘を受けましたが、早めのテンポでキビキビと、しかもゴージャスな音で迫り来るタイプのこういう演奏はもはや現代では聞かれない貴重な遺産だと思いました。
録音や映像を残すことに執念を燃やしたカラヤン
は、こうして私の心の中でずーっと生き続けてくれてます。(^◇^)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
巨匠指揮者讃 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
巨匠指揮者讃のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75482人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6442人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208286人