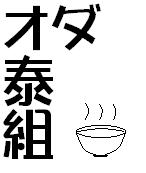共同研究食グループの報告を始めます。
指導は、小田泰夫先生、神明久先生
メンバーご覧の通りです。
私たちの研究は三年間にわたっておこなう共同研究食グループ課題の「私たち食から生活を考え社会を見る」の二年目にあたります
今年度、私達共同研究食グループは昨年度の研究に引き続き「食を賢く選ぶ」をテーマとして研究を進めてきました。論文構成(pp)はこのようになっております。
(読まないよ)1章 日本の食事情
2章 食品の流通(生産と消費を結ぶ機能)変化と実態
3章 食選択が持つ意味
4章 自由学園の食教育
5章 私たちの食の学び
6章 結論
7章 提案
(pp)今回の報告では日本の食事情、食選択、自由学園の食教育、研究の結論と提案、私達の1年間の活動内容について述べます。
(読まないよ)・日本の食事情
・食選択
・自由学園の食育
・結論
・提案
・実践
(pp)≪日本の食事情≫
社旗情勢の変化に伴い消費者のニーズ、農業の在り方、流通形態など、日本の食の在り方も変化してきました。現在、日本社会は農業の後継者不足や国内自給率の停滞、食文化の崩壊、輸入依存、食糧廃棄物の増加、自然破壊など、食をめぐる様々な弊害を抱えています。
このような食問題の中でも私たちに最も身近なことは(pp)?何を食べるか(pp)?どのような環境で食べるか、という食の選択です。スーパーなどの市場では消費者の生活様式や価値観に対応した需要を満たす為に、(pp)品揃えが豊富であること、調理方法が簡単であること、見た目や彩がきれいであること、季節を問わず入手できることなど様々な食品を提供するようになりました。また市場の提供する商品が消費者の食生活の基盤になっています。
(読まないよ)消費者のニーズ
・ 種類が豊富である事
・ 調理方法が簡単である事
・ 見た目や彩りがきれいである事(着色料、農薬使用栽培)
・ 管理し易い事(防腐剤、個包装)
・ 機能的である事(栄養剤)
・ 季節を問わず入手できる事(野菜・果物)
・ 多国籍な食材が入手できる事
このような食材の多様化や入手方法の利便化に伴い、私達の食選択は自由になりました。しかしその代わりとして、日本の食文化や食材を選ぶ基準が曖昧になってきてはいないでしょうか。
食選択
(PP) 本研究において、私たちが考える「食選力」とは、複雑化する社会において
「よい食を選ぶことの出来る力」「自らの意志で食を選択できる能力」です。そして食教育はこの力を育むことにおいて大きな意味を持つものであると考えました。
(PP)最善の食選択を定義づける事は出来ません。なぜなら、個々によってライフスタイルや、何に対して重きを置くかという価値観が異なり、その人に合った無理の無い食のライフスタイルであることが第1条件であるからです。
食教育は食選力を育むことにおいて大きな意味を持つ、と先に述べましたが、自由学園で食教育はどのようになされているのでしょうか。
自由学園の食教育
創立当初、昼食に弁当を持参していた生徒たちはミセス羽仁の
(pp)「育ち盛りの生徒が弁当では栄養上十分に懸念される」
(pp)「生徒たちに温かい食事を」
という考えのもと、食事作りを通した(pp)実生活を学ぶ教育を始め、生徒たちは交代で材料の仕入れや管理、調理、配膳などの(pp)昼食の用意を任されました。
時代の移り変わりとともに各部の食への取り組みも変化し、(pp)(pp)現在の女子部の昼食の用意は調理、配膳のみになっています。また、最高学部では一部の学生しか食に関われていないのが現状です。創立当初から行われてきた取り組みが生徒の負担、各部のカリキュラムの新体制によりなくなってしまったこともありますが、その中でも現在の生徒、学生の生活に合わせた取り組みが行われています。
(pp)現在の食への取り組み
平成17年度からは3年計画で(pp)「食の学び推進委員会」が発足されました。
今までの食の学びをさらに価値あるものにし、生産から廃棄までを学び、社会に関心を持つとともに一人一人が社会に出てから、(pp)食材を自分で選ぶ力を身につけることを目的としました。
このプロジェクトを推進するために、
自由学園創立当初から大切にされてきた食事時間を(pp)よりよい時間にすること、
学部の食に関する3つの活動を(pp)食糧部と連携して3年計画で行うこと、
各部の学業報告会で(pp)食に関することを取り上げる
など各部で行ってきました。
例えば、学部では、平成17年度から学部1年が交代で学部の昼食の献立作りを行っています。また、今年度からは自由学園で使用する米の3分の1を那須で生産された米にすることが具体的に進められ、女子部普通科1年、男子部普通科2年、学部3年の共同研究食グループが那須で米作りを経験しました。
(pp)食材使用のガイドライン
食糧部では食材使用のガイドラインに基づき各部に食材を供給しています。このガイドラインの理念は(pp)自由学園内に供給される食材が(pp)「作り手の見える食」であること、その食事を食べることによって(pp)「感謝する心」社会に出てからも活かせる「食選力が身につく」ように考えられたものです。この理念を実現させるために、食材の美味しさはもちろん、安全性、経済性、利便性、環境性を十分に考慮した食材選びを行い、これらの理念を理解して対応してくださる(pp)業者の方との食材選択を心がけ、取り組みを始めています。現在、食材を選ぶということを行っていない生徒、学生に、食糧部がどのような理念を持って食材の購入を行っているかを知ってもらうことで、生徒、学生が食の選び方について考えるきっかけとなるのではないでしょうか。
(pp)自由学園の食教育は、食と関わる機会が多く、食選力を培う(pp)場が多くあるといえます。しかし、必ずしもその環境を活かしきれていないことが現状です。私たちは、自由学園の生徒・学生として、これらの環境を活かしていくことが望まれるのではないでしょうか。
(pp)結論(田中H)
ライフスタイル、流通の変化は人々の食環境に影響を与えました。
(pp)食選択は人々の「生き方」の選択でもあり、自分自身の健康や子孫への影響、地球環境の未来へと、多岐に渡る問題です。つまり、私たち個人の「食」の選びかたによっては、(pp)大きくは地球環境の破壊、小さくは私たち自身の健康の害へとつながるものなのです。
「食の選び方」は、(pp)個人のライフスタイル、社会の動きによって異なります。そのため、一つの「正しい食選択」を提示することは困難といえます。しかし、これからの時代においての、「食の選び方」に、(pp)自分のことだけを考えるのではなく、(pp)他者のことも考えた食選択の視点が重要になっていくと思います。
では、そのような「食選択」を行うには、どのようにしたらよいのでしょうか。この問に対し、私たちは(pp)「積極的に食に関わりを持つ」という結論に至りました。(pp)この「食に関わりを持つこと」は食材がどこで作られたものであるかを知ることなど、特別な環境がなくても、簡単なことから始めることが出来ます。
今年度、私たちは(pp)那須農場での米作り、(pp)地域農家との関わり(pp)流通市場の見学など、実際に私たちが現場に足を運ぶなどの体験を通して学びました。
これらの活動を通して、私たち自身、4月に共同研究を始めた時点よりも食に対する考えが深まり、食品、食環境においても、私たちなりの考え方が形成されました。そして、この活動は、自由学園という環境があったからこそできた学びでした。一つの「正しい食選択」を提示することは出来ませんが、私たちはこれらの経験から、(pp)「食へ関わることが、賢い食選択へつながる」ということを導き出しました。
提案・実践(田窪)
私たちは今年度の活動から、自由学園の生徒、学生の食にたいする意識の向上のため、提案し、実践できたことを報告します。
(pp)?地域産野菜を食事に取り入れる(読んでね)
私たちは1学期に地産地消すなわち「地域で作られた作物を同地域で消費する」という一つの方法をしり、そのことから東久留米の農業に興味をもちフィールドワークをおこないました。この「地域で作られた作物を地域で消費する」ということが、私たちの関心を高める、と考え、(pp)食料部に相談し、まずは女子部で実践しました。青果物に関して取引している中卸業者の荒川青果にご協力をいただき、地元の農作物を優先的に仕入れていただけることになりました。
2月23日に(pp)(pp)東久留米産のほうれん草と清瀬産の人参が使用されました。
(写真)今後はブロッコリー、水菜、にんじん、といった食材が取り入れられる予定です。
?学部生の食に対する意識の向上(読んでね)
現在学部の昼食で行われている献立の報告をより豊かにすることで、学生の食に対する関心を高められると考え、昼食で使われている食材の産地や栄養値を、耳で聞くだけでなく目でも見ることが出来るようにホワイトボードを用いて報告できるようにしました。また、盛り付け例のディスプレイを行っています。
(写真)今後は、報告の内容を充実させ、継続的におこなわれるように活動します。
まとめ(木下)
私たちは共同研究の時間を通じて食選択について考える時を多く持ち、自分たち自身が普段食しているものに対する関心が薄いことに気づきました。
すべての食材、食品は生産されてから、私たちの手元に届くまで多くの要素が関わっています。私たちは、消費者の一人として自分が食するものについて、より関心を持つことが大切なのではないでしょうか。
私たちはこれからこの研究でそれぞれが学んできたことを活かし、社会に出てから、また家庭を持ってからも、自分が食するものに対する関心を持ち続け、よい食の選択とは何であるかを考え、発信していきたいと考えています。
参考文献は以下とおりのです
指導は、小田泰夫先生、神明久先生
メンバーご覧の通りです。
私たちの研究は三年間にわたっておこなう共同研究食グループ課題の「私たち食から生活を考え社会を見る」の二年目にあたります
今年度、私達共同研究食グループは昨年度の研究に引き続き「食を賢く選ぶ」をテーマとして研究を進めてきました。論文構成(pp)はこのようになっております。
(読まないよ)1章 日本の食事情
2章 食品の流通(生産と消費を結ぶ機能)変化と実態
3章 食選択が持つ意味
4章 自由学園の食教育
5章 私たちの食の学び
6章 結論
7章 提案
(pp)今回の報告では日本の食事情、食選択、自由学園の食教育、研究の結論と提案、私達の1年間の活動内容について述べます。
(読まないよ)・日本の食事情
・食選択
・自由学園の食育
・結論
・提案
・実践
(pp)≪日本の食事情≫
社旗情勢の変化に伴い消費者のニーズ、農業の在り方、流通形態など、日本の食の在り方も変化してきました。現在、日本社会は農業の後継者不足や国内自給率の停滞、食文化の崩壊、輸入依存、食糧廃棄物の増加、自然破壊など、食をめぐる様々な弊害を抱えています。
このような食問題の中でも私たちに最も身近なことは(pp)?何を食べるか(pp)?どのような環境で食べるか、という食の選択です。スーパーなどの市場では消費者の生活様式や価値観に対応した需要を満たす為に、(pp)品揃えが豊富であること、調理方法が簡単であること、見た目や彩がきれいであること、季節を問わず入手できることなど様々な食品を提供するようになりました。また市場の提供する商品が消費者の食生活の基盤になっています。
(読まないよ)消費者のニーズ
・ 種類が豊富である事
・ 調理方法が簡単である事
・ 見た目や彩りがきれいである事(着色料、農薬使用栽培)
・ 管理し易い事(防腐剤、個包装)
・ 機能的である事(栄養剤)
・ 季節を問わず入手できる事(野菜・果物)
・ 多国籍な食材が入手できる事
このような食材の多様化や入手方法の利便化に伴い、私達の食選択は自由になりました。しかしその代わりとして、日本の食文化や食材を選ぶ基準が曖昧になってきてはいないでしょうか。
食選択
(PP) 本研究において、私たちが考える「食選力」とは、複雑化する社会において
「よい食を選ぶことの出来る力」「自らの意志で食を選択できる能力」です。そして食教育はこの力を育むことにおいて大きな意味を持つものであると考えました。
(PP)最善の食選択を定義づける事は出来ません。なぜなら、個々によってライフスタイルや、何に対して重きを置くかという価値観が異なり、その人に合った無理の無い食のライフスタイルであることが第1条件であるからです。
食教育は食選力を育むことにおいて大きな意味を持つ、と先に述べましたが、自由学園で食教育はどのようになされているのでしょうか。
自由学園の食教育
創立当初、昼食に弁当を持参していた生徒たちはミセス羽仁の
(pp)「育ち盛りの生徒が弁当では栄養上十分に懸念される」
(pp)「生徒たちに温かい食事を」
という考えのもと、食事作りを通した(pp)実生活を学ぶ教育を始め、生徒たちは交代で材料の仕入れや管理、調理、配膳などの(pp)昼食の用意を任されました。
時代の移り変わりとともに各部の食への取り組みも変化し、(pp)(pp)現在の女子部の昼食の用意は調理、配膳のみになっています。また、最高学部では一部の学生しか食に関われていないのが現状です。創立当初から行われてきた取り組みが生徒の負担、各部のカリキュラムの新体制によりなくなってしまったこともありますが、その中でも現在の生徒、学生の生活に合わせた取り組みが行われています。
(pp)現在の食への取り組み
平成17年度からは3年計画で(pp)「食の学び推進委員会」が発足されました。
今までの食の学びをさらに価値あるものにし、生産から廃棄までを学び、社会に関心を持つとともに一人一人が社会に出てから、(pp)食材を自分で選ぶ力を身につけることを目的としました。
このプロジェクトを推進するために、
自由学園創立当初から大切にされてきた食事時間を(pp)よりよい時間にすること、
学部の食に関する3つの活動を(pp)食糧部と連携して3年計画で行うこと、
各部の学業報告会で(pp)食に関することを取り上げる
など各部で行ってきました。
例えば、学部では、平成17年度から学部1年が交代で学部の昼食の献立作りを行っています。また、今年度からは自由学園で使用する米の3分の1を那須で生産された米にすることが具体的に進められ、女子部普通科1年、男子部普通科2年、学部3年の共同研究食グループが那須で米作りを経験しました。
(pp)食材使用のガイドライン
食糧部では食材使用のガイドラインに基づき各部に食材を供給しています。このガイドラインの理念は(pp)自由学園内に供給される食材が(pp)「作り手の見える食」であること、その食事を食べることによって(pp)「感謝する心」社会に出てからも活かせる「食選力が身につく」ように考えられたものです。この理念を実現させるために、食材の美味しさはもちろん、安全性、経済性、利便性、環境性を十分に考慮した食材選びを行い、これらの理念を理解して対応してくださる(pp)業者の方との食材選択を心がけ、取り組みを始めています。現在、食材を選ぶということを行っていない生徒、学生に、食糧部がどのような理念を持って食材の購入を行っているかを知ってもらうことで、生徒、学生が食の選び方について考えるきっかけとなるのではないでしょうか。
(pp)自由学園の食教育は、食と関わる機会が多く、食選力を培う(pp)場が多くあるといえます。しかし、必ずしもその環境を活かしきれていないことが現状です。私たちは、自由学園の生徒・学生として、これらの環境を活かしていくことが望まれるのではないでしょうか。
(pp)結論(田中H)
ライフスタイル、流通の変化は人々の食環境に影響を与えました。
(pp)食選択は人々の「生き方」の選択でもあり、自分自身の健康や子孫への影響、地球環境の未来へと、多岐に渡る問題です。つまり、私たち個人の「食」の選びかたによっては、(pp)大きくは地球環境の破壊、小さくは私たち自身の健康の害へとつながるものなのです。
「食の選び方」は、(pp)個人のライフスタイル、社会の動きによって異なります。そのため、一つの「正しい食選択」を提示することは困難といえます。しかし、これからの時代においての、「食の選び方」に、(pp)自分のことだけを考えるのではなく、(pp)他者のことも考えた食選択の視点が重要になっていくと思います。
では、そのような「食選択」を行うには、どのようにしたらよいのでしょうか。この問に対し、私たちは(pp)「積極的に食に関わりを持つ」という結論に至りました。(pp)この「食に関わりを持つこと」は食材がどこで作られたものであるかを知ることなど、特別な環境がなくても、簡単なことから始めることが出来ます。
今年度、私たちは(pp)那須農場での米作り、(pp)地域農家との関わり(pp)流通市場の見学など、実際に私たちが現場に足を運ぶなどの体験を通して学びました。
これらの活動を通して、私たち自身、4月に共同研究を始めた時点よりも食に対する考えが深まり、食品、食環境においても、私たちなりの考え方が形成されました。そして、この活動は、自由学園という環境があったからこそできた学びでした。一つの「正しい食選択」を提示することは出来ませんが、私たちはこれらの経験から、(pp)「食へ関わることが、賢い食選択へつながる」ということを導き出しました。
提案・実践(田窪)
私たちは今年度の活動から、自由学園の生徒、学生の食にたいする意識の向上のため、提案し、実践できたことを報告します。
(pp)?地域産野菜を食事に取り入れる(読んでね)
私たちは1学期に地産地消すなわち「地域で作られた作物を同地域で消費する」という一つの方法をしり、そのことから東久留米の農業に興味をもちフィールドワークをおこないました。この「地域で作られた作物を地域で消費する」ということが、私たちの関心を高める、と考え、(pp)食料部に相談し、まずは女子部で実践しました。青果物に関して取引している中卸業者の荒川青果にご協力をいただき、地元の農作物を優先的に仕入れていただけることになりました。
2月23日に(pp)(pp)東久留米産のほうれん草と清瀬産の人参が使用されました。
(写真)今後はブロッコリー、水菜、にんじん、といった食材が取り入れられる予定です。
?学部生の食に対する意識の向上(読んでね)
現在学部の昼食で行われている献立の報告をより豊かにすることで、学生の食に対する関心を高められると考え、昼食で使われている食材の産地や栄養値を、耳で聞くだけでなく目でも見ることが出来るようにホワイトボードを用いて報告できるようにしました。また、盛り付け例のディスプレイを行っています。
(写真)今後は、報告の内容を充実させ、継続的におこなわれるように活動します。
まとめ(木下)
私たちは共同研究の時間を通じて食選択について考える時を多く持ち、自分たち自身が普段食しているものに対する関心が薄いことに気づきました。
すべての食材、食品は生産されてから、私たちの手元に届くまで多くの要素が関わっています。私たちは、消費者の一人として自分が食するものについて、より関心を持つことが大切なのではないでしょうか。
私たちはこれからこの研究でそれぞれが学んできたことを活かし、社会に出てから、また家庭を持ってからも、自分が食するものに対する関心を持ち続け、よい食の選択とは何であるかを考え、発信していきたいと考えています。
参考文献は以下とおりのです
|
|
|
|
|
|
|
|
食06’s 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
食06’sのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6470人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19249人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208305人