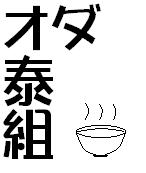序章(田部井)
自由学園の「食の学びプロジェクト」発足に伴い、学園創立当初からの「食教育」の見直し、活性化が注目されている。自由学園では創立当初から「食べ物」と生徒との密接な関わりを大切にしてきた。しかし、一口に「食教育」といっても、時代の変化と共に「食べ物」と生徒との相互関係も変化してきている。自由学園生と「食」の関係は大きく3つの時代に区分できるのではないだろうか。まず一つ目の時代は創立当初から第二次大戦までの時代。この時代の「食」は良家の子女の花嫁勉強の「教材」としての役割が大きい。2つ目の時代は戦時中である。この時代の「食」との関わりは「教育」の為というよりは、生きる為の手段であった。3つ目の時代は「豊食の時代」とよばれ、「食文化の崩壊」が叫ばれる現代における「健康に生きる」為の学びである。
自由学園の創立者、羽仁もと子は学園創立時、育ち盛りの生徒に温かい昼食を食べさせたいと考えた。家でつくったお弁当では昼食の時間までに冷めてしまう、学園で温かい食事をとる為にはどうすれば良いか。この問題を解決する為、もと子は生徒自らが食事を用意する事を考案した。この方法は生徒に「食べ物」との「関わり方」を学ばせる勉強の場を与えた。当時の生徒の家庭では家政婦を雇っている事が多く、自分の食事を自ら用意するといった経験が無い者ばかりであった。やがて生徒は料理のみに限らず、野菜の栽培や購入、テーブルセット、お客を招いての行事の企画なども手がけるようになった。
一方、戦時中、生徒は生きるか死ぬかの為に「食べ物」が必要であった。生徒は大芝生を耕して畑にし、野菜を栽培して貴重な食糧を得た。当時の生徒にとって「食べ物」イコール貴重な栄養源であった。また、戦後は欧米の食文化の流入に伴い乳製品を積極的に取り入れるようになった。
21世紀を迎えた現代、生徒と「食べ物」の関係は戦時中の生徒とはいうまでもなく、創立当初の生徒とも大きく変化している。大衆の生活水準の向上に伴い、学園に通う生徒の家庭環境も変化した。今では多くの生徒の家庭で食事の買い物や料理、後片付けを家族や自らが行うことが普通である。また、「食べ物」の入手手段も容易になった。たいていどの町にも庶民の日常生活に事欠かないだけの品物を揃えた食料品店が設置されているし、品物の種類も豊富である。単に栄養補給をする為や簡単な加熱で食べることが可能になった機能的な商品も続々と開発されている。また、核家族化や両親の共働きによる家族別々の食事、偏食、過剰なダイエットといった生活タイルの変化も顕著になった。こうして多くの人々は便利で好き勝手、自由な食生活を享受するようになった。しかし、今日、日本では「食教育の重要性」を主張する声が大きくなってきている。これはどうしてであろうか。
実はここ3~40年の間、以前から日本社会で増加傾向にある凶悪犯罪、暴力、いじめ、引きこもり、精神疾患といった「事件や症状」と「食事」との密接な関係が注目されるようになってきたのだ。つまり、従来からの「良い食事」と「健康な身体」の相関関係に「健康な心」が加えて講じられるようになったのである。ある少年鑑別所に勤める警察官は少年院の子供が清涼飲料水やスナック菓子を特に好むことから乱れた食生活と犯罪の関係性を問うている。また、ビタミンB不足による学習障害、疲労、記憶障害、精神混乱、行動障害、興奮、衝動性、不眠、無気力感動、慢性的頭痛などの事例も多数報告されている。
それなら清涼飲料水やスナック菓子を減らしてビタミンBをタブレットや栄養ドリンクから摂取すれば良いではないか、と問われれば、そうではない。「食事」を単なる「栄養補給の手段」ではなく、健康な心でより良い人生を築く為の「生きる力を育てるもの」として考えることが大切である。「食教育」の必要性はそこにあるのだ。具体的には、農作物栽培や流通ルート、加工課程、調理などを学び、体験を通して自然の恵みや生産者、家族への感謝の心を育む事、家族や友人との食事を通して礼儀やマナー・対人関係を学ぶ事、地域の作物や季節の料理を食事に取り入れ郷土料理や日本の食文化を学ぶ事などが挙げられる。こうして人が子供の頃から「食する」事を「生きる基本」と考え、「食」を通して心の豊かさや寛容・謙遜、そして感謝や礼儀を備えた人間を育てることが、現代の「食」と生徒との大切な関わり方であると考えられる。
1章 日本の食事情(ふじお 中山)
ふじおの??
年表(中山)
45.8.15 日本無条件降伏
10.20 地主的土地所有無償ぼしゅう
30 米穀総合供出制実施
11.2 地主的土地所有の有償ぼしゅう
46.5.19 食糧メーデ
11.11 第二次農地改革法
47.6.19 農業復興会議
7.19 救援米供出国民運動
25 全国農民組合結成
11.19 農業共同組合法公布
48.10.23 全国指導農業共同組合連合会設立
49.6.6 土地改良法公布
12.15 漁業法公布
50.9.11 自作農の創設に関する政令公布
11.27 全国共済農業共同組合連合会創立総会
51.1.31 全国共済農業共同組合連合会創立
3.31 農業委員会法
4.7 農漁業共同組合再検整備法公布
7.25 国際小麦協定に加盟
9.8 日米安全保障条約調印
52.7.15 農地法公布
53.1.21 農民組合総同盟結成
8.17 農産物価格安定法
27 農業機械化促進法公布
11.10 冷害地帯緊急農村対策要項決定
12.29 昭和9年以来の大凶作
54.6.14 酪農復興法公布
9.16 日本中央競馬会設立
55.4.15 日中民間漁業協定調印
5.7 米の予約買い付け製採用決定 6.7 GATTに正式加盟
7.8 第一回小作料対策協議会開催
8.15 自作農維持創設資金融通法公布
10.31 中央畜産会設立
12.14 全国開放農地国家補償連合会
56.6.18 農林水産業生産制向上会設立
12.25 熊本水俣湾に奇病発生(水俣病)
57.2.20 日本農地犠牲者連盟結成
8.21農林省初の農林白書
9.10 日本農林組合全国連合会を結成
12.12 日本農地犠牲者連合会結成
12.28 水稲集団栽培始まる
58.3.24 全日本農林組合連合会
10.16 米の代表者供出制度実施決定
59.4.20 農林漁業基本問題調査会設置法公布
5.? 農業改良資金助成法公布
9.26 伊勢湾台風
10.? 米配給制度完全協議会
60.2.1 世界農林業センサス本調査実施
6.30 農地非買収者問題調査会法公布
8.15 全国農民大会結成
10.? 農林水産物121品目自由化実施
61。2.24 中央労農会議結成
3.20 果樹農業復興特別措置法公布
4.1 農協合併助成法成立
6.11 農業基本法公布
7.31 米の予約受け渡し制
11.10 農業近代化資金発足
11.? 開拓営農復興審議会
12.26 第一回農業白書
62.2.? 農業構造改善事業
4.17 アジア農協会議開催
7.30 EEC共通農業政策実施
8.8 中央酪農会議実施
10.1農業機械化研究所設立
63.3.28 全国農民総連盟発足
4.1 バナナ等輸入自由化
5.1 農林省地方農政局発足
6.4 第一回世界食糧会議
7.8 アジア農業復興機関設立
8.1 沿岸漁業復興法公布
9.? 粗目(ざらめ)自由化決定
ササニシキ発表!
64.2.21 経済同友会(農業近代化への提言を発表)
3.31 甘味資源特別処置法公布
4.8 林業基本法公布
10.10 オリンピック東京大会
65.3.6 農村労働組合全国連合会結成
5.11 山村復興法公布
6.1 全国初のカントリーエレベーター完成
2 加工原料乳生産者補給金暫定措置法公布
3 農地非買収者等に対する給付金の支給に関する法律公布
10.21 韓国6万トン輸入を契約
10.31 稲作集団栽培
12.16 農業収容人口990万人初めて一千万人を割る
66.5.17 農薬中毒対策協議会設立
7.1 畜産復興審議所設立
8.18 全国鶏卵価格安定基金設立
11.1 野菜生産出荷安定資金協会発足
12.13 全国農協畜産団地協議会結成総会
67.4.25 稲作生産組織研究会を設置
8.4 農業構造政策の基本方針を発表
9.25 物価安定推進会議 米価について提言発表
12.22 昭和42年産米収穫高1445万一千トン 史上最高の豊作
68.7.13 総合農政の展開について所信表明 西村さん!
11.16 農産物の需要と生産の長期見通し(農林省発表)
政府米異常在庫問題化
69.1.23 稲作転換対策を発表
2.10 新規開田の抑制
5.16 自主流通米発足
7.1 農業復興地域の整備に関する法律
7.19 自主流通協議会発足
70.2.1 世界農林業センサス実施
3.12 米の輸出促進法案掲出
5.15 改正農地法公布
5.20 農業者年金基金法公布
9.21 佐藤首相が『農業の過保護は避ける』と言明
10.20 BHC・DDT・ドリン経済の稲作使用を前面禁止
穀物自給率48パーセントで遂に50パーセントを切る
米の限飯政策始まる
71.2.5 米の予約限度制を導入
3.30 基本法農政10年を総括した45年度(農業白書発表)
4.2 卸売り市場法公布
6.21 農村地域工業導入促進法公布
6.22 近畿穀類問屋共同組合が自由米の仲間取引を発足させると発表
6.29 グレープフルーツなどの20品目を輸入自由化決定
11.30 BHCの販売、使用の全面禁止
72.1,20 標準価格米制度を作る
3.31 全国農業共同組合連合会(全農)設立
7.1 消費者米価の物価統制令適用廃止
6.1 農協牛乳の販売を始める
8.2 牛乳南北戦争始まる
12.19 米平均収穫量456キロ(10アールあたり)
異常気象による世界穀物危機
73.4.25 市街化区域内農地の宅地並み課税法案成立
12.7 シカゴ小麦相場暴騰
74.5.10 田中首相に日本農業の構想を手渡す
27 国土利用計画法 生産緑地法政策 10.1 中央漁業信用基金
11.6世界食糧会議 ローマで開催
75.2.1 配合飼料価格安定特別基金設立
中間農業センサス実施
5.21 国民食糧会議開催
9.9 食糧自給力の向上などの報告を首相に提出
12.19 10アール当たり収量481キロ至上最高
11.15ランブイエサミット
76.4.9 国営福島潟干拓地で200人あまりの農民が水田構起強行
5.26 FAO水産用食国際会議開催
9.27 日本経済調査協議会総合食糧政策の樹立に関する提言
10.1 野菜供給安定基金が発足
12.29 全熱量にしめる穀物のカロリー初めて50パーセント割る
77.4.18 マツクイムシ防除特別処置法公布
4.? 魚価急騰
5.3 水域暫定諸地方公布
8.11 アメリカ産さくらんぼ輸入自由化決定
8.28 薩摩灘に赤潮異常発生!!
10.21 農地改革30周年記念式典
78.7.5 農林省、農林水産省となる
19 農業依存度29.4 初めて30パー割る
8.16 干ばつ
11.20 政策推進労働組合会議農水省に牛肉の自由化、果物の季節自由化を申し出る
79.2.20 全国果実生産出荷安定協議会
3.28 中央酪農会議 牛乳の自主的調整決める
11.2 第一回日米農産物定期協議開催
12.20 農地制度研究会(第三次発足)
80.4.8 衆議院(食糧自給力強化に関する決議)を全会一致で採択
23日参院も同様の決議
8.29 日本経済調査会提言(食糧管理制度の抜本的改正)
10.31 80年代農政の基本法(農産物の生産と見通し)
11.21 農住組合法公布
81.2.2 中央協同組合 ミルクボード構想発表
4.3 日本協同組合学会創立
5.11経団連農政部会設置を決定
6.11 食糧管理法改正公布(米穀通帳廃止!!贈答米は自由化でなし崩しと間接統制がはじまる)
6.29 転作激励金減額と自主米激励金禁止など提言
4.28 食糧備蓄強化を提言
82.4.22 農産物輸入自由化反対を決議
83.1.24農産物市場開放を5年計画で行うなど提言
3.17 日本型食生活の推進
6.13 協同組合間提携
6.22 経済同友会市場メカニズム活用 保護農政は交代させるべき、と提言を発表
84.3.19 北海道農民連盟(農業不要論を唱える3企業ダイエー・味の素・ソニー)製品および販売品の不快運動展開
5.28 韓国産米の緊急輸入
6.20 米輸入の日韓協議合意
10アールあたり517キロ至上最高
85.6.26 食糧安全経団連食糧安全保障について発表
86.1.29 果樹農業復興基本方針を発表
9.10 日本の米輸入制限撤廃をアメリカ通商代表部に逓送
87.6.2 長粒種の水稲新品種『ホシユタカ』発表
11.12 全国消費者大会米輸入自由化反対を特別決議
12.2 日本および欧米の農業団体は食料自給率向上で共同声明発表
88.2.2 10品目の輸入制限をGAT違反として自由化を勧告
21 総理府世論調査国民の7割が食糧安全保障を支持
3.16 米自由化影響を試算国内生産が現在の2割にまで激減する、と予測
8.2 農産物12品目問題の自由化合意を正式決定 輸入製品品目は13に。
2.16 肉用牛子牛生産安定特別処置法成立
89.4.1 プロセスチーズ輸入自由化
5.2 東京神田市場が閉市
5.6 中央卸売り市場 大田市場で初競り
11.13 GAT農業交渉に関する国際シンポジウムが東京で開催
11.27 自主流通米の第一回入札が始まる
90.3.20 転用規制緩和
4.? 肉牛子牛生産者補給金制度補足
6.15 市民農園整備促進法公布
6.22 21世紀村作り塾スタート
7.9 学者グループが米自給を求め声明発表
8.30 自主流通米価格形成機構発足
11.13 農産物貿易の自由化に反対 GAT本部にデモ
12.12 酪農ヘルパー全国協会設立
91.1.23 全中新しい農協マーカーにJA決定
4.1 牛肉の輸入自由化
8.22 第21回国際農業経済学会が東京で開幕
12.9 農薬残留基準案を決定
92.2.13 全国村作りサミット開催
3.5 農業保護宅減の国別表をGATに提出
5.13 市町村農地保有合理化法人が自由化
8.6 全国農協合併推進支援基金が発足
9.29 有機農産物の表示ガイドラインをまとめる
93.4.14 水田活用協議会を設置
5.16 日本湖孫飢饉
8.27 冷夏で40年ぶりの米不作を発表。
9.25 米の不作により緊急輸入を決定
11.11 米の緊急輸入90万トンを発表
12.27 食糧庁外国産米80万トンの追加輸入発表
94.1.8 リフレシュビレッチ研究会を発足
3.7 食糧庁国産米の単品販売禁止
3.29 追加輸入米75万トンを決定。輸入総量は265万トン
7.14 輸入米の値引き販売
8.24 輸入量254万4千トンで米輸入終わる
10.25 UR農業合理化対策大綱
95.3.17 農協合併 助成法が改正
3.22 世界初のもち性コムギ
4.26 森林性備法促進
9.22 農業基本法に関する研究会を設置
10.16 ケベック宣言
10.27 輸入豚肉に政府ガード
11,1 主要食糧の自給および価格の安定に関する法律
96.2.27 狂牛病の進入防止のため、イギリス本土と北アイルランドからの牛肉製品の輸入を全面禁止
4.4. 1996年農業法が成立
7.1 精米の産地品種産年の表示義務化がスタート
輸入豚肉、政府ガード発動
5 JA全中2000年に30万人体制とするJA改革指針を決定
9.20 野菜5品目について原産地表示が義務化
2章 多種多様化する流通及びマーケティング (田中 栗原)
(流通とは)
流通とは生産者から消費者に至るまでの商品やサービスの流れを指す。そのため自給自足の時代、また物々交換の時代に流通は不要だった。
しかし貨幣経済の時代に入り、社会的分業が急速に進展する。なぜなら各地域が得意な分野に特化し手分けして仕事をするほうが、より効率的な経済社会と豊かな生活を生むからである。そうなってくると、生産地と消費地が分断され、両者をつなぐ流通機能が不可欠になってきた。つまり生産者と消費の間にある人的、地理的、時間的隔たりを埋め、生産者から消費者にスムーズに商品が流れる一連の機能を担うのが流通である。
そういった意味がある流通は現代のインフラと言える。
(流通業の仕事内容)
一般的に流通業とは以下の3つにまとめることができる。
?取引や売買を担う「卸売業」と「小売業」
?商品の輸送を担う「輸送業」
?商品の保管を担う「倉庫業」
(流通経路の種類と仕組み)
商品はどのように流れるのだろうか。生産された商品が消費者の手元に届くまでのルートを「流通経路」または「流通チャンネル」という。流通経路は商品の種類、規模によって多種多様だが、大きく分けると四つのパターンに分類できる
※この4つの具体例を出す→現在調査中
※学園の流通を上の図にあてはめる。(野菜、肉など)→新学期に食糧部の方に伺う
(米の流通の仕組み)
※計画外流通米などの政治政策は農政で説明と仮定
(自由学園の米の流通システム)
2006年10月まで
農家(生産者)→JA(流通業者)→町田米店(流通業者)→自由学園(消費者)
※学園で購入していた米がJAを通っていたか不明瞭なため、後日町田さんにインタビューする。
2006年10月から
契約農家(生産者)→町田米店(流通業者)→自由学園(消費者)
(農家八月朔日氏と売買契約)
自由学園の所有する水田は那須農場近隣に在住している農家の八月朔日氏が管理している。2005年度自由学園は八月朔日氏に自由学園の水田のお米を自由学園が買い取ることを提案。これに八月朔日氏が同意し両者の思惑は合致する。そして2006年の秋に実施された。
両者のメリットとして自由学園は、創立者が購入した由緒ある水田を有効活用できること、生産者の顔が見えるお米をいただく安全性と安心感、生徒の田植え体験など教育的側面が挙げられる。八月朔日氏としては、毎年確実に大量の米を固定価格で販売することから、経営の安定化とJAなどの中間業者を通さなくなることからマージンのコストを削減できる面が挙げられる。
(町田米店の助け)
自由学園の水田では約6トンの米が収穫され、それを自由学園が購入する契約の件とは別に問題が2つあった。一つ目は輸送システム。6トンの米を栃木県から学園まで運搬しなければならない。輸送を何度かに分けて遠隔地の栃木県からの輸送にかかる費用が馬鹿にならない。二つ目は米を保管する倉庫の問題。自由学園には6トンのお米を保管する倉庫がない。倉庫も米の品質保持ができる湿度、温度の調節であることが必須となる。また玄米が輸送されるため精米機の調達もしなければならない。
以上の問題点に遭遇した自由学園はこのことを町田米店と相談する。相談した結果町田米店が栃木県から学園までの運搬、6トン米の保管を請け負うことなる。また精米も町田米店が担うことから、すべての問題は町田米店に委託することで解決した。マージンが少しかかるが、倉庫建造や運搬のコストを考えると妥当な方法である。
自由学園の米の流通の中での町田米店の助けにあったように、現代社会に流通業はなくてはならいものだと理解できる。
2−2−1多種多様化する流通形態
生産者、販売者側から青果物マーケティングを考える
生産者と消費者の考え方の変化から流通形態も変化している。現在、青果物全流通の約7割が卸売市場を通って取引されている。生産者の視点から見ると、市場は価格の変動が激しい事に加え、規格による細かい選定や卸の数量による経費がかかる事、ブランド重視で大量に出荷できる農家に有利な点が多く、小規模農家には不利な流通体制であった。輸入野菜の流通への参入は価格競争を呼び、この傾向を一層強めてしまった。しかし、大手スーパーや生活協同組合による生産者との相対取引やインターネットの普及により無店舗販売が可能になった事で、卸売市場の経由率も徐々に下がっているのも現状である。過去に比べ生産者から消費者に届くまでの流通形態が多種多様化してきている。再び生産者から消費者までの距離が短まってきている現在、生産者、販売者はこれまで以上に消費者を意識し、消費者の要望に応えていかなければならい。
2−2−2現在行われている青果物のマーケティング方法
多種多様化する現在、消費者に青果物を買ってもらうために、生産者や販売者は、ただ青果物を単なる商品として売るのではなく、消費者が青果物を買いやすい様に工夫する事やブランド商品を「安心」「健康」などの付加価値を付けていかなければいけない。現在行われているマーケティング方法を例に挙げ、消費者にどの様にアプローチしているのかを考察する。
<生産者・販売者の取り組み>
・地産地消
地域の中で生産者の顔、生産地の実態を知ることが出来、新鮮で安全性の高い青果物を消費者に届けることが出来る。地域農業の特性を生かすことが出来る。
・産地直送
信頼できる生産者から青果物を買う。情報技術の進む中で、手軽に注文、受注が可能であり、利便性に問題もない。地方の青果物を新鮮に届けることが出来る。
・契約栽培
(※説明文考え中)
・有機栽培
農薬を使わない有機農業の方法で生産すること。「安全性」を支持する消費者、また現在は「ロハス」などの流れで人々の関心を集めている。
販売者側(量販店、生活共同組合の取り組み、工夫)
・大手スーパーの工夫、取り組み
・生活協同組合
・小売店(八百屋、米店)の工夫、取り組み
月泉 博,『よくわかる流通業界』,日本実業出版社,2004年11月
内村 系,『流通のしくみがわかる本』,ダイヤモンド社,1997年9月
石井寛治,『日本流通史』, 有斐閣,2003年1
3章 『食』の選び方(雨谷 山口 小野)
なぜ食選力が必要なのか(雨谷)
「食」は健康を維持するために必要不可欠なもの、ライフスタイルの多様化に伴い日本人の食事の偏りや乱れが目立つ。また、日本全国、添加物などの身体に悪いものを含む食物があふれている。健康な食生活を送るために、「どんなものを食べたら安全か危険かを知り、必要な食物をバランスよく選ぶ目」すなわち「食選力」を養うことが重要。
根底にあるのは食育
食選力を考える上で、食育という言葉は無くてはならない。むしろ食育の中に食選力があると考えるのが望ましいのかもしれない。
食育とは、国民一人一人が、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるように、自らの食について考える習慣や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付けるための学習等の取組みを指す。
日本の食
日本の食生活は、伝統的に主食であるご飯を中心に、魚や野菜、大豆から作る豆腐や納豆などの副食の中心とするものであった。
戦後、経済成長や社会の変化を背景に畜産物や油脂などの摂取が増加し、昭和50年ごろには、カロリー摂取量がほぼ満足すべき基準に達し、たんぱく質、脂肪、炭水化物のエネルギー比率のバランスがとれているなど、いわゆる「日本型食生活」ともいうべき理想的な食生活を達成していた。
しかし、その後も脂質の消費が引き続き増加したことに加え、米の消費が減少したことにより、脂質のとりすぎと炭水化物の摂取量の減少が顕著になり、不規則な食事の形態に代表されるような食生活の乱れが生じてきた。
このような偏った食生活もあり、肥満や糖尿病等が若い世代の人たちに及ぶようになり、心臓病、脳卒中、がんといった従来の「成人病」を「生活習慣病」と言い替えるようになる事態となった。健康のまま寿命を延ばすためにも、また、今後ますます増大すると見込まれる医療費を抑制することにもつながるため、食生活の改善が重要となっている。
2005年6月に食育に関する法律、「食育基本法」が制定された。
フードチェーンの多様化・複雑化や家庭等における食の教育力の低下など環境変化の中で、国民個々の自主的な努力に委ねるだけでは健全な食生活の実現が望めない状況
このような現状を踏まえ、食育に取り組む厚生労働省・文部科学省・農林水産省の3省では、食育の推進母体である「食を考える国民会議」とともに2000年3月に策定された「食生活指針」を推進している。
基本のガイドラインとして、食生活に関する健康・栄養・環境・農(漁)業・文化などの情報をもって、未来をになう子どもたちを対象に生きる力を育むため、食育を、国をあげて取り組むようになっている。従来、教育の世界では「知育・徳育・体育」が基本とされていたが、今後、「食育」の重要性は法律にもされたことからも、その重要性は増していく。
参考文献
昭和堂 新山陽子 編 食品トレーサビリティ
白桃書房 梅沢昌太郎 編著 トレーサビリティ
青春出版 武田邦彦 著 何を食べれば安全か!
ビジネス社 外食産業総合調査研究センター・編 日本の食文化と外食産業
農林統計協会 農政ジャーナリストの会 編 「食育」その可能性と必要性
農林統計協会 農政ジャーナリストの会 編 食の安全性を問う−農薬は今−
ダイヤモンド社 大来佐武郎 著 成長の限界
(山口)
昨年度の研究
昨年度の共同研究では、「自分たちの食を正しく選ぶ」というテーマのもと、「自由学園における食の概念的ガイドライン」を研究目的として進められた。研究手法として、じゃがいも、鶏肉、米の背景調査を行った。その上で、食を選ぶ要素として「安全性」「経済性」「環境性」「利便性」の4つを挙げ、食の概念的ガイドラインとしてまとめている。
1. 安全性
絶対に安全なものはないが、安心感が重要である。安心感をつくるためには信頼できる業者との長い付き合いが必要で、そこでの関わりを私たちが知ることで更に信頼が深まる。また、安全に食べることができる知識を増やすことも必要である。
2. 経済性
品質相応の価格であること。
3. 環境性
過剰包装をしない。空容器回収を行う。運搬距離が短い。
4. 利便性
生活スタイルに対応できる。
昨年度の研究から、自由学園での最も重要な食の選択要素は安全性であるという結論が出された。団体であるということで、健康維持も含め、安全性を守る必要がある。そこで、選ぶ要素として挙げられた4つの中から安全性を特に重点的に研究行った。食品の安全を消費者に伝えるために食品表示、原材料表示、また国の規定などが設けられている。しかし、先に述べたとおり、「安全なものはない」中、消費者の求める安全性とは科学的安全、精神的安全ではないかという意見であった。この精神的な安全性は、安全性とは異なる安心感近代と位置づけることができる。また近年、インターネットなどを通して比較的簡単に食品の情報を得ることが出来る。しかし一方で情報過多の時代にそれらの情報を的確に判断することは難しいものである。
前章までに述べたとおり、時代の変化に伴い、食を取り巻く環境も大きく変化してきた。私たちはそれらの変化を踏まえ、食を選ぶことが必要になっていく。
食の選択基準(小野)
「食べること」において人が幸福感を得るには、「美味しさ」を感じるか否かが本来重要であった。つまり、「味」の好みを基準にして食べるものを選んでいた。社会は消費者のニーズに合わせ物を生産し、販売する。当然、味だけでは満足感は瞬間的なものであり、栄養が偏ることで「食べること」の働きとしては不十分であり、不満足である、ということになる。人々は味に加え、どのような要素を「食べること」に求めているのだろうか。
・「美味しさ」≠「安さ」「利便性」
現在、人々は「美味しさ」に加え、新たな選択の価値基準を置くようになった。「価格」、そして「安全性」である。食材に限らず、食べ方に関しても「選び方」を考えるのであれば、「利便性」も重要な要素となるだろう。
嶋野道弘氏は『生きる力を育む、食と農の教育』(家の光教会、2006.1.1)の中で「食と農の乖離」の恐ろしさについて述べている。日本社会の急速な経済成長がそれをもたらしたことを指摘している。前に述べた「利便性」は大量消費社会となった中で日本人が安さと量と同時に求めたものである。「食」の選択基準において「利便性」が用いられるということは「食と農の乖離」した社会のうちで、「食と農」が経済活動の1部に巻き込まれ、自然のうちで行われる人間の基本的活動が、金銭で動かされる中に組み込まれた、ということである。
3−3.農産物輸入自由化
1980年代、日本は農産物輸入自由化を図った。米国からは麦を始めとする農産物が多量に入ってくるようになった。工業製品との輸出入の引き合いによって、進められた農産物貿易自由化は日本国内の自給率に大きな影響を与えることになった。
国外の農産物は日本産の農産物に比べはるかに安い値で販売されている。米には未だ関税がかかっているが、他のものはかけられていないので、日本の消費者にとっても買い物する時に「安さ」か「国産」か、とスーパーや八百屋でさえ、迷う消費者を見かけるようになった。
消費者は先に述べたように「安さ」に躍らせながら大量消費社会を築いていたが、現在はBSEや安全性を問う問題は浮上し、「安さ」「安全性」の駆け引きを自分の価値基準を決め行うようになった。
岩村暢子氏は『変わる家族 変わる食卓』の中で消費者について「自己愛型情報収集」という言葉を用いて批判している。
「自己愛型情報収集」=その時々、自分に都合のいい使える情報だけを集め、当てはめていくこと。(岩村暢子)
「安全性」が問われるようになった社会ではあるが、「安全性」を問う情報が簡単にしかも必要以上に入手可能な社会で人々はどのような情報を頼りにするのか、それは消費者自身による判断で異なってしまう。
食生活の概念として『変わりゆく食環境と食の安全性』(ぎょうせい、2001.5.20)では4つの条件をあげている。
? 地理的条件
? 社会的条件
? 経済的条件
? 文化的条件
これらの4つの条件、特に?と?は時代とともに大きく変化するものである。その中で?ち?で築かれた食生活の文化、意識が人々の「食」への関心度に差をもたらすことにもなるだろう。
3−4.選ぶ人々
「選ぶ」のは消費者だけではない。2章であげた仲卸や卸、販売業、そして生産者の立場でも「選ぶ」、そして「選ばれる」ことは重要なキーポイントとなっているのだ。東京都東久留米市で梨園を営まれている奥住実さんは「生産者は消費者のつもりで必要とされているものを考えて生産する。生産者としてプロでも、消費者としてプロの自覚が無いといけない。」と生産と消費の2つは同じ価値観を持って実行されなくてはいけないことを話された。つまり、食を選ぶのは消費者ではあるが、それを選ばされるのは生産者、仲卸、販売者の役目である。
私達は自由学園食糧部を例にあげ、一消費者として置く選択基準を導き出すことを試みた。
3−5.自由学園食糧部の取り組み(※確認後執筆)
・ ガイドラインのこと
・ 地域の農産物を出してくれるように仲卸に頼んでいること
参考資料・文献:
有吉佐和子『複合汚染 その後』潮出版社,1977
岩村暢子『変わる家族 変わる食卓』勁草書房
大塚滋『食の文化史』中央公論社,1975
『日本の食事様式』中央公論社,1980
大野和興『日本の農業を考える』岩波ジュニア新書,2004
クローズアップシリーズ『変わりゆく食環境と食の安全性』ぎょうせい,2001
嶋野道弘『生きる力を育む』家の光教会,2006
食料白書編集委員会「食料白書 2006年版 「地産地消」の現状と展望」,農山漁村文化協会,2006
岸田芳朗『地方から地産地消宣言』吉備人出版,2006現代農業11月増刊号『スローフードな日本! ‐地産地消・食の地元学‐』農山漁村文化協会,2002
藤田和芳『農業の出番だ!』ダイヤモンド社,1995
FAO世界農業予測2015-2030年「世界の農業と食糧確保」国際連合食料農業機関,2003
神門善久『日本の食と農 危機の本質』NTT出版,2006
竹下登志成『学校給食が子どもと地域を育てる』2000
山路健『飽食と粗食』1980
4章 自由学園の食教育(木下 広橋)
社会における食教育(広橋)
現在日本人の食離れが問題になっている。その中でも朝食を欠食する、栄養バランスがとれた食事をとらない、肥満傾向などの食生活の乱れている子供が増えている。子供たちが正しい食習慣と知識を身につけることができるようになるために地域や社会を挙げて食育に取り組み、推進していくことが必要とされている。平成17年7月には食育基本法が施行された。この基本法を基に食いく推進会議が設置され、平成18年3月31日に食育推進基本計画が決定した。学校において食育を推進するうえで地産地消の推進や給食の充実、子供たちの体験活動の推進があげられている。
1−1 創立者の食教育への理念(木下)
1921年、生徒の学校での昼食は各家庭から持参した弁当を食するのが当然であった創立当時、ミセス羽仁は
「頭もからだも激しく使う学校生活において育ち盛りの子供たちが小学校から女学校、或はその上の学校と10年以上も、お弁当では栄養上十分に懸念させられる」
と考え、栄養の配慮された食事を生徒が交代で炊事し、食卓を整えることで「家族」としての交流をする機会を作るのと同時に、炊事を通した実際生活を学ぶ教育を始められた。食事の一つ一つに心を配り、おいしく、栄養もあり、経済的に無駄のない昼食を作ることが即ち立派な料理の勉強になるのだと教えられ、身の回りのことは女中や雇い人にさせるのが普通であった生徒たちは、生活の中の生きた勉強になると喜んで食事に集まってきていた。
1−2 生徒の役割
創立当時、30人であった生徒は6人ずつの家族に分けられ、交代で平日の昼食の炊事を行った。料理の当番ではない他の家族は同じ時間に花畑の手入れや、鶏の飼育、また衣類や寝具などの新調や洗濯をする仕事を稽古し、生活を学ぶ時間としていた。炊事の当番は、市場へ買い付けに行く材料の仕入れや管理から、調理、配膳まで任された。
1−3 時代の移り変わり
創立から1年後、それまで料理は創立者宅の台所で行っていたが、当時一般では考えられないほど水準の高い設備が整った台所と食堂が完成し、それと同時に香欄社製の高価な食器が導入されるようになった。
12年後の1934年、学校のキャンパスが目白から南沢へと移され、台所には粉炭のオーブンや薪石炭の釜が導入され、数年(6)後にはパン焼き釜が導入されるなど、台所設備が豊富になる。
1941年に英米からの宣戦布告を受け配給制度が厳しくなったために、現在の食糧部の前身である食事中央事務局が誕生する。戦争中から戦後の食糧難時代では大芝生の前面開墾など、構内の至る所を畑に変えることで65%の自給がなされる程になった。これにより、手作りである学校での昼食と寮での朝食、夕食を続けることが可能であった。これを可能にしたのも、早期の産業教育の採用の成果だと言える。
終戦から7年後の1952年、卒業生が運営していた食事中央事務局が女子部高等科三年で運営されるようになり、経済教室が完成する。その2年後にはパン工場が設立され、市販のものから工場産のパンが食べられるようになった。
1997年、勉強など他に行わなければならないことが増え、寮生の中で体調を壊す者が多く、今の制度では生徒の負担が大きいと考え、教師会が中心となり清風寮の食事作りを週に3日、お手伝いの方に依頼するようになる。これには自治の生活に誇りのある生徒や卒業生から多くの反対意見もあった。
(自由学園の歴史1 自由学園女学校)
(自由学園の教育 羽仁恵子 実生活の指導)
(今世紀の食生活から私たちの食を考える 女子学部1996生活研究)
2−1現在の状況(広橋)
男子部は平成10年から週に1度男子部高等科2年が昼食作りを行い、昭和13年から始められた産業の授業は現在も続いている。女子部は平成11年まで高等科3年生が食料部の運営に携わり、注文や分配を行っていたが学部の新体制とともに食料部の体制も変わり、食料部の運営は教師が行うことになった。学部では現在2年課程の特別実習の食グループが献立作りや梅干作り、ジャム作りを行い、2年課程の1年生から食材の分配を行う係りをだしている。また、平成17年度からは学部1年生全員が交代で学部の昼食の献立作りを行っている。
2−2食の学びプロジェクト
平成17年度より3年計画で「食の学び推進委員会」が発足され、学園長・副学園長・事務長・食事部長・各部の責任者と委員会リーダーからなる推進委員会を基に各部の推進担当教師が活動している。長い間、普段の生活を通し生産・養豚・農芸などの体験を通して多くの食の学びをしてきた。このプロジェクトは今までの食の学びをさらに価値あるものにするため自由学園の環境、生活を生かした「食の循環」に関わる学習を基に一貫教育の中で食材の生産から廃棄までの流れを通して学び、社会に関心を持つとともに一人一人が社会に出てから自分で食する食材を選ぶ力を身につけることを目標とする活動である。
2−2−2具体的な活動
このプロジェクトを推進するために学園創立当時から礼拝と食事時間は大切にされてきた食事時間をよりよい時間とすること、食の学びをよりよいものとするためのカリキュラムの体系化をすることを、全校を中心に各部でおこなってきた。また、今年度から学園で使用する米の1/3を那須で生産された米にすることが具体的に勧められている。
2−2−3食材供給のガイドライン
また、現在、食料部では食材供給のガイドラインに基づき食材を供給している。このガイドラインは学園内の各部の台所・食堂に供給される食事が「作り手の見える食」であり、その食事を食べることによって感謝する心、社会に出てからも健康に過ごせる選食力が身につくよう考えられたものである。この理念を実現させるために食材の美味しさを前提とし、安全性・経済性・利便性・環境性をポイントにおき、これらの理念を理解し、対応してくれる業者の選択に心がけている。食材を選ぶ上で、多くの問題点はあるが全てのことをシャットアウトしてしまうのではなく、上手に選んでいくことが大切である。
5章 米作り(田窪)
5−1
那須の水田(歴史的背景・吉一先生)
5−2
一年間の様子(田植えから収穫まで)
那須の農家では稲の収穫作業を、9月の半ばから10月上旬にかけて行うのが一般的。そのため体操会前の10月3日に、2反ほど収穫作業を行った。収穫の前日まで雨が激しく降っていたが、収穫当日はよく晴れ、日差しが強い中、収穫作業を行うことができた。
収穫の際には「釜を使った手刈り」や「コンバイン操作」といった収穫方法を、学園提携農家の八月朔日さんに教えていただきながら行い、コンバインが回りきらない水田の「曲がり角」は、手刈りで収穫し、その他の部分はコンバインで収穫した。また脱穀したお米を「精米して袋詰にする」過程も見学し学んだ。
5−3
生徒、学生の参加
学園生が米作りの生産過程に携わる、参加する事によって、どのような過程を経てできるかを体験し、お米に対しての価値観を上げることを目的とした。
5月の連休中に八月朔日さんの所有している水田に学生と生徒が田植え作業を一反分、行い7月と8月には除草に行った。
10月3日には「食」グループの学生10人が収穫作業の一部に参加し、また女子部の普通科1年生、男子部の生徒も学部生とは別の日に収穫作業を体験した。
男子部、女子部普通科は自分たちで植えた米を学園に持ち帰り天日干しなどを行った。
自由学園の「食の学びプロジェクト」発足に伴い、学園創立当初からの「食教育」の見直し、活性化が注目されている。自由学園では創立当初から「食べ物」と生徒との密接な関わりを大切にしてきた。しかし、一口に「食教育」といっても、時代の変化と共に「食べ物」と生徒との相互関係も変化してきている。自由学園生と「食」の関係は大きく3つの時代に区分できるのではないだろうか。まず一つ目の時代は創立当初から第二次大戦までの時代。この時代の「食」は良家の子女の花嫁勉強の「教材」としての役割が大きい。2つ目の時代は戦時中である。この時代の「食」との関わりは「教育」の為というよりは、生きる為の手段であった。3つ目の時代は「豊食の時代」とよばれ、「食文化の崩壊」が叫ばれる現代における「健康に生きる」為の学びである。
自由学園の創立者、羽仁もと子は学園創立時、育ち盛りの生徒に温かい昼食を食べさせたいと考えた。家でつくったお弁当では昼食の時間までに冷めてしまう、学園で温かい食事をとる為にはどうすれば良いか。この問題を解決する為、もと子は生徒自らが食事を用意する事を考案した。この方法は生徒に「食べ物」との「関わり方」を学ばせる勉強の場を与えた。当時の生徒の家庭では家政婦を雇っている事が多く、自分の食事を自ら用意するといった経験が無い者ばかりであった。やがて生徒は料理のみに限らず、野菜の栽培や購入、テーブルセット、お客を招いての行事の企画なども手がけるようになった。
一方、戦時中、生徒は生きるか死ぬかの為に「食べ物」が必要であった。生徒は大芝生を耕して畑にし、野菜を栽培して貴重な食糧を得た。当時の生徒にとって「食べ物」イコール貴重な栄養源であった。また、戦後は欧米の食文化の流入に伴い乳製品を積極的に取り入れるようになった。
21世紀を迎えた現代、生徒と「食べ物」の関係は戦時中の生徒とはいうまでもなく、創立当初の生徒とも大きく変化している。大衆の生活水準の向上に伴い、学園に通う生徒の家庭環境も変化した。今では多くの生徒の家庭で食事の買い物や料理、後片付けを家族や自らが行うことが普通である。また、「食べ物」の入手手段も容易になった。たいていどの町にも庶民の日常生活に事欠かないだけの品物を揃えた食料品店が設置されているし、品物の種類も豊富である。単に栄養補給をする為や簡単な加熱で食べることが可能になった機能的な商品も続々と開発されている。また、核家族化や両親の共働きによる家族別々の食事、偏食、過剰なダイエットといった生活タイルの変化も顕著になった。こうして多くの人々は便利で好き勝手、自由な食生活を享受するようになった。しかし、今日、日本では「食教育の重要性」を主張する声が大きくなってきている。これはどうしてであろうか。
実はここ3~40年の間、以前から日本社会で増加傾向にある凶悪犯罪、暴力、いじめ、引きこもり、精神疾患といった「事件や症状」と「食事」との密接な関係が注目されるようになってきたのだ。つまり、従来からの「良い食事」と「健康な身体」の相関関係に「健康な心」が加えて講じられるようになったのである。ある少年鑑別所に勤める警察官は少年院の子供が清涼飲料水やスナック菓子を特に好むことから乱れた食生活と犯罪の関係性を問うている。また、ビタミンB不足による学習障害、疲労、記憶障害、精神混乱、行動障害、興奮、衝動性、不眠、無気力感動、慢性的頭痛などの事例も多数報告されている。
それなら清涼飲料水やスナック菓子を減らしてビタミンBをタブレットや栄養ドリンクから摂取すれば良いではないか、と問われれば、そうではない。「食事」を単なる「栄養補給の手段」ではなく、健康な心でより良い人生を築く為の「生きる力を育てるもの」として考えることが大切である。「食教育」の必要性はそこにあるのだ。具体的には、農作物栽培や流通ルート、加工課程、調理などを学び、体験を通して自然の恵みや生産者、家族への感謝の心を育む事、家族や友人との食事を通して礼儀やマナー・対人関係を学ぶ事、地域の作物や季節の料理を食事に取り入れ郷土料理や日本の食文化を学ぶ事などが挙げられる。こうして人が子供の頃から「食する」事を「生きる基本」と考え、「食」を通して心の豊かさや寛容・謙遜、そして感謝や礼儀を備えた人間を育てることが、現代の「食」と生徒との大切な関わり方であると考えられる。
1章 日本の食事情(ふじお 中山)
ふじおの??
年表(中山)
45.8.15 日本無条件降伏
10.20 地主的土地所有無償ぼしゅう
30 米穀総合供出制実施
11.2 地主的土地所有の有償ぼしゅう
46.5.19 食糧メーデ
11.11 第二次農地改革法
47.6.19 農業復興会議
7.19 救援米供出国民運動
25 全国農民組合結成
11.19 農業共同組合法公布
48.10.23 全国指導農業共同組合連合会設立
49.6.6 土地改良法公布
12.15 漁業法公布
50.9.11 自作農の創設に関する政令公布
11.27 全国共済農業共同組合連合会創立総会
51.1.31 全国共済農業共同組合連合会創立
3.31 農業委員会法
4.7 農漁業共同組合再検整備法公布
7.25 国際小麦協定に加盟
9.8 日米安全保障条約調印
52.7.15 農地法公布
53.1.21 農民組合総同盟結成
8.17 農産物価格安定法
27 農業機械化促進法公布
11.10 冷害地帯緊急農村対策要項決定
12.29 昭和9年以来の大凶作
54.6.14 酪農復興法公布
9.16 日本中央競馬会設立
55.4.15 日中民間漁業協定調印
5.7 米の予約買い付け製採用決定 6.7 GATTに正式加盟
7.8 第一回小作料対策協議会開催
8.15 自作農維持創設資金融通法公布
10.31 中央畜産会設立
12.14 全国開放農地国家補償連合会
56.6.18 農林水産業生産制向上会設立
12.25 熊本水俣湾に奇病発生(水俣病)
57.2.20 日本農地犠牲者連盟結成
8.21農林省初の農林白書
9.10 日本農林組合全国連合会を結成
12.12 日本農地犠牲者連合会結成
12.28 水稲集団栽培始まる
58.3.24 全日本農林組合連合会
10.16 米の代表者供出制度実施決定
59.4.20 農林漁業基本問題調査会設置法公布
5.? 農業改良資金助成法公布
9.26 伊勢湾台風
10.? 米配給制度完全協議会
60.2.1 世界農林業センサス本調査実施
6.30 農地非買収者問題調査会法公布
8.15 全国農民大会結成
10.? 農林水産物121品目自由化実施
61。2.24 中央労農会議結成
3.20 果樹農業復興特別措置法公布
4.1 農協合併助成法成立
6.11 農業基本法公布
7.31 米の予約受け渡し制
11.10 農業近代化資金発足
11.? 開拓営農復興審議会
12.26 第一回農業白書
62.2.? 農業構造改善事業
4.17 アジア農協会議開催
7.30 EEC共通農業政策実施
8.8 中央酪農会議実施
10.1農業機械化研究所設立
63.3.28 全国農民総連盟発足
4.1 バナナ等輸入自由化
5.1 農林省地方農政局発足
6.4 第一回世界食糧会議
7.8 アジア農業復興機関設立
8.1 沿岸漁業復興法公布
9.? 粗目(ざらめ)自由化決定
ササニシキ発表!
64.2.21 経済同友会(農業近代化への提言を発表)
3.31 甘味資源特別処置法公布
4.8 林業基本法公布
10.10 オリンピック東京大会
65.3.6 農村労働組合全国連合会結成
5.11 山村復興法公布
6.1 全国初のカントリーエレベーター完成
2 加工原料乳生産者補給金暫定措置法公布
3 農地非買収者等に対する給付金の支給に関する法律公布
10.21 韓国6万トン輸入を契約
10.31 稲作集団栽培
12.16 農業収容人口990万人初めて一千万人を割る
66.5.17 農薬中毒対策協議会設立
7.1 畜産復興審議所設立
8.18 全国鶏卵価格安定基金設立
11.1 野菜生産出荷安定資金協会発足
12.13 全国農協畜産団地協議会結成総会
67.4.25 稲作生産組織研究会を設置
8.4 農業構造政策の基本方針を発表
9.25 物価安定推進会議 米価について提言発表
12.22 昭和42年産米収穫高1445万一千トン 史上最高の豊作
68.7.13 総合農政の展開について所信表明 西村さん!
11.16 農産物の需要と生産の長期見通し(農林省発表)
政府米異常在庫問題化
69.1.23 稲作転換対策を発表
2.10 新規開田の抑制
5.16 自主流通米発足
7.1 農業復興地域の整備に関する法律
7.19 自主流通協議会発足
70.2.1 世界農林業センサス実施
3.12 米の輸出促進法案掲出
5.15 改正農地法公布
5.20 農業者年金基金法公布
9.21 佐藤首相が『農業の過保護は避ける』と言明
10.20 BHC・DDT・ドリン経済の稲作使用を前面禁止
穀物自給率48パーセントで遂に50パーセントを切る
米の限飯政策始まる
71.2.5 米の予約限度制を導入
3.30 基本法農政10年を総括した45年度(農業白書発表)
4.2 卸売り市場法公布
6.21 農村地域工業導入促進法公布
6.22 近畿穀類問屋共同組合が自由米の仲間取引を発足させると発表
6.29 グレープフルーツなどの20品目を輸入自由化決定
11.30 BHCの販売、使用の全面禁止
72.1,20 標準価格米制度を作る
3.31 全国農業共同組合連合会(全農)設立
7.1 消費者米価の物価統制令適用廃止
6.1 農協牛乳の販売を始める
8.2 牛乳南北戦争始まる
12.19 米平均収穫量456キロ(10アールあたり)
異常気象による世界穀物危機
73.4.25 市街化区域内農地の宅地並み課税法案成立
12.7 シカゴ小麦相場暴騰
74.5.10 田中首相に日本農業の構想を手渡す
27 国土利用計画法 生産緑地法政策 10.1 中央漁業信用基金
11.6世界食糧会議 ローマで開催
75.2.1 配合飼料価格安定特別基金設立
中間農業センサス実施
5.21 国民食糧会議開催
9.9 食糧自給力の向上などの報告を首相に提出
12.19 10アール当たり収量481キロ至上最高
11.15ランブイエサミット
76.4.9 国営福島潟干拓地で200人あまりの農民が水田構起強行
5.26 FAO水産用食国際会議開催
9.27 日本経済調査協議会総合食糧政策の樹立に関する提言
10.1 野菜供給安定基金が発足
12.29 全熱量にしめる穀物のカロリー初めて50パーセント割る
77.4.18 マツクイムシ防除特別処置法公布
4.? 魚価急騰
5.3 水域暫定諸地方公布
8.11 アメリカ産さくらんぼ輸入自由化決定
8.28 薩摩灘に赤潮異常発生!!
10.21 農地改革30周年記念式典
78.7.5 農林省、農林水産省となる
19 農業依存度29.4 初めて30パー割る
8.16 干ばつ
11.20 政策推進労働組合会議農水省に牛肉の自由化、果物の季節自由化を申し出る
79.2.20 全国果実生産出荷安定協議会
3.28 中央酪農会議 牛乳の自主的調整決める
11.2 第一回日米農産物定期協議開催
12.20 農地制度研究会(第三次発足)
80.4.8 衆議院(食糧自給力強化に関する決議)を全会一致で採択
23日参院も同様の決議
8.29 日本経済調査会提言(食糧管理制度の抜本的改正)
10.31 80年代農政の基本法(農産物の生産と見通し)
11.21 農住組合法公布
81.2.2 中央協同組合 ミルクボード構想発表
4.3 日本協同組合学会創立
5.11経団連農政部会設置を決定
6.11 食糧管理法改正公布(米穀通帳廃止!!贈答米は自由化でなし崩しと間接統制がはじまる)
6.29 転作激励金減額と自主米激励金禁止など提言
4.28 食糧備蓄強化を提言
82.4.22 農産物輸入自由化反対を決議
83.1.24農産物市場開放を5年計画で行うなど提言
3.17 日本型食生活の推進
6.13 協同組合間提携
6.22 経済同友会市場メカニズム活用 保護農政は交代させるべき、と提言を発表
84.3.19 北海道農民連盟(農業不要論を唱える3企業ダイエー・味の素・ソニー)製品および販売品の不快運動展開
5.28 韓国産米の緊急輸入
6.20 米輸入の日韓協議合意
10アールあたり517キロ至上最高
85.6.26 食糧安全経団連食糧安全保障について発表
86.1.29 果樹農業復興基本方針を発表
9.10 日本の米輸入制限撤廃をアメリカ通商代表部に逓送
87.6.2 長粒種の水稲新品種『ホシユタカ』発表
11.12 全国消費者大会米輸入自由化反対を特別決議
12.2 日本および欧米の農業団体は食料自給率向上で共同声明発表
88.2.2 10品目の輸入制限をGAT違反として自由化を勧告
21 総理府世論調査国民の7割が食糧安全保障を支持
3.16 米自由化影響を試算国内生産が現在の2割にまで激減する、と予測
8.2 農産物12品目問題の自由化合意を正式決定 輸入製品品目は13に。
2.16 肉用牛子牛生産安定特別処置法成立
89.4.1 プロセスチーズ輸入自由化
5.2 東京神田市場が閉市
5.6 中央卸売り市場 大田市場で初競り
11.13 GAT農業交渉に関する国際シンポジウムが東京で開催
11.27 自主流通米の第一回入札が始まる
90.3.20 転用規制緩和
4.? 肉牛子牛生産者補給金制度補足
6.15 市民農園整備促進法公布
6.22 21世紀村作り塾スタート
7.9 学者グループが米自給を求め声明発表
8.30 自主流通米価格形成機構発足
11.13 農産物貿易の自由化に反対 GAT本部にデモ
12.12 酪農ヘルパー全国協会設立
91.1.23 全中新しい農協マーカーにJA決定
4.1 牛肉の輸入自由化
8.22 第21回国際農業経済学会が東京で開幕
12.9 農薬残留基準案を決定
92.2.13 全国村作りサミット開催
3.5 農業保護宅減の国別表をGATに提出
5.13 市町村農地保有合理化法人が自由化
8.6 全国農協合併推進支援基金が発足
9.29 有機農産物の表示ガイドラインをまとめる
93.4.14 水田活用協議会を設置
5.16 日本湖孫飢饉
8.27 冷夏で40年ぶりの米不作を発表。
9.25 米の不作により緊急輸入を決定
11.11 米の緊急輸入90万トンを発表
12.27 食糧庁外国産米80万トンの追加輸入発表
94.1.8 リフレシュビレッチ研究会を発足
3.7 食糧庁国産米の単品販売禁止
3.29 追加輸入米75万トンを決定。輸入総量は265万トン
7.14 輸入米の値引き販売
8.24 輸入量254万4千トンで米輸入終わる
10.25 UR農業合理化対策大綱
95.3.17 農協合併 助成法が改正
3.22 世界初のもち性コムギ
4.26 森林性備法促進
9.22 農業基本法に関する研究会を設置
10.16 ケベック宣言
10.27 輸入豚肉に政府ガード
11,1 主要食糧の自給および価格の安定に関する法律
96.2.27 狂牛病の進入防止のため、イギリス本土と北アイルランドからの牛肉製品の輸入を全面禁止
4.4. 1996年農業法が成立
7.1 精米の産地品種産年の表示義務化がスタート
輸入豚肉、政府ガード発動
5 JA全中2000年に30万人体制とするJA改革指針を決定
9.20 野菜5品目について原産地表示が義務化
2章 多種多様化する流通及びマーケティング (田中 栗原)
(流通とは)
流通とは生産者から消費者に至るまでの商品やサービスの流れを指す。そのため自給自足の時代、また物々交換の時代に流通は不要だった。
しかし貨幣経済の時代に入り、社会的分業が急速に進展する。なぜなら各地域が得意な分野に特化し手分けして仕事をするほうが、より効率的な経済社会と豊かな生活を生むからである。そうなってくると、生産地と消費地が分断され、両者をつなぐ流通機能が不可欠になってきた。つまり生産者と消費の間にある人的、地理的、時間的隔たりを埋め、生産者から消費者にスムーズに商品が流れる一連の機能を担うのが流通である。
そういった意味がある流通は現代のインフラと言える。
(流通業の仕事内容)
一般的に流通業とは以下の3つにまとめることができる。
?取引や売買を担う「卸売業」と「小売業」
?商品の輸送を担う「輸送業」
?商品の保管を担う「倉庫業」
(流通経路の種類と仕組み)
商品はどのように流れるのだろうか。生産された商品が消費者の手元に届くまでのルートを「流通経路」または「流通チャンネル」という。流通経路は商品の種類、規模によって多種多様だが、大きく分けると四つのパターンに分類できる
※この4つの具体例を出す→現在調査中
※学園の流通を上の図にあてはめる。(野菜、肉など)→新学期に食糧部の方に伺う
(米の流通の仕組み)
※計画外流通米などの政治政策は農政で説明と仮定
(自由学園の米の流通システム)
2006年10月まで
農家(生産者)→JA(流通業者)→町田米店(流通業者)→自由学園(消費者)
※学園で購入していた米がJAを通っていたか不明瞭なため、後日町田さんにインタビューする。
2006年10月から
契約農家(生産者)→町田米店(流通業者)→自由学園(消費者)
(農家八月朔日氏と売買契約)
自由学園の所有する水田は那須農場近隣に在住している農家の八月朔日氏が管理している。2005年度自由学園は八月朔日氏に自由学園の水田のお米を自由学園が買い取ることを提案。これに八月朔日氏が同意し両者の思惑は合致する。そして2006年の秋に実施された。
両者のメリットとして自由学園は、創立者が購入した由緒ある水田を有効活用できること、生産者の顔が見えるお米をいただく安全性と安心感、生徒の田植え体験など教育的側面が挙げられる。八月朔日氏としては、毎年確実に大量の米を固定価格で販売することから、経営の安定化とJAなどの中間業者を通さなくなることからマージンのコストを削減できる面が挙げられる。
(町田米店の助け)
自由学園の水田では約6トンの米が収穫され、それを自由学園が購入する契約の件とは別に問題が2つあった。一つ目は輸送システム。6トンの米を栃木県から学園まで運搬しなければならない。輸送を何度かに分けて遠隔地の栃木県からの輸送にかかる費用が馬鹿にならない。二つ目は米を保管する倉庫の問題。自由学園には6トンのお米を保管する倉庫がない。倉庫も米の品質保持ができる湿度、温度の調節であることが必須となる。また玄米が輸送されるため精米機の調達もしなければならない。
以上の問題点に遭遇した自由学園はこのことを町田米店と相談する。相談した結果町田米店が栃木県から学園までの運搬、6トン米の保管を請け負うことなる。また精米も町田米店が担うことから、すべての問題は町田米店に委託することで解決した。マージンが少しかかるが、倉庫建造や運搬のコストを考えると妥当な方法である。
自由学園の米の流通の中での町田米店の助けにあったように、現代社会に流通業はなくてはならいものだと理解できる。
2−2−1多種多様化する流通形態
生産者、販売者側から青果物マーケティングを考える
生産者と消費者の考え方の変化から流通形態も変化している。現在、青果物全流通の約7割が卸売市場を通って取引されている。生産者の視点から見ると、市場は価格の変動が激しい事に加え、規格による細かい選定や卸の数量による経費がかかる事、ブランド重視で大量に出荷できる農家に有利な点が多く、小規模農家には不利な流通体制であった。輸入野菜の流通への参入は価格競争を呼び、この傾向を一層強めてしまった。しかし、大手スーパーや生活協同組合による生産者との相対取引やインターネットの普及により無店舗販売が可能になった事で、卸売市場の経由率も徐々に下がっているのも現状である。過去に比べ生産者から消費者に届くまでの流通形態が多種多様化してきている。再び生産者から消費者までの距離が短まってきている現在、生産者、販売者はこれまで以上に消費者を意識し、消費者の要望に応えていかなければならい。
2−2−2現在行われている青果物のマーケティング方法
多種多様化する現在、消費者に青果物を買ってもらうために、生産者や販売者は、ただ青果物を単なる商品として売るのではなく、消費者が青果物を買いやすい様に工夫する事やブランド商品を「安心」「健康」などの付加価値を付けていかなければいけない。現在行われているマーケティング方法を例に挙げ、消費者にどの様にアプローチしているのかを考察する。
<生産者・販売者の取り組み>
・地産地消
地域の中で生産者の顔、生産地の実態を知ることが出来、新鮮で安全性の高い青果物を消費者に届けることが出来る。地域農業の特性を生かすことが出来る。
・産地直送
信頼できる生産者から青果物を買う。情報技術の進む中で、手軽に注文、受注が可能であり、利便性に問題もない。地方の青果物を新鮮に届けることが出来る。
・契約栽培
(※説明文考え中)
・有機栽培
農薬を使わない有機農業の方法で生産すること。「安全性」を支持する消費者、また現在は「ロハス」などの流れで人々の関心を集めている。
販売者側(量販店、生活共同組合の取り組み、工夫)
・大手スーパーの工夫、取り組み
・生活協同組合
・小売店(八百屋、米店)の工夫、取り組み
月泉 博,『よくわかる流通業界』,日本実業出版社,2004年11月
内村 系,『流通のしくみがわかる本』,ダイヤモンド社,1997年9月
石井寛治,『日本流通史』, 有斐閣,2003年1
3章 『食』の選び方(雨谷 山口 小野)
なぜ食選力が必要なのか(雨谷)
「食」は健康を維持するために必要不可欠なもの、ライフスタイルの多様化に伴い日本人の食事の偏りや乱れが目立つ。また、日本全国、添加物などの身体に悪いものを含む食物があふれている。健康な食生活を送るために、「どんなものを食べたら安全か危険かを知り、必要な食物をバランスよく選ぶ目」すなわち「食選力」を養うことが重要。
根底にあるのは食育
食選力を考える上で、食育という言葉は無くてはならない。むしろ食育の中に食選力があると考えるのが望ましいのかもしれない。
食育とは、国民一人一人が、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるように、自らの食について考える習慣や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付けるための学習等の取組みを指す。
日本の食
日本の食生活は、伝統的に主食であるご飯を中心に、魚や野菜、大豆から作る豆腐や納豆などの副食の中心とするものであった。
戦後、経済成長や社会の変化を背景に畜産物や油脂などの摂取が増加し、昭和50年ごろには、カロリー摂取量がほぼ満足すべき基準に達し、たんぱく質、脂肪、炭水化物のエネルギー比率のバランスがとれているなど、いわゆる「日本型食生活」ともいうべき理想的な食生活を達成していた。
しかし、その後も脂質の消費が引き続き増加したことに加え、米の消費が減少したことにより、脂質のとりすぎと炭水化物の摂取量の減少が顕著になり、不規則な食事の形態に代表されるような食生活の乱れが生じてきた。
このような偏った食生活もあり、肥満や糖尿病等が若い世代の人たちに及ぶようになり、心臓病、脳卒中、がんといった従来の「成人病」を「生活習慣病」と言い替えるようになる事態となった。健康のまま寿命を延ばすためにも、また、今後ますます増大すると見込まれる医療費を抑制することにもつながるため、食生活の改善が重要となっている。
2005年6月に食育に関する法律、「食育基本法」が制定された。
フードチェーンの多様化・複雑化や家庭等における食の教育力の低下など環境変化の中で、国民個々の自主的な努力に委ねるだけでは健全な食生活の実現が望めない状況
このような現状を踏まえ、食育に取り組む厚生労働省・文部科学省・農林水産省の3省では、食育の推進母体である「食を考える国民会議」とともに2000年3月に策定された「食生活指針」を推進している。
基本のガイドラインとして、食生活に関する健康・栄養・環境・農(漁)業・文化などの情報をもって、未来をになう子どもたちを対象に生きる力を育むため、食育を、国をあげて取り組むようになっている。従来、教育の世界では「知育・徳育・体育」が基本とされていたが、今後、「食育」の重要性は法律にもされたことからも、その重要性は増していく。
参考文献
昭和堂 新山陽子 編 食品トレーサビリティ
白桃書房 梅沢昌太郎 編著 トレーサビリティ
青春出版 武田邦彦 著 何を食べれば安全か!
ビジネス社 外食産業総合調査研究センター・編 日本の食文化と外食産業
農林統計協会 農政ジャーナリストの会 編 「食育」その可能性と必要性
農林統計協会 農政ジャーナリストの会 編 食の安全性を問う−農薬は今−
ダイヤモンド社 大来佐武郎 著 成長の限界
(山口)
昨年度の研究
昨年度の共同研究では、「自分たちの食を正しく選ぶ」というテーマのもと、「自由学園における食の概念的ガイドライン」を研究目的として進められた。研究手法として、じゃがいも、鶏肉、米の背景調査を行った。その上で、食を選ぶ要素として「安全性」「経済性」「環境性」「利便性」の4つを挙げ、食の概念的ガイドラインとしてまとめている。
1. 安全性
絶対に安全なものはないが、安心感が重要である。安心感をつくるためには信頼できる業者との長い付き合いが必要で、そこでの関わりを私たちが知ることで更に信頼が深まる。また、安全に食べることができる知識を増やすことも必要である。
2. 経済性
品質相応の価格であること。
3. 環境性
過剰包装をしない。空容器回収を行う。運搬距離が短い。
4. 利便性
生活スタイルに対応できる。
昨年度の研究から、自由学園での最も重要な食の選択要素は安全性であるという結論が出された。団体であるということで、健康維持も含め、安全性を守る必要がある。そこで、選ぶ要素として挙げられた4つの中から安全性を特に重点的に研究行った。食品の安全を消費者に伝えるために食品表示、原材料表示、また国の規定などが設けられている。しかし、先に述べたとおり、「安全なものはない」中、消費者の求める安全性とは科学的安全、精神的安全ではないかという意見であった。この精神的な安全性は、安全性とは異なる安心感近代と位置づけることができる。また近年、インターネットなどを通して比較的簡単に食品の情報を得ることが出来る。しかし一方で情報過多の時代にそれらの情報を的確に判断することは難しいものである。
前章までに述べたとおり、時代の変化に伴い、食を取り巻く環境も大きく変化してきた。私たちはそれらの変化を踏まえ、食を選ぶことが必要になっていく。
食の選択基準(小野)
「食べること」において人が幸福感を得るには、「美味しさ」を感じるか否かが本来重要であった。つまり、「味」の好みを基準にして食べるものを選んでいた。社会は消費者のニーズに合わせ物を生産し、販売する。当然、味だけでは満足感は瞬間的なものであり、栄養が偏ることで「食べること」の働きとしては不十分であり、不満足である、ということになる。人々は味に加え、どのような要素を「食べること」に求めているのだろうか。
・「美味しさ」≠「安さ」「利便性」
現在、人々は「美味しさ」に加え、新たな選択の価値基準を置くようになった。「価格」、そして「安全性」である。食材に限らず、食べ方に関しても「選び方」を考えるのであれば、「利便性」も重要な要素となるだろう。
嶋野道弘氏は『生きる力を育む、食と農の教育』(家の光教会、2006.1.1)の中で「食と農の乖離」の恐ろしさについて述べている。日本社会の急速な経済成長がそれをもたらしたことを指摘している。前に述べた「利便性」は大量消費社会となった中で日本人が安さと量と同時に求めたものである。「食」の選択基準において「利便性」が用いられるということは「食と農の乖離」した社会のうちで、「食と農」が経済活動の1部に巻き込まれ、自然のうちで行われる人間の基本的活動が、金銭で動かされる中に組み込まれた、ということである。
3−3.農産物輸入自由化
1980年代、日本は農産物輸入自由化を図った。米国からは麦を始めとする農産物が多量に入ってくるようになった。工業製品との輸出入の引き合いによって、進められた農産物貿易自由化は日本国内の自給率に大きな影響を与えることになった。
国外の農産物は日本産の農産物に比べはるかに安い値で販売されている。米には未だ関税がかかっているが、他のものはかけられていないので、日本の消費者にとっても買い物する時に「安さ」か「国産」か、とスーパーや八百屋でさえ、迷う消費者を見かけるようになった。
消費者は先に述べたように「安さ」に躍らせながら大量消費社会を築いていたが、現在はBSEや安全性を問う問題は浮上し、「安さ」「安全性」の駆け引きを自分の価値基準を決め行うようになった。
岩村暢子氏は『変わる家族 変わる食卓』の中で消費者について「自己愛型情報収集」という言葉を用いて批判している。
「自己愛型情報収集」=その時々、自分に都合のいい使える情報だけを集め、当てはめていくこと。(岩村暢子)
「安全性」が問われるようになった社会ではあるが、「安全性」を問う情報が簡単にしかも必要以上に入手可能な社会で人々はどのような情報を頼りにするのか、それは消費者自身による判断で異なってしまう。
食生活の概念として『変わりゆく食環境と食の安全性』(ぎょうせい、2001.5.20)では4つの条件をあげている。
? 地理的条件
? 社会的条件
? 経済的条件
? 文化的条件
これらの4つの条件、特に?と?は時代とともに大きく変化するものである。その中で?ち?で築かれた食生活の文化、意識が人々の「食」への関心度に差をもたらすことにもなるだろう。
3−4.選ぶ人々
「選ぶ」のは消費者だけではない。2章であげた仲卸や卸、販売業、そして生産者の立場でも「選ぶ」、そして「選ばれる」ことは重要なキーポイントとなっているのだ。東京都東久留米市で梨園を営まれている奥住実さんは「生産者は消費者のつもりで必要とされているものを考えて生産する。生産者としてプロでも、消費者としてプロの自覚が無いといけない。」と生産と消費の2つは同じ価値観を持って実行されなくてはいけないことを話された。つまり、食を選ぶのは消費者ではあるが、それを選ばされるのは生産者、仲卸、販売者の役目である。
私達は自由学園食糧部を例にあげ、一消費者として置く選択基準を導き出すことを試みた。
3−5.自由学園食糧部の取り組み(※確認後執筆)
・ ガイドラインのこと
・ 地域の農産物を出してくれるように仲卸に頼んでいること
参考資料・文献:
有吉佐和子『複合汚染 その後』潮出版社,1977
岩村暢子『変わる家族 変わる食卓』勁草書房
大塚滋『食の文化史』中央公論社,1975
『日本の食事様式』中央公論社,1980
大野和興『日本の農業を考える』岩波ジュニア新書,2004
クローズアップシリーズ『変わりゆく食環境と食の安全性』ぎょうせい,2001
嶋野道弘『生きる力を育む』家の光教会,2006
食料白書編集委員会「食料白書 2006年版 「地産地消」の現状と展望」,農山漁村文化協会,2006
岸田芳朗『地方から地産地消宣言』吉備人出版,2006現代農業11月増刊号『スローフードな日本! ‐地産地消・食の地元学‐』農山漁村文化協会,2002
藤田和芳『農業の出番だ!』ダイヤモンド社,1995
FAO世界農業予測2015-2030年「世界の農業と食糧確保」国際連合食料農業機関,2003
神門善久『日本の食と農 危機の本質』NTT出版,2006
竹下登志成『学校給食が子どもと地域を育てる』2000
山路健『飽食と粗食』1980
4章 自由学園の食教育(木下 広橋)
社会における食教育(広橋)
現在日本人の食離れが問題になっている。その中でも朝食を欠食する、栄養バランスがとれた食事をとらない、肥満傾向などの食生活の乱れている子供が増えている。子供たちが正しい食習慣と知識を身につけることができるようになるために地域や社会を挙げて食育に取り組み、推進していくことが必要とされている。平成17年7月には食育基本法が施行された。この基本法を基に食いく推進会議が設置され、平成18年3月31日に食育推進基本計画が決定した。学校において食育を推進するうえで地産地消の推進や給食の充実、子供たちの体験活動の推進があげられている。
1−1 創立者の食教育への理念(木下)
1921年、生徒の学校での昼食は各家庭から持参した弁当を食するのが当然であった創立当時、ミセス羽仁は
「頭もからだも激しく使う学校生活において育ち盛りの子供たちが小学校から女学校、或はその上の学校と10年以上も、お弁当では栄養上十分に懸念させられる」
と考え、栄養の配慮された食事を生徒が交代で炊事し、食卓を整えることで「家族」としての交流をする機会を作るのと同時に、炊事を通した実際生活を学ぶ教育を始められた。食事の一つ一つに心を配り、おいしく、栄養もあり、経済的に無駄のない昼食を作ることが即ち立派な料理の勉強になるのだと教えられ、身の回りのことは女中や雇い人にさせるのが普通であった生徒たちは、生活の中の生きた勉強になると喜んで食事に集まってきていた。
1−2 生徒の役割
創立当時、30人であった生徒は6人ずつの家族に分けられ、交代で平日の昼食の炊事を行った。料理の当番ではない他の家族は同じ時間に花畑の手入れや、鶏の飼育、また衣類や寝具などの新調や洗濯をする仕事を稽古し、生活を学ぶ時間としていた。炊事の当番は、市場へ買い付けに行く材料の仕入れや管理から、調理、配膳まで任された。
1−3 時代の移り変わり
創立から1年後、それまで料理は創立者宅の台所で行っていたが、当時一般では考えられないほど水準の高い設備が整った台所と食堂が完成し、それと同時に香欄社製の高価な食器が導入されるようになった。
12年後の1934年、学校のキャンパスが目白から南沢へと移され、台所には粉炭のオーブンや薪石炭の釜が導入され、数年(6)後にはパン焼き釜が導入されるなど、台所設備が豊富になる。
1941年に英米からの宣戦布告を受け配給制度が厳しくなったために、現在の食糧部の前身である食事中央事務局が誕生する。戦争中から戦後の食糧難時代では大芝生の前面開墾など、構内の至る所を畑に変えることで65%の自給がなされる程になった。これにより、手作りである学校での昼食と寮での朝食、夕食を続けることが可能であった。これを可能にしたのも、早期の産業教育の採用の成果だと言える。
終戦から7年後の1952年、卒業生が運営していた食事中央事務局が女子部高等科三年で運営されるようになり、経済教室が完成する。その2年後にはパン工場が設立され、市販のものから工場産のパンが食べられるようになった。
1997年、勉強など他に行わなければならないことが増え、寮生の中で体調を壊す者が多く、今の制度では生徒の負担が大きいと考え、教師会が中心となり清風寮の食事作りを週に3日、お手伝いの方に依頼するようになる。これには自治の生活に誇りのある生徒や卒業生から多くの反対意見もあった。
(自由学園の歴史1 自由学園女学校)
(自由学園の教育 羽仁恵子 実生活の指導)
(今世紀の食生活から私たちの食を考える 女子学部1996生活研究)
2−1現在の状況(広橋)
男子部は平成10年から週に1度男子部高等科2年が昼食作りを行い、昭和13年から始められた産業の授業は現在も続いている。女子部は平成11年まで高等科3年生が食料部の運営に携わり、注文や分配を行っていたが学部の新体制とともに食料部の体制も変わり、食料部の運営は教師が行うことになった。学部では現在2年課程の特別実習の食グループが献立作りや梅干作り、ジャム作りを行い、2年課程の1年生から食材の分配を行う係りをだしている。また、平成17年度からは学部1年生全員が交代で学部の昼食の献立作りを行っている。
2−2食の学びプロジェクト
平成17年度より3年計画で「食の学び推進委員会」が発足され、学園長・副学園長・事務長・食事部長・各部の責任者と委員会リーダーからなる推進委員会を基に各部の推進担当教師が活動している。長い間、普段の生活を通し生産・養豚・農芸などの体験を通して多くの食の学びをしてきた。このプロジェクトは今までの食の学びをさらに価値あるものにするため自由学園の環境、生活を生かした「食の循環」に関わる学習を基に一貫教育の中で食材の生産から廃棄までの流れを通して学び、社会に関心を持つとともに一人一人が社会に出てから自分で食する食材を選ぶ力を身につけることを目標とする活動である。
2−2−2具体的な活動
このプロジェクトを推進するために学園創立当時から礼拝と食事時間は大切にされてきた食事時間をよりよい時間とすること、食の学びをよりよいものとするためのカリキュラムの体系化をすることを、全校を中心に各部でおこなってきた。また、今年度から学園で使用する米の1/3を那須で生産された米にすることが具体的に勧められている。
2−2−3食材供給のガイドライン
また、現在、食料部では食材供給のガイドラインに基づき食材を供給している。このガイドラインは学園内の各部の台所・食堂に供給される食事が「作り手の見える食」であり、その食事を食べることによって感謝する心、社会に出てからも健康に過ごせる選食力が身につくよう考えられたものである。この理念を実現させるために食材の美味しさを前提とし、安全性・経済性・利便性・環境性をポイントにおき、これらの理念を理解し、対応してくれる業者の選択に心がけている。食材を選ぶ上で、多くの問題点はあるが全てのことをシャットアウトしてしまうのではなく、上手に選んでいくことが大切である。
5章 米作り(田窪)
5−1
那須の水田(歴史的背景・吉一先生)
5−2
一年間の様子(田植えから収穫まで)
那須の農家では稲の収穫作業を、9月の半ばから10月上旬にかけて行うのが一般的。そのため体操会前の10月3日に、2反ほど収穫作業を行った。収穫の前日まで雨が激しく降っていたが、収穫当日はよく晴れ、日差しが強い中、収穫作業を行うことができた。
収穫の際には「釜を使った手刈り」や「コンバイン操作」といった収穫方法を、学園提携農家の八月朔日さんに教えていただきながら行い、コンバインが回りきらない水田の「曲がり角」は、手刈りで収穫し、その他の部分はコンバインで収穫した。また脱穀したお米を「精米して袋詰にする」過程も見学し学んだ。
5−3
生徒、学生の参加
学園生が米作りの生産過程に携わる、参加する事によって、どのような過程を経てできるかを体験し、お米に対しての価値観を上げることを目的とした。
5月の連休中に八月朔日さんの所有している水田に学生と生徒が田植え作業を一反分、行い7月と8月には除草に行った。
10月3日には「食」グループの学生10人が収穫作業の一部に参加し、また女子部の普通科1年生、男子部の生徒も学部生とは別の日に収穫作業を体験した。
男子部、女子部普通科は自分たちで植えた米を学園に持ち帰り天日干しなどを行った。
|
|
|
|
|
|
|
|
食06’s 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
食06’sのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90014人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37150人