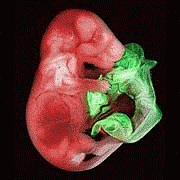JST:中国の科学技術文献の検索サービスを開始
http://
科学技術振興機構(JST)は、中国で発表された科学技術関連の文献の検索サービスを始めた。日本語を使ってウェブサイト上で文献の抄録を検索できる。著作権等の処理が済んでいる文献については、有料で全文のコピーを入手することも可能。3月31日までは試行期間で平日9時−17時のサービスだが、4月2日からは24時間の利用が可能になる。
同機構は◆複数の政府系研究機関や大学などが重要資料に選定した文献、◆世界的に利用度の高い文献引用情報データベース(ISI)に収録された資料、◆中国国家自然科学基金委員会(NSFC)が財政的支援を行っている資料などの基準で約740誌を選定。08年3月までには10万件以上の日本語抄録データを作成し、閲覧可能にすることを目標にしている。
専門誌の最新号については、発行後1.5−2カ月以内に抄録データを閲覧可能にすることを目処とする。
日本語の抄録を検索するので漢字も日本語字体を使う。また「石炭」というキーワードで検索する場合、中国語の「煤」でなく日本語の「石炭」で検索することになる。
検索サービスを担当している同機構中国総合研究センターは、検索サービス開始の理由に「科学技術情報などを知りたいという企業や、共同研究者の情報を求める研究者など、中国の成長にともないニーズが急増している」ことを挙げた。逆に中国語版サイトには日本関連の情報を掲載しており、「科学技術分野などで日中の懸け橋となることを目指したい」と話している。(編集担当:如月隼人)
・科学技術振興機構 中国総合研究センター(日本語版)
http://
http://
科学技術振興機構(JST)は、中国で発表された科学技術関連の文献の検索サービスを始めた。日本語を使ってウェブサイト上で文献の抄録を検索できる。著作権等の処理が済んでいる文献については、有料で全文のコピーを入手することも可能。3月31日までは試行期間で平日9時−17時のサービスだが、4月2日からは24時間の利用が可能になる。
同機構は◆複数の政府系研究機関や大学などが重要資料に選定した文献、◆世界的に利用度の高い文献引用情報データベース(ISI)に収録された資料、◆中国国家自然科学基金委員会(NSFC)が財政的支援を行っている資料などの基準で約740誌を選定。08年3月までには10万件以上の日本語抄録データを作成し、閲覧可能にすることを目標にしている。
専門誌の最新号については、発行後1.5−2カ月以内に抄録データを閲覧可能にすることを目処とする。
日本語の抄録を検索するので漢字も日本語字体を使う。また「石炭」というキーワードで検索する場合、中国語の「煤」でなく日本語の「石炭」で検索することになる。
検索サービスを担当している同機構中国総合研究センターは、検索サービス開始の理由に「科学技術情報などを知りたいという企業や、共同研究者の情報を求める研究者など、中国の成長にともないニーズが急増している」ことを挙げた。逆に中国語版サイトには日本関連の情報を掲載しており、「科学技術分野などで日中の懸け橋となることを目指したい」と話している。(編集担当:如月隼人)
・科学技術振興機構 中国総合研究センター(日本語版)
http://
|
|
|
|
コメント(8)
生命科学の情報を網羅…統合データベース作成
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20071107ur01.htm
遺伝情報の解読が急速に進んだ生命科学の分野では、遺伝子やたんぱく質の構造、機能をまとめたデータベースが研究機関ごとに乱立している。
これらをすべて、検索可能にして、関連した学術論文の情報も一緒に調べられる統合データベース作りが、今年度から始まった。
大学共同利用機関法人「情報・システム研究機構」のライフサイエンス統合データベースセンターが、文部科学省の委託で、4年計画で作業を進めている。
既存のデータベースをすべて網羅する基盤システムを目指す。これまでバラバラだった専門用語についても、英語や日本語表記を包括する辞書機能を持たせて、日本語や英語を使って簡単に生命科学の情報を取り出せるようにする。現在、データベースの洗い出しを進めている。
遺伝情報の配列や、たんぱく質の構造、機能などを集めた生命科学のデータベースは、主要なものだけでも世界に約1万、国内には大学や研究機関を合わせて200〜250、理化学研究所だけでも80もある。
研究者は調べものがある場合、いくつものデータベースを検索する必要があった。それぞれの機関が独自に構築したため、内容に重複も少なくない。せっかく作っても、知名度が低く、ほとんど利用されていないデータベースもあった。
しかも、データベースや、関連する学術論文は、英語表記がほとんどだ。
研究者でも、自分の専門分野以外を英語で検索するのは、用語に不慣れなこともあって難しい。まして、一般の人たちが、少し関心を持ったテーマを手軽に検索することは不可能に近かった。
日本語で簡単に検索して読める素材が増えれば、作業効率が上がるだけでなく、健康や生命に関心のある一般の人たちも、自分たちで最先端の知見を調べることができるようになる。そのため、検索可能な日本語の論文や解説文も充実させていく方針だ。
論文に関しては掲載された学術誌との著作権の問題も残っているが、「税金を使って行われた研究の成果が、社会に還元されるべきだ」として、出版後一定期間が経過したものは無料公開するように、各学術誌と個別に交渉を進めている。
センター長の高木利久・東京大教授は「使いやすいデータベースを作ることは、分野の垣根を下げて風通しを良くし、より多角的な視点からの学際研究も可能にする。生命科学研究全体の底上げにつながるほか、一般の人が最先端の科学に触れることが可能になる」と期待している。(山田聡)
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20071107ur01.htm
遺伝情報の解読が急速に進んだ生命科学の分野では、遺伝子やたんぱく質の構造、機能をまとめたデータベースが研究機関ごとに乱立している。
これらをすべて、検索可能にして、関連した学術論文の情報も一緒に調べられる統合データベース作りが、今年度から始まった。
大学共同利用機関法人「情報・システム研究機構」のライフサイエンス統合データベースセンターが、文部科学省の委託で、4年計画で作業を進めている。
既存のデータベースをすべて網羅する基盤システムを目指す。これまでバラバラだった専門用語についても、英語や日本語表記を包括する辞書機能を持たせて、日本語や英語を使って簡単に生命科学の情報を取り出せるようにする。現在、データベースの洗い出しを進めている。
遺伝情報の配列や、たんぱく質の構造、機能などを集めた生命科学のデータベースは、主要なものだけでも世界に約1万、国内には大学や研究機関を合わせて200〜250、理化学研究所だけでも80もある。
研究者は調べものがある場合、いくつものデータベースを検索する必要があった。それぞれの機関が独自に構築したため、内容に重複も少なくない。せっかく作っても、知名度が低く、ほとんど利用されていないデータベースもあった。
しかも、データベースや、関連する学術論文は、英語表記がほとんどだ。
研究者でも、自分の専門分野以外を英語で検索するのは、用語に不慣れなこともあって難しい。まして、一般の人たちが、少し関心を持ったテーマを手軽に検索することは不可能に近かった。
日本語で簡単に検索して読める素材が増えれば、作業効率が上がるだけでなく、健康や生命に関心のある一般の人たちも、自分たちで最先端の知見を調べることができるようになる。そのため、検索可能な日本語の論文や解説文も充実させていく方針だ。
論文に関しては掲載された学術誌との著作権の問題も残っているが、「税金を使って行われた研究の成果が、社会に還元されるべきだ」として、出版後一定期間が経過したものは無料公開するように、各学術誌と個別に交渉を進めている。
センター長の高木利久・東京大教授は「使いやすいデータベースを作ることは、分野の垣根を下げて風通しを良くし、より多角的な視点からの学際研究も可能にする。生命科学研究全体の底上げにつながるほか、一般の人が最先端の科学に触れることが可能になる」と期待している。(山田聡)
未発表の学術論文を投稿・共有する「My Open Archive」、正式サービス開始
http://japan.internet.com/linuxtoday/20080516/5.html
学術論文のオープンアクセス推進団体であるオープン・アーカイブ・コンソーシアムは2008年5月16日、未発表の学術論文の投稿/共有サイト「My Open Archive」(β版)のサービスを開始する、と発表した。
同サイトは昨年9月、招待制によりプライベートテストを開始しているが、今回デザインを全面的に刷新、β版として正式リリースするもの。サービスはすべて無償。
主な機能は、クリエイティブコモンズライセンスによる論文の著作権管理、Microsoft Office や Adobe Acrobat で作成された投稿論文のフラッシュ形式変換(ブラウザで閲覧できるようにするため)、タグ付け、タグ検索、検索結果への関連タグ表示など。
現在、学術論文のオープンアクセス化は浸透しつつあり、Web で閲覧できる論文は増加中だが、査読・評価や著作権などの、従来の業界枠組みは変わらず、Web の仕組みにうまく適合していないことから、気軽に論文を公開できる現状にはない。
My Open Archive では、トップクラスの研究者のみならず、大学・大学院の学生や研究者も利用できるよう、セルフアーカイビング機能を搭載した。
http://japan.internet.com/linuxtoday/20080516/5.html
学術論文のオープンアクセス推進団体であるオープン・アーカイブ・コンソーシアムは2008年5月16日、未発表の学術論文の投稿/共有サイト「My Open Archive」(β版)のサービスを開始する、と発表した。
同サイトは昨年9月、招待制によりプライベートテストを開始しているが、今回デザインを全面的に刷新、β版として正式リリースするもの。サービスはすべて無償。
主な機能は、クリエイティブコモンズライセンスによる論文の著作権管理、Microsoft Office や Adobe Acrobat で作成された投稿論文のフラッシュ形式変換(ブラウザで閲覧できるようにするため)、タグ付け、タグ検索、検索結果への関連タグ表示など。
現在、学術論文のオープンアクセス化は浸透しつつあり、Web で閲覧できる論文は増加中だが、査読・評価や著作権などの、従来の業界枠組みは変わらず、Web の仕組みにうまく適合していないことから、気軽に論文を公開できる現状にはない。
My Open Archive では、トップクラスの研究者のみならず、大学・大学院の学生や研究者も利用できるよう、セルフアーカイビング機能を搭載した。
研究者向けPubMedデータベースの利用を助けるOlogeez
http://jp.techcrunch.com/archives/20080715ologeez-wants-to-make-finding-research-articles-easier/
生命科学の分野の学生や研究者たちにとって、なくてはならないのがPubMedだ。保健医療やそのほかの生物科学分野をカバーする無料の大規模データベースだが、巨大データベースの検索は初心者がびびってしまうほど複雑で難しい。しかもインタフェイスは、ここ10年まったく改良されていないみたいだ。
最近Stanfordで起業され、ベータバージョンを公開したOlogeez!は、この問題を解決してくれる。このサイトは、分かりやすくて使いやすいポータルとして科学記事の検索を助け、また科学者が研究資料や研究仲間を素早く探したいときの手伝いもしてくれる。ユーザは今のところ大学内部に限られているが、ファウンダーのJason Hoytは最終的には一般公開したいと言っている。
OlogeezはPubMedの記事にこのデータベースのAPIからアクセスするが、しかし単にインタフェイスを改善するだけには終わっていない。たとえば、ユーザが記事を評価したり、記事について議論することができる。そうすると、やがて、良質で信頼性の高い記事が検索で上位にランクされるようになる。ユーザはPubMedのデータベースにない記事をOlogeezにアップロードできる。記事は分類されるので、Netflixふうの推奨:“関連してこんな記事もございます”のメッセージも可能だ。
このサイトのSNSふうの機能は、個人が対象ではない(科学者のためのFacebookではない)。対象は、互いにコラボしている科学者グループだ。たとえば、ある研究所のメンバーたちが、このサイトを利用してスケジュール表や安全性基準、研究所の規約などを共有化できる―一種の、仮想BBSだ。Hoytによれば、ユーザはキーワードや分野でデータベースを検索できるから、お互いに新しい研究仲間も見つけやすいという。
Ologeezの現状の欠点は、まだ記事のランク付けや記事に関する議論がとても少ないことだ(つまりユーザ数がまだ少ない)。だからといって、ユーザーを増やすために一般公開するにはまだ早すぎる。成功するためには、記事のランク付けのみで人気のあるサイトで終わってはならない。科学者たちから信用され信頼されるサイトになることが第一だ。もちろんそれは、簡単なことではない。
http://jp.techcrunch.com/archives/20080715ologeez-wants-to-make-finding-research-articles-easier/
生命科学の分野の学生や研究者たちにとって、なくてはならないのがPubMedだ。保健医療やそのほかの生物科学分野をカバーする無料の大規模データベースだが、巨大データベースの検索は初心者がびびってしまうほど複雑で難しい。しかもインタフェイスは、ここ10年まったく改良されていないみたいだ。
最近Stanfordで起業され、ベータバージョンを公開したOlogeez!は、この問題を解決してくれる。このサイトは、分かりやすくて使いやすいポータルとして科学記事の検索を助け、また科学者が研究資料や研究仲間を素早く探したいときの手伝いもしてくれる。ユーザは今のところ大学内部に限られているが、ファウンダーのJason Hoytは最終的には一般公開したいと言っている。
OlogeezはPubMedの記事にこのデータベースのAPIからアクセスするが、しかし単にインタフェイスを改善するだけには終わっていない。たとえば、ユーザが記事を評価したり、記事について議論することができる。そうすると、やがて、良質で信頼性の高い記事が検索で上位にランクされるようになる。ユーザはPubMedのデータベースにない記事をOlogeezにアップロードできる。記事は分類されるので、Netflixふうの推奨:“関連してこんな記事もございます”のメッセージも可能だ。
このサイトのSNSふうの機能は、個人が対象ではない(科学者のためのFacebookではない)。対象は、互いにコラボしている科学者グループだ。たとえば、ある研究所のメンバーたちが、このサイトを利用してスケジュール表や安全性基準、研究所の規約などを共有化できる―一種の、仮想BBSだ。Hoytによれば、ユーザはキーワードや分野でデータベースを検索できるから、お互いに新しい研究仲間も見つけやすいという。
Ologeezの現状の欠点は、まだ記事のランク付けや記事に関する議論がとても少ないことだ(つまりユーザ数がまだ少ない)。だからといって、ユーザーを増やすために一般公開するにはまだ早すぎる。成功するためには、記事のランク付けのみで人気のあるサイトで終わってはならない。科学者たちから信用され信頼されるサイトになることが第一だ。もちろんそれは、簡単なことではない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
生命科学研究ハイライト 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
生命科学研究ハイライトのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6462人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19244人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208300人