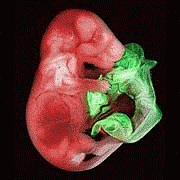世界大学ランキング
国外から優秀な頭脳を集め、研究はアウトソーシング――世界に開かれた大学の実力をグローバル度で格付け
ニューズウィーク日本版
2006-9・27号(9/20発売)
http://
1. Harvard University
2. Stanford University
3. Yale University
4. California Institute of Technology
5. University of California at Berkeley
6. University of Cambridge
7. Massachusetts Institute Technology
8. Oxford University
9. University of California at San Francisco
10. Columbia University
11. University of Michigan at Ann Arbor
12. University of California at Los Angeles
13. University of Pennsylvania
14. Duke University
15. Princeton Universitty
16. Tokyo University
17. Imperial College London
18. University of Toronto
19. Cornell University
20. University of Chicago
21. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
22. University of Washington at Seattle
23. University of California at San Diego
24. Johns Hopkins University
25. University College London
26. Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
27. University Texas at Austin
28. University of Wisconsin at Madison
29. Kyoto University
30. University of Minnesota Twin Cities
31. University of British Columbia
32. University of Geneva
33. Washington University in St. Louis
34. London School of Economics
35. Northwestern University
36. National University of Singapore
37. University of Pittsburgh
38. Australian National University
39. New York University
40. Pennsylvania State University
41. University of North Carolina at Chapel Hill
42. McGill University
43. Ecole Polytechnique
44. University of Basel
45. University of Maryland
46. University of Zurich
47. University of Edinburgh
48. University of Illinois at Urbana Champaign
49. University of Bristol
50. University of Sydney
51. University of Colorado at Boulder
52. Utrecht University
53. University of Melbourne
54. University of Southern California
55. University of Alberta
56. Brown University
57. Osaka University
58. University of Manchester
59. University of California at Santa Barbara
60. Hong Kong University of Science and Technology
61. Wageningen University
62. Michigan State University
63. University of Munich
64. University of New South Wales
65. Boston University
66. Vanderbilt University
67. University of Rochester
68. Tohoku University
69. University of Hong Kong
70. University of Sheffield
71. Nanyang Technological University
72. University of Vienna
73. Monash University
74. University of Nottingham
75. Carnegie Mellon University
76. Lund University
77. Texas A&M University
78. University of Western Australia
79. Ecole Normale Super Paris
80. University of Virginia
81. Technical University of Munich
82. Hebrew University of Jerusalem
83. Leiden University
84. University of Waterloo
85. King's College London
86. Purdue University
87. University of Birmingham
88. Uppsala University
89. University of Amsterdam
90. University of Heidelberg
91. University of Queensland
92. University of Leuven
93. Emory University
94. Nagoya University
95. Case Western Reserve University
96. Chinese University of Hong Kong
97. University of Newcastle
98. Innsbruck University
99. University of Massachusetts at Amherst
100. Sussex University
http://
国外から優秀な頭脳を集め、研究はアウトソーシング――世界に開かれた大学の実力をグローバル度で格付け
ニューズウィーク日本版
2006-9・27号(9/20発売)
http://
1. Harvard University
2. Stanford University
3. Yale University
4. California Institute of Technology
5. University of California at Berkeley
6. University of Cambridge
7. Massachusetts Institute Technology
8. Oxford University
9. University of California at San Francisco
10. Columbia University
11. University of Michigan at Ann Arbor
12. University of California at Los Angeles
13. University of Pennsylvania
14. Duke University
15. Princeton Universitty
16. Tokyo University
17. Imperial College London
18. University of Toronto
19. Cornell University
20. University of Chicago
21. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
22. University of Washington at Seattle
23. University of California at San Diego
24. Johns Hopkins University
25. University College London
26. Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
27. University Texas at Austin
28. University of Wisconsin at Madison
29. Kyoto University
30. University of Minnesota Twin Cities
31. University of British Columbia
32. University of Geneva
33. Washington University in St. Louis
34. London School of Economics
35. Northwestern University
36. National University of Singapore
37. University of Pittsburgh
38. Australian National University
39. New York University
40. Pennsylvania State University
41. University of North Carolina at Chapel Hill
42. McGill University
43. Ecole Polytechnique
44. University of Basel
45. University of Maryland
46. University of Zurich
47. University of Edinburgh
48. University of Illinois at Urbana Champaign
49. University of Bristol
50. University of Sydney
51. University of Colorado at Boulder
52. Utrecht University
53. University of Melbourne
54. University of Southern California
55. University of Alberta
56. Brown University
57. Osaka University
58. University of Manchester
59. University of California at Santa Barbara
60. Hong Kong University of Science and Technology
61. Wageningen University
62. Michigan State University
63. University of Munich
64. University of New South Wales
65. Boston University
66. Vanderbilt University
67. University of Rochester
68. Tohoku University
69. University of Hong Kong
70. University of Sheffield
71. Nanyang Technological University
72. University of Vienna
73. Monash University
74. University of Nottingham
75. Carnegie Mellon University
76. Lund University
77. Texas A&M University
78. University of Western Australia
79. Ecole Normale Super Paris
80. University of Virginia
81. Technical University of Munich
82. Hebrew University of Jerusalem
83. Leiden University
84. University of Waterloo
85. King's College London
86. Purdue University
87. University of Birmingham
88. Uppsala University
89. University of Amsterdam
90. University of Heidelberg
91. University of Queensland
92. University of Leuven
93. Emory University
94. Nagoya University
95. Case Western Reserve University
96. Chinese University of Hong Kong
97. University of Newcastle
98. Innsbruck University
99. University of Massachusetts at Amherst
100. Sussex University
http://
|
|
|
|
コメント(40)
−最近11年間の論文引用パフォーマンスを分析−
出典: Essential Science IndicatorsSM, 1995年1月-2005年12月
http://www.thomsonscientific.jp/news/press/esi2006/ranking.html
トムソンコーポレーションの1事業部であるトムソンサイエンティフィックでは、学術論文の引用動向データをもとに、最近11年間の国内研究機関の論文引用パフォーマンスを分析しました。全分野の総合ランキングトップ20と、特に日本の貢献が著しい3分野についてそれぞれトップ10を発表いたします。
調査内容:
学術論文の引用動向データを提供する統計データベースで、論文の被引用数をもとに、世界のトップ1パーセントにランクされる研究者と研究機関の情報を収録しています。
収録対象期間: 1995-2005の11年間
分析内容:
世界の研究機関ランキングより、日本の研究機関のみを抽出・再集計し、国内研究機関トップ20としてまとめました(表1)。また、Essential Science Indicatorsで定義されている22分野のうち、世界のトップ5位以内に日本の機関がエントリーしている3分野(材料科学、物理学、化学)について同様に集計し、それぞれトップ10をまとめました(表2, 3, 4)。いずれの表も、日本国内でのランキングとあわせて、世界において何位に位置するかが示されています。
出典: Essential Science IndicatorsSM, 1995年1月-2005年12月
http://www.thomsonscientific.jp/news/press/esi2006/ranking.html
トムソンコーポレーションの1事業部であるトムソンサイエンティフィックでは、学術論文の引用動向データをもとに、最近11年間の国内研究機関の論文引用パフォーマンスを分析しました。全分野の総合ランキングトップ20と、特に日本の貢献が著しい3分野についてそれぞれトップ10を発表いたします。
調査内容:
学術論文の引用動向データを提供する統計データベースで、論文の被引用数をもとに、世界のトップ1パーセントにランクされる研究者と研究機関の情報を収録しています。
収録対象期間: 1995-2005の11年間
分析内容:
世界の研究機関ランキングより、日本の研究機関のみを抽出・再集計し、国内研究機関トップ20としてまとめました(表1)。また、Essential Science Indicatorsで定義されている22分野のうち、世界のトップ5位以内に日本の機関がエントリーしている3分野(材料科学、物理学、化学)について同様に集計し、それぞれトップ10をまとめました(表2, 3, 4)。いずれの表も、日本国内でのランキングとあわせて、世界において何位に位置するかが示されています。
英THES紙で世界のトップ大学にランクイン
http://www.ogi.keio.ac.jp/news-thesrankings2006.html
2006年10月6日付のThe Times Higher Education Supplement (THES) 紙 (注)において世界のトップ200大学が発表され、慶應義塾大学は昨年の215位から大幅に順位を上げ、120位にランクされました。同紙は2004年から世界の大学ランキングを実施しており、今回は第3回目。日本の大学では、11校がトップ200位に入りました。慶應義塾は日本の大学の中では5位(私立大学の中でトップ)、また北米とヨーロッパ以外の地域では30位にランクされています。
(注) The Times Higher Education Supplement (THES) は英国のThe Times紙系列の専門紙(週刊)で、高等教育分野では世界的に権威のある新聞です。
日本の大学のランキング
東京大学 19位 (16)
京都大学 29 (31)
大阪大学 70 (105)
東京工業大学 118 (99)
慶應義塾大学 120 (215)
九州大学 128 (222)
名古屋大学 128 (129)
北海道大学 133 (157)
早稲田大学 158 (202)
東北大学 168 (136)
神戸大学 181 (172)
( )の数字は2005年のランキング
<参考>
トップ10校
1位 ハーバード大学
2 ケンブリッジ大学
3 オックスフォード大学
4 マサチューセッツ工科大学
4 イェール大学
6 スタンフォード大学
7 カリフォルニア工科大学
8 カリフォルニア大学バークレー校
9 インペリアル・カレッジ・ロンドン
10 プリンストン大学
http://www.ogi.keio.ac.jp/news-thesrankings2006.html
2006年10月6日付のThe Times Higher Education Supplement (THES) 紙 (注)において世界のトップ200大学が発表され、慶應義塾大学は昨年の215位から大幅に順位を上げ、120位にランクされました。同紙は2004年から世界の大学ランキングを実施しており、今回は第3回目。日本の大学では、11校がトップ200位に入りました。慶應義塾は日本の大学の中では5位(私立大学の中でトップ)、また北米とヨーロッパ以外の地域では30位にランクされています。
(注) The Times Higher Education Supplement (THES) は英国のThe Times紙系列の専門紙(週刊)で、高等教育分野では世界的に権威のある新聞です。
日本の大学のランキング
東京大学 19位 (16)
京都大学 29 (31)
大阪大学 70 (105)
東京工業大学 118 (99)
慶應義塾大学 120 (215)
九州大学 128 (222)
名古屋大学 128 (129)
北海道大学 133 (157)
早稲田大学 158 (202)
東北大学 168 (136)
神戸大学 181 (172)
( )の数字は2005年のランキング
<参考>
トップ10校
1位 ハーバード大学
2 ケンブリッジ大学
3 オックスフォード大学
4 マサチューセッツ工科大学
4 イェール大学
6 スタンフォード大学
7 カリフォルニア工科大学
8 カリフォルニア大学バークレー校
9 インペリアル・カレッジ・ロンドン
10 プリンストン大学
ソウル大51位、東京大17位=世界大学ランキング
http://www.chosunonline.com/article/20071109000033
今年の世界大学ランキングで、韓国のソウル大学は昨年(63位)よりランクを上げ、米テキサス大とともに51位に入った。
同ランキングは、英国の教育専門誌「タイムズ・ハイアー・エデュケーション・サプルメント」(THES)と海外留学専門会社のQSが共同で世界200大学をランク付けしたもので、米ハーバード大が4年連続で1位に選ばれた。2位は英ケンブリッジ大、オックスフォード大、米エール大が入った。
韓国からはソウル大のほかに、韓国科学技術院(KAIST)が仏ピエール・アンド・マリーキュリー大とともに132位に入った。昨年150位だった高麗大はランク外に転落した。
アジア地域では、東京大(17位)、香港大(18位)、北京大(36位)が上位に入った。北京大は昨年(14位)よりランクを下げた。
http://www.chosunonline.com/article/20071109000033
今年の世界大学ランキングで、韓国のソウル大学は昨年(63位)よりランクを上げ、米テキサス大とともに51位に入った。
同ランキングは、英国の教育専門誌「タイムズ・ハイアー・エデュケーション・サプルメント」(THES)と海外留学専門会社のQSが共同で世界200大学をランク付けしたもので、米ハーバード大が4年連続で1位に選ばれた。2位は英ケンブリッジ大、オックスフォード大、米エール大が入った。
韓国からはソウル大のほかに、韓国科学技術院(KAIST)が仏ピエール・アンド・マリーキュリー大とともに132位に入った。昨年150位だった高麗大はランク外に転落した。
アジア地域では、東京大(17位)、香港大(18位)、北京大(36位)が上位に入った。北京大は昨年(14位)よりランクを下げた。
[中国之最:第31回]大学ランキング、第一位は?
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2008&d=0317&f=column_0317_002.shtml
写真:大 / 写真特集
中国語で「排行榜」とはランキングのことだ。各都市の不動産価格から人気女優、最も危険な食べ物ランキングまで、実に様々な「排行榜」がある。そんなランキングの中、ひと際目立つのが、大学ランキングだ。
中国には現在2000校近くの大学がある。過去10年間で700校以上が新設され、80年代に2%ほどだった大学進学率も、現在では20%に達する勢いだ。そんな中国の大学ランキングを追ってみた。
【12年連続で清華大学がトップ】
毎年、中国では『中国大学評価』というランキングが発表される。このランキングでは人材教育(学部生と研究生)と科学研究(自然科学と社会科学)という項目をそれぞれ点数化し、中国の各大学を評価している。
08年の大学評価で、第1位は清華大学、12年連続でトップとなった。また2位には北京大学、3位には浙江大学が入り、この上位3校の順位は9年連続だ。以下、上海交通大学、南京大学と続く。
【「状元」は北京大学へ】
「状元」とは、科挙で第1位の成績で合格した者のことで、現在では全国統一試験における各省の首席合格者を表す。00年から06年の各省の秀才「状元」の56%は北京大学進学を選択している。
こんな中国一もある。大学のキャンパスが最も広いのは中国民航飛行学院で、1164ヘクタール。これは東京ドーム250個分に相当する。中国人学生の数が最も多いのは六つの大学が合併した吉林大学で、6.4万人。学費が中国一高額なのは、映画スターの養成所でもある中央戯劇学院で約14万元。写真は最高学府のひとつである北京大学。(編集担当:長谷川昌志)
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2008&d=0317&f=column_0317_002.shtml
写真:大 / 写真特集
中国語で「排行榜」とはランキングのことだ。各都市の不動産価格から人気女優、最も危険な食べ物ランキングまで、実に様々な「排行榜」がある。そんなランキングの中、ひと際目立つのが、大学ランキングだ。
中国には現在2000校近くの大学がある。過去10年間で700校以上が新設され、80年代に2%ほどだった大学進学率も、現在では20%に達する勢いだ。そんな中国の大学ランキングを追ってみた。
【12年連続で清華大学がトップ】
毎年、中国では『中国大学評価』というランキングが発表される。このランキングでは人材教育(学部生と研究生)と科学研究(自然科学と社会科学)という項目をそれぞれ点数化し、中国の各大学を評価している。
08年の大学評価で、第1位は清華大学、12年連続でトップとなった。また2位には北京大学、3位には浙江大学が入り、この上位3校の順位は9年連続だ。以下、上海交通大学、南京大学と続く。
【「状元」は北京大学へ】
「状元」とは、科挙で第1位の成績で合格した者のことで、現在では全国統一試験における各省の首席合格者を表す。00年から06年の各省の秀才「状元」の56%は北京大学進学を選択している。
こんな中国一もある。大学のキャンパスが最も広いのは中国民航飛行学院で、1164ヘクタール。これは東京ドーム250個分に相当する。中国人学生の数が最も多いのは六つの大学が合併した吉林大学で、6.4万人。学費が中国一高額なのは、映画スターの養成所でもある中央戯劇学院で約14万元。写真は最高学府のひとつである北京大学。(編集担当:長谷川昌志)
上位狙いか疑問視か 海外発「世界大学ランキング」
2008年04月01日
http://www.asahi.com/edu/university/zennyu/TKY200803310215.html
国内の有力大学の間で、海外発「世界大学ランキング」への関心が高まっている。「順位上昇作戦」を展開したり、目標順位を掲げたりする大学もある。一方、「非英語圏は不利」「文系軽視」など、ランキングに対する疑問も根強い。「たかがランキング、されどランキング」――大学関係者がこう語るランキングとの付き合い方をみた。
◆東大「順位は恣意的」
東京大が21日、米カリフォルニア大バークリー校、米エール大、英ケンブリッジ大という名門大学と教育力を比較する研究会を開いた。
小宮山宏総長は「ランキングの多くは恣意的(しいてき)で、順位に一喜一憂するのは本末転倒」とあいさつ。浜田純一副学長も「ランキングは教育など大学の総合力を正確に反映しているわけではない。むしろ、似ている大学と比べることで長所や短所をはっきりさせた方が有益だ」と話す。
「世界の知の頂点を目指す」(小宮山総長)東大だが、英紙タイムズの07年のランキング(以下同じ)では17位。専門家評価は百点満点だが、国際性が50点以下なのが弱点だ。最近力を入れている国際化は「順位上昇作戦」にも見えるが、浜田副学長は「総合力ではすでに世界の10位以内だと思っている。ランキングの上昇自体が目的の努力をするつもりはない」。
◆東北大「30以内目標」
一方、ランキングに対応しているように見える大学もある。
一橋大は200位にも入らず、「順位の低さに衝撃を受けた」(加藤哲郎・研究担当役員補佐)。そこで、同じ社会科学の総合大学でありながら06年には東大よりも上位(17位)に入った英ロンドン大経済政治学院(LSE)を現地調査。論文の英訳支援も始めた。加藤補佐は「人文科学と社会科学の部門別ランキングでまず100位以内を目指す」と意気込む。
大阪大(46位)は07年に初めてトップ50入りしたが、「論文の引用回数からみると30位以内に入っていてもおかしくない。10〜20位台にはいきたい」(高杉英一副学長)。タイムズ側に対し、評価にあたる専門家が欧米に偏っているのではないかとして改善を求めるなど積極的だ。
慶応大(161位)は安西祐一郎塾長が05年、日本の大学のトップとしては初めてタイムズの編集部を訪れて算出の基準などを尋ね、そのころから塾長の海外出張を約2.5倍に増やした。坂本達哉常任理事は「慶応の国際的な存在感が高まり、結果としてランキングにもプラスに働いているかもしれない。50位に近づきたい」。
東北大(102位)は昨春、井上明久総長が「井上プラン」で「10年後のトップ30入り」を宣言。北村幸久副学長は「そのためにも世界中から優れた研究者や学生を獲得したい」。新年度からは優れた教授に月給を上乗せする「抜群教授」(ディスティングイッシュトプロフェッサー)制度を始めて、優秀な「頭脳」獲得に本腰を入れる。
東京工業大(90位)は「レベルに比べて国際的な知名度が低い」(大倉一郎副学長)弱点への対策として、07年3月から世界的な科学誌「ネイチャー」に大学紹介などの広告を出している。大倉副学長は「電子メールで購読者1万人にも配信されるので、評価にあたる専門家が見る可能性もある」と期待する。
◆「ミカンとリンゴ比べるよう」
これに対し、ランキングに懐疑的な大学もある。
京都大(25位)の木谷雅人副学長は「多種多様な大学を順位付けできるのか疑問だ。信用が置けるものとは思っていない」。早稲田大(180位)の堀口健治副総長も「ランキングは英語の論文や理系が中心で、人文・社会科学系の力を十分反映していない。順位の上がり下がりに一喜一憂するのは間違っている」と話す。
一方、国立大学協会副会長でもある九州大(136位)の梶山千里総長は「順位を上げることは重要」としながらも、「カンフル剤のような一時的なものではなく、実質の向上がともなうような努力をすべきだ」。
大学は、ランキングとどう付き合えばいいのか。
東大の小林雅之教授(高等教育論)は「大学の力には数量化できないものも多い。リンゴとミカンを比べるようなものなので、距離を置いた方がいい」と言う。一方、神戸親和女子大の間渕泰尚専任講師(同)は「歌のヒットチャートと似ていて、上位でなくても、いい曲(大学)はあるが、上位にあるのはそれなりにいい曲(大学)だ。自校の改善のために賢く使えばいい」と話している。
2008年04月01日
http://www.asahi.com/edu/university/zennyu/TKY200803310215.html
国内の有力大学の間で、海外発「世界大学ランキング」への関心が高まっている。「順位上昇作戦」を展開したり、目標順位を掲げたりする大学もある。一方、「非英語圏は不利」「文系軽視」など、ランキングに対する疑問も根強い。「たかがランキング、されどランキング」――大学関係者がこう語るランキングとの付き合い方をみた。
◆東大「順位は恣意的」
東京大が21日、米カリフォルニア大バークリー校、米エール大、英ケンブリッジ大という名門大学と教育力を比較する研究会を開いた。
小宮山宏総長は「ランキングの多くは恣意的(しいてき)で、順位に一喜一憂するのは本末転倒」とあいさつ。浜田純一副学長も「ランキングは教育など大学の総合力を正確に反映しているわけではない。むしろ、似ている大学と比べることで長所や短所をはっきりさせた方が有益だ」と話す。
「世界の知の頂点を目指す」(小宮山総長)東大だが、英紙タイムズの07年のランキング(以下同じ)では17位。専門家評価は百点満点だが、国際性が50点以下なのが弱点だ。最近力を入れている国際化は「順位上昇作戦」にも見えるが、浜田副学長は「総合力ではすでに世界の10位以内だと思っている。ランキングの上昇自体が目的の努力をするつもりはない」。
◆東北大「30以内目標」
一方、ランキングに対応しているように見える大学もある。
一橋大は200位にも入らず、「順位の低さに衝撃を受けた」(加藤哲郎・研究担当役員補佐)。そこで、同じ社会科学の総合大学でありながら06年には東大よりも上位(17位)に入った英ロンドン大経済政治学院(LSE)を現地調査。論文の英訳支援も始めた。加藤補佐は「人文科学と社会科学の部門別ランキングでまず100位以内を目指す」と意気込む。
大阪大(46位)は07年に初めてトップ50入りしたが、「論文の引用回数からみると30位以内に入っていてもおかしくない。10〜20位台にはいきたい」(高杉英一副学長)。タイムズ側に対し、評価にあたる専門家が欧米に偏っているのではないかとして改善を求めるなど積極的だ。
慶応大(161位)は安西祐一郎塾長が05年、日本の大学のトップとしては初めてタイムズの編集部を訪れて算出の基準などを尋ね、そのころから塾長の海外出張を約2.5倍に増やした。坂本達哉常任理事は「慶応の国際的な存在感が高まり、結果としてランキングにもプラスに働いているかもしれない。50位に近づきたい」。
東北大(102位)は昨春、井上明久総長が「井上プラン」で「10年後のトップ30入り」を宣言。北村幸久副学長は「そのためにも世界中から優れた研究者や学生を獲得したい」。新年度からは優れた教授に月給を上乗せする「抜群教授」(ディスティングイッシュトプロフェッサー)制度を始めて、優秀な「頭脳」獲得に本腰を入れる。
東京工業大(90位)は「レベルに比べて国際的な知名度が低い」(大倉一郎副学長)弱点への対策として、07年3月から世界的な科学誌「ネイチャー」に大学紹介などの広告を出している。大倉副学長は「電子メールで購読者1万人にも配信されるので、評価にあたる専門家が見る可能性もある」と期待する。
◆「ミカンとリンゴ比べるよう」
これに対し、ランキングに懐疑的な大学もある。
京都大(25位)の木谷雅人副学長は「多種多様な大学を順位付けできるのか疑問だ。信用が置けるものとは思っていない」。早稲田大(180位)の堀口健治副総長も「ランキングは英語の論文や理系が中心で、人文・社会科学系の力を十分反映していない。順位の上がり下がりに一喜一憂するのは間違っている」と話す。
一方、国立大学協会副会長でもある九州大(136位)の梶山千里総長は「順位を上げることは重要」としながらも、「カンフル剤のような一時的なものではなく、実質の向上がともなうような努力をすべきだ」。
大学は、ランキングとどう付き合えばいいのか。
東大の小林雅之教授(高等教育論)は「大学の力には数量化できないものも多い。リンゴとミカンを比べるようなものなので、距離を置いた方がいい」と言う。一方、神戸親和女子大の間渕泰尚専任講師(同)は「歌のヒットチャートと似ていて、上位でなくても、いい曲(大学)はあるが、上位にあるのはそれなりにいい曲(大学)だ。自校の改善のために賢く使えばいい」と話している。
◇
主な大学ランキング
最も有名なのは、英国の日刊紙タイムズの別冊高等教育版などが04年から発表しているもの。(1)研究力(専門家による評価が40%、教員1人あたりの論文引用回数が20%)(2)卒業生の被雇用力(企業の採用担当者による評価、10%)(3)教育力(学生1人あたりの教員数、20%)(4)国際性(外国人教員比率と留学生比率、各5%)から算出している。
上海交通大学が03年から発表しているものは、ノーベル、フィールズ両賞の受賞者数や科学誌「ネイチャー」「サイエンス」の掲載論文数などを基準にしていて、「研究力ランキング」の性格が強い。
米誌ニューズウィークが06年に発表したものは、タイムズと上海交通大学のランキングなどをもとにしている。
主な大学ランキング
最も有名なのは、英国の日刊紙タイムズの別冊高等教育版などが04年から発表しているもの。(1)研究力(専門家による評価が40%、教員1人あたりの論文引用回数が20%)(2)卒業生の被雇用力(企業の採用担当者による評価、10%)(3)教育力(学生1人あたりの教員数、20%)(4)国際性(外国人教員比率と留学生比率、各5%)から算出している。
上海交通大学が03年から発表しているものは、ノーベル、フィールズ両賞の受賞者数や科学誌「ネイチャー」「サイエンス」の掲載論文数などを基準にしていて、「研究力ランキング」の性格が強い。
米誌ニューズウィークが06年に発表したものは、タイムズと上海交通大学のランキングなどをもとにしている。
日本の自民党、東大の世界トップ10入りを推進
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=98556&servcode=A00§code=A00
日本の与党、自民党と名門大学が学校の競争力を高めるために国際化を推進している。
自民党は東京大学の「大学ランキング向上プロジェクト」を新設した。このプロジェクトは東京大学のランクを世界10位以内に入る水準まで向上させようというものだ。自民党は党傘下の国家戦略本部内に「大学ランキング向上プロジェクトチーム」(座長・河村建夫元文部科学相)を新設したと読売新聞が9日、報道した。
京都大も積極的な改革を試みている。京都大は8日から講義の映像を世界最大の動画サイトであるユーチューブ(YOUTUBE)に公開している。国内外の優秀な学生と研究者を誘致するための大学の広報が目的だ。
◇大学のランキング向上=自民党はまず世界各国で有能な人材を日本に呼び込むために力を注ぐ方針だ。東京大学が世界大学ランキングで米国の名門大に大きく引き離されているのは外国人教員と留学生の比率が低いからだという分析結果を受けたものだ。
自民党は、東京大学が英紙ザ・タイムズ(2007年)、米誌ニューズウィーク(2006年)、上海交通大学(中国、2007年)が発表した「世界大学ランキング」でこれまで一度も10位以内に入れなかったと指摘した。これらの調査では東京大学が競争モデルとして設定している米国のハーバード大がいずれのランキングでも1位だった。
東京大学の場合、ニューズウィークの調査で16位につけたのが最も高かった。ザ・タイムズの調査では17位、上海交通大が発表したランキングでは20位だった。
自民党はザ・タイムズの場合、①各国学者の評価②教員1人あたりの論文引用数③学生と教員の比率④企業採用担当者の評価⑤外国人教員比率⑥留学生の比率など6分野を基準に査定していることに注目した。東大の場合、①〜④の評価は100点満点でほぼ90点以上を確保し、トップ10に入っているが、留学生の比率と外国人教員の比率がそれぞれ25点と44点にとどまっていた。
自民党は東京大学のランクを上げるためには留学生と外国人教員の比率を上げる必要があると判断した。東京大学や早稲田、慶応、京都大など日本の名門大学は外国人留学生に対する奨学金支給を大幅に充実させ、今年からさまざまな誘致プログラムを強化している。
◇講義内容をユーチューブで公開=京都大は2005年から「ウェブサイト教材の公開プロジェクト」を推進してきた。ユーチューブにはこれまで準備してきた講義の映像199本を段階的に公開している。一般人はただで京都大の講義を閲覧できる。講義の動画は時間に制限されず長時間視聴できるように設定されている。
また医学部の臓器移植過程を含んだ授業内容と地震に関するシミュレーション動画、ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士の業績を京都大の教授が説明する映像も公開している。ホームページだけでなく日本最大の通信会社NTTドコモの携帯電話を利用して動画を見ることもできる。
東京大学術情報メディアセンターの土佐尚子教授は「学問は共有することによって価値がある」と述べ「今後さらに映像を増やし、開かれた知識を追求していきたい」と話している。
ユーチューブを運営しているグーグルは、明治学院大学などほかの日本の大学にもこのサービスを拡大する方針だ。
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=98556&servcode=A00§code=A00
日本の与党、自民党と名門大学が学校の競争力を高めるために国際化を推進している。
自民党は東京大学の「大学ランキング向上プロジェクト」を新設した。このプロジェクトは東京大学のランクを世界10位以内に入る水準まで向上させようというものだ。自民党は党傘下の国家戦略本部内に「大学ランキング向上プロジェクトチーム」(座長・河村建夫元文部科学相)を新設したと読売新聞が9日、報道した。
京都大も積極的な改革を試みている。京都大は8日から講義の映像を世界最大の動画サイトであるユーチューブ(YOUTUBE)に公開している。国内外の優秀な学生と研究者を誘致するための大学の広報が目的だ。
◇大学のランキング向上=自民党はまず世界各国で有能な人材を日本に呼び込むために力を注ぐ方針だ。東京大学が世界大学ランキングで米国の名門大に大きく引き離されているのは外国人教員と留学生の比率が低いからだという分析結果を受けたものだ。
自民党は、東京大学が英紙ザ・タイムズ(2007年)、米誌ニューズウィーク(2006年)、上海交通大学(中国、2007年)が発表した「世界大学ランキング」でこれまで一度も10位以内に入れなかったと指摘した。これらの調査では東京大学が競争モデルとして設定している米国のハーバード大がいずれのランキングでも1位だった。
東京大学の場合、ニューズウィークの調査で16位につけたのが最も高かった。ザ・タイムズの調査では17位、上海交通大が発表したランキングでは20位だった。
自民党はザ・タイムズの場合、①各国学者の評価②教員1人あたりの論文引用数③学生と教員の比率④企業採用担当者の評価⑤外国人教員比率⑥留学生の比率など6分野を基準に査定していることに注目した。東大の場合、①〜④の評価は100点満点でほぼ90点以上を確保し、トップ10に入っているが、留学生の比率と外国人教員の比率がそれぞれ25点と44点にとどまっていた。
自民党は東京大学のランクを上げるためには留学生と外国人教員の比率を上げる必要があると判断した。東京大学や早稲田、慶応、京都大など日本の名門大学は外国人留学生に対する奨学金支給を大幅に充実させ、今年からさまざまな誘致プログラムを強化している。
◇講義内容をユーチューブで公開=京都大は2005年から「ウェブサイト教材の公開プロジェクト」を推進してきた。ユーチューブにはこれまで準備してきた講義の映像199本を段階的に公開している。一般人はただで京都大の講義を閲覧できる。講義の動画は時間に制限されず長時間視聴できるように設定されている。
また医学部の臓器移植過程を含んだ授業内容と地震に関するシミュレーション動画、ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士の業績を京都大の教授が説明する映像も公開している。ホームページだけでなく日本最大の通信会社NTTドコモの携帯電話を利用して動画を見ることもできる。
東京大学術情報メディアセンターの土佐尚子教授は「学問は共有することによって価値がある」と述べ「今後さらに映像を増やし、開かれた知識を追求していきたい」と話している。
ユーチューブを運営しているグーグルは、明治学院大学などほかの日本の大学にもこのサービスを拡大する方針だ。
論文引用国内トップは東大 米社がランキング
2008年4月14日 11時23分
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008041401000177.html
米国の学術情報会社トムソンコーポレーションは14日、1997−2007年に論文が引用された回数が多い日本の研究機関のランキングを発表。トップは今回も東京大で、世界の約3800機関の中では昨年の13位から順位を1つ上げ、12位だった。
2位は京大(世界28位)、3位は大阪大(同33位)、4位は東北大(同65位)。国内順位は昨年と同じだが、世界順位はいずれも1−5位上がった。
分野別では世界の上位5位以内に、材料科学で東北大(世界3位)と産業技術総合研究所(茨城県つくば市、同4位)、化学で京大(同4位)と東大(同5位)、物理学で東大(同2位)、生物学・生化学で東大(同3位)が入った。
2008年4月14日 11時23分
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008041401000177.html
米国の学術情報会社トムソンコーポレーションは14日、1997−2007年に論文が引用された回数が多い日本の研究機関のランキングを発表。トップは今回も東京大で、世界の約3800機関の中では昨年の13位から順位を1つ上げ、12位だった。
2位は京大(世界28位)、3位は大阪大(同33位)、4位は東北大(同65位)。国内順位は昨年と同じだが、世界順位はいずれも1−5位上がった。
分野別では世界の上位5位以内に、材料科学で東北大(世界3位)と産業技術総合研究所(茨城県つくば市、同4位)、化学で京大(同4位)と東大(同5位)、物理学で東大(同2位)、生物学・生化学で東大(同3位)が入った。
−最近11年間の論文引用パフォーマンスを分析−
出典: Essential Science IndicatorsSM, 1997年1月-2007年12月
http://www.thomsonscientific.jp/news/press/esi2008/index.shtml
トムソンコーポレーションの1事業部であるトムソンサイエンティフィックでは、学術論文の引用動向データをもとに、最近11年間の国内研究機関の論文引用パフォーマンスを分析しました。全分野の総合ランキングトップ20と、特に日本の貢献が著しい4分野についてそれぞれトップ10を発表いたします。
調査内容
分析に用いたデータベース:
Essential Science IndicatorsSM
学術論文の引用動向データを提供する統計データベースで、論文の被引用数をもとに、世界のトップ1パーセントにランクされる研究者と研究機関の情報を収録しています。
収録対象期間:
1997-2007の11年間
分析内容:
世界の研究機関ランキングより、日本の研究機関のみを抽出・再集計し、国内研究機関トップ20としてまとめました(表1)。また、Essential Science Indicatorsで定義されている22分野のうち、世界のトップ5位以内に日本の機関がエントリーしている4分野(材料科学、物理学、化学、生物学・生化学)について同様に集計し、それぞれトップ10をまとめました(表2, 3, 4, 5)。いずれの表も、日本国内でのランキングとあわせて、世界において何位に位置するかが示されています。
出典: Essential Science IndicatorsSM, 1997年1月-2007年12月
http://www.thomsonscientific.jp/news/press/esi2008/index.shtml
トムソンコーポレーションの1事業部であるトムソンサイエンティフィックでは、学術論文の引用動向データをもとに、最近11年間の国内研究機関の論文引用パフォーマンスを分析しました。全分野の総合ランキングトップ20と、特に日本の貢献が著しい4分野についてそれぞれトップ10を発表いたします。
調査内容
分析に用いたデータベース:
Essential Science IndicatorsSM
学術論文の引用動向データを提供する統計データベースで、論文の被引用数をもとに、世界のトップ1パーセントにランクされる研究者と研究機関の情報を収録しています。
収録対象期間:
1997-2007の11年間
分析内容:
世界の研究機関ランキングより、日本の研究機関のみを抽出・再集計し、国内研究機関トップ20としてまとめました(表1)。また、Essential Science Indicatorsで定義されている22分野のうち、世界のトップ5位以内に日本の機関がエントリーしている4分野(材料科学、物理学、化学、生物学・生化学)について同様に集計し、それぞれトップ10をまとめました(表2, 3, 4, 5)。いずれの表も、日本国内でのランキングとあわせて、世界において何位に位置するかが示されています。
今回の分析結果のハイライト
ここ数年の傾向として、全体的に論文数、被引用数ともに漸増傾向であり、日本のトップ研究機関の学術発信はより活発化していることがわかります。
全体的に、研究機関の顔ぶれに大きな変化は見られません。日本順位で上位を占める研究機関の多くは、昨年の国内順位を守りつつ、世界順位でも上昇の傾向がみられます。一方、国内順位を維持している研究機関であっても、世界順位が下降している機関も見られます。
昨年に続いて、政府系研究機関の順位に上昇が見られます。これらの研究機関の多くは、近年に独立行政法人化されたものです。
材料科学、物理学、化学のそれぞれで国内1位を維持した東北大学、東京大学、京都大学は、世界順位でも昨年と同じ位置にあります。生物学・生化学分野では、国内1位の東京大学は、世界順位では昨年の5位から第3位へと上昇しました。
下に続く解説“「組織戦略」とランキング”、“世界第1位をどう見るか”もご参照ください。
世界のトップ1パーセント以内の論文被引用実績
Essential Science Indicators は世界の研究機関によって利用されている、研究パフォーマンスを論文引用動向データから計るための統計分析データベースです。各表において、括弧内の機関数は、同データベースに収載されている各分野の世界上位1パーセントの集合を表しています。例えば、表2の材料科学では、589機関が論文被引用数によって世界の上位1パーセントとして抽出・収録されました。
「組織戦略」とランキング
Essential Science Indicators の研究機関ランキングでは、論文の著者が記載した所属機関名にもとづいて引用データを処理することを原則としています。下部組織名称や旧組織名により表れたデータを取りまとめてランキングに反映することによって、研究機関はその研究成果をより高くアピールすることができます。こうした客観データを組織戦略に活用している研究機関は少なくありません。
世界第1位をどう見るか
その一例として、ドイツのマックス・プランク研究所や、中国の中国科学院があげられます。傘下の研究機関をそれぞれ、Max Planck Society、Chinese Academy of Sciencesという名称の元に集めた結果、これらの研究機関はEssential Science Indicators データベースが集計する多くの分野で世界のトップ1パーセントにランクインすることとなりました。今回の4分野のうち、昨年に続いて今年も、マックス・プランク研究所が化学、物理学の2分野で世界1位、また中国科学院が材料科学分野で世界1位となっています。しかしこれはそれぞれが傘下に擁する研究機関名をひとつに取りまとめた結果であり、2004年まで世界第1位であった東北大学(材料科学)、東京大学(物理学)などの研究パフォーマンスが下がったと見るべきではありません。
今回のランキング集計にあたって
今回の集計では、2007年12月末までに行われた大学・研究機関の統合等を反映し、また下部組織名称・旧組織名などによって複数がランクされた機関名については現在の親組織の名称に統一しました。このような組織名の集計が行われた研究機関は、表中では*マークにより示されています。
各表は各機関の発表した論文が引用された数(被引用数)の総数順となっていますが、これを発表論文数や、平均被引用数(一論文あたりの被引用数)によって並べ替えても興味深い結果が得られます。こうしたランキングは絶対的なものではありませんが、世界から注目される、顕著な研究業績をあげている研究機関がどこであるかのおおよその目安にすることができます。
Essential Science Indicators、その他の情報源について
なお、今回の調査の出典であるEssential Science Indicators は、論文引用の世界標準等が分析できる統計データベースで、収録データは2ヶ月ごとに更新されています。大学・研究機関等の組織単位での契約により、インターネットを通じて提供されるもので、個人でのご契約には対応しておりません。米国ペンシルバニア州フィラデルフィアにある本社では、Essential Science Indicatorsをソースデータとしてさまざまな引用分析を行い、ScienceWatch.comというウェブサイトで無料公開しています。詳しくは以下のURLからご覧ください。
Essential Science Indicators
http://www.scientific.thomson.com/jp/products/esi/
ScienceWatch.com
http://sciencewatch.com
また、日本の研究者による注目論文とインタビューについても弊社ウェブサイト内のKnowledgeLinkにてご紹介しておりますので、ご参照ください。
http://www.thomsonscientific.jp/knowledgelink/esi-topics/
昨年(2007年)版プレスリリース
http://www.scientific.thomson.com/jp/news/press/esi2007/
ここ数年の傾向として、全体的に論文数、被引用数ともに漸増傾向であり、日本のトップ研究機関の学術発信はより活発化していることがわかります。
全体的に、研究機関の顔ぶれに大きな変化は見られません。日本順位で上位を占める研究機関の多くは、昨年の国内順位を守りつつ、世界順位でも上昇の傾向がみられます。一方、国内順位を維持している研究機関であっても、世界順位が下降している機関も見られます。
昨年に続いて、政府系研究機関の順位に上昇が見られます。これらの研究機関の多くは、近年に独立行政法人化されたものです。
材料科学、物理学、化学のそれぞれで国内1位を維持した東北大学、東京大学、京都大学は、世界順位でも昨年と同じ位置にあります。生物学・生化学分野では、国内1位の東京大学は、世界順位では昨年の5位から第3位へと上昇しました。
下に続く解説“「組織戦略」とランキング”、“世界第1位をどう見るか”もご参照ください。
世界のトップ1パーセント以内の論文被引用実績
Essential Science Indicators は世界の研究機関によって利用されている、研究パフォーマンスを論文引用動向データから計るための統計分析データベースです。各表において、括弧内の機関数は、同データベースに収載されている各分野の世界上位1パーセントの集合を表しています。例えば、表2の材料科学では、589機関が論文被引用数によって世界の上位1パーセントとして抽出・収録されました。
「組織戦略」とランキング
Essential Science Indicators の研究機関ランキングでは、論文の著者が記載した所属機関名にもとづいて引用データを処理することを原則としています。下部組織名称や旧組織名により表れたデータを取りまとめてランキングに反映することによって、研究機関はその研究成果をより高くアピールすることができます。こうした客観データを組織戦略に活用している研究機関は少なくありません。
世界第1位をどう見るか
その一例として、ドイツのマックス・プランク研究所や、中国の中国科学院があげられます。傘下の研究機関をそれぞれ、Max Planck Society、Chinese Academy of Sciencesという名称の元に集めた結果、これらの研究機関はEssential Science Indicators データベースが集計する多くの分野で世界のトップ1パーセントにランクインすることとなりました。今回の4分野のうち、昨年に続いて今年も、マックス・プランク研究所が化学、物理学の2分野で世界1位、また中国科学院が材料科学分野で世界1位となっています。しかしこれはそれぞれが傘下に擁する研究機関名をひとつに取りまとめた結果であり、2004年まで世界第1位であった東北大学(材料科学)、東京大学(物理学)などの研究パフォーマンスが下がったと見るべきではありません。
今回のランキング集計にあたって
今回の集計では、2007年12月末までに行われた大学・研究機関の統合等を反映し、また下部組織名称・旧組織名などによって複数がランクされた機関名については現在の親組織の名称に統一しました。このような組織名の集計が行われた研究機関は、表中では*マークにより示されています。
各表は各機関の発表した論文が引用された数(被引用数)の総数順となっていますが、これを発表論文数や、平均被引用数(一論文あたりの被引用数)によって並べ替えても興味深い結果が得られます。こうしたランキングは絶対的なものではありませんが、世界から注目される、顕著な研究業績をあげている研究機関がどこであるかのおおよその目安にすることができます。
Essential Science Indicators、その他の情報源について
なお、今回の調査の出典であるEssential Science Indicators は、論文引用の世界標準等が分析できる統計データベースで、収録データは2ヶ月ごとに更新されています。大学・研究機関等の組織単位での契約により、インターネットを通じて提供されるもので、個人でのご契約には対応しておりません。米国ペンシルバニア州フィラデルフィアにある本社では、Essential Science Indicatorsをソースデータとしてさまざまな引用分析を行い、ScienceWatch.comというウェブサイトで無料公開しています。詳しくは以下のURLからご覧ください。
Essential Science Indicators
http://www.scientific.thomson.com/jp/products/esi/
ScienceWatch.com
http://sciencewatch.com
また、日本の研究者による注目論文とインタビューについても弊社ウェブサイト内のKnowledgeLinkにてご紹介しておりますので、ご参照ください。
http://www.thomsonscientific.jp/knowledgelink/esi-topics/
昨年(2007年)版プレスリリース
http://www.scientific.thomson.com/jp/news/press/esi2007/
【2008年4月15日 日本のトップ研究機関の学術発信力 】
http://scienceportal.jp/news/review/0804/0804151.html
トムソンサイエンティフィックが、重要な論文がどれだけ引用されているかから算出した日本の研究機関のランキングを公表した(4月15日ニュース【重要論文被引用数世界のトップ200に日本の11機関】参照)。
このランキングは毎年、発表されている。トムソンサイエンティフィックは「ここ数年の傾向として、全体的に論文数、被引用数ともに漸増傾向で、日本のトップ研究機関の学術発信はより活発化している」と評価している。
ことしのトップ20に入った研究機関は、昨年と全く同じ顔ぶれとなっており、順位の入れ替わりも科学技術振興機構(6位から5位)、理化学研究所(9位から8位)、東京医科歯科大学(20位から19位)がそれぞれすぐ上だった大学を追い越しただけだった。世界でのランクは「日本順位で上位を占める研究機関の多くは、昨年の国内順位を守りつつ、世界順位でも上昇の傾向がみられる一方、国内順位を維持している研究機関であっても、世界順位が下降している機関も見られる」という結果になった。
このランキングの特徴は、被引用数が多い順になっており、当然のことながら研究者を多く抱える大きな大学、研究機関が最初から有利になっていること。当然、トムソンサイエンティフィックも承知の上で、「下部組織名称や旧組織名により表れたデータをとりまとめてランキングに反映することによって、研究機関はその研究成果をより高くアピールすることができる」とコメントしている。
こうした典型例として挙げられているのが、傘下の研究機関を「Max Planck Society」、「Chinese Academy ob Science」という名称で一まとめにしているドイツのマックス・プランク研究所と中国科学院。マックス・プランク研究所は、今回併せて公表された「化学」「物理学」の分野ごとランキングで昨年に続き世界1位、中国科学院も「材料科学」分野で昨年に続き世界1位となっている。しかし、これらはこうした理由によるもので、2004年まで「材料科学」、「物理学」分野でそれぞれ世界1位にランクされていた東北大学(ことしは「材料科学」で世界3位)や東京大学(同「物理学」で2位)の研究活動が低下したと見る必要はない、とトムソンサイエンティフィックは言っている。
一方、被引用数の総数で国内上位20位にランクされた各研究機関について、平均被引用数の数値も併記されている。仮にこれで上位20位をランク付けし直したとすると、1位、科学技術振興機構(平均被引用数16.55)、2位、理化学研究所(14.42)、3位、自然科学研究機構(13.30)、4位、東京医科歯科大学(12.94)、5位、東京大学(12.81)と順位はだいぶ入れ替わることがわかる。
http://scienceportal.jp/news/review/0804/0804151.html
トムソンサイエンティフィックが、重要な論文がどれだけ引用されているかから算出した日本の研究機関のランキングを公表した(4月15日ニュース【重要論文被引用数世界のトップ200に日本の11機関】参照)。
このランキングは毎年、発表されている。トムソンサイエンティフィックは「ここ数年の傾向として、全体的に論文数、被引用数ともに漸増傾向で、日本のトップ研究機関の学術発信はより活発化している」と評価している。
ことしのトップ20に入った研究機関は、昨年と全く同じ顔ぶれとなっており、順位の入れ替わりも科学技術振興機構(6位から5位)、理化学研究所(9位から8位)、東京医科歯科大学(20位から19位)がそれぞれすぐ上だった大学を追い越しただけだった。世界でのランクは「日本順位で上位を占める研究機関の多くは、昨年の国内順位を守りつつ、世界順位でも上昇の傾向がみられる一方、国内順位を維持している研究機関であっても、世界順位が下降している機関も見られる」という結果になった。
このランキングの特徴は、被引用数が多い順になっており、当然のことながら研究者を多く抱える大きな大学、研究機関が最初から有利になっていること。当然、トムソンサイエンティフィックも承知の上で、「下部組織名称や旧組織名により表れたデータをとりまとめてランキングに反映することによって、研究機関はその研究成果をより高くアピールすることができる」とコメントしている。
こうした典型例として挙げられているのが、傘下の研究機関を「Max Planck Society」、「Chinese Academy ob Science」という名称で一まとめにしているドイツのマックス・プランク研究所と中国科学院。マックス・プランク研究所は、今回併せて公表された「化学」「物理学」の分野ごとランキングで昨年に続き世界1位、中国科学院も「材料科学」分野で昨年に続き世界1位となっている。しかし、これらはこうした理由によるもので、2004年まで「材料科学」、「物理学」分野でそれぞれ世界1位にランクされていた東北大学(ことしは「材料科学」で世界3位)や東京大学(同「物理学」で2位)の研究活動が低下したと見る必要はない、とトムソンサイエンティフィックは言っている。
一方、被引用数の総数で国内上位20位にランクされた各研究機関について、平均被引用数の数値も併記されている。仮にこれで上位20位をランク付けし直したとすると、1位、科学技術振興機構(平均被引用数16.55)、2位、理化学研究所(14.42)、3位、自然科学研究機構(13.30)、4位、東京医科歯科大学(12.94)、5位、東京大学(12.81)と順位はだいぶ入れ替わることがわかる。
大学ランク「過信ご注意」
専門家が警鐘 OECD、各国影響調査
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20080610-OYT8T00220.htm
経済協力開発機構(OECD)などが、大学ランキングについて、各国の高等教育への影響を調べている。
この調査で来日した高等教育の専門家、アイルランド・ダブリン工科大のエレン・ハゼルコーン副学長は「ランキングの過信は禁物」と警鐘を鳴らした。
最近は、英国の大衆紙がアイルランドを含むランクを発表、ポーランドやチェコでも始まるなど、ヨーロッパ諸国にも大学ランキングが広がっているという。この結果、「順位が上がると学生や資金が集まるので、どの大学も順位を気にするようになった。産業界でも、英国では、ある順位以上の大学の学生しか採用しない企業が現れた」。
また、経済同様、高等教育のグローバル化が進む中、「留学生獲得のため、大学は世界での順位を上げようとする。チェコの大学は、ドイツ語だけではなく、英語での授業プログラムも導入するようになった」。
しかし、ランキングには問題も多いという。「データの集め方が不正確だったり、総合順位で比較する傾向が強いため、一つ一つの大学の良さが評価されなかったりする。その点、日本のメディアによるランキングは、多様な基準を用いて多面的に評価しようとするところがよい」
順位の結果に、大学も政府も一喜一憂すべきでないという。「大学が自校の改善のために評価結果を用いるのはよいが、順位アップを目標にすべきではない。政府は、国民がランキングを過信しないように、大学に関する多様な情報を発信する責任がある」
国際調査は、ドイツやオーストラリアでも実施され、ハゼルコーン氏らの手で分析が進められる。(石塚公康)
大学ランキング 1980年代後半に米国の雑誌「USニューズ」が始めたのが、本格的なものでは最初。日本でも90年代から、雑誌の特集や書籍の出版がされるようになった。21世紀に入ると、タイムズ・ハイアー社(英国)や上海交通大学(中国)、「ニューズウィーク」誌(米国)が世界ランキングを発表。昨年のタイムズでは、日本では東大の17位が最高だった。
専門家が警鐘 OECD、各国影響調査
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20080610-OYT8T00220.htm
経済協力開発機構(OECD)などが、大学ランキングについて、各国の高等教育への影響を調べている。
この調査で来日した高等教育の専門家、アイルランド・ダブリン工科大のエレン・ハゼルコーン副学長は「ランキングの過信は禁物」と警鐘を鳴らした。
最近は、英国の大衆紙がアイルランドを含むランクを発表、ポーランドやチェコでも始まるなど、ヨーロッパ諸国にも大学ランキングが広がっているという。この結果、「順位が上がると学生や資金が集まるので、どの大学も順位を気にするようになった。産業界でも、英国では、ある順位以上の大学の学生しか採用しない企業が現れた」。
また、経済同様、高等教育のグローバル化が進む中、「留学生獲得のため、大学は世界での順位を上げようとする。チェコの大学は、ドイツ語だけではなく、英語での授業プログラムも導入するようになった」。
しかし、ランキングには問題も多いという。「データの集め方が不正確だったり、総合順位で比較する傾向が強いため、一つ一つの大学の良さが評価されなかったりする。その点、日本のメディアによるランキングは、多様な基準を用いて多面的に評価しようとするところがよい」
順位の結果に、大学も政府も一喜一憂すべきでないという。「大学が自校の改善のために評価結果を用いるのはよいが、順位アップを目標にすべきではない。政府は、国民がランキングを過信しないように、大学に関する多様な情報を発信する責任がある」
国際調査は、ドイツやオーストラリアでも実施され、ハゼルコーン氏らの手で分析が進められる。(石塚公康)
大学ランキング 1980年代後半に米国の雑誌「USニューズ」が始めたのが、本格的なものでは最初。日本でも90年代から、雑誌の特集や書籍の出版がされるようになった。21世紀に入ると、タイムズ・ハイアー社(英国)や上海交通大学(中国)、「ニューズウィーク」誌(米国)が世界ランキングを発表。昨年のタイムズでは、日本では東大の17位が最高だった。
08年度中国大学ランキング発表 清華大と北京大はトップ2
http://www.asahi.com/international/jinmin/TKY200806110166.html
2008年度大学ランキングで1位、2位を争うのはどちらか? 清華大学、北京大学が確実に引き続き1位と2位の座を獲得した。全国大学統一入試が終了したばかりの10日、中国の教育専門の大手ポータルサイト「網大」(www.netbig.com)が深センで2008年中国大学ランキングを発表した。「網大」は1999年に始めて中国大学総合ランキングを公表し、今回はその第10回目となる。「南方日報」が伝えた。
清華大、北京大の地位は揺るぎがたいが、総合ランキングの中では、第3位から第10位まではある種の「動態性均衡」の状態にあり、昨年第5位の浙江大学は南京大学と復旦大学を追い越して第3位になった。中国科学技術大学、南京大学、復旦大学、上海交通大学、北京師範大学、哈爾濱工業大学、南開大学、中国人民大学(並列を含む)が第4位から第10位までに連なる。昨年、10位だった中山大学は今年は18位になった。
http://www.asahi.com/international/jinmin/TKY200806110166.html
2008年度大学ランキングで1位、2位を争うのはどちらか? 清華大学、北京大学が確実に引き続き1位と2位の座を獲得した。全国大学統一入試が終了したばかりの10日、中国の教育専門の大手ポータルサイト「網大」(www.netbig.com)が深センで2008年中国大学ランキングを発表した。「網大」は1999年に始めて中国大学総合ランキングを公表し、今回はその第10回目となる。「南方日報」が伝えた。
清華大、北京大の地位は揺るぎがたいが、総合ランキングの中では、第3位から第10位まではある種の「動態性均衡」の状態にあり、昨年第5位の浙江大学は南京大学と復旦大学を追い越して第3位になった。中国科学技術大学、南京大学、復旦大学、上海交通大学、北京師範大学、哈爾濱工業大学、南開大学、中国人民大学(並列を含む)が第4位から第10位までに連なる。昨年、10位だった中山大学は今年は18位になった。
英国大学ランキング、総合1位はオックスフォード
2008-06-20 15:00:07
http://www.web-tab.jp/article/2994
【ロンドン 6月19日 IANS】英国で最も優良な大学はオックスフォード―英国紙タイムズ編集による国内大学ガイド本「Times Good University Guide 2009」のランキングで発表された。2位はケンブリッジ大学だった。
同ガイドでは「学生の満足度」、「研究成果」、「在籍する学生と指導者の比率」、「設備投資額」、「入学基準」、「修業率」、「卒業後の進路」などの項目について各大学が評価され、総合ランキングが決定されている。
今年もオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、インペリアル・カレッジ・ロンドンの「御三家」がトップ3。1994年に設立された「ラッセル・グループ(訳注:大規模な研究型大学20校で構成されている)」に所属する大学が上位に名を連ねている。
多くの伝統校が名を連ねる「ラッセル・グループ」。グループに所属する大学が上位を占めた背景について、同ガイドの編集に携わったジョン・オリアリー氏は「学生の確保における学校間での競争が激しくなっています。伝統校は高い地位を保つために、レベルアップに努めているのです」と説明する。
1位のオックスフォード大学と2位のケンブリッジ大学の差はわずかだった。オックスフォード大学は「設備投資額」の項目でケンブリッジ大学を上回っている。(c)IANS
2008-06-20 15:00:07
http://www.web-tab.jp/article/2994
【ロンドン 6月19日 IANS】英国で最も優良な大学はオックスフォード―英国紙タイムズ編集による国内大学ガイド本「Times Good University Guide 2009」のランキングで発表された。2位はケンブリッジ大学だった。
同ガイドでは「学生の満足度」、「研究成果」、「在籍する学生と指導者の比率」、「設備投資額」、「入学基準」、「修業率」、「卒業後の進路」などの項目について各大学が評価され、総合ランキングが決定されている。
今年もオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、インペリアル・カレッジ・ロンドンの「御三家」がトップ3。1994年に設立された「ラッセル・グループ(訳注:大規模な研究型大学20校で構成されている)」に所属する大学が上位に名を連ねている。
多くの伝統校が名を連ねる「ラッセル・グループ」。グループに所属する大学が上位を占めた背景について、同ガイドの編集に携わったジョン・オリアリー氏は「学生の確保における学校間での競争が激しくなっています。伝統校は高い地位を保つために、レベルアップに努めているのです」と説明する。
1位のオックスフォード大学と2位のケンブリッジ大学の差はわずかだった。オックスフォード大学は「設備投資額」の項目でケンブリッジ大学を上回っている。(c)IANS
竹中平蔵(慶應義塾大学教授 グローバルセキュリティ研究所所長)、上田晋也(タレント)
【第16回】 2008年07月28日
大学改革で日本は強くなる!
大学教授の給料を9ヵ月分にせよ!
http://diamond.jp/series/nippon/10016/
上田 今回のテーマは「日本の大学」についてです。まず、世界における日本の大学の位置づけを確認しておきましょう。
右の表はイギリスの大学情報誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・サプリメント」が発表した世界の大学ランキングです。これを見ると、東京大学が17位、慶応大学が161位、早稲田大学が180位にランク付けされています。この結果を見て、どう思われますか?
竹中 私が教鞭を執っている慶応大学は去年120位で、今回はトップ100入りを期待していたのですが、残念ですね。ちなみにトップ100に日本の大学は4校ランクインしています。
上田 日本の大学はもっと優秀なのかと思っていました。ちなみにこの評価の基準はいったい何ですか?
竹中 具体的には6つの分野について評価されています。「引用論文数」などの客観指標と「専門家の意見」という主観的な指標をミックスして評価するのがポイントです。客観的な数字だけでは偏ってしまうので主観的な判断を混ぜるのですが、そうなるとどうしてもアメリカやヨーロッパの専門家の意見が増え、その地域の大学が圧倒的に有利になってしまう。だから、客観指標だけで判断すれば、日本の大学のランクはもう少し上がるでしょう。
上田 大学のレベルは、国の経済に影響を及ぼすのでしょうか?
竹中 大学は「労働市場に優秀な人材を送り出す」という重要な役割を担っています。実際、欧米の大学の強さと経済の強さを比較すれば、やはり関連性は高いと言えます。現在の日本経済は知識経済で、知識やノウハウ、技術力が発展するとそれに比例して経済も強くなる傾向があります。そういう意味でも、経済を強くするには強い大学が必要でしょうね。
今年1月に開かれたダボス会議で、フランスのフィヨン首相は「5年以内にフランス国内の大学を10校ランクインさせてみせる」と明言しました。これは大学を強くすることでフランス経済を強くするという政治的リーダーの意思表明です。
上田 日本の大学のどこに問題があると思いますか?
竹中 まず、海外と比べて教育に対する情熱が低い。教育は国がタダでやってくれるという意識がありますが、クオリティの高い教育にはお金をかけて、教える側も相当の努力をしなければなりません。「教えるほうも教えられるほうも真剣勝負」という意識が海外の一流大学は徹底しています。
私がハーバード大学生だったとき、学生たちが授業中に辞書を引けばすぐにわかるような初歩的な質問をバンバンするんです。日本人から見ると、「ノーベル賞レベルの学者にそんな質問するなよ」と思うけど、教授のほうも必死で学生の質問に答える。まさに「教授と学生の真剣勝負」であり、海外と日本の違いを感じましたね。
教授は「給料9ヵ月制」を受け入れ
切磋琢磨せよ!
上田 では、日本の大学のランキングを上げるために必要なことはなんだと思いますか?
竹中 私なら、「大学教授の給料を9ヵ月分にする」ことを提案しますね。アメリカの大学はすでにこのようなシステムになっており、あとの3ヵ月分は教授自身が学外などで稼いでくるんです。
【第16回】 2008年07月28日
大学改革で日本は強くなる!
大学教授の給料を9ヵ月分にせよ!
http://diamond.jp/series/nippon/10016/
上田 今回のテーマは「日本の大学」についてです。まず、世界における日本の大学の位置づけを確認しておきましょう。
右の表はイギリスの大学情報誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・サプリメント」が発表した世界の大学ランキングです。これを見ると、東京大学が17位、慶応大学が161位、早稲田大学が180位にランク付けされています。この結果を見て、どう思われますか?
竹中 私が教鞭を執っている慶応大学は去年120位で、今回はトップ100入りを期待していたのですが、残念ですね。ちなみにトップ100に日本の大学は4校ランクインしています。
上田 日本の大学はもっと優秀なのかと思っていました。ちなみにこの評価の基準はいったい何ですか?
竹中 具体的には6つの分野について評価されています。「引用論文数」などの客観指標と「専門家の意見」という主観的な指標をミックスして評価するのがポイントです。客観的な数字だけでは偏ってしまうので主観的な判断を混ぜるのですが、そうなるとどうしてもアメリカやヨーロッパの専門家の意見が増え、その地域の大学が圧倒的に有利になってしまう。だから、客観指標だけで判断すれば、日本の大学のランクはもう少し上がるでしょう。
上田 大学のレベルは、国の経済に影響を及ぼすのでしょうか?
竹中 大学は「労働市場に優秀な人材を送り出す」という重要な役割を担っています。実際、欧米の大学の強さと経済の強さを比較すれば、やはり関連性は高いと言えます。現在の日本経済は知識経済で、知識やノウハウ、技術力が発展するとそれに比例して経済も強くなる傾向があります。そういう意味でも、経済を強くするには強い大学が必要でしょうね。
今年1月に開かれたダボス会議で、フランスのフィヨン首相は「5年以内にフランス国内の大学を10校ランクインさせてみせる」と明言しました。これは大学を強くすることでフランス経済を強くするという政治的リーダーの意思表明です。
上田 日本の大学のどこに問題があると思いますか?
竹中 まず、海外と比べて教育に対する情熱が低い。教育は国がタダでやってくれるという意識がありますが、クオリティの高い教育にはお金をかけて、教える側も相当の努力をしなければなりません。「教えるほうも教えられるほうも真剣勝負」という意識が海外の一流大学は徹底しています。
私がハーバード大学生だったとき、学生たちが授業中に辞書を引けばすぐにわかるような初歩的な質問をバンバンするんです。日本人から見ると、「ノーベル賞レベルの学者にそんな質問するなよ」と思うけど、教授のほうも必死で学生の質問に答える。まさに「教授と学生の真剣勝負」であり、海外と日本の違いを感じましたね。
教授は「給料9ヵ月制」を受け入れ
切磋琢磨せよ!
上田 では、日本の大学のランキングを上げるために必要なことはなんだと思いますか?
竹中 私なら、「大学教授の給料を9ヵ月分にする」ことを提案しますね。アメリカの大学はすでにこのようなシステムになっており、あとの3ヵ月分は教授自身が学外などで稼いでくるんです。
大学教授の給料を9ヵ月分にせよ!
たとえば、世界的な業績を上げている教授は、夏休みの3ヵ月間世界中から引っ張りだこです。でも、あまり優秀でない教授はどこからも呼ばれませんから、高校生相手にアルバイトをしたりする。そうなれば、「もうちょっと頑張らなくては」というメカニズムが働くようになります。
また、欧米の大学は「競争の中からよいものができる」という大原則が成り立っています。日本の大学にはありませんが、アメリカの大学のほとんどは学生が教授を評価するシステムをとっています。評価の低い教授は給料を下げられてしまうので、双方に厳しい緊張関係がある。
上田 つまり、「日本の大学は甘やかされている」と。
竹中 その通りです。特に国立大学は文部科学省から支給される補助金で運営されていますが、教育の質には関係なく支給されます。もちろん頑張っている大学もありますが、善意だけで教育は向上しません。
上田 たとえば、給与を9ヵ月分制にしてしまうと、地方大学や注目されにくい分野を専攻している教授は困ってしまいませんか?
竹中 逆に「困ってもらうことが重要」なんです。そうすれば努力せざるを得なくなる。厳しい意見かもしれませんが、大学はそうやって力をつけて行くしかないでしょう。
さらに学生の意識向上も必要です。以前、台湾の国立大学生に「あなたの大学のライバルはどこか」と質問したとき、全員が「シンガポール国立大学」と答えました。おそらく同じ質問を日本の学生にすれば、京大の学生なら東大、早稲田の学生なら慶応とでも答えるでしょう。今の時代、そんなレベルではダメなんです。日本の学生は、「大学同士が国際的に競争している」ということをよく認識しなければなりません。
ただ、ひとつだけ弁護しますが、日本の国立大学制度は、戦後大学や教育の大衆化に重要な役割を果たしています。この制度のおかげで、和歌山県生まれの私も大学に進学することができた。とはいえ、大学制度は「国際化」という次のステップへ進むべき時期に来ています。
たとえば、世界的な業績を上げている教授は、夏休みの3ヵ月間世界中から引っ張りだこです。でも、あまり優秀でない教授はどこからも呼ばれませんから、高校生相手にアルバイトをしたりする。そうなれば、「もうちょっと頑張らなくては」というメカニズムが働くようになります。
また、欧米の大学は「競争の中からよいものができる」という大原則が成り立っています。日本の大学にはありませんが、アメリカの大学のほとんどは学生が教授を評価するシステムをとっています。評価の低い教授は給料を下げられてしまうので、双方に厳しい緊張関係がある。
上田 つまり、「日本の大学は甘やかされている」と。
竹中 その通りです。特に国立大学は文部科学省から支給される補助金で運営されていますが、教育の質には関係なく支給されます。もちろん頑張っている大学もありますが、善意だけで教育は向上しません。
上田 たとえば、給与を9ヵ月分制にしてしまうと、地方大学や注目されにくい分野を専攻している教授は困ってしまいませんか?
竹中 逆に「困ってもらうことが重要」なんです。そうすれば努力せざるを得なくなる。厳しい意見かもしれませんが、大学はそうやって力をつけて行くしかないでしょう。
さらに学生の意識向上も必要です。以前、台湾の国立大学生に「あなたの大学のライバルはどこか」と質問したとき、全員が「シンガポール国立大学」と答えました。おそらく同じ質問を日本の学生にすれば、京大の学生なら東大、早稲田の学生なら慶応とでも答えるでしょう。今の時代、そんなレベルではダメなんです。日本の学生は、「大学同士が国際的に競争している」ということをよく認識しなければなりません。
ただ、ひとつだけ弁護しますが、日本の国立大学制度は、戦後大学や教育の大衆化に重要な役割を果たしています。この制度のおかげで、和歌山県生まれの私も大学に進学することができた。とはいえ、大学制度は「国際化」という次のステップへ進むべき時期に来ています。
これからは自治ではなく
「マネジメント」の時代
上田 それでは、日本の「大学改革」に必要なポイントを教えてください。
竹中 まず、第1のポイントは教育にお金をかけるべきこと。そう言うと、「教育費をこれ以上上げるのか」という反論も出るでしょうが、日本の教育費が高い原因は、主に塾の費用や地方大学生の下宿代などです。
つまり、教育にかかる「関連費用」が高いのであって、本来の「教育」そのものにはそこまでお金をかけていないんです。たとえば、慶応大学の文系の場合、1年間の授業料は約100万円ですが、ハーバード大学、イェール大学はその3倍の約300万円もかかります。さらに日本の大学は、講義の仕方も安上がりです。日本の講義は百人単位ですが、ハーバード大学では30人以下が原則。学生が何百人もいれば、コストがかからないぶん、教授が学生一人ひとりの理解度を把握することが困難になります。しかし、30人程度だと、コストはかかるけどきめ細かい講義ができる。そういう面でも教育の質は違ってきますよね。
上田 よい教育にはどうしてもお金がかかってしまうことを、教育を受ける側も提供する側も認識しなければいけないわけですね。
竹中 第2のポイントは、教育の中身そのものの見直しです。現代の日本人にとっては、「勉強イコール暗記」ですから、暗記力のいい人は非常に楽です。ところが、実際社会に出てみると、暗記力が役に立つ場面はほとんどない。物事を「暗記」させるのではなく、「創造的な思考力」を持たせることこそが、教育の本質なんです。これからは、伝統的な知識の切り売りではなく、創造力を養う教育を施さなくてはなりません。
そして第3のポイントは大学のマネジメント。よく言われる「大学の自治」とは、戦前、大学に国家の介入があり学問の自由が奪われたことに対する反省から生まれましたが、現在必要なのは「自治」ではなく「経営」です。
たとえば、一般的に教授会で決められる大学経営は、教授たちの都合のよい環境になってしまいがちです。一般企業でも、「会社の経営は社員で決めろ」なんて言いませんよね。経営は経営者が決めるべきであって、それが「マネジメント」なんです。日本の大学にも同じ仕組みが必要です。
上田 大学同士を競争させることについては、「大学格差や学生の教育格差につながるのではないか」という反発意見も出てきそうですが。
竹中 日本では少子化の影響で年々学生の数が減り、定員割れの大学も増えてきています。そんな時代だからこそ、日本の大学は「優勝劣敗の競争」を行ない、互いに切磋琢磨すべきです。「一時的にせよ格差が広がるから改革はしない」という考えでは、日本の大学はいつまでたっても世界のトップ100にもランク入りできないでしょう。
上田 なるほど。前回採り上げたスポーツ界だけでなく、日本の大学も「世界ランク入り」を目指して頑張ってほしいところですね。
「マネジメント」の時代
上田 それでは、日本の「大学改革」に必要なポイントを教えてください。
竹中 まず、第1のポイントは教育にお金をかけるべきこと。そう言うと、「教育費をこれ以上上げるのか」という反論も出るでしょうが、日本の教育費が高い原因は、主に塾の費用や地方大学生の下宿代などです。
つまり、教育にかかる「関連費用」が高いのであって、本来の「教育」そのものにはそこまでお金をかけていないんです。たとえば、慶応大学の文系の場合、1年間の授業料は約100万円ですが、ハーバード大学、イェール大学はその3倍の約300万円もかかります。さらに日本の大学は、講義の仕方も安上がりです。日本の講義は百人単位ですが、ハーバード大学では30人以下が原則。学生が何百人もいれば、コストがかからないぶん、教授が学生一人ひとりの理解度を把握することが困難になります。しかし、30人程度だと、コストはかかるけどきめ細かい講義ができる。そういう面でも教育の質は違ってきますよね。
上田 よい教育にはどうしてもお金がかかってしまうことを、教育を受ける側も提供する側も認識しなければいけないわけですね。
竹中 第2のポイントは、教育の中身そのものの見直しです。現代の日本人にとっては、「勉強イコール暗記」ですから、暗記力のいい人は非常に楽です。ところが、実際社会に出てみると、暗記力が役に立つ場面はほとんどない。物事を「暗記」させるのではなく、「創造的な思考力」を持たせることこそが、教育の本質なんです。これからは、伝統的な知識の切り売りではなく、創造力を養う教育を施さなくてはなりません。
そして第3のポイントは大学のマネジメント。よく言われる「大学の自治」とは、戦前、大学に国家の介入があり学問の自由が奪われたことに対する反省から生まれましたが、現在必要なのは「自治」ではなく「経営」です。
たとえば、一般的に教授会で決められる大学経営は、教授たちの都合のよい環境になってしまいがちです。一般企業でも、「会社の経営は社員で決めろ」なんて言いませんよね。経営は経営者が決めるべきであって、それが「マネジメント」なんです。日本の大学にも同じ仕組みが必要です。
上田 大学同士を競争させることについては、「大学格差や学生の教育格差につながるのではないか」という反発意見も出てきそうですが。
竹中 日本では少子化の影響で年々学生の数が減り、定員割れの大学も増えてきています。そんな時代だからこそ、日本の大学は「優勝劣敗の競争」を行ない、互いに切磋琢磨すべきです。「一時的にせよ格差が広がるから改革はしない」という考えでは、日本の大学はいつまでたっても世界のトップ100にもランク入りできないでしょう。
上田 なるほど。前回採り上げたスポーツ界だけでなく、日本の大学も「世界ランク入り」を目指して頑張ってほしいところですね。
東海地区大学ランキング 「中京大」知名度1位の衝撃
2008/8/ 1
http://www.j-cast.com/2008/08/01024519.html
さまざまなメディアが「大学ランキング」を発表するなか、高校生へのアンケートをまとめた「知名度ランキング」で、意外な結果が出た。全国的に早稲田大学が慶應義塾大学を大きく引き離して圧倒的な強さを見せているほか、東海地区では、「中京大」が1位にランクされた。どのような事情があるのだろうか。
在学生6人が北京五輪の代表選手
調査は進学情報サイトなどを運営するリクルート(東京都千代田区)が2008年7月31日に発表したもので、同社が発行する進学情報誌に会員登録した高校3年生約8000人から得た結果をもとに集計、「知名度」と「志願度」をランキング化した。調査は関東・関西・東海の3エリアの高3を対象に行われ、集計・分析もエリアごとに行われた。
衝撃的な結果が出たのが、東海地方。「知名度」ランキングで、名門と言われる名古屋大学(3位)や南山大学(8位)を押さえて1位に輝いたのは、中京大学だ。同大は、「志願度」でも2位にランクインしており、名古屋出身者からも、「意外」との声があがっている。これに対するリクルート側の説明はこうだ。
「早大と同様に、定員規模が大きい、ということはあると思います。また、学部や学科の新設・改組が多いですので、その分高校生に大学の情報が伝わっているのではないでしょうか」
大学に動きが多いほど、結果として大学PRにもなる、との見方だ。ただし、
「これが一番大きいのかも知れませんが…」
と断ったうえで、こうも話す。
「やっぱり、スポーツ選手を多く輩出していますので、メディアへの露出が増えますよね」
中京大からは在学生6人が北京五輪の代表選手として選ばれているほか、フィギュアスケートの浅田真央選手の姉の浅田舞選手や、安藤美姫選手が同大に在籍していることも広く知られている。
リクルートでは、調査結果を踏まえて、
「『全入時代』を控えて、大学は『高校生から選ばれる側』になりつつある。受験生に伝えるべきことをきちんと伝え、他大学との差別化が重要だ」
と話す。
「志願度」でも、慶大は早大に大きく水をあけられている
また早稲田大学の圧倒的な知名度も目を引く。各地の知名度ランキングを見ると、関東地区の1位に続いて、東海地区では旧7帝大の名古屋大学(3位)を押しのけて2位にランクイン。関西地区でも、地元の名門である関西学院大学(9位)や大阪大学(10位)を上回る8位だ。一方「ライバル」慶応はどうかというと、関東では、明治、東大、青山学院に続いて5位と、それなりに健闘しているものの、東海地区では11位で、関西地区にいたっては、ランクインすらしなかった。さらに、「知名度」のみならず、「志願度」でも、慶大は早大に大きく水をあけられている、という状況だ。
リクルートでは、その原因を
「早大は定員規模が大きく、学部ごとの偏差値の幅が大きいんです。その一方、で慶大は、定員規模が比較的小さいということが言えると思います」
と説明。高校生にとって「自分が進学できる気がするか」どうかが、「志願度」のみならず知名度の高低に影響してくる、との見方だ。
2008/8/ 1
http://www.j-cast.com/2008/08/01024519.html
さまざまなメディアが「大学ランキング」を発表するなか、高校生へのアンケートをまとめた「知名度ランキング」で、意外な結果が出た。全国的に早稲田大学が慶應義塾大学を大きく引き離して圧倒的な強さを見せているほか、東海地区では、「中京大」が1位にランクされた。どのような事情があるのだろうか。
在学生6人が北京五輪の代表選手
調査は進学情報サイトなどを運営するリクルート(東京都千代田区)が2008年7月31日に発表したもので、同社が発行する進学情報誌に会員登録した高校3年生約8000人から得た結果をもとに集計、「知名度」と「志願度」をランキング化した。調査は関東・関西・東海の3エリアの高3を対象に行われ、集計・分析もエリアごとに行われた。
衝撃的な結果が出たのが、東海地方。「知名度」ランキングで、名門と言われる名古屋大学(3位)や南山大学(8位)を押さえて1位に輝いたのは、中京大学だ。同大は、「志願度」でも2位にランクインしており、名古屋出身者からも、「意外」との声があがっている。これに対するリクルート側の説明はこうだ。
「早大と同様に、定員規模が大きい、ということはあると思います。また、学部や学科の新設・改組が多いですので、その分高校生に大学の情報が伝わっているのではないでしょうか」
大学に動きが多いほど、結果として大学PRにもなる、との見方だ。ただし、
「これが一番大きいのかも知れませんが…」
と断ったうえで、こうも話す。
「やっぱり、スポーツ選手を多く輩出していますので、メディアへの露出が増えますよね」
中京大からは在学生6人が北京五輪の代表選手として選ばれているほか、フィギュアスケートの浅田真央選手の姉の浅田舞選手や、安藤美姫選手が同大に在籍していることも広く知られている。
リクルートでは、調査結果を踏まえて、
「『全入時代』を控えて、大学は『高校生から選ばれる側』になりつつある。受験生に伝えるべきことをきちんと伝え、他大学との差別化が重要だ」
と話す。
「志願度」でも、慶大は早大に大きく水をあけられている
また早稲田大学の圧倒的な知名度も目を引く。各地の知名度ランキングを見ると、関東地区の1位に続いて、東海地区では旧7帝大の名古屋大学(3位)を押しのけて2位にランクイン。関西地区でも、地元の名門である関西学院大学(9位)や大阪大学(10位)を上回る8位だ。一方「ライバル」慶応はどうかというと、関東では、明治、東大、青山学院に続いて5位と、それなりに健闘しているものの、東海地区では11位で、関西地区にいたっては、ランクインすらしなかった。さらに、「知名度」のみならず、「志願度」でも、慶大は早大に大きく水をあけられている、という状況だ。
リクルートでは、その原因を
「早大は定員規模が大きく、学部ごとの偏差値の幅が大きいんです。その一方、で慶大は、定員規模が比較的小さいということが言えると思います」
と説明。高校生にとって「自分が進学できる気がするか」どうかが、「志願度」のみならず知名度の高低に影響してくる、との見方だ。
東は早大、西は関西大 高3に大学の知名度調査
http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008073101000666.html
「知名度1位、関東は早大、東海は中京大、関西は関西大」。高校生に進学情報を提供しているリクルート(東京)が高校3年生を対象に大学の知名度やイメージを調査し31日、ランキングを発表した。
同社が発行する進学情報誌の会員登録者で関東、東海、関西の3エリアの高3を対象に調査。約8000人から回答があり、地域別に分析した。
関東エリアで知名度96・6%と1位だった早大は東海で2位の89・6%、関西でも8位の85・9%。3エリアすべてで10位以内にランクインした唯一の大学となった。中京大は東海で知名度91・4%、関西大は関西で95・6%だった。
イメージランキングでは、「就職に有利」1位は東大(関東、東海)と京大(関西)。「おしゃれ」は青山学院大(関東、東海)と関西学院大(関西)だった。
リクルートは「大学全入時代を迎え、大学は『選ぶ側から選ばれる側』へと変わりつつある。受験生に伝えたいことをきちんと伝え、ほかの大学との差別化を図ってほしい」と話している。
http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008073101000666.html
「知名度1位、関東は早大、東海は中京大、関西は関西大」。高校生に進学情報を提供しているリクルート(東京)が高校3年生を対象に大学の知名度やイメージを調査し31日、ランキングを発表した。
同社が発行する進学情報誌の会員登録者で関東、東海、関西の3エリアの高3を対象に調査。約8000人から回答があり、地域別に分析した。
関東エリアで知名度96・6%と1位だった早大は東海で2位の89・6%、関西でも8位の85・9%。3エリアすべてで10位以内にランクインした唯一の大学となった。中京大は東海で知名度91・4%、関西大は関西で95・6%だった。
イメージランキングでは、「就職に有利」1位は東大(関東、東海)と京大(関西)。「おしゃれ」は青山学院大(関東、東海)と関西学院大(関西)だった。
リクルートは「大学全入時代を迎え、大学は『選ぶ側から選ばれる側』へと変わりつつある。受験生に伝えたいことをきちんと伝え、ほかの大学との差別化を図ってほしい」と話している。
全米一の「パーティー大学」は? 大学生活ランキング発表
http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200807290014.html
フロリダ州ゲインズビル――全米で最もパーティー好きな大学はどこか――。米教育サービス会社のプリンストン・レビューは28日、全米368大学の学生生活や教育環境について調査したランキングを発表した。
同社は学生12万人のアンケートをもとに、教授、学食、学生寮、奨学金など62項目について毎年ランキングを作成している。なお、プリンストン大学とは無関係。
今年「パーティー大学」のタイトルに輝いたのはフロリダ大学だった。強豪チームがそろうスポーツの名門校として知られ、試合後の派手な祝賀会でも有名だ。パーティー大学のランキングでは過去15年間、常に上位20位に入っていたが、今年初めてウェストバージニア大学から首位を奪った。
フロリダ大学はバスケットボールの全米選手権で2006年と2007年に連覇、アメリカンフットボールの2006年シーズンでも優勝した実績を持つ。大学広報は、この実績がパーティー大学のタイトル獲得にも貢献したのだろうと指摘する。
ジャーナリズムと政治学を専攻する1年生のアリソン・ビレンジャーさん(17)は、入学して数週間しかたたないのにパーティーには事欠かないといい、「勉学にもパーティーにも熱心な学生が多い」と話した。
ちなみに今年は「学生が最も勉強しない大学」「スポーツ観戦に出かける学生が最も多い大学」のランキングでもフロリダ大学がトップに輝いた。ただし広報は、成績優秀な学生でないと同大には入学できないと強調している。
一方、「まじめ一筋の大学」のランキングは、ユタ州にあるブリガム・ヤング大学が11年連続で首位を守った。
このほかの項目では「教授陣」がマルベリー大学(バーモント州)、「学食のおいしさ」ではウィートンカレッジ(イリノイ州)、「学生寮」はロヨラカレッジ(メリーランド州)、「学資援助」と「キャンパスの美しさ」ではプリンストン大学(ニュージャージー州)が首位に選ばれた。
http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200807290014.html
フロリダ州ゲインズビル――全米で最もパーティー好きな大学はどこか――。米教育サービス会社のプリンストン・レビューは28日、全米368大学の学生生活や教育環境について調査したランキングを発表した。
同社は学生12万人のアンケートをもとに、教授、学食、学生寮、奨学金など62項目について毎年ランキングを作成している。なお、プリンストン大学とは無関係。
今年「パーティー大学」のタイトルに輝いたのはフロリダ大学だった。強豪チームがそろうスポーツの名門校として知られ、試合後の派手な祝賀会でも有名だ。パーティー大学のランキングでは過去15年間、常に上位20位に入っていたが、今年初めてウェストバージニア大学から首位を奪った。
フロリダ大学はバスケットボールの全米選手権で2006年と2007年に連覇、アメリカンフットボールの2006年シーズンでも優勝した実績を持つ。大学広報は、この実績がパーティー大学のタイトル獲得にも貢献したのだろうと指摘する。
ジャーナリズムと政治学を専攻する1年生のアリソン・ビレンジャーさん(17)は、入学して数週間しかたたないのにパーティーには事欠かないといい、「勉学にもパーティーにも熱心な学生が多い」と話した。
ちなみに今年は「学生が最も勉強しない大学」「スポーツ観戦に出かける学生が最も多い大学」のランキングでもフロリダ大学がトップに輝いた。ただし広報は、成績優秀な学生でないと同大には入学できないと強調している。
一方、「まじめ一筋の大学」のランキングは、ユタ州にあるブリガム・ヤング大学が11年連続で首位を守った。
このほかの項目では「教授陣」がマルベリー大学(バーモント州)、「学食のおいしさ」ではウィートンカレッジ(イリノイ州)、「学生寮」はロヨラカレッジ(メリーランド州)、「学資援助」と「キャンパスの美しさ」ではプリンストン大学(ニュージャージー州)が首位に選ばれた。
世界の大学ランキングで中国勢がじわじわ上昇
2008年08月07日 11:36 発信地:上海/中国
http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2501789/3191691
【8月7日 AFP】中国の上海交通大学(Shanghai Jiaotong University)が今月15日に発表する「世界の大学ランキング」では、米国の大学が依然として上位を占めているものの、中国の大学がじわじわと順位を上げている。
このランキングは、江沢民(Jiang Zemin)前国家主席の出身校でもある同大の高等教育研究所が、卒業生や研究員におけるノーベル賞受賞者数や権威ある学術専門誌に発表された論文の数などを基準に選定するもので、今年で6回目を数える。
中国の大学は、「アジア太平洋地域のトップ100」では18校がランクインし、前年の14校から増えた。しかし「世界のトップ100」へのランクインは今年も果たせず、19位に入った東京大学(Tokyo University)などアジアのトップ校には大きく遅れをとっている。
1位は今年もハーバード大学(Harvard University)で、2位はスタンフォード大学(Stanford University)、3位はカリフォルニア大学バークレー校(University of California Berkeley)だった。上位10校中8校を米国勢が占めるなか、英国のオックスフォード大学(Oxford University)は4位、ケンブリッジ大学(Cambridge University)は10位に食い込んだ。
世界ランキングにおける中国(香港除く)の最高位は223位の南京大学(Nanjing University)で、長らく中国の最高学府と考えられてきた北京大学(Peking University)を2ランク上回った。(c)AFP
2008年08月07日 11:36 発信地:上海/中国
http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2501789/3191691
【8月7日 AFP】中国の上海交通大学(Shanghai Jiaotong University)が今月15日に発表する「世界の大学ランキング」では、米国の大学が依然として上位を占めているものの、中国の大学がじわじわと順位を上げている。
このランキングは、江沢民(Jiang Zemin)前国家主席の出身校でもある同大の高等教育研究所が、卒業生や研究員におけるノーベル賞受賞者数や権威ある学術専門誌に発表された論文の数などを基準に選定するもので、今年で6回目を数える。
中国の大学は、「アジア太平洋地域のトップ100」では18校がランクインし、前年の14校から増えた。しかし「世界のトップ100」へのランクインは今年も果たせず、19位に入った東京大学(Tokyo University)などアジアのトップ校には大きく遅れをとっている。
1位は今年もハーバード大学(Harvard University)で、2位はスタンフォード大学(Stanford University)、3位はカリフォルニア大学バークレー校(University of California Berkeley)だった。上位10校中8校を米国勢が占めるなか、英国のオックスフォード大学(Oxford University)は4位、ケンブリッジ大学(Cambridge University)は10位に食い込んだ。
世界ランキングにおける中国(香港除く)の最高位は223位の南京大学(Nanjing University)で、長らく中国の最高学府と考えられてきた北京大学(Peking University)を2ランク上回った。(c)AFP
米国の大学ランキング、ハーバードが単独トップに返り咲き
http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200808220024.html
(AP) 米国のUSニューズ&ワールド・レポート誌による恒例の大学ランキングが22日、同誌のウェブサイトで発表され、ハーバード大学が単独トップに返り咲いた。1校が単独首位になるのは、12年ぶりとなる。
総合大学部門のランキング首位になったことについて、ハーバード大学は「このように評価してもらえることはありがたいが、大学入学を目指す人々にはランキングの順位ではなく、自分にとって必要な学問ができる大学を選ぶべきだ」と述べている。
昨年まで8年連続でハーバード大と首位に並んでいたプリンストン大学が2位となった。
3位はイェール大学、4位はマサチューセッツ工科大学(MIT)とスタンフォードが並んだ。
国公立大学のトップはカリフォルニア大学バークレー校の21位。
リベラル・アーツ大学部門では、アマースト大学がトップだった。
http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200808220024.html
(AP) 米国のUSニューズ&ワールド・レポート誌による恒例の大学ランキングが22日、同誌のウェブサイトで発表され、ハーバード大学が単独トップに返り咲いた。1校が単独首位になるのは、12年ぶりとなる。
総合大学部門のランキング首位になったことについて、ハーバード大学は「このように評価してもらえることはありがたいが、大学入学を目指す人々にはランキングの順位ではなく、自分にとって必要な学問ができる大学を選ぶべきだ」と述べている。
昨年まで8年連続でハーバード大と首位に並んでいたプリンストン大学が2位となった。
3位はイェール大学、4位はマサチューセッツ工科大学(MIT)とスタンフォードが並んだ。
国公立大学のトップはカリフォルニア大学バークレー校の21位。
リベラル・アーツ大学部門では、アマースト大学がトップだった。
1. Harvard University (Cambridge, Mass.)
2. Princeton University (Princeton, N.J.)
3. Yale University (New Haven, Conn.)
4. Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Mass.)
4. Stanford University (Stanford, Calif.)
6. California Institute of Technology (Pasadena, Calif.)
6. University of Pennsylvania (Philadelphia, Penn.)
8. Columbia University (New York, N.Y.)
8. Duke University (Durham, N.C.)
8. University of Chicago (Chicago, Ill.)
11. Dartmouth College (Hanover, N.H.)
12. Northwestern University (Evanston, Ill.)
12. Washington University (St. Louis, Mo.)
14. Cornell University (Ithaca, N.Y.)
15. Johns Hopkins University (Baltimore, Md.)
16. Brown University (Providence, R.I.)
17. Rice University (Houston, Texas)
18. Emory University (Atlanta, Ga.)
18. University of Notre Dame (Notre Dame, Ind.)
18. Vanderbilt University (Nashville, Tenn.)
21. University of California-Berkeley (Berkeley, Calif.)
22. Carnegie Mellon University (Pittsburgh, Penn.)
23. Georgetown University (Washington, D.C.)
23. University of Virginia (Charlottesville, Va.)
25. University of California-Los Angeles (Los Angeles, Calif.)
26. University of Michigan-Ann Arbor (Ann Arbor, Mich.)
27. University of Southern California (Los Angeles, Calif.)
28. Tufts University (Medford, Mass.)
28. Wake Forest University (Winston-Salem, N.C.)
30. University of North Carolina-Chapel Hill (Chapel Hill, N.C.)
31. Brandeis University (Waltham, Mass.)
32. College of William and Mary (Williamsburg, Va.)
33. New York University (New York, N.Y.)
34. Boston College (Chestnut Hill, Mass.)
35. Georgia Institute of Technology (Atlanta, Ga.)
35. Lehigh University (Bethlehem, Penn.)
35. University of California-San Diego (La Jolla, Calif.)
35. University of Rochester (Rochester, N.Y.)
35. University of Wisconsin-Madison (Madison, Wis.)
40. University of Illinois-Urbana-Champaign (Champaign, Ill.)
41. Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio)
41. Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, N.Y.)
41. University of Washington (Seattle, Wash.)
44. University of California-Davis (Davis, Calif.)
44. University of California-Irvine (Irvine, Calif.)
44. University of California-Santa Barbara (Santa Barbara, Calif.)
47. Pennsylvania State University-University Park (University Park, Penn.)
47. University of Texas-Austin (Austin, Texas)
49. University of Florida (Gainesville, Fla.)
50. Yeshiva University (New York, N.Y.)
http://www.cbsnews.com/stories/2008/08/22/fyi/main4374922.shtml
2. Princeton University (Princeton, N.J.)
3. Yale University (New Haven, Conn.)
4. Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Mass.)
4. Stanford University (Stanford, Calif.)
6. California Institute of Technology (Pasadena, Calif.)
6. University of Pennsylvania (Philadelphia, Penn.)
8. Columbia University (New York, N.Y.)
8. Duke University (Durham, N.C.)
8. University of Chicago (Chicago, Ill.)
11. Dartmouth College (Hanover, N.H.)
12. Northwestern University (Evanston, Ill.)
12. Washington University (St. Louis, Mo.)
14. Cornell University (Ithaca, N.Y.)
15. Johns Hopkins University (Baltimore, Md.)
16. Brown University (Providence, R.I.)
17. Rice University (Houston, Texas)
18. Emory University (Atlanta, Ga.)
18. University of Notre Dame (Notre Dame, Ind.)
18. Vanderbilt University (Nashville, Tenn.)
21. University of California-Berkeley (Berkeley, Calif.)
22. Carnegie Mellon University (Pittsburgh, Penn.)
23. Georgetown University (Washington, D.C.)
23. University of Virginia (Charlottesville, Va.)
25. University of California-Los Angeles (Los Angeles, Calif.)
26. University of Michigan-Ann Arbor (Ann Arbor, Mich.)
27. University of Southern California (Los Angeles, Calif.)
28. Tufts University (Medford, Mass.)
28. Wake Forest University (Winston-Salem, N.C.)
30. University of North Carolina-Chapel Hill (Chapel Hill, N.C.)
31. Brandeis University (Waltham, Mass.)
32. College of William and Mary (Williamsburg, Va.)
33. New York University (New York, N.Y.)
34. Boston College (Chestnut Hill, Mass.)
35. Georgia Institute of Technology (Atlanta, Ga.)
35. Lehigh University (Bethlehem, Penn.)
35. University of California-San Diego (La Jolla, Calif.)
35. University of Rochester (Rochester, N.Y.)
35. University of Wisconsin-Madison (Madison, Wis.)
40. University of Illinois-Urbana-Champaign (Champaign, Ill.)
41. Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio)
41. Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, N.Y.)
41. University of Washington (Seattle, Wash.)
44. University of California-Davis (Davis, Calif.)
44. University of California-Irvine (Irvine, Calif.)
44. University of California-Santa Barbara (Santa Barbara, Calif.)
47. Pennsylvania State University-University Park (University Park, Penn.)
47. University of Texas-Austin (Austin, Texas)
49. University of Florida (Gainesville, Fla.)
50. Yeshiva University (New York, N.Y.)
http://www.cbsnews.com/stories/2008/08/22/fyi/main4374922.shtml
世界大学ランキング、中国の大学は「トップ100」には遠く
中国: 科学時報[中国語]
2008年 8月20日
http://crds.jst.go.jp/watcher/data/495-007.html
2008年8月20日付けでアップされた「サイエンス・ネット」の記載では、ポイントとして以下のようなことが記されています。
8月15日、上海交通大学高等教育研究院は、2008年の「世界大学学術ランキング500(略称:ARWU)」を発表した。同ランキング(上位500校)には中国の大学30校がランクインしたものの、世界一流大学との差異は依然大きく、1校も100位内に入らなかった。
ARWUは、全世界の大学を対象とした多角的な指標による最初の総合ランキングであり、世界で最も広く使用されている。ARWUでは、研究成果や学術面での国際比較のために、教育の質、教員の質、研究成果等の側面について、ノーベル賞等受賞者の輩出率、Nature誌等への発表論文数、各分野で被引用度が最高レベルの教員数等により決定される。
今年のランキング1位はハーバード大学で、ARWUが最初に作成された2003年以来6年連続して首位となった。トップ10は米国の大学がほとんどを占める等米国の大学が優勢で、英国がこれに続く。アジア・太平洋地区の大学は総体的に振るわない。上位500校の大多数は先進国の大学であり、経済や科技、高等教育の実力が表されている。
ARWUにランクインする中国の大学は年々着実に増加しており、2003年は12校であったが、2008年は30校となった。しかし、中国の著名な大学(北大、清華大、上海交通大、南京大、等)は201位から302位の間に甘んじる。中国の名門大学が上位にランキングされないことについて、その研究成果の数的規模は大きい(SCI論文数は2,000件を超える)ものの、国際レベルでインパクトのあるオリジナリティの高い成果が乏しいことに原因があると上海交通大学研究員は分析する。
一方、ランキングそのものの意義、合理性についても議論が絶えない。これについてARWU作成に携わった研究員は、世界大学・学術ランキングは客観的に国際比較を可能とするところに特長があると話している。
中国: 科学時報[中国語]
2008年 8月20日
http://crds.jst.go.jp/watcher/data/495-007.html
2008年8月20日付けでアップされた「サイエンス・ネット」の記載では、ポイントとして以下のようなことが記されています。
8月15日、上海交通大学高等教育研究院は、2008年の「世界大学学術ランキング500(略称:ARWU)」を発表した。同ランキング(上位500校)には中国の大学30校がランクインしたものの、世界一流大学との差異は依然大きく、1校も100位内に入らなかった。
ARWUは、全世界の大学を対象とした多角的な指標による最初の総合ランキングであり、世界で最も広く使用されている。ARWUでは、研究成果や学術面での国際比較のために、教育の質、教員の質、研究成果等の側面について、ノーベル賞等受賞者の輩出率、Nature誌等への発表論文数、各分野で被引用度が最高レベルの教員数等により決定される。
今年のランキング1位はハーバード大学で、ARWUが最初に作成された2003年以来6年連続して首位となった。トップ10は米国の大学がほとんどを占める等米国の大学が優勢で、英国がこれに続く。アジア・太平洋地区の大学は総体的に振るわない。上位500校の大多数は先進国の大学であり、経済や科技、高等教育の実力が表されている。
ARWUにランクインする中国の大学は年々着実に増加しており、2003年は12校であったが、2008年は30校となった。しかし、中国の著名な大学(北大、清華大、上海交通大、南京大、等)は201位から302位の間に甘んじる。中国の名門大学が上位にランキングされないことについて、その研究成果の数的規模は大きい(SCI論文数は2,000件を超える)ものの、国際レベルでインパクトのあるオリジナリティの高い成果が乏しいことに原因があると上海交通大学研究員は分析する。
一方、ランキングそのものの意義、合理性についても議論が絶えない。これについてARWU作成に携わった研究員は、世界大学・学術ランキングは客観的に国際比較を可能とするところに特長があると話している。
上海交通大学
2008年「世界大学学術ランキング(ARWU)」
1 Harvard Univ
2 Stanford Univ
3 Univ California - Berkeley
4 Univ Cambridge
5 Massachusetts Inst Tech (MIT)
6 California Inst Tech
7 Columbia Univ
8 Princeton Univ
9 Univ Chicago
10 Univ Oxford
11 Yale Univ
12 Cornell Univ
13 Univ California - Los Angeles
14 Univ California - San Diego
15 Univ Pennsylvania
16 Univ Washington - Seattle
17 Univ Wisconsin - Madison
18 Univ California - San Francisco
19 Tokyo Univ
20 Johns Hopkins Univ
21 Univ Michigan - Ann Arbor
22 Univ Coll London
23 Kyoto Univ
24 Swiss Fed Inst Tech - Zurich
24 Univ Toronto
26 Univ Illinois - Urbana Champaign
27 Imperial Coll London
28 Univ Minnesota - Twin Cities
29 Washington Univ - St. Louis
30 Northwestern Univ
31 New York Univ
32 Duke Univ
32 Rockefeller Univ
34 Univ Colorado - Boulder
35 Univ British Columbia
36 Univ California - Santa Barbara
37 Univ Maryland - Coll Park
38 Univ North Carolina - Chapel Hill
39 Univ Texas - Austin
40 Univ Manchester
41 Univ Texas Southwestern Med Center
42 Pennsylvania State Univ - Univ Park
42 Univ Paris 06
42 Vanderbilt Univ
45 Univ Copenhagen
46 Univ California - Irvine
47 Univ Utrecht
48 Univ California - Davis
49 Univ Paris 11
50 Univ Southern California
51 Karolinska Inst Stockholm
52 Univ Pittsburgh - Pittsburgh
53 Univ Zurich
54 Rutgers State Univ - New Brunswick
55 Univ Edinburgh
55 Univ Munich
57 Tech Univ Munich
58 Univ Florida
59 Australian Natl Univ
60 McGill Univ
61 Univ Bristol
62 Carnegie Mellon Univ
62 Ohio State Univ - Columbus
64 Univ Oslo
65 Hebrew Univ Jerusalem
65 Purdue Univ - West Lafayette
67 Univ Heidelberg
68 Osaka Univ
68 Univ Helsinki
70 Moscow State Univ
71 Brown Univ
71 Uppsala Univ
73 Ecole Normale Super Paris
73 Univ Melbourne
73 Univ Rochester
76 Univ Leiden
77 Univ Arizona
77 Univ Sheffield
79 Tohoku Univ
79 Univ Utah
81 King's Coll London
82 Univ Nottingham
83 Boston Univ
83 Case Western Reserve Univ
83 Michigan State Univ
86 Stockholm Univ
87 Univ Basel
88 Texas A&M Univ - Coll Station
89 McMaster Univ
90 Univ Goettingen
91 Univ Birmingham
92 Indiana Univ - Bloomington
93 Aarhus Univ
93 Arizona State Univ - Tempe
95 Univ Virginia
96 Univ Freiburg
97 Lund Univ
97 Rice Univ
97 Univ Bonn
97 Univ Sydney
2008年「世界大学学術ランキング(ARWU)」
1 Harvard Univ
2 Stanford Univ
3 Univ California - Berkeley
4 Univ Cambridge
5 Massachusetts Inst Tech (MIT)
6 California Inst Tech
7 Columbia Univ
8 Princeton Univ
9 Univ Chicago
10 Univ Oxford
11 Yale Univ
12 Cornell Univ
13 Univ California - Los Angeles
14 Univ California - San Diego
15 Univ Pennsylvania
16 Univ Washington - Seattle
17 Univ Wisconsin - Madison
18 Univ California - San Francisco
19 Tokyo Univ
20 Johns Hopkins Univ
21 Univ Michigan - Ann Arbor
22 Univ Coll London
23 Kyoto Univ
24 Swiss Fed Inst Tech - Zurich
24 Univ Toronto
26 Univ Illinois - Urbana Champaign
27 Imperial Coll London
28 Univ Minnesota - Twin Cities
29 Washington Univ - St. Louis
30 Northwestern Univ
31 New York Univ
32 Duke Univ
32 Rockefeller Univ
34 Univ Colorado - Boulder
35 Univ British Columbia
36 Univ California - Santa Barbara
37 Univ Maryland - Coll Park
38 Univ North Carolina - Chapel Hill
39 Univ Texas - Austin
40 Univ Manchester
41 Univ Texas Southwestern Med Center
42 Pennsylvania State Univ - Univ Park
42 Univ Paris 06
42 Vanderbilt Univ
45 Univ Copenhagen
46 Univ California - Irvine
47 Univ Utrecht
48 Univ California - Davis
49 Univ Paris 11
50 Univ Southern California
51 Karolinska Inst Stockholm
52 Univ Pittsburgh - Pittsburgh
53 Univ Zurich
54 Rutgers State Univ - New Brunswick
55 Univ Edinburgh
55 Univ Munich
57 Tech Univ Munich
58 Univ Florida
59 Australian Natl Univ
60 McGill Univ
61 Univ Bristol
62 Carnegie Mellon Univ
62 Ohio State Univ - Columbus
64 Univ Oslo
65 Hebrew Univ Jerusalem
65 Purdue Univ - West Lafayette
67 Univ Heidelberg
68 Osaka Univ
68 Univ Helsinki
70 Moscow State Univ
71 Brown Univ
71 Uppsala Univ
73 Ecole Normale Super Paris
73 Univ Melbourne
73 Univ Rochester
76 Univ Leiden
77 Univ Arizona
77 Univ Sheffield
79 Tohoku Univ
79 Univ Utah
81 King's Coll London
82 Univ Nottingham
83 Boston Univ
83 Case Western Reserve Univ
83 Michigan State Univ
86 Stockholm Univ
87 Univ Basel
88 Texas A&M Univ - Coll Station
89 McMaster Univ
90 Univ Goettingen
91 Univ Birmingham
92 Indiana Univ - Bloomington
93 Aarhus Univ
93 Arizona State Univ - Tempe
95 Univ Virginia
96 Univ Freiburg
97 Lund Univ
97 Rice Univ
97 Univ Bonn
97 Univ Sydney
世界の大学ランキング 東大19位、京大23位
2008年9月11日
http://www.asahi.com/edu/news/TKY200809100287.html
中国の上海交通大学高等教育研究所が、「08年世界の大学学術ランキング」を発表した。東京大はアジアで1位、京都大は2位に入ったものの、世界レベルでは米国の大学に圧倒され、それぞれ19位、23位にとどまった。
研究所が03年から始めたもので、英タイムズ紙別冊高等教育版のランキングとともに世界的に有名なランキングの一つ。ノーベル賞、フィールズ賞を受賞した卒業生や教員数、各分野で引用回数が多い教員数、科学誌「ネイチャー」「サイエンス」への発表論文数などを得点化してランクづけしている。
それによると、1位は米ハーバード大、2位は米スタンフォード大、3位は米カリフォルニア大バークリー校で、18位までのうち、16校が米国の大学。昨年20位の東大は順位を一つ上げたが、22位の京大は一つ落とした。
日本でベスト100入りしたのは東大、京大のほか、大阪大(68位)と東北大(79位)の2校。200位までには、九州大、名古屋大、東京工業大、北海道大、筑波大も加わり、計9校が名を連ねた。(杉本潔)
2008年9月11日
http://www.asahi.com/edu/news/TKY200809100287.html
中国の上海交通大学高等教育研究所が、「08年世界の大学学術ランキング」を発表した。東京大はアジアで1位、京都大は2位に入ったものの、世界レベルでは米国の大学に圧倒され、それぞれ19位、23位にとどまった。
研究所が03年から始めたもので、英タイムズ紙別冊高等教育版のランキングとともに世界的に有名なランキングの一つ。ノーベル賞、フィールズ賞を受賞した卒業生や教員数、各分野で引用回数が多い教員数、科学誌「ネイチャー」「サイエンス」への発表論文数などを得点化してランクづけしている。
それによると、1位は米ハーバード大、2位は米スタンフォード大、3位は米カリフォルニア大バークリー校で、18位までのうち、16校が米国の大学。昨年20位の東大は順位を一つ上げたが、22位の京大は一つ落とした。
日本でベスト100入りしたのは東大、京大のほか、大阪大(68位)と東北大(79位)の2校。200位までには、九州大、名古屋大、東京工業大、北海道大、筑波大も加わり、計9校が名を連ねた。(杉本潔)
ノーベル賞に沸くが…日本の大学、トップ10入りなし
2008年10月10日14時39分
http://www.asahi.com/national/update/1010/TKY200810100155.html
英タイムズ紙別冊高等教育版などは9日、08年世界トップ200大学を発表した。日本からは東京大の19位が最高で、100位以内には4校。ノーベル賞の4人受賞にわく日本だが、大学では米英に水をあけられているようだ。
04年から始め、研究者による評価、論文の引用数など研究力を中心に、教育力、企業からの評価、留学生比率などで総合ランクを付けている。1位は米ハーバード、2位は米エール、3位は英ケンブリッジで、20位までに米国が13校、英国が4校入った。
日本勢では東大のほか京都が25位、大阪が44位、東京工業が61位。トップ200入りは計10校で昨年より1校減った。先日発表された上海交通大学高等教育研究所のランキングでも、100位以内は東大、京大、阪大、東北大の4校だった。
政府の教育再生会議は昨年6月の第2次報告で、10年以内に、国際ランキングで日本の大学が上位30校に5校は入ることを目指すとしている。
ノーベル物理学賞受賞者の江崎玲於奈・茨城県科学技術振興財団理事長は「欧米の大学では研究者は実力で評価される。研究力の違いが、ランキングにも反映したのではないか」と話している。(杉本潔)
■日本の大学の順位(英タイムズ紙別冊高等教育版などの「08年トップ200大学」から)
東京(19)、京都(25)、大阪(44)、東京工業(61)、東北(112)、名古屋(120)、九州(158)、北海道(174)、早稲田(180)、神戸(199)
2008年10月10日14時39分
http://www.asahi.com/national/update/1010/TKY200810100155.html
英タイムズ紙別冊高等教育版などは9日、08年世界トップ200大学を発表した。日本からは東京大の19位が最高で、100位以内には4校。ノーベル賞の4人受賞にわく日本だが、大学では米英に水をあけられているようだ。
04年から始め、研究者による評価、論文の引用数など研究力を中心に、教育力、企業からの評価、留学生比率などで総合ランクを付けている。1位は米ハーバード、2位は米エール、3位は英ケンブリッジで、20位までに米国が13校、英国が4校入った。
日本勢では東大のほか京都が25位、大阪が44位、東京工業が61位。トップ200入りは計10校で昨年より1校減った。先日発表された上海交通大学高等教育研究所のランキングでも、100位以内は東大、京大、阪大、東北大の4校だった。
政府の教育再生会議は昨年6月の第2次報告で、10年以内に、国際ランキングで日本の大学が上位30校に5校は入ることを目指すとしている。
ノーベル物理学賞受賞者の江崎玲於奈・茨城県科学技術振興財団理事長は「欧米の大学では研究者は実力で評価される。研究力の違いが、ランキングにも反映したのではないか」と話している。(杉本潔)
■日本の大学の順位(英タイムズ紙別冊高等教育版などの「08年トップ200大学」から)
東京(19)、京都(25)、大阪(44)、東京工業(61)、東北(112)、名古屋(120)、九州(158)、北海道(174)、早稲田(180)、神戸(199)
世界大学ランキング…東大19位、京大25位
【ロンドン=森千春】英ザ・タイムズ紙系の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エジュケーション・サプリメント(THES)」は9日、毎年恒例の「世界大学ランキング」を発表した。
世界中の大学の研究力、教育力などを評価し、トップ200を選ぶもので、米ハーバード大が同ランキング開始以来5年連続の1位となるなど、米英系優位の構図が続いている。
日本の大学では、東京大が19位で最高位。京都大25位、大阪大44位、東京工業大61位など、昨年より1校減の計10校がランキング入り。日本以外のアジア勢では、香港大26位、シンガポール国立大30位、北京大とソウル大が同率50位などとなっている。
上位20校を見ると、米国がエール大2位、カリフォルニア工科大5位など計13校、英国がケンブリッジ大3位など計4校で、米英両国で17校を占めた。同誌は、米国の大学の強みとして、同窓生、企業、慈善団体による「広範な資金提供」と、海外の優秀な学生が集まる傾向を指摘した。
同誌のランキングは、世界の大学関係者による相互評価や研究成果が論文に引用された回数、企業の人事担当者の評価などを総合して作成される。
(2008年10月11日10時25分 読売新聞)
【ロンドン=森千春】英ザ・タイムズ紙系の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エジュケーション・サプリメント(THES)」は9日、毎年恒例の「世界大学ランキング」を発表した。
世界中の大学の研究力、教育力などを評価し、トップ200を選ぶもので、米ハーバード大が同ランキング開始以来5年連続の1位となるなど、米英系優位の構図が続いている。
日本の大学では、東京大が19位で最高位。京都大25位、大阪大44位、東京工業大61位など、昨年より1校減の計10校がランキング入り。日本以外のアジア勢では、香港大26位、シンガポール国立大30位、北京大とソウル大が同率50位などとなっている。
上位20校を見ると、米国がエール大2位、カリフォルニア工科大5位など計13校、英国がケンブリッジ大3位など計4校で、米英両国で17校を占めた。同誌は、米国の大学の強みとして、同窓生、企業、慈善団体による「広範な資金提供」と、海外の優秀な学生が集まる傾向を指摘した。
同誌のランキングは、世界の大学関係者による相互評価や研究成果が論文に引用された回数、企業の人事担当者の評価などを総合して作成される。
(2008年10月11日10時25分 読売新聞)
【2008年10月14日 日本の大学が国際評価で見劣りするのは 】
http://scienceportal.jp/news/review/0810/0810141.html
英国のザ・タイムズ紙系列の専門誌「ザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・サプリメント」が9日に発表した、ことしの「世界のトップ200大学」に東京大学など日本の10大学が入っている。
上位にランクされた日本の大学を上位から並べると(かっこ内が世界の順位)、1位が東京大学(19)、2位が京都大学(25)、3位が大阪大学(44)、4位が東京工業大学(61)、5位が東北大学(112)となっており、以下6位(120)名古屋大学、7位(158)九州大学、8位(174)北海道大学、9位(180)早稲田大学、10位(199)神戸大学の順となっている。
昨年の世界ランクと比較すると、順位が変わらないか、わずかに下がった大学が大半で、ランクを上げたのは、90位から61位まで上昇した東京工業大学と、46位から44位に上がった大阪大学だけだった。
ちなみにトップ10にランクされたのは、1位から順にハーバード大学、イェール大学、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、カリフォルニア工科大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、シカゴ大学、マサチューセッツ工科大学、コロンビア大学で、米、英両国の大学で占められている。
さて、日本の大学は国際的に見て何が劣っているのだろうか。最も目立つのは外国人スタッフの数である。もっともよい大学を100とした場合の指数で見ると、東京大学が27、京都大学が30、大阪大学が25、東京工業大学が25、東北大学が38。世界のトップ5、ハーバード大学、イェール大学、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、カリフォルニア工科大学の数値が、それぞれ87、89、98、96、100であるのと比べると、どうしようもない差が付いている。
次に数値が低いのは外国人学生の数だ。世界のトップ5大学が81、71、95、96、93という数値に対し、日本の上位5大学は40、26、28、45、31でしかない。
スタッフ当たりのサイテーション(論文被引用率)指数では、日本の上位5大学が、78、91、70、87、63と、世界のトップ5大学(100、98、89、85、100)に対して、まずまず健闘している。「Peer Review」(同分野の専門家による評価)でも、日本の上位5大学が、100、99、90、77、63と世界のトップ級ないしそこそこのレベルにあるのを見ても、足を引っぱっている要因が何かは明らかだ。
もっとも、大学に対するこの種の評価に対しては、「客観性を重んじているというものの一面しかとらえていない。主要な評価になるのは疑問」(ノーベル物理学賞を受賞した小林誠・高エネルギー加速器研究機構名誉教授。10日、日本学術振興会主催の記者会見で)といった声も聞かれるが。
http://scienceportal.jp/news/review/0810/0810141.html
英国のザ・タイムズ紙系列の専門誌「ザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・サプリメント」が9日に発表した、ことしの「世界のトップ200大学」に東京大学など日本の10大学が入っている。
上位にランクされた日本の大学を上位から並べると(かっこ内が世界の順位)、1位が東京大学(19)、2位が京都大学(25)、3位が大阪大学(44)、4位が東京工業大学(61)、5位が東北大学(112)となっており、以下6位(120)名古屋大学、7位(158)九州大学、8位(174)北海道大学、9位(180)早稲田大学、10位(199)神戸大学の順となっている。
昨年の世界ランクと比較すると、順位が変わらないか、わずかに下がった大学が大半で、ランクを上げたのは、90位から61位まで上昇した東京工業大学と、46位から44位に上がった大阪大学だけだった。
ちなみにトップ10にランクされたのは、1位から順にハーバード大学、イェール大学、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、カリフォルニア工科大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、シカゴ大学、マサチューセッツ工科大学、コロンビア大学で、米、英両国の大学で占められている。
さて、日本の大学は国際的に見て何が劣っているのだろうか。最も目立つのは外国人スタッフの数である。もっともよい大学を100とした場合の指数で見ると、東京大学が27、京都大学が30、大阪大学が25、東京工業大学が25、東北大学が38。世界のトップ5、ハーバード大学、イェール大学、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、カリフォルニア工科大学の数値が、それぞれ87、89、98、96、100であるのと比べると、どうしようもない差が付いている。
次に数値が低いのは外国人学生の数だ。世界のトップ5大学が81、71、95、96、93という数値に対し、日本の上位5大学は40、26、28、45、31でしかない。
スタッフ当たりのサイテーション(論文被引用率)指数では、日本の上位5大学が、78、91、70、87、63と、世界のトップ5大学(100、98、89、85、100)に対して、まずまず健闘している。「Peer Review」(同分野の専門家による評価)でも、日本の上位5大学が、100、99、90、77、63と世界のトップ級ないしそこそこのレベルにあるのを見ても、足を引っぱっている要因が何かは明らかだ。
もっとも、大学に対するこの種の評価に対しては、「客観性を重んじているというものの一面しかとらえていない。主要な評価になるのは疑問」(ノーベル物理学賞を受賞した小林誠・高エネルギー加速器研究機構名誉教授。10日、日本学術振興会主催の記者会見で)といった声も聞かれるが。
日本の高等教育力は世界6位、国別世界ランキングを初めて発表−英情報会社
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081011-00000078-jij-soci
英国の大学情報会社タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)とQS社は11日までに、高等教育力の国別世界ランキングを初めて発表し、日本は6位に入った。
今年5年目となる世界大学順位では、上位200校から慶応大が外れ、前年の11校から10校 に減少。国内トップは引き続き東京大だが、昨年の 17位から19位へ低下した。国内勢が低下傾向の中、国内4位の東京工業大は90位から61位に躍進した。
近年、大学や企業の国際的な人材争奪が激しくなっており、国内でも国立大が法人化で業績が予算に反映される中、ランキングは一定の影響力があるとみられている。
◇高等教育力の国別順位
*1 米国
*2 英国
*3 豪州
*4 ドイツ
*5 カナダ
*6 日本
*7 フランス
*8 オランダ
*9 韓国
10 スウェーデン
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081011-00000078-jij-soci
英国の大学情報会社タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)とQS社は11日までに、高等教育力の国別世界ランキングを初めて発表し、日本は6位に入った。
今年5年目となる世界大学順位では、上位200校から慶応大が外れ、前年の11校から10校 に減少。国内トップは引き続き東京大だが、昨年の 17位から19位へ低下した。国内勢が低下傾向の中、国内4位の東京工業大は90位から61位に躍進した。
近年、大学や企業の国際的な人材争奪が激しくなっており、国内でも国立大が法人化で業績が予算に反映される中、ランキングは一定の影響力があるとみられている。
◇高等教育力の国別順位
*1 米国
*2 英国
*3 豪州
*4 ドイツ
*5 カナダ
*6 日本
*7 フランス
*8 オランダ
*9 韓国
10 スウェーデン
世界大学ランキング 東大は22位、京大は25位
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091008127.html
英教育専門誌、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)は8日までに、今年の「世界大学ランキング」を発表、日本では東京大が22位(昨年19位)、京都大が25位(同25位)など計11校が上位200位に入った。
1位は米ハーバード大で、2004年の開始以来6年連続トップを維持。2位以下は英ケンブリッジ大、米エール大、英ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン(UCL)の順だった。アジアの大学では、香港大が24位(同26位)、中国の清華大が49位(同56位)などで、東大がアジアのトップを維持した。
同誌は、アジアの大学が昨年よりランキングを上げたと指摘している。
ランキングは世界の大学関係者、企業の人事担当者の評価や、研究論文の引用回数、スタッフ1人当たりの学生数など、教育力と研究力を総合的に分析して決める。
日本の大学では、大阪大43位(同44位)、東京工業大55位(同61位)、名古屋大92位(同120位)、東北大97位(同112位)、慶応大142位(同214位)、早稲田大148位(同180位)、九州大155位(同158位)、北海道大171位(同174位)、筑波大174位(同216位)となっている。
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091008127.html
英教育専門誌、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)は8日までに、今年の「世界大学ランキング」を発表、日本では東京大が22位(昨年19位)、京都大が25位(同25位)など計11校が上位200位に入った。
1位は米ハーバード大で、2004年の開始以来6年連続トップを維持。2位以下は英ケンブリッジ大、米エール大、英ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン(UCL)の順だった。アジアの大学では、香港大が24位(同26位)、中国の清華大が49位(同56位)などで、東大がアジアのトップを維持した。
同誌は、アジアの大学が昨年よりランキングを上げたと指摘している。
ランキングは世界の大学関係者、企業の人事担当者の評価や、研究論文の引用回数、スタッフ1人当たりの学生数など、教育力と研究力を総合的に分析して決める。
日本の大学では、大阪大43位(同44位)、東京工業大55位(同61位)、名古屋大92位(同120位)、東北大97位(同112位)、慶応大142位(同214位)、早稲田大148位(同180位)、九州大155位(同158位)、北海道大171位(同174位)、筑波大174位(同216位)となっている。
2009年 世界大学ランキング TOP25
1位(1) HARVARD University ■United States
2 位(3) University of CAMBRIDGE ■United Kingdom
3 位(2) YALE University ■United States
4 位(7) UCL (University College London) ■United Kingdom
5 位(6) IMPERIAL College London ■United Kingdom
5 位(4) University of OXFORD ■United Kingdom
7 位(8) University of CHICAGO ■United States
8 位(12) PRINCETON University ■United States
9 位(9) MASSACHUSETTS Institute of Technology (MIT) ■United States
10位(5) CALIFORNIA Institute of Technology (Caltech) ■United States
11位(10) COLUMBIAUniversity ■United States
12位(11) University of PENNSYLVANIA ■United States
13位(13) JOHNS HOPKINS University ■United States
14位(13) DUKE University ■United States
15位(15) CORNELL University ■United States
16位(17) STANFORD University ■United States
17位(16) AUSTRALIAN National University ■Australia
18位(20) MCGILL University ■Canada
19位(18) University of MICHIGAN ■United States
20位(23 ) University of EDINBURGH ■United Kingdom
20位(24) ETH Zurich(Swiss FederalInstitute ofTechnology)■Switzerland
22位(19) University of TOKYO ■Japan
23位(22) KING'S College London ■United Kingdom
24位(26) University of HONG KONG ■Hong Kong
25位(25) KYOTO University ■Japan
1位(1) HARVARD University ■United States
2 位(3) University of CAMBRIDGE ■United Kingdom
3 位(2) YALE University ■United States
4 位(7) UCL (University College London) ■United Kingdom
5 位(6) IMPERIAL College London ■United Kingdom
5 位(4) University of OXFORD ■United Kingdom
7 位(8) University of CHICAGO ■United States
8 位(12) PRINCETON University ■United States
9 位(9) MASSACHUSETTS Institute of Technology (MIT) ■United States
10位(5) CALIFORNIA Institute of Technology (Caltech) ■United States
11位(10) COLUMBIAUniversity ■United States
12位(11) University of PENNSYLVANIA ■United States
13位(13) JOHNS HOPKINS University ■United States
14位(13) DUKE University ■United States
15位(15) CORNELL University ■United States
16位(17) STANFORD University ■United States
17位(16) AUSTRALIAN National University ■Australia
18位(20) MCGILL University ■Canada
19位(18) University of MICHIGAN ■United States
20位(23 ) University of EDINBURGH ■United Kingdom
20位(24) ETH Zurich(Swiss FederalInstitute ofTechnology)■Switzerland
22位(19) University of TOKYO ■Japan
23位(22) KING'S College London ■United Kingdom
24位(26) University of HONG KONG ■Hong Kong
25位(25) KYOTO University ■Japan
大学評価:韓国の大学、平均45段階アップ(上)
国際的な知名度高まる
http://www.chosunonline.com/news/20091008000043
英大学情報誌タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)と世界的な大学評価機関クアクアレリ・シモンズ(QS)が8日に発表した「2009年世界大学ランキング」では、韓国の大学の躍進が目立った。韓国の大学で昨年同ランキング200位以内に入ったのは、ソウル大・韓国科学技術院(KAIST)・ポステック(旧浦項工大)の3大学のみ。07年にはソウル大とKAISTだけだった。
しかし、今年はソウル大・KAIST・ポステック・延世大の4大学が200位以内に入り、高麗大も211位と、200位圏内に一歩近づいた。QSのソーター評価総括責任者は、「ここ数年間における韓国の大学の善戦には目を見張る。大学総長(学長)のリーダーシップや大学革新がもたらした結果だろう」と評価した。
■「韓国の大学、平均45段階アップ」
ソウル大は今回、世界47位になり、北京大の52位よりも高く評価された。
昨年は両大学とも50位だったが、今回はソウル大がわずかな差でリードした。両大学に対する評価要素でほぼ同程度だったが、卒業生の評判度や教授論文でソウル大のほうが優れていたという。
ソウル大のチュ・ジョンナム企画課長は、「ソウル大教授の研究実績は世界最高レベルに近づいている。最近は国際化やインフラ部門に多くの努力を傾け、国際的な知名度を高めた効果が現れている」と話す。
徐南杓(ソ・ナムピョ)総長が改革を指揮するKAISTの勢いも著しい。07年世界大学ランキングで132位だったKAISTは昨年95位、今年は26ランクアップの69位になった。KAISTはスウェーデンの名門ウプサラ大学やシンガポールの南洋理工大学よりも高く評価された。わずか2年の間に、恐ろしいほどの勢いで世界一流大学に追いつきつつあるのだ。
昨年188位で、初めて200位以内に入ったポステックは今年134位に選ばれた。ポステックは今年5月、本紙とQSによる「アジア大学ランキング」でも教授一人当たりの論文数でアジア最高であることを証明したほど、研究に強い大学だ。
延世大は昨年の203位から今年は151位へと躍進した。延世大の金漢中(キム・ハンジュン)総長は、「学界の評価点数が多かったようだ。国際学術大会を招致し、国際化に力を入れた」と自己分析している。
アン・ソクペ記者
国際的な知名度高まる
http://www.chosunonline.com/news/20091008000043
英大学情報誌タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)と世界的な大学評価機関クアクアレリ・シモンズ(QS)が8日に発表した「2009年世界大学ランキング」では、韓国の大学の躍進が目立った。韓国の大学で昨年同ランキング200位以内に入ったのは、ソウル大・韓国科学技術院(KAIST)・ポステック(旧浦項工大)の3大学のみ。07年にはソウル大とKAISTだけだった。
しかし、今年はソウル大・KAIST・ポステック・延世大の4大学が200位以内に入り、高麗大も211位と、200位圏内に一歩近づいた。QSのソーター評価総括責任者は、「ここ数年間における韓国の大学の善戦には目を見張る。大学総長(学長)のリーダーシップや大学革新がもたらした結果だろう」と評価した。
■「韓国の大学、平均45段階アップ」
ソウル大は今回、世界47位になり、北京大の52位よりも高く評価された。
昨年は両大学とも50位だったが、今回はソウル大がわずかな差でリードした。両大学に対する評価要素でほぼ同程度だったが、卒業生の評判度や教授論文でソウル大のほうが優れていたという。
ソウル大のチュ・ジョンナム企画課長は、「ソウル大教授の研究実績は世界最高レベルに近づいている。最近は国際化やインフラ部門に多くの努力を傾け、国際的な知名度を高めた効果が現れている」と話す。
徐南杓(ソ・ナムピョ)総長が改革を指揮するKAISTの勢いも著しい。07年世界大学ランキングで132位だったKAISTは昨年95位、今年は26ランクアップの69位になった。KAISTはスウェーデンの名門ウプサラ大学やシンガポールの南洋理工大学よりも高く評価された。わずか2年の間に、恐ろしいほどの勢いで世界一流大学に追いつきつつあるのだ。
昨年188位で、初めて200位以内に入ったポステックは今年134位に選ばれた。ポステックは今年5月、本紙とQSによる「アジア大学ランキング」でも教授一人当たりの論文数でアジア最高であることを証明したほど、研究に強い大学だ。
延世大は昨年の203位から今年は151位へと躍進した。延世大の金漢中(キム・ハンジュン)総長は、「学界の評価点数が多かったようだ。国際学術大会を招致し、国際化に力を入れた」と自己分析している。
アン・ソクペ記者
慶應1位、東大2位 大学ブランドランキング
2009年12月10日 16:01更新
http://jp.ibtimes.com/article/biznews/091210/46041.html
日経BPコンサルティングは「大学ブランド・イメージ調査 2010 (首都圏編)」の調査結果を10日、発表した。1位は慶應義塾大学、2位は東京大学、3位は早稲田大学だった。
これは首都圏の主要大学120校を対象に、同地域在住のビジネス・パーソンや中学生以上の子供のいる父母の目線から調査したもの。大学の「認知度/認知経路」「採用意向度」「入学推薦度」や「子供の進学に対する意識」などのほか、大学や学生などに対する47項目に及ぶブランド・イメージを調査してランキングした。
その結果、ブランドの総合力を表す「大学ブランド偏差値」1位は89.3ポイントを獲得した慶應義塾大学だった。僅差での2位が東京大学(89.1ポイント)。3位には早稲田大学(86.0ポイント)が続いた。
大学ブランド偏差値ランキング トップ10
順位、大学名(ブランド偏差値)
1位 慶應義塾大学(89.3)
2位 東京大学、(89.1)
3位 早稲田大学(86.0)
4位 上智大学(76.3)
5位 一橋大学(73.0)
6位 東京工業大学(70.3)
7位 青山学院大学(67.2)
8位 お茶の水女子大学(65.3)
9位 東京外国語大学(65.1)
10位 学習院大学(63.9)
2009年12月10日 16:01更新
http://jp.ibtimes.com/article/biznews/091210/46041.html
日経BPコンサルティングは「大学ブランド・イメージ調査 2010 (首都圏編)」の調査結果を10日、発表した。1位は慶應義塾大学、2位は東京大学、3位は早稲田大学だった。
これは首都圏の主要大学120校を対象に、同地域在住のビジネス・パーソンや中学生以上の子供のいる父母の目線から調査したもの。大学の「認知度/認知経路」「採用意向度」「入学推薦度」や「子供の進学に対する意識」などのほか、大学や学生などに対する47項目に及ぶブランド・イメージを調査してランキングした。
その結果、ブランドの総合力を表す「大学ブランド偏差値」1位は89.3ポイントを獲得した慶應義塾大学だった。僅差での2位が東京大学(89.1ポイント)。3位には早稲田大学(86.0ポイント)が続いた。
大学ブランド偏差値ランキング トップ10
順位、大学名(ブランド偏差値)
1位 慶應義塾大学(89.3)
2位 東京大学、(89.1)
3位 早稲田大学(86.0)
4位 上智大学(76.3)
5位 一橋大学(73.0)
6位 東京工業大学(70.3)
7位 青山学院大学(67.2)
8位 お茶の水女子大学(65.3)
9位 東京外国語大学(65.1)
10位 学習院大学(63.9)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
生命科学研究ハイライト 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
生命科学研究ハイライトのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人