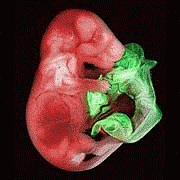トムソン:2006年ノーベル賞の有力候補者を発表
−科学の進歩に多大な貢献を果たした27名のThomson Scientific Laureates−
米国ペンシルベニア州フィラデルフィア/英国ロンドン
2006年9月5日
http://
2006年ノーベル賞受賞者発表に先立ち、トムソンはノーベル賞受賞の可能性のある研究者として、2006 Thomson Scientific Laureates (トムソンサイエンティフィック栄誉賞)をここに発表します。
「物理学」、「化学」、「医学・生理学」、「経済学」の各 ノーベル賞分野において、最も影響力のある研究者のリストが、毎年、トムソンサイエンティフィックの研究ソリューションである ISI Web of Knowledge からのデータによって定量的に決定されています。これらの影響力の高い研究者は、Thomson Scientific Laureates として名付けられ、その著作の総被引用数から、今年あるいは近い将来におけるノーベル賞候補として予想されました。2002年以来、Thomson Scientific Laureates として発表された27名のうち、4名がノーベル賞を受賞しました。7分の1以上の的中率です。
「論文の引用とは、先行研究を明示して先駆者への敬意を表する行為であり、学術分野における影響度を直接的に反映するものです。」と、トムソンサイエンティフィック、チーフ・サイエンティストのヘンリー・スモールは述べています。「過去30年以上にわたるISI社での研究によって、学術論文の被引用数と、ピア・エスティーム(同分野の研究者からの敬意)には、強い相関関係があることが分かっています。したがって、同じ分野の研究者からそのような信望を得ている研究者は、様々な賞や名誉に推薦されることが多いのです。」
トムソンサイエンティフィックはノーベル賞有力候補者を毎年決定するための定量的なデータを有する唯一の組織です。Thomson Scientific Laureates は、過去20年以上にわたって彼らが出版した学術論文の被引用数に基づいて、各分野の上位0.1パーセントにランクする研究者たちです。
2006 Thomson Scientific Laureates の選考にあたって、主なノーベル賞の分野に相当する総被引用数とハイインパクト論文の数が調査されました。これらのデータは、ノーベル委員会による注目に値すると考えられるカテゴリ(物理学、化学、医学・生理学、経済学)に振り分けられました。これらの判断基準により、各分野において、特に注目すべき研究領域のリーダーと目される候補者が選ばれました。
ノーベル賞4分野について、2006 Thomson Scientific Laureates を発表します。
−科学の進歩に多大な貢献を果たした27名のThomson Scientific Laureates−
米国ペンシルベニア州フィラデルフィア/英国ロンドン
2006年9月5日
http://
2006年ノーベル賞受賞者発表に先立ち、トムソンはノーベル賞受賞の可能性のある研究者として、2006 Thomson Scientific Laureates (トムソンサイエンティフィック栄誉賞)をここに発表します。
「物理学」、「化学」、「医学・生理学」、「経済学」の各 ノーベル賞分野において、最も影響力のある研究者のリストが、毎年、トムソンサイエンティフィックの研究ソリューションである ISI Web of Knowledge からのデータによって定量的に決定されています。これらの影響力の高い研究者は、Thomson Scientific Laureates として名付けられ、その著作の総被引用数から、今年あるいは近い将来におけるノーベル賞候補として予想されました。2002年以来、Thomson Scientific Laureates として発表された27名のうち、4名がノーベル賞を受賞しました。7分の1以上の的中率です。
「論文の引用とは、先行研究を明示して先駆者への敬意を表する行為であり、学術分野における影響度を直接的に反映するものです。」と、トムソンサイエンティフィック、チーフ・サイエンティストのヘンリー・スモールは述べています。「過去30年以上にわたるISI社での研究によって、学術論文の被引用数と、ピア・エスティーム(同分野の研究者からの敬意)には、強い相関関係があることが分かっています。したがって、同じ分野の研究者からそのような信望を得ている研究者は、様々な賞や名誉に推薦されることが多いのです。」
トムソンサイエンティフィックはノーベル賞有力候補者を毎年決定するための定量的なデータを有する唯一の組織です。Thomson Scientific Laureates は、過去20年以上にわたって彼らが出版した学術論文の被引用数に基づいて、各分野の上位0.1パーセントにランクする研究者たちです。
2006 Thomson Scientific Laureates の選考にあたって、主なノーベル賞の分野に相当する総被引用数とハイインパクト論文の数が調査されました。これらのデータは、ノーベル委員会による注目に値すると考えられるカテゴリ(物理学、化学、医学・生理学、経済学)に振り分けられました。これらの判断基準により、各分野において、特に注目すべき研究領域のリーダーと目される候補者が選ばれました。
ノーベル賞4分野について、2006 Thomson Scientific Laureates を発表します。
|
|
|
|
コメント(44)
米医学賞ラスカー賞、うつ病認知療法の創始者など5人に
http://www.asahi.com/health/news/TKY200609170179.html
ノーベル賞に近いといわれ、優れた医学研究者に与えられる米国の医学賞「ラスカー賞」の今年の受賞者5人を17日、ラスカー財団が発表した。
臨床医学部門には、うつ病の認知療法の創始者として知られる米ペンシルベニア大の精神科医、アーロン・ベック教授が選ばれた。
基礎医学部門は、老化の仕組みにかかわると考えられる「テロメアーゼ」という酵素の発見で、米カリフォルニア大のエリザベス・ブラックバーン教授、米ジョンズホプキンス大のキャロル・グレイダー教授、米ハーバード大のジャック・ゾスタク教授の3氏。
特別賞は米カーネギー研究所のジョゼフ・ガル氏。細胞生物学と染色体構造の研究に貢献した。
http://www.asahi.com/health/news/TKY200609170179.html
ノーベル賞に近いといわれ、優れた医学研究者に与えられる米国の医学賞「ラスカー賞」の今年の受賞者5人を17日、ラスカー財団が発表した。
臨床医学部門には、うつ病の認知療法の創始者として知られる米ペンシルベニア大の精神科医、アーロン・ベック教授が選ばれた。
基礎医学部門は、老化の仕組みにかかわると考えられる「テロメアーゼ」という酵素の発見で、米カリフォルニア大のエリザベス・ブラックバーン教授、米ジョンズホプキンス大のキャロル・グレイダー教授、米ハーバード大のジャック・ゾスタク教授の3氏。
特別賞は米カーネギー研究所のジョゼフ・ガル氏。細胞生物学と染色体構造の研究に貢献した。
初日のまとめ:医学・生理学賞
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006
"for their discovery of RNA interference - gene silencing by double-stranded RNA"
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2006/
Andrew Z. Fire
USA
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Cambridge, MA, USA; Stanford University School of Medicine
Stanford, CA, USA
b. 1959
Craig C. Mello
USA
Harvard University
Boston, MA, USA; University of Massachusetts Medical School
Worcester, MA, USA
b. 1960
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006
"for their discovery of RNA interference - gene silencing by double-stranded RNA"
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2006/
Andrew Z. Fire
USA
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Cambridge, MA, USA; Stanford University School of Medicine
Stanford, CA, USA
b. 1959
Craig C. Mello
USA
Harvard University
Boston, MA, USA; University of Massachusetts Medical School
Worcester, MA, USA
b. 1960
受賞論文
Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans.
Fire A, Xu S, Montgomery MK, Kostas SA, Driver SE, Mello CC.
Nature. 1998 Feb 19;391(6669):806-11.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9486653&query_hl=22&itool=pubmed_docsum
Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans.
Fire A, Xu S, Montgomery MK, Kostas SA, Driver SE, Mello CC.
Nature. 1998 Feb 19;391(6669):806-11.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9486653&query_hl=22&itool=pubmed_docsum
<ノーベル医学生理学賞>米の2氏に…「RNA干渉」発見
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061002-00000123-mai-soci
スウェーデンのカロリンスカ研究所は2日、06年のノーベル医学生理学賞をアンドルー・ファイアー・米スタンフォード大医学部教授(47)と、クレイグ・メロー・米マサチューセッツ大教授(45)の2氏に授与すると発表した。両氏は生物の遺伝情報を伝える役のRNA(リボ核酸)が対になった「二重鎖RNA」で、遺伝子の発現が阻害される「RNA干渉」という現象を線虫で発見し、98年に発表した。この現象は人間にも共通しており、二重鎖RNAを人工的に作ることで新薬開発などに道を開いたことが評価された。この分野では、国内第一人者とされる東京大教授の論文不正疑惑が発覚、同教授が一部の論文を取り下げるなど、研究競争が過熱している。
授賞式は12月10日にストックホルムで開かれ、賞金計1000万クローナ(約1億6000万円)が贈られる。
両氏は、ひも状のRNA2本がはしごのように対構造になった二重鎖RNAを線虫の細胞に入れた。すると、鎖がほどけて1本になり、対応する遺伝子の発現が阻害され、たんぱく質が合成されないことを発見した。
生体内でも、こうした二重鎖RNAが作られ、有害な遺伝子の発現が抑えられている場合があることも発見された。この機能を応用し、網膜の加齢黄斑変性症やC型肝炎、エイズ、がん、ホルモン異常などの治療薬の研究が進んでいる。
◇画期的な技術
東京大医科学研究所の中村義一教授(遺伝子動態分野)の話 最初は「まゆつば」とも思われていた研究だ。それなのに、2人が98年に最初の論文を発表してからわずか8年しかたっていないのに、いまや世界中でこの技術を用いて医学研究が行われ、実用化一歩手前の新薬が開発されつつある。米国では、高齢者に多く、失明の原因となる「加齢黄斑変性症」で実用化が間近になっており、抗がん剤などでの開発が盛んだ。DNAの複製反応を人工的に繰り返して増幅させる「PCR(合成酵素連鎖反応)」に匹敵する画期的な技術だ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061002-00000123-mai-soci
スウェーデンのカロリンスカ研究所は2日、06年のノーベル医学生理学賞をアンドルー・ファイアー・米スタンフォード大医学部教授(47)と、クレイグ・メロー・米マサチューセッツ大教授(45)の2氏に授与すると発表した。両氏は生物の遺伝情報を伝える役のRNA(リボ核酸)が対になった「二重鎖RNA」で、遺伝子の発現が阻害される「RNA干渉」という現象を線虫で発見し、98年に発表した。この現象は人間にも共通しており、二重鎖RNAを人工的に作ることで新薬開発などに道を開いたことが評価された。この分野では、国内第一人者とされる東京大教授の論文不正疑惑が発覚、同教授が一部の論文を取り下げるなど、研究競争が過熱している。
授賞式は12月10日にストックホルムで開かれ、賞金計1000万クローナ(約1億6000万円)が贈られる。
両氏は、ひも状のRNA2本がはしごのように対構造になった二重鎖RNAを線虫の細胞に入れた。すると、鎖がほどけて1本になり、対応する遺伝子の発現が阻害され、たんぱく質が合成されないことを発見した。
生体内でも、こうした二重鎖RNAが作られ、有害な遺伝子の発現が抑えられている場合があることも発見された。この機能を応用し、網膜の加齢黄斑変性症やC型肝炎、エイズ、がん、ホルモン異常などの治療薬の研究が進んでいる。
◇画期的な技術
東京大医科学研究所の中村義一教授(遺伝子動態分野)の話 最初は「まゆつば」とも思われていた研究だ。それなのに、2人が98年に最初の論文を発表してからわずか8年しかたっていないのに、いまや世界中でこの技術を用いて医学研究が行われ、実用化一歩手前の新薬が開発されつつある。米国では、高齢者に多く、失明の原因となる「加齢黄斑変性症」で実用化が間近になっており、抗がん剤などでの開発が盛んだ。DNAの複製反応を人工的に繰り返して増幅させる「PCR(合成酵素連鎖反応)」に匹敵する画期的な技術だ。
ノーベル物理学賞、宇宙背景放射の研究で米国の2氏に
2006.10.03
Web posted at: 19:04 JST
- CNN/AP
http://www.cnn.co.jp/science/CNN200610030029.html
ストックホルム──スウェーデン王立科学アカデミーは3日、今年のノーベル物理学賞を、米航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センターのジョン・C・メイザー氏(60)と、カリフォルニア大学バークレー校のジョージ・F・スムート氏(61)に授与すると発表した。
授賞理由は、「完全放射体と宇宙背景放射のゆらぎ」の発見。1989年にNASAが打ち上げた人工衛星COBEの観測結果をもとに、宇宙の起源とされるビッグバン理論を裏付け、近代宇宙学の発展に寄与したと評価した。
ビッグバン理論によれば、宇宙は誕生直後から膨張を続けており、温度もどんどんと下がり続けている。メイザー博士らは、宇宙空間で観測されるさまざまな周波数の電磁波の放射、「宇宙背景放射」のゆらぎを観測し、ビッグバン理論を裏付けた。
両氏には、賞金1000万スウェーデン・クローナ(約1億6400万円)が贈られる。授賞式は12月10日に、ストックホルムで行われる。
2006.10.03
Web posted at: 19:04 JST
- CNN/AP
http://www.cnn.co.jp/science/CNN200610030029.html
ストックホルム──スウェーデン王立科学アカデミーは3日、今年のノーベル物理学賞を、米航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センターのジョン・C・メイザー氏(60)と、カリフォルニア大学バークレー校のジョージ・F・スムート氏(61)に授与すると発表した。
授賞理由は、「完全放射体と宇宙背景放射のゆらぎ」の発見。1989年にNASAが打ち上げた人工衛星COBEの観測結果をもとに、宇宙の起源とされるビッグバン理論を裏付け、近代宇宙学の発展に寄与したと評価した。
ビッグバン理論によれば、宇宙は誕生直後から膨張を続けており、温度もどんどんと下がり続けている。メイザー博士らは、宇宙空間で観測されるさまざまな周波数の電磁波の放射、「宇宙背景放射」のゆらぎを観測し、ビッグバン理論を裏付けた。
両氏には、賞金1000万スウェーデン・クローナ(約1億6400万円)が贈られる。授賞式は12月10日に、ストックホルムで行われる。
ノーベル物理学賞に米の2氏、ビッグバンを証明
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20061003i111.htm?from=main1
スウェーデン王立科学アカデミーは3日、2006年のノーベル物理学賞を、米航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センターのジョン・マザー上級研究員(60)と米カリフォルニア大バークレー校のジョージ・スムート教授(61)に授与すると発表した。
授賞理由は「宇宙背景放射の黒体放射スペクトルと異方性の発見」。賞金は1000万スウェーデン・クローナ(約1億6000万円)で、受賞者2人が等分する。
授賞式はアルフレッド・ノーベルの命日にあたる12月10日にストックホルムで行われる。
宇宙は膨張しているのかいないのか――。この問いに最終的に決着をつけたのが、1989年に打ち上げられた観測衛星COBEを使った両氏の業績だ。これにより、宇宙は約137億年前に、ビッグバンと呼ばれる大爆発で始まったとする理論が認められた。
両氏が観測したのは、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)と呼ばれる宇宙創生期の熱の名残。これが現在、絶対温度で2・7度(セ氏零下270・4度)に相当する極低温となって宇宙を満たしているという宇宙膨張の証拠を、マザー氏が確認。スムート氏は、この熱の名残の分布に、銀河の生成などを説明できるわずかな異方性(むら)があることを突き止めた。
COBEのプロジェクトにかかわった研究者や技術者などは1000人を超えるが、マザー氏は当初からプロジェクトのリーダーを務め、スムート氏は背景放射の微細なゆらぎの観測の責任者を務めた。
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20061003i111.htm?from=main1
スウェーデン王立科学アカデミーは3日、2006年のノーベル物理学賞を、米航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センターのジョン・マザー上級研究員(60)と米カリフォルニア大バークレー校のジョージ・スムート教授(61)に授与すると発表した。
授賞理由は「宇宙背景放射の黒体放射スペクトルと異方性の発見」。賞金は1000万スウェーデン・クローナ(約1億6000万円)で、受賞者2人が等分する。
授賞式はアルフレッド・ノーベルの命日にあたる12月10日にストックホルムで行われる。
宇宙は膨張しているのかいないのか――。この問いに最終的に決着をつけたのが、1989年に打ち上げられた観測衛星COBEを使った両氏の業績だ。これにより、宇宙は約137億年前に、ビッグバンと呼ばれる大爆発で始まったとする理論が認められた。
両氏が観測したのは、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)と呼ばれる宇宙創生期の熱の名残。これが現在、絶対温度で2・7度(セ氏零下270・4度)に相当する極低温となって宇宙を満たしているという宇宙膨張の証拠を、マザー氏が確認。スムート氏は、この熱の名残の分布に、銀河の生成などを説明できるわずかな異方性(むら)があることを突き止めた。
COBEのプロジェクトにかかわった研究者や技術者などは1000人を超えるが、マザー氏は当初からプロジェクトのリーダーを務め、スムート氏は背景放射の微細なゆらぎの観測の責任者を務めた。
ノーベル物理学賞は米の2氏 電波「背景放射」を観測
http://www.asahi.com/science/news/TKY200610030412.html
スウェーデン王立科学アカデミーは3日、今年のノーベル物理学賞を、米航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センターのジョン・マザー上席研究員(60)と米カリフォルニア大バークリー校のジョージ・スムート教授(61)に贈ると発表した。人工衛星を使った宇宙の電波観測でビッグバンの直接証拠をとらえ、銀河の「種」となる温度のゆらぎを発見したことが評価された。賞金は1000万クローナ(約1億6000万円)で2人で分ける。授賞式は12月10日、ストックホルムである。
宇宙は高温の火の玉で始まったというのがビッグバン理論だ。そのとき宇宙に満ちていた電磁波は宇宙の膨張とともに変化し、今は波長の長い電波になっている。これを宇宙背景放射と呼ぶ。64年に電波雑音として発見されたが、大気に吸収されるため、地上での観測には限界があった。
2人は、89年に打ち上げられた宇宙背景放射観測衛星「COBE(コービー)」を使って、宇宙のあらゆる方向からやってくる電波を詳細にとらえた。その結果、宇宙背景放射が絶対温度約3度(零下約270度)であることや、この温度は方向によってわずかにゆらいでいることを明らかにし、92年に発表した。
このゆらぎが成長して物質の「種」ができ、そこに周りの物質が引きつけられ、やがて星や銀河ができて現在のような宇宙になったと考えられている。
COBEの成果によって、宇宙論は頭のなかで考えるものから、観測データをもとに議論する「観測宇宙論」に変わった。宇宙の進化を研究するスティーブン・ホーキング博士は、COBEの成果を「20世紀最大の発見」と呼んだ。
http://www.asahi.com/science/news/TKY200610030412.html
スウェーデン王立科学アカデミーは3日、今年のノーベル物理学賞を、米航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センターのジョン・マザー上席研究員(60)と米カリフォルニア大バークリー校のジョージ・スムート教授(61)に贈ると発表した。人工衛星を使った宇宙の電波観測でビッグバンの直接証拠をとらえ、銀河の「種」となる温度のゆらぎを発見したことが評価された。賞金は1000万クローナ(約1億6000万円)で2人で分ける。授賞式は12月10日、ストックホルムである。
宇宙は高温の火の玉で始まったというのがビッグバン理論だ。そのとき宇宙に満ちていた電磁波は宇宙の膨張とともに変化し、今は波長の長い電波になっている。これを宇宙背景放射と呼ぶ。64年に電波雑音として発見されたが、大気に吸収されるため、地上での観測には限界があった。
2人は、89年に打ち上げられた宇宙背景放射観測衛星「COBE(コービー)」を使って、宇宙のあらゆる方向からやってくる電波を詳細にとらえた。その結果、宇宙背景放射が絶対温度約3度(零下約270度)であることや、この温度は方向によってわずかにゆらいでいることを明らかにし、92年に発表した。
このゆらぎが成長して物質の「種」ができ、そこに周りの物質が引きつけられ、やがて星や銀河ができて現在のような宇宙になったと考えられている。
COBEの成果によって、宇宙論は頭のなかで考えるものから、観測データをもとに議論する「観測宇宙論」に変わった。宇宙の進化を研究するスティーブン・ホーキング博士は、COBEの成果を「20世紀最大の発見」と呼んだ。
ノーベル文学賞:発表 12日か19日の可能性
http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20061004k0000m030110000c.html
スウェーデン・アカデミーは3日、今年のノーベル文学賞の発表日が来週以降となることを確認した。発表日は、毎年10月の木曜日が慣例で、ロイター通信によると、12日か19日とみられる。
スウェーデン・アカデミーは候補者の名前を明らかにしないが、今年は、トルコの作家オルハン・パムク氏やポーランドのジャーナリスト、リシャルド・カプシチンスキ氏らのほか、日本の作家、村上春樹氏も有力候補とみられている。(ストックホルム共同)
http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20061004k0000m030110000c.html
スウェーデン・アカデミーは3日、今年のノーベル文学賞の発表日が来週以降となることを確認した。発表日は、毎年10月の木曜日が慣例で、ロイター通信によると、12日か19日とみられる。
スウェーデン・アカデミーは候補者の名前を明らかにしないが、今年は、トルコの作家オルハン・パムク氏やポーランドのジャーナリスト、リシャルド・カプシチンスキ氏らのほか、日本の作家、村上春樹氏も有力候補とみられている。(ストックホルム共同)
アーサー・コーンバーグの息子だ。
ノーベル化学賞、スタンフォード大のコーンバーグ教授
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20061004i411.htm
スウェーデン王立科学アカデミーは4日、2006年のノーベル化学賞を米スタンフォード大医学部のロジャー・D・コーンバーグ教授(59)に授与すると発表した。
授賞理由は「真核生物の遺伝情報転写の仕組みについての研究」。賞金は1000万スウェーデン・クローナ(約1億6000万円)。授賞式は12月10日にストックホルムで開かれる。
人間など細胞の中に核を持つ生物が生きていくのに必要な情報は、DNA(デオキシリボ核酸)に記録されており、その情報をもとにたんぱく質を合成する。DNAの情報はいったんRNA(リボ核酸)に写し取られ、RNAがたんぱく質を作り出す。
コーンバーグ教授は、生命活動の基本であるDNAからRNAへの情報の「転写」について、分子レベルでの解明に挑んだ。転写をつかさどる酵素「RNAポリメラーゼ」など、転写の際に働く様々な物質の複雑な立体構造を電子顕微鏡やX線を使って分析し、図示することに成功した。
転写の仕組みの解明は、医学的に極めて重要で、転写を自由に調節できるようになれば、がんや心臓病など様々な病気の根源的な治療が可能になると考えられている。
ロジャー・コーンバーグ教授は、DNAの合成によって1959年にノーベル生理学医学賞を受賞したアーサー・コーンバーグ氏の長男。親子受賞は7組目。
ノーベル化学賞、スタンフォード大のコーンバーグ教授
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20061004i411.htm
スウェーデン王立科学アカデミーは4日、2006年のノーベル化学賞を米スタンフォード大医学部のロジャー・D・コーンバーグ教授(59)に授与すると発表した。
授賞理由は「真核生物の遺伝情報転写の仕組みについての研究」。賞金は1000万スウェーデン・クローナ(約1億6000万円)。授賞式は12月10日にストックホルムで開かれる。
人間など細胞の中に核を持つ生物が生きていくのに必要な情報は、DNA(デオキシリボ核酸)に記録されており、その情報をもとにたんぱく質を合成する。DNAの情報はいったんRNA(リボ核酸)に写し取られ、RNAがたんぱく質を作り出す。
コーンバーグ教授は、生命活動の基本であるDNAからRNAへの情報の「転写」について、分子レベルでの解明に挑んだ。転写をつかさどる酵素「RNAポリメラーゼ」など、転写の際に働く様々な物質の複雑な立体構造を電子顕微鏡やX線を使って分析し、図示することに成功した。
転写の仕組みの解明は、医学的に極めて重要で、転写を自由に調節できるようになれば、がんや心臓病など様々な病気の根源的な治療が可能になると考えられている。
ロジャー・コーンバーグ教授は、DNAの合成によって1959年にノーベル生理学医学賞を受賞したアーサー・コーンバーグ氏の長男。親子受賞は7組目。
ノーベル化学賞 「転写」の仕組みの米国人研究者に
http://www.asahi.com/science/news/TKY200610040372.html
スウェーデン王立科学アカデミーは4日、06年のノーベル化学賞を、米スタンフォード大のロジャー・コーンバーグ教授(59)に贈ると発表した。授賞理由は、真核生物における遺伝情報の転写の基礎的研究。賞金は1千万クローナ(約1億6千万円)で、授賞式は12月10日にストックホルムである。
コーンバーグ教授の父親は、DNAを合成する酵素DNAポリメラーゼを発見した業績で、1959年にノーベル医学生理学賞を受けたアーサー・コーンバーグ氏。ノーベル財団によると、親子2代の受賞はこれで7組になる。
転写とは、生物が生きていく上で最も基本的な仕組みのひとつ。遺伝子を構成するDNAに蓄えられた遺伝情報から、酵素の働きで伝令RNA(mRNA)が合成されることを指す。mRNAに写し取られた情報をもとに、細胞内でたんぱく質が作られていく。
コーンバーグ教授は、膜に包まれた核を持つヒトなど真核生物の転写の研究を進め、複雑な仕組みの理解を進めた。01年には酵母で、mRNAを合成する「RNAポリメラーゼ2」という酵素の構造を決定し解析。その結果、原子のレベルでどのように転写が進むのかもわかるようになった。
転写の理解が進むことで今後、病気の治療のほか、体の細胞や臓器の成長を制御することにつながるかもしれない、と期待されている。
●ロジャー・コーンバーグ氏 47年生まれ。72年に米スタンフォード大で博士号取得。現在、スタンフォード大医学部教授。
http://www.asahi.com/science/news/TKY200610040372.html
スウェーデン王立科学アカデミーは4日、06年のノーベル化学賞を、米スタンフォード大のロジャー・コーンバーグ教授(59)に贈ると発表した。授賞理由は、真核生物における遺伝情報の転写の基礎的研究。賞金は1千万クローナ(約1億6千万円)で、授賞式は12月10日にストックホルムである。
コーンバーグ教授の父親は、DNAを合成する酵素DNAポリメラーゼを発見した業績で、1959年にノーベル医学生理学賞を受けたアーサー・コーンバーグ氏。ノーベル財団によると、親子2代の受賞はこれで7組になる。
転写とは、生物が生きていく上で最も基本的な仕組みのひとつ。遺伝子を構成するDNAに蓄えられた遺伝情報から、酵素の働きで伝令RNA(mRNA)が合成されることを指す。mRNAに写し取られた情報をもとに、細胞内でたんぱく質が作られていく。
コーンバーグ教授は、膜に包まれた核を持つヒトなど真核生物の転写の研究を進め、複雑な仕組みの理解を進めた。01年には酵母で、mRNAを合成する「RNAポリメラーゼ2」という酵素の構造を決定し解析。その結果、原子のレベルでどのように転写が進むのかもわかるようになった。
転写の理解が進むことで今後、病気の治療のほか、体の細胞や臓器の成長を制御することにつながるかもしれない、と期待されている。
●ロジャー・コーンバーグ氏 47年生まれ。72年に米スタンフォード大で博士号取得。現在、スタンフォード大医学部教授。
ノーベル化学賞は米のコーンバーグ氏に、父も受賞者
http://www.cnn.co.jp/science/CNN200610040030.html
Web posted at: 18:49 JST
- CNN/AP
ストックホルム──スウェーデン王立科学アカデミーは4日、今年のノーベル化学賞を、米スタンフォード大学のロジャー・D・コーンバーグ氏(59)に授与すると発表した。授賞理由は「真核生物における遺伝情報の転写に関する分子基盤研究」。
ロジャー・D・コーンバーグ氏は、動植物や細菌など、遺伝情報を保持する染色体が核膜で覆われている生物(真核生物)において、どのように遺伝情報がDNA(デオキシリボ核酸)から複写され、遺伝情報を伝達する伝令RNA(リボ核酸)に伝えるかを、分子レベルで解明した。
同氏の父アーサー・コーンバーグ博士はDNAポリメラーゼを発見し、遺伝情報がどのように娘細胞へ伝わるかを解明して、1959年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。AP通信によると、父子でノーベル賞を受賞するのは、6度目。
当時12歳だったコーンバーグ氏は、父親のノーベル賞授賞式出席に伴って、ストックホルムを訪れている。親子2代で、遺伝情報の伝達について研究し、ともにノーベル賞を受賞した。
コーンバーグ氏には賞金1千万スウェーデン・クローナ(約1億6400万円)が贈られる。
授賞式は12月10日に、ストックホルムで行われる。
http://www.cnn.co.jp/science/CNN200610040030.html
Web posted at: 18:49 JST
- CNN/AP
ストックホルム──スウェーデン王立科学アカデミーは4日、今年のノーベル化学賞を、米スタンフォード大学のロジャー・D・コーンバーグ氏(59)に授与すると発表した。授賞理由は「真核生物における遺伝情報の転写に関する分子基盤研究」。
ロジャー・D・コーンバーグ氏は、動植物や細菌など、遺伝情報を保持する染色体が核膜で覆われている生物(真核生物)において、どのように遺伝情報がDNA(デオキシリボ核酸)から複写され、遺伝情報を伝達する伝令RNA(リボ核酸)に伝えるかを、分子レベルで解明した。
同氏の父アーサー・コーンバーグ博士はDNAポリメラーゼを発見し、遺伝情報がどのように娘細胞へ伝わるかを解明して、1959年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。AP通信によると、父子でノーベル賞を受賞するのは、6度目。
当時12歳だったコーンバーグ氏は、父親のノーベル賞授賞式出席に伴って、ストックホルムを訪れている。親子2代で、遺伝情報の伝達について研究し、ともにノーベル賞を受賞した。
コーンバーグ氏には賞金1千万スウェーデン・クローナ(約1億6400万円)が贈られる。
授賞式は12月10日に、ストックホルムで行われる。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■ ノーベル賞医学生理学賞はRNA干渉を発見したメロー氏、ファイアー氏
└──────────────────────────────────
スウェーデンよりノーベル賞が続々と発表されました。ノーベル医学生理学賞は、
アンドルー・ファイアー・米スタンフォード大医学部教授と、クレイグ・メロー・
米マサチューセッツ大教授の2氏に授与されます。両氏の研究「RNA干渉」は、
新薬開発に画期的な技術とされています。
Nature10/5号では、わずか8年間で成功を遂げた両氏について書かれています。
<http://www.naturejpn.com/go.php?id=5216>
□■ ノーベル賞医学生理学賞はRNA干渉を発見したメロー氏、ファイアー氏
└──────────────────────────────────
スウェーデンよりノーベル賞が続々と発表されました。ノーベル医学生理学賞は、
アンドルー・ファイアー・米スタンフォード大医学部教授と、クレイグ・メロー・
米マサチューセッツ大教授の2氏に授与されます。両氏の研究「RNA干渉」は、
新薬開発に画期的な技術とされています。
Nature10/5号では、わずか8年間で成功を遂げた両氏について書かれています。
<http://www.naturejpn.com/go.php?id=5216>
これかぁ(笑)。
「教師に聞こえない携帯着信音」にイグ・ノーベル平和賞
http://www.asahi.com/international/update/1006/008.html
ユーモアにあふれ、科学への関心を高めた研究に贈られる「イグ・ノーベル賞」の06年の受賞者が5日発表され、平和賞には高周波雑音発生装置「モスキート」を発明した英国のハワード・ステイプルトンさんが選ばれた。
これは、若者しか聞き取れない高周波の雑音を発して、街にたむろする若者を追い払うための装置。だが、その技術が「教師に聞こえない携帯電話の着信音」として欧米で大ブレークし、米国では今年に入って「モスキート着信音」を使って教室で携帯電話をかける若者が増え、社会問題に発展しているほど。新たな若者文化をつくったことなどが評価された。
米ハーバード大サンダース講堂で米東部時間5日午後7時半(日本時間6日午前8時半)に始まった授賞式には、同大や、近くの米マサチューセッツ工科大などから本物のノーベル賞受賞者も多数参加。ステイプルトンさんは家庭の事情で欠席したが、会場では「高齢」のノーベル賞受賞者らにこの音が聞こえるかを調べる実験もあり、大いにわいた。
今年はこのほか、鳥類学賞に「キツツキはなぜ頭が痛くならないのか」(米カリフォルニア大デービス校など)、物理学賞に「乾燥スパゲティを曲げると、しばしば二つより多くの部分に折れてしまうのはなぜか」(仏ピエール・マリー・キュリー大)など、計10部門で賞が贈られた。
イグ・ノーベル賞は米ハーバード大系のユーモア科学誌が91年に創設。毎年10部門前後の「人々を笑わせ、考えさせてくれた研究」に贈られる。
日本からも、カラオケ発明者の井上大佑さんが04年平和賞、犬語翻訳機「バウリンガル」を開発した玩具メーカなどが02年平和賞を受けるなど、多くの受賞者が輩出していることで知られる。
「教師に聞こえない携帯着信音」にイグ・ノーベル平和賞
http://www.asahi.com/international/update/1006/008.html
ユーモアにあふれ、科学への関心を高めた研究に贈られる「イグ・ノーベル賞」の06年の受賞者が5日発表され、平和賞には高周波雑音発生装置「モスキート」を発明した英国のハワード・ステイプルトンさんが選ばれた。
これは、若者しか聞き取れない高周波の雑音を発して、街にたむろする若者を追い払うための装置。だが、その技術が「教師に聞こえない携帯電話の着信音」として欧米で大ブレークし、米国では今年に入って「モスキート着信音」を使って教室で携帯電話をかける若者が増え、社会問題に発展しているほど。新たな若者文化をつくったことなどが評価された。
米ハーバード大サンダース講堂で米東部時間5日午後7時半(日本時間6日午前8時半)に始まった授賞式には、同大や、近くの米マサチューセッツ工科大などから本物のノーベル賞受賞者も多数参加。ステイプルトンさんは家庭の事情で欠席したが、会場では「高齢」のノーベル賞受賞者らにこの音が聞こえるかを調べる実験もあり、大いにわいた。
今年はこのほか、鳥類学賞に「キツツキはなぜ頭が痛くならないのか」(米カリフォルニア大デービス校など)、物理学賞に「乾燥スパゲティを曲げると、しばしば二つより多くの部分に折れてしまうのはなぜか」(仏ピエール・マリー・キュリー大)など、計10部門で賞が贈られた。
イグ・ノーベル賞は米ハーバード大系のユーモア科学誌が91年に創設。毎年10部門前後の「人々を笑わせ、考えさせてくれた研究」に贈られる。
日本からも、カラオケ発明者の井上大佑さんが04年平和賞、犬語翻訳機「バウリンガル」を開発した玩具メーカなどが02年平和賞を受けるなど、多くの受賞者が輩出していることで知られる。
The 2006 Ig Nobel Prize winners
http://improbable.com/ig/ig-pastwinners.html#ig2006
The 2006 Ig Nobel Prize Winners
The 2006 Ig Nobel Prize winners were awarded on Thursday night, October 5, at the 16th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony, at Harvard's Sanders Theatre.
The ceremony was webcast at www.improbable.com. Recorded video will be posted here soon.
Two days after the ceremon y -- on Saturday, October 7 -- the new winners will give free public lectures at the Ig Informal Lectures.
ORNITHOLOGY: Ivan R. Schwab, of the University of California Davis, and the late Philip R.A. May of the University of California Los Angeles, for exploring and explaining why woodpeckers don't get headaches.
REFERENCE: "Cure for a Headache," Ivan R Schwab, British Journal of Ophthalmology, vol. 86, 2002, p. 843.
REFERENCE: "Woodpeckers and Head Injury," Philip R.A. May, Joaquin M. Fuster, Paul Newman and Ada Hirschman, Lancet, vol. 307, no. 7957, February 28, 1976, pp. 454-5.
REFERENCE: "Woodpeckers and Head Injury," Philip R.A. May, Joaquin M. Fuster, Paul Newman and Ada Hirschman, Lancet, vol. 307, no. 7973, June 19, 1976, pp. 1347-8.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Ivan Schwab
NUTRITION: Wasmia Al-Houty of Kuwait University and Faten Al-Mussalam of the Kuwait Environment Public Authority, for showing that dung beetles are finicky eaters.
REFERENCE: "Dung Preference of the Dung Beetle Scarabaeus cristatus Fab (Coleoptera-Scarabaeidae) from Kuwait," Wasmia Al-Houty and Faten Al-Musalam, Journal of Arid Environments, vol. 35, no. 3, 1997, pp. 511-6.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Faten Al-Musalam
PEACE: Howard Stapleton of Merthyr Tydfil, Wales, for inventing an electromechanical teenager repellant -- a device that makes annoying noise designed to be audible to teenagers but not to adults; and for later using that same technology to make telephone ringtones that are audible to teenagers but not to their teachers.
REFERENCE: http://www.compoundsecurity.co.uk
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Howard Stapleton planned to attend, but his plans were interrupted by a family medical situation.
ACOUSTICS: D. Lynn Halpern (of Harvard Vanguard Medical Associates, and Brandeis University, and Northwestern University), Randolph Blake (of Vanderbilt University and Northwestern University) and James Hillenbrand (of Western Michigan University and Northwestern University) for conducting experiments to learn why people dislike the sound of fingernails scraping on a blackboard.
REFERENCE: "Psychoacoustics of a Chilling Sound," D. Lynn Halpern, Randolph Blake and James Hillenbrand, Perception and Psychophysics, vol. 39,1986, pp. 77-80.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Lynn Halpern and Randolph Blake
MATHEMATICS: Nic Svenson and Piers Barnes of the Australian Commonwealth Scientific and Research Organization, for calculating the number of photographs you must take to (almost) ensure that nobody in a group photo will have their eyes closed
REFERENCE: "Blink-Free Photos, Guaranteed," Velocity, June 2006,
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Nic Svenson and Piers Barnes
CONTACT: Nic Svenson, Communications Officer, CSIRO Industrial Physics, Phone: +61 (2) 9413 7643, Fax: +61 (2) 9413 7644, nic.svenson@csiro.au
CONTACT: Dr. Piers Barnes, Post Doctoral Fellow, CSIRO Industrial Physics, Office: +61 2 9413 7179, Mobile: +61 410 273 353, Fax: +61 2 9413 7200, <piers.barnes@csiro.au>
LITERATURE: Daniel Oppenheimer of Princeton University for his report "Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly."
REFERENCE: "Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly," Daniel M. Oppenheimer, Applied Cognitive Psychology, vol. 20, no. 2, March 2006, pp. 139-56.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Daniel Oppenheimer
MEDICINE: Francis M. Fesmire of the University of Tennessee College of Medicine, for his medical case report "Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage"; and Majed Odeh, Harry Bassan, and Arie Oliven of Bnai Zion Medical Center, Haifa, Israel, for their subsequent medical case report also titled "Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage."
REFERENCE: "Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage," Francis M. Fesmire, Annals of Emergency Medicine, vol. 17, no. 8, August 1988 p. 872.
REFERENCE: "Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage,"
Majed Odeh, Harry Bassan, and Arie Oliven, Journal of Internal Medicine, vol. 227, no. 2, February 1990, pp. 145-6. They are at the Department of Internal Medicine, Bnai Zion Medical Center, Haifa, Israel.
REFERENCE: "Hiccups and Digital Rectal Massage," M. Odeh and A. Oliven, Archives of Otolaryngology -- Head and Neck Surgery, vol. 119, 1993, p. 1383.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Francis Fesmire
PHYSICS: Basile Audoly and Sebastien Neukirch of the Universit? Pierre et Marie Curie, in Paris, for their insights into why, when you bend dry spaghetti, it often breaks into more than two pieces.
REFERENCE: "Fragmentation of Rods by Cascading Cracks: Why Spaghetti Does Not Break in Half," Basile Audoly and Sebastien Neukirch, Physical Review Letters, vol. 95, no. 9, August 26, 2005, pp. 95505-1 to 95505-1.
REFERENCE: video and other details at <http://www.lmm.jussieu.fr/spaghetti/index.html>
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Basile Audoly and Sebastien Neukirch
CHEMISTRY: Antonio Mulet, Jos? Javier Benedito and Jos? Bon of the University of Valencia, Spain, and Carmen Rossell? of the University of Illes Balears, in Palma de Mallorca, Spain, for their study "Ultrasonic Velocity in Cheddar Cheese as Affected by Temperature."
REFERENCE: "Ultrasonic Velocity in Cheddar Cheese as Affected by Temperature," Antonio Mulet, Jos? Javier Benedito, Jos? Bon, and Carmen Rossell?, Journal of Food Science, vol. 64, no. 6, 1999, pp. 1038-41.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: The winners delivered their acceptance speech via video recording.
BIOLOGY: Bart Knols (of Wageningen Agricultural University, in Wageningen, the Netherlands; and of the National Institute for Medical Research, in Ifakara Centre, Tanzania, and of the International Atomic Energy Agency, in Vienna Austria) and Ruurd de Jong (of Wageningen Agricultural University and of Santa Maria degli Angeli, Italy) for showing that the female malaria mosquito Anopheles gambiae is attracted equally to the smell of limburger cheese and to the smell of human feet.
REFERENCE: "On Human Odour, Malaria Mosquitoes, and Limburger Cheese," Bart. G.J. Knols, The Lancet, vol. 348 , November 9, 1996, p. 1322.
REFERENCE: “Behavioural and electrophysiological responses of the female malaria mosquito Anopheles gambiae (Diptera: Culicidae) to Limburger cheese volatiles,” Bulletin of Entomological Research, B.G.J. Knols, J.J.A. van Loon, A. Cork, R.D. Robinson, et al., vol. 87, 1997, pp. 151-159.
REFERENCE: "Limburger Cheese as an Attractant for the Malaria Mosquito Anopheles gambiae s.s.," B.G,J. Knols and R. De Jong, Parasitology Today, yd. 12, no. 4, 1996, pp. 159-61.
REFERENCE: "Selection of Biting Sites on Man by Two Malaria Mosquito Species," R. De Jong and B.G.J. Knols, Experientia, vol. 51, 1995, pp. 80?84.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Bart Knols
http://improbable.com/ig/ig-pastwinners.html#ig2006
The 2006 Ig Nobel Prize Winners
The 2006 Ig Nobel Prize winners were awarded on Thursday night, October 5, at the 16th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony, at Harvard's Sanders Theatre.
The ceremony was webcast at www.improbable.com. Recorded video will be posted here soon.
Two days after the ceremon y -- on Saturday, October 7 -- the new winners will give free public lectures at the Ig Informal Lectures.
ORNITHOLOGY: Ivan R. Schwab, of the University of California Davis, and the late Philip R.A. May of the University of California Los Angeles, for exploring and explaining why woodpeckers don't get headaches.
REFERENCE: "Cure for a Headache," Ivan R Schwab, British Journal of Ophthalmology, vol. 86, 2002, p. 843.
REFERENCE: "Woodpeckers and Head Injury," Philip R.A. May, Joaquin M. Fuster, Paul Newman and Ada Hirschman, Lancet, vol. 307, no. 7957, February 28, 1976, pp. 454-5.
REFERENCE: "Woodpeckers and Head Injury," Philip R.A. May, Joaquin M. Fuster, Paul Newman and Ada Hirschman, Lancet, vol. 307, no. 7973, June 19, 1976, pp. 1347-8.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Ivan Schwab
NUTRITION: Wasmia Al-Houty of Kuwait University and Faten Al-Mussalam of the Kuwait Environment Public Authority, for showing that dung beetles are finicky eaters.
REFERENCE: "Dung Preference of the Dung Beetle Scarabaeus cristatus Fab (Coleoptera-Scarabaeidae) from Kuwait," Wasmia Al-Houty and Faten Al-Musalam, Journal of Arid Environments, vol. 35, no. 3, 1997, pp. 511-6.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Faten Al-Musalam
PEACE: Howard Stapleton of Merthyr Tydfil, Wales, for inventing an electromechanical teenager repellant -- a device that makes annoying noise designed to be audible to teenagers but not to adults; and for later using that same technology to make telephone ringtones that are audible to teenagers but not to their teachers.
REFERENCE: http://www.compoundsecurity.co.uk
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Howard Stapleton planned to attend, but his plans were interrupted by a family medical situation.
ACOUSTICS: D. Lynn Halpern (of Harvard Vanguard Medical Associates, and Brandeis University, and Northwestern University), Randolph Blake (of Vanderbilt University and Northwestern University) and James Hillenbrand (of Western Michigan University and Northwestern University) for conducting experiments to learn why people dislike the sound of fingernails scraping on a blackboard.
REFERENCE: "Psychoacoustics of a Chilling Sound," D. Lynn Halpern, Randolph Blake and James Hillenbrand, Perception and Psychophysics, vol. 39,1986, pp. 77-80.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Lynn Halpern and Randolph Blake
MATHEMATICS: Nic Svenson and Piers Barnes of the Australian Commonwealth Scientific and Research Organization, for calculating the number of photographs you must take to (almost) ensure that nobody in a group photo will have their eyes closed
REFERENCE: "Blink-Free Photos, Guaranteed," Velocity, June 2006,
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Nic Svenson and Piers Barnes
CONTACT: Nic Svenson, Communications Officer, CSIRO Industrial Physics, Phone: +61 (2) 9413 7643, Fax: +61 (2) 9413 7644, nic.svenson@csiro.au
CONTACT: Dr. Piers Barnes, Post Doctoral Fellow, CSIRO Industrial Physics, Office: +61 2 9413 7179, Mobile: +61 410 273 353, Fax: +61 2 9413 7200, <piers.barnes@csiro.au>
LITERATURE: Daniel Oppenheimer of Princeton University for his report "Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly."
REFERENCE: "Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly," Daniel M. Oppenheimer, Applied Cognitive Psychology, vol. 20, no. 2, March 2006, pp. 139-56.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Daniel Oppenheimer
MEDICINE: Francis M. Fesmire of the University of Tennessee College of Medicine, for his medical case report "Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage"; and Majed Odeh, Harry Bassan, and Arie Oliven of Bnai Zion Medical Center, Haifa, Israel, for their subsequent medical case report also titled "Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage."
REFERENCE: "Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage," Francis M. Fesmire, Annals of Emergency Medicine, vol. 17, no. 8, August 1988 p. 872.
REFERENCE: "Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage,"
Majed Odeh, Harry Bassan, and Arie Oliven, Journal of Internal Medicine, vol. 227, no. 2, February 1990, pp. 145-6. They are at the Department of Internal Medicine, Bnai Zion Medical Center, Haifa, Israel.
REFERENCE: "Hiccups and Digital Rectal Massage," M. Odeh and A. Oliven, Archives of Otolaryngology -- Head and Neck Surgery, vol. 119, 1993, p. 1383.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Francis Fesmire
PHYSICS: Basile Audoly and Sebastien Neukirch of the Universit? Pierre et Marie Curie, in Paris, for their insights into why, when you bend dry spaghetti, it often breaks into more than two pieces.
REFERENCE: "Fragmentation of Rods by Cascading Cracks: Why Spaghetti Does Not Break in Half," Basile Audoly and Sebastien Neukirch, Physical Review Letters, vol. 95, no. 9, August 26, 2005, pp. 95505-1 to 95505-1.
REFERENCE: video and other details at <http://www.lmm.jussieu.fr/spaghetti/index.html>
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Basile Audoly and Sebastien Neukirch
CHEMISTRY: Antonio Mulet, Jos? Javier Benedito and Jos? Bon of the University of Valencia, Spain, and Carmen Rossell? of the University of Illes Balears, in Palma de Mallorca, Spain, for their study "Ultrasonic Velocity in Cheddar Cheese as Affected by Temperature."
REFERENCE: "Ultrasonic Velocity in Cheddar Cheese as Affected by Temperature," Antonio Mulet, Jos? Javier Benedito, Jos? Bon, and Carmen Rossell?, Journal of Food Science, vol. 64, no. 6, 1999, pp. 1038-41.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: The winners delivered their acceptance speech via video recording.
BIOLOGY: Bart Knols (of Wageningen Agricultural University, in Wageningen, the Netherlands; and of the National Institute for Medical Research, in Ifakara Centre, Tanzania, and of the International Atomic Energy Agency, in Vienna Austria) and Ruurd de Jong (of Wageningen Agricultural University and of Santa Maria degli Angeli, Italy) for showing that the female malaria mosquito Anopheles gambiae is attracted equally to the smell of limburger cheese and to the smell of human feet.
REFERENCE: "On Human Odour, Malaria Mosquitoes, and Limburger Cheese," Bart. G.J. Knols, The Lancet, vol. 348 , November 9, 1996, p. 1322.
REFERENCE: “Behavioural and electrophysiological responses of the female malaria mosquito Anopheles gambiae (Diptera: Culicidae) to Limburger cheese volatiles,” Bulletin of Entomological Research, B.G.J. Knols, J.J.A. van Loon, A. Cork, R.D. Robinson, et al., vol. 87, 1997, pp. 151-159.
REFERENCE: "Limburger Cheese as an Attractant for the Malaria Mosquito Anopheles gambiae s.s.," B.G,J. Knols and R. De Jong, Parasitology Today, yd. 12, no. 4, 1996, pp. 159-61.
REFERENCE: "Selection of Biting Sites on Man by Two Malaria Mosquito Species," R. De Jong and B.G.J. Knols, Experientia, vol. 51, 1995, pp. 80?84.
WHO ATTENDED THE IG NOBEL PRIZE CEREMONY: Bart Knols
ノーベル文学賞は12日発表 村上春樹氏にも注目
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=home&NWID=2006100601000661
【ロンドン6日共同】スウェーデン・アカデミーは6日、今年のノーベル文学賞を12日午後1時(日本時間同8時)に発表することを明らかにした。
2004年、05年の受賞者はいずれもその年のフランツ・カフカ賞(チェコ)を受賞。今年のカフカ賞は日本の作家、村上春樹氏が受賞を決めており、注目されている。スウェーデン・アカデミーは候補者を明らかにしていない。
村上氏は今年、アイルランドのフランク・オコナー国際短編賞も受賞している。
有力候補としては、トルコのオルハン・パムク氏やポーランドのジャーナリスト、リシャルド・カプシチンスキ氏らの名前が報じられている。
他のノーベル各賞は2日(医学生理学賞)から13日(平和賞)までに、すべての賞が発表されることが決まっている。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=home&NWID=2006100601000661
【ロンドン6日共同】スウェーデン・アカデミーは6日、今年のノーベル文学賞を12日午後1時(日本時間同8時)に発表することを明らかにした。
2004年、05年の受賞者はいずれもその年のフランツ・カフカ賞(チェコ)を受賞。今年のカフカ賞は日本の作家、村上春樹氏が受賞を決めており、注目されている。スウェーデン・アカデミーは候補者を明らかにしていない。
村上氏は今年、アイルランドのフランク・オコナー国際短編賞も受賞している。
有力候補としては、トルコのオルハン・パムク氏やポーランドのジャーナリスト、リシャルド・カプシチンスキ氏らの名前が報じられている。
他のノーベル各賞は2日(医学生理学賞)から13日(平和賞)までに、すべての賞が発表されることが決まっている。
「直腸刺激でしゃっくり止める」に、イグ・ノーベル医学賞
2006.10.06
Web posted at: 21:03 JST
- CNN/AP
http://www.cnn.co.jp/science/CNN200610060022.html
ボストン──「笑えるとしか言いようがなく、しかも記憶に残り、人々を考えさせる業績」に贈られる毎年恒例のイグ・ノーベル賞の第16回授賞式が5日、米ハーバード大学サンダース・シアターであり、「しつこいしゃっくりを直腸刺激で止めることに成功した」という研究報告に、医学賞が贈られた。
今年の全受賞者は以下の通り。
○鳥類学賞:「頭を振り続けるキツツキはなぜ頭痛に見舞われないのか」の研究で、米カリフォルニア大学デイビス校のアイバン・R・シュワブ氏とカリフォルニア大学ロサンゼルス校のフィリップ・R・A・メイ氏に授与。
○栄養学賞:「フンコロガシの食嗜好(しこう)についての研究」で、クウェート大学のワスミア・アルフティ氏と、クウェート環境公衆局のファテン・アルムッサーラム氏に授与。2氏は、動物の糞を食物とするフンコロガシの食嗜好について調査し、フンコロガシが肉食動物よりも草食動物の糞を好み、草食動物の中でも、馬が一番で、続いて羊、ラクダの糞の順に好みがあることを突き止めた。
○平和賞:高周波雑音発生装置「モスキート」を発明した英国ウェールズのハワード・ステープルトン氏に授与。同氏が発明したのは、年寄りには聞こえず、若者だけに聞こえる高周波の雑音を利用した「若者よけ」の装置だったが、若者がこの機能を逆に利用。授業中の教室内でも教師に知られない携帯電話の着信メロディとして、欧米で大流行した。
○音響学賞:「爪(つめ)で黒板をひっかいた時に発生する音が嫌われる理由についての実験」で、米ノースウェスタン大学のD・リン・ハルパーン氏とラドルフ・ブレイク氏、ジェイムズ・ヒレンブランド氏の3人に授与。3氏は、黒板を爪でひっかいた時の音が、どうしてこれほどまで、全世界中で嫌がられるのかを研究した。
○数学賞:「グループ写真を撮る際、目を閉じた人が1人もいない写真を撮るためには、何枚撮影する必要があるか」を計算した、オーストラリア国立科学技術研究機構のニック・スベンソン氏とピアース・バーンズ氏に授与。
○文学賞:「必要性に関係なく用いられる学問的専門用語がもたらす影響について──不必要に長い単語の使用における問題」の研究で、プリンストン大学のダニエル・オッペンハイマー氏に授与。同氏の研究報告書の題が、不必要に長い単語を用いている。
○医学賞:「直腸刺激による、しつこく続くしゃっくりの停止」の研究で、米テネシー大学医学部のフランシス・M・フェスマイア氏と、イスラエル・ハイファにあるブナイシオン医療センターのマジェド・オデー氏、ハリー・バッサン氏、アリエ・オリベン氏に授与。研究によると、急性すい炎を発症して経鼻チューブを挿入された60歳男性が、経鼻チューブがきっかけでしゃっくりが止まらなくなった。しつこいしゃっくりは、チューブを外したり薬物を投与しても止まらなかったが、直腸刺激によって止めることに成功。数時間後に再びしゃっくりが始まった際も、同様に止めることができたという。
○物理学賞:「乾燥スパゲティを曲げると、しばしば2つ以上の部分に折れてしまうのはなぜか」を調べた仏ピエール・マリー・キュリー大学のバジル・オードリー氏とセバスティアン・ヌーキルシュ氏に授与。
○化学賞:「温度影響を受けるチェダーチーズの超音波速度」についての研究で、スペイン・バレンシア大学のアントニオ・ミュレ氏、ホセ・ハビエル・ベネディート氏、ホセ・ボン氏、スペイン・マジョルカ島バレアレス大学のカルメン・ロッセロ氏に授与。
○生物学賞:「マラリア媒介蚊のメスが、リンブルガー・チーズと人間の足のにおいを好むこと」を示した、オランダ・ワーヘニンゲン農業大学のバート・クノールズ氏とルルド・デ・ジョン氏に授与。両氏の研究によって、マラリアを媒介するガンビアハマダラカが、ベルギー産のチーズ「リンブルガー」と人間の足のにおいの両方に、まったく同じように惹き付けられることが判明した。
2006.10.06
Web posted at: 21:03 JST
- CNN/AP
http://www.cnn.co.jp/science/CNN200610060022.html
ボストン──「笑えるとしか言いようがなく、しかも記憶に残り、人々を考えさせる業績」に贈られる毎年恒例のイグ・ノーベル賞の第16回授賞式が5日、米ハーバード大学サンダース・シアターであり、「しつこいしゃっくりを直腸刺激で止めることに成功した」という研究報告に、医学賞が贈られた。
今年の全受賞者は以下の通り。
○鳥類学賞:「頭を振り続けるキツツキはなぜ頭痛に見舞われないのか」の研究で、米カリフォルニア大学デイビス校のアイバン・R・シュワブ氏とカリフォルニア大学ロサンゼルス校のフィリップ・R・A・メイ氏に授与。
○栄養学賞:「フンコロガシの食嗜好(しこう)についての研究」で、クウェート大学のワスミア・アルフティ氏と、クウェート環境公衆局のファテン・アルムッサーラム氏に授与。2氏は、動物の糞を食物とするフンコロガシの食嗜好について調査し、フンコロガシが肉食動物よりも草食動物の糞を好み、草食動物の中でも、馬が一番で、続いて羊、ラクダの糞の順に好みがあることを突き止めた。
○平和賞:高周波雑音発生装置「モスキート」を発明した英国ウェールズのハワード・ステープルトン氏に授与。同氏が発明したのは、年寄りには聞こえず、若者だけに聞こえる高周波の雑音を利用した「若者よけ」の装置だったが、若者がこの機能を逆に利用。授業中の教室内でも教師に知られない携帯電話の着信メロディとして、欧米で大流行した。
○音響学賞:「爪(つめ)で黒板をひっかいた時に発生する音が嫌われる理由についての実験」で、米ノースウェスタン大学のD・リン・ハルパーン氏とラドルフ・ブレイク氏、ジェイムズ・ヒレンブランド氏の3人に授与。3氏は、黒板を爪でひっかいた時の音が、どうしてこれほどまで、全世界中で嫌がられるのかを研究した。
○数学賞:「グループ写真を撮る際、目を閉じた人が1人もいない写真を撮るためには、何枚撮影する必要があるか」を計算した、オーストラリア国立科学技術研究機構のニック・スベンソン氏とピアース・バーンズ氏に授与。
○文学賞:「必要性に関係なく用いられる学問的専門用語がもたらす影響について──不必要に長い単語の使用における問題」の研究で、プリンストン大学のダニエル・オッペンハイマー氏に授与。同氏の研究報告書の題が、不必要に長い単語を用いている。
○医学賞:「直腸刺激による、しつこく続くしゃっくりの停止」の研究で、米テネシー大学医学部のフランシス・M・フェスマイア氏と、イスラエル・ハイファにあるブナイシオン医療センターのマジェド・オデー氏、ハリー・バッサン氏、アリエ・オリベン氏に授与。研究によると、急性すい炎を発症して経鼻チューブを挿入された60歳男性が、経鼻チューブがきっかけでしゃっくりが止まらなくなった。しつこいしゃっくりは、チューブを外したり薬物を投与しても止まらなかったが、直腸刺激によって止めることに成功。数時間後に再びしゃっくりが始まった際も、同様に止めることができたという。
○物理学賞:「乾燥スパゲティを曲げると、しばしば2つ以上の部分に折れてしまうのはなぜか」を調べた仏ピエール・マリー・キュリー大学のバジル・オードリー氏とセバスティアン・ヌーキルシュ氏に授与。
○化学賞:「温度影響を受けるチェダーチーズの超音波速度」についての研究で、スペイン・バレンシア大学のアントニオ・ミュレ氏、ホセ・ハビエル・ベネディート氏、ホセ・ボン氏、スペイン・マジョルカ島バレアレス大学のカルメン・ロッセロ氏に授与。
○生物学賞:「マラリア媒介蚊のメスが、リンブルガー・チーズと人間の足のにおいを好むこと」を示した、オランダ・ワーヘニンゲン農業大学のバート・クノールズ氏とルルド・デ・ジョン氏に授与。両氏の研究によって、マラリアを媒介するガンビアハマダラカが、ベルギー産のチーズ「リンブルガー」と人間の足のにおいの両方に、まったく同じように惹き付けられることが判明した。
愉快な研究にイグ・ノーベル賞 日本人受賞は11人
http://www.asahi.com/science/news/TKY200610070186.html
イグ・ノーベル賞は「人々を笑わせ、考えさせてくれた研究」に贈られる。米ハーバード大サンダース講堂で5日行われた授賞式は熱気と大歓声、そして笑いに包まれた。米国最古の「学問の町」で研究者や市民が式典を支える姿に、科学大国・米国の奥深さとおおらかさを見た。
◇
「科学者はユーモアにあふれているのに、堅苦しくて無味乾燥な人たちだと誤解されている」
ほうきを手に会場に現れたハーバード大のロイ・グラウバー教授(81)は熱っぽく語った。
授賞式では紙飛行機が飛び交う。10年ほど前から会場を掃除してきた。昨年、レーザーの理論で本物のノーベル物理学賞を受賞した。「掃除のおかげではありません」と紹介されると、ほうきを掲げて大歓声に応えた。
16回目の授賞式の今回は6人の科学系ノーベル賞学者が参加した。いずれもケンブリッジや周辺が拠点の研究者たちだ。
平和賞の受賞研究となった、若者にしか聞こえない高周波雑音発生器「モスキート」を使い、ノーベル賞学者が聞き取れるかどうかを調べる実験も行われた。「もちろん私には聞こえなかった。聴力は年齢で敏感に変わる。科学の基本だ」とグラウバー教授。
イグ・ノーベル賞は91年、ハーバード大系の科学雑誌「ありそうもない研究」の編集者マーク・エイブラハムズさん(50)が創設した。「賞といえばノーベル賞やアカデミー賞みたいに『最善』か、逆に『最悪』に贈られるものばかり。でも、何かを考えるきっかけを与えてくれるものって大切でしょう」
受賞研究は「キツツキはなぜ頭が痛くならないのか」(鳥類学賞)、「乾燥スパゲティを曲げると、しばしば二つより多い部分に折れてしまうのはなぜか」(物理学賞)、「だれも目を閉じていない集合写真を撮るには、何枚撮影すればいいか」(数学賞)など素朴な疑問に答えるテーマが多い。研究自体は極めてまじめだ。
「スパゲティ」研究チームの一人、仏ピエール・マリー・キュリー大のバジル・オードリーさん(32)は「力を加えた時に物がどう壊れるかは、工学の最も重要な研究テーマの一つです」。大学ではDNAに力を加えた時にどう壊れるのかも調べている。
受賞者の旅費は自己負担、贈られるのは「栄誉」と手づくりの記念品だけ。運営を支えるのは研究者や市民らのボランティアだ。
受賞者を決めるのはエイブラハムズさんと50人ほどの仲間たち。「日本人も何人かいる。名前は秘密だけどね」
◇
日本はイグ・ノーベル賞大国だ。日本人が関係した受賞は11件に上る。
03年に「ハトに嫌われた銅像の化学的考察」で化学賞を受けた広瀬幸雄さん(現・金沢学院大教授)は「認められて自信にもつながりました」と振り返る。今は講演の依頼が相次ぐ。
97年の生物学賞を受けた柳生隆視・寝屋川サナトリウム副院長は本業の統合失調症研究ではなく、関西医科大の講師時代、ガムの味の違いで脳波の変化をみた研究が対象になった。受賞は雑誌で知った。「授賞式の招待状を見たような気もするが、よく覚えてないんです」
http://www.asahi.com/science/news/TKY200610070186.html
イグ・ノーベル賞は「人々を笑わせ、考えさせてくれた研究」に贈られる。米ハーバード大サンダース講堂で5日行われた授賞式は熱気と大歓声、そして笑いに包まれた。米国最古の「学問の町」で研究者や市民が式典を支える姿に、科学大国・米国の奥深さとおおらかさを見た。
◇
「科学者はユーモアにあふれているのに、堅苦しくて無味乾燥な人たちだと誤解されている」
ほうきを手に会場に現れたハーバード大のロイ・グラウバー教授(81)は熱っぽく語った。
授賞式では紙飛行機が飛び交う。10年ほど前から会場を掃除してきた。昨年、レーザーの理論で本物のノーベル物理学賞を受賞した。「掃除のおかげではありません」と紹介されると、ほうきを掲げて大歓声に応えた。
16回目の授賞式の今回は6人の科学系ノーベル賞学者が参加した。いずれもケンブリッジや周辺が拠点の研究者たちだ。
平和賞の受賞研究となった、若者にしか聞こえない高周波雑音発生器「モスキート」を使い、ノーベル賞学者が聞き取れるかどうかを調べる実験も行われた。「もちろん私には聞こえなかった。聴力は年齢で敏感に変わる。科学の基本だ」とグラウバー教授。
イグ・ノーベル賞は91年、ハーバード大系の科学雑誌「ありそうもない研究」の編集者マーク・エイブラハムズさん(50)が創設した。「賞といえばノーベル賞やアカデミー賞みたいに『最善』か、逆に『最悪』に贈られるものばかり。でも、何かを考えるきっかけを与えてくれるものって大切でしょう」
受賞研究は「キツツキはなぜ頭が痛くならないのか」(鳥類学賞)、「乾燥スパゲティを曲げると、しばしば二つより多い部分に折れてしまうのはなぜか」(物理学賞)、「だれも目を閉じていない集合写真を撮るには、何枚撮影すればいいか」(数学賞)など素朴な疑問に答えるテーマが多い。研究自体は極めてまじめだ。
「スパゲティ」研究チームの一人、仏ピエール・マリー・キュリー大のバジル・オードリーさん(32)は「力を加えた時に物がどう壊れるかは、工学の最も重要な研究テーマの一つです」。大学ではDNAに力を加えた時にどう壊れるのかも調べている。
受賞者の旅費は自己負担、贈られるのは「栄誉」と手づくりの記念品だけ。運営を支えるのは研究者や市民らのボランティアだ。
受賞者を決めるのはエイブラハムズさんと50人ほどの仲間たち。「日本人も何人かいる。名前は秘密だけどね」
◇
日本はイグ・ノーベル賞大国だ。日本人が関係した受賞は11件に上る。
03年に「ハトに嫌われた銅像の化学的考察」で化学賞を受けた広瀬幸雄さん(現・金沢学院大教授)は「認められて自信にもつながりました」と振り返る。今は講演の依頼が相次ぐ。
97年の生物学賞を受けた柳生隆視・寝屋川サナトリウム副院長は本業の統合失調症研究ではなく、関西医科大の講師時代、ガムの味の違いで脳波の変化をみた研究が対象になった。受賞は雑誌で知った。「授賞式の招待状を見たような気もするが、よく覚えてないんです」
ノーベル経済学賞に米コロンビア大・フェルプス教授
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061009-00000413-yom-soci
【ロンドン=中村宏之】スウェーデン王立科学アカデミーは9日、2006年のノーベル経済学賞を米コロンビア大学のエドムンド・フェルプス教授(73)に授与すると発表した。
授賞理由について同アカデミーは、マクロ経済におけるインフレ率と失業率との関係について論理的な分析を行った功績としている。フェルプス教授は1933年米国生まれで、米イエール大大学院修了。
授賞式は12月10日にスウェーデンのストックホルムで行われ、賞金1千万スウェーデン・クローナ(約1億5千万円)が贈られる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061009-00000413-yom-soci
【ロンドン=中村宏之】スウェーデン王立科学アカデミーは9日、2006年のノーベル経済学賞を米コロンビア大学のエドムンド・フェルプス教授(73)に授与すると発表した。
授賞理由について同アカデミーは、マクロ経済におけるインフレ率と失業率との関係について論理的な分析を行った功績としている。フェルプス教授は1933年米国生まれで、米イエール大大学院修了。
授賞式は12月10日にスウェーデンのストックホルムで行われ、賞金1千万スウェーデン・クローナ(約1億5千万円)が贈られる。
ノーベル賞:基礎研究に光 自然科学3分野、米国勢独占
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/kagaku/news/20061011ddm016040071000c.html
◇今年のノーベル賞
06年の自然科学3分野のノーベル賞受賞者5人が決まった。化学賞と医学生理学賞は、DNA(デオキシリボ核酸)の遺伝情報を基に必要なたんぱく質を作ったり、不要なたんぱく質が作られるのを防ぐ仕組みを解明した研究に贈られる。物理学賞の2人は、宇宙誕生を説明する「ビッグバン理論」を観測で裏付けた。いずれも、生命現象の基本原理や宇宙の起源という根源的な謎の解明に迫った業績で、基礎研究に光が当てられた。受賞者は全員米国人で、米国勢の独占は23年ぶりとなる。【山田大輔、西川拓】
■医学生理学賞
◆RNAがDNAの働き制御
◇「伝令の脇役」説覆し、がん治療にも応用へ
生物の遺伝の主役は、情報を4種類の塩基の配列として記憶するDNA。この配列を写し取るRNA(リボ核酸)は伝令の脇役−−。これが長らく信じられてきた生物学の「セントラルドグマ(中心教義)」だった。しかし、医学生理学賞に決まったアンドルー・ファイアー米スタンフォード大教授(47)とクレイグ・メロー米マサチューセッツ大教授(45)は、RNAがDNAの働きを制御していることを発見し、セントラルドグマを覆した。
2人は、2本の短いRNAがペアになった二重鎖RNAを線虫に注入すると、筋肉が正常に作られなくなることを見つけ、98年に報告した。DNAの情報を運ぶ伝令RNA(mRNA)を二重鎖RNAが破壊する現象のため、「RNA干渉」=図=と名付けた。
理化学研究所遺伝子構造・機能研究グループの林崎良英プロジェクトディレクターは「半世紀前のDNAの二重らせん構造の発見に匹敵する業績だ」と評価する。RNA干渉を応用すれば標的とする異常な遺伝子の機能を阻害できるため、がんやエイズなど多くの病気の治療法の開発を目指した研究も進んでいる。
■化学賞
◆mRNAの転写、仕組み分析
◇酵母の酵素結晶化、三次元構造を解明
そのmRNAがDNAの情報を写し取って作られる過程(転写)を、その際に働くさまざまな物質を含めて巧妙に描き出したのが、化学賞に選ばれたロジャー・コーンバーグ米スタンフォード大教授(59)だ。すべて01年以後の新しい成果。最新論文の筆頭執筆者で受賞発表の3日前、独立して教授の研究室を離れたばかりの高木雄一郎・インディアナ大助教授(構造生物学)は「居合わせられなかったのは残念だが、おかげで私の研究も注目の的」と喜ぶ。
mRNAの転写は「RNAポリメラーゼ」という酵素がつかさどる。教授は酵母から取り出した酵素を結晶化し、X線で三次元構造を解明することに成功。転写の仕組みを精密に分析した=図。教授の研究は、再生医療や転写ミスが原因とされるがんや心臓病などの新薬開発に大きなインパクトを与えている。
◇親子で受賞者に
コーンバーグ教授は、59年ノーベル医学生理学賞を受賞したアーサー・コーンバーグ博士(88)の長男。8歳のころから「好きな場所は実験室」と言うほど、父の影響を受けた。12歳の時にはストックホルムで父の授賞式に立ち会った。今回の授賞業績も、父の成果「RNAとDNAの合成メカニズムの発見」をさらに追究した結果だ。
「ノーベル賞学者の息子というプレッシャーはあったはず」と高木さん。酵素の構造解明が近づいた99年、高木さんはだるまを贈った。しかし、解明しても、だるまは片目のまま。「この意味、分かるでしょ」と受賞発表の翌朝、やっと両目の入っただるまの写真が元同僚からメールで届いた。
■物理学賞
◆宇宙…火の玉大爆発し誕生
◇「ゆらぎ」10万分の1、COBEで放射観測
宇宙は遠い昔、小さな火の玉が大爆発して生まれ、これまで膨張を続けてきた−−。壮大な宇宙誕生の物語「ビッグバン理論」を観測で証明したことが物理学賞となった。米航空宇宙局(NASA)のジョン・マザー博士(60)と米カリフォルニア大のジョージ・スムート教授(61)は、89年に打ち上げられた米観測衛星「COBE(コービー)」の研究責任者だ。
超高温・超高密度で何もかもが溶け合っていた熱い宇宙の名残が、絶対温度2・7度(氷点下約270度)の「宇宙背景放射」となって、今も宇宙を満たしている。マザー博士らはCOBEで放射を精密に観測、理論通りの特徴を確認して「ビッグバンはあった」と証明した。スムート教授らは、放射に10万分の1レベルの温度差(ゆらぎ)を発見。温度のゆらぎは物質の偏りにつながり、現在の銀河や星を生んだと考えられている。
東京大大学院の佐藤勝彦教授(宇宙理論)らが提唱する「インフレーション理論」では、ゆらぎの素は「火の玉」以前からあるとされる。佐藤教授は「これより小さければ、銀河も何も生まれないギリギリのゆらぎだった」と説明する。
ビッグバン理論は46年、ロシア出身で米に亡命した物理学者ガモフ(04〜68年)が初めて提唱。DNAが4種の暗号(塩基)で遺伝情報を記録しているという学説も、実はガモフの創案だ。今年の陰の主役は、ノーベル賞をもらい損ねた巨人、ガモフかもしれない。
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/kagaku/news/20061011ddm016040071000c.html
◇今年のノーベル賞
06年の自然科学3分野のノーベル賞受賞者5人が決まった。化学賞と医学生理学賞は、DNA(デオキシリボ核酸)の遺伝情報を基に必要なたんぱく質を作ったり、不要なたんぱく質が作られるのを防ぐ仕組みを解明した研究に贈られる。物理学賞の2人は、宇宙誕生を説明する「ビッグバン理論」を観測で裏付けた。いずれも、生命現象の基本原理や宇宙の起源という根源的な謎の解明に迫った業績で、基礎研究に光が当てられた。受賞者は全員米国人で、米国勢の独占は23年ぶりとなる。【山田大輔、西川拓】
■医学生理学賞
◆RNAがDNAの働き制御
◇「伝令の脇役」説覆し、がん治療にも応用へ
生物の遺伝の主役は、情報を4種類の塩基の配列として記憶するDNA。この配列を写し取るRNA(リボ核酸)は伝令の脇役−−。これが長らく信じられてきた生物学の「セントラルドグマ(中心教義)」だった。しかし、医学生理学賞に決まったアンドルー・ファイアー米スタンフォード大教授(47)とクレイグ・メロー米マサチューセッツ大教授(45)は、RNAがDNAの働きを制御していることを発見し、セントラルドグマを覆した。
2人は、2本の短いRNAがペアになった二重鎖RNAを線虫に注入すると、筋肉が正常に作られなくなることを見つけ、98年に報告した。DNAの情報を運ぶ伝令RNA(mRNA)を二重鎖RNAが破壊する現象のため、「RNA干渉」=図=と名付けた。
理化学研究所遺伝子構造・機能研究グループの林崎良英プロジェクトディレクターは「半世紀前のDNAの二重らせん構造の発見に匹敵する業績だ」と評価する。RNA干渉を応用すれば標的とする異常な遺伝子の機能を阻害できるため、がんやエイズなど多くの病気の治療法の開発を目指した研究も進んでいる。
■化学賞
◆mRNAの転写、仕組み分析
◇酵母の酵素結晶化、三次元構造を解明
そのmRNAがDNAの情報を写し取って作られる過程(転写)を、その際に働くさまざまな物質を含めて巧妙に描き出したのが、化学賞に選ばれたロジャー・コーンバーグ米スタンフォード大教授(59)だ。すべて01年以後の新しい成果。最新論文の筆頭執筆者で受賞発表の3日前、独立して教授の研究室を離れたばかりの高木雄一郎・インディアナ大助教授(構造生物学)は「居合わせられなかったのは残念だが、おかげで私の研究も注目の的」と喜ぶ。
mRNAの転写は「RNAポリメラーゼ」という酵素がつかさどる。教授は酵母から取り出した酵素を結晶化し、X線で三次元構造を解明することに成功。転写の仕組みを精密に分析した=図。教授の研究は、再生医療や転写ミスが原因とされるがんや心臓病などの新薬開発に大きなインパクトを与えている。
◇親子で受賞者に
コーンバーグ教授は、59年ノーベル医学生理学賞を受賞したアーサー・コーンバーグ博士(88)の長男。8歳のころから「好きな場所は実験室」と言うほど、父の影響を受けた。12歳の時にはストックホルムで父の授賞式に立ち会った。今回の授賞業績も、父の成果「RNAとDNAの合成メカニズムの発見」をさらに追究した結果だ。
「ノーベル賞学者の息子というプレッシャーはあったはず」と高木さん。酵素の構造解明が近づいた99年、高木さんはだるまを贈った。しかし、解明しても、だるまは片目のまま。「この意味、分かるでしょ」と受賞発表の翌朝、やっと両目の入っただるまの写真が元同僚からメールで届いた。
■物理学賞
◆宇宙…火の玉大爆発し誕生
◇「ゆらぎ」10万分の1、COBEで放射観測
宇宙は遠い昔、小さな火の玉が大爆発して生まれ、これまで膨張を続けてきた−−。壮大な宇宙誕生の物語「ビッグバン理論」を観測で証明したことが物理学賞となった。米航空宇宙局(NASA)のジョン・マザー博士(60)と米カリフォルニア大のジョージ・スムート教授(61)は、89年に打ち上げられた米観測衛星「COBE(コービー)」の研究責任者だ。
超高温・超高密度で何もかもが溶け合っていた熱い宇宙の名残が、絶対温度2・7度(氷点下約270度)の「宇宙背景放射」となって、今も宇宙を満たしている。マザー博士らはCOBEで放射を精密に観測、理論通りの特徴を確認して「ビッグバンはあった」と証明した。スムート教授らは、放射に10万分の1レベルの温度差(ゆらぎ)を発見。温度のゆらぎは物質の偏りにつながり、現在の銀河や星を生んだと考えられている。
東京大大学院の佐藤勝彦教授(宇宙理論)らが提唱する「インフレーション理論」では、ゆらぎの素は「火の玉」以前からあるとされる。佐藤教授は「これより小さければ、銀河も何も生まれないギリギリのゆらぎだった」と説明する。
ビッグバン理論は46年、ロシア出身で米に亡命した物理学者ガモフ(04〜68年)が初めて提唱。DNAが4種の暗号(塩基)で遺伝情報を記録しているという学説も、実はガモフの創案だ。今年の陰の主役は、ノーベル賞をもらい損ねた巨人、ガモフかもしれない。
ノーベル文学賞はトルコのオルハン・パムク氏
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061012-00000513-yom-soci
【ストックホルム=本間圭一】スウェーデン・アカデミー(本部・ストックホルム)は12日、2006年のノーベル文学賞を・トルコの作家オルハン・パムク氏(54)に与えると発表した。
トルコ人の同賞受賞は初めて。同アカデミーは授賞理由として、「異文化の衝突と混合の新たな象徴を見いだした」と指摘した。賞金は1000万スウェーデン・クローナ(約1億6600万円)。授賞式は12月10日、ストックホルムで開かれる。
パムク氏は、イスタンブール生まれ。82年にデビューし、17世紀のイスタンブールを舞台にした「白い城」(85年)で国外でも評価を高め、「黒き書」(90年)や「新しき人生」(96年)ではトルコの古い文化を描いた。西洋と非西洋の文化の違いを描いた「わたしの名は紅(あか)」(2000年)、イスラム原理主義と世俗主義との対立を示した「雪」(02年)は日本でも翻訳されている。
一応。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061012-00000513-yom-soci
【ストックホルム=本間圭一】スウェーデン・アカデミー(本部・ストックホルム)は12日、2006年のノーベル文学賞を・トルコの作家オルハン・パムク氏(54)に与えると発表した。
トルコ人の同賞受賞は初めて。同アカデミーは授賞理由として、「異文化の衝突と混合の新たな象徴を見いだした」と指摘した。賞金は1000万スウェーデン・クローナ(約1億6600万円)。授賞式は12月10日、ストックホルムで開かれる。
パムク氏は、イスタンブール生まれ。82年にデビューし、17世紀のイスタンブールを舞台にした「白い城」(85年)で国外でも評価を高め、「黒き書」(90年)や「新しき人生」(96年)ではトルコの古い文化を描いた。西洋と非西洋の文化の違いを描いた「わたしの名は紅(あか)」(2000年)、イスラム原理主義と世俗主義との対立を示した「雪」(02年)は日本でも翻訳されている。
一応。
韓国にも「猟奇ノーベル賞」受賞者が2人…
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/10/09/20061009000055.html
先週、ノーベル生理学賞をはじめ、物理学、化学賞が相次いで発表された。もしかしたらと思っていたが、今年も韓国人の受賞者は出なかった。
しかし、もうひとつのノーベル賞には韓国人受賞者が2人もいる。猟奇ノーベル賞とも呼ばれる「Ig」ノーベル賞だ。
今月6日、米国科学技術界の「ありえなそうな研究年譜(Annals of Improbable Research)」誌は、ハーバード大で「もう2度とできず、してもいけない」奇抜な研究と業績に対し、Igノーベル賞を授与した。まさに猟奇ノーベル賞と言えよう。
今年の受賞者で最も目立ったのは、子供や青少年にしか聞こえない超音波を放出する機械を発明して平和賞を受賞した英国のハワード・ステイプルトンだ。超音波で蚊を追い払うように、この機械で食料品店やショッピングモールで叫び声をあげたり悪態をついてうろつく青少年らを追い出し、店に平和をもたらしたというもの。
科学分野では、テネシー大学の応急医学者が肛門に指を入れてひどいしゃっくりを治した功労で医学賞を受賞、キツツキが脳震盪にかからない理由を明らかにしたカリフォルニア大学の研究陣が鳥類学賞を受けた。彼らによると、キツツキの脳は贈り物を包む包装材のようにスポンジ形態の厚い頭蓋骨が脳を保護している上、木をつつく1000分の1秒前に目をつぶって目玉が飛び出すのを防ぐという。また、バンダビルト大学の研究陣は黒板をつめで引っかく音がチンパンジーの警告音と似ているということを発見し、音響学賞を受賞した。経済学賞はジャンク・ボンド(junk bond)の創始者であるマイケル・ミルケンが受賞した。
猟奇ノーベル賞ではあるが、韓国人受賞者もいる。1999年にクォン・ヒョクホ氏が香りが出るスーツを開発した功労で環境保護賞を、2000年には文鮮明(ムン・ソンミョン)統一教教祖が、1960年の36組をはじめ、97年には3600組まで合同結婚させた功労で経済学賞を受賞している。笑うべきか、泣くべきか、少しもの寂しい。
猟奇・・。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/10/09/20061009000055.html
先週、ノーベル生理学賞をはじめ、物理学、化学賞が相次いで発表された。もしかしたらと思っていたが、今年も韓国人の受賞者は出なかった。
しかし、もうひとつのノーベル賞には韓国人受賞者が2人もいる。猟奇ノーベル賞とも呼ばれる「Ig」ノーベル賞だ。
今月6日、米国科学技術界の「ありえなそうな研究年譜(Annals of Improbable Research)」誌は、ハーバード大で「もう2度とできず、してもいけない」奇抜な研究と業績に対し、Igノーベル賞を授与した。まさに猟奇ノーベル賞と言えよう。
今年の受賞者で最も目立ったのは、子供や青少年にしか聞こえない超音波を放出する機械を発明して平和賞を受賞した英国のハワード・ステイプルトンだ。超音波で蚊を追い払うように、この機械で食料品店やショッピングモールで叫び声をあげたり悪態をついてうろつく青少年らを追い出し、店に平和をもたらしたというもの。
科学分野では、テネシー大学の応急医学者が肛門に指を入れてひどいしゃっくりを治した功労で医学賞を受賞、キツツキが脳震盪にかからない理由を明らかにしたカリフォルニア大学の研究陣が鳥類学賞を受けた。彼らによると、キツツキの脳は贈り物を包む包装材のようにスポンジ形態の厚い頭蓋骨が脳を保護している上、木をつつく1000分の1秒前に目をつぶって目玉が飛び出すのを防ぐという。また、バンダビルト大学の研究陣は黒板をつめで引っかく音がチンパンジーの警告音と似ているということを発見し、音響学賞を受賞した。経済学賞はジャンク・ボンド(junk bond)の創始者であるマイケル・ミルケンが受賞した。
猟奇ノーベル賞ではあるが、韓国人受賞者もいる。1999年にクォン・ヒョクホ氏が香りが出るスーツを開発した功労で環境保護賞を、2000年には文鮮明(ムン・ソンミョン)統一教教祖が、1960年の36組をはじめ、97年には3600組まで合同結婚させた功労で経済学賞を受賞している。笑うべきか、泣くべきか、少しもの寂しい。
猟奇・・。
論文の被引用度世界1位に輝いた審良・阪大教授、
ノーベル賞発表3日前にJSTでレクチャー会
http://biotech.nikkeibp.co.jp/bionewsn/detail.jsp?id=20039794&newsid=SPC2006102742188&pg_nm=1&sai1=0&new1=1&news1=1&icate=0&yunw=1
2006年10月27日未明現在、米NCBIのPubMedにおいて検索語「Akira S」がヒットする論文はちょうど600報。このうち550報ほどは、自然免疫(関連記事1)の重要性を世に知らしめた審良静男・大阪大学微生物病研究所自然免疫学分野教授(関連記事2)が著者に名を連ねる論文だ。2006年のノーベル医学生理学賞がRNA干渉(RNAi)現象を1998年に報告した線虫の研究者2人に贈ると発表された06年10月2日(関連記事3)の3日前の9月29日、科学技術振興機構(JST)は、審良教授を招いた報道機関向けレクチャー会を東京本部で開催した(この講義および懇親会のリポートは、10月25日発行の「BTJジャーナル」10月号P.14-15に掲載)。
ノーベル賞発表3日前にJSTでレクチャー会
http://biotech.nikkeibp.co.jp/bionewsn/detail.jsp?id=20039794&newsid=SPC2006102742188&pg_nm=1&sai1=0&new1=1&news1=1&icate=0&yunw=1
2006年10月27日未明現在、米NCBIのPubMedにおいて検索語「Akira S」がヒットする論文はちょうど600報。このうち550報ほどは、自然免疫(関連記事1)の重要性を世に知らしめた審良静男・大阪大学微生物病研究所自然免疫学分野教授(関連記事2)が著者に名を連ねる論文だ。2006年のノーベル医学生理学賞がRNA干渉(RNAi)現象を1998年に報告した線虫の研究者2人に贈ると発表された06年10月2日(関連記事3)の3日前の9月29日、科学技術振興機構(JST)は、審良教授を招いた報道機関向けレクチャー会を東京本部で開催した(この講義および懇親会のリポートは、10月25日発行の「BTJジャーナル」10月号P.14-15に掲載)。
2006年度ノーベル賞授賞式、ストックホルムで開催 - スウェーデン
http://www.afpbb.com/article/1155006
【ストックホルム/スウェーデン 7日 AFP】ストックホルム(Stockholm)で7日、2006年度ノーベル賞授賞式が開催された。写真は同日、王立科学アカデミー(Royal Academy of Science)で記者会見するノーベル賞受賞者たち。(左から)物理学賞のジョン・マザー(John C. Mather)、ジョージ・スムート(George F. Smoot)両氏、化学賞のロジャー・コーンバーグ(Roger Kornberg)氏および経済学賞のエドモンド・フェルプス(Edmund Phelps)氏。
http://www.afpbb.com/article/1155006
【ストックホルム/スウェーデン 7日 AFP】ストックホルム(Stockholm)で7日、2006年度ノーベル賞授賞式が開催された。写真は同日、王立科学アカデミー(Royal Academy of Science)で記者会見するノーベル賞受賞者たち。(左から)物理学賞のジョン・マザー(John C. Mather)、ジョージ・スムート(George F. Smoot)両氏、化学賞のロジャー・コーンバーグ(Roger Kornberg)氏および経済学賞のエドモンド・フェルプス(Edmund Phelps)氏。
2006年ノーベル賞の授賞式開催 - スウェーデン
http://www.afpbb.com/article/1163461
【ストックホルム/スウェーデン 10日 AFP】ストックホルム(Stockholm)で10日、ノーベル賞の授与式が行われた。文学、生理学・医学、物理学、化学、経済学の受賞者が、それぞれ賞を授与された。受賞式の終了後には、祝宴晩さん会が開催された。写真は同日、授与式でカール16世グスタフ(King Carl XVI Gustaf)国王からノーベル生理学・医学賞を授与される、米国のマサチューセッツ州、ウースター(Worcester)にあるマサチューセッツ大学のクレイグ・C・メロー(Craig C. Mello)医学教授。
http://www.afpbb.com/article/1163461
【ストックホルム/スウェーデン 10日 AFP】ストックホルム(Stockholm)で10日、ノーベル賞の授与式が行われた。文学、生理学・医学、物理学、化学、経済学の受賞者が、それぞれ賞を授与された。受賞式の終了後には、祝宴晩さん会が開催された。写真は同日、授与式でカール16世グスタフ(King Carl XVI Gustaf)国王からノーベル生理学・医学賞を授与される、米国のマサチューセッツ州、ウースター(Worcester)にあるマサチューセッツ大学のクレイグ・C・メロー(Craig C. Mello)医学教授。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
生命科学研究ハイライト 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
生命科学研究ハイライトのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23167人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人