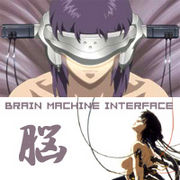人が感じる全ては脳で処理された電気信号と神経伝達物質の交換であるということが解った。つまり、物理的、科学的に脳の原理は簡単に説明できる。しかし、感情や閃きなどはいまだ詳しい解明がなされていない。詳しいところはほとんど解っていないというのが現状だ。まぁ生きた脳に直接実験をすればその持ち主の命に関わるのだからそうそう研究も進まないだろう。その脳のどこがすごいかというと、まずその記憶容量である。これが真実かは個人差も大きく影響するだろうし簡単には量れないことであるが、ヒトの脳の記憶容量は約1000億ビットだそうである。これを身近なパソコンのバイトという単位に換算すると、8ビットで1バイトだから、12.5ギガバイトとなる。最新のパソコンのハードディスク容量は、40〜60ギガバイトが当たり前となっている所からすれば、そう大した量ではない。しかし、これは人間が意識的に記憶として利用できる範囲の容量だそうだ。人間は、生まれてから見たものをほぼ全て、実は記憶しているそうで、全てを思い出すことが可能だと記憶の混乱を起こすためそのほんの一部だけが日常使える記憶となっているそうだ。その無意識下の記憶は意識下のそれの10万倍はあるらしい。たしかに、私たちが意識してなにかを記憶したとき、それでも早ければ数日、大体1年程でそのことを忘れてしまう。数年もすればそれを覚えたことすら忘れることも多いだろう。しかし、なにかの折にその記憶した事柄にであったとき、これを覚えたことがある、と思い出すことが出来る。試験のまえに覚えたことなど、テスト中にどうしても思い出せなくても、あとから確認して見ると確かにその前に覚えた内容であるのが確認できる。ただ、10万倍もあるとといわれると信憑性に欠ける気もするが、そこまでではないにしろ、フロイトの理論でも意識と無意識の比率は1:9の割合とされているくらいだから、少なくとも無意識下の記憶容量は意識化の容量より10倍はあるのではないかと思われる。これだけの記憶容量を持つ脳を持つ我々が、なぜ自由に記憶し、それを思い出すことが出来ないかというと、どうやらそれは思いだす側の機能の事情らしい。先ほども少し書いたが、ヒトの脳はそれまでに感じたあらゆる情報をほぼ全て記憶しているらしい。しかし、その全てが無意識下に記憶されるため、自由には思い出すことが出来ないのだ。なんか記憶術の前口上みたいになってきたが、そういうことも最近の研究でわかってきたらしい(※1)。どうも人間の脳は記憶するのは得意だが、思い出すのが苦手で思い出せなかったり、思い出すのにとても時間がかかったりするらしいのだ。これではどこがすごいんだという話になるが、いまは記憶容量について書いていたので、そのすごさは自分で納得したので、次に行きたいと思う。まぁ、後は思い出し方の工夫で記憶に関しては大きな発展ももうすぐという気もする。 次に閃きについて。これは量の問題ではなく、いまだコンピュータには真似のできないことである。そもそも、閃きとは、大体なにか問題に直面したときにその解決方法が一瞬にして頭に浮かぶというようなものであるが、これに関してはヒトも意識して10分の1とかですらなく、意識的にできることではない。しかし一部の研究者はこの起こし方があるとして、研究してしているそうだ(※2)。ヒトが閃くには3つの段階があり、まず第1に問題に理詰めで取り組み、それに解くにあたって有用な情報を収集したりする段階。第2に問題に取り組んだが行き詰まり、一時的に棚上げしてしまっている状態。そして第3段階として「問題を解決するためのアイデアが閃く」、もしくは偶然(これは実は必然だそうである)になにかをヒントとして解決することができる。この3つを行うのが閃くということであるが、これをコンピュータにさせようとすると、まず第1段階の時点でつまづいている気がする。問題を解くために試行錯誤するというのはプログラムでループ上に一つ一つの条件を確認していく、というような作業であらわせるが、そのためにいちいちその問題解決用のプログラムが必要だし、抽象的な問題に関してはプログラムで表しきれないため、その行為にすら至らないということがありえるからである。ともあれ、ここは限定された問題であればコンピュータは人間以上の速さと正確さで問題を解いていく。ここで行き詰まると第2段階となるわけだが、普通、コンピュータはプログラムが行き詰まるとフリーズし、問題を横にのけておくことが出来ない。ここでも人間との差が出てくるが、これも最近の優秀なOSを用いれば、パソコンそのものがフリーズするということは少なくなってきた。そのプログラムのみを停止させ、ユーザーに警告を発する余裕が出来たのだ。これも完全ではないがコンピュータにも出来ることである。しかし第3段階、実際に「閃く」となると途端にコンピュータには出来ない。これは当たり前と言ってしまえば当たり前のことではある。コンピュータは基本的に1から10まで人間が作ったものである為、人間の能力を超えることは出来ても、人間が説明できないことをすることは出来ないのだ。つまり閃くということは基本的にはそのメカニズムは全くわかっておらず、一部の研究者が完全には実証されていないいわば仮説を出しているに過ぎないのだ。人間は自分でも良くわかっていないすばらしい機能を活用しきれておらず、大変もったいないことをしているのが解る。閃きについての話に戻るが、研究者に言わせると、コンピュータに閃きがないのは右脳が無いかららしい。人間の脳は表面側の大脳の部分で右脳と左脳の2つに別れており、右脳が主に想像や閃き、イメージなどを司り、左脳は言語や計算、論理などを処理するというのはいまでは常識として知られることであるが、コンピュータはまさに左脳の塊であるのだ。理論的に理屈の通ったことは人間をはるかに越える精度、速度で処理できるが、イメージや想像などは全く出来ない。映像に関しても、ヒトは映像を像としてとらえるため、細部はわからなくても大した記憶容量は食わず、簡単におぼえることが出来るが、コンピュータは絵を点の集合としてとらえ、1点1点、律儀に正確に覚えるため、文字などに比べそれに要するデータ量は跳ね上がる。これも本来ヒトが右脳で記憶すべきところを左脳的に記憶するため、起きる現象である。しかし、そういうものとは全く別に、右脳には特殊な能力があり、それによりヒトが問題にぶつかったときにその解決法が見付かるのは右脳により必然的に起こされたものである、という考えがあるそうだが、これについては自分で感心はするもののあまり信じていないためこの考えについて説明しているサイトのアドレスを載せるにとどめておく。 以上の点においてだけでも脳のすごさはかなり自分の中で顕在化されたわけだが、本当に書きたかったのは脳のすごさについてではなく、脳の可能性についてである。この世の中のシステム、人工物はすべてヒトが作り上げたものである。一人の妄想から始まったことが今では極当たり前のこととして世の中に数多く出回っている。脳が外部刺激に対して様々な反応を行った結果である。いま、私は22世紀の初頭に生きている、19歳の学生であるが、人類の最初のヒトと比べると、数百万年の時を経て出来上がった今の世の中を普通に生きる私の方が世の中の法則や原理、それにより可能となる事象について、かなりのことを知っている。そこで、今、私が思考に支障の無い状態で肉体を捨て、思考だけの存在となれたら、今の世の中を創造しえるだろうか。既にわたしは多くの先人が苦労して発見した法則や式を手に入れている。この状態で、例えば今私が全く知らない事柄について想像をあらゆる角度から進めていったら、それを理解することは出来るのだろうか。全てはヒトの脳が考え、作り出してきたもので出来ているこのヒトの世界を私一人で再構築するには、どのくらいの時間がかかるだろう。全てをシミュレートしきれるだろうか。これから私が得る情報というのは基本的に他人から与えられる情報であり、人の手が加わった情報である。全ては多くの脳がそう認識している世界で多くの脳が作り上げた世界なのであるから私がたどり着き得る情報であると思う。今この時点で外界との接触を断ち、すべてを自分で考え、ひとつずつ答えを出していくことができるなら、それはわたしの一つの理想である。外からの入力に重きを置かず、自らの内面に無限を見出し、そこから何かを得るというのは、過去の哲学者も目指した真理の求め方の一つである。私はこの方法で世の中の全て=真理にたどりついてみるのも面白いと思っている。話がバラバラになったが、最初書こうと思っていたのは最後に書いた内容である。前置きを書いているうちにそれに夢中になって書き連ねてしまうのは良いことではないが、自分の思ったことを全て言葉として浮かぶままに書き表すのも自分の探求として哲学的であると思われるので、良しとして、ここで文を終える。
|
|
|
|
コメント(25)
19歳といっているわりに難しい言葉だらけだなぁ。
英文を直訳したような感じ。
英語も得意そうだし、将来有望ですね。AIとかの開発チームになってくれたら良いな。
AIに興味があるんですが、個人で作成するには知識・技術がまだまだ足りません。(笑
以下、本文を読んで私なりの解釈です。
>問題を解くために試行錯誤
これは、OSでいうところのパスで良いと思う。
カレント>環境変数のパス で検索する仕組み
または、googleなどの「もしかして」みたいなヤツ。
>問題を横にのけておくこと
Windowsで言うと、強制再起動を行った後にSTOPエラーなどを出力する事がこれにあたりそうですね。
あとで解析するかどうかも個々によって違うでしょ?
>実際に「閃く」となると途端にコンピュータには
これってインターネットで検索させると面白いよね。
なんでそうしないんだろ。
その時その時の結果(トップに出たもの)を取得するとかにすれば、個別の結果を得ることができるんじゃない?
殆どの端末では○○○と答えを出すが、たまに×××とか、△△△などの答えを拾ってくるヤツも。
>コンピュータは絵を点の集合としてとらえ、1点1点、律儀に正確に
これって、動画でいえば、MPEG1とかMPEG4で表せそうだよね。
MPEG1>>律儀に・・・
MPEG4>>多少あいまいでも簡単に(低容量)で覚える(記録する)
画像で言えば以下ですかね
Bmp、PNG>>律儀に・・・
JPG、gif>>多少あいまいでも簡単に(低容量)で覚える(記録する)
デジタルとアナログって別々にする人が多いけど、デジタルって人が作ったものだし、
文章などで説明できる仕組みであれば、デジタル化できるはず。
個人的には、デジタルもアナログもあまり変わらないと思う。
たしかに、デジタルは律儀系ですね。それに対してアナログは臨機応変型にあたるかな。
お互いの特性を生かして、お互いのマイナスを埋め合い、より良い融合を期待しています。
ただし、全てにおいて、陰と陽が存在すると思う。
英文を直訳したような感じ。
英語も得意そうだし、将来有望ですね。AIとかの開発チームになってくれたら良いな。
AIに興味があるんですが、個人で作成するには知識・技術がまだまだ足りません。(笑
以下、本文を読んで私なりの解釈です。
>問題を解くために試行錯誤
これは、OSでいうところのパスで良いと思う。
カレント>環境変数のパス で検索する仕組み
または、googleなどの「もしかして」みたいなヤツ。
>問題を横にのけておくこと
Windowsで言うと、強制再起動を行った後にSTOPエラーなどを出力する事がこれにあたりそうですね。
あとで解析するかどうかも個々によって違うでしょ?
>実際に「閃く」となると途端にコンピュータには
これってインターネットで検索させると面白いよね。
なんでそうしないんだろ。
その時その時の結果(トップに出たもの)を取得するとかにすれば、個別の結果を得ることができるんじゃない?
殆どの端末では○○○と答えを出すが、たまに×××とか、△△△などの答えを拾ってくるヤツも。
>コンピュータは絵を点の集合としてとらえ、1点1点、律儀に正確に
これって、動画でいえば、MPEG1とかMPEG4で表せそうだよね。
MPEG1>>律儀に・・・
MPEG4>>多少あいまいでも簡単に(低容量)で覚える(記録する)
画像で言えば以下ですかね
Bmp、PNG>>律儀に・・・
JPG、gif>>多少あいまいでも簡単に(低容量)で覚える(記録する)
デジタルとアナログって別々にする人が多いけど、デジタルって人が作ったものだし、
文章などで説明できる仕組みであれば、デジタル化できるはず。
個人的には、デジタルもアナログもあまり変わらないと思う。
たしかに、デジタルは律儀系ですね。それに対してアナログは臨機応変型にあたるかな。
お互いの特性を生かして、お互いのマイナスを埋め合い、より良い融合を期待しています。
ただし、全てにおいて、陰と陽が存在すると思う。
脳を構成する細胞が有限で、脳が電気回路なら、その回路がとりうる状態は有限。
でもその場合の数は膨大で、一人のヒトが一生にすべての状態を経験することはできないっぽい。
脳ができてすぐは回路がある部分集合のうちの一状態に落ち着いていて、そこから時間軸にそって状態遷移を繰り返すと仮定すれば、もっといろんな人がいてもよさそうですが、結構似たようなことを考えている人が身の回りにいることを考慮すると、なかなか個性的な確率分布がありそうで、その分布を文化と呼んだりしようかな?
なんて思いっきり独り言です。
まぁそんな状態遷移を繰り返してヒトが大人になっていくとすれば、世の中が上手く行かないのにも納得がいきますね♪
分布を操作してみたいものです。
でもその場合の数は膨大で、一人のヒトが一生にすべての状態を経験することはできないっぽい。
脳ができてすぐは回路がある部分集合のうちの一状態に落ち着いていて、そこから時間軸にそって状態遷移を繰り返すと仮定すれば、もっといろんな人がいてもよさそうですが、結構似たようなことを考えている人が身の回りにいることを考慮すると、なかなか個性的な確率分布がありそうで、その分布を文化と呼んだりしようかな?
なんて思いっきり独り言です。
まぁそんな状態遷移を繰り返してヒトが大人になっていくとすれば、世の中が上手く行かないのにも納得がいきますね♪
分布を操作してみたいものです。
経済学にはミクロとマクロの両視点で捉える観点があるけど、
脳科学にも同様のスコープが必要とされるのかも知れないですね。
探求の末、理屈や数式で表せない領域が出てくると、人はより大きなうねりのようなモノを感じ、よりマクロな構造にシフトしていく。
しかし一方で、ミクロな領域に対する探求が消えることはない。
例えば、脳インターフェースがもの凄く技術的な領域で議論される一方、脳神経倫理学のような社会を見据えた分野が育っていく。互いの存在を認め合うことで技術は本当に利用可能なものに伸びていくのでしょうね。
この技術は単なる技術的興味にとどまらず、病気で手足を失ったりした人への救済へと繋がるもの。世間と乖離した技術者のマスターベーションになってしまうことは避けるよう、気をつけたいものです。
少なくとも、論文を書かれる時は、読みやすいように改行を入れることをお奨めしたいと思います。
脳科学にも同様のスコープが必要とされるのかも知れないですね。
探求の末、理屈や数式で表せない領域が出てくると、人はより大きなうねりのようなモノを感じ、よりマクロな構造にシフトしていく。
しかし一方で、ミクロな領域に対する探求が消えることはない。
例えば、脳インターフェースがもの凄く技術的な領域で議論される一方、脳神経倫理学のような社会を見据えた分野が育っていく。互いの存在を認め合うことで技術は本当に利用可能なものに伸びていくのでしょうね。
この技術は単なる技術的興味にとどまらず、病気で手足を失ったりした人への救済へと繋がるもの。世間と乖離した技術者のマスターベーションになってしまうことは避けるよう、気をつけたいものです。
少なくとも、論文を書かれる時は、読みやすいように改行を入れることをお奨めしたいと思います。
話それるかもしれないけど、みんなで人生方程式というのかな・・・?を作ってみたいと思っているのですが・・・。
あらゆる事に対応した式を考え出すのが以前からの夢です。
アナログをデジタル化ということで。
言いだしっぺなので、以下に例を書きますね。
お金=労力+時間
お金=情報+応用
時間=お金+応用
応用という要素は曖昧すぎますが、
たとえば、「移動時間」をい作る場合の式だけで考えると以下にるかと。距離とかの要素は別で。
時間=お金+労力
時間=タクシー料金大きめ+徒歩が少ない
時間=お金ゼロ+徒歩全部(めちゃ疲れる)
こういう方程式?を考えた事ある人って他にどれだけいるのかなぁ。
もしかして、自分だけ?(汗
少なくとも、天才様々さんから同じ匂いを感じるのですが・・・如何でしょう。(と振ってみる
neucomさんとか、りきぞうさん、にもコメント頂けると嬉しいな・・・。もちろん、他の人もジャンジャン書いてください。
それから、個人的には、難しそうに見せなくてもみんなに分かりやすく書くっていうのも「力」と言う要素に値すると思います。
と言う事でカタっ苦しいのは抜きで。
どうぞ↓
あらゆる事に対応した式を考え出すのが以前からの夢です。
アナログをデジタル化ということで。
言いだしっぺなので、以下に例を書きますね。
お金=労力+時間
お金=情報+応用
時間=お金+応用
応用という要素は曖昧すぎますが、
たとえば、「移動時間」をい作る場合の式だけで考えると以下にるかと。距離とかの要素は別で。
時間=お金+労力
時間=タクシー料金大きめ+徒歩が少ない
時間=お金ゼロ+徒歩全部(めちゃ疲れる)
こういう方程式?を考えた事ある人って他にどれだけいるのかなぁ。
もしかして、自分だけ?(汗
少なくとも、天才様々さんから同じ匂いを感じるのですが・・・如何でしょう。(と振ってみる
neucomさんとか、りきぞうさん、にもコメント頂けると嬉しいな・・・。もちろん、他の人もジャンジャン書いてください。
それから、個人的には、難しそうに見せなくてもみんなに分かりやすく書くっていうのも「力」と言う要素に値すると思います。
と言う事でカタっ苦しいのは抜きで。
どうぞ↓
ち、ばれやしたか・・・まぁ、あっしのばやいは
「運命方程式」ですがね。
森羅万象の変化はすべて「因果関係」から成り立つ。過去から現在にかけての状態の変化を代入することにより、未来の状態を求めることができる方程式なのですよ。逆関数に過去から現在にかけての状態の変化と期待する未来像を代入することで、そこに到達するのに必要となる時間を求めることができる「Xデイ関数」もあります。
まぁ人生方程式を無機物にまで一般化したものになるでしょうから人生方程式からはじめましょうか。
(そうじゃないとトピ違いどころかコミュ違いに・・・)
あ、でも脳の話に入ったらきっと電子とか電界・磁界とか音とか光とか結局無機質な話になってしまいそう。
う〜ん早くもみくろまくろしてきましたね!?
「運命方程式」ですがね。
森羅万象の変化はすべて「因果関係」から成り立つ。過去から現在にかけての状態の変化を代入することにより、未来の状態を求めることができる方程式なのですよ。逆関数に過去から現在にかけての状態の変化と期待する未来像を代入することで、そこに到達するのに必要となる時間を求めることができる「Xデイ関数」もあります。
まぁ人生方程式を無機物にまで一般化したものになるでしょうから人生方程式からはじめましょうか。
(そうじゃないとトピ違いどころかコミュ違いに・・・)
あ、でも脳の話に入ったらきっと電子とか電界・磁界とか音とか光とか結局無機質な話になってしまいそう。
う〜ん早くもみくろまくろしてきましたね!?
>>天才様々さん
自分には難しすぎます・・・。
「運命方程式」ですか〜。
>過去から現在にかけての状態の変化を代入することにより、未来の状態を求めることができる方程式
なんだか自分のと似ている気がしますが・・・。
得たい要素=失える要素
お金=給料=時間x(知力+体力)
こういう感じになりそう。
ただし、天才様々さんの様に時間軸という概念が入っていないのですが・・・。
たしかに、時間はみんなに平等で共通の要素ですよね。
>(そうじゃないとトピ違いどころかコミュ違いに・・・)
あ、これ考えていなかった・・・。
>>いささん
神秘や霊的な理解・・・これまた難しい話ですね〜。
>見えない世界の神秘や構造はまだまだこれから
新しい発見と応用で、ますますの進歩というのも期待しつつ、自分たちでもあれやこれやと想像していたい気も半分あります。
自分には難しすぎます・・・。
「運命方程式」ですか〜。
>過去から現在にかけての状態の変化を代入することにより、未来の状態を求めることができる方程式
なんだか自分のと似ている気がしますが・・・。
得たい要素=失える要素
お金=給料=時間x(知力+体力)
こういう感じになりそう。
ただし、天才様々さんの様に時間軸という概念が入っていないのですが・・・。
たしかに、時間はみんなに平等で共通の要素ですよね。
>(そうじゃないとトピ違いどころかコミュ違いに・・・)
あ、これ考えていなかった・・・。
>>いささん
神秘や霊的な理解・・・これまた難しい話ですね〜。
>見えない世界の神秘や構造はまだまだこれから
新しい発見と応用で、ますますの進歩というのも期待しつつ、自分たちでもあれやこれやと想像していたい気も半分あります。
>12.5G
ヒトは3%程度しか脳を使っていないということを聞いたことがありますが・・・
そうすると0.375Gってことですか?(汗) もちろん、記憶容量としての計算とのことですので、きっと違いますね。
とはいえ、12.5Gってのはなんとも悲しいかしら〜
他の方々のコメントのように能力や才能の個体差をどうとらえるかにも興味があります。記憶量だけで見れば、例えば東大に入れたり弁護士になれたりとか、ある種受験社会を加味すると(→狭く捉えてすいません)、単に“興味”だけで片付けられるのか疑問も思います。 整形手術感覚で実装する人は、結構いると思いますよ。もちろん、お金があって未来への可能性を手に入れたい人なら。
また、余談ですが、脳インターフェイスの進化の行き着く先は、人工脳ってことに?などということも率直に感じました。脳インターフェイスが実装されるだけの技術があるなら、脳も作れてしまうのでは?(汗)
以上のコメントについては、内容とずれているかもしれませんが・・・(汗)
ヒトは3%程度しか脳を使っていないということを聞いたことがありますが・・・
そうすると0.375Gってことですか?(汗) もちろん、記憶容量としての計算とのことですので、きっと違いますね。
とはいえ、12.5Gってのはなんとも悲しいかしら〜
他の方々のコメントのように能力や才能の個体差をどうとらえるかにも興味があります。記憶量だけで見れば、例えば東大に入れたり弁護士になれたりとか、ある種受験社会を加味すると(→狭く捉えてすいません)、単に“興味”だけで片付けられるのか疑問も思います。 整形手術感覚で実装する人は、結構いると思いますよ。もちろん、お金があって未来への可能性を手に入れたい人なら。
また、余談ですが、脳インターフェイスの進化の行き着く先は、人工脳ってことに?などということも率直に感じました。脳インターフェイスが実装されるだけの技術があるなら、脳も作れてしまうのでは?(汗)
以上のコメントについては、内容とずれているかもしれませんが・・・(汗)
米軍、「テレパシー」研究を本格化
戦場無線も、軍用携帯情報端末(PDA)も、歩兵の手信号でさえ、もういらない。将来の兵士たちが連絡を取りたくなったときは、お互いの思考を読むようになるからだ。
少なくとも、米国防総省のマッド・サイエンス研究部門である国防高等研究計画庁(DARPA)の研究者たちは、そうなることを望んでいる。次の会計年度におけるDARPAの予算には、『Silent Talk』(無言の会話)と呼ばれるプログラムに着手するための400万ドルが含まれているのだ。
プログラムの目標は、「発声による会話を使わずに、神経信号を分析することによって、戦場での人から人へのコミュニケーションを可能にすること」だ。これ以外にも、米軍では昨年、コンピューターを仲介とするテレパシーの可能性を研究するために、カリフォルニア大学に400万ドルを提供している(日本語版記事)。
http://wiredvision.jp/news/200905/2009051923.html
戦場無線も、軍用携帯情報端末(PDA)も、歩兵の手信号でさえ、もういらない。将来の兵士たちが連絡を取りたくなったときは、お互いの思考を読むようになるからだ。
少なくとも、米国防総省のマッド・サイエンス研究部門である国防高等研究計画庁(DARPA)の研究者たちは、そうなることを望んでいる。次の会計年度におけるDARPAの予算には、『Silent Talk』(無言の会話)と呼ばれるプログラムに着手するための400万ドルが含まれているのだ。
プログラムの目標は、「発声による会話を使わずに、神経信号を分析することによって、戦場での人から人へのコミュニケーションを可能にすること」だ。これ以外にも、米軍では昨年、コンピューターを仲介とするテレパシーの可能性を研究するために、カリフォルニア大学に400万ドルを提供している(日本語版記事)。
http://wiredvision.jp/news/200905/2009051923.html
☆心を読み取るシステム」:脳にある視覚情報の解読に成功
『Nature』誌オンライン版で3月5日(米国時間)、カリフォルニア大学バークレー校の神経科学者らがある解読システムを公開した。
研究者チームは、リアルタイムで脳をスキャンする機能的磁気共鳴画像(fMRI)装置を使用して、何千枚もの写真を見ている人の精神活動を記録した。写真は、人物、動物、風景、物体など、日常生活で目にするさまざまなもので、この記録から、人がさまざまな写真を見ることで発生するメンタル・パターンを予測する計算モデルを開発した。
この計算モデルを、別の写真群を見ている時に生成される神経学的な読み取り情報とつきあわせて試験したところ、見ていた写真をかつてない正確さで判別し、きわめて有効であることが示された。
いつか、夢の中で見たものさえ再現できるようになるかもしれない」とGallant博士は語った。
http://wiredvision.jp/news/200803/2008031022.html
☆脳の活動パターンから「空間記憶の読み取り」に成功
バーチャル空間の中にいる被験者の脳をスキャンし、脳の活動を分析したところ、被験者が空間のどの位置にいるのか特定することができたというのだ。
「いわば被験者の空間記憶を読み取ることに成功したわけだ」と、今回の研究論文を執筆した1人で、ロンドン大学ユニバーシティー・カレッジ(UCL)の認知神経科学者であるEleanor Maguire氏は話す。「空間記憶がニューロン(神経単位)で符号化される過程には、必ず何らかの構造が存在するはずだ。そうでなければ、われわれに記憶を予測できたはずがない」
http://wiredvision.jp/news/200905/2009052723.html
『Nature』誌オンライン版で3月5日(米国時間)、カリフォルニア大学バークレー校の神経科学者らがある解読システムを公開した。
研究者チームは、リアルタイムで脳をスキャンする機能的磁気共鳴画像(fMRI)装置を使用して、何千枚もの写真を見ている人の精神活動を記録した。写真は、人物、動物、風景、物体など、日常生活で目にするさまざまなもので、この記録から、人がさまざまな写真を見ることで発生するメンタル・パターンを予測する計算モデルを開発した。
この計算モデルを、別の写真群を見ている時に生成される神経学的な読み取り情報とつきあわせて試験したところ、見ていた写真をかつてない正確さで判別し、きわめて有効であることが示された。
いつか、夢の中で見たものさえ再現できるようになるかもしれない」とGallant博士は語った。
http://wiredvision.jp/news/200803/2008031022.html
☆脳の活動パターンから「空間記憶の読み取り」に成功
バーチャル空間の中にいる被験者の脳をスキャンし、脳の活動を分析したところ、被験者が空間のどの位置にいるのか特定することができたというのだ。
「いわば被験者の空間記憶を読み取ることに成功したわけだ」と、今回の研究論文を執筆した1人で、ロンドン大学ユニバーシティー・カレッジ(UCL)の認知神経科学者であるEleanor Maguire氏は話す。「空間記憶がニューロン(神経単位)で符号化される過程には、必ず何らかの構造が存在するはずだ。そうでなければ、われわれに記憶を予測できたはずがない」
http://wiredvision.jp/news/200905/2009052723.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
脳コンピュータインターフェイス 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
脳コンピュータインターフェイスのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90011人
- 2位
- 酒好き
- 170662人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人