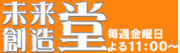第101回(2008年3月21日23:00〜放送分)は、「自動串刺機の未来を切り拓いた男の物語」。
スタジオゲストはダチョウ倶楽部。そのこだわりは・・・・
○郷土の名物・ポークはサイコー!!・肥後克広
沖縄出身の肥後さん。沖縄の味といえば、缶詰の「ポーク」なのだとか。「庶民の味」、「おふくろの味」で毎日食べていたという。スタジオに「ポーク」数種類を並べ、中でも一番うまい!という食べ方の「ポークたまご」をみんなで試食する。肥後さんのために、故郷沖縄の懐かしい味、「ナーベラ炒め」も登場する。
○命の次に大切なもの、懐中電灯!・寺門ジモン
寺門さんにとって「懐中電灯」は命の次に大切なものなのだとか。趣味は山ごもりにオオクワガタ採集で、その際に欠かすことのできない“懐中電灯”には子供の頃からとことんこだわってきたという。寺門さんの懐中電灯コレクションを出して、懐中電灯への思いを語ります。色々な懐中電灯を使って実際に光の違いを体感する。
○「熱湯」は“芸”である!・上島竜兵
「『熱湯』は計算されつくした芸である!」と語る上島さん。温度計が無くても手を入れただけで適温(45℃)かどうか分かるというので、上島さん、「熱湯温度当て」に挑戦。手の感覚だけでお湯を45℃に調整できるか!?「熱湯コマーシャル」の秘話や、熱湯芸の奥深さを語る。そこで、熱湯芸の真髄を披露していただくために、スタジオには「熱湯風呂」を用意。ダチョウ倶楽部メンバーは海パンに着替え「熱湯芸」を披露する!
今夜のVTRは・・・
○自動串刺機の未来を切り拓いた男の物語
おでんをはじめ、日本国内だけでも1日200万本もの串料理が消費されている。日本だけでなく、中国やアメリカでも大ブームになっている串料理を裏で支えているのが、「万能自動串刺機」。日本人の大好きな串料理を、手軽にどこでも美味しく食べられるようにしたい。そんな想いを抱き、日本の、世界の串料理の歴史を塗り替えた男がいた。今夜は、「串料理」の未来を切り拓いた男の物語。
時は1970年代。高度成長期の真っただ中。消費の伸びに比例して、多くのものが機械によって自動で生産されるようになった。今夜の主人公、小嶋實は、家電用品の部品を組み立てる機械を作っていた。仕事に追われる毎日。帰りに焼き鳥を食べるのが何よりも楽しみだった。「大将、焼き鳥ちょうだい」「悪い、今日はもう切れだ」 焼き鳥の串刺しは時間も手間もかかるため、作り置きには限界がある。だから遅くなるといつも売り切れ。どんなに熟練した職人でも1時間に100本刺せるかどうか。「機械屋なら、串刺しの機械でも作ってくれよ!」この何気ない一言が串刺機開発のきっかけとなった。
小嶋は早速、狭い工場に籠り、串刺機の開発に取り組んだ。部品作りの機械のノウハウを応用すれば鶏肉に串を刺す装置を作るのはお手の物!のはずであった。しかし、出来上がったものは、焼くと材料が抜け落ちてしまったり、串が突き出したりしてしまったのだ。「なぜ職人が刺したものは抜けないのだろう?」小嶋は悩んだ。焼き鳥屋で焼き鳥をにらむ小嶋に大将が、「明日の開店前の店に来なよ」。大将は焼き鳥の切り方や部位によって形や固さが違うこと、筋の向きがあることなど教えてくれた。さらに、串職人の手の動きからも驚くべきことが分かったのだ。職人は、鶏肉に串をさすとき、串の先端を軽く持ち、波を描くように手を動かしていたのだ。波縫いの要領で串を鶏肉に刺していたから、抜けにくいのだ。「素材を知れば刺せないものはない!」小嶋は再び工場に籠もった。串を波のように動かしながら食材に指すことを繰り返し、研究は続くのだが・・・。
■出演者
木梨憲武
西尾由佳理(日本テレビアナウンサー)
ゲスト:ダチョウ倶楽部
スタジオゲストはダチョウ倶楽部。そのこだわりは・・・・
○郷土の名物・ポークはサイコー!!・肥後克広
沖縄出身の肥後さん。沖縄の味といえば、缶詰の「ポーク」なのだとか。「庶民の味」、「おふくろの味」で毎日食べていたという。スタジオに「ポーク」数種類を並べ、中でも一番うまい!という食べ方の「ポークたまご」をみんなで試食する。肥後さんのために、故郷沖縄の懐かしい味、「ナーベラ炒め」も登場する。
○命の次に大切なもの、懐中電灯!・寺門ジモン
寺門さんにとって「懐中電灯」は命の次に大切なものなのだとか。趣味は山ごもりにオオクワガタ採集で、その際に欠かすことのできない“懐中電灯”には子供の頃からとことんこだわってきたという。寺門さんの懐中電灯コレクションを出して、懐中電灯への思いを語ります。色々な懐中電灯を使って実際に光の違いを体感する。
○「熱湯」は“芸”である!・上島竜兵
「『熱湯』は計算されつくした芸である!」と語る上島さん。温度計が無くても手を入れただけで適温(45℃)かどうか分かるというので、上島さん、「熱湯温度当て」に挑戦。手の感覚だけでお湯を45℃に調整できるか!?「熱湯コマーシャル」の秘話や、熱湯芸の奥深さを語る。そこで、熱湯芸の真髄を披露していただくために、スタジオには「熱湯風呂」を用意。ダチョウ倶楽部メンバーは海パンに着替え「熱湯芸」を披露する!
今夜のVTRは・・・
○自動串刺機の未来を切り拓いた男の物語
おでんをはじめ、日本国内だけでも1日200万本もの串料理が消費されている。日本だけでなく、中国やアメリカでも大ブームになっている串料理を裏で支えているのが、「万能自動串刺機」。日本人の大好きな串料理を、手軽にどこでも美味しく食べられるようにしたい。そんな想いを抱き、日本の、世界の串料理の歴史を塗り替えた男がいた。今夜は、「串料理」の未来を切り拓いた男の物語。
時は1970年代。高度成長期の真っただ中。消費の伸びに比例して、多くのものが機械によって自動で生産されるようになった。今夜の主人公、小嶋實は、家電用品の部品を組み立てる機械を作っていた。仕事に追われる毎日。帰りに焼き鳥を食べるのが何よりも楽しみだった。「大将、焼き鳥ちょうだい」「悪い、今日はもう切れだ」 焼き鳥の串刺しは時間も手間もかかるため、作り置きには限界がある。だから遅くなるといつも売り切れ。どんなに熟練した職人でも1時間に100本刺せるかどうか。「機械屋なら、串刺しの機械でも作ってくれよ!」この何気ない一言が串刺機開発のきっかけとなった。
小嶋は早速、狭い工場に籠り、串刺機の開発に取り組んだ。部品作りの機械のノウハウを応用すれば鶏肉に串を刺す装置を作るのはお手の物!のはずであった。しかし、出来上がったものは、焼くと材料が抜け落ちてしまったり、串が突き出したりしてしまったのだ。「なぜ職人が刺したものは抜けないのだろう?」小嶋は悩んだ。焼き鳥屋で焼き鳥をにらむ小嶋に大将が、「明日の開店前の店に来なよ」。大将は焼き鳥の切り方や部位によって形や固さが違うこと、筋の向きがあることなど教えてくれた。さらに、串職人の手の動きからも驚くべきことが分かったのだ。職人は、鶏肉に串をさすとき、串の先端を軽く持ち、波を描くように手を動かしていたのだ。波縫いの要領で串を鶏肉に刺していたから、抜けにくいのだ。「素材を知れば刺せないものはない!」小嶋は再び工場に籠もった。串を波のように動かしながら食材に指すことを繰り返し、研究は続くのだが・・・。
■出演者
木梨憲武
西尾由佳理(日本テレビアナウンサー)
ゲスト:ダチョウ倶楽部
|
|
|
|
|
|
|
|
未来創造堂 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
未来創造堂のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37846人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31947人