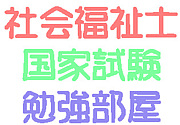|
|
|
|
コメント(7)
善意の第三者との関係〜詐欺による取り消しの場合〜
例えばAを騙して不当に安く不動産を購入したBが、善意の第三者Cにその不動産をさらに転売した場合について考えてみます。詐欺による意思表示は取り消されるまでは有効だから、Cはその不動産を有効に取得できます。ところが後になってAの意思表示が詐欺を理由に取り消されたとすると、その意思表示は最初からなかったものとして扱われちゃいます。A-B間の売買契約もさかのぼって無効になり、Cは権利のないBから不動産を購入したことになるので所有権が… となってしまいます。
となってしまいます。
騙されたAもですがBを所有者だと信じた第三者Cも法律は保護しないといけないです。CがA-B間の詐欺の事実を知らなかった以上、AはCから不動産を取り戻せないと民法では決まってます 結局、騙されたAにも多少の落ち度があると考え、なんら落ち度のないCの利益を犠牲にしてまでAが保護されるべきではないということになります。
結局、騙されたAにも多少の落ち度があると考え、なんら落ち度のないCの利益を犠牲にしてまでAが保護されるべきではないということになります。
例えばAを騙して不当に安く不動産を購入したBが、善意の第三者Cにその不動産をさらに転売した場合について考えてみます。詐欺による意思表示は取り消されるまでは有効だから、Cはその不動産を有効に取得できます。ところが後になってAの意思表示が詐欺を理由に取り消されたとすると、その意思表示は最初からなかったものとして扱われちゃいます。A-B間の売買契約もさかのぼって無効になり、Cは権利のないBから不動産を購入したことになるので所有権が…
騙されたAもですがBを所有者だと信じた第三者Cも法律は保護しないといけないです。CがA-B間の詐欺の事実を知らなかった以上、AはCから不動産を取り戻せないと民法では決まってます
法定相続分について
被相続人Aは 1200万円の財産を残して死亡した。この遺産を妻Bと3人の子供C、D、Eが相続する場合、各自の相続額はいくらか?
この場合、2つのケースが考えられます。
?配偶者及び嫡出子の相続分
?配偶者及び非嫡出子の相続分
です。
?の場合
配偶者である妻Bの相続額は 1200万円×1/2=600万円 です。一方、嫡出子は3人で均分相続だから、 1200万円-600万円=600万円(嫡出子の総額) 600万円×1/3=200万円 がそれぞれの子供の相続額になります。
?の場合
C、Dが嫡出子、Eだけが非嫡出子だとすると、
どちらも同一順位の相続権をもつことに変わりはないですが、非嫡出子の相続額は嫡出子の1/2になります。(民法900条4号)
そのため 3人の子供の相続額は C:D:E=2:2:1の割合で分けられことになります。
よってC、Dはそれぞれ
600万円×2/5=240万円を
Eは 600万円×1/5=120万円を相続することになります。
被相続人Aは 1200万円の財産を残して死亡した。この遺産を妻Bと3人の子供C、D、Eが相続する場合、各自の相続額はいくらか?
この場合、2つのケースが考えられます。
?配偶者及び嫡出子の相続分
?配偶者及び非嫡出子の相続分
です。
?の場合
配偶者である妻Bの相続額は 1200万円×1/2=600万円 です。一方、嫡出子は3人で均分相続だから、 1200万円-600万円=600万円(嫡出子の総額) 600万円×1/3=200万円 がそれぞれの子供の相続額になります。
?の場合
C、Dが嫡出子、Eだけが非嫡出子だとすると、
どちらも同一順位の相続権をもつことに変わりはないですが、非嫡出子の相続額は嫡出子の1/2になります。(民法900条4号)
そのため 3人の子供の相続額は C:D:E=2:2:1の割合で分けられことになります。
よってC、Dはそれぞれ
600万円×2/5=240万円を
Eは 600万円×1/5=120万円を相続することになります。
相続人間の公平
相続人として子(嫡出子)A、B、C がいる。遺産総額が5000万円で、子Aは500万円の寄与分がある。子Bは、生計の資本として生前に1500万円の贈与を受けている。子A、B、C の相続額はいくらずつになるか?
被相続人の生前に、その財産の維持・増加に貢献した者がいるときは、遺産分割の際、その寄与分を評価しないと不公平になってしまいます。
そこで、相続人の中に寄与分を受けることが出来る者がいるときは、あらかじめその寄与分を相続財産から控除して、これを 「みなし相続財産」 として相続分の計算を行います。この相続分と、先に控除した寄与分とを加えたものが、寄与した相続人の具体的な相続分になります。(民法904条の2第1項)
→寄与した者は法定相続分を超える相続分を取得できることになります。贈与された場合は贈与分を減産した分が相続になります。
そこで、あらためて先の問題を考えてみましょう。遺産総額は5000万円ですが、相続人Aには500万円の寄与分、Bは生前贈与された1500万円の特別受益があります。
そうすると
「みなし相続財産」は
特別受益額1500万円を加算する一方、寄与分500万円を控除するから
5000万円+1500万円-500万円=6000万円
が「みなし相続財産」になります。
これを前提とする3人の嫡出子の法定相続分は
6000万円×1/3=2000万円
ですが、Aはこの相続額に寄与分を加えた額
2000万円+500万円=2500万円
を相続することになります。
一方、Bはすでに1500万円の生前贈与を受けているので
2000万円-1500万円=500万円
を相続することになります。
Cは2000万円の相続になります。
相続人として子(嫡出子)A、B、C がいる。遺産総額が5000万円で、子Aは500万円の寄与分がある。子Bは、生計の資本として生前に1500万円の贈与を受けている。子A、B、C の相続額はいくらずつになるか?
被相続人の生前に、その財産の維持・増加に貢献した者がいるときは、遺産分割の際、その寄与分を評価しないと不公平になってしまいます。
そこで、相続人の中に寄与分を受けることが出来る者がいるときは、あらかじめその寄与分を相続財産から控除して、これを 「みなし相続財産」 として相続分の計算を行います。この相続分と、先に控除した寄与分とを加えたものが、寄与した相続人の具体的な相続分になります。(民法904条の2第1項)
→寄与した者は法定相続分を超える相続分を取得できることになります。贈与された場合は贈与分を減産した分が相続になります。
そこで、あらためて先の問題を考えてみましょう。遺産総額は5000万円ですが、相続人Aには500万円の寄与分、Bは生前贈与された1500万円の特別受益があります。
そうすると
「みなし相続財産」は
特別受益額1500万円を加算する一方、寄与分500万円を控除するから
5000万円+1500万円-500万円=6000万円
が「みなし相続財産」になります。
これを前提とする3人の嫡出子の法定相続分は
6000万円×1/3=2000万円
ですが、Aはこの相続額に寄与分を加えた額
2000万円+500万円=2500万円
を相続することになります。
一方、Bはすでに1500万円の生前贈与を受けているので
2000万円-1500万円=500万円
を相続することになります。
Cは2000万円の相続になります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
社会福祉士国家試験勉強部屋 更新情報
-
最新のアンケート
社会福祉士国家試験勉強部屋のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77426人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209463人
- 3位
- 空を見上げるのが好き
- 139119人