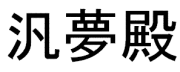9/23に、「追想五断章」発売を記念したトークセッションが、オリオン書房ノルテ店(東京・立川)にて行われました。
当日は録音・撮影が禁止されておりましたが、メモを取ることと、当日の講和内容のWEB掲載について書店担当の方と米澤先生に許可を頂きました。
東京近郊在住でない為参加できなかった方々にも有益なものと思い、ここに掲載させていただきます。
<注意>
・「追想五断章」のネタバレ内容を含みます。その点をご理解の上でお読み下さい。
・私は「追想五断章」が読了していない為、一部表現に不正確な点があるかもしれませんこと、
ご了承下さい
・私が聞いてメモしたものから下記内容を起こしています。微妙なニュアンス・一部表現・解釈については私の感じた考えを元にしておりますこと、あらかじめご了承下さい。
・他の作品のネタバレと考えた部分等、あえて掲載していない部分がございます
本内容が参加できなかった方々のお役に立てられるようであれば、幸いです。
<トーク内容>
日時:2009年9月23日(水)16:00〜17:30+サイン会
場所:オリオン書房ノルテ店(立川)
登壇者:米澤穂信先生、
聞き手:瀧井朝世様
*冒頭の()内の文は聞き手からの質問
・(今回作品を書いた経緯などをご教授下さい)
今回は編集からやや高めの年齢層の方々が読まれるような作品を、(「渋め」の内容)ということでスタートした
・(舞台が古書店となっているのは、意識してそうしたのでしょうか)
プロットを組み立てているうちに決まった。「古書店ありき」で決めたわけではない。自身が古書店好きということもあり、古書店を舞台にしてしまうと自家中毒になりはしないかと悩んだ。
古書店には「魔境」や「魔界」というイメージが強く、おいそれと描きにくい何かがある。宮部みゆきの「寂しい狩人」でやわらかいイメージの古書店がでてきた。これがなければ、今回作品の舞台として使わなかったかもしれない。
・今回リドルストーリーとなっているが、以前からリドルストーリー(物語中に示された謎に明確な答えを与えないまま終了すること)をやろうと考えていた。今回は題材とうまくかけあったこともあり、こういう形となった。
・今回は初の長編連載小説。毎月締め切りがあり、終わらせていくわけだが、一つ一つのリドルストーリはむしろスラスラと書けた。
・(書いた内容にはどんな意図が込められていますか?)
悲劇ではあるが、絢爛とした過去の事件があり、それを「平凡な現代」と対比させるような演出ができないか、ということで構成を考えた。
・主人公は、あえて親族でなく、直接関係のない人物(古書店員)としているのは、主人公に傍観者としての客観性を与えるため。亡くなった作家の子の視点から書いてしまっては、それはどうしても家族の話になってしまうので、それを避けた。
・第五章はもともとプロットになく、編集の人からのアドバイスで加えた(芳光の父の一周忌の話を加えた)。この話を加えたことで、話にしまりが出たように思う。「さすがは編集!」と感じた。
・参吾も主人公である。いや、芳光よりも、この人こそが主人公かもしれない。
・参吾は望むでもなく主人公に押し上げられてしまった人。芳光は筋書上の主人公であるが、熱意も薄い。この両者を対比させるところにも、当初からの狙いがあった。
(芳光は自身の考えをシーンごとに描いているが、参吾が自身の考えを語るシーンはほとんどないという点でも対比となっている。これは、参吾が作品を通して考えが伝わるので、自身で語らなくてよいためできること)
・謎を残す時、理想なのは「なぜ謎を残したのか」と周りが自然に謎を考え始める状況である。
・(なぜハッピーエンドの物語が無いのか)
ハッピーエンドがない、とよく言われるが、ハッピーエンドもバッドエンドも書くのが苦手。物語が最後に収束していく際、割り算していくと、きっちり割り切れるのではなく、最後に「割り切れない余り」がのこり、そこに余韻が秘められているのではないだろうか。そういう意味でミステリーは割り切れないほうが良いと思う。書き手として「割り切れない何か」を残すのが好きであり、そのようなものを書くように目指している。
「氷菓」も元々、氷菓の意味がわかったところで終わっていた (編集の指摘で、エピローグは追加した)。
・(作家として譲れないものがありますか)
読者に「ミステリーの書き手」として認識してもらえるよう、しっかりしたミステリーを書くこと。自分はミステリー以外でも書いたことはある。一方で書いた以上は読者に満足いただける作品にしたい。いろいろなジャンルを書く場合、どの作品も面白いというならばよいが、このジャンルは苦手、というものがあるようでは、「ただ書ける」というだけでしかない。そういった意味で、いろいろ手を出して「書ける人」よりも何か一つしっかり書いて届けられる人になりたい。私にとってそれはミステリー。
・今は青春ミステリーというところからちょっと離れつつある。古典部シリーズ、小市民シリーズはありがたくも支持を頂いているが、書き始めてからもう何年もたち、読者の方も年齢が上がってきた中で、そういった人々を満足できる作品ということで考えている。
・次作は古典部の予定。発売時期は、まだ未定。決まったら発表します。
・(これまでにインスパイアされた作品は?)
久生十蘭の「白雪姫」、「妖女の眠り」とか
・「奇跡の娘」
「令嬢クリスティーナ」のイメージを出したいと思い書いた。
・(各短編についての思いいれなどをご教授下さい)
・「転生の地」
転生をテーマにしたのは「妖女の眠り」にかかわってきている。舞台がインドなのは、大学で学んだ影響。大学で、ある地域文化を学んだ際、本来専攻ではない教授に指導を受けた。その教授の専攻はインドで、教授に師事するなかでインドを学んだ事に影響を受けている。
・「小碑伝来」
小学生・中学生のころに三国志、水滸伝といった中国文学に数多く触れた。そこでは人の死があまりにあっさりと描かれており、そういったイメージを目指して書いた。
・暗いすいどう
自身の持つ南米イメージを元に書いた。舞台はボリビアである必然はなかった。
自分は南米について偏ったイメージを持っていると思っている。共産VS反政府の戦いであったり、ミステリーな雰囲気であったり。
・五編とした意味だが、五以外の数字はキリが悪く、アントワープの銃声にしっくり来るのが五だった。
図表を書いた人がいたらわかるかもしれないが、最後のトリックは奇数よりも本来偶数がしっくりくるが、最後をどうしてもあの一編にしたかったというのがあり。
・長編連載で、本当に大変だった。よく作家さんが「長編連載で編集の人を困らせてしまった」という話をされるが、まさか自分がその当事者になるとは思わなかった。
・執筆中、どうしても見たい映画があったが、スケジュールの都合でなかなかいけなかった。上映最終日、書き上がりの目処がついたので、鑑賞に出かけた。映画終了後、携帯に何件も着信履歴があり、編集さんに悪いことをした、と思った。(でも、ちゃんと書きあがりましたよ?)
・今年はまったくと言っていいほど出かけられず、映画も殆ど見ていない。
・(好きな本は?)
文章のうまい人の本を読むのが好き。エンタメ、ミステリーが多いと思う。
・(卒業後は書店員をしながら執筆していたということだが)
そうです。でも、在学中に書き溜めたものを応募したところ、一本目ですぐに通った(氷菓)。二冊目の執筆(愚者のエンドロール)まで書店員を続け、その後辞めた。
・(書店では内緒にしていたのか)
基本的に秘匿していたが、店長だけには話をし、他の店員にばれないようにした。とこらが、次回の文庫入荷時に、店長が氷菓を200冊も発注していたことが発覚(笑)。他の店員にもばれてしまう。
・(自分で自分の本を売るということもあったのか?)
自身で売ることもあり、カバーをかけたりもした。
・本屋で夜勤をする際にプロットなどを組み立てていた。夜勤時はお客さん対応が少なく、他の仕事を一通りした後でも時間に余裕が出た為。
・その時期は今思うと最も読みたいものを読みたいように読めた時期だと思う。
・今は(書き手の意図を想像してしまうなど)純粋に一読者として読むのが難しくなってきたようにおもう。ミステリー以外だと、気楽に読める
・(舞台の一つに松本が出てくるのは?)
「文学的なゆかりがあり、定番でない土地」を探した。東京への状況のしやすさなども考慮した。
金沢という案もあったが、ボトルネックで出てきたので、見送り。鎌倉という案は、「いかにも」という感じで、見送り。
・松本の決め手となったのは、自身が松本の空の広さが好きであったこと。
・(創作ノートを作っているとの事だが、それはどんなものか)
情報の提示の仕方・順序の組み立てをメモするもの。ミステリーは、情報の出る順番でまったく印象が変わるため、その構成を良く練る必要がある。リドルの順や、その仕掛け、解決編での情報提示の組み立てなど。
・具体例を挙げると、今回の小説でも、連載時と単行本出版時で、解決編の情報提示の組み立てが違う。
雑誌掲載時はインパクト重視だったが、単行本化にあたり再構築した。
・自分の小説は、既に起きてしまった事件を主人公が後追いするという形が多いと考えている。主人公が動き始めたときは、既にどうにもならない場合が多い。唯一「インシテミル」が現在進行形。「犬はどこだ」も被っているようだが、主人公が動き始めた際は殆ど終わっている。
・連載でアントワープの銃声を書いているころに「ロス疑惑」ニュースに脚光が集まったり、連載中でバブルがはじけたことを書いているあたりから世の中の経済状況が日増しに悪化していった。「時代が自分に追いついてきている!」という感じだった(笑)
・(芳光に込めた思いとはどんなものであったか)
光の当たる舞台を、暗い舞台袖から見ているという構図にするなかで、芳光には客観的に見られる立ち位置からの傍観者という位置づけにしたかった。
・(理詰めなんですね)
自分が書くものは理詰めのものである。それは、感性とか直感からでは自分が書けないからで、逆に他の方の作品でそういったものを読むと、「自分にはないものがここにある、これは自分には書けない」と感銘を受ける。
・「ミステリーは一つのゲームである」という言葉がある。読者がある程度読み進めると、犯人がわかるような真相を言い当てられるようになっていなければならないと思う。一方で、読者は犯人を当てることができてしまうとつまらない、と感じてしまう。読者が途中で犯人を察しつつも、そのときに犯人が秘めている気持ちなどが最後にわかり、読者に何か感じさせるような要素を織り交ぜたい。
“Who done it ?”のサプライズも読者としては好きである。一方で、それだけに驚きをゆだねるべきでないと考えている。
・(リドルストーリーがお好きであれば、たとえばそれだけの短編を書いてはどうか)
全部そればかりだと、欲求不満にならないだろうかと思う。
・(今後の展望について教えて下さい)
古典部・小市民シリーズは今後も大事にしたい。その他についても、ミステリーの中でやっていきたいと考えている(10月から野生時代で連載予定)。
・(小市民シリーズは次の「冬」でおわってしまうのか?
そんなことはないですよ!(力説) 人間が四季過ぎたら死んでしまうわけでない様に、冬の後には春が来ます。・・・まあ、一般論としてですが(笑)
・「さよなら妖精」の続編?
10数年後の太刀洗を主人公とした話(短編?)
・(ブログにはいろいろなことをかかれていますが、何か決め事をつくっていますか)
いえ、特に何も。だからなのか、気づくと夕飯の話が多くなっているような気がして、まずいと思っています。
―――ここで時間となり、終了。
長文にお付き合いいただきありがとうございます。
冒頭に述べたとおり、私が聞いてメモしたものを起こしていますので、ニュアンス・一部表現・解釈については私の感じた考えを元にしておりますこと、ご了承下さい。
(明らかな誤りなどがありましたら、大変申し訳ありません)
文責については米澤先生でも書店でもなく、あくまで山鳥木寸にありますこと、ご承知おきください。
本内容が参加できなかった方々のお役に立てられるようであれば、幸いです。
|
|
|
|
|
|
|
|
米澤穂信 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
米澤穂信のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37846人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人