「え→E・ℇ→イィ→飯→℮(ENERGY)→謂い」、です。
「五行」思想と「十干」を
+甲・−乙=±木・・・現実的な現物の「木=wood(tree)」ではない
+丙・−丁=±火・・・現実的な現物の「火=fire(flame)」ではない
+戊・−己=±土・・・現実的な現物の「土=soil(earth)」ではない
+庚・−辛=±金・・・現実的な現物の「金=metal(metallic)」ではない
+壬・−癸=±水・・・現実的な現物の「水=water(liquid)」ではない
モノとして現代科学概念と重ねて考えてみる。
「木=wood(tree)」
「火=fire(flame)」
「土=soil(earth)」
「金=metal(metallic)」
「水=water(liquid)」
を「特殊具体的な個別概念」としてではなく、「質的な意味としての一般概念=抽象化されたコトバ」として追求したい。
簡略した物質と物質の関係性による反応変化の流れとは
+−プラズマ結合→原子結合→分子結合→構造物質(無生物結晶)
└ →形態物質(生物細胞)
現実的に五感で確認できるモノは「動的な物質」であり、「動的変化しつつある物質」で
あるモノの状態が、ある分子結合として存在している。
水分子の
個体(solid)は氷、
液体(liquid)は水、
気体(gas)は蒸気
で、この変化の原点は境界温度差と、圧力(衝撃)の強弱、「磁場」によっても「形を変化」させる。
±H
↓
H + H=H2(水素原子2)
↓
┣→ H2O=水(原子結合の水分子)→水そのものの形状変化
↑
O(酸素原子)
↑
±O
水の極性、水分子の極性においてO=酸素原子核は水素の電子を引き付けるため、酸素は負(−)の電気的な偏りを持ち、逆に水素は正(+)の電気的な偏りを持つことになる。とにかく水とはは水素2と酸素1の結合変化体の物質であり、水自体も変化する、と言うことだ。
物質の変化とは現象的に、「原子」そのものも、温度の高低と圧力の強弱によって形を変化させる。そして、「水分子」にかぎらず、存在としてのあらゆる物質が状況、環境に応じて個体、液体、気体と変化する。
「外形変化」とは「内的な構造、形態変化」でもある。
「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」の説明によれば、「水」とは、特殊で有るらしい。
__________
”常温、大気圧下で僅かに青緑色を呈す透明な液体。
1気圧の大気圧下での沸点は約100 °C(より正確には99.9839 °C )。
融点は0 °C (実際には99.9839 °C 以下の水蒸気も、0 °C 以下の水も存在する)。
3.98 °C のとき最も比重が大きく、固体は液体より比重が小さい(通常気圧において、氷の比重は0.9168 である)。
そのため固体である氷は液体の水に浮き、氷に圧力をかけると融ける。
これは多くの他の分子とは異なる水の特性であり、水分子間での水素結合によるものである。
液体の状態では 10?7 (mol/L) (25 °C) が電離し、
水素イオン(正確にはオキソニウムイオン)と水酸化物イオンとなっている。
一般に無色透明と言われる場合が多いが実際には
この「電離したイオンの関係」でごく僅かな「青緑色」を呈す。
↑
なぜイオンの関係で青緑色になるのか?
*(↑の説明に対するボク自身の?デス。以下のヤジルシ=↑も同じ)
沸点と融点が100 °C と0 °C というきりのいい数値であるのは、水の性質を基準として摂氏での温度の目盛りが定義されたためである。
前述の通り、水は液体の方が固体よりも体積が小さい異常液体の1種としても知られる。
氷が融解して水になると、その体積は約11分の1減少する。詳細については氷の項も参照。
水は比熱容量が非常に大きいことでも知られる。
反磁性の性質を示す代表的な物質でもある。
強力な磁界に晒された水はそこから逃れるように動くことが知られており、旧約聖書の逸話にちなみこの現象を「モーゼ効果」と呼ぶ。
↑
「反磁性?」・・・この「現象的」な説明、「水が磁界から逃げるように動く」であるが、まさにこれは「現象の起こる本質の説明」ではない。現象そのものの説明である。ならば水が不安定に「+、−として電磁的に反発」しているからではないのか?
また、水はマイクロ波なども吸収しやすく、電子レンジはそれを利用して加熱をしている。
↑
「吸収」とはなにか?マイクロ波の「振動波」が水のナニを激しく不安定にし運動(加熱)させるのか?
天然の水には、僅かに重水が含まれている。
一般的に水は電気絶縁性が低いと言われるが、これはイオンなどの不純物が含まれる通常の水の性質である。
純粋な水は電気(電流)を通さない絶縁体である。
↑
「緑」と「縁」の漢字が似ている・・・けれど、関係ない、か。
亜臨界水・超臨界水
水は22.1MPaの圧力をかけると374 °C (647K) まで液体の状態を保つ。これを亜臨界水という。
これ以上の圧力、温度の状態の水を超臨界水という。
その性質は通常の状態と異なりイオン積が高く通常の水より水酸化物イオンの濃度が高くなる。また比誘電率が低い。
過冷却水
融点(1気圧では摂氏0度)以下でも凍っていない過冷却状態の液体の水のこと。
不安定であり、「振動」などの物理的ショックにより結晶化を開始して氷に転移する。
↑
「ショック」を与えるとナゼ「結晶化」するのか?
↓
過冷却水の入っている容器にビー玉などを落とすと、物体が底に着く前に着水点から凍結が広がり、全体がシャーベット状に凍りつく。
__________
と説明されている。
以下の説明展開も「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」からの抜粋記事そのものと、これを参考にし、後述したモノはボクが思考し、模索しつつある「五行・十干思想・四柱推命学」に重ねようとして展開したモノです。
*「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」に関してのコトバの意味は「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」本文にリンクして本文そのものを参照してください。
___________
分子(ぶんし)とは、電荷に中性(+−)な1つ以上の原子から構成される物質である。即ち、分子=(±原子)+(±原子)+(±原子)・・・
*(電荷(でんか)は、物質や原子・電子などが帯びている電気やその量であり、電磁相互作用の大きさを決めるものである。
電荷には正(+)と負(−)の二つの状態が存在し、それぞれ正電荷、負電荷。
原子を構成するものでは陽子が正電荷、電子が負電荷、中性子は電荷を持たない。
↑
「陽子=正電荷」、「電子=負電荷」ならば、ナゼ「電子」を「陰子」と言うコトバを使用しないんだか、ネッ?・・・対概念なら「陽子(+)」に対する「陰子(−)」だろう。
電磁相互作用(でんじそうごさよう)は、電場あるいは磁場から電荷が力を受ける相互作用のことをいい、基本相互作用の一つである。
電磁相互作用で発生する力は電磁気力(でんじきりょく)といい
電荷には(+=陽)プラスと(−=陰)マイナスがあり、同じもの同士で斥力(反発)、異なるもの同士で引力(接近結合力)が働く。
↑
( )はボクが記入したモノ。
電子の持つ電荷量の絶対値を電気素量といい、それを記号eで表わすと陽子は+e 、電子は-e、中性子は0の電荷をそれぞれ持っている。
↑
「中性子は0の電荷」ではなく、「+と−電荷」を有しないか、「±」で「電荷の現象が抑えられている、と言うこと?なんせ、「中性(子)」だから「+」「−」に偏っていないと言うことではないのか?
イオンを表わすMg2+やOH-などはそれぞれ+2eや-eだけ帯電していることを示す。
素粒子であるクオークは(-1/3)eまたは(+2/3)eの電荷を持っている。
なお反粒子はその対になる粒子と正負が逆で絶対値が等しい電荷を持つ。
↑
「粒子」に対になっている「反粒子」とはなんぞや?
「粒子」→対←「反粒子」ならば「反粒子」ではなく「対粒子」だろうがネッ!・・・あるいは「異粒子」だろう。
たとえば電子の反粒子である陽電子は+eの電荷を持ち、陽子の反粒子である反陽子は-eの電荷を持つ。
通常、物質や空間の正電荷と負電荷の量は等しく、中性を保たれる。
この「中性」とは「+」と「−」の「量」の均衡、同量ということだな。
これは原子レベルでは陽子の個数と電子の個数が等しいことを意味する。
反粒子(はんりゅうし)とは、通常の粒子と比較すると、質量とスピンが等しく、電荷など正負の属性が逆の粒子を言う。
↑
「逆粒子」と言えば少しは理解できる・・・「反粒子」とコトバを使用するなら、実際に存在するモノなのか、どうなのか?、「反粒子」とは「粒子」ではないモノなのか?「非粒子」ではない「反粒子」?・・・「電子(−)の反粒子である陽電子(+)」ならば「電子は陰電子(−)」で、「陽電子の反粒子」は「反陽電子」である。その「反陽電子(−)」とは「電子(−)」であるならば「陰電子」とすればイイのではないか?・・・ボクがコトバとして理解できるならば「陽電子」の「対粒子」である「陰電子」なのだが・・・
電子の反粒子は陽電子であり、同様に陽子には反陽子、中性子には反中性子がある。
↑
言いなおすと、「電子(−)の対粒子は陽電子であり、同様に陽子(+)には対陽子の電子(−)があり、中性子(±)には対中性子がある」と・・・チガウのカナ?
(中性子は中性であるが反中性子は構成粒子であるそれぞれのクォークが反粒子であるため反粒子が存在する)
↑
意味不明ですな・・・「構成粒子」は「粒子」だろう?←「粒子=クォーク」が「反粒子」とはナニを言ってんだか?
反粒子が通常の粒子と衝突すると対消滅を起こし、
すべての質量がエネルギーに変換される。
↑
「消滅」とは「消えて無くなるコト」だろう。「物質=エネルギー不滅」の物理学者のコトバは「乱学」であるな。
では、エネルギーとはナニか?・・・熱、光?・・・反応、動き、振動?・・・仕事?・・・?
↓
ある系が他の系に対して仕事をした場合、仕事をした系のエネルギーが仕事をした分だけ減少する。
一方、仕事をされた系はその分だけエネルギーを得て、仕事をされる前よりも行うことができる仕事量が増加する。 また、熱や光といった形態で仕事を介さずに系から系へ直接エネルギーが移動することもある。
このようにエネルギーは他の系に移動することはあるが、それ自身は不滅であり、両方の系のエネルギーの合計は保存される。
これを「エネルギー保存の法則」という。
逆に、粒子反粒子対の質量よりも大きなエネルギーを何らかの方法(粒子同士の衝突や光子などの相互作用)によって与えると、ある確率で粒子反粒子対を生成することができ、これを対生成と呼ぶ。
*(対生成(ついせいせい, Pair production)は、高いエネルギーを持った光子が原子核などに衝突したときに、粒子と反粒子が生成される自然現象のこと。量子力学の用語である。対生成とは逆に粒子と反粒子とが衝突すると、対消滅が起こる。)
↑
「無の消滅」ではなく「有の粒子⇔対粒子の変化」である。「無からの生成」ではなく「有からの変化形成」である、なッ。
数学的取り扱いにおいては、粒子が時間軸を過去に向かって進んでいるものを反粒子である、と解釈することもできる。
↑
「数学的取り扱い」とは「観念上」と言うことか?
何かの原因によって正負の電荷のバランスが崩れた時、その物質や空間は帯電しているという。
* ↑
ならば、「物質の正常安定」とは「±物質」で、不安定とは「物質の帯電(+と−の分離状態)」であると言うことらしい、なッ?
帯電した物体は電場を作り出したりそれに影響を与える。
↑
「帯電」とは「物質の属性」なのか、それとも「+と−の電荷」そのものが「物質」なのか・・・「帯電」するもしないも「物質の属性」である。
クーロンの法則によると、電荷を持った物体は電荷の符号が同じものどうしは反発し、異符号のものは互いに引きつけあう。
その力はそれぞれの電荷の積に比例し距離の2乗に反比例する。
電荷がある面を単位時間に通過する総量が電流の大きさであり,その次元はC/sとなる。これはA(アンペア)であり、クーロン量Q[C]は電流I[A]と時間t[s]の積に等しい。つまり Q = It となる。国際単位系(SI)ではAを基本単位に選んでいるので,Cは組立単位となる。)
*(物質(ぶっしつ) とは物体を構成し、空間を占有する性質のある存在のことである。
日常的には単に「物」や「モノ」とも呼ばれ、元素から構成される固体、液体あるいは気体の状態をとる物体を指す。
物質の元素は、さらに素粒子によって構成されている。
物質はあくまで宇宙を構成する諸存在のうちのひとつである。
↑
「物質はあくまで宇宙を構成する諸存在のうちのひとつである。」
↑
「宇宙」は「物質そのもの」である。「諸存在」とは「諸物質」と「諸物質」の諸関係性で「存在」するのである。
人間の「生物」としての「意識・精神」も「諸物質、諸存在」の必然としてこの「宇宙」に、「地球上」に「動的変化」によって形成されたのだ、と・・・
物質と対置される存在は「非物質」と呼ばれ、空間、時間、情報を始めとして、多数存在する。
↑
ボクの考え・・・→空間=モノとモノの間のコト、時間=モノとモノによる関係した変化のプロセスで、「物質の存在」は「空間=二つ以上の物質の相対位置関係」と「時間=二つ以上の物質間の反応と物質自体の変化」が必要、かつ絶対条件である。「情報」とはなにかであるが、「情報」ではなく、モノとモノの関係でその影響物質を「伝達・運搬・移動」する「モノ→間隙→モノ→感激モノだな?」のモノはナニか?を問いたい。
「非物質(空間、時間、情報)」は認識対象である「モノ」を歴史的知的レベルの状況の中で、人間が意識し、その「モノのあり方」を意味説明する「コトバ・概念・規範・カテゴリー」として「音声化・文字化」し時間的に獲得してきたものである。「モノ」としての意識的人間の対象として「人間、家族、社会」も含まれる。
物質 →「空間・間隙」←物質
A物質→「関係=移動・結合・反発・時間=変化プロセス」←B物質→変化したA物質とB物質
相互間の物質構造の全部、あるいは部分を移動結合か移動反発分散が「相互物質の変化」と言うことだ。逆に言えば「空間」が存在しないところには物質は存在せず、「時間」プロセスで変化しない物質は存在しない。
「二物質以上の相互諸存在の諸関係」が「空間」と「時間」を存在させ、「相互変化する諸存在」として存在しているのである。
物質存在の「必要、絶対存在条件」の三位一体である。
_____
分子は常温、常圧環境下においては第18族元素の場合に一個の原子で分子を形成するが、多くの場合は同種あるいは異なる元素の原子が複数個集合して分子が形成される。
前者を単原子分子と呼び、後者を多原子分子と呼ぶ。
つまり希ガス以外の分子は多原子分子である。
見方を変えるならば、分子は連続したポテンシャル表面を共有する永続的な化学結合により結びつれられた原子の集団である。
化学結合に結び付けられた分子内の原子は
内部エネルギーにより「振動」しているので、
↑
「振動」?・・・電子レンジの水の加熱・・・マイクロ波が照射されると、極性をもつ水分子を繋ぐ振動子が振動エネルギーを吸収して振動をし始め、エネルギー準位を上げていく。すると、いわゆる、結合の手(振動子)を放して蒸発することになる
分子の構造は必ずしも静的ではない。
↑
必ず「動的」なのである。
分子内の化学結合の乖離や新しい結合の生成し構成する原子の組み換えが起こると分子の種類、すなわち物質の変化として認識される。
あるいは分子から電子が付加あるいは脱離したものはイオンと呼ばれる。
*(イオン(ion, 発音記号 ai?n)は、原子あるいは分子が、電子を授受することによって電荷を持ったものをいう。
電離層などのプラズマ、電解質の水溶液、イオン結晶などのイオン結合性を持つ物質内などに存在する。
プラズマはイオン化した気体である。)
________
さて、イイたいコトとはこれからである・・・
人間を対象にするならば人体の肉体を構成している諸器官の働きと、諸器官同士の相互作用、及びその器官を構成している諸細胞、さらには細胞間に於ける諸機能と「相互反応作用」ならば、生命維持活動は「調和としての新陳代謝」であることは理解できる。しかも、単純に言えば、細胞機能、器官機能を「強める(活発化する)」か、「弱める(抑制する)」かのリズムとバランスである。そのほとんどは「人体内の酸化作用(酸素+他の元素との結合反応によるエネルギー代謝)」のバランス調和である。
解剖学的に人体の個々の諸器官は「形態と色彩」として確認できる。
「+、−の十干の関係結合、±(変通)、±(十二運)」は、ソレを基本とスル生命活動には不十分のようにも思えるが、「遺伝子染色体」が「A-T-C-Gのタンパク質の二重螺旋」から成り立っていることを思えば「±の10干」は複雑な形態、構造、構成を創り出すには充分である。
目に見えて確認できるのは、諸状況、諸環境との関係の中でモノ(物質)が「形=立体構造・立体形態」と「色彩」が「存在」を決定している、と言うことである。そして、自然界の中で「リズム的=動的に調和、不調和」として存在しているコトである。
形の原点は球状の粒である「●」と、「○」である・・・
”球(きゅう、ball)あるいは球体(きゅうたい、solid sphere)とは、空間上のある 1 点から等距離にあるすべての点の集合である球面 (sphere) とその内部にある点からなる集合。通常は3次元空間にあるものを指す場合が多い。そして平面図形の「△」を基本としたあらゆる「立体的な結晶」である。”
・・・らしい。
立体の初形成は△を四面にした「△+▽+△+▼=三角錐=四面体」で、あらゆる同質立体形のモノは全方向から圧力をかければ限り無く「球状」になる。サッカーボールは「球状」に見えるのだが、何面の「球状」か・・・
「一般的にイメージされる切頂二十面体のサッカーボール。黒い五角形のパネル12枚と白い六角形のパネル20枚で構成される。」
・・・らしい。
さらに「正多面体 (regular polyhedron)、またはプラトンの立体 (Platonic solid) とは、すべての面が同一の正多角形で構成されてあり、かつすべての頂点において接する面の数が等しい多面体のこと。
正多面体には正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体の五種類がある。」
・・・らしい。
正二十面体(せいにじゅうめんたい、regular icosahedron)は立体の名称の1つ。空間を正三角形20枚で囲んだ凸多面体。3次元空間で最大の面数を持つ正多面体である。
辺30本、頂点12個からなる。
向かい合う面は平行である。
正十二面体とは双対の関係にある。
正多面体、ゾーン多面体、デルタ多面体の一種。
正二十面体(せいにじゅうめんたい)
↑↓
双五角錐反柱→五行・十干の立体と変通事象
正反五角柱の両底面に正五角錐を貼り付けた形である。よって、正二十面体を双五角錐反柱 (gyroelongated pentagonal bipyramid) と呼ぶ場合がある。
↑
五行、十干思想とは「五角形=正三角形△+正三角形△+正三角形△」の合体平面図である。「正二十面体」は空間を「正三角形X20枚」で囲んだ凸多面体だが、その立体が回転しながら複雑かつ幾何学的な面を見せていく。ある位置で視線は「五角形=五角錐」を認識するだろう。人生は複雑怪奇であるが、「生物的生死」だけではなく、その「人生履歴」はなんらかの「法則性」によっているらしい・・・
http://
「五行」思想と「十干」を
+甲・−乙=±木・・・現実的な現物の「木=wood(tree)」ではない
+丙・−丁=±火・・・現実的な現物の「火=fire(flame)」ではない
+戊・−己=±土・・・現実的な現物の「土=soil(earth)」ではない
+庚・−辛=±金・・・現実的な現物の「金=metal(metallic)」ではない
+壬・−癸=±水・・・現実的な現物の「水=water(liquid)」ではない
モノとして現代科学概念と重ねて考えてみる。
「木=wood(tree)」
「火=fire(flame)」
「土=soil(earth)」
「金=metal(metallic)」
「水=water(liquid)」
を「特殊具体的な個別概念」としてではなく、「質的な意味としての一般概念=抽象化されたコトバ」として追求したい。
簡略した物質と物質の関係性による反応変化の流れとは
+−プラズマ結合→原子結合→分子結合→構造物質(無生物結晶)
└ →形態物質(生物細胞)
現実的に五感で確認できるモノは「動的な物質」であり、「動的変化しつつある物質」で
あるモノの状態が、ある分子結合として存在している。
水分子の
個体(solid)は氷、
液体(liquid)は水、
気体(gas)は蒸気
で、この変化の原点は境界温度差と、圧力(衝撃)の強弱、「磁場」によっても「形を変化」させる。
±H
↓
H + H=H2(水素原子2)
↓
┣→ H2O=水(原子結合の水分子)→水そのものの形状変化
↑
O(酸素原子)
↑
±O
水の極性、水分子の極性においてO=酸素原子核は水素の電子を引き付けるため、酸素は負(−)の電気的な偏りを持ち、逆に水素は正(+)の電気的な偏りを持つことになる。とにかく水とはは水素2と酸素1の結合変化体の物質であり、水自体も変化する、と言うことだ。
物質の変化とは現象的に、「原子」そのものも、温度の高低と圧力の強弱によって形を変化させる。そして、「水分子」にかぎらず、存在としてのあらゆる物質が状況、環境に応じて個体、液体、気体と変化する。
「外形変化」とは「内的な構造、形態変化」でもある。
「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」の説明によれば、「水」とは、特殊で有るらしい。
__________
”常温、大気圧下で僅かに青緑色を呈す透明な液体。
1気圧の大気圧下での沸点は約100 °C(より正確には99.9839 °C )。
融点は0 °C (実際には99.9839 °C 以下の水蒸気も、0 °C 以下の水も存在する)。
3.98 °C のとき最も比重が大きく、固体は液体より比重が小さい(通常気圧において、氷の比重は0.9168 である)。
そのため固体である氷は液体の水に浮き、氷に圧力をかけると融ける。
これは多くの他の分子とは異なる水の特性であり、水分子間での水素結合によるものである。
液体の状態では 10?7 (mol/L) (25 °C) が電離し、
水素イオン(正確にはオキソニウムイオン)と水酸化物イオンとなっている。
一般に無色透明と言われる場合が多いが実際には
この「電離したイオンの関係」でごく僅かな「青緑色」を呈す。
↑
なぜイオンの関係で青緑色になるのか?
*(↑の説明に対するボク自身の?デス。以下のヤジルシ=↑も同じ)
沸点と融点が100 °C と0 °C というきりのいい数値であるのは、水の性質を基準として摂氏での温度の目盛りが定義されたためである。
前述の通り、水は液体の方が固体よりも体積が小さい異常液体の1種としても知られる。
氷が融解して水になると、その体積は約11分の1減少する。詳細については氷の項も参照。
水は比熱容量が非常に大きいことでも知られる。
反磁性の性質を示す代表的な物質でもある。
強力な磁界に晒された水はそこから逃れるように動くことが知られており、旧約聖書の逸話にちなみこの現象を「モーゼ効果」と呼ぶ。
↑
「反磁性?」・・・この「現象的」な説明、「水が磁界から逃げるように動く」であるが、まさにこれは「現象の起こる本質の説明」ではない。現象そのものの説明である。ならば水が不安定に「+、−として電磁的に反発」しているからではないのか?
また、水はマイクロ波なども吸収しやすく、電子レンジはそれを利用して加熱をしている。
↑
「吸収」とはなにか?マイクロ波の「振動波」が水のナニを激しく不安定にし運動(加熱)させるのか?
天然の水には、僅かに重水が含まれている。
一般的に水は電気絶縁性が低いと言われるが、これはイオンなどの不純物が含まれる通常の水の性質である。
純粋な水は電気(電流)を通さない絶縁体である。
↑
「緑」と「縁」の漢字が似ている・・・けれど、関係ない、か。
亜臨界水・超臨界水
水は22.1MPaの圧力をかけると374 °C (647K) まで液体の状態を保つ。これを亜臨界水という。
これ以上の圧力、温度の状態の水を超臨界水という。
その性質は通常の状態と異なりイオン積が高く通常の水より水酸化物イオンの濃度が高くなる。また比誘電率が低い。
過冷却水
融点(1気圧では摂氏0度)以下でも凍っていない過冷却状態の液体の水のこと。
不安定であり、「振動」などの物理的ショックにより結晶化を開始して氷に転移する。
↑
「ショック」を与えるとナゼ「結晶化」するのか?
↓
過冷却水の入っている容器にビー玉などを落とすと、物体が底に着く前に着水点から凍結が広がり、全体がシャーベット状に凍りつく。
__________
と説明されている。
以下の説明展開も「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」からの抜粋記事そのものと、これを参考にし、後述したモノはボクが思考し、模索しつつある「五行・十干思想・四柱推命学」に重ねようとして展開したモノです。
*「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」に関してのコトバの意味は「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」本文にリンクして本文そのものを参照してください。
___________
分子(ぶんし)とは、電荷に中性(+−)な1つ以上の原子から構成される物質である。即ち、分子=(±原子)+(±原子)+(±原子)・・・
*(電荷(でんか)は、物質や原子・電子などが帯びている電気やその量であり、電磁相互作用の大きさを決めるものである。
電荷には正(+)と負(−)の二つの状態が存在し、それぞれ正電荷、負電荷。
原子を構成するものでは陽子が正電荷、電子が負電荷、中性子は電荷を持たない。
↑
「陽子=正電荷」、「電子=負電荷」ならば、ナゼ「電子」を「陰子」と言うコトバを使用しないんだか、ネッ?・・・対概念なら「陽子(+)」に対する「陰子(−)」だろう。
電磁相互作用(でんじそうごさよう)は、電場あるいは磁場から電荷が力を受ける相互作用のことをいい、基本相互作用の一つである。
電磁相互作用で発生する力は電磁気力(でんじきりょく)といい
電荷には(+=陽)プラスと(−=陰)マイナスがあり、同じもの同士で斥力(反発)、異なるもの同士で引力(接近結合力)が働く。
↑
( )はボクが記入したモノ。
電子の持つ電荷量の絶対値を電気素量といい、それを記号eで表わすと陽子は+e 、電子は-e、中性子は0の電荷をそれぞれ持っている。
↑
「中性子は0の電荷」ではなく、「+と−電荷」を有しないか、「±」で「電荷の現象が抑えられている、と言うこと?なんせ、「中性(子)」だから「+」「−」に偏っていないと言うことではないのか?
イオンを表わすMg2+やOH-などはそれぞれ+2eや-eだけ帯電していることを示す。
素粒子であるクオークは(-1/3)eまたは(+2/3)eの電荷を持っている。
なお反粒子はその対になる粒子と正負が逆で絶対値が等しい電荷を持つ。
↑
「粒子」に対になっている「反粒子」とはなんぞや?
「粒子」→対←「反粒子」ならば「反粒子」ではなく「対粒子」だろうがネッ!・・・あるいは「異粒子」だろう。
たとえば電子の反粒子である陽電子は+eの電荷を持ち、陽子の反粒子である反陽子は-eの電荷を持つ。
通常、物質や空間の正電荷と負電荷の量は等しく、中性を保たれる。
この「中性」とは「+」と「−」の「量」の均衡、同量ということだな。
これは原子レベルでは陽子の個数と電子の個数が等しいことを意味する。
反粒子(はんりゅうし)とは、通常の粒子と比較すると、質量とスピンが等しく、電荷など正負の属性が逆の粒子を言う。
↑
「逆粒子」と言えば少しは理解できる・・・「反粒子」とコトバを使用するなら、実際に存在するモノなのか、どうなのか?、「反粒子」とは「粒子」ではないモノなのか?「非粒子」ではない「反粒子」?・・・「電子(−)の反粒子である陽電子(+)」ならば「電子は陰電子(−)」で、「陽電子の反粒子」は「反陽電子」である。その「反陽電子(−)」とは「電子(−)」であるならば「陰電子」とすればイイのではないか?・・・ボクがコトバとして理解できるならば「陽電子」の「対粒子」である「陰電子」なのだが・・・
電子の反粒子は陽電子であり、同様に陽子には反陽子、中性子には反中性子がある。
↑
言いなおすと、「電子(−)の対粒子は陽電子であり、同様に陽子(+)には対陽子の電子(−)があり、中性子(±)には対中性子がある」と・・・チガウのカナ?
(中性子は中性であるが反中性子は構成粒子であるそれぞれのクォークが反粒子であるため反粒子が存在する)
↑
意味不明ですな・・・「構成粒子」は「粒子」だろう?←「粒子=クォーク」が「反粒子」とはナニを言ってんだか?
反粒子が通常の粒子と衝突すると対消滅を起こし、
すべての質量がエネルギーに変換される。
↑
「消滅」とは「消えて無くなるコト」だろう。「物質=エネルギー不滅」の物理学者のコトバは「乱学」であるな。
では、エネルギーとはナニか?・・・熱、光?・・・反応、動き、振動?・・・仕事?・・・?
↓
ある系が他の系に対して仕事をした場合、仕事をした系のエネルギーが仕事をした分だけ減少する。
一方、仕事をされた系はその分だけエネルギーを得て、仕事をされる前よりも行うことができる仕事量が増加する。 また、熱や光といった形態で仕事を介さずに系から系へ直接エネルギーが移動することもある。
このようにエネルギーは他の系に移動することはあるが、それ自身は不滅であり、両方の系のエネルギーの合計は保存される。
これを「エネルギー保存の法則」という。
逆に、粒子反粒子対の質量よりも大きなエネルギーを何らかの方法(粒子同士の衝突や光子などの相互作用)によって与えると、ある確率で粒子反粒子対を生成することができ、これを対生成と呼ぶ。
*(対生成(ついせいせい, Pair production)は、高いエネルギーを持った光子が原子核などに衝突したときに、粒子と反粒子が生成される自然現象のこと。量子力学の用語である。対生成とは逆に粒子と反粒子とが衝突すると、対消滅が起こる。)
↑
「無の消滅」ではなく「有の粒子⇔対粒子の変化」である。「無からの生成」ではなく「有からの変化形成」である、なッ。
数学的取り扱いにおいては、粒子が時間軸を過去に向かって進んでいるものを反粒子である、と解釈することもできる。
↑
「数学的取り扱い」とは「観念上」と言うことか?
何かの原因によって正負の電荷のバランスが崩れた時、その物質や空間は帯電しているという。
* ↑
ならば、「物質の正常安定」とは「±物質」で、不安定とは「物質の帯電(+と−の分離状態)」であると言うことらしい、なッ?
帯電した物体は電場を作り出したりそれに影響を与える。
↑
「帯電」とは「物質の属性」なのか、それとも「+と−の電荷」そのものが「物質」なのか・・・「帯電」するもしないも「物質の属性」である。
クーロンの法則によると、電荷を持った物体は電荷の符号が同じものどうしは反発し、異符号のものは互いに引きつけあう。
その力はそれぞれの電荷の積に比例し距離の2乗に反比例する。
電荷がある面を単位時間に通過する総量が電流の大きさであり,その次元はC/sとなる。これはA(アンペア)であり、クーロン量Q[C]は電流I[A]と時間t[s]の積に等しい。つまり Q = It となる。国際単位系(SI)ではAを基本単位に選んでいるので,Cは組立単位となる。)
*(物質(ぶっしつ) とは物体を構成し、空間を占有する性質のある存在のことである。
日常的には単に「物」や「モノ」とも呼ばれ、元素から構成される固体、液体あるいは気体の状態をとる物体を指す。
物質の元素は、さらに素粒子によって構成されている。
物質はあくまで宇宙を構成する諸存在のうちのひとつである。
↑
「物質はあくまで宇宙を構成する諸存在のうちのひとつである。」
↑
「宇宙」は「物質そのもの」である。「諸存在」とは「諸物質」と「諸物質」の諸関係性で「存在」するのである。
人間の「生物」としての「意識・精神」も「諸物質、諸存在」の必然としてこの「宇宙」に、「地球上」に「動的変化」によって形成されたのだ、と・・・
物質と対置される存在は「非物質」と呼ばれ、空間、時間、情報を始めとして、多数存在する。
↑
ボクの考え・・・→空間=モノとモノの間のコト、時間=モノとモノによる関係した変化のプロセスで、「物質の存在」は「空間=二つ以上の物質の相対位置関係」と「時間=二つ以上の物質間の反応と物質自体の変化」が必要、かつ絶対条件である。「情報」とはなにかであるが、「情報」ではなく、モノとモノの関係でその影響物質を「伝達・運搬・移動」する「モノ→間隙→モノ→感激モノだな?」のモノはナニか?を問いたい。
「非物質(空間、時間、情報)」は認識対象である「モノ」を歴史的知的レベルの状況の中で、人間が意識し、その「モノのあり方」を意味説明する「コトバ・概念・規範・カテゴリー」として「音声化・文字化」し時間的に獲得してきたものである。「モノ」としての意識的人間の対象として「人間、家族、社会」も含まれる。
物質 →「空間・間隙」←物質
A物質→「関係=移動・結合・反発・時間=変化プロセス」←B物質→変化したA物質とB物質
相互間の物質構造の全部、あるいは部分を移動結合か移動反発分散が「相互物質の変化」と言うことだ。逆に言えば「空間」が存在しないところには物質は存在せず、「時間」プロセスで変化しない物質は存在しない。
「二物質以上の相互諸存在の諸関係」が「空間」と「時間」を存在させ、「相互変化する諸存在」として存在しているのである。
物質存在の「必要、絶対存在条件」の三位一体である。
_____
分子は常温、常圧環境下においては第18族元素の場合に一個の原子で分子を形成するが、多くの場合は同種あるいは異なる元素の原子が複数個集合して分子が形成される。
前者を単原子分子と呼び、後者を多原子分子と呼ぶ。
つまり希ガス以外の分子は多原子分子である。
見方を変えるならば、分子は連続したポテンシャル表面を共有する永続的な化学結合により結びつれられた原子の集団である。
化学結合に結び付けられた分子内の原子は
内部エネルギーにより「振動」しているので、
↑
「振動」?・・・電子レンジの水の加熱・・・マイクロ波が照射されると、極性をもつ水分子を繋ぐ振動子が振動エネルギーを吸収して振動をし始め、エネルギー準位を上げていく。すると、いわゆる、結合の手(振動子)を放して蒸発することになる
分子の構造は必ずしも静的ではない。
↑
必ず「動的」なのである。
分子内の化学結合の乖離や新しい結合の生成し構成する原子の組み換えが起こると分子の種類、すなわち物質の変化として認識される。
あるいは分子から電子が付加あるいは脱離したものはイオンと呼ばれる。
*(イオン(ion, 発音記号 ai?n)は、原子あるいは分子が、電子を授受することによって電荷を持ったものをいう。
電離層などのプラズマ、電解質の水溶液、イオン結晶などのイオン結合性を持つ物質内などに存在する。
プラズマはイオン化した気体である。)
________
さて、イイたいコトとはこれからである・・・
人間を対象にするならば人体の肉体を構成している諸器官の働きと、諸器官同士の相互作用、及びその器官を構成している諸細胞、さらには細胞間に於ける諸機能と「相互反応作用」ならば、生命維持活動は「調和としての新陳代謝」であることは理解できる。しかも、単純に言えば、細胞機能、器官機能を「強める(活発化する)」か、「弱める(抑制する)」かのリズムとバランスである。そのほとんどは「人体内の酸化作用(酸素+他の元素との結合反応によるエネルギー代謝)」のバランス調和である。
解剖学的に人体の個々の諸器官は「形態と色彩」として確認できる。
「+、−の十干の関係結合、±(変通)、±(十二運)」は、ソレを基本とスル生命活動には不十分のようにも思えるが、「遺伝子染色体」が「A-T-C-Gのタンパク質の二重螺旋」から成り立っていることを思えば「±の10干」は複雑な形態、構造、構成を創り出すには充分である。
目に見えて確認できるのは、諸状況、諸環境との関係の中でモノ(物質)が「形=立体構造・立体形態」と「色彩」が「存在」を決定している、と言うことである。そして、自然界の中で「リズム的=動的に調和、不調和」として存在しているコトである。
形の原点は球状の粒である「●」と、「○」である・・・
”球(きゅう、ball)あるいは球体(きゅうたい、solid sphere)とは、空間上のある 1 点から等距離にあるすべての点の集合である球面 (sphere) とその内部にある点からなる集合。通常は3次元空間にあるものを指す場合が多い。そして平面図形の「△」を基本としたあらゆる「立体的な結晶」である。”
・・・らしい。
立体の初形成は△を四面にした「△+▽+△+▼=三角錐=四面体」で、あらゆる同質立体形のモノは全方向から圧力をかければ限り無く「球状」になる。サッカーボールは「球状」に見えるのだが、何面の「球状」か・・・
「一般的にイメージされる切頂二十面体のサッカーボール。黒い五角形のパネル12枚と白い六角形のパネル20枚で構成される。」
・・・らしい。
さらに「正多面体 (regular polyhedron)、またはプラトンの立体 (Platonic solid) とは、すべての面が同一の正多角形で構成されてあり、かつすべての頂点において接する面の数が等しい多面体のこと。
正多面体には正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体の五種類がある。」
・・・らしい。
正二十面体(せいにじゅうめんたい、regular icosahedron)は立体の名称の1つ。空間を正三角形20枚で囲んだ凸多面体。3次元空間で最大の面数を持つ正多面体である。
辺30本、頂点12個からなる。
向かい合う面は平行である。
正十二面体とは双対の関係にある。
正多面体、ゾーン多面体、デルタ多面体の一種。
正二十面体(せいにじゅうめんたい)
↑↓
双五角錐反柱→五行・十干の立体と変通事象
正反五角柱の両底面に正五角錐を貼り付けた形である。よって、正二十面体を双五角錐反柱 (gyroelongated pentagonal bipyramid) と呼ぶ場合がある。
↑
五行、十干思想とは「五角形=正三角形△+正三角形△+正三角形△」の合体平面図である。「正二十面体」は空間を「正三角形X20枚」で囲んだ凸多面体だが、その立体が回転しながら複雑かつ幾何学的な面を見せていく。ある位置で視線は「五角形=五角錐」を認識するだろう。人生は複雑怪奇であるが、「生物的生死」だけではなく、その「人生履歴」はなんらかの「法則性」によっているらしい・・・
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
運命時計 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
運命時計のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31947人
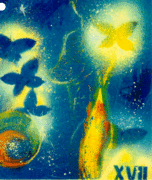















![@[無料自己ワクチン療法] の勧め](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/17/63/61763_133s.jpg)






