四柱推命の自然弁証法、あるいは、宇宙弁証法
「形態論的」諸関係と「構造論的」諸関係
最近の「生命・生物学」に於ける最高の興味あるニュースは京都大学が研究している「万能細胞」であろう。
「染色体遺伝子」の「構造」が明らかにされてから既に年月を経たが、その染色体の遺伝子DNAが生物諸細胞の「発生」に如何なる機能性を有するのかの解明研究も日進月歩の速さで進行している。
「万能細胞」・・・ある細胞が生物の「生きた諸器官」に分化形成され、その「諸器官」が生物システムとしての「形態」になっていくには、その「万能細胞」が、他の何らかの「刺激」を受けねばならないと言うことであった。当初、その「万能細胞の分化」に「スイッチ-On」として刺激反応を与えたモノが「がん細胞」を発生さる「ヴィルス」であったらしい。
50年前ほどの中学校の「理科・生物学」の教科書には、ダーゥインの「種の起源」や、メンデルの「遺伝法則」が記され、人間の男女の「染色体数」の数の違いも記されていた。
そして雌の卵子と雄の精子での「両性生殖」での個体発生や、カエルの卵子を針で刺激することによっての「単為生殖」でオタマジャクシが発生することも記されていた、と思う。
何かと何かの「関係性」で何ものかが新たな個体ととして形成されていく。そして何かと何かの「関係性」で何ものかの個体がバラバラに壊されていく。
ある一つのモノの「形成」も「破壊」も「関係性」の結果であり、簡単に言えば、その「関係性」での「変化」である、と言える。
「形成変化」には、生物学的な「生きた形態的形成」と、無生物学的、「鉱物的」な結晶の「構造的形成」がある。
生命を形成する諸細胞の「生きたシステム機能」を有する存在をここでは「形態」と呼びたい。「生命形態」である。
無機物でそれ自体生命を有しないモノの構成存在を「構造」と呼びたい。人間が設計し、造り出す建築物、機械類も各部品から成る「構造物」である。
「形態物」は物理的、電気、電磁的、それに「化学的」な反応システムで存在する「生物」のあり方である。それ自体が「新陳代謝システム」で存在しているモノである。それ自体が息づいて「形態変化」をするモノと定義したい。
「構造物」は物理的、電気、電磁的な反応のみで存在する「無生物」のあり方である。生物以外の自然界に存在し、あるいは形成された固体、液体、気体を含めた存在物のあり方である。それ自体が自然の外的な要因の影響を受けて無機的に「構造変化」をするモノ、そして人為的に構造物として「構成」されたモノと定義したい。
そして、この宇宙、地球に「存在」するあらゆるモノは、それ自体では「存在」していない、と言うことに尽きる。すなわち、「存在」と「諸存在」の「諸関係」でしか「存在」しないのである。
しかもその「存在」のあり方は、「形態変化」と「構造変化」のプロセスとして「存在」している。
「弁証法」とは字のごとく、モノとモノの「関係性」と、その関係性に於ける「変化のあり方」を「説明」する「論理方法」である。
「変化」とは「時間」である。「時間」とはモノの「変化」である。
「四柱推命」とは、ある時間帯、ある時点の生命体の「変化形態」の「命」のあり方である。
そして、この「人間の命」が、自然、社会の諸関係で影響され、反応しながら「変化」していくプロセスを「推理」していく「自然弁証法」であり、「社会弁証法」の「論理」なのである。
「自然弁証法」はその肉体的実体の変化、「社会弁証法」はその精神的観念思考の変化であり、対人諸関係での「存在行動」の傾向性である。
・・・つづきはマタの機会で・・・
前述のつづき・・・
前回、「弁証法」とは字のごとく、モノとモノの「関係性」と、その関係性に於ける「変化のあり方」を「説明」する「論理方法」である、と記したが、この「弁証法」なるモノは意外と「自明」なモノとして「理解」しているヒトは少ないのではないだろうか・・・
和英辞典の「弁証法」は英語で「DIALECTIC」と記されている。
では「DIALECTIC」を英和辞典で調べてみると、
形容詞として
「1)弁証(法)的」、「2)方言の」、
名詞として
「1)(哲学)弁証法」、「2)(しばしば)論理的討論」
と記されている。前後の単語を見ると、
DIAGRPH・・・分度尺・作図器
DIAL・・・日時計・指針面・目盛盤・ダイアル
DIALECT・・・方言・ある階級、職業、仲間などの慣用語
DIALCTAL・・・方言の
DIALECTIAL MATERIALISM・・・唯物弁証法
DIALECTOLOGY・・・方言学・方言研究
DIALING・・・ダイアルを使っての測定
DIALOGIC・・・問答の・対話体の
DIALOGIST・・・対話者
DIALOGUE・・・対話・問答・対話(劇)・対話の台詞
DIALPHONE・・・自動式電話
DIALPLATE・・・文字盤・指針面
DIALTONE・・・発信音
DIALYSE・・・(化学)を透析する
DIALYSIS・・・分離・透析・隔膜分離
DIALYTIC・・・分離力のある・透膜性の
DIALYZER・・・透析器
とあり、「弁証法」そのものの具体的な「意味説明」、いかなる「論理内容」かの「説明」はない。で、漢和辞典を調べてみると、「弁論して証明するコト」とあるだけである。
「弁」の意味は、
1)冠・早い・急ぐ・怖れる・慄く・擦る・撫ぜる・打つ・叩く
2)別ける・裂く・区別する・分離する・わきまえる
3)明らかにする・調べる・おさめる・正す
4)ウリのなかご
5)ウリの種子を含んだ柔らかい部分
6)ウリの種
7)果物の房・ミカンなどの肉の一片
8)花びら・花弁・花片
9)弁・チュウブ(器管)を通す気体、液体の調節膜
10)二者間の対話、論議の是非を判断するコト
とある。
「DIALYSIS=分離・透析・隔膜分離」で、
「弁=別ける・裂く・区別する・分離する・わきまえる」
であるから、以上を踏まえて考えると、「二者間の論議の是非」は二者間のどちらが筋が通っているかを証明する「論法」であるらしい。だが、この「是非」を「判断する基準」はナンであるだろうか?・・・コトバに筋が通っているとは、「事実・事件」の「発端」と「プロセス」とその「結果」の「事実的説明」である。では、この「事実・事件」はどのようにコトバで「説明」されるのか?
どんな場合でも「事実・事件」は「5W・1H」での言語法則で述べられるであろう。即ち、主語と述語と目的語とその関係性の状態説明であり、
WHO・・・・誰
WHEN・・・何時
WHERE・・何処
WHAT・・・何
WHY・・・何故
HOW・・・どのように
を駆使した「コトバ」での説明である。既にこの叙述パターンが「事実・事件」と一致し、第三者にも共通認識されるならば、「弁証法」である、と言える。問題は「事実・事件」に遭遇した「立場」によってこの「事実・事件」が歪められる場合である。人間同士の関係性での「心理」は、状況によっては「事実」をコトバにしない、出来ない、と言うコトがママあるからだ。しかも「妄想・空想・幻想」は人間の特権である。
だが、自然界の「モノ」に関する叙述は共通の言葉を有する人間の間ではそのモノの存在のあり方には共通認識ができるだろう。「1+1=2」、「水=ミズ=WATER=H2O」と共通認識できる。
「弁証法=DIALECTIC」とは、あるモノの「構造」、あるいは「形態」の「コトバ」を駆使した説明である。
ここでは「DIALECTIC=弁証法」とは「存在物」のあり方を説明する「DIALECTIAL MATERIALISM=唯物弁証法」に限られる。
「DIALECTIAL MATERIALISM=唯物弁証法」の「MATERIALISM」が「唯物」とされるのは「弁証法」が「唯一」、「物質のみを対象」に認識説明するモノであるからだ。
「DIALECTIAL MATERIALISM=唯物弁証法」が「人間心理」や「人間妄想」を説明するものではないのは自明であるだろう。そして、単なる「モノ」の説明ではない。モノ、生物、無生物を含めた存在のあり方を「構造=構成の形成物質の部分」として、「形態=生態の形成物質の部分と機能(新陳代謝・反応)」として説明する「コトバの論法」が「弁証法」なのである。
すなわち、人間の「認識対象」とする「モノ」を「個別なコトバ」、「特殊なコトバ」、「普遍的なコトバ」としての意味の区別性を持たせ、その「機能性」として説明される「論法」である。
「存在」しないモノはこの論法からは排除されるのである。故に「唯一」対象とするのは「存在するモノ」だけの「論法」なのだ。
人間の「観念内部」それ自体に形成された「妄想・幻想・空想」は別次元の「論法」で説明される。その「説明論法」は「自己存在=実存」の「快=不快」、「利己=利他」の「心理学」の領域である。
当然にも、自然環境の枠内で生活する「人間社会」の個々人のあり方の根源は「人間諸関係」に於ける「利害関係」の「心理の動き」による。
今夜はココまで・・・オヤスミ・・・
http://
「形態論的」諸関係と「構造論的」諸関係
最近の「生命・生物学」に於ける最高の興味あるニュースは京都大学が研究している「万能細胞」であろう。
「染色体遺伝子」の「構造」が明らかにされてから既に年月を経たが、その染色体の遺伝子DNAが生物諸細胞の「発生」に如何なる機能性を有するのかの解明研究も日進月歩の速さで進行している。
「万能細胞」・・・ある細胞が生物の「生きた諸器官」に分化形成され、その「諸器官」が生物システムとしての「形態」になっていくには、その「万能細胞」が、他の何らかの「刺激」を受けねばならないと言うことであった。当初、その「万能細胞の分化」に「スイッチ-On」として刺激反応を与えたモノが「がん細胞」を発生さる「ヴィルス」であったらしい。
50年前ほどの中学校の「理科・生物学」の教科書には、ダーゥインの「種の起源」や、メンデルの「遺伝法則」が記され、人間の男女の「染色体数」の数の違いも記されていた。
そして雌の卵子と雄の精子での「両性生殖」での個体発生や、カエルの卵子を針で刺激することによっての「単為生殖」でオタマジャクシが発生することも記されていた、と思う。
何かと何かの「関係性」で何ものかが新たな個体ととして形成されていく。そして何かと何かの「関係性」で何ものかの個体がバラバラに壊されていく。
ある一つのモノの「形成」も「破壊」も「関係性」の結果であり、簡単に言えば、その「関係性」での「変化」である、と言える。
「形成変化」には、生物学的な「生きた形態的形成」と、無生物学的、「鉱物的」な結晶の「構造的形成」がある。
生命を形成する諸細胞の「生きたシステム機能」を有する存在をここでは「形態」と呼びたい。「生命形態」である。
無機物でそれ自体生命を有しないモノの構成存在を「構造」と呼びたい。人間が設計し、造り出す建築物、機械類も各部品から成る「構造物」である。
「形態物」は物理的、電気、電磁的、それに「化学的」な反応システムで存在する「生物」のあり方である。それ自体が「新陳代謝システム」で存在しているモノである。それ自体が息づいて「形態変化」をするモノと定義したい。
「構造物」は物理的、電気、電磁的な反応のみで存在する「無生物」のあり方である。生物以外の自然界に存在し、あるいは形成された固体、液体、気体を含めた存在物のあり方である。それ自体が自然の外的な要因の影響を受けて無機的に「構造変化」をするモノ、そして人為的に構造物として「構成」されたモノと定義したい。
そして、この宇宙、地球に「存在」するあらゆるモノは、それ自体では「存在」していない、と言うことに尽きる。すなわち、「存在」と「諸存在」の「諸関係」でしか「存在」しないのである。
しかもその「存在」のあり方は、「形態変化」と「構造変化」のプロセスとして「存在」している。
「弁証法」とは字のごとく、モノとモノの「関係性」と、その関係性に於ける「変化のあり方」を「説明」する「論理方法」である。
「変化」とは「時間」である。「時間」とはモノの「変化」である。
「四柱推命」とは、ある時間帯、ある時点の生命体の「変化形態」の「命」のあり方である。
そして、この「人間の命」が、自然、社会の諸関係で影響され、反応しながら「変化」していくプロセスを「推理」していく「自然弁証法」であり、「社会弁証法」の「論理」なのである。
「自然弁証法」はその肉体的実体の変化、「社会弁証法」はその精神的観念思考の変化であり、対人諸関係での「存在行動」の傾向性である。
・・・つづきはマタの機会で・・・
前述のつづき・・・
前回、「弁証法」とは字のごとく、モノとモノの「関係性」と、その関係性に於ける「変化のあり方」を「説明」する「論理方法」である、と記したが、この「弁証法」なるモノは意外と「自明」なモノとして「理解」しているヒトは少ないのではないだろうか・・・
和英辞典の「弁証法」は英語で「DIALECTIC」と記されている。
では「DIALECTIC」を英和辞典で調べてみると、
形容詞として
「1)弁証(法)的」、「2)方言の」、
名詞として
「1)(哲学)弁証法」、「2)(しばしば)論理的討論」
と記されている。前後の単語を見ると、
DIAGRPH・・・分度尺・作図器
DIAL・・・日時計・指針面・目盛盤・ダイアル
DIALECT・・・方言・ある階級、職業、仲間などの慣用語
DIALCTAL・・・方言の
DIALECTIAL MATERIALISM・・・唯物弁証法
DIALECTOLOGY・・・方言学・方言研究
DIALING・・・ダイアルを使っての測定
DIALOGIC・・・問答の・対話体の
DIALOGIST・・・対話者
DIALOGUE・・・対話・問答・対話(劇)・対話の台詞
DIALPHONE・・・自動式電話
DIALPLATE・・・文字盤・指針面
DIALTONE・・・発信音
DIALYSE・・・(化学)を透析する
DIALYSIS・・・分離・透析・隔膜分離
DIALYTIC・・・分離力のある・透膜性の
DIALYZER・・・透析器
とあり、「弁証法」そのものの具体的な「意味説明」、いかなる「論理内容」かの「説明」はない。で、漢和辞典を調べてみると、「弁論して証明するコト」とあるだけである。
「弁」の意味は、
1)冠・早い・急ぐ・怖れる・慄く・擦る・撫ぜる・打つ・叩く
2)別ける・裂く・区別する・分離する・わきまえる
3)明らかにする・調べる・おさめる・正す
4)ウリのなかご
5)ウリの種子を含んだ柔らかい部分
6)ウリの種
7)果物の房・ミカンなどの肉の一片
8)花びら・花弁・花片
9)弁・チュウブ(器管)を通す気体、液体の調節膜
10)二者間の対話、論議の是非を判断するコト
とある。
「DIALYSIS=分離・透析・隔膜分離」で、
「弁=別ける・裂く・区別する・分離する・わきまえる」
であるから、以上を踏まえて考えると、「二者間の論議の是非」は二者間のどちらが筋が通っているかを証明する「論法」であるらしい。だが、この「是非」を「判断する基準」はナンであるだろうか?・・・コトバに筋が通っているとは、「事実・事件」の「発端」と「プロセス」とその「結果」の「事実的説明」である。では、この「事実・事件」はどのようにコトバで「説明」されるのか?
どんな場合でも「事実・事件」は「5W・1H」での言語法則で述べられるであろう。即ち、主語と述語と目的語とその関係性の状態説明であり、
WHO・・・・誰
WHEN・・・何時
WHERE・・何処
WHAT・・・何
WHY・・・何故
HOW・・・どのように
を駆使した「コトバ」での説明である。既にこの叙述パターンが「事実・事件」と一致し、第三者にも共通認識されるならば、「弁証法」である、と言える。問題は「事実・事件」に遭遇した「立場」によってこの「事実・事件」が歪められる場合である。人間同士の関係性での「心理」は、状況によっては「事実」をコトバにしない、出来ない、と言うコトがママあるからだ。しかも「妄想・空想・幻想」は人間の特権である。
だが、自然界の「モノ」に関する叙述は共通の言葉を有する人間の間ではそのモノの存在のあり方には共通認識ができるだろう。「1+1=2」、「水=ミズ=WATER=H2O」と共通認識できる。
「弁証法=DIALECTIC」とは、あるモノの「構造」、あるいは「形態」の「コトバ」を駆使した説明である。
ここでは「DIALECTIC=弁証法」とは「存在物」のあり方を説明する「DIALECTIAL MATERIALISM=唯物弁証法」に限られる。
「DIALECTIAL MATERIALISM=唯物弁証法」の「MATERIALISM」が「唯物」とされるのは「弁証法」が「唯一」、「物質のみを対象」に認識説明するモノであるからだ。
「DIALECTIAL MATERIALISM=唯物弁証法」が「人間心理」や「人間妄想」を説明するものではないのは自明であるだろう。そして、単なる「モノ」の説明ではない。モノ、生物、無生物を含めた存在のあり方を「構造=構成の形成物質の部分」として、「形態=生態の形成物質の部分と機能(新陳代謝・反応)」として説明する「コトバの論法」が「弁証法」なのである。
すなわち、人間の「認識対象」とする「モノ」を「個別なコトバ」、「特殊なコトバ」、「普遍的なコトバ」としての意味の区別性を持たせ、その「機能性」として説明される「論法」である。
「存在」しないモノはこの論法からは排除されるのである。故に「唯一」対象とするのは「存在するモノ」だけの「論法」なのだ。
人間の「観念内部」それ自体に形成された「妄想・幻想・空想」は別次元の「論法」で説明される。その「説明論法」は「自己存在=実存」の「快=不快」、「利己=利他」の「心理学」の領域である。
当然にも、自然環境の枠内で生活する「人間社会」の個々人のあり方の根源は「人間諸関係」に於ける「利害関係」の「心理の動き」による。
今夜はココまで・・・オヤスミ・・・
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
運命時計 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
運命時計のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6468人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19248人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208303人
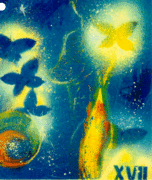















![@[無料自己ワクチン療法] の勧め](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/17/63/61763_133s.jpg)






