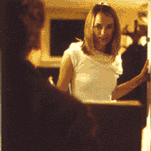みんな見せちゃうね!映画『フラメンコフラメンコ』のすべて。『キム・ホセの感想編集・』
わたしはこれほどの圧倒的な「フラメンコ・ミュージカル」というよりも「ショー」を観たことはない。ただ物語性もなくただ「フラメンコ・ショー」なのだ。
それは渋谷Bunkamura、「ル・シネマ」で上演された、カルロス・サウラの映画『フラメンコフラメンコ』だ。
何せフラメンコは友人から借りたDVDやビデオをたくさん観ていたが、いかんせん家庭のモニターである。この大画面の“ど迫力”には圧倒された。
映画を観るのは30年ぶり。
大画面の“ど迫力”というよりも、そこで「ショー」が行われていて、ついにわたしは各幕毎に【ハレオ(Jaleo) 掛け声】したくなったほど。『オーレ!!』(お見事!) や 『ビエン!!』(いいぞ!) と。
これには全くわたしの感想はいらないように思える。
ならば、探したそのいくつもの「シーン写真」を徹底的に見せてみたい。つまりこれがわたしの感想である。
ただし、いくつか気になった点についてはときおり述べよう。
その編集は私の責任において。
この映画は以下の21幕によって構成されている。
1幕●ルンバ(ホセミ・カルモナ/カルロス・ガルシア/マリア・アンヘレス・フェルナンデス他)
2幕●アレグリア(サラ・バラス/ミゲル・デ・ラ・トレア/ホセ・マリア・バンデーラ他多数)
3幕●ソレア・ポル・ブレリアス(モンセ・コルテス/ディエゴ・エル・モラオ/カルロス・グリロ他)
4幕●カルタヘネラ・イ・ブレリアス(ドランテス/ディエゴ・アマドール)
5幕●ガロティン(ロシオ・モリーナ/パコ・クルス/ロサリオ・ラ・トレメンディーダ他)
6幕●コプラ・ポル・ブレリア(ミゲル・ポベーダ/カルロス・グリロ他)
7幕●ソレア(エバ・ジェルバブエナ/パコ・ハラナ/ホセ・バレンシア/エンリケ・エル・エストレメーニョ他)
8幕●サエタ(マリア・バラ)
9幕●マルチャ・プロセシオナル(ホセ・エンリケ・デ・ラ・ベガ/ハビエル・ラトーレ/マルタ・ノガル/マイテ・ベルトラン他多数)
10幕●マルティネーテ・イ・トナ(ホセ・メルセー/セサール・モレノ・エル・グイト)
11幕●ブレリア(エル・カルペータ/アントニオ・スニーガ/ヘスス・ゲレーロ他)
12幕●シレンシオ(イスラエル・ガルバン)
13幕●グアヒーラ(アルカンヘル/ミゲル・アンヘル・コルテス/ダニ・デ・モロン/ラファエル・エステベス/ナニ・パーニョス他)
14幕●アレグリア(マノロ・サンルーカル/ダビ・カルモナ/アグスティン・ディアセーラ他)
15幕●タンゴス(エストレージャ・モレンテ/モントジータ/エンリケ・モレンテ・カルボネル・キキ/ソレア・モレンテ他多数)
16幕●エル・ティエンポ(ハビエル・ラトーレ/コレン・ルビオ/マルタ・ノガル/マイテ・ベルトラン他)
17幕●ラ・レジェンダ・デル・ティエンポ(トマティート/ニーニャ・パストーリ/ホセミ・カルモナ/パキート・ゴンサレス他)
18幕●カンシオン・デ・クーナ(エバ・ジェルバブエナ/ミゲル・ポベーダ/パコ・ハラーナ他)
19幕●サパテアオ(ファルキート/アントニオ・レイ/ベルナルド・パリージャ/ラモン・ビセンティ/イシドロ・スアレス/ペドロ・エレディア他多数)
20幕●ブレリア・ポル・ソレア(パコ・デ・ルシア/ラ・タナ/キケ・マジャ/ラ・フリ/エル・ナオ他)
21幕●ブレリア・デ・ヘレス(ルイス・エル・サンボ/モライート・チコ/ボボーテ/ボー/チチャーロ/ジョジャ/クーラ/ラ・フンケリータ他多数)
であるが、実際のところ“素人”のわたしには分からないのだが、観ている内に何となく“分かったふり”つまり魅了され“のまれる”のであった。
1995年に『フラメンコ』を撮ったカルロス・サウラ監督と、ヴィットリオ・ストラーロ撮影監督が、再びタッグを組み、21世紀に進化したフラメンコの真髄に迫った『フラメンコ フラメンコ』だ。
21幕の宴。
それは
予告に続いて、何枚もの巨大な絵が飾られた大きな倉庫のような建物の中を、カメラが進んでいく。
マリア・アンヘレスが歌う「緑よ、お前を愛している」から、21幕の宴が始まる。
2幕目、いきなり肌が透けるような赤いドレスをまとったサラ・バラスの肢体が圧倒的な存在感を画面いっぱいに見せ付ける。
シューズのかかとを踏み鳴らす「サバテアード」は、ダンサーの体の中にたぎる情熱を刻む。
もう、それだけで「フラメンコ」という情熱と官能のとりこになる。
ひとつひとつの幕が、ひとつの世界を作りながら、21幕全体で「生命の旅」と「光」という要素によって結ばれている。
陰影のある構成と圧倒的なカメラワーク
21もある幕を、どのように最後まで見せるのかと思っていたのだが、さすがフラメンコを知り尽くした両監督の手腕は卓越していた。
4幕では、なかなか触れることのない「フラメンコピアノ」という、男性二人の洗練された演奏が見られる。
8幕目には、フラメンコの名門に生まれ、マリア・バラが宗教歌を披露する。聖母マリアをたてまつる歌を無伴奏で歌い上げる80歳あまりの女性の存在感は、フラメンコの「血脈」そのものだ。
16幕の「エル・ティエンポ」は、6人の美女による群舞だ。2幕目の「いとしのサリータ」が奏でる情熱と官能とは違った、何か流れるような美しさの中に、気品が感じられる舞だ。
センターで踊るダンサーの、射るような、見るものをとりこにする視線を追ううちに、あっという間に美しすぎる幕は閉じる。
18幕の「子守唄」は、いきなり土砂降りの雨。 水煙にかすむ絵の前で歌うミゲル・ポペダにまとわりつくように濡れ髪を振り乱しながら踊るエバ・ジェル・パブエナの上半身をカメラが追う。
そう、この映画は、カメラワークが素晴らしすぎる。観客と演じ手の間には、どうしても肉薄できない「距離」があるものだが、この映画ではカメラが踊り手の間を縫っていく。…
わたしキム・ホセは何かフラメンコのあたらしき展開を見せているような、スーツにコルドバス帽でタバコを吸いながら演じるのが好きになった。いや、単に趣味なのかも・・・。
サウラ監督の新作映画。フラメンコの今をリアルに満喫できる新たな名作!
フラメンコの映像化に計りしれない功績を残したカルロス・サウラ監督の最新作。20世紀フラメンコの巨匠たちを総出演させたあの名作「FLAMENCO」から14年、フラメンコの今を最前線で疾走するアルティスタたちをズラリ揃えて、その続編ともいえる「FLAMENCO FLAMENCO」を映画化した。
サウラの撮影チームには欠かせない撮影監督のビットリオ・ストラオと音楽監督のイシドロ・ムニョスも参加して、よりドラマチックに、よりリアルにフラメンコの魅力を凝縮した作品に仕上げられている。
収録されているのは全21演目。出演者はエバ・ジェルバブエナ、サラ・バラス、ミゲル・ポベダを筆頭にイスラエル・ガルバン、ファルキート、トマティート、ロシオ・モリーナ、エストレージャ・モレンテ、アルカンヘル、ディエゴ・デル・モラオ……出演者を見ると、およそ15年の時を経た世代交代という以上に若い顔ぶれが目立つ。現代フラメンコに焦点を当てたキャスティングといっていいだろう。
そんな中でパコ・デ・ルシア、マノロ・サンルーカル、そして今は亡きモライートが燻銀の存在感を放つ。洗練の極みともいえるフラメンコが、次から次へと登場する中、ラストはヘレスのフィエスタで締められる。フラメンコ映画の巨匠サウラの絶妙なバランス感覚、フラメンコへの深い眼力は健在だ。フラメンコの今をこの一本で体感できるフラメンコ映画の新たな名作。
『カラスの飼育』、『血の婚礼』、『カルメン』などの名作を次々と生み出した、スペイン映画界の巨匠カルロス・サウラ監督による『フラメンコ・フラメンコ』が2012年正月に公開されることがわかった。
名実共に世界的巨匠と謳われるカルロス・サウラ監督と、『暗殺の森』、『ラストエンペラー』などで“光の魔術師”という異名で称される撮影監督のヴィットリオ・ストラーロが初めてタッグを組んだ作品が、1994年の映画『フラメンコ』だった。世界的に活躍していたバイラオール(男性舞踊家)のホアキン・コルテス、バイラオーラ(女性舞踏家)のメルチェ・エスメラルダ、マリア・パヘスなどを迎えたこの作品は、日本でもヒットし、フラメンコ熱が一気に加速した。
その後も『タンゴ』、『サロメ』、『ドン・ジョバンニ 天才劇作家とモーツァルトの出会い』など、ダンスと音楽をテーマにした作品を真摯に撮り続けてきたカルロス・サウラ監督がヴィットリオ・ストラーロと組み、満を持してさらなるフラメンコの真髄に迫ったのが本作だ。本作では、フラメンコ界の神と称されるマエストロたち、パコ・デ・ルシア、マノロ・サンルーカル、ホセ・メルセーが、新世代の豪華なアーティストたち、サラ・バラス、エストレージャ・モレンテ、ミゲル・ポベダ、イスラエル・ガルバン、エバ・ジェルバブエナ、ファルキート、ニーニャ・パストーリと出会い、華麗なるフラメンコの世界を体現している。
本作でフラメンコを通して描かれるテーマは“生命の旅と光”。生命の旅とは、“音楽に乗って人間の一生を巡る”ことである。カルロス・サウラ監督は、人の誕生から晩年、そして再生までを多彩なフラメンコのパロ(曲種)を用い、全21幕の構成で描き出す。「私の経験によると、“ハード”なフラメンコと“軽妙”なフラメンコの間に、交互に印象的な演目の上演を規則的に並べたり、カンテ、バイレ、演奏を単なるブロックに分けたり、あるいはスタイルで区分したりすることは無意味なことだ」と話すカルロス・サウラ監督。「このようなことから、物語を紡ぐように演目を並べ、ドラマチックな場面を演出するということはあえてしなかった。音楽やバイレの美しさ以上の何かを、カメラの前に持ち込むことは、ただフラメンコの純粋さに対する背徳行為にしか思えてならないのだ」と、熱い思いを語っている。
つづいて、カルロス・サウラ監督からの言葉を紹介する。
『音楽映画の構想を練った時に、私を駆り立てたアイデアを『言葉で表現することはいつも難しい。』
『なぜ難しいのかと言うと、台本自体はわずか3〜4ページしかなく、作品のために選んだ各演目とアーティスト名が列記してあるだけだからだ。そして余白には、展開するかもしれない方向性をかなり大雑把に書き込んであるにすぎない。更に言葉にすることを難しくさせるのは、撮影時に感じる、刺激と楽しさが、この種の作品によって引き出される即興力に基づいているからだ。
映画化に向けて、最初に行ったことは作品に出演してくれるアーティストを探すことだった。当然のことだが、大きな責任を負えるほど、自分自身のことを才気あふれるエキスパートだとは思っていない。素晴らしい助言者であるマノロ・サンルーカルの弟、イシドロ・ムニョス(*本作の音楽監督。有能な音楽プロデューサーであり、ギタリストや作曲家でも知られる)の助けなしでは遂行できなかった。
我々2人は、とても力強く且つ新しいフラメンコが存在すると認識している。スペイン国内外で、新しい道を模索している才能ある若者たちのフラメンコだ。それは伝統的なフラメンコにおける最も正統なものと同様に多様性に富んでおり、他のジャンルの音楽との融合やコラボレーションという新しい道が開かれている。
同時に、スペインが誇る偉大なマエストロたち抜きには、フラメンコの芸術の真実を反映させられないことも、我々は認識していた。だから我々の最初の使命は、フラメンコの歴史を構成してきたアーティストたち<パコ・デ・ルシア、マノロ・サンルーカル、ホセ・メルセー>を、異なるフラメンコのパロ(フラメンコの曲種)の間に“配置”することだった。個人的に彼らと話をし、映画に対してどんな意見があるかなど彼らの視点から提案を聞く一方で、我々の考えも申し入れた。
そして幸いなことに、この偉大なアーティストたちからなる一団が、映画の音楽的構成の“中心軸”となってくれた。後に展開するものを支える中心的な木の幹のようなものだ。その展開とは、前回の作品『フラメンコ』に登場しなかった、より若いアーティストたちの登場だ。そのような意味で、出演者リストは本当に興味深いものとなった。サラ・バラス、エストレージャ・モレンテ、ミゲル・ポベダ、イスラエル・ガルバン、エバ・ジェルバブエナ、ファルキート、ニーニャ・パストーリ。なんという顔ぶれだ!
初めに言ったように、いわゆる“最終版の台本“を完成させる前に、私はあらゆる可能性を残しておくのが好きなのだ。少なくとも、アーティストたちが見せてくれるリハーサルを、製作陣と一緒によく見るまでは。あるいは、送られてきたデモテープを聞くまでは。
私の経験によると、“ハード”なフラメンコと“軽妙”なフラメンコの間に、交互に印象的な演目の上演を規則的に並べたり、カンテ、バイレ、演奏を単なるブロックに分けたり、あるいはスタイルで区分けしたりすることは、無意味なことだ。
しかしこのようなことから、物語を紡ぐように演目を並べ、ドラマチックな場面を演出するということはあえてしなかった。音楽やバイレの美しさ以上の何かを、カメラの前に持ち込むことは、ただフラメンコの純粋さに対する背徳行為にしか思えてならないのだ。
そこでイシドロ・ムニョスに提案したアイデアは、2つの異なる叙述的な要素を維持することだった。演目を支えるのに役立つであろうし、展開するにつれ観衆と意識下のコミュニケーションを取ることができると考えたからだ
〜その2つの要素とは〜【生命の旅と光】
1番目の要素だが、生命の旅とは“音楽に乗って人間の一生を巡ること”だ。それを達成するためには、フラメンコのパロ(曲種)を独創的に使いこなすことが必要だ。誕生(子守唄)から始まり、幼少期(アンダルシア音楽、パキスタン音楽、その融合と成熟した音楽)、思春期(より成熟したパロ)、成人期(重厚なカンテ)、“死期”(奥深く、純粋で清浄な感情)と続き、再生で終わる。それは若い舞踊家たちの提案に基づくものだ。
この旅では、マエストロたち<パコ・デ・ルシア、マノロ・サンルーカル>が新しいアーティストたちに付き添う。未来の生命の炎が燃え続けるような独創的なセッションで、人生そのものを演出する。
2番目の要素である“光”は、基本色のグラデーションという面から1番目の要素を支える。
誕生は午後の強い白い光に包まれる。幼少期は低い位置の太陽の黄色に覆われ、長い影と通りのにぎわいを描く。思春期は、夕暮れ(橙色と水色)に向かい、人生における出会いやパティオでの日常を描いている。そして徐々に、成人期に入り始めると、濃い青、藍色、紫色が現れる。そして“死期”では(文字どおりにではなく、厳粛で神聖な空間と理解いただきたい)、白と黒が基調だ。空が薄明るくなって行き、そして希望の緑に向かう。それは再生へ導いてくれる色だ。エメラルドグリーンで強調された魂の領域である。そして、薄い青色から濃い橙色のグラデーション、フィナーレを飾るのは赤みを帯びた橙色、夜明けだ。
この2つの要素が台本の基本である。おそらく観客の皆さんは直接的には理解しづらいかもしれないが、観賞しているうちに、じわじわと分かって下さるようになると思う。それは、フラメンコを深く知って頂くことにも役立つと願いたい』。
* この文中で、「幼少期(アンダルシア音楽、パキスタン音楽、その融合と成熟した音楽)」の「パキスタン」とは、いまだ未確認なのだが、インド西北部が出自のヒターノ(ジプシー)をさしているのだろう(註:キム・ホセ)。
まあ、ほとんど言い尽くされている。
だから、文頭で、誰が観たってこの「感想」はいらないと言ったのである。
ただ“観れば”分かる。
わたしキム・ホセにとって、なぜ「フラメンコ」なのか。
わたしは“ひょんなこと”から「スペイン内戦」の研究に入っていた。
そして、“ありよう”としてのスペインの個人重視の世界に深く見入っていた。そのわたしも一応「スペイン内戦」考察を終えて、その功罪である「ロシア革命」つまり「ボルキヴィズム」批判の旅に出るべく、言い換えれば「パリ・コミューン」や「マルクス批判」に出会うために、とりあえず「ローザ・ルクセンンブルク」に寄っただけだったつもりが、ここでもうそれらは“火花を散らして”いて、けっきょくそれで「充足」するようなまたそれを徹底的に研鑽することこそ、わたしの「ボルキヴィズム批判」であり「マルクスへの肉薄」であるような“気分”になった。
『破産した革命』と。
さらに私的なことを重ねると。
こんな気分で、ある「パソコン教室」に通ったら、何とその隣席の女性がプロのフラメンコ・ダンサーであり、長く何度もスペインはアンダルシアに住んで舞踊を研鑽していたというではないか。
そこで、わたしは「スペイン内戦」という惨劇の史実以外に、スペインのアンダルシアの民衆の“ありよう”や“こころ”に、「民族の融合」に出会ったのである。
「民族の融合」。
これはとても“胡散臭い”とわたしは思った。でもそれは、「アジア的段階」を考察する上で、とても参考になったし、そこにみられるのはとても「アジア的段階」に類似しているのに驚かされた。
わたしのスペイン内戦については、アントニー・ヴィーバー著の『スペイン内戦』(上下)で一応“節目”をつけた。
それで、今度はその友人のフラメンコ・ダンサーからお借りしたDVDやビデオを毎日観た。その中に「カルロス・サウラ」がいたことは当然であった。
そして、わたしはおくらばせながら『カルメン』を読み、ビセンテ・アランダの『カルメン』を観た。そしてついにあの難解なカミロ・ホセ・セラの『アンダルシア紀行』の「風来坊」と出会い“幻視の友”となったのである。一緒に「幻視の風来坊との旅」なる文章も書いた。
さらにわたしは昂じて、「スペインにハポン姓を求めて」という文章を書き、スペイン在住の著名人たちからの、とても親切な「お返事」いや「教え」をいただき、そこでわたしは日本人の血を引くミス・スペイン、「マリア・ホセ・スアレス」を知ったのである。
なぜ、こんな私事を持ち出したかと言うと。
例えばアントニー・ヴィーバー著の『スペイン内戦』の中で、内戦中にあっても夜半に行われる「フラメンコ・ショー」に、束の間の休息を得た義勇兵たちが訪れたり、またカミロ・ホセ・セラの『アンダルシア紀行』の「風来坊」は、そのフラメンコ特に【カンテ(Cante) 歌】の地方的なありようにとても詳しくそうとうなページを用意しているからである。
まさに、スペインはこの「フラメンコ」そのものである。
それをカルロス・サウラは描きたかったといっても過言ではあるまい。
実際に、このフラメンコ・ダンサーに誘われて、「フラメンコ・ショー」はとてもいいものであり、わたしもパリージョを購入したほどだ。
そして、その情報で彼女よりも早くこの『フラメンコフラメンコ』を観たわたしは彼女にすぐメールを送った。
『〜速報〜
夜分に失礼します。
カルロス・サウラの『フラメンコ・フラメンコ』を観て、渋谷で一杯やって頭を冷やして今帰りました。
ぼくは映画評論家ではないので、あらすじは書きません。ましてやSさんも観るのだから余計なことは言いたくありません。
でも、以下の点を注視していただきたく思います。
1.背景がすばらしい山なんです。そこに始め雪かな?と思わせる白いものがたくさん浮遊しています。それは思うに蜉蝣(川の虫、カゲロウ)だと思います。山があれば川がある。カルロス・サウラはそれを自然に取り込んでいるんです。ぼくが例の梶井基次郎の「桜の木の下には」を、かんたんに言えば「嘘つき」と言ったのもこれで解ると思います。まあ、観て下さい。
2. それと背景の山の上に輝く月です。これは注意して観て下さい。ある場面でそれが地球になっていると思えることを。
3. それとラストシーンのカメラ・アングル。フラメンコの会場からカメラは外に退いて行きます。そして外では救急車のサイレンが聞こえます。これはカルロス・サウラがきっと意図したものだと思えます。その心情は現代のスペインを嘆いているのか、あるいは単にその変容を描写しているのかもしれません。フラメンコ・ショーが外部あるいは現代と時空を異にしているようにも見えますし、共存しているようにも見えます。
4. カンタはとてもいいです。その歌には何かまたスペイン内戦を思わせるものがあります。
さて、たこの刺身とまぐろの刺身を食べて感慨に浸っていて、途中でトイレに行ったのですが、パンツを前後逆に履いていました。今日はカーキのコートにオリーブのハットを被り、例の風来坊を気取ってみたものの、この様でした(笑い)。
とにかく凄い映画というかフラメンコです!
ぼくはこの世界に入れて良かったと思います。それはSさんのおかげだと思っています。
夜分に失礼します。』(キム・ホセ)と。
この映画のすべての情景は、引用に出尽くしている。
この映画の優れた展開は、カルロス・サウラが言っているように「物語性」を省いて、21幕の「ショー」でフラメンコの展開と変容と、その発展の可能性をみていることである。
ところどころで、あの「スペイン内戦」に触れる「詞」があり、また、「キューバの娘を想う」その「詞」があることに注意しよう。
そして、この映画はとにかくそんなことを意識せずに、映画としてではなく「フラメンコ・ショー」として観ることが一番なんだって想う。
おまけ『フラメンコ用語について』を紹介します。(編集)
【カンテ(Cante) 歌】
男性の歌い手 → カンタオール(cantaor)
女性の歌い手 → カンタオーラ(cantaora)
魂の奥底から響く深い歌声は聴き応えがあります
【バイレ(Baile) 踊り】
男性の踊り手 → バイラオール(Bailaor)
女性の踊り手 → バイラオーラ(bailaora)
つま先やかかとで床をふみならしてリズムをとる事をサパテアード、手の動きをブラッソと言い、フラメンコの命と言われています。
【トケ(Toque) ギター演奏】
アコースティックギターの一種であるフラメンコギターを用いることが多いです。
指先でギターを叩いてリズムを取りながら演奏します。
【パリージョ(palillos) カスタネット】
踊り子が両手に持つカスタネットの事。利き手には高音が出るもの、逆手には低音が出るものをつけます。
【ハレオ(Jaleo) 掛け声】
『オーレ!!』(お見事!) や 『ビエン!!』(いいぞ!) などの掛け声で場を盛り上げます。
【パルマ(Palma) 手拍子】
甲高い音→『セコ(seco)』 低くこもった音→ 『バホ(bajo)』
踊り手、ギタリスト、歌い手それぞれの呼吸に合わせて音を使い分けながら叩きます。
フラメンコの音楽の形成に重要な役割を持ちます。
わたしはこれほどの圧倒的な「フラメンコ・ミュージカル」というよりも「ショー」を観たことはない。ただ物語性もなくただ「フラメンコ・ショー」なのだ。
それは渋谷Bunkamura、「ル・シネマ」で上演された、カルロス・サウラの映画『フラメンコフラメンコ』だ。
何せフラメンコは友人から借りたDVDやビデオをたくさん観ていたが、いかんせん家庭のモニターである。この大画面の“ど迫力”には圧倒された。
映画を観るのは30年ぶり。
大画面の“ど迫力”というよりも、そこで「ショー」が行われていて、ついにわたしは各幕毎に【ハレオ(Jaleo) 掛け声】したくなったほど。『オーレ!!』(お見事!) や 『ビエン!!』(いいぞ!) と。
これには全くわたしの感想はいらないように思える。
ならば、探したそのいくつもの「シーン写真」を徹底的に見せてみたい。つまりこれがわたしの感想である。
ただし、いくつか気になった点についてはときおり述べよう。
その編集は私の責任において。
この映画は以下の21幕によって構成されている。
1幕●ルンバ(ホセミ・カルモナ/カルロス・ガルシア/マリア・アンヘレス・フェルナンデス他)
2幕●アレグリア(サラ・バラス/ミゲル・デ・ラ・トレア/ホセ・マリア・バンデーラ他多数)
3幕●ソレア・ポル・ブレリアス(モンセ・コルテス/ディエゴ・エル・モラオ/カルロス・グリロ他)
4幕●カルタヘネラ・イ・ブレリアス(ドランテス/ディエゴ・アマドール)
5幕●ガロティン(ロシオ・モリーナ/パコ・クルス/ロサリオ・ラ・トレメンディーダ他)
6幕●コプラ・ポル・ブレリア(ミゲル・ポベーダ/カルロス・グリロ他)
7幕●ソレア(エバ・ジェルバブエナ/パコ・ハラナ/ホセ・バレンシア/エンリケ・エル・エストレメーニョ他)
8幕●サエタ(マリア・バラ)
9幕●マルチャ・プロセシオナル(ホセ・エンリケ・デ・ラ・ベガ/ハビエル・ラトーレ/マルタ・ノガル/マイテ・ベルトラン他多数)
10幕●マルティネーテ・イ・トナ(ホセ・メルセー/セサール・モレノ・エル・グイト)
11幕●ブレリア(エル・カルペータ/アントニオ・スニーガ/ヘスス・ゲレーロ他)
12幕●シレンシオ(イスラエル・ガルバン)
13幕●グアヒーラ(アルカンヘル/ミゲル・アンヘル・コルテス/ダニ・デ・モロン/ラファエル・エステベス/ナニ・パーニョス他)
14幕●アレグリア(マノロ・サンルーカル/ダビ・カルモナ/アグスティン・ディアセーラ他)
15幕●タンゴス(エストレージャ・モレンテ/モントジータ/エンリケ・モレンテ・カルボネル・キキ/ソレア・モレンテ他多数)
16幕●エル・ティエンポ(ハビエル・ラトーレ/コレン・ルビオ/マルタ・ノガル/マイテ・ベルトラン他)
17幕●ラ・レジェンダ・デル・ティエンポ(トマティート/ニーニャ・パストーリ/ホセミ・カルモナ/パキート・ゴンサレス他)
18幕●カンシオン・デ・クーナ(エバ・ジェルバブエナ/ミゲル・ポベーダ/パコ・ハラーナ他)
19幕●サパテアオ(ファルキート/アントニオ・レイ/ベルナルド・パリージャ/ラモン・ビセンティ/イシドロ・スアレス/ペドロ・エレディア他多数)
20幕●ブレリア・ポル・ソレア(パコ・デ・ルシア/ラ・タナ/キケ・マジャ/ラ・フリ/エル・ナオ他)
21幕●ブレリア・デ・ヘレス(ルイス・エル・サンボ/モライート・チコ/ボボーテ/ボー/チチャーロ/ジョジャ/クーラ/ラ・フンケリータ他多数)
であるが、実際のところ“素人”のわたしには分からないのだが、観ている内に何となく“分かったふり”つまり魅了され“のまれる”のであった。
1995年に『フラメンコ』を撮ったカルロス・サウラ監督と、ヴィットリオ・ストラーロ撮影監督が、再びタッグを組み、21世紀に進化したフラメンコの真髄に迫った『フラメンコ フラメンコ』だ。
21幕の宴。
それは
予告に続いて、何枚もの巨大な絵が飾られた大きな倉庫のような建物の中を、カメラが進んでいく。
マリア・アンヘレスが歌う「緑よ、お前を愛している」から、21幕の宴が始まる。
2幕目、いきなり肌が透けるような赤いドレスをまとったサラ・バラスの肢体が圧倒的な存在感を画面いっぱいに見せ付ける。
シューズのかかとを踏み鳴らす「サバテアード」は、ダンサーの体の中にたぎる情熱を刻む。
もう、それだけで「フラメンコ」という情熱と官能のとりこになる。
ひとつひとつの幕が、ひとつの世界を作りながら、21幕全体で「生命の旅」と「光」という要素によって結ばれている。
陰影のある構成と圧倒的なカメラワーク
21もある幕を、どのように最後まで見せるのかと思っていたのだが、さすがフラメンコを知り尽くした両監督の手腕は卓越していた。
4幕では、なかなか触れることのない「フラメンコピアノ」という、男性二人の洗練された演奏が見られる。
8幕目には、フラメンコの名門に生まれ、マリア・バラが宗教歌を披露する。聖母マリアをたてまつる歌を無伴奏で歌い上げる80歳あまりの女性の存在感は、フラメンコの「血脈」そのものだ。
16幕の「エル・ティエンポ」は、6人の美女による群舞だ。2幕目の「いとしのサリータ」が奏でる情熱と官能とは違った、何か流れるような美しさの中に、気品が感じられる舞だ。
センターで踊るダンサーの、射るような、見るものをとりこにする視線を追ううちに、あっという間に美しすぎる幕は閉じる。
18幕の「子守唄」は、いきなり土砂降りの雨。 水煙にかすむ絵の前で歌うミゲル・ポペダにまとわりつくように濡れ髪を振り乱しながら踊るエバ・ジェル・パブエナの上半身をカメラが追う。
そう、この映画は、カメラワークが素晴らしすぎる。観客と演じ手の間には、どうしても肉薄できない「距離」があるものだが、この映画ではカメラが踊り手の間を縫っていく。…
わたしキム・ホセは何かフラメンコのあたらしき展開を見せているような、スーツにコルドバス帽でタバコを吸いながら演じるのが好きになった。いや、単に趣味なのかも・・・。
サウラ監督の新作映画。フラメンコの今をリアルに満喫できる新たな名作!
フラメンコの映像化に計りしれない功績を残したカルロス・サウラ監督の最新作。20世紀フラメンコの巨匠たちを総出演させたあの名作「FLAMENCO」から14年、フラメンコの今を最前線で疾走するアルティスタたちをズラリ揃えて、その続編ともいえる「FLAMENCO FLAMENCO」を映画化した。
サウラの撮影チームには欠かせない撮影監督のビットリオ・ストラオと音楽監督のイシドロ・ムニョスも参加して、よりドラマチックに、よりリアルにフラメンコの魅力を凝縮した作品に仕上げられている。
収録されているのは全21演目。出演者はエバ・ジェルバブエナ、サラ・バラス、ミゲル・ポベダを筆頭にイスラエル・ガルバン、ファルキート、トマティート、ロシオ・モリーナ、エストレージャ・モレンテ、アルカンヘル、ディエゴ・デル・モラオ……出演者を見ると、およそ15年の時を経た世代交代という以上に若い顔ぶれが目立つ。現代フラメンコに焦点を当てたキャスティングといっていいだろう。
そんな中でパコ・デ・ルシア、マノロ・サンルーカル、そして今は亡きモライートが燻銀の存在感を放つ。洗練の極みともいえるフラメンコが、次から次へと登場する中、ラストはヘレスのフィエスタで締められる。フラメンコ映画の巨匠サウラの絶妙なバランス感覚、フラメンコへの深い眼力は健在だ。フラメンコの今をこの一本で体感できるフラメンコ映画の新たな名作。
『カラスの飼育』、『血の婚礼』、『カルメン』などの名作を次々と生み出した、スペイン映画界の巨匠カルロス・サウラ監督による『フラメンコ・フラメンコ』が2012年正月に公開されることがわかった。
名実共に世界的巨匠と謳われるカルロス・サウラ監督と、『暗殺の森』、『ラストエンペラー』などで“光の魔術師”という異名で称される撮影監督のヴィットリオ・ストラーロが初めてタッグを組んだ作品が、1994年の映画『フラメンコ』だった。世界的に活躍していたバイラオール(男性舞踊家)のホアキン・コルテス、バイラオーラ(女性舞踏家)のメルチェ・エスメラルダ、マリア・パヘスなどを迎えたこの作品は、日本でもヒットし、フラメンコ熱が一気に加速した。
その後も『タンゴ』、『サロメ』、『ドン・ジョバンニ 天才劇作家とモーツァルトの出会い』など、ダンスと音楽をテーマにした作品を真摯に撮り続けてきたカルロス・サウラ監督がヴィットリオ・ストラーロと組み、満を持してさらなるフラメンコの真髄に迫ったのが本作だ。本作では、フラメンコ界の神と称されるマエストロたち、パコ・デ・ルシア、マノロ・サンルーカル、ホセ・メルセーが、新世代の豪華なアーティストたち、サラ・バラス、エストレージャ・モレンテ、ミゲル・ポベダ、イスラエル・ガルバン、エバ・ジェルバブエナ、ファルキート、ニーニャ・パストーリと出会い、華麗なるフラメンコの世界を体現している。
本作でフラメンコを通して描かれるテーマは“生命の旅と光”。生命の旅とは、“音楽に乗って人間の一生を巡る”ことである。カルロス・サウラ監督は、人の誕生から晩年、そして再生までを多彩なフラメンコのパロ(曲種)を用い、全21幕の構成で描き出す。「私の経験によると、“ハード”なフラメンコと“軽妙”なフラメンコの間に、交互に印象的な演目の上演を規則的に並べたり、カンテ、バイレ、演奏を単なるブロックに分けたり、あるいはスタイルで区分したりすることは無意味なことだ」と話すカルロス・サウラ監督。「このようなことから、物語を紡ぐように演目を並べ、ドラマチックな場面を演出するということはあえてしなかった。音楽やバイレの美しさ以上の何かを、カメラの前に持ち込むことは、ただフラメンコの純粋さに対する背徳行為にしか思えてならないのだ」と、熱い思いを語っている。
つづいて、カルロス・サウラ監督からの言葉を紹介する。
『音楽映画の構想を練った時に、私を駆り立てたアイデアを『言葉で表現することはいつも難しい。』
『なぜ難しいのかと言うと、台本自体はわずか3〜4ページしかなく、作品のために選んだ各演目とアーティスト名が列記してあるだけだからだ。そして余白には、展開するかもしれない方向性をかなり大雑把に書き込んであるにすぎない。更に言葉にすることを難しくさせるのは、撮影時に感じる、刺激と楽しさが、この種の作品によって引き出される即興力に基づいているからだ。
映画化に向けて、最初に行ったことは作品に出演してくれるアーティストを探すことだった。当然のことだが、大きな責任を負えるほど、自分自身のことを才気あふれるエキスパートだとは思っていない。素晴らしい助言者であるマノロ・サンルーカルの弟、イシドロ・ムニョス(*本作の音楽監督。有能な音楽プロデューサーであり、ギタリストや作曲家でも知られる)の助けなしでは遂行できなかった。
我々2人は、とても力強く且つ新しいフラメンコが存在すると認識している。スペイン国内外で、新しい道を模索している才能ある若者たちのフラメンコだ。それは伝統的なフラメンコにおける最も正統なものと同様に多様性に富んでおり、他のジャンルの音楽との融合やコラボレーションという新しい道が開かれている。
同時に、スペインが誇る偉大なマエストロたち抜きには、フラメンコの芸術の真実を反映させられないことも、我々は認識していた。だから我々の最初の使命は、フラメンコの歴史を構成してきたアーティストたち<パコ・デ・ルシア、マノロ・サンルーカル、ホセ・メルセー>を、異なるフラメンコのパロ(フラメンコの曲種)の間に“配置”することだった。個人的に彼らと話をし、映画に対してどんな意見があるかなど彼らの視点から提案を聞く一方で、我々の考えも申し入れた。
そして幸いなことに、この偉大なアーティストたちからなる一団が、映画の音楽的構成の“中心軸”となってくれた。後に展開するものを支える中心的な木の幹のようなものだ。その展開とは、前回の作品『フラメンコ』に登場しなかった、より若いアーティストたちの登場だ。そのような意味で、出演者リストは本当に興味深いものとなった。サラ・バラス、エストレージャ・モレンテ、ミゲル・ポベダ、イスラエル・ガルバン、エバ・ジェルバブエナ、ファルキート、ニーニャ・パストーリ。なんという顔ぶれだ!
初めに言ったように、いわゆる“最終版の台本“を完成させる前に、私はあらゆる可能性を残しておくのが好きなのだ。少なくとも、アーティストたちが見せてくれるリハーサルを、製作陣と一緒によく見るまでは。あるいは、送られてきたデモテープを聞くまでは。
私の経験によると、“ハード”なフラメンコと“軽妙”なフラメンコの間に、交互に印象的な演目の上演を規則的に並べたり、カンテ、バイレ、演奏を単なるブロックに分けたり、あるいはスタイルで区分けしたりすることは、無意味なことだ。
しかしこのようなことから、物語を紡ぐように演目を並べ、ドラマチックな場面を演出するということはあえてしなかった。音楽やバイレの美しさ以上の何かを、カメラの前に持ち込むことは、ただフラメンコの純粋さに対する背徳行為にしか思えてならないのだ。
そこでイシドロ・ムニョスに提案したアイデアは、2つの異なる叙述的な要素を維持することだった。演目を支えるのに役立つであろうし、展開するにつれ観衆と意識下のコミュニケーションを取ることができると考えたからだ
〜その2つの要素とは〜【生命の旅と光】
1番目の要素だが、生命の旅とは“音楽に乗って人間の一生を巡ること”だ。それを達成するためには、フラメンコのパロ(曲種)を独創的に使いこなすことが必要だ。誕生(子守唄)から始まり、幼少期(アンダルシア音楽、パキスタン音楽、その融合と成熟した音楽)、思春期(より成熟したパロ)、成人期(重厚なカンテ)、“死期”(奥深く、純粋で清浄な感情)と続き、再生で終わる。それは若い舞踊家たちの提案に基づくものだ。
この旅では、マエストロたち<パコ・デ・ルシア、マノロ・サンルーカル>が新しいアーティストたちに付き添う。未来の生命の炎が燃え続けるような独創的なセッションで、人生そのものを演出する。
2番目の要素である“光”は、基本色のグラデーションという面から1番目の要素を支える。
誕生は午後の強い白い光に包まれる。幼少期は低い位置の太陽の黄色に覆われ、長い影と通りのにぎわいを描く。思春期は、夕暮れ(橙色と水色)に向かい、人生における出会いやパティオでの日常を描いている。そして徐々に、成人期に入り始めると、濃い青、藍色、紫色が現れる。そして“死期”では(文字どおりにではなく、厳粛で神聖な空間と理解いただきたい)、白と黒が基調だ。空が薄明るくなって行き、そして希望の緑に向かう。それは再生へ導いてくれる色だ。エメラルドグリーンで強調された魂の領域である。そして、薄い青色から濃い橙色のグラデーション、フィナーレを飾るのは赤みを帯びた橙色、夜明けだ。
この2つの要素が台本の基本である。おそらく観客の皆さんは直接的には理解しづらいかもしれないが、観賞しているうちに、じわじわと分かって下さるようになると思う。それは、フラメンコを深く知って頂くことにも役立つと願いたい』。
* この文中で、「幼少期(アンダルシア音楽、パキスタン音楽、その融合と成熟した音楽)」の「パキスタン」とは、いまだ未確認なのだが、インド西北部が出自のヒターノ(ジプシー)をさしているのだろう(註:キム・ホセ)。
まあ、ほとんど言い尽くされている。
だから、文頭で、誰が観たってこの「感想」はいらないと言ったのである。
ただ“観れば”分かる。
わたしキム・ホセにとって、なぜ「フラメンコ」なのか。
わたしは“ひょんなこと”から「スペイン内戦」の研究に入っていた。
そして、“ありよう”としてのスペインの個人重視の世界に深く見入っていた。そのわたしも一応「スペイン内戦」考察を終えて、その功罪である「ロシア革命」つまり「ボルキヴィズム」批判の旅に出るべく、言い換えれば「パリ・コミューン」や「マルクス批判」に出会うために、とりあえず「ローザ・ルクセンンブルク」に寄っただけだったつもりが、ここでもうそれらは“火花を散らして”いて、けっきょくそれで「充足」するようなまたそれを徹底的に研鑽することこそ、わたしの「ボルキヴィズム批判」であり「マルクスへの肉薄」であるような“気分”になった。
『破産した革命』と。
さらに私的なことを重ねると。
こんな気分で、ある「パソコン教室」に通ったら、何とその隣席の女性がプロのフラメンコ・ダンサーであり、長く何度もスペインはアンダルシアに住んで舞踊を研鑽していたというではないか。
そこで、わたしは「スペイン内戦」という惨劇の史実以外に、スペインのアンダルシアの民衆の“ありよう”や“こころ”に、「民族の融合」に出会ったのである。
「民族の融合」。
これはとても“胡散臭い”とわたしは思った。でもそれは、「アジア的段階」を考察する上で、とても参考になったし、そこにみられるのはとても「アジア的段階」に類似しているのに驚かされた。
わたしのスペイン内戦については、アントニー・ヴィーバー著の『スペイン内戦』(上下)で一応“節目”をつけた。
それで、今度はその友人のフラメンコ・ダンサーからお借りしたDVDやビデオを毎日観た。その中に「カルロス・サウラ」がいたことは当然であった。
そして、わたしはおくらばせながら『カルメン』を読み、ビセンテ・アランダの『カルメン』を観た。そしてついにあの難解なカミロ・ホセ・セラの『アンダルシア紀行』の「風来坊」と出会い“幻視の友”となったのである。一緒に「幻視の風来坊との旅」なる文章も書いた。
さらにわたしは昂じて、「スペインにハポン姓を求めて」という文章を書き、スペイン在住の著名人たちからの、とても親切な「お返事」いや「教え」をいただき、そこでわたしは日本人の血を引くミス・スペイン、「マリア・ホセ・スアレス」を知ったのである。
なぜ、こんな私事を持ち出したかと言うと。
例えばアントニー・ヴィーバー著の『スペイン内戦』の中で、内戦中にあっても夜半に行われる「フラメンコ・ショー」に、束の間の休息を得た義勇兵たちが訪れたり、またカミロ・ホセ・セラの『アンダルシア紀行』の「風来坊」は、そのフラメンコ特に【カンテ(Cante) 歌】の地方的なありようにとても詳しくそうとうなページを用意しているからである。
まさに、スペインはこの「フラメンコ」そのものである。
それをカルロス・サウラは描きたかったといっても過言ではあるまい。
実際に、このフラメンコ・ダンサーに誘われて、「フラメンコ・ショー」はとてもいいものであり、わたしもパリージョを購入したほどだ。
そして、その情報で彼女よりも早くこの『フラメンコフラメンコ』を観たわたしは彼女にすぐメールを送った。
『〜速報〜
夜分に失礼します。
カルロス・サウラの『フラメンコ・フラメンコ』を観て、渋谷で一杯やって頭を冷やして今帰りました。
ぼくは映画評論家ではないので、あらすじは書きません。ましてやSさんも観るのだから余計なことは言いたくありません。
でも、以下の点を注視していただきたく思います。
1.背景がすばらしい山なんです。そこに始め雪かな?と思わせる白いものがたくさん浮遊しています。それは思うに蜉蝣(川の虫、カゲロウ)だと思います。山があれば川がある。カルロス・サウラはそれを自然に取り込んでいるんです。ぼくが例の梶井基次郎の「桜の木の下には」を、かんたんに言えば「嘘つき」と言ったのもこれで解ると思います。まあ、観て下さい。
2. それと背景の山の上に輝く月です。これは注意して観て下さい。ある場面でそれが地球になっていると思えることを。
3. それとラストシーンのカメラ・アングル。フラメンコの会場からカメラは外に退いて行きます。そして外では救急車のサイレンが聞こえます。これはカルロス・サウラがきっと意図したものだと思えます。その心情は現代のスペインを嘆いているのか、あるいは単にその変容を描写しているのかもしれません。フラメンコ・ショーが外部あるいは現代と時空を異にしているようにも見えますし、共存しているようにも見えます。
4. カンタはとてもいいです。その歌には何かまたスペイン内戦を思わせるものがあります。
さて、たこの刺身とまぐろの刺身を食べて感慨に浸っていて、途中でトイレに行ったのですが、パンツを前後逆に履いていました。今日はカーキのコートにオリーブのハットを被り、例の風来坊を気取ってみたものの、この様でした(笑い)。
とにかく凄い映画というかフラメンコです!
ぼくはこの世界に入れて良かったと思います。それはSさんのおかげだと思っています。
夜分に失礼します。』(キム・ホセ)と。
この映画のすべての情景は、引用に出尽くしている。
この映画の優れた展開は、カルロス・サウラが言っているように「物語性」を省いて、21幕の「ショー」でフラメンコの展開と変容と、その発展の可能性をみていることである。
ところどころで、あの「スペイン内戦」に触れる「詞」があり、また、「キューバの娘を想う」その「詞」があることに注意しよう。
そして、この映画はとにかくそんなことを意識せずに、映画としてではなく「フラメンコ・ショー」として観ることが一番なんだって想う。
おまけ『フラメンコ用語について』を紹介します。(編集)
【カンテ(Cante) 歌】
男性の歌い手 → カンタオール(cantaor)
女性の歌い手 → カンタオーラ(cantaora)
魂の奥底から響く深い歌声は聴き応えがあります
【バイレ(Baile) 踊り】
男性の踊り手 → バイラオール(Bailaor)
女性の踊り手 → バイラオーラ(bailaora)
つま先やかかとで床をふみならしてリズムをとる事をサパテアード、手の動きをブラッソと言い、フラメンコの命と言われています。
【トケ(Toque) ギター演奏】
アコースティックギターの一種であるフラメンコギターを用いることが多いです。
指先でギターを叩いてリズムを取りながら演奏します。
【パリージョ(palillos) カスタネット】
踊り子が両手に持つカスタネットの事。利き手には高音が出るもの、逆手には低音が出るものをつけます。
【ハレオ(Jaleo) 掛け声】
『オーレ!!』(お見事!) や 『ビエン!!』(いいぞ!) などの掛け声で場を盛り上げます。
【パルマ(Palma) 手拍子】
甲高い音→『セコ(seco)』 低くこもった音→ 『バホ(bajo)』
踊り手、ギタリスト、歌い手それぞれの呼吸に合わせて音を使い分けながら叩きます。
フラメンコの音楽の形成に重要な役割を持ちます。
|
|
|
|
|
|
|
|
感動の映画ランキング 更新情報
-
最新のアンケート
感動の映画ランキングのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90033人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6415人
- 3位
- 独り言
- 9044人