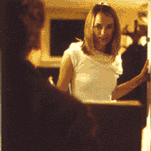〜総集編〜 映画『ゆれる』(監督・原案・脚本:西川美和)の感想。
友から薦められて観た映画、『ゆれる』にはいやはやおそれいった。
実はこのDVDを借りたが直ぐには観ず、5日放置していた。
その理由は、友人のフラメンコ・ダンサーから借りたビデオ映画、カルロス・サウラの『フラメンコ』『カルメン』と『LA NOCHE FURAMENCA』と音楽CD2枚。私はそれらを何度も観ていたからである。何せアンダルシアは私の憧れ地であり、約束の地であったので4日間、どっぷりとつかっていた。
私は、その友人フラメンコ・ダンサーの「しぐさ」や「生きる」に寡黙で懸命な姿に驚嘆していた。パソコン教室に通い、パリージョ奏者として練習に励む、とても魅力的で活動的な人。優れた「女性」を毎日隣の席に見ていた。その感動に、ついに私は、私の「自前の思想に」、彼の地の民族の融合あるいは「共同体」のあり様に、勝手な想像から「協調」という概念をシンフォニーさせたのだが、何の違和感もなかった。
このことを前段で述べるのは、私が、「幻想域」に彷徨った後、自覚的にそれをシンフォニーさせることで、この『ゆれる』を検証的に観ることができたからである。
★
落ち着いた私は、ついにこの『ゆれる』を観た。
なめていた。軽い気持ちでプレーヤーにその『ゆれる』DVDを入れた。
しかし、だんだん眼が釘付けになった。最後には泣いていた。それから夕食をとったのだが涙が止まらない。
実は私は男3人兄弟の長男であり、次男にはいつも参っていたので、この映画にはとても肩入れがあったのだろうと思う。
それにしても、この監督・原案・脚本を手がけた西川美和は凄い観察力と思惟をもった人である。生まれが1974年7月8日で、作品が公表されたのが2006年7月8日だから、彼女は32歳でこれを発表しているのである。この若さで、しかも女性(失礼!)で、この男兄弟の関係を深く理解しているのは“おそるべき者”と言わざるを得ない。さらに伏線(あるいはそれが本線なのかもしれない)が凄い。
『ゆれる』の他の批評をいくつかみたが、どれも私を納得させるものではなかった。
一般的に、この『ゆれる』は、都会の次男が帰郷して、以前の“彼女”に出会い、次男坊特有の“振る舞い”をする。そこでその「兄弟関係」を鋭く描写したものとなっている。
私の観方は、それも含むが、全く違う。
私は、もう一度、私の「観方」を検証するためにこのDVDを50円で借りた。
涙もすこし落ちついたので、シーンを振り返りながら以下に感想を述べよう。
★★
この『ゆれる』は、兄と次男のことを語っていながら、実は、田舎と都会、言い換えれば、「田舎の共同体」と、異郷の「都会の共同体」というモチーフが濃厚にあると想う。しかも「意図的」に。
いろいろな評論家には、これが観えていない。
そうでなければ、あの真木よう子が演じる、「川端智恵子」の存在はあまり重要ではない。しかし、彼女のこの「存在」と「死」はとても重要なものである。
冒頭のシーンは、父と子の争いにみえるが、後で分かるように、それは、互いが、つまり父とその次男坊が「次男」としてある存在で、その自我のぶつかりあいである。それは後のシーンで知ることができる。
私は思うに、川端智恵子を演ずる真木よう子が、単なる幼なじみで、昔、恋人?であったオダギリジョーが演じる、早川猛(弟)と性交渉をもつことに何のためらいもなかったとは思わない。
意識的なのだ。
彼女は言う。「何であの時、貴方について行けなかったのかと」。
きっと、その時期、川端智恵子は、あこがれの都会に行くことをためらったのだと思う。彼女には、都会という異郷に魅力があったのにも拘わらず、ついに諦めてしまったのだろう。
その理由は何であろうか?
都会という“臭い”をもった、オダギリジョーが演じる、早川猛(弟)に、「異郷のシンボル」をみたのである。
川端智恵子の家族は「母」の再婚というかたちで、現実的には別居であり、その分、何か解放感のようなものがあるように感ずるが、それは違う焦燥感と諦めの念である。そして川端智恵子の描写には悪意があるよう私には写る。
彼女は、伊武雅刀が演じる早川勇(父)と、香川照之が演ずる早川稔(兄)の経営するガソリンスタンド(早川商店)でアルバイトをしていて、互いに、おそらく好意をもっているが、どこか“つまらない”という感慨がある。つまり、「田舎の共同体」につまらないと思っているのだ。
川端智恵子の家には、都会で写真家となった早川猛(弟)の本が飾ってあるが、あれは、早川猛(弟)を好いているというものではなく、異郷の都会に憧れる「シンボル」であろうと思われる。
やってきた昔の恋人、早川猛(弟)。それがきっかけで、ようやく異郷の地に赴く決意を感じたのに違いない。
オダギリジョーが演じる、早川猛(弟)も都会に出て、一応、成功しているものの、何か都会のあり様、つまり、「都会の共同体」には、けっきょく違和感をもっている。
ふたりの性交渉は、そうした想いの重奏で行われる。
川端智恵子は、早川猛(弟)に同伴して、都会という異郷に赴くべき覚悟をしたのに違いない。否、この田舎の共同体を捨てようというタブーを犯そうと決意したのである。
そのことを、監督は示唆していると思える。
そのタブー破りにおいて、悲劇は生じる。
河原で川端智恵子は早川猛(弟)に言う。「もうふたりの関係は、お兄さんにはばれている」って。
吊り橋で、川端智恵子は先にその吊り橋を渡った早川猛(弟)を追う。
そして早川稔(兄)はこの川端智恵子を追う。そのとき、川端智恵子には早川稔(兄)が「田舎の共同体」の権化にみえ、懸命にタブーを犯そうとして(否、すでに意識の中で禁忌が行われている)、それから逃れようとする。
早川稔(兄)はすでに、川端智恵子と早川猛(弟)の関係を知っている。
前段の、再会と性交渉、吊り橋でのあり様はこのように観るべきだ。
そうでなければ、それから展開される「兄弟の葛藤」のためのロマンス、濡れ場は、とても品のない三文小説のイントロではないか。
この映画は、実は「兄」と「次男」の葛藤を物語っているようにみえるが、「都会という共同体」、「田舎という共同体」の関係をモチーフにしているのである。
智恵子は、帰郷した早川猛(弟)にいわば「異人」を感じ、「田舎の共同体」を捨てる決意をしたのだ。
ついでに言うが、「都会」と「田舎」に監督は、そのシーンで距離感を与えていない。帰郷する早川猛(弟)が高速へ乗ると次のシーンはもう田舎である(それはおそらく山梨と思われるが場所はどうでもいい。私はフライフィッシャーだから、この川や地方のことが手に取るように分かるのである)。
これは、監督の意図した手法であろう。
その分、ことさら「都会」と「田舎」に「距離感」を与えていない手法をとりながら逆に「距離感」を与えている。
恐るべきものだ。
これもついでだが、私はビジネスで、また釣りで、日本中を歩いた。流れ者でない限り、「地方の共同体」から抜けるのは、そうとうな覚悟がいる。都会には憧れるが、何も「禁忌」(タブー)までは犯さないのが普通である。
普通の映画鑑賞者は、この映画に、「兄弟」の葛藤のみを観ることが普通であろうが、独善的鑑賞者としての私にはそのようにみえる。むしろ、そっちの方が主題かな、とさえ思わせる作品である。
同時に、実に「兄」と「次男」の関係と、あり様を精緻にあつかった作品である。
こう私は言いたい。
★★★
さて、それでは【男兄弟の関係と葛藤】、「長男」と「次男」の幕に入ろう。
ガソリンスタンドで、早川猛(弟)は、早川稔(兄)と川端智恵子の仲良しぶりに、嫉妬というよりも、横恋慕して、兄からまた奪おうという気持ちが、むらむらと湧き上がる。そうして性交渉に至る。
まず注意しておかなくてはいけないのは、男兄弟は、「父」を、協力して排除し、それに換わろうとするものである(母についてはここでは言わない)。 しかし父の死後は、兄弟の誰かがその代理を務めなくてはならない。いわば「対なる幻想」は家族の中で、関係的にそうあるのが普通だ。
この作品の場合、早川稔(兄)はなにか頼りない家族長にみえる。それはおそらく「次男」としての「父」が頑固に生存しているから、そのような風体にみえるのを継承せざるを得ないようにこの映画はみせる。
でも兄はおそらく、それまで早川猛(弟)には全てを「とられて」いたであろうことは想像できる。
その早川猛(弟)は成長して写真家として職と「個」を獲得し、「都会の共同体」で一応成功しているようである。しかし、何か“不安”なのである。そして、母のお通夜?に赤いジャンバーで現れ、冒頭の父との喧嘩に至る。
★★★★
『次男坊』。
このことについては、私が言うより、ネットで発見した文書が簡潔に物語っているので、それを借用しよう(ごめんなさい)。
〜porcaroの日記2008-11-07 【次男坊理論】〜
『みなさんは周りに男3人兄弟はいますか?
いる場合次男坊は、長男、三男に比べてどういった特徴を持ってますか?次男坊だけちょっとおかしいでしょ?その理由を僕なりに考えてみました。
一番の理由は「親の愛の独占期間。両親にとって長男が初めて体験する事は、両親にとっても、自分の経験はあっても「人の親」としては初めてです。なので長男はいつでも両親の注目を受けます。三男は「末っ子」という必殺技でかわいがられて、常に両親の関心の的です。しかし次男はどうでしょう、長男で大抵の事は経験しているので、次男のイベントではあまり新鮮味はありません。しかも次男は三男が生まれるまでの短い期間しか親の愛を独占できません。だから次男は放っとかれます。放っとかれるのが常なので自立心が強くなります。自我も強くなるでしょう。
二番目の理由は、「長男に対する気持ち」です。三男は上の兄弟を見て育ちますが、特に長男を見ます。それは長男が三男を可愛がるからです。次男も幼少期は長男のマネばかりしますが、ある時期で「反発心」が生まれます。それは小学校・中学校で長男とずっと比べられる。それがある時期から嫌になるからです。なので長男とは違う選択をするようになります。それが成長するにつれて「人とは違う事を好む傾向」に拡張していきます。
三番目の理由は、次男の身軽さです。ちょっと古い感覚しれませんが、長男というのは親戚付き合いのなかで中心的は役割を果たします。将来親の面倒を見るのも長男です。自営業であれば、家業を次ぐのも長男です。長男は責任が重い。親もそういう教育をするので、長男も将来の責任を当然のものとして受け入れます。次男は楽。なんも無い。身軽です。自由です。この差は意外に大きい。
四番目の理由は、これらの事象が相乗効果を発揮する事です。「自立心」と「人とは違う事を好む傾向」と「自由さ」が相乗効果を発揮して、ますます兄弟からかけ離れていきます。長男と三男が仲が良いのを見ると、ますます違う方向に進もうとします。そんな次男を両親は「次男は何でも自分でやるから大丈夫」と放っときます。こうして次男の「天の邪鬼化」は着々と進んでいくのです。
以上の理由より、3兄弟において次男が異質である事が説明できます。これを「次男坊理論」と言います。
そして、こういうブログを書いてる僕は次男坊です。』
【この筆者は簡素だが、実によく書けている。もちろん、もっと深いものをもっているに違いない。】(キム記)
余談ではあるが、私も三人男兄弟で、それぞれの特徴はもうほとんど同じである。
私は、私の次男には全てをと・ら・れ・た。
自転車も、スケートも、しまいには、病気で倒れた母も。「看病は俺がみる」って。今でも私を非難し寄せ付けない。酒癖も悪い。
でも長男である私は、早川稔(兄)とは違う。
それは、幼少の頃から、戦傷者の父の代理として、家長であらざるを得ず、また、親族長であらざるを得なかったからだと思える。だから、私は、「原形は存在し現象する」という概念を創造したのである。それは概念のようであり、分析理論だと思っている。
★★★★★
中略するが、この『ゆれる』ではいろいろな【男兄弟の関係と葛藤】が展開される。
早川稔(兄)の裁判の弁護士は、早川猛(弟)が頼んだ、叔父である。
それは何と、父である早川勇(父)の蟹江敬三が演じる早川修弁護士で、父、勇の兄なのである。早川修弁護士は、すでに弟である早川勇を、「次男坊」を見抜いている。その葛藤を、監督は早川稔(兄)と早川猛(弟)との葛藤に摺り合わせようとする。
おもしろい。
けっきょく、兄は7年の刑に処せられるが、その前の、刑務所での「接見室」での【男兄弟の関係と葛藤】、早川稔(兄)と早川猛(弟)の“やりとり”が凄まじい。 この場面を、接見室という空間の中で、対面ガラスを「仕切り」として、それぞれ、幽閉された空間と現実の空間の中で、兄弟はそれぞれの意識をもって“いがみあう”。そこでは空間の差異があって、兄が弟に、何かぶちまけるような言葉が出る。弟は、それに戸惑い激怒する。
と観るべきではないと思う。監督が意図したものは、そうした舞台を設け、異なる「共同体」を戦わせたことにあると思う。
そこに、この監督の見事さがある。
兄は確かに、刑務所という異空間にあって、それ実際としての“田舎の共同体”意識を希有にし、急激に己、つまり「個」を確立していったようにみえる。それはもともと兄にあったものである。
つまり、それはいわば“猫っかぶり”であり、悪意であると私にはみえた。
そうして兄弟という絆は壊れて行き決定的な場面を迎える。
わたしにはこの兄、早川稔には何か「悪意」を感じたと言った。
早川猛(弟)は、その兄の変身したような変わり身に「驚き」と「不安」また「激怒」を覚え、再び【次男の天の邪鬼】が頭を上げるようにみえる。
そして、ついに、証言台で、“立場”を逆転させる。
兄に不利な証言をするのである。
そのとき、兄は“にやっ”っと笑う。
その結果、兄、7年の刑。
その前の裁判過程で、木村祐一が演じる丸尾明人検察官が、川端智恵子の膣内に精子が入っていたことを告知し追求する。
そのとき、早川稔(兄)は“くるり”と身体を返して、早川猛(弟)に「すまない」と言って、深々と頭を垂れる。このとき、兄はまだ長男であったことを示唆している。しかし、この行為に、早川猛(弟)はそうとうな「いらつき」を覚えるのだ。
この木村祐一が演じる丸尾明人検察官は適役で、とても迫力がある。実にいい。
いいと言えば、新井浩文が演じる岡島洋平もいい。
彼は、レストランに家族で来て(いい設定だ)、早川猛(弟)を諭す。「信じられないって」。このとき、岡島洋平は、普通の人が言う「平常心」や「平衡感覚」の持ち主ではなく、「田舎の普通の共同体」の一員であることを示している。
ついにその時が来た。
岡島洋平が早川猛(弟)に、兄の出所を告げる。また、父がぼけて来ていることを告げる。
早川猛(弟)は言う。「兄はクリーニング店には、もう戻らないよ」って。
東京で、早川猛(弟)は兄の出所の日、母の形見であるフィルムを廻す。
そこには、あの家族で行った川があり、幼少の兄と弟、つまり「長男」と「次男」が映し出される。兄が弟を遊んでいる。
気をつけなくてはいけないのは、このシーンは何も「感慨」のシーンではない。
何か、弟が【次男の身勝手さ】に気付いた訳でもなく、ましてや「反省」ではない。
感動的ではあるが、この監督はその徹底さにおいて、こんな“お涙ちょうーだい”のシーンなんか用意する訳がない。
ここで、早川猛(弟)は、己が不安は「田舎の共同体」にあったと気付くのだ。
そして、その衝動は、「兄の出所を迎えに行こう」という意識に変わるのだ。
つまり、兄はきっとあの川端智恵子が死んだ川に行くに違いないと感じるのだ。
それがこの映画のまたは監督のおもしろさであり優れたところである。
このシーンを、何か弟のいわばお涙ちょうだいのものとみるのはつまらない。
それでは三文映画ではないか。
監督は、この弟にもっと凄い「ねじれ」を与えているものと思われる。
確かに、弟は、岡島洋平と一緒に兄の出所を迎えに行ったが、兄は“行方知れず”。
ここで、早川猛(弟)は、「もしや・・・」という「不安」にまた囚われる。
後のシーンは、すべて早川猛(弟)の「妄想」である。
その妄想とは、「兄はきっと、川端智恵子のところに行ったんだ」。「あの川に
行ったんだ」。「川端智恵子に求婚に行ったに違いない」という妄想と次男特有のものが現れる。
映画のシーンの最後に、妄想の「甲府行きのバス」が来る。
兄が何かうれしそうにしている。しかしその顔はすでに“死の相”である。
おそろしく完成度の高い作品である。めずらしく“魅せる”日本映画だ。
この映画は海外で評価されたが(文末参照)、しかし、「西欧的な・・・」を思念に入れるとき、この監督作品は海外で良く理解されたであろうか?
まあ、映画は己の心境に重ねて観るものだから、いろんな観方があってもいいと思うが!
【紹介】
西川美和監督の「蛇イチゴ」に続く長編第2作。自分が見た「友人が殺人を犯す」という悪夢から着想した。第59回カンヌ国際映画祭監督週間 正式出品作品。優れた演出力が高く評価され、多くの映画賞を受賞し、2006年度の日本映画における最も高い評価を得た作品の一つとなった。
• 監督・原案・脚本:西川美和
• 音楽:カリフラワーズ
• 主題歌:カリフラワーズ『うちに帰ろう』
【追記1】 この『ゆれる』は兄弟をあつかっているが、ぜひ「母」と「姉妹」を登場させた、家族を描いて欲しいと思う。私には、西川美和監督は、それをすでに用意しているものと推察する。
【追記2】 この「感想文」は1回観た後、約1ケ月の想いの中で、ついに2回目を観ただけです。これもまた、一気に書き殴りましたので、誤字や重複をお許し下さい。
【追記3】 「porcaroの日記2008-11-07 【次男坊理論】」さんには、あらためて感謝申し上げるとともに、勝手な掲載をお許し下さい、と申し上げる。
【追記4】 この映画を薦めてくれた友人Fさんにはお礼を述べる。貴女のお陰で、私はとてつもなく映画鑑賞に成長したと思える。
【雑感としての補足〜1〜】
先日、『ゆれる』(監督・原案・脚本:西川美和)の感想を書いた。
その中で、映画はそれぞれの思い入れにおいて観るのだから、独善的などという批評家的批判は傲慢なものの言うものであると書いた。
しかし、再びネットのいろいろな「批評」を見てとことん嫌になった。
全くこの映画を理解していない水準にある。
例えば、この『ゆれる』を、単なる兄弟の葛藤劇と観るのはあまりにも情けなすぎる。それでは愚鈍である。この優れた監督はそんな映画つくりはしていないと思う。
兄弟、特に長男と次男の関係、親子の関係(この場合は父)、つまり対としての幻想はそれ自体としては成立しない。対としての幻想は他者と関係することにおいて成立する概念である。
ここでは「田舎の共同体」として表現されている。そして、その共同体は「都会という共同体」あるいは、次男に象徴的に“見せるもの”との相克として表現されていると思える。
そう考えなければ、例えば、検事のもの言いが、どうも関西弁のようであったり、あのガソリンスタンドのアルバイトの青年の言説と存在は、単なる“常識的な”言説としてしか見えない。そうではなく、検事もまた、異なる共同体の人間であり、ガソリンスタンドのアルバイトの青年の言説と存在は、まことにこの村落共同体のものとしてあると言える。
この『ゆれる』は、実はその主題を「兄弟」に置いているように見えるが、その主題は実は「共同体」のあり様にあると言っても過言ではないと思う。
「対としての幻想」が際立つ、「村落共同幻想」との関係。そして“憧れの都会”への禁忌破りに対する「制裁」。
兄弟や家族(この場合は父)の悪意、そして川端智恵子の悪意が表現されている。
これが、『ゆれる』が表現した映画の全体としてのあり様が実に優れており、評価される点であろう。
最初はそんなことも分からず、己の原形と現象に重ね合わせすぎて、おいおい、と泣いたのには、振り返ってあきれる。
それと同時に、こんな見方もできない映画批評家はどんなにつまらないかも分かる。単に、己が得た知でのみ映画を測り、それを思想まで咀嚼もできずに筋のみを追う職業かとぞ思う。
この映画『ゆれる』を「サスペンス:ドラマ」なんて評論し紹介しているのには、ただただあきれるしかない。
また、映画愛好家である我々も、観る最低の分別は獲得しなければならないと思う。知を思想まで、あるいは自分の生き方まで昇華することなく、ゴシップを集めては遊んでいる知。そんなものはペットと遊ぶに等しいにすぎない。
不健康なのである。
【雑感としての補足〜2〜】(『ゆれる』の本を読んで)
友への手紙から(要約)
・・・・・私は、こんなところばっかり見てしまうので、ついに小説を読むのをやめたものでした。でも、あなたから、吉本ばななの『ハチ公の最後の恋人』を薦められて読み、ふっと考えるところがありました。
いま私は、先に私が長々と“感想”を述べた西川美和の映画『ゆれる』の「本」を読んでいます(ブックオフで100円で買った)。吉本ばななとは雰囲気の異なる文章です。
そうして、私はその映画の“感想”で、もう少し家族について触れて欲しかった、と駄々をこねたのですが、何と、小説ではやはりその「家族関係」が描かれていました。
また、映画では見え隠れしていた、兄と死ぬ女性に何となく「悪意」や「故意」を感じていましたが、映画ではなかなか見えませんでした(わたしにはみえた)が、この小説では、はっきりとそのことを言っています。
そして、弟が言う、「何かこの村には訳の解らないものが存在し、常にそれに見張られているような気がしてならなかった」という主旨の表現がありました。
私が映画感想で言った、幻想つまり「村落共同体」が明らかに存在しているではありませんか。
兄の悪意は「村落共同体」の持つもので、「私」という意識を持たなかった女性の、他の「村落共同体」への悪意のようです。
まあ、小説と映画とは異なっていてもいいのですが、映画にもう少しそれらの示唆があってもいいのではなかったか、と思います。
しかし、そのことを表現していたのが、兄であり女性の見事な(悪意っぽい)演技で代弁させたものでしょう。なかなかしたたかです!
私は、この映画の観方について、友にお叱りをいただきました。
『独善すぎる!』って。
でも、小説を読めば分かりますが、私の感想はそんなにズレてはいない、独善的すぎるよりも極めてノーマルなものであったことに、我ながら驚きました・・・・・
友から薦められて観た映画、『ゆれる』にはいやはやおそれいった。
実はこのDVDを借りたが直ぐには観ず、5日放置していた。
その理由は、友人のフラメンコ・ダンサーから借りたビデオ映画、カルロス・サウラの『フラメンコ』『カルメン』と『LA NOCHE FURAMENCA』と音楽CD2枚。私はそれらを何度も観ていたからである。何せアンダルシアは私の憧れ地であり、約束の地であったので4日間、どっぷりとつかっていた。
私は、その友人フラメンコ・ダンサーの「しぐさ」や「生きる」に寡黙で懸命な姿に驚嘆していた。パソコン教室に通い、パリージョ奏者として練習に励む、とても魅力的で活動的な人。優れた「女性」を毎日隣の席に見ていた。その感動に、ついに私は、私の「自前の思想に」、彼の地の民族の融合あるいは「共同体」のあり様に、勝手な想像から「協調」という概念をシンフォニーさせたのだが、何の違和感もなかった。
このことを前段で述べるのは、私が、「幻想域」に彷徨った後、自覚的にそれをシンフォニーさせることで、この『ゆれる』を検証的に観ることができたからである。
★
落ち着いた私は、ついにこの『ゆれる』を観た。
なめていた。軽い気持ちでプレーヤーにその『ゆれる』DVDを入れた。
しかし、だんだん眼が釘付けになった。最後には泣いていた。それから夕食をとったのだが涙が止まらない。
実は私は男3人兄弟の長男であり、次男にはいつも参っていたので、この映画にはとても肩入れがあったのだろうと思う。
それにしても、この監督・原案・脚本を手がけた西川美和は凄い観察力と思惟をもった人である。生まれが1974年7月8日で、作品が公表されたのが2006年7月8日だから、彼女は32歳でこれを発表しているのである。この若さで、しかも女性(失礼!)で、この男兄弟の関係を深く理解しているのは“おそるべき者”と言わざるを得ない。さらに伏線(あるいはそれが本線なのかもしれない)が凄い。
『ゆれる』の他の批評をいくつかみたが、どれも私を納得させるものではなかった。
一般的に、この『ゆれる』は、都会の次男が帰郷して、以前の“彼女”に出会い、次男坊特有の“振る舞い”をする。そこでその「兄弟関係」を鋭く描写したものとなっている。
私の観方は、それも含むが、全く違う。
私は、もう一度、私の「観方」を検証するためにこのDVDを50円で借りた。
涙もすこし落ちついたので、シーンを振り返りながら以下に感想を述べよう。
★★
この『ゆれる』は、兄と次男のことを語っていながら、実は、田舎と都会、言い換えれば、「田舎の共同体」と、異郷の「都会の共同体」というモチーフが濃厚にあると想う。しかも「意図的」に。
いろいろな評論家には、これが観えていない。
そうでなければ、あの真木よう子が演じる、「川端智恵子」の存在はあまり重要ではない。しかし、彼女のこの「存在」と「死」はとても重要なものである。
冒頭のシーンは、父と子の争いにみえるが、後で分かるように、それは、互いが、つまり父とその次男坊が「次男」としてある存在で、その自我のぶつかりあいである。それは後のシーンで知ることができる。
私は思うに、川端智恵子を演ずる真木よう子が、単なる幼なじみで、昔、恋人?であったオダギリジョーが演じる、早川猛(弟)と性交渉をもつことに何のためらいもなかったとは思わない。
意識的なのだ。
彼女は言う。「何であの時、貴方について行けなかったのかと」。
きっと、その時期、川端智恵子は、あこがれの都会に行くことをためらったのだと思う。彼女には、都会という異郷に魅力があったのにも拘わらず、ついに諦めてしまったのだろう。
その理由は何であろうか?
都会という“臭い”をもった、オダギリジョーが演じる、早川猛(弟)に、「異郷のシンボル」をみたのである。
川端智恵子の家族は「母」の再婚というかたちで、現実的には別居であり、その分、何か解放感のようなものがあるように感ずるが、それは違う焦燥感と諦めの念である。そして川端智恵子の描写には悪意があるよう私には写る。
彼女は、伊武雅刀が演じる早川勇(父)と、香川照之が演ずる早川稔(兄)の経営するガソリンスタンド(早川商店)でアルバイトをしていて、互いに、おそらく好意をもっているが、どこか“つまらない”という感慨がある。つまり、「田舎の共同体」につまらないと思っているのだ。
川端智恵子の家には、都会で写真家となった早川猛(弟)の本が飾ってあるが、あれは、早川猛(弟)を好いているというものではなく、異郷の都会に憧れる「シンボル」であろうと思われる。
やってきた昔の恋人、早川猛(弟)。それがきっかけで、ようやく異郷の地に赴く決意を感じたのに違いない。
オダギリジョーが演じる、早川猛(弟)も都会に出て、一応、成功しているものの、何か都会のあり様、つまり、「都会の共同体」には、けっきょく違和感をもっている。
ふたりの性交渉は、そうした想いの重奏で行われる。
川端智恵子は、早川猛(弟)に同伴して、都会という異郷に赴くべき覚悟をしたのに違いない。否、この田舎の共同体を捨てようというタブーを犯そうと決意したのである。
そのことを、監督は示唆していると思える。
そのタブー破りにおいて、悲劇は生じる。
河原で川端智恵子は早川猛(弟)に言う。「もうふたりの関係は、お兄さんにはばれている」って。
吊り橋で、川端智恵子は先にその吊り橋を渡った早川猛(弟)を追う。
そして早川稔(兄)はこの川端智恵子を追う。そのとき、川端智恵子には早川稔(兄)が「田舎の共同体」の権化にみえ、懸命にタブーを犯そうとして(否、すでに意識の中で禁忌が行われている)、それから逃れようとする。
早川稔(兄)はすでに、川端智恵子と早川猛(弟)の関係を知っている。
前段の、再会と性交渉、吊り橋でのあり様はこのように観るべきだ。
そうでなければ、それから展開される「兄弟の葛藤」のためのロマンス、濡れ場は、とても品のない三文小説のイントロではないか。
この映画は、実は「兄」と「次男」の葛藤を物語っているようにみえるが、「都会という共同体」、「田舎という共同体」の関係をモチーフにしているのである。
智恵子は、帰郷した早川猛(弟)にいわば「異人」を感じ、「田舎の共同体」を捨てる決意をしたのだ。
ついでに言うが、「都会」と「田舎」に監督は、そのシーンで距離感を与えていない。帰郷する早川猛(弟)が高速へ乗ると次のシーンはもう田舎である(それはおそらく山梨と思われるが場所はどうでもいい。私はフライフィッシャーだから、この川や地方のことが手に取るように分かるのである)。
これは、監督の意図した手法であろう。
その分、ことさら「都会」と「田舎」に「距離感」を与えていない手法をとりながら逆に「距離感」を与えている。
恐るべきものだ。
これもついでだが、私はビジネスで、また釣りで、日本中を歩いた。流れ者でない限り、「地方の共同体」から抜けるのは、そうとうな覚悟がいる。都会には憧れるが、何も「禁忌」(タブー)までは犯さないのが普通である。
普通の映画鑑賞者は、この映画に、「兄弟」の葛藤のみを観ることが普通であろうが、独善的鑑賞者としての私にはそのようにみえる。むしろ、そっちの方が主題かな、とさえ思わせる作品である。
同時に、実に「兄」と「次男」の関係と、あり様を精緻にあつかった作品である。
こう私は言いたい。
★★★
さて、それでは【男兄弟の関係と葛藤】、「長男」と「次男」の幕に入ろう。
ガソリンスタンドで、早川猛(弟)は、早川稔(兄)と川端智恵子の仲良しぶりに、嫉妬というよりも、横恋慕して、兄からまた奪おうという気持ちが、むらむらと湧き上がる。そうして性交渉に至る。
まず注意しておかなくてはいけないのは、男兄弟は、「父」を、協力して排除し、それに換わろうとするものである(母についてはここでは言わない)。 しかし父の死後は、兄弟の誰かがその代理を務めなくてはならない。いわば「対なる幻想」は家族の中で、関係的にそうあるのが普通だ。
この作品の場合、早川稔(兄)はなにか頼りない家族長にみえる。それはおそらく「次男」としての「父」が頑固に生存しているから、そのような風体にみえるのを継承せざるを得ないようにこの映画はみせる。
でも兄はおそらく、それまで早川猛(弟)には全てを「とられて」いたであろうことは想像できる。
その早川猛(弟)は成長して写真家として職と「個」を獲得し、「都会の共同体」で一応成功しているようである。しかし、何か“不安”なのである。そして、母のお通夜?に赤いジャンバーで現れ、冒頭の父との喧嘩に至る。
★★★★
『次男坊』。
このことについては、私が言うより、ネットで発見した文書が簡潔に物語っているので、それを借用しよう(ごめんなさい)。
〜porcaroの日記2008-11-07 【次男坊理論】〜
『みなさんは周りに男3人兄弟はいますか?
いる場合次男坊は、長男、三男に比べてどういった特徴を持ってますか?次男坊だけちょっとおかしいでしょ?その理由を僕なりに考えてみました。
一番の理由は「親の愛の独占期間。両親にとって長男が初めて体験する事は、両親にとっても、自分の経験はあっても「人の親」としては初めてです。なので長男はいつでも両親の注目を受けます。三男は「末っ子」という必殺技でかわいがられて、常に両親の関心の的です。しかし次男はどうでしょう、長男で大抵の事は経験しているので、次男のイベントではあまり新鮮味はありません。しかも次男は三男が生まれるまでの短い期間しか親の愛を独占できません。だから次男は放っとかれます。放っとかれるのが常なので自立心が強くなります。自我も強くなるでしょう。
二番目の理由は、「長男に対する気持ち」です。三男は上の兄弟を見て育ちますが、特に長男を見ます。それは長男が三男を可愛がるからです。次男も幼少期は長男のマネばかりしますが、ある時期で「反発心」が生まれます。それは小学校・中学校で長男とずっと比べられる。それがある時期から嫌になるからです。なので長男とは違う選択をするようになります。それが成長するにつれて「人とは違う事を好む傾向」に拡張していきます。
三番目の理由は、次男の身軽さです。ちょっと古い感覚しれませんが、長男というのは親戚付き合いのなかで中心的は役割を果たします。将来親の面倒を見るのも長男です。自営業であれば、家業を次ぐのも長男です。長男は責任が重い。親もそういう教育をするので、長男も将来の責任を当然のものとして受け入れます。次男は楽。なんも無い。身軽です。自由です。この差は意外に大きい。
四番目の理由は、これらの事象が相乗効果を発揮する事です。「自立心」と「人とは違う事を好む傾向」と「自由さ」が相乗効果を発揮して、ますます兄弟からかけ離れていきます。長男と三男が仲が良いのを見ると、ますます違う方向に進もうとします。そんな次男を両親は「次男は何でも自分でやるから大丈夫」と放っときます。こうして次男の「天の邪鬼化」は着々と進んでいくのです。
以上の理由より、3兄弟において次男が異質である事が説明できます。これを「次男坊理論」と言います。
そして、こういうブログを書いてる僕は次男坊です。』
【この筆者は簡素だが、実によく書けている。もちろん、もっと深いものをもっているに違いない。】(キム記)
余談ではあるが、私も三人男兄弟で、それぞれの特徴はもうほとんど同じである。
私は、私の次男には全てをと・ら・れ・た。
自転車も、スケートも、しまいには、病気で倒れた母も。「看病は俺がみる」って。今でも私を非難し寄せ付けない。酒癖も悪い。
でも長男である私は、早川稔(兄)とは違う。
それは、幼少の頃から、戦傷者の父の代理として、家長であらざるを得ず、また、親族長であらざるを得なかったからだと思える。だから、私は、「原形は存在し現象する」という概念を創造したのである。それは概念のようであり、分析理論だと思っている。
★★★★★
中略するが、この『ゆれる』ではいろいろな【男兄弟の関係と葛藤】が展開される。
早川稔(兄)の裁判の弁護士は、早川猛(弟)が頼んだ、叔父である。
それは何と、父である早川勇(父)の蟹江敬三が演じる早川修弁護士で、父、勇の兄なのである。早川修弁護士は、すでに弟である早川勇を、「次男坊」を見抜いている。その葛藤を、監督は早川稔(兄)と早川猛(弟)との葛藤に摺り合わせようとする。
おもしろい。
けっきょく、兄は7年の刑に処せられるが、その前の、刑務所での「接見室」での【男兄弟の関係と葛藤】、早川稔(兄)と早川猛(弟)の“やりとり”が凄まじい。 この場面を、接見室という空間の中で、対面ガラスを「仕切り」として、それぞれ、幽閉された空間と現実の空間の中で、兄弟はそれぞれの意識をもって“いがみあう”。そこでは空間の差異があって、兄が弟に、何かぶちまけるような言葉が出る。弟は、それに戸惑い激怒する。
と観るべきではないと思う。監督が意図したものは、そうした舞台を設け、異なる「共同体」を戦わせたことにあると思う。
そこに、この監督の見事さがある。
兄は確かに、刑務所という異空間にあって、それ実際としての“田舎の共同体”意識を希有にし、急激に己、つまり「個」を確立していったようにみえる。それはもともと兄にあったものである。
つまり、それはいわば“猫っかぶり”であり、悪意であると私にはみえた。
そうして兄弟という絆は壊れて行き決定的な場面を迎える。
わたしにはこの兄、早川稔には何か「悪意」を感じたと言った。
早川猛(弟)は、その兄の変身したような変わり身に「驚き」と「不安」また「激怒」を覚え、再び【次男の天の邪鬼】が頭を上げるようにみえる。
そして、ついに、証言台で、“立場”を逆転させる。
兄に不利な証言をするのである。
そのとき、兄は“にやっ”っと笑う。
その結果、兄、7年の刑。
その前の裁判過程で、木村祐一が演じる丸尾明人検察官が、川端智恵子の膣内に精子が入っていたことを告知し追求する。
そのとき、早川稔(兄)は“くるり”と身体を返して、早川猛(弟)に「すまない」と言って、深々と頭を垂れる。このとき、兄はまだ長男であったことを示唆している。しかし、この行為に、早川猛(弟)はそうとうな「いらつき」を覚えるのだ。
この木村祐一が演じる丸尾明人検察官は適役で、とても迫力がある。実にいい。
いいと言えば、新井浩文が演じる岡島洋平もいい。
彼は、レストランに家族で来て(いい設定だ)、早川猛(弟)を諭す。「信じられないって」。このとき、岡島洋平は、普通の人が言う「平常心」や「平衡感覚」の持ち主ではなく、「田舎の普通の共同体」の一員であることを示している。
ついにその時が来た。
岡島洋平が早川猛(弟)に、兄の出所を告げる。また、父がぼけて来ていることを告げる。
早川猛(弟)は言う。「兄はクリーニング店には、もう戻らないよ」って。
東京で、早川猛(弟)は兄の出所の日、母の形見であるフィルムを廻す。
そこには、あの家族で行った川があり、幼少の兄と弟、つまり「長男」と「次男」が映し出される。兄が弟を遊んでいる。
気をつけなくてはいけないのは、このシーンは何も「感慨」のシーンではない。
何か、弟が【次男の身勝手さ】に気付いた訳でもなく、ましてや「反省」ではない。
感動的ではあるが、この監督はその徹底さにおいて、こんな“お涙ちょうーだい”のシーンなんか用意する訳がない。
ここで、早川猛(弟)は、己が不安は「田舎の共同体」にあったと気付くのだ。
そして、その衝動は、「兄の出所を迎えに行こう」という意識に変わるのだ。
つまり、兄はきっとあの川端智恵子が死んだ川に行くに違いないと感じるのだ。
それがこの映画のまたは監督のおもしろさであり優れたところである。
このシーンを、何か弟のいわばお涙ちょうだいのものとみるのはつまらない。
それでは三文映画ではないか。
監督は、この弟にもっと凄い「ねじれ」を与えているものと思われる。
確かに、弟は、岡島洋平と一緒に兄の出所を迎えに行ったが、兄は“行方知れず”。
ここで、早川猛(弟)は、「もしや・・・」という「不安」にまた囚われる。
後のシーンは、すべて早川猛(弟)の「妄想」である。
その妄想とは、「兄はきっと、川端智恵子のところに行ったんだ」。「あの川に
行ったんだ」。「川端智恵子に求婚に行ったに違いない」という妄想と次男特有のものが現れる。
映画のシーンの最後に、妄想の「甲府行きのバス」が来る。
兄が何かうれしそうにしている。しかしその顔はすでに“死の相”である。
おそろしく完成度の高い作品である。めずらしく“魅せる”日本映画だ。
この映画は海外で評価されたが(文末参照)、しかし、「西欧的な・・・」を思念に入れるとき、この監督作品は海外で良く理解されたであろうか?
まあ、映画は己の心境に重ねて観るものだから、いろんな観方があってもいいと思うが!
【紹介】
西川美和監督の「蛇イチゴ」に続く長編第2作。自分が見た「友人が殺人を犯す」という悪夢から着想した。第59回カンヌ国際映画祭監督週間 正式出品作品。優れた演出力が高く評価され、多くの映画賞を受賞し、2006年度の日本映画における最も高い評価を得た作品の一つとなった。
• 監督・原案・脚本:西川美和
• 音楽:カリフラワーズ
• 主題歌:カリフラワーズ『うちに帰ろう』
【追記1】 この『ゆれる』は兄弟をあつかっているが、ぜひ「母」と「姉妹」を登場させた、家族を描いて欲しいと思う。私には、西川美和監督は、それをすでに用意しているものと推察する。
【追記2】 この「感想文」は1回観た後、約1ケ月の想いの中で、ついに2回目を観ただけです。これもまた、一気に書き殴りましたので、誤字や重複をお許し下さい。
【追記3】 「porcaroの日記2008-11-07 【次男坊理論】」さんには、あらためて感謝申し上げるとともに、勝手な掲載をお許し下さい、と申し上げる。
【追記4】 この映画を薦めてくれた友人Fさんにはお礼を述べる。貴女のお陰で、私はとてつもなく映画鑑賞に成長したと思える。
【雑感としての補足〜1〜】
先日、『ゆれる』(監督・原案・脚本:西川美和)の感想を書いた。
その中で、映画はそれぞれの思い入れにおいて観るのだから、独善的などという批評家的批判は傲慢なものの言うものであると書いた。
しかし、再びネットのいろいろな「批評」を見てとことん嫌になった。
全くこの映画を理解していない水準にある。
例えば、この『ゆれる』を、単なる兄弟の葛藤劇と観るのはあまりにも情けなすぎる。それでは愚鈍である。この優れた監督はそんな映画つくりはしていないと思う。
兄弟、特に長男と次男の関係、親子の関係(この場合は父)、つまり対としての幻想はそれ自体としては成立しない。対としての幻想は他者と関係することにおいて成立する概念である。
ここでは「田舎の共同体」として表現されている。そして、その共同体は「都会という共同体」あるいは、次男に象徴的に“見せるもの”との相克として表現されていると思える。
そう考えなければ、例えば、検事のもの言いが、どうも関西弁のようであったり、あのガソリンスタンドのアルバイトの青年の言説と存在は、単なる“常識的な”言説としてしか見えない。そうではなく、検事もまた、異なる共同体の人間であり、ガソリンスタンドのアルバイトの青年の言説と存在は、まことにこの村落共同体のものとしてあると言える。
この『ゆれる』は、実はその主題を「兄弟」に置いているように見えるが、その主題は実は「共同体」のあり様にあると言っても過言ではないと思う。
「対としての幻想」が際立つ、「村落共同幻想」との関係。そして“憧れの都会”への禁忌破りに対する「制裁」。
兄弟や家族(この場合は父)の悪意、そして川端智恵子の悪意が表現されている。
これが、『ゆれる』が表現した映画の全体としてのあり様が実に優れており、評価される点であろう。
最初はそんなことも分からず、己の原形と現象に重ね合わせすぎて、おいおい、と泣いたのには、振り返ってあきれる。
それと同時に、こんな見方もできない映画批評家はどんなにつまらないかも分かる。単に、己が得た知でのみ映画を測り、それを思想まで咀嚼もできずに筋のみを追う職業かとぞ思う。
この映画『ゆれる』を「サスペンス:ドラマ」なんて評論し紹介しているのには、ただただあきれるしかない。
また、映画愛好家である我々も、観る最低の分別は獲得しなければならないと思う。知を思想まで、あるいは自分の生き方まで昇華することなく、ゴシップを集めては遊んでいる知。そんなものはペットと遊ぶに等しいにすぎない。
不健康なのである。
【雑感としての補足〜2〜】(『ゆれる』の本を読んで)
友への手紙から(要約)
・・・・・私は、こんなところばっかり見てしまうので、ついに小説を読むのをやめたものでした。でも、あなたから、吉本ばななの『ハチ公の最後の恋人』を薦められて読み、ふっと考えるところがありました。
いま私は、先に私が長々と“感想”を述べた西川美和の映画『ゆれる』の「本」を読んでいます(ブックオフで100円で買った)。吉本ばななとは雰囲気の異なる文章です。
そうして、私はその映画の“感想”で、もう少し家族について触れて欲しかった、と駄々をこねたのですが、何と、小説ではやはりその「家族関係」が描かれていました。
また、映画では見え隠れしていた、兄と死ぬ女性に何となく「悪意」や「故意」を感じていましたが、映画ではなかなか見えませんでした(わたしにはみえた)が、この小説では、はっきりとそのことを言っています。
そして、弟が言う、「何かこの村には訳の解らないものが存在し、常にそれに見張られているような気がしてならなかった」という主旨の表現がありました。
私が映画感想で言った、幻想つまり「村落共同体」が明らかに存在しているではありませんか。
兄の悪意は「村落共同体」の持つもので、「私」という意識を持たなかった女性の、他の「村落共同体」への悪意のようです。
まあ、小説と映画とは異なっていてもいいのですが、映画にもう少しそれらの示唆があってもいいのではなかったか、と思います。
しかし、そのことを表現していたのが、兄であり女性の見事な(悪意っぽい)演技で代弁させたものでしょう。なかなかしたたかです!
私は、この映画の観方について、友にお叱りをいただきました。
『独善すぎる!』って。
でも、小説を読めば分かりますが、私の感想はそんなにズレてはいない、独善的すぎるよりも極めてノーマルなものであったことに、我ながら驚きました・・・・・
|
|
|
|
|
|
|
|
感動の映画ランキング 更新情報
-
最新のアンケート
感動の映画ランキングのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 89997人
- 3位
- 酒好き
- 170649人