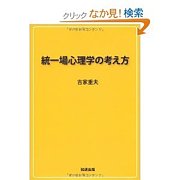とりあえず、現時点での目次を書いておきます。
目 次
はじめに
実践心理学派宣言
第1部 個人と心
第1章 本冊子を活かす方法
1−1 読み方
1−2 全体の構造
第2章 心とは何か
2−1 心の特徴
2−2 心の環境
2−3 主体と心
2−4 内なる世界
第3章 様々な現れ
3−1 心の問題
3−1−1 孤独
3−1−2 老化
3−1−3 病苦
3−1−4 死
3−1−5 心を開く
3−1−6 実践(1)アファーメーション
3−2 心の不足
3−2−1 自分探し
3−2−2 寄り添うことの不足
3−2−3 ゆだねることの不足
3−2−4 包み込むことの不足
3−2−5 感謝することの不足
3−2−6 実践(2)時間を共にする
3−3 心の成長
3−3−1 感じること
3−3−2 行動すること
3−3−3 自分に気づくこと
3−3−4 感情移入すること
3−3−5 実践(3)ビデオを見る
3−4 仮説の構築(1)
3−4−1 問題とは何か
3−4−2 不足とは何か
3−4−3 成長とは何か
3−4−4 心の仮説
3−5 映画館での体験
第4章 内在者理論
4−1 心の発生
4−1−1 心の始まり
4−1−2 内在者の発生
4−1−3 内在者の増加と心の成長
4−1−4 実践(4)歌に感情移入する
4−2 心の成長
4−2−1 情報化能と実働化能
4−2−2 二つの私
4−2−3 内在者チームの編成
4−2−4 ブロック型の拡張
4−2−5 ブロックの統合
4−2−6 実践(5)心の中の人間関係を描く
4−3 内在者ときめ細かい認識
4−3−1 内在者と結びつけた認識
4−3−2 擬人的な認識
4−3−3 感情移入と追体験
4−3−4 実践(6)演劇の利用
4−4 意識の働き
4−4−1 三つの働き
4−4−2 つながる
4−4−3 移動する
4−4−4 実感する
4−4−5 実践(7)連想の分析
4−5 内在者チームと意識
4−5−1 普段の私
4−5−2 内在者チームによる拒絶
4−5−3 意識の固定とチームの分断
4−5−4 意識の移動
4−5−4 普段の私への統合
4−5−5 実践(8)普段の私へ切り替える
4−6 仮説の構築(2)
4−6−1 記録上の内在者と意識下の内在者
4−6−2 内在者の二面性
4−6−3 内在者の発生と分布
4−6−4 様々な図解
4−7 ビジョンクエストの体験
4−7−1 スウェット・ロッジ
4−7−2 ビジョンクエスト(1)別の自分
4−7−3 ビジョンクエスト(2)過去の統合
第5章 象徴収束理論
5−1 心を物理現象として捉える
5−1−1 安定化と心の動き
5−1−2 脳量子場理論と収束イメージ
5−1−3 象徴性とグルーピング
5−1−4 基本的な事例
5−1−5 実践(9)積極性と心の安定
5−2 収束性
5−2−1 収束イメージの象徴性と収束性
5−2−2 収束性と排他性
5−2−3 収束性と優先イメージ
5−2−4 概念の優先と実感の優先
5−2−5 実践(10)頭と心
5−3 内在者理論の捉え直し
5−3−1 内在者という収束イメージ
5−3−2 内在者チームと収束イメージ
5−3−3 内在者ブロックと収束イメージ
5−3−4 様々な収束イメージ
5−3−5 実践(11)
5−4 様々な問題の図解
5−4−1 好き嫌いと能力
5−4−2 上がり症
5−4−3 父親の嫌いな娘
5−4−4 父親の嫌いな息子
5−4−5 母親の嫌いな子ども
5−4−6 思春期の構造
5−4−7 外界に近い意識
5−4−8 外界から離れた意識(1)
5−4−9 外界から離れた意識(2)
5−4−10 一部しか使われない心
5−4−11 実践(12)今を図解する
5−5 情報化能と実働化能
5−5−1 情報化能と収束イメージ
5−5−2 実働化能と実体化
5−5−3 情報のサイクルによる認識の強化
5−5−4 実践(13)人の真似をする
5−7 仮説の構築(3)
5−8 人生終焉の体験
第6章 普遍主体仮説
6−1 二つの私
6−1−1 私とは何か
6−1−2 自分を感じる方法
6−1−3 二つの私
6−1−4 波と私
6−1−5 私という概念
6−1−6 実践(14)私を感じる私
6−2 時間と主体
6−2−1 動きと認識
6−2−2 宇宙に投げられたボール
6−2−3 時間と実感、主体
6−2−4 時間の方向性と主体
6−2−5 意識現象と固定的な記憶
6−2−6 二つの時間
4−2−7 実践(15)映像と音
6−3 5次元仮説と認識方法
6−3−1 3次元の情報と文化の補填
6−3−2 対象の観察と寄り添う実感
6−3−3 寄り添うことと時間ベクトル
6−3−4 委ねる、包み込む、同調する
6−3−5 再現性と科学?、科学?
6−3−6 実践(16)二つの時間軸
6−4 5次元仮説と内認識
6−4−1 意識現象と認識
6−4−2 認識の次元数
6−4−3 私と情報化能、実働化能
6−4−3 意識現象と複数の私
6−4−4 実践(17)嫌いな人と音楽
6−5 生物と心
6−5−1 収束イメージの安定と情報エントロピーの減少
6−5−2 時間軸と情報エントロピーの減少
6−5−3 心の広がり
6−5−4 実践(18)瞑想
6−6 仮説の構築(4)
6−7 高校時代の体験
第7章 コミュニケーション
7−1 内在者理論とコミュニケーション
7−1−1 内在者の許容と拒絶
7−1−2 自我状態の内在者チームの性質
7−1−3 特別な内在者ブロック
7−1−4 未知の内在者との融和
7−2 象徴収束理論とコミュニケーション
7−2−1 コミュニケーションの構造
7−2−2 象徴イメージとコミュニケーション
7−2−2 収束イメージとコミュニケーション
7−2−3 日本人の収束イメージ
7−2−4 個人の収束イメージ
7−3 コミュニケーションの実際
7−3−1 コミュニケーションの目的
7−3−2 コミュニケーション以外の相互作用
7−3−3 コミュニケーションの改善
7−3−4 会議と議論の改善
7−4 コミュニケーションと心の統合
7−4−1 心の構造とコミュニケーション
7−4−2 心の地図を作る
7−4−3 自分の心を知る
7−4−4 自分の中の他人
7−4−5 実働化能を活用したコミュニケーションと演劇の利用
第8章 心理支援
8−1 心理支援の基本
8−1−1 心理支援と教育(心の構造と内容)
8−1−2 心の統合が目的
8−1−3 支援者のあり方
8−1−4 どの次元を統合するのか
8−2 自力統合を支援する
8−2−1 統一場心理学による教育
8−2−2 積極性と心の統合
8−2−3 いくつかのワーク
8−3 統合を誘導する
8−3−1 寄り添うこと(内在者の創造)
8−3−2 教育と心の再構築
8−3−3 権威と宗教
8−3−4 合目的な誘導瞑想
第2部 トランスパーソナルな構造
第9章 体験という方法
9−1 科学とは何か
9−1−1 象徴イメージの共有と科学
9−1−2 仮説の変遷(象徴イメージの影に隠れている収束イメージ)
9−1−3 科学と論理
9−2 5次元に於ける調和
9−2−1 体験の次元
9−2−2 論理の調和
9−2−3 実感の調和
9−3 論理+実感
9−3−1 象徴イメージの調和の限界
9−3−2 体験は論理を含む
9−3−3 普遍性と理知の世界
第10章 人、動物、虫
10−1 トランスパーソナルな体験(1)動物
10−1−1 野良犬との遭遇
10−1−2 床屋の猫
10−1−3 目に見えることと4−5次元
10−2 トランスパーソナルな体験(2)人間
10−2−1 新幹線で
10−2−2 山手線で
10−2−3 細かい多くのこと
10−3 虫の進化
10−3−1 いくつかの事例
10−3−2 偶然という説明の無理
10−3−3 4−5次元を前提とした進化
第11章 普遍主体理論より
11−1 意識現象の広がり
11−1−1 1−5次元の性質
11−1−2 4−5次元の特徴
11−1−3 4−5次元の意味(共通文化の必要性)
11−2 1−3次元と4−5次元
11−2−1 4−5次元での接触
11−2−2 1−5次元での調和
11−2−3 1−3次元での類似性と調和
11−3 翻訳と補填
11−3−1 1−3次元の翻訳と補填
11−3−2 4−5次元の翻訳と補填
11−3−3 特別な能力とは
第12章 心の統合とトランスパーソナルな関係
12−1 トランスパーソナルな安定
12−1−1 無意識の安定
12−1−2 洗脳
12−1−3 1−5次元での洗脳外し
12−2 統合への二つの方法
12−2−1 共鳴する集合的実感を決める
12−2−2 個人の心を統合する
12−2−3 山の頂を目指す
12−3 集合的実感
12−3−1 日常の中に潜む実感
12−3−2 宗教者の冷静さ
12−3−3 予想される頂
第13章 普通の覚醒
13−1 心の統合は覚醒である
13−1−1 意識現象に含まれている内在者
13−1−2 4−5次元と目覚め
13−1−3 統合、目覚め、豊かな感性
13−2 瞑想法
13−2−1 内認識による自己確認
13−2−2 内認識による調整
13−2−3 自己一致
13−3 普通の覚醒
13−3−1 あるがまま
13−3−2 全体性
13−3−3 調和力
第14章 一つの私へ
14−1 私が一つであるという実感
14−1−1 動物の肉体と心
14−1−2 全体の調和
14−1−3 あるがまま
14−2 再び波のモデル
14−2−1 私とは
14−2−2 存在に広がる私の実感
14−2−3 始終の営み
14−3 人類という私
14−3−1 不公平感の不自由
14−3−2 役割の充実感
14−3−3 人類に必要な実感
第15章 心と価値観
15−1 心の安定と価値
15−1−1 自分の価値
15−1−2 価値の共有
15−1−3 価値の進化
15−2 普遍的な価値への問い
15−2−1 個性と価値
15−2−2 共通した価値の有無
15−2−3 価値と社会制度
15−3 情報主義社会と価値
15−3−1 開かれた社会
15−3−2 社会としての人類の進化
15−3−3 情報主義社会を描く
第16章 普遍的価値への貢献
16−1 務めとして
16−1−1 理知的な理解
16−1−2 1−5次元での調和
16−1−3 日々の繰り返し
16−2 表現すること
16−2−1 相手に合った表現
16−2−2 教育、整理、自律的進化
16−2−3 自己表現
16−3 統合すること
16−3−1 宗教との関係
16−3−2 仏教との関係
16−3−3 哲学との関係
16−4 組織としての貢献
16−4−1 理解を広める
16−4−2 共感を広める
16−4−3 働きを広める
第17章 心の共有
17−1 心の開放
17−1−1 委ねること、寄り添うこと、包み込むこと
17−1−2 明確であること、透明であること
17−1−3 全体から感じること
17−2 一体感
17−2−1 心の共有
17−2−2 恐れのない心
17−2−3 大安心
17−3 祈り
17−3−1 心の統合
17−3−2 隣人の幸福
17−3−3 人類の未来
第3部 用語解説
第18章 本書の用語
第19章 他書で用いた用語との関係
目 次
はじめに
実践心理学派宣言
第1部 個人と心
第1章 本冊子を活かす方法
1−1 読み方
1−2 全体の構造
第2章 心とは何か
2−1 心の特徴
2−2 心の環境
2−3 主体と心
2−4 内なる世界
第3章 様々な現れ
3−1 心の問題
3−1−1 孤独
3−1−2 老化
3−1−3 病苦
3−1−4 死
3−1−5 心を開く
3−1−6 実践(1)アファーメーション
3−2 心の不足
3−2−1 自分探し
3−2−2 寄り添うことの不足
3−2−3 ゆだねることの不足
3−2−4 包み込むことの不足
3−2−5 感謝することの不足
3−2−6 実践(2)時間を共にする
3−3 心の成長
3−3−1 感じること
3−3−2 行動すること
3−3−3 自分に気づくこと
3−3−4 感情移入すること
3−3−5 実践(3)ビデオを見る
3−4 仮説の構築(1)
3−4−1 問題とは何か
3−4−2 不足とは何か
3−4−3 成長とは何か
3−4−4 心の仮説
3−5 映画館での体験
第4章 内在者理論
4−1 心の発生
4−1−1 心の始まり
4−1−2 内在者の発生
4−1−3 内在者の増加と心の成長
4−1−4 実践(4)歌に感情移入する
4−2 心の成長
4−2−1 情報化能と実働化能
4−2−2 二つの私
4−2−3 内在者チームの編成
4−2−4 ブロック型の拡張
4−2−5 ブロックの統合
4−2−6 実践(5)心の中の人間関係を描く
4−3 内在者ときめ細かい認識
4−3−1 内在者と結びつけた認識
4−3−2 擬人的な認識
4−3−3 感情移入と追体験
4−3−4 実践(6)演劇の利用
4−4 意識の働き
4−4−1 三つの働き
4−4−2 つながる
4−4−3 移動する
4−4−4 実感する
4−4−5 実践(7)連想の分析
4−5 内在者チームと意識
4−5−1 普段の私
4−5−2 内在者チームによる拒絶
4−5−3 意識の固定とチームの分断
4−5−4 意識の移動
4−5−4 普段の私への統合
4−5−5 実践(8)普段の私へ切り替える
4−6 仮説の構築(2)
4−6−1 記録上の内在者と意識下の内在者
4−6−2 内在者の二面性
4−6−3 内在者の発生と分布
4−6−4 様々な図解
4−7 ビジョンクエストの体験
4−7−1 スウェット・ロッジ
4−7−2 ビジョンクエスト(1)別の自分
4−7−3 ビジョンクエスト(2)過去の統合
第5章 象徴収束理論
5−1 心を物理現象として捉える
5−1−1 安定化と心の動き
5−1−2 脳量子場理論と収束イメージ
5−1−3 象徴性とグルーピング
5−1−4 基本的な事例
5−1−5 実践(9)積極性と心の安定
5−2 収束性
5−2−1 収束イメージの象徴性と収束性
5−2−2 収束性と排他性
5−2−3 収束性と優先イメージ
5−2−4 概念の優先と実感の優先
5−2−5 実践(10)頭と心
5−3 内在者理論の捉え直し
5−3−1 内在者という収束イメージ
5−3−2 内在者チームと収束イメージ
5−3−3 内在者ブロックと収束イメージ
5−3−4 様々な収束イメージ
5−3−5 実践(11)
5−4 様々な問題の図解
5−4−1 好き嫌いと能力
5−4−2 上がり症
5−4−3 父親の嫌いな娘
5−4−4 父親の嫌いな息子
5−4−5 母親の嫌いな子ども
5−4−6 思春期の構造
5−4−7 外界に近い意識
5−4−8 外界から離れた意識(1)
5−4−9 外界から離れた意識(2)
5−4−10 一部しか使われない心
5−4−11 実践(12)今を図解する
5−5 情報化能と実働化能
5−5−1 情報化能と収束イメージ
5−5−2 実働化能と実体化
5−5−3 情報のサイクルによる認識の強化
5−5−4 実践(13)人の真似をする
5−7 仮説の構築(3)
5−8 人生終焉の体験
第6章 普遍主体仮説
6−1 二つの私
6−1−1 私とは何か
6−1−2 自分を感じる方法
6−1−3 二つの私
6−1−4 波と私
6−1−5 私という概念
6−1−6 実践(14)私を感じる私
6−2 時間と主体
6−2−1 動きと認識
6−2−2 宇宙に投げられたボール
6−2−3 時間と実感、主体
6−2−4 時間の方向性と主体
6−2−5 意識現象と固定的な記憶
6−2−6 二つの時間
4−2−7 実践(15)映像と音
6−3 5次元仮説と認識方法
6−3−1 3次元の情報と文化の補填
6−3−2 対象の観察と寄り添う実感
6−3−3 寄り添うことと時間ベクトル
6−3−4 委ねる、包み込む、同調する
6−3−5 再現性と科学?、科学?
6−3−6 実践(16)二つの時間軸
6−4 5次元仮説と内認識
6−4−1 意識現象と認識
6−4−2 認識の次元数
6−4−3 私と情報化能、実働化能
6−4−3 意識現象と複数の私
6−4−4 実践(17)嫌いな人と音楽
6−5 生物と心
6−5−1 収束イメージの安定と情報エントロピーの減少
6−5−2 時間軸と情報エントロピーの減少
6−5−3 心の広がり
6−5−4 実践(18)瞑想
6−6 仮説の構築(4)
6−7 高校時代の体験
第7章 コミュニケーション
7−1 内在者理論とコミュニケーション
7−1−1 内在者の許容と拒絶
7−1−2 自我状態の内在者チームの性質
7−1−3 特別な内在者ブロック
7−1−4 未知の内在者との融和
7−2 象徴収束理論とコミュニケーション
7−2−1 コミュニケーションの構造
7−2−2 象徴イメージとコミュニケーション
7−2−2 収束イメージとコミュニケーション
7−2−3 日本人の収束イメージ
7−2−4 個人の収束イメージ
7−3 コミュニケーションの実際
7−3−1 コミュニケーションの目的
7−3−2 コミュニケーション以外の相互作用
7−3−3 コミュニケーションの改善
7−3−4 会議と議論の改善
7−4 コミュニケーションと心の統合
7−4−1 心の構造とコミュニケーション
7−4−2 心の地図を作る
7−4−3 自分の心を知る
7−4−4 自分の中の他人
7−4−5 実働化能を活用したコミュニケーションと演劇の利用
第8章 心理支援
8−1 心理支援の基本
8−1−1 心理支援と教育(心の構造と内容)
8−1−2 心の統合が目的
8−1−3 支援者のあり方
8−1−4 どの次元を統合するのか
8−2 自力統合を支援する
8−2−1 統一場心理学による教育
8−2−2 積極性と心の統合
8−2−3 いくつかのワーク
8−3 統合を誘導する
8−3−1 寄り添うこと(内在者の創造)
8−3−2 教育と心の再構築
8−3−3 権威と宗教
8−3−4 合目的な誘導瞑想
第2部 トランスパーソナルな構造
第9章 体験という方法
9−1 科学とは何か
9−1−1 象徴イメージの共有と科学
9−1−2 仮説の変遷(象徴イメージの影に隠れている収束イメージ)
9−1−3 科学と論理
9−2 5次元に於ける調和
9−2−1 体験の次元
9−2−2 論理の調和
9−2−3 実感の調和
9−3 論理+実感
9−3−1 象徴イメージの調和の限界
9−3−2 体験は論理を含む
9−3−3 普遍性と理知の世界
第10章 人、動物、虫
10−1 トランスパーソナルな体験(1)動物
10−1−1 野良犬との遭遇
10−1−2 床屋の猫
10−1−3 目に見えることと4−5次元
10−2 トランスパーソナルな体験(2)人間
10−2−1 新幹線で
10−2−2 山手線で
10−2−3 細かい多くのこと
10−3 虫の進化
10−3−1 いくつかの事例
10−3−2 偶然という説明の無理
10−3−3 4−5次元を前提とした進化
第11章 普遍主体理論より
11−1 意識現象の広がり
11−1−1 1−5次元の性質
11−1−2 4−5次元の特徴
11−1−3 4−5次元の意味(共通文化の必要性)
11−2 1−3次元と4−5次元
11−2−1 4−5次元での接触
11−2−2 1−5次元での調和
11−2−3 1−3次元での類似性と調和
11−3 翻訳と補填
11−3−1 1−3次元の翻訳と補填
11−3−2 4−5次元の翻訳と補填
11−3−3 特別な能力とは
第12章 心の統合とトランスパーソナルな関係
12−1 トランスパーソナルな安定
12−1−1 無意識の安定
12−1−2 洗脳
12−1−3 1−5次元での洗脳外し
12−2 統合への二つの方法
12−2−1 共鳴する集合的実感を決める
12−2−2 個人の心を統合する
12−2−3 山の頂を目指す
12−3 集合的実感
12−3−1 日常の中に潜む実感
12−3−2 宗教者の冷静さ
12−3−3 予想される頂
第13章 普通の覚醒
13−1 心の統合は覚醒である
13−1−1 意識現象に含まれている内在者
13−1−2 4−5次元と目覚め
13−1−3 統合、目覚め、豊かな感性
13−2 瞑想法
13−2−1 内認識による自己確認
13−2−2 内認識による調整
13−2−3 自己一致
13−3 普通の覚醒
13−3−1 あるがまま
13−3−2 全体性
13−3−3 調和力
第14章 一つの私へ
14−1 私が一つであるという実感
14−1−1 動物の肉体と心
14−1−2 全体の調和
14−1−3 あるがまま
14−2 再び波のモデル
14−2−1 私とは
14−2−2 存在に広がる私の実感
14−2−3 始終の営み
14−3 人類という私
14−3−1 不公平感の不自由
14−3−2 役割の充実感
14−3−3 人類に必要な実感
第15章 心と価値観
15−1 心の安定と価値
15−1−1 自分の価値
15−1−2 価値の共有
15−1−3 価値の進化
15−2 普遍的な価値への問い
15−2−1 個性と価値
15−2−2 共通した価値の有無
15−2−3 価値と社会制度
15−3 情報主義社会と価値
15−3−1 開かれた社会
15−3−2 社会としての人類の進化
15−3−3 情報主義社会を描く
第16章 普遍的価値への貢献
16−1 務めとして
16−1−1 理知的な理解
16−1−2 1−5次元での調和
16−1−3 日々の繰り返し
16−2 表現すること
16−2−1 相手に合った表現
16−2−2 教育、整理、自律的進化
16−2−3 自己表現
16−3 統合すること
16−3−1 宗教との関係
16−3−2 仏教との関係
16−3−3 哲学との関係
16−4 組織としての貢献
16−4−1 理解を広める
16−4−2 共感を広める
16−4−3 働きを広める
第17章 心の共有
17−1 心の開放
17−1−1 委ねること、寄り添うこと、包み込むこと
17−1−2 明確であること、透明であること
17−1−3 全体から感じること
17−2 一体感
17−2−1 心の共有
17−2−2 恐れのない心
17−2−3 大安心
17−3 祈り
17−3−1 心の統合
17−3−2 隣人の幸福
17−3−3 人類の未来
第3部 用語解説
第18章 本書の用語
第19章 他書で用いた用語との関係
|
|
|
|
コメント(8)
新しい目次を「象徴収束理論」のところまで挙げておきます。
目 次
はじめに 1
実践心理学派宣言 2
第1部 個人と心 12
第1章 本冊子を活かす方法 13
1−1 読み方 13
1−2 全体の構造 14
第2章 心とは何か
2−1 心の特徴 15
2−2 心の環境 16
2−3 主体と心 16
2−4 内なる世界 16
第3章 様々な現れ
3−1 心の問題
3−1−1 孤独 18
3−1−2 老化 21
3−1−3 病苦 23
3−1−4 死 24
3−1−5 心を開く 26
3−1−6 実践(1)アファーメーション 27
3−2 心の不足
3−2−1 自分探し 30
3−2−2 寄り添うことの不足 31
3−2−3 ゆだねることの不足 33
3−2−4 包み込むことの不足 35
3−2−5 感謝することの不足 37
3−2−6 実践(2)時間を共にする 38
3−3 心の成長
3−3−1 感じること 40
3−3−2 行動すること 41
3−3−3 自分に気づくこと 43
3−3−4 感情移入すること 44
3−3−5 実践(3)ビデオを見る 45
3−4 仮説の構築(1) 46
3−4−1 問題とは何か 46
3−4−2 不足とは何か 47
3−4−3 成長とは何か 47
3−4−4 心の仮説 47
3−5 映画館での体験
目 次
はじめに 1
実践心理学派宣言 2
第1部 個人と心 12
第1章 本冊子を活かす方法 13
1−1 読み方 13
1−2 全体の構造 14
第2章 心とは何か
2−1 心の特徴 15
2−2 心の環境 16
2−3 主体と心 16
2−4 内なる世界 16
第3章 様々な現れ
3−1 心の問題
3−1−1 孤独 18
3−1−2 老化 21
3−1−3 病苦 23
3−1−4 死 24
3−1−5 心を開く 26
3−1−6 実践(1)アファーメーション 27
3−2 心の不足
3−2−1 自分探し 30
3−2−2 寄り添うことの不足 31
3−2−3 ゆだねることの不足 33
3−2−4 包み込むことの不足 35
3−2−5 感謝することの不足 37
3−2−6 実践(2)時間を共にする 38
3−3 心の成長
3−3−1 感じること 40
3−3−2 行動すること 41
3−3−3 自分に気づくこと 43
3−3−4 感情移入すること 44
3−3−5 実践(3)ビデオを見る 45
3−4 仮説の構築(1) 46
3−4−1 問題とは何か 46
3−4−2 不足とは何か 47
3−4−3 成長とは何か 47
3−4−4 心の仮説 47
3−5 映画館での体験
第4章 内在者理論
4−1 心の発生 50
4−1−1 心の始まり 51
4−1−2 心の構造 52
4−1−3 内在者の発生 54
4−1−4 内在者の増加と心の成長 57
4−1−5 実践(4)歌に感情移入する 58
4−2 心の成長
4−2−1 情報化能と実働化能 60
4−2−2 二つの私 60
4−2−3 内在者チームの編成 62
4−2−4 ブロック型の拡張 62
4−2−5 ブロックの統合 63
4−2−6 実践(5)心の中の人間関係を描く 64
4−3 内在者ときめ細かい認識
4−3−1 内在者と結びつけた認識 65
4−3−2 擬人的な認識 66
4−3−3 感情移入と追体験 66
4−3−4 実践(6)演劇の利用 67
4−4 意識の働き
4−4−1 三つの働き 68
4−4−2 つなげる 69
4−4−3 移動する 69
4−4−4 実感する 71
4−4−5 実践(7)連想の分析 71
4−5 内在者チームと意識
4−5−1 普段の私 73
4−5−2 内在者チームによる拒絶 73
4−5−3 意識の固定とチームの分断 76
4−5−4 意識の移動 77
4−5−4 普段の私への統合 78
4−5−5 実践(8)普段の私へ切り替える 79
4−6 仮説の構築(2)
4−6−1 記録上の内在者と意識下の内在者 80
4−6−2 内在者の二面性 80
4−6−3 内在者の発生と分布 80
4−6−4 様々な図解 81
4−7 ビジョンクエストの体験
4−7−1 スウェット・ロッジ 81
4−7−2 ビジョンクエスト(1)別の自分 83
4−7−3 ビジョンクエスト(2)過去の統合 85
4−1 心の発生 50
4−1−1 心の始まり 51
4−1−2 心の構造 52
4−1−3 内在者の発生 54
4−1−4 内在者の増加と心の成長 57
4−1−5 実践(4)歌に感情移入する 58
4−2 心の成長
4−2−1 情報化能と実働化能 60
4−2−2 二つの私 60
4−2−3 内在者チームの編成 62
4−2−4 ブロック型の拡張 62
4−2−5 ブロックの統合 63
4−2−6 実践(5)心の中の人間関係を描く 64
4−3 内在者ときめ細かい認識
4−3−1 内在者と結びつけた認識 65
4−3−2 擬人的な認識 66
4−3−3 感情移入と追体験 66
4−3−4 実践(6)演劇の利用 67
4−4 意識の働き
4−4−1 三つの働き 68
4−4−2 つなげる 69
4−4−3 移動する 69
4−4−4 実感する 71
4−4−5 実践(7)連想の分析 71
4−5 内在者チームと意識
4−5−1 普段の私 73
4−5−2 内在者チームによる拒絶 73
4−5−3 意識の固定とチームの分断 76
4−5−4 意識の移動 77
4−5−4 普段の私への統合 78
4−5−5 実践(8)普段の私へ切り替える 79
4−6 仮説の構築(2)
4−6−1 記録上の内在者と意識下の内在者 80
4−6−2 内在者の二面性 80
4−6−3 内在者の発生と分布 80
4−6−4 様々な図解 81
4−7 ビジョンクエストの体験
4−7−1 スウェット・ロッジ 81
4−7−2 ビジョンクエスト(1)別の自分 83
4−7−3 ビジョンクエスト(2)過去の統合 85
第2部 心の物理学
第5章 象徴収束理論
5−1 心を物理現象として捉える
5−1−1 固定した記憶と意識
5−1−2 安定化と心の動き
5−1−3 イメージ情報の統合と象徴イメージ
5−1−4 象徴イメージと象徴性
5−1−5 象徴イメージの安定化の例
5−1−6 象徴イメージの標準化と客観性
5−1−7 象徴イメージの固定化
5−1−8 象徴イメージに隠れている要素
5−1−9 実践(9)心の動いた理由
5−2 情感と収束イメージ
5−2−1 情感の源泉
5−2−2 情感と収束イメージ
5−2−3 収束イメージの安定性
5−2−4 収束イメージの変化と情感の種類
5−2−5 優先イメージの発生
5−2−6 イメージ情報の象徴性と収束性
5−2−7 象徴イメージと収束イメージの使い分け
5−2−8 実践(10)意味づけと時間
5−3 内在者理論の捉え直し
5−3−1 心の発生と収束イメージ
5−3−2 雰囲気と収束イメージ
5−3−3 内在者という収束イメージ
5−3−4 内在者チームと収束イメージ
5−3−5 強烈な思いと収束イメージ
5−3−6 内在者ブロックと収束イメージ
5−3−7 実践(11)自分の雰囲気を感じる
5−4 様々な問題の図解
5−4−1 好き嫌いと能力
5−4−2 性差の問題
5−4−3 上がり症
5−4−4 父親の嫌いな娘
5−4−5 父親の嫌いな息子
5−4−6 母親の嫌いな子ども
5−4−7 外界に近い意識
5−4−8 外界から離れた意識(1)
5−4−9 外界から離れた意識(2)
5−4−10 一部しか使われない心
5−4−11 実践(12)今を図解する
5−5 思春期の構造
5−5−1 心の成長と収束イメージ
5−5−2 親子の収束イメージと思春期
5−5−3 親子の関係の固定
5−5−4 引きこもりについて
5−5−5 親子関係を固定しない方法
5−5−6 実践(13)インナーチャイルドの誘導瞑想
5−6 情報化能と実働化能
5−6−1 情報化能と収束イメージ
5−6−2 実働化能と実体化
5−6−3 情報のサイクルによる認識の強化
5−6−4 実践(13)人の真似をする
5−7 仮説の構築(3)
5−8 人生終焉の体験
第5章 象徴収束理論
5−1 心を物理現象として捉える
5−1−1 固定した記憶と意識
5−1−2 安定化と心の動き
5−1−3 イメージ情報の統合と象徴イメージ
5−1−4 象徴イメージと象徴性
5−1−5 象徴イメージの安定化の例
5−1−6 象徴イメージの標準化と客観性
5−1−7 象徴イメージの固定化
5−1−8 象徴イメージに隠れている要素
5−1−9 実践(9)心の動いた理由
5−2 情感と収束イメージ
5−2−1 情感の源泉
5−2−2 情感と収束イメージ
5−2−3 収束イメージの安定性
5−2−4 収束イメージの変化と情感の種類
5−2−5 優先イメージの発生
5−2−6 イメージ情報の象徴性と収束性
5−2−7 象徴イメージと収束イメージの使い分け
5−2−8 実践(10)意味づけと時間
5−3 内在者理論の捉え直し
5−3−1 心の発生と収束イメージ
5−3−2 雰囲気と収束イメージ
5−3−3 内在者という収束イメージ
5−3−4 内在者チームと収束イメージ
5−3−5 強烈な思いと収束イメージ
5−3−6 内在者ブロックと収束イメージ
5−3−7 実践(11)自分の雰囲気を感じる
5−4 様々な問題の図解
5−4−1 好き嫌いと能力
5−4−2 性差の問題
5−4−3 上がり症
5−4−4 父親の嫌いな娘
5−4−5 父親の嫌いな息子
5−4−6 母親の嫌いな子ども
5−4−7 外界に近い意識
5−4−8 外界から離れた意識(1)
5−4−9 外界から離れた意識(2)
5−4−10 一部しか使われない心
5−4−11 実践(12)今を図解する
5−5 思春期の構造
5−5−1 心の成長と収束イメージ
5−5−2 親子の収束イメージと思春期
5−5−3 親子の関係の固定
5−5−4 引きこもりについて
5−5−5 親子関係を固定しない方法
5−5−6 実践(13)インナーチャイルドの誘導瞑想
5−6 情報化能と実働化能
5−6−1 情報化能と収束イメージ
5−6−2 実働化能と実体化
5−6−3 情報のサイクルによる認識の強化
5−6−4 実践(13)人の真似をする
5−7 仮説の構築(3)
5−8 人生終焉の体験
第6章 普遍主体仮説
6−1 二つの私
6−1−1 私とは何か
6−1−2 自分を感じる方法
6−1−3 二つの私
6−1−4 波と私
6−1−5 主体に関する疑問
6−1−6 実践(14)私を感じる私
6−2 時間と主体
6−2−1 動きと認識
6−2−2 宇宙に投げられたボール
6−2−3 時間と実感、主体
6−2−4 時間の方向性と主体
6−2−5 意識現象と固定的な記憶
6−2−6 実践(15)映像と音
6−3 実感と5次元仮説
6−3−1 実感と時間の幅
6−3−2 主体ベクトルの方向性
6−3−3 5次元仮説
6−3−4 委ねる、包み込む、同調する
6−3−5 拒絶したイメージ情報と優先イメージの構造
6−3−6 実践(16)二つの時間軸
6−4 5次元仮説と内認識
6−4−1 内認識のようす
6−4−2 五感とイメージ情報
6−4−3 人間関係と内認識
6−4−4 覚醒について
6−4−5 実践(17)嫌いな人と音楽
6−5 私とは何か
6−5−1 意識現象の次元数
6−5−2 私と情報化能、実働化能
6−5−3 意識現象と複数の私
6−5−4 無我について
6−5−5 実践(18)瞑想
6−5 仮説の構築(4)
6−6 高校時代の体験
6−1 二つの私
6−1−1 私とは何か
6−1−2 自分を感じる方法
6−1−3 二つの私
6−1−4 波と私
6−1−5 主体に関する疑問
6−1−6 実践(14)私を感じる私
6−2 時間と主体
6−2−1 動きと認識
6−2−2 宇宙に投げられたボール
6−2−3 時間と実感、主体
6−2−4 時間の方向性と主体
6−2−5 意識現象と固定的な記憶
6−2−6 実践(15)映像と音
6−3 実感と5次元仮説
6−3−1 実感と時間の幅
6−3−2 主体ベクトルの方向性
6−3−3 5次元仮説
6−3−4 委ねる、包み込む、同調する
6−3−5 拒絶したイメージ情報と優先イメージの構造
6−3−6 実践(16)二つの時間軸
6−4 5次元仮説と内認識
6−4−1 内認識のようす
6−4−2 五感とイメージ情報
6−4−3 人間関係と内認識
6−4−4 覚醒について
6−4−5 実践(17)嫌いな人と音楽
6−5 私とは何か
6−5−1 意識現象の次元数
6−5−2 私と情報化能、実働化能
6−5−3 意識現象と複数の私
6−5−4 無我について
6−5−5 実践(18)瞑想
6−5 仮説の構築(4)
6−6 高校時代の体験
免疫学やホメオパシーなどいろいろありますが、特に自律神経失調症などを代表する「心と身体の不可分性」については
>第14章 一つの私へ
>14−1 私が一つであるという実感
> 14−1−1 動物の肉体と心
のあたりでしょうか?
それとも、統一場心理学とは違ったまた別の分野のお話になっていくのでしょうか・・・
心の状態によって身体の健康状態も影響するといったところ。
鬱病には軽い運動がいいとかもよく聞きますよね?
身体を動かすことで自分の心の統合をより確かなものへと高めることができたら、きっと楽しいですよね☆
ちなみに私は自転車に乗って走りまわっている時に、イメージの位置づけの整理をしたり、記憶のデフラグしてたりしています。
何故か身体動かしている時が一番高エネルギー状態のイメージを安定させられるんですよね・・・
>第14章 一つの私へ
>14−1 私が一つであるという実感
> 14−1−1 動物の肉体と心
のあたりでしょうか?
それとも、統一場心理学とは違ったまた別の分野のお話になっていくのでしょうか・・・
心の状態によって身体の健康状態も影響するといったところ。
鬱病には軽い運動がいいとかもよく聞きますよね?
身体を動かすことで自分の心の統合をより確かなものへと高めることができたら、きっと楽しいですよね☆
ちなみに私は自転車に乗って走りまわっている時に、イメージの位置づけの整理をしたり、記憶のデフラグしてたりしています。
何故か身体動かしている時が一番高エネルギー状態のイメージを安定させられるんですよね・・・
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
統一場心理学 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-