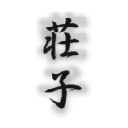━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━秋水篇━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(8)師と无
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昔者堯舜譲而帝 昔者(むかし)、堯と舜とは譲られて帝たらしも、
之噲譲而絶 之(し)と噲(かい)とは譲られて絶えたり。
湯武爭而王 湯(とう)と武とは争いて王たらしも、
白公爭而滅 白公は争いて滅びたり。
由此観之 此れに由りてこれを観れば、
爭譲之禮 争譲(そうじょう)の礼も、
堯桀之行 堯桀の行も、
貴賤有時 貴賤に時有りて、
未可以爲常也 未だ以て常と為すべからざるなり。
梁麗可以衝城 梁麗(りょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、
而不可以窒穴 以て穴を窒(ふさ)ぐべからず。
言殊器也 器を殊(こと)にするを言うなり。
騏驥驊騮一日而馳千里 騏驥驊騮(ききかりゅう)は一日にして千里を馳するも、
捕鼠不如狸狌 鼠(ねずみ)を捕らうるは狸狌(りせい)に如(し)かず。
言殊技也 技(わざ)を殊にするを言うなり。
鴟鵂夜撮蚤察豪末 鴟鵂(しきゅう)は夜蚤(のみ)を撮り、豪末を察するも、
晝出瞋目而不見丘山 昼に出づれば目を瞋(いか)らすとも丘山を見ず。
言殊性也 性を殊にするを言うなり。
故曰蓋師是而无非 故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を无(む)とし、
師治而无亂乎 治を師として乱を无とせざるやと曰くは、
是未明天地之理萬物之情者也 是未だ天地の理、万物の情に明らかならざる者なり。
是猶師天而无地 是猶(な)お天を師として地を无とし、
師陰而无陽 陰を師として陽を无とするがごとく、
其不可行明矣 其の行なうべからざること明らかなり。
然且語而不舎 然れども且つ語って舎(お)かざるは、
非愚則誣也 愚に非ずして、則ち誣(ふ)なり。
帝王殊禪 三代殊繼 帝王は禅(ぜん)を殊にし、三代は継(けい)を殊にす。
差其時 逆其俗者 其の時に差(たが)い、其の俗に逆らう者、
謂之簒夫 これを簒夫(さんふ)と謂う。
當其時 順其俗者 其の時に当たり、其の俗に順(したが)う者、
謂之義之徒 これを義の徒と謂う。
黙黙乎河伯 黙黙乎(こ)たれ、河伯よ。
女惡知貴賤之門小大之家 女(なんじ)悪(いず)くんぞ貴賤の門、大小の家を知らん。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
むかし、堯と舜とは位を譲って〔平和的に〕帝王となったが、子之(しし)と燕(えん)王の噲(かい)とは位を譲って王位を断絶させた。殷(いん)の湯(とう)王と周の武王とは戦争を起こして〔革命によって〕王となったが、楚(そ)の白公は戦争を起こして殺された。このことから考えると、争って位につくのがよいか、譲りあって位につくのがよいかということは、聖人の堯の行為がよいか、暴君の桀(けつ)の行為がよいかというのと同様に、よいも悪いもその時の状況しだいであって、一定のきまりがあるわけではないのである。家の梁(はり)や棟木(むなぎ)の大木は、それで城壁を突き崩すことはできても、小さい穴はふさげない。それは物それぞれに違った用いどころがあることを物語っている。騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)の駿馬は、一日に千里の道をも走破するが、鼠(ねずみ)を捕らえることでは野猫(やびょう)や鼬(いたち)に及ばない。それは物それぞれに違った技能があることを物語っている。鴟(ふくろう)は夜なかに蚤(のみ)をとらえて細かい毛さきも見わけられるが、昼まに出てくると、いくら目を見張っても大きな山も見えない。それは物それぞれに違った性質があることを物語っている。だから、『どうして善いことに従って悪いことを無視し、治に従って乱を無視しないのか』などというのは、これは天地の道理や万物の実情をさとらないもののことばである。これはちょうど天に従って地を無視し、陰に従って陽を無視するようなもので、とてもうまくいかないことは明白である。にもかかわらず、なおそれを主張してやめないというのは、馬鹿ものでなければごまかしである。
むかしの帝王もその位の伝えかたはさまざまであったし、夏・殷・周の三代もそのつづきかたはさまざまであった。その時代の情勢に従わず、社会の風習に逆らったものを、簒奪者(さんだつしゃ)とよび、その時代の情勢にかない、社会の風習に順応したものを、正義の人とよぶのである。ただ黙っているがよい、河伯よ。貴賤の区別が出てくるところとか大小の区別のありかなど、お前などにどうしてわかろうか。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
むかし、堯と舜は位を譲られて帝王となったが、
燕(えん)の子之(しし)と噲(かい)は位を譲られて王位を途絶えさせた。
殷(いん)の湯(とう)王と周の武王は戦争を起こして王となったが、
楚(そ)の白公は戦争を起こして自滅した。
この比較に由ってこれらを観れば、
争ってのことか譲ってのことか王位継承の儀礼も、
堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、
その<貴賤>の違いはその時の状況次第で、
未だ以て一定の評価を下すことはできないのだ。
家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大きな穴をあけることはできるが、
それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。
それは、器量に違いがあることを物語っている。
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、
ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチには及ばない。
それは、技量に違いがあることを物語っている。
フクロウやミミズクは夜ノミをつまみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、
昼間に出れば、どんなに目をみはっても、丘や山を見ることができない。
それは、性能に違いがあることを物語っている。
故に、『どうして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>にしないのか、
どうして治めることを<師>として、乱れることを<无>にしないのか』と言うのは、
これは未だに天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。
それはまるで天を<師>として地を<无>とし、
陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、
その行いをうまく進めさせられないことは明らかだ。
それにもかかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、
愚(心の内を水鏡のようにしているの)ではなく、
つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこじつけていることになるのだ。
帝王はその王位の譲り方に違いがあり、三王朝はその継承の仕方に違いがあった。
その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、
これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。
その時代の動向に当てはまり、世俗のならわしに順(したが)う者、
これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶだけだ。
(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。
お前にどうしたら貴賤の違いの狭き門や、大小の違いのありかがわかるだろうか。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(8)師と无
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昔者堯舜譲而帝 昔者(むかし)、堯と舜とは譲られて帝たらしも、
之噲譲而絶 之(し)と噲(かい)とは譲られて絶えたり。
湯武爭而王 湯(とう)と武とは争いて王たらしも、
白公爭而滅 白公は争いて滅びたり。
由此観之 此れに由りてこれを観れば、
爭譲之禮 争譲(そうじょう)の礼も、
堯桀之行 堯桀の行も、
貴賤有時 貴賤に時有りて、
未可以爲常也 未だ以て常と為すべからざるなり。
梁麗可以衝城 梁麗(りょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、
而不可以窒穴 以て穴を窒(ふさ)ぐべからず。
言殊器也 器を殊(こと)にするを言うなり。
騏驥驊騮一日而馳千里 騏驥驊騮(ききかりゅう)は一日にして千里を馳するも、
捕鼠不如狸狌 鼠(ねずみ)を捕らうるは狸狌(りせい)に如(し)かず。
言殊技也 技(わざ)を殊にするを言うなり。
鴟鵂夜撮蚤察豪末 鴟鵂(しきゅう)は夜蚤(のみ)を撮り、豪末を察するも、
晝出瞋目而不見丘山 昼に出づれば目を瞋(いか)らすとも丘山を見ず。
言殊性也 性を殊にするを言うなり。
故曰蓋師是而无非 故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を无(む)とし、
師治而无亂乎 治を師として乱を无とせざるやと曰くは、
是未明天地之理萬物之情者也 是未だ天地の理、万物の情に明らかならざる者なり。
是猶師天而无地 是猶(な)お天を師として地を无とし、
師陰而无陽 陰を師として陽を无とするがごとく、
其不可行明矣 其の行なうべからざること明らかなり。
然且語而不舎 然れども且つ語って舎(お)かざるは、
非愚則誣也 愚に非ずして、則ち誣(ふ)なり。
帝王殊禪 三代殊繼 帝王は禅(ぜん)を殊にし、三代は継(けい)を殊にす。
差其時 逆其俗者 其の時に差(たが)い、其の俗に逆らう者、
謂之簒夫 これを簒夫(さんふ)と謂う。
當其時 順其俗者 其の時に当たり、其の俗に順(したが)う者、
謂之義之徒 これを義の徒と謂う。
黙黙乎河伯 黙黙乎(こ)たれ、河伯よ。
女惡知貴賤之門小大之家 女(なんじ)悪(いず)くんぞ貴賤の門、大小の家を知らん。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
むかし、堯と舜とは位を譲って〔平和的に〕帝王となったが、子之(しし)と燕(えん)王の噲(かい)とは位を譲って王位を断絶させた。殷(いん)の湯(とう)王と周の武王とは戦争を起こして〔革命によって〕王となったが、楚(そ)の白公は戦争を起こして殺された。このことから考えると、争って位につくのがよいか、譲りあって位につくのがよいかということは、聖人の堯の行為がよいか、暴君の桀(けつ)の行為がよいかというのと同様に、よいも悪いもその時の状況しだいであって、一定のきまりがあるわけではないのである。家の梁(はり)や棟木(むなぎ)の大木は、それで城壁を突き崩すことはできても、小さい穴はふさげない。それは物それぞれに違った用いどころがあることを物語っている。騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)の駿馬は、一日に千里の道をも走破するが、鼠(ねずみ)を捕らえることでは野猫(やびょう)や鼬(いたち)に及ばない。それは物それぞれに違った技能があることを物語っている。鴟(ふくろう)は夜なかに蚤(のみ)をとらえて細かい毛さきも見わけられるが、昼まに出てくると、いくら目を見張っても大きな山も見えない。それは物それぞれに違った性質があることを物語っている。だから、『どうして善いことに従って悪いことを無視し、治に従って乱を無視しないのか』などというのは、これは天地の道理や万物の実情をさとらないもののことばである。これはちょうど天に従って地を無視し、陰に従って陽を無視するようなもので、とてもうまくいかないことは明白である。にもかかわらず、なおそれを主張してやめないというのは、馬鹿ものでなければごまかしである。
むかしの帝王もその位の伝えかたはさまざまであったし、夏・殷・周の三代もそのつづきかたはさまざまであった。その時代の情勢に従わず、社会の風習に逆らったものを、簒奪者(さんだつしゃ)とよび、その時代の情勢にかない、社会の風習に順応したものを、正義の人とよぶのである。ただ黙っているがよい、河伯よ。貴賤の区別が出てくるところとか大小の区別のありかなど、お前などにどうしてわかろうか。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
むかし、堯と舜は位を譲られて帝王となったが、
燕(えん)の子之(しし)と噲(かい)は位を譲られて王位を途絶えさせた。
殷(いん)の湯(とう)王と周の武王は戦争を起こして王となったが、
楚(そ)の白公は戦争を起こして自滅した。
この比較に由ってこれらを観れば、
争ってのことか譲ってのことか王位継承の儀礼も、
堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、
その<貴賤>の違いはその時の状況次第で、
未だ以て一定の評価を下すことはできないのだ。
家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大きな穴をあけることはできるが、
それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。
それは、器量に違いがあることを物語っている。
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、
ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチには及ばない。
それは、技量に違いがあることを物語っている。
フクロウやミミズクは夜ノミをつまみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、
昼間に出れば、どんなに目をみはっても、丘や山を見ることができない。
それは、性能に違いがあることを物語っている。
故に、『どうして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>にしないのか、
どうして治めることを<師>として、乱れることを<无>にしないのか』と言うのは、
これは未だに天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。
それはまるで天を<師>として地を<无>とし、
陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、
その行いをうまく進めさせられないことは明らかだ。
それにもかかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、
愚(心の内を水鏡のようにしているの)ではなく、
つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこじつけていることになるのだ。
帝王はその王位の譲り方に違いがあり、三王朝はその継承の仕方に違いがあった。
その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、
これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。
その時代の動向に当てはまり、世俗のならわしに順(したが)う者、
これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶだけだ。
(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。
お前にどうしたら貴賤の違いの狭き門や、大小の違いのありかがわかるだろうか。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
|
|
|
コメント(22)
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 昔者堯舜譲而帝 ┃【昔者(むかし)、堯と舜とは譲られて帝たらしも、】
┃ 之噲譲而絶 ┃【之(し)と噲(かい)とは譲られて絶えたり。】
┃ 湯武爭而王 ┃【湯(とう)と武とは争いて王たらしも、】
┃ 白公爭而滅 ┃【白公は争いて滅びたり。】
┗━━━━━━━━━━┛
むかし、堯と舜は位を譲られて帝王となったが、
燕(えん)の子之(しし)と噲(かい)は位を譲られて王位を途絶えさせた。
殷(いん)の湯(とう)王と周の武王は戦争を起こして王となったが、
楚(そ)の白公は戦争を起こして自滅した。
…………………………………………………………………………………………………………
*【之】は戦国時代の燕の宰相、子之のこと。後に燕王を称しました(在位:紀元前316
年 - 紀元前314年)。燕王であった噲の下で宰相をつとめ、国事の全てを決裁していま
した。その後、噲から王位を譲られましたが後に殺されます。
*【噲】は、戦国時代の燕の君主(在位:紀元前320年 - 紀元前318年)。父である先代
の易王から王位を譲られましたが後に殺されます。
*【白公】は、春秋時代の楚(そ)の恵王の時、白公は反乱を起こしました。白公は子西と
子期を殺し、恵王を拉致して高府に置きました。恵王の従者の圉公陽が王を背負って昭
王夫人宮に脱出しました。葉公が蔡から帰国して国人とともに白公を攻めると、白公は
山に逃れて自ら縊死(いし/首吊り)しました。
◆通説では、「【堯舜譲】──堯が世界じゅうから選んで舜を抜擢し、その帝位を譲って、
二人とも聖人とされた。【之噲譲】──戦国時代の燕(えん)の国王の噲は、実力者の宰
相子之(しし)に王位を譲ったが、そのために燕は内乱になり、斉(せい)のために一時滅
ぼされることになった。【白公爭】──白公は春秋時代の楚(そ)の平王の孫。名は勝、
白邑に封ぜられ、公と僭称(せんしょう)した。幼時、父が鄭(てい)国で殺されたので、
鄭を攻めて仇をうとうと進言したがきかれず、ついに反乱して殺された。」と説明して
います。
【譲】は「譲って」と能動態としています。
【昔者(むかし)、堯と舜とは譲りて帝たらしも、之(し)と噲(かい)とは譲りて絶えたり。
湯(とう)と武とは争いて王たらしも、白公は争いて滅びたり。】は「むかし、堯と舜と
は位を譲って〔平和的に〕帝王となったが、子之(しし)と燕(えん)王の噲(かい)とは位
を譲って王位を断絶させた。殷(いん)の湯(とう)王と周の武王とは戦争を起こして〔革
命によって〕王となったが、楚(そ)の白公は戦争を起こして殺された。」としています。
◇【譲】は「譲られて」と受動態にしました。
【昔者(むかし)、堯と舜とは譲られて帝たらしも、之(し)と噲(かい)とは譲られ絶えた
り。湯(とう)と武とは争いて王たらしも、白公は争いて滅びたり。】は「むかし、堯と
舜は位を譲られて帝王となったが、燕(えん)の子之(しし)と噲(かい)は位を譲られて王
位を途絶えさせた。殷(いん)の湯(とう)王と周の武王は戦争を起こして王となったが、
楚(そ)の白公は戦争を起こして自滅した。」としました。
┃▼ 昔者堯舜譲而帝 ┃【昔者(むかし)、堯と舜とは譲られて帝たらしも、】
┃ 之噲譲而絶 ┃【之(し)と噲(かい)とは譲られて絶えたり。】
┃ 湯武爭而王 ┃【湯(とう)と武とは争いて王たらしも、】
┃ 白公爭而滅 ┃【白公は争いて滅びたり。】
┗━━━━━━━━━━┛
むかし、堯と舜は位を譲られて帝王となったが、
燕(えん)の子之(しし)と噲(かい)は位を譲られて王位を途絶えさせた。
殷(いん)の湯(とう)王と周の武王は戦争を起こして王となったが、
楚(そ)の白公は戦争を起こして自滅した。
…………………………………………………………………………………………………………
*【之】は戦国時代の燕の宰相、子之のこと。後に燕王を称しました(在位:紀元前316
年 - 紀元前314年)。燕王であった噲の下で宰相をつとめ、国事の全てを決裁していま
した。その後、噲から王位を譲られましたが後に殺されます。
*【噲】は、戦国時代の燕の君主(在位:紀元前320年 - 紀元前318年)。父である先代
の易王から王位を譲られましたが後に殺されます。
*【白公】は、春秋時代の楚(そ)の恵王の時、白公は反乱を起こしました。白公は子西と
子期を殺し、恵王を拉致して高府に置きました。恵王の従者の圉公陽が王を背負って昭
王夫人宮に脱出しました。葉公が蔡から帰国して国人とともに白公を攻めると、白公は
山に逃れて自ら縊死(いし/首吊り)しました。
◆通説では、「【堯舜譲】──堯が世界じゅうから選んで舜を抜擢し、その帝位を譲って、
二人とも聖人とされた。【之噲譲】──戦国時代の燕(えん)の国王の噲は、実力者の宰
相子之(しし)に王位を譲ったが、そのために燕は内乱になり、斉(せい)のために一時滅
ぼされることになった。【白公爭】──白公は春秋時代の楚(そ)の平王の孫。名は勝、
白邑に封ぜられ、公と僭称(せんしょう)した。幼時、父が鄭(てい)国で殺されたので、
鄭を攻めて仇をうとうと進言したがきかれず、ついに反乱して殺された。」と説明して
います。
【譲】は「譲って」と能動態としています。
【昔者(むかし)、堯と舜とは譲りて帝たらしも、之(し)と噲(かい)とは譲りて絶えたり。
湯(とう)と武とは争いて王たらしも、白公は争いて滅びたり。】は「むかし、堯と舜と
は位を譲って〔平和的に〕帝王となったが、子之(しし)と燕(えん)王の噲(かい)とは位
を譲って王位を断絶させた。殷(いん)の湯(とう)王と周の武王とは戦争を起こして〔革
命によって〕王となったが、楚(そ)の白公は戦争を起こして殺された。」としています。
◇【譲】は「譲られて」と受動態にしました。
【昔者(むかし)、堯と舜とは譲られて帝たらしも、之(し)と噲(かい)とは譲られ絶えた
り。湯(とう)と武とは争いて王たらしも、白公は争いて滅びたり。】は「むかし、堯と
舜は位を譲られて帝王となったが、燕(えん)の子之(しし)と噲(かい)は位を譲られて王
位を途絶えさせた。殷(いん)の湯(とう)王と周の武王は戦争を起こして王となったが、
楚(そ)の白公は戦争を起こして自滅した。」としました。
●通説では、次のようになっています。
むかし、堯と舜とは位を譲って〔平和的に〕帝王となったが、子之(しし)と燕(えん)王の噲(かい)とは位を譲って王位を断絶させた。殷(いん)の湯(とう)王と周の武王とは戦争を起こして〔革命によって〕王となったが、楚(そ)の白公は戦争を起こして殺された。
〇新解釈では、次のようになります。
むかし、堯と舜は位を譲られて帝王となったが、
燕(えん)の子之(しし)と噲(かい)は位を譲られて王位を途絶えさせた。
殷(いん)の湯(とう)王と周の武王は戦争を起こして王となったが、
楚(そ)の白公は戦争を起こして自滅した。
【昔者堯舜譲而帝】【昔者(むかし)、堯と舜とは譲られ帝たらしも、】
〔むかし、堯と舜は位を譲られて帝王となったが、〕
──『史記』「五帝本紀」によれば、堯は嚳(こく)の次子として生まれ、嚳の後を継いだ兄の死後譲られて帝となりました。「その仁は天のごとく、その知は神のごとく」などと最大級の賛辞で描かれています。
禅譲に当たり、堯には息子がいましたが、臣下から推薦者を挙げさせました。みなが舜を跡継ぎに挙げ、性質がよくない父と母、弟に囲まれながら、彼らが悪に陥らないよう導いていると言ったのでした。堯は舜に興味を示し、二人の娘を嫁せました。それから民と官吏を3年間治めさせたところ、功績が著しかったため、舜に譲位することにしました。舜は固辞しましたが、強いて天子の政を行なわせたのでした。
【之噲譲而絶】【之(し)と噲(かい)とは譲られ絶えたり。】
〔子之(しし)と噲(かい)は王位を譲られて国を途絶えさせた。〕
──燕(えん)の噲(かい)は王位を譲られても、王としての能力に欠けており、酒色に溺れ、逸楽だけに貪って朝廷で政治を行おうとしませんでした。国政を宰相の子之に任せっきりにして表舞台から隠退同然の生活を送っていました。
その後、子之は噲から王位を譲られました。しかし内乱が起こり燕は荒廃していました。これを機とみた斉の宣王が将軍の匡章を派遣して燕を攻撃しました。国都が陥落して、噲は殺害され、子之は逃亡しましたが、後に捕らえられて殺害されました。
王位を譲られても、不幸な運命にあったと言えそうです。
【湯武爭而王】【湯(とう)と武とは争いて王たらしも、】
〔湯(とう)王と武王は戦争を起こして王となったが、〕
──前にも同じことを説明しましたが、夏の第17代の暴君だった桀(けつ)王の時、湯(とう)王が彼を滅ぼして殷王朝を創始しました。そして殷の第30代のこれまた暴君だった紂(ちゅう)王の時、武王が彼を滅ぼして、周王朝になりました。
一般的評価としては、桀王と紂王の両者に共通することは、有名な暴君だったということです。その政治を辞めされるために攻めらて、真っ当な政治をするために戦争を起こされたという経緯です。こういった事情があるとこれまた一方的に単純に戦争だけが悪いとも言えなくなりそうです。
【白公爭而滅】【白公は争いて滅びたり。】
〔白公は戦争を起こして自滅した。〕
──白公は、紀元前487年に鄭(てい)の公孫喬によって殺害された亡父の恨みを忘れず、その仇を討つべく、昭王の太子であった従弟の恵王に上奏しました。しかし、聞き入れてもらえなかったのです。そこで紀元前479年夏6月に白公は反旗を翻して、刺客の石乞に命じて宮中で、公子申の弟で(白公の)叔父の司馬の公子結と公子啓を暗殺させたのでした。さらに、恵王を別邸で幽閉しましたが、恵王はひそかに一族の屈固に救助されて、継母の邸宅に匿われました。
白公は自ら「楚王」と称しましたが、翌秋7月に恵王が一族の葉公の沈戌の子である沈諸梁に命じて、白公を攻撃させて彼を山中に追い詰めました。その結果白公は自決することになったのです。
戦争をして王位を奪おうとしても、失敗して不幸な運命にあったと言えそうです。
むかし、堯と舜とは位を譲って〔平和的に〕帝王となったが、子之(しし)と燕(えん)王の噲(かい)とは位を譲って王位を断絶させた。殷(いん)の湯(とう)王と周の武王とは戦争を起こして〔革命によって〕王となったが、楚(そ)の白公は戦争を起こして殺された。
〇新解釈では、次のようになります。
むかし、堯と舜は位を譲られて帝王となったが、
燕(えん)の子之(しし)と噲(かい)は位を譲られて王位を途絶えさせた。
殷(いん)の湯(とう)王と周の武王は戦争を起こして王となったが、
楚(そ)の白公は戦争を起こして自滅した。
【昔者堯舜譲而帝】【昔者(むかし)、堯と舜とは譲られ帝たらしも、】
〔むかし、堯と舜は位を譲られて帝王となったが、〕
──『史記』「五帝本紀」によれば、堯は嚳(こく)の次子として生まれ、嚳の後を継いだ兄の死後譲られて帝となりました。「その仁は天のごとく、その知は神のごとく」などと最大級の賛辞で描かれています。
禅譲に当たり、堯には息子がいましたが、臣下から推薦者を挙げさせました。みなが舜を跡継ぎに挙げ、性質がよくない父と母、弟に囲まれながら、彼らが悪に陥らないよう導いていると言ったのでした。堯は舜に興味を示し、二人の娘を嫁せました。それから民と官吏を3年間治めさせたところ、功績が著しかったため、舜に譲位することにしました。舜は固辞しましたが、強いて天子の政を行なわせたのでした。
【之噲譲而絶】【之(し)と噲(かい)とは譲られ絶えたり。】
〔子之(しし)と噲(かい)は王位を譲られて国を途絶えさせた。〕
──燕(えん)の噲(かい)は王位を譲られても、王としての能力に欠けており、酒色に溺れ、逸楽だけに貪って朝廷で政治を行おうとしませんでした。国政を宰相の子之に任せっきりにして表舞台から隠退同然の生活を送っていました。
その後、子之は噲から王位を譲られました。しかし内乱が起こり燕は荒廃していました。これを機とみた斉の宣王が将軍の匡章を派遣して燕を攻撃しました。国都が陥落して、噲は殺害され、子之は逃亡しましたが、後に捕らえられて殺害されました。
王位を譲られても、不幸な運命にあったと言えそうです。
【湯武爭而王】【湯(とう)と武とは争いて王たらしも、】
〔湯(とう)王と武王は戦争を起こして王となったが、〕
──前にも同じことを説明しましたが、夏の第17代の暴君だった桀(けつ)王の時、湯(とう)王が彼を滅ぼして殷王朝を創始しました。そして殷の第30代のこれまた暴君だった紂(ちゅう)王の時、武王が彼を滅ぼして、周王朝になりました。
一般的評価としては、桀王と紂王の両者に共通することは、有名な暴君だったということです。その政治を辞めされるために攻めらて、真っ当な政治をするために戦争を起こされたという経緯です。こういった事情があるとこれまた一方的に単純に戦争だけが悪いとも言えなくなりそうです。
【白公爭而滅】【白公は争いて滅びたり。】
〔白公は戦争を起こして自滅した。〕
──白公は、紀元前487年に鄭(てい)の公孫喬によって殺害された亡父の恨みを忘れず、その仇を討つべく、昭王の太子であった従弟の恵王に上奏しました。しかし、聞き入れてもらえなかったのです。そこで紀元前479年夏6月に白公は反旗を翻して、刺客の石乞に命じて宮中で、公子申の弟で(白公の)叔父の司馬の公子結と公子啓を暗殺させたのでした。さらに、恵王を別邸で幽閉しましたが、恵王はひそかに一族の屈固に救助されて、継母の邸宅に匿われました。
白公は自ら「楚王」と称しましたが、翌秋7月に恵王が一族の葉公の沈戌の子である沈諸梁に命じて、白公を攻撃させて彼を山中に追い詰めました。その結果白公は自決することになったのです。
戦争をして王位を奪おうとしても、失敗して不幸な運命にあったと言えそうです。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 由此観之 ┃【此れに由りてこれを観れば、】
┃ 爭譲之禮 ┃【争譲(そうじょう)の礼も、】
┃ 堯桀之行 ┃【堯桀の行も、】
┃ 貴賤有時 ┃【貴賤に時有りて、】
┃ 未可以爲常也 ┃【未だ以て常と為すべからざるなり。】
┗━━━━━━━━━┛
この比較に由ってこれらを観れば、
争ってのことか譲ってのことか王位継承の儀礼も、
堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、
その<貴賤>の違いはその時代の状況次第で、
未だ以て一定の評価を下すことはできないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【禮(礼)】は「示(祭壇)+豊(たかつきに形よくお供えを盛ったさま)」で、「形よく整え
られた祭礼」を示します。
*【時】は「日+寸(て)+止(あし)」で「日が進行すること。」「時間。」「時代。そのこ
ろ。その時代の状況。」「適当な時機。ころあい。機会。」「適時の。よいしおどき。」
*【常】は形声文字で「つね(いつまでも同じ姿でかわらないこと。いつまでも長く続いて
かわらない物事や道理)。」「一定していること。」
◆通説では、【此れに由りてこれを観れば、争譲(そうじょう)の礼、堯桀の行も、貴賤に
時有りて、未だ以て常と為すべからざるなり。】は「このことから考えると、争って位
につくのがよいか、譲りあって位につくのがよいかということは、聖人の堯の行為がよ
いか、暴君の桀(けつ)の行為がよいかというのと同様に、よいも悪いもその時の状況し
だいであって、一定のきまりがあるわけではないのである。」と意訳しています。
◇【由此観之】は「以上のことから考えてみると」という意味の常套句ですが、【此】と
いう字を荘子が用いる時、いつもそれまでのことを「ならべて比較する」時に用いてい
ることから、あえて「この比較に由ってこれらを観れば」と訳しました。
【此れに由りてこれを観れば、争譲(そうじょう)の礼も堯桀の行も、貴賤に時有りて、
未だ以て常と為すべからざるなり。】は「この比較に由ってこれらを観れば、争っての
ことか譲ってのことか王位継承の儀礼も、堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、その
<貴賤>の違いはその時の状況次第で、未だ以て一定の評価を下すことはできないの
だ。」としました。
┃▼ 由此観之 ┃【此れに由りてこれを観れば、】
┃ 爭譲之禮 ┃【争譲(そうじょう)の礼も、】
┃ 堯桀之行 ┃【堯桀の行も、】
┃ 貴賤有時 ┃【貴賤に時有りて、】
┃ 未可以爲常也 ┃【未だ以て常と為すべからざるなり。】
┗━━━━━━━━━┛
この比較に由ってこれらを観れば、
争ってのことか譲ってのことか王位継承の儀礼も、
堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、
その<貴賤>の違いはその時代の状況次第で、
未だ以て一定の評価を下すことはできないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【禮(礼)】は「示(祭壇)+豊(たかつきに形よくお供えを盛ったさま)」で、「形よく整え
られた祭礼」を示します。
*【時】は「日+寸(て)+止(あし)」で「日が進行すること。」「時間。」「時代。そのこ
ろ。その時代の状況。」「適当な時機。ころあい。機会。」「適時の。よいしおどき。」
*【常】は形声文字で「つね(いつまでも同じ姿でかわらないこと。いつまでも長く続いて
かわらない物事や道理)。」「一定していること。」
◆通説では、【此れに由りてこれを観れば、争譲(そうじょう)の礼、堯桀の行も、貴賤に
時有りて、未だ以て常と為すべからざるなり。】は「このことから考えると、争って位
につくのがよいか、譲りあって位につくのがよいかということは、聖人の堯の行為がよ
いか、暴君の桀(けつ)の行為がよいかというのと同様に、よいも悪いもその時の状況し
だいであって、一定のきまりがあるわけではないのである。」と意訳しています。
◇【由此観之】は「以上のことから考えてみると」という意味の常套句ですが、【此】と
いう字を荘子が用いる時、いつもそれまでのことを「ならべて比較する」時に用いてい
ることから、あえて「この比較に由ってこれらを観れば」と訳しました。
【此れに由りてこれを観れば、争譲(そうじょう)の礼も堯桀の行も、貴賤に時有りて、
未だ以て常と為すべからざるなり。】は「この比較に由ってこれらを観れば、争っての
ことか譲ってのことか王位継承の儀礼も、堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、その
<貴賤>の違いはその時の状況次第で、未だ以て一定の評価を下すことはできないの
だ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
このことから考えると、争って位につくのがよいか、譲りあって位につくのがよいかということは、聖人の堯の行為がよいか、暴君の桀(けつ)の行為がよいかというのと同様に、よいも悪いもその時の状況しだいであって、一定のきまりがあるわけではないのである。
〇新解釈では、次のようになります。
この比較に由ってこれらを観れば、
争ってのことか譲ってのことか王位継承の儀礼も、
堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、
その<貴賤>の違いはその時の状況次第で、
未だ以て一定の評価を下すことはできないのだ。
【由此観之】【此れに由りてこれを観れば、】
〔この比較に由ってこれらを観れば、〕
──王位に就くのを評価するのは様々な背景や経緯があることを忘れてはなりません。国政に就いても様々な施策の評価は分かれるところです。簡単に比較することができず、複雑な事情があることを考慮してものごとを観たならば、どのような評価が下せるでしょうか。
【爭譲之禮】【争譲(そうじょう)の礼も、】
〔争ってのことか譲られてのことか、王位継承の儀礼も、〕
──王位を継承するといった節目の儀礼を執り行うことになるまでに、争って勝ち取るがいいのか、譲られて受け入れるのがいいのかわかったものではないようです。
【堯桀之行】【堯桀の行も、】
〔堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、〕
──堯は徳によって国を治めようとしましたが、その徳の施行が過剰に働き、他国においてもそうでないとみると矯正しようと手を出して、国王を殺すなどして正義を貫こうとする傾向にあったようです。
一方、桀は武力によって国を治めようとしました。また、桀は有施氏を討った際に末喜という美女を捕らえ、自らの妃としましたが、桀は末喜に溺れ、政治を省みなくなりました。豪華な宴会を催し、国力は衰えていきました。
【貴賤有時】【貴賤に時有りて、】
〔その<貴賤>の違いはその時の状況次第で、〕
──世間では、王位継承は譲った方が<貴>、争った方が<賤>と見なす傾向があるかもしれません。また、堯は聖君、桀は暴君、つまり、堯は<貴>、桀は<賤>の代表的な比較対象とされていますが、前にも説明したとおり、北海若(荘子)は、そんな固定概念にとらわれていません。時代背景、時代情勢次第で、その評価は違ってくる…と言っているようです。
【未可以爲常也】【未だ以て常と為すべからざるなり。】
〔未だ以て一定の評価を下すことはできないのだ。〕
──王位を譲られるのも<貴賤>の評価はあいまいなのです。かといって、王位を争うのも<貴賤>の評価も偏った見方で決めつけることはできないようです。世間で聖君と言われようとも暴君と言われようとも、実情はどちらが<貴>で、どちらが<賤>なのか、一定の評価を下すことはできない…ということのようですね。
このことから考えると、争って位につくのがよいか、譲りあって位につくのがよいかということは、聖人の堯の行為がよいか、暴君の桀(けつ)の行為がよいかというのと同様に、よいも悪いもその時の状況しだいであって、一定のきまりがあるわけではないのである。
〇新解釈では、次のようになります。
この比較に由ってこれらを観れば、
争ってのことか譲ってのことか王位継承の儀礼も、
堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、
その<貴賤>の違いはその時の状況次第で、
未だ以て一定の評価を下すことはできないのだ。
【由此観之】【此れに由りてこれを観れば、】
〔この比較に由ってこれらを観れば、〕
──王位に就くのを評価するのは様々な背景や経緯があることを忘れてはなりません。国政に就いても様々な施策の評価は分かれるところです。簡単に比較することができず、複雑な事情があることを考慮してものごとを観たならば、どのような評価が下せるでしょうか。
【爭譲之禮】【争譲(そうじょう)の礼も、】
〔争ってのことか譲られてのことか、王位継承の儀礼も、〕
──王位を継承するといった節目の儀礼を執り行うことになるまでに、争って勝ち取るがいいのか、譲られて受け入れるのがいいのかわかったものではないようです。
【堯桀之行】【堯桀の行も、】
〔堯と桀の(対照的な)国を治める行為も、〕
──堯は徳によって国を治めようとしましたが、その徳の施行が過剰に働き、他国においてもそうでないとみると矯正しようと手を出して、国王を殺すなどして正義を貫こうとする傾向にあったようです。
一方、桀は武力によって国を治めようとしました。また、桀は有施氏を討った際に末喜という美女を捕らえ、自らの妃としましたが、桀は末喜に溺れ、政治を省みなくなりました。豪華な宴会を催し、国力は衰えていきました。
【貴賤有時】【貴賤に時有りて、】
〔その<貴賤>の違いはその時の状況次第で、〕
──世間では、王位継承は譲った方が<貴>、争った方が<賤>と見なす傾向があるかもしれません。また、堯は聖君、桀は暴君、つまり、堯は<貴>、桀は<賤>の代表的な比較対象とされていますが、前にも説明したとおり、北海若(荘子)は、そんな固定概念にとらわれていません。時代背景、時代情勢次第で、その評価は違ってくる…と言っているようです。
【未可以爲常也】【未だ以て常と為すべからざるなり。】
〔未だ以て一定の評価を下すことはできないのだ。〕
──王位を譲られるのも<貴賤>の評価はあいまいなのです。かといって、王位を争うのも<貴賤>の評価も偏った見方で決めつけることはできないようです。世間で聖君と言われようとも暴君と言われようとも、実情はどちらが<貴>で、どちらが<賤>なのか、一定の評価を下すことはできない…ということのようですね。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 梁麗可以衝城 ┃【梁麗(りょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、】
┃ 而不可以窒穴 ┃【以て穴を窒(ふさ)ぐべからず。】
┃ 言殊器也 ┃【器を殊(こと)にするを言うなり。】
┗━━━━━━━━━┛
家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大きな穴をあけることはできるが、
それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。
それは、器量に違いがあることを物語っている。
…………………………………………………………………………………………………………
*【梁】は、「水+刅(両がわに刃のついた刀)+木」で、「左右の両岸に支柱を立て、その
上にかけた木のはし。」「はし。」「はり(屋根をささえる材)。」
*【麗】は、「鹿の角がきれいに二本ならんだ姿」を描いた象形文字。「ならぶ。」「つく
・つける。」「かかる(ひっかかる)。」「うるわしい」は派生義。
*【衝】は、「行+重(人が地上をつきぬくように、とんと重みをかける)」で、「どんとつ
きぬける大通りのこと。」また「つきぬく勢いでぶちあたること。」
*【窒】は、「穴(あな)+至(矢が一線にとどいて、その先に勧めなこと。」「ふさぐ。」
*【器】は、「口四つ+犬」で「さまざまな容器」を示します。「うつわ(いろいろな入れ
物」。「うつわ(才能)」。「こまごました実用にだけ役立つもの」。
*【殊】は、「歹(死ぬ)+朱(木を一印で切断するさま・切り株)」で、「株を切るように切
断して殺すこと。」「たつ(株を切るように胴切りにする)。」「ことなる・ことにする
(普通とまったく違う)。」
◆通説では、【梁麗(じょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、以て穴を窒(ふさ)ぐべから
ずとは、器を殊(こと)にするを言えるなり。】は「家の梁(はり)や棟木(むなぎ)の大
木は、それで城壁を突き崩すことはできても、小さい穴はふさげない。それは物それぞ
れに違った用いどころがあることを物語っている。」としています。
◇【梁麗(じょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、以て穴を窒(ふさ)ぐべからずず。器を
殊(こと)にするを言うなり。】は「家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大き
な穴をあけることはできるが、それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。そ
れは、器量に違いがあることを物語っている。」としました。
┃▼ 梁麗可以衝城 ┃【梁麗(りょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、】
┃ 而不可以窒穴 ┃【以て穴を窒(ふさ)ぐべからず。】
┃ 言殊器也 ┃【器を殊(こと)にするを言うなり。】
┗━━━━━━━━━┛
家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大きな穴をあけることはできるが、
それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。
それは、器量に違いがあることを物語っている。
…………………………………………………………………………………………………………
*【梁】は、「水+刅(両がわに刃のついた刀)+木」で、「左右の両岸に支柱を立て、その
上にかけた木のはし。」「はし。」「はり(屋根をささえる材)。」
*【麗】は、「鹿の角がきれいに二本ならんだ姿」を描いた象形文字。「ならぶ。」「つく
・つける。」「かかる(ひっかかる)。」「うるわしい」は派生義。
*【衝】は、「行+重(人が地上をつきぬくように、とんと重みをかける)」で、「どんとつ
きぬける大通りのこと。」また「つきぬく勢いでぶちあたること。」
*【窒】は、「穴(あな)+至(矢が一線にとどいて、その先に勧めなこと。」「ふさぐ。」
*【器】は、「口四つ+犬」で「さまざまな容器」を示します。「うつわ(いろいろな入れ
物」。「うつわ(才能)」。「こまごました実用にだけ役立つもの」。
*【殊】は、「歹(死ぬ)+朱(木を一印で切断するさま・切り株)」で、「株を切るように切
断して殺すこと。」「たつ(株を切るように胴切りにする)。」「ことなる・ことにする
(普通とまったく違う)。」
◆通説では、【梁麗(じょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、以て穴を窒(ふさ)ぐべから
ずとは、器を殊(こと)にするを言えるなり。】は「家の梁(はり)や棟木(むなぎ)の大
木は、それで城壁を突き崩すことはできても、小さい穴はふさげない。それは物それぞ
れに違った用いどころがあることを物語っている。」としています。
◇【梁麗(じょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、以て穴を窒(ふさ)ぐべからずず。器を
殊(こと)にするを言うなり。】は「家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大き
な穴をあけることはできるが、それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。そ
れは、器量に違いがあることを物語っている。」としました。
●通説では、次のようになっています。
家の梁(はり)や棟木(むなぎ)の大木は、それで城壁を突き崩すことはできても、小さい穴はふさげない。それは物それぞれに違った用いどころがあることを物語っている。
〇新解釈では、次のようになります。
家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大きな穴をあけることはできるが、
それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。
それは、器量に違いがあることを物語っている。
【梁麗可以衝城】【梁麗(りょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、】
【而不可以窒穴】【以て穴を窒(ふさ)ぐべからず。】
〔家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大きな穴をあけることはできるが、〕
〔それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。〕
──「梁(はり)」は支柱の上で屋根を支える数本の大木です。「麗」は、通説では「棟木」としていますが、それは屋根の頂上に一本だけ用いるものです。新解釈では、字源からすると、「麗」は「二つがきれいに並んでいること」を意味することから、「梁」を取り付けるために垂直に位置する二本並んだ「桁(けた)」のことではないかと推察しました。「桁」も「梁」同様に屋根を支える重要な大木です。
「梁や桁」を用いたならば、頑丈に作られている城壁でさえ突き抜いて、「大きな穴をあける」という役を果たすことはできても、「小さな穴を窒(ふさ)ぐ」という役は担うことはできない…と言っているようです。
【言殊器也】【器を殊(こと)にするを言うなり。】
〔それは、器量に違いがあることを物語っている。〕
──どんなものにもそれなりの「器」があり、その「役割、才能」はそれぞれ違っていると言えるのだ…と言っているようです。
なんでも「大きいことがいいことだ、すばらしいのだ」とは言えないことがはっきりわかる例だと言えそうです。
家の梁(はり)や棟木(むなぎ)の大木は、それで城壁を突き崩すことはできても、小さい穴はふさげない。それは物それぞれに違った用いどころがあることを物語っている。
〇新解釈では、次のようになります。
家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大きな穴をあけることはできるが、
それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。
それは、器量に違いがあることを物語っている。
【梁麗可以衝城】【梁麗(りょうれい)は以て城を衝(つ)くべきも、】
【而不可以窒穴】【以て穴を窒(ふさ)ぐべからず。】
〔家の梁(はり)や桁(けた)で以て、城壁を衝いて大きな穴をあけることはできるが、〕
〔それで以て、小さな穴を窒(ふさ)ぐことはできない。〕
──「梁(はり)」は支柱の上で屋根を支える数本の大木です。「麗」は、通説では「棟木」としていますが、それは屋根の頂上に一本だけ用いるものです。新解釈では、字源からすると、「麗」は「二つがきれいに並んでいること」を意味することから、「梁」を取り付けるために垂直に位置する二本並んだ「桁(けた)」のことではないかと推察しました。「桁」も「梁」同様に屋根を支える重要な大木です。
「梁や桁」を用いたならば、頑丈に作られている城壁でさえ突き抜いて、「大きな穴をあける」という役を果たすことはできても、「小さな穴を窒(ふさ)ぐ」という役は担うことはできない…と言っているようです。
【言殊器也】【器を殊(こと)にするを言うなり。】
〔それは、器量に違いがあることを物語っている。〕
──どんなものにもそれなりの「器」があり、その「役割、才能」はそれぞれ違っていると言えるのだ…と言っているようです。
なんでも「大きいことがいいことだ、すばらしいのだ」とは言えないことがはっきりわかる例だと言えそうです。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 騏驥驊騮一日而馳千里 ┃【騏驥驊騮は一日にして千里を馳するも、】
┃ 捕鼠不如狸狌 ┃【鼠を捕らうるは狸狌(りせい)に如(し)かず。】
┃ 言殊技也 ┃【技(わざ)を殊にするを言うなり。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、
ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチには及ばない。
それは、技量に違いがあることを物語っている。
…………………………………………………………………………………………………………
*【騏】(き)は、「よく走るすぐれた馬のこと。駿馬。」「青黒色。くろみどり。」
*【驥】(き)は、「一日千里をいくというすぐれた馬のこと。すぐれた馬。」
*【騏驥】で一頭の馬を表すこともあります。
*【驊】(か)は、「すぐれたよい馬」。
*【騮】(りゅう)は、「くりげ。つやのある黒いたてがみをした赤毛の馬。また、つやの
ある黒い尾をした赤毛の馬」。
*【驊騮】とは、周の穆(ぼく)王が持っていた八頭の名馬のうちの一頭の名。穆王が天下
を周遊するときに乗ったという。
*【狸】は、「むじな。」「たぬき。」
*【狌】は、「いたち。」
*【技】は、「手+支(細かい枝を手に持つさま)」で、「細い枝のような細かい手細工の
こと。」
◆通説では、【騏驥驊騮(ききかりゅう)は一日にして千里を馳するも、鼠(ねずみ)を捕ら
うるは狸狌(りせい)に如(し)かずとは、技(わざ)を殊にするを言えるなり。】は「騏驥
(きき)や驊騮(かりゅう)の駿馬は、一日に千里の道をも走破するが、鼠(ねずみ)を捕ら
えることでは野猫(やびょう)や鼬(いたち)に及ばない。それは物それぞれに違った技能
があることを物語っている。」としています。
◇【騏驥驊騮(ききかりゅう)は一日にして千里を馳するも、鼠(ねずみ)を捕らうるは狸狌
(りせい)に如(し)かず。技(わざ)を殊にするを言うなり。】は「騏驥(きき)や驊騮(か
りゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、ネズミを捕らえることにおいては、
タヌキやイタチには及ばない。それは、技量に違いがあることを物語っている。」とし
ました。
┃▼ 騏驥驊騮一日而馳千里 ┃【騏驥驊騮は一日にして千里を馳するも、】
┃ 捕鼠不如狸狌 ┃【鼠を捕らうるは狸狌(りせい)に如(し)かず。】
┃ 言殊技也 ┃【技(わざ)を殊にするを言うなり。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、
ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチには及ばない。
それは、技量に違いがあることを物語っている。
…………………………………………………………………………………………………………
*【騏】(き)は、「よく走るすぐれた馬のこと。駿馬。」「青黒色。くろみどり。」
*【驥】(き)は、「一日千里をいくというすぐれた馬のこと。すぐれた馬。」
*【騏驥】で一頭の馬を表すこともあります。
*【驊】(か)は、「すぐれたよい馬」。
*【騮】(りゅう)は、「くりげ。つやのある黒いたてがみをした赤毛の馬。また、つやの
ある黒い尾をした赤毛の馬」。
*【驊騮】とは、周の穆(ぼく)王が持っていた八頭の名馬のうちの一頭の名。穆王が天下
を周遊するときに乗ったという。
*【狸】は、「むじな。」「たぬき。」
*【狌】は、「いたち。」
*【技】は、「手+支(細かい枝を手に持つさま)」で、「細い枝のような細かい手細工の
こと。」
◆通説では、【騏驥驊騮(ききかりゅう)は一日にして千里を馳するも、鼠(ねずみ)を捕ら
うるは狸狌(りせい)に如(し)かずとは、技(わざ)を殊にするを言えるなり。】は「騏驥
(きき)や驊騮(かりゅう)の駿馬は、一日に千里の道をも走破するが、鼠(ねずみ)を捕ら
えることでは野猫(やびょう)や鼬(いたち)に及ばない。それは物それぞれに違った技能
があることを物語っている。」としています。
◇【騏驥驊騮(ききかりゅう)は一日にして千里を馳するも、鼠(ねずみ)を捕らうるは狸狌
(りせい)に如(し)かず。技(わざ)を殊にするを言うなり。】は「騏驥(きき)や驊騮(か
りゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、ネズミを捕らえることにおいては、
タヌキやイタチには及ばない。それは、技量に違いがあることを物語っている。」とし
ました。
●通説では、次のようになっています。
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)の駿馬は、一日に千里の道をも走破するが、鼠(ねずみ)を捕らえることでは野猫(やびょう)や鼬(いたち)に及ばない。それは物それぞれに違った技能があることを物語っている。
〇新解釈では、次のようになります。
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、
ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチには及ばない。
それは、技量に違いがあることを物語っている。
【騏驥驊騮一日而馳千里】【騏驥驊騮は一日にして千里を馳するも、】
【捕鼠不如狸狌】【鼠を捕らうるは狸狌(りせい)に如(し)かず。】
〔騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、〕
〔ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチには及ばない。〕
──馬において「すぐれている」とされるものは、短距離を猛スピードで駆けぬくものか、長距離をハイペースで走れるタフなものか、重い荷物を運べる馬力のあるものかでしょう。
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)は、一日に千里も走れるタフな馬だったようです。すばらしい能力です。
ところが、ネズミを捕らえられるかというと、それはできません。そんな能力は備わっていないからです。
ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチに及びもしません。
通説で、「狸」が「野猫」と訳されていますが、「タヌキ」のままで問題ないと思います。タヌキは雑食です。ドングリやクリなどを含む果実、植物の茎、根、葉など、そして昆虫やミミズなども食べているようです。さらに住む場所によってネズミや鳥(卵も)、ヘビやトカゲなどの爬虫類、カニやウニなどの甲殻類を食べることもあるということです。
イタチは動物性の餌を食べる傾向が強く、主にネズミを中心に捕食しているようです。
ですからネズミを捕らえることにおいては、その習性からタヌキやイタチはすばらしい能力を持っていると言えそうです。
【言殊技也】【技(わざ)を殊にするを言うなり。】
〔それは、技量に違いがあることを物語っている。〕
──このようにそれぞれ生まれ付き持っている能力、スキルが違うのです。つまり、技量が違うのです。どちらが「すばらしい」かなどは単純に決められません。
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)の駿馬は、一日に千里の道をも走破するが、鼠(ねずみ)を捕らえることでは野猫(やびょう)や鼬(いたち)に及ばない。それは物それぞれに違った技能があることを物語っている。
〇新解釈では、次のようになります。
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、
ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチには及ばない。
それは、技量に違いがあることを物語っている。
【騏驥驊騮一日而馳千里】【騏驥驊騮は一日にして千里を馳するも、】
【捕鼠不如狸狌】【鼠を捕らうるは狸狌(りせい)に如(し)かず。】
〔騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)といった駿馬は、一日に千里も馳せるが、〕
〔ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチには及ばない。〕
──馬において「すぐれている」とされるものは、短距離を猛スピードで駆けぬくものか、長距離をハイペースで走れるタフなものか、重い荷物を運べる馬力のあるものかでしょう。
騏驥(きき)や驊騮(かりゅう)は、一日に千里も走れるタフな馬だったようです。すばらしい能力です。
ところが、ネズミを捕らえられるかというと、それはできません。そんな能力は備わっていないからです。
ネズミを捕らえることにおいては、タヌキやイタチに及びもしません。
通説で、「狸」が「野猫」と訳されていますが、「タヌキ」のままで問題ないと思います。タヌキは雑食です。ドングリやクリなどを含む果実、植物の茎、根、葉など、そして昆虫やミミズなども食べているようです。さらに住む場所によってネズミや鳥(卵も)、ヘビやトカゲなどの爬虫類、カニやウニなどの甲殻類を食べることもあるということです。
イタチは動物性の餌を食べる傾向が強く、主にネズミを中心に捕食しているようです。
ですからネズミを捕らえることにおいては、その習性からタヌキやイタチはすばらしい能力を持っていると言えそうです。
【言殊技也】【技(わざ)を殊にするを言うなり。】
〔それは、技量に違いがあることを物語っている。〕
──このようにそれぞれ生まれ付き持っている能力、スキルが違うのです。つまり、技量が違うのです。どちらが「すばらしい」かなどは単純に決められません。
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 鴟鵂夜撮蚤察豪末 ┃【鴟鵂(しきゅう)は夜蚤(のみ)を撮り豪末を察するも、】
┃ 晝出瞋目而不見丘山 ┃【昼に出づれば目を瞋(いか)らすとも丘山を見ず。】
┃ 言殊性也 ┃【性を殊にするを言うなり。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
フクロウやミミズクは夜ノミをつまみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、
昼間に出れば、どんなに目をみはっても、丘や山を見ることができない。
それは、性能に違いがあることを物語っている。
…………………………………………………………………………………………………………
*【鴟】は、「じっと止まっている鳥。」「トビ。」「フクロウ。」
*【鵂】は、「昼間は木かげで休んでいる鳥。」「ミミズク。」
*【晝(昼)】は、「筆を手に持つ姿+日を四つにくぎった形」で、「日の照る時間をここか
らここまでと筆でくぎって書くさま」を示します。
*【撮】の「最」は、「曰(おかす) +取」からなり、「ごく少量をおかしてとること。」
【撮】は「手+最」で、「親指、人差し指、中指の三本でごく少量をつまみとること。」
「つまむ。」「とる(必要な部分だけとる」。(撮影の意味は日本だけ。)
*【察】は、前にも説明しましたが、「宀(やね)+祭(お供えの肉をすみずみまで清めるこ
と)」で、「家のすみずみまで、曇りなく清めること」。転じて「曇りなく目をきかす」
意。
*【瞋】は、「目+眞(ごちそうをいっぱいにつめこむこと)」で、「目のわくいっぱいに目
をむき出すこと。」
*【性】は、「心+生(芽が地上に生え出るさま)」で、「うまれつきのすみきった心。」
◆通説では【鵂】は省略されています。あったとしても二字とも「ふくろうの類」を指す
としています。
【鴟 (し)は夜蚤(のみ)を撮り豪末を察するも、昼に出づれば目を瞋(みは)るとも丘山を
見ずとは、性を殊にするを言えるなり。】は「鴟(ふくろう)は夜なかに蚤(のみ)をとら
えて細かい毛さきも見わけられるが、昼まに出てくると、いくら目を見張っても大きな
山も見えない。それは物それぞれに違った性質があることを物語っている。」としてい
ます。
◇【鴟鵂(しきゅう)は夜蚤(のみ)を撮り豪末を察するも、昼に出づれば目を瞋(いか)らす
とも丘山を見ず。性を殊にするを言うなり。】は、「フクロウやミミズクは夜ノミをつ
まみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、昼間に出れば、どんなに目をみは
っても、丘や山を見ることができない。それは、性能に違いがあることを物語ってい
る。」としました。
┃▼ 鴟鵂夜撮蚤察豪末 ┃【鴟鵂(しきゅう)は夜蚤(のみ)を撮り豪末を察するも、】
┃ 晝出瞋目而不見丘山 ┃【昼に出づれば目を瞋(いか)らすとも丘山を見ず。】
┃ 言殊性也 ┃【性を殊にするを言うなり。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
フクロウやミミズクは夜ノミをつまみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、
昼間に出れば、どんなに目をみはっても、丘や山を見ることができない。
それは、性能に違いがあることを物語っている。
…………………………………………………………………………………………………………
*【鴟】は、「じっと止まっている鳥。」「トビ。」「フクロウ。」
*【鵂】は、「昼間は木かげで休んでいる鳥。」「ミミズク。」
*【晝(昼)】は、「筆を手に持つ姿+日を四つにくぎった形」で、「日の照る時間をここか
らここまでと筆でくぎって書くさま」を示します。
*【撮】の「最」は、「曰(おかす) +取」からなり、「ごく少量をおかしてとること。」
【撮】は「手+最」で、「親指、人差し指、中指の三本でごく少量をつまみとること。」
「つまむ。」「とる(必要な部分だけとる」。(撮影の意味は日本だけ。)
*【察】は、前にも説明しましたが、「宀(やね)+祭(お供えの肉をすみずみまで清めるこ
と)」で、「家のすみずみまで、曇りなく清めること」。転じて「曇りなく目をきかす」
意。
*【瞋】は、「目+眞(ごちそうをいっぱいにつめこむこと)」で、「目のわくいっぱいに目
をむき出すこと。」
*【性】は、「心+生(芽が地上に生え出るさま)」で、「うまれつきのすみきった心。」
◆通説では【鵂】は省略されています。あったとしても二字とも「ふくろうの類」を指す
としています。
【鴟 (し)は夜蚤(のみ)を撮り豪末を察するも、昼に出づれば目を瞋(みは)るとも丘山を
見ずとは、性を殊にするを言えるなり。】は「鴟(ふくろう)は夜なかに蚤(のみ)をとら
えて細かい毛さきも見わけられるが、昼まに出てくると、いくら目を見張っても大きな
山も見えない。それは物それぞれに違った性質があることを物語っている。」としてい
ます。
◇【鴟鵂(しきゅう)は夜蚤(のみ)を撮り豪末を察するも、昼に出づれば目を瞋(いか)らす
とも丘山を見ず。性を殊にするを言うなり。】は、「フクロウやミミズクは夜ノミをつ
まみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、昼間に出れば、どんなに目をみは
っても、丘や山を見ることができない。それは、性能に違いがあることを物語ってい
る。」としました。
●通説では、次のようになっています。
鴟(ふくろう)は夜なかに蚤(のみ)をとらえて細かい毛さきも見わけられるが、昼まに出てくると、いくら目を見張っても大きな山も見えない。それは物それぞれに違った性質があることを物語っている。
〇新解釈では、次のようになります。
フクロウやミミズクは夜ノミをつまみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、
昼間に出れば、どんなに目をみはっても、丘や山を見ることができない。
それは、性能に違いがあることを物語っている。
【鴟鵂夜撮蚤察豪末】【鴟鵂(しきゅう)は夜蚤(のみ)を撮り、豪末を察するも、】
【晝出瞋目而不見丘山】【昼に出づれば目を瞋(いか)らすとも丘山を見ず。】
〔フクロウやミミズクは夜ノミをつまみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、〕
〔昼間に出れば、どんなに目をみはっても、丘や山を見ることができない。〕
──フクロウやミミズクは夜活動する習性をもっています。暗闇に適応するように、その目はカメラの絞りに相当する瞳(ひとみ)の部分、虹彩(こうさい)の筋肉の働きによって、網膜に入る光の量が多くなるように調節されているのではないかと思います。つまり他の鳥と違って、黒目の部分の瞳孔(どうこう)が大きく開いているものと思われます。
また、毛様体の筋肉の働きによって、水晶体、つまり網膜上に像を映し出すための透明な凸形レンズの厚みを変えることで、光の屈折を微調整し、極小の物を遠くからでもはっきり見わけることができるように、ピント調節できる仕組みになっているようです。
こうしたわけで、フクロウやミミズクは夜、ノミや豪末にフォーカスできる能力があるのですが、昼間はどんなに目をみはっても、まぶしすぎるのと大きなものに焦点を合わせることができないため、丘や山を見る能力がないのだ…と言っているようです。
【言殊性也】【性を殊にするを言うなり。】
〔それは、性能に違いがあることを物語っている。〕
──フクロウ類の目は人間の100倍の視力があり、尚且つわずかな光で暗闇を見ることができる感度のいい「すばらしい」性能をもっているのです。
ところが、明るい昼間、大きなものを見ることに関しては、その目の性能では「能なし」と言うことになってしまうようです。
「すばらしい」とも「能なし」ともなってしまうのも、生まれながらの性能の違いがあるからだ…という話ですね。
鴟(ふくろう)は夜なかに蚤(のみ)をとらえて細かい毛さきも見わけられるが、昼まに出てくると、いくら目を見張っても大きな山も見えない。それは物それぞれに違った性質があることを物語っている。
〇新解釈では、次のようになります。
フクロウやミミズクは夜ノミをつまみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、
昼間に出れば、どんなに目をみはっても、丘や山を見ることができない。
それは、性能に違いがあることを物語っている。
【鴟鵂夜撮蚤察豪末】【鴟鵂(しきゅう)は夜蚤(のみ)を撮り、豪末を察するも、】
【晝出瞋目而不見丘山】【昼に出づれば目を瞋(いか)らすとも丘山を見ず。】
〔フクロウやミミズクは夜ノミをつまみとり、細かい毛先に目をきかすことができるが、〕
〔昼間に出れば、どんなに目をみはっても、丘や山を見ることができない。〕
──フクロウやミミズクは夜活動する習性をもっています。暗闇に適応するように、その目はカメラの絞りに相当する瞳(ひとみ)の部分、虹彩(こうさい)の筋肉の働きによって、網膜に入る光の量が多くなるように調節されているのではないかと思います。つまり他の鳥と違って、黒目の部分の瞳孔(どうこう)が大きく開いているものと思われます。
また、毛様体の筋肉の働きによって、水晶体、つまり網膜上に像を映し出すための透明な凸形レンズの厚みを変えることで、光の屈折を微調整し、極小の物を遠くからでもはっきり見わけることができるように、ピント調節できる仕組みになっているようです。
こうしたわけで、フクロウやミミズクは夜、ノミや豪末にフォーカスできる能力があるのですが、昼間はどんなに目をみはっても、まぶしすぎるのと大きなものに焦点を合わせることができないため、丘や山を見る能力がないのだ…と言っているようです。
【言殊性也】【性を殊にするを言うなり。】
〔それは、性能に違いがあることを物語っている。〕
──フクロウ類の目は人間の100倍の視力があり、尚且つわずかな光で暗闇を見ることができる感度のいい「すばらしい」性能をもっているのです。
ところが、明るい昼間、大きなものを見ることに関しては、その目の性能では「能なし」と言うことになってしまうようです。
「すばらしい」とも「能なし」ともなってしまうのも、生まれながらの性能の違いがあるからだ…という話ですね。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 故曰蓋師是而无非 ┃【故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を无(む)とし、
┃ 師治而无亂乎 ┃ 治を師として乱を无とせざるやと曰くは、】
┃ 是未明天地之理 ┃【是未だ天地の理、
┃ 萬物之情者也 ┃ 万物の情に明らかならざる者なり。】
┗━━━━━━━━━━━┛
故に、『どうして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>にしないのか、
どうして治めることを<師>として、乱れることを<无>にしないのか』と言うのは、
これは未だに天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【蓋】は、「なんぞ…せざる(どうして…しないのか)」という反問。
*【理】は「玉+里(すじみちをつけた土地)」で、「宝石の表面にすけて見えるすじめ。」
動詞としては「すじみちをつけること。」「ことわり(物事のすじみち)。」
◆通説では、【故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を無(なみ)し、治を師として乱
を無(なみ)せざるやと曰うは、是未だ天地の理、万物の情に明らかならざる者なり。】
は「だから、『どうして善いことに従って悪いことを無視し、治に従って乱を無視しな
いのか』などというのは、これは天地の道理や万物の実情をさとらないもののことばで
ある。」としています。
◇【故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を无(む)とし、治を師として乱を无とせざ
るやと曰くは、是未だ天地の理、万物の情に明らかならざる者なり。】は「故に、『ど
うして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>としないのか、どうして治め
ることを<師>として、乱れることを<无>としかいのか』と言うのは、これは未だに
天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。」としました。
┃▼ 故曰蓋師是而无非 ┃【故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を无(む)とし、
┃ 師治而无亂乎 ┃ 治を師として乱を无とせざるやと曰くは、】
┃ 是未明天地之理 ┃【是未だ天地の理、
┃ 萬物之情者也 ┃ 万物の情に明らかならざる者なり。】
┗━━━━━━━━━━━┛
故に、『どうして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>にしないのか、
どうして治めることを<師>として、乱れることを<无>にしないのか』と言うのは、
これは未だに天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【蓋】は、「なんぞ…せざる(どうして…しないのか)」という反問。
*【理】は「玉+里(すじみちをつけた土地)」で、「宝石の表面にすけて見えるすじめ。」
動詞としては「すじみちをつけること。」「ことわり(物事のすじみち)。」
◆通説では、【故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を無(なみ)し、治を師として乱
を無(なみ)せざるやと曰うは、是未だ天地の理、万物の情に明らかならざる者なり。】
は「だから、『どうして善いことに従って悪いことを無視し、治に従って乱を無視しな
いのか』などというのは、これは天地の道理や万物の実情をさとらないもののことばで
ある。」としています。
◇【故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を无(む)とし、治を師として乱を无とせざ
るやと曰くは、是未だ天地の理、万物の情に明らかならざる者なり。】は「故に、『ど
うして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>としないのか、どうして治め
ることを<師>として、乱れることを<无>としかいのか』と言うのは、これは未だに
天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
だから、『どうして善いことに従って悪いことを無視し、治に従って乱を無視しないのか』などというのは、これは天地の道理や万物の実情をさとらないもののことばである。
〇新解釈では、次のようになります。
故に、『どうして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>にしないのか、
どうして治めることを<師>として、乱れることを<无>にしないのか』と言うのは、
これは未だに天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。
【故曰蓋師是而无非】【故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を无(む) とし、】
【師治而无亂乎】【治を師として乱を无とせざるやと曰くは、】
〔故に、『どうして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>にしないのか、
どうして治めることを<師>として、乱れることを<无>にしないのか』と言うのは、〕
──故に…今まで述べてきたように、価値判断は見る基準の違いで変わってくるものだということであるが故に…ということでしょう。
ものごとを善いとか悪いとか、見る視点によって善悪の判断も変わってきます。人類の進歩にはその両方が必要なのです。世の中が治まっているとか乱れているとか、治まっている時にも乱れている時には世界を刷新するする時に両方か必要な要素になるのです。一つの価値観から一辺倒に判断することはできないということの理解を求めるように話を進めてきたのにもかかわらず、それでも「どうして善いことを<師(導き手)>として、悪いことを<无(ないものとすること)>としないのだろうか、してもいいのではないか」とか、「どうして世が治まっていることを<師(導き手)>として、世が乱れることを<无(ないものとすること)>としないのだろうか、してもいいのではないか」と判断はするとの表面的なことで、自然の摂理はそう単純ではないのです。ところがつい表面的なところの判断から一方を<師>とし、一方を「无(なし)」と言うことがあるようだが…と言っています。
【是未明天地之理萬物之情者也】【是未だ天地の理、万物の情に明らかならざる者なり。】
〔これは未だに天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。〕
──そんな言いぐさは、天地の理(ことわり)として、また万物の情として、多角度的に判断するなら善悪、治乱が入れ込んで存在していて、両方が備わっていることが自然だということに明るくない者のことばだ…と言い切っているようです。
だから、『どうして善いことに従って悪いことを無視し、治に従って乱を無視しないのか』などというのは、これは天地の道理や万物の実情をさとらないもののことばである。
〇新解釈では、次のようになります。
故に、『どうして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>にしないのか、
どうして治めることを<師>として、乱れることを<无>にしないのか』と言うのは、
これは未だに天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。
【故曰蓋師是而无非】【故に、蓋(な)んぞ是(ぜ)を師として非(ひ)を无(む) とし、】
【師治而无亂乎】【治を師として乱を无とせざるやと曰くは、】
〔故に、『どうして善いことを<師>として、悪いことを<无(なし)>にしないのか、
どうして治めることを<師>として、乱れることを<无>にしないのか』と言うのは、〕
──故に…今まで述べてきたように、価値判断は見る基準の違いで変わってくるものだということであるが故に…ということでしょう。
ものごとを善いとか悪いとか、見る視点によって善悪の判断も変わってきます。人類の進歩にはその両方が必要なのです。世の中が治まっているとか乱れているとか、治まっている時にも乱れている時には世界を刷新するする時に両方か必要な要素になるのです。一つの価値観から一辺倒に判断することはできないということの理解を求めるように話を進めてきたのにもかかわらず、それでも「どうして善いことを<師(導き手)>として、悪いことを<无(ないものとすること)>としないのだろうか、してもいいのではないか」とか、「どうして世が治まっていることを<師(導き手)>として、世が乱れることを<无(ないものとすること)>としないのだろうか、してもいいのではないか」と判断はするとの表面的なことで、自然の摂理はそう単純ではないのです。ところがつい表面的なところの判断から一方を<師>とし、一方を「无(なし)」と言うことがあるようだが…と言っています。
【是未明天地之理萬物之情者也】【是未だ天地の理、万物の情に明らかならざる者なり。】
〔これは未だに天地の理(ことわり)、万物の情に明らかになっていない者のことばだ。〕
──そんな言いぐさは、天地の理(ことわり)として、また万物の情として、多角度的に判断するなら善悪、治乱が入れ込んで存在していて、両方が備わっていることが自然だということに明るくない者のことばだ…と言い切っているようです。
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 是猶師天而无地 ┃【是猶(な)お天を師として地を无とし、】
┃ 師陰而无陽 ┃【陰を師として陽を无とするがごとく、】
┃ 其不可行明矣 ┃【其の行なうべからざること明らかなり。】
┗━━━━━━━━━━┛
それはまるで天を<師>として地を<无>とし、
陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、
その行いをうまく進めさせられないことは明らかだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【猶】は、「なお…のごとし(まるで…のようだ)。」
◆通説では、【是れ猶(な)お天を師として地を無(なみ)し、陰を師として陽を無(なみ)する
がごとく、其の行なうべからざること明らかなり。】は「これはちょうど天に従って地
を無視し、陰に従って陽を無視するようなもので、とてもうまくいかないことは明白で
ある。」としています。
◇【是れ猶(な)お天を師として地を无とし、陰を師として陽を无とするがごとく、其の行
なうべからざること明らかなり。】は「それはまるで天を<師>として地を<无>と
し、陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、その行いをうまく進めさ
せられないことは明らかだ。」としました。
┃▼ 是猶師天而无地 ┃【是猶(な)お天を師として地を无とし、】
┃ 師陰而无陽 ┃【陰を師として陽を无とするがごとく、】
┃ 其不可行明矣 ┃【其の行なうべからざること明らかなり。】
┗━━━━━━━━━━┛
それはまるで天を<師>として地を<无>とし、
陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、
その行いをうまく進めさせられないことは明らかだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【猶】は、「なお…のごとし(まるで…のようだ)。」
◆通説では、【是れ猶(な)お天を師として地を無(なみ)し、陰を師として陽を無(なみ)する
がごとく、其の行なうべからざること明らかなり。】は「これはちょうど天に従って地
を無視し、陰に従って陽を無視するようなもので、とてもうまくいかないことは明白で
ある。」としています。
◇【是れ猶(な)お天を師として地を无とし、陰を師として陽を无とするがごとく、其の行
なうべからざること明らかなり。】は「それはまるで天を<師>として地を<无>と
し、陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、その行いをうまく進めさ
せられないことは明らかだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
これはちょうど天に従って地を無視し、陰に従って陽を無視するようなもので、とてもうまくいかないことは明白である。
〇新解釈では、次のようになります。
それはまるで天を<師>として地を<无>とし、
陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、
その行いをうまく進めさせられないことは明らかだ。
【是猶師天而无地】【是猶(な)お天を師として地を无とし、】
【師陰而无陽】【陰を師として陽を无とするがごとく、】
〔それはまるで天を<師>として地を<无>とし、〕
〔陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、〕
──善悪の悪が、治乱の乱が、なぜ必要なのかはまだ納得していない人もあるかもしれませんが、天地の地が、陰陽の陽が必要なのは、誰もが認めるところでしょう。
それはまるで天を<師(導き手)>として、地を<无(ないものにすること)>とし、陰を<師(導き手)>として、陽を<无(ないものとすること)>のようなものだ…と言っています。
【其不可行明矣】【其の行なうべからざること明らかなり。】
〔その行いをうまく進めさせられないことは明らかだ。〕
──それでは天地の理や万物の情に沿ったものではないことは理解できるでしょう。そんな偏った行いはどんなものであれ、うまく進めることは不可能だということは、あきらかなことだ…ということになりそうです。
これはちょうど天に従って地を無視し、陰に従って陽を無視するようなもので、とてもうまくいかないことは明白である。
〇新解釈では、次のようになります。
それはまるで天を<師>として地を<无>とし、
陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、
その行いをうまく進めさせられないことは明らかだ。
【是猶師天而无地】【是猶(な)お天を師として地を无とし、】
【師陰而无陽】【陰を師として陽を无とするがごとく、】
〔それはまるで天を<師>として地を<无>とし、〕
〔陰を<師>として陽を<无>とすることのようなもので、〕
──善悪の悪が、治乱の乱が、なぜ必要なのかはまだ納得していない人もあるかもしれませんが、天地の地が、陰陽の陽が必要なのは、誰もが認めるところでしょう。
それはまるで天を<師(導き手)>として、地を<无(ないものにすること)>とし、陰を<師(導き手)>として、陽を<无(ないものとすること)>のようなものだ…と言っています。
【其不可行明矣】【其の行なうべからざること明らかなり。】
〔その行いをうまく進めさせられないことは明らかだ。〕
──それでは天地の理や万物の情に沿ったものではないことは理解できるでしょう。そんな偏った行いはどんなものであれ、うまく進めることは不可能だということは、あきらかなことだ…ということになりそうです。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 然且語而不舎 ┃【然れども且つ語って舎(お)かざるは、】
┃ 非愚則誣也 ┃【愚に非ずして、則ち誣(ふ)なり。】
┗━━━━━━━━━┛
それにもかかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、
愚(心の内を水鏡のようにしているの)ではなく、
つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこじつけていることになるのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【舎】は「口(ある場所)+余(土を伸ばすスコップのさま)」で、「手足を伸ばす場所。」
つまり「休みどころや宿舎のこと」。「やどる・やどす(からだをのばしてくつろぐこ
と)。」「おく・すてる(手をゆるめてはなしておく。すておく。はなす) 。」
*【誣】は、「言+巫(わからないものをむりに探し求める、むりじいをする)」で、「何
もないのにむりに話をつくりあげて、人の悪口をいうこと。」「ないものをむりにある
ものにする、相手のいうことを無視する。」「しいる(そういう事実がないものをあるよ
うにいいたてて、人をそしる。人のいうことをないがしろにする)。」「事実をまげてこ
じつける。」
◆通説では、【然れども且(な)お語って舎(お)かざるは、愚に非ざれば則ち誣(し)うるな
り。】は「にもかかわらず、なおそれを主張してやめないというのは、馬鹿ものでなけ
ればごまかしである。」としています。
◇新解釈では【愚】は「馬鹿もの」といった否定的な意味ではなく、「(猿真似するかのよ
うに)そっくりな心になれる状態」つまり「心の内を水鏡のようにしてそっくりに写し取
ることができること」といった肯定的な意味だととらえました。
【然れども且つ語って舎(お)かざるは、愚に非ずして、則ち誣(ふ)なり。】は「それにも
かかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、愚(心の内を水鏡
のようにしているの)ではなく、つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこ
じつけていることになるのだ。」としました。
┃▼ 然且語而不舎 ┃【然れども且つ語って舎(お)かざるは、】
┃ 非愚則誣也 ┃【愚に非ずして、則ち誣(ふ)なり。】
┗━━━━━━━━━┛
それにもかかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、
愚(心の内を水鏡のようにしているの)ではなく、
つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこじつけていることになるのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【舎】は「口(ある場所)+余(土を伸ばすスコップのさま)」で、「手足を伸ばす場所。」
つまり「休みどころや宿舎のこと」。「やどる・やどす(からだをのばしてくつろぐこ
と)。」「おく・すてる(手をゆるめてはなしておく。すておく。はなす) 。」
*【誣】は、「言+巫(わからないものをむりに探し求める、むりじいをする)」で、「何
もないのにむりに話をつくりあげて、人の悪口をいうこと。」「ないものをむりにある
ものにする、相手のいうことを無視する。」「しいる(そういう事実がないものをあるよ
うにいいたてて、人をそしる。人のいうことをないがしろにする)。」「事実をまげてこ
じつける。」
◆通説では、【然れども且(な)お語って舎(お)かざるは、愚に非ざれば則ち誣(し)うるな
り。】は「にもかかわらず、なおそれを主張してやめないというのは、馬鹿ものでなけ
ればごまかしである。」としています。
◇新解釈では【愚】は「馬鹿もの」といった否定的な意味ではなく、「(猿真似するかのよ
うに)そっくりな心になれる状態」つまり「心の内を水鏡のようにしてそっくりに写し取
ることができること」といった肯定的な意味だととらえました。
【然れども且つ語って舎(お)かざるは、愚に非ずして、則ち誣(ふ)なり。】は「それにも
かかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、愚(心の内を水鏡
のようにしているの)ではなく、つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこ
じつけていることになるのだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
にもかかわらず、なおそれを主張してやめないというのは、馬鹿ものでなければごまかしである。
〇新解釈では、次のようになります。
それにもかかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、
愚(心の内を水鏡のようにしているの)ではなく、
つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこじつけていることになる。
【然且語而不舎】【然れども且つ語って舎(やど)さざるは、】
〔それにもかかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、〕
──何をさらに語り続けようとしていると言っているのでしょうか。
それは、どんなことであっても対極のうち、片方だけではその行いをうまく進められないと聞いても、善悪、治乱だけではなく、さらに(例えば)「どうしてポジティブなことを<師(導き手)>とし、ネガティブなことを<无(ないもの)>にしないのか。してもいいのではないだろうか。」といったことを(外に向かって)言い続けようとしている…ということでしょう。
そうして、対極があったとしても両極とも必要不可欠なものだと、何か一方を<師>とし、もう一方を<无>とすることなく、自然に存在する両方を認めることによって(心の内に)くつろいでいられればいいのだが、実状はそうはできない状態にいるということはどういうことになるか、次に説明をしているようです。
【非愚則誣也】【愚に非ずして、則ち誣(ふ)なり。】
〔愚(心の内を水鏡のようにしているの)ではなく、
つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこじつけていることになる。〕
──「愚」…今までも何度か説明してきましたが、荘子は「愚」を肯定的に用いています。よってここでも肯定的な含みをもったものとしてとらえました。「愚」は「そっくりな状態の猿まねができる心」、つまり「流動的な心の内の波を凪にして、どんなものでも内側にそっくりに写し取ることができる水鏡のような状態の心」という意味だと解釈しました。
何かを<師>とし、その対極のものを<无>とする主張は、分裂が起き、心を凪のように、水鏡のように保つことはできません。つまり「愚のようにはなれない」のです。
ものごとの半面、表だけを肯定して追い求め、裏を否定する状態は、真実(事実)をまげてこじつけているだけだということになる…と言っているのです。真実というのは、表があったとするなら必ず裏があるものなのです。言葉には限界があります。表現できるのは半面であるしかないのですが、隠れたところにもう半面があるという理解が必要なのかもしれません。
にもかかわらず、なおそれを主張してやめないというのは、馬鹿ものでなければごまかしである。
〇新解釈では、次のようになります。
それにもかかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、
愚(心の内を水鏡のようにしているの)ではなく、
つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこじつけていることになる。
【然且語而不舎】【然れども且つ語って舎(やど)さざるは、】
〔それにもかかわらず、さらに(外に)語り続けて(内に)くつろごうとしないのは、〕
──何をさらに語り続けようとしていると言っているのでしょうか。
それは、どんなことであっても対極のうち、片方だけではその行いをうまく進められないと聞いても、善悪、治乱だけではなく、さらに(例えば)「どうしてポジティブなことを<師(導き手)>とし、ネガティブなことを<无(ないもの)>にしないのか。してもいいのではないだろうか。」といったことを(外に向かって)言い続けようとしている…ということでしょう。
そうして、対極があったとしても両極とも必要不可欠なものだと、何か一方を<師>とし、もう一方を<无>とすることなく、自然に存在する両方を認めることによって(心の内に)くつろいでいられればいいのだが、実状はそうはできない状態にいるということはどういうことになるか、次に説明をしているようです。
【非愚則誣也】【愚に非ずして、則ち誣(ふ)なり。】
〔愚(心の内を水鏡のようにしているの)ではなく、
つまりは、(外に発言することによって)事実をまげてこじつけていることになる。〕
──「愚」…今までも何度か説明してきましたが、荘子は「愚」を肯定的に用いています。よってここでも肯定的な含みをもったものとしてとらえました。「愚」は「そっくりな状態の猿まねができる心」、つまり「流動的な心の内の波を凪にして、どんなものでも内側にそっくりに写し取ることができる水鏡のような状態の心」という意味だと解釈しました。
何かを<師>とし、その対極のものを<无>とする主張は、分裂が起き、心を凪のように、水鏡のように保つことはできません。つまり「愚のようにはなれない」のです。
ものごとの半面、表だけを肯定して追い求め、裏を否定する状態は、真実(事実)をまげてこじつけているだけだということになる…と言っているのです。真実というのは、表があったとするなら必ず裏があるものなのです。言葉には限界があります。表現できるのは半面であるしかないのですが、隠れたところにもう半面があるという理解が必要なのかもしれません。
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 帝王殊禪 三代殊繼 ┃【帝王は禅(ぜん)を殊にし、三代は継(けい)を殊にす。】
┃ 差其時 逆其俗者 ┃【其の時に差(たが)い、其の俗に逆らう者、】
┃ 謂之簒夫 ┃【これを簒夫(さんふ)と謂う。】
┃ 當其時 順其俗者 ┃【其の時に当たり、其の俗に順(したが)う者、】
┃ 謂之義之徒 ┃【これを義の徒と謂う。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
帝王はその王位の譲り方に違いがあり、三王朝はその継承の仕方に違いがあった。
その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、
これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。
その時代の動向に当てはまり、世俗のならわしに順(したが)う者、
これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶだけだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【禪(禅)】は、「示(祭壇)+單(たいら)」で「たいらな土の壇の上で天をまつる儀式。」
「ゆずり(壇上で天をまつる天子の特権) 。」「ゆずる(天子が天子の特権をゆずる) 。」
*【三代】は、中国の古代の、夏・殷・周の三王朝。
*【繼(継)】は、「糸+[右の字]」で「切れた糸をつなぐこと。」「つぐ(切れた糸をつな
ぐ。糸でつなぐように、前人の位・仕事・物などを受けて行う。あとをつぐ。」
*【差】は、「たがう(同じようにそろわない。じくざぐになる) 。」
*【逆】は、「辵+屰(大の字型の人をさかさまにしたさま)」で、「さかさの方向に進むこ
と」。「さからう。たがう(そむく) 。」
*【簒】は、「ム(かこいこんで私有する)+算」で「くぼむ、もぐりこむ」意を含み、「す
きまにもぐりこんで盗みとり、自分のものにとすること」。「うばう」。「むほん」
*【夫]は、「大の字にたった人の頭に、まげ、または冠のしるしをつけた姿」を描いた象形
文字。
*【當(当)】は、「田+尚」の形声文字。「あたる(まともに引き受ける・相当する・あて
はまる)」。
*【順】は、「川+頁(あたま)」は「ルートに沿って水が流れるように、頭を向けて進むこ
と」を示します。「したがう(ルールや道すじどおりに進む)」。
*【義】は「羊(形のよいひつじ)+我」で、もと「かどめがたってかっこうがよいこと。
きちんとしてかっこうがよいとと認められるやり方」。「すじ道・かどめ・かどめが正
しい」。「利欲に引かれず、すじ道をたてる心」。「公共のためにつくすこと」。
*【徒】は、「止(あし)+彳(いく)+土」で、「陸地を一歩一歩あゆむこと」。「歩いてい
く兵隊」。「ともがら(下級のなかま)」。
◆通説では、【簒夫】を【簒之夫】と「之」を加えて解釈しています。
【帝王は禅(ぜん/伝)を殊(こと)にし、三代は継(つ)ぐを殊にす。其の時に差(たが)い、
其の俗に逆らう者は、これを簒(さん)の夫(ふ)と謂う。其の時に当たり、其の俗に順
(したが)う者は、これを義の徒と謂う。】は「むかしの帝王もその位の伝えかたはさ
まざまであったし、夏・殷・周の三代もそのつづきかたはさまざまであった。その時代
の情勢に従わず、社会の風習に逆らったものを、簒奪者(さんだつしゃ)とよび、その時
代の情勢にかない、社会の風習に順応したものを、正義の人とよぶのである。」としてい
ます。
◇新解釈では、「之」を加えることなくそのまま訳しましたが、ほとんど影響はないです。
王位継承の話であるため【夫】の原義に「冠をつけた男」というのは合点がいきますが、
【徒】の原義にはどう考えても「王」につながらず、「凡人」としました。
【帝王は禅(ぜん)を殊(こと)にし、三代は継(けい)を殊にす。其の時に差(たが)い、其
の俗に逆らう者、これを簒夫(さんふ)と謂う。其の時に当たり、其の俗に順(したが) う
者、これを義の徒と謂う。】は「帝王はその王位の譲り方に違いがあり、三王朝はそ
の継承の仕方に違いがあった。その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、
これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。その時代の動向に当てはま
り、世俗のならわしに順(したが)う者、これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶ
だけだ。」としました。
┃▼ 帝王殊禪 三代殊繼 ┃【帝王は禅(ぜん)を殊にし、三代は継(けい)を殊にす。】
┃ 差其時 逆其俗者 ┃【其の時に差(たが)い、其の俗に逆らう者、】
┃ 謂之簒夫 ┃【これを簒夫(さんふ)と謂う。】
┃ 當其時 順其俗者 ┃【其の時に当たり、其の俗に順(したが)う者、】
┃ 謂之義之徒 ┃【これを義の徒と謂う。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
帝王はその王位の譲り方に違いがあり、三王朝はその継承の仕方に違いがあった。
その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、
これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。
その時代の動向に当てはまり、世俗のならわしに順(したが)う者、
これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶだけだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【禪(禅)】は、「示(祭壇)+單(たいら)」で「たいらな土の壇の上で天をまつる儀式。」
「ゆずり(壇上で天をまつる天子の特権) 。」「ゆずる(天子が天子の特権をゆずる) 。」
*【三代】は、中国の古代の、夏・殷・周の三王朝。
*【繼(継)】は、「糸+[右の字]」で「切れた糸をつなぐこと。」「つぐ(切れた糸をつな
ぐ。糸でつなぐように、前人の位・仕事・物などを受けて行う。あとをつぐ。」
*【差】は、「たがう(同じようにそろわない。じくざぐになる) 。」
*【逆】は、「辵+屰(大の字型の人をさかさまにしたさま)」で、「さかさの方向に進むこ
と」。「さからう。たがう(そむく) 。」
*【簒】は、「ム(かこいこんで私有する)+算」で「くぼむ、もぐりこむ」意を含み、「す
きまにもぐりこんで盗みとり、自分のものにとすること」。「うばう」。「むほん」
*【夫]は、「大の字にたった人の頭に、まげ、または冠のしるしをつけた姿」を描いた象形
文字。
*【當(当)】は、「田+尚」の形声文字。「あたる(まともに引き受ける・相当する・あて
はまる)」。
*【順】は、「川+頁(あたま)」は「ルートに沿って水が流れるように、頭を向けて進むこ
と」を示します。「したがう(ルールや道すじどおりに進む)」。
*【義】は「羊(形のよいひつじ)+我」で、もと「かどめがたってかっこうがよいこと。
きちんとしてかっこうがよいとと認められるやり方」。「すじ道・かどめ・かどめが正
しい」。「利欲に引かれず、すじ道をたてる心」。「公共のためにつくすこと」。
*【徒】は、「止(あし)+彳(いく)+土」で、「陸地を一歩一歩あゆむこと」。「歩いてい
く兵隊」。「ともがら(下級のなかま)」。
◆通説では、【簒夫】を【簒之夫】と「之」を加えて解釈しています。
【帝王は禅(ぜん/伝)を殊(こと)にし、三代は継(つ)ぐを殊にす。其の時に差(たが)い、
其の俗に逆らう者は、これを簒(さん)の夫(ふ)と謂う。其の時に当たり、其の俗に順
(したが)う者は、これを義の徒と謂う。】は「むかしの帝王もその位の伝えかたはさ
まざまであったし、夏・殷・周の三代もそのつづきかたはさまざまであった。その時代
の情勢に従わず、社会の風習に逆らったものを、簒奪者(さんだつしゃ)とよび、その時
代の情勢にかない、社会の風習に順応したものを、正義の人とよぶのである。」としてい
ます。
◇新解釈では、「之」を加えることなくそのまま訳しましたが、ほとんど影響はないです。
王位継承の話であるため【夫】の原義に「冠をつけた男」というのは合点がいきますが、
【徒】の原義にはどう考えても「王」につながらず、「凡人」としました。
【帝王は禅(ぜん)を殊(こと)にし、三代は継(けい)を殊にす。其の時に差(たが)い、其
の俗に逆らう者、これを簒夫(さんふ)と謂う。其の時に当たり、其の俗に順(したが) う
者、これを義の徒と謂う。】は「帝王はその王位の譲り方に違いがあり、三王朝はそ
の継承の仕方に違いがあった。その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、
これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。その時代の動向に当てはま
り、世俗のならわしに順(したが)う者、これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶ
だけだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
むかしの帝王もその位の伝えかたはさまざまであったし、夏・殷・周の三代もそのつづきかたはさまざまであった。その時代の情勢に従わず、社会の風習に逆らったものを、簒奪者(さんだつしゃ)とよび、その時代の情勢にかない、社会の風習に順応したものを、正義の人とよぶのである。
〇新解釈では、次のようになります。
帝王はその王位の禅(ゆず)り方に違いがあり、三王朝はその継承の仕方に違いがあった。
その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、
これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。
その時代の動向に当てはまり、世俗のならわしに順(したが)う者、
これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶだけだ。
【帝王殊禪 三代殊繼】【帝王は禅(ぜん)を殊にし、三代は継(けい)を殊にす。】
〔帝王はその王位の禅り方に違いがあり、三王朝はその継承の仕方に違いがあった。〕
──五帝は前にも説明したように、黄帝から堯までは血族に王位を禅(ゆず)ることになりましたが、堯は息子には譲らず、徳の高い舜に禅(ゆず)りました。それぞれ禅(ゆず)り方に違いがありました。
三代は、王位継承の仕方には、禅譲、戦争、世襲という違いがありました。
舜が、禹に王位を禅譲し、始まったのが「夏」王朝です。明確な資料かないため、はっきりしたことはわかりませんが、史記等による伝承の最古の王朝とされています。最初の世襲制王朝のようで17代続いたようです。紀元前1900年ころ〜前1600年ころの約300年続いたとされています。
夏の暴君だった第17代桀王を湯(とう)王が滅ぼして、「殷」王朝を創始しました。そこから30代に渡り殷王朝は紀元前約1600年ころ〜前1046年まで約550年続いたとされています。
殷の暴君だった第30代紂(ちゅう)王を武王が滅ぼして、「周」王朝を創始しました。紀元前1046年〜前770年までを「西周」が、紀元前770年〜前256年(秦に滅ぼされる) まで「東周」が続きます。西周(12代)・東周(25代)の両方を合わせると740年、中国史上最も長く続いた王朝だとされています。
むかしの帝王もその位の伝えかたはさまざまであったし、夏・殷・周の三代もそのつづきかたはさまざまであった。その時代の情勢に従わず、社会の風習に逆らったものを、簒奪者(さんだつしゃ)とよび、その時代の情勢にかない、社会の風習に順応したものを、正義の人とよぶのである。
〇新解釈では、次のようになります。
帝王はその王位の禅(ゆず)り方に違いがあり、三王朝はその継承の仕方に違いがあった。
その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、
これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。
その時代の動向に当てはまり、世俗のならわしに順(したが)う者、
これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶだけだ。
【帝王殊禪 三代殊繼】【帝王は禅(ぜん)を殊にし、三代は継(けい)を殊にす。】
〔帝王はその王位の禅り方に違いがあり、三王朝はその継承の仕方に違いがあった。〕
──五帝は前にも説明したように、黄帝から堯までは血族に王位を禅(ゆず)ることになりましたが、堯は息子には譲らず、徳の高い舜に禅(ゆず)りました。それぞれ禅(ゆず)り方に違いがありました。
三代は、王位継承の仕方には、禅譲、戦争、世襲という違いがありました。
舜が、禹に王位を禅譲し、始まったのが「夏」王朝です。明確な資料かないため、はっきりしたことはわかりませんが、史記等による伝承の最古の王朝とされています。最初の世襲制王朝のようで17代続いたようです。紀元前1900年ころ〜前1600年ころの約300年続いたとされています。
夏の暴君だった第17代桀王を湯(とう)王が滅ぼして、「殷」王朝を創始しました。そこから30代に渡り殷王朝は紀元前約1600年ころ〜前1046年まで約550年続いたとされています。
殷の暴君だった第30代紂(ちゅう)王を武王が滅ぼして、「周」王朝を創始しました。紀元前1046年〜前770年までを「西周」が、紀元前770年〜前256年(秦に滅ぼされる) まで「東周」が続きます。西周(12代)・東周(25代)の両方を合わせると740年、中国史上最も長く続いた王朝だとされています。
(続きです)
【差其時 逆其俗者】【其の時に差(たが)い、其の俗に逆らう者、】
【謂之簒夫】【これを簒夫(さんふ)と謂う。】
〔その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、〕
〔これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。〕
──その時代の流れにそぐわず、君主に従うという世俗のならわしに逆らって、戦を起こして王位を武力で略奪した者を、社会の「悪人」とみなしがちです。だが、それだけで善悪の判断がつけられるわけではなく、ただそうした者のことを「簒奪者(さんだつしゃ)」あるいは「むほん人」と呼ぶだけなのだ…と言っています。
その例で有名なのが、殷の湯王と周の武王です。戦を起こしたことは事実ですが、だからといって社会の「悪人」とはみなされていません。というのも、殺した相手が、桀王、紂王、両者ともに暴君の代名詞となったほどの者だったからです。王としてその悪行の政治はひどいものだったとされています。両者ともその人物像は酷似していて、武力にものをいわせ、美女(末喜と妲己)に溺れ、政を省みず豪著な宴会を催し、諫言をする臣を殺して回ったりしていたのです。だからむしろ「簒奪者」を歓迎する風潮があったとされていたようです。
しかし、どちらも殺戮を行ったという事実から、善悪つけがたいところがあります。また、史実には勝者の都合のいいように塗り替えられた別の側面があったという人もいて、実際の真相はわからないものなのです。
【當其時 順其俗者】【其の時に当たり、其の俗に順(したが)う者、】
【謂之義之徒】【これを義の徒と謂う。】
〔その時代の動向に当てはまり、世俗のならわしに順(したが)う者、〕
〔これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶだけだ。〕
──その時代の流れに乗って、君主に従うという世俗のならわしに従って、平和に、平穏に政を行った者を、社会の「善人」とみなしがちです。だが、それだけで善悪の判断がつけられるわけではなく、ただそうした者のことを「義の徒」と呼ぶだけなのだ…と言っています。
通説では「義の徒」を「正義の人」と訳していますが、「徒」という漢字を使っているところから、そう単純に「夫」と同じく「人(者)」と訳していいものかどうか考えさせられる所です。というのも、話の流れからすると、君主の話をしているのに、なぜ「徒(馬などにものらない徒歩でゆく兵隊・下級のともがら)」という字を用いたのか、その意図を深読みしたくなるところだからです。
そもそも世俗のならわしに従って、平穏に暮らすことが、人間というか人類にとって生きている価値を全うすることになるかどうか疑わしいところです。世襲によって引き継いだ王位の位をもっていても、実質は「公共のために尽くすだけの凡人(凡庸な人物)」にすぎない…と言っているのではないかと推察しました。
堯や舜の政事(指導)は平和、平穏だけではなく、人の徳性を高めようと意図した政治を司ろうと努力していたのではないでしょうか。一方、ここの「義の徒」は、人を進化へといざなう生き方を指導できるような人だったとは言えない「凡庸な人物だ」…と言っているような気がしています。
世俗のならわしに、逆らおうと、順(したが)おうと、どちらにしてもそれは世俗にとらわれているところから一歩も出ない行為にすぎないのかもしれませんね。政治での指導力のある権力の座にいる人に何を期待しても、自分が俗から脱却していなければ、意味をなさないのかもしれません。俗の善悪こもごもから、超然として目覚めるためにはどうすればいいのか、次のことばに秘密があるのかもしれません。
【差其時 逆其俗者】【其の時に差(たが)い、其の俗に逆らう者、】
【謂之簒夫】【これを簒夫(さんふ)と謂う。】
〔その時代の動向にそぐわず、世俗のならわしに逆らう者、〕
〔これを簒奪者(さんだつしゃ/むほん人)と呼ぶだけだけだ。〕
──その時代の流れにそぐわず、君主に従うという世俗のならわしに逆らって、戦を起こして王位を武力で略奪した者を、社会の「悪人」とみなしがちです。だが、それだけで善悪の判断がつけられるわけではなく、ただそうした者のことを「簒奪者(さんだつしゃ)」あるいは「むほん人」と呼ぶだけなのだ…と言っています。
その例で有名なのが、殷の湯王と周の武王です。戦を起こしたことは事実ですが、だからといって社会の「悪人」とはみなされていません。というのも、殺した相手が、桀王、紂王、両者ともに暴君の代名詞となったほどの者だったからです。王としてその悪行の政治はひどいものだったとされています。両者ともその人物像は酷似していて、武力にものをいわせ、美女(末喜と妲己)に溺れ、政を省みず豪著な宴会を催し、諫言をする臣を殺して回ったりしていたのです。だからむしろ「簒奪者」を歓迎する風潮があったとされていたようです。
しかし、どちらも殺戮を行ったという事実から、善悪つけがたいところがあります。また、史実には勝者の都合のいいように塗り替えられた別の側面があったという人もいて、実際の真相はわからないものなのです。
【當其時 順其俗者】【其の時に当たり、其の俗に順(したが)う者、】
【謂之義之徒】【これを義の徒と謂う。】
〔その時代の動向に当てはまり、世俗のならわしに順(したが)う者、〕
〔これを義の徒(公共のために尽くす凡人)と呼ぶだけだ。〕
──その時代の流れに乗って、君主に従うという世俗のならわしに従って、平和に、平穏に政を行った者を、社会の「善人」とみなしがちです。だが、それだけで善悪の判断がつけられるわけではなく、ただそうした者のことを「義の徒」と呼ぶだけなのだ…と言っています。
通説では「義の徒」を「正義の人」と訳していますが、「徒」という漢字を使っているところから、そう単純に「夫」と同じく「人(者)」と訳していいものかどうか考えさせられる所です。というのも、話の流れからすると、君主の話をしているのに、なぜ「徒(馬などにものらない徒歩でゆく兵隊・下級のともがら)」という字を用いたのか、その意図を深読みしたくなるところだからです。
そもそも世俗のならわしに従って、平穏に暮らすことが、人間というか人類にとって生きている価値を全うすることになるかどうか疑わしいところです。世襲によって引き継いだ王位の位をもっていても、実質は「公共のために尽くすだけの凡人(凡庸な人物)」にすぎない…と言っているのではないかと推察しました。
堯や舜の政事(指導)は平和、平穏だけではなく、人の徳性を高めようと意図した政治を司ろうと努力していたのではないでしょうか。一方、ここの「義の徒」は、人を進化へといざなう生き方を指導できるような人だったとは言えない「凡庸な人物だ」…と言っているような気がしています。
世俗のならわしに、逆らおうと、順(したが)おうと、どちらにしてもそれは世俗にとらわれているところから一歩も出ない行為にすぎないのかもしれませんね。政治での指導力のある権力の座にいる人に何を期待しても、自分が俗から脱却していなければ、意味をなさないのかもしれません。俗の善悪こもごもから、超然として目覚めるためにはどうすればいいのか、次のことばに秘密があるのかもしれません。
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 黙黙乎河伯 ┃【黙黙乎(こ)たれ、河伯よ。】
┃ 女惡知貴賤之門小大之家 ┃【女悪(いず)くんぞ貴賤の門、大小の家を知らん。】
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。
お前にどうしたら貴賤の違いが生じる門や、大小の違いが生じる家がわかるだろうか。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【門】は、左右二まいのとびらを設けたもんの姿を描いた象形文字。「やっと出入りで
きる程度に、狭くとじている」の意を含みます。「やっと通れる程度のせまい入口。」
「物事の分類上のわく。」
*【家】は、「宀(やね)+豕(ぶた)」で、「たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。」
「いえ(家族。その家族が住む住居)。」「専門の学問・技術の流派。」
◆通説では、【悪…】を反語とみなして、否定形と解釈しています。
【黙黙(もくもく)たれよ河伯よ。女(なんじ)、悪(いず)くんぞ貴賤の門、大小の家を
知らんやと。】は「ただ黙っているがよい、河伯よ。貴賤の区別が出てくるところとか
大小の区別のありかなど、お前などにどうしてわかろうか。」としています。
◇新解釈では、【悪…】は反問とみなして、疑問形と解釈しました。
【黙黙乎(こ)たれ、河伯よ。女悪(いず)くんぞ貴賤の門、大小の家を知らん。】は、
「(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。お前にどうしたら貴賤の違いが生じる門や、大小
の違いが生じる家がわかるだろうか。」としました。
┃▼ 黙黙乎河伯 ┃【黙黙乎(こ)たれ、河伯よ。】
┃ 女惡知貴賤之門小大之家 ┃【女悪(いず)くんぞ貴賤の門、大小の家を知らん。】
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。
お前にどうしたら貴賤の違いが生じる門や、大小の違いが生じる家がわかるだろうか。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【門】は、左右二まいのとびらを設けたもんの姿を描いた象形文字。「やっと出入りで
きる程度に、狭くとじている」の意を含みます。「やっと通れる程度のせまい入口。」
「物事の分類上のわく。」
*【家】は、「宀(やね)+豕(ぶた)」で、「たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。」
「いえ(家族。その家族が住む住居)。」「専門の学問・技術の流派。」
◆通説では、【悪…】を反語とみなして、否定形と解釈しています。
【黙黙(もくもく)たれよ河伯よ。女(なんじ)、悪(いず)くんぞ貴賤の門、大小の家を
知らんやと。】は「ただ黙っているがよい、河伯よ。貴賤の区別が出てくるところとか
大小の区別のありかなど、お前などにどうしてわかろうか。」としています。
◇新解釈では、【悪…】は反問とみなして、疑問形と解釈しました。
【黙黙乎(こ)たれ、河伯よ。女悪(いず)くんぞ貴賤の門、大小の家を知らん。】は、
「(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。お前にどうしたら貴賤の違いが生じる門や、大小
の違いが生じる家がわかるだろうか。」としました。
●通説では、次のようになっています。
ただ黙っているがよい、河伯よ。貴賤の区別が出てくるところとか大小の区別のありかなど、お前などにどうしてわかろうか。」
〇新解釈では、次のようになります。
(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。
お前にどうしたら貴賤の違いが生じる門や、大小の違いが生じる家がわかるだろうか。」
【黙黙乎河伯】【黙黙乎(こ)たれ、河伯よ。】
〔(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。〕
──「黙々とあれ」と北海若は言っています。それは通説のように「ただ黙っているがよい」とよい行為のあり方を示したというニュアンスとは違うと思います。言葉を発しないという外の行為だけでは不十分なのです。この「黙々乎」は、自分の心の内を静まらせる必要があるのだ…と河伯に呼び掛けているのではないでしょうか。
そこで付け加えました。「愚のように」と。それは「愚のように、心の中を水鏡のようにするために静かに静かに、黙々としてものごとをとらえよ。」と言っているのだと解釈したからです。
自分の疑問に振り回されて、言葉で解答を得ようとすればするほど、それをのがすことになると思うのです。俗人の心の中は、常にさざ波立っているのです。解答を知るためには、心の中にある微塵だに動かぬ水面による鏡で写し取る必要があるのです。そのためには、黙々とすることが大事なのです。それが善悪こもごも判断に迷っている俗から超然としていられる唯一の道だからなのです。
【女惡知貴賤之門小大之家】【女(なんじ)悪くんぞ貴賤の門、大小の家を知らん。】
〔お前にどうしたら貴賤の違いが生じる門や、大小の違いが生じる家がわかるだろうか。」〕
──ここは、「河伯にはわかりっこない」と上から目線で否定しているのではないと考えます。北海若の切実なる願望のあらわれた言葉なのではないでしょうか。つまり「河伯にどうやったらわかるだろうか」という疑問形で誘っているのです。「貴賤の違いが生じる門」をどこに便宜上暫定的に設け、その開閉によって貴賤があったりなかったりするツボを知ることができないだろうか、「大小の違いが生じる家」をどこに便宜上暫定的に設け、その蓋(屋根)のかぶせ方で大小があったりなかったりするツボを知ることはできないだろうか…と言っているのではないでしょうか。
ただ黙っているがよい、河伯よ。貴賤の区別が出てくるところとか大小の区別のありかなど、お前などにどうしてわかろうか。」
〇新解釈では、次のようになります。
(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。
お前にどうしたら貴賤の違いが生じる門や、大小の違いが生じる家がわかるだろうか。」
【黙黙乎河伯】【黙黙乎(こ)たれ、河伯よ。】
〔(愚のように)黙々とあれ、河伯よ。〕
──「黙々とあれ」と北海若は言っています。それは通説のように「ただ黙っているがよい」とよい行為のあり方を示したというニュアンスとは違うと思います。言葉を発しないという外の行為だけでは不十分なのです。この「黙々乎」は、自分の心の内を静まらせる必要があるのだ…と河伯に呼び掛けているのではないでしょうか。
そこで付け加えました。「愚のように」と。それは「愚のように、心の中を水鏡のようにするために静かに静かに、黙々としてものごとをとらえよ。」と言っているのだと解釈したからです。
自分の疑問に振り回されて、言葉で解答を得ようとすればするほど、それをのがすことになると思うのです。俗人の心の中は、常にさざ波立っているのです。解答を知るためには、心の中にある微塵だに動かぬ水面による鏡で写し取る必要があるのです。そのためには、黙々とすることが大事なのです。それが善悪こもごも判断に迷っている俗から超然としていられる唯一の道だからなのです。
【女惡知貴賤之門小大之家】【女(なんじ)悪くんぞ貴賤の門、大小の家を知らん。】
〔お前にどうしたら貴賤の違いが生じる門や、大小の違いが生じる家がわかるだろうか。」〕
──ここは、「河伯にはわかりっこない」と上から目線で否定しているのではないと考えます。北海若の切実なる願望のあらわれた言葉なのではないでしょうか。つまり「河伯にどうやったらわかるだろうか」という疑問形で誘っているのです。「貴賤の違いが生じる門」をどこに便宜上暫定的に設け、その開閉によって貴賤があったりなかったりするツボを知ることができないだろうか、「大小の違いが生じる家」をどこに便宜上暫定的に設け、その蓋(屋根)のかぶせ方で大小があったりなかったりするツボを知ることはできないだろうか…と言っているのではないでしょうか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
荘子 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
荘子のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8447人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82528人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208285人