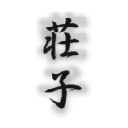━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━秋水篇━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(7)然と非
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯曰 河伯曰く。
若物之外 若物之内 若(も)しくは物の外、若しくは物の内、
惡至而倪貴賤 悪(いず)くに至りて貴賤を倪(げい)とし、
惡至而倪小大 悪くに至りて小大を倪(げい)とするかと。
北海若曰 北海若曰く。
以道観之 物无貴賤 道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。
以物観之 自貴而相賤 物を以てこれを観れば、自らを貴として相(あい)賤とす。
以俗観之 貴賤不在已 俗を以てこれを観れば、貴賤は己(おのれ)に在(あ)らず。
以差観之 差を以てこれを観れば、
因其所大而大之 其の大なる所に因(よ)りてこれを大とすると、
則萬物莫不大 則ち万物は大ならざるは莫(な)く、
因其所小而小之 其の小なる所に因りてこれを小とすると、
則萬物莫不小 則ち万物は小ならざるは莫し。
知天地之爲稊米也 天地の稊米(ていまい)たるを知り、
知豪末之爲丘山也 豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、
則差數覩矣 則ち差は数を覩(み)ん。
以功観之 功を以てこれを観れば、
因其所有而有之 其の有(ゆう)なる所に因りてこれを有とすると、
則萬物莫不有 則ち万物は有ならざるは莫く、
因其所无而无之 其の无(む)なる所に因りてこれを无とすると、
則萬物莫不无 則ち万物は无ならざるは莫し。
知東西之相反而不可以相无 東西の相反しながら而も相以て无べからざるを知れば、
則功分定矣 則ち功は分を定めん。
以趣観之 趣(しゅ)を以てこれを観れば、
因其所然而然之 其の然(しか)る所に因りてこれを然りとすると、
則萬物莫不然 則ち万物は然らざるは莫く、
因其所非而非之 其の非なる所に因りてこれを非とすると、
則萬物莫不非 則ち万物は非ならざるは莫し。
知堯桀之自然而相非 堯桀(ぎょうけつ)の自ら然りとして相非とするを知れば、
則趣操覩矣 則ち趣は操を覩(み)ん。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
河伯はいった、「万物の外でのことか、あるいは万物の中でのことか、いったいどこで貴賤の区別がつけられ、どこで大小の区別がつけられるのだろうか。」
北海若は答えた。「道の立場からみれば〔万物は斉同で〕物には貴賤はない。しかし、物の立場からみると、〔その相対の立場にとらわれて〕自分を貴いとして相手を賤しみあうものだ。世俗の立場からみると、〔大衆の評価に従うだけだから〕貴賤の分別は自分のことではなくなってしまう。いったい物の差別という観点からみるなら、それぞれの大きい点についてそれを大きいとしていれば、どんな物でもすべて大きいことになるが、それぞれの小さい点についてそれを小さいとするなら、どんな物でもすべて小さいことになる。こうして、天地も稊(ひえ)つぶと同様に小さいともいえるのだとわかり、細い毛さきも丘や山と同様に大きいともいえるのだとわかったなら、物の差別の道理は明らかになるであろう。また物のはたらきという観点からみるなら、それぞれの役立つ点についてそれを有用だとしていれば、どんな物でもすべて有用だということになるが、それぞれの役立たない点につしてそれを無用だとするなら、どんな物でもすべて無用だということになる。こうして、東と西とは反対でありながらたがいに相手を必要とするのだということがわかったなら〔つまり有用無用を一方的にきめられないということがわかったなら〕、物のはたらきの本質ははっきりするであろう。また心の志向という観点からみるなら、それぞれの正しい点についてそれを正しいとしていれば、どんな物でもすべて正しいことになるが、それぞれの誤った点についてそれを誤りとするなら、どんな物でもすべて誤っていることになる。こうして、聖人の堯(ぎょう)と暴君の桀(けつ)でさえ、たがいに自分を正しいとして相手を誤りとしていることがわかったなら、〔正しいと誤りも相対的だということがわかって、〕心の志向の根拠は明らかになるであろう。
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯は言った。
「物の外でのことなのか、もしくは物の内でのことなのか、
どこに至ったら、<貴賤>は微々たる違いにすぎないとみなせ、
どこに至ったら、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせるのだろうか。」
北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。
物(人物)を以てこれを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。
俗(一般的評価)を以てこれを観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。
差を以てこれを観るならば、
その<大>なる所に起因してこれを<大>とすると、
則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、
その<小>なる所に起因してこれを<小>とすると、
則ちその結果、万物は<小>でないものはなくなる。
天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、
細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、
則ち差で(<大小>の判断をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
功(働きの結果)を以てこれを観るならば、
その<有用>だとする所に起因してこれを<有用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことになり、
その<無用>だとする所に起因してこれを<無用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<無用>でないものはないことになる。
東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないことを知れば、
則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定しているだけのこととなるだろう。
趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、
その<然(正)>とする所に起因してこれを<然(正)>とすると、
則ちその結果、万物は<然(正)>でないものはなくなり、
その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、
則ちその結果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。
堯(ぎょう)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>としたのを知れば、
則ち趣(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(7)然と非
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯曰 河伯曰く。
若物之外 若物之内 若(も)しくは物の外、若しくは物の内、
惡至而倪貴賤 悪(いず)くに至りて貴賤を倪(げい)とし、
惡至而倪小大 悪くに至りて小大を倪(げい)とするかと。
北海若曰 北海若曰く。
以道観之 物无貴賤 道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。
以物観之 自貴而相賤 物を以てこれを観れば、自らを貴として相(あい)賤とす。
以俗観之 貴賤不在已 俗を以てこれを観れば、貴賤は己(おのれ)に在(あ)らず。
以差観之 差を以てこれを観れば、
因其所大而大之 其の大なる所に因(よ)りてこれを大とすると、
則萬物莫不大 則ち万物は大ならざるは莫(な)く、
因其所小而小之 其の小なる所に因りてこれを小とすると、
則萬物莫不小 則ち万物は小ならざるは莫し。
知天地之爲稊米也 天地の稊米(ていまい)たるを知り、
知豪末之爲丘山也 豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、
則差數覩矣 則ち差は数を覩(み)ん。
以功観之 功を以てこれを観れば、
因其所有而有之 其の有(ゆう)なる所に因りてこれを有とすると、
則萬物莫不有 則ち万物は有ならざるは莫く、
因其所无而无之 其の无(む)なる所に因りてこれを无とすると、
則萬物莫不无 則ち万物は无ならざるは莫し。
知東西之相反而不可以相无 東西の相反しながら而も相以て无べからざるを知れば、
則功分定矣 則ち功は分を定めん。
以趣観之 趣(しゅ)を以てこれを観れば、
因其所然而然之 其の然(しか)る所に因りてこれを然りとすると、
則萬物莫不然 則ち万物は然らざるは莫く、
因其所非而非之 其の非なる所に因りてこれを非とすると、
則萬物莫不非 則ち万物は非ならざるは莫し。
知堯桀之自然而相非 堯桀(ぎょうけつ)の自ら然りとして相非とするを知れば、
則趣操覩矣 則ち趣は操を覩(み)ん。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
河伯はいった、「万物の外でのことか、あるいは万物の中でのことか、いったいどこで貴賤の区別がつけられ、どこで大小の区別がつけられるのだろうか。」
北海若は答えた。「道の立場からみれば〔万物は斉同で〕物には貴賤はない。しかし、物の立場からみると、〔その相対の立場にとらわれて〕自分を貴いとして相手を賤しみあうものだ。世俗の立場からみると、〔大衆の評価に従うだけだから〕貴賤の分別は自分のことではなくなってしまう。いったい物の差別という観点からみるなら、それぞれの大きい点についてそれを大きいとしていれば、どんな物でもすべて大きいことになるが、それぞれの小さい点についてそれを小さいとするなら、どんな物でもすべて小さいことになる。こうして、天地も稊(ひえ)つぶと同様に小さいともいえるのだとわかり、細い毛さきも丘や山と同様に大きいともいえるのだとわかったなら、物の差別の道理は明らかになるであろう。また物のはたらきという観点からみるなら、それぞれの役立つ点についてそれを有用だとしていれば、どんな物でもすべて有用だということになるが、それぞれの役立たない点につしてそれを無用だとするなら、どんな物でもすべて無用だということになる。こうして、東と西とは反対でありながらたがいに相手を必要とするのだということがわかったなら〔つまり有用無用を一方的にきめられないということがわかったなら〕、物のはたらきの本質ははっきりするであろう。また心の志向という観点からみるなら、それぞれの正しい点についてそれを正しいとしていれば、どんな物でもすべて正しいことになるが、それぞれの誤った点についてそれを誤りとするなら、どんな物でもすべて誤っていることになる。こうして、聖人の堯(ぎょう)と暴君の桀(けつ)でさえ、たがいに自分を正しいとして相手を誤りとしていることがわかったなら、〔正しいと誤りも相対的だということがわかって、〕心の志向の根拠は明らかになるであろう。
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯は言った。
「物の外でのことなのか、もしくは物の内でのことなのか、
どこに至ったら、<貴賤>は微々たる違いにすぎないとみなせ、
どこに至ったら、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせるのだろうか。」
北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。
物(人物)を以てこれを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。
俗(一般的評価)を以てこれを観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。
差を以てこれを観るならば、
その<大>なる所に起因してこれを<大>とすると、
則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、
その<小>なる所に起因してこれを<小>とすると、
則ちその結果、万物は<小>でないものはなくなる。
天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、
細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、
則ち差で(<大小>の判断をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
功(働きの結果)を以てこれを観るならば、
その<有用>だとする所に起因してこれを<有用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことになり、
その<無用>だとする所に起因してこれを<無用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<無用>でないものはないことになる。
東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないことを知れば、
則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定しているだけのこととなるだろう。
趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、
その<然(正)>とする所に起因してこれを<然(正)>とすると、
則ちその結果、万物は<然(正)>でないものはなくなり、
その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、
則ちその結果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。
堯(ぎょう)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>としたのを知れば、
則ち趣(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
|
|
|
コメント(16)
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 河伯曰 ┃【河伯曰く、】
┃ 若物之外 若物之内 ┃【若(も)しくは物の外、若しくは物の内、】
┃ 惡至而倪貴賤 ┃【悪(いず)くに至りて貴賤を倪(げい)とし、】
┃ 惡至而倪小大 ┃【悪くに至りて小大を倪(げい)とするかと。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
河伯は言った。
「物の外でのことなのか、もしくは物の内でのことなのか、
どこに至ったら、<貴賤>は微々たる違いにすぎないとみなせ、
どこに至ったら、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせるのだろうか。」
…………………………………………………………………………………………………………
◆通説では、【至】の意味は無視しています。【倪】は「かぎり」と読んで、「区別をつけ
る」と意訳しています。
【河伯曰く、若(も)しくは物の外、若しくは物の内、悪(いず)くに至りて貴賤を倪(かぎ)
り、悪くに至りて小大を倪(かぎ)らんやと。】は〔河伯はいった、「万物の外でのこと
か、あるいは万物の中でのことか、いったいどこで貴賤の区別がつけられ、どこで大小
の区別がつけられるのだろうか。」〕としています。
◇新解釈では、【惡至】は「どこに至ったら」と言っているものだとみなしました。
【倪】については、前にも説明したように難しい概念ですが、「(最小限の末端→)微々た
る違い」としました。
【河伯曰く、若(も)しくは物の外、若しくは物の内、悪(いず)くに至りて貴賤を倪(げい)
とし、悪くに至りて小大を倪(げい)とするかと。】は〔河伯は言った。「物の外でのこ
となのか、もしくは物の内でのことなのか、どこに至ったら、<貴賤>は微々たる違い
にすぎないとみなせ、どこに至ったら、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせる
のだろうか。」〕としました。
┃▼ 河伯曰 ┃【河伯曰く、】
┃ 若物之外 若物之内 ┃【若(も)しくは物の外、若しくは物の内、】
┃ 惡至而倪貴賤 ┃【悪(いず)くに至りて貴賤を倪(げい)とし、】
┃ 惡至而倪小大 ┃【悪くに至りて小大を倪(げい)とするかと。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
河伯は言った。
「物の外でのことなのか、もしくは物の内でのことなのか、
どこに至ったら、<貴賤>は微々たる違いにすぎないとみなせ、
どこに至ったら、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせるのだろうか。」
…………………………………………………………………………………………………………
◆通説では、【至】の意味は無視しています。【倪】は「かぎり」と読んで、「区別をつけ
る」と意訳しています。
【河伯曰く、若(も)しくは物の外、若しくは物の内、悪(いず)くに至りて貴賤を倪(かぎ)
り、悪くに至りて小大を倪(かぎ)らんやと。】は〔河伯はいった、「万物の外でのこと
か、あるいは万物の中でのことか、いったいどこで貴賤の区別がつけられ、どこで大小
の区別がつけられるのだろうか。」〕としています。
◇新解釈では、【惡至】は「どこに至ったら」と言っているものだとみなしました。
【倪】については、前にも説明したように難しい概念ですが、「(最小限の末端→)微々た
る違い」としました。
【河伯曰く、若(も)しくは物の外、若しくは物の内、悪(いず)くに至りて貴賤を倪(げい)
とし、悪くに至りて小大を倪(げい)とするかと。】は〔河伯は言った。「物の外でのこ
となのか、もしくは物の内でのことなのか、どこに至ったら、<貴賤>は微々たる違い
にすぎないとみなせ、どこに至ったら、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせる
のだろうか。」〕としました。
●通説では、次のようになっています。
河伯はいった、「万物の外でのことか、あるいは万物の中でのことか、いったいどこで貴賤の区別がつけられ、どこで大小の区別がつけられるのだろうか。」
〇新解釈では、次のようになります。
河伯は言った。「物の外でのことなのか、もしくは物の内でのことなのか、
どこに至ったら、<貴賤>は微々たる違いにすぎないとみなし、
どこに至ったら、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせるのだろうか。」
【河伯曰】【河伯曰く、】
【若物之外 若物之内】【若(も)しくは物の外、若しくは物の内、】
〔河伯は言った。〕
〔「物の外でのことなのか、もしくは物の内でのことなのか、〕
──「物の外」「物の内」…言葉は簡単ですが、どういったことを指すのか、実感をつかみにくい概念です。別の言葉で言いかえたなら、「物の外」とは天地よりもっと大きい、あるいは粗よりもっと大きい「外宇宙の世界」のことを指し、「物の内」とは細い毛先よりもっと小さい、あるいは精よりもっと小さい「内宇宙の世界」といったニュアンスでしょうか。
【惡至而倪貴賤】【悪(いず)くに至りて貴賤を倪(げい)とし、】
【惡至而倪小大】【悪くに至りて小大を倪(げい)とするかと。】
〔どこに至って、<貴賤>は微々たる違いにすぎないとみなせ、〕
〔どこに至って、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせるのだろうか。」〕
──どこに至ったら、つまり、どのような境地に至れば、大きな違いがあると思っていた<貴賤>のへだたりが最小限の微々たる違いにすぎないと思えるようになれるのだろうか。またどのような境地に至れば、大きな違いがあると思っていた<大小>のへだたりは最小限の微々たる違いに過ぎないと思えるようになれるのだろうか…と疑問を投げかけているようです。
河伯はいった、「万物の外でのことか、あるいは万物の中でのことか、いったいどこで貴賤の区別がつけられ、どこで大小の区別がつけられるのだろうか。」
〇新解釈では、次のようになります。
河伯は言った。「物の外でのことなのか、もしくは物の内でのことなのか、
どこに至ったら、<貴賤>は微々たる違いにすぎないとみなし、
どこに至ったら、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせるのだろうか。」
【河伯曰】【河伯曰く、】
【若物之外 若物之内】【若(も)しくは物の外、若しくは物の内、】
〔河伯は言った。〕
〔「物の外でのことなのか、もしくは物の内でのことなのか、〕
──「物の外」「物の内」…言葉は簡単ですが、どういったことを指すのか、実感をつかみにくい概念です。別の言葉で言いかえたなら、「物の外」とは天地よりもっと大きい、あるいは粗よりもっと大きい「外宇宙の世界」のことを指し、「物の内」とは細い毛先よりもっと小さい、あるいは精よりもっと小さい「内宇宙の世界」といったニュアンスでしょうか。
【惡至而倪貴賤】【悪(いず)くに至りて貴賤を倪(げい)とし、】
【惡至而倪小大】【悪くに至りて小大を倪(げい)とするかと。】
〔どこに至って、<貴賤>は微々たる違いにすぎないとみなせ、〕
〔どこに至って、<小大>は微々たる違いにすぎないとみなせるのだろうか。」〕
──どこに至ったら、つまり、どのような境地に至れば、大きな違いがあると思っていた<貴賤>のへだたりが最小限の微々たる違いにすぎないと思えるようになれるのだろうか。またどのような境地に至れば、大きな違いがあると思っていた<大小>のへだたりは最小限の微々たる違いに過ぎないと思えるようになれるのだろうか…と疑問を投げかけているようです。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 北海若曰 ┃【北海若曰く。】
┃ 以道観之 ┃【道を以てこれを観れば、】
┃ 物无貴賤 ┃【物に貴賤なし。】
┃ 以物観之 ┃【物を以てこれを観れば、】
┃ 自貴而相賤 ┃【自らを貴とし、相(あい)賤とす。】
┃ 以俗観之 ┃【俗を以てこれを観れば、】
┃ 貴賤不在已 ┃【貴賤は己(おのれ)に在(あ)らず。】
┗━━━━━━━━┛
北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。
物(人物)を以てこれを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。
俗(一般的評価)を以てこれを観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【俗】は、「人+谷(あなから水が八型に流れ出るさま)」で、「中にはいりこむ」意を含
み、「人間がその中にはいりこみ、ひたりこんでいる環境、つまり、ならわしのこと」。
「だれにもそうだと認められるやり方・一般の常識」。
◆通説では、【北海若曰く、道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。物を以てこれを観れば、
自らを貴しとして相(あい)賤しむ。俗を以てこれを観れば、貴賤は己(おのれ)に在(あ)
らず。】は、〔北海若は答えた。「道の立場からみれば〔万物は斉同で〕物には貴賤はな
い。しかし、物の立場からみると、〔その相対の立場にとらわれて〕自分を貴いとして相
手を賤しみあうものだ。世俗の立場からみると、〔大衆の評価に従うだけだから〕貴賤の
分別は自分のことではなくなってしまう。〕としています。
◇【北海若曰く。道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。物を以てこれを観れば、自らを
貴として相(あい)賤とす。俗を以てこれを観れば、貴賤は己(おのれ)に在(あ)らず。】
は、〔北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。物(人物)を以て
これを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。俗(一般的評価)を以てこれを
観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。〕としました。
┃▼ 北海若曰 ┃【北海若曰く。】
┃ 以道観之 ┃【道を以てこれを観れば、】
┃ 物无貴賤 ┃【物に貴賤なし。】
┃ 以物観之 ┃【物を以てこれを観れば、】
┃ 自貴而相賤 ┃【自らを貴とし、相(あい)賤とす。】
┃ 以俗観之 ┃【俗を以てこれを観れば、】
┃ 貴賤不在已 ┃【貴賤は己(おのれ)に在(あ)らず。】
┗━━━━━━━━┛
北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。
物(人物)を以てこれを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。
俗(一般的評価)を以てこれを観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【俗】は、「人+谷(あなから水が八型に流れ出るさま)」で、「中にはいりこむ」意を含
み、「人間がその中にはいりこみ、ひたりこんでいる環境、つまり、ならわしのこと」。
「だれにもそうだと認められるやり方・一般の常識」。
◆通説では、【北海若曰く、道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。物を以てこれを観れば、
自らを貴しとして相(あい)賤しむ。俗を以てこれを観れば、貴賤は己(おのれ)に在(あ)
らず。】は、〔北海若は答えた。「道の立場からみれば〔万物は斉同で〕物には貴賤はな
い。しかし、物の立場からみると、〔その相対の立場にとらわれて〕自分を貴いとして相
手を賤しみあうものだ。世俗の立場からみると、〔大衆の評価に従うだけだから〕貴賤の
分別は自分のことではなくなってしまう。〕としています。
◇【北海若曰く。道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。物を以てこれを観れば、自らを
貴として相(あい)賤とす。俗を以てこれを観れば、貴賤は己(おのれ)に在(あ)らず。】
は、〔北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。物(人物)を以て
これを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。俗(一般的評価)を以てこれを
観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。〕としました。
●通説では、次のようになっています。
北海若は答えた。「道の立場からみれば〔万物は斉同で〕物には貴賤はない。しかし、物の立場からみると、〔その相対の立場にとらわれて〕自分を貴いとして相手を賤しみあうものだ。世俗の立場からみると、〔大衆の評価に従うだけだから〕貴賤の分別は自分のことではなくなってしまう。
〇新解釈では、次のようになります。
北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。
物(人物)を以てこれを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。
俗(一般的評価)を以てこれを観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。
【北海若曰】【北海若曰く。】
【以道観之 物无貴賤】【道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。】
〔北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。〕
──北海若は河伯の問いに応じて語ります。
(人間の関与の有無に関係ない)道の立場よりこれを観たならば、物(万物、人物、物体)には、貴賤といった差別に通じる違いは微塵もない…と言っているようです。
【以物観之】【物を以てこれを観れば、】
【自貴而相賤】【自らを貴とし、相(あい)賤とす。】
〔物(人物)を以てこれを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。〕
──物(個人という人物)の立場よりこれを観たならば、自己本位になりがちで、大きな差別の意識が生まれ、それぞれが自分を<貴い>と見なすようになると、おのずと相手を<賤しい>とお互いに見なすようになっているものだ…と言っているようです。
<貴賤>の違いは微々たるものに思える境地に至れるどころか、大きな違いを意識することになるということでしょう。
【以俗観之】【俗を以てこれを観れば、】
【貴賤不在已】【貴賤は己(おのれ)に在(あ)らず。】
〔俗(一般的評価)を以てこれを観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。〕
──俗(個々人ではなく、一般大衆の評価)の立場からこれを観たならば、一般的な<貴賤>の差別意識をもったままの境地にとどまり、己自身の中で<貴賤>が微々たる違いとみなせるまでの境地に至れるルートとは切り離されたものになってしまう…と言っているようです。
北海若は答えた。「道の立場からみれば〔万物は斉同で〕物には貴賤はない。しかし、物の立場からみると、〔その相対の立場にとらわれて〕自分を貴いとして相手を賤しみあうものだ。世俗の立場からみると、〔大衆の評価に従うだけだから〕貴賤の分別は自分のことではなくなってしまう。
〇新解釈では、次のようになります。
北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。
物(人物)を以てこれを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。
俗(一般的評価)を以てこれを観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。
【北海若曰】【北海若曰く。】
【以道観之 物无貴賤】【道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。】
〔北海若は言った。「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。〕
──北海若は河伯の問いに応じて語ります。
(人間の関与の有無に関係ない)道の立場よりこれを観たならば、物(万物、人物、物体)には、貴賤といった差別に通じる違いは微塵もない…と言っているようです。
【以物観之】【物を以てこれを観れば、】
【自貴而相賤】【自らを貴とし、相(あい)賤とす。】
〔物(人物)を以てこれを観れば、自分を<貴>とし相手を<賤>としあう。〕
──物(個人という人物)の立場よりこれを観たならば、自己本位になりがちで、大きな差別の意識が生まれ、それぞれが自分を<貴い>と見なすようになると、おのずと相手を<賤しい>とお互いに見なすようになっているものだ…と言っているようです。
<貴賤>の違いは微々たるものに思える境地に至れるどころか、大きな違いを意識することになるということでしょう。
【以俗観之】【俗を以てこれを観れば、】
【貴賤不在已】【貴賤は己(おのれ)に在(あ)らず。】
〔俗(一般的評価)を以てこれを観れば、<貴賤>は己の境地とは関係なくなってしまう。〕
──俗(個々人ではなく、一般大衆の評価)の立場からこれを観たならば、一般的な<貴賤>の差別意識をもったままの境地にとどまり、己自身の中で<貴賤>が微々たる違いとみなせるまでの境地に至れるルートとは切り離されたものになってしまう…と言っているようです。
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 以差観之 ┃【差を以てこれを観れば、】
┃ 因其所大而大之 ┃【其の大なる所に因(よ)りてこれを大とすると、】
┃ 則萬物莫不大 ┃【則ち万物は大ならざるは莫(な)く、】
┃ 因其所小而小之 ┃【其の小なる所に因りてこれを小とすると、】
┃ 則萬物莫不小 ┃【則ち万物は小ならざるは莫し。】
┗━━━━━━━━━━┛
差を以てこれを観るならば、
その<大>なる所に起因してこれを<大>とすると、
則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、
その<小>なる所に起因してこれを<小>とすると、
則ちその結果、万物は<小>でないものはなくなる。
…………………………………………………………………………………………………………
*【差】は、「[穂の形]+左(そばから左手でささえる・交叉)」で、「穂を交差してささ
えると、上端は×型となり、そろわない。そのじくざくした姿」を示します。「違い」。
◆通説では、【差】を「差別」と訳しています。
【差を以てこれを観れば、其の大なる所に因(よ)りてこれを大とするときは、則ち万物
は大ならざるは莫(な)く、其の小なる所に因りてこれを小とするときは、則ち万物は小
ならざるは莫し。】は「いったい物の差別という観点からみるなら、それぞれの大きい
点についてそれを大きいとしていれば、どんな物でもすべて大きいことになるが、それ
ぞれの小さい点についてそれを小さいとするなら、どんな物でもすべて小さいことにな
る。」としています。
◇【差】は「差」のままにしました (<貴賤>と言えば「差別」の感情が生まれるでしょ
うが、<大小>と言えば「差異」の感覚でとらえらると思うからです) 。
【差を以てこれを観れば、其の大なる所に因(よ)りてこれを大とすると、則ち万物は大
ならざるは莫(な)く、其の小なる所に因りてこれを小とすると、則ち万物は小ならざる
は莫し。】は「差を以てこれを観るならば、その<大>なる所に起因してこれ<大>と
すると、則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、その<小>なるを所に起
因してこれを<小>とすると、則ちその結果、万物は<小>でないものはなくなる。」
としました。
┃▼ 以差観之 ┃【差を以てこれを観れば、】
┃ 因其所大而大之 ┃【其の大なる所に因(よ)りてこれを大とすると、】
┃ 則萬物莫不大 ┃【則ち万物は大ならざるは莫(な)く、】
┃ 因其所小而小之 ┃【其の小なる所に因りてこれを小とすると、】
┃ 則萬物莫不小 ┃【則ち万物は小ならざるは莫し。】
┗━━━━━━━━━━┛
差を以てこれを観るならば、
その<大>なる所に起因してこれを<大>とすると、
則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、
その<小>なる所に起因してこれを<小>とすると、
則ちその結果、万物は<小>でないものはなくなる。
…………………………………………………………………………………………………………
*【差】は、「[穂の形]+左(そばから左手でささえる・交叉)」で、「穂を交差してささ
えると、上端は×型となり、そろわない。そのじくざくした姿」を示します。「違い」。
◆通説では、【差】を「差別」と訳しています。
【差を以てこれを観れば、其の大なる所に因(よ)りてこれを大とするときは、則ち万物
は大ならざるは莫(な)く、其の小なる所に因りてこれを小とするときは、則ち万物は小
ならざるは莫し。】は「いったい物の差別という観点からみるなら、それぞれの大きい
点についてそれを大きいとしていれば、どんな物でもすべて大きいことになるが、それ
ぞれの小さい点についてそれを小さいとするなら、どんな物でもすべて小さいことにな
る。」としています。
◇【差】は「差」のままにしました (<貴賤>と言えば「差別」の感情が生まれるでしょ
うが、<大小>と言えば「差異」の感覚でとらえらると思うからです) 。
【差を以てこれを観れば、其の大なる所に因(よ)りてこれを大とすると、則ち万物は大
ならざるは莫(な)く、其の小なる所に因りてこれを小とすると、則ち万物は小ならざる
は莫し。】は「差を以てこれを観るならば、その<大>なる所に起因してこれ<大>と
すると、則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、その<小>なるを所に起
因してこれを<小>とすると、則ちその結果、万物は<小>でないものはなくなる。」
としました。
●通説では、次のようになっています。
いったい物の差別という観点からみるなら、それぞれの大きい点についてそれを大きいとしていれば、どんな物でもすべて大きいことになるが、それぞれの小さい点についてそれを小さいとするなら、どんな物でもすべて小さいことになる。
〇新解釈では、次のようになります。
差を以てこれを観るならば、
その<大>なる所に起因してこれ<大>とすると、
則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、
その<小>なるを所に起因してこれを<小>とすると、
則ちその結果、万物は<小>でないものはなくなる。
【以差観之】【差を以てこれを観れば、】
〔差を以てこれを観るならば、〕
──ものの「差」を感じる、「違い」を認識するというのは、もともと自分が普通にもっている尺度で既に<大小>の判断をしているものなのです。すでに判断を下している「差」で以て対象を観るならば、どんな認識の仕方ができるのでしょうか。
【因其所大而大之】【其の大なる所に因(よ)りてこれを大とすると、】
【則萬物莫不大】【則ち万物は大ならざるは莫(な)く、】
〔その<大>なる所に起因してこれを<大>とすると、〕
〔則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、〕
──ある対象を、もともともっている判断基準で、これが<大>だという所を起点した上に下す判断で<大>だとすると、その結果は、万物、つまりどんな物であっても<大>ではないというものはなくなり、太鼓判を押したかのようにこれは<大>なのだという固定概念が生まれるということになりそうです。
【因其所小而小之】【其の小なる所に因りてこれを小とすると、】
【則萬物莫不小】【則ち万物は小ならざるは莫し。】
〔その<小>なる所に起因してこれを<小>とすると、〕
〔則ち(その結果)万物は<小>でないものはなくなる。〕
──<大>という意識が確定している時、もう一方で同様の過程を通して<小>を意識しているものです。ですから、ある対象をこれが<小>だという所を起点とした上に下す判断が<小>だとすると、その結果は、万物、つまりどんな物であっても<小>ではないというものはなくなり、決定的にこれは<小>なのだという固定概念が生まれることになりそうです。
このようにして「差」を以て対象を観ている限り、<大>は<大>、<小>は<小>として断定的なはっきりと大きな違いになってしまい、微々たる違いと思えるような境地には至れないようです。また、一方では万物は<大>、一方では万物は<小>とする偏った意識が、その両方を認めようとすると矛盾を孕んだままの認識をすることにもなるかもしれません。
いったい物の差別という観点からみるなら、それぞれの大きい点についてそれを大きいとしていれば、どんな物でもすべて大きいことになるが、それぞれの小さい点についてそれを小さいとするなら、どんな物でもすべて小さいことになる。
〇新解釈では、次のようになります。
差を以てこれを観るならば、
その<大>なる所に起因してこれ<大>とすると、
則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、
その<小>なるを所に起因してこれを<小>とすると、
則ちその結果、万物は<小>でないものはなくなる。
【以差観之】【差を以てこれを観れば、】
〔差を以てこれを観るならば、〕
──ものの「差」を感じる、「違い」を認識するというのは、もともと自分が普通にもっている尺度で既に<大小>の判断をしているものなのです。すでに判断を下している「差」で以て対象を観るならば、どんな認識の仕方ができるのでしょうか。
【因其所大而大之】【其の大なる所に因(よ)りてこれを大とすると、】
【則萬物莫不大】【則ち万物は大ならざるは莫(な)く、】
〔その<大>なる所に起因してこれを<大>とすると、〕
〔則ちその結果、万物は<大>でないものはなくなり、〕
──ある対象を、もともともっている判断基準で、これが<大>だという所を起点した上に下す判断で<大>だとすると、その結果は、万物、つまりどんな物であっても<大>ではないというものはなくなり、太鼓判を押したかのようにこれは<大>なのだという固定概念が生まれるということになりそうです。
【因其所小而小之】【其の小なる所に因りてこれを小とすると、】
【則萬物莫不小】【則ち万物は小ならざるは莫し。】
〔その<小>なる所に起因してこれを<小>とすると、〕
〔則ち(その結果)万物は<小>でないものはなくなる。〕
──<大>という意識が確定している時、もう一方で同様の過程を通して<小>を意識しているものです。ですから、ある対象をこれが<小>だという所を起点とした上に下す判断が<小>だとすると、その結果は、万物、つまりどんな物であっても<小>ではないというものはなくなり、決定的にこれは<小>なのだという固定概念が生まれることになりそうです。
このようにして「差」を以て対象を観ている限り、<大>は<大>、<小>は<小>として断定的なはっきりと大きな違いになってしまい、微々たる違いと思えるような境地には至れないようです。また、一方では万物は<大>、一方では万物は<小>とする偏った意識が、その両方を認めようとすると矛盾を孕んだままの認識をすることにもなるかもしれません。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 知天地之爲稊米也 ┃【天地の稊米(ていまい)たるを知り、】
┃ 知豪末之爲丘山也 ┃【豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、】
┃ 則差數覩矣 ┃【則ち差は数を覩(み)ん。】
┗━━━━━━━━━━━┛
天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、
細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、
則ち差で(<大小>の判断をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【覩(睹)】は、「視線を集めてみる」意。
◆通説では、【差數覩矣】の「【数】は理の意。【差数】は差別の原理ということ。万物の
大小・貴賤の差別がどこから生まれ、どのようなものとして規定されるかという原理。
結局、それが相対的なものであることがあきらかになるだろうということ。」と説明し
ています。
【天地の稊米(ていまい)たるを知り、豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、
則ち差数覩(さすうみ)えん。】は「こうして、天地も稊(ひえ)つぶと同様に小さいとも
いえるのだとわかり、細い毛さきも丘や山と同様に大きいともいえるのだとわかったな
ら、物の差別の道理は明らかになるであろう。」としています。
◇【天地の稊米(ていまい)たるを知り、豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、
則ち差は数を覩(み)ん。】は「天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、
細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、則ち差で(<大小>の判断
をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。」としまし
た。
┃▼ 知天地之爲稊米也 ┃【天地の稊米(ていまい)たるを知り、】
┃ 知豪末之爲丘山也 ┃【豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、】
┃ 則差數覩矣 ┃【則ち差は数を覩(み)ん。】
┗━━━━━━━━━━━┛
天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、
細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、
則ち差で(<大小>の判断をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【覩(睹)】は、「視線を集めてみる」意。
◆通説では、【差數覩矣】の「【数】は理の意。【差数】は差別の原理ということ。万物の
大小・貴賤の差別がどこから生まれ、どのようなものとして規定されるかという原理。
結局、それが相対的なものであることがあきらかになるだろうということ。」と説明し
ています。
【天地の稊米(ていまい)たるを知り、豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、
則ち差数覩(さすうみ)えん。】は「こうして、天地も稊(ひえ)つぶと同様に小さいとも
いえるのだとわかり、細い毛さきも丘や山と同様に大きいともいえるのだとわかったな
ら、物の差別の道理は明らかになるであろう。」としています。
◇【天地の稊米(ていまい)たるを知り、豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、
則ち差は数を覩(み)ん。】は「天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、
細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、則ち差で(<大小>の判断
をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。」としまし
た。
●通説では、次のようになっています。
こうして、天地も稊(ひえ)つぶと同様に小さいともいえるのだとわかり、細い毛さきも丘や山と同様に大きいともいえるのだとわかったなら、物の差別の道理は明らかになるであろう。
〇新解釈では、次のようになります。
天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、
細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、
則ち差で(<大小>の判断をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
【知天地之爲稊米也】【天地の稊米(ていまい)たるを知り、】
【知豪末之爲丘山也】【豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、】
〔(ところが、)天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、〕
〔細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、
──通常の判断では<大>とみなされる天地でさえも、のびえ粒のように<小>とも言えることを知るには、通常の常識的なものを観るピントでない、望遠鏡的ピント意識が必要かもしれません。
通常の判断では<小>とみなせる細かい毛先さえも、丘や山のように<大>とも言えることを知るには、顕微鏡的ピント意識が必要かもしれません。
つまりは、<大小>の差が無いに等しいほど微々たる違いとみなせる境地は、肉眼的ピントに加えて望遠鏡的ピントや顕微鏡的ピントを必要に応じて自在に駆使してものごとを知ってゆくことにあり、<大小>の判断は固定されたものはなく、<大>が<小>になったり、<小>が<大>になったり、その都度の視点から生まれる暫定的な判断だということになり、無限に広がる境地なのだ…と言っているようです。
【則差數覩矣】【則ち差は数を覩(み)えん。】
〔則ち差で(<大小>の判断をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみるだけのこととなるだろう。〕
──「数」とはいったい何を意味しているのでしょうか。
それは「19、河伯と北海若(5)精と粗」で表現されていた、
- - - - -
(本当の)形ないものは、「数」で分けることは不可能であり、
(本当の)枠づけできないものは、「数」で窮めることは不可能である。
- - - - -
と言っていた言葉の中にヒントがあるのかもしれません。「数」で計れるものはいくらがんばって増えても有限なのだと言えそうです。常識的(肉眼的)ピント意識で認識できる<大小>の「差」は「数」で把握できるもので、有限なものに意識を狭めてみるだけのこととなるだろう…と言っているようです。
「観る」は、ありのままを「観察する」ということになるでしょうが、「覩(み)る」は一所に「視線を集めてみる」ということなので、物の外にも物の内にも無限に向かって意識の視野が広がっていくのではなく、限られた所(有限のもの)に視野が狭められるようなイメージで、わざわざ使い分けているのではないかと思います。
こうして、天地も稊(ひえ)つぶと同様に小さいともいえるのだとわかり、細い毛さきも丘や山と同様に大きいともいえるのだとわかったなら、物の差別の道理は明らかになるであろう。
〇新解釈では、次のようになります。
天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、
細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、
則ち差で(<大小>の判断をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
【知天地之爲稊米也】【天地の稊米(ていまい)たるを知り、】
【知豪末之爲丘山也】【豪末(ごうまつ)の丘山(きゅうざん)たるを知れば、】
〔(ところが、)天地ものびえ粒のように<小>とも言えることを知り、〕
〔細かい毛先も丘や山のように<大>とも言えることを知れば、
──通常の判断では<大>とみなされる天地でさえも、のびえ粒のように<小>とも言えることを知るには、通常の常識的なものを観るピントでない、望遠鏡的ピント意識が必要かもしれません。
通常の判断では<小>とみなせる細かい毛先さえも、丘や山のように<大>とも言えることを知るには、顕微鏡的ピント意識が必要かもしれません。
つまりは、<大小>の差が無いに等しいほど微々たる違いとみなせる境地は、肉眼的ピントに加えて望遠鏡的ピントや顕微鏡的ピントを必要に応じて自在に駆使してものごとを知ってゆくことにあり、<大小>の判断は固定されたものはなく、<大>が<小>になったり、<小>が<大>になったり、その都度の視点から生まれる暫定的な判断だということになり、無限に広がる境地なのだ…と言っているようです。
【則差數覩矣】【則ち差は数を覩(み)えん。】
〔則ち差で(<大小>の判断をするの)は、(有限な)数に視線を集めてみるだけのこととなるだろう。〕
──「数」とはいったい何を意味しているのでしょうか。
それは「19、河伯と北海若(5)精と粗」で表現されていた、
- - - - -
(本当の)形ないものは、「数」で分けることは不可能であり、
(本当の)枠づけできないものは、「数」で窮めることは不可能である。
- - - - -
と言っていた言葉の中にヒントがあるのかもしれません。「数」で計れるものはいくらがんばって増えても有限なのだと言えそうです。常識的(肉眼的)ピント意識で認識できる<大小>の「差」は「数」で把握できるもので、有限なものに意識を狭めてみるだけのこととなるだろう…と言っているようです。
「観る」は、ありのままを「観察する」ということになるでしょうが、「覩(み)る」は一所に「視線を集めてみる」ということなので、物の外にも物の内にも無限に向かって意識の視野が広がっていくのではなく、限られた所(有限のもの)に視野が狭められるようなイメージで、わざわざ使い分けているのではないかと思います。
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 以功観之 ┃【功を以てこれを観れば、】
┃ 因其所有而有之 ┃【其の有(ゆう)の所に因りてこれを有とすると、】
┃ 則萬物莫不有 ┃【則ち万物は有ならざるは莫く、】
┃ 因其所无而无之 ┃【其の无(む)の所に因りてこれを无とすると、】
┃ 則萬物莫不无 ┃【則ち万物は无ならざるは莫し。】
┗━━━━━━━━━━┛
功(働きの結果)を以てこれを観るならば、
その<有用>だとする所を起因としてこれを<有用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことになり、
その<無用>だとする所を起因としてこれを<無用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<無用>でないものはないことになる。
…………………………………………………………………………………………………………
*【功】は、「力+工(上下両面にあなをあけること)」で、「あなをあけることはむつか
しい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえのこと」。「てがら・
やりばえ)」「働きの結果、成し遂げた仕事」。「ききめ、実り」。「努力、工夫」。
◆通説では、【功を以てこれを観れば、其の有る所に因りてこれを有りとするときは、則ち
万物は有らざるは莫く、其の無(な)き所に因りてこれを無しとするときは、則ち万物は
無からざるは莫し。】は「また物のはたらきという観点からみるなら、それぞれの役立
つ点についてそれを有用だとしていれば、どんな物でもすべて有用だということになる
が、それぞれの役立たない点につしてそれを無用だとするなら、どんな物でもすべて無
用だということになる。」としています。
◇【功を以てこれを観れば、其の有(ゆう)の所に因りてこれを有とすると、則ち万物は有
ならざるは莫く、其の无(む)の所に因りこれを无とすると、則ち万物は无ならざるは莫
し。】は「功(働きの結果)を以てこれを観れば、その<有用>だとする所を起因として
これを<有用>だとすれば、則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことにな
り、その<無用>だとする所を起因としてこれを<無用>だとすれば、則ちその結果、
万物は<無用>でないものはないことになる。」としました。
┃▼ 以功観之 ┃【功を以てこれを観れば、】
┃ 因其所有而有之 ┃【其の有(ゆう)の所に因りてこれを有とすると、】
┃ 則萬物莫不有 ┃【則ち万物は有ならざるは莫く、】
┃ 因其所无而无之 ┃【其の无(む)の所に因りてこれを无とすると、】
┃ 則萬物莫不无 ┃【則ち万物は无ならざるは莫し。】
┗━━━━━━━━━━┛
功(働きの結果)を以てこれを観るならば、
その<有用>だとする所を起因としてこれを<有用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことになり、
その<無用>だとする所を起因としてこれを<無用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<無用>でないものはないことになる。
…………………………………………………………………………………………………………
*【功】は、「力+工(上下両面にあなをあけること)」で、「あなをあけることはむつか
しい仕事で努力を要するので、その工夫をこらした仕事とできばえのこと」。「てがら・
やりばえ)」「働きの結果、成し遂げた仕事」。「ききめ、実り」。「努力、工夫」。
◆通説では、【功を以てこれを観れば、其の有る所に因りてこれを有りとするときは、則ち
万物は有らざるは莫く、其の無(な)き所に因りてこれを無しとするときは、則ち万物は
無からざるは莫し。】は「また物のはたらきという観点からみるなら、それぞれの役立
つ点についてそれを有用だとしていれば、どんな物でもすべて有用だということになる
が、それぞれの役立たない点につしてそれを無用だとするなら、どんな物でもすべて無
用だということになる。」としています。
◇【功を以てこれを観れば、其の有(ゆう)の所に因りてこれを有とすると、則ち万物は有
ならざるは莫く、其の无(む)の所に因りこれを无とすると、則ち万物は无ならざるは莫
し。】は「功(働きの結果)を以てこれを観れば、その<有用>だとする所を起因として
これを<有用>だとすれば、則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことにな
り、その<無用>だとする所を起因としてこれを<無用>だとすれば、則ちその結果、
万物は<無用>でないものはないことになる。」としました。
●通説では、次のようになっています。
また物のはたらきという観点からみるなら、それぞれの役立つ点についてそれを有用だとしていれば、どんな物でもすべて有用だということになるが、それぞれの役立たない点につしてそれを無用だとするなら、どんな物でもすべて無用だということになる。
〇新解釈では、次のようになります。
功(働きの結果)を以てこれを観れば、
その<有用>だとする所を起因としてこれを<有用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことになり、
その<無用>だとする所を起因としてこれを<無用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<無用>でないものはないことになる。
【以功観之】【功を以てこれを観れば、】
〔功(働きの結果)を以てこれを観れば、〕
──ものの「功」、「功績」を実感する、「働きの結果」を認識するというのは、もともと自分が普通にもっている尺度で既に用の<有無>の判断をしているものなのです。すでに判断を下している「働きの結果」で以て対象を観るならば、どんな認識の仕方ができるのでしょうか。
【因其所有而有之】【其の有(ゆう)の所に因りてこれを有とすると、】
【則萬物莫不有】【則ち万物は有ならざるは莫く、】
〔その<有用>だとする所を起因としてこれを<有用>だとすれば、〕
〔則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことになり、〕
──既成概念で、ある「働きの結果」をすでに<有用>なことだと判断しているところをもとにして、これは<有用>だと認識する方法をとるならば、万物、どんなことでも<有用>ではないものはない、つまり、すべては<有用>なのだという固定概念が生まれる…と言っているようです。
【因其所无而无之】【其の无(む)の所を因としてこれを无とすると、】
【則萬物莫不无】【則ち万物は无ならざるは莫し。】
〔その<無用>だとする所を起因としてこれを<無用>だとすれば、〕
〔則ちその結果、万物は<無用>でないものはないことになる。〕
──ある「働きの結果」が一方で<有用>と判断を下している時には、別のもう一方の何かの「働きの結果」を<無用>なものだと判断を下しているものなのです。既成概念で、ある「働きの結果」をすでに<無用>なことだと判断しているところをもとにして、これは<無用>だと認識する方法をとるならば、万物、どんなことでも<無用>ではないものはない、つまり、すべては<無用>なだという固定概念が生まれる…と言っているようです。
この概念の認識をそのまま認めることにしたら矛盾を孕むことになるようです。
また物のはたらきという観点からみるなら、それぞれの役立つ点についてそれを有用だとしていれば、どんな物でもすべて有用だということになるが、それぞれの役立たない点につしてそれを無用だとするなら、どんな物でもすべて無用だということになる。
〇新解釈では、次のようになります。
功(働きの結果)を以てこれを観れば、
その<有用>だとする所を起因としてこれを<有用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことになり、
その<無用>だとする所を起因としてこれを<無用>だとすれば、
則ちその結果、万物は<無用>でないものはないことになる。
【以功観之】【功を以てこれを観れば、】
〔功(働きの結果)を以てこれを観れば、〕
──ものの「功」、「功績」を実感する、「働きの結果」を認識するというのは、もともと自分が普通にもっている尺度で既に用の<有無>の判断をしているものなのです。すでに判断を下している「働きの結果」で以て対象を観るならば、どんな認識の仕方ができるのでしょうか。
【因其所有而有之】【其の有(ゆう)の所に因りてこれを有とすると、】
【則萬物莫不有】【則ち万物は有ならざるは莫く、】
〔その<有用>だとする所を起因としてこれを<有用>だとすれば、〕
〔則ちその結果、万物は<有用>でないものはないことになり、〕
──既成概念で、ある「働きの結果」をすでに<有用>なことだと判断しているところをもとにして、これは<有用>だと認識する方法をとるならば、万物、どんなことでも<有用>ではないものはない、つまり、すべては<有用>なのだという固定概念が生まれる…と言っているようです。
【因其所无而无之】【其の无(む)の所を因としてこれを无とすると、】
【則萬物莫不无】【則ち万物は无ならざるは莫し。】
〔その<無用>だとする所を起因としてこれを<無用>だとすれば、〕
〔則ちその結果、万物は<無用>でないものはないことになる。〕
──ある「働きの結果」が一方で<有用>と判断を下している時には、別のもう一方の何かの「働きの結果」を<無用>なものだと判断を下しているものなのです。既成概念で、ある「働きの結果」をすでに<無用>なことだと判断しているところをもとにして、これは<無用>だと認識する方法をとるならば、万物、どんなことでも<無用>ではないものはない、つまり、すべては<無用>なだという固定概念が生まれる…と言っているようです。
この概念の認識をそのまま認めることにしたら矛盾を孕むことになるようです。
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 知東西之相反 ┃【東西の相反しながら而も相以て无べからざるを知れば、】
┃ 而不可以相无 ┃
┃ 則功分定矣 ┃【則ち功は分を定めん。】
┗━━━━━━━━━━┛
東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないことを知れば、
則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定しているだけのこととなるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【定】は、「宀(やね)+正」で、「足をまっすぐ家の中にたててとどまるさま」を示しま
す。「ひと所に落ち着いて動かないこと。」「さだめる。」「さだまる。」
◆通説では、【功分定矣】の「【功】は働き、効用。【分】は本分・本質。物の効用性の本
質がはっきりする。それぞれの働きが相対的相補的で優劣のつけられないことがわかると
いうこと。」と説明しています。
【東西の相い反しながらも而も相い無かるべからざるを知れば、則ち功分(こうぶん)定ま
らん。】は「こうして、東と西とは反対でありながらたがいに相手を必要とするのだとい
うことがわかったなら〔つまり有用無用を一方的にきめられないということがわかったな
ら〕、物のはたらきの本質ははっきりするであろう。」としています。
◇【東西の相反しながら而も相以て无べからざるを知れば、則ち功は分を定めん。】は、
「東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないこ
とを知れば、則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定して
いるだけのこととなるだろう。」としました。
┃▼ 知東西之相反 ┃【東西の相反しながら而も相以て无べからざるを知れば、】
┃ 而不可以相无 ┃
┃ 則功分定矣 ┃【則ち功は分を定めん。】
┗━━━━━━━━━━┛
東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないことを知れば、
則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定しているだけのこととなるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【定】は、「宀(やね)+正」で、「足をまっすぐ家の中にたててとどまるさま」を示しま
す。「ひと所に落ち着いて動かないこと。」「さだめる。」「さだまる。」
◆通説では、【功分定矣】の「【功】は働き、効用。【分】は本分・本質。物の効用性の本
質がはっきりする。それぞれの働きが相対的相補的で優劣のつけられないことがわかると
いうこと。」と説明しています。
【東西の相い反しながらも而も相い無かるべからざるを知れば、則ち功分(こうぶん)定ま
らん。】は「こうして、東と西とは反対でありながらたがいに相手を必要とするのだとい
うことがわかったなら〔つまり有用無用を一方的にきめられないということがわかったな
ら〕、物のはたらきの本質ははっきりするであろう。」としています。
◇【東西の相反しながら而も相以て无べからざるを知れば、則ち功は分を定めん。】は、
「東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないこ
とを知れば、則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定して
いるだけのこととなるだろう。」としました。
●通説では、次のようになっています。
こうして、東と西とは反対でありながらたがいに相手を必要とするのだということがわかったなら〔つまり有用無用を一方的にきめられないということがわかったなら〕、物のはたらきの本質ははっきりするであろう。
〇新解釈では、次のようになります。
東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないことを知れば、
則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定しているだけのこととなるだろう。
【知東西之相反而不可以相无】【東西の相反しながら而も相以て无べからざるを知れば、】
〔東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないことを知れば、〕
──東と西は真逆の方角です。そこに人間が関与して進む道を決定する時、どちらかの方角を<有用>だとしてしまいます。すると、もう一方の方角は<無用>のものになるのは事実です。しかし、存在は西があっての東です。東あっての西です。互いに存在そのものを<無用>だとすることができないことは理解できるのではないでしょうか。<有用>だとするものが存在すると、必ず相反するものが存在しているもので、その時それは<無用>だと判断されてきた対象であったにもかかわらず、実は<無用>なものではないとすることは矛盾ではありません。ただ用の<有無>は不可分だ…と言っているようです。
【則功分定矣】【則ち功は分を定まらん。】
〔則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定しているだけのこととなるだろう。〕
──ものごとを<有用>だとか<無用>だとか功(働きの結果)で判断することは、その分け目が不可分なものだと感じて微々たる違いとみなせるようになるどころか、はっきりとした違いとして固定概念になっているだろう…と言っているようです。
こうして、東と西とは反対でありながらたがいに相手を必要とするのだということがわかったなら〔つまり有用無用を一方的にきめられないということがわかったなら〕、物のはたらきの本質ははっきりするであろう。
〇新解釈では、次のようになります。
東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないことを知れば、
則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定しているだけのこととなるだろう。
【知東西之相反而不可以相无】【東西の相反しながら而も相以て无べからざるを知れば、】
〔東と西は相反するものでありながら、互いに相手を<無用>だとすることができないことを知れば、〕
──東と西は真逆の方角です。そこに人間が関与して進む道を決定する時、どちらかの方角を<有用>だとしてしまいます。すると、もう一方の方角は<無用>のものになるのは事実です。しかし、存在は西があっての東です。東あっての西です。互いに存在そのものを<無用>だとすることができないことは理解できるのではないでしょうか。<有用>だとするものが存在すると、必ず相反するものが存在しているもので、その時それは<無用>だと判断されてきた対象であったにもかかわらず、実は<無用>なものではないとすることは矛盾ではありません。ただ用の<有無>は不可分だ…と言っているようです。
【則功分定矣】【則ち功は分を定まらん。】
〔則ち功(働きの結果)で(用の<有無>の判断をするの)は、分け目を固定しているだけのこととなるだろう。〕
──ものごとを<有用>だとか<無用>だとか功(働きの結果)で判断することは、その分け目が不可分なものだと感じて微々たる違いとみなせるようになるどころか、はっきりとした違いとして固定概念になっているだろう…と言っているようです。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼以趣観之 ┃【趣(しゅ)を以てこれを観れば、】
┃ 因其所然而然之 ┃【其の然(しか)る所に因りてこれを然りとすると、】
┃ 則萬物莫不然 ┃【則ち万物は然らざるは莫く、】
┃ 因其所非而非之 ┃【其の非なる所に因りてこれを非とすると、】
┃ 則萬物莫不非 ┃【則ち万物は非ならざるは莫し。】
┗━━━━━━━━━┛
趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、
その<然(正)>とする所に起因してこれを<然(正)>とすると、
則ちその結果、万物は<然(正)>でないものはなくなり、
その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、
則ちその結果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。
…………………………………………………………………………………………………………
*【趣】は、「走(はしる)+取(ぐっと指をちぢめてつかむこと)」で、「時間をちぢめてせ
かせかといくこと。」「おもむく(足ばやにいく)。」「おもむき(心の向くところ・めざ
すところ)。」
*【然】は「しかり(肯定・同意・承認をあらわすことば)。」転じて「そう、よろしい。」
「そのとおり・そうだ。」
*【非】は、羽が左と右とにそむいたさまを描いた象形文字。「反対の意や否定の意をあら
わすことば。」「正しくない・まちがっている。」「…ではない。」
◆通説では、【趣(しゅ)を以てこれを観れば、其の然(しか)る所に因りてこれを然りとする
ときは、則ち万物は然らざるは莫く、其の非(ひ)なる所に因りてこれを非とするときは、
則ち万物は非ならざるは莫し。】は「また心の志向という観点からみるなら、それぞれの
正しい点についてそれを正しいとしていれば、どんな物でもすべて正しいことになるが、
それぞれの誤った点についてそれを誤りとするなら、どんな物でもすべて誤っていること
になる。」としています。
◇【趣(しゅ)を以てこれを観れば、其の然(しか)る所を因にしてこれを然りとすると、則ち
万物は然らざるは莫く、其の非なる所を因にしてこれを非とすると、則ち万物は非ならざ
るは莫し。】は「趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、その<然(正)>とする
所に起因してこれを<然(正)>とすると、則ちその結果、万物は<然(正)>でないものは
なくなり、その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、則ちその結
果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。」としました。
┃▼以趣観之 ┃【趣(しゅ)を以てこれを観れば、】
┃ 因其所然而然之 ┃【其の然(しか)る所に因りてこれを然りとすると、】
┃ 則萬物莫不然 ┃【則ち万物は然らざるは莫く、】
┃ 因其所非而非之 ┃【其の非なる所に因りてこれを非とすると、】
┃ 則萬物莫不非 ┃【則ち万物は非ならざるは莫し。】
┗━━━━━━━━━┛
趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、
その<然(正)>とする所に起因してこれを<然(正)>とすると、
則ちその結果、万物は<然(正)>でないものはなくなり、
その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、
則ちその結果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。
…………………………………………………………………………………………………………
*【趣】は、「走(はしる)+取(ぐっと指をちぢめてつかむこと)」で、「時間をちぢめてせ
かせかといくこと。」「おもむく(足ばやにいく)。」「おもむき(心の向くところ・めざ
すところ)。」
*【然】は「しかり(肯定・同意・承認をあらわすことば)。」転じて「そう、よろしい。」
「そのとおり・そうだ。」
*【非】は、羽が左と右とにそむいたさまを描いた象形文字。「反対の意や否定の意をあら
わすことば。」「正しくない・まちがっている。」「…ではない。」
◆通説では、【趣(しゅ)を以てこれを観れば、其の然(しか)る所に因りてこれを然りとする
ときは、則ち万物は然らざるは莫く、其の非(ひ)なる所に因りてこれを非とするときは、
則ち万物は非ならざるは莫し。】は「また心の志向という観点からみるなら、それぞれの
正しい点についてそれを正しいとしていれば、どんな物でもすべて正しいことになるが、
それぞれの誤った点についてそれを誤りとするなら、どんな物でもすべて誤っていること
になる。」としています。
◇【趣(しゅ)を以てこれを観れば、其の然(しか)る所を因にしてこれを然りとすると、則ち
万物は然らざるは莫く、其の非なる所を因にしてこれを非とすると、則ち万物は非ならざ
るは莫し。】は「趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、その<然(正)>とする
所に起因してこれを<然(正)>とすると、則ちその結果、万物は<然(正)>でないものは
なくなり、その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、則ちその結
果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。」としました。
●通説では、次のようになっています。
また心の志向という観点からみるなら、それぞれの正しい点についてそれを正しいとしていれば、どんな物でもすべて正しいことになるが、それぞれの誤った点についてそれを誤りとするなら、どんな物でもすべて誤っていることになる。
〇新解釈では、次のようになります。
趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、
その<然(正)>とする所に起因してこれを<然(正)>とすると、
則ちその結果、万物は<然(正)>でないものはなくなり、
その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、
則ちその結果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。
【以趣観之】【趣(しゅ)を以てこれを観れば、】
〔趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、〕
──趣(心のめざすところ)を認識するというのは、もともと自分が普通にもっている主義主張で既に<正誤>の判断をしているものです。すでに判断を下している「心のめざすところ」で以て対象を観るならば、どんな認識の仕方ができるのでしょうか。
【因其所然而然之】【其の然(しか)る所に因りてこれを然りとすると、】
【則萬物莫不然】【則ち万物は然らざるは莫く、】
〔その<然(正)>とする所に起因してこれを<然(正)>とすると、〕
〔則ちその結果、万物は<然(正)>でないものはなくなり、〕
──もともと自分の判断で<然り(正しい)>と思っていることに基づき、これを<正しい>とするならば、万物、どんなものでも<正しい>と言えないものはなくなり、全てが<正しい>ということになる…と言っているようです。
【因其所非而非之】【其の非なる所に因りてこれを非とすると、】
【則萬物莫不非】【則ち万物は非ならざるは莫し。】
〔その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、〕
〔則ちその結果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。〕
──あるものに対して<然り(正しい)>という判断がある限り、そこには<非(誤り)>とするものがあるということを前提にしていることになります。もともと自分の判断で<非(誤り)>と思っていることに基づき、これを<誤り>とするならば、万物、どんなものでも<誤り>と言えないものはなくなり、全てが<誤り>ということになる…と言っているようです。
そうなると、<正しい>と<誤り>の判断には大きな違いがあるとしながら、万物はすべて<正しい>とすることと万物はすべて<誤り>とすることが同居するという結果を招き、この概念には矛盾が起こります。
また心の志向という観点からみるなら、それぞれの正しい点についてそれを正しいとしていれば、どんな物でもすべて正しいことになるが、それぞれの誤った点についてそれを誤りとするなら、どんな物でもすべて誤っていることになる。
〇新解釈では、次のようになります。
趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、
その<然(正)>とする所に起因してこれを<然(正)>とすると、
則ちその結果、万物は<然(正)>でないものはなくなり、
その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、
則ちその結果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。
【以趣観之】【趣(しゅ)を以てこれを観れば、】
〔趣(心のめざすところ)を以てこれを観るならば、〕
──趣(心のめざすところ)を認識するというのは、もともと自分が普通にもっている主義主張で既に<正誤>の判断をしているものです。すでに判断を下している「心のめざすところ」で以て対象を観るならば、どんな認識の仕方ができるのでしょうか。
【因其所然而然之】【其の然(しか)る所に因りてこれを然りとすると、】
【則萬物莫不然】【則ち万物は然らざるは莫く、】
〔その<然(正)>とする所に起因してこれを<然(正)>とすると、〕
〔則ちその結果、万物は<然(正)>でないものはなくなり、〕
──もともと自分の判断で<然り(正しい)>と思っていることに基づき、これを<正しい>とするならば、万物、どんなものでも<正しい>と言えないものはなくなり、全てが<正しい>ということになる…と言っているようです。
【因其所非而非之】【其の非なる所に因りてこれを非とすると、】
【則萬物莫不非】【則ち万物は非ならざるは莫し。】
〔その<非(誤)>とする所に起因してこれを<非(誤)>とすると、〕
〔則ちその結果、万物は<非(誤)>でないものはなくなる。〕
──あるものに対して<然り(正しい)>という判断がある限り、そこには<非(誤り)>とするものがあるということを前提にしていることになります。もともと自分の判断で<非(誤り)>と思っていることに基づき、これを<誤り>とするならば、万物、どんなものでも<誤り>と言えないものはなくなり、全てが<誤り>ということになる…と言っているようです。
そうなると、<正しい>と<誤り>の判断には大きな違いがあるとしながら、万物はすべて<正しい>とすることと万物はすべて<誤り>とすることが同居するという結果を招き、この概念には矛盾が起こります。
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 知堯桀之自然而相非 ┃【堯桀の自ら然りとして相非とするを知れば、】
┃ 則趣操覩矣 ┃【則ち趣は操を覩(み)ん。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
堯(ぎょう)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>としたのを知れば、
則ち趣(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【堯】(ぎょう)は中国神話に登場する帝王。姓は伊祁(いき)、名は放勲(ほうくん)。
儒家により神聖視され、聖人と崇められました。
*【桀】(けつ)は夏王朝の末帝。殷(いん)の紂(ちゆう)王とならんで中国上古の暴君の代
表とされています。桀は徳で統治をするのでなく武力で諸侯や民衆を押さえつけたの
で、諸侯や民衆に憎まれました。
*【操】は、「手+喿(うわついてせわしないこと)」で「手先をせわしく動かし、うわべ
をかすめてたぐること」。
◆通説では、「【趣】は心の旨趣・志向。【操】は節操・操守の意。心の志向の守りどこ
ろ、根拠。それがいかに不安定な相対的なものであるかがわかるということ。」と説明
しています。
【堯桀の自ら然りとして相い非とするを知れば、則ち趣操(しゅそう)覩(み)えん。】は
「聖人の堯(ぎょう)と暴君の桀(けつ)でさえ、たがいに自分を正しいとして相手を誤り
としていることがわかったなら、〔正しいと誤りも相対的だということがわかって、〕
心の志向の根拠は明らかになるであろう。」としています。
◇【堯桀の自ら然りとして相非とするを知れば、則ち趣は操を覩(み)ん。】は「堯(ぎょ
う)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>とするのを知れば、則ち趣
(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみ
ているだけのこととなるだろう。」としました。
┃▼ 知堯桀之自然而相非 ┃【堯桀の自ら然りとして相非とするを知れば、】
┃ 則趣操覩矣 ┃【則ち趣は操を覩(み)ん。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
堯(ぎょう)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>としたのを知れば、
則ち趣(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【堯】(ぎょう)は中国神話に登場する帝王。姓は伊祁(いき)、名は放勲(ほうくん)。
儒家により神聖視され、聖人と崇められました。
*【桀】(けつ)は夏王朝の末帝。殷(いん)の紂(ちゆう)王とならんで中国上古の暴君の代
表とされています。桀は徳で統治をするのでなく武力で諸侯や民衆を押さえつけたの
で、諸侯や民衆に憎まれました。
*【操】は、「手+喿(うわついてせわしないこと)」で「手先をせわしく動かし、うわべ
をかすめてたぐること」。
◆通説では、「【趣】は心の旨趣・志向。【操】は節操・操守の意。心の志向の守りどこ
ろ、根拠。それがいかに不安定な相対的なものであるかがわかるということ。」と説明
しています。
【堯桀の自ら然りとして相い非とするを知れば、則ち趣操(しゅそう)覩(み)えん。】は
「聖人の堯(ぎょう)と暴君の桀(けつ)でさえ、たがいに自分を正しいとして相手を誤り
としていることがわかったなら、〔正しいと誤りも相対的だということがわかって、〕
心の志向の根拠は明らかになるであろう。」としています。
◇【堯桀の自ら然りとして相非とするを知れば、則ち趣は操を覩(み)ん。】は「堯(ぎょ
う)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>とするのを知れば、則ち趣
(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみ
ているだけのこととなるだろう。」としました。
●通説では、次のようになっています。
聖人の堯(ぎょう)と暴君の桀(けつ)でさえ、たがいに自分を正しいとして相手を誤りとしていることがわかったなら、〔正しいと誤りも相対的だということがわかって、〕心の志向の根拠は明らかになるであろう。
〇新解釈では、次のようになります。
堯(ぎょう)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>としたのを知れば、
則ち趣(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
【知堯桀之自然而相非】【堯桀の自ら然りとして相非とするを知れば、】
〔堯(ぎょう)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>としたのを知れば、
(<正誤>の認識は奥深いものと言え、) 〕
──世俗的立場では、堯(ぎょう)を聖人の代表とし、桀(けつ)を暴君の代表とすることから、堯を<然(正)>とし、桀を<非(誤)>という判断で認識しがちです。ところが、北海若(荘子)は単純にそんな評価で終わってはいないのです。お互い、自分を<然(正)>とし、相手を<非(誤)>とした…と言っています。
人間世篇の中にこんな話がありますので、要約してみます。
- - - - -
むかし桀(けつ)は関竜逢(かんりゅうほう)を殺したということがあったが、関竜逢はわが身を修めて他人の支配下の人民を甘やかして手なづけ、臣下の身分でありながら、君主の心に逆らった者だったからだ。
(略)
一方、堯(ぎょう)は、ある国々を攻め、国々は空虚なむごいありさまにされ、君主たちは死刑にされた。彼らがあくまで戦争好きで実益を求めてやまなかったからだ。これ(被害者)はみな名誉と実益を求めたために害にあったのである。
- - - - -
桀はともかく、聖人と言われる堯も正義の名のもと、人を殺しているのです。それももしかすると桀よりも多くの人を殺しているのかもしれません。
こうなると、どちらが<然(正)>で、どちらが<非(誤)>の政治を行っていたか単純に判断がつかず、奥深い話となってきます。両者ともに自分が<然(正)>で、相手が<非(誤)>という認識だったと言えるだけで、客観的な判断では白黒はっきりつけられないことになります。
【則趣操覩矣】【則ち趣は操を覩(み)ん。】
〔則ち趣(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。〕
──人それぞれ心のめざすところが違うものです。他人と比較して、その行動のどちらかが<正しく>、もう一方が<誤り>だと判断するのは、うわべの操作という点にのみに視線を狭めてみていることになるのだ…と言っているようです。
聖人の堯(ぎょう)と暴君の桀(けつ)でさえ、たがいに自分を正しいとして相手を誤りとしていることがわかったなら、〔正しいと誤りも相対的だということがわかって、〕心の志向の根拠は明らかになるであろう。
〇新解釈では、次のようになります。
堯(ぎょう)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>としたのを知れば、
則ち趣(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。
【知堯桀之自然而相非】【堯桀の自ら然りとして相非とするを知れば、】
〔堯(ぎょう)と桀(けつ)は自らを<然(正)>とし、相手を<非(誤)>としたのを知れば、
(<正誤>の認識は奥深いものと言え、) 〕
──世俗的立場では、堯(ぎょう)を聖人の代表とし、桀(けつ)を暴君の代表とすることから、堯を<然(正)>とし、桀を<非(誤)>という判断で認識しがちです。ところが、北海若(荘子)は単純にそんな評価で終わってはいないのです。お互い、自分を<然(正)>とし、相手を<非(誤)>とした…と言っています。
人間世篇の中にこんな話がありますので、要約してみます。
- - - - -
むかし桀(けつ)は関竜逢(かんりゅうほう)を殺したということがあったが、関竜逢はわが身を修めて他人の支配下の人民を甘やかして手なづけ、臣下の身分でありながら、君主の心に逆らった者だったからだ。
(略)
一方、堯(ぎょう)は、ある国々を攻め、国々は空虚なむごいありさまにされ、君主たちは死刑にされた。彼らがあくまで戦争好きで実益を求めてやまなかったからだ。これ(被害者)はみな名誉と実益を求めたために害にあったのである。
- - - - -
桀はともかく、聖人と言われる堯も正義の名のもと、人を殺しているのです。それももしかすると桀よりも多くの人を殺しているのかもしれません。
こうなると、どちらが<然(正)>で、どちらが<非(誤)>の政治を行っていたか単純に判断がつかず、奥深い話となってきます。両者ともに自分が<然(正)>で、相手が<非(誤)>という認識だったと言えるだけで、客観的な判断では白黒はっきりつけられないことになります。
【則趣操覩矣】【則ち趣は操を覩(み)ん。】
〔則ち趣(心のめざすところ)で(<正誤>の判断をするの)は、うわべの操作に視線を集めてみているだけのこととなるだろう。〕
──人それぞれ心のめざすところが違うものです。他人と比較して、その行動のどちらかが<正しく>、もう一方が<誤り>だと判断するのは、うわべの操作という点にのみに視線を狭めてみていることになるのだ…と言っているようです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
荘子 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
荘子のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37849人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31945人