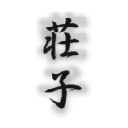━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━秋水篇━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(6)多と賤
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
是故大人之行 是の故に大人(だいじん)の行(こう)は、
不出乎害人 不多仁恩 人を害するに出(い)でざるも、仁恩を多とはせず。
動不為利 不賤門隷 動くに利の為ならざるも、門隷を賤とはせず。
貨財弗争 不多辞譲 貨財は争わざるも、辞譲を多とはせず。
事焉不借人 不多食乎力 事には人に借らざるも、力に食(は)むを多とはせず。
(・・・) 不賤貪汙 (・・・、)貪汙(たんお)を賤とはせず。
行殊乎俗 不多辟異 行いは俗に殊(こと)なるも、辟異(へきい)を多とはせず。
為在従衆 不賤佞諂 為(な)すは衆に従うに在るも、佞諂(ねんてい)を賤とはせず。
世之爵禄不足以為勸 世の爵禄で以て勧めと為すに足らず、
戮恥不足以為辱 戮恥(りくち)で以て辱(じょく)と為すに足らず。
知是非之不可為分 是非の分を為すべからず、
細大之不可為倪 細大の倪(がい)を為すべからざるを知ればなり。
聞曰道人不聞 聞くに曰く、道人は聞こえず、
至徳不得 大人无己 至徳(しとく)は得とせず、大人は己なしと。
約分之至也 約分の至りなり。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
こうしたわけで、大人(だいじん/──すなわち偉大な人物)の行為は、〔ことさらな区別を立てないで、あるがままに自然である。〕他人を害するようなふるまいはしないが、だからといって仁恩を尊ぶわけではない。利益のために動くことはないが、だからといって利益にはしる門番を賤しむわけではない。貨財を求めて争うことはないが、だからといって他人にゆずることを尊ぶわけではない。仕事について他人の力を借りることはないが、だからといって自力の生活を自慢にするわけではない。……また貪欲を賤しむこともない。その行動は世俗とは違っているが、だからといってことさら変わったことをするのをよいとしているわけではない。そのふるまいは大衆に従うのを旨(むね)としているが、だからといって一人こっそり媚(こ)びへつらうものを賤しむこともない。世間的な爵位(しゃくい)や俸禄(ほうろく)では彼を勧(はげ)ますことはできず、刑罰や恥ずかしめも彼を汚辱(おじょく)におとしこむことはできない。つまり、善し悪しは分けられないものであり、大小も区別できないものだということをよくわきまえているからである。『道人(どうじん/道を体得した人)は名声のあがることがなく、至徳(しとく/最高の徳に達した人)は徳を得たおもむきもなく、大人(だいじん/偉大な人)は私心を持たない、』といわれているが、まことに自己の本分を守る極致である。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これ故に、大いなる人の行いは、
人を害するような出方もしないが、仁や恩を<多>ともしない。
利益の為に動くこともないが、(利益のために働く)門番を<賤>ともしない。
財貨によって争うこともないが、人にゆずることを<多>ともしない。
事を為すのに人の力を借りることもないが、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。
(・・・、) 財貨をため込んで欲深いことを<賤>ともしない。
行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へそれることを<多>ともしない。
為すことも衆(日のもとで多くの人と共に働くこと)に従うことにあるが、
陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。
世間的な爵位や俸禄で以て、彼を力づけることもできないが、
ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもできない。
<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、
<細><大>の微々たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。
聞くに『道を会得した人は(名声を)聞くこともなく、
徳(人間のもっている本性)に至った人は(徳を)得たようすもなく、
大いなる人は己がない』と言うが、
割り切ってシンプルになっていくことによって至る境地である。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(6)多と賤
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
是故大人之行 是の故に大人(だいじん)の行(こう)は、
不出乎害人 不多仁恩 人を害するに出(い)でざるも、仁恩を多とはせず。
動不為利 不賤門隷 動くに利の為ならざるも、門隷を賤とはせず。
貨財弗争 不多辞譲 貨財は争わざるも、辞譲を多とはせず。
事焉不借人 不多食乎力 事には人に借らざるも、力に食(は)むを多とはせず。
(・・・) 不賤貪汙 (・・・、)貪汙(たんお)を賤とはせず。
行殊乎俗 不多辟異 行いは俗に殊(こと)なるも、辟異(へきい)を多とはせず。
為在従衆 不賤佞諂 為(な)すは衆に従うに在るも、佞諂(ねんてい)を賤とはせず。
世之爵禄不足以為勸 世の爵禄で以て勧めと為すに足らず、
戮恥不足以為辱 戮恥(りくち)で以て辱(じょく)と為すに足らず。
知是非之不可為分 是非の分を為すべからず、
細大之不可為倪 細大の倪(がい)を為すべからざるを知ればなり。
聞曰道人不聞 聞くに曰く、道人は聞こえず、
至徳不得 大人无己 至徳(しとく)は得とせず、大人は己なしと。
約分之至也 約分の至りなり。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
こうしたわけで、大人(だいじん/──すなわち偉大な人物)の行為は、〔ことさらな区別を立てないで、あるがままに自然である。〕他人を害するようなふるまいはしないが、だからといって仁恩を尊ぶわけではない。利益のために動くことはないが、だからといって利益にはしる門番を賤しむわけではない。貨財を求めて争うことはないが、だからといって他人にゆずることを尊ぶわけではない。仕事について他人の力を借りることはないが、だからといって自力の生活を自慢にするわけではない。……また貪欲を賤しむこともない。その行動は世俗とは違っているが、だからといってことさら変わったことをするのをよいとしているわけではない。そのふるまいは大衆に従うのを旨(むね)としているが、だからといって一人こっそり媚(こ)びへつらうものを賤しむこともない。世間的な爵位(しゃくい)や俸禄(ほうろく)では彼を勧(はげ)ますことはできず、刑罰や恥ずかしめも彼を汚辱(おじょく)におとしこむことはできない。つまり、善し悪しは分けられないものであり、大小も区別できないものだということをよくわきまえているからである。『道人(どうじん/道を体得した人)は名声のあがることがなく、至徳(しとく/最高の徳に達した人)は徳を得たおもむきもなく、大人(だいじん/偉大な人)は私心を持たない、』といわれているが、まことに自己の本分を守る極致である。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これ故に、大いなる人の行いは、
人を害するような出方もしないが、仁や恩を<多>ともしない。
利益の為に動くこともないが、(利益のために働く)門番を<賤>ともしない。
財貨によって争うこともないが、人にゆずることを<多>ともしない。
事を為すのに人の力を借りることもないが、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。
(・・・、) 財貨をため込んで欲深いことを<賤>ともしない。
行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へそれることを<多>ともしない。
為すことも衆(日のもとで多くの人と共に働くこと)に従うことにあるが、
陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。
世間的な爵位や俸禄で以て、彼を力づけることもできないが、
ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもできない。
<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、
<細><大>の微々たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。
聞くに『道を会得した人は(名声を)聞くこともなく、
徳(人間のもっている本性)に至った人は(徳を)得たようすもなく、
大いなる人は己がない』と言うが、
割り切ってシンプルになっていくことによって至る境地である。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
|
|
|
コメント(12)
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 是故大人之行 ┃【是の故に大人(だいじん)の行(こう)は、】
┃ 不出乎害人 不多仁恩 ┃【人を害するに出(い)でざるも、仁恩を多とはせず。】
┃ 動不為利 不賤門隷 ┃【動くに利の為ならざるも、門隷を賤とはせず。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
これ故に、大いなる人の行いは、
人を害するような出方もしないが、仁や恩を<多>ともしない。
利益の為に動くこともないが、(利益のために働く)門番を<賤>ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【恩】は、「心+因(上から下に押さえる)」で「心の上にのしかかって何かの印象を残す
こと」。「恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと」。「人にありがたいと印
象づけたこと」。「ありがたみ」。「恵み」。「いつくしむ」。「たいせつにする」。
*【賤】は「貝+戔(少ない・小さい)」で、「財貨が少ないこと」の意。「いやしむ(み
さげる。さげしむ。)」などの意。
*【隷】は、「しもべ」。「人に使われる、身分のいやしい者」。「雑務係の下級役人」。
◆通説では、【是の故に大人(だいじん)の行(こう)は、人を害するに出ざるも、仁恩を多と
せず、動いて利の為にはせざるも、門隷を賤(いや)しとはせず。】は「こうしたわけで、
大人 (だいじん/──すなわち偉大な人物)の行為は、〔ことさらな区別を立てないで、
あるがままに自然である。〕他人を害するようなふるまいはしないが、だからといって
仁恩を尊ぶわけではない。利益のために動くことはないが、だからといって利益にはし
る門番を賤しむわけではない。」としています。
◇【是の故に大人(だいじん)の行(こう)は、人を害するに出ざるも、仁恩を多とはせず。
動くに利の為ならざるも、門隷を賤(せん)とはせず。】は「これ故に、大いなる人の行
いは、人を害するような出方もしないが、仁や恩を<多>ともしない。利益の為に動く
こともないが、(利益のために働く)門番を<賤>ともしない。」としました。
┃▼ 是故大人之行 ┃【是の故に大人(だいじん)の行(こう)は、】
┃ 不出乎害人 不多仁恩 ┃【人を害するに出(い)でざるも、仁恩を多とはせず。】
┃ 動不為利 不賤門隷 ┃【動くに利の為ならざるも、門隷を賤とはせず。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
これ故に、大いなる人の行いは、
人を害するような出方もしないが、仁や恩を<多>ともしない。
利益の為に動くこともないが、(利益のために働く)門番を<賤>ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【恩】は、「心+因(上から下に押さえる)」で「心の上にのしかかって何かの印象を残す
こと」。「恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと」。「人にありがたいと印
象づけたこと」。「ありがたみ」。「恵み」。「いつくしむ」。「たいせつにする」。
*【賤】は「貝+戔(少ない・小さい)」で、「財貨が少ないこと」の意。「いやしむ(み
さげる。さげしむ。)」などの意。
*【隷】は、「しもべ」。「人に使われる、身分のいやしい者」。「雑務係の下級役人」。
◆通説では、【是の故に大人(だいじん)の行(こう)は、人を害するに出ざるも、仁恩を多と
せず、動いて利の為にはせざるも、門隷を賤(いや)しとはせず。】は「こうしたわけで、
大人 (だいじん/──すなわち偉大な人物)の行為は、〔ことさらな区別を立てないで、
あるがままに自然である。〕他人を害するようなふるまいはしないが、だからといって
仁恩を尊ぶわけではない。利益のために動くことはないが、だからといって利益にはし
る門番を賤しむわけではない。」としています。
◇【是の故に大人(だいじん)の行(こう)は、人を害するに出ざるも、仁恩を多とはせず。
動くに利の為ならざるも、門隷を賤(せん)とはせず。】は「これ故に、大いなる人の行
いは、人を害するような出方もしないが、仁や恩を<多>ともしない。利益の為に動く
こともないが、(利益のために働く)門番を<賤>ともしない。」としました。
●通説では、次のようになっています。
こうしたわけで、大人(だいじん/──すなわち偉大な人物)の行為は、〔ことさらな区別を立てないで、あるがままに自然である。〕他人を害するようなふるまいはしないが、だからといって仁恩を尊ぶわけではない。利益のために動くことはないが、だからといって利益にはしる門番を賤しむわけではない。
〇新解釈では、次のようになります。
これ故に、大いなる人の行いは、
人を害するような出方もしないが、仁や恩を<多>ともしない。
利益の為に動くこともないが、(利益のために働く)門番を<賤>ともしない。
【是故大人之行】【是の故に大人(だいじん)の行(こう)は、】
〔これ故に、大いなる人の行いは、〕
──これ故に…何の故に? <精粗>とか<大小>といった一定期間のものを基準に判断することがないが故に…でしょうか。大いなる人の行いはきわめて自然体だ…と言っているようです。
【不出乎害人 不多仁恩】【人を害するに出(い)でざるも、仁恩を多とはせず。】
〔人を害するような出方もしないが、仁や恩を<多>ともしない。〕
──大いなる人は、けっして人の気分を害するような出方もしないが、かといって仁や恩を<多>ともしない…としました。前には<少>の対語として<多>が用いられていました。そこでは、特に通説のように、<少>を「つまらなさ」、<多>を「得意になる」と意訳することなく、水量の違いを含んだ表現として、そのまま<少>と<多>としました。今回、<賤(いやしむ)>の対語として<多>を使っていることから、ここの<多>は、通説のように「貴ぶ(尊ぶ)」の意と思われがちですが、そうはしませんでした。<貴賤>で対語になるのにあえて<貴>を用いず、<多>を用いているのにはそれなりの意図があるように思い、「過剰なほどたっぷりと存在していて大事にすること」の意が含まれているものだとみなし、ここでも<多>のままにしておきました。
通説に言うように、「仁恩を多とはせず」は「仁や恩を尊ばない」と言っているのではないと思います。大いなる人は当然のようにして「尊んではいる」のだと思います。「<多>ともしない」という語を選んだのは、儒教でありがちな「過剰にとりたてて重大事にすることはない」と言っているものだと感じました。<過多>にならない、気負いのない自然体だ…と言っているのだとみなしました。
【動不為利 不賤門隷】【動くに利の為ならざるも、門隷を賤とはせず。】
〔利益の為に動くこともないが、(利益のために働く)門番を<賤>ともしない。〕
──自分の行動の動機は「利益の為」ということはありえないが、門番のような「利益の為」に働いている他人に対して、上から目線で<賤(いやしい)>と見下げることもありえない…と言っているようです。
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 貨財弗争 不多辞譲 ┃【貨財は争わざるも、辞譲を多とはせず。】
┃ 事焉不借人 不多食乎力 ┃【事には人に借らざるも、力に食むを多とはせず。】
┃ (・・・) 不賤貪汙 ┃【(・・・、)貪汙(たんお)を賤とはせず。】
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
財貨をめぐって争うこともないが、人にゆずることを<多>ともしない。
事を為すのに人の力を借りることもないが、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。(・・・、)財貨をため込んで欲深いことを<賤>ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【貨財】は、「金銭と、ねうちのある物質、財貨」。
*【弗】は、打ち消しをあらわすことば。
*【辞譲】は、「へりくだってことわり、人にゆずる」。
*【食】は、「食いぶち」。
*【貪】は、「貝+今(物を封じこめるさま)」で、「財貨を奥深くためこむこと」をあら
わします。
*【汙(汚)】は、「水+于(伸びる息が─印につっかえて曲がったさま・曲がりくぼむ)」
で「∪型にくぼんだ水たまり。」「その濁った水のことからよごれる」意となります。
◆【不賤貪汙】の句は前後が二句ずつの対応になっているのに合わない…としています。
【貨財は争わざるも辞譲を多とはせず、事には人に借らざるも力に食(は)むを多とはせ
ず、貪汙(たんお)を賤とはせず。】は、「貨財を求めて争うことはないが、だからとい
って他人にゆずることを尊ぶわけではない。仕事について他人の力を借りることはない
が、だからといって自力の生活を自慢にするわけではない。……また貪欲を賤しむこと
もない。」としています。
◇新解釈も【不賤貪汙】の前に脱句(・・・)があったものとみなしました。
【貨財は争わざるも、辞譲を多とはせず。事には人に借らざるも、力に食(は)むを多と
はせず。(・・・、)貪汙(たんお)を賤とはせず。】は、「財貨をめぐって争うことも
ないが、人に譲ることを<多>ともしない。事を為すのに人の力を借りることもない
が、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。(・・・、)財貨をため込んで欲深い
ことを<賤>ともしない。」としました。
┃▼ 貨財弗争 不多辞譲 ┃【貨財は争わざるも、辞譲を多とはせず。】
┃ 事焉不借人 不多食乎力 ┃【事には人に借らざるも、力に食むを多とはせず。】
┃ (・・・) 不賤貪汙 ┃【(・・・、)貪汙(たんお)を賤とはせず。】
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
財貨をめぐって争うこともないが、人にゆずることを<多>ともしない。
事を為すのに人の力を借りることもないが、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。(・・・、)財貨をため込んで欲深いことを<賤>ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【貨財】は、「金銭と、ねうちのある物質、財貨」。
*【弗】は、打ち消しをあらわすことば。
*【辞譲】は、「へりくだってことわり、人にゆずる」。
*【食】は、「食いぶち」。
*【貪】は、「貝+今(物を封じこめるさま)」で、「財貨を奥深くためこむこと」をあら
わします。
*【汙(汚)】は、「水+于(伸びる息が─印につっかえて曲がったさま・曲がりくぼむ)」
で「∪型にくぼんだ水たまり。」「その濁った水のことからよごれる」意となります。
◆【不賤貪汙】の句は前後が二句ずつの対応になっているのに合わない…としています。
【貨財は争わざるも辞譲を多とはせず、事には人に借らざるも力に食(は)むを多とはせ
ず、貪汙(たんお)を賤とはせず。】は、「貨財を求めて争うことはないが、だからとい
って他人にゆずることを尊ぶわけではない。仕事について他人の力を借りることはない
が、だからといって自力の生活を自慢にするわけではない。……また貪欲を賤しむこと
もない。」としています。
◇新解釈も【不賤貪汙】の前に脱句(・・・)があったものとみなしました。
【貨財は争わざるも、辞譲を多とはせず。事には人に借らざるも、力に食(は)むを多と
はせず。(・・・、)貪汙(たんお)を賤とはせず。】は、「財貨をめぐって争うことも
ないが、人に譲ることを<多>ともしない。事を為すのに人の力を借りることもない
が、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。(・・・、)財貨をため込んで欲深い
ことを<賤>ともしない。」としました。
●通説では、次のようになっています。
貨財を求めて争うことはないが、だからといって他人にゆずることを尊ぶわけではない。仕事について他人の力を借りることはないが、だからといって自力の生活を自慢にするわけではない。……また貪欲を賤しむこともない。
〇新解釈では、次のようになります。
財貨によって争うこともないが、人に譲ることを<多>ともしない。
事を為すのに人の力を借りることもないが、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。(・・・、) 財貨をため込んで欲深いことを<賤>ともしない。
【貨財弗争 不多辞譲】【貨財は争わざるも、辞譲を多とはせず。】
〔財貨をめぐって争うこともないが、人に譲ることを<多>ともしない。〕
──大いなる人は欲をもって財貨の獲得において人と争うことはないようです。といっても、世間の中で生きていくためには財貨の価値はそれなりに認め、その必要性は感じているに違いありません。自分にも必要だし、人にも必要だということはわかっているのです。自分に多少なり余裕があり、目の前の人が苦しむほど貧困にあえいでいたら、その時は惜しむことなく譲ることもあるかもしれませんが、通常、自分の無欲さを強調するように、誰構わず財貨を人に譲ることを<過多>にするわけではない…と言っているようです。
【事焉不借人 不多食乎力】【事には人に借らざるも、力に食むを多とはせず。】
〔事を為すのに人の力を借りることもないが、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。〕
──大いなる人は自力で事を為す能力があるのです。そのため人の力を借りることを必要ともしていないようです。ところがその能力は食べるための金銭の獲得は適度に必要としても、そのためだけに<過多>に力を費やすことはない…と言っているようです。
【(・・・) 不賤貪汙】【(・・・、)貪汙(たんお)を賤とはせず。】
〔(・・・、)財貨をため込んで欲深いことを<賤>ともしない。〕
──欠落してしまったと思われる、【不賤貪汙】に組する前の句(・・・)には何が書かれていたのかわかりませんが、【貪】に「財貨を奥深くためこむこと」、【汙(汚)】に「くぼんだ水たまり」という原義があるところから、その対句にあたる前の句には、「金は天下の回りものとしつつ、所有欲もないが、」といったような主旨の言葉があったのではないかと推察します。
欲深い人は、財貨を適切に「回すこと」を考えることよりも、「ためこむ」ことを念頭においており、増やすことに必死になって所有欲を満たしているものだが、大いなる人はそれを<賤>とすることもない…と解釈しました。
貨財を求めて争うことはないが、だからといって他人にゆずることを尊ぶわけではない。仕事について他人の力を借りることはないが、だからといって自力の生活を自慢にするわけではない。……また貪欲を賤しむこともない。
〇新解釈では、次のようになります。
財貨によって争うこともないが、人に譲ることを<多>ともしない。
事を為すのに人の力を借りることもないが、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。(・・・、) 財貨をため込んで欲深いことを<賤>ともしない。
【貨財弗争 不多辞譲】【貨財は争わざるも、辞譲を多とはせず。】
〔財貨をめぐって争うこともないが、人に譲ることを<多>ともしない。〕
──大いなる人は欲をもって財貨の獲得において人と争うことはないようです。といっても、世間の中で生きていくためには財貨の価値はそれなりに認め、その必要性は感じているに違いありません。自分にも必要だし、人にも必要だということはわかっているのです。自分に多少なり余裕があり、目の前の人が苦しむほど貧困にあえいでいたら、その時は惜しむことなく譲ることもあるかもしれませんが、通常、自分の無欲さを強調するように、誰構わず財貨を人に譲ることを<過多>にするわけではない…と言っているようです。
【事焉不借人 不多食乎力】【事には人に借らざるも、力に食むを多とはせず。】
〔事を為すのに人の力を借りることもないが、力を食いぶちにすることを<多>ともしない。〕
──大いなる人は自力で事を為す能力があるのです。そのため人の力を借りることを必要ともしていないようです。ところがその能力は食べるための金銭の獲得は適度に必要としても、そのためだけに<過多>に力を費やすことはない…と言っているようです。
【(・・・) 不賤貪汙】【(・・・、)貪汙(たんお)を賤とはせず。】
〔(・・・、)財貨をため込んで欲深いことを<賤>ともしない。〕
──欠落してしまったと思われる、【不賤貪汙】に組する前の句(・・・)には何が書かれていたのかわかりませんが、【貪】に「財貨を奥深くためこむこと」、【汙(汚)】に「くぼんだ水たまり」という原義があるところから、その対句にあたる前の句には、「金は天下の回りものとしつつ、所有欲もないが、」といったような主旨の言葉があったのではないかと推察します。
欲深い人は、財貨を適切に「回すこと」を考えることよりも、「ためこむ」ことを念頭においており、増やすことに必死になって所有欲を満たしているものだが、大いなる人はそれを<賤>とすることもない…と解釈しました。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 行殊乎俗 ┃【行いは俗に殊(こと)なるも、】
┃ 不多辟異 ┃【辟異(へきい)を多とはせず。】
┃ 為在従衆 ┃【為(な)すは衆に従うに在るも、】
┃ 不賤佞諂 ┃【佞諂(ねんてい)を賤とはせず。】
┗━━━━━━━┛
行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へそれることを<多>ともしない。
為すことも衆(日のもとで多くの人と共に働くこと)に従うことにあるが、
陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【殊】は、「ことなる」。「ことにする」。「普通とまったく違う」。
*【辟】は、「その人の占めている座から横にひっぱる」。「横によける」。「正しい筋道
から横にそれたこと」。「中心からそれている。ずれている」。
*【衆】は「日(太陽)+人が三人(多くの人)」で「太陽のもとで多くの人が集団労働をして
いるさま」。(「日」は後に誤って「血」と書くようになったようです。)
*【佞】は、「女+仁(人ずきがよく親切)」ですが、原義だったその意に反し、「口先だけ
が巧みで、人あたりはよいが、心中は知れない」意に傾いたことばです。
*【諂】は、「言+[右側の字](くぼむ、穴におとす)」で、「わざとへりくだって、相手を
穴におとすこと」。「へつらう」。「人の気に入るようなことをいってこびる」。
◆通説では、【行いは俗に殊(こと)なるも、辟異(へきい)を多とはせず。為(な)すは衆に従
うに在るも、佞諂(ねんてい)を賤とはせず。】は[その行動は世俗とは違っているが、
だからといってことさら変わったことをするのをよいとしているわけではない。そのふ
るまいは大衆に従うのを旨(むね)としているが、だからといって一人こっそり媚(こ)び
へつらうものを賤しむこともない。]としています。
◇【行いは俗に殊(こと)なるも、辟異(へきい)を多とはせず。為(な)すは衆に従うに在る
も、佞諂(ねんてい)を賤とはせず。】は[行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へ
それることを<多>ともしない。為すことも衆(日のもとで多くの人と共に働くこと)
に従うことにあるが、陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。]
としました。
┃▼ 行殊乎俗 ┃【行いは俗に殊(こと)なるも、】
┃ 不多辟異 ┃【辟異(へきい)を多とはせず。】
┃ 為在従衆 ┃【為(な)すは衆に従うに在るも、】
┃ 不賤佞諂 ┃【佞諂(ねんてい)を賤とはせず。】
┗━━━━━━━┛
行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へそれることを<多>ともしない。
為すことも衆(日のもとで多くの人と共に働くこと)に従うことにあるが、
陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【殊】は、「ことなる」。「ことにする」。「普通とまったく違う」。
*【辟】は、「その人の占めている座から横にひっぱる」。「横によける」。「正しい筋道
から横にそれたこと」。「中心からそれている。ずれている」。
*【衆】は「日(太陽)+人が三人(多くの人)」で「太陽のもとで多くの人が集団労働をして
いるさま」。(「日」は後に誤って「血」と書くようになったようです。)
*【佞】は、「女+仁(人ずきがよく親切)」ですが、原義だったその意に反し、「口先だけ
が巧みで、人あたりはよいが、心中は知れない」意に傾いたことばです。
*【諂】は、「言+[右側の字](くぼむ、穴におとす)」で、「わざとへりくだって、相手を
穴におとすこと」。「へつらう」。「人の気に入るようなことをいってこびる」。
◆通説では、【行いは俗に殊(こと)なるも、辟異(へきい)を多とはせず。為(な)すは衆に従
うに在るも、佞諂(ねんてい)を賤とはせず。】は[その行動は世俗とは違っているが、
だからといってことさら変わったことをするのをよいとしているわけではない。そのふ
るまいは大衆に従うのを旨(むね)としているが、だからといって一人こっそり媚(こ)び
へつらうものを賤しむこともない。]としています。
◇【行いは俗に殊(こと)なるも、辟異(へきい)を多とはせず。為(な)すは衆に従うに在る
も、佞諂(ねんてい)を賤とはせず。】は[行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へ
それることを<多>ともしない。為すことも衆(日のもとで多くの人と共に働くこと)
に従うことにあるが、陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。]
としました。
●通説では、次のようになっています。
その行動は世俗とは違っているが、だからといってことさら変わったことをするのをよいとしているわけではない。そのふるまいは大衆に従うのを旨(むね)としているが、だからといって一人こっそり媚(こ)びへつらうものを賤しむこともない。
〇新解釈では、次のようになります。
行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へそれることを<多>ともしない。
為すことも衆(日のもとで働くこと)に従うことにあるが、陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。
【行殊乎俗 不多辟異】【行いは俗に殊(こと)なるも、辟異(へきい)を多とはせず。】
〔行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へそれることを<多>ともしない。〕
──行いも自然にしているにもかかわらず、世俗とはまったく違っているものの、奇をてらってのことではないのです。ですから世俗の筋道と違う特異なことを<多く>しているというわけではない…と言っているようです。
【為在従衆 不賤佞諂】【為(な)すは衆に従うに在るも、佞諂(ねんてい)を賤とはせず。】
〔為すことも衆(日のもとで多くの人と共に働くこと)に従うことにあるが、陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。〕
──大いなる人の為すことは、特別に想像を絶するようなことをしているようなイメージを持たれがちですが、けっしてそんなことを為しているわけではなく、日のもとで多くの人と共に働くことに従っているのです。そんな中で、陰で口先巧みに一人だけに従って、気に入られるように媚びへつらうことをしている人がいても、それを<賤しい>と見下すこともない…ということのようです。
その行動は世俗とは違っているが、だからといってことさら変わったことをするのをよいとしているわけではない。そのふるまいは大衆に従うのを旨(むね)としているが、だからといって一人こっそり媚(こ)びへつらうものを賤しむこともない。
〇新解釈では、次のようになります。
行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へそれることを<多>ともしない。
為すことも衆(日のもとで働くこと)に従うことにあるが、陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。
【行殊乎俗 不多辟異】【行いは俗に殊(こと)なるも、辟異(へきい)を多とはせず。】
〔行いも世俗とまったく違うが、異なる筋道へそれることを<多>ともしない。〕
──行いも自然にしているにもかかわらず、世俗とはまったく違っているものの、奇をてらってのことではないのです。ですから世俗の筋道と違う特異なことを<多く>しているというわけではない…と言っているようです。
【為在従衆 不賤佞諂】【為(な)すは衆に従うに在るも、佞諂(ねんてい)を賤とはせず。】
〔為すことも衆(日のもとで多くの人と共に働くこと)に従うことにあるが、陰で口先巧みに一人に媚びへつらうことを<賤>ともしない。〕
──大いなる人の為すことは、特別に想像を絶するようなことをしているようなイメージを持たれがちですが、けっしてそんなことを為しているわけではなく、日のもとで多くの人と共に働くことに従っているのです。そんな中で、陰で口先巧みに一人だけに従って、気に入られるように媚びへつらうことをしている人がいても、それを<賤しい>と見下すこともない…ということのようです。
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 世之爵禄不足以為勸 ┃【世の爵禄で以て勧めと為すに足らず、】
┃ 戮恥不足以為辱 ┃【戮恥(りくち)で以て辱(じょく)と為すに足らず。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
世間的な爵位や俸禄で以て、彼を力づけることもできないが、
ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもできない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【爵】は、「爵位」。公・侯・伯・子・男の五階級がある。
*【禄】は、「神からのおこぼれ」。「おかみの手からこぼれおちた扶持米」などの意。
*【勸(勧)】は、「[左側の字(口々になきかわす鳥)+力」で、「口々にやかましくい
って力づけること。」
*【戮】(りく)は、「死刑。」「殺害。」「はずかしめ。」
*【戮恥】(りくち)は、「ひどくはずかしめる。」「恥・恥辱。」
*【辱】は、「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、「強さをくじい
て、ぐったりと柔らかくさせること。」
◆通説では、【世の爵禄(しゃくろく)も以て勧(はげ)みと為すに足らず、戮恥(りくち)も
以て辱(じょく)と為すに足らず。】は「世間的な爵位(しゃくい)や俸禄(ほうろく)では
彼を勧(はげ)ますことはできず、刑罰や恥ずかしめも彼を汚辱(おじょく)におとしこむ
ことはできない。」としています。
◇【世の爵禄(しゃくろく)で以て勧めることと為すに足らず、戮恥(りくち)で以て辱(じ
ょく)と為すに足らず。】は「世間的な爵位や俸禄で以て、彼を力づけることもできな
いが、ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもで
きない。」としました。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 知是非之不可為分 ┃【是非の分を為すべからず、
┃ 細大之不可為倪 ┃ 細大の倪(がい)を為すべからざるを知れるなり。】
┗━━━━━━━━━━━┛
<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、
<細><大>の微々たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【倪】の「兒(=児)」は、泉門がまだふさがらない頭と足のついた幼児を描いたもの。
【倪】は「人+兒」で、兒に含まれている、「弱くて小さい」の意味を表わす言葉。
◆通説では、【倪】を「区別」としています。
【是非の分を為すべからず、細大の倪(がい)を為すべからざるを知れるなり。】は、
「つまり、善し悪しは分けられないものであり、大小も区別できないものだということ
をよくわきまえているからである。」としています。
◇【倪】は前にも出てきましたが、辞書にはない、普通に把握しにくい微妙なニュアンス
をもった意味で使われていると思うのですが、訳しにくいことばです。ここでは「微々
たる違い」としました。
【是非の分を為すべからず、細大の倪(がい)を為すべからざるを知ればなり。】は、
「<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、<細><大>の微
微たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。」としました。
┃▼ 世之爵禄不足以為勸 ┃【世の爵禄で以て勧めと為すに足らず、】
┃ 戮恥不足以為辱 ┃【戮恥(りくち)で以て辱(じょく)と為すに足らず。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
世間的な爵位や俸禄で以て、彼を力づけることもできないが、
ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもできない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【爵】は、「爵位」。公・侯・伯・子・男の五階級がある。
*【禄】は、「神からのおこぼれ」。「おかみの手からこぼれおちた扶持米」などの意。
*【勸(勧)】は、「[左側の字(口々になきかわす鳥)+力」で、「口々にやかましくい
って力づけること。」
*【戮】(りく)は、「死刑。」「殺害。」「はずかしめ。」
*【戮恥】(りくち)は、「ひどくはずかしめる。」「恥・恥辱。」
*【辱】は、「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、「強さをくじい
て、ぐったりと柔らかくさせること。」
◆通説では、【世の爵禄(しゃくろく)も以て勧(はげ)みと為すに足らず、戮恥(りくち)も
以て辱(じょく)と為すに足らず。】は「世間的な爵位(しゃくい)や俸禄(ほうろく)では
彼を勧(はげ)ますことはできず、刑罰や恥ずかしめも彼を汚辱(おじょく)におとしこむ
ことはできない。」としています。
◇【世の爵禄(しゃくろく)で以て勧めることと為すに足らず、戮恥(りくち)で以て辱(じ
ょく)と為すに足らず。】は「世間的な爵位や俸禄で以て、彼を力づけることもできな
いが、ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもで
きない。」としました。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 知是非之不可為分 ┃【是非の分を為すべからず、
┃ 細大之不可為倪 ┃ 細大の倪(がい)を為すべからざるを知れるなり。】
┗━━━━━━━━━━━┛
<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、
<細><大>の微々たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【倪】の「兒(=児)」は、泉門がまだふさがらない頭と足のついた幼児を描いたもの。
【倪】は「人+兒」で、兒に含まれている、「弱くて小さい」の意味を表わす言葉。
◆通説では、【倪】を「区別」としています。
【是非の分を為すべからず、細大の倪(がい)を為すべからざるを知れるなり。】は、
「つまり、善し悪しは分けられないものであり、大小も区別できないものだということ
をよくわきまえているからである。」としています。
◇【倪】は前にも出てきましたが、辞書にはない、普通に把握しにくい微妙なニュアンス
をもった意味で使われていると思うのですが、訳しにくいことばです。ここでは「微々
たる違い」としました。
【是非の分を為すべからず、細大の倪(がい)を為すべからざるを知ればなり。】は、
「<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、<細><大>の微
微たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
世間的な爵位(しゃくい)や俸禄(ほうろく)では彼を勧(はげ)ますことはできず、刑罰や恥ずかしめも彼を汚辱(おじょく)におとしこむことはできない。つまり、善し悪しは分けられないものであり、大小も区別できないものだということをよくわきまえているからである。
〇新解釈では、次のようになります。
世間的な爵位や俸禄で力づけることを為すこともできないが、
ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもできない。
<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、
<細><大>の微々たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。
【世之爵禄 不足以為勸】【世の爵禄も以て勧めることと為すに足らず、】
〔世間的な爵位や俸禄で力づけることこともできないが、〕
──世間で高い爵位を与えらることになると、普通の人なら名誉欲が満たされ、喜びに心浮かれることになるでしょう。また、その俸禄(支給された米または金銭)をもらえることになると所有欲も満たされ、心おどり、生きていく上でとても力づけられることになるでしょう。ところが、大いなる人はそんなことで心を動かされることは一切ないようです。
【戮恥不足以為辱】【戮恥(りくち)も以て辱(じょく)と為すに足らず。】
〔ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもできない。〕
──反対に、ひどく恥ずかしめられることになると、普通の人なら自尊心が傷つけられ、落胆に心を痛めることになり、生きていく上で心にダメージを受け、ぐったりとしてしまうことになるでしょう。ところが、大いなる人はそんなことでも心をまったく心を動かされることはないようです。
【知是非之不可為分】【是非の分を為すべからず、
〔<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、〕
──<良い>として<肯定>して取り入れるばかりに<多>としたり、<悪い>として<否定>して排除するばかりに<賤>としたり、両極端な判断によって、自分の中で分け目をつけることなどはけっしてできないものなのだということを知っているからだ…と言っています。
【細大之不可為倪】 細大の倪(がい)を為すべからざるを知ればなり。】
[<細><大>の微々たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。〕
──ある視点からすれば、<細>や<大>の違いを認識することがあるかもしれないが、それは一時的な姿の違いであって、微々たる違いにすぎないのだが、それさえも判断基準を変えたり、あるいは時間が経過して視点が変わったりすれば、その違いさえつけることができないことだと知っているからだ…と言っているようです。
世間的な爵位(しゃくい)や俸禄(ほうろく)では彼を勧(はげ)ますことはできず、刑罰や恥ずかしめも彼を汚辱(おじょく)におとしこむことはできない。つまり、善し悪しは分けられないものであり、大小も区別できないものだということをよくわきまえているからである。
〇新解釈では、次のようになります。
世間的な爵位や俸禄で力づけることを為すこともできないが、
ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもできない。
<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、
<細><大>の微々たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。
【世之爵禄 不足以為勸】【世の爵禄も以て勧めることと為すに足らず、】
〔世間的な爵位や俸禄で力づけることこともできないが、〕
──世間で高い爵位を与えらることになると、普通の人なら名誉欲が満たされ、喜びに心浮かれることになるでしょう。また、その俸禄(支給された米または金銭)をもらえることになると所有欲も満たされ、心おどり、生きていく上でとても力づけられることになるでしょう。ところが、大いなる人はそんなことで心を動かされることは一切ないようです。
【戮恥不足以為辱】【戮恥(りくち)も以て辱(じょく)と為すに足らず。】
〔ひどく恥ずかしめることで以て、強さをくじいて彼をぐったりとさせることもできない。〕
──反対に、ひどく恥ずかしめられることになると、普通の人なら自尊心が傷つけられ、落胆に心を痛めることになり、生きていく上で心にダメージを受け、ぐったりとしてしまうことになるでしょう。ところが、大いなる人はそんなことでも心をまったく心を動かされることはないようです。
【知是非之不可為分】【是非の分を為すべからず、
〔<是(良い)><非(悪い)>で分けることができないということも、〕
──<良い>として<肯定>して取り入れるばかりに<多>としたり、<悪い>として<否定>して排除するばかりに<賤>としたり、両極端な判断によって、自分の中で分け目をつけることなどはけっしてできないものなのだということを知っているからだ…と言っています。
【細大之不可為倪】 細大の倪(がい)を為すべからざるを知ればなり。】
[<細><大>の微々たる違いさえつけることができないということも知っているからだ。〕
──ある視点からすれば、<細>や<大>の違いを認識することがあるかもしれないが、それは一時的な姿の違いであって、微々たる違いにすぎないのだが、それさえも判断基準を変えたり、あるいは時間が経過して視点が変わったりすれば、その違いさえつけることができないことだと知っているからだ…と言っているようです。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 聞曰道人不聞 ┃【聞くに曰く、道人は聞こえず、】
┃ 至徳不得 ┃【至徳(しとく)は得とせず、】
┃ 大人无己 ┃【大人は己なしと。】
┃ 約分之至也 ┃【約分の至りなりと。】
┗━━━━━━━━━┛
聞くに『道を会得した人は(名声を)聞くこともなく、
徳(人間のもっている本性)に至った人は(徳を)得たようすもなく、
大いなる人は己がない』と言うが、
割り切ってシンプルになっていいくことによって至る境地である。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【約】の勺は、一部を高くくみあげるさまで、杓(ひしゃく)や酌(くみあげる)の原字。
「約」は「糸+勺(目だつようとりあげる)」で、「ひもを引きしめて結び、目だつように
した目じるし。」「二つ以上の数を共通に割ること。」「一点にむけて引きしめる。」
「つづめる・つづまる(細く小さくしてまとめる・簡略にする) 。」
*【約分】は「分数の分母と分子の両方を公約数で割って簡単にすること。」
◆通説では、【聞くならく、道人は聞こえず、至徳(しとく)は得(徳)とせず、大人は己なし
と。約分の至りなりと。】は〔『道人(どうじん/道を体得した人)は名声のあがること
がなく、至徳(しとく/最高の徳に達した人)は徳を得たおもむきもなく、大人(だいじ
ん/偉大な人)は私心を持たない、』といわれているが、まことに自己の本分を守る極致
である。」〕としています。
◇【聞くに曰く、道人は聞こえず、至徳(しとく)は得とせず、大人は己なしと。約分の至
りなりと。】は〔聞くに『道を会得した人は(名声を)聞くこともなく、徳(人間のもっ
ている本性)に至った人は(徳を)得たようすもなく、大いなる人は己がない』と言うが、
割り切ってシンプルになっていくことによって至る境地である。」〕としました。
┃▼ 聞曰道人不聞 ┃【聞くに曰く、道人は聞こえず、】
┃ 至徳不得 ┃【至徳(しとく)は得とせず、】
┃ 大人无己 ┃【大人は己なしと。】
┃ 約分之至也 ┃【約分の至りなりと。】
┗━━━━━━━━━┛
聞くに『道を会得した人は(名声を)聞くこともなく、
徳(人間のもっている本性)に至った人は(徳を)得たようすもなく、
大いなる人は己がない』と言うが、
割り切ってシンプルになっていいくことによって至る境地である。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【約】の勺は、一部を高くくみあげるさまで、杓(ひしゃく)や酌(くみあげる)の原字。
「約」は「糸+勺(目だつようとりあげる)」で、「ひもを引きしめて結び、目だつように
した目じるし。」「二つ以上の数を共通に割ること。」「一点にむけて引きしめる。」
「つづめる・つづまる(細く小さくしてまとめる・簡略にする) 。」
*【約分】は「分数の分母と分子の両方を公約数で割って簡単にすること。」
◆通説では、【聞くならく、道人は聞こえず、至徳(しとく)は得(徳)とせず、大人は己なし
と。約分の至りなりと。】は〔『道人(どうじん/道を体得した人)は名声のあがること
がなく、至徳(しとく/最高の徳に達した人)は徳を得たおもむきもなく、大人(だいじ
ん/偉大な人)は私心を持たない、』といわれているが、まことに自己の本分を守る極致
である。」〕としています。
◇【聞くに曰く、道人は聞こえず、至徳(しとく)は得とせず、大人は己なしと。約分の至
りなりと。】は〔聞くに『道を会得した人は(名声を)聞くこともなく、徳(人間のもっ
ている本性)に至った人は(徳を)得たようすもなく、大いなる人は己がない』と言うが、
割り切ってシンプルになっていくことによって至る境地である。」〕としました。
●通説では、次のようになっています。
『道人(どうじん/道を体得した人)は名声のあがることがなく、至徳(しとく/最高の徳に達した人)は徳を得たおもむきもなく、大人(だいじん/偉大な人)は私心を持たない、』といわれているが、まことに自己の本分を守る極致である。」
〇新解釈では、次のようになります。
聞くに『道を会得した人は(名声を)聞くこともなく、
徳(人間のもっている本性)に至った人は(徳を)得たようすもなく、
大いなる人は己がない』と言うが、
割り切ってシンプルになっていくことによって至る境地である。」
【聞曰道人不聞】【聞くに曰く、道人は聞こえず、】
【至徳不得】【至徳(しとく)は得とせず、】
【大人无己】【大人は己なしと。】
〔聞くに『道を会得した人は(名声を)聞くこともなく、〕
〔最高の徳に至った人は(徳を)得たようすもなく、大いなる人は己がない』と言うが、〕
──道を会得した人は、名誉欲は微塵もないのです。だからその行為は他人の評価など問題外にしているため、その名声を聞くこともないのだと言われている…と言っているようです。
徳(人間のもっている本性)に至った人は、所有欲は微塵もないのです。だからその行為は何かを獲得することを問題外にしているため、その最高の徳でさえ得たようすもないのだと言われている…と言っているようです。
大いなる人は、自尊心は微塵もないのです。だからその行為は自意識を守ることを問題外にしているため、その己とするものもないのだと言われている…と言っているようです。
【約分之至也】【約分の至りなりと。】
〔割り切ってシンプルになっていいくことによって至る境地である。」〕
──「約分」は数学用語です。分数の概念は、中国の『九章算術』(紀元一世紀ごろ漢の時代?の著作)には分母や分子が登場していますので約二千年前には利用していたと考えられています。『荘子』は紀元前280年ごろに完成させた書といわれています。よってここの「約分」の概念は数学で言われているものとは別のものかもしれません(とはいえ、両方とも時代が確実ではありませんので、ひょっとしたら約分の概念もあったかもしれません)。
ただ人間に置き換えて考える時、共通するような概念だったのではないかと推察します。「約」は「つづめる・つづまる(細く小さくしてまとめる・簡略にする)」という意味をもっています。人間性に於ける「約分」とは、余計なものを過剰に<多>として身につけて増やしていくのではなく、「割り切れる」ものはどんどん減らしていって身軽に「シンプルになっていくこと」を表しているのかもしれないと想像しました。
「割り切る」とは、個人的な感情や心情などを交えることなくきっぱりと答えを出すというニュアンスで使います。私利私欲、名誉欲、所有欲も、自尊心も消え、シンプルになっていっても、その内部に残っているものは個性が際立つユニークな存在だと言えるかもしれません。ところが、それがあまりに自然体なので、外部においては、目だたない存在だ…と言っているのかもしれません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
荘子 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
荘子のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90011人
- 2位
- 酒好き
- 170663人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人