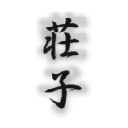━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━庚桑楚(こうそうそ)篇━━━
18、信頼関係
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
蹍市人之足則辭以放驁 市人の足を蹍(ふ)めば、則ち放驁(ほうごう)を以て辞する。
兄則以嫗 兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。
大親則已矣 大いなる親なれば、則ち已(や)む。
故曰 故に曰く、
至禮有不人 至礼は人とせざる有り。
至義不物 至義は物とせず。
至知不謀 至知は謀(はか)らず。
至仁无親 至仁は親(した)しむなし。
至信辟金 至信は金を辟(さ)く。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
市場の雑踏のなかで他人の足をふみつけたときは、失礼をしましたとわびて謝るが、自分の兄の場合にはそこをいたわるだけで、父母の場合にはなにもしないで済ませる。そこでこういうことが言われる、「最高の礼ではあいてを他人扱いにしないところがあり、最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、最高の仁では親しむことはなく、最高の信では黄金を預けるようなことはやめる。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市場で人の足を踏んだならば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。
兄だったならば、かがんでみていたわるだけだ。
大いなる親だったならば、何もしない。
故にこのように言える。
「至上なる礼ともなると、いっさい他人行儀にしないものである。
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
至上なる仁ともなると、親しむこともない。
至上なる信ともなると、お金のやりとりも避ける。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、信頼関係
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
蹍市人之足則辭以放驁 市人の足を蹍(ふ)めば、則ち放驁(ほうごう)を以て辞する。
兄則以嫗 兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。
大親則已矣 大いなる親なれば、則ち已(や)む。
故曰 故に曰く、
至禮有不人 至礼は人とせざる有り。
至義不物 至義は物とせず。
至知不謀 至知は謀(はか)らず。
至仁无親 至仁は親(した)しむなし。
至信辟金 至信は金を辟(さ)く。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
市場の雑踏のなかで他人の足をふみつけたときは、失礼をしましたとわびて謝るが、自分の兄の場合にはそこをいたわるだけで、父母の場合にはなにもしないで済ませる。そこでこういうことが言われる、「最高の礼ではあいてを他人扱いにしないところがあり、最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、最高の仁では親しむことはなく、最高の信では黄金を預けるようなことはやめる。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市場で人の足を踏んだならば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。
兄だったならば、かがんでみていたわるだけだ。
大いなる親だったならば、何もしない。
故にこのように言える。
「至上なる礼ともなると、いっさい他人行儀にしないものである。
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
至上なる仁ともなると、親しむこともない。
至上なる信ともなると、お金のやりとりも避ける。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
|
|
|
コメント(10)
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 蹍市人之足 則辭以放驁 ┃【市人の足を蹍(ふ)めば、則ち放驁を以て辞する。】
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
市場で人の足を踏んだならば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。
…………………………………………………………………………………………………………
*【蹍】は、「ふむ」。「重みをかけてふみのばす」。「足でふみつける」。
*【辭(辞)】は、「ことわる」。「いいわけをする」。「あいさつをのべて去る」。
*【放驁(ほうごう)】は、「不注意で慎重を欠くこと」。
*【驁】は、「馬+(かってきまま)」で、「おごる」。「あなどる」。
◆通説では、【放驁】は「放傲」と同じで「無礼なこと」としています。
【市人の足を蹍(ふ)めば、則ち辞するに放驁(ほうごう)を以てす。】は、「市場の雑踏
の中で他人の足をふみつけたときは、失礼をしましたとわびて謝るが」としています。
◇【市人の足を蹍(ふ)めば、則ち放驁を以て辞する。】は、「市場で人の足を踏んだなら
ば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。」としました。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 兄則以嫗 ┃【兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。】
┃ 大親則已矣 ┃【大いなる親なれば、則ち已(や)む。】
┗━━━━━━━━┛
兄だったならば、かがんでみていたわるだけだ。
大いなる親だったならば、何もしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【嫗】は、「女+.區(小さくかがむ)」。「せなかのかがんだ老婆」。
◆通説では、【嫗】は、「嫗煦(うく/あたためる。いたわる。) 」の意としています。
【大親】は「父母」として【大】の意味は訳していません。
【兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。大親なれば、則ち已(や)む。】は、「自分の兄の場合
にはそこをいたわるだけで、父母の場合にはなにもしないで済ませる。」としています。
◇新解釈では、【大】に意味があるものだとして、「大いなる」と形容しました。
【兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。大いなる親なれば、則ち已(や)む。】は、「兄だっ
たならば、かがんでみていたわるだけだ。大いなる親だったならば、何もしない。」とし
ました。
┃▼ 蹍市人之足 則辭以放驁 ┃【市人の足を蹍(ふ)めば、則ち放驁を以て辞する。】
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
市場で人の足を踏んだならば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。
…………………………………………………………………………………………………………
*【蹍】は、「ふむ」。「重みをかけてふみのばす」。「足でふみつける」。
*【辭(辞)】は、「ことわる」。「いいわけをする」。「あいさつをのべて去る」。
*【放驁(ほうごう)】は、「不注意で慎重を欠くこと」。
*【驁】は、「馬+(かってきまま)」で、「おごる」。「あなどる」。
◆通説では、【放驁】は「放傲」と同じで「無礼なこと」としています。
【市人の足を蹍(ふ)めば、則ち辞するに放驁(ほうごう)を以てす。】は、「市場の雑踏
の中で他人の足をふみつけたときは、失礼をしましたとわびて謝るが」としています。
◇【市人の足を蹍(ふ)めば、則ち放驁を以て辞する。】は、「市場で人の足を踏んだなら
ば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。」としました。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 兄則以嫗 ┃【兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。】
┃ 大親則已矣 ┃【大いなる親なれば、則ち已(や)む。】
┗━━━━━━━━┛
兄だったならば、かがんでみていたわるだけだ。
大いなる親だったならば、何もしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【嫗】は、「女+.區(小さくかがむ)」。「せなかのかがんだ老婆」。
◆通説では、【嫗】は、「嫗煦(うく/あたためる。いたわる。) 」の意としています。
【大親】は「父母」として【大】の意味は訳していません。
【兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。大親なれば、則ち已(や)む。】は、「自分の兄の場合
にはそこをいたわるだけで、父母の場合にはなにもしないで済ませる。」としています。
◇新解釈では、【大】に意味があるものだとして、「大いなる」と形容しました。
【兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。大いなる親なれば、則ち已(や)む。】は、「兄だっ
たならば、かがんでみていたわるだけだ。大いなる親だったならば、何もしない。」とし
ました。
●通説では、次のようになっています。
市場の雑踏のなかで他人の足をふみつけたときは、失礼をしましたとわびて謝るが、自分の兄の場合にはそこをいたわるだけで、父母の場合にはなにもしないで済ませる。
〇新解釈では、次のようになります。
市場で人の足を踏んだならば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。
兄だったならば、かがんでみていたわるだけだ。
大いなる親だったならば、何もしない。
【蹍市人之足 則辭以放驁】【市人の足を蹍(ふ)めば、則ち放驁を以て辞する。】
〔市場で人の足を踏んだならば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。〕
──市場という場所は、人が行き交い混雑しているものです。また、買い物に注意が注がれて、足元にまで気が回らないものです。
そんな市場で他人の足を踏んだなら、何はともあれ、まずは自分の不注意をわびて「すみません」とか「ごめんなさい」などと謝るでしょう。その他人とは、何の信頼関係をも結んでいません。赦してもらうには、もっともな理由が必要だと「混みあっていたもので…」とか「人に押させて…」とか何とか言い訳するものです。なるべく、状況の責任にして、自己責任から免れるような弁解を持ち出すでしょう。
信頼関係を結んでいない人に対しては、「理由をつけて謝る」という「礼儀」が、世間でのトラブルを回避する円滑油のようなものになるのです。
【兄則以嫗】【兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。】
〔兄だったならば、かがんでみていたわるだけだ。〕
──相手が兄の場合は、対応が違ってきます。兄弟ですから、それなりの信頼関係をもっています。いちいち「礼儀」のようにしてかしこまって理由をつけて謝らなくても、無言でかがんでいたわるように兄の足元を軽くなでるとか、あるいは、ただ大丈夫かどうか様子を見るだけとかですむでしょう。
【大親則已矣】【大いなる親なれば、則ち已(や)む。】
〔大いなる親だったならば、何もしない。〕
──これが「大いなる」親の場合だと、また違った対応になると言っています。まるで、何もなかったかのようにスルーしてもいいのです。「大いなる」親子関係は愛情で結ばれたしっかりとした信頼関係が成り立っているからです。子供が、心の底で「まずい」と思っている気持ちがあるのを即座に察知しての暗黙の「赦し」が生まれるのです。そんな関係に何の言うこともやることもないのだ…と言っているようです。
このように、「親」に「大いなる」という言葉がついていることがミソかもしれません。
どんな「親」でもそうかというと、そうとは言えないからです。反対に怒るだけの親もいるかもしれません。「しつけ」と称して「礼儀作法」を重んじる親もいるかもしれません。「親しき仲にも礼儀あり」と言う親の方が実際問題は多いのではないでしょうか。普通の親はそんなものです。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉は、江戸時代初期の西田庄兵衛の『世話盡(づくし)』中の言葉、「思う仲には垣をせよ。心安いは不和の基。親しき仲に垣をせよ。親しき仲は遠くなる。近しき仲にも礼儀あり。良い仲には垣をせよ。良い仲も笠を脱げ。」から生まれたことわざのようです。「垣をせよ」と繰り返しているのが、特徴的です。
古代中国では、『論語』の中に「礼」を尊重するニュアンスの言葉があるので、儒教的なにおいがします。
でも「大いなる」親は違うのです。何も言わなくても、何もしなくてもいいのです。「わたしはあなた、あなたはわたし」状態にあるからです。深い信頼関係は、すべての「垣」を取り除いた時に生まれるものです。
このように「礼」というのは、いつでも同じ「形式」をとるとは限らず、相手との信頼関係や愛情関係の深さによって表現が異なると言っているようです。
市場の雑踏のなかで他人の足をふみつけたときは、失礼をしましたとわびて謝るが、自分の兄の場合にはそこをいたわるだけで、父母の場合にはなにもしないで済ませる。
〇新解釈では、次のようになります。
市場で人の足を踏んだならば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。
兄だったならば、かがんでみていたわるだけだ。
大いなる親だったならば、何もしない。
【蹍市人之足 則辭以放驁】【市人の足を蹍(ふ)めば、則ち放驁を以て辞する。】
〔市場で人の足を踏んだならば、その不注意を謝った上で、言い訳をする。〕
──市場という場所は、人が行き交い混雑しているものです。また、買い物に注意が注がれて、足元にまで気が回らないものです。
そんな市場で他人の足を踏んだなら、何はともあれ、まずは自分の不注意をわびて「すみません」とか「ごめんなさい」などと謝るでしょう。その他人とは、何の信頼関係をも結んでいません。赦してもらうには、もっともな理由が必要だと「混みあっていたもので…」とか「人に押させて…」とか何とか言い訳するものです。なるべく、状況の責任にして、自己責任から免れるような弁解を持ち出すでしょう。
信頼関係を結んでいない人に対しては、「理由をつけて謝る」という「礼儀」が、世間でのトラブルを回避する円滑油のようなものになるのです。
【兄則以嫗】【兄なれば、則ち嫗(う)を以てす。】
〔兄だったならば、かがんでみていたわるだけだ。〕
──相手が兄の場合は、対応が違ってきます。兄弟ですから、それなりの信頼関係をもっています。いちいち「礼儀」のようにしてかしこまって理由をつけて謝らなくても、無言でかがんでいたわるように兄の足元を軽くなでるとか、あるいは、ただ大丈夫かどうか様子を見るだけとかですむでしょう。
【大親則已矣】【大いなる親なれば、則ち已(や)む。】
〔大いなる親だったならば、何もしない。〕
──これが「大いなる」親の場合だと、また違った対応になると言っています。まるで、何もなかったかのようにスルーしてもいいのです。「大いなる」親子関係は愛情で結ばれたしっかりとした信頼関係が成り立っているからです。子供が、心の底で「まずい」と思っている気持ちがあるのを即座に察知しての暗黙の「赦し」が生まれるのです。そんな関係に何の言うこともやることもないのだ…と言っているようです。
このように、「親」に「大いなる」という言葉がついていることがミソかもしれません。
どんな「親」でもそうかというと、そうとは言えないからです。反対に怒るだけの親もいるかもしれません。「しつけ」と称して「礼儀作法」を重んじる親もいるかもしれません。「親しき仲にも礼儀あり」と言う親の方が実際問題は多いのではないでしょうか。普通の親はそんなものです。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉は、江戸時代初期の西田庄兵衛の『世話盡(づくし)』中の言葉、「思う仲には垣をせよ。心安いは不和の基。親しき仲に垣をせよ。親しき仲は遠くなる。近しき仲にも礼儀あり。良い仲には垣をせよ。良い仲も笠を脱げ。」から生まれたことわざのようです。「垣をせよ」と繰り返しているのが、特徴的です。
古代中国では、『論語』の中に「礼」を尊重するニュアンスの言葉があるので、儒教的なにおいがします。
でも「大いなる」親は違うのです。何も言わなくても、何もしなくてもいいのです。「わたしはあなた、あなたはわたし」状態にあるからです。深い信頼関係は、すべての「垣」を取り除いた時に生まれるものです。
このように「礼」というのは、いつでも同じ「形式」をとるとは限らず、相手との信頼関係や愛情関係の深さによって表現が異なると言っているようです。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 故曰 至禮有不人 ┃【故に曰く、至礼は人とせざる有り。】
┗━━━━━━━━━━━┛
故にこのように言える。
「至上なる礼ともなると、いっさいを他人行儀にしないものである。
…………………………………………………………………………………………………………
*【禮(礼)】は、「示(祭壇)+豊(レイ/たかつきに形よくお供え物を盛ったさま)」で
「形よく整えた祭礼」を示します。「かたちよく整えられた作法、儀式」。「社会生活上
の慣習」。「ていねいに応待する」。「あいさつやおじぎ」。
◆通説では、【故に曰く、至礼(しれい)は人とせざるあり。】は「そこでこういうことが言
われる、『最高の礼ではあいてを他人扱いにしないところがあり、」としています。
◇【故に曰く、至礼は人とせざる有り。】は「故にこう言われる。『至上なる礼ともなる
と、いっさいを他人行儀にしないものである。」としました。
┃▼ 故曰 至禮有不人 ┃【故に曰く、至礼は人とせざる有り。】
┗━━━━━━━━━━━┛
故にこのように言える。
「至上なる礼ともなると、いっさいを他人行儀にしないものである。
…………………………………………………………………………………………………………
*【禮(礼)】は、「示(祭壇)+豊(レイ/たかつきに形よくお供え物を盛ったさま)」で
「形よく整えた祭礼」を示します。「かたちよく整えられた作法、儀式」。「社会生活上
の慣習」。「ていねいに応待する」。「あいさつやおじぎ」。
◆通説では、【故に曰く、至礼(しれい)は人とせざるあり。】は「そこでこういうことが言
われる、『最高の礼ではあいてを他人扱いにしないところがあり、」としています。
◇【故に曰く、至礼は人とせざる有り。】は「故にこう言われる。『至上なる礼ともなる
と、いっさいを他人行儀にしないものである。」としました。
●通説では、次のようになっています。
そこでこういうことが言われる、「最高の礼ではあいてを他人扱いにしないところがあり、
〇新解釈では、次のようになります。
故にこのように言える。
「至上なる礼ともなると、いっさいを他人行儀にしないものである。
【故曰 至禮有不人】【故に曰く、至礼は人とせざる有り。】
故にこのように言える。「至上なる礼ともなると、他人行儀にしないものである。
──まず、普通にとらえられている「礼」とはどういったものでしょうか。それは、二人の関係が円満におさまるようにするための礼儀作法と言えるかもしれません。迷惑をかけた場合には謝罪を、恩恵をこうむった場合には感謝を、言葉や態度で相手に伝えることと言えそうです。また、上下関係を保つために目上の人に対して、目下の人は立って挨拶をしたり、敬語を使ったりするものです。そうやって一線を画する「わたし」と「あなた」の間の関係を良好にするための社会的円滑油のような働きをするものと言えそうです。社会には自分とは違う「(他)人」が存在するために、「行儀」よくすることを求めることと言えそうです。
では、「礼」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
先の足を踏んだ場合の例で明らかになったように、「大いなる」親のように、愛情によって信頼が深まると、「わたし」と「あなた」という区別、垣が段々となくなってきます。「(他)人」の過ち、過失、失敗も、あたかも「自分」のことのように考えてしまうものです。愛情あれば、失敗した側が「まずい」という気持ちが生じることも読み取れるものです。そうしたら、もうそれだけで寛大に赦してしまっているのです。
過ち、過失、失敗をした者は、「まずい」と思った気持ちをどこに向けるか…それが問題なのかもしれません。信頼関係が成り立っていない場合は、他人に気を使います。よって礼儀正しく謝ることを優先します。ところが、深い信頼関係にある他人に対しては、謝ったりいたたわったりする必要はなくなっているようですね。
「(他)人」に対してどうこうするよりも優先すべきは、「自分」の不注意、無意識に注目して、同じ過ち、過失、失敗を繰り返さないように意識的になることを肝に銘じることが重要になってくるのかもしれません。自己責任を免れる弁解よりも、とことん自分に責任があることを認めることに意味があるのかもしれません。それが「至上なる礼」になるというわけです。
また、「大いなる」信頼関係が結ばれていると、多大な恩恵をこうむっても「大いなる」親に対しては、「感謝」を述べることも「返礼」をすることも必要もないでしょう。無償の愛を注いだだけの「大いなる」親は、相手が当たり前然としていても一向に意に介さないのです。
やはりこの場合も「(他)人」に対して感謝の表現をするよりも、「自分」の無意識だったところから、意識的になることに意味があるようですね。いつの日にか当たり前のことが実は特別のことだと気づいて、「自分」の成長の糧になっていたことに心底から感謝に溢れて喜びに打ち震えている状態になることがあったならば、それが「至上なる礼」になるというわけです。何一つ言動に表さなくても、「大いなる」親はそれを察知して一緒に喜んでいることでしょう。
このように「至上なる礼」ともなれば、他人行儀に形式ばって人に気を配ることよりも、自分の今の行動に意識的になって失敗を改めたり、恩恵を糧にしたりする方に重きがあると言えるかもしれません。
「至上なるもの」とは、「大いなる」親子関係のように、「絶対的な信頼によって成り立っているもの」と言えそうです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っている至上なる礼ともなると、いっさいがっさい他人行儀にしないものである。」と言いかえることができるかもしれませんね。
そこでこういうことが言われる、「最高の礼ではあいてを他人扱いにしないところがあり、
〇新解釈では、次のようになります。
故にこのように言える。
「至上なる礼ともなると、いっさいを他人行儀にしないものである。
【故曰 至禮有不人】【故に曰く、至礼は人とせざる有り。】
故にこのように言える。「至上なる礼ともなると、他人行儀にしないものである。
──まず、普通にとらえられている「礼」とはどういったものでしょうか。それは、二人の関係が円満におさまるようにするための礼儀作法と言えるかもしれません。迷惑をかけた場合には謝罪を、恩恵をこうむった場合には感謝を、言葉や態度で相手に伝えることと言えそうです。また、上下関係を保つために目上の人に対して、目下の人は立って挨拶をしたり、敬語を使ったりするものです。そうやって一線を画する「わたし」と「あなた」の間の関係を良好にするための社会的円滑油のような働きをするものと言えそうです。社会には自分とは違う「(他)人」が存在するために、「行儀」よくすることを求めることと言えそうです。
では、「礼」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
先の足を踏んだ場合の例で明らかになったように、「大いなる」親のように、愛情によって信頼が深まると、「わたし」と「あなた」という区別、垣が段々となくなってきます。「(他)人」の過ち、過失、失敗も、あたかも「自分」のことのように考えてしまうものです。愛情あれば、失敗した側が「まずい」という気持ちが生じることも読み取れるものです。そうしたら、もうそれだけで寛大に赦してしまっているのです。
過ち、過失、失敗をした者は、「まずい」と思った気持ちをどこに向けるか…それが問題なのかもしれません。信頼関係が成り立っていない場合は、他人に気を使います。よって礼儀正しく謝ることを優先します。ところが、深い信頼関係にある他人に対しては、謝ったりいたたわったりする必要はなくなっているようですね。
「(他)人」に対してどうこうするよりも優先すべきは、「自分」の不注意、無意識に注目して、同じ過ち、過失、失敗を繰り返さないように意識的になることを肝に銘じることが重要になってくるのかもしれません。自己責任を免れる弁解よりも、とことん自分に責任があることを認めることに意味があるのかもしれません。それが「至上なる礼」になるというわけです。
また、「大いなる」信頼関係が結ばれていると、多大な恩恵をこうむっても「大いなる」親に対しては、「感謝」を述べることも「返礼」をすることも必要もないでしょう。無償の愛を注いだだけの「大いなる」親は、相手が当たり前然としていても一向に意に介さないのです。
やはりこの場合も「(他)人」に対して感謝の表現をするよりも、「自分」の無意識だったところから、意識的になることに意味があるようですね。いつの日にか当たり前のことが実は特別のことだと気づいて、「自分」の成長の糧になっていたことに心底から感謝に溢れて喜びに打ち震えている状態になることがあったならば、それが「至上なる礼」になるというわけです。何一つ言動に表さなくても、「大いなる」親はそれを察知して一緒に喜んでいることでしょう。
このように「至上なる礼」ともなれば、他人行儀に形式ばって人に気を配ることよりも、自分の今の行動に意識的になって失敗を改めたり、恩恵を糧にしたりする方に重きがあると言えるかもしれません。
「至上なるもの」とは、「大いなる」親子関係のように、「絶対的な信頼によって成り立っているもの」と言えそうです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っている至上なる礼ともなると、いっさいがっさい他人行儀にしないものである。」と言いかえることができるかもしれませんね。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 至義不物 ┃【至義は物とせず。】
┗━━━━━━━┛
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【義】は「羊(形のよいひつじ)+我(ぎざぎざとかどめのたったほこ)」で、もと「か
どめがたってかっこうのよいこと」。「きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方
のこと」。「すじ道・かどめ。かどめがただしい」。「利欲に引かれず、すじ道をたてる
心」。「約束をしてちかった信頼関係」。
◆通説では、【至義は物とせず、】は「最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、」と
しています。
◇【至義は物とせず。】は、「至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。」としま
した。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 至知不謀 ┃【至知は謀(はか)らず。】
┗━━━━━━━┛
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【謀】は「言+某(暗くてよくわからないこと)」で、「よくわからない先のことをことば
で相談すること」。「わからない先のことをどうするか考える・うつ手をさぐる・また、
その計画」。「悪事をたくらむ」。「さぐりもとめる」。
◆通説では、【至知は謀(はか)らず、】は「最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、」と
しています。
◇【至知は謀(はか)らず。】は「至上なる知ともなると、先のことをことばで考えるこ
ともない。」としました。
┃▼ 至義不物 ┃【至義は物とせず。】
┗━━━━━━━┛
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【義】は「羊(形のよいひつじ)+我(ぎざぎざとかどめのたったほこ)」で、もと「か
どめがたってかっこうのよいこと」。「きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方
のこと」。「すじ道・かどめ。かどめがただしい」。「利欲に引かれず、すじ道をたてる
心」。「約束をしてちかった信頼関係」。
◆通説では、【至義は物とせず、】は「最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、」と
しています。
◇【至義は物とせず。】は、「至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。」としま
した。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 至知不謀 ┃【至知は謀(はか)らず。】
┗━━━━━━━┛
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【謀】は「言+某(暗くてよくわからないこと)」で、「よくわからない先のことをことば
で相談すること」。「わからない先のことをどうするか考える・うつ手をさぐる・また、
その計画」。「悪事をたくらむ」。「さぐりもとめる」。
◆通説では、【至知は謀(はか)らず、】は「最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、」と
しています。
◇【至知は謀(はか)らず。】は「至上なる知ともなると、先のことをことばで考えるこ
ともない。」としました。
●通説では、次のようになっています。
最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、
〇新解釈では、次のようになります。
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
【至義不物】【至義は物とせず。】
〔至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。〕
──まず、普通にとらえられている「義」とはどういったものでしょうか。それは、二人の疎遠だった関係が段々と接近する時に、単に馴れ合う関係にならないように、折り目正しい「かどめ」を立てることだと言えるかもしれません。また、人として「正しいとするすじ道」、「義理」や「正義」を表沙汰にして押し通すことだと言えるかもしれません。
そうしてできあがる二人の関係は、「約束をして誓いあった信頼関係」です。そんな関係は、お互いに裏切ることがないよう確認しつつ、固く約束していることを常に示威していなければ落ち着かないものだと言えそうです。
疎遠だった二人の関係が深くなっても、単になあなあの関係になってしまうのでは、ただ長く一緒にいるというだけで馴れ合いになってしまい、次第に何事に対しても「鈍感」になってしまうものです。互いに「鈍感」になっていることに注意を促すためには、襟を正し、「義」による「かどめ」が必要になってくるというものです。
では、「義」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
約束を結んで関係を保つのではなく、ただただ愛に満たされて、二人の信頼関係が深くなっていく状態になると、相手に対しても自分に対してもより「敏感」になってゆくものです。「敏感」になるということは、細心の注意を怠ることなく極めて意識的になってゆくことなのです。「わたし」と「あなた」の境界線が段々なくなってきていても、自分同様に相手を思いやり、尊重する気持ちを忘れないことが当たり前になってきます。そんな状態ともなれば、「正しいすじ道」を誇示しなくても、もうその「道」を歩んでいるのです。そこに確たる見えない関係性の絆ができているならば、いちいち襟を正すための約束を結んで「かどめ」をつける必要もなくなっているのです。
それが「至上なる義」になるというわけです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っていると言える至上なる義ともなると、折り目正しいかどめなどまったくの問題外として物ともしない。」と言いかえることができるかもしれませんね。
【至知不謀】【至知は謀(はか)らず。】
〔至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。〕
──まず、普通にとらえられている「知」とはどういったものでしょうか。「知」というのは、「ことば」と結びつき、ものごとに明るくなることだと言えるかもしれません。過去からの蓄積によって記憶している「ことば」の量によって、人から賞賛を受けることに期待している面があるかもしれません。けれども、ものごとに明るいことと、意識が明るいこととは同じことではありません。普通の「知」というのは、暗くてよく見えない未知の未来に対して心配を払拭するために、「ことば」を頼りにしてもっともらしい計画を立てて少しでも明るくなるようにあれこれ考えあぐねるはめに陥るだけかもしれません。喩えて言うなら、その知識は、未来にいつ川に遭遇するかもしれないと、重い舟を常に持ち歩いているようなものです。一度それを使っても、また今度のためにと手放すことができない状態に陥っているようなものです。どんどん「ことば」という舟で頭の中が重くなって、現場の足取りはおぼつかないものになります。
では、「知」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
過去でも未来でもない「今ここ」で一瞬一瞬に対応できる意識的な知力(知識や知恵)の明るさで、その場の足元をはっきりと照らしてきていくことができるようになるのです。わからない先のことを心配して「ことば」で考え、計画する必要など一切いらないものだということのようです。喩えで言うなら、川に出くわしたらその時舟を調達すればいいし、川を渡れば舟は手放して、いつでも手軽にいられるのです。その頭脳の巡りと足取りは常に軽やかなのです。
それが、「至上なる知」になるというわけです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っていると言える至上なる知ともなると、何が起こるかわからない未来のことは未来に任せて、今だけを大切にして、先のことをことばで考えたり、計画したりはしないものだ。」と言いかえることができるかもしれませんね。
最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、
〇新解釈では、次のようになります。
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
【至義不物】【至義は物とせず。】
〔至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。〕
──まず、普通にとらえられている「義」とはどういったものでしょうか。それは、二人の疎遠だった関係が段々と接近する時に、単に馴れ合う関係にならないように、折り目正しい「かどめ」を立てることだと言えるかもしれません。また、人として「正しいとするすじ道」、「義理」や「正義」を表沙汰にして押し通すことだと言えるかもしれません。
そうしてできあがる二人の関係は、「約束をして誓いあった信頼関係」です。そんな関係は、お互いに裏切ることがないよう確認しつつ、固く約束していることを常に示威していなければ落ち着かないものだと言えそうです。
疎遠だった二人の関係が深くなっても、単になあなあの関係になってしまうのでは、ただ長く一緒にいるというだけで馴れ合いになってしまい、次第に何事に対しても「鈍感」になってしまうものです。互いに「鈍感」になっていることに注意を促すためには、襟を正し、「義」による「かどめ」が必要になってくるというものです。
では、「義」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
約束を結んで関係を保つのではなく、ただただ愛に満たされて、二人の信頼関係が深くなっていく状態になると、相手に対しても自分に対してもより「敏感」になってゆくものです。「敏感」になるということは、細心の注意を怠ることなく極めて意識的になってゆくことなのです。「わたし」と「あなた」の境界線が段々なくなってきていても、自分同様に相手を思いやり、尊重する気持ちを忘れないことが当たり前になってきます。そんな状態ともなれば、「正しいすじ道」を誇示しなくても、もうその「道」を歩んでいるのです。そこに確たる見えない関係性の絆ができているならば、いちいち襟を正すための約束を結んで「かどめ」をつける必要もなくなっているのです。
それが「至上なる義」になるというわけです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っていると言える至上なる義ともなると、折り目正しいかどめなどまったくの問題外として物ともしない。」と言いかえることができるかもしれませんね。
【至知不謀】【至知は謀(はか)らず。】
〔至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。〕
──まず、普通にとらえられている「知」とはどういったものでしょうか。「知」というのは、「ことば」と結びつき、ものごとに明るくなることだと言えるかもしれません。過去からの蓄積によって記憶している「ことば」の量によって、人から賞賛を受けることに期待している面があるかもしれません。けれども、ものごとに明るいことと、意識が明るいこととは同じことではありません。普通の「知」というのは、暗くてよく見えない未知の未来に対して心配を払拭するために、「ことば」を頼りにしてもっともらしい計画を立てて少しでも明るくなるようにあれこれ考えあぐねるはめに陥るだけかもしれません。喩えて言うなら、その知識は、未来にいつ川に遭遇するかもしれないと、重い舟を常に持ち歩いているようなものです。一度それを使っても、また今度のためにと手放すことができない状態に陥っているようなものです。どんどん「ことば」という舟で頭の中が重くなって、現場の足取りはおぼつかないものになります。
では、「知」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
過去でも未来でもない「今ここ」で一瞬一瞬に対応できる意識的な知力(知識や知恵)の明るさで、その場の足元をはっきりと照らしてきていくことができるようになるのです。わからない先のことを心配して「ことば」で考え、計画する必要など一切いらないものだということのようです。喩えで言うなら、川に出くわしたらその時舟を調達すればいいし、川を渡れば舟は手放して、いつでも手軽にいられるのです。その頭脳の巡りと足取りは常に軽やかなのです。
それが、「至上なる知」になるというわけです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っていると言える至上なる知ともなると、何が起こるかわからない未来のことは未来に任せて、今だけを大切にして、先のことをことばで考えたり、計画したりはしないものだ。」と言いかえることができるかもしれませんね。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 至義不物 ┃【至義は物とせず。】
┗━━━━━━━┛
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【義】は「羊(形のよいひつじ)+我(ぎざぎざとかどめのたったほこ)」で、もと「か
どめがたってかっこうのよいこと」。「きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方
のこと」。「すじ道・かどめ。かどめがただしい」。「利欲に引かれず、すじ道をたてる
心」。「約束をしてちかった信頼関係」。
◆通説では、【至義は物とせず、】は「最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、」と
しています。
◇【至義は物とせず。】は、「至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。」としま
した。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 至知不謀 ┃【至知は謀(はか)らず。】
┗━━━━━━━┛
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【謀】は「言+某(暗くてよくわからないこと)」で、「よくわからない先のことをことば
で相談すること」。「わからない先のことをどうするか考える・うつ手をさぐる・また、
その計画」。「悪事をたくらむ」。「さぐりもとめる」。
◆通説では、【至知は謀(はか)らず、】は「最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、」と
しています。
◇【至知は謀(はか)らず。】は「至上なる知ともなると、先のことをことばで考えるこ
ともない。」としました。
┃▼ 至義不物 ┃【至義は物とせず。】
┗━━━━━━━┛
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【義】は「羊(形のよいひつじ)+我(ぎざぎざとかどめのたったほこ)」で、もと「か
どめがたってかっこうのよいこと」。「きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方
のこと」。「すじ道・かどめ。かどめがただしい」。「利欲に引かれず、すじ道をたてる
心」。「約束をしてちかった信頼関係」。
◆通説では、【至義は物とせず、】は「最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、」と
しています。
◇【至義は物とせず。】は、「至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。」としま
した。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 至知不謀 ┃【至知は謀(はか)らず。】
┗━━━━━━━┛
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【謀】は「言+某(暗くてよくわからないこと)」で、「よくわからない先のことをことば
で相談すること」。「わからない先のことをどうするか考える・うつ手をさぐる・また、
その計画」。「悪事をたくらむ」。「さぐりもとめる」。
◆通説では、【至知は謀(はか)らず、】は「最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、」と
しています。
◇【至知は謀(はか)らず。】は「至上なる知ともなると、先のことをことばで考えるこ
ともない。」としました。
●通説では、次のようになっています。
最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、
〇新解釈では、次のようになります。
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
【至義不物】【至義は物とせず。】
〔至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。〕
──まず、普通にとらえられている「義」とはどういったものでしょうか。それは、二人の疎遠だった関係が段々と接近する時に、単に馴れ合う関係にならないように、折り目正しい「かどめ」を立てることだと言えるかもしれません。また、人として「正しいとするすじ道」、「義理」や「正義」を表沙汰にして押し通すことだと言えるかもしれません。
そうしてできあがる二人の関係は、「約束をして誓いあった信頼関係」です。そんな関係は、お互いに裏切ることがないよう確認しつつ、固く約束していることを常に確認していなければ落ち着かないものだと言えそうです。
疎遠だった二人の関係が深くなっても、単になあなあの関係になってしまうのでは、ただ長く一緒にいるというだけで馴れ合いになってしまい、次第に何事に対しても「鈍感」になってしまうものです。互いに「鈍感」になっていることに注意を促すためには、襟を正し、「義」による「かどめ」が必要になってくるというものです。
では、「義」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
約束を結んで関係を保つのではなく、ただただ愛に満たされて、二人の信頼関係が深くなっていく状態になると、相手に対しても自分に対してもより「敏感」になってゆくものです。「敏感」になるということは、細心の注意を怠ることなく極めて意識的になってゆくことなのです。「わたし」と「あなた」の境界線が段々なくなってきていても、自分同様に相手を思いやり、尊重する気持ちを忘れないことが当たり前になってきます。そんな状態ともなれば、「正しいすじ道」を誇示しなくても、もうその「道」を歩んでいるのです。そこに確たる見えない関係性の絆ができているならば、いちいち襟を正すための約束を結んで「かどめ」をつける必要もなくなっているのです。
それが「至上なる義」になるというわけです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っていると言える至上なる義ともなると、折り目正しいかどめなどまったくの問題外として物ともしない。」と言いかえることができるかもしれませんね。
【至知不謀】【至知は謀(はか)らず。】
〔至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。〕
──まず、普通にとらえられている「知」とはどういったものでしょうか。「知」というのは、「ことば」と結びつき、ものごとに明るくなることだと言えるかもしれません。過去からの蓄積によって記憶している「ことば」の量によって、人から賞賛を受けることに期待している面があるかもしれません。けれども、ものごとに明るいことと、意識が明るいこととは同じことではありません。普通の「知」というのは、暗くてよく見えない未知の未来に対して心配を払拭するために、「ことば」を頼りにしてもっともらしい計画を立てて少しでも明るくなるようにあれこれ考えあぐねるはめに陥るだけかもしれません。喩えて言うなら、その知識は、未来にいつ川に遭遇するかもしれないと、重い舟を常に持ち歩いているようなものです。一度それを使っても、また今度のためにと手放すことができない状態に陥っているようなものです。どんどん「ことば」という舟で頭の中が重くなって、現場の足取りはおぼつかないものになります。
では、「知」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
過去でも未来でもない「今ここ」で一瞬一瞬に対応できる意識的な知力(知識や知恵)の明るさで、その場の足元をはっきりと照らしてきていくことができるようになるのです。わからない先のことを心配して「ことば」で考え、計画する必要など一切いらないものだということのようです。喩えで言うなら、川に出くわしたらその時舟を調達すればいいし、川を渡れば舟は手放して、いつでも手軽にいられるのです。その頭脳の巡りと足取りは常に軽やかなのです。
それが、「至上なる知」になるというわけです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っていると言える至上なる知ともなると、何が起こるかわからない未来のことは未来に任せて、今だけを大切にして、先のことをことばで考えたり、計画したりはしないものだ。」と言いかえることができるかもしれませんね。
最高の義では物事のけじめをつけたりはせず、最高の知では慮(はか)り考えたりはせず、
〇新解釈では、次のようになります。
至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。
至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。
【至義不物】【至義は物とせず。】
〔至上なる義ともなると、かどめを物ともしない。〕
──まず、普通にとらえられている「義」とはどういったものでしょうか。それは、二人の疎遠だった関係が段々と接近する時に、単に馴れ合う関係にならないように、折り目正しい「かどめ」を立てることだと言えるかもしれません。また、人として「正しいとするすじ道」、「義理」や「正義」を表沙汰にして押し通すことだと言えるかもしれません。
そうしてできあがる二人の関係は、「約束をして誓いあった信頼関係」です。そんな関係は、お互いに裏切ることがないよう確認しつつ、固く約束していることを常に確認していなければ落ち着かないものだと言えそうです。
疎遠だった二人の関係が深くなっても、単になあなあの関係になってしまうのでは、ただ長く一緒にいるというだけで馴れ合いになってしまい、次第に何事に対しても「鈍感」になってしまうものです。互いに「鈍感」になっていることに注意を促すためには、襟を正し、「義」による「かどめ」が必要になってくるというものです。
では、「義」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
約束を結んで関係を保つのではなく、ただただ愛に満たされて、二人の信頼関係が深くなっていく状態になると、相手に対しても自分に対してもより「敏感」になってゆくものです。「敏感」になるということは、細心の注意を怠ることなく極めて意識的になってゆくことなのです。「わたし」と「あなた」の境界線が段々なくなってきていても、自分同様に相手を思いやり、尊重する気持ちを忘れないことが当たり前になってきます。そんな状態ともなれば、「正しいすじ道」を誇示しなくても、もうその「道」を歩んでいるのです。そこに確たる見えない関係性の絆ができているならば、いちいち襟を正すための約束を結んで「かどめ」をつける必要もなくなっているのです。
それが「至上なる義」になるというわけです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っていると言える至上なる義ともなると、折り目正しいかどめなどまったくの問題外として物ともしない。」と言いかえることができるかもしれませんね。
【至知不謀】【至知は謀(はか)らず。】
〔至上なる知ともなると、先のことをことばで考えることもない。〕
──まず、普通にとらえられている「知」とはどういったものでしょうか。「知」というのは、「ことば」と結びつき、ものごとに明るくなることだと言えるかもしれません。過去からの蓄積によって記憶している「ことば」の量によって、人から賞賛を受けることに期待している面があるかもしれません。けれども、ものごとに明るいことと、意識が明るいこととは同じことではありません。普通の「知」というのは、暗くてよく見えない未知の未来に対して心配を払拭するために、「ことば」を頼りにしてもっともらしい計画を立てて少しでも明るくなるようにあれこれ考えあぐねるはめに陥るだけかもしれません。喩えて言うなら、その知識は、未来にいつ川に遭遇するかもしれないと、重い舟を常に持ち歩いているようなものです。一度それを使っても、また今度のためにと手放すことができない状態に陥っているようなものです。どんどん「ことば」という舟で頭の中が重くなって、現場の足取りはおぼつかないものになります。
では、「知」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
過去でも未来でもない「今ここ」で一瞬一瞬に対応できる意識的な知力(知識や知恵)の明るさで、その場の足元をはっきりと照らしてきていくことができるようになるのです。わからない先のことを心配して「ことば」で考え、計画する必要など一切いらないものだということのようです。喩えで言うなら、川に出くわしたらその時舟を調達すればいいし、川を渡れば舟は手放して、いつでも手軽にいられるのです。その頭脳の巡りと足取りは常に軽やかなのです。
それが、「至上なる知」になるというわけです。
「絶対的な大いなる信頼によって成り立っていると言える至上なる知ともなると、何が起こるかわからない未来のことは未来に任せて、今だけを大切にして、先のことをことばで考えたり、計画したりはしないものだ。」と言いかえることができるかもしれませんね。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 至仁无親 ┃【至仁は親(した)しむなし。】
┗━━━━━━━┛
至上なる仁ともなると、親しむこともない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【仁】は、「人+二」で、「二人が相対等に親しむこと。」を示します。
■『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』より
【仁】
儒教が主張した愛情の一形態。愛とは、他人を大切に思い、いつくしむ感情をさす語で
ある。それとは別に仁という語が成立しているからには、仁と愛とは同義ではない。語
源については、一般には、仁とは、人間の姿を示す象形文字であるが、(太古において
は、他部族の者は人ではないから) 自分の身近にいる親しい間柄の「仲間」、または、
二人の人と人との間の愛情の意味、といわれる。儒教でも、仁をほぼ同様の意味で用いて
いる。「克己復礼」、すなわち、私的なわがままを押えて、礼すなわち社会的規範に従う
ことが仁である、と孔子が述べているように、仁という愛では他人との身分的境界が常に
意識され、礼という公の規準が先行している。したがって、普遍的な人間愛 Humanism
や仏教の平等愛である慈悲などとは違う。
*【親】は「見+[シン](木をナイフで切ったなま木)」で、「ナイフで身を切るように身近
に接して見ていること」。「じかに刺激をうける近しい間がら」。「身近に接している」
「じかにはだ身にふれる」。
◆通説では【至仁は親(した)しむなく、】は「最高の仁では親しむことはなく、」としてい
ます。
◇【至仁は親(した)しむなし。】は「至上なる仁ともなると、親しむこともない。」としま
した。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 至信辟金 ┃【至信は金を辟(さ)く。】
┗━━━━━━━┛
至上なる信ともなると、お金のやりとりも避ける。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【信】は、「人+言(はっきりいう)」で、「一度言明したことを押し通す人間の行為」を
あらわします。「途中で屈することなく、まっすぐのび進む」の意を含みます。「まこと
(言明や約束をどこまでも通すこと)」。「信用する」。
*【辟】は、「人+辛(刑罰を加える刃物)+口」で、人の処刑を命じ、平伏させる君主を
あらわします。また、人体を刃物で引き裂く刑罰をあらわすとも解せられられます。
「平らに横にひらく」意を含みます。「さける」。「横によける」。
◆通説では、【辟】は、「預けるようなことはやめる」と意訳しています。
【至信は金を辟(さ)く。】は、「最高の信では黄金を預けるようなことはやめる。」とし
ています。
◇【至信は金を辟(さ)く。】は、「至上なる信ともなると、お金のやりとりを避ける。」と
しました。
┃▼ 至仁无親 ┃【至仁は親(した)しむなし。】
┗━━━━━━━┛
至上なる仁ともなると、親しむこともない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【仁】は、「人+二」で、「二人が相対等に親しむこと。」を示します。
■『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』より
【仁】
儒教が主張した愛情の一形態。愛とは、他人を大切に思い、いつくしむ感情をさす語で
ある。それとは別に仁という語が成立しているからには、仁と愛とは同義ではない。語
源については、一般には、仁とは、人間の姿を示す象形文字であるが、(太古において
は、他部族の者は人ではないから) 自分の身近にいる親しい間柄の「仲間」、または、
二人の人と人との間の愛情の意味、といわれる。儒教でも、仁をほぼ同様の意味で用いて
いる。「克己復礼」、すなわち、私的なわがままを押えて、礼すなわち社会的規範に従う
ことが仁である、と孔子が述べているように、仁という愛では他人との身分的境界が常に
意識され、礼という公の規準が先行している。したがって、普遍的な人間愛 Humanism
や仏教の平等愛である慈悲などとは違う。
*【親】は「見+[シン](木をナイフで切ったなま木)」で、「ナイフで身を切るように身近
に接して見ていること」。「じかに刺激をうける近しい間がら」。「身近に接している」
「じかにはだ身にふれる」。
◆通説では【至仁は親(した)しむなく、】は「最高の仁では親しむことはなく、」としてい
ます。
◇【至仁は親(した)しむなし。】は「至上なる仁ともなると、親しむこともない。」としま
した。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 至信辟金 ┃【至信は金を辟(さ)く。】
┗━━━━━━━┛
至上なる信ともなると、お金のやりとりも避ける。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【信】は、「人+言(はっきりいう)」で、「一度言明したことを押し通す人間の行為」を
あらわします。「途中で屈することなく、まっすぐのび進む」の意を含みます。「まこと
(言明や約束をどこまでも通すこと)」。「信用する」。
*【辟】は、「人+辛(刑罰を加える刃物)+口」で、人の処刑を命じ、平伏させる君主を
あらわします。また、人体を刃物で引き裂く刑罰をあらわすとも解せられられます。
「平らに横にひらく」意を含みます。「さける」。「横によける」。
◆通説では、【辟】は、「預けるようなことはやめる」と意訳しています。
【至信は金を辟(さ)く。】は、「最高の信では黄金を預けるようなことはやめる。」とし
ています。
◇【至信は金を辟(さ)く。】は、「至上なる信ともなると、お金のやりとりを避ける。」と
しました。
●通説では、次のようになっています。
最高の仁では親しむことはなく、最高の信では黄金を預けるようなことはやめる。
〇新解釈では、次のようになります。
至上なる仁ともなると、親しむこともない。
至上なる信ともなると、お金のやりとりも避ける。
【至仁无親】【至仁は親(した)しむなし。】
〔至上なる仁ともなると、親しむこともない。〕
──まず「仁」とはどういったものでしょうか。「仁」とは、主に「他人に対する親愛の情、優しさ」を意味していますが、古代から近代に至るまで中国人の倫理規定の最重要項目となってきたものです。中国では、社会秩序(礼)を支える精神、心のあり方としています。
そのため、「仁」という徳を高め、人と「親しくすること」の必要を唱えているのです。
では、「仁」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
一般的な愛情を超越した「至上なる仁」ともなると、「親しくなること」を求めません。その出会いの瞬間瞬間に幸福感で満たされているからです。それが実感できるからです。だから、相手が見えないところで何をしていても、心配や疑いをもちません。深い愛情と信頼とで結ばれていれば、互いを束縛することもありません。あらためて「親しくする」必要がないほど、深く信頼しあっているからです。
それが「至上なる仁」になるというわけです。
「絶対的な大いなる深い信頼関係、愛情関係で成り立っていると言える至上なる仁ともなると、ただ親しくして近づくことではなく、相手との距離感を自在に変えられるような完全な自由な立場でいられるのだ。」と言いかえることができるかもしれませんね。
【至信辟金】【至信は金を辟(さ)く。】
〔至上なる信ともなると、お金のやりとりも避ける。〕
──まず、普通にとらえられている「信」はどういったものでしょうか。お金や、それ相応のプレゼントなどを媒介として、信頼や信用を得ようとすることが多々あります。そのため世の中は、賄賂工作が横行しています。そうして築いた信頼や信用は、ちょっとしたきっかけで、いとも簡単に崩れ去ってしまうことが往々にしてあります。これでは、本当の信頼や信用を得ることはとうてい無理でしょう。なのに信頼関係を築くために、昔も今もなかなかお金がらみの縁を切ることができないでいます。
では、「信」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるでしょうか。
いかなる媒介、裏取引ももたずに、ただひたすら「信じ合える」心こそ、何にも代えられるものではありません。まったく利害関係のない心と心の強い絆です。それ以上、何も必要としていないのです。もっとも避けて通るのはお金のやりとりということになりそうです。
それが、「至上なる信」になるというわけです。
「疑うことがない大いなる信頼で成り立っている至上なる信ともなると、お金にものを言わせることは微塵もなく、そのやりとりをすることを避けて通ることなのだ。」と言いかえることができるかもしれませんね。
儒教では、五常(仁、義、礼、智、信)の徳性を拡充することにより、父子、君臣、夫婦、長幼、朋友の五倫の道をまっとうすることを説いていることから、それに絡めた話の展開になっているのかもしれませんね。いずれにしても「至上なる礼・義・知・仁・信」は、五常の概念を超越したものと言えそうです。
最高の仁では親しむことはなく、最高の信では黄金を預けるようなことはやめる。
〇新解釈では、次のようになります。
至上なる仁ともなると、親しむこともない。
至上なる信ともなると、お金のやりとりも避ける。
【至仁无親】【至仁は親(した)しむなし。】
〔至上なる仁ともなると、親しむこともない。〕
──まず「仁」とはどういったものでしょうか。「仁」とは、主に「他人に対する親愛の情、優しさ」を意味していますが、古代から近代に至るまで中国人の倫理規定の最重要項目となってきたものです。中国では、社会秩序(礼)を支える精神、心のあり方としています。
そのため、「仁」という徳を高め、人と「親しくすること」の必要を唱えているのです。
では、「仁」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるのでしょうか。
一般的な愛情を超越した「至上なる仁」ともなると、「親しくなること」を求めません。その出会いの瞬間瞬間に幸福感で満たされているからです。それが実感できるからです。だから、相手が見えないところで何をしていても、心配や疑いをもちません。深い愛情と信頼とで結ばれていれば、互いを束縛することもありません。あらためて「親しくする」必要がないほど、深く信頼しあっているからです。
それが「至上なる仁」になるというわけです。
「絶対的な大いなる深い信頼関係、愛情関係で成り立っていると言える至上なる仁ともなると、ただ親しくして近づくことではなく、相手との距離感を自在に変えられるような完全な自由な立場でいられるのだ。」と言いかえることができるかもしれませんね。
【至信辟金】【至信は金を辟(さ)く。】
〔至上なる信ともなると、お金のやりとりも避ける。〕
──まず、普通にとらえられている「信」はどういったものでしょうか。お金や、それ相応のプレゼントなどを媒介として、信頼や信用を得ようとすることが多々あります。そのため世の中は、賄賂工作が横行しています。そうして築いた信頼や信用は、ちょっとしたきっかけで、いとも簡単に崩れ去ってしまうことが往々にしてあります。これでは、本当の信頼や信用を得ることはとうてい無理でしょう。なのに信頼関係を築くために、昔も今もなかなかお金がらみの縁を切ることができないでいます。
では、「信」に「至上なる」という形容がつくとどこがどう違ってくるでしょうか。
いかなる媒介、裏取引ももたずに、ただひたすら「信じ合える」心こそ、何にも代えられるものではありません。まったく利害関係のない心と心の強い絆です。それ以上、何も必要としていないのです。もっとも避けて通るのはお金のやりとりということになりそうです。
それが、「至上なる信」になるというわけです。
「疑うことがない大いなる信頼で成り立っている至上なる信ともなると、お金にものを言わせることは微塵もなく、そのやりとりをすることを避けて通ることなのだ。」と言いかえることができるかもしれませんね。
儒教では、五常(仁、義、礼、智、信)の徳性を拡充することにより、父子、君臣、夫婦、長幼、朋友の五倫の道をまっとうすることを説いていることから、それに絡めた話の展開になっているのかもしれませんね。いずれにしても「至上なる礼・義・知・仁・信」は、五常の概念を超越したものと言えそうです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
荘子 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
荘子のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90055人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人