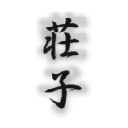━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、瞿鵲子と長梧子(2)夢と目覚め
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
予惡乎知説生之非惑邪 予(われ)いずくんぞ生を説くことの惑にあらざるを知らんや。
予惡乎知惡死之非弱喪 予いずくんぞ死を悪(にく)むことの弱を喪(うしな)いて
而不知帰者邪 帰るを知らざる者にあらざるを知らんや。
麗之姫艾封人之子也 麗 (り)の 姫(き)は艾(がい)の封人の子なり。
晋国之始得之也 晋国の始めてこれを得るや、
涕泣沾襟 涕泣(ていきゅう)して襟(えり)を沾(うるお)せるも、
及其至於王所 その王の所に至り、
与王同筐牀 王と筐牀(きょうしょう)を同じくし、
食芻豢 芻豢(すうけん)を食らうに及びて、
而後悔其泣也 而る後にその泣きしを悔いたり。
予惡乎知夫死者 予いずくんぞ、かの死者の
不悔其始之蘄生 その始めの生を蘄(か)るに悔いざるを知らんや。
夢飲酒者 夢に酒を飲む者は、
旦而哭泣 旦にして哭泣(こくきゅう)し、
夢哭泣者 夢に哭泣する者は、
旦而田猟 旦にして田猟(でんりょう)す。
方其夢也 方にして、その夢や、
不知其夢也 その夢なることを知らず。
夢之中又占其夢焉 夢の中で又その夢を占い、
覺而後知其夢也 覚めて後にその夢なることを知る。
且有大覺 且、大覚あり。
而後知此其大夢焉 而る後此れその大夢なることを知る。
而愚者自以為覺 而して愚者は自ずと覚を為すを以って、
竊竊然知之 竊竊(せつせつ)然としてこれを知る。
君乎牧乎 固哉 君や牧や、固(もと)よりかな。
丘也与女皆夢也 丘や女(なんじ)はともに皆夢なり。
予謂女夢亦夢也 予(われ)の女(なんじ)を夢と謂うのも亦夢なり。
是其言也 是、その言や、
其名為弔詭 その名を弔詭(ちょうき)と為す。
万世之後而一遇大聖 万世の後にして、一たび大聖と遇し、
知其解者 その解を知る者は、
是旦暮遇之也 是、旦暮にこれに遇するなり。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
生を喜ぶことが惑い〔であるかも知れない、そう〕ではないとはわしには決められない。死を憎むことが、幼いころに故郷を離れて帰ることを忘れた者と同じで〔あるかも知れない、そうで〕ないとは、わしには決められない。麗姫(りき)は〔麗戎国の〕艾(がい)の地の国境役人の娘だが、始めて晋の国につれていかれようとしたときは、さめざめと泣き悲しんで涙で襟を濡らすほどであったのに、さて王の宮殿に行きついて王と起居を共にし、牛や豚の美食を口にするようになってからは、はじめに泣いたことを後悔したという。
あのすでに死んだ人々も、その生きていたときに生を求めたことを後悔してい〔るかも知れない、そうで〕ないとは、わしには決められない。
夢のなかで酒を飲んで楽しんでいた者が、朝になると不幸な現実に泣き悲しみ、夢の中で泣き悲しんでいた者が、朝になると楽しく狩りに出かけるということがある。夢を見ているときには、それが夢であることは分からず、夢のなかでまた夢占いをしたりして、目が覚めてからはじめてそれが夢であったことが分かるのである。〔人生も同じことだ。〕本当の目覚めがあってこそ、始めてこの人生が大きな一場の夢であることが分かるのだ。それなのに、愚か者は自分で目が覚めているとうぬぼれて、あれこれと穿鑿(せんさく)してはもの知り顔をして、君主だといっては貴び牧人だといっては賤しんで差別する。頑くななことだ。孔丘もお前もみな夢を見ているのだ。そして、わしがお前に夢の話をしているのも、また夢だ。こうした話こそそれを名づけて弔詭(てきき/──すなわちとてもかわった話)という。この話の意味が分かる大聖人に〔めぐり会うのはむずかしいことで、〕万代もの後に一度めぐりあったとしても、それは朝晩に会っているほど〔の幸運〕なのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
▽(岸陽子 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
こう見てくると、人間が生に執着することは迷いであるかもしれず、死を厭(いと)うことは旅人が帰るべき故郷を忘れたようなものかも知れぬ。たとえば、かの美女麗姫(りき)は、艾(がい)の防人(さきもり)の娘だったが、捕らえられて晋(しん)に来た時は、泣いて泣いて泣き明かしたものだった。やがて後宮(こうきゅう)に迎えられ、王と臥床(ふしど)をともにし、ぜいたく三昧(ざんまい)に日を送るようになると、かえって昔泣いたことを後悔したということだ。してみると、死者にしても、かつて生に執着したことを、後になって後悔しているかも知れないのだ。
また、夢の中で歓楽をつくした者が、一夜明けると辛い現実に声をあげ泣き、夢の中で泣いていた者が、一夜明けるとけろりとして猟を楽しむこともある。夢を見ている時は、それは夢だと気づかない。夢の中でさらに夢占いをすることさえあるが、目覚めてはじめて夢だだったと気づくのだ。人生にしても長い夢のようなもの、真の悟りに到達した者だけが、その夢であることに気づくのだ。だがおろかにも人々は、目覚めた人間をもって自任し、小知をこれ見よがしにふりかざして、何が貴いの何が賤しいのと論じたてる。まったく、くだらん話しだ。
孔丘にせよ、おまえにせよ、みな夢を見ているのだ。いや夢だといっているこのわたしでさえ、例外なしに夢を見ているのだ。こういえば、さぞかし奇怪千万な意見ととられるだろう。わからないのが当たり前。この説を受け容れてくれる大聖人は、数十万年にひとり出るか出ないかというところなのだからな。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)ではないと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人の娘だったが、晋の国に捕らえられたその始めは、ぽろぽろと流れ落ちる涙で襟(えり)を濡らすほどだったというのに、その王の宮殿に行きつき、王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及び、すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。
そうして死んでいった者(彼女)が、その始めの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
夢の中で、酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、
夢の中で、大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。
あてもなく進行する夢の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。
夢の中で、また夢占いをしていたりもする。
だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるものだ。
さらに言えば、大いなる目覚めもある。
目覚めてはじめて大きな夢を見ていたことを知ることができるものだ。
<愚者(鏡のような無我な心をもつ者)>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、人知れず内部から少しずつあたかも(滋養物を) 竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。
(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に相当する滋養物)なるものが、それぞれもとからあるからだ。
丘(孔子)もお前もみな夢の中だ。
予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。
このようなことをこういうふうに言える。
その名は<弔詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。
長い時を経た後、一たび大いなる聖なるものと遇し(出会ってそっくりに歩み)、これ(聖なるものの実態)がどういうものか紐解かれることを知った者は、これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことになるだろう。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、瞿鵲子と長梧子(2)夢と目覚め
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
予惡乎知説生之非惑邪 予(われ)いずくんぞ生を説くことの惑にあらざるを知らんや。
予惡乎知惡死之非弱喪 予いずくんぞ死を悪(にく)むことの弱を喪(うしな)いて
而不知帰者邪 帰るを知らざる者にあらざるを知らんや。
麗之姫艾封人之子也 麗 (り)の 姫(き)は艾(がい)の封人の子なり。
晋国之始得之也 晋国の始めてこれを得るや、
涕泣沾襟 涕泣(ていきゅう)して襟(えり)を沾(うるお)せるも、
及其至於王所 その王の所に至り、
与王同筐牀 王と筐牀(きょうしょう)を同じくし、
食芻豢 芻豢(すうけん)を食らうに及びて、
而後悔其泣也 而る後にその泣きしを悔いたり。
予惡乎知夫死者 予いずくんぞ、かの死者の
不悔其始之蘄生 その始めの生を蘄(か)るに悔いざるを知らんや。
夢飲酒者 夢に酒を飲む者は、
旦而哭泣 旦にして哭泣(こくきゅう)し、
夢哭泣者 夢に哭泣する者は、
旦而田猟 旦にして田猟(でんりょう)す。
方其夢也 方にして、その夢や、
不知其夢也 その夢なることを知らず。
夢之中又占其夢焉 夢の中で又その夢を占い、
覺而後知其夢也 覚めて後にその夢なることを知る。
且有大覺 且、大覚あり。
而後知此其大夢焉 而る後此れその大夢なることを知る。
而愚者自以為覺 而して愚者は自ずと覚を為すを以って、
竊竊然知之 竊竊(せつせつ)然としてこれを知る。
君乎牧乎 固哉 君や牧や、固(もと)よりかな。
丘也与女皆夢也 丘や女(なんじ)はともに皆夢なり。
予謂女夢亦夢也 予(われ)の女(なんじ)を夢と謂うのも亦夢なり。
是其言也 是、その言や、
其名為弔詭 その名を弔詭(ちょうき)と為す。
万世之後而一遇大聖 万世の後にして、一たび大聖と遇し、
知其解者 その解を知る者は、
是旦暮遇之也 是、旦暮にこれに遇するなり。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
生を喜ぶことが惑い〔であるかも知れない、そう〕ではないとはわしには決められない。死を憎むことが、幼いころに故郷を離れて帰ることを忘れた者と同じで〔あるかも知れない、そうで〕ないとは、わしには決められない。麗姫(りき)は〔麗戎国の〕艾(がい)の地の国境役人の娘だが、始めて晋の国につれていかれようとしたときは、さめざめと泣き悲しんで涙で襟を濡らすほどであったのに、さて王の宮殿に行きついて王と起居を共にし、牛や豚の美食を口にするようになってからは、はじめに泣いたことを後悔したという。
あのすでに死んだ人々も、その生きていたときに生を求めたことを後悔してい〔るかも知れない、そうで〕ないとは、わしには決められない。
夢のなかで酒を飲んで楽しんでいた者が、朝になると不幸な現実に泣き悲しみ、夢の中で泣き悲しんでいた者が、朝になると楽しく狩りに出かけるということがある。夢を見ているときには、それが夢であることは分からず、夢のなかでまた夢占いをしたりして、目が覚めてからはじめてそれが夢であったことが分かるのである。〔人生も同じことだ。〕本当の目覚めがあってこそ、始めてこの人生が大きな一場の夢であることが分かるのだ。それなのに、愚か者は自分で目が覚めているとうぬぼれて、あれこれと穿鑿(せんさく)してはもの知り顔をして、君主だといっては貴び牧人だといっては賤しんで差別する。頑くななことだ。孔丘もお前もみな夢を見ているのだ。そして、わしがお前に夢の話をしているのも、また夢だ。こうした話こそそれを名づけて弔詭(てきき/──すなわちとてもかわった話)という。この話の意味が分かる大聖人に〔めぐり会うのはむずかしいことで、〕万代もの後に一度めぐりあったとしても、それは朝晩に会っているほど〔の幸運〕なのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
▽(岸陽子 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
こう見てくると、人間が生に執着することは迷いであるかもしれず、死を厭(いと)うことは旅人が帰るべき故郷を忘れたようなものかも知れぬ。たとえば、かの美女麗姫(りき)は、艾(がい)の防人(さきもり)の娘だったが、捕らえられて晋(しん)に来た時は、泣いて泣いて泣き明かしたものだった。やがて後宮(こうきゅう)に迎えられ、王と臥床(ふしど)をともにし、ぜいたく三昧(ざんまい)に日を送るようになると、かえって昔泣いたことを後悔したということだ。してみると、死者にしても、かつて生に執着したことを、後になって後悔しているかも知れないのだ。
また、夢の中で歓楽をつくした者が、一夜明けると辛い現実に声をあげ泣き、夢の中で泣いていた者が、一夜明けるとけろりとして猟を楽しむこともある。夢を見ている時は、それは夢だと気づかない。夢の中でさらに夢占いをすることさえあるが、目覚めてはじめて夢だだったと気づくのだ。人生にしても長い夢のようなもの、真の悟りに到達した者だけが、その夢であることに気づくのだ。だがおろかにも人々は、目覚めた人間をもって自任し、小知をこれ見よがしにふりかざして、何が貴いの何が賤しいのと論じたてる。まったく、くだらん話しだ。
孔丘にせよ、おまえにせよ、みな夢を見ているのだ。いや夢だといっているこのわたしでさえ、例外なしに夢を見ているのだ。こういえば、さぞかし奇怪千万な意見ととられるだろう。わからないのが当たり前。この説を受け容れてくれる大聖人は、数十万年にひとり出るか出ないかというところなのだからな。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)ではないと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人の娘だったが、晋の国に捕らえられたその始めは、ぽろぽろと流れ落ちる涙で襟(えり)を濡らすほどだったというのに、その王の宮殿に行きつき、王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及び、すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。
そうして死んでいった者(彼女)が、その始めの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
夢の中で、酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、
夢の中で、大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。
あてもなく進行する夢の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。
夢の中で、また夢占いをしていたりもする。
だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるものだ。
さらに言えば、大いなる目覚めもある。
目覚めてはじめて大きな夢を見ていたことを知ることができるものだ。
<愚者(鏡のような無我な心をもつ者)>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、人知れず内部から少しずつあたかも(滋養物を) 竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。
(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に相当する滋養物)なるものが、それぞれもとからあるからだ。
丘(孔子)もお前もみな夢の中だ。
予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。
このようなことをこういうふうに言える。
その名は<弔詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。
長い時を経た後、一たび大いなる聖なるものと遇し(出会ってそっくりに歩み)、これ(聖なるものの実態)がどういうものか紐解かれることを知った者は、これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことになるだろう。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
|
|
|
コメント(25)
>>[1]
ここで展開されている夢と目覚めは、単に逆転の発想などというものではないと思っています。ましてや敗北者を慰めるためでもありません。その理由はゆっくりと話を紐解きながら説明していきたいと思っています。
生きているということは、必ず死ぬということですよね。一大イベントです。
でも、生きていけるのは日々小さなところで古い物質が死に、新しいものが生まれるということによって、成り立っているものです。幾多の小さな生死を繰り返しているのです。
そんな生死を繰り返す「生」の中で、人間は何のために生きているのでしょうね?
ゆうさんは人間は今生きている一代限りの存在だと思っていますか?
それとも、人間は転生(生まれ変わり)する存在だと思っていますか?
人間は、肉体が主役で、意識や心や魂のようなものは、この生の副産物のようなものだと考えますか?
ここで展開されている夢と目覚めは、単に逆転の発想などというものではないと思っています。ましてや敗北者を慰めるためでもありません。その理由はゆっくりと話を紐解きながら説明していきたいと思っています。
生きているということは、必ず死ぬということですよね。一大イベントです。
でも、生きていけるのは日々小さなところで古い物質が死に、新しいものが生まれるということによって、成り立っているものです。幾多の小さな生死を繰り返しているのです。
そんな生死を繰り返す「生」の中で、人間は何のために生きているのでしょうね?
ゆうさんは人間は今生きている一代限りの存在だと思っていますか?
それとも、人間は転生(生まれ変わり)する存在だと思っていますか?
人間は、肉体が主役で、意識や心や魂のようなものは、この生の副産物のようなものだと考えますか?
>>[2]
>ここで展開されている夢と目覚めは、単に逆転の発想などというものではないと思っています。ましてや敗北者を慰めるためでもありません。その理由はゆっくりと話を紐解きながら説明していきたいと思っています。
分かりました。
>生きているということは、必ず死ぬということですよね。一大イベントです。
>でも、生きていけるのは日々小さなところで古い物質が死に、新しいものが生まれるということによって、成り立っているものです。幾多の小さな生死を繰り返しているのです。
>そんな生死を繰り返す「生」の中で、人間は何のために生きているのでしょうね?
一般の人にとっては何のためかは分かりませんが、私の場合は、生まれた以上は史上一番スゲエことをやってやるゾ!ということでした。まあそれは挫折したのですが。ですから今の私にとっては、人間は何のために生きているのかは分かりません。
>ゆうさんは人間は今生きている一代限りの存在だと思っていますか?
>それとも、人間は転生(生まれ変わり)する存在だと思っていますか?
はっきりとは分かりません。しかし私は「生物は死後モノとなり、モノである間は将来に向かって生物に生まれ変わるまでタイムスリップする」という仮説を考え出しました。
>人間は、肉体が主役で、意識や心や魂のようなものは、この生の副産物のようなものだと考えますか?
意識や心や魂のようなものが生の主役だと思っています。
>ここで展開されている夢と目覚めは、単に逆転の発想などというものではないと思っています。ましてや敗北者を慰めるためでもありません。その理由はゆっくりと話を紐解きながら説明していきたいと思っています。
分かりました。
>生きているということは、必ず死ぬということですよね。一大イベントです。
>でも、生きていけるのは日々小さなところで古い物質が死に、新しいものが生まれるということによって、成り立っているものです。幾多の小さな生死を繰り返しているのです。
>そんな生死を繰り返す「生」の中で、人間は何のために生きているのでしょうね?
一般の人にとっては何のためかは分かりませんが、私の場合は、生まれた以上は史上一番スゲエことをやってやるゾ!ということでした。まあそれは挫折したのですが。ですから今の私にとっては、人間は何のために生きているのかは分かりません。
>ゆうさんは人間は今生きている一代限りの存在だと思っていますか?
>それとも、人間は転生(生まれ変わり)する存在だと思っていますか?
はっきりとは分かりません。しかし私は「生物は死後モノとなり、モノである間は将来に向かって生物に生まれ変わるまでタイムスリップする」という仮説を考え出しました。
>人間は、肉体が主役で、意識や心や魂のようなものは、この生の副産物のようなものだと考えますか?
意識や心や魂のようなものが生の主役だと思っています。
>>[3]
>私の場合は、生まれた以上は史上一番スゲエことをやってやるゾ!ということでした。まあそれは挫折したのですが。ですから今の私にとっては、人間は何のために生きているのかは分かりません。
このテーマは簡単には言いつくすことはできないところがあると思いますが、唯一言えることがあるとすれば、生きている意味は、なにかを「やる」ことが主眼にあるのではなく、なにがしかの存在に「なる」(バイブレーションのことで肩書のことではない)ことが主眼となって、様々なことを「やる」ことが付随するのではないかと私は考えます。
>私は「生物は死後モノとなり、モノである間は将来に向かって生物に生まれ変わるまでタイムスリップする」という仮説を考え出しました。
モノというのは非生物のことでしょうから、「輪廻転生」とはちょっと違う独自の考えなのですね。
私は人間は人間に生まれ変わる(転生)と思っています。死ぬときのあり方(存在)の波長で次の生が決まるのだと思っています。だから、いかに死んでいくかも問題になると思っています。
荘子の場合、そのことに明らかに言及していることはありませんが、生死を越えた話や、万歳までの話をしていることから、転生を前提にしているのではないかと推察しています。
>意識や心や魂のようなものが生の主役だと思っています。
肉体至上主義でなければ、『荘子』もまた興味深く読めるかもしれませんよ。
通説とはちょっと違う解釈を交えて、解説してみますね。
>私の場合は、生まれた以上は史上一番スゲエことをやってやるゾ!ということでした。まあそれは挫折したのですが。ですから今の私にとっては、人間は何のために生きているのかは分かりません。
このテーマは簡単には言いつくすことはできないところがあると思いますが、唯一言えることがあるとすれば、生きている意味は、なにかを「やる」ことが主眼にあるのではなく、なにがしかの存在に「なる」(バイブレーションのことで肩書のことではない)ことが主眼となって、様々なことを「やる」ことが付随するのではないかと私は考えます。
>私は「生物は死後モノとなり、モノである間は将来に向かって生物に生まれ変わるまでタイムスリップする」という仮説を考え出しました。
モノというのは非生物のことでしょうから、「輪廻転生」とはちょっと違う独自の考えなのですね。
私は人間は人間に生まれ変わる(転生)と思っています。死ぬときのあり方(存在)の波長で次の生が決まるのだと思っています。だから、いかに死んでいくかも問題になると思っています。
荘子の場合、そのことに明らかに言及していることはありませんが、生死を越えた話や、万歳までの話をしていることから、転生を前提にしているのではないかと推察しています。
>意識や心や魂のようなものが生の主役だと思っています。
肉体至上主義でなければ、『荘子』もまた興味深く読めるかもしれませんよ。
通説とはちょっと違う解釈を交えて、解説してみますね。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 予惡乎知説生之非惑邪 ┃【予(われ)いずくんぞ生を説くことの惑にあらざるを知
┗━━━━━━━━━━━━━┛らんや。】
生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)ではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。
…………………………………………………………………………………………………………
*【説】は「言+兌(ときはなす⇒人の着物をときはなすこと)」で、「いわれや理屈など
をときあかした意見、主張」のこと。※「よろこぶ」の意は、「悦」との通用。
*【惑】は「心+或(一区域を武器で守る)」で「心が狭いわくに囲まれること」。
◆通説では、【予悪乎知説生之非惑邪】は「生を喜ぶことが惑い〔であるかも知れない、そ
う〕ではないとはわしには決められない。」としています。
◇【説】は「悦」を通用させたものではなく、「言葉で説き明すこと」という本来の字義で
そのまま「説くこと」としました。【惑】は「迷い」といったニュアンスではなく、原義
の「心が狭い枠で囲まれること」と解釈すると納得がいきます。「生」におけるしがらみ
を「言葉で説くこと」で解放しようとすることが、意図とは違った形で、反対に「心」に
おいては「狭い枠で囲まれること」になるという皮肉な現実となってはいないと断言でき
るかどうか、どうしてわたしにわかるだろうかと反語的に反問しているようです。
断定していなころがミソかもしれません。
よって【予悪乎知説生之非惑邪】は「生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)
ではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。」とし
ました。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 予惡乎知惡死之非弱喪 ┃【予いずくんぞ死を悪(にく)むことの弱を喪いて
┃ 而不知帰者邪 ┃ 帰るを知らざる者にあらざるを知らんや。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。
…………………………………………………………………………………………………………
*【弱】は「〔弓+彡〕×2」で、もとは「模様や飾りのついた柔らかい弓」。
*【喪】は「哭(なく)+口×2+亡(なくなる)」で、「ばらばらに離散する」意を含み
「死人を送って口々に泣くこと」。⇒「うしなう」。
*【帰(歸)】は、もと「〔阜の上部〕(土盛りの堆積)+帚(ほうき/清め)」。のちに「止
(あし)」が加えられたもので、「あちこち回ったすえ、落ち着き場所(定位置)にもどる」
ことを表します。
◆通説では、【予悪乎知悪死之非弱喪而不知帰者邪】は「死を憎むことが、幼いころに故郷
を離れて帰ることを忘れた者と同じで〔あるかも知れない、そうで〕ないとは、わしには
決められない。」としています。【弱】を幼少と解釈しています。
◇【弱喪】は、「(心の)弱(柔らかな弾力性)を喪失して」と考えられ、【不知帰】の「帰る
ことを知らない」とは、以前にも出てきた意味と同様で、物理的な場所(故郷)ではなく、
「本来あるべき心の落ち着き場所に帰ってくることを知らない」という意味でしょう。
よって生きている間のことでもあり、また生まれたところ(=死)に帰るともとれます。
【予悪乎知悪死之非弱喪而不知帰者邪】で、「死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪
われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと(言い切れるかど
うか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。」と言っているととらえました。
┃▼ 予惡乎知説生之非惑邪 ┃【予(われ)いずくんぞ生を説くことの惑にあらざるを知
┗━━━━━━━━━━━━━┛らんや。】
生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)ではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。
…………………………………………………………………………………………………………
*【説】は「言+兌(ときはなす⇒人の着物をときはなすこと)」で、「いわれや理屈など
をときあかした意見、主張」のこと。※「よろこぶ」の意は、「悦」との通用。
*【惑】は「心+或(一区域を武器で守る)」で「心が狭いわくに囲まれること」。
◆通説では、【予悪乎知説生之非惑邪】は「生を喜ぶことが惑い〔であるかも知れない、そ
う〕ではないとはわしには決められない。」としています。
◇【説】は「悦」を通用させたものではなく、「言葉で説き明すこと」という本来の字義で
そのまま「説くこと」としました。【惑】は「迷い」といったニュアンスではなく、原義
の「心が狭い枠で囲まれること」と解釈すると納得がいきます。「生」におけるしがらみ
を「言葉で説くこと」で解放しようとすることが、意図とは違った形で、反対に「心」に
おいては「狭い枠で囲まれること」になるという皮肉な現実となってはいないと断言でき
るかどうか、どうしてわたしにわかるだろうかと反語的に反問しているようです。
断定していなころがミソかもしれません。
よって【予悪乎知説生之非惑邪】は「生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)
ではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。」とし
ました。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 予惡乎知惡死之非弱喪 ┃【予いずくんぞ死を悪(にく)むことの弱を喪いて
┃ 而不知帰者邪 ┃ 帰るを知らざる者にあらざるを知らんや。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。
…………………………………………………………………………………………………………
*【弱】は「〔弓+彡〕×2」で、もとは「模様や飾りのついた柔らかい弓」。
*【喪】は「哭(なく)+口×2+亡(なくなる)」で、「ばらばらに離散する」意を含み
「死人を送って口々に泣くこと」。⇒「うしなう」。
*【帰(歸)】は、もと「〔阜の上部〕(土盛りの堆積)+帚(ほうき/清め)」。のちに「止
(あし)」が加えられたもので、「あちこち回ったすえ、落ち着き場所(定位置)にもどる」
ことを表します。
◆通説では、【予悪乎知悪死之非弱喪而不知帰者邪】は「死を憎むことが、幼いころに故郷
を離れて帰ることを忘れた者と同じで〔あるかも知れない、そうで〕ないとは、わしには
決められない。」としています。【弱】を幼少と解釈しています。
◇【弱喪】は、「(心の)弱(柔らかな弾力性)を喪失して」と考えられ、【不知帰】の「帰る
ことを知らない」とは、以前にも出てきた意味と同様で、物理的な場所(故郷)ではなく、
「本来あるべき心の落ち着き場所に帰ってくることを知らない」という意味でしょう。
よって生きている間のことでもあり、また生まれたところ(=死)に帰るともとれます。
【予悪乎知悪死之非弱喪而不知帰者邪】で、「死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪
われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと(言い切れるかど
うか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。」と言っているととらえました。
●通説では、次のようになっています。
生を喜ぶことが惑い〔であるかも知れない、そう〕ではないとはわしには決められない。
死を憎むことが、幼いころに故郷を離れて帰ることを忘れた者と同じで〔あるかも知れない、そうで〕ないかもとは、わしには決められない。
〇新解釈では、次のようになります。
生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)ではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。
>@ ⊃彡
⊃彡
【予惡乎知説生之非惑邪】【予いずくんぞ生を説くことの惑にあらざるを知らんや。】
〔生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)ではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。〕
──しばらくすると、丘のほうから山林に向かって、小さな旋風がやってきました。老木の太い幹のウロからは、「クルクル」とも「ホロホロ」とも聞こえるような、そんな歌声を伴いながら、続く話がこぼれてきました。
「お前さんに限らず、あの先生をはじめ、丘にいるような者たちは皆、口々に<生>を説きたがるものだ。<生きている意義はこれこれだ><生きているからいろんなことを知ることができる><生きているから成長できる><生きているから様々な活動ができる><生きているから楽しめる><生きているから苦しみを抱えることになる>などなど、そうやって、<生>の中にだけに焦点を合わせてあれこれ説き始めるものだ。
だがな、そうやって<生>を説き明かすことによって、外的には活動が盛んになるかも知れないが、内的には次第に<こう生きるべきだ><ああ生きなくてはならない><生きている証に何かを成し遂げなくてはいけない>など、まさに生きる者の<心を狭いわくで縛り付けていくこと>になってはいないと言い切れるかどうか、わかったものではないぞ。」
【予惡乎知惡死之非弱喪而不知帰者邪】【予いずくんぞ死を悪(にく)むことの弱を喪いて、帰るを知らざる者にあらざるを知らんや。】
〔死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。〕
──「<生>を受けたものは必ず<死>が訪れる。だが誰もが、<死ぬのはいやだ><死ぬのは怖い><死の時のことなど考えたくもない>などと<死>を忌み嫌うものだ。だから、<死>の足音が聞こえ始めても、<いかに死んでいくか>に心を馳せるようなことはしないものだ。かたくなに<生>にしがみつくかのように<死>から気をそらすようにし、自然の流れに逆らい続けようとするものだ。そのため自然に元に戻ろうとする<弾力性を喪う>ことになるのだ。そうなると常に何かをすることによって気をまぎらわせていないと落ち着かなくなるのだ。<帰るところ>とは、<心(気)が落ち着くところ>だが、それがどこにあるのか迷うだけになってしまうかもしれないな。
ある人が生まれ変わりがあるものとして、次のような話をしていた。死に際のバイブレーションによって、次の生がどこから始まるのかが決まるのだ、と。悲しみにひたったまま終われば、悲しみの生から始まる。怒りに満ちたまま終われば、怒りの生から始まる。安らかに逝けば、安らかな生から始まる。感謝に満ちて逝けば、やさしさに満ちた生から始まる、と。だから<いかに死んでいくか>が重要になるのだ、と。
生きている限り、何かを<すること(doing)>が問題となる。だが、<死>を境にしてそれは持っていけないものだ。だが、存在(バイブレーション)として<あること(being)>は<死>を境にしても継続しているものかもしれない。もしそうなら、生きている間に<すること(doing)>を通して、どれだけ<あること(being)>を定着させたかによって<心の落ち着き場所>を見出すことができるかもしれないし、そうでないかもしれないが、それに関して私はどちらとも言えない。
<死>を厭うことは、死に際の自然に起こるバイブレーション…つまり、やわらかな弾力性による振動を喪うことになるのだ。そうなると死にゆく者の心が落ち着ける振動に帰ってくることができなくなると言えるかもしれないし、そうでないかもしれないし、それ以上のことはわたしの知ったことではない。」
生を喜ぶことが惑い〔であるかも知れない、そう〕ではないとはわしには決められない。
死を憎むことが、幼いころに故郷を離れて帰ることを忘れた者と同じで〔あるかも知れない、そうで〕ないかもとは、わしには決められない。
〇新解釈では、次のようになります。
生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)ではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。
>@
【予惡乎知説生之非惑邪】【予いずくんぞ生を説くことの惑にあらざるを知らんや。】
〔生を説くことは、惑(心が狭い枠で囲まれること)ではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。〕
──しばらくすると、丘のほうから山林に向かって、小さな旋風がやってきました。老木の太い幹のウロからは、「クルクル」とも「ホロホロ」とも聞こえるような、そんな歌声を伴いながら、続く話がこぼれてきました。
「お前さんに限らず、あの先生をはじめ、丘にいるような者たちは皆、口々に<生>を説きたがるものだ。<生きている意義はこれこれだ><生きているからいろんなことを知ることができる><生きているから成長できる><生きているから様々な活動ができる><生きているから楽しめる><生きているから苦しみを抱えることになる>などなど、そうやって、<生>の中にだけに焦点を合わせてあれこれ説き始めるものだ。
だがな、そうやって<生>を説き明かすことによって、外的には活動が盛んになるかも知れないが、内的には次第に<こう生きるべきだ><ああ生きなくてはならない><生きている証に何かを成し遂げなくてはいけない>など、まさに生きる者の<心を狭いわくで縛り付けていくこと>になってはいないと言い切れるかどうか、わかったものではないぞ。」
【予惡乎知惡死之非弱喪而不知帰者邪】【予いずくんぞ死を悪(にく)むことの弱を喪いて、帰るを知らざる者にあらざるを知らんや。】
〔死を厭うことは、弱(柔らかな弾力性)が喪われ、(心の落ち着き場所に)帰ることを知らないでいることではないと(言い切れるかどうか)、予(わたし)がどうしてそれを知れるだろうか。〕
──「<生>を受けたものは必ず<死>が訪れる。だが誰もが、<死ぬのはいやだ><死ぬのは怖い><死の時のことなど考えたくもない>などと<死>を忌み嫌うものだ。だから、<死>の足音が聞こえ始めても、<いかに死んでいくか>に心を馳せるようなことはしないものだ。かたくなに<生>にしがみつくかのように<死>から気をそらすようにし、自然の流れに逆らい続けようとするものだ。そのため自然に元に戻ろうとする<弾力性を喪う>ことになるのだ。そうなると常に何かをすることによって気をまぎらわせていないと落ち着かなくなるのだ。<帰るところ>とは、<心(気)が落ち着くところ>だが、それがどこにあるのか迷うだけになってしまうかもしれないな。
ある人が生まれ変わりがあるものとして、次のような話をしていた。死に際のバイブレーションによって、次の生がどこから始まるのかが決まるのだ、と。悲しみにひたったまま終われば、悲しみの生から始まる。怒りに満ちたまま終われば、怒りの生から始まる。安らかに逝けば、安らかな生から始まる。感謝に満ちて逝けば、やさしさに満ちた生から始まる、と。だから<いかに死んでいくか>が重要になるのだ、と。
生きている限り、何かを<すること(doing)>が問題となる。だが、<死>を境にしてそれは持っていけないものだ。だが、存在(バイブレーション)として<あること(being)>は<死>を境にしても継続しているものかもしれない。もしそうなら、生きている間に<すること(doing)>を通して、どれだけ<あること(being)>を定着させたかによって<心の落ち着き場所>を見出すことができるかもしれないし、そうでないかもしれないが、それに関して私はどちらとも言えない。
<死>を厭うことは、死に際の自然に起こるバイブレーション…つまり、やわらかな弾力性による振動を喪うことになるのだ。そうなると死にゆく者の心が落ち着ける振動に帰ってくることができなくなると言えるかもしれないし、そうでないかもしれないし、それ以上のことはわたしの知ったことではない。」
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 麗之姫艾封人之子也 ┃【麗 (り)の 姫(き)は艾(がい)の封人の子なり。】
┃ 晋国之始得之也 ┃【晋国の始めてこれを得るや、】
┃ 涕泣沾襟 ┃【涕泣(ていきゅう)して襟(えり)を沾(うるお)せるも】
┗━━━━━━━━━━━━┛
麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人の娘だったが、
晋の国に捕らえられたその始めは、
ぽろぽろと流す涙で襟を濡らすほどだったというのに、
…………………………………………………………………………………………………………
*【艾】は前にも説明しましたが、「艸+乂(はさみでかりとること)」で、「よもぎ」「も
ぐさ」のことです。ちなみに動詞の意味には、「草や邪魔者をかりとる」「反乱や賊を平
らげて世の中を安らかにする」「やすんじる」「おさまる」などが含まれます。
*【封人】は「国境を守る役人」「防人」のこと。
■『春秋左氏伝』に「晋の献公が麗戎(りじゆう)国を攻めて麗姫を手に入れた」という
話があるようです。
◆【麗之姫艾封人之子也】は、通説では「麗姫(りき)は〔麗戎国の〕艾(がい)の地の国境
役人の娘だが、」としています。
◇【麗之姫】は、「麗姫(りき)」のことでしょうが、どうして【之】がはさまれているの
かは不明です。【艾】は、単に地名と考えられているようですが、以前に「蓬艾」とし
て登場した時の示唆と同様の、「素朴に自然に沿った生活をしているところ」という意
味が込められているのかもしれません。
【麗之姫艾封人之子也】は通説と大差なく「麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人
の娘だったが、」としました。
*【涕】は「水+弟(上→下につるの巻いた棒の低い所)」で、「なみだが上から下へ、
低くたれおちること」。
*【泣】は「水+粒(つぶ)の略体」。
*【沾】は「水+占(しめる)」で、「ひと所に定着する」。
*【襟】は「衣+禁(ふさぐ)」で、「えり」の意の他「胸のうち」も表します。
◆通説では、【晋国之始得之也 涕泣沾襟】は、「始めて晋の国につれていかれようとし
たきは、さめざめと泣き悲しんで涙で襟を濡らすほどであったのに、」としています。
◇【晋国之始得之也 涕泣沾襟】は、通説と大差なく、「晋の国に捕らえられたその始め
は、ぽろぽろと流す涙で襟を濡らすほどだったというのに、」としました。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 及其至於王所 ┃【その王の所に至り、】
┃ 与王同筐牀 ┃【王と筐牀(きょうしょう)を同じくし、】
┃ 食芻豢 ┃【芻豢(すうけん)を食らうに及びて、】
┃ 而後悔其泣也 ┃【而る後にその泣きしを悔いたり。】
┗━━━━━━━━━┛
その王の宮殿に行きつき、
王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、
(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及び、
すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。
…………………………………………………………………………………………………………
*【筐】は「竹+匡(中を空にした四角いわく)」で、「寝台」「竹かご」の意。
*【牀】は「木+爿(細長い台を縦に描いたもの)」で、「寝台」「台」「床」の意。
*【芻豢】は、前にも登場したように「家畜」のこととされています。
「刈り取った草(⇒草食動物)」と、「囲いの中で飼われる豚」。
◆【及其至於王所 与王同筐牀食芻豢 而後悔其泣也】は、通説では、「さて王の宮殿に
行きついて王と起居を共にし、牛や豚の美食を口にするようになってからは、はじめに
泣いたことを後悔したという。」としています。
◇【牀】だけで「寝台」の意味があるのにわざわざ【筐】の字を加えているところから、
その漢字のもっている「竹かごのような四角いわくの中の生活」というイメージがこめ
られているように思います。贅沢三昧で心の充実ではなく、肉体の快楽が優先するよう
になったのでしょう。
【及其至於王所 与王同筐牀食芻豢 而後悔其泣也】は、「その王の宮殿に行きつき、
王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及
び、すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。」としました。
┃▼ 麗之姫艾封人之子也 ┃【麗 (り)の 姫(き)は艾(がい)の封人の子なり。】
┃ 晋国之始得之也 ┃【晋国の始めてこれを得るや、】
┃ 涕泣沾襟 ┃【涕泣(ていきゅう)して襟(えり)を沾(うるお)せるも】
┗━━━━━━━━━━━━┛
麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人の娘だったが、
晋の国に捕らえられたその始めは、
ぽろぽろと流す涙で襟を濡らすほどだったというのに、
…………………………………………………………………………………………………………
*【艾】は前にも説明しましたが、「艸+乂(はさみでかりとること)」で、「よもぎ」「も
ぐさ」のことです。ちなみに動詞の意味には、「草や邪魔者をかりとる」「反乱や賊を平
らげて世の中を安らかにする」「やすんじる」「おさまる」などが含まれます。
*【封人】は「国境を守る役人」「防人」のこと。
■『春秋左氏伝』に「晋の献公が麗戎(りじゆう)国を攻めて麗姫を手に入れた」という
話があるようです。
◆【麗之姫艾封人之子也】は、通説では「麗姫(りき)は〔麗戎国の〕艾(がい)の地の国境
役人の娘だが、」としています。
◇【麗之姫】は、「麗姫(りき)」のことでしょうが、どうして【之】がはさまれているの
かは不明です。【艾】は、単に地名と考えられているようですが、以前に「蓬艾」とし
て登場した時の示唆と同様の、「素朴に自然に沿った生活をしているところ」という意
味が込められているのかもしれません。
【麗之姫艾封人之子也】は通説と大差なく「麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人
の娘だったが、」としました。
*【涕】は「水+弟(上→下につるの巻いた棒の低い所)」で、「なみだが上から下へ、
低くたれおちること」。
*【泣】は「水+粒(つぶ)の略体」。
*【沾】は「水+占(しめる)」で、「ひと所に定着する」。
*【襟】は「衣+禁(ふさぐ)」で、「えり」の意の他「胸のうち」も表します。
◆通説では、【晋国之始得之也 涕泣沾襟】は、「始めて晋の国につれていかれようとし
たきは、さめざめと泣き悲しんで涙で襟を濡らすほどであったのに、」としています。
◇【晋国之始得之也 涕泣沾襟】は、通説と大差なく、「晋の国に捕らえられたその始め
は、ぽろぽろと流す涙で襟を濡らすほどだったというのに、」としました。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 及其至於王所 ┃【その王の所に至り、】
┃ 与王同筐牀 ┃【王と筐牀(きょうしょう)を同じくし、】
┃ 食芻豢 ┃【芻豢(すうけん)を食らうに及びて、】
┃ 而後悔其泣也 ┃【而る後にその泣きしを悔いたり。】
┗━━━━━━━━━┛
その王の宮殿に行きつき、
王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、
(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及び、
すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。
…………………………………………………………………………………………………………
*【筐】は「竹+匡(中を空にした四角いわく)」で、「寝台」「竹かご」の意。
*【牀】は「木+爿(細長い台を縦に描いたもの)」で、「寝台」「台」「床」の意。
*【芻豢】は、前にも登場したように「家畜」のこととされています。
「刈り取った草(⇒草食動物)」と、「囲いの中で飼われる豚」。
◆【及其至於王所 与王同筐牀食芻豢 而後悔其泣也】は、通説では、「さて王の宮殿に
行きついて王と起居を共にし、牛や豚の美食を口にするようになってからは、はじめに
泣いたことを後悔したという。」としています。
◇【牀】だけで「寝台」の意味があるのにわざわざ【筐】の字を加えているところから、
その漢字のもっている「竹かごのような四角いわくの中の生活」というイメージがこめ
られているように思います。贅沢三昧で心の充実ではなく、肉体の快楽が優先するよう
になったのでしょう。
【及其至於王所 与王同筐牀食芻豢 而後悔其泣也】は、「その王の宮殿に行きつき、
王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及
び、すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。」としました。
●通説では、次のようになっています。
麗姫(りき)は〔麗戎国の〕艾(がい)の地の国境役人の娘だが、始めて晋の国につれていかれようとしたきは、さめざめと泣き悲しんで涙で襟を濡らすほどであったのに、さて王の宮殿に行きついて王と起居を共にし、牛や豚の美食を口にするようになってからは、はじめに泣いたことを後悔したという。
〇新解釈では、次のようになります。
麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人の娘だったが、晋の国に捕らえられたその始めは、ぽろぽろと流す涙で襟を濡らすほどだったというのに、その王の宮殿に行きつき、王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及び、すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。
>@ ⊃彡
⊃彡
【麗之姫艾封人之子也】【麗 (り)の 姫(き)は艾(がい)の封人の子なり。】
【晋国之始得之也】【晋国の始めてこれを得るや、】
【涕泣沾襟】【涕泣(ていきゅう)して襟(えり)を沾(うるお)せるも】
〔麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人の娘だったが、晋の国に捕らえられたその始めは、ぽろぽろと流す涙で襟を濡らすほどだったというのに、〕
──「なあ、カササギくん。もしお前さんが、誰か知らない者に捕まえられて、見知らぬ土地に連れていかれ、カゴの中に閉じ込められたなら、その始めにはショックで騒ぎ暴れて逃げようとしないか? 麗姫のように涙を流すことはないかもしれないが、悲痛な思いで、鳴き叫ぶかもしれないね。」
カササギは何も言いませんでしたが、うなずいて老木の話を聞いていました。
【及其至於王所】【その王の所に至り、】
【与王同筐牀】【王と筐牀(きょうしょう)を同じくし、】
【食芻豢】【芻豢(すうけん)を食らうに及びて、】
【而後悔其泣也】【而る後にその泣きしを悔いたり。】
〔その王の宮殿に行きつき、王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及び、すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。〕
──「だがな、もしその飼い主が、毎日お前さんの美しい姿を愛でてくれ、お前さんの食べていた木の実や昆虫よりももっとおいしい、食べたこともないご馳走を、毎日たっぷりと準備してくれるとしたらどうだろう? もう自分で、死なないようにと必死で自分で餌を探し求めて飛び続ける必要がなくなるのだ。また、雌のカササギと一緒に暮らすことになって、ヒナが生まれたとしても、カラスなどの天敵に襲われる心配もいらなくなるというものだ。安全なねぐらを約束され、ぐっすりと眠りにつけ季節ごとの移動や準備に忙しくすることもないような、そういった生活は慣れてしまえば反対に極楽に感じるようになって、はじめに騒いだことを後悔するのかもしれないな。麗姫も泣いたことを後悔したというのもありえることだ。」
∈∋
麗姫(りき)は〔麗戎国の〕艾(がい)の地の国境役人の娘だが、始めて晋の国につれていかれようとしたきは、さめざめと泣き悲しんで涙で襟を濡らすほどであったのに、さて王の宮殿に行きついて王と起居を共にし、牛や豚の美食を口にするようになってからは、はじめに泣いたことを後悔したという。
〇新解釈では、次のようになります。
麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人の娘だったが、晋の国に捕らえられたその始めは、ぽろぽろと流す涙で襟を濡らすほどだったというのに、その王の宮殿に行きつき、王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及び、すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。
>@
【麗之姫艾封人之子也】【麗 (り)の 姫(き)は艾(がい)の封人の子なり。】
【晋国之始得之也】【晋国の始めてこれを得るや、】
【涕泣沾襟】【涕泣(ていきゅう)して襟(えり)を沾(うるお)せるも】
〔麗姫(りき)は、艾(がい)の国境を守る役人の娘だったが、晋の国に捕らえられたその始めは、ぽろぽろと流す涙で襟を濡らすほどだったというのに、〕
──「なあ、カササギくん。もしお前さんが、誰か知らない者に捕まえられて、見知らぬ土地に連れていかれ、カゴの中に閉じ込められたなら、その始めにはショックで騒ぎ暴れて逃げようとしないか? 麗姫のように涙を流すことはないかもしれないが、悲痛な思いで、鳴き叫ぶかもしれないね。」
カササギは何も言いませんでしたが、うなずいて老木の話を聞いていました。
【及其至於王所】【その王の所に至り、】
【与王同筐牀】【王と筐牀(きょうしょう)を同じくし、】
【食芻豢】【芻豢(すうけん)を食らうに及びて、】
【而後悔其泣也】【而る後にその泣きしを悔いたり。】
〔その王の宮殿に行きつき、王と(四角いわくの中で)寝床を共にして、(囲まれた中で飼育される)家畜を食べるに及び、すっかりその後には、かえって泣いたことを後悔したという。〕
──「だがな、もしその飼い主が、毎日お前さんの美しい姿を愛でてくれ、お前さんの食べていた木の実や昆虫よりももっとおいしい、食べたこともないご馳走を、毎日たっぷりと準備してくれるとしたらどうだろう? もう自分で、死なないようにと必死で自分で餌を探し求めて飛び続ける必要がなくなるのだ。また、雌のカササギと一緒に暮らすことになって、ヒナが生まれたとしても、カラスなどの天敵に襲われる心配もいらなくなるというものだ。安全なねぐらを約束され、ぐっすりと眠りにつけ季節ごとの移動や準備に忙しくすることもないような、そういった生活は慣れてしまえば反対に極楽に感じるようになって、はじめに騒いだことを後悔するのかもしれないな。麗姫も泣いたことを後悔したというのもありえることだ。」
∈∋
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 予惡乎知夫死者 ┃【予いずくんぞ、かの死者の
┃ 不悔其始之蘄生 ┃ その始めの生を蘄(か)るに悔いざるを知らんや。】
┗━━━━━━━━━━┛
そうして死んでいった者(彼女)が、その始めの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
…………………………………………………………………………………………………………
*【蘄】は「艸+單+斤(きる)」で、「刈り取られた山芹」として使われる他は、「祈」
との通用として「もとめる」の意だとされています。
◆【予悪乎知夫死者不悔其始之蘄生也】は、通説では「あの死んだ人々も、その生きてい
たときに生を求めたことを後悔してい〔るかも知れない、そうで〕ないとは、わしには
決められない。」としています。
◇ここの【死者】は一般的な別の人々のことを指しているのではなく、【夫(かの)】という
指示代名詞がついていることからして、「麗姫」が【死者】になる時のことを指している
のではないかと思います。そして、その【始】とは、「艾での(責任ある自由な)生活」を
示し、【蘄生】でその「生き方」が、まるで「刈り取られた山ぜり」のごとく、「途中で
切断されて」、魂主体の生活ではなく、肉体主体の生活をしたことを、悔やんでいないと
言えるどうかは、わからないではないか‥と言っているのではないでしょうか。
【予悪乎知夫死者不悔其始之蘄生也】は、「そうして死んでいった者(彼女)が、その始め
の(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)が
それを知れるだろうか。」としました。
┃▼ 予惡乎知夫死者 ┃【予いずくんぞ、かの死者の
┃ 不悔其始之蘄生 ┃ その始めの生を蘄(か)るに悔いざるを知らんや。】
┗━━━━━━━━━━┛
そうして死んでいった者(彼女)が、その始めの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
…………………………………………………………………………………………………………
*【蘄】は「艸+單+斤(きる)」で、「刈り取られた山芹」として使われる他は、「祈」
との通用として「もとめる」の意だとされています。
◆【予悪乎知夫死者不悔其始之蘄生也】は、通説では「あの死んだ人々も、その生きてい
たときに生を求めたことを後悔してい〔るかも知れない、そうで〕ないとは、わしには
決められない。」としています。
◇ここの【死者】は一般的な別の人々のことを指しているのではなく、【夫(かの)】という
指示代名詞がついていることからして、「麗姫」が【死者】になる時のことを指している
のではないかと思います。そして、その【始】とは、「艾での(責任ある自由な)生活」を
示し、【蘄生】でその「生き方」が、まるで「刈り取られた山ぜり」のごとく、「途中で
切断されて」、魂主体の生活ではなく、肉体主体の生活をしたことを、悔やんでいないと
言えるどうかは、わからないではないか‥と言っているのではないでしょうか。
【予悪乎知夫死者不悔其始之蘄生也】は、「そうして死んでいった者(彼女)が、その始め
の(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)が
それを知れるだろうか。」としました。
●通説では、次のようになっています。
あの死んだ人々も、その生きていたときに生を求めたことを後悔してい〔るかも知れない、そうで〕ないとは、わしには決められない。
〇新解釈では、次のようになります。
そうして死んでいった者(彼女)が、その始めの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
>@ ⊃彡
⊃彡
【予惡乎知夫死者】【予いずくんぞ、かの死者の
【不悔其始之蘄生】その始めの生を蘄(か)るに悔いざるを知らんや。】
〔そうして死んでいった者(彼女)が、その始めの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。〕
──老木の話は続きます。
「カササギくんよ、自由に生活していた時は、常に<死>と隣り合わせに生きていたと言えるかもしれないね。でもカゴの中で生活するようになったら、<死>のことなどすっかり忘れてしまう甘い誘惑があると言えるかもしれない。そこにある日突然、老いか病気のせいで<死>の予感、その足音が聞こえてきたならば、どう思うだろう。急に不安になるか恐ろしく感じるか、その影におびえるようになるかもしれないね。そう、カゴは<死>のことを一時忘れさせることはできても、<死>から逃れられないことに変わりがないからね。<死>の訪れを感じ始める時、やり残したことはなかったと思えるだろうか。ああしておけばよかったのにと後悔の念が湧き起こらないだろうか。封印されたかのように使えなくなってしまった翼で思いっきり風を切って飛べなくなったことを無念に思ったりしないだろうか。逃げ出すことをあきらめていたことを悔いはしないだろうか。かつてその命を天にあずけ、草や木々の生い茂る丘で、身の危険を感じつつも、たくましく暮らしていた時のことを、想い出しはしないだろうか。
そういったことを考え合わせると、麗姫も逃げ出して元の生活に戻ることもできたかもしれないが、そういう生き方を選択しなかったわけだが、死んでいく時、もとの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと言い切れるかどうか、だれにも分からないことだ。」
老木は西に傾く夕日に、長い影を落としていました。そうこうしているうちに、あたりはすっかり夕闇に包まれていました。鳥は、日が沈んでしまうとすぐに眠くなってしまうものです。古老の大樹に抱かれるようにして、カササギは古巣に帰ることもなく、知らぬまに心地よい眠りに誘われていました。
∈∋
あの死んだ人々も、その生きていたときに生を求めたことを後悔してい〔るかも知れない、そうで〕ないとは、わしには決められない。
〇新解釈では、次のようになります。
そうして死んでいった者(彼女)が、その始めの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。
>@
【予惡乎知夫死者】【予いずくんぞ、かの死者の
【不悔其始之蘄生】その始めの生を蘄(か)るに悔いざるを知らんや。】
〔そうして死んでいった者(彼女)が、その始めの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと、どうして予(わたし)がそれを知れるだろうか。〕
──老木の話は続きます。
「カササギくんよ、自由に生活していた時は、常に<死>と隣り合わせに生きていたと言えるかもしれないね。でもカゴの中で生活するようになったら、<死>のことなどすっかり忘れてしまう甘い誘惑があると言えるかもしれない。そこにある日突然、老いか病気のせいで<死>の予感、その足音が聞こえてきたならば、どう思うだろう。急に不安になるか恐ろしく感じるか、その影におびえるようになるかもしれないね。そう、カゴは<死>のことを一時忘れさせることはできても、<死>から逃れられないことに変わりがないからね。<死>の訪れを感じ始める時、やり残したことはなかったと思えるだろうか。ああしておけばよかったのにと後悔の念が湧き起こらないだろうか。封印されたかのように使えなくなってしまった翼で思いっきり風を切って飛べなくなったことを無念に思ったりしないだろうか。逃げ出すことをあきらめていたことを悔いはしないだろうか。かつてその命を天にあずけ、草や木々の生い茂る丘で、身の危険を感じつつも、たくましく暮らしていた時のことを、想い出しはしないだろうか。
そういったことを考え合わせると、麗姫も逃げ出して元の生活に戻ることもできたかもしれないが、そういう生き方を選択しなかったわけだが、死んでいく時、もとの(艾での)生き方を断絶してしまったことを悔やんでなかったと言い切れるかどうか、だれにも分からないことだ。」
老木は西に傾く夕日に、長い影を落としていました。そうこうしているうちに、あたりはすっかり夕闇に包まれていました。鳥は、日が沈んでしまうとすぐに眠くなってしまうものです。古老の大樹に抱かれるようにして、カササギは古巣に帰ることもなく、知らぬまに心地よい眠りに誘われていました。
∈∋
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 夢飲酒者 旦而哭泣 ┃【夢に酒を飲む者は、旦にして哭泣(こくきゅう)し、
┃ 夢哭泣者 旦而田猟 ┃ 夢に哭泣する者は、旦にして田猟(でんりょう)す。
┗━━━━━━━━━━━━┛
夢の中で、酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、
夢の中で、大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。
…………………………………………………………………………………………………………
*【夢】は、「[蔑の上側](羊の赤くただれた目)+冖(おおい)+夕(つき)」で
「夜のやみにおおわれて、物が見えないこと」。
*【哭】は「口×2+犬」で、「大声でなくこと」。
*【旦】は「日+一印(地平線)」で、「太陽が地上にあらわれること」。
*【田猟】は「平地に人手を配して平らに押していくかりのこと」。
◆【夢飲酒者 旦而哭泣 夢哭泣者 旦而田猟】は、通説では「夢のなかで酒を飲んで楽
しんでいた者が、朝になると不幸な現実に泣き悲しみ、夢のなかで泣き悲しんでいた者
が、朝になると楽しく狩りに出かけるということがある。」としています。
◇【夢飲酒者 旦而哭泣 夢哭泣者 旦而田猟】は、通説と大差ありません。「夢の中で
酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、夢の中で
大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。」としました。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 方其夢也 ┃【方にして、その夢や、】
┃ 不知其夢也 ┃【その夢なることを知らず。】
┃ 夢之中又占其夢焉 ┃【夢の中で又その夢を占い、】
┃ 覺而後知其夢也 ┃【覚めて後にその夢なることを知る。】
┗━━━━━━━━━━━┛
あてもなく進行する夢の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。
夢の中で、また夢占いをしていたりもする。
だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるものだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【方】は、「左右に柄の張り出したすき」を描いた象形文字。いろいろな意味があります
が、「あてもなく出歩く」「どこまでも広がる」意もあります。
*【占】は、「卜(うらなう)+口(場所)」で「うらないによって、一つの物や場所を選
び決めること」。
*【覺(覚)】は「見+〔上部/両手+交差するさま+宀(いえ)/學の原字〕」で、(上部
の意味は「片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家」)「見聞きした刺激
が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること」。
◆通説では、【方其夢也 不知其夢也 夢之中又占其夢焉 覺而後知其夢也】の【方】の意
味は省略して訳していません。「夢を見ているときには、それが夢であることは分からず
夢のなかでまた夢占いをしたりして、目が覚めてからはじめてそれが夢であったことが
分かるのである。」としています。
◇【方】は「あてもなく進行する」という意と解釈しましたが、【方其夢也 不知其夢也
夢之中又占其夢焉 覺而後知其夢也】の大意は大差ありません。「あてもなく進行する夢
の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。夢の中で、また夢占いをし
ていたりもする。だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるもの
だ。」としました。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 且有大覺 ┃【且、大覚あり。】
┃ 而後知此其大夢焉 ┃【而る後此れその大夢なることを知る。】
┗━━━━━━━━━━━┛
さらに言えば、大いなる目覚めもある。
覚めてはじめて大きな夢を見ていたことがわかるものだ。
…………………………………………………………………………………………………………
◆【且有大覺 而後知此其大夢焉】は通説では「〔人生も同じことだ。〕本当の目覚めがあ
ってこそ、始めてこの人生が大きな一場の夢であることが分かるのだ。」としています。
◇通説と大差ありませんが、直訳して「さらに言えば、大いなる目覚めもある。目覚めて
はじめて大きな夢を見ていたことを知ることができるものだ。」としました。
┃▼ 夢飲酒者 旦而哭泣 ┃【夢に酒を飲む者は、旦にして哭泣(こくきゅう)し、
┃ 夢哭泣者 旦而田猟 ┃ 夢に哭泣する者は、旦にして田猟(でんりょう)す。
┗━━━━━━━━━━━━┛
夢の中で、酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、
夢の中で、大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。
…………………………………………………………………………………………………………
*【夢】は、「[蔑の上側](羊の赤くただれた目)+冖(おおい)+夕(つき)」で
「夜のやみにおおわれて、物が見えないこと」。
*【哭】は「口×2+犬」で、「大声でなくこと」。
*【旦】は「日+一印(地平線)」で、「太陽が地上にあらわれること」。
*【田猟】は「平地に人手を配して平らに押していくかりのこと」。
◆【夢飲酒者 旦而哭泣 夢哭泣者 旦而田猟】は、通説では「夢のなかで酒を飲んで楽
しんでいた者が、朝になると不幸な現実に泣き悲しみ、夢のなかで泣き悲しんでいた者
が、朝になると楽しく狩りに出かけるということがある。」としています。
◇【夢飲酒者 旦而哭泣 夢哭泣者 旦而田猟】は、通説と大差ありません。「夢の中で
酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、夢の中で
大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。」としました。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 方其夢也 ┃【方にして、その夢や、】
┃ 不知其夢也 ┃【その夢なることを知らず。】
┃ 夢之中又占其夢焉 ┃【夢の中で又その夢を占い、】
┃ 覺而後知其夢也 ┃【覚めて後にその夢なることを知る。】
┗━━━━━━━━━━━┛
あてもなく進行する夢の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。
夢の中で、また夢占いをしていたりもする。
だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるものだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【方】は、「左右に柄の張り出したすき」を描いた象形文字。いろいろな意味があります
が、「あてもなく出歩く」「どこまでも広がる」意もあります。
*【占】は、「卜(うらなう)+口(場所)」で「うらないによって、一つの物や場所を選
び決めること」。
*【覺(覚)】は「見+〔上部/両手+交差するさま+宀(いえ)/學の原字〕」で、(上部
の意味は「片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家」)「見聞きした刺激
が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること」。
◆通説では、【方其夢也 不知其夢也 夢之中又占其夢焉 覺而後知其夢也】の【方】の意
味は省略して訳していません。「夢を見ているときには、それが夢であることは分からず
夢のなかでまた夢占いをしたりして、目が覚めてからはじめてそれが夢であったことが
分かるのである。」としています。
◇【方】は「あてもなく進行する」という意と解釈しましたが、【方其夢也 不知其夢也
夢之中又占其夢焉 覺而後知其夢也】の大意は大差ありません。「あてもなく進行する夢
の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。夢の中で、また夢占いをし
ていたりもする。だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるもの
だ。」としました。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 且有大覺 ┃【且、大覚あり。】
┃ 而後知此其大夢焉 ┃【而る後此れその大夢なることを知る。】
┗━━━━━━━━━━━┛
さらに言えば、大いなる目覚めもある。
覚めてはじめて大きな夢を見ていたことがわかるものだ。
…………………………………………………………………………………………………………
◆【且有大覺 而後知此其大夢焉】は通説では「〔人生も同じことだ。〕本当の目覚めがあ
ってこそ、始めてこの人生が大きな一場の夢であることが分かるのだ。」としています。
◇通説と大差ありませんが、直訳して「さらに言えば、大いなる目覚めもある。目覚めて
はじめて大きな夢を見ていたことを知ることができるものだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
夢のなかで酒を飲んで楽しんでいた者が、朝になると不幸な現実に泣き悲しみ、夢の中で泣き悲しんでいた者が、朝になると楽しく狩りに出かけるということがある。夢を見ているときには、それが夢であることは分からず、夢のなかでまた夢占いをしたりして、目が覚めてからはじめてそれが夢であったことが分かるのである。〔人生も同じことだ。〕本当の目覚めがあってこそ、始めてこの人生が大きな一場の夢であることが分かるのだ。
〇新解釈では、次のようになります。
夢の中で、酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、夢の中で、大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。あてもなく進行する夢の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。夢の中で、また夢占いをしていたりもする。だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるものだ。さらに言えば、大いなる目覚めもある。目覚めてはじめて大きな夢を見ていたことを知ることができるものだ。
>@ ⊃彡
⊃彡
【夢飲酒者 旦而哭泣】【夢に酒を飲む者は、旦にして哭泣(こくきゅう)し、】
【夢哭泣者 旦而田猟】【夢に哭泣する者は、旦にして田猟(でんりょう)す。】
〔夢の中で、酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、夢の中で、大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。〕
──翌朝、やさしい陽射しと、風に揺れる木の葉の音とに、カササギは起こされました。「おはよう、カササギくん。ゆっくり休めたのだろうか? 朝方、なんだか泣いているような鳴き声が聞こえてきたのだが…。」老木はやさしく尋ねました。
それに対し、カササギはとっさに「朝食を取りにひとッ飛びしてきます。」とだけ言って、東に向かって飛んでいきました。しばらくすると舞い戻ってきたカササギは嬉々として「あ〜おいしかった」とご機嫌のようでした。
老木は「カササギくん、何か夢を見ていたのではないのかい?」と尋ねました。それに対し、カササギは少々ばつが悪そうに、ごまかし笑いをしながら「はい、そのとおりです。実は、夢の中では生まれたてのヒナになっていたのです。親兄弟が皆、遠くの方に飛び去り、空腹のままおいてきぼりにされて、どうしたらいいかわからずに、おもわず必死に鳴いてしまっていました。」と白状しました。
老木は言いました。「みんなそんなものだよ。夢の中で泣き悲しんでいる者が、朝には、狩りを楽しそうにしたりするものだよ。当然また逆のパターンもある。夢と現実は不思議な関係にあるものだ。」
【方其夢也 不知其夢也】【方にして、その夢や、その夢なることを知らず。】
【夢之中又占其夢焉】【夢の中で又その夢を占い、】
【覺而後知其夢也】【覚めて後にその夢なることを知る。】
〔あてもなく進行する夢の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。夢の中で、また夢占いをしていたりもする。だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるものだ。〕
──「あてもなく展開されていく夢の中にいる時は誰でも、まさにそれが<現実>だと思っているもので、夢の中だとは思ってもみない。そこでの泣いたり笑ったりは、実感そのものだからね。
その夢の中で、自分自身に自信がもてなくなったり、不安になったり、進む先に迷ったりすると、また夢占いをしたりして、人や棒に<おうかがい>を立てたりもする。<この夢は吉なのか凶なのか>とか、<この夢にどんな意味があるのか>とか、まったく意味のないことを真剣になってやっていることがあるものだ。
ところが、朝になって目覚めてはじめて<夢の中の自分>は<幻>で、<現実の自分>とは違うと気付くもんだよね。」
【且有大覺】【且、大覚あり。】
【而後知此其大夢焉】【而る後此れその大夢なることを知る。】
〔さらに言えば、大いなる目覚めもある。目覚めてはじめて大きな夢を見ていたことを知ることができるものだ。〕
──「さらに言えば、人生における<大いなる目覚め>があるということを聞いたことがあるだろう。<大いなる目覚め>とは、<覚醒>とか<悟り>とか呼ばれることがある。その境地に至ってはじめて、普通に目覚めて生活していると思っていることが、実は<大きな夢>だということをことを理解することになるのだ。
そのことを概念的には、もう既に「知ってる」と思っている人も少なくないだろうが、果たして、予想しているイメージと一致するかどうか、わかったものではないぞ。」
∈∋
夢のなかで酒を飲んで楽しんでいた者が、朝になると不幸な現実に泣き悲しみ、夢の中で泣き悲しんでいた者が、朝になると楽しく狩りに出かけるということがある。夢を見ているときには、それが夢であることは分からず、夢のなかでまた夢占いをしたりして、目が覚めてからはじめてそれが夢であったことが分かるのである。〔人生も同じことだ。〕本当の目覚めがあってこそ、始めてこの人生が大きな一場の夢であることが分かるのだ。
〇新解釈では、次のようになります。
夢の中で、酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、夢の中で、大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。あてもなく進行する夢の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。夢の中で、また夢占いをしていたりもする。だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるものだ。さらに言えば、大いなる目覚めもある。目覚めてはじめて大きな夢を見ていたことを知ることができるものだ。
>@
【夢飲酒者 旦而哭泣】【夢に酒を飲む者は、旦にして哭泣(こくきゅう)し、】
【夢哭泣者 旦而田猟】【夢に哭泣する者は、旦にして田猟(でんりょう)す。】
〔夢の中で、酒を飲んで(楽しんで)いた者が、朝には、(辛い出来事に)大声を上げて泣き、夢の中で、大声で泣いていた者が、朝には、(楽しく)狩りをしていることもある。〕
──翌朝、やさしい陽射しと、風に揺れる木の葉の音とに、カササギは起こされました。「おはよう、カササギくん。ゆっくり休めたのだろうか? 朝方、なんだか泣いているような鳴き声が聞こえてきたのだが…。」老木はやさしく尋ねました。
それに対し、カササギはとっさに「朝食を取りにひとッ飛びしてきます。」とだけ言って、東に向かって飛んでいきました。しばらくすると舞い戻ってきたカササギは嬉々として「あ〜おいしかった」とご機嫌のようでした。
老木は「カササギくん、何か夢を見ていたのではないのかい?」と尋ねました。それに対し、カササギは少々ばつが悪そうに、ごまかし笑いをしながら「はい、そのとおりです。実は、夢の中では生まれたてのヒナになっていたのです。親兄弟が皆、遠くの方に飛び去り、空腹のままおいてきぼりにされて、どうしたらいいかわからずに、おもわず必死に鳴いてしまっていました。」と白状しました。
老木は言いました。「みんなそんなものだよ。夢の中で泣き悲しんでいる者が、朝には、狩りを楽しそうにしたりするものだよ。当然また逆のパターンもある。夢と現実は不思議な関係にあるものだ。」
【方其夢也 不知其夢也】【方にして、その夢や、その夢なることを知らず。】
【夢之中又占其夢焉】【夢の中で又その夢を占い、】
【覺而後知其夢也】【覚めて後にその夢なることを知る。】
〔あてもなく進行する夢の中にいる時は、それが夢であることは知らずにいるものだ。夢の中で、また夢占いをしていたりもする。だが、目覚めてはじめてその後に、それが夢だと知ることができるものだ。〕
──「あてもなく展開されていく夢の中にいる時は誰でも、まさにそれが<現実>だと思っているもので、夢の中だとは思ってもみない。そこでの泣いたり笑ったりは、実感そのものだからね。
その夢の中で、自分自身に自信がもてなくなったり、不安になったり、進む先に迷ったりすると、また夢占いをしたりして、人や棒に<おうかがい>を立てたりもする。<この夢は吉なのか凶なのか>とか、<この夢にどんな意味があるのか>とか、まったく意味のないことを真剣になってやっていることがあるものだ。
ところが、朝になって目覚めてはじめて<夢の中の自分>は<幻>で、<現実の自分>とは違うと気付くもんだよね。」
【且有大覺】【且、大覚あり。】
【而後知此其大夢焉】【而る後此れその大夢なることを知る。】
〔さらに言えば、大いなる目覚めもある。目覚めてはじめて大きな夢を見ていたことを知ることができるものだ。〕
──「さらに言えば、人生における<大いなる目覚め>があるということを聞いたことがあるだろう。<大いなる目覚め>とは、<覚醒>とか<悟り>とか呼ばれることがある。その境地に至ってはじめて、普通に目覚めて生活していると思っていることが、実は<大きな夢>だということをことを理解することになるのだ。
そのことを概念的には、もう既に「知ってる」と思っている人も少なくないだろうが、果たして、予想しているイメージと一致するかどうか、わかったものではないぞ。」
∈∋
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 而愚者自以為覺 ┃【而して愚者は自ずと覚を為すを以って、】
┃ 竊竊然知之 ┃【竊竊(せつせつ)然としてこれを知る。】
┗━━━━━━━━━━┛
<愚者(鏡のような無我な心をもつ者)>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、人知れず内部から少しずつあたかも(滋養物を) 竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【竊】は、もと「穴+廿+米+〔集まる小虫の意の字〕」で、「穴にしまった米を小虫が
ひそかに食う」「外からは見えない内側を空にする」⇒「ぬすむ」「ひそかに」という意
味です。
◆通説では、【愚者】は一般的な尺度における「おろかもの」とされています。それ故、
【而愚者自以為覺 竊竊然知之】は、「それなのに、愚か者は、自分では目が覚めている
とうぬぼれて、あれこれと穿鑿(せんさく)してはもの知り顔をして」とかなり原文とはか
け離れたような意訳をしています。
◇【愚】に関しては、前にも説明しましたが、荘子は一般的な「おろか」という批判的なニ
ュアンスは一切もっておらず、積極的に肯定的な意味をもっているものとして用いている
のです。「禺」は「猿に似たもの」とはとえらずに、「そっくりなもの」という意味がこ
められていると説明してきましたが、【愚】は単純に言えば「そっくりな心」ということ
になります。そうなると【愚者】は「そっくりな心をもつ者」ということになりますが、
これだけではちょっとピンとこないかもしれません。そこで、「鏡のような無我な心をも
つ者」と補足しました。どうしてなのかというと、自我をもつ心はいつも波風が立って静
かになることはありませんが、無我の状態の心は、静まりかえっているため鏡のように、
ありのままの「そっくりな」姿をとらえることができるからです。【愚者】とはそんな心
境でいられる者と言えるのではないでしょうか。
◇【而愚者自以為覺】は、「<愚者>こそが、自ずと目覚めるようになれる」と言っている
のであって、「うぬぼれる」などとはどこにも書いていません。どうして自ずと目覚める
かは、【竊竊然知之】つまり、「人知れず内部から少しずつあたかも滋養物を竊(ぬす)
み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。」と説明しています。
┃▼ 而愚者自以為覺 ┃【而して愚者は自ずと覚を為すを以って、】
┃ 竊竊然知之 ┃【竊竊(せつせつ)然としてこれを知る。】
┗━━━━━━━━━━┛
<愚者(鏡のような無我な心をもつ者)>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、人知れず内部から少しずつあたかも(滋養物を) 竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【竊】は、もと「穴+廿+米+〔集まる小虫の意の字〕」で、「穴にしまった米を小虫が
ひそかに食う」「外からは見えない内側を空にする」⇒「ぬすむ」「ひそかに」という意
味です。
◆通説では、【愚者】は一般的な尺度における「おろかもの」とされています。それ故、
【而愚者自以為覺 竊竊然知之】は、「それなのに、愚か者は、自分では目が覚めている
とうぬぼれて、あれこれと穿鑿(せんさく)してはもの知り顔をして」とかなり原文とはか
け離れたような意訳をしています。
◇【愚】に関しては、前にも説明しましたが、荘子は一般的な「おろか」という批判的なニ
ュアンスは一切もっておらず、積極的に肯定的な意味をもっているものとして用いている
のです。「禺」は「猿に似たもの」とはとえらずに、「そっくりなもの」という意味がこ
められていると説明してきましたが、【愚】は単純に言えば「そっくりな心」ということ
になります。そうなると【愚者】は「そっくりな心をもつ者」ということになりますが、
これだけではちょっとピンとこないかもしれません。そこで、「鏡のような無我な心をも
つ者」と補足しました。どうしてなのかというと、自我をもつ心はいつも波風が立って静
かになることはありませんが、無我の状態の心は、静まりかえっているため鏡のように、
ありのままの「そっくりな」姿をとらえることができるからです。【愚者】とはそんな心
境でいられる者と言えるのではないでしょうか。
◇【而愚者自以為覺】は、「<愚者>こそが、自ずと目覚めるようになれる」と言っている
のであって、「うぬぼれる」などとはどこにも書いていません。どうして自ずと目覚める
かは、【竊竊然知之】つまり、「人知れず内部から少しずつあたかも滋養物を竊(ぬす)
み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。」と説明しています。
●通説では、次のようになっています。
それなのに、愚か者は、自分では目が覚めているとうぬぼれて、あれこれと穿鑿(せんさく)してはもの知り顔をして
〇新解釈では、次のようになります。
<愚者(鏡のような無我な心をもつ者)>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、人知れず内部から少しずつあたかも(滋養物を) 竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。
>@ ⊃彡
⊃彡
【而愚者自以為覺】【而して愚者は自ずと覚を為すを以って、】
〔<愚者(鏡のような無我な心をもつ者)>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、〕
──老木の話は続きます。
「<愚者>の対極側にいるのは<賢人(知識人)>と言えるかもしれないな。彼らは<既知の箱>にたくさんの知識を詰め込んでいるかもしれないが、どんなにそれを増やしても<目覚め>は起きないのだ。彼らはもの知りだ。もちろん<目覚め>についての情報も知識としてもう<知っている>と言うだろう。我流の解説付きのラベルを張った言葉をたくさんもっている。だが、その解説は想像の中で自我という色メガネかさざ波に歪められたものに過ぎない。物知りは人から賞賛を受けるが、自分の中で何の変化も起こさないのでその<知>は眠ったままでいつも<夢>を見ているだけで、欲求不満を感じているものだ。彼らは寄せ集めてきた知識は<卵>や<種>のようなものとして扱うことはない。
<愚者>は無我な状態で、心の鏡に映される入手した情報を<卵>や<種>のようなものだと認識するので、その実態はまだ<知らない>と言うだろう。彼は入手した言葉に反応して、自分の中に内在する<そっくりな卵や種>を探し出し、じっくり意識の光を当てて見守ってみるのだ。するとどうだろう、<卵>や<種>が、願望のような<飢え>を感じていることに気づくのだが、まだその正体は<知らない>ままだ。その<飢え>を満たすようにするうち突然、そこに<ヒナ>や<芽>といった実態が現れる。小さな<目覚め>だ。そうなってはじめて<卵>や<種>が、小さな<夢>を見ていたのだと悟るのだ。<愚者>はそういう形で自ずと<目覚め>、その言葉の指し示していた実態の正体をはじめてそこで<知る>ことができるのだ。」
【竊竊然知之】【竊竊(せつせつ)然としてこれを知る。】
〔人知れず内部から少しずつあたかも(滋養物を) 竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。〕
──「山木篇の中に、<君主は盗を為さず、賢人は竊(せつ)を為さず>という下りがある。通説では、<君子は人のものを盗まず、賢人もこそ泥はしない。>としている。もしこの解釈が妥当だとしたら、いったいその意味のどこに<食えるようなうまみ>があるというのだろうか。確かに<盗>も<竊>も<ぬすむ>という意味が含まれているが、<盗>と<竊>の違いは大きい。<盗>は、人のものを勝手に<所有すること>だが、<竊>は、<中身をひそかに食う>という意味が含まれているからだ。
<ぬすむ>という語のもつイメージを固定概念のみで考えるなら、すぐに<悪いこと>と決め込んでしまいがちだが、実際どうだろうか。多かれ少なかれ、<言葉の伝達><知識の継承>などの根底には、広い意味での<ぬすみ>なくしては、ありえないと言えないだろうか。つまり言葉を学ぶこと自体が<ぬすみ>と言えるのではないだろうか。
先の言葉を補足するならば、<君主は竊んでも(中身をぬすみ食いしても)盗まず、賢人は盗んでも竊まず(中身をぬすみ食いしない)>ということにはならないだろうか。つまり<君主は、言葉の中身をぬすみ食いしてそれを滋養として新たな誕生という目覚めが起き、自ずとオリジナルの言葉が芽生えるので、他人の言葉を盗むことはないが、賢人は人の言葉を盗んで自分のものにしても、それの中身を食べようとはしない>という意味だと解釈したならば、まさにこれこそ<食えるようなうまみ>がある下りだったということになりはしないだろうか。
<愚者>はどうして<君>の<飢え>を満たすようにできたのか。<既知の箱>に放置せずに、<竊竊然>としたからだ。つまり、<滋養になるものを人知れず内部でこつこつと食い尽くしている状態>といったイメージが浮かんでくる。
要するに、自分の内側に存在する鏡のような無我な心をもつ者、つまり内在する<愚者>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、滋養物を人知れずこつこつと竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ、と言っているようだ。」
それなのに、愚か者は、自分では目が覚めているとうぬぼれて、あれこれと穿鑿(せんさく)してはもの知り顔をして
〇新解釈では、次のようになります。
<愚者(鏡のような無我な心をもつ者)>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、人知れず内部から少しずつあたかも(滋養物を) 竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。
>@
【而愚者自以為覺】【而して愚者は自ずと覚を為すを以って、】
〔<愚者(鏡のような無我な心をもつ者)>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、〕
──老木の話は続きます。
「<愚者>の対極側にいるのは<賢人(知識人)>と言えるかもしれないな。彼らは<既知の箱>にたくさんの知識を詰め込んでいるかもしれないが、どんなにそれを増やしても<目覚め>は起きないのだ。彼らはもの知りだ。もちろん<目覚め>についての情報も知識としてもう<知っている>と言うだろう。我流の解説付きのラベルを張った言葉をたくさんもっている。だが、その解説は想像の中で自我という色メガネかさざ波に歪められたものに過ぎない。物知りは人から賞賛を受けるが、自分の中で何の変化も起こさないのでその<知>は眠ったままでいつも<夢>を見ているだけで、欲求不満を感じているものだ。彼らは寄せ集めてきた知識は<卵>や<種>のようなものとして扱うことはない。
<愚者>は無我な状態で、心の鏡に映される入手した情報を<卵>や<種>のようなものだと認識するので、その実態はまだ<知らない>と言うだろう。彼は入手した言葉に反応して、自分の中に内在する<そっくりな卵や種>を探し出し、じっくり意識の光を当てて見守ってみるのだ。するとどうだろう、<卵>や<種>が、願望のような<飢え>を感じていることに気づくのだが、まだその正体は<知らない>ままだ。その<飢え>を満たすようにするうち突然、そこに<ヒナ>や<芽>といった実態が現れる。小さな<目覚め>だ。そうなってはじめて<卵>や<種>が、小さな<夢>を見ていたのだと悟るのだ。<愚者>はそういう形で自ずと<目覚め>、その言葉の指し示していた実態の正体をはじめてそこで<知る>ことができるのだ。」
【竊竊然知之】【竊竊(せつせつ)然としてこれを知る。】
〔人知れず内部から少しずつあたかも(滋養物を) 竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ。〕
──「山木篇の中に、<君主は盗を為さず、賢人は竊(せつ)を為さず>という下りがある。通説では、<君子は人のものを盗まず、賢人もこそ泥はしない。>としている。もしこの解釈が妥当だとしたら、いったいその意味のどこに<食えるようなうまみ>があるというのだろうか。確かに<盗>も<竊>も<ぬすむ>という意味が含まれているが、<盗>と<竊>の違いは大きい。<盗>は、人のものを勝手に<所有すること>だが、<竊>は、<中身をひそかに食う>という意味が含まれているからだ。
<ぬすむ>という語のもつイメージを固定概念のみで考えるなら、すぐに<悪いこと>と決め込んでしまいがちだが、実際どうだろうか。多かれ少なかれ、<言葉の伝達><知識の継承>などの根底には、広い意味での<ぬすみ>なくしては、ありえないと言えないだろうか。つまり言葉を学ぶこと自体が<ぬすみ>と言えるのではないだろうか。
先の言葉を補足するならば、<君主は竊んでも(中身をぬすみ食いしても)盗まず、賢人は盗んでも竊まず(中身をぬすみ食いしない)>ということにはならないだろうか。つまり<君主は、言葉の中身をぬすみ食いしてそれを滋養として新たな誕生という目覚めが起き、自ずとオリジナルの言葉が芽生えるので、他人の言葉を盗むことはないが、賢人は人の言葉を盗んで自分のものにしても、それの中身を食べようとはしない>という意味だと解釈したならば、まさにこれこそ<食えるようなうまみ>がある下りだったということになりはしないだろうか。
<愚者>はどうして<君>の<飢え>を満たすようにできたのか。<既知の箱>に放置せずに、<竊竊然>としたからだ。つまり、<滋養になるものを人知れず内部でこつこつと食い尽くしている状態>といったイメージが浮かんでくる。
要するに、自分の内側に存在する鏡のような無我な心をもつ者、つまり内在する<愚者>こそが、自ずと目覚めるようになれるのは、滋養物を人知れずこつこつと竊(ぬす)み食いするかのようにして、これ(実態)を知るからだ、と言っているようだ。」
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 君乎牧乎 固哉 ┃【君や牧や、固(もと)よりかな。】
┗━━━━━━━━━━┛
(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に相当する滋養物)なるものが、それぞれもとからあるからだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【君】は「口+尹(手+亅印/上下を調和する働き・神と人の間をとりもつ)」で、後に
「人々に号令して円満周到におさめまとめる人」となったものです。
*【牧】は「牛+攴(動詞の記号)」で、「牛を繁殖させる行い」を示します。「かう(家
畜を飼う)」「まき・まきば」「養う」「自分の人格・教養を豊かにする」などの意。
◆通説では、【君】や【牧】を貴賤のある他人のこととしています。【君乎牧乎】は「君主
だといっては貴び牧人だといっては賤しんで差別する。」としています。
◇【君乎牧乎】は、他人のことを言っているのではなく、ましてや「差別する」などどこに
も書いていません。自分の中の愚者が「ひそかにぬすみ食いすること」がどうして「夢」
から「目覚めること」になるのかを説明しているのです。【君】というのは、喩えて言う
ならば、「種」の中で「胚」と呼ばれる小さな部位ですが、天からの生きるための青写真
を授かった主要な存在です。一方【牧】は【君】を養うための滋養物がたっぷりとつま
っている「胚乳」と呼ばれる部位に相当するものだと喩えられそうです。まだ「種」で
ある間は【君】も可能性の「夢」を見てい愚者にすぎず、【牧】(胚乳)の栄養(滋養物)
を「ぬすみ食い」することによって少しずつ「目覚めて」ゆくのです。このように、一
人の人間の中には、【君】と【牧】という「主体として生きるもの」と「滋養物として
食われて姿を消す(死んでいく)もの」という別々の存在があると言っているようです。
【君乎牧乎】は「(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に
相当する滋養物)なるものは、」と補足した訳としました。
*【固】は、ここは「もとより」「もちろん」「固定して決まっている」意。
◆【固哉】は、通説では「固陋(かたくな)なことだ。」としています。
◇【固哉】は、「それぞれもとからあるからだ」としました。つまり、一人の人間の中に
もともと絶対的に違う役割をもつものが存在していると言っているのでしょう。
┃▼ 君乎牧乎 固哉 ┃【君や牧や、固(もと)よりかな。】
┗━━━━━━━━━━┛
(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に相当する滋養物)なるものが、それぞれもとからあるからだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【君】は「口+尹(手+亅印/上下を調和する働き・神と人の間をとりもつ)」で、後に
「人々に号令して円満周到におさめまとめる人」となったものです。
*【牧】は「牛+攴(動詞の記号)」で、「牛を繁殖させる行い」を示します。「かう(家
畜を飼う)」「まき・まきば」「養う」「自分の人格・教養を豊かにする」などの意。
◆通説では、【君】や【牧】を貴賤のある他人のこととしています。【君乎牧乎】は「君主
だといっては貴び牧人だといっては賤しんで差別する。」としています。
◇【君乎牧乎】は、他人のことを言っているのではなく、ましてや「差別する」などどこに
も書いていません。自分の中の愚者が「ひそかにぬすみ食いすること」がどうして「夢」
から「目覚めること」になるのかを説明しているのです。【君】というのは、喩えて言う
ならば、「種」の中で「胚」と呼ばれる小さな部位ですが、天からの生きるための青写真
を授かった主要な存在です。一方【牧】は【君】を養うための滋養物がたっぷりとつま
っている「胚乳」と呼ばれる部位に相当するものだと喩えられそうです。まだ「種」で
ある間は【君】も可能性の「夢」を見てい愚者にすぎず、【牧】(胚乳)の栄養(滋養物)
を「ぬすみ食い」することによって少しずつ「目覚めて」ゆくのです。このように、一
人の人間の中には、【君】と【牧】という「主体として生きるもの」と「滋養物として
食われて姿を消す(死んでいく)もの」という別々の存在があると言っているようです。
【君乎牧乎】は「(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に
相当する滋養物)なるものは、」と補足した訳としました。
*【固】は、ここは「もとより」「もちろん」「固定して決まっている」意。
◆【固哉】は、通説では「固陋(かたくな)なことだ。」としています。
◇【固哉】は、「それぞれもとからあるからだ」としました。つまり、一人の人間の中に
もともと絶対的に違う役割をもつものが存在していると言っているのでしょう。
●通説では、次のようになっています。
君主だといっては貴び牧人だといっては賤しんで差別をする。固陋(かたくな)なことだ。
〇新解釈では、次のようになります。
(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に相当する滋養物)なるものが、それぞれもとからあるからだ。
>@ ⊃彡
⊃彡
【君乎牧乎 固哉】【君や牧や、固(もと)よりかな。】
〔(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に相当する滋養物)なるものが、それぞれもとからあるからだ。〕
──「無我な<君>は、天から授かった独自の青写真があるために、それを<現実のもの>にしたくて、可能性の願望的<飢え>を感じているのだ。それ故それに応えるべき<牧(養ってくれるもの)>を<食べたい>と望むのだ。
ところが<牧>となるべきものもそれぞれの願望があって自らは<食べられて死のう>とはなかなかしない無数の自我のようなものと言ってもいいかもしれないな。それを視覚的イメージでのみで喩えるなら、大きな種の中に構造的に相似形をなす無数の小さな種が潜んでいるフラクタルのような状態と言えるかもしれない。そこで<君>の前身のような<愚者>の存在が必要になるのだ。まずは一つ一つの自我の願望の種を<現実のもの>にするために、<愚者>は一つずつ小さな自我を<仮の主>としてその<牧>となるものを<ぬすみ食い>してその実態を知るのだ。もしそれに満足したならば<小さな自我>はそこで<目覚め>、自分は<小さな夢>を見ていただけで、いずれ訪れる<死>に際し、そのままだと<無駄死に>するところだったと自覚し、その価値を知ることによって、小さな<飢え>は消えてなくなるのだ。ところがそれにもかかわらず、違う大きな<飢え>がまだ満たされないと感じるのだ。そこで、小さなその自我は全体の<主>ではなく、本当の<君(主)>のための<牧>となる運命にあることを悟るのだ。そうなってはじめて無我な<君>のための<牧>に喜んで自らなって、<食べられる死>を選択するのだ。その<死>こそ価値あるものなのだ。というのも、そうして最終的に無我な<君>に融合し、少しずつ変容しながら新たな<生>を<一>となって生きていくことになるからだ。
<種>の中の<胚(君)>は、<胚乳(牧)>から、変容のために必要な分ずつ<頂戴する(ぬすみ食いする)>。<君>の<飢え>は、本当に必要な<牧>を<食べない>限り満たされないもので、ごまかしがきかないのだ。
この絶対的な関係を結んでいる<君>なるものと<牧>なるものが、一人の人間の中に別々に存在するのだ。<食べる君>と<食べられる牧>はもともと決まったものとしてあるのだ。」
∈∋
君主だといっては貴び牧人だといっては賤しんで差別をする。固陋(かたくな)なことだ。
〇新解釈では、次のようになります。
(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に相当する滋養物)なるものが、それぞれもとからあるからだ。
>@
【君乎牧乎 固哉】【君や牧や、固(もと)よりかな。】
〔(つまり種に喩えるなら)君(胚に相当する主)なるものと、牧(胚乳に相当する滋養物)なるものが、それぞれもとからあるからだ。〕
──「無我な<君>は、天から授かった独自の青写真があるために、それを<現実のもの>にしたくて、可能性の願望的<飢え>を感じているのだ。それ故それに応えるべき<牧(養ってくれるもの)>を<食べたい>と望むのだ。
ところが<牧>となるべきものもそれぞれの願望があって自らは<食べられて死のう>とはなかなかしない無数の自我のようなものと言ってもいいかもしれないな。それを視覚的イメージでのみで喩えるなら、大きな種の中に構造的に相似形をなす無数の小さな種が潜んでいるフラクタルのような状態と言えるかもしれない。そこで<君>の前身のような<愚者>の存在が必要になるのだ。まずは一つ一つの自我の願望の種を<現実のもの>にするために、<愚者>は一つずつ小さな自我を<仮の主>としてその<牧>となるものを<ぬすみ食い>してその実態を知るのだ。もしそれに満足したならば<小さな自我>はそこで<目覚め>、自分は<小さな夢>を見ていただけで、いずれ訪れる<死>に際し、そのままだと<無駄死に>するところだったと自覚し、その価値を知ることによって、小さな<飢え>は消えてなくなるのだ。ところがそれにもかかわらず、違う大きな<飢え>がまだ満たされないと感じるのだ。そこで、小さなその自我は全体の<主>ではなく、本当の<君(主)>のための<牧>となる運命にあることを悟るのだ。そうなってはじめて無我な<君>のための<牧>に喜んで自らなって、<食べられる死>を選択するのだ。その<死>こそ価値あるものなのだ。というのも、そうして最終的に無我な<君>に融合し、少しずつ変容しながら新たな<生>を<一>となって生きていくことになるからだ。
<種>の中の<胚(君)>は、<胚乳(牧)>から、変容のために必要な分ずつ<頂戴する(ぬすみ食いする)>。<君>の<飢え>は、本当に必要な<牧>を<食べない>限り満たされないもので、ごまかしがきかないのだ。
この絶対的な関係を結んでいる<君>なるものと<牧>なるものが、一人の人間の中に別々に存在するのだ。<食べる君>と<食べられる牧>はもともと決まったものとしてあるのだ。」
∈∋
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 丘也与女皆夢也 ┃【丘や女(なんじ)はともに皆夢なり。】
┃ 予謂女夢亦夢也 ┃【予(われ)の女(なんじ)を夢と謂うのも亦夢なり。】
┗━━━━━━━━━━┛
丘(孔子)もお前もみな夢の中だ。
予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。
…………………………………………………………………………………………………………
◆【丘也与女皆夢也 予謂女夢亦夢也】は、通説では「孔丘もお前もみな夢を見ているの
だ。そして、わしがお前に夢の話をしているのも、また夢だ。」としています。
◇【丘也与女皆夢也 予謂女夢亦夢也】は、通説と大差なく「丘(孔子)もお前もみな夢
の中だ。予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。」としました。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 是其言也 其名為弔詭 ┃【是、その言や、その名を弔詭(ちょうき)と為す。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
このようなことをこういうふうに言える。
その名は<弔詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。
…………………………………………………………………………………………………………
*【弔】は「棒につるが巻きついたさま」で「上から下にたれる」意を含み、「天の神が下
界に恩恵をたれること」⇒転じて「他人に同情をたれること」、また、「死んだ人に対す
る悔やみを述べる」ことにも使われます。
*【詭】は「言+危(変にとがった、並はずれてきつい)」で、「ふつうのものとちがうさ
ま」「特異であるさま」を表しています。
◆通説では、【是其言也 其名為弔詭】は「こうした話こそ、それを名づけて弔詭(てきき)
(──すなわちとても変わった話)という。」としています。【弔】は「テキ」と読んで、
無上至極の意、と説明していますが、辞書にはその音(と意味)は入っていません。
◇【弔詭(ちょうき)】とは、「数々の<夢>を見ている<自我>が死んで(消えて)いくこ
とにお悔やみを言いつつ、それが<無我>にになって甦って<目覚めていく>恩恵をた
れるという、普通考えられないような特異な話」といったようなニュアンスでしょうか。
【是其言也 其名為弔詭】は「このようなことをこういうふうに言える。その名は<弔
詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。」としました。
┃▼ 丘也与女皆夢也 ┃【丘や女(なんじ)はともに皆夢なり。】
┃ 予謂女夢亦夢也 ┃【予(われ)の女(なんじ)を夢と謂うのも亦夢なり。】
┗━━━━━━━━━━┛
丘(孔子)もお前もみな夢の中だ。
予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。
…………………………………………………………………………………………………………
◆【丘也与女皆夢也 予謂女夢亦夢也】は、通説では「孔丘もお前もみな夢を見ているの
だ。そして、わしがお前に夢の話をしているのも、また夢だ。」としています。
◇【丘也与女皆夢也 予謂女夢亦夢也】は、通説と大差なく「丘(孔子)もお前もみな夢
の中だ。予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。」としました。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 是其言也 其名為弔詭 ┃【是、その言や、その名を弔詭(ちょうき)と為す。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
このようなことをこういうふうに言える。
その名は<弔詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。
…………………………………………………………………………………………………………
*【弔】は「棒につるが巻きついたさま」で「上から下にたれる」意を含み、「天の神が下
界に恩恵をたれること」⇒転じて「他人に同情をたれること」、また、「死んだ人に対す
る悔やみを述べる」ことにも使われます。
*【詭】は「言+危(変にとがった、並はずれてきつい)」で、「ふつうのものとちがうさ
ま」「特異であるさま」を表しています。
◆通説では、【是其言也 其名為弔詭】は「こうした話こそ、それを名づけて弔詭(てきき)
(──すなわちとても変わった話)という。」としています。【弔】は「テキ」と読んで、
無上至極の意、と説明していますが、辞書にはその音(と意味)は入っていません。
◇【弔詭(ちょうき)】とは、「数々の<夢>を見ている<自我>が死んで(消えて)いくこ
とにお悔やみを言いつつ、それが<無我>にになって甦って<目覚めていく>恩恵をた
れるという、普通考えられないような特異な話」といったようなニュアンスでしょうか。
【是其言也 其名為弔詭】は「このようなことをこういうふうに言える。その名は<弔
詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。」としました。
●通説では、次のようになっています。
孔丘もお前もみな夢を見ているのだ。そして、わしがお前に夢の話をしているのも、また夢だ。こうした話こそ、それを名づけて弔詭(てきき)(──すなわちとても変わった話)という。
〇新解釈では、次のようになります。
丘(孔子)もお前もみな夢の中だ。予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。
このようなことをこういうふうに言える。その名は<弔詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。
>@ ⊃彡
⊃彡
【丘也与女皆夢也】【丘や女(なんじ)はともに皆夢なり。】
【予謂女夢亦夢也】【予(われ)の女(なんじ)を夢と謂うのも亦夢なり。】
〔丘(孔子)もお前もみな夢の中だ。予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。〕
──老木の話は続きます。
「孔子やお前さんが、どんなに<既知の箱>に十把一からげに知識の量を増やそうとも、常に一種の<飢え・渇望>に苛まれ続け、心が落ち着かないでいるのはどうしてなのか、今なら少しはわかるのではないだろうか。<飢え・渇望>が続く限り、それは<必要>を満たす自らの<内>に既にあるものを<食べていない>からだ。そうとも知らず、皆は<外>を巡って遥か彼方まで探し回ってそれを解決できるような情報をまだ知ろうとしている。それではいつまで経っても<夢の中>だ。予(わたし)がお前さんも<夢の中>だと言うことも、また<夢>の話で終わってしまうに違いない。」
カササギは、ゆうべの夢のことがまた浮かんできて、奇妙な感覚に襲われました。心の奥底のどこかが、<道>のことを知りたいと<飢えて渇望している>が、まだ満たされないで、老木に同意を求めて確かめようとしている自分がいることに気づいたからでした。つまり、あの<夢>の中で飢えたヒナであった自分の方が、より現実味を帯び、今、姿こそは成鳥である自分は、ある意味むしろ<夢>の中の借りの姿ではないだろうか、といった一種のめまいのようなものを感じたからでした。
【是其言也 其名為弔詭】【是、その言や、その名を弔詭(ちょうき)と為す。】
〔このようなことをこういうふうに言える。その名は<弔詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。〕
──老木は話を続けました。
「<君>という存在は天から永遠の命を授けられているかもしれないが、最初から確たるものとして認識できるものではなく、育てるのが難しい存在だ。成長した<君>の<知>は計り知れないものになるかもしれないが、その前身は<愚者>であるかのように、あるいは幼子であるかのように純粋無垢な、表面上は何も<知らない>と答えるような無我な者として存在していると言えるかもしれない。
一方、多くの<牧(自我)>は着々と成長して、主導権を交代しながら、その都度好きなものを<食べて>その場しのぎをしているようだ。知識欲、食欲、セックス欲などを満たしながら…。しかし、どうがんばってもこの<生>の期間の終わりを迎える時、全ては何ひとつ持って行けず死んでしまうものだということに本当は気づいているのだ。だから<死>を恐れて極力考えないでいようとし、長生きすることを望むようになるのだ。そうして自分が生きているという証を得ようと奮闘しているようだ。
だが、<半ば目覚めた自我>は、いくらがんばってもこのままでは、結局のところ<無駄死に>するだけだと悟るのだ。すると<無駄死に>したくないという願望が沸き上がる。<半ば目覚めた自我>は永遠の命が与えられていると思われる<無我な君>の望むことに加担しようと思いつくのだ。例えば自分の中に自然や宇宙の調和や進展などを基盤とするバイブレーションを身につけたいと考えたり、他人に真実に出会う幸福感をシェアしたいと願ったりする<君>の役に立つ<牧>として<死んでいこう(食べられよう)>と覚悟を決めるかもしれない。この<自我の自殺>を決行した状態を名づけるなら<特異な弔いごと>と言えるかもしれないな。」
∈∋
孔丘もお前もみな夢を見ているのだ。そして、わしがお前に夢の話をしているのも、また夢だ。こうした話こそ、それを名づけて弔詭(てきき)(──すなわちとても変わった話)という。
〇新解釈では、次のようになります。
丘(孔子)もお前もみな夢の中だ。予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。
このようなことをこういうふうに言える。その名は<弔詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。
>@
【丘也与女皆夢也】【丘や女(なんじ)はともに皆夢なり。】
【予謂女夢亦夢也】【予(われ)の女(なんじ)を夢と謂うのも亦夢なり。】
〔丘(孔子)もお前もみな夢の中だ。予(わたし)がお前を夢の中だと言うことも、また夢だ。〕
──老木の話は続きます。
「孔子やお前さんが、どんなに<既知の箱>に十把一からげに知識の量を増やそうとも、常に一種の<飢え・渇望>に苛まれ続け、心が落ち着かないでいるのはどうしてなのか、今なら少しはわかるのではないだろうか。<飢え・渇望>が続く限り、それは<必要>を満たす自らの<内>に既にあるものを<食べていない>からだ。そうとも知らず、皆は<外>を巡って遥か彼方まで探し回ってそれを解決できるような情報をまだ知ろうとしている。それではいつまで経っても<夢の中>だ。予(わたし)がお前さんも<夢の中>だと言うことも、また<夢>の話で終わってしまうに違いない。」
カササギは、ゆうべの夢のことがまた浮かんできて、奇妙な感覚に襲われました。心の奥底のどこかが、<道>のことを知りたいと<飢えて渇望している>が、まだ満たされないで、老木に同意を求めて確かめようとしている自分がいることに気づいたからでした。つまり、あの<夢>の中で飢えたヒナであった自分の方が、より現実味を帯び、今、姿こそは成鳥である自分は、ある意味むしろ<夢>の中の借りの姿ではないだろうか、といった一種のめまいのようなものを感じたからでした。
【是其言也 其名為弔詭】【是、その言や、その名を弔詭(ちょうき)と為す。】
〔このようなことをこういうふうに言える。その名は<弔詭(ちょうき/特異な弔いごと)>と。〕
──老木は話を続けました。
「<君>という存在は天から永遠の命を授けられているかもしれないが、最初から確たるものとして認識できるものではなく、育てるのが難しい存在だ。成長した<君>の<知>は計り知れないものになるかもしれないが、その前身は<愚者>であるかのように、あるいは幼子であるかのように純粋無垢な、表面上は何も<知らない>と答えるような無我な者として存在していると言えるかもしれない。
一方、多くの<牧(自我)>は着々と成長して、主導権を交代しながら、その都度好きなものを<食べて>その場しのぎをしているようだ。知識欲、食欲、セックス欲などを満たしながら…。しかし、どうがんばってもこの<生>の期間の終わりを迎える時、全ては何ひとつ持って行けず死んでしまうものだということに本当は気づいているのだ。だから<死>を恐れて極力考えないでいようとし、長生きすることを望むようになるのだ。そうして自分が生きているという証を得ようと奮闘しているようだ。
だが、<半ば目覚めた自我>は、いくらがんばってもこのままでは、結局のところ<無駄死に>するだけだと悟るのだ。すると<無駄死に>したくないという願望が沸き上がる。<半ば目覚めた自我>は永遠の命が与えられていると思われる<無我な君>の望むことに加担しようと思いつくのだ。例えば自分の中に自然や宇宙の調和や進展などを基盤とするバイブレーションを身につけたいと考えたり、他人に真実に出会う幸福感をシェアしたいと願ったりする<君>の役に立つ<牧>として<死んでいこう(食べられよう)>と覚悟を決めるかもしれない。この<自我の自殺>を決行した状態を名づけるなら<特異な弔いごと>と言えるかもしれないな。」
∈∋
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 万世之後而一遇大聖 ┃【万世の後にして、一たび大聖と遇し、】
┃ 知其解者 ┃【その解を知る者は、】
┃ 是旦暮遇之也 ┃【是、旦暮にこれに遇するなり。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
長い時を経た後、一たび大いなる聖なるものと遇し(出会ってそっくりに歩み)、これ(聖なるものの実態)がどういうものか紐解かれることを知った者は、これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことになるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【遇】は「しんにょう(足の動作)+禺(そっくりのもの)」で「二つのものが歩み寄
り、ふと出あってペアをなすこと」。
*【聖】は「耳+呈(まっすぐに述べる・まっすぐにさしだす)」で「耳がまっすぐに通る
こと」「わかりがよい」「さとい」などの意。「おかしがたくおごそかなさま」「その
道で最高にすぐれた人」「この上なくすぐれている」などの意。
*【解】は「角+刀+牛」で、「刀で牛のからだばらばらに分解すること」。
「とく」「ときあかす」「とける」「さとる」などの意。
◆【万世之後而一遇大聖 知其解者】は、通説では「この話の意味が分かる大聖人に〔め
ぐり会うのはむつかしいことで〕、万代もの後に一度めぐりあったとしても」としてい
ます。
◇【大聖知其解者】とは、「この話(弔詭)の意味がわかる者」のことでもなければ「大聖
人」のことでもないと思われます。【遇】の一般的意味は「出会う」ことに重点が置か
れていますが、字義からすると「そっくりに歩む」という意味が含まれていたのではな
いかと推察しました。何と「そっくりに歩む」かと言えば、【大聖】(大いなる聖なるも
の)と<一>となって歩むといとうことになると思います。
また何を【解】するかといえば、【大聖】(大いなる聖なるもの)がどういうものなのかを
「紐解くことができる」と言っているのだと思います。
【万世之後而一遇大聖 知其解者】は、「長い時を経た後、一たび大いなる聖なるものと
遇し(出会ってそっくりに歩み)、これ(聖なるものの実態)がどういうものか紐解かれるこ
とを知った者は」としました。
◆【是旦暮遇之也】は、通説では「それは朝晩に会っているほど〔の幸運〕なのだ。」とし
ています。
◇【是旦暮遇之也】は、「これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも
(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことにな
るだろう。」としました。
┃▼ 万世之後而一遇大聖 ┃【万世の後にして、一たび大聖と遇し、】
┃ 知其解者 ┃【その解を知る者は、】
┃ 是旦暮遇之也 ┃【是、旦暮にこれに遇するなり。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
長い時を経た後、一たび大いなる聖なるものと遇し(出会ってそっくりに歩み)、これ(聖なるものの実態)がどういうものか紐解かれることを知った者は、これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことになるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【遇】は「しんにょう(足の動作)+禺(そっくりのもの)」で「二つのものが歩み寄
り、ふと出あってペアをなすこと」。
*【聖】は「耳+呈(まっすぐに述べる・まっすぐにさしだす)」で「耳がまっすぐに通る
こと」「わかりがよい」「さとい」などの意。「おかしがたくおごそかなさま」「その
道で最高にすぐれた人」「この上なくすぐれている」などの意。
*【解】は「角+刀+牛」で、「刀で牛のからだばらばらに分解すること」。
「とく」「ときあかす」「とける」「さとる」などの意。
◆【万世之後而一遇大聖 知其解者】は、通説では「この話の意味が分かる大聖人に〔め
ぐり会うのはむつかしいことで〕、万代もの後に一度めぐりあったとしても」としてい
ます。
◇【大聖知其解者】とは、「この話(弔詭)の意味がわかる者」のことでもなければ「大聖
人」のことでもないと思われます。【遇】の一般的意味は「出会う」ことに重点が置か
れていますが、字義からすると「そっくりに歩む」という意味が含まれていたのではな
いかと推察しました。何と「そっくりに歩む」かと言えば、【大聖】(大いなる聖なるも
の)と<一>となって歩むといとうことになると思います。
また何を【解】するかといえば、【大聖】(大いなる聖なるもの)がどういうものなのかを
「紐解くことができる」と言っているのだと思います。
【万世之後而一遇大聖 知其解者】は、「長い時を経た後、一たび大いなる聖なるものと
遇し(出会ってそっくりに歩み)、これ(聖なるものの実態)がどういうものか紐解かれるこ
とを知った者は」としました。
◆【是旦暮遇之也】は、通説では「それは朝晩に会っているほど〔の幸運〕なのだ。」とし
ています。
◇【是旦暮遇之也】は、「これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも
(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことにな
るだろう。」としました。
●通説では、次のようになっています。
この話の意味が分かる大聖人に〔めぐり会うのはむつかしいことで〕、万代もの後に一度めぐりあったとしても、それは朝晩に会っているほど〔の幸運〕なのだ。
〇新解釈では、次のようになります。
長い時を経た後、一たび大いなる聖なるもの(の実態)がどういうものか紐解かれることを知った者は、これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことになるだろう。
>@ ⊃彡
⊃彡
【万世之後而一遇大聖】【万世の後にして、一たび大聖と遇し、】
【知其解者】【その解を知る者は、】
【是旦暮遇之也】【是、旦暮にこれに遇するなり。】
〔長い時を経た後、一たび大いなる聖なるものと遇し(出会ってそっくりに歩み)、これ(聖なるものの実態)がどういうものか紐解かれることを知った者は、これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことになるだろう。〕
──「なあ、カササギくん、<梵我一如>という言葉を聞いたことはあるだろうか? それは古代インドにおけるヴェーダ哲学の究極の悟りとされる境地のことだ。どういうことかと言うと、この宇宙に普遍的に存在する万物の原理・生命の源と考えられている<梵(ブラフマン)>と、個人の中に存在する多数の自我を<幻(マーヤー)>と看破して、唯一無二の<真我(アートマン)>とが本質的には同一であると<悟る>境地だ。宇宙と<わたし>は<一>であることを知ることにより、自由になり、苦が消え、永遠の至福に到達するとされている思想だ。<涅槃>や<解脱>とも言われることがある。
宇宙普遍の<梵(ブラフマン)>と<真我(アートマン)>が<一>であるとなると、人間の中の<真我(アートマン)>も不滅だと考えられ、生まれ変わりの思想もここから生まれてくることになるのだ。
簡単に横滑り的に言葉をはめられるものではないが、仮に<大聖>は<梵(ブラフマン)>、<夢>は<幻 (マーヤー)>、<吾(君なる者)>は<真我(アートマン)>、<目覚め>は<悟り>と置き換えてみると、多少は理解しやすくなるかもしれないな。
よって<大聖>を普通<大聖人>と解釈しているが、人ではなく状態を示しているのだ。自分の中の<愚者>は、小さな様々なものの真相(実態)を少しずつ確実に知っていくという意味においては、こつこつといわば<小聖>に出会ってそっくりに歩んでゆくことになるかもしれない。内なる<愚者>がそうしたことを積み重ねてゆくならば、内なる<君(主)>は(生まれ変わりながら)長い年月の後に、一たび<大聖>に出会ってそっくりに歩むことになって、その宇宙的自然の原理を解き明かすことができたならば、<大いなる目覚め>が起き、人生における<大夢>が消え去ることになるだろう。つまり、朝晩を通してどんな時でも<大聖>と<わたし>が<一>となって一緒に歩む境地に至るのだ。そうなった人をはじめて<聖人>と呼ぶことができるのだよ。」
カササギは、<聖人>のことを知ったかぶりしていたことを恥ずかしく思いました。
∈∋
この話の意味が分かる大聖人に〔めぐり会うのはむつかしいことで〕、万代もの後に一度めぐりあったとしても、それは朝晩に会っているほど〔の幸運〕なのだ。
〇新解釈では、次のようになります。
長い時を経た後、一たび大いなる聖なるもの(の実態)がどういうものか紐解かれることを知った者は、これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことになるだろう。
>@
【万世之後而一遇大聖】【万世の後にして、一たび大聖と遇し、】
【知其解者】【その解を知る者は、】
【是旦暮遇之也】【是、旦暮にこれに遇するなり。】
〔長い時を経た後、一たび大いなる聖なるものと遇し(出会ってそっくりに歩み)、これ(聖なるものの実態)がどういうものか紐解かれることを知った者は、これこそ(大夢から覚め)、明けてからだけでなく暮れてからも(夢見ることなく)これ(聖なるものの実態)と遇する(出会ってそっくりに歩む)ことになるだろう。〕
──「なあ、カササギくん、<梵我一如>という言葉を聞いたことはあるだろうか? それは古代インドにおけるヴェーダ哲学の究極の悟りとされる境地のことだ。どういうことかと言うと、この宇宙に普遍的に存在する万物の原理・生命の源と考えられている<梵(ブラフマン)>と、個人の中に存在する多数の自我を<幻(マーヤー)>と看破して、唯一無二の<真我(アートマン)>とが本質的には同一であると<悟る>境地だ。宇宙と<わたし>は<一>であることを知ることにより、自由になり、苦が消え、永遠の至福に到達するとされている思想だ。<涅槃>や<解脱>とも言われることがある。
宇宙普遍の<梵(ブラフマン)>と<真我(アートマン)>が<一>であるとなると、人間の中の<真我(アートマン)>も不滅だと考えられ、生まれ変わりの思想もここから生まれてくることになるのだ。
簡単に横滑り的に言葉をはめられるものではないが、仮に<大聖>は<梵(ブラフマン)>、<夢>は<幻 (マーヤー)>、<吾(君なる者)>は<真我(アートマン)>、<目覚め>は<悟り>と置き換えてみると、多少は理解しやすくなるかもしれないな。
よって<大聖>を普通<大聖人>と解釈しているが、人ではなく状態を示しているのだ。自分の中の<愚者>は、小さな様々なものの真相(実態)を少しずつ確実に知っていくという意味においては、こつこつといわば<小聖>に出会ってそっくりに歩んでゆくことになるかもしれない。内なる<愚者>がそうしたことを積み重ねてゆくならば、内なる<君(主)>は(生まれ変わりながら)長い年月の後に、一たび<大聖>に出会ってそっくりに歩むことになって、その宇宙的自然の原理を解き明かすことができたならば、<大いなる目覚め>が起き、人生における<大夢>が消え去ることになるだろう。つまり、朝晩を通してどんな時でも<大聖>と<わたし>が<一>となって一緒に歩む境地に至るのだ。そうなった人をはじめて<聖人>と呼ぶことができるのだよ。」
カササギは、<聖人>のことを知ったかぶりしていたことを恥ずかしく思いました。
∈∋
>ゆうさん
以上をもって、この話は逆転の発想でもなければ、人生の敗北者を慰めるためのものでもないことを理解していただけたでしょうか。
生きている意味をつかむための本当の<目覚め>を望むのであれば、自分自身の<君(主)>のための<牧>となるべく<自我の自殺(死)>(特異な弔いごと)ということが隠れたキーポイントになるかもしれません。言うは簡単なことですが、実際<自我>はよっぽどのことがなければ<自殺>しようなどとは考えないものです。ただの<自我の死>と、<君(主)>のための<自我の死>ではまるっきり違うものですが、そもそもふつうの人は、自分の中に<無我の君(主)>を認めることができないので難しい話になるのです。<自我>がなくなけば<わたし>が生きている意味がなくなるのではないかと考えるからです。しかし、実際には<自我という牧の死>の後に待っているのは、<無我となった牧の生>だと言ってもいいかもしれません。<牧>が存在しているのは、三次元世界で豊かになるように自然(天)が<君(主)>をサポートする役割を与えているからではないかと考えます。<種>や<卵>の夢見の世界が完全に役割を終え死んでから、発芽や誕生を迎え、はじめて本当の<目覚めた>人間の生きている意味がスタートすると言ってもいいかもしれません。<君(主)>は、<天(宇宙)>と<一>となって、はじめて<独自>の世界を生きると言えるでしょう。これらはパラドックスに満ちています。
概念論だけでは話が見えにくいと思うので、もう少しかみ砕いた話をしましょう。
普通の<自我>はどんなことを夢見ているかと言えば、お金持ちになりたい、衣食住において贅沢な生活をしたい、モテたい、異性を自分のものにしたい、セックスで快楽を味わいたい、良縁に恵まれたい、愛されたい、家族円満でいたい、もの知りだと思われたい、賢いと思われたい、人があっと驚くようなことがしたい、有名になりたい、多くの人から賞賛されたい、人より優位な立場に立って施したり教えたりしたく、それの見返りとして感謝されたい、多くの人と知り合いでいたい(孤独でいたくない)、人とおしゃべりしたい、いつも忙しくしていたい(暇をもてあましたくない)、勝負ごとや言いあいにどんな時でも勝ちたい、健康で長生きしたい、会社や社会の一員でありたい(つまはじきされたくない)、一方で会社や社会に縛られたくない、人間関係のしがらみに束縛されたくない、自由(気まま)でいたい、いつも楽しい気分でいたい、心身苦しみたくない…などといったようなことが挙げられそうです。
一方、<君>はどんなことを願っているかと言えば、宇宙、自然の法則に則った人類の進化と発展に貢献したい…といった言葉に集約できるでしょう。金言「なんじ自身を知れ」に従って、まず進化のためには自分自身の内部に光を当てなくてはならないでしょう。自分自身の中に存在するあらゆる真実に直面して、一つ一つの<自我>が<君>のための<牧(滋養)>となるように鍛える制御力が必要となるかもしれません。人類のことを考えているので、自分の中で得た一歩一歩の光明への道しるべを他人にもシェアしたいと願うでしょう。発展は<自我>が死んだのち生まれ変わった<牧>が<君>の願いに沿った、学問、文化、芸術、医学、建設、宇宙科学など様々な分野で、宇宙の意志を反映するような活動ができるように願っていると言えるかもしれません。
<無我に生まれ変わった牧>は<君>のためにどのような貢献ができるかと言えば、自立できるだけの経済力をもち、異性のみならず人を惹きつける魅力を身につけ、セックスを通して愛することを学び、性を超えた仁を育み、人を慈しみ、見返りを求めないシェアを許し、すること(doing)に忙しくすることもあれば、在ること(being)にゆったりすることもあり、時には言葉を用い、時には無言の存在感によって人に影響を与え、健康に留意しながらも、寿命は天にまかせ、バランスよく自分に役立つ知識と知恵を身につけ、議論をしても勝敗にこだわらず、社会の中に留まりつつも、独りであることに落ち着き、複雑に絡みついている人間関係のしがらみから逃れようとするのではなく、根気よくそれのからくりを紐解くことを反対に楽しみ、心身の苦しみを避けて通ろうとすることなく、その味を噛みしめながら、タフさに磨きをかけ、乗り越える道を模索し、いかなる時も被害者意識はなく、自由を満喫する…といったようなことが挙げられるでしょうか。
イメージで言えば、人生は<君>の縦軸(↑)での進化と、<牧>の横軸(⇔)での発展で豊かさを織りなすといった感じでしょうか。
ゆうさんは<君>の為の<自我の自殺>を想定できますか?
以上をもって、この話は逆転の発想でもなければ、人生の敗北者を慰めるためのものでもないことを理解していただけたでしょうか。
生きている意味をつかむための本当の<目覚め>を望むのであれば、自分自身の<君(主)>のための<牧>となるべく<自我の自殺(死)>(特異な弔いごと)ということが隠れたキーポイントになるかもしれません。言うは簡単なことですが、実際<自我>はよっぽどのことがなければ<自殺>しようなどとは考えないものです。ただの<自我の死>と、<君(主)>のための<自我の死>ではまるっきり違うものですが、そもそもふつうの人は、自分の中に<無我の君(主)>を認めることができないので難しい話になるのです。<自我>がなくなけば<わたし>が生きている意味がなくなるのではないかと考えるからです。しかし、実際には<自我という牧の死>の後に待っているのは、<無我となった牧の生>だと言ってもいいかもしれません。<牧>が存在しているのは、三次元世界で豊かになるように自然(天)が<君(主)>をサポートする役割を与えているからではないかと考えます。<種>や<卵>の夢見の世界が完全に役割を終え死んでから、発芽や誕生を迎え、はじめて本当の<目覚めた>人間の生きている意味がスタートすると言ってもいいかもしれません。<君(主)>は、<天(宇宙)>と<一>となって、はじめて<独自>の世界を生きると言えるでしょう。これらはパラドックスに満ちています。
概念論だけでは話が見えにくいと思うので、もう少しかみ砕いた話をしましょう。
普通の<自我>はどんなことを夢見ているかと言えば、お金持ちになりたい、衣食住において贅沢な生活をしたい、モテたい、異性を自分のものにしたい、セックスで快楽を味わいたい、良縁に恵まれたい、愛されたい、家族円満でいたい、もの知りだと思われたい、賢いと思われたい、人があっと驚くようなことがしたい、有名になりたい、多くの人から賞賛されたい、人より優位な立場に立って施したり教えたりしたく、それの見返りとして感謝されたい、多くの人と知り合いでいたい(孤独でいたくない)、人とおしゃべりしたい、いつも忙しくしていたい(暇をもてあましたくない)、勝負ごとや言いあいにどんな時でも勝ちたい、健康で長生きしたい、会社や社会の一員でありたい(つまはじきされたくない)、一方で会社や社会に縛られたくない、人間関係のしがらみに束縛されたくない、自由(気まま)でいたい、いつも楽しい気分でいたい、心身苦しみたくない…などといったようなことが挙げられそうです。
一方、<君>はどんなことを願っているかと言えば、宇宙、自然の法則に則った人類の進化と発展に貢献したい…といった言葉に集約できるでしょう。金言「なんじ自身を知れ」に従って、まず進化のためには自分自身の内部に光を当てなくてはならないでしょう。自分自身の中に存在するあらゆる真実に直面して、一つ一つの<自我>が<君>のための<牧(滋養)>となるように鍛える制御力が必要となるかもしれません。人類のことを考えているので、自分の中で得た一歩一歩の光明への道しるべを他人にもシェアしたいと願うでしょう。発展は<自我>が死んだのち生まれ変わった<牧>が<君>の願いに沿った、学問、文化、芸術、医学、建設、宇宙科学など様々な分野で、宇宙の意志を反映するような活動ができるように願っていると言えるかもしれません。
<無我に生まれ変わった牧>は<君>のためにどのような貢献ができるかと言えば、自立できるだけの経済力をもち、異性のみならず人を惹きつける魅力を身につけ、セックスを通して愛することを学び、性を超えた仁を育み、人を慈しみ、見返りを求めないシェアを許し、すること(doing)に忙しくすることもあれば、在ること(being)にゆったりすることもあり、時には言葉を用い、時には無言の存在感によって人に影響を与え、健康に留意しながらも、寿命は天にまかせ、バランスよく自分に役立つ知識と知恵を身につけ、議論をしても勝敗にこだわらず、社会の中に留まりつつも、独りであることに落ち着き、複雑に絡みついている人間関係のしがらみから逃れようとするのではなく、根気よくそれのからくりを紐解くことを反対に楽しみ、心身の苦しみを避けて通ろうとすることなく、その味を噛みしめながら、タフさに磨きをかけ、乗り越える道を模索し、いかなる時も被害者意識はなく、自由を満喫する…といったようなことが挙げられるでしょうか。
イメージで言えば、人生は<君>の縦軸(↑)での進化と、<牧>の横軸(⇔)での発展で豊かさを織りなすといった感じでしょうか。
ゆうさんは<君>の為の<自我の自殺>を想定できますか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
荘子 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
荘子のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170671人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人