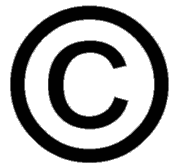創作物(のほとんど)が著作物となり、従って著作権が発生するという著作権法上の原則がある以上、「著作権とは?」という問いには
「創作物」とは何か?
そこから派生して、
創作とは? 創作行為とは?
という問いが生まれてくるものと思います。
このトピックでは、「創作物、創作、創作行為とは何か?」ということを議論してください。
その上で、制度論としての「著作権(制度)はどうあるべきか?」という議論については
著作権はどうあるべきか?
http://
でお願いします。
「創作物」とは何か?
そこから派生して、
創作とは? 創作行為とは?
という問いが生まれてくるものと思います。
このトピックでは、「創作物、創作、創作行為とは何か?」ということを議論してください。
その上で、制度論としての「著作権(制度)はどうあるべきか?」という議論については
著作権はどうあるべきか?
http://
でお願いします。
|
|
|
|
コメント(49)
いろいろ文章を書いていたら、またいろいろなことだ頭に浮かんできます。
前に書いた「絵」はその構造上、分離できない、という話。
しかし実演(パフォーマンス)を考えなくても、3DCGを描いたときには(『沈黙の美女』という作品)
頭の中にある「自分が求める美女」を形にしたいと考える
仮想空間の中で、「面」を表現するための「線」を紡ぎ出していく。
この「線」には太さ(面積)がありません、純粋な線です。
この線を描くときに使うのは、スタイラスペン(タブレット)ではなく、マウスです。
筋肉の動きの乱れは完璧に排除せねばなりません。方眼で表されたXYZの三軸上のグリッドの中で、自分が求める線を、デジタルで書き込んでいきました。点と点の間に線を描きたいときは、画面をいったん拡大して、線を描きます。
絵は、設計図(ワイヤーフレーム)と仕上げたもの(レンダリングされた絵)に、分離できることになったのです。
最終的にレンダリングされた結果出力された絵はありきたりなものですが、ぼくは仮想空間の中に描かれた、慣れでは制御できない、揺らぎを極力排除した線の魅力に取り憑かれました。クルマのボディに光を反射させて、面の歪みを消していく作業にも似てました。
その時、著作権はどこにあるのか?
別々に保護することが出来るのか?
またぼくはこうして挑戦していく際に、このアプリケーションを開発したスタッフに直接、作者からの要望を伝え、アプリケーションが進化するお手伝いをしました。その交流もまた、とても楽しい思い出です。
前に書いた「絵」はその構造上、分離できない、という話。
しかし実演(パフォーマンス)を考えなくても、3DCGを描いたときには(『沈黙の美女』という作品)
頭の中にある「自分が求める美女」を形にしたいと考える
仮想空間の中で、「面」を表現するための「線」を紡ぎ出していく。
この「線」には太さ(面積)がありません、純粋な線です。
この線を描くときに使うのは、スタイラスペン(タブレット)ではなく、マウスです。
筋肉の動きの乱れは完璧に排除せねばなりません。方眼で表されたXYZの三軸上のグリッドの中で、自分が求める線を、デジタルで書き込んでいきました。点と点の間に線を描きたいときは、画面をいったん拡大して、線を描きます。
絵は、設計図(ワイヤーフレーム)と仕上げたもの(レンダリングされた絵)に、分離できることになったのです。
最終的にレンダリングされた結果出力された絵はありきたりなものですが、ぼくは仮想空間の中に描かれた、慣れでは制御できない、揺らぎを極力排除した線の魅力に取り憑かれました。クルマのボディに光を反射させて、面の歪みを消していく作業にも似てました。
その時、著作権はどこにあるのか?
別々に保護することが出来るのか?
またぼくはこうして挑戦していく際に、このアプリケーションを開発したスタッフに直接、作者からの要望を伝え、アプリケーションが進化するお手伝いをしました。その交流もまた、とても楽しい思い出です。
スポーツの試合のときの駆け引きはエンタテインメントになりうると思います。ただ勝つだけでなく、観客をよろこばせるため、勝ち方を工夫する。
自転車ロードレースでは、グループの集団から飛び出して、1人向かい風に挑戦し、でもけっきょく力つきてグループに追いつかれる、というのが繰り返されます。
なぜか。
理由の一つに、先頭に出ることで、中継カメラを独り占めできるから。ユニフォームに印刷されたスポンサーのロゴを大写しに出来るから、なんですねー。これが、観てても面白い。中継の解説者が説明してくれるまで、ぼくは意味が判りませんでした。もちろんほんとうに勝ちをねらってのものもあります。それがどちらかは、観客にも知識がないとまったくわかりません。
他にもいろいろな勝ち方があって、けっこうプロレスに近いかもしれません。実力だけでは勝てないときの方が多い。
しかし10年ほど前、常に勝つ男が出て来て、大ブーイング。
野球もサッカーもバスケも、試合を楽しくするために、「制限する」ルールがありますよね。サッカーの「オフサイド」などはその典型です。スポーツをエンタテインメントにするためだけのルールが。
『ライブペイント』のときは、ただ完成させるだけではないんです。
自分が思っても見なかった発想で、自分の絵が変えられている(時として、それは自分の気にそわないこともある)。だから、観客の反応を見ながら、(おー、とか わーとか、笑いがそのまま聞こえてくるような距離だったので)なるべく観客が驚くような意外な展開にもっていこうと作者も工夫する。
その場でお客さんからお題をいただくのもやりました。
海外のイラストレーターの1人は、観客にカンバスに漢字を書いてもらって、それを元に絵を付け加えていく。そのとき観客が書いた漢字は「悪」つまり「デビル」であると通訳さんが説明して、イラストレーターさんは観客が何を望んでいたかが判る。
そのイラストレーターさんは、「悪」という漢字をもとにその、本人に取っては意味のない線の集合体をデビルに育てていく。でも、実はその絵は、あまり面白い絵になっていかなかった。だから、他の絵が何度も何度も3人の間を行ったり来たりしているのに、床にぽつんと置かれたままでした。でも、ぼくが次に手がける絵がそれしか残っていないという「タイミング」や「雰囲気」が、その場にできた。そこでぼくがそれをイーゼルに置いたときは、観客から「あー、気の毒に」のため息が聞こえてきましたよ(^^)
そこでぼくは、皆を驚かせてやろうと一念発起・・・
ここで大事なのは、観客が創作にも加わっている(直接、間接の両方があった)、ということですかねー。
自転車ロードレースでは、グループの集団から飛び出して、1人向かい風に挑戦し、でもけっきょく力つきてグループに追いつかれる、というのが繰り返されます。
なぜか。
理由の一つに、先頭に出ることで、中継カメラを独り占めできるから。ユニフォームに印刷されたスポンサーのロゴを大写しに出来るから、なんですねー。これが、観てても面白い。中継の解説者が説明してくれるまで、ぼくは意味が判りませんでした。もちろんほんとうに勝ちをねらってのものもあります。それがどちらかは、観客にも知識がないとまったくわかりません。
他にもいろいろな勝ち方があって、けっこうプロレスに近いかもしれません。実力だけでは勝てないときの方が多い。
しかし10年ほど前、常に勝つ男が出て来て、大ブーイング。
野球もサッカーもバスケも、試合を楽しくするために、「制限する」ルールがありますよね。サッカーの「オフサイド」などはその典型です。スポーツをエンタテインメントにするためだけのルールが。
『ライブペイント』のときは、ただ完成させるだけではないんです。
自分が思っても見なかった発想で、自分の絵が変えられている(時として、それは自分の気にそわないこともある)。だから、観客の反応を見ながら、(おー、とか わーとか、笑いがそのまま聞こえてくるような距離だったので)なるべく観客が驚くような意外な展開にもっていこうと作者も工夫する。
その場でお客さんからお題をいただくのもやりました。
海外のイラストレーターの1人は、観客にカンバスに漢字を書いてもらって、それを元に絵を付け加えていく。そのとき観客が書いた漢字は「悪」つまり「デビル」であると通訳さんが説明して、イラストレーターさんは観客が何を望んでいたかが判る。
そのイラストレーターさんは、「悪」という漢字をもとにその、本人に取っては意味のない線の集合体をデビルに育てていく。でも、実はその絵は、あまり面白い絵になっていかなかった。だから、他の絵が何度も何度も3人の間を行ったり来たりしているのに、床にぽつんと置かれたままでした。でも、ぼくが次に手がける絵がそれしか残っていないという「タイミング」や「雰囲気」が、その場にできた。そこでぼくがそれをイーゼルに置いたときは、観客から「あー、気の毒に」のため息が聞こえてきましたよ(^^)
そこでぼくは、皆を驚かせてやろうと一念発起・・・
ここで大事なのは、観客が創作にも加わっている(直接、間接の両方があった)、ということですかねー。
うーん,微妙なところですね。
1. 街の一角に真っ黒いポスターを貼る
ということと,それが
2. 他の部分とのコントラストを生じさせ,
3. 見る人に衝撃を与えることを狙って作られたものだ
ということ,そしてそれは
4. 白い紙を黒く加工するということによって作った
ということを考えると,4+1で既に表現と化しているように思えますし,2+3が作品そのものを街角+黒いポスターと考えた創作的表現のように思えます。
つまり,その作品は「黒いポスター」単体で成り立っているのではなく,それがどこかに貼られること(元々は街角)によって,その周囲と関連して,全体が作品として成立するもの,と考えれば,創作的表現足りうる気がします。
私は詳しくはないにせよ,モダンアートやインスタレーションが結構好きで,J.タレルなんかに感銘を受けたりもしているので,比較的広く著作物を捉えてますよ。
ただ,難しいんですよね。
キャンバスのど真ん中に一本線を引いただけで,それがアートだと言われてしまうと,うーん,と考え込んでしまいますから…。
それでも,美術の創作物というのは,ある程度「作品」たる部分を,それ以外の部分から分離させて考えることができ,そしてその「作品」を抽象化することが難しい点で,音楽の創作物のような抽象化が比較的容易な創作物とは違うよな,とは思っています。
1. 街の一角に真っ黒いポスターを貼る
ということと,それが
2. 他の部分とのコントラストを生じさせ,
3. 見る人に衝撃を与えることを狙って作られたものだ
ということ,そしてそれは
4. 白い紙を黒く加工するということによって作った
ということを考えると,4+1で既に表現と化しているように思えますし,2+3が作品そのものを街角+黒いポスターと考えた創作的表現のように思えます。
つまり,その作品は「黒いポスター」単体で成り立っているのではなく,それがどこかに貼られること(元々は街角)によって,その周囲と関連して,全体が作品として成立するもの,と考えれば,創作的表現足りうる気がします。
私は詳しくはないにせよ,モダンアートやインスタレーションが結構好きで,J.タレルなんかに感銘を受けたりもしているので,比較的広く著作物を捉えてますよ。
ただ,難しいんですよね。
キャンバスのど真ん中に一本線を引いただけで,それがアートだと言われてしまうと,うーん,と考え込んでしまいますから…。
それでも,美術の創作物というのは,ある程度「作品」たる部分を,それ以外の部分から分離させて考えることができ,そしてその「作品」を抽象化することが難しい点で,音楽の創作物のような抽象化が比較的容易な創作物とは違うよな,とは思っています。
そーぶんどー様
========
「創作」ではないものの例を考えてみたんです。
美術品の「複製物」などは、創作されてはいない。
高度なテクニックを使って作ってはいるけれど、創ってはいない。
真似をすることは、事実の写し取りであって、創作ではないんですよ
========
機械的な「複製物」もあれば、人間の手による「複製物」もありますよねー。
歴史的な建築物の襖や壁に描かれた絵。一部や全体が剥がれ落ちたり褪色したものを、補修するのではなく、別のところに、学者の指示のもと、後世の画家や学生が「再現」するのは、テレビの文化なんとか記念でよく放送されてます。
でも、絵は、レントゲンや、いずれMRIがもっと進歩すればある程度推測できるけど、陶器のように、偶然なのか、積み上げたテクニックなのか判らないものがあります。同じ色やひび割れを再現するのは、とってもタイヘン。
そして、もっと極端な例を思いついたですよ。
派生元トピックで出ていた能や歌舞伎の継承
親から子へ、孫へ継承していく時、
まだ何も理解できない幼児が、親に叱られながら分けも判らないままに覚え込まされた「型」と、おぼろげながらも自身が理解できてから学んだ「型」とは違うようにも思えて来て。
========
「創作」ではないものの例を考えてみたんです。
美術品の「複製物」などは、創作されてはいない。
高度なテクニックを使って作ってはいるけれど、創ってはいない。
真似をすることは、事実の写し取りであって、創作ではないんですよ
========
機械的な「複製物」もあれば、人間の手による「複製物」もありますよねー。
歴史的な建築物の襖や壁に描かれた絵。一部や全体が剥がれ落ちたり褪色したものを、補修するのではなく、別のところに、学者の指示のもと、後世の画家や学生が「再現」するのは、テレビの文化なんとか記念でよく放送されてます。
でも、絵は、レントゲンや、いずれMRIがもっと進歩すればある程度推測できるけど、陶器のように、偶然なのか、積み上げたテクニックなのか判らないものがあります。同じ色やひび割れを再現するのは、とってもタイヘン。
そして、もっと極端な例を思いついたですよ。
派生元トピックで出ていた能や歌舞伎の継承
親から子へ、孫へ継承していく時、
まだ何も理解できない幼児が、親に叱られながら分けも判らないままに覚え込まされた「型」と、おぼろげながらも自身が理解できてから学んだ「型」とは違うようにも思えて来て。
Simonさん
グラフィックデザインが実用的なものだから、という意味がよくわかりません(^^)
ぼくは「グラフィックデザイン」を学校で学びましたが、グラフィックデザインの中に「イラストレーション」もありました。
イラストレーションも起源は実用的なもの、です。
それが顕著なのは
★テクニカルイラスト(図面の立体版←間違いがあってはならない)
しかし、輪郭線と構造線、手前に来る面の境界を示す線などの太さをそれぞれ変えることによって、絵に「味」が出ます。
(職人には「味」が出ることを嫌う人がいますけど。)
別ジャンルでは、
★建築物の図面
一般の家屋は別にして、公的なものがコンペで競われる時、まだ構想段階のものが図面に描かれたり、縮尺模型で作られます。それらも実用的なものですが、著作権があります。
★地図
地図の制作者の団体が、昔、日本美術著作権連合に加盟してました。しかし、地図に、著作物と著作物でないものの区別が生まれた時、著作物性のある地図はイラストレーションに吸収され、著作物性のない地図を描いている人たちは、加盟している意味がなくなったということで日本美術著作権連合を脱会しました。
グラフィックデザインが実用的なものだから、という意味がよくわかりません(^^)
ぼくは「グラフィックデザイン」を学校で学びましたが、グラフィックデザインの中に「イラストレーション」もありました。
イラストレーションも起源は実用的なもの、です。
それが顕著なのは
★テクニカルイラスト(図面の立体版←間違いがあってはならない)
しかし、輪郭線と構造線、手前に来る面の境界を示す線などの太さをそれぞれ変えることによって、絵に「味」が出ます。
(職人には「味」が出ることを嫌う人がいますけど。)
別ジャンルでは、
★建築物の図面
一般の家屋は別にして、公的なものがコンペで競われる時、まだ構想段階のものが図面に描かれたり、縮尺模型で作られます。それらも実用的なものですが、著作権があります。
★地図
地図の制作者の団体が、昔、日本美術著作権連合に加盟してました。しかし、地図に、著作物と著作物でないものの区別が生まれた時、著作物性のある地図はイラストレーションに吸収され、著作物性のない地図を描いている人たちは、加盟している意味がなくなったということで日本美術著作権連合を脱会しました。
↑短時間でやったので、↓のレベルでかんべんしてください。だいたい意味は包含していると思います:
ーーーーー
ugcについて
スーザの引用。talking machine(一種の放送ツール? 詳細はここには出てこない)は、歌があちこちで唄われる(ながらmodifyされる)のを阻害し、アメリカの人々の創造性を奪っている」
現代的な言葉で言うread/write cultureが失われ>read onlyへ
trespasserについて。私有地の上空を飛行する飛行機は土地の所有者の権利を侵害しているか?>それは**常識として**「そんなことはない」とされた。
common sense revolts the idea
コンテンツの権利の侵害者としての放送。ASCAPが権利金を上げて行った。
BMIがパブリックドメインの音楽を使い始めた。質が高いので大丈夫とタカをくくっていたASCAPは結局負けた。
以下はwikipediaより引用:
In 1940, when ASCAP tried to double license fees again, radio broadcasters started to boycott ASCAP and formed their own royalty agency Broadcast Music Incorporated (BMI). During a ten month period lasting from January 1 to October 29, 1941, no music licensed by ASCAP (1,250,000 songs) was broadcasted on NBC and CBS radio stations. Instead, they played more regional music and styles (like rhythm and blues or country) that had been traditionally neglected by ASCAP. Eventually, the differences between ASCAP and the broadcasters were settled, and ASCAP agreed to fees much lower than in the preceding years. In the 1950s and 1960s, ASCAP initiated a series of lawsuits to recover the position they lost during the boycott of 1941, without success.
ここまで
議論
インターネットは再びRO>RW文化へ向かわせている:それがugc
アマチュアカルチャー(アマチュア的カルチャーでない):お金でなく愛で作っているコンテンツ
スーザの言ったことの現代版。
例:アニメ映像を別の音楽トラックとリミックスしたもの:
キリストらしい人物がディスコミュージックを踊り出す
ジョージブッシュとブレア首相が音楽「マイ・エンドレス・ラブ」で愛を語り合う(*)
これらはリミックスであり、パイラシーではない。他人のコンテツを使って、re-creationして、別のことを表現している。(*)などは典型か。
AV編集者の手を離れてツールがdemocratizeされた。これが今の子供たちの表現方法となっている。
文化の新たな使用方法である。
現代の著作権法はこれに対応できていない。
これらの使用法をtrespasserとして侵害と言えるか?
権利の両側から問題がおきている。これらの極論は双方を強めあう
・権利物を使ったリミックスがが自動的にネットから削除されるなどのきつい縛り
・子供達は著作権を無視するようになっている
どちらも極論であり、バランスしたところに答えがある。
解決法は?
private solution
BMIの歴史的事実にみられる現実的なバランスを考えよう
1.クリエイターは自分のコンテンツの一部をフリーユースにさせる
2.このフリーユースを支援する組織
more freeとless freeが同じ土俵で競い合う
これらと子供の影響
彼らは私たちと違う。我々はテレビを見る世代、彼らはAVテクノロジーでテレビを作る世代。
テクノロジーと創作本能のある子供たちは、そう(リミックス)せざるを得ない。それを単に犯罪、アンダーグラウンドとして非難していていいのか?
ーーーー
ここまで
ーーーーー
ugcについて
スーザの引用。talking machine(一種の放送ツール? 詳細はここには出てこない)は、歌があちこちで唄われる(ながらmodifyされる)のを阻害し、アメリカの人々の創造性を奪っている」
現代的な言葉で言うread/write cultureが失われ>read onlyへ
trespasserについて。私有地の上空を飛行する飛行機は土地の所有者の権利を侵害しているか?>それは**常識として**「そんなことはない」とされた。
common sense revolts the idea
コンテンツの権利の侵害者としての放送。ASCAPが権利金を上げて行った。
BMIがパブリックドメインの音楽を使い始めた。質が高いので大丈夫とタカをくくっていたASCAPは結局負けた。
以下はwikipediaより引用:
In 1940, when ASCAP tried to double license fees again, radio broadcasters started to boycott ASCAP and formed their own royalty agency Broadcast Music Incorporated (BMI). During a ten month period lasting from January 1 to October 29, 1941, no music licensed by ASCAP (1,250,000 songs) was broadcasted on NBC and CBS radio stations. Instead, they played more regional music and styles (like rhythm and blues or country) that had been traditionally neglected by ASCAP. Eventually, the differences between ASCAP and the broadcasters were settled, and ASCAP agreed to fees much lower than in the preceding years. In the 1950s and 1960s, ASCAP initiated a series of lawsuits to recover the position they lost during the boycott of 1941, without success.
ここまで
議論
インターネットは再びRO>RW文化へ向かわせている:それがugc
アマチュアカルチャー(アマチュア的カルチャーでない):お金でなく愛で作っているコンテンツ
スーザの言ったことの現代版。
例:アニメ映像を別の音楽トラックとリミックスしたもの:
キリストらしい人物がディスコミュージックを踊り出す
ジョージブッシュとブレア首相が音楽「マイ・エンドレス・ラブ」で愛を語り合う(*)
これらはリミックスであり、パイラシーではない。他人のコンテツを使って、re-creationして、別のことを表現している。(*)などは典型か。
AV編集者の手を離れてツールがdemocratizeされた。これが今の子供たちの表現方法となっている。
文化の新たな使用方法である。
現代の著作権法はこれに対応できていない。
これらの使用法をtrespasserとして侵害と言えるか?
権利の両側から問題がおきている。これらの極論は双方を強めあう
・権利物を使ったリミックスがが自動的にネットから削除されるなどのきつい縛り
・子供達は著作権を無視するようになっている
どちらも極論であり、バランスしたところに答えがある。
解決法は?
private solution
BMIの歴史的事実にみられる現実的なバランスを考えよう
1.クリエイターは自分のコンテンツの一部をフリーユースにさせる
2.このフリーユースを支援する組織
more freeとless freeが同じ土俵で競い合う
これらと子供の影響
彼らは私たちと違う。我々はテレビを見る世代、彼らはAVテクノロジーでテレビを作る世代。
テクノロジーと創作本能のある子供たちは、そう(リミックス)せざるを得ない。それを単に犯罪、アンダーグラウンドとして非難していていいのか?
ーーーー
ここまで
> talking machine(一種の放送ツール? 詳細はここには出てこない)は
蓄音機のことです。「スーザは蓄音機が出たときに、この機械は国の音楽の発展を阻害すると言った」が、そんなことはなかった。というのが話のつかみ。
レコードによって創造性(recreativity)から再創造性(recreativity)という形で文化の発展があったが、現代はメディアの発展やテクノロジーの進歩によって、さらにその再々創造性(re-recreativity)みたいなものが発展しつつあるんだから、それを簡単に「侵害」とか海賊行為とかいって阻害しないほうがいいんじゃねーの?って話じゃないですかね。
蓄音機のことです。「スーザは蓄音機が出たときに、この機械は国の音楽の発展を阻害すると言った」が、そんなことはなかった。というのが話のつかみ。
レコードによって創造性(recreativity)から再創造性(recreativity)という形で文化の発展があったが、現代はメディアの発展やテクノロジーの進歩によって、さらにその再々創造性(re-recreativity)みたいなものが発展しつつあるんだから、それを簡単に「侵害」とか海賊行為とかいって阻害しないほうがいいんじゃねーの?って話じゃないですかね。
なるほど>「蓄音機」 ありがとうございます。
「そんなことはなかった」とは言っていないのかも。蓄音機(ま、レコードなどの記録された音源をイメージすればよくて)は、人が自由に歌を歌うことの可塑性、自分が歌の形を書き換えているということでRead/Writeカルチャーだったのが、形になった音をそのまま聞く形態、つまりReadOnlyカルチャーの時代をもたらして、20世紀の音楽産業はだいたいはそういう時代の進展だった、というのが<1>の部分の話かな。
<2>はtresspassingを法が権利侵害と規定したが、上空を飛ぶ飛行機などの場合は、常識的にその法律がオーバールールされちゃったよね、という話
<3>は高音質の権利音楽を持つASCAPが絶対勝つと思っていたら、パブリックドメインの(そこまでは高品質でない)音楽を使ったBMIに負けちゃった、という歴史的事実
で、それらを背景とした議論として、PCとインターネットによる、新しいRWの世界では、音源のコピペと編集は、新たな形の(re)creativityを生んでいて、それが今の時代の若い世代の(re)creativityのツールなんだから、それを違法だ犯罪だ、っていって非難しているだけではものごとは正しく進まないだろうから、過去のBMIのケースの歴史に学んで、どこか中道的な解決策をさがそうぜ、って感じですかね。
その中で具体的な解決策として彼が言ってることを、ここはわたし的にすこし敷衍して書くと;
・たとえば音楽権利者は、ビットレートを落とすとか、モノラルにするとかした彼の権利物「の一部」のフリーユースを認めなさいよ(それは上空のtrespasserのように、厳密な法律論的にはいくらか権利者を侵害しているが、まあそれが世間の常識ってもんでしょ(というところが、こと音楽著作権ではまだ成熟した関係性として成立していない))
・そうすれば(re)creatorたちはそれを使って、たとえば「ブッシュとブレアが蜜月だ」という、イラク戦争における米英の関係を揶揄/非難/皮肉る作品を作れるよね。(それは「マイエンドレスラブ」そのものの意味とは別の意味を創造しているよね。別に特に曲は「マイエンドレスラブ」である必要もないし、高音質も必要でない。「ラブラブな二人」を表す、誰でも認知できるよく知られた音楽が手近に使えればいいだけ。それなら元権利者の素晴らしい音楽と、それをチープに換骨奪胎して意味だけ援用?した作品は同じ土俵にいることができるでしょ。)
そこらへんに創造性とか権利のいい落としどころがあるのかも、という話ですかね。
「そんなことはなかった」とは言っていないのかも。蓄音機(ま、レコードなどの記録された音源をイメージすればよくて)は、人が自由に歌を歌うことの可塑性、自分が歌の形を書き換えているということでRead/Writeカルチャーだったのが、形になった音をそのまま聞く形態、つまりReadOnlyカルチャーの時代をもたらして、20世紀の音楽産業はだいたいはそういう時代の進展だった、というのが<1>の部分の話かな。
<2>はtresspassingを法が権利侵害と規定したが、上空を飛ぶ飛行機などの場合は、常識的にその法律がオーバールールされちゃったよね、という話
<3>は高音質の権利音楽を持つASCAPが絶対勝つと思っていたら、パブリックドメインの(そこまでは高品質でない)音楽を使ったBMIに負けちゃった、という歴史的事実
で、それらを背景とした議論として、PCとインターネットによる、新しいRWの世界では、音源のコピペと編集は、新たな形の(re)creativityを生んでいて、それが今の時代の若い世代の(re)creativityのツールなんだから、それを違法だ犯罪だ、っていって非難しているだけではものごとは正しく進まないだろうから、過去のBMIのケースの歴史に学んで、どこか中道的な解決策をさがそうぜ、って感じですかね。
その中で具体的な解決策として彼が言ってることを、ここはわたし的にすこし敷衍して書くと;
・たとえば音楽権利者は、ビットレートを落とすとか、モノラルにするとかした彼の権利物「の一部」のフリーユースを認めなさいよ(それは上空のtrespasserのように、厳密な法律論的にはいくらか権利者を侵害しているが、まあそれが世間の常識ってもんでしょ(というところが、こと音楽著作権ではまだ成熟した関係性として成立していない))
・そうすれば(re)creatorたちはそれを使って、たとえば「ブッシュとブレアが蜜月だ」という、イラク戦争における米英の関係を揶揄/非難/皮肉る作品を作れるよね。(それは「マイエンドレスラブ」そのものの意味とは別の意味を創造しているよね。別に特に曲は「マイエンドレスラブ」である必要もないし、高音質も必要でない。「ラブラブな二人」を表す、誰でも認知できるよく知られた音楽が手近に使えればいいだけ。それなら元権利者の素晴らしい音楽と、それをチープに換骨奪胎して意味だけ援用?した作品は同じ土俵にいることができるでしょ。)
そこらへんに創造性とか権利のいい落としどころがあるのかも、という話ですかね。
31
あたりからの流れ、翻訳「歌詞」に関して興味をもっています。
原語の曲では日本人に理解してもらえないため
翻訳→訳詞をのせて演奏、
というのは普通にあると思いますが、これと著作権利の関連が
今一つよくわかりません。
一人の歌手がCDを作成をしようとしたところ、
・「法定翻訳」である翻訳は、
それ以外の歌詞をつけることが許されないので使用できない。
・法定翻訳の歌詞は、その日本語詞の作者に料金を払えば歌える。
と説明を受けたそうです。
youtubeではその限りではないようで、
さまざまな歌詞で同じ曲を聴くことができますが、
CD作成、販売であるからちがってくるのでしょうか。
原曲の歌詞を違う国の言葉に訳す、あるいは広い意味でパロディを作るには
オリジナルの曲の持ち主の許可をとるのが必要だ、ということまでは
ぼんやり把握しています。
しかし一つの国、ひとつの国語のなかに、ひとつしか翻訳が存在してはならない、というのはなんとなく不自然に見えてしまうのです。
ご意見いただければ幸いです。
あたりからの流れ、翻訳「歌詞」に関して興味をもっています。
原語の曲では日本人に理解してもらえないため
翻訳→訳詞をのせて演奏、
というのは普通にあると思いますが、これと著作権利の関連が
今一つよくわかりません。
一人の歌手がCDを作成をしようとしたところ、
・「法定翻訳」である翻訳は、
それ以外の歌詞をつけることが許されないので使用できない。
・法定翻訳の歌詞は、その日本語詞の作者に料金を払えば歌える。
と説明を受けたそうです。
youtubeではその限りではないようで、
さまざまな歌詞で同じ曲を聴くことができますが、
CD作成、販売であるからちがってくるのでしょうか。
原曲の歌詞を違う国の言葉に訳す、あるいは広い意味でパロディを作るには
オリジナルの曲の持ち主の許可をとるのが必要だ、ということまでは
ぼんやり把握しています。
しかし一つの国、ひとつの国語のなかに、ひとつしか翻訳が存在してはならない、というのはなんとなく不自然に見えてしまうのです。
ご意見いただければ幸いです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
著作権 更新情報
-
最新のアンケート
著作権のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170675人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90051人