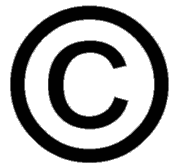|
|
|
|
コメント(24)
それは技術的に問題もありそうですけど、それ以前に法制度の問題もあるんですよね。
法律って基本的に属地主義といってその行為地の法律が適用されることになるんですけど、インターネット上に国境ないですからね。どこの法律適用するの? って問題があるわけです。
例えば具体的な問題としては、アメリカで合法的に権利処理をして音楽をネット上で流せるサーバがあっても、日本から送信することは違法だとJASRACは考えている(解釈問題)といったことがあります。
日本国著作権法では、公衆送信権とか送信可能化権といった形でインターネット上に著作物流すときに働く権利があるんですが、その辺の取り扱いがアメリカと日本でも色々違うから、そういうことになるわけです。
その辺は分かりにくいので詳しくは述べません(知りたい方は著作権質問スレッドにどうぞ)けれども、そういう法制度の問題が落ち着かないと、技術的なやり方どうこうという話にもならないでしょうね。
法律って基本的に属地主義といってその行為地の法律が適用されることになるんですけど、インターネット上に国境ないですからね。どこの法律適用するの? って問題があるわけです。
例えば具体的な問題としては、アメリカで合法的に権利処理をして音楽をネット上で流せるサーバがあっても、日本から送信することは違法だとJASRACは考えている(解釈問題)といったことがあります。
日本国著作権法では、公衆送信権とか送信可能化権といった形でインターネット上に著作物流すときに働く権利があるんですが、その辺の取り扱いがアメリカと日本でも色々違うから、そういうことになるわけです。
その辺は分かりにくいので詳しくは述べません(知りたい方は著作権質問スレッドにどうぞ)けれども、そういう法制度の問題が落ち着かないと、技術的なやり方どうこうという話にもならないでしょうね。
なんとなく、利用者と著作権について考えてみたくなって、どのトピックに書くべきか悩んだんですが、考え方としてはここかもしれないと思って、ここに書いてみます。
ネットワークというか、インターネットによって著作物を「創作し、発表する」という行為は非常に手軽になりました。そのことは、様々な文化を享受することができる点で非常に喜ばしいことですが、「創作し、発表する」ことが手軽にできるようになると、勢い「利用する」行為についても手軽に行ないたいと考えるようになってきます。
しかし、現状の著作権の姿というのは商業利用される(つまり、商品としての)著作物のことを念頭に置いて考えられており、著作物の利用者についても商業的利用を念頭に置いて構築されています。
つまり、かつてネットワークが普及する前は、著作権の扱いについて考える必要があったものは、商業的な目的で著作物を利用する場合が主であり、私的な利用や非営利で利用する場合は、著作権法の私的利用の範疇に収まるものか、あるいは自由利用の規定が存在しており、煩雑な手続きをする必要があるのは商業的に利用する場合のみであったと云えます。
しかし、ネットワークという新たな流通経路は、著作物の商業的利用と私的利用の間の敷居を非常に低くし、それらを峻別することはほぼ不可能と思われるほどになってしまいました。
このことが、現在の著作権に関する様々な軋轢が生じる理由そのものであると私は考えています。
そして同時に、商業目的であれ、私的目的であれ、様々な著作物が発表され、非常に多くの著作物に触れることができるようになった現在、その著作物を享受する一般消費者にとっては、商品としての著作物の価値が相対的に下がってきていることも事実です。
なぜなら、商品としての著作物は対価を払う必要がありますが、私的に発表された著作物は自由に触れることができ、無料であることが多く、その中には商業的に発表された著作物よりも優れたものも多く含まれているからです。
著作権という権利そのものが、そもそもは商品としての著作物に対して設定されてきたことから考えると、私的に著作物を利用したいと考える場合に著作権の在り方や、様々な著作権法の規定は非常に窮屈で、文化の発展を妨げる側面さえも持ち始めています。しかしながら、それが即ち著作権法を無視しても良いということにはならないのは当然のことです。
個人的には、より緩い著作物の利用を促進するような制度なり仕組みなりを作って、一般利用者が安価に著作物を利用できるようにするべきだと思っていますし、著作物を元にお金を稼ごうと思うと、著作者が著作権を丸ごと預けるような行為に出ないといけない流通の仕組みも変えなきゃならないと思ってるのですが…さてはて。
こうやれば一挙解決!なんていう劇的な案は出てこないにしても、もうちょっとどうにかなりそうなやり方はないもんですかね。
ネットワークというか、インターネットによって著作物を「創作し、発表する」という行為は非常に手軽になりました。そのことは、様々な文化を享受することができる点で非常に喜ばしいことですが、「創作し、発表する」ことが手軽にできるようになると、勢い「利用する」行為についても手軽に行ないたいと考えるようになってきます。
しかし、現状の著作権の姿というのは商業利用される(つまり、商品としての)著作物のことを念頭に置いて考えられており、著作物の利用者についても商業的利用を念頭に置いて構築されています。
つまり、かつてネットワークが普及する前は、著作権の扱いについて考える必要があったものは、商業的な目的で著作物を利用する場合が主であり、私的な利用や非営利で利用する場合は、著作権法の私的利用の範疇に収まるものか、あるいは自由利用の規定が存在しており、煩雑な手続きをする必要があるのは商業的に利用する場合のみであったと云えます。
しかし、ネットワークという新たな流通経路は、著作物の商業的利用と私的利用の間の敷居を非常に低くし、それらを峻別することはほぼ不可能と思われるほどになってしまいました。
このことが、現在の著作権に関する様々な軋轢が生じる理由そのものであると私は考えています。
そして同時に、商業目的であれ、私的目的であれ、様々な著作物が発表され、非常に多くの著作物に触れることができるようになった現在、その著作物を享受する一般消費者にとっては、商品としての著作物の価値が相対的に下がってきていることも事実です。
なぜなら、商品としての著作物は対価を払う必要がありますが、私的に発表された著作物は自由に触れることができ、無料であることが多く、その中には商業的に発表された著作物よりも優れたものも多く含まれているからです。
著作権という権利そのものが、そもそもは商品としての著作物に対して設定されてきたことから考えると、私的に著作物を利用したいと考える場合に著作権の在り方や、様々な著作権法の規定は非常に窮屈で、文化の発展を妨げる側面さえも持ち始めています。しかしながら、それが即ち著作権法を無視しても良いということにはならないのは当然のことです。
個人的には、より緩い著作物の利用を促進するような制度なり仕組みなりを作って、一般利用者が安価に著作物を利用できるようにするべきだと思っていますし、著作物を元にお金を稼ごうと思うと、著作者が著作権を丸ごと預けるような行為に出ないといけない流通の仕組みも変えなきゃならないと思ってるのですが…さてはて。
こうやれば一挙解決!なんていう劇的な案は出てこないにしても、もうちょっとどうにかなりそうなやり方はないもんですかね。
日本の著作権法について、全員が専門家になる必要はないけど「各人のレベル」において、皆が知る必要がありますよね。
道路交通法について司法関係者はプロとしての知識が必要だし、運転を許可された者は内容についての知識があるハズですが第**条1項に該当するとかしないとかまでは事故でも起こさない限り覚えていないし関係ないけど一応、遵守している。クルマを運転しないから道路交通法は知らなくてもいいということにもならない。幼稚園児もクルマは左、人は右、赤止まれ、青進め程度は知らなければ自分の命も守れない時代なのだから。
文化庁関係者によれば日本の著作権法は権利の保護については世界のトップレベルにあるとのことです。誰もが簡単に利用できる時代になったからこそ「自分の権利と他人の権利の衝突」について考えなければならない。
私は、ネットラジオを行ってはいないが、ネットラジオを運営する人がコンテンツ利用に不便を感じ、著作権を不快に思い脱法行為をすることが許されるワケではないでしょう。あなたのネットラジオを誰かがそのまま録音し、勝手にCD化して商売にされたら(売れる売れないは関係なく)あなたは「著作権法」を楯にしなければ戦えないはずです。
先ずは、冷静に日本の著作権法を学んで、意義ある議論になればいいいなと期待しています。
道路交通法について司法関係者はプロとしての知識が必要だし、運転を許可された者は内容についての知識があるハズですが第**条1項に該当するとかしないとかまでは事故でも起こさない限り覚えていないし関係ないけど一応、遵守している。クルマを運転しないから道路交通法は知らなくてもいいということにもならない。幼稚園児もクルマは左、人は右、赤止まれ、青進め程度は知らなければ自分の命も守れない時代なのだから。
文化庁関係者によれば日本の著作権法は権利の保護については世界のトップレベルにあるとのことです。誰もが簡単に利用できる時代になったからこそ「自分の権利と他人の権利の衝突」について考えなければならない。
私は、ネットラジオを行ってはいないが、ネットラジオを運営する人がコンテンツ利用に不便を感じ、著作権を不快に思い脱法行為をすることが許されるワケではないでしょう。あなたのネットラジオを誰かがそのまま録音し、勝手にCD化して商売にされたら(売れる売れないは関係なく)あなたは「著作権法」を楯にしなければ戦えないはずです。
先ずは、冷静に日本の著作権法を学んで、意義ある議論になればいいいなと期待しています。
>・現代に於いてこの内容をどう解釈したら良いのでしょうか?
新聞協会の見解ですが、これは、市民の著作権に関する無知
に付け込んで、超法規的、我田引水的な解釈を押し付けている
としか自分には思えません。松本邦彦・山形大学助教授の
「リンク問題資料室」でも槍玉に挙げられています。
http://www-h.yamagata-u.ac.jp/~matumoto/link/link_check.htm
(以下引用)
しかしその理由も、インターネット上の「引用」について事前審査を求めるのかどうかも不明確なので読み進めると、「本文」にて、
新聞・通信社が発信する記事、ニュース速報、写真、図版類には著作権があり、無断で使用すれば、著作権侵害になります。使用を希望する場合には著作権者の承諾が欠かせません。引用や、記事の要旨紹介などで、法的には著作権者の承諾なく使えるというケースでも、本当にその条件を満たしているかどうか、微妙な場合も少なくありません。また、インターネットの特徴の一つであるリンクについても、表示の仕方によっては、問題が発生する可能性がある場合も少なくありません。
---- とありますが、具体的にどういう「表示の仕方」を問題にしているのかは不明なままです(おそらくはフレーム内リンクを問題にしているのでしょうけど)。ただ、どうやら「引用」においても事前審査を要求するつもりであることが明らかになってきました。これに続けてのおしまいの段落は、
利用者の側が、情報をどのような形で利用しようとしているか、動機も、利用形態もまちまちなため、新聞・通信社としても、個々の事情をうかがわないと利用を承諾していいものかどうか、一般論としてだけでは結論をお伝えすることはむずかしい側面もあります。リンクや引用の場合も含め、インターネットやLANの上での利用を希望されるときは、まず、発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談をしていただくよう、お願いします。
---- とあり、「引用」であっても事前審査をする気であることが明らかになりました。「動機」を問うことを含めて論外ですね。
(引用終わり)
私が新聞不信になった理由の一つは、紛れもなくこの新聞
協会の見解です。言論・表現の自由を謳ったところで、それは
自分達が何とでも言う自由のことであって、市民の権利など
屁とも思っていない(笑)。
ついこの前も、自分の日記で、読売新聞の「無断引用」と
いう見出しを槍玉に挙げたのですが、著作権法上の要件を
満たした「引用」であれば「無断」で行える筈で、「無断引用」
なるおかしな言葉を使って著作権法の趣旨を捻じ曲げていると
感じました。読売といえば、見出しに著作権を主張してデジタ
ルアライアンスと争っているわけですが、高裁も(恐ろしく
低額の)賠償は認めたものの「見出しの著作権」は認めません
でした。でも言葉を捻じ曲げることが出来るから創作、著作物
なのかと皮肉も言いたくなります。
見出しの著作権といい、中古ゲーム裁判といい、権利者側の
言い分は往々にして外れるものです。こういったものに惑わさ
れず、自分できちんと調べてリテラシーを高めることが必要か
と思います。
悪徳商法?マニアックス
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
では、「悪のニュース」で、サイト訪問者が自分で新聞記事を
登録できる機能があるのですが、その際リンクが張られるだけ
でなく、自動的にコピーが作成されます。他のサイトに「悪の
ニュース」を埋め込むことも可能で、例えば、
弁護士紀藤正樹のLINC
http://homepage1.nifty.com/kito/
では、「消費者ニュース速報」にこれを利用しています
(「一般」「芸能」ニュースに関してはデジタルアライアンス
を利用していたので、配信停止中です)。
この仕組みに対して、以前、産経新聞社の編集者(と称する
人物)が「記事削除要請」を出したことがあります。
【記事削除要請】
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg89776.html
産経新聞の主張を考えてみる会
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg90148.html
なお著作権からは外れますが、実名報道に関してもこちらで
考察しています。
実名報道と人権を考えるツリー
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg90215.html
この問題に関して、「悪マニ」管理人の反論は
(1)そもそも、元の新聞記事は著作物ではない。
(2)仮に著作物であるとしても、「引用」の範囲である。
というものでした。
http://beyond.2log.net/akutoku/topics/topics2003.html
(5月6日から15日の項を参照)
新聞協会の見解ですが、これは、市民の著作権に関する無知
に付け込んで、超法規的、我田引水的な解釈を押し付けている
としか自分には思えません。松本邦彦・山形大学助教授の
「リンク問題資料室」でも槍玉に挙げられています。
http://www-h.yamagata-u.ac.jp/~matumoto/link/link_check.htm
(以下引用)
しかしその理由も、インターネット上の「引用」について事前審査を求めるのかどうかも不明確なので読み進めると、「本文」にて、
新聞・通信社が発信する記事、ニュース速報、写真、図版類には著作権があり、無断で使用すれば、著作権侵害になります。使用を希望する場合には著作権者の承諾が欠かせません。引用や、記事の要旨紹介などで、法的には著作権者の承諾なく使えるというケースでも、本当にその条件を満たしているかどうか、微妙な場合も少なくありません。また、インターネットの特徴の一つであるリンクについても、表示の仕方によっては、問題が発生する可能性がある場合も少なくありません。
---- とありますが、具体的にどういう「表示の仕方」を問題にしているのかは不明なままです(おそらくはフレーム内リンクを問題にしているのでしょうけど)。ただ、どうやら「引用」においても事前審査を要求するつもりであることが明らかになってきました。これに続けてのおしまいの段落は、
利用者の側が、情報をどのような形で利用しようとしているか、動機も、利用形態もまちまちなため、新聞・通信社としても、個々の事情をうかがわないと利用を承諾していいものかどうか、一般論としてだけでは結論をお伝えすることはむずかしい側面もあります。リンクや引用の場合も含め、インターネットやLANの上での利用を希望されるときは、まず、発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談をしていただくよう、お願いします。
---- とあり、「引用」であっても事前審査をする気であることが明らかになりました。「動機」を問うことを含めて論外ですね。
(引用終わり)
私が新聞不信になった理由の一つは、紛れもなくこの新聞
協会の見解です。言論・表現の自由を謳ったところで、それは
自分達が何とでも言う自由のことであって、市民の権利など
屁とも思っていない(笑)。
ついこの前も、自分の日記で、読売新聞の「無断引用」と
いう見出しを槍玉に挙げたのですが、著作権法上の要件を
満たした「引用」であれば「無断」で行える筈で、「無断引用」
なるおかしな言葉を使って著作権法の趣旨を捻じ曲げていると
感じました。読売といえば、見出しに著作権を主張してデジタ
ルアライアンスと争っているわけですが、高裁も(恐ろしく
低額の)賠償は認めたものの「見出しの著作権」は認めません
でした。でも言葉を捻じ曲げることが出来るから創作、著作物
なのかと皮肉も言いたくなります。
見出しの著作権といい、中古ゲーム裁判といい、権利者側の
言い分は往々にして外れるものです。こういったものに惑わさ
れず、自分できちんと調べてリテラシーを高めることが必要か
と思います。
悪徳商法?マニアックス
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
では、「悪のニュース」で、サイト訪問者が自分で新聞記事を
登録できる機能があるのですが、その際リンクが張られるだけ
でなく、自動的にコピーが作成されます。他のサイトに「悪の
ニュース」を埋め込むことも可能で、例えば、
弁護士紀藤正樹のLINC
http://homepage1.nifty.com/kito/
では、「消費者ニュース速報」にこれを利用しています
(「一般」「芸能」ニュースに関してはデジタルアライアンス
を利用していたので、配信停止中です)。
この仕組みに対して、以前、産経新聞社の編集者(と称する
人物)が「記事削除要請」を出したことがあります。
【記事削除要請】
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg89776.html
産経新聞の主張を考えてみる会
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg90148.html
なお著作権からは外れますが、実名報道に関してもこちらで
考察しています。
実名報道と人権を考えるツリー
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg90215.html
この問題に関して、「悪マニ」管理人の反論は
(1)そもそも、元の新聞記事は著作物ではない。
(2)仮に著作物であるとしても、「引用」の範囲である。
というものでした。
http://beyond.2log.net/akutoku/topics/topics2003.html
(5月6日から15日の項を参照)
問題は、「リンクの張り方」ですよね。
* * *
ケース1
「(●●新聞の記事)について・・・・・と思う。」()部分にリンク
と言うような場合であれば、問題ないです。
なにも「引用」していないからです。
* * *
ケース2
(見出し)←()部分にリンク
>記事引用
についての私の見解は・・・・
と言うような場合も、ほとんど問題ないでしょう。
ただ、この場合は「引用」があるので、ケース1とは若干異なります。
リンク切れ後も引用元がわかるようにと言う点では、
「●●新聞の●月●日付の記事(見出し)」
の方が望ましいのは明らかです。
記事のトレーサビリティを考えると、ここまでしないと、
「引用元を明らかにする」条件を満たさないケースが考えられるからです。
(トレーサビリティが相手に依存した状況になっていると言うことです。)
また、引用記事が署名付きの(記者の名前が出ている)場合には、
著作者人格権への配慮も考え、その記者の名前も明記することが望ましいです。
* * *
ただ、結構、不必要な「引用」ってやっちゃいます。
例えば、雪兎さんが最後に紹介されている、「悪マニ」管理人さんの記事を題材にちょっと思考実験をしてみました。
5月12日分では、3紙から、恐らく1つの事件についての記事が丸々「引用」されています。ただ、この場合、同じ1つの事件において、新聞各紙でどの程度表現に違いがあるかを検証し、「創作性を否定し、著作物でないこと」を主張するための行為なので、「必要最小限」だろうと思います。
(私自身は、その若干の違いこそ、1つの紙面上文字数が限られている新聞では重要で、創作性の発揮する部分だろうと思うので、当該記事は著作物だと思います。)
一方、5月6日分では、MacFanの表紙の写真が掲載されています。これは「必要最小限」の中に入るでしょうか?無くても、記事の信憑性・説得性になんら影響はありません。よって、必要不可欠で最小限度ではないので、「引用ではない」と思います。
まぁ、私個人の見解ですが。
* * *
自分なりに「引用の最小限度化」を探る努力をしつつ、しっかりと元記事へ辿り着く最大限の配慮を怠らない。
これを維持していれば、自分の主張の中での引用で心配することはありませんよ。
* * *
ケース1
「(●●新聞の記事)について・・・・・と思う。」()部分にリンク
と言うような場合であれば、問題ないです。
なにも「引用」していないからです。
* * *
ケース2
(見出し)←()部分にリンク
>記事引用
についての私の見解は・・・・
と言うような場合も、ほとんど問題ないでしょう。
ただ、この場合は「引用」があるので、ケース1とは若干異なります。
リンク切れ後も引用元がわかるようにと言う点では、
「●●新聞の●月●日付の記事(見出し)」
の方が望ましいのは明らかです。
記事のトレーサビリティを考えると、ここまでしないと、
「引用元を明らかにする」条件を満たさないケースが考えられるからです。
(トレーサビリティが相手に依存した状況になっていると言うことです。)
また、引用記事が署名付きの(記者の名前が出ている)場合には、
著作者人格権への配慮も考え、その記者の名前も明記することが望ましいです。
* * *
ただ、結構、不必要な「引用」ってやっちゃいます。
例えば、雪兎さんが最後に紹介されている、「悪マニ」管理人さんの記事を題材にちょっと思考実験をしてみました。
5月12日分では、3紙から、恐らく1つの事件についての記事が丸々「引用」されています。ただ、この場合、同じ1つの事件において、新聞各紙でどの程度表現に違いがあるかを検証し、「創作性を否定し、著作物でないこと」を主張するための行為なので、「必要最小限」だろうと思います。
(私自身は、その若干の違いこそ、1つの紙面上文字数が限られている新聞では重要で、創作性の発揮する部分だろうと思うので、当該記事は著作物だと思います。)
一方、5月6日分では、MacFanの表紙の写真が掲載されています。これは「必要最小限」の中に入るでしょうか?無くても、記事の信憑性・説得性になんら影響はありません。よって、必要不可欠で最小限度ではないので、「引用ではない」と思います。
まぁ、私個人の見解ですが。
* * *
自分なりに「引用の最小限度化」を探る努力をしつつ、しっかりと元記事へ辿り着く最大限の配慮を怠らない。
これを維持していれば、自分の主張の中での引用で心配することはありませんよ。
著作権の問題からは少し外れますが、リンク問題に関して、
思うところを述べます。
>ただ、実際にニュースサイト等では、リンクについてもその旨の連絡が必要であると明記しているところも多いですから、いまはそれに従っています。
単なるリンクであれば、「引用」にすら当たらず(学術論文
で文献を明示するのと同じ)、著作権上の問題は生じません。
従って、リンク元サイトが何と言おうと、リンクに許諾は不要
です。
松本助教授の「リンク問題資料集」
http://www-h.yamagata-u.ac.jp/~matumoto/link/link_index.htm
の他、
後藤斉・東北大学助教授
http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/webpolicy.html
夏井高人・明治大学教授
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/Web_info.htm
あたりが「無断リンク禁止」批判で有名で、これらのサイトに
一通り読まれることをお勧めします。
インターネットは、そもそもリンクしあうことによって情報
が有機的に結びつき発展してきたのであって、「無断リンク禁止」
はインターネットの理念そのものを否定するものだと思います。
まあ、法のプロ集団の日弁連ですら、過去に掲げていた
サイトへのリンク条件を撤回して180度転換したという、情け
ないことをやらかしたくらいですから。
http://ascii24.com/news/i/topi/article/2002/06/17/636577-000.html
(この記事の中で、前出の後藤助教授が新聞協会の名前も出し
ています)
http://ascii24.com/news/i/topi/article/2002/07/02/636937-000.html
思うところを述べます。
>ただ、実際にニュースサイト等では、リンクについてもその旨の連絡が必要であると明記しているところも多いですから、いまはそれに従っています。
単なるリンクであれば、「引用」にすら当たらず(学術論文
で文献を明示するのと同じ)、著作権上の問題は生じません。
従って、リンク元サイトが何と言おうと、リンクに許諾は不要
です。
松本助教授の「リンク問題資料集」
http://www-h.yamagata-u.ac.jp/~matumoto/link/link_index.htm
の他、
後藤斉・東北大学助教授
http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/webpolicy.html
夏井高人・明治大学教授
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/Web_info.htm
あたりが「無断リンク禁止」批判で有名で、これらのサイトに
一通り読まれることをお勧めします。
インターネットは、そもそもリンクしあうことによって情報
が有機的に結びつき発展してきたのであって、「無断リンク禁止」
はインターネットの理念そのものを否定するものだと思います。
まあ、法のプロ集団の日弁連ですら、過去に掲げていた
サイトへのリンク条件を撤回して180度転換したという、情け
ないことをやらかしたくらいですから。
http://ascii24.com/news/i/topi/article/2002/06/17/636577-000.html
(この記事の中で、前出の後藤助教授が新聞協会の名前も出し
ています)
http://ascii24.com/news/i/topi/article/2002/07/02/636937-000.html
>各氏の意見がはたして社会的なコンセンサスを得ているのか
>どうかという観点で見た場合一抹の不安が残ります。
繰り返し述べますが、そもそも、インターネット自体が
リンクする、されることを前提としたシステムであって、
リンクに許諾を前提としていたのであれば、インターネットは
ここまで発展していなかっただろうという指摘もあります。
無断リンクされるのが嫌なら認証を要する会員制サイトにする
か、そもそもサイトを公開などしなければよいことです。
同様に、リンク先をトップページに限定したいのであれば、
cgiか何かを使って、技術的にトップページを経由しなければ
下位ページにいけないような仕組みを構築するのが筋だと考え
ます。
>ネット上でのエチケットあるいはむしろ一般社会における礼節の問題として、著作権者側の主張にもある程度配慮することは、現段階ではまだ必要なのではないでしょうか。
個人サイトならともかく、企業・団体(目的を持って作られ
た組織に「人格」を擬制しているので「法人」であり、
「個人」の人格とは意味合いが異なります))、ましてや
官公庁や独立行政法人は、その存在自体が公益性を帯びている
わけですから、「ネット上でのエチケットあるいはむしろ一般
社会における礼節の問題」よりも優先すると思います。
ちなみに、「ネット上のエチケット」に関しては、明文化さ
れたものがあります(RFC1855)
http://www.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855j.html
が、そのなかでも無断リンクはエチケット違反とする文言は
ありません。無断リンクはエチケット違反とする考えは元々
無かったものであり、どうやらそれを言い出したのは、日本で
商業ネットが勃興した頃の日本人だったようです。同じことを
海外でも言った人がいたようですが、いずれにせよネット一般
のエチケットとは成り得ていません。
>ちょっと慎重に考えすぎでしょうか。
無断リンク禁止というのは全く根拠のないものであり、権利
者側からの納得のいく根拠が示されたという事例を知りません。
それに萎縮していたのでは、かえって「リンクに許諾が必要」
という悪弊を拡大しかねないと思うので、私は反対です。
>リンクごときで妙なトラブルには巻き込まれたくありませんし。
私であれば、自らの言論表現の自由を守るために戦う覚悟が
あります。憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
は、お飾りではありません。
>どうかという観点で見た場合一抹の不安が残ります。
繰り返し述べますが、そもそも、インターネット自体が
リンクする、されることを前提としたシステムであって、
リンクに許諾を前提としていたのであれば、インターネットは
ここまで発展していなかっただろうという指摘もあります。
無断リンクされるのが嫌なら認証を要する会員制サイトにする
か、そもそもサイトを公開などしなければよいことです。
同様に、リンク先をトップページに限定したいのであれば、
cgiか何かを使って、技術的にトップページを経由しなければ
下位ページにいけないような仕組みを構築するのが筋だと考え
ます。
>ネット上でのエチケットあるいはむしろ一般社会における礼節の問題として、著作権者側の主張にもある程度配慮することは、現段階ではまだ必要なのではないでしょうか。
個人サイトならともかく、企業・団体(目的を持って作られ
た組織に「人格」を擬制しているので「法人」であり、
「個人」の人格とは意味合いが異なります))、ましてや
官公庁や独立行政法人は、その存在自体が公益性を帯びている
わけですから、「ネット上でのエチケットあるいはむしろ一般
社会における礼節の問題」よりも優先すると思います。
ちなみに、「ネット上のエチケット」に関しては、明文化さ
れたものがあります(RFC1855)
http://www.cgh.ed.jp/netiquette/rfc1855j.html
が、そのなかでも無断リンクはエチケット違反とする文言は
ありません。無断リンクはエチケット違反とする考えは元々
無かったものであり、どうやらそれを言い出したのは、日本で
商業ネットが勃興した頃の日本人だったようです。同じことを
海外でも言った人がいたようですが、いずれにせよネット一般
のエチケットとは成り得ていません。
>ちょっと慎重に考えすぎでしょうか。
無断リンク禁止というのは全く根拠のないものであり、権利
者側からの納得のいく根拠が示されたという事例を知りません。
それに萎縮していたのでは、かえって「リンクに許諾が必要」
という悪弊を拡大しかねないと思うので、私は反対です。
>リンクごときで妙なトラブルには巻き込まれたくありませんし。
私であれば、自らの言論表現の自由を守るために戦う覚悟が
あります。憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
は、お飾りではありません。
リンクの是非については私は雪兎さんの意見に賛成です。
このような問題に対する見解を求める先で注意しなければならないのは、その見解を出している主体と今問題にしている著作物の著作者の関係です。
例えば今のこの問題でいうと、新聞記事のリンクに対する見解が「新聞協会」から出されていれば、それは当然新聞社に有利な見解を出している、と見るべきである、ということです。
著作者の権利(利用は許諾の上で有料でよろしく)とその利用者の権利(無断でタダで使いたい)が必ず衝突する、というのが著作権の大きな特徴ですから、著作物の利用などについての是非を求める際にはその双方の言い分に耳を傾け、そしてさらに第三者的な観点から法律や契約、その他の状況などを含めて判定されるべきものである、と私は考えます。
このような問題に対する見解を求める先で注意しなければならないのは、その見解を出している主体と今問題にしている著作物の著作者の関係です。
例えば今のこの問題でいうと、新聞記事のリンクに対する見解が「新聞協会」から出されていれば、それは当然新聞社に有利な見解を出している、と見るべきである、ということです。
著作者の権利(利用は許諾の上で有料でよろしく)とその利用者の権利(無断でタダで使いたい)が必ず衝突する、というのが著作権の大きな特徴ですから、著作物の利用などについての是非を求める際にはその双方の言い分に耳を傾け、そしてさらに第三者的な観点から法律や契約、その他の状況などを含めて判定されるべきものである、と私は考えます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
著作権 更新情報
-
最新のアンケート
著作権のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90053人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208284人