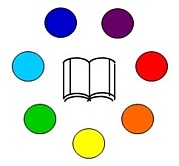桜満開の中、風が強くて肌寒い日の午前、今話題のノンフィクション、ブレイディみかこ著の『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を課題本に6人での読書会を開催しました。
(感染予防のため、全員マスク着用と、ドアを開けての換気、読書会後のランチを自粛としました。)
わかりやすくて、巧みで、ユーモアがあり、読んでいて非常におもしろいと感じる文章で、自身の息子を通した英国での様々な問題を提起しつつ、読者に考えさせる話題盛りだくさんの課題本でした。
読書会でも様々な話題があがり、拙い司会でしたが、互いに会話が飛び交っていたので、結果オーライで楽しい読書会になったかと思います。
まずはいつも通り大まかな感想を聴いて絵みると、
・読みやすい。著者本人の成長の記録。
・無知と頭が悪いことは違う。言葉で受け取るイメージが違うので気を付けたい。
・性教育に対しての感覚が海外と日本で違う。
・人気の理由も実感、考えさせられるいい本。
・暗い本かと思って読んでみたらよかった。
・英国の音楽が好きで、好きなバンドが出てきてテンションが上がった。
・小説のような伏線もありおもしろい。
・多様性はいいイメージだけどやっぱり問題があると感じた。
・性教育や、演劇で気持ちを伝える教育など、生きるための教育が進んでいる。
・決めつけるほうが楽だけどエンパシーは大事。
・教育環境がうらやましい。日本は正しいことを教える管理教育。変わってほしい。
・自分は多様性の乏しい環境で大人になった。
・読書会も対話で多様性を学ぶことができる。
・仕事が変わった関係でマイノリティな気分にあったのでリンクして読めた。
・英国はブレグジットもあって難しい環境にある。
などなど、書ききれないほどたくさんの感想をいただきました。
中でも一番大きな話題となったのは、教育についてだったように思います。
英国と日本での教育の違い、同じ英国でも学校によっての教育の違いがあり、著者の息子が通う元底辺中学校の教育を通して、日本の教育の問題点を様々な角度から意見交換できたと思います。
一つ例を挙げると、教育に演劇を取り入れているという話から派生した、喜怒哀楽の表現の難しさ。
喜怒哀楽を表現することはコミュニケーションの上で大切なことだけれど、実際は自身が思っている感情表現が相手には伝わっていないことがよくあるということ。
たしかに自身も含め周りを見渡せば、感情表現が正しく伝わらないがためのコミュニケーション障害が起きているような気もします。
マイノリティについても話題になりました。
自分がマイノリティだと思ったことありますか?という参加者からの質問があり、それぞれに自分だけ周りと違うと感じた行動や思考、天然現象など経験談を語り合って盛り上がりました。
普段周りには受け入れてもらえない独特な発言や体験も読書会では発することができて、そんなところも読書会の魅力なんだなと改めて思ったのでした。
いじめについても話題になりました。
一部の人を仲間はずれにするような状況はどうやって起こるのか?村八分とかって誰が得をするのか?といった疑問が出て、誰かを攻撃することによって自身の存在を示そうとする人がいる。誰かを罰することで脳は快感を得るようにできている。敵を一人つくることで団結力を維持しようとする思考が働くのではないか。といったような意見が挙がりました。
読書会では言っていなかったことを少し。
差別的な発言がひどい息子の友人の話のところで、著者が、「無知なんだよ。」と息子に話すシーンがあり、「つまりバカなの?」と返す息子に対して、「頭が悪いことと無知は違う。知らないことは、知るときが来ればその人は無知ではなくなる。」と、いったような会話があります。
ここで思ったのは、無知はやはり悲惨な状況を生んでしまうということ。けれど、その人が知ることによって悲惨な状況を一つ回避できるということ。
悲惨な状況を生まないために知らなければいけないことがあるのだと思います。
そのためには偏りのない読書、そして多種多様な人との対話が必要であり、ここでも読書会は有効であると思ったり。
この他にもたくさんの話題がありました。
今回は、読んだけれど直前になって参加できなかったという方たちもいました。
是非たくさんのコメント、待ってま〜す。
(感染予防のため、全員マスク着用と、ドアを開けての換気、読書会後のランチを自粛としました。)
わかりやすくて、巧みで、ユーモアがあり、読んでいて非常におもしろいと感じる文章で、自身の息子を通した英国での様々な問題を提起しつつ、読者に考えさせる話題盛りだくさんの課題本でした。
読書会でも様々な話題があがり、拙い司会でしたが、互いに会話が飛び交っていたので、結果オーライで楽しい読書会になったかと思います。
まずはいつも通り大まかな感想を聴いて絵みると、
・読みやすい。著者本人の成長の記録。
・無知と頭が悪いことは違う。言葉で受け取るイメージが違うので気を付けたい。
・性教育に対しての感覚が海外と日本で違う。
・人気の理由も実感、考えさせられるいい本。
・暗い本かと思って読んでみたらよかった。
・英国の音楽が好きで、好きなバンドが出てきてテンションが上がった。
・小説のような伏線もありおもしろい。
・多様性はいいイメージだけどやっぱり問題があると感じた。
・性教育や、演劇で気持ちを伝える教育など、生きるための教育が進んでいる。
・決めつけるほうが楽だけどエンパシーは大事。
・教育環境がうらやましい。日本は正しいことを教える管理教育。変わってほしい。
・自分は多様性の乏しい環境で大人になった。
・読書会も対話で多様性を学ぶことができる。
・仕事が変わった関係でマイノリティな気分にあったのでリンクして読めた。
・英国はブレグジットもあって難しい環境にある。
などなど、書ききれないほどたくさんの感想をいただきました。
中でも一番大きな話題となったのは、教育についてだったように思います。
英国と日本での教育の違い、同じ英国でも学校によっての教育の違いがあり、著者の息子が通う元底辺中学校の教育を通して、日本の教育の問題点を様々な角度から意見交換できたと思います。
一つ例を挙げると、教育に演劇を取り入れているという話から派生した、喜怒哀楽の表現の難しさ。
喜怒哀楽を表現することはコミュニケーションの上で大切なことだけれど、実際は自身が思っている感情表現が相手には伝わっていないことがよくあるということ。
たしかに自身も含め周りを見渡せば、感情表現が正しく伝わらないがためのコミュニケーション障害が起きているような気もします。
マイノリティについても話題になりました。
自分がマイノリティだと思ったことありますか?という参加者からの質問があり、それぞれに自分だけ周りと違うと感じた行動や思考、天然現象など経験談を語り合って盛り上がりました。
普段周りには受け入れてもらえない独特な発言や体験も読書会では発することができて、そんなところも読書会の魅力なんだなと改めて思ったのでした。
いじめについても話題になりました。
一部の人を仲間はずれにするような状況はどうやって起こるのか?村八分とかって誰が得をするのか?といった疑問が出て、誰かを攻撃することによって自身の存在を示そうとする人がいる。誰かを罰することで脳は快感を得るようにできている。敵を一人つくることで団結力を維持しようとする思考が働くのではないか。といったような意見が挙がりました。
読書会では言っていなかったことを少し。
差別的な発言がひどい息子の友人の話のところで、著者が、「無知なんだよ。」と息子に話すシーンがあり、「つまりバカなの?」と返す息子に対して、「頭が悪いことと無知は違う。知らないことは、知るときが来ればその人は無知ではなくなる。」と、いったような会話があります。
ここで思ったのは、無知はやはり悲惨な状況を生んでしまうということ。けれど、その人が知ることによって悲惨な状況を一つ回避できるということ。
悲惨な状況を生まないために知らなければいけないことがあるのだと思います。
そのためには偏りのない読書、そして多種多様な人との対話が必要であり、ここでも読書会は有効であると思ったり。
この他にもたくさんの話題がありました。
今回は、読んだけれど直前になって参加できなかったという方たちもいました。
是非たくさんのコメント、待ってま〜す。
|
|
|
|
コメント(4)
コロナ騒動の中開催していただきありがとうございました。参加メンバーの方々もありがとうございました。
以下感想です↓
教育について改めて考察ができました。自分は教育の目的とは何かを日頃意識して考える癖があります。教育の目的とは「自立し、幸福になる」ことではないかと考えています。この本は「親子の成長の記録」であると思いました。ただ、また読みたいかと聞かれれば読みたいとは思いませんでした。冷徹な言い方ですみませんが、所詮他人の人生なんだよなぁ〜という見方もあるからです。そして子供の可能性や成長を見守る表現にはとても尊敬できました。保管するのでいつか子供が興味を持って読んでくれると嬉しく思います。
あと会でマイノリティーというに過敏に反応してしまった自分をゆっくり反省したいと思います。
会の最後でゆりかさんが「どうやったら貧困が無くなるか」とおっしゃっていました。自分の考えでは「無くなりません」との結論です。贅沢な悩みです。なぜなら諸悪の根源には連続性がある可能性が高いと考察しているからです。養護施設の子供とふれあう機会が多々ある自分の経験上での考えです。例えば、いじめを無くそう!差別を無くそう!虐待を無くそう!自殺を無くそう!…素晴らしい正義感です。
そんな世界も見てみたいですが、これらが世界から無くなった事例が知りたいです。自分が養護施設の子供と長年に渡りふれあう最大の目的とは「ただの思い出つくり」です。必ずしもこの行動が良しとされるわけではありません。わずかな時間と手間で虐待やネグレクトをその子たちが大人になって家族を持った時に過去の思い出を参考に0ではなく低減できるか…ある意味個人勝手な大実験であると自負しています。そしてもっと人を幸せに導けるチカラが欲しいと願っています。養護施設においては貧困を生んだ要因の一つに「児童福祉法」に社会が甘えてきた歴史的な側面もあります。これ以上は長くなるのでここまでにします。
とにかく根が深い!(笑)
話が長くなりました。
色々と生活環境の変化が多い時期になるかと思いますが健康で乗り切りましょう。次の機会もよろしくお願いします。
以下感想です↓
教育について改めて考察ができました。自分は教育の目的とは何かを日頃意識して考える癖があります。教育の目的とは「自立し、幸福になる」ことではないかと考えています。この本は「親子の成長の記録」であると思いました。ただ、また読みたいかと聞かれれば読みたいとは思いませんでした。冷徹な言い方ですみませんが、所詮他人の人生なんだよなぁ〜という見方もあるからです。そして子供の可能性や成長を見守る表現にはとても尊敬できました。保管するのでいつか子供が興味を持って読んでくれると嬉しく思います。
あと会でマイノリティーというに過敏に反応してしまった自分をゆっくり反省したいと思います。
会の最後でゆりかさんが「どうやったら貧困が無くなるか」とおっしゃっていました。自分の考えでは「無くなりません」との結論です。贅沢な悩みです。なぜなら諸悪の根源には連続性がある可能性が高いと考察しているからです。養護施設の子供とふれあう機会が多々ある自分の経験上での考えです。例えば、いじめを無くそう!差別を無くそう!虐待を無くそう!自殺を無くそう!…素晴らしい正義感です。
そんな世界も見てみたいですが、これらが世界から無くなった事例が知りたいです。自分が養護施設の子供と長年に渡りふれあう最大の目的とは「ただの思い出つくり」です。必ずしもこの行動が良しとされるわけではありません。わずかな時間と手間で虐待やネグレクトをその子たちが大人になって家族を持った時に過去の思い出を参考に0ではなく低減できるか…ある意味個人勝手な大実験であると自負しています。そしてもっと人を幸せに導けるチカラが欲しいと願っています。養護施設においては貧困を生んだ要因の一つに「児童福祉法」に社会が甘えてきた歴史的な側面もあります。これ以上は長くなるのでここまでにします。
とにかく根が深い!(笑)
話が長くなりました。
色々と生活環境の変化が多い時期になるかと思いますが健康で乗り切りましょう。次の機会もよろしくお願いします。
まるちゃん、コメントありがと〜待ってました〜
教育の目的は「自立し、幸福になる」というのは、まさにその通りだと思います。一人一人が自らを幸せにすることができれば、この世から不幸な人はいなくなります。そして、本当の意味で自分のことを幸せにすることができるのは、各々自分しかいないのだと思います。
あと、「どうやったら貧困が無くなるか」という大事な話題を思い出させてくれてありがとう〜忘れてた(^_^;)
貧困を無くすためには教育が重要だ、けれど、充分な教育を受けて高学歴となった人でも、貧困に陥らないとは限らない。という話をしたようなしていないような…。
やはり、教育と言っても生きるための教育が重要なのであって、日本ではそういった教育が不充分なんだろうと思われる。
まるちゃんの言うように、「無くなりません」というのもその通りだと思うし、0にすることはできなくても0に近づけていくことはできるはずで、そのためにはどうしたらよいのかと考えることは無駄ではないはずです。「ファクトフルネス」で学んだように、世界の貧困は減り続けているし、そのために努力している人たちがたくさんいるということも知っておきたい。
ただ、貧困の減少にもこれ以上下がらないという限界があるだろうし、日本での貧困率の推移はほぼ横ばいとなっています。
「どうしたら貧困が無くなるか」という疑問についてもう一度考えてみると、「父が娘に語る経済の話」で学んだように、資本主義に大きな問題があるように思います。簡単に言うと、資本主義というゲームが上手い人とそうでない人がいて、上手い人は富み、苦手な人は貧困に陥ってしまう。その仕組は複雑なんだけれど簡単に言えばそういうことなのではないか。なので、本気で貧困を無くそうとするなら、ゲームのルール(資本主義)から変えていく必要を感じます。
少しずつでも…。
教育の目的は「自立し、幸福になる」というのは、まさにその通りだと思います。一人一人が自らを幸せにすることができれば、この世から不幸な人はいなくなります。そして、本当の意味で自分のことを幸せにすることができるのは、各々自分しかいないのだと思います。
あと、「どうやったら貧困が無くなるか」という大事な話題を思い出させてくれてありがとう〜忘れてた(^_^;)
貧困を無くすためには教育が重要だ、けれど、充分な教育を受けて高学歴となった人でも、貧困に陥らないとは限らない。という話をしたようなしていないような…。
やはり、教育と言っても生きるための教育が重要なのであって、日本ではそういった教育が不充分なんだろうと思われる。
まるちゃんの言うように、「無くなりません」というのもその通りだと思うし、0にすることはできなくても0に近づけていくことはできるはずで、そのためにはどうしたらよいのかと考えることは無駄ではないはずです。「ファクトフルネス」で学んだように、世界の貧困は減り続けているし、そのために努力している人たちがたくさんいるということも知っておきたい。
ただ、貧困の減少にもこれ以上下がらないという限界があるだろうし、日本での貧困率の推移はほぼ横ばいとなっています。
「どうしたら貧困が無くなるか」という疑問についてもう一度考えてみると、「父が娘に語る経済の話」で学んだように、資本主義に大きな問題があるように思います。簡単に言うと、資本主義というゲームが上手い人とそうでない人がいて、上手い人は富み、苦手な人は貧困に陥ってしまう。その仕組は複雑なんだけれど簡単に言えばそういうことなのではないか。なので、本気で貧困を無くそうとするなら、ゲームのルール(資本主義)から変えていく必要を感じます。
少しずつでも…。
面白い本だったので、当日参加自粛して残念でしたが、せめてコメントだけでも残しておこうかと思います。
(多分たくさんの話題がのぼったでしょうから、話題になっていない事柄を書けるとよいのですが。)
著者がもともと音楽ライター上がりということもあってか、音楽絡みのネタが印象的でした。第一章の、学校見学会で目の当たりにした、雑多でバラバラなんだけど一丸となってグルーヴを生み出すステージのことなどは、序盤を飾るにふさわしい象徴的なシーンでした。他にも音楽ネタはたくさん散りばめられていますが、その中でも自分が注目したいのは、最終章の、息子が「グリーン・イディオット」を結成するくだりです。「パンクさ」が向けられる対象の変遷が見え、この本の中で最もクリティカルな部分の一つだったのではないかと思います。
どういうことか。一般的に、いわゆる「パンク」(特にイギリスのそれ)は、当時の不況・失業率の高さ等の社会の閉塞感に対する若者の「怒り」が反体制的な楽曲・アートを生み出すムーブメントになった、と整理されます。そこでの怒りは、あらゆる既成価値に向けられていました。しかし我らがグリーン・イディオットが歌うのは、その既成価値に基づくアクション(環境問題に関するデモ)から自分たちが締め出されてしまっているという怒り、でした。ざっくばらんに言うと、「社会に対して反抗していく」スタンスから「社会へ参入できないことへ反抗する」スタンスへの、闘争軸の変遷。
本書にも「アイデンティティ・ポリティクス」という言葉が登場しますが、本書のベースにある作法は、アイデンティティ(と、経済格差)の現場を、子供の目を通して見る、というものです。語られるのは、いくつものアイデンティティのいくつもの結節点が動揺し振動する様子でした。そこでは、「ひとつの」アイデンティティを主張し固持することはクレバーであるとは言えず、常に悩み当惑するしかない。その状況で我らがグリーン・イディオットが歌ったのは、「俺たちも環境問題に関わらせろ」でした。その叫びが叫ぶ環境問題とは、個別のアイデンティティのどれかひとつを代表するものではなく、人間(=近代的な市民)が求めるべき普遍的価値であり、基本的な権利や自由などと同じく、「シチズンシップ」に与するものです。「マイノリティがアイデンティティを主張する」時代から「マジョリティがアイデンティティを濫用する」時代を経て、「マイノリティがシチズンシップを叫ぶ」時代へ。マイノリティ側の主張が元来「シチズンシップの補完」的側面を有していたことを考えると、とても正当で正統な抵抗手段を彼らは手にしているように思えます。
つまりは、息子(と母ちゃん)の成長が、とても頼もしかった、と思ったということです。
(多分たくさんの話題がのぼったでしょうから、話題になっていない事柄を書けるとよいのですが。)
著者がもともと音楽ライター上がりということもあってか、音楽絡みのネタが印象的でした。第一章の、学校見学会で目の当たりにした、雑多でバラバラなんだけど一丸となってグルーヴを生み出すステージのことなどは、序盤を飾るにふさわしい象徴的なシーンでした。他にも音楽ネタはたくさん散りばめられていますが、その中でも自分が注目したいのは、最終章の、息子が「グリーン・イディオット」を結成するくだりです。「パンクさ」が向けられる対象の変遷が見え、この本の中で最もクリティカルな部分の一つだったのではないかと思います。
どういうことか。一般的に、いわゆる「パンク」(特にイギリスのそれ)は、当時の不況・失業率の高さ等の社会の閉塞感に対する若者の「怒り」が反体制的な楽曲・アートを生み出すムーブメントになった、と整理されます。そこでの怒りは、あらゆる既成価値に向けられていました。しかし我らがグリーン・イディオットが歌うのは、その既成価値に基づくアクション(環境問題に関するデモ)から自分たちが締め出されてしまっているという怒り、でした。ざっくばらんに言うと、「社会に対して反抗していく」スタンスから「社会へ参入できないことへ反抗する」スタンスへの、闘争軸の変遷。
本書にも「アイデンティティ・ポリティクス」という言葉が登場しますが、本書のベースにある作法は、アイデンティティ(と、経済格差)の現場を、子供の目を通して見る、というものです。語られるのは、いくつものアイデンティティのいくつもの結節点が動揺し振動する様子でした。そこでは、「ひとつの」アイデンティティを主張し固持することはクレバーであるとは言えず、常に悩み当惑するしかない。その状況で我らがグリーン・イディオットが歌ったのは、「俺たちも環境問題に関わらせろ」でした。その叫びが叫ぶ環境問題とは、個別のアイデンティティのどれかひとつを代表するものではなく、人間(=近代的な市民)が求めるべき普遍的価値であり、基本的な権利や自由などと同じく、「シチズンシップ」に与するものです。「マイノリティがアイデンティティを主張する」時代から「マジョリティがアイデンティティを濫用する」時代を経て、「マイノリティがシチズンシップを叫ぶ」時代へ。マイノリティ側の主張が元来「シチズンシップの補完」的側面を有していたことを考えると、とても正当で正統な抵抗手段を彼らは手にしているように思えます。
つまりは、息子(と母ちゃん)の成長が、とても頼もしかった、と思ったということです。
ヤトリさん、コメントありがとぉぉ 待ってましたぁぁ
グリーン・イディオットの話題はたしかしてなかったので、ナイスです。
息子(母ちゃんも)の成長が頼もしく感じる。ほんとにそうですよねー。
この章で自分は、一番最後、人種も階級も性的指向も関係なく子供たちには未熟な色があるだけ、そしてこの色は変わり続けるといった締めくくりにグッときました。
多様性を超えた子供たちが共有する未熟という価値観があるということと、
固定されずに変わり続ける柔軟性を子供たちは持っているということに。
ここで考えたのは、自分は今何色だろうか?ということ。
40歳過ぎてもまだまだ未熟なグリーンだけどな。と、思ったのでした。
グリーン・イディオットの話題はたしかしてなかったので、ナイスです。
息子(母ちゃんも)の成長が頼もしく感じる。ほんとにそうですよねー。
この章で自分は、一番最後、人種も階級も性的指向も関係なく子供たちには未熟な色があるだけ、そしてこの色は変わり続けるといった締めくくりにグッときました。
多様性を超えた子供たちが共有する未熟という価値観があるということと、
固定されずに変わり続ける柔軟性を子供たちは持っているということに。
ここで考えたのは、自分は今何色だろうか?ということ。
40歳過ぎてもまだまだ未熟なグリーンだけどな。と、思ったのでした。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|