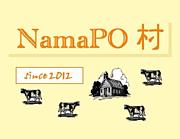1,死刑制度廃止について
これまでは、死刑制度は「死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたもの」というのが、実質的理由であった。しかしながら、昨今、この実質的理由は、近時の死刑廃止論によって再考を迫られている。 引用文献 芦部 憲法第四版 ページ241貢
参考
死刑制度廃止せず 首相「凶悪犯罪に鑑み」
2012.3.30 22:13
野田佳彦首相は30日の記者会見で、死刑囚3人に対する29日の刑執行に触れ、死刑制度を維持する考えを示した。「凶悪犯罪が減らない状況なども鑑みて、直ちに死刑を廃止するのは困難だ。死刑を廃止する方針はない」と述べた。
同時に、平成21年12月に内閣府が実施した世論調査で「場合によっては死刑もやむを得ない」と答えた人が85.6%だったと指摘。「死刑制度の在り方について、国民世論に十分配慮しながら、社会正義の実現などさまざまな観点から慎重に検討しなければいけない」と強調した。
産経ニュース 2012年3月30日 22時13分
ポイントとしては、
「死刑制度の在り方については、国民世論に十分配慮しながら、社会正義の実現とさまざまな観点から慎重に検討しなければいけない」
とした点である。
(1)
条文 憲法36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」
1(この残虐な刑罰に、死刑は該当するのであろうか?)
ポイント 残虐刑とは何か?
死刑とは残虐刑であろうか?
2(社会的正義とは何か)
ポイント
社会的正義と良く使うが、正義とは抽象的な文言であり、明確にする必要があるのではないか?
正義とは、
悪とは、
(2)
(検討)
条文 憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
憲法31条「何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
憲法36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」
○(この残虐な刑罰に、死刑は該当するであろうか?)
残虐な刑罰とは何か
残虐な刑罰⇔残虐刑 の区別
残虐刑とは、「死刑の執行方法が火あぶり、はりつけ等『その時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合』のこと」
芦部憲法 第4版参照
判例(最大判昭和23年3月12日刑集二巻三号一九一貢)は、死刑そのものは残虐刑に該当しないと解している。→憲法13条は公共の福祉という基本的原則に反する場合、生命に対する国民の権利といえども立法上、剥奪されることが予想されていた。
憲法31条は、国民個人の生命がいかに尊いものであるといえども、法律の定める適理の手続きによってこれを奪う刑罰を科せられることが、明確に定められている。
だからこそ↓
憲法は死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、
また、個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解することができる。
死刑が残虐刑に該当し、憲法上否定される場合
上記判例 判旨 下から19行目参照 島・藤田・岩松・河村裁判官の補充意見
1、 国家の文化が高度に発展して正義と秩序正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。
憲法31条の解釈もおのずから制限されて、死刑は残虐な刑罰として憲法に違反するものとして、排除されることもあろう。
しかし、今日はまだこのような時期に達したものとはいうことができない。
2、 憲法13条、31条の「裏面解釈」より、36条は絶対に死刑を許さぬ趣旨ではないが、「憲法は・・・固より死刑の存置を命じて居るものではないことは勿論であるから、若し死刑を必要としない、若しくは国民全体の感情が死刑を忍びないと云う様な時が来れば国会は進んで死刑の条文を廃止するであろうし又条文は残って居ても事実上裁判官が死刑を選択しないであろう。」
○(社会的正義とは何か?)
犯罪者を殺すことが社会的に「正義」と捉えるのか、それとも「悪」と捉えるのか。
→社会的に「正義」であると捉える場合
→社会的に「悪」であると捉える場合
○死刑に代えて、終身刑を導入する。← 1つの可能性
世論調査において、死刑存置に対する意見は強い。そして、政府の死刑制度維持に対する理由としては、この「国民多数の考え」が挙げられている。
○死刑と「国民感情」
死刑の是非をめぐる論点は、これまで論じた刑の目的等のほか、人道主義、誤判の可能性、被害者感情、社会契約論など多岐にわたる。ここでは最後に、本判決の補充意見で重要な位置を占めている、死刑に対する「国民感情」に触れておこう。
各種の世論調査によれば、現在までのところ死刑の存置を支持する声が強い。政府は死刑制度を維持する主たる理由の一つとして、この「国民多数の考え」を挙げる。本判決の補充意見は、「国民感情」が死刑を否定する場合、死刑が違憲となる可能性を示唆し、あるいは立法上廃止されたり死刑判決が消滅する事態を予測するが、これは国民の声がそうならない場合、死刑存続を正当化する論拠となる。しかしこの問題において、一般国民の意識にこのような決定的地位が与えられるべきだろうか。
まず、死刑が憲法上の人権の問題である限り、それが違憲か否かは多数者の意思によって左右されるべきものではないはずである。既述の、規約人権委員会による1998年の日本政府に対する最終所見でも、「人権の保護や人権の基準は、世論調査によって決定されるものではないことを強調する」としている。また、立法論の次元でも、それが人権と密接な関係にある刑事政策の問題であることに留意しなければならない。確かに立法過程において世論を全く無視することはでいないだろう。しかしながら例えばイギリスでの1969年の通常犯罪における死刑廃止(後にすべての犯罪で廃止)および81年のフランスでの全面的死刑廃止は、世論の多数が死刑存置を支持する中で実現したものであった。当時のフランスの法相バダンテール氏は、「民主主義は世論に追従することではなく、市民の意見を尊重することである」とする。立法府は世論を尊重する一方、国民に対し充分な情報を与え、問題の実態を明らかにするとともに、場合によっては世論を指導していくことが要請される場合がある。少なくとも立法者は、「国民感情」のみを正当化根拠として現状に安住することは許されないと言うべきである。
(ジュリスト 憲法判例百選? 126死刑と残虐な刑罰 P267 引用)
参照文献 憲法 芦部第4版 ジュリスト 憲法判例百選?(東海大学 押久保倫夫)
2, 刑罰とは何か?
刑罰論とは、「なぜ、国民にとって重大な害悪とされる刑罰を、国家が科すことが正当化されるのか」という刑罰についての考え方。
○刑罰論は、「応報刑論」と「目的刑論」の二つに分けられる。(重要)
応報刑論とは「刑罰は犯罪に対する公的応報である」とする考え方のことである。しかしながら、刑罰を科すに際しては犯罪防止などの目的を考慮すべきではないとする。
目的刑論とは「犯罪が起こらないように刑を科す」という考え方のこと。
参照文献 前田雅英 刑法総論講義 第4版
刑罰とは何か?
それは、「刑罰は犯罪のゆえにその行為者に加えられる国家的非難の形式である」。
「
1、 刑罰は犯罪と均衡を保つものであることを要する。
2、 刑罰は非難の意味をもつ点で、本質的に規範的であり、倫理的なものである。
」
さて、では刑罰を行う目的とは何か?
1、 刑罰は、犯罪に対する非難として加えられるものである。
しかしながら、
2、 刑罰は、犯罪の規範的意味を明らかにすることで、一般人の規範意識を覚醒し強化するべきであり、その意味では、刑の一般予防的及び特別予防的作用を認められなければならない。
○一般予防とは、「刑罰の持つ広い意味での威嚇力により、一般人が犯罪に陥ることを防止しようとする考え方」
例 見せしめ刑
「犯罪を犯すことによって得られる快楽より大きい不快が、刑罰として科されることが予め明示されていれば、犯罪を防止し得る。」(フォイエルバッハ)
○特別予防は、「刑罰により犯罪者自身が再び犯罪に陥ることを防止しようとする考え方」」
上記1、2の意味で、刑罰は「応報」なのである。
それを超えてまで、犯人に無用の苦痛や害悪を加えることは許されない。
刑罰は非人道的なものではなく、人道的なものである。
ここにベッカリーアの理論が息づいている。
日本国憲法36条において、残虐な刑罰を禁止している。
では、死刑は残虐な刑罰か?・・・・NO 根拠条文は憲法31条
ベッカリーア 「最大多数に分配された最大幸福」こそが目標である。
参照文献 ベッカリーア 「犯罪と刑罰」
団頭・・・「刑罰は、非人道的であってはならないとするのは不十分であり、それは積極的に人道的でなければならない。」 (アンセル・・・犯人の「社会復帰への権利」)
そこで、刑罰の目的は、「刑罰は、犯罪と均衡を保つことを要し、それよりも重くてはならないが、その範囲内で、犯人の社会復帰を実現させるべく、合理的に運営されなければならない。」
参照文献 団当重光 刑法総論
死刑廃止論 ベッカリーアの見解
「通常の社会契約の中で、国民が自分の生命をあらかじめ放棄することはありえない。少なくとも、正常な事態では、死刑は、廃止されるべきである。
刑はその重さよりも、その長さによって威嚇的な効果を発揮し、死刑の威嚇力は、長期の自由刑よりも劣るとした。また、国家が死刑を行うことは、国民に悪い手本を示すこととなるとした。」
↓
例 残虐な刑罰を、もしも見たとしよう。その直後どのような感情を抱くか?
→おそらく、死刑の否定は思いつかない。
死刑確定後、完全に改悛して執行台に上る前、祈りをささげている犯人に接する者はどうか?
(例えば、前回の話に出てきたゼミでの死刑執行の映像を見せたという話でも同じことである。なぜ、人の死に対し無言となるのか。)
→おそらくは、人は死刑を肯定する気持ちになれないのである。
・・・→刑罰の裏付けとなっているのは、「事情」である。
↓
すなわち、そこには必ず「変化」がある。
参照文献 団頭重光 刑法総論
近年は、現実に生命侵害を伴うことなしに死刑の言い渡された例は、絶無である。改正刑法草案48条3項で死刑の適用には特に慎重でなければならない旨を定めている。また、死刑を科しうる罪を大幅に減らし、結果的加重犯について死刑を科しうる場合を強盗致死だけとした。
例えば、列車を顚覆させた乗客多数を死亡させた場合、死の結果について故意を欠くならば、死刑の適用はない。
参照文献 藤木英夫 刑法総論
自分の見解→
死刑についての威嚇力については、さまざまな検証の為されている中、決め手となる論証方法は無いとされている。そのため、死刑制度の廃止又は存置は、国民の規範的意識によるものと解されるのである。前田教授も刑法総論のなかで「刑罰は現代社会においても被害者の報復感情の鎮静化や、犯罪抑止効果を有する倫理・道徳の維持ないし増強という役割をはたいていることは否定し得ない。」と言っている。
私もその見解には賛成であり、死刑制度は現状の国民の規範的意識を鑑みるに、存置すべきであるとの結論に至る。
以上
これまでは、死刑制度は「死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたもの」というのが、実質的理由であった。しかしながら、昨今、この実質的理由は、近時の死刑廃止論によって再考を迫られている。 引用文献 芦部 憲法第四版 ページ241貢
参考
死刑制度廃止せず 首相「凶悪犯罪に鑑み」
2012.3.30 22:13
野田佳彦首相は30日の記者会見で、死刑囚3人に対する29日の刑執行に触れ、死刑制度を維持する考えを示した。「凶悪犯罪が減らない状況なども鑑みて、直ちに死刑を廃止するのは困難だ。死刑を廃止する方針はない」と述べた。
同時に、平成21年12月に内閣府が実施した世論調査で「場合によっては死刑もやむを得ない」と答えた人が85.6%だったと指摘。「死刑制度の在り方について、国民世論に十分配慮しながら、社会正義の実現などさまざまな観点から慎重に検討しなければいけない」と強調した。
産経ニュース 2012年3月30日 22時13分
ポイントとしては、
「死刑制度の在り方については、国民世論に十分配慮しながら、社会正義の実現とさまざまな観点から慎重に検討しなければいけない」
とした点である。
(1)
条文 憲法36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」
1(この残虐な刑罰に、死刑は該当するのであろうか?)
ポイント 残虐刑とは何か?
死刑とは残虐刑であろうか?
2(社会的正義とは何か)
ポイント
社会的正義と良く使うが、正義とは抽象的な文言であり、明確にする必要があるのではないか?
正義とは、
悪とは、
(2)
(検討)
条文 憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
憲法31条「何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
憲法36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」
○(この残虐な刑罰に、死刑は該当するであろうか?)
残虐な刑罰とは何か
残虐な刑罰⇔残虐刑 の区別
残虐刑とは、「死刑の執行方法が火あぶり、はりつけ等『その時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合』のこと」
芦部憲法 第4版参照
判例(最大判昭和23年3月12日刑集二巻三号一九一貢)は、死刑そのものは残虐刑に該当しないと解している。→憲法13条は公共の福祉という基本的原則に反する場合、生命に対する国民の権利といえども立法上、剥奪されることが予想されていた。
憲法31条は、国民個人の生命がいかに尊いものであるといえども、法律の定める適理の手続きによってこれを奪う刑罰を科せられることが、明確に定められている。
だからこそ↓
憲法は死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、
また、個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解することができる。
死刑が残虐刑に該当し、憲法上否定される場合
上記判例 判旨 下から19行目参照 島・藤田・岩松・河村裁判官の補充意見
1、 国家の文化が高度に発展して正義と秩序正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。
憲法31条の解釈もおのずから制限されて、死刑は残虐な刑罰として憲法に違反するものとして、排除されることもあろう。
しかし、今日はまだこのような時期に達したものとはいうことができない。
2、 憲法13条、31条の「裏面解釈」より、36条は絶対に死刑を許さぬ趣旨ではないが、「憲法は・・・固より死刑の存置を命じて居るものではないことは勿論であるから、若し死刑を必要としない、若しくは国民全体の感情が死刑を忍びないと云う様な時が来れば国会は進んで死刑の条文を廃止するであろうし又条文は残って居ても事実上裁判官が死刑を選択しないであろう。」
○(社会的正義とは何か?)
犯罪者を殺すことが社会的に「正義」と捉えるのか、それとも「悪」と捉えるのか。
→社会的に「正義」であると捉える場合
→社会的に「悪」であると捉える場合
○死刑に代えて、終身刑を導入する。← 1つの可能性
世論調査において、死刑存置に対する意見は強い。そして、政府の死刑制度維持に対する理由としては、この「国民多数の考え」が挙げられている。
○死刑と「国民感情」
死刑の是非をめぐる論点は、これまで論じた刑の目的等のほか、人道主義、誤判の可能性、被害者感情、社会契約論など多岐にわたる。ここでは最後に、本判決の補充意見で重要な位置を占めている、死刑に対する「国民感情」に触れておこう。
各種の世論調査によれば、現在までのところ死刑の存置を支持する声が強い。政府は死刑制度を維持する主たる理由の一つとして、この「国民多数の考え」を挙げる。本判決の補充意見は、「国民感情」が死刑を否定する場合、死刑が違憲となる可能性を示唆し、あるいは立法上廃止されたり死刑判決が消滅する事態を予測するが、これは国民の声がそうならない場合、死刑存続を正当化する論拠となる。しかしこの問題において、一般国民の意識にこのような決定的地位が与えられるべきだろうか。
まず、死刑が憲法上の人権の問題である限り、それが違憲か否かは多数者の意思によって左右されるべきものではないはずである。既述の、規約人権委員会による1998年の日本政府に対する最終所見でも、「人権の保護や人権の基準は、世論調査によって決定されるものではないことを強調する」としている。また、立法論の次元でも、それが人権と密接な関係にある刑事政策の問題であることに留意しなければならない。確かに立法過程において世論を全く無視することはでいないだろう。しかしながら例えばイギリスでの1969年の通常犯罪における死刑廃止(後にすべての犯罪で廃止)および81年のフランスでの全面的死刑廃止は、世論の多数が死刑存置を支持する中で実現したものであった。当時のフランスの法相バダンテール氏は、「民主主義は世論に追従することではなく、市民の意見を尊重することである」とする。立法府は世論を尊重する一方、国民に対し充分な情報を与え、問題の実態を明らかにするとともに、場合によっては世論を指導していくことが要請される場合がある。少なくとも立法者は、「国民感情」のみを正当化根拠として現状に安住することは許されないと言うべきである。
(ジュリスト 憲法判例百選? 126死刑と残虐な刑罰 P267 引用)
参照文献 憲法 芦部第4版 ジュリスト 憲法判例百選?(東海大学 押久保倫夫)
2, 刑罰とは何か?
刑罰論とは、「なぜ、国民にとって重大な害悪とされる刑罰を、国家が科すことが正当化されるのか」という刑罰についての考え方。
○刑罰論は、「応報刑論」と「目的刑論」の二つに分けられる。(重要)
応報刑論とは「刑罰は犯罪に対する公的応報である」とする考え方のことである。しかしながら、刑罰を科すに際しては犯罪防止などの目的を考慮すべきではないとする。
目的刑論とは「犯罪が起こらないように刑を科す」という考え方のこと。
参照文献 前田雅英 刑法総論講義 第4版
刑罰とは何か?
それは、「刑罰は犯罪のゆえにその行為者に加えられる国家的非難の形式である」。
「
1、 刑罰は犯罪と均衡を保つものであることを要する。
2、 刑罰は非難の意味をもつ点で、本質的に規範的であり、倫理的なものである。
」
さて、では刑罰を行う目的とは何か?
1、 刑罰は、犯罪に対する非難として加えられるものである。
しかしながら、
2、 刑罰は、犯罪の規範的意味を明らかにすることで、一般人の規範意識を覚醒し強化するべきであり、その意味では、刑の一般予防的及び特別予防的作用を認められなければならない。
○一般予防とは、「刑罰の持つ広い意味での威嚇力により、一般人が犯罪に陥ることを防止しようとする考え方」
例 見せしめ刑
「犯罪を犯すことによって得られる快楽より大きい不快が、刑罰として科されることが予め明示されていれば、犯罪を防止し得る。」(フォイエルバッハ)
○特別予防は、「刑罰により犯罪者自身が再び犯罪に陥ることを防止しようとする考え方」」
上記1、2の意味で、刑罰は「応報」なのである。
それを超えてまで、犯人に無用の苦痛や害悪を加えることは許されない。
刑罰は非人道的なものではなく、人道的なものである。
ここにベッカリーアの理論が息づいている。
日本国憲法36条において、残虐な刑罰を禁止している。
では、死刑は残虐な刑罰か?・・・・NO 根拠条文は憲法31条
ベッカリーア 「最大多数に分配された最大幸福」こそが目標である。
参照文献 ベッカリーア 「犯罪と刑罰」
団頭・・・「刑罰は、非人道的であってはならないとするのは不十分であり、それは積極的に人道的でなければならない。」 (アンセル・・・犯人の「社会復帰への権利」)
そこで、刑罰の目的は、「刑罰は、犯罪と均衡を保つことを要し、それよりも重くてはならないが、その範囲内で、犯人の社会復帰を実現させるべく、合理的に運営されなければならない。」
参照文献 団当重光 刑法総論
死刑廃止論 ベッカリーアの見解
「通常の社会契約の中で、国民が自分の生命をあらかじめ放棄することはありえない。少なくとも、正常な事態では、死刑は、廃止されるべきである。
刑はその重さよりも、その長さによって威嚇的な効果を発揮し、死刑の威嚇力は、長期の自由刑よりも劣るとした。また、国家が死刑を行うことは、国民に悪い手本を示すこととなるとした。」
↓
例 残虐な刑罰を、もしも見たとしよう。その直後どのような感情を抱くか?
→おそらく、死刑の否定は思いつかない。
死刑確定後、完全に改悛して執行台に上る前、祈りをささげている犯人に接する者はどうか?
(例えば、前回の話に出てきたゼミでの死刑執行の映像を見せたという話でも同じことである。なぜ、人の死に対し無言となるのか。)
→おそらくは、人は死刑を肯定する気持ちになれないのである。
・・・→刑罰の裏付けとなっているのは、「事情」である。
↓
すなわち、そこには必ず「変化」がある。
参照文献 団頭重光 刑法総論
近年は、現実に生命侵害を伴うことなしに死刑の言い渡された例は、絶無である。改正刑法草案48条3項で死刑の適用には特に慎重でなければならない旨を定めている。また、死刑を科しうる罪を大幅に減らし、結果的加重犯について死刑を科しうる場合を強盗致死だけとした。
例えば、列車を顚覆させた乗客多数を死亡させた場合、死の結果について故意を欠くならば、死刑の適用はない。
参照文献 藤木英夫 刑法総論
自分の見解→
死刑についての威嚇力については、さまざまな検証の為されている中、決め手となる論証方法は無いとされている。そのため、死刑制度の廃止又は存置は、国民の規範的意識によるものと解されるのである。前田教授も刑法総論のなかで「刑罰は現代社会においても被害者の報復感情の鎮静化や、犯罪抑止効果を有する倫理・道徳の維持ないし増強という役割をはたいていることは否定し得ない。」と言っている。
私もその見解には賛成であり、死刑制度は現状の国民の規範的意識を鑑みるに、存置すべきであるとの結論に至る。
以上
|
|
|
|
|
|
|
|
NamaPO村 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
NamaPO村のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37859人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人