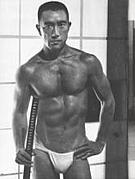十一月二十六日付「朝日新聞」の報道によると、牛込署捜査本部は二十五日同夜二人の遺体を同署で検視し、結果を次のように発表した。三島の短刀による傷はヘソに下四?ぐらいで、左から右へ一三?真一文字に切っていた。深さは約5?。腸が傷口から外へ飛び出していた。
日本刀での介錯による傷は、首あたりに三か所、右肩に一か所あった。
森田は腹に十?の浅い傷があったが、出血はほとんどなかった。首は一刀のもとに切られていた。三島と森田は「楯の会」の制服の下には下着をつけず、二人とも「さらし」の新しい ”六尺“ ふんどしをつけていた。 検視にに立ち会った東京大学医学部講師・内藤道興氏は、「三島氏の切腹の傷は深く文字通り真一文字、という状態で、森田の傷がかすり傷程度だったのに比べるとその意気込みのすさまじさがにじみでている」と話した。
もう一つ、十二月一三日付「毎日新聞」掲載の「解剖所見」を引用すると(三島由紀夫氏・十一月二十六日午前十一時二十分から午後一時二十五分、慶応大学病院医学部解剖室・齋藤教授の執刀)。死因は頚部割創による離断。左右の頸動脈、静脈がきれいに切られており、切断の凶器は鋭利な刃器による、死後二十四時間。頚部は三回切りかけており、七?、六?、四?、三?の切り口がある。右肩に、刀がはずれたと見られる一一・五?の切創、左アゴ下に小さな刃こぼれ。 腹部はヘソを中心に右へ五・五?、左へ八・五?の切創、深さ四?、左は小腸に達し、左から右へ真一文字。身長一六三?、四十五歳だが三十歳代の発達した若々しい筋肉。
森田必勝(船生助教授執刀)については、死因は頚部割創による切断離断、第三頸椎と第四頸椎の中間を一刀のもとに切り落としている。腹部のキズは左から右に水平、ヘソの左七?に深さ四?のキズ、そこから右へ五・四?の浅い切創、ヘソの右五?に切創。右肩に〇・五?の小さなキズ。身長百六十七?。若いきれいな体をしていた。
三島の切腹で一つだけ〈奇異な感じを抱かされた〉のは、あの腹の切り方は一人で死ぬ場合の切り方であったということである。三島が作品「憂国」や「奔馬」で描き、映画「人斬り」で自ら田中新兵衛に扮してみせた切り方であって、介錯を予定した切り方ではない。
しかし三島はこの挙に出る前に、森田あるいは古賀が介錯することを打ち合わせているのである。そうとすれば、他人による介錯、すなわち〈斬首〉ということを予定した腹の切り方をすべきではなかったか。 三島のように、あれほどの深さで横一文字に切った場合(これは常人のなしえざるところである)、肉体はどうゆう反応を示すのであろうか。刀を腹へ突き立てたとき二つの倒れ方が想定される。 それは切腹の際の身体の角度による。瞬時に
襲ってくる全身の痙攣と硬直により、膝の関節で折れ曲がっていた両脚がぐっと一直線に伸びるためか、角度が深いときはガバとのめるように前へ倒れ、角度の浅いときは後へのけぞるのである。
これは切腹なしの斬首のばあいも同様で、押さえ役がいるときは前へ倒れるように押さえているからよいが、支えがない場合の多くは後へ立ち上がるようにして倒れ、そのために首打ち役もその介添え人も血をあびることがある。(斬首のさい〈首の皮一枚残して斬る〉とよくいわれるのは、押え役のいない場合、そうすることで前にぶら下がった首が錘となって身体を前へ倒れさせるからで、これは幕末の吟味方与力・佐久間長敬が『江戸町奉行事蹟問答』の中ではっきり述べている。)
三島の場合、どちらの倒れ方をしたかわからないが、いずれにしても腹から刀(この場合は鎧通し)を抜く暇もなく失神状態に陥り、首は堅く肩にめり込み、ひょっとしたら両眼はカッと見開かれ、歯は舌を堅く噛み、腹部の圧力で腸も一部はみ出すといったぜつ凄惨な場面が展開されたかもしれない。それはとても正規の介錯のできる状態ではなかったと思われるのである。
介錯人としての森田の立たされた悲劇的立場が思いやられる。 なぜなら、介錯人というものは〈一刀のもとに〉首を刎ねるのが義務であり名誉であって、もしそれに失敗したとなれば、かっては〈末代までの恥〉と考えるくらい不名誉とされたからである。
昔の首打役の不文律として、斬り損った場合、三太刀以上はくださないとされ、したがって二太刀まで失敗したときには、死罪人を俯伏せに倒して「押し斬り」にすることさえあった。 死罪場においてちゃんと死罪人を押さえて首をのばさせ、斬首のプロが斬るときでさえ失敗することがあるのである。まして三島のような身体的反応が起った場合には、一太刀で介錯することは不可能といってよかったのではあるまいか。
昭和四十六年四月十九日および六月二十日の第二回と第六回の公判記録によると、右肩の傷は初太刀の失敗であった。おそらく最初三島は後へのけぞったものと思われる。森田は三島が前へ倒れるものとばかり思って打ち下ろしたとき、以外にも逆に頚部が眼の前に上がってきたため手許が狂い、右肩を叩きつける格好になったのであろう。
そのため前へ俯伏せに倒れた三島が額を床につけて前屈みに悶え動くので首の位置が定まらず、森田はそのまま三島の首に斬りつけたか、それとも三島の身体を抱き起して急いで斬らねばならなかったかわからないが、いずれにしても介錯人には最悪の状態でさらに二太刀(齋藤教授の「解剖所見」によると三太刀か?)斬りつけ、結局は森田に代わった古賀がもう一太刀ふるわねばならなかったのかは、致し方なかったと思われる。 最後はあるいは「押し斬り」に斬ったかもしれない。現場写真で三島の倒れていた部分の血溜りが、ほぼ九十度のひらきで二方向に見えているのは、その結果ではあるまいか。森田は自分の敬慕してやまない先生を一太刀で介錯できなかったことを恥じ、「先生、申し訳ありません」と泣く思いで刀をふるったことであろう。
しかしここで愕くべきは森田の精神力である。 普通の介錯人は初太刀に斬り損じた場合、それだけで気が転倒し、二の太刀はさらに無様になるか、別な人間に代わってもらうものである。そのために介添人がいるのである。それほど斬首ということは極度の精神的緊張とエネルギーの消耗をともなう。
それなのに三太刀(ないし四太刀)も斬りつけ、しかも介錯を完了いえなかった人間が、三島の握っている鎧通しを取って続いて自分の腹を切るということは、これまた常人の到底なしえないことなのである。しかも腹の皮を薄く切って、一太刀で自分の首を刎ねさせている。 腹の傷が浅いということでこれを「ためらい傷があった」と報じた新聞もあるが、それはあたらない。人間の腹はなかなか刃物の通りにくいもので、むしろこれをはじき返すようにできている。「さらし」でもきっちり巻いているなら別だが、直接皮膚に刃物を突き立てたのでは、相当の圧力がなければはじき返されるものである。
森田の場合は初めから薄く切って介錯を見事にしてもらおうという考えであったと思われる。切腹する人間は首を斬られて死ぬのではなく、介錯人に首をうまく斬らせるのである。それが昔の武士たちが実際の経験の積み重ねから作り上げた一番〈見苦しくない〉切腹の美学であった。そうゆう意味では、森田のほうが昔の切腹の美学にかなっていたといえよう。さすがに三島が最も信頼した人物にふさわしい腹の切り方であったように思われる。
三島は
生前、映画「憂国」【小説・憂国(抄)】を制作したさい、二・二六事件で決起に遅れて自宅で割腹自殺をとげた青島中尉(「憂国」のモデルといわれる)の割腹現場に駆けつけた軍医から、そのときの実見談を聴取していたといわれる。 そして青島中尉が割腹後五・六時間たってもなお死にきれず、腹から腸を飛び出させたまま意識を失い、のたうちまわっていた有様をよく知っていた。したがって介錯がなければ切腹が見苦しい死にざまを曝すおそれのあることを十分に認識しており、そのため介錯を予定したことは正しい計算であった。
それなのに敢えてあのような深い腹の切り方をしたのは、なぜであろうか。 三島ほどの綿密な計算をする人にも、切腹後の肉体的変化までは計算しえなかった千慮の一矢なのであろうか。〈奇異な感じを抱かされた〉と述べたのはそのためである。
これはなにも三島の切腹を貶しめようとするものではない。三島はその文学においても、必ず自己を主張しなければやまぬ人間であった。そのエゴの強さ、抜きがたい自己顕示性からあの赫奕たる文学が生まれたのである。
そして切腹の場にいたるまでそのエゴを押し通したのである。
日本刀での介錯による傷は、首あたりに三か所、右肩に一か所あった。
森田は腹に十?の浅い傷があったが、出血はほとんどなかった。首は一刀のもとに切られていた。三島と森田は「楯の会」の制服の下には下着をつけず、二人とも「さらし」の新しい ”六尺“ ふんどしをつけていた。 検視にに立ち会った東京大学医学部講師・内藤道興氏は、「三島氏の切腹の傷は深く文字通り真一文字、という状態で、森田の傷がかすり傷程度だったのに比べるとその意気込みのすさまじさがにじみでている」と話した。
もう一つ、十二月一三日付「毎日新聞」掲載の「解剖所見」を引用すると(三島由紀夫氏・十一月二十六日午前十一時二十分から午後一時二十五分、慶応大学病院医学部解剖室・齋藤教授の執刀)。死因は頚部割創による離断。左右の頸動脈、静脈がきれいに切られており、切断の凶器は鋭利な刃器による、死後二十四時間。頚部は三回切りかけており、七?、六?、四?、三?の切り口がある。右肩に、刀がはずれたと見られる一一・五?の切創、左アゴ下に小さな刃こぼれ。 腹部はヘソを中心に右へ五・五?、左へ八・五?の切創、深さ四?、左は小腸に達し、左から右へ真一文字。身長一六三?、四十五歳だが三十歳代の発達した若々しい筋肉。
森田必勝(船生助教授執刀)については、死因は頚部割創による切断離断、第三頸椎と第四頸椎の中間を一刀のもとに切り落としている。腹部のキズは左から右に水平、ヘソの左七?に深さ四?のキズ、そこから右へ五・四?の浅い切創、ヘソの右五?に切創。右肩に〇・五?の小さなキズ。身長百六十七?。若いきれいな体をしていた。
三島の切腹で一つだけ〈奇異な感じを抱かされた〉のは、あの腹の切り方は一人で死ぬ場合の切り方であったということである。三島が作品「憂国」や「奔馬」で描き、映画「人斬り」で自ら田中新兵衛に扮してみせた切り方であって、介錯を予定した切り方ではない。
しかし三島はこの挙に出る前に、森田あるいは古賀が介錯することを打ち合わせているのである。そうとすれば、他人による介錯、すなわち〈斬首〉ということを予定した腹の切り方をすべきではなかったか。 三島のように、あれほどの深さで横一文字に切った場合(これは常人のなしえざるところである)、肉体はどうゆう反応を示すのであろうか。刀を腹へ突き立てたとき二つの倒れ方が想定される。 それは切腹の際の身体の角度による。瞬時に
襲ってくる全身の痙攣と硬直により、膝の関節で折れ曲がっていた両脚がぐっと一直線に伸びるためか、角度が深いときはガバとのめるように前へ倒れ、角度の浅いときは後へのけぞるのである。
これは切腹なしの斬首のばあいも同様で、押さえ役がいるときは前へ倒れるように押さえているからよいが、支えがない場合の多くは後へ立ち上がるようにして倒れ、そのために首打ち役もその介添え人も血をあびることがある。(斬首のさい〈首の皮一枚残して斬る〉とよくいわれるのは、押え役のいない場合、そうすることで前にぶら下がった首が錘となって身体を前へ倒れさせるからで、これは幕末の吟味方与力・佐久間長敬が『江戸町奉行事蹟問答』の中ではっきり述べている。)
三島の場合、どちらの倒れ方をしたかわからないが、いずれにしても腹から刀(この場合は鎧通し)を抜く暇もなく失神状態に陥り、首は堅く肩にめり込み、ひょっとしたら両眼はカッと見開かれ、歯は舌を堅く噛み、腹部の圧力で腸も一部はみ出すといったぜつ凄惨な場面が展開されたかもしれない。それはとても正規の介錯のできる状態ではなかったと思われるのである。
介錯人としての森田の立たされた悲劇的立場が思いやられる。 なぜなら、介錯人というものは〈一刀のもとに〉首を刎ねるのが義務であり名誉であって、もしそれに失敗したとなれば、かっては〈末代までの恥〉と考えるくらい不名誉とされたからである。
昔の首打役の不文律として、斬り損った場合、三太刀以上はくださないとされ、したがって二太刀まで失敗したときには、死罪人を俯伏せに倒して「押し斬り」にすることさえあった。 死罪場においてちゃんと死罪人を押さえて首をのばさせ、斬首のプロが斬るときでさえ失敗することがあるのである。まして三島のような身体的反応が起った場合には、一太刀で介錯することは不可能といってよかったのではあるまいか。
昭和四十六年四月十九日および六月二十日の第二回と第六回の公判記録によると、右肩の傷は初太刀の失敗であった。おそらく最初三島は後へのけぞったものと思われる。森田は三島が前へ倒れるものとばかり思って打ち下ろしたとき、以外にも逆に頚部が眼の前に上がってきたため手許が狂い、右肩を叩きつける格好になったのであろう。
そのため前へ俯伏せに倒れた三島が額を床につけて前屈みに悶え動くので首の位置が定まらず、森田はそのまま三島の首に斬りつけたか、それとも三島の身体を抱き起して急いで斬らねばならなかったかわからないが、いずれにしても介錯人には最悪の状態でさらに二太刀(齋藤教授の「解剖所見」によると三太刀か?)斬りつけ、結局は森田に代わった古賀がもう一太刀ふるわねばならなかったのかは、致し方なかったと思われる。 最後はあるいは「押し斬り」に斬ったかもしれない。現場写真で三島の倒れていた部分の血溜りが、ほぼ九十度のひらきで二方向に見えているのは、その結果ではあるまいか。森田は自分の敬慕してやまない先生を一太刀で介錯できなかったことを恥じ、「先生、申し訳ありません」と泣く思いで刀をふるったことであろう。
しかしここで愕くべきは森田の精神力である。 普通の介錯人は初太刀に斬り損じた場合、それだけで気が転倒し、二の太刀はさらに無様になるか、別な人間に代わってもらうものである。そのために介添人がいるのである。それほど斬首ということは極度の精神的緊張とエネルギーの消耗をともなう。
それなのに三太刀(ないし四太刀)も斬りつけ、しかも介錯を完了いえなかった人間が、三島の握っている鎧通しを取って続いて自分の腹を切るということは、これまた常人の到底なしえないことなのである。しかも腹の皮を薄く切って、一太刀で自分の首を刎ねさせている。 腹の傷が浅いということでこれを「ためらい傷があった」と報じた新聞もあるが、それはあたらない。人間の腹はなかなか刃物の通りにくいもので、むしろこれをはじき返すようにできている。「さらし」でもきっちり巻いているなら別だが、直接皮膚に刃物を突き立てたのでは、相当の圧力がなければはじき返されるものである。
森田の場合は初めから薄く切って介錯を見事にしてもらおうという考えであったと思われる。切腹する人間は首を斬られて死ぬのではなく、介錯人に首をうまく斬らせるのである。それが昔の武士たちが実際の経験の積み重ねから作り上げた一番〈見苦しくない〉切腹の美学であった。そうゆう意味では、森田のほうが昔の切腹の美学にかなっていたといえよう。さすがに三島が最も信頼した人物にふさわしい腹の切り方であったように思われる。
三島は
生前、映画「憂国」【小説・憂国(抄)】を制作したさい、二・二六事件で決起に遅れて自宅で割腹自殺をとげた青島中尉(「憂国」のモデルといわれる)の割腹現場に駆けつけた軍医から、そのときの実見談を聴取していたといわれる。 そして青島中尉が割腹後五・六時間たってもなお死にきれず、腹から腸を飛び出させたまま意識を失い、のたうちまわっていた有様をよく知っていた。したがって介錯がなければ切腹が見苦しい死にざまを曝すおそれのあることを十分に認識しており、そのため介錯を予定したことは正しい計算であった。
それなのに敢えてあのような深い腹の切り方をしたのは、なぜであろうか。 三島ほどの綿密な計算をする人にも、切腹後の肉体的変化までは計算しえなかった千慮の一矢なのであろうか。〈奇異な感じを抱かされた〉と述べたのはそのためである。
これはなにも三島の切腹を貶しめようとするものではない。三島はその文学においても、必ず自己を主張しなければやまぬ人間であった。そのエゴの強さ、抜きがたい自己顕示性からあの赫奕たる文学が生まれたのである。
そして切腹の場にいたるまでそのエゴを押し通したのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
「三島由紀夫氏」 【文武両道】 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-