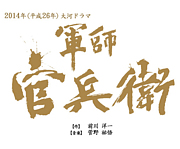日本統一が近づくにつれて秀吉は、外敵に対する憂慮から、権力を安定や確立に邁進するようになります。
四国平定(四国の役、四国征伐とも呼ばれます)・九州平定(島津攻め、九州攻め、九州征伐などとも呼ばれます)、小田原攻め(これにより、戦国時代の多くの大名が口では言いつつも本気で成功するとは思っていなかった日本統一が達成されます)、二度の朝鮮出兵、を含むこの時代について、色々コメントお願いします。
秀吉が家臣に「わしに代わって次に天下を治めるのは誰だ」と尋ねると、家臣達はそれぞれ徳川家康や前田利家の名前を挙げますが、秀吉は「官兵衛がその気になれば、わしが生きている間にも天下を取るだろう」と言い、側近が「官兵衛殿は10万石の大名に過ぎません」と返すと、秀吉は「お前達は奴の本当の力量を
分かっていない。奴に100万石を与えたら途端に天下を奪ってしまう」と言います。
これを伝え聞いた官兵衛は、「我家の禍なり」と直ちに剃髪し、出家して如水と号します。多くの功績を立てた官兵衛に対し、秀吉が与えたのは大坂から遥か遠い豊前中津。しかも僅か12万5,000石(検地後に17万石)。(官兵衛と並び「両兵衛」「二兵衛」と称された竹中半兵衛も、やはりわずかな知行)
1596年の慶長伏見地震の際、如水が倒壊した伏見城に駆けつけると、秀吉は同じ蟄居中の加藤清正は賞賛し、如水に対しては、「俺が死ななくて残念であったであろう」と言ったそうです。
こちらの歴史トピ↓もあります。
(歴史トピ)本能寺〜中国大返し〜小牧長久手の戦い(1582〜1584年頃。軍馬について・)
http://
軍馬についてはこちら↑でお願いします。
四国平定(四国の役、四国征伐とも呼ばれます)・九州平定(島津攻め、九州攻め、九州征伐などとも呼ばれます)、小田原攻め(これにより、戦国時代の多くの大名が口では言いつつも本気で成功するとは思っていなかった日本統一が達成されます)、二度の朝鮮出兵、を含むこの時代について、色々コメントお願いします。
秀吉が家臣に「わしに代わって次に天下を治めるのは誰だ」と尋ねると、家臣達はそれぞれ徳川家康や前田利家の名前を挙げますが、秀吉は「官兵衛がその気になれば、わしが生きている間にも天下を取るだろう」と言い、側近が「官兵衛殿は10万石の大名に過ぎません」と返すと、秀吉は「お前達は奴の本当の力量を
分かっていない。奴に100万石を与えたら途端に天下を奪ってしまう」と言います。
これを伝え聞いた官兵衛は、「我家の禍なり」と直ちに剃髪し、出家して如水と号します。多くの功績を立てた官兵衛に対し、秀吉が与えたのは大坂から遥か遠い豊前中津。しかも僅か12万5,000石(検地後に17万石)。(官兵衛と並び「両兵衛」「二兵衛」と称された竹中半兵衛も、やはりわずかな知行)
1596年の慶長伏見地震の際、如水が倒壊した伏見城に駆けつけると、秀吉は同じ蟄居中の加藤清正は賞賛し、如水に対しては、「俺が死ななくて残念であったであろう」と言ったそうです。
こちらの歴史トピ↓もあります。
(歴史トピ)本能寺〜中国大返し〜小牧長久手の戦い(1582〜1584年頃。軍馬について・)
http://
軍馬についてはこちら↑でお願いします。
|
|
|
|
コメント(141)
秀吉トピの話題から派生して・・・。
秀吉の信頼という意味では羽柴秀長に勝る人物はいないでしょう。
彼こそ関白の名代であり、官兵衛や三成が束になってかかっても到底勝ち目はありません。
それ以外では宮部継潤だと思われます。
毛利との交渉窓口こそ小六・官兵衛でしたが、本能寺前後含め中国地方攻略という意味では同等の働きをしていますし、一時期秀次を養子として迎い入れていました。
一、高麗の御留守居として、宮部中務卿法印(※継潤)召し寄せらるべく候。用意せしめ相待つべき旨、仰せ出だされ候事
一、大唐都へ叡慮(※天皇)うつし申すべく候。其の御用意有るべく候。明後年行幸たるべく候。然らば、都廻りの国十ヶ國、これを進上すべく候。其の内にて諸公家衆何れも知行仰せ付けらるべく候。下の衆十増倍たるべく候。其の上の衆は仁躰に依るべき事
一、大唐関白(※秀吉)、右仰せられ候如く、秀次へ譲りなさるべく候。然らば都廻りの百ヶ国御渡しなさるべく候。日本関白は大和中納言(※羽柴秀保)、備前宰相(※宇喜多秀家)両人の内、覚悟次第に仰せ出ださるべき事
一、日本帝位の儀、若宮(※政仁親王)、八条殿(※智仁親王)、何れにても相究めらるべき事
一、高麗の儀は岐阜宰相(※羽柴秀勝)か、然らざれば備前宰相置かるべく候。然らば丹波中納言(※羽柴秀俊)は九州に置かるべく候事
これは天正20年5月、秀吉は秀次に与えた朱印状の一部です。
天皇・関白の話題と共に「高麗留守居」として、一門衆以外で唯一名が挙げられている事が確認できます。
文禄年間の奉行連署状でも前田玄以や石田三成を差し置いて最上位で署名していますね。
・・・一部ドラマの進行より先の内容が含まれているので、念のため歴史トピに。
秀吉の信頼という意味では羽柴秀長に勝る人物はいないでしょう。
彼こそ関白の名代であり、官兵衛や三成が束になってかかっても到底勝ち目はありません。
それ以外では宮部継潤だと思われます。
毛利との交渉窓口こそ小六・官兵衛でしたが、本能寺前後含め中国地方攻略という意味では同等の働きをしていますし、一時期秀次を養子として迎い入れていました。
一、高麗の御留守居として、宮部中務卿法印(※継潤)召し寄せらるべく候。用意せしめ相待つべき旨、仰せ出だされ候事
一、大唐都へ叡慮(※天皇)うつし申すべく候。其の御用意有るべく候。明後年行幸たるべく候。然らば、都廻りの国十ヶ國、これを進上すべく候。其の内にて諸公家衆何れも知行仰せ付けらるべく候。下の衆十増倍たるべく候。其の上の衆は仁躰に依るべき事
一、大唐関白(※秀吉)、右仰せられ候如く、秀次へ譲りなさるべく候。然らば都廻りの百ヶ国御渡しなさるべく候。日本関白は大和中納言(※羽柴秀保)、備前宰相(※宇喜多秀家)両人の内、覚悟次第に仰せ出ださるべき事
一、日本帝位の儀、若宮(※政仁親王)、八条殿(※智仁親王)、何れにても相究めらるべき事
一、高麗の儀は岐阜宰相(※羽柴秀勝)か、然らざれば備前宰相置かるべく候。然らば丹波中納言(※羽柴秀俊)は九州に置かるべく候事
これは天正20年5月、秀吉は秀次に与えた朱印状の一部です。
天皇・関白の話題と共に「高麗留守居」として、一門衆以外で唯一名が挙げられている事が確認できます。
文禄年間の奉行連署状でも前田玄以や石田三成を差し置いて最上位で署名していますね。
・・・一部ドラマの進行より先の内容が含まれているので、念のため歴史トピに。
>> ネルさん
個人的な意見になりますが、唐入りの成否は信長・秀吉の軍事的才能の優劣とは若干違うような気がしています。
秀吉にとって最大の敵は兵糧と輸送であり、信長には秀吉がやった外交交渉や九州征伐・小田原征伐のような大規模遠征を殆んど経験してお らず、正当な評価は難しいのではないでしょうか。
高麗も大唐の支援がなければ日本軍の侵攻を食い止めることは難しかったと思いますが、その唐とて女真族の侵攻を受けてしまいます。
もしかしたら捕縛した朝鮮王(王子だったか?)をそのまま抱え込めば外交交渉を有利に運べた可能性かも?
あと、信長がどれほど世界の情勢を理解していたかもよく分からないところですね。
・・・答えになっておらずすみません。
個人的な意見になりますが、唐入りの成否は信長・秀吉の軍事的才能の優劣とは若干違うような気がしています。
秀吉にとって最大の敵は兵糧と輸送であり、信長には秀吉がやった外交交渉や九州征伐・小田原征伐のような大規模遠征を殆んど経験してお らず、正当な評価は難しいのではないでしょうか。
高麗も大唐の支援がなければ日本軍の侵攻を食い止めることは難しかったと思いますが、その唐とて女真族の侵攻を受けてしまいます。
もしかしたら捕縛した朝鮮王(王子だったか?)をそのまま抱え込めば外交交渉を有利に運べた可能性かも?
あと、信長がどれほど世界の情勢を理解していたかもよく分からないところですね。
・・・答えになっておらずすみません。
>>[118]
すみません、滝野川さん、文禄・慶長の役の時代では、朝鮮は李朝、中国の王朝は明になります。
当時の李朝朝鮮では、日本の軍事力に対抗する事は適わなかったと思います。李朝は中央集権官僚国家、軍も文官統制です。日本と逆に、文官が武官の上に立ちます。朝廷内は東人派西人派の権力闘争に明け暮れ腐敗していました。文禄の役で活躍した李瞬臣将軍が、憶えなき讒言で一平卒に落とされてしまうような様です。圧政や腐敗への不満で日本に味方した民衆も少なくなかったとも言われます。守備軍指揮者も中央から派遣された官僚で、初戦では戦う事なく逃げ出してしまっています。朝鮮単独では戦う事すら難しかったと思います。
日本の李朝に対する要求は、服属して明へ進行する道を開けよ、とのものでした。最初から征服目的地は朝鮮ではなく明国です。
秀吉は調略と時間を掛けての包囲戦で勝ち進んできました。その自身の戦い方を、朝鮮では忘れてしまったように思います。調略も、ある程度は試みたようですが実を結んでいません。腐敗した政権に対する不満もあり、朝廷内部抗争も激しい。内部結束の堅かった毛利などよりも、付け込む隙は多かったように思います。目的が明だっただけに朝鮮を侮ったのか、秀吉が耄碌して気が短くなったのか、事前準備が不足しています。やり方によっては、嘗て元が行ったように、逆に朝鮮軍を従えて明に攻め上る事も不可能では無かったかも知れません。
すみません、滝野川さん、文禄・慶長の役の時代では、朝鮮は李朝、中国の王朝は明になります。
当時の李朝朝鮮では、日本の軍事力に対抗する事は適わなかったと思います。李朝は中央集権官僚国家、軍も文官統制です。日本と逆に、文官が武官の上に立ちます。朝廷内は東人派西人派の権力闘争に明け暮れ腐敗していました。文禄の役で活躍した李瞬臣将軍が、憶えなき讒言で一平卒に落とされてしまうような様です。圧政や腐敗への不満で日本に味方した民衆も少なくなかったとも言われます。守備軍指揮者も中央から派遣された官僚で、初戦では戦う事なく逃げ出してしまっています。朝鮮単独では戦う事すら難しかったと思います。
日本の李朝に対する要求は、服属して明へ進行する道を開けよ、とのものでした。最初から征服目的地は朝鮮ではなく明国です。
秀吉は調略と時間を掛けての包囲戦で勝ち進んできました。その自身の戦い方を、朝鮮では忘れてしまったように思います。調略も、ある程度は試みたようですが実を結んでいません。腐敗した政権に対する不満もあり、朝廷内部抗争も激しい。内部結束の堅かった毛利などよりも、付け込む隙は多かったように思います。目的が明だっただけに朝鮮を侮ったのか、秀吉が耄碌して気が短くなったのか、事前準備が不足しています。やり方によっては、嘗て元が行ったように、逆に朝鮮軍を従えて明に攻め上る事も不可能では無かったかも知れません。
>>[121]
いやぁ、歴史って面白い!
私は何故、歴史に詳しい滝野川さんが、こんな初歩的な(失礼!)ミスを犯したのか疑問に感じていました。HNでご推察頂いていると思いますが、私の場合、歴史小説は中国物の方がメインです。日本の資料の方に知識が不足していまして、滝野川さんのお使いになった意味が理解できませんでした。
唐は907年、高麗は1392年には滅んでいます。文禄の役は1592年ですので、その時点ではすでに次の王朝、明と李朝朝鮮になっています。ですので、現在の世界史では間違いなのですが、確かに、秀吉軍の渡海には「唐入り(からいり)」「高麗陣」とかの言葉が使われていたようですね。恥ずかしながら知りませんでした。つまりは、中国・朝鮮の王朝名ではなく、地域名として使われていたのでしょうね。中国渡りの物も、唐時代の物でなくても「中国製」との意味で「唐物(からもの)」と呼ばれていたようですし。また、実権者・行政当事者(幕府等)は変わっても、王朝変更の無かった日本では、中国・朝鮮での王朝交代に対する捉え方も薄かったのかも知れません。勉強になりました。
いやぁ、歴史って面白い!
私は何故、歴史に詳しい滝野川さんが、こんな初歩的な(失礼!)ミスを犯したのか疑問に感じていました。HNでご推察頂いていると思いますが、私の場合、歴史小説は中国物の方がメインです。日本の資料の方に知識が不足していまして、滝野川さんのお使いになった意味が理解できませんでした。
唐は907年、高麗は1392年には滅んでいます。文禄の役は1592年ですので、その時点ではすでに次の王朝、明と李朝朝鮮になっています。ですので、現在の世界史では間違いなのですが、確かに、秀吉軍の渡海には「唐入り(からいり)」「高麗陣」とかの言葉が使われていたようですね。恥ずかしながら知りませんでした。つまりは、中国・朝鮮の王朝名ではなく、地域名として使われていたのでしょうね。中国渡りの物も、唐時代の物でなくても「中国製」との意味で「唐物(からもの)」と呼ばれていたようですし。また、実権者・行政当事者(幕府等)は変わっても、王朝変更の無かった日本では、中国・朝鮮での王朝交代に対する捉え方も薄かったのかも知れません。勉強になりました。
当時の朝鮮に関して少し書かせてください。朝鮮と日本、江戸時代に派遣されてきた朝鮮通信使に日本の人々が争って面会を求め、教えを乞うたとの話もあります。つまり、朝鮮を先進国として書いています。朝鮮にも日本を後進国と蔑んだ見方が見られます。実際に朝鮮は先進国だったのでしょうか?
朝鮮の先進部分は、儒教的部分に限られていたように思います。朝鮮国では武官より文官を上位とします。科挙により登用されますが、四書五経を始めとする”学問”が重視され、実学は軽視される傾向がありました。労働は卑賤なものとされ、両班(韓国貴族)の肉体労働は禁じられていました。宮廷内での派閥抗争は熾烈で、讒言や暗殺も頻繁でした。中央主権国家で中央から派遣される官僚により運営されていましたが、短期で交代する地方官に地元への愛着などあろうはずもなく、過酷な搾取に農民は虐げられていました。身分制度も厳しく、日本での様な商人の興隆も見られず、貨幣経済の進展も遅れていました。文化芸術や観念的学問分野では進んだ国であっても、実学部分、軍事はもちろん、農業・商業分野においても、寧ろ日本の方が先を行っていた部分が多かったように思います。その点で、やり方次第では、朝鮮の農民や反主流派を取り込み、親日政権を樹立する事は十分に可能だったように思います。結果としての失敗と、征服戦争を”悪”とする現代的価値観の上に立ち、当時の実像が正確に捉えられていないように思っています。
朝鮮の先進部分は、儒教的部分に限られていたように思います。朝鮮国では武官より文官を上位とします。科挙により登用されますが、四書五経を始めとする”学問”が重視され、実学は軽視される傾向がありました。労働は卑賤なものとされ、両班(韓国貴族)の肉体労働は禁じられていました。宮廷内での派閥抗争は熾烈で、讒言や暗殺も頻繁でした。中央主権国家で中央から派遣される官僚により運営されていましたが、短期で交代する地方官に地元への愛着などあろうはずもなく、過酷な搾取に農民は虐げられていました。身分制度も厳しく、日本での様な商人の興隆も見られず、貨幣経済の進展も遅れていました。文化芸術や観念的学問分野では進んだ国であっても、実学部分、軍事はもちろん、農業・商業分野においても、寧ろ日本の方が先を行っていた部分が多かったように思います。その点で、やり方次第では、朝鮮の農民や反主流派を取り込み、親日政権を樹立する事は十分に可能だったように思います。結果としての失敗と、征服戦争を”悪”とする現代的価値観の上に立ち、当時の実像が正確に捉えられていないように思っています。
秀吉の渡海の件ですが、文禄2年1月の前田利家書状に
「来三月御渡海相定ニ付て」
とあり、3月に予定されていた事が分かります。
本人は何度も渡海の意思を示していましたが、その都度様々な理由により見送られていますね。
また一般的に徳川や前田は渡海せずに済んだと思われがちですが、同年の史料により上杉景勝や最上義光、長谷川秀一、木村重茲らと共に出陣命令が出ていた事が分かっています。
ちなみにその順序は
一番、伊達・浅野
二番、前田・蒲生
三番、徳川
となっていたようです。
しかし5月、戦況の変化を理由にメンバーが見直され、家康らは日本に残ることになりました。
文禄4年にも「高麗城留守居」の中に徳川秀忠の名前が確認できます。
「来三月御渡海相定ニ付て」
とあり、3月に予定されていた事が分かります。
本人は何度も渡海の意思を示していましたが、その都度様々な理由により見送られていますね。
また一般的に徳川や前田は渡海せずに済んだと思われがちですが、同年の史料により上杉景勝や最上義光、長谷川秀一、木村重茲らと共に出陣命令が出ていた事が分かっています。
ちなみにその順序は
一番、伊達・浅野
二番、前田・蒲生
三番、徳川
となっていたようです。
しかし5月、戦況の変化を理由にメンバーが見直され、家康らは日本に残ることになりました。
文禄4年にも「高麗城留守居」の中に徳川秀忠の名前が確認できます。
秀頼の誕生と秀次の切腹が直接結びつくような説明をする本を時々見かけますが、少々早計な気がします。
少なくとも誕生から切腹まで2年の開きがあり、その間の秀吉・秀次の関係が良好であった事が無視されています。
秀吉は日本の半分以上を譲り、秀次女と秀頼の婚姻を計画するなど一定の配慮をしています。
また実子誕生で秀秋や秀康が厄介払いで養子に出されたという解釈も、鶴松誕生の際にそうした動きは見られず成立しないでしょう。
秀次が高野山に行ってから(追放されてから、ではなく)切腹するまでの時間も気になります。
連座された者が大量発生したというのも重要です。
近年、矢部健太郎氏が、実は秀次は潔白を訴えるために自ら切腹したのではないか?という論考を展開していますね。
少なくとも誕生から切腹まで2年の開きがあり、その間の秀吉・秀次の関係が良好であった事が無視されています。
秀吉は日本の半分以上を譲り、秀次女と秀頼の婚姻を計画するなど一定の配慮をしています。
また実子誕生で秀秋や秀康が厄介払いで養子に出されたという解釈も、鶴松誕生の際にそうした動きは見られず成立しないでしょう。
秀次が高野山に行ってから(追放されてから、ではなく)切腹するまでの時間も気になります。
連座された者が大量発生したというのも重要です。
近年、矢部健太郎氏が、実は秀次は潔白を訴えるために自ら切腹したのではないか?という論考を展開していますね。
私見ですが、秀吉は天下を家康に渡すつもりだったのだろうと思います。
勿論ただでくれてやるつもりはありません。
天下や家督は与奪が原則で、織田・武田・伊達・上杉・今川など多くの大名家で権力継承時に血が流れていますし、家康もまた息子を殺しています。
家康に次期天下人としての器量が無ければそれまでです。
当時政庁機能は伏見にあり、これを家康に任せることがその事を意味していると思います。
一方大坂は「豊家の家(イエ)」のような場所で、「天下は徳川に、豊家は前田に委ねる」という事だと考えます。
勿論、秀頼に天下が戻って来る事を望んでいたに違いありません。
しかし、それが儚い願いである事は秀吉自身が一番よく知っています。
もし家康を警戒・敵対視していたなら、小牧合戦以降、家康を優遇していた理由が説明出来ません。
文禄4年の政変以後も何も手をつけず、むしろ家康の重要性は高まる一方でした。
推測するに、秀吉が考える理想の天下は「名目のトップ関白秀頼、実質のトップ(将軍?)家康」という構図ではないでしょうか。
この構図は龍造寺鍋島、足利織田、織田羽柴、京極浅井など数多く見られる事例であり何ら問題ありません。家康を筆頭とする十人衆が秀頼を盛り立ててくれれば、それで良かったのです。
「秀頼のこと、お頼み申す」とはそういう事だと思います。
勿論ただでくれてやるつもりはありません。
天下や家督は与奪が原則で、織田・武田・伊達・上杉・今川など多くの大名家で権力継承時に血が流れていますし、家康もまた息子を殺しています。
家康に次期天下人としての器量が無ければそれまでです。
当時政庁機能は伏見にあり、これを家康に任せることがその事を意味していると思います。
一方大坂は「豊家の家(イエ)」のような場所で、「天下は徳川に、豊家は前田に委ねる」という事だと考えます。
勿論、秀頼に天下が戻って来る事を望んでいたに違いありません。
しかし、それが儚い願いである事は秀吉自身が一番よく知っています。
もし家康を警戒・敵対視していたなら、小牧合戦以降、家康を優遇していた理由が説明出来ません。
文禄4年の政変以後も何も手をつけず、むしろ家康の重要性は高まる一方でした。
推測するに、秀吉が考える理想の天下は「名目のトップ関白秀頼、実質のトップ(将軍?)家康」という構図ではないでしょうか。
この構図は龍造寺鍋島、足利織田、織田羽柴、京極浅井など数多く見られる事例であり何ら問題ありません。家康を筆頭とする十人衆が秀頼を盛り立ててくれれば、それで良かったのです。
「秀頼のこと、お頼み申す」とはそういう事だと思います。
秀吉恩顧で槍働きをメインにしていた武将たちを武断派として一括りにするのは、いわゆる江戸期史観の影響だと私は考えています。
早川長政、寺沢広高、毛利(森)父子、黒田父子、蜂須賀政家等の行動が一致していない所を見てもそれが窺えます。
さてその中で加藤清正ですが、彼は慶長4年に徳川家康と前田利家が対立した際、長岡忠興と共に前田側として行動しています。
尚この時、親三成と云われている大谷吉継が家康方であった事は留意すべき点でしょう。
前田利長による家康暗殺計画(事のシロクロは別として)が露見した際、家康の指示により三成らが清正に対し警戒の兵を充てがったという噂が流れました。
また関ヶ原では黒田長政・寺沢高広・長岡忠興が家康と共に上杉討伐軍に加わっているのに対し、彼は出兵無用として国元に留められています。
こうして見ると、清正は福島正則や黒田長政とは少し違う立ち位置にいたような気がしますね。
早川長政、寺沢広高、毛利(森)父子、黒田父子、蜂須賀政家等の行動が一致していない所を見てもそれが窺えます。
さてその中で加藤清正ですが、彼は慶長4年に徳川家康と前田利家が対立した際、長岡忠興と共に前田側として行動しています。
尚この時、親三成と云われている大谷吉継が家康方であった事は留意すべき点でしょう。
前田利長による家康暗殺計画(事のシロクロは別として)が露見した際、家康の指示により三成らが清正に対し警戒の兵を充てがったという噂が流れました。
また関ヶ原では黒田長政・寺沢高広・長岡忠興が家康と共に上杉討伐軍に加わっているのに対し、彼は出兵無用として国元に留められています。
こうして見ると、清正は福島正則や黒田長政とは少し違う立ち位置にいたような気がしますね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
2014年大河ドラマ「軍師官兵衛」 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-