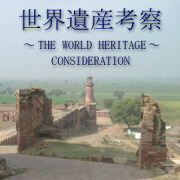【危機遺産】
世界遺産に登録された物件の中で、
未来に残すことが難しくなっているものは、危機遺産に指定されます。
その理由は地震や竜巻などの天災によるものや、
都市化による環境の悪化、紛争や密猟など様々です。
現在危機遺産に指定されている34件は以下の通りです(2006年1月現在)。
・遺産名[危機遺産掲載年](遺産保有国)
・エルサレム旧市街と城壁[1982年](エルサレム(ヨルダン申請))
・アボメーの王宮[1985年](ベナン)
・チャン・チャン遺跡地帯[1986年](ペルー)
・マナス野生生物保護区[1992年](インド)
・ニンバ山厳正自然保護区[1992年](ギニア/コートジボワール)
・アイルとテネレの自然保護区[1992年](ニジェール)
・エヴァーグレーズ国立公園[1993年](アメリカ合衆国)
・ヴィルンガ国立公園[1994年](コンゴ)
・シミエン国立公園[1996年](エチオピア)
・ガランバ国立公園[1996年](コンゴ)
・イシュケウル国立公園[1996年](チュニジア)
・リオ・プラターノ生物圏保護区[1996年](ホンジュラス)
・オカピ野生生物保護区[1997年](コンゴ)
・カフジ=ビエガ国立公園[1997年](コンゴ)
・マノヴォ=グンダ・サン・フローリス国立公園[1997年](中央アフリカ)
・サロンガ国立公園[1999年](コンゴ)
・ハンピの建造物群[1999年](インド)
・古都ザビド[2000年](イエメン)
・ジュジ国立鳥類保護区[2000年](セネガル)
・ラホールの城塞とシャリマール庭園[2000年](パキスタン)
・アブメナ[2001年](エジプト)
・フィリピンの山地の棚田群[2001年](フィリピン)
・ジャームのミナレットと考古遺跡群[2002年](アフガニスタン)
・ティパサ[2002年](アルジェリア)
・バーミヤン渓谷の文化的景観と考古遺跡群[2003年](アフガニスタン)
・アッシュール (カラート・シャルガート)[2003年](イラク)
・シルヴァンシャー宮殿と乙女の塔がある城壁都市バクー[2003年](アゼルバイジャン)
・コモエ国立公園[2003年](コートジボワール)
・カトマンズ渓谷[2004年](ネパール)
・バムとその文化的景観[2004年](イラン)
・キルワ・キシワニ遺跡群とソンゴ・ムナラ遺跡群[2004年](タンザニア)
・ケルン大聖堂[2004年](ドイツ)
・ハンバーストーンおよびサンタ・ラウラの硝石工場群[2005年](チリ)
・コロとその港[2005年](ベネズエラ)
このうち、深刻なのはコンゴです。
コンゴは5つの自然遺産を保有していますが、
なんとその全てが危機遺産に指定されています(2006年1月現在)。
紛争による難民流出や密猟などにより自然遺産の価値も失われつつあります。
国は貧困にあえぎ、とても自然を保護できるような状況にはないのが現状です。
世界遺産に登録された物件の中で、
未来に残すことが難しくなっているものは、危機遺産に指定されます。
その理由は地震や竜巻などの天災によるものや、
都市化による環境の悪化、紛争や密猟など様々です。
現在危機遺産に指定されている34件は以下の通りです(2006年1月現在)。
・遺産名[危機遺産掲載年](遺産保有国)
・エルサレム旧市街と城壁[1982年](エルサレム(ヨルダン申請))
・アボメーの王宮[1985年](ベナン)
・チャン・チャン遺跡地帯[1986年](ペルー)
・マナス野生生物保護区[1992年](インド)
・ニンバ山厳正自然保護区[1992年](ギニア/コートジボワール)
・アイルとテネレの自然保護区[1992年](ニジェール)
・エヴァーグレーズ国立公園[1993年](アメリカ合衆国)
・ヴィルンガ国立公園[1994年](コンゴ)
・シミエン国立公園[1996年](エチオピア)
・ガランバ国立公園[1996年](コンゴ)
・イシュケウル国立公園[1996年](チュニジア)
・リオ・プラターノ生物圏保護区[1996年](ホンジュラス)
・オカピ野生生物保護区[1997年](コンゴ)
・カフジ=ビエガ国立公園[1997年](コンゴ)
・マノヴォ=グンダ・サン・フローリス国立公園[1997年](中央アフリカ)
・サロンガ国立公園[1999年](コンゴ)
・ハンピの建造物群[1999年](インド)
・古都ザビド[2000年](イエメン)
・ジュジ国立鳥類保護区[2000年](セネガル)
・ラホールの城塞とシャリマール庭園[2000年](パキスタン)
・アブメナ[2001年](エジプト)
・フィリピンの山地の棚田群[2001年](フィリピン)
・ジャームのミナレットと考古遺跡群[2002年](アフガニスタン)
・ティパサ[2002年](アルジェリア)
・バーミヤン渓谷の文化的景観と考古遺跡群[2003年](アフガニスタン)
・アッシュール (カラート・シャルガート)[2003年](イラク)
・シルヴァンシャー宮殿と乙女の塔がある城壁都市バクー[2003年](アゼルバイジャン)
・コモエ国立公園[2003年](コートジボワール)
・カトマンズ渓谷[2004年](ネパール)
・バムとその文化的景観[2004年](イラン)
・キルワ・キシワニ遺跡群とソンゴ・ムナラ遺跡群[2004年](タンザニア)
・ケルン大聖堂[2004年](ドイツ)
・ハンバーストーンおよびサンタ・ラウラの硝石工場群[2005年](チリ)
・コロとその港[2005年](ベネズエラ)
このうち、深刻なのはコンゴです。
コンゴは5つの自然遺産を保有していますが、
なんとその全てが危機遺産に指定されています(2006年1月現在)。
紛争による難民流出や密猟などにより自然遺産の価値も失われつつあります。
国は貧困にあえぎ、とても自然を保護できるような状況にはないのが現状です。
|
|
|
|
コメント(11)
ども、こんにちは。
「フィリピンの山地の棚田群」は個人的に非常に興味のある世界遺産です。
特に、人々の伝統農業が作る文化的景観には心惹かれるものがあります。
現地の在住されているということで、さまざまな情報をお持ちでしょう。
ぜひいろいろご教授ください。
まず、具体的にイフガオでは、人々の生活がどのように変わっていっているのでしょうか?
農業の近代化でしょうか、それとも後継者の不足でしょうか。
またそれが棚田にどのような影響を与えているのでしょうか。
あと、2001年に危機遺産に登録されてからもう5年が経ちますが、
フィリピン政府は世界遺産登録維持のために、
どのような対策をしているのでしょうか?
「フィリピンの山地の棚田群」は2000年の歴史を持つ貴重な伝統風習。
ぜひとも後世に繋いでいってほしいと思います。
「フィリピンの山地の棚田群」は個人的に非常に興味のある世界遺産です。
特に、人々の伝統農業が作る文化的景観には心惹かれるものがあります。
現地の在住されているということで、さまざまな情報をお持ちでしょう。
ぜひいろいろご教授ください。
まず、具体的にイフガオでは、人々の生活がどのように変わっていっているのでしょうか?
農業の近代化でしょうか、それとも後継者の不足でしょうか。
またそれが棚田にどのような影響を与えているのでしょうか。
あと、2001年に危機遺産に登録されてからもう5年が経ちますが、
フィリピン政府は世界遺産登録維持のために、
どのような対策をしているのでしょうか?
「フィリピンの山地の棚田群」は2000年の歴史を持つ貴重な伝統風習。
ぜひとも後世に繋いでいってほしいと思います。
文化財保護法における文化的景観についてしらべていたところ、
文化庁のサイトにあった「農林水産業に関連する文化的景観の
保護に関する調査研究」の報告書に
「フィリピンの山地の棚田群」についての記述が見られました。
それによると、同遺産が危機遺産とされている理由は次のようなものだそうです。
・過酷な労働を嫌う若年層が都市へと流出し労働力が著しく不足しつつある
・現代的な材料及び工法の導入が棚田の体系及び景観を微妙に脅かしつつある
・観光客の増加に伴って各自作農家の所得が漸増し各農家の屋根が
茅葺きからトタン葺き等に変化するなど景観への影響が出始めている
一つ目、二つ目はおおむね予想がついたことではありますが、
三つ目には、う〜んとうなってしまいます。
やっぱ、観光客の金が現地の人にも落ちてるんですね。
本来は農業をやって生計を立てている人たちの前に、
突然の金が落ちてくるのでは、確かにいろいろ問題が起きそうですな。
ここのあたりはもう少し詳しくお話をうかがいたいところです。
なお同webサイトには、危機遺産登録を受け、
「フィリピン政府はユネスコの支援のもと、登録地域の正確な地図の作成と
管理計画の策定を行い、地域共同体への支援を開始したところ」とあります。
っていうか、それまで正確な地図や管理計画がなかったんですかい。
管理計画なしに世界遺産申請が受理されるものなのか……
農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査研究(報告)
http://www.bunka.go.jp/1hogo/nourinsuisan_bunkatekikeikan_houkoku.html
文化庁のサイトにあった「農林水産業に関連する文化的景観の
保護に関する調査研究」の報告書に
「フィリピンの山地の棚田群」についての記述が見られました。
それによると、同遺産が危機遺産とされている理由は次のようなものだそうです。
・過酷な労働を嫌う若年層が都市へと流出し労働力が著しく不足しつつある
・現代的な材料及び工法の導入が棚田の体系及び景観を微妙に脅かしつつある
・観光客の増加に伴って各自作農家の所得が漸増し各農家の屋根が
茅葺きからトタン葺き等に変化するなど景観への影響が出始めている
一つ目、二つ目はおおむね予想がついたことではありますが、
三つ目には、う〜んとうなってしまいます。
やっぱ、観光客の金が現地の人にも落ちてるんですね。
本来は農業をやって生計を立てている人たちの前に、
突然の金が落ちてくるのでは、確かにいろいろ問題が起きそうですな。
ここのあたりはもう少し詳しくお話をうかがいたいところです。
なお同webサイトには、危機遺産登録を受け、
「フィリピン政府はユネスコの支援のもと、登録地域の正確な地図の作成と
管理計画の策定を行い、地域共同体への支援を開始したところ」とあります。
っていうか、それまで正確な地図や管理計画がなかったんですかい。
管理計画なしに世界遺産申請が受理されるものなのか……
農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査研究(報告)
http://www.bunka.go.jp/1hogo/nourinsuisan_bunkatekikeikan_houkoku.html
東京藝術大学大学美術館にて行われていた
「世界遺産からのSOS」という写真・映像展に行ってきました。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=3907899&comment_count=24&comm_id=2467
この展覧会はアジアの危機遺産の写真パネルが説明付きで紹介され、
危機遺産物件の現状やそれがなぜ指定されたのかを知ることができました。
展示されていた危機遺産は「バーミヤン渓谷の文化的景観と考古遺跡群」、
「フィリピン・コルディリェーラの棚田群」、「バムとその文化的景観」、
「カトマンドゥ渓谷」の4つの危機遺産。
それに加えて危機遺産から復帰した例として「アンコール」もありました。
これらの危機遺産につき、ざっと書いてみるとします。
「世界遺産からのSOS」という写真・映像展に行ってきました。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=3907899&comment_count=24&comm_id=2467
この展覧会はアジアの危機遺産の写真パネルが説明付きで紹介され、
危機遺産物件の現状やそれがなぜ指定されたのかを知ることができました。
展示されていた危機遺産は「バーミヤン渓谷の文化的景観と考古遺跡群」、
「フィリピン・コルディリェーラの棚田群」、「バムとその文化的景観」、
「カトマンドゥ渓谷」の4つの危機遺産。
それに加えて危機遺産から復帰した例として「アンコール」もありました。
これらの危機遺産につき、ざっと書いてみるとします。
■バーミヤン渓谷の文化的景観と考古遺跡群(アフガニスタン)
2001年、タリバンに大仏が爆破されたというのは記憶に新しいかと思います。
しかし、バーミヤンの被害はそれだけではありません。
バーミヤンにはたくさんの石窟と壁画が残されています。
それらの壁画が人の手により剥ぎ取られ、密輸されているのです。
密輸された壁画の一部はなんと日本で発見され、会場に展示されていました。
ちょっと意外に思ったのは、バーミヤンの大仏は
現地の人にとっても心のよりどころだったという話です。
偶像崇拝を禁止しているイスラム教を信じるバーミヤンの人々ではありますが、
そのような中でも二体の大仏はそれぞれ
お父さん、お母さんと呼ばれ親しまれていたようです。
また、バーミヤンの石窟は、以前は住居や砦として現地の人々に使われていたようです。
現在は世界遺産に登録されたことで誰も住んではいけないことになっているようですが。
2001年、タリバンに大仏が爆破されたというのは記憶に新しいかと思います。
しかし、バーミヤンの被害はそれだけではありません。
バーミヤンにはたくさんの石窟と壁画が残されています。
それらの壁画が人の手により剥ぎ取られ、密輸されているのです。
密輸された壁画の一部はなんと日本で発見され、会場に展示されていました。
ちょっと意外に思ったのは、バーミヤンの大仏は
現地の人にとっても心のよりどころだったという話です。
偶像崇拝を禁止しているイスラム教を信じるバーミヤンの人々ではありますが、
そのような中でも二体の大仏はそれぞれ
お父さん、お母さんと呼ばれ親しまれていたようです。
また、バーミヤンの石窟は、以前は住居や砦として現地の人々に使われていたようです。
現在は世界遺産に登録されたことで誰も住んではいけないことになっているようですが。
■フィリピン・コルディリェーラの棚田群(フィリピン)
ここの現状は自分が思っていたよりも深刻なようです。
危機遺産登録理由は>3で述べたのとおおむね同じですが、
その他にも水をためる役割を持つ棚田の周辺の森林が
伐採されているなどという理由もあるようです。
棚田の一部が崩れている写真はショッキングでした。
若者の都市流出や、観光業に力を入れるようになったことなどにより労働力が不足し、
畑の維持が十分になされていない場所もあるようです。
棚田で農業を行うだけでは十分な収入にはならないという背景があるのでしょう。
そのような棚田の現状に対し各国は、
伐採された山に木を植えたり、村人に生活改善の方法を教えたり、
棚田の未来を担う子供への教育などを行っているようです。
なお、棚田の文化を持つイフガオ族のフドゥフドゥ詠歌が、
無形文化遺産にも登録されていることも初めて知りました。
これは米の収穫などを願って歌われる歌だそうです。
ここの現状は自分が思っていたよりも深刻なようです。
危機遺産登録理由は>3で述べたのとおおむね同じですが、
その他にも水をためる役割を持つ棚田の周辺の森林が
伐採されているなどという理由もあるようです。
棚田の一部が崩れている写真はショッキングでした。
若者の都市流出や、観光業に力を入れるようになったことなどにより労働力が不足し、
畑の維持が十分になされていない場所もあるようです。
棚田で農業を行うだけでは十分な収入にはならないという背景があるのでしょう。
そのような棚田の現状に対し各国は、
伐採された山に木を植えたり、村人に生活改善の方法を教えたり、
棚田の未来を担う子供への教育などを行っているようです。
なお、棚田の文化を持つイフガオ族のフドゥフドゥ詠歌が、
無形文化遺産にも登録されていることも初めて知りました。
これは米の収穫などを願って歌われる歌だそうです。
■バムとその文化的景観(イラン)
バムは世界最大の日干しレンガで作られた建築物でした。
城塞を中心にさまざまな日干しレンガの建物がならぶバムは
2000年以上の歴史がある古都でした。
イランは世界遺産に登録しようと準備を進めていたようです。
そんな矢先の2003年、ここは地震が襲われ一瞬にして壊滅しました。
街も城塞も潰れてしまい、歴史地区の70%が崩壊したといいます。
死者は4万人。バムの人口の1/3が亡くなったそうです。
会場には写真が並んでいましたが、美しい土色をした建物が並ぶ地震前の写真と、
崩壊して土砂と化した地震後の写真を比べてみると、
そこが同じ場所だったとは思えないくらいの変わりようです。
いくら日干しレンガは耐震性が低いとはいえ、驚きました。
その深刻度はおそらくどの危機遺産よりも高いでしょう。
バムを復旧させるといいますが、それはバムの街すべてを再建するのと
同じ意味を持つものだと思います。
気の遠くなるほどの時間と労力が必要となるでしょう。
いつかはかつての美しい古都が復活することを願っています。
バムは世界最大の日干しレンガで作られた建築物でした。
城塞を中心にさまざまな日干しレンガの建物がならぶバムは
2000年以上の歴史がある古都でした。
イランは世界遺産に登録しようと準備を進めていたようです。
そんな矢先の2003年、ここは地震が襲われ一瞬にして壊滅しました。
街も城塞も潰れてしまい、歴史地区の70%が崩壊したといいます。
死者は4万人。バムの人口の1/3が亡くなったそうです。
会場には写真が並んでいましたが、美しい土色をした建物が並ぶ地震前の写真と、
崩壊して土砂と化した地震後の写真を比べてみると、
そこが同じ場所だったとは思えないくらいの変わりようです。
いくら日干しレンガは耐震性が低いとはいえ、驚きました。
その深刻度はおそらくどの危機遺産よりも高いでしょう。
バムを復旧させるといいますが、それはバムの街すべてを再建するのと
同じ意味を持つものだと思います。
気の遠くなるほどの時間と労力が必要となるでしょう。
いつかはかつての美しい古都が復活することを願っています。
■カトマンドゥ渓谷(ネパール)
カトマンドゥはその町並みの急激な都市化により伝統的な町並みが失われつつあります。
町並みを考えずに無秩序な開発がどんどん行われ、
歴史的建造物がかなり破壊されているようです。
また、処理しきれない膨大な量のゴミ、排気ガスによる
世界最悪レベルの空気汚染など環境面の悪化もあるようです。
また、衛星放送やインターネットなどを通じて情報が膨大に入り、
人々の考え方も急激に都会化しつつあります。
神々への信仰心が低下し、同時に文化財への関心も低下してしまい、
個人個人による文化財の保護レベルが著しく下がっているようです。
国が保護しようにも、そもそもネパールの政治が非常に不安定ですので、
満足な保護策を打てない状況なのかと思います。
カトマンドゥはその町並みの急激な都市化により伝統的な町並みが失われつつあります。
町並みを考えずに無秩序な開発がどんどん行われ、
歴史的建造物がかなり破壊されているようです。
また、処理しきれない膨大な量のゴミ、排気ガスによる
世界最悪レベルの空気汚染など環境面の悪化もあるようです。
また、衛星放送やインターネットなどを通じて情報が膨大に入り、
人々の考え方も急激に都会化しつつあります。
神々への信仰心が低下し、同時に文化財への関心も低下してしまい、
個人個人による文化財の保護レベルが著しく下がっているようです。
国が保護しようにも、そもそもネパールの政治が非常に不安定ですので、
満足な保護策を打てない状況なのかと思います。
■カンボジアのアンコール以外の遺跡群
「アンコール」は、危機遺産から脱した例という位置づけでした。
フランスや日本による支援、現地の人の専門家の育成などにより、
「アンコール」は確かに危機を脱しました。
しかし、カンボジアには「アンコール」にも引けをとらない遺跡がまだたくさんあります
(カンボジアの世界遺産暫定リストには10の物件が記載されています)。
確かに「アンコール」は盗掘や破壊から守られるようになりましたが、
「アンコール」に手を出せなくなってからは
地方に散らばる他の遺跡が盗掘のターゲットとなっているようです。
これまでにもレリーフが剥ぎ取られたり、
破壊されたりと文化財の甚大な損失が続いているようです。
その価値はアンコールと同様なだけに、非常に心配です。
「アンコール」は、危機遺産から脱した例という位置づけでした。
フランスや日本による支援、現地の人の専門家の育成などにより、
「アンコール」は確かに危機を脱しました。
しかし、カンボジアには「アンコール」にも引けをとらない遺跡がまだたくさんあります
(カンボジアの世界遺産暫定リストには10の物件が記載されています)。
確かに「アンコール」は盗掘や破壊から守られるようになりましたが、
「アンコール」に手を出せなくなってからは
地方に散らばる他の遺跡が盗掘のターゲットとなっているようです。
これまでにもレリーフが剥ぎ取られたり、
破壊されたりと文化財の甚大な損失が続いているようです。
その価値はアンコールと同様なだけに、非常に心配です。
現在リトアニアのビリニュスで開催している第30回世界遺産委員会で、
次の物件が”危機遺産リストから”削除されました
(世界遺産リストからの登録抹消ではないのでお間違いなく)。
・ケルン大聖堂(ドイツ)
・ジュッジ国立鳥類保護区(セネガル)
・シュウケル国立公園(チュニジア)
・ハンピの建造物(インド)
中でも注目はケルン大聖堂でしょう。
ケルン大聖堂は、ゴシック建築の傑作として
世界遺産リストに登録された物件ですが、
その背後に高層ビル建設が計画され、
それにより空間的統合性が損なわれるとして、
2004年の世界遺産委員会で危機遺産リストに登録されました。
しかし、新しく建設される高層ビルの高さが低くなったことと、
周辺の管理状況が改善されたということで、
今回危機遺産リストから削除されるにいたりました。
物件そのものの保存状態に不備がなくても、
背後の景観が破壊されるという理由で危機遺産リストに
登録されたのはケルン大聖堂が初めてで、
この件はさまざまな議論を呼びました。
「ビルが建設されたのならば、世界遺産から登録抹消すべきだ」
という意見もあり、今回の世界遺産委員会ではケルン大聖堂が
世界遺産から登録抹消されるのではと注目されていました。
近年、世界遺産では「景観」が重要視されてきています。
しかしながら、景観破壊が世界遺産登録抹消の理由になるとしたら、
都市部に存在するすべての世界遺産について
登録抹消の可能性が出てくるということです。
日本でも、原爆ドームの背後にマンションが建つということで、
その景観破壊が問題となり、その建設中止が叫ばれています。
ケルン大聖堂の危機遺産登録は、景観破壊に対する警鐘、
見せしめのようなことだったのでしょう。
世界遺産リストからの登録削除まで論じられておきながら、
思ったより甘い改善で危機リストから削除されたことは、
多くの人にとって意外なことだったのではないかと思います。
とはいえ、このケルン大聖堂の問題が今後の世界遺産に与える
影響は極めて大きいものに違いありません。
次の物件が”危機遺産リストから”削除されました
(世界遺産リストからの登録抹消ではないのでお間違いなく)。
・ケルン大聖堂(ドイツ)
・ジュッジ国立鳥類保護区(セネガル)
・シュウケル国立公園(チュニジア)
・ハンピの建造物(インド)
中でも注目はケルン大聖堂でしょう。
ケルン大聖堂は、ゴシック建築の傑作として
世界遺産リストに登録された物件ですが、
その背後に高層ビル建設が計画され、
それにより空間的統合性が損なわれるとして、
2004年の世界遺産委員会で危機遺産リストに登録されました。
しかし、新しく建設される高層ビルの高さが低くなったことと、
周辺の管理状況が改善されたということで、
今回危機遺産リストから削除されるにいたりました。
物件そのものの保存状態に不備がなくても、
背後の景観が破壊されるという理由で危機遺産リストに
登録されたのはケルン大聖堂が初めてで、
この件はさまざまな議論を呼びました。
「ビルが建設されたのならば、世界遺産から登録抹消すべきだ」
という意見もあり、今回の世界遺産委員会ではケルン大聖堂が
世界遺産から登録抹消されるのではと注目されていました。
近年、世界遺産では「景観」が重要視されてきています。
しかしながら、景観破壊が世界遺産登録抹消の理由になるとしたら、
都市部に存在するすべての世界遺産について
登録抹消の可能性が出てくるということです。
日本でも、原爆ドームの背後にマンションが建つということで、
その景観破壊が問題となり、その建設中止が叫ばれています。
ケルン大聖堂の危機遺産登録は、景観破壊に対する警鐘、
見せしめのようなことだったのでしょう。
世界遺産リストからの登録削除まで論じられておきながら、
思ったより甘い改善で危機リストから削除されたことは、
多くの人にとって意外なことだったのではないかと思います。
とはいえ、このケルン大聖堂の問題が今後の世界遺産に与える
影響は極めて大きいものに違いありません。
本日の世界遺産委員会において、
ドイツのドレスデン・エルベ渓谷が危機遺産リストに登録されました。
その危機遺産登録理由は、ドレスデンのエルベ川に
架橋工事の計画があるためです。この架橋工事について委員会は、
世界遺産に登録される価値を無くすまでの影響がある
とし、もし計画が実行されたら2007年に
世界遺産リストから削除するしています。
驚くことに、今回の危機遺産登録も景観破壊という理由、
しかもまたもやドイツの物件から登録されてしまいました。
ドレスデン・エルベ渓谷は、エルベ川沿い18kmに渡って、
18世紀から19世紀の文化的景観を残す近代の産業遺産です。
その文化的景観の適用範囲は幅広く、牧草地から
16世紀から20世紀に作られた建造物、庭園、
19世紀末に建造された鉄橋、ケーブルカー、蒸気船、
造船所などがその文化的景観を構成する要素とされています。
ドレスデン・エルベ渓谷は、文化遺産登録基準(ii)(iii)(iv)(v)に加え
文化的景観も適用されている物件です。
ゆえに、その景観はドレスデン・エルベ渓谷が
世界遺産に登録された大きな理由であり、
今回の危機遺産リスト登録はケルン大聖堂に比べると
誰もが納得しやすい危機遺産リスト登録だということができます。
ケルン大聖堂の場合は工事の規模縮小と周辺環境の向上により
危機遺産から脱しましたが、今回は文化的景観適用物件だけに、
工事の規模縮小だけでは危機遺産リストからの脱却は難しいと思います。
危機遺産リストから脱却できるとしたら、
それは工事の中止のみででしょう。
近年世界遺産ではその景観が重要視されています。
今後文化的景観が適用される物件はますます増えていくことでしょう。
日本でも、2004年に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」が
文化的景観適用物件ですし、来年の世界遺産委員会で審議される
「石見銀山とその文化的景観」および来年推薦予定の
「平泉―浄土思想に関連する文化的景観―」もまた
文化的景観がキーとなっています。
今後は、世界遺産は文化財が単体として登録されるのではなく、
周辺環境もまとめて保護するのが当然となっていくのかもしれません。
ドイツのドレスデン・エルベ渓谷が危機遺産リストに登録されました。
その危機遺産登録理由は、ドレスデンのエルベ川に
架橋工事の計画があるためです。この架橋工事について委員会は、
世界遺産に登録される価値を無くすまでの影響がある
とし、もし計画が実行されたら2007年に
世界遺産リストから削除するしています。
驚くことに、今回の危機遺産登録も景観破壊という理由、
しかもまたもやドイツの物件から登録されてしまいました。
ドレスデン・エルベ渓谷は、エルベ川沿い18kmに渡って、
18世紀から19世紀の文化的景観を残す近代の産業遺産です。
その文化的景観の適用範囲は幅広く、牧草地から
16世紀から20世紀に作られた建造物、庭園、
19世紀末に建造された鉄橋、ケーブルカー、蒸気船、
造船所などがその文化的景観を構成する要素とされています。
ドレスデン・エルベ渓谷は、文化遺産登録基準(ii)(iii)(iv)(v)に加え
文化的景観も適用されている物件です。
ゆえに、その景観はドレスデン・エルベ渓谷が
世界遺産に登録された大きな理由であり、
今回の危機遺産リスト登録はケルン大聖堂に比べると
誰もが納得しやすい危機遺産リスト登録だということができます。
ケルン大聖堂の場合は工事の規模縮小と周辺環境の向上により
危機遺産から脱しましたが、今回は文化的景観適用物件だけに、
工事の規模縮小だけでは危機遺産リストからの脱却は難しいと思います。
危機遺産リストから脱却できるとしたら、
それは工事の中止のみででしょう。
近年世界遺産ではその景観が重要視されています。
今後文化的景観が適用される物件はますます増えていくことでしょう。
日本でも、2004年に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」が
文化的景観適用物件ですし、来年の世界遺産委員会で審議される
「石見銀山とその文化的景観」および来年推薦予定の
「平泉―浄土思想に関連する文化的景観―」もまた
文化的景観がキーとなっています。
今後は、世界遺産は文化財が単体として登録されるのではなく、
周辺環境もまとめて保護するのが当然となっていくのかもしれません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
世界遺産考察 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
世界遺産考察のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90059人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208291人