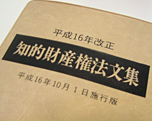弁理士の資格をとるべきか悩んでいます。アドバイス頂ければと思います。
過去に弁理士自体を目指すかたの似たようなトピックがありましたが、研究職を続ける上でのメリットについて教えてください。
私は二十代後半、医薬系企業勤務(研究職)、資格としては化学系で博士と危険物取扱-甲種を持っています。
弁理士は学生時代から興味があり勉強をはじめようと考えているのですが、資格を取るまでに必要となる費用・労力を考えると中々踏み出せません。
研究職を続けていく前提で、弁理士資格取得のメリットについて以下の点などがあると考えています。
・研究開発品の特許化における実務への対応
・知財部の方とのスムーズな連携
・昇進のため(スキルアップ、能力の証明)
・知財部への移動という選択肢の増加
・同業他社への転職などにおいて有利な資格
これらは正しいのでしょうか?また、他のメリットはあるのでしょうか?弁理士・知財部・研究職で弁理士を目指している・研究職で弁理士を持っている方々の様々な経験・意見を募集いたします。
過去に弁理士自体を目指すかたの似たようなトピックがありましたが、研究職を続ける上でのメリットについて教えてください。
私は二十代後半、医薬系企業勤務(研究職)、資格としては化学系で博士と危険物取扱-甲種を持っています。
弁理士は学生時代から興味があり勉強をはじめようと考えているのですが、資格を取るまでに必要となる費用・労力を考えると中々踏み出せません。
研究職を続けていく前提で、弁理士資格取得のメリットについて以下の点などがあると考えています。
・研究開発品の特許化における実務への対応
・知財部の方とのスムーズな連携
・昇進のため(スキルアップ、能力の証明)
・知財部への移動という選択肢の増加
・同業他社への転職などにおいて有利な資格
これらは正しいのでしょうか?また、他のメリットはあるのでしょうか?弁理士・知財部・研究職で弁理士を目指している・研究職で弁理士を持っている方々の様々な経験・意見を募集いたします。
|
|
|
|
コメント(69)
しばらく見ていない間にたくさんの回答ありがとうございます。
資格を早く取ると損する可能性がある。という話は非常に興味深いですね。
ただあまり後になると合格するのが大変そうです。私は記憶力も落ちてきてますし。
私の考えは夢を食う動物バカ さんに近いものです。
研究は努力したからといって結果がでるものではないです、相当な努力、才能は当然として大きくは運が絡んできます。ほとんどの大きな研究結果は努力に裏打ちされた幸運・偶然の発見によって得られます(セレンディピティといいます)。田中さんのノーベル賞研究はかなり特殊な例です。
また、仮に昇進して研究のマネージメント業務に携わるようになれば、特許関連の仕事もあると思います。その時に、資格を持っていて「損はない」ということです。
少なくともまったく関係無いが一流の資格(行政書士、公認会計士)などにチャレンジするよりは活かせると考えているのですが・・・。
かけた時間・資金を回収しなければ意味がない。といわれると博士の資格とはとれなかったなぁとも思います。
自分の人生の経験、達成感として弁理士資格が挑戦する価値があるとともに、業務に活かせる(かも)、転職の際に使える。など総合的に判断しました。
逆に、研究職(化学・薬学)が時間・資金を投資して、回収できる資格があるのならアドバイスが欲しいところです。あとは英語くらいでしょうか?
資格を早く取ると損する可能性がある。という話は非常に興味深いですね。
ただあまり後になると合格するのが大変そうです。私は記憶力も落ちてきてますし。
私の考えは夢を食う動物バカ さんに近いものです。
研究は努力したからといって結果がでるものではないです、相当な努力、才能は当然として大きくは運が絡んできます。ほとんどの大きな研究結果は努力に裏打ちされた幸運・偶然の発見によって得られます(セレンディピティといいます)。田中さんのノーベル賞研究はかなり特殊な例です。
また、仮に昇進して研究のマネージメント業務に携わるようになれば、特許関連の仕事もあると思います。その時に、資格を持っていて「損はない」ということです。
少なくともまったく関係無いが一流の資格(行政書士、公認会計士)などにチャレンジするよりは活かせると考えているのですが・・・。
かけた時間・資金を回収しなければ意味がない。といわれると博士の資格とはとれなかったなぁとも思います。
自分の人生の経験、達成感として弁理士資格が挑戦する価値があるとともに、業務に活かせる(かも)、転職の際に使える。など総合的に判断しました。
逆に、研究職(化学・薬学)が時間・資金を投資して、回収できる資格があるのならアドバイスが欲しいところです。あとは英語くらいでしょうか?
カミサカさんのお気持ち私もよく分かります。根本的には何か大きなことに挑戦して達成したいという欲求から来たものではないですか?
私も理系大学院卒業してちょっと知的財産のライセンス関連の仕事していたため、また仕事でもプライベートでも夢中で熱中できるものがなく、無為に時間を費やすよりは達成した暁には涙がでるくらい大きな達成感が欲しいと勉強始めました(数ヶ月勉強したらソウル異動になったのですが)。いろいろ調べた結果としても、実際やってみた結果としても、どなたかおっしゃっているように予備校は「時間をお金で買うことができること」が最大のメリットで独学では得られないものと思います。とはいえ動機がそんなものですので試験前数ヶ月に集中的にやって2回受験した程度です。結局今年は1次試験合格に4点足りず、来年の再受験を考えている状態ですので、余り参考にならないかもしれませんが。
一言で言うならば保険という気持ちもありますがやはり挑戦という部分が大きいのでは。ただ、皆様おっしゃっているように、そしてカミサカさんもご存知のように時間もお金も弁理士試験の代償は膨大です。しかし、私は単なる資格そのものという意味だけでなく、それに向かって努力して成果を残したという結果が将来の自信とPRにつながるという意味で挑戦の価値はあると考えています。
志したもののモチベーションが続かずに弁理士を断念する人も後を絶たないことも紛れもない事実ですが。そして私もその候補になりつつあるような(笑)。
私も理系大学院卒業してちょっと知的財産のライセンス関連の仕事していたため、また仕事でもプライベートでも夢中で熱中できるものがなく、無為に時間を費やすよりは達成した暁には涙がでるくらい大きな達成感が欲しいと勉強始めました(数ヶ月勉強したらソウル異動になったのですが)。いろいろ調べた結果としても、実際やってみた結果としても、どなたかおっしゃっているように予備校は「時間をお金で買うことができること」が最大のメリットで独学では得られないものと思います。とはいえ動機がそんなものですので試験前数ヶ月に集中的にやって2回受験した程度です。結局今年は1次試験合格に4点足りず、来年の再受験を考えている状態ですので、余り参考にならないかもしれませんが。
一言で言うならば保険という気持ちもありますがやはり挑戦という部分が大きいのでは。ただ、皆様おっしゃっているように、そしてカミサカさんもご存知のように時間もお金も弁理士試験の代償は膨大です。しかし、私は単なる資格そのものという意味だけでなく、それに向かって努力して成果を残したという結果が将来の自信とPRにつながるという意味で挑戦の価値はあると考えています。
志したもののモチベーションが続かずに弁理士を断念する人も後を絶たないことも紛れもない事実ですが。そして私もその候補になりつつあるような(笑)。
本当にいろいろな意見が出ましたね。私も皆さんのご意見を拝見してとても勉強になります。これらのご意見を拝見して考えたことを書きます。
18番:カミサカさん
>個人的には両方が必要な時代と考えています。弁理士は、生み出された発明の権利を守り、経済発展に寄与できる素晴らしいかつ重要な職業と思います。
弁理士業という職業にあこがれのようなものを抱いておられると拝察しましたが、弁理士業の実際を身近なところで見ていると、そんなに素晴らしいわけではないと思います。
そもそも特許出願とは何かですが、人間は発明をしたら、「俺の発明は俺のものだ。他人にはまねされたくない」というエゴイズムをいだくわけじゃないですか。そういう発明の秘匿への志向性に歯止めをかけ、これを公開させるというのが特許の制度だと私は理解しています。
つまり、特許制度の発明者へのメッセージは、「お前の発明を特許出願して公開せよ。そのかわり『俺の発明は俺のものだ。他人にはまねさせない』というエゴイズムを一定期間認めてやる」ということに過ぎないと思います。すると、特許出願の業としての代理人である弁理士とは、こういう出願人のエゴイズムの手続上の代理人でしかないという解釈も成り立つと思います。
だから、「素晴らしいかつ重要な職業」というのはちょっと甘い幻想かな、という気もします。
28番:ゆっき〜♪さん
>仮に取得してから10年後に使おうとしてもそれはもう使えない資格になっているでしょう。
>弁理士の資格を持っているという肩書きだけで実力は無くなっているからです。肩書きだけで仕事を貰えるとは思えません。
このゆっき〜♪さんの着眼点はとても重要だと思います。なおとさんも触れておられたと思いますが、弁理士は資格を取った直後が旬だと思うんですよ。野菜でも果物でも魚でも旬のころが一番おいしいし、買いどきであり、売りどきでもあります。
もしカミサカさんが弁理士資格を取得されたら、弁理士として旬であるうちに自分を高く売り込むようにするべきです。具体的には、良い特許事務所に転職するとか、知財部に配置転換してもらってそこの幹部として活躍するなどの方向に進むべきです。「弁理士として旬であるうちに自分を高く売り込む」というのは、いかにも処世術という感じがしますが、人生とはそういうものだと思います。
逆に言うと、そういう方向に行動する意思が明確ではないなら、資格取得は労力が報われないだろうと考えます。
カミサカさんが研究部門の管理職になったときに弁理士の資格があると役立つ、というお考えもあるようですが、これは知財部のスタッフや外注機関としての特許事務所とコンタクトをするときの障害にならない程度に特許法の枠組みを知っていさえすれば問題はないと思います。
逆に、カミサカさんが研究部門の管理職になったときに本当に求められる能力は、もっと別のところにあります。それは研究者の目利きをすることです。つまり、若い研究者の卵たちを見て、「この人は伸びそうだ」という人を発掘するとか、「いまこの人にはこういう啓発を与えることが必要だ」とか、そういう洞察をして問題解決に行動することです。いまの日本には、特に部長級管理職の人でそういうことがちゃんとできる人が本当に少ない。カミサカさんはそういうことがちゃんとできる人に成長して欲しいと思います。
逆に、下手に弁理士資格など取ってしまうと、管理職としてものの考え方が官僚的になってしまい、組織の硬直化をまねくことだってありえます。
18番:カミサカさん
>個人的には両方が必要な時代と考えています。弁理士は、生み出された発明の権利を守り、経済発展に寄与できる素晴らしいかつ重要な職業と思います。
弁理士業という職業にあこがれのようなものを抱いておられると拝察しましたが、弁理士業の実際を身近なところで見ていると、そんなに素晴らしいわけではないと思います。
そもそも特許出願とは何かですが、人間は発明をしたら、「俺の発明は俺のものだ。他人にはまねされたくない」というエゴイズムをいだくわけじゃないですか。そういう発明の秘匿への志向性に歯止めをかけ、これを公開させるというのが特許の制度だと私は理解しています。
つまり、特許制度の発明者へのメッセージは、「お前の発明を特許出願して公開せよ。そのかわり『俺の発明は俺のものだ。他人にはまねさせない』というエゴイズムを一定期間認めてやる」ということに過ぎないと思います。すると、特許出願の業としての代理人である弁理士とは、こういう出願人のエゴイズムの手続上の代理人でしかないという解釈も成り立つと思います。
だから、「素晴らしいかつ重要な職業」というのはちょっと甘い幻想かな、という気もします。
28番:ゆっき〜♪さん
>仮に取得してから10年後に使おうとしてもそれはもう使えない資格になっているでしょう。
>弁理士の資格を持っているという肩書きだけで実力は無くなっているからです。肩書きだけで仕事を貰えるとは思えません。
このゆっき〜♪さんの着眼点はとても重要だと思います。なおとさんも触れておられたと思いますが、弁理士は資格を取った直後が旬だと思うんですよ。野菜でも果物でも魚でも旬のころが一番おいしいし、買いどきであり、売りどきでもあります。
もしカミサカさんが弁理士資格を取得されたら、弁理士として旬であるうちに自分を高く売り込むようにするべきです。具体的には、良い特許事務所に転職するとか、知財部に配置転換してもらってそこの幹部として活躍するなどの方向に進むべきです。「弁理士として旬であるうちに自分を高く売り込む」というのは、いかにも処世術という感じがしますが、人生とはそういうものだと思います。
逆に言うと、そういう方向に行動する意思が明確ではないなら、資格取得は労力が報われないだろうと考えます。
カミサカさんが研究部門の管理職になったときに弁理士の資格があると役立つ、というお考えもあるようですが、これは知財部のスタッフや外注機関としての特許事務所とコンタクトをするときの障害にならない程度に特許法の枠組みを知っていさえすれば問題はないと思います。
逆に、カミサカさんが研究部門の管理職になったときに本当に求められる能力は、もっと別のところにあります。それは研究者の目利きをすることです。つまり、若い研究者の卵たちを見て、「この人は伸びそうだ」という人を発掘するとか、「いまこの人にはこういう啓発を与えることが必要だ」とか、そういう洞察をして問題解決に行動することです。いまの日本には、特に部長級管理職の人でそういうことがちゃんとできる人が本当に少ない。カミサカさんはそういうことがちゃんとできる人に成長して欲しいと思います。
逆に、下手に弁理士資格など取ってしまうと、管理職としてものの考え方が官僚的になってしまい、組織の硬直化をまねくことだってありえます。
こんにちは。
私は研究職を続けつつ、企業内で弁理士として働こうと考え、勉強しているものです。
このスレッドの趣旨とは外れているかもしれませんが、何らかの参考になればと思います。
また、携帯からなので文章がいまいち変かもしれませんが、ご容赦ください。
研究者が弁理士の勉強をするメリットがあります。
これは自分で勉強してて思ったのですが、実は研究者って、精神的に不安定なことが多いです。
というのも、研究成果ってなかなか出るものではないからです。
研究成果が出ないと焦りますが、そんなとき弁理士の勉強してると、結構落ち着くことができました。理由はいろいろありますが、
1.自分には別の道もあり得るから、ここで無理に成果出さなくても大丈夫だと思えること
2.頭をリフレッシュできること
などが挙げられると思います。
正直、私は弁理士の試験勉強をしてからの方が、始める前よりはるかに成果をあげています。論文の勉強はそのまま各種プレゼンに役立ちますしね。
どんな仕事でも、時間を割けば割くほど結果が出るわけではない、と考えています。仕事に没頭すればするほど結果を客観視できなくなるためです。もちろん必要な程度の時間は働かなければなりませんが。
逆に、弁理士が研究をするメリットを考えますと、
1.最先端の技術を理解できる
2.その分野のエキスパートでもあるため、発明者に信用されやすい
まだ弁理士になってもいないうちからすみません。
しかし、現在発明者として出願してますが、その立場からみると上記のように思います。また、上記は重複していると思いますが、両方重要です。
最先端の技術が理解するのはそもそも研究者でさえ厳しいですが、弁理士にはもっと厳しいでしょう。結果、単語の使い方が全くおかしいか、数年前のスタンダードに立脚した明細書が出来上がりかねません。
これは弁理士さんが悪いのではなく、現在の技術が高度に細分化専門化されたためです。そのため、明細書を書くことに長けた弁理士のほかに、技術と法律の双方に詳しい研究者弁理士の人材は、これから需要があると考えます。
また、研究開発に携わる人は、えてして技術を理解していない人を軽視し、信用しない傾向にあります(私はそんなことしません!)。担当弁理士を選ぶ権限が研究開発部門にあるかどうかはともかく、強い特許を生み出すという観点からすると、研究開発担当者と弁理士との信頼関係は必要不可欠です。
以上のように、私は研究職兼弁理士を目指すメリットはあると思います。
駄文失礼しました
私は研究職を続けつつ、企業内で弁理士として働こうと考え、勉強しているものです。
このスレッドの趣旨とは外れているかもしれませんが、何らかの参考になればと思います。
また、携帯からなので文章がいまいち変かもしれませんが、ご容赦ください。
研究者が弁理士の勉強をするメリットがあります。
これは自分で勉強してて思ったのですが、実は研究者って、精神的に不安定なことが多いです。
というのも、研究成果ってなかなか出るものではないからです。
研究成果が出ないと焦りますが、そんなとき弁理士の勉強してると、結構落ち着くことができました。理由はいろいろありますが、
1.自分には別の道もあり得るから、ここで無理に成果出さなくても大丈夫だと思えること
2.頭をリフレッシュできること
などが挙げられると思います。
正直、私は弁理士の試験勉強をしてからの方が、始める前よりはるかに成果をあげています。論文の勉強はそのまま各種プレゼンに役立ちますしね。
どんな仕事でも、時間を割けば割くほど結果が出るわけではない、と考えています。仕事に没頭すればするほど結果を客観視できなくなるためです。もちろん必要な程度の時間は働かなければなりませんが。
逆に、弁理士が研究をするメリットを考えますと、
1.最先端の技術を理解できる
2.その分野のエキスパートでもあるため、発明者に信用されやすい
まだ弁理士になってもいないうちからすみません。
しかし、現在発明者として出願してますが、その立場からみると上記のように思います。また、上記は重複していると思いますが、両方重要です。
最先端の技術が理解するのはそもそも研究者でさえ厳しいですが、弁理士にはもっと厳しいでしょう。結果、単語の使い方が全くおかしいか、数年前のスタンダードに立脚した明細書が出来上がりかねません。
これは弁理士さんが悪いのではなく、現在の技術が高度に細分化専門化されたためです。そのため、明細書を書くことに長けた弁理士のほかに、技術と法律の双方に詳しい研究者弁理士の人材は、これから需要があると考えます。
また、研究開発に携わる人は、えてして技術を理解していない人を軽視し、信用しない傾向にあります(私はそんなことしません!)。担当弁理士を選ぶ権限が研究開発部門にあるかどうかはともかく、強い特許を生み出すという観点からすると、研究開発担当者と弁理士との信頼関係は必要不可欠です。
以上のように、私は研究職兼弁理士を目指すメリットはあると思います。
駄文失礼しました
企業内弁理士の者です。
研究者の方が、弁理士資格を取得するメリットは
あるのではないかと思います。
発明者の方の中には、特許を出願して、
特許制度を良く知らずに知財部に任せて
おられる方もいますが、
優秀な発明者の方ほど、特許制度に興味を持たれ、
積極的に意見されています。
但し、弁理士資格=実務に生かせる
訳ではありません。
弁理士資格の中で、企業内で生かせる知識は、
特許法の前半、49条位まででしょう。
実務の中で効率的に知識を生かしていきたいのであれば、
特許法の前半、及び、外国の特許制度(米国、欧州、中国)
を勉強されることをお勧めします。
補正の時期はいつか、補正の範囲はどれくらいか、
分割の時期はいつか等、拒絶の回数は何回か、
知っておくべき知識は、僅かですし、ポイントを抑えて
各国制度の違いを勉強されると、いいと思います。
明細書作成、中間対応にも興味を持たれれば、
弁理士の実務も学べますし、
弁理士資格の中には無駄な?知識も多いですが、
研究者の方が弁理士資格を取得されるのは、
理想的だと思います。
「達成感+実益」
のうち、達成感はあると思います。
実益に関しても、上記のようにあるんじゃないですか?
ただ、常に実務でどう生かしていくのか考えられたほうが
いいと思います。弁理士資格が目標にならないように
しないといけないと思います。
研究者の方が、弁理士資格を取得するメリットは
あるのではないかと思います。
発明者の方の中には、特許を出願して、
特許制度を良く知らずに知財部に任せて
おられる方もいますが、
優秀な発明者の方ほど、特許制度に興味を持たれ、
積極的に意見されています。
但し、弁理士資格=実務に生かせる
訳ではありません。
弁理士資格の中で、企業内で生かせる知識は、
特許法の前半、49条位まででしょう。
実務の中で効率的に知識を生かしていきたいのであれば、
特許法の前半、及び、外国の特許制度(米国、欧州、中国)
を勉強されることをお勧めします。
補正の時期はいつか、補正の範囲はどれくらいか、
分割の時期はいつか等、拒絶の回数は何回か、
知っておくべき知識は、僅かですし、ポイントを抑えて
各国制度の違いを勉強されると、いいと思います。
明細書作成、中間対応にも興味を持たれれば、
弁理士の実務も学べますし、
弁理士資格の中には無駄な?知識も多いですが、
研究者の方が弁理士資格を取得されるのは、
理想的だと思います。
「達成感+実益」
のうち、達成感はあると思います。
実益に関しても、上記のようにあるんじゃないですか?
ただ、常に実務でどう生かしていくのか考えられたほうが
いいと思います。弁理士資格が目標にならないように
しないといけないと思います。
あと、早く弁理士資格を取った人の方が、
価値があまりないようなことが記載されていましたが、
むしろ逆だと思います。
先に合格された方の方が
どちらかというと重宝されます。
慣習のようですが。
弁理士であれば、最新の法改正も把握していて
当然だと思われますし、
遅く合格した方が有利だとの話は聞いたことがありません。
また、単に特許事務所で働いている弁理士よりも、
技術に実際に携わっている弁理士の方が価値があると
思います。
明細書の実務は5年もやれば身につくと思いますが、
技術は後から身につけられませんからね。
企業内におられるのであれば、
知財部でも働けますし、弁理士取得のメリットはあるんじゃ
ないですか?
最近は、技術トレンドの変化が早すぎて、
技術者の方も大変のようですね。
息抜き、精神的安定のために勉強されるのもいいと思います。
価値があまりないようなことが記載されていましたが、
むしろ逆だと思います。
先に合格された方の方が
どちらかというと重宝されます。
慣習のようですが。
弁理士であれば、最新の法改正も把握していて
当然だと思われますし、
遅く合格した方が有利だとの話は聞いたことがありません。
また、単に特許事務所で働いている弁理士よりも、
技術に実際に携わっている弁理士の方が価値があると
思います。
明細書の実務は5年もやれば身につくと思いますが、
技術は後から身につけられませんからね。
企業内におられるのであれば、
知財部でも働けますし、弁理士取得のメリットはあるんじゃ
ないですか?
最近は、技術トレンドの変化が早すぎて、
技術者の方も大変のようですね。
息抜き、精神的安定のために勉強されるのもいいと思います。
あと、実際に弁理士資格を取得して感じることですが、
弁理士資格の知識の中には、
実務ではあまり生かせない知識が多い(意匠、商標、著作権等)ので、
それを覚悟する必要があります。
雑学を必死で勉強する意志があれば、
勉強されればいいと思います。
また、論文の勉強がプレゼンに生かせるとの記載がありましたが、
実際は生かせないと思います。
今の試験の論文は項目列挙になっていますので、
プレゼンに生かせるかと言われるとかなり疑問です。
資格を取得することで、考えが凝り固まるような記載もありましたが、
条文を正しく理解することで、なぜ考えが固まるのか理解できません。
むしろ、マネージャーになるときに、
知財管理がうまくできていいように思いますが。
弁理士資格を持っているということで、
周りから凝り固まっているような印象を与えてしまうのでしょうか?
正しい知識で主張すれば、むしろ有利にも思えますが。
連休で暇だったので、大量に記載してしまいましたが、
参考になる点を拾って行って下さい。
弁理士資格の知識の中には、
実務ではあまり生かせない知識が多い(意匠、商標、著作権等)ので、
それを覚悟する必要があります。
雑学を必死で勉強する意志があれば、
勉強されればいいと思います。
また、論文の勉強がプレゼンに生かせるとの記載がありましたが、
実際は生かせないと思います。
今の試験の論文は項目列挙になっていますので、
プレゼンに生かせるかと言われるとかなり疑問です。
資格を取得することで、考えが凝り固まるような記載もありましたが、
条文を正しく理解することで、なぜ考えが固まるのか理解できません。
むしろ、マネージャーになるときに、
知財管理がうまくできていいように思いますが。
弁理士資格を持っているということで、
周りから凝り固まっているような印象を与えてしまうのでしょうか?
正しい知識で主張すれば、むしろ有利にも思えますが。
連休で暇だったので、大量に記載してしまいましたが、
参考になる点を拾って行って下さい。
>ゆずまんひろさん
>弁理士資格の中で、企業内で生かせる知識は、特許法の前半、49条位まででしょう。
>弁理士資格の中には無駄な?知識も多い
>実務ではあまり生かせない知識が多い(意匠、商標、著作権等)ので、それを覚悟する必要があります。
この辺りのご指摘は大変興味を覚えます。多分おっしゃるとおりなんだろうと思います。そうだとすると、これらのことは、トピ主さんが弁理士資格取得を目指して努力を傾注した場合の「努力のコストパーフォーマンス」を評価するにあたって、マイナスに作用しますね。
私は例えばカミサカさんのような企業内研究者の方の場合は、弁理士資格の取得よりは、まず研究実績をあげること、あとはマネージャーに昇進することをめざすほうが現実的だと思うのです。
37番でちょっと言い忘れたことがありますが、カミサカさんが研究部門の管理職になったときに求められる能力として部下の育成能力が挙げられるわけですが、研究部門のような部署ならなおさら部下の育成能力は重要です。会社の上層部のマネージャーに寄せる期待のもっとも大きい部分であるといえます。
逆に言うと、部下の育成能力が無いマネージャーは首を斬られるか閑職に配置転換させられます。ではどういうときに「部下の育成能力が無い」とみなされるかというと、例えば部下が立て続けに会社を辞めたような場合です。
その人の部署で例えば誰かが辞めたとします。すると会社は一度は補充人員を採ってくれます。ところがその補充人員がまた辞めたとします。会社は再び補充人員を採ってくれるのでしょうか。こういう場合、たいていのケースでその部署のマネージャーに「部下の育成能力が無い」とみなされるようですね。そしてそのようにみなされたマネージャーは首を斬られるか閑職に配置転換させられます。
トピ主さんのお考えは、「そういう人生リスクがあるからこそ弁理士資格でもとっておいて保険にする必要がある」ということなのでしょう。だが、私はこの考え方は間違っていると思う。やはり、正攻法の考え方は、マネージャー昇進をめざすならば、ちゃんと育成能力のあるマネージャーにならなければならない、そのためにはどういう努力をするか、ということだと思うのです。
では具体的にはどういう努力をするべきなのかというと、それは残念ながら私には的確なアドバイスはできません。しかし弁理士資格取得がその努力でないことは確かだと思います。
>弁理士資格の中で、企業内で生かせる知識は、特許法の前半、49条位まででしょう。
>弁理士資格の中には無駄な?知識も多い
>実務ではあまり生かせない知識が多い(意匠、商標、著作権等)ので、それを覚悟する必要があります。
この辺りのご指摘は大変興味を覚えます。多分おっしゃるとおりなんだろうと思います。そうだとすると、これらのことは、トピ主さんが弁理士資格取得を目指して努力を傾注した場合の「努力のコストパーフォーマンス」を評価するにあたって、マイナスに作用しますね。
私は例えばカミサカさんのような企業内研究者の方の場合は、弁理士資格の取得よりは、まず研究実績をあげること、あとはマネージャーに昇進することをめざすほうが現実的だと思うのです。
37番でちょっと言い忘れたことがありますが、カミサカさんが研究部門の管理職になったときに求められる能力として部下の育成能力が挙げられるわけですが、研究部門のような部署ならなおさら部下の育成能力は重要です。会社の上層部のマネージャーに寄せる期待のもっとも大きい部分であるといえます。
逆に言うと、部下の育成能力が無いマネージャーは首を斬られるか閑職に配置転換させられます。ではどういうときに「部下の育成能力が無い」とみなされるかというと、例えば部下が立て続けに会社を辞めたような場合です。
その人の部署で例えば誰かが辞めたとします。すると会社は一度は補充人員を採ってくれます。ところがその補充人員がまた辞めたとします。会社は再び補充人員を採ってくれるのでしょうか。こういう場合、たいていのケースでその部署のマネージャーに「部下の育成能力が無い」とみなされるようですね。そしてそのようにみなされたマネージャーは首を斬られるか閑職に配置転換させられます。
トピ主さんのお考えは、「そういう人生リスクがあるからこそ弁理士資格でもとっておいて保険にする必要がある」ということなのでしょう。だが、私はこの考え方は間違っていると思う。やはり、正攻法の考え方は、マネージャー昇進をめざすならば、ちゃんと育成能力のあるマネージャーにならなければならない、そのためにはどういう努力をするか、ということだと思うのです。
では具体的にはどういう努力をするべきなのかというと、それは残念ながら私には的確なアドバイスはできません。しかし弁理士資格取得がその努力でないことは確かだと思います。
コメントありがとうございます。
>ゆずまんひろさん
企業内弁理士の方の貴重なご意見ありがとうございます。
研究職+弁理士資格に賛否両論あるようですが、メリットについての
教えて頂けるとやる気が湧きます。
>tomtomさん
「企業内研究者の方の場合は、弁理士資格の取得よりは、まず研究実績をあげること、あとはマネージャーに昇進することをめざすほうが現実的だと思うのです。」
確かにそれが可能なら全く問題ないと思います。
ただ現実には努力しても研究結果に報われない研究職の方はたくさんいます。
運の要素もかなり大きいですので。
「マネージャー昇進をめざすならば、ちゃんと育成能力のあるマネージャーにならなければならない、そのためにはどういう努力をするか、ということだと思うのです。・・・ 弁理士資格取得がその努力でないことは確かだと思います。」
弁理士資格取得に向けて努力して時間を使うことが、部下育成能力の欠如になるのでしょうか?社会人経験の浅い私の拙い意見かもしれませんが、そのような能力は日々の仕事のなかで養っていくものではないかと思います。
帰宅後に弁理士試験勉強することとは関係ないように思うのですが、どうでしょう?
>ゆずまんひろさん
企業内弁理士の方の貴重なご意見ありがとうございます。
研究職+弁理士資格に賛否両論あるようですが、メリットについての
教えて頂けるとやる気が湧きます。
>tomtomさん
「企業内研究者の方の場合は、弁理士資格の取得よりは、まず研究実績をあげること、あとはマネージャーに昇進することをめざすほうが現実的だと思うのです。」
確かにそれが可能なら全く問題ないと思います。
ただ現実には努力しても研究結果に報われない研究職の方はたくさんいます。
運の要素もかなり大きいですので。
「マネージャー昇進をめざすならば、ちゃんと育成能力のあるマネージャーにならなければならない、そのためにはどういう努力をするか、ということだと思うのです。・・・ 弁理士資格取得がその努力でないことは確かだと思います。」
弁理士資格取得に向けて努力して時間を使うことが、部下育成能力の欠如になるのでしょうか?社会人経験の浅い私の拙い意見かもしれませんが、そのような能力は日々の仕事のなかで養っていくものではないかと思います。
帰宅後に弁理士試験勉強することとは関係ないように思うのですが、どうでしょう?
つい最近、日本人のノーベル賞受賞者が4人も出たことが報道されていますよね。その顔ぶれをみると、4人のうち2人(南部さん、下村さん)までが海外流出組です。日本の研究環境があまり良くないということが、頭脳流出を招くのではないでしょうか。
それと、日本では、優秀な人材を発掘したり育成したりするための方法論がきちんと確立していないように感じます。だから、日本で研究生活を送る若い研究者は、「自分を責任をもってちゃんと育成してもらっていない」という不安感や物足りなさを感じてしまうのではないでしょうか。
カミサカさんは、「弁理士を取ろうと思うんだけど、どうだろうか」という質問を投げかけています。そして多くのメンバーのみなさんが、それにむけて親切にアドバイスをしておられます。だが、本当に考えるべきことは、なぜカミサカさんが保険としての弁理士資格取得に関心を持ってしまうのか、言い換えると、なぜ研究生活にひたすら没頭し、そこに喜びとやりがいを見出す方向に進んでいかないのか、ということにあるのではないでしょうか。
そして私なりのこの問題に対する答えは、日本では、優秀な人材を発掘したり育成したりするための方法論がきちんと確立していないということにあるような気がするのです。
それと、日本では、優秀な人材を発掘したり育成したりするための方法論がきちんと確立していないように感じます。だから、日本で研究生活を送る若い研究者は、「自分を責任をもってちゃんと育成してもらっていない」という不安感や物足りなさを感じてしまうのではないでしょうか。
カミサカさんは、「弁理士を取ろうと思うんだけど、どうだろうか」という質問を投げかけています。そして多くのメンバーのみなさんが、それにむけて親切にアドバイスをしておられます。だが、本当に考えるべきことは、なぜカミサカさんが保険としての弁理士資格取得に関心を持ってしまうのか、言い換えると、なぜ研究生活にひたすら没頭し、そこに喜びとやりがいを見出す方向に進んでいかないのか、ということにあるのではないでしょうか。
そして私なりのこの問題に対する答えは、日本では、優秀な人材を発掘したり育成したりするための方法論がきちんと確立していないということにあるような気がするのです。
ちょっと思ったんですが、研究職にある人が弁理士を目指すことがいけないとかできればやめたほうが良いなら、弁理士を目指していい人って誰になるんでしょうか?
「研究職に就いたからには一生研究職に全力を注ぐべき」とする意見は、恐らく研究職に限定されるわけじゃなくて、例えばSEの人や、文系出身で企業法務に入った人もすべて一生その仕事に専念すべきってことなんですよね?
そうすると、結局は学生時代に「弁理士を目指すぞ!」と決めて特許事務所に就職して特許技術者をやりながら試験勉強する人くらいしか弁理士を目指せなくないですか?
近年の600人も合格者が出る時代に、そんな人だけだったら弁理士試験はものすごく倍率が低くて簡単な試験になりそうですね。。
そしてその意見に従えば、逆に弁理士だって他の仕事に色目を使うのは良くないってことになりそうですね。
正直、独立できる資格だと思って取ってみましたが、わずか5年で弁理士数が倍増しちゃうし、高学歴化も進んで競争も激しくなってきてるしで、これからはあまりオイシイ資格ではないように思うんですよね。
「日本一の弁理士」を目指すのもアリかもしれませんが、もっと割りの良い仕事があるなら私はいつまでも弁理士にこだわるつもりは全然ないんですが・・・間違ってるんですかね^^;
友達も働いてますが、今は転職産業がだいぶ流行っているようですね。
より良い条件というか、より自分に適した人生を選ぶために、転職というのはもはや社会人一般におけるありふれた選択肢じゃないのかな、って気がします。
「研究職に就いたからには一生研究職に全力を注ぐべき」とする意見は、恐らく研究職に限定されるわけじゃなくて、例えばSEの人や、文系出身で企業法務に入った人もすべて一生その仕事に専念すべきってことなんですよね?
そうすると、結局は学生時代に「弁理士を目指すぞ!」と決めて特許事務所に就職して特許技術者をやりながら試験勉強する人くらいしか弁理士を目指せなくないですか?
近年の600人も合格者が出る時代に、そんな人だけだったら弁理士試験はものすごく倍率が低くて簡単な試験になりそうですね。。
そしてその意見に従えば、逆に弁理士だって他の仕事に色目を使うのは良くないってことになりそうですね。
正直、独立できる資格だと思って取ってみましたが、わずか5年で弁理士数が倍増しちゃうし、高学歴化も進んで競争も激しくなってきてるしで、これからはあまりオイシイ資格ではないように思うんですよね。
「日本一の弁理士」を目指すのもアリかもしれませんが、もっと割りの良い仕事があるなら私はいつまでも弁理士にこだわるつもりは全然ないんですが・・・間違ってるんですかね^^;
友達も働いてますが、今は転職産業がだいぶ流行っているようですね。
より良い条件というか、より自分に適した人生を選ぶために、転職というのはもはや社会人一般におけるありふれた選択肢じゃないのかな、って気がします。
>わずか5年で弁理士数が倍増しちゃうし、高学歴化も進んで競争も激しくなってきてるしで、
>これからはあまりオイシイ資格ではないように思うんですよね。「日本一の弁理士」を目指す
>のもアリかもしれませんが、もっと割りの良い仕事があるなら私はいつまでも弁理士にこだわる
>つもりは全然ないんですが・・・間違ってるんですかね
弁理士業があまり割の良い職業ではないということをおっしゃっておられると思いますが、そうであれば、ますます弁理士資格を取得することは「労多くして功少なし」になり、弁理士資格取得への努力は人には勧められないということになりませんか。
出発点に戻ると、トピ主さんであるカミサカさんは、「人生の保険として弁理士資格を取得しておこうと思うのですがどうでしょう」と相談を持ちかけられているんですよね。夢を食う動物バカさんは、弁理士業があまり割の良い職業ではないということをおっしゃっているわけですから、これは「人生の保険としてたいして値打ちはない」という結論になりませんか。
>これからはあまりオイシイ資格ではないように思うんですよね。「日本一の弁理士」を目指す
>のもアリかもしれませんが、もっと割りの良い仕事があるなら私はいつまでも弁理士にこだわる
>つもりは全然ないんですが・・・間違ってるんですかね
弁理士業があまり割の良い職業ではないということをおっしゃっておられると思いますが、そうであれば、ますます弁理士資格を取得することは「労多くして功少なし」になり、弁理士資格取得への努力は人には勧められないということになりませんか。
出発点に戻ると、トピ主さんであるカミサカさんは、「人生の保険として弁理士資格を取得しておこうと思うのですがどうでしょう」と相談を持ちかけられているんですよね。夢を食う動物バカさんは、弁理士業があまり割の良い職業ではないということをおっしゃっているわけですから、これは「人生の保険としてたいして値打ちはない」という結論になりませんか。
その部分だけを捉えたらそう言えるかもしれません。
正直なところ、私は研究職を経験したことがないのでそこらのことは正確にはわかりません。
しかし、いくらオイシイ職業でなくなってきているとはいえ、おそらく私が普通にサラリーマンをしているよりは稼げていると思いますし、今後も稼げると思います。
さらに適職があれば移ることも選択肢にある、ということです。
ご指摘のように、仮に弁理士になっても今よりも儲からないしやりがいもないならわざわざ目指す意味はないと思いますが、その議論をせずに転職の検討をすること自体を否定してしまう価値観は、世の中のコンセンサスを得られてないんじゃないかな、と思ったのでコメントさせていただきました。
正直なところ、私は研究職を経験したことがないのでそこらのことは正確にはわかりません。
しかし、いくらオイシイ職業でなくなってきているとはいえ、おそらく私が普通にサラリーマンをしているよりは稼げていると思いますし、今後も稼げると思います。
さらに適職があれば移ることも選択肢にある、ということです。
ご指摘のように、仮に弁理士になっても今よりも儲からないしやりがいもないならわざわざ目指す意味はないと思いますが、その議論をせずに転職の検討をすること自体を否定してしまう価値観は、世の中のコンセンサスを得られてないんじゃないかな、と思ったのでコメントさせていただきました。
>オイシイ職業でなくなってきているとはいえ、おそらく私が普通にサラリーマンをしている
>よりは稼げていると思いますし、今後も稼げると思います。さらに適職があれば移ることも
>選択肢にある、ということです。
そういうことであれば、今度は、弁理士資格を取得したのなら、直ちに知財の方面に本格的に進路を変えればいいと思うのですよ。このことはこのトピックの中ですでに私は申し上げています。
再び出発点に戻ると、トピ主さんであるカミサカさんは、「人生の保険として弁理士資格を取得しておこうと思うのですがどうでしょう」と相談を持ちかけられているんですよね。私は、研究職にある人が弁理士を目指すことがいけないとか、できればやめたほうが良いということを言っているのではないのです。
そうではなく、「人生の保険として弁理士資格を取得しておく」という考え方、特に「人生の保険として」という部分が疑問だと思うわけです。「人生の保険として弁理士資格を取得しておく」という考え方に従えば、首尾よく試験に合格して資格取得しても、当面は知財の方面には進路を取らないわけでしょう。そして、万が一研究職を続けていくことが難しくなるときが来たら、そこで知財の方面に進むわけでしょう。そういう「人生の保険として弁理士資格を取得しておく」という考え方が疑問だと思うわけです。
>よりは稼げていると思いますし、今後も稼げると思います。さらに適職があれば移ることも
>選択肢にある、ということです。
そういうことであれば、今度は、弁理士資格を取得したのなら、直ちに知財の方面に本格的に進路を変えればいいと思うのですよ。このことはこのトピックの中ですでに私は申し上げています。
再び出発点に戻ると、トピ主さんであるカミサカさんは、「人生の保険として弁理士資格を取得しておこうと思うのですがどうでしょう」と相談を持ちかけられているんですよね。私は、研究職にある人が弁理士を目指すことがいけないとか、できればやめたほうが良いということを言っているのではないのです。
そうではなく、「人生の保険として弁理士資格を取得しておく」という考え方、特に「人生の保険として」という部分が疑問だと思うわけです。「人生の保険として弁理士資格を取得しておく」という考え方に従えば、首尾よく試験に合格して資格取得しても、当面は知財の方面には進路を取らないわけでしょう。そして、万が一研究職を続けていくことが難しくなるときが来たら、そこで知財の方面に進むわけでしょう。そういう「人生の保険として弁理士資格を取得しておく」という考え方が疑問だと思うわけです。
うーん、正直何が疑問なのかわかりかねます。
取れるうちに取っておけばいいんじゃないでしょうか。
もしかしたら将来取りたいと思っても、年齢や家族等の環境によっては取れなくなっているかもしれません。
で、いずれ必要があれば転職する、なければ研究職を続ければいい。
他人よりも選択肢が増えるわけです。何が問題なのですか?
例えば、以前から繰り返している通り、私は将来の可能性として弁理士以外の道も考えています。
仮に、(本当は別のことですが)将来の転職のためにいま中国語を勉強しているとします。
tomtomさんのお考えだと、今すぐ転職するつもりがないなら中国語の勉強なんかやめろ、その時間と労力を弁理士としての成長のために費やせ、ということでしょうか?
しかし、いざ転職しようと思ってから勉強を始めても遅いのではないですか?
それとも、中国語の勉強と弁理士のような国家資格とでは、何か根本的な違いがあるとお考えでしょうか?
いま生活できるだけの収入があって、余った時間で将来の保険をかけておく。
私には至って普通の選択に思えます。
取れるうちに取っておけばいいんじゃないでしょうか。
もしかしたら将来取りたいと思っても、年齢や家族等の環境によっては取れなくなっているかもしれません。
で、いずれ必要があれば転職する、なければ研究職を続ければいい。
他人よりも選択肢が増えるわけです。何が問題なのですか?
例えば、以前から繰り返している通り、私は将来の可能性として弁理士以外の道も考えています。
仮に、(本当は別のことですが)将来の転職のためにいま中国語を勉強しているとします。
tomtomさんのお考えだと、今すぐ転職するつもりがないなら中国語の勉強なんかやめろ、その時間と労力を弁理士としての成長のために費やせ、ということでしょうか?
しかし、いざ転職しようと思ってから勉強を始めても遅いのではないですか?
それとも、中国語の勉強と弁理士のような国家資格とでは、何か根本的な違いがあるとお考えでしょうか?
いま生活できるだけの収入があって、余った時間で将来の保険をかけておく。
私には至って普通の選択に思えます。
>tomtomさんのお考えだと、今すぐ転職するつもりがないなら中国語の勉強なんかやめろ、
>その時間と労力を弁理士としての成長のために費やせ、ということでしょうか?
そうですね。それに近いです。
例えば弁理士としてそこそこ活躍している中、中国語の勉強をして、中国語についてある程度の学力がついてきたとします。例えば英語で言えば英検準1級相当ぐらいの中国語の語学力を身につけることができたとします。しかしこれくらいの中国語の学力では、中国語を使った仕事はまだ本格的にはできないと思います。もう1段階ないし2段階上の実力が必要です。
しかし、もう1段階ないし2段階上の実力を身につけるには、やはり、中国語を実際に仕事に使ってみて、実戦を通じて語学力に磨きをかけるということがぜひとも必要なのではないですか。つまり、個人的な努力によって英検準1級相当ぐらいの中国語の語学力を身につけたとしても、これを実戦で使わずに温存しておいては、むしろ錆びついて学力は低下するのではないですか。
弁理士の仕事のスキルでも同じですよ。弁理士の仕事の一番の中核部分はやはり良い明細書を書くということではないでしょうか。これは弁理士のライフワークですよ。良い明細書が書ける弁理士はほぼ確実に失業しないと思います。
ある弁理士が弁理士業を続けることに思わしくない情勢になったとしても、しかし弁理士全員が同時にそうなるわけではありません。そんな情勢が生じても、生き残る弁理士は相当数いるはずです。弁理士業を現にやっているということは、弁理士としての実力を磨きうる環境に身を置いているということに他なりません。そのアドバンテージを生かして「生き残る弁理士」になればいいのです。
つまり、弁理士業を現にやっているという、弁理士としての実力を磨きうる環境に身を置いているアドバンテージを生かすことが、それ自体「人生の保険」になると思うのです。
>その時間と労力を弁理士としての成長のために費やせ、ということでしょうか?
そうですね。それに近いです。
例えば弁理士としてそこそこ活躍している中、中国語の勉強をして、中国語についてある程度の学力がついてきたとします。例えば英語で言えば英検準1級相当ぐらいの中国語の語学力を身につけることができたとします。しかしこれくらいの中国語の学力では、中国語を使った仕事はまだ本格的にはできないと思います。もう1段階ないし2段階上の実力が必要です。
しかし、もう1段階ないし2段階上の実力を身につけるには、やはり、中国語を実際に仕事に使ってみて、実戦を通じて語学力に磨きをかけるということがぜひとも必要なのではないですか。つまり、個人的な努力によって英検準1級相当ぐらいの中国語の語学力を身につけたとしても、これを実戦で使わずに温存しておいては、むしろ錆びついて学力は低下するのではないですか。
弁理士の仕事のスキルでも同じですよ。弁理士の仕事の一番の中核部分はやはり良い明細書を書くということではないでしょうか。これは弁理士のライフワークですよ。良い明細書が書ける弁理士はほぼ確実に失業しないと思います。
ある弁理士が弁理士業を続けることに思わしくない情勢になったとしても、しかし弁理士全員が同時にそうなるわけではありません。そんな情勢が生じても、生き残る弁理士は相当数いるはずです。弁理士業を現にやっているということは、弁理士としての実力を磨きうる環境に身を置いているということに他なりません。そのアドバンテージを生かして「生き残る弁理士」になればいいのです。
つまり、弁理士業を現にやっているという、弁理士としての実力を磨きうる環境に身を置いているアドバンテージを生かすことが、それ自体「人生の保険」になると思うのです。
tomtomさんがおっしゃっているように覚悟を決めて何か一つの道を極めることも大事だと思いますが、見識を広める意味でも他の分野について知識を得ることは有益だと考えます。
スレ主は、現在研究職のようですし、研究職を続けながら、自分の発明の明細書を書く、中間処理に積極的に関わる等で、弁理士としての実務も積みながら、研究を行っていくことも十分可能だと思います。その意味で、十分保険の意味はあるのではないでしょうか?自分で明細書書いて、拒絶でたたかれて、再度、明細書の書き方を見直してみることで実力はつくと思います。
スレ主が全く畑違いの資格を目指されるのであれば、保険の意味も薄れるかもしれませんが、研究職の方が、弁理士資格を目指されることが保険にならないとは思えないのですが。
知財の観点を強く意識することで、事業性等もより深く考えることができますし、自然とマネージャーとしての考えも身につくのではないでしょうか?うまく使えば、相乗効果のある資格であると思います。少なくとも、私が見てきた優秀な発明者の方は、知財に深い興味を示されていますし、研究にのみ没頭している研究者の方が、マネージャーとしてはどうかと思います。
研究にのみ没頭したいのであれば、大学で行うべきであって、利益が必要となる企業ではなかなか難しいのも現実です。最近の大学も企業に似て来ているのも問題ですが。
その分野のことだけを一筋にやって結果を出される方もいれば、見識を広げていく中で結果を出される方もおられますので、一概に弁理士資格取得が、全くスレ主の保険にならないかというと疑問です。
弁理士資格を生かすも殺すもスレ主次第でしょう。
スレ主は、現在研究職のようですし、研究職を続けながら、自分の発明の明細書を書く、中間処理に積極的に関わる等で、弁理士としての実務も積みながら、研究を行っていくことも十分可能だと思います。その意味で、十分保険の意味はあるのではないでしょうか?自分で明細書書いて、拒絶でたたかれて、再度、明細書の書き方を見直してみることで実力はつくと思います。
スレ主が全く畑違いの資格を目指されるのであれば、保険の意味も薄れるかもしれませんが、研究職の方が、弁理士資格を目指されることが保険にならないとは思えないのですが。
知財の観点を強く意識することで、事業性等もより深く考えることができますし、自然とマネージャーとしての考えも身につくのではないでしょうか?うまく使えば、相乗効果のある資格であると思います。少なくとも、私が見てきた優秀な発明者の方は、知財に深い興味を示されていますし、研究にのみ没頭している研究者の方が、マネージャーとしてはどうかと思います。
研究にのみ没頭したいのであれば、大学で行うべきであって、利益が必要となる企業ではなかなか難しいのも現実です。最近の大学も企業に似て来ているのも問題ですが。
その分野のことだけを一筋にやって結果を出される方もいれば、見識を広げていく中で結果を出される方もおられますので、一概に弁理士資格取得が、全くスレ主の保険にならないかというと疑問です。
弁理士資格を生かすも殺すもスレ主次第でしょう。
なるほど、どうやら根本的に考え方が違うようです。
私は、弁理士資格は単なる肩書で、その仕事の質とは無関係の、オン/オフ(=持っているか/いないか)だけで差がつくものだと思っています。
これは弁理士試験を経験した人なら納得できると思います。
あの試験は、別に良い明細書が書けるかどうかを試す試験ではありません。
未経験の場合、良い明細書は転職後に書けるようになるしかありません。
そして特許業界では、それを受け入れる体勢ができていると思います。
いま活躍している弁理士も、最初は素人だったはずです。
研究をしながら資格を取って→資格を持って転職
十分可能なコースだと思います。
弁理士試験の知識など実務で使える部分は少ないですし、取得直後でなければいい明細書が書けないということもないと思います。(もしそうであるなら、弁理士試験に合格していないいわゆる特許技術者というものは世の中に存在していないはずです)
>もう1段階ないし2段階上の実力を身につけるには、やはり、中国語を実際に仕事に使ってみて、実戦を通じて語学力に磨きをかけるということがぜひとも必要
その通りだと思います。
なので、まずはある程度まで自分で高めて、その後転職して実務レベルまで高めれば良いのではないですか?
tomtomさんは、現職弁理士のレベルアップによる価値を強調されますが、それ以外の道、すなわち研究職から弁理士に転職し成功を収めている多くの弁理士についてはどうお考えなのですか?
彼らは弁理士取得直後に転職したから成功したのであって、間が開いていたらそうはいかなかったということですか?
もしくは、上の例では、仮に私が中国語関係の仕事をしたいのであれば、まず転職して、そして仕事をしながら実務レベルまでめるべきだとお考えなのですか?
自分である程度まで高めて、転職後に必要なレベルまで上げる場合との違いは何ですか?
弁理士としてのスキルを磨くことは、転職してからやればいいことで、研究職にある人が弁理士資格を取得することとは背反ではないと思うのですが。
私は、弁理士資格は単なる肩書で、その仕事の質とは無関係の、オン/オフ(=持っているか/いないか)だけで差がつくものだと思っています。
これは弁理士試験を経験した人なら納得できると思います。
あの試験は、別に良い明細書が書けるかどうかを試す試験ではありません。
未経験の場合、良い明細書は転職後に書けるようになるしかありません。
そして特許業界では、それを受け入れる体勢ができていると思います。
いま活躍している弁理士も、最初は素人だったはずです。
研究をしながら資格を取って→資格を持って転職
十分可能なコースだと思います。
弁理士試験の知識など実務で使える部分は少ないですし、取得直後でなければいい明細書が書けないということもないと思います。(もしそうであるなら、弁理士試験に合格していないいわゆる特許技術者というものは世の中に存在していないはずです)
>もう1段階ないし2段階上の実力を身につけるには、やはり、中国語を実際に仕事に使ってみて、実戦を通じて語学力に磨きをかけるということがぜひとも必要
その通りだと思います。
なので、まずはある程度まで自分で高めて、その後転職して実務レベルまで高めれば良いのではないですか?
tomtomさんは、現職弁理士のレベルアップによる価値を強調されますが、それ以外の道、すなわち研究職から弁理士に転職し成功を収めている多くの弁理士についてはどうお考えなのですか?
彼らは弁理士取得直後に転職したから成功したのであって、間が開いていたらそうはいかなかったということですか?
もしくは、上の例では、仮に私が中国語関係の仕事をしたいのであれば、まず転職して、そして仕事をしながら実務レベルまでめるべきだとお考えなのですか?
自分である程度まで高めて、転職後に必要なレベルまで上げる場合との違いは何ですか?
弁理士としてのスキルを磨くことは、転職してからやればいいことで、研究職にある人が弁理士資格を取得することとは背反ではないと思うのですが。
こんにちは。
企業で研究を続けていく人にとって、10年〜20年の研究生活の後、どういう道に進むかというのは、非常に重要なことかと思います。研究業績を出して大学教員になるとか、管理職の道を進むか、田中耕一さんのように生涯研究者を続けるとか。
この戦略なく、ただ研究者を続けている人をたくさん知っているので、カミサカさんの問題意識は非常に重要だと思うんです。
弁理士の資格を若いうちに取得しておけば、可能性は広がると思うので、大学生や大学院生の間に弁理士試験に合格している人を見ていると羨ましく思うことはあります。
カミサカさんの場合、博士号の学位をもっていて、20歳代の企業研究者ということは、まだ、企業で働き始めてまだ間もないんですよね。研究生活は楽しいですか。
私の意見ですが、研究生活が楽しい(すくなくとも、この研究分野でいい業績を出したい)と思っているならば、若い間は、とりあえずは、研究に打ち込むべきなんじゃないですか。弁理士の勉強を始めるのは、後5年ぐらい後でもいいと思います。逆に、企業で勤めてみて、「なんか自分の居場所(活躍場所)と違うな」と違和感を感じておられるならば、弁理士試験の勉強を始めてみるのもいいんじゃないかと思います。
働きながら、特に会社の人にナイショにしながら、弁理士試験の資格を取るのは非常に大変です。勉強時間という意味でも、人間付き合いという意味でも。
残業はあるでしょうけれど、なるべく仕事に精を出さず(笑)、就業時間を過ぎたら、また、週末のほとんどの時間を、弁理士試験の勉強に打ち込むわけですから。飲み会や週末のイベントの誘いを断って、勉強を頑張ることになるんですよ。
上で別の方もおっしゃっておられましたが、予備校に通うお金のことよりも、そこまで苦労しても弁理士試験に合格するんだ!というモティベーションの方が重要だと思います。
企業で研究を続けていく人にとって、10年〜20年の研究生活の後、どういう道に進むかというのは、非常に重要なことかと思います。研究業績を出して大学教員になるとか、管理職の道を進むか、田中耕一さんのように生涯研究者を続けるとか。
この戦略なく、ただ研究者を続けている人をたくさん知っているので、カミサカさんの問題意識は非常に重要だと思うんです。
弁理士の資格を若いうちに取得しておけば、可能性は広がると思うので、大学生や大学院生の間に弁理士試験に合格している人を見ていると羨ましく思うことはあります。
カミサカさんの場合、博士号の学位をもっていて、20歳代の企業研究者ということは、まだ、企業で働き始めてまだ間もないんですよね。研究生活は楽しいですか。
私の意見ですが、研究生活が楽しい(すくなくとも、この研究分野でいい業績を出したい)と思っているならば、若い間は、とりあえずは、研究に打ち込むべきなんじゃないですか。弁理士の勉強を始めるのは、後5年ぐらい後でもいいと思います。逆に、企業で勤めてみて、「なんか自分の居場所(活躍場所)と違うな」と違和感を感じておられるならば、弁理士試験の勉強を始めてみるのもいいんじゃないかと思います。
働きながら、特に会社の人にナイショにしながら、弁理士試験の資格を取るのは非常に大変です。勉強時間という意味でも、人間付き合いという意味でも。
残業はあるでしょうけれど、なるべく仕事に精を出さず(笑)、就業時間を過ぎたら、また、週末のほとんどの時間を、弁理士試験の勉強に打ち込むわけですから。飲み会や週末のイベントの誘いを断って、勉強を頑張ることになるんですよ。
上で別の方もおっしゃっておられましたが、予備校に通うお金のことよりも、そこまで苦労しても弁理士試験に合格するんだ!というモティベーションの方が重要だと思います。
>彼らは弁理士取得直後に転職したから成功したのであって、間が開いていたらそうはいかなかった
>ということですか?
そう、私はその可能性が結構高いと思うのです。すでにトピックの中で申し上げましたが、弁理士の試験に合格したてのころは、「新進の弁理士」ということで旬なんですよ。野菜でも果物でも魚でも旬のころがおいしいし、高く売れます。このときにこそ弁理士としてのキャリアデヴェロップメントを開始するべきだと思います。そして「弁理士として成功する」という目標に向かって全力投球されたらよろしいと思います。
なお、カミサカさんの場合は、仮に弁理士資格を取得されたとして、ただちに特許事務所等に転職する必要はないと思います。というのは、カミサカさんがお勤めの会社にも多分知財部はあるでしょう。知財部へのジョブローテーションを願い出て、そこで知財部のスタッフとして活躍されるという途が現実的でいいと思います。
>もしくは、上の例では、仮に私が中国語関係の仕事をしたいのであれば、まず転職して、そして
>仕事をしながら実務レベルまでめるべきだとお考えなのですか?
ある程度近いですが、ちょっと違うところもあります。
語学の勉強というのは、自力でこつこつと勉強して到達可能なレベルと、実務でどんどん使う経験を積んでいかないと到達できないレベルとがあると思うのです。
英語で言えば英検準1級くらいのレベルなら自力でこつこつと勉強して到達可能なレベルです。しかしこれ以上のレベルを望むのなら、実務でどんどん使う経験を積んでいかないとダメです。だから、英検準1級くらいのレベルまで来たら、ほうっておかないで、これを育てるようにしたらいいんじゃないですか。
弁理士だってそうでしょう。弁理士の受験勉強をして資格を取得するという段階までなら、自力でこつこつと勉強することで到達できます。ところがおっしゃるように、弁理士資格を取得したからといって良い明細書が書けるわけではありません。だからこそ、せっかく取得したのなら、良い明細書を書く経験が積める場所(環境)に身を置いて、経験を積めばいいと思うのです。それが、取得した弁理士という資格の価値に磨きをかけることになります。
>ということですか?
そう、私はその可能性が結構高いと思うのです。すでにトピックの中で申し上げましたが、弁理士の試験に合格したてのころは、「新進の弁理士」ということで旬なんですよ。野菜でも果物でも魚でも旬のころがおいしいし、高く売れます。このときにこそ弁理士としてのキャリアデヴェロップメントを開始するべきだと思います。そして「弁理士として成功する」という目標に向かって全力投球されたらよろしいと思います。
なお、カミサカさんの場合は、仮に弁理士資格を取得されたとして、ただちに特許事務所等に転職する必要はないと思います。というのは、カミサカさんがお勤めの会社にも多分知財部はあるでしょう。知財部へのジョブローテーションを願い出て、そこで知財部のスタッフとして活躍されるという途が現実的でいいと思います。
>もしくは、上の例では、仮に私が中国語関係の仕事をしたいのであれば、まず転職して、そして
>仕事をしながら実務レベルまでめるべきだとお考えなのですか?
ある程度近いですが、ちょっと違うところもあります。
語学の勉強というのは、自力でこつこつと勉強して到達可能なレベルと、実務でどんどん使う経験を積んでいかないと到達できないレベルとがあると思うのです。
英語で言えば英検準1級くらいのレベルなら自力でこつこつと勉強して到達可能なレベルです。しかしこれ以上のレベルを望むのなら、実務でどんどん使う経験を積んでいかないとダメです。だから、英検準1級くらいのレベルまで来たら、ほうっておかないで、これを育てるようにしたらいいんじゃないですか。
弁理士だってそうでしょう。弁理士の受験勉強をして資格を取得するという段階までなら、自力でこつこつと勉強することで到達できます。ところがおっしゃるように、弁理士資格を取得したからといって良い明細書が書けるわけではありません。だからこそ、せっかく取得したのなら、良い明細書を書く経験が積める場所(環境)に身を置いて、経験を積めばいいと思うのです。それが、取得した弁理士という資格の価値に磨きをかけることになります。
>私は、弁理士資格は単なる肩書で、その仕事の質とは無関係の、オン/オフ
>(=持っているか/いないか)だけで差がつくものだと思っています。
おっしゃっている意味がよくわかりませんでしたが、多分こういうことだと思います。
弁理士は一旦取得して登録してしまうと、そこから何年年月が経過しようと弁理士は弁理士だ、ということでしょう。「弁理士」という資格に防腐剤を施さなければ腐敗してしまうというわけではない、ということでしょう。
ある意味ではその通りです。しかしトピックの中でも意見が出ていますが、資格取得してその後何年も経過して、その間、実務経験の蓄積がおろそかになっている弁理士を、クライアントは特許出願の代理人として評価するのでしょうか。クライアントから評価されない弁理士は仕事が取れるのでしょうか。
>(=持っているか/いないか)だけで差がつくものだと思っています。
おっしゃっている意味がよくわかりませんでしたが、多分こういうことだと思います。
弁理士は一旦取得して登録してしまうと、そこから何年年月が経過しようと弁理士は弁理士だ、ということでしょう。「弁理士」という資格に防腐剤を施さなければ腐敗してしまうというわけではない、ということでしょう。
ある意味ではその通りです。しかしトピックの中でも意見が出ていますが、資格取得してその後何年も経過して、その間、実務経験の蓄積がおろそかになっている弁理士を、クライアントは特許出願の代理人として評価するのでしょうか。クライアントから評価されない弁理士は仕事が取れるのでしょうか。
やはり根本的な部分で考え方が違うようです。
私は、弁理士試験は弁理士実務の能力とは別に関係ないと考えています。
言い換えれば、弁理士資格の有無と弁理士実無能力は関係ないということです。
弁理士という肩書きで得られる価値は、実務能力の評価ではなく、もっと形式的なもの、弁理士の名前で仕事ができるとか、審査官・審判官と面接等ができるとかいったことで、だから直接客を担当させられたり、仕事を取ってきたりできる、その点で資格を持たない人よりも事務所としては価値があるんだと思います。
この意味でオン/オフである(=資格を有すること自体が価値がある)と言っているのです。
実務能力の腐敗は、未経験者の場合、資格取得後の時間経過とは何の関係もないと思います。
ですので、弁理士の「旬」というものはないと思います。
少なくとも、合格後の時間経過で劣化するような価値はないと思います。
どうせ試験で覚えた知識などほとんど使いませんし、重要な部分は繰り返し勉強しているので忘れないでしょうし、もし忘れてももう一度勉強し直せばいいだけです。
試験と実務で重複する知識などすぐ勉強し直せるくらいしかないと思います。
このように考えているので、研究職から特許業界に入ることは、弁理士資格の有無に関わらず、実務能力はゼロからのスタートになると思っています。
その場合に、弁理士資格というのは形式的な要件ですので、取れるうちに取っておいて何の問題もないというのが繰り返し述べている私の考えです。
おっしゃるように、実務の経験を積まないと弁理士として活躍できません。
ですので、早めに転職した方がその後早く一人前になれると思います。
しかし、状況によってはすぐに転職できないかもしれません。
そんなことは他人の知ったことではないでしょうし、ご本人にしても将来のことはおわかりにならないでしょう。
たしかにすぐに弁理士として転職or異動できなければその分一人前になるのは遅れるかもしれませんが、これをもってして形式要件である弁理士資格取得を否定することはちょっとずれているのではないかと思います。
---
オマケで付け加えさせていただくと、恐らくうちの事務所では、資格取得後の年月経過は、採用を検討する際のかなり優先順位の低い要素(×要件)に過ぎないと思います。
それ以外の条件がほぼすべて同じであるなら、最近合格した人を優先して採用するかもしれません。
しかし、化学系の博士で研究職にある弁理士が同じ椅子を争って同時に何人も受けにくるとも思えません。
仮にうちの事務所でそうなっても、他の事務所も受ければまずそんなことはないでしょう。
私は、カミサカさんのような経歴の方は採用でもその後の実務習得でも有利だと思うので、その余力があるなら、研究職の方が保険として弁理士資格を取得される意義は十分にあると考えます。
私は、弁理士試験は弁理士実務の能力とは別に関係ないと考えています。
言い換えれば、弁理士資格の有無と弁理士実無能力は関係ないということです。
弁理士という肩書きで得られる価値は、実務能力の評価ではなく、もっと形式的なもの、弁理士の名前で仕事ができるとか、審査官・審判官と面接等ができるとかいったことで、だから直接客を担当させられたり、仕事を取ってきたりできる、その点で資格を持たない人よりも事務所としては価値があるんだと思います。
この意味でオン/オフである(=資格を有すること自体が価値がある)と言っているのです。
実務能力の腐敗は、未経験者の場合、資格取得後の時間経過とは何の関係もないと思います。
ですので、弁理士の「旬」というものはないと思います。
少なくとも、合格後の時間経過で劣化するような価値はないと思います。
どうせ試験で覚えた知識などほとんど使いませんし、重要な部分は繰り返し勉強しているので忘れないでしょうし、もし忘れてももう一度勉強し直せばいいだけです。
試験と実務で重複する知識などすぐ勉強し直せるくらいしかないと思います。
このように考えているので、研究職から特許業界に入ることは、弁理士資格の有無に関わらず、実務能力はゼロからのスタートになると思っています。
その場合に、弁理士資格というのは形式的な要件ですので、取れるうちに取っておいて何の問題もないというのが繰り返し述べている私の考えです。
おっしゃるように、実務の経験を積まないと弁理士として活躍できません。
ですので、早めに転職した方がその後早く一人前になれると思います。
しかし、状況によってはすぐに転職できないかもしれません。
そんなことは他人の知ったことではないでしょうし、ご本人にしても将来のことはおわかりにならないでしょう。
たしかにすぐに弁理士として転職or異動できなければその分一人前になるのは遅れるかもしれませんが、これをもってして形式要件である弁理士資格取得を否定することはちょっとずれているのではないかと思います。
---
オマケで付け加えさせていただくと、恐らくうちの事務所では、資格取得後の年月経過は、採用を検討する際のかなり優先順位の低い要素(×要件)に過ぎないと思います。
それ以外の条件がほぼすべて同じであるなら、最近合格した人を優先して採用するかもしれません。
しかし、化学系の博士で研究職にある弁理士が同じ椅子を争って同時に何人も受けにくるとも思えません。
仮にうちの事務所でそうなっても、他の事務所も受ければまずそんなことはないでしょう。
私は、カミサカさんのような経歴の方は採用でもその後の実務習得でも有利だと思うので、その余力があるなら、研究職の方が保険として弁理士資格を取得される意義は十分にあると考えます。
こんにちは
久しぶりにコメントさせていただきます。
私も、弁理士試験と実務能力が無関係という点では賛成です。
しかし、だからといって特許法を知らずに実務が行えるとも思えません。
その点で、直近合格者は改正法までカバーしているという安心感があります。
> 弁理士という肩書きで得られる価値は、実務能力の評価ではなく、もっと形式的なもの、弁理士の名前で仕事ができるとか、審査官・審判官と面接等ができるとかいったことで、だから直接客を担当させられたり、仕事を取ってきたりできる、その点で資格を持たない人よりも事務所としては価値があるんだと思います。
あくまで私の個人的意見ですが・・・。
全ての「特許事務所」には、必ず一人以上弁理士がいます。
この場合、上記形式的な面はその弁理士の名前で行えば良く、
「実務未経験者の」価値にはつながらないのではないでしょうか?
もちろん、「自分で開業する」というのであれば話は別ですが、
「特許事務所に就職する」際の価値にはつながりにくいと思います。
少なくとも私なら、
クライアントからいただいた大切な出願の審査官面接を、
「弁理士である」という肩書きだけで任せることはできませんし、
クライアントの立場でも同様だと思います。
また、現在私の事務所では弁理士を募集していますが、
(実務経験が無い場合には)資格取得後の経過年月は優先順位の高い要素です。
他の事務所さんのスタンスまでは分かりませんが、
例えば、5年以上前に合格しその後研究職に就いている人であれば、
博士号があろうと英語力があろうと面接にすら呼ぶつもりはありません。
(これは「恐らく」ではなく、私の事務所の「現実」です。)
もちろん、
現職の企業から年20件も30件も出願を持ってこられる等の、
特別な事情があれば別ですが・・・。
既に話したように弁理士試験と実務能力とが無関係である以上、
実務未経験者で差がつく条件は限られてくるのではないでしょうか?
(最近は、化学系で博士号取得者は珍しくありませんし)
これは繰り返しになってしまいますが、
研究職の方が「転職するために」弁理士資格を取得する意義はあると思いますが、
「いつか転職するための保険として」弁理士資格を取得する意義は少ないと思います。
保健代にしては、大きすぎる対価だと思うのですが・・・。
久しぶりにコメントさせていただきます。
私も、弁理士試験と実務能力が無関係という点では賛成です。
しかし、だからといって特許法を知らずに実務が行えるとも思えません。
その点で、直近合格者は改正法までカバーしているという安心感があります。
> 弁理士という肩書きで得られる価値は、実務能力の評価ではなく、もっと形式的なもの、弁理士の名前で仕事ができるとか、審査官・審判官と面接等ができるとかいったことで、だから直接客を担当させられたり、仕事を取ってきたりできる、その点で資格を持たない人よりも事務所としては価値があるんだと思います。
あくまで私の個人的意見ですが・・・。
全ての「特許事務所」には、必ず一人以上弁理士がいます。
この場合、上記形式的な面はその弁理士の名前で行えば良く、
「実務未経験者の」価値にはつながらないのではないでしょうか?
もちろん、「自分で開業する」というのであれば話は別ですが、
「特許事務所に就職する」際の価値にはつながりにくいと思います。
少なくとも私なら、
クライアントからいただいた大切な出願の審査官面接を、
「弁理士である」という肩書きだけで任せることはできませんし、
クライアントの立場でも同様だと思います。
また、現在私の事務所では弁理士を募集していますが、
(実務経験が無い場合には)資格取得後の経過年月は優先順位の高い要素です。
他の事務所さんのスタンスまでは分かりませんが、
例えば、5年以上前に合格しその後研究職に就いている人であれば、
博士号があろうと英語力があろうと面接にすら呼ぶつもりはありません。
(これは「恐らく」ではなく、私の事務所の「現実」です。)
もちろん、
現職の企業から年20件も30件も出願を持ってこられる等の、
特別な事情があれば別ですが・・・。
既に話したように弁理士試験と実務能力とが無関係である以上、
実務未経験者で差がつく条件は限られてくるのではないでしょうか?
(最近は、化学系で博士号取得者は珍しくありませんし)
これは繰り返しになってしまいますが、
研究職の方が「転職するために」弁理士資格を取得する意義はあると思いますが、
「いつか転職するための保険として」弁理士資格を取得する意義は少ないと思います。
保健代にしては、大きすぎる対価だと思うのですが・・・。
夢を食うバカさんと私の考え方の違いをこんなふうにいうことも出来るような気がします。
まず、現在はカミサカさんは企業の研究者として仕事をしておられるわけです。ところがそこでは、ご自分がいつまでも研究者としてやっていけるか心配しておられるわけです。いうなれば、研究者という職業もサバイバルゲームにさらされているわけですね。だから、ご自分がこの研究者という職業におけるサバイバルゲームの敗者となったときの保険が欲しいということでした。
ところが、弁理士という職業も、実は現に弁理士として仕事をしている人たちの間にもサバイバルゲームがあり、実務能力や経験が十分あり、クライアントから評価されたり信任されたりする弁理士でないと、このサバイバルゲームに勝ち残れないおそれがあるわけですよね。つまり弁理士という職業もサバイバルゲームが結構過酷なわけですよね。
そうすると、カミサカさんは研究者という職業におけるサバイバルゲームの敗者となったときの保険として、サバイバルゲームが過酷な弁理士という別の職業を考えているということになります。これは、保険の選び方として不適切なのではないですか。
つまり、研究者という職業におけるサバイバルゲームの敗者となったときの保険として、何か別の職業を考えるのなら、その別の職業は、例えば収入はそれほど高くは望めないがサバイバルゲームが緩やかであるようなリスクの低い職業を選ぶほうがいいのではないですか。
例えば看護師なんかいいと思うな。これは職場を選ばなければほぼ絶対失業しないですよ。看護師の資格はどう取得すればいいのか私は不案内ですが、もしできるのなら資格取得して損はないですよ。
まず、現在はカミサカさんは企業の研究者として仕事をしておられるわけです。ところがそこでは、ご自分がいつまでも研究者としてやっていけるか心配しておられるわけです。いうなれば、研究者という職業もサバイバルゲームにさらされているわけですね。だから、ご自分がこの研究者という職業におけるサバイバルゲームの敗者となったときの保険が欲しいということでした。
ところが、弁理士という職業も、実は現に弁理士として仕事をしている人たちの間にもサバイバルゲームがあり、実務能力や経験が十分あり、クライアントから評価されたり信任されたりする弁理士でないと、このサバイバルゲームに勝ち残れないおそれがあるわけですよね。つまり弁理士という職業もサバイバルゲームが結構過酷なわけですよね。
そうすると、カミサカさんは研究者という職業におけるサバイバルゲームの敗者となったときの保険として、サバイバルゲームが過酷な弁理士という別の職業を考えているということになります。これは、保険の選び方として不適切なのではないですか。
つまり、研究者という職業におけるサバイバルゲームの敗者となったときの保険として、何か別の職業を考えるのなら、その別の職業は、例えば収入はそれほど高くは望めないがサバイバルゲームが緩やかであるようなリスクの低い職業を選ぶほうがいいのではないですか。
例えば看護師なんかいいと思うな。これは職場を選ばなければほぼ絶対失業しないですよ。看護師の資格はどう取得すればいいのか私は不案内ですが、もしできるのなら資格取得して損はないですよ。
>>64(なおとさん)
みなさんのいろいろな話を伺えて私にも非常に参考になります。
5年以上前の合格者(かつ未経験者)は面接にすら呼ばないというお話には正直驚きました。
弁理士によって、また事務所によっても考え方がだいぶ違うものですね。
私は、もちろん弁理士に特許法の知識が要らないと考えているのではありません。
しかし、既述の通り、弁理士試験と弁理士実務で重複する部分だけなら、比較的簡単に勉強できるとは考えています。
なおとさんの事務所は比較的規模の大きい事務所なのではないでしょうか。
うちのように小さな事務所だと、一人弁理士が増えるということはある程度大きな意味を持ちます。(なお、日本の特許事務所の多くは個人事務所だと聞いたことがあります。)
小規模事務所だと、担当弁理士を誰にするかでその分野の仕事の流れが大きく動くからです。
形式的には所長の名前ですべて処理すればいいのかもしれませんが、最近は名義貸しもうるさいですし、何よりそれだと機動性に欠けます。
そういう意味で、「弁理士であるか否か」はおっしゃる以上に大きな意味があると感じています。
それに、取得後5年以上経過してる弁理士は博士のように技術知識があっても採用しないということは、私には技術力よりも最近の法律知識の方が重要だと言ってるようにも聞こえます。
最近の法律知識に疎いからという理由で技術知識があっても採用されないなら、いわゆる特許技術者のような方々はどのような理由で採用されるのでしょうか?
未経験で無資格の人はもはや採用の余地がないように思われます。(現実にはそうでないので違和感を感じます。)
私はなにも、資格さえあれば実務ができなくても面接に行けると言っているのではありません。
実務で修行を積みながら一人前になるしかない、そして一人前の弁理士でないと責任を持って面接に行かせられない、この点ではなおとさんやtomtomさんと同じ意見です。
しかし、実務能力が一人前になっても、最近は弁理士でないと面接に行けません。
その意味で弁理士資格はオン/オフだと思うのです。
実務能力と弁理士資格は別問題です。
そしてオンである場合、差がつく要素としては、私は最近の法律知識よりも、技術バックグラウンドや文章能力が弁理士の素養だと考えています。
最近は化学系博士は珍しくないとのことですが、それ以上に最近受かっただけの弁理士は珍しくありません。
>保健代にしては、大きすぎる対価だと思うのですが・・・。
これについてはこれまでに両方の立場からの意見がありました。
たしかに簡単に取れる資格ではありませんので、取得には大きな労力と資金が必要となります。
結局は本人次第なのでしょうが、上述のように私は資格所有が転職に際し(仮に取得後時間が経過していても)不利にならないどころか有利になると考えているので、やはり取れるのであれば取っておけばいいと思います(水掛け論ですね・・)。
みなさんのいろいろな話を伺えて私にも非常に参考になります。
5年以上前の合格者(かつ未経験者)は面接にすら呼ばないというお話には正直驚きました。
弁理士によって、また事務所によっても考え方がだいぶ違うものですね。
私は、もちろん弁理士に特許法の知識が要らないと考えているのではありません。
しかし、既述の通り、弁理士試験と弁理士実務で重複する部分だけなら、比較的簡単に勉強できるとは考えています。
なおとさんの事務所は比較的規模の大きい事務所なのではないでしょうか。
うちのように小さな事務所だと、一人弁理士が増えるということはある程度大きな意味を持ちます。(なお、日本の特許事務所の多くは個人事務所だと聞いたことがあります。)
小規模事務所だと、担当弁理士を誰にするかでその分野の仕事の流れが大きく動くからです。
形式的には所長の名前ですべて処理すればいいのかもしれませんが、最近は名義貸しもうるさいですし、何よりそれだと機動性に欠けます。
そういう意味で、「弁理士であるか否か」はおっしゃる以上に大きな意味があると感じています。
それに、取得後5年以上経過してる弁理士は博士のように技術知識があっても採用しないということは、私には技術力よりも最近の法律知識の方が重要だと言ってるようにも聞こえます。
最近の法律知識に疎いからという理由で技術知識があっても採用されないなら、いわゆる特許技術者のような方々はどのような理由で採用されるのでしょうか?
未経験で無資格の人はもはや採用の余地がないように思われます。(現実にはそうでないので違和感を感じます。)
私はなにも、資格さえあれば実務ができなくても面接に行けると言っているのではありません。
実務で修行を積みながら一人前になるしかない、そして一人前の弁理士でないと責任を持って面接に行かせられない、この点ではなおとさんやtomtomさんと同じ意見です。
しかし、実務能力が一人前になっても、最近は弁理士でないと面接に行けません。
その意味で弁理士資格はオン/オフだと思うのです。
実務能力と弁理士資格は別問題です。
そしてオンである場合、差がつく要素としては、私は最近の法律知識よりも、技術バックグラウンドや文章能力が弁理士の素養だと考えています。
最近は化学系博士は珍しくないとのことですが、それ以上に最近受かっただけの弁理士は珍しくありません。
>保健代にしては、大きすぎる対価だと思うのですが・・・。
これについてはこれまでに両方の立場からの意見がありました。
たしかに簡単に取れる資格ではありませんので、取得には大きな労力と資金が必要となります。
結局は本人次第なのでしょうが、上述のように私は資格所有が転職に際し(仮に取得後時間が経過していても)不利にならないどころか有利になると考えているので、やはり取れるのであれば取っておけばいいと思います(水掛け論ですね・・)。
>>65(tomtomさん)
おそらくカミサカさんは、そういう逃げ腰で保険をかけようとしているのではないと思います。
より適職で、より高収入の仕事があれば、タイミングが合えば移りたい、そして今までの経験や知識を生かせる仕事に特許業界が考えられて、特許業界に入るなら弁理士資格があったほうが良いだろう、取得までの労力と取得後の価値を天秤にかけたらどっちが重いでしょうか、ということをおききなのだと思います。
これは以前も述べましたが、保険として弁理士を選んだ場合、さらにその保険が必要になる、そしてそこでもまたさらに保険が・・・となって永遠に落ち着けないじゃないかというご指摘があります。
これはそうだと思います。
私自身もその悪循環に嵌ってしまっている気もします。
しかし、やはり私は、人生などそんなものだと思うのです。
一本の道を信じて積極的に進める人は少ないのではないでしょうか。
間違いを繰り返して、そのたびに修正して成長していく。
その修正の方法に転職という選択肢があっても良いのではないでしょうか。
なので、別にサバイバルゲームに負けたから弁理士に転職するとも限りませんし、また、仮にそうだとしても、次に弁理士としてのサバイバルゲームには勝てるかもしれません。
不安であればさらに保険をかけ直せばいいだけです。
なお、余談ですが、私のかなり近い関係の人に看護士がいますが、まぁ正直選べるならあれは辞めておいた方が無難だと思いますよ。
三交代制で生活も乱れるし、患者の命を扱うからいざというときの責任は重いし、見た目以上にストレスの溜まる仕事のようですし、そのくせ年収は400万くらいだったりします。
弁理士だって職場を選ばなければそうそう失業はしないでしょうし、看護士よりは良い労働環境で収入も上でしょうし、看護学校に数年通うよりも弁理士試験の予備校の方が安いでしょうし、弁理士を目指す覚悟があるなら私は弁理士をお勧めします。
おそらくカミサカさんは、そういう逃げ腰で保険をかけようとしているのではないと思います。
より適職で、より高収入の仕事があれば、タイミングが合えば移りたい、そして今までの経験や知識を生かせる仕事に特許業界が考えられて、特許業界に入るなら弁理士資格があったほうが良いだろう、取得までの労力と取得後の価値を天秤にかけたらどっちが重いでしょうか、ということをおききなのだと思います。
これは以前も述べましたが、保険として弁理士を選んだ場合、さらにその保険が必要になる、そしてそこでもまたさらに保険が・・・となって永遠に落ち着けないじゃないかというご指摘があります。
これはそうだと思います。
私自身もその悪循環に嵌ってしまっている気もします。
しかし、やはり私は、人生などそんなものだと思うのです。
一本の道を信じて積極的に進める人は少ないのではないでしょうか。
間違いを繰り返して、そのたびに修正して成長していく。
その修正の方法に転職という選択肢があっても良いのではないでしょうか。
なので、別にサバイバルゲームに負けたから弁理士に転職するとも限りませんし、また、仮にそうだとしても、次に弁理士としてのサバイバルゲームには勝てるかもしれません。
不安であればさらに保険をかけ直せばいいだけです。
なお、余談ですが、私のかなり近い関係の人に看護士がいますが、まぁ正直選べるならあれは辞めておいた方が無難だと思いますよ。
三交代制で生活も乱れるし、患者の命を扱うからいざというときの責任は重いし、見た目以上にストレスの溜まる仕事のようですし、そのくせ年収は400万くらいだったりします。
弁理士だって職場を選ばなければそうそう失業はしないでしょうし、看護士よりは良い労働環境で収入も上でしょうし、看護学校に数年通うよりも弁理士試験の予備校の方が安いでしょうし、弁理士を目指す覚悟があるなら私は弁理士をお勧めします。
> 夢を食う動物バカさん
こんばんは
私も、自分と違う立場の人の意見は参考になります。
さて、コメントを拝見させていただき、
お互いの前提条件が若干違うように感じました。
「化学系の技術知識を有する直近の合格者が多数存在する。」
を、私は前提としています。
つまり、技術知識よりも法律知識を優先するという意図ではなく、
両方有するものが多数存在する現状で、
法律知識が古い方を優先する理由がないという意図です。
また、技術知識についても、
私は高度な専門性を有している必要はないと考えています。
確かに、博士号を有している人は化学系とはいえ多くはないかもしれません。
私も博士まで進んでいますが、完全に専門分野を担当することは皆無であり、
せいぜい学士・修士レベルのいわゆる技術知識で十分だと考えています。
(うちは小規模ですので、大規模特許事務所だと事情は少し違うでしょうが)
とすると、
「博士号を有し5年以上前の合格者」と「文系学部を卒業した昨年度合格者」
の、どちらを採用するかと言う質問であればまた別の結論かもしれませんが、
「博士号を有し5年以上前の合格者」と「化学系学部を卒業した近年合格者」
であれば、後者を選択します。
そして、現状後者に該当する人は多数存在するため、前者は選択しないという意図です。
(この意味では、私は博士号の有無について、全く重要視していません。)
また、若干揚げ足取りになってしまうかもしれませんが、
> 最近は化学系博士は珍しくないとのことですが、それ以上に最近受かっただけの弁理士は珍しくありません。
「受かっただけの弁理士」という表現は、
「資格を持っているだけで役に立たない弁理士」という考えの表れのように見えます。
とすると、「弁理士であるか否か」はあまり重要でないようにも思えますが・・・。
なお、余談ですが・・・
私が事務所に入ったとき(+数年)の年収は400万を軽く下回っています。
修行だと言われて夜中まで明細書を書き、
いつ受かるか分からない弁理士試験の予備校に通い、
命ほどではないにせよ、中小企業の命運を握る特許権を扱う責任も重い。
私なら、看護師を選ぶかもしれません。
(この点は、個人の価値判断なので水掛け論ですね)
こんばんは
私も、自分と違う立場の人の意見は参考になります。
さて、コメントを拝見させていただき、
お互いの前提条件が若干違うように感じました。
「化学系の技術知識を有する直近の合格者が多数存在する。」
を、私は前提としています。
つまり、技術知識よりも法律知識を優先するという意図ではなく、
両方有するものが多数存在する現状で、
法律知識が古い方を優先する理由がないという意図です。
また、技術知識についても、
私は高度な専門性を有している必要はないと考えています。
確かに、博士号を有している人は化学系とはいえ多くはないかもしれません。
私も博士まで進んでいますが、完全に専門分野を担当することは皆無であり、
せいぜい学士・修士レベルのいわゆる技術知識で十分だと考えています。
(うちは小規模ですので、大規模特許事務所だと事情は少し違うでしょうが)
とすると、
「博士号を有し5年以上前の合格者」と「文系学部を卒業した昨年度合格者」
の、どちらを採用するかと言う質問であればまた別の結論かもしれませんが、
「博士号を有し5年以上前の合格者」と「化学系学部を卒業した近年合格者」
であれば、後者を選択します。
そして、現状後者に該当する人は多数存在するため、前者は選択しないという意図です。
(この意味では、私は博士号の有無について、全く重要視していません。)
また、若干揚げ足取りになってしまうかもしれませんが、
> 最近は化学系博士は珍しくないとのことですが、それ以上に最近受かっただけの弁理士は珍しくありません。
「受かっただけの弁理士」という表現は、
「資格を持っているだけで役に立たない弁理士」という考えの表れのように見えます。
とすると、「弁理士であるか否か」はあまり重要でないようにも思えますが・・・。
なお、余談ですが・・・
私が事務所に入ったとき(+数年)の年収は400万を軽く下回っています。
修行だと言われて夜中まで明細書を書き、
いつ受かるか分からない弁理士試験の予備校に通い、
命ほどではないにせよ、中小企業の命運を握る特許権を扱う責任も重い。
私なら、看護師を選ぶかもしれません。
(この点は、個人の価値判断なので水掛け論ですね)
なるほど、そういうことでしたら話は変わってきます。
もし弁理士において評価される技術レベルが博士でも学士でも変わらないのであれば、特に近年の合格者増で化学系出身の弁理士も増えていますので、やはり法律知識の新しさという部分での差が大きく影響することになると思います。
私は直接採用に関わるような立場にはないので、この業界におけるそういった実情を知りませんでした。
よく耳にする化学分野の特殊性(化学分野は知識量が物を言うので、最低学士、できれば修士、などといった話です)というものも頭の隅にあったのかもしれませんし、一緒に就職活動をした博士号保有者が有利に活動を進めていたイメージもあったのですが、これらも、修士と博士の差についてはあまり聞いたことがないような気もしますし、その年の合格者という枠組みの中だったからなのかもしれません。
化学系では修士まで進む人が多いことを併せて考えると、「保険」としての価値はあまりないのかもしれません。
博士号の保有や研究経験の長さが評価されないのであれば、いつかするかもしれない転職のためにとりあえず弁理士資格を取っておくことは、費用対効果の面からあまり意味がないかもしれません。
ただし、いざ転職しようと決意した後から勉強を始めてもすぐに弁理士資格が取れる保証はまったくありませんし、以前tomtomさんがご指摘されたように、知財部に異動するという選択肢も考えられます。
これらのリスクや可能性、あるいはあまり評価されないかもしれないけれど持っていないよりはマシかもしれない弁理士資格を取得しておくことは、天秤にかけられるかもしれません。
いずれにせよ、ご本人の人生設計の上で価値判断をされることになるかと思います。
上のなおとさんのコメントを前提としますと、私の今までの主張も結論が変わってくる部分もあるように思います。
もしかしたら間違ったことを言ってトピ主さんに謝った情報を与え混乱させてしまったかもしれません。どうもすみません。
こういった議論の中で出てきた意見や現実が多少でも参考になっていれば良いなと思います。
もし弁理士において評価される技術レベルが博士でも学士でも変わらないのであれば、特に近年の合格者増で化学系出身の弁理士も増えていますので、やはり法律知識の新しさという部分での差が大きく影響することになると思います。
私は直接採用に関わるような立場にはないので、この業界におけるそういった実情を知りませんでした。
よく耳にする化学分野の特殊性(化学分野は知識量が物を言うので、最低学士、できれば修士、などといった話です)というものも頭の隅にあったのかもしれませんし、一緒に就職活動をした博士号保有者が有利に活動を進めていたイメージもあったのですが、これらも、修士と博士の差についてはあまり聞いたことがないような気もしますし、その年の合格者という枠組みの中だったからなのかもしれません。
化学系では修士まで進む人が多いことを併せて考えると、「保険」としての価値はあまりないのかもしれません。
博士号の保有や研究経験の長さが評価されないのであれば、いつかするかもしれない転職のためにとりあえず弁理士資格を取っておくことは、費用対効果の面からあまり意味がないかもしれません。
ただし、いざ転職しようと決意した後から勉強を始めてもすぐに弁理士資格が取れる保証はまったくありませんし、以前tomtomさんがご指摘されたように、知財部に異動するという選択肢も考えられます。
これらのリスクや可能性、あるいはあまり評価されないかもしれないけれど持っていないよりはマシかもしれない弁理士資格を取得しておくことは、天秤にかけられるかもしれません。
いずれにせよ、ご本人の人生設計の上で価値判断をされることになるかと思います。
上のなおとさんのコメントを前提としますと、私の今までの主張も結論が変わってくる部分もあるように思います。
もしかしたら間違ったことを言ってトピ主さんに謝った情報を与え混乱させてしまったかもしれません。どうもすみません。
こういった議論の中で出てきた意見や現実が多少でも参考になっていれば良いなと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
弁理士受験生 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
弁理士受験生のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90024人
- 2位
- 酒好き
- 170668人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人