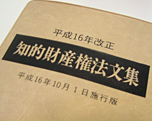特許法に関連する疑問で、短答的疑問とも論文的疑問とも区別ができない疑問について話し合うトピックを立てさせていただきました。
で、早速皆さんのご意見を伺いたいのです。ある裁判例(大阪高裁判決平成15年2月27日)の判決文に「『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正は、親出願の出願当初明細書又は図面に記載されておらず、子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み、上記補正後の子出願の明細書は、親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むものであるから、子出願は、親出願から特許法44条1項に基づき適法に分割されたものといえないことになる」というくだりがあります。
この部分を読む限り、『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正は特許請求の範囲における補正なのか、それとも実施例の記載等における補正なのかは判然としません。仮に『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正が実施例の記載等における補正であるものとします。すなわち、親出願の明細書には『線状の支持部材』と書いてあり、子出願の明細書にその記載部分を移植する際に、『線状の支持部材』の文言を『支持部材』に変更することがなされたものと考えます。
ここでまず、「下位概念の記載からはその上位概念の記載が認定できる」ものと考えるわけです。『線状の支持部材』は(単なる)『支持部材』の下位概念であるわけです。すると、『線状の支持部材』という記載からは、その下位概念そのものの構成のみならず、上位概念である『支持部材』の記載も認定できると考えられます。
すると、子出願における明細書において『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正により、親出願の出願当初明細書または図面の範囲内でない事項を含むことになったとはいえないのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。
で、早速皆さんのご意見を伺いたいのです。ある裁判例(大阪高裁判決平成15年2月27日)の判決文に「『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正は、親出願の出願当初明細書又は図面に記載されておらず、子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み、上記補正後の子出願の明細書は、親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むものであるから、子出願は、親出願から特許法44条1項に基づき適法に分割されたものといえないことになる」というくだりがあります。
この部分を読む限り、『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正は特許請求の範囲における補正なのか、それとも実施例の記載等における補正なのかは判然としません。仮に『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正が実施例の記載等における補正であるものとします。すなわち、親出願の明細書には『線状の支持部材』と書いてあり、子出願の明細書にその記載部分を移植する際に、『線状の支持部材』の文言を『支持部材』に変更することがなされたものと考えます。
ここでまず、「下位概念の記載からはその上位概念の記載が認定できる」ものと考えるわけです。『線状の支持部材』は(単なる)『支持部材』の下位概念であるわけです。すると、『線状の支持部材』という記載からは、その下位概念そのものの構成のみならず、上位概念である『支持部材』の記載も認定できると考えられます。
すると、子出願における明細書において『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正により、親出願の出願当初明細書または図面の範囲内でない事項を含むことになったとはいえないのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。
|
|
|
|
コメント(10)
上に設定した問題はやや複雑かもしれませんが、問題を逆に設定するとそれが解明のヒントになるかもしれません。つまり、親出願の明細書には単に『支持部材』と書いてあり、子出願の明細書にその記載部分を移植する際に、『支持部材』の文言を『線状の支持部材』に変更することがなされたものと考えてみます。
この場合は、子出願の明細書には「線状の」という語句があらたに加わったわけですから、単なる「支持部材」は「線状の支持部材」でなければならないという話になり、親出願の明細書に書かれていない事項が新規に加わったということがはっきりわかるわけです。
ところが問題のようなケースだと、なぜ
「『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正は、親出願の出願当初明細書又は図面に記載されておらず、子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み、上記補正後の子出願の明細書は、親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むものであるから、子出願は、親出願から特許法44条1項に基づき適法に分割されたものといえないことになる」
という判断がなされるのでしょう。ここがポイントになっているわけです。
この場合は、子出願の明細書には「線状の」という語句があらたに加わったわけですから、単なる「支持部材」は「線状の支持部材」でなければならないという話になり、親出願の明細書に書かれていない事項が新規に加わったということがはっきりわかるわけです。
ところが問題のようなケースだと、なぜ
「『線状の支持部材』を『支持部材』とした補正は、親出願の出願当初明細書又は図面に記載されておらず、子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み、上記補正後の子出願の明細書は、親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むものであるから、子出願は、親出願から特許法44条1項に基づき適法に分割されたものといえないことになる」
という判断がなされるのでしょう。ここがポイントになっているわけです。
初めまして。
出願の分割は、補正の一種と考えることができます。
補正は、当初明細書の記載から自明な範囲(少し前は、当初明細書の記載から直接、一義的と言っていました)で行わなければならず、新規事項の追加は認められません。
まず、『線状の支持部材』を『支持部材』に補正することについて考えます。
『支持部材』には、色々な形状が考えられます。
この場合、当初明細書で自ら「線状の」支持部材と限定的に記載し、図面にも「線状の」ものしか記載されていないのだとしたら、「線状の」を削除することにより、当初明細書に記載されていなかったその他の形状の支持部材を含む(追加する)ことになります。
よって、このような補正は、当初の記載を拡張し、一般化することになり、認められません。
次に、『支持部材』を『線状の支持部材』に補正する場合。
当初明細書にも図面にも「線状の」支持部材が記載されていないにも関わらず、「線状の」を追加することは、勿論、許されません。
しかし、請求項に『支持部材』と記載されていて、明細書の詳細な説明や実施の形態に具体的なものとして「線状の」支持部材が記載されていれば、『支持部材』を『線状の支持部材』に補正することは、限定的減縮に当たり、全く問題ありません。
最も典型的な例として、出願当初は「ゴム」しか記載されていなかったものを「弾性部材」に補正することは認められないが、出願当初に「弾性部材」という記載と共に具体例として、「ゴム」や「バネ」が記載されていれば、「ゴム」又は「バネ」に補正することは認められるというのがあります。
今回のケースは、これと同じだと思うのですが、如何でしょうか。
出願の分割は、補正の一種と考えることができます。
補正は、当初明細書の記載から自明な範囲(少し前は、当初明細書の記載から直接、一義的と言っていました)で行わなければならず、新規事項の追加は認められません。
まず、『線状の支持部材』を『支持部材』に補正することについて考えます。
『支持部材』には、色々な形状が考えられます。
この場合、当初明細書で自ら「線状の」支持部材と限定的に記載し、図面にも「線状の」ものしか記載されていないのだとしたら、「線状の」を削除することにより、当初明細書に記載されていなかったその他の形状の支持部材を含む(追加する)ことになります。
よって、このような補正は、当初の記載を拡張し、一般化することになり、認められません。
次に、『支持部材』を『線状の支持部材』に補正する場合。
当初明細書にも図面にも「線状の」支持部材が記載されていないにも関わらず、「線状の」を追加することは、勿論、許されません。
しかし、請求項に『支持部材』と記載されていて、明細書の詳細な説明や実施の形態に具体的なものとして「線状の」支持部材が記載されていれば、『支持部材』を『線状の支持部材』に補正することは、限定的減縮に当たり、全く問題ありません。
最も典型的な例として、出願当初は「ゴム」しか記載されていなかったものを「弾性部材」に補正することは認められないが、出願当初に「弾性部材」という記載と共に具体例として、「ゴム」や「バネ」が記載されていれば、「ゴム」又は「バネ」に補正することは認められるというのがあります。
今回のケースは、これと同じだと思うのですが、如何でしょうか。
>「線状の」を削除することにより、当初明細書に記載されていなかったその他の形状の支持部材を
>含む(追加する)ことになります。よって、このような補正は、当初の記載を拡張し、一般化する
>ことになり、認められません。
きむさん、レス有難うございます。おそらくこういう解釈になるのだろうとは思います。
ところで次のようなケースはどう説明できると思われますか?
ここに出願Aがあり、その請求項は「a+b+『支持部材』」となっていたとします。
ところが出願Aの出願時以前に先行技術文献Bが存在し、そこに「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていたとします。
すると、「a+b+『線状の支持部材』」という構成の記載からは「a+b+『支持部材』」という構成の記載は認定できるわけですよね。このため、出願Aはこの先行技術文献Bの存在を理由として新規性欠如で拒絶されるはずです。つまり、「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、「a+b+『支持部材』」という構成は記載されているも同然であるという考えが背後にあるわけです。
そうだとすると、親出願に「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、分割にかかる子出願において「a+b+『支持部材』」という構成の記載に変更したとしても、もともと親出願に記載されているも同然の内容に基づいて変更したのだから、拡張にはあたらないはずだ、という論理が成立するかのように見えます。この論理はどこが間違っていると思われますか?
>含む(追加する)ことになります。よって、このような補正は、当初の記載を拡張し、一般化する
>ことになり、認められません。
きむさん、レス有難うございます。おそらくこういう解釈になるのだろうとは思います。
ところで次のようなケースはどう説明できると思われますか?
ここに出願Aがあり、その請求項は「a+b+『支持部材』」となっていたとします。
ところが出願Aの出願時以前に先行技術文献Bが存在し、そこに「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていたとします。
すると、「a+b+『線状の支持部材』」という構成の記載からは「a+b+『支持部材』」という構成の記載は認定できるわけですよね。このため、出願Aはこの先行技術文献Bの存在を理由として新規性欠如で拒絶されるはずです。つまり、「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、「a+b+『支持部材』」という構成は記載されているも同然であるという考えが背後にあるわけです。
そうだとすると、親出願に「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、分割にかかる子出願において「a+b+『支持部材』」という構成の記載に変更したとしても、もともと親出願に記載されているも同然の内容に基づいて変更したのだから、拡張にはあたらないはずだ、という論理が成立するかのように見えます。この論理はどこが間違っていると思われますか?
>「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、「a+b+『支持部材』」という構成は
>記載されているも同然であるという考えが背後にあるわけです。
これは、違うと思います。
下位概念の先願と上位概念の後願との関係で、上位概念の後願が拒絶されるのは、上位概念の中に含まれる下位概念の部分が二重特許になってしまうからです。後願に対して、先願の発明を含む、より広い範囲で権利を認めると、後願によって先願の権利が侵され、先願の権利を守ることができなくなり、先願主義に反することになります。
よって、上位概念の後願は特許として認められません。
同様に、下位概念を上位概念に補正することを認めると、日付を遡って出願当初よりも広い権利を認めることになり、第三者に不利益をもたらすことになってしまうので、不適法と言えます。
因みに、上位概念の先願と下位概念の後願があった場合、下位概念の後願は上位概念の先願に含まれることになります。
しかし、下位概念の後願が必ず拒絶されるかと言うと、そうではありません。
上位概念(『支持部材』)の先願の中に、下位概念として具体的に『線状の支持部材』が記載されておらず、『線状の支持部材』という下位概念によって、上位概念では得られなかった顕著な作用、効果が認められば特許になります。
勿論、この場合、下位概念の後願が、上位概念の先願に含まれることに変わりはなく、利用関係となるので、先願を無視して後願を勝手に実施することはできません。
>記載されているも同然であるという考えが背後にあるわけです。
これは、違うと思います。
下位概念の先願と上位概念の後願との関係で、上位概念の後願が拒絶されるのは、上位概念の中に含まれる下位概念の部分が二重特許になってしまうからです。後願に対して、先願の発明を含む、より広い範囲で権利を認めると、後願によって先願の権利が侵され、先願の権利を守ることができなくなり、先願主義に反することになります。
よって、上位概念の後願は特許として認められません。
同様に、下位概念を上位概念に補正することを認めると、日付を遡って出願当初よりも広い権利を認めることになり、第三者に不利益をもたらすことになってしまうので、不適法と言えます。
因みに、上位概念の先願と下位概念の後願があった場合、下位概念の後願は上位概念の先願に含まれることになります。
しかし、下位概念の後願が必ず拒絶されるかと言うと、そうではありません。
上位概念(『支持部材』)の先願の中に、下位概念として具体的に『線状の支持部材』が記載されておらず、『線状の支持部材』という下位概念によって、上位概念では得られなかった顕著な作用、効果が認められば特許になります。
勿論、この場合、下位概念の後願が、上位概念の先願に含まれることに変わりはなく、利用関係となるので、先願を無視して後願を勝手に実施することはできません。
tomtomさん>
この論理は、「親出願の一部」の判断基準が間違っております。
39条の先後願関係の趣旨は、重複特許の排除です。
一方、分割要件の「親出願の一部」の趣旨は、出願日遡及効のための「新しい発明の開示」かどうかで、分割出願に記載できる範囲は補正要件の17条の2第3項と同じです。
つまり・・・
親出願の明細書等に記載された事項から自明な事項
の範囲内で子出願がされたかどうかで判断され、「線状の」という技術的思想が、親出願明細書等に記載されているか、または親出願の出願時当業者から見て親出願明細書等に記載されているも同然である場合にのみ、出願日遡及効が認められます。
上位/下位概念は自明かどうかの判断とは無関係です。
>親出願に「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、分割
>にかかる子出願において「a+b+『支持部材』」という構成の記載に変更した
>としても、もともと親出願に記載されているも同然の内容に基づいて変更したの
>だから、拡張にはあたらないはずだ、という論理が成立するかのように見えます。
>この論理はどこが間違っていると思われますか?
この論理は、「親出願の一部」の判断基準が間違っております。
39条の先後願関係の趣旨は、重複特許の排除です。
一方、分割要件の「親出願の一部」の趣旨は、出願日遡及効のための「新しい発明の開示」かどうかで、分割出願に記載できる範囲は補正要件の17条の2第3項と同じです。
つまり・・・
親出願の明細書等に記載された事項から自明な事項
の範囲内で子出願がされたかどうかで判断され、「線状の」という技術的思想が、親出願明細書等に記載されているか、または親出願の出願時当業者から見て親出願明細書等に記載されているも同然である場合にのみ、出願日遡及効が認められます。
上位/下位概念は自明かどうかの判断とは無関係です。
>親出願に「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、分割
>にかかる子出願において「a+b+『支持部材』」という構成の記載に変更した
>としても、もともと親出願に記載されているも同然の内容に基づいて変更したの
>だから、拡張にはあたらないはずだ、という論理が成立するかのように見えます。
>この論理はどこが間違っていると思われますか?
>>「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、「a+b+『支持部材』」という
>>構成は記載されているも同然であるという考えが背後にあるわけです。
>これは、違うと思います。
>下位概念の先願と上位概念の後願との関係で、上位概念の後願が拒絶されるのは、
>上位概念の中に含まれる下位概念の部分が二重特許になってしまうからです。後願
>に対して、先願の発明を含む、より広い範囲で権利を認めると、後願によって先願
>の権利が侵され、先願の権利を守ることができなくなり、先願主義に反することになります。
これは「なるほど!」と思います。
しかし次のような問題点はどう説明されますか。
3番で私が導入した設例において、
>ここに出願Aがあり、その請求項は「a+b+『支持部材』」となっていたとします。
>ところが出願Aの出願時以前に先行技術文献Bが存在し、そこに「a+b+『線状の
>支持部材』」という構成が記載されていたとします。
>すると、「a+b+『線状の支持部材』」という構成の記載からは「a+b+『支持部材』」
>という構成の記載は認定できるわけですよね。このため、出願Aはこの先行技術文献Bの
>存在を理由として新規性欠如で拒絶されるはずです。
この場合において先行技術文献Bの開示部分は、実施例の記載の中に記載されており、請求項の記載ではないものと仮定します。そうすると39条の先願主義違反は適用できなくなるのではないでしょうか。なぜかというと、39条違反が適用されるためには、先願発明も請求項に係る発明、後願発明も請求項に係る発明、そして両者の請求項に係る発明が同一ならば、出願日が遅い出願Aのほうが拒絶される、ということが出願Aに対する拒絶理由になるわけです。
ところが先行技術文献Bの開示部分は、実施例の記載であり、請求項の記載ではないものと仮定しますと、請求項同士の対比はできないことになります。すると出願Aを39条で拒絶することは出来ないのではないでしょうか。
すると、出願Aを先行技術文献Bの実施例の記載の開示部分により拒絶するのであれば、拒絶理由の適用条文は29条1項3号になります。すると29条1項の趣旨は、「特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明は新規性がないものとして拒絶する」ということですから、この条文を適用する限りは、先行技術文献Bに「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、「a+b+『支持部材』」という構成は記載されているも同然であるという考えが背後にあるのでなければならない、ということにならないでしょうか。
>>構成は記載されているも同然であるという考えが背後にあるわけです。
>これは、違うと思います。
>下位概念の先願と上位概念の後願との関係で、上位概念の後願が拒絶されるのは、
>上位概念の中に含まれる下位概念の部分が二重特許になってしまうからです。後願
>に対して、先願の発明を含む、より広い範囲で権利を認めると、後願によって先願
>の権利が侵され、先願の権利を守ることができなくなり、先願主義に反することになります。
これは「なるほど!」と思います。
しかし次のような問題点はどう説明されますか。
3番で私が導入した設例において、
>ここに出願Aがあり、その請求項は「a+b+『支持部材』」となっていたとします。
>ところが出願Aの出願時以前に先行技術文献Bが存在し、そこに「a+b+『線状の
>支持部材』」という構成が記載されていたとします。
>すると、「a+b+『線状の支持部材』」という構成の記載からは「a+b+『支持部材』」
>という構成の記載は認定できるわけですよね。このため、出願Aはこの先行技術文献Bの
>存在を理由として新規性欠如で拒絶されるはずです。
この場合において先行技術文献Bの開示部分は、実施例の記載の中に記載されており、請求項の記載ではないものと仮定します。そうすると39条の先願主義違反は適用できなくなるのではないでしょうか。なぜかというと、39条違反が適用されるためには、先願発明も請求項に係る発明、後願発明も請求項に係る発明、そして両者の請求項に係る発明が同一ならば、出願日が遅い出願Aのほうが拒絶される、ということが出願Aに対する拒絶理由になるわけです。
ところが先行技術文献Bの開示部分は、実施例の記載であり、請求項の記載ではないものと仮定しますと、請求項同士の対比はできないことになります。すると出願Aを39条で拒絶することは出来ないのではないでしょうか。
すると、出願Aを先行技術文献Bの実施例の記載の開示部分により拒絶するのであれば、拒絶理由の適用条文は29条1項3号になります。すると29条1項の趣旨は、「特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明は新規性がないものとして拒絶する」ということですから、この条文を適用する限りは、先行技術文献Bに「a+b+『線状の支持部材』」という構成が記載されていれば、「a+b+『支持部材』」という構成は記載されているも同然であるという考えが背後にあるのでなければならない、ということにならないでしょうか。
>39条の先後願関係の趣旨は、重複特許の排除です。
>一方、分割要件の「親出願の一部」の趣旨は、出願日遡及効のための「新しい発明の
>開示」かどうかで、分割出願に記載できる範囲は補正要件の17条の2第3項と同じです。
7番のメッセージに書いた問題点が存在するために、結局wantaさんがおっしゃっていることがダイレクトな解答になるかもしれません。
すなわち、親出願に「a+b+『線状の支持部材』」という構成の新しい発明の開示がなされていることをもって、この親出願に「a+b+『支持部材』」という構成の新しい発明が開示されているとみなしていいのかということですね。これは、このような「みなし」は成立しないという理解になるのでしょう。
>一方、分割要件の「親出願の一部」の趣旨は、出願日遡及効のための「新しい発明の
>開示」かどうかで、分割出願に記載できる範囲は補正要件の17条の2第3項と同じです。
7番のメッセージに書いた問題点が存在するために、結局wantaさんがおっしゃっていることがダイレクトな解答になるかもしれません。
すなわち、親出願に「a+b+『線状の支持部材』」という構成の新しい発明の開示がなされていることをもって、この親出願に「a+b+『支持部材』」という構成の新しい発明が開示されているとみなしていいのかということですね。これは、このような「みなし」は成立しないという理解になるのでしょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
弁理士受験生 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
弁理士受験生のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人