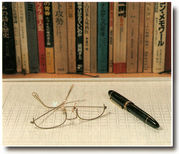池上です。
「下読みの鉄人」の間違いを指摘したメールを
みなさんに流したら、数人の方からメールをもらいました。
みんな読んでいて、信用していた、というから、
びっくりびっくり。影響力が大きいんだなあ。
ひょっとしたら、講座の生徒の半分以上は
読んでるかもしれない。
ということで、ちょっと心配になり、
もういちどホームページを読んで、
問題点を摘出しました。
下のほうに、僕なりの感想を述べます。
引用文が長いので、長文になりましたが、お許しを。
それにしても、「下読みの鉄人」は罪作りだなあ。
各方面から間違いを指摘されて、それで、
更新がとまっているのかもしれない。
●以下、問題点です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−
まず、基本中の基本、“新人賞の選考システム”に
間違いがある。鉄人は、
●編集部内での予備チェック
●一次選考(社外の下読み)
●二次選考(編集部内の選考会議)
●最終選考(選考委員による選考会)
の4段階にわけているが、これは正しくはない。
この“下読みの鉄人”は、困ったことに(はっきりいって
無知なことに)、“予選委員”という制度があるのを知らない。
いいですか、新人賞の選考には“下読み”だけでなく
“予選委員”も関わっている。
では、下読みと予選委員はどう違うのか?
下読みとは一次、ないしは二次選考にたずさわる人間のこと。
予選委員とは一次から最終候補まで(もしくは
それに準じる段階まで)決める人間のこと。
江戸川乱歩賞も、いまはなきサントリーミステリー大賞も
“予選委員”制度である(であった)。
編集者はいっさいタッチせずに、予選委員(評論家)たちが
議論して最終候補作を決める(決めた)。
日本ホラー小説大賞も、予選委員(評論家)6人と
編集部数名で最終候補作を決める。
合同で会議を開き、議論を戦わせて、最終候補作を決める。
「このミステリーがすごい大賞」も、ホームページを
みればわかるように、編集部はいっさいタッチせずに、
評論家たちが最終候補を決めている。
ただし、小説すばる新人賞、ホラーサスペンス大賞、らいらっく文学賞、
朝日新人文学賞など多くは、下読みが一次、ないしは二次選考を
おこない、最終候補作は編集部が決める。
つまり、“新人賞の選考システム”には、
下読みと予選委員の二つの制度がある、
ということを認識するように。
そして、そんな常識的なことを、下読みの鉄人は知らない。
困ったもんです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
▼“プロフィールの書き方”の項目のところ
> ●落選歴は書くな
> 応募歴を書けという指示がある時に、
> 「第○回○○賞・一次選考落選」
> などというふうに、落選歴を延々と書く人がいるのですが、
> これは全く無意味なことです。書くのであれば、
> せめて「一次選考通過」からにしてください。
> 本当は「最終選考に残った」以上の戦歴がなければ、
> 無理に応募歴を書く必要はありません。
この見解は評論家によってわかれるだろう。
僕は落選歴も書いてほしい。
何を狙っているのか、何を書きたがっているのかがわかるから。
あとは多少“経歴”があると、慎重に読む可能性が高い、
ということもあるよ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●同人誌歴は書くな
> 同人誌に参加しているという話は、特に書かないほうが
> 無難な場合が多いです。
> ただし、例外は、今回の応募原稿が、同人誌に
> 発表済の作品であるという場合です。
> これは、きちんと明記してください。
同人雑誌歴も書いていいと思う。
文章のキャリアのあるなしは重要だよ。
たしかに同人誌歴というのは、“色”がついていて、
“ああ、いくら頑張っても受賞できない人たちね”と
皮肉な目をむける評論家もいるが(僕ではない)、
でも、キャリアがあることは誇ったほうがいい。
さきほども書いたが、読む方も慎重になる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●原稿は必ず綴じる
> 右上の角の1ヵ所、あるいは右横中央の2ヵ所に穴を開け、
> ヒモのようなもので綴じてください。
右肩をとじるというのは常識。
でも、“右横中央2個所に穴を開け”は賛成できない。
というか、僕は(おそらく他の評論家も)勘弁してほしい(と思ってる)。
かさばると(100枚越えると)、ずっと右手で押さえて
読まなくてはいけなくなる。ひじょうに面倒くさい。
たぶんこの“下読みの鉄人”という人、
短篇中心の下読みさんなのでは?
長篇を続けて読む苦労をしらない。
前回も書いたけれど、“頁をめくる”のも疲れるのだ(笑)。
ましてや、右横に穴あけられたら、ずっと右手で
押さえて読まなくてはいけない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●封筒の宛名には必ず「御中」を付ける
> これを採点項目の一つとしてチェックしている賞もあります。
これには笑った。
“御中”は郵便送付の常識だが、だからといって、
それが“選考”に関係することはまずありえない。
いったい、どこの賞なの?
そんなのをチェックするなんて、よっぽど暇な賞だなあ。
というか、そんなのがチェックポイントになるなんて、
集まってくる小説のレベルが低すぎるんじゃないかな。
だいいち袋をあけるのはバイトか編集者1、2年の人たちで、
次々に来る郵便物に圧倒されて、
封筒に“御中”があるかどうかなんて確認しませんよ(笑)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●名前入りの原稿用紙は不可
> 団体名や個人名などが印刷された特殊な原稿用紙を
> 使ってはいけません。
> 賞によっては、作者の名前を伏せて、タイトルと本編だけで
> 審査を行なうことがあるからです。
そんなことはないと思うよ。
作者の名前を伏せて審査するなんて、僕はきいたこともない。
いったいどこの賞なんだろう。
むしろ名前を明らかにしたほうが、トラブルを防げる。
同じ人間が、ちょこちょこっと内容を変えて、
あちこちに応募するパターンが多いからね。
そういう二重三重投稿が多いので、名前を明らかにする。
下読みの段階で、評論家に見つけてほしがる。編集部が。
たいていみんな掛け持ちでやっているから、
情報は自ずと伝わるし、わかっちゃう。
僕の場合、N賞とサントリーミステリー大賞と
江戸川乱歩賞の選考(予選委員です。下読みではなく)を
やっていた時期が重なるが、いやあ、けっこう多いよ。
N賞で読んだものがサンミスにきて、
サンミスで落ちたものが、江戸川乱歩賞。
いや逆か。江戸川乱歩賞でおちたものが、サンミスだね。
サンミスは、他の賞の落ちたものの吹き溜まりだった(笑)。
下読み(予選委員)に評論家が選ばれるのは
(重宝されるのは)、実はそういう情報に詳しいからでもある。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●コピーでの応募は不可
> 原稿用紙のコピーを取ったものでの応募は不可です。
> 多重投稿などの疑いをかけられます。
> 必ず手書きした本物の原稿を送ってください。
基本的にそうなんだが、僕はコピーで読みたいと思っているほう。
手書き=手垢のついた原稿は、ちょっとイヤだ。
実際、コピーも多いですよ。これは人(賞)それぞれですね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●ヘッダーやフッターの使用は不可
> ワープロのヘッダー&フッター機能を使って、
> 余白にいろいろなことを印字する人がいるのですが、
> これはやめてください。特に本編の原稿の余白に作者の名前が
> 印字されていたりすると「名前入りの原稿用紙」と
> 同じ状態になって致命的です。
“致命的”という根拠がわからない。さきほども書いたように
名前はわかったほうがいい場合がある。
これも無視していい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●感熱紙の使用は不可
> 感熱紙は応募後の保存状態により、
> 用紙が変色したり印字が褪色するなどして、
> 原稿が読めなくなってしまうことがあります。
> また、変質した感熱紙には独特の匂いと手触りが発生して、
> これを嫌う選考委員もいます。
感熱紙の使用は避けたほうがいいが、
でも、実際問題としてけっこう多いですよ。
変にかすれた印字よりも、印字が鮮やかな
感熱紙のほうがいい場合もある。
ただし光の反射がきついので、逆に嫌がる人も多い。
それにしても、おかしいのは、
> また、変質した感熱紙には独特の匂いと手触りが発生して、
> これを嫌う選考委員もいます。
というくだり。
普通ね、選考委員の先生がたにはコピーをお送りしますよ。
予選委員だってコピーで読むんですから。きれいで汚れのない
コピーした原稿をね。生原稿をたらいまわしで読んでいたら
時間がかかってしょうがない。
それなのに、「下読みの鉄人」がかかわる(?)賞では、
応募者が送ってよこした感熱紙の原稿を
選考委員の先生がたが、そのまま読むんですね。
コピーする金がないのでしょうか。
いくらなんでも、下読みと編集者が読んだあとの
手垢のついたものを選考委員に読ませるなんて・・・。
そんなの大手では絶対にない。僕はきいたことがない。
いったいコピーする金もない出版社ってどこよ(笑)。
なんという賞? なんか知りたくなるね(笑)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> よけいな文章を書くと自滅する
> 応募規定に指示がない限り「まえがき」や「あとがき」などを
> 付けていはいけません。「献辞」や「謝辞」なども同様です。
> これらはプロが自分の本を出す時に書くべきものであって、
> 素人が新人賞の応募原稿に書くようなものではありません。
> まえがきが付いていたから自動的に落選にされる
> というわけではないのですが、審査を行なう上での
> マイナスの判断材料に使われる可能性が高い
> ということは知っておいてください。
そうかなあ。僕は別にいいと思うけどなあ。
愛すべき稚気として、僕なんか歓迎しますけどね。
ほとんど笑ってしまうことも多いんですが、
選考の息抜きになって、僕なんか歓迎するけど。
短期間に集中して何十本も読んでいると、しかも
けっこう愛想のない原稿が続くと疲れるのよ。好きでもね。
そういうときに、そういう稚気に出会うと、もう嬉しくなる(笑)。
“こいつ何考えてんだろう?”とニヤニヤしながら、
読んじゃうね。息抜きになって楽しくなる(笑)。
これは下読みの楽しみのひとつでもあるんだけどなあ。
「下読みの鉄人」さんは真面目だなあ。
> 特に、こんなことが書かれていると確実に不利、
>
> ●自分で解説を書いている
> 自分の作品がいかに素晴らしいものであるかを延々と
> 解説した文章を自分で付けているというものです。
いますね。そういう人たちが。
“世紀の傑作”であるとか、“名作だと思っています”とか、
堂々と書くんですよ。あるいは略歴のところでは、
“著書多数。ただしまだ1冊も出版されていません”とかね(笑)。
笑わせてくれるんです。ほとんど駄目ですが。
でも、解説つけても(余計なことを書いても)、僕はいいと思いますよ。
解説をつける人間の99パーセントは自信過剰タイプで、
実力の伴っていない人間ですが、でも、ときどき、感心するくらいに
冷静に解説をほどこす人間もいて(理科系に多い)、
“ふむふむ、なるほど。なかなか面白そうじゃないか・・”
なんて、期待をかきたてられてしまう場合もある。
いちがいにはいえない。“不利”とはね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> 最終選考で落ちても、落胆する必要はありません。
> 最終選考まで残れば、実は、入選と落選の間には、
> それほど大きな差はないからです。かなり運の要素が強く
> 「選考委員が変われば入選作品と落選作品が入れ替わっても
> 不思議ではない」というケースも珍しくありません。
まあ、それはいえるでしょう。
ただ、万年最終候補作家というのも存在する。
よくできました、というタイプの個性のない作品ね。
2時間サスペンスの中身のある原作という感じ。
> 最終選考に残ったということは、編集部の中に、
> あなたの作品を非常に高く評価してくれた人物がいるということです。
> あなたの作品が入選することを期待してくれていた人物が
> いるということです。その人物とコンタクトを取り、指導を受けましょう。
最終候補作=編集部が選んだ作品、というふうに考えていますね。
最初に書いたように、それは違うって。
予選委員(評論家)の場合もある。
編集者なのか、評論家なのかをみきわめること。
“その人物とコンタクトを取り、指導を受けましょう”と簡単に書くが、
編集者の中には、“最終候補に残ったぐらいで
コンタクトをとらないでほしい”と考える輩もたくさんいます。
一回や二回、まぐれで最終候補になることもあるんです(笑)。
賞をとったからといって次々にいいものが書ける訳でもない、
ということも、編集者たちは経験で、とことん知っています。
だから一回ぐらい、最終候補になったからといって、
舞い上がって(「下読みの鉄人」の話をうのみにして)、
編集部に電話して、指導をよろしく! なんてことはしないように。
変に思われるからね。この人、ちょっと精神的におかしいかもと。
ほんとうに編集者が気に入ったなら、電話をかけますよ。
その人にね。一度会いませんか、と。
そういうことはよくあります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「下読みの鉄人」の間違いを指摘したメールを
みなさんに流したら、数人の方からメールをもらいました。
みんな読んでいて、信用していた、というから、
びっくりびっくり。影響力が大きいんだなあ。
ひょっとしたら、講座の生徒の半分以上は
読んでるかもしれない。
ということで、ちょっと心配になり、
もういちどホームページを読んで、
問題点を摘出しました。
下のほうに、僕なりの感想を述べます。
引用文が長いので、長文になりましたが、お許しを。
それにしても、「下読みの鉄人」は罪作りだなあ。
各方面から間違いを指摘されて、それで、
更新がとまっているのかもしれない。
●以下、問題点です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−
まず、基本中の基本、“新人賞の選考システム”に
間違いがある。鉄人は、
●編集部内での予備チェック
●一次選考(社外の下読み)
●二次選考(編集部内の選考会議)
●最終選考(選考委員による選考会)
の4段階にわけているが、これは正しくはない。
この“下読みの鉄人”は、困ったことに(はっきりいって
無知なことに)、“予選委員”という制度があるのを知らない。
いいですか、新人賞の選考には“下読み”だけでなく
“予選委員”も関わっている。
では、下読みと予選委員はどう違うのか?
下読みとは一次、ないしは二次選考にたずさわる人間のこと。
予選委員とは一次から最終候補まで(もしくは
それに準じる段階まで)決める人間のこと。
江戸川乱歩賞も、いまはなきサントリーミステリー大賞も
“予選委員”制度である(であった)。
編集者はいっさいタッチせずに、予選委員(評論家)たちが
議論して最終候補作を決める(決めた)。
日本ホラー小説大賞も、予選委員(評論家)6人と
編集部数名で最終候補作を決める。
合同で会議を開き、議論を戦わせて、最終候補作を決める。
「このミステリーがすごい大賞」も、ホームページを
みればわかるように、編集部はいっさいタッチせずに、
評論家たちが最終候補を決めている。
ただし、小説すばる新人賞、ホラーサスペンス大賞、らいらっく文学賞、
朝日新人文学賞など多くは、下読みが一次、ないしは二次選考を
おこない、最終候補作は編集部が決める。
つまり、“新人賞の選考システム”には、
下読みと予選委員の二つの制度がある、
ということを認識するように。
そして、そんな常識的なことを、下読みの鉄人は知らない。
困ったもんです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
▼“プロフィールの書き方”の項目のところ
> ●落選歴は書くな
> 応募歴を書けという指示がある時に、
> 「第○回○○賞・一次選考落選」
> などというふうに、落選歴を延々と書く人がいるのですが、
> これは全く無意味なことです。書くのであれば、
> せめて「一次選考通過」からにしてください。
> 本当は「最終選考に残った」以上の戦歴がなければ、
> 無理に応募歴を書く必要はありません。
この見解は評論家によってわかれるだろう。
僕は落選歴も書いてほしい。
何を狙っているのか、何を書きたがっているのかがわかるから。
あとは多少“経歴”があると、慎重に読む可能性が高い、
ということもあるよ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●同人誌歴は書くな
> 同人誌に参加しているという話は、特に書かないほうが
> 無難な場合が多いです。
> ただし、例外は、今回の応募原稿が、同人誌に
> 発表済の作品であるという場合です。
> これは、きちんと明記してください。
同人雑誌歴も書いていいと思う。
文章のキャリアのあるなしは重要だよ。
たしかに同人誌歴というのは、“色”がついていて、
“ああ、いくら頑張っても受賞できない人たちね”と
皮肉な目をむける評論家もいるが(僕ではない)、
でも、キャリアがあることは誇ったほうがいい。
さきほども書いたが、読む方も慎重になる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●原稿は必ず綴じる
> 右上の角の1ヵ所、あるいは右横中央の2ヵ所に穴を開け、
> ヒモのようなもので綴じてください。
右肩をとじるというのは常識。
でも、“右横中央2個所に穴を開け”は賛成できない。
というか、僕は(おそらく他の評論家も)勘弁してほしい(と思ってる)。
かさばると(100枚越えると)、ずっと右手で押さえて
読まなくてはいけなくなる。ひじょうに面倒くさい。
たぶんこの“下読みの鉄人”という人、
短篇中心の下読みさんなのでは?
長篇を続けて読む苦労をしらない。
前回も書いたけれど、“頁をめくる”のも疲れるのだ(笑)。
ましてや、右横に穴あけられたら、ずっと右手で
押さえて読まなくてはいけない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●封筒の宛名には必ず「御中」を付ける
> これを採点項目の一つとしてチェックしている賞もあります。
これには笑った。
“御中”は郵便送付の常識だが、だからといって、
それが“選考”に関係することはまずありえない。
いったい、どこの賞なの?
そんなのをチェックするなんて、よっぽど暇な賞だなあ。
というか、そんなのがチェックポイントになるなんて、
集まってくる小説のレベルが低すぎるんじゃないかな。
だいいち袋をあけるのはバイトか編集者1、2年の人たちで、
次々に来る郵便物に圧倒されて、
封筒に“御中”があるかどうかなんて確認しませんよ(笑)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●名前入りの原稿用紙は不可
> 団体名や個人名などが印刷された特殊な原稿用紙を
> 使ってはいけません。
> 賞によっては、作者の名前を伏せて、タイトルと本編だけで
> 審査を行なうことがあるからです。
そんなことはないと思うよ。
作者の名前を伏せて審査するなんて、僕はきいたこともない。
いったいどこの賞なんだろう。
むしろ名前を明らかにしたほうが、トラブルを防げる。
同じ人間が、ちょこちょこっと内容を変えて、
あちこちに応募するパターンが多いからね。
そういう二重三重投稿が多いので、名前を明らかにする。
下読みの段階で、評論家に見つけてほしがる。編集部が。
たいていみんな掛け持ちでやっているから、
情報は自ずと伝わるし、わかっちゃう。
僕の場合、N賞とサントリーミステリー大賞と
江戸川乱歩賞の選考(予選委員です。下読みではなく)を
やっていた時期が重なるが、いやあ、けっこう多いよ。
N賞で読んだものがサンミスにきて、
サンミスで落ちたものが、江戸川乱歩賞。
いや逆か。江戸川乱歩賞でおちたものが、サンミスだね。
サンミスは、他の賞の落ちたものの吹き溜まりだった(笑)。
下読み(予選委員)に評論家が選ばれるのは
(重宝されるのは)、実はそういう情報に詳しいからでもある。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●コピーでの応募は不可
> 原稿用紙のコピーを取ったものでの応募は不可です。
> 多重投稿などの疑いをかけられます。
> 必ず手書きした本物の原稿を送ってください。
基本的にそうなんだが、僕はコピーで読みたいと思っているほう。
手書き=手垢のついた原稿は、ちょっとイヤだ。
実際、コピーも多いですよ。これは人(賞)それぞれですね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●ヘッダーやフッターの使用は不可
> ワープロのヘッダー&フッター機能を使って、
> 余白にいろいろなことを印字する人がいるのですが、
> これはやめてください。特に本編の原稿の余白に作者の名前が
> 印字されていたりすると「名前入りの原稿用紙」と
> 同じ状態になって致命的です。
“致命的”という根拠がわからない。さきほども書いたように
名前はわかったほうがいい場合がある。
これも無視していい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> ●感熱紙の使用は不可
> 感熱紙は応募後の保存状態により、
> 用紙が変色したり印字が褪色するなどして、
> 原稿が読めなくなってしまうことがあります。
> また、変質した感熱紙には独特の匂いと手触りが発生して、
> これを嫌う選考委員もいます。
感熱紙の使用は避けたほうがいいが、
でも、実際問題としてけっこう多いですよ。
変にかすれた印字よりも、印字が鮮やかな
感熱紙のほうがいい場合もある。
ただし光の反射がきついので、逆に嫌がる人も多い。
それにしても、おかしいのは、
> また、変質した感熱紙には独特の匂いと手触りが発生して、
> これを嫌う選考委員もいます。
というくだり。
普通ね、選考委員の先生がたにはコピーをお送りしますよ。
予選委員だってコピーで読むんですから。きれいで汚れのない
コピーした原稿をね。生原稿をたらいまわしで読んでいたら
時間がかかってしょうがない。
それなのに、「下読みの鉄人」がかかわる(?)賞では、
応募者が送ってよこした感熱紙の原稿を
選考委員の先生がたが、そのまま読むんですね。
コピーする金がないのでしょうか。
いくらなんでも、下読みと編集者が読んだあとの
手垢のついたものを選考委員に読ませるなんて・・・。
そんなの大手では絶対にない。僕はきいたことがない。
いったいコピーする金もない出版社ってどこよ(笑)。
なんという賞? なんか知りたくなるね(笑)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> よけいな文章を書くと自滅する
> 応募規定に指示がない限り「まえがき」や「あとがき」などを
> 付けていはいけません。「献辞」や「謝辞」なども同様です。
> これらはプロが自分の本を出す時に書くべきものであって、
> 素人が新人賞の応募原稿に書くようなものではありません。
> まえがきが付いていたから自動的に落選にされる
> というわけではないのですが、審査を行なう上での
> マイナスの判断材料に使われる可能性が高い
> ということは知っておいてください。
そうかなあ。僕は別にいいと思うけどなあ。
愛すべき稚気として、僕なんか歓迎しますけどね。
ほとんど笑ってしまうことも多いんですが、
選考の息抜きになって、僕なんか歓迎するけど。
短期間に集中して何十本も読んでいると、しかも
けっこう愛想のない原稿が続くと疲れるのよ。好きでもね。
そういうときに、そういう稚気に出会うと、もう嬉しくなる(笑)。
“こいつ何考えてんだろう?”とニヤニヤしながら、
読んじゃうね。息抜きになって楽しくなる(笑)。
これは下読みの楽しみのひとつでもあるんだけどなあ。
「下読みの鉄人」さんは真面目だなあ。
> 特に、こんなことが書かれていると確実に不利、
>
> ●自分で解説を書いている
> 自分の作品がいかに素晴らしいものであるかを延々と
> 解説した文章を自分で付けているというものです。
いますね。そういう人たちが。
“世紀の傑作”であるとか、“名作だと思っています”とか、
堂々と書くんですよ。あるいは略歴のところでは、
“著書多数。ただしまだ1冊も出版されていません”とかね(笑)。
笑わせてくれるんです。ほとんど駄目ですが。
でも、解説つけても(余計なことを書いても)、僕はいいと思いますよ。
解説をつける人間の99パーセントは自信過剰タイプで、
実力の伴っていない人間ですが、でも、ときどき、感心するくらいに
冷静に解説をほどこす人間もいて(理科系に多い)、
“ふむふむ、なるほど。なかなか面白そうじゃないか・・”
なんて、期待をかきたてられてしまう場合もある。
いちがいにはいえない。“不利”とはね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> 最終選考で落ちても、落胆する必要はありません。
> 最終選考まで残れば、実は、入選と落選の間には、
> それほど大きな差はないからです。かなり運の要素が強く
> 「選考委員が変われば入選作品と落選作品が入れ替わっても
> 不思議ではない」というケースも珍しくありません。
まあ、それはいえるでしょう。
ただ、万年最終候補作家というのも存在する。
よくできました、というタイプの個性のない作品ね。
2時間サスペンスの中身のある原作という感じ。
> 最終選考に残ったということは、編集部の中に、
> あなたの作品を非常に高く評価してくれた人物がいるということです。
> あなたの作品が入選することを期待してくれていた人物が
> いるということです。その人物とコンタクトを取り、指導を受けましょう。
最終候補作=編集部が選んだ作品、というふうに考えていますね。
最初に書いたように、それは違うって。
予選委員(評論家)の場合もある。
編集者なのか、評論家なのかをみきわめること。
“その人物とコンタクトを取り、指導を受けましょう”と簡単に書くが、
編集者の中には、“最終候補に残ったぐらいで
コンタクトをとらないでほしい”と考える輩もたくさんいます。
一回や二回、まぐれで最終候補になることもあるんです(笑)。
賞をとったからといって次々にいいものが書ける訳でもない、
ということも、編集者たちは経験で、とことん知っています。
だから一回ぐらい、最終候補になったからといって、
舞い上がって(「下読みの鉄人」の話をうのみにして)、
編集部に電話して、指導をよろしく! なんてことはしないように。
変に思われるからね。この人、ちょっと精神的におかしいかもと。
ほんとうに編集者が気に入ったなら、電話をかけますよ。
その人にね。一度会いませんか、と。
そういうことはよくあります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|
|
|
|
コメント(5)
原稿を綴じることについて。
個人的には、ダブルクリップで綴じていただくのが一番いいですね。なんで応募要項に「ダブルクリップで綴じること」と明記してくれないのか、と思います。
回し読みや最終選考に残った場合はコピーをとるのだから、編集者だってその方が楽だろうに。
わたしはあんまり厚い場合は、綴じ紐を切って、ダブルクリップで小分けにして読みます。
字組について
40字*40行だったら文句は言えませんが、個人的には35字*35行くらいで行間に余裕がある方がいいなあ。
いまは横溝正史ミステリー大賞やこのミス大賞が、たしかデジタルデータ応募が可になっています。それで編集者が読みやすい字組やフォントで印刷してくれた方が嬉しいですね。
中にはこんな印字で、君は読み返してみたのかよ! と怒りにかられるようなひどい原稿がありますから。
個人的には、ダブルクリップで綴じていただくのが一番いいですね。なんで応募要項に「ダブルクリップで綴じること」と明記してくれないのか、と思います。
回し読みや最終選考に残った場合はコピーをとるのだから、編集者だってその方が楽だろうに。
わたしはあんまり厚い場合は、綴じ紐を切って、ダブルクリップで小分けにして読みます。
字組について
40字*40行だったら文句は言えませんが、個人的には35字*35行くらいで行間に余裕がある方がいいなあ。
いまは横溝正史ミステリー大賞やこのミス大賞が、たしかデジタルデータ応募が可になっています。それで編集者が読みやすい字組やフォントで印刷してくれた方が嬉しいですね。
中にはこんな印字で、君は読み返してみたのかよ! と怒りにかられるようなひどい原稿がありますから。
そうだよね。shintaさんは感熱紙、駄目だったよね(笑)。たしかに目にチカチカするといって嫌がる人も多いかな。ただ僕は汚い原稿よりも(手垢にまみれた原稿が多いんですよ)感熱紙なら、まだまし・・というところかな。
> 中にはこんな印字で、君は読み返してみたのかよ! と怒りにかられるようなひどい原稿がありますから。
というのは、たぶん字間の空きすぎの原稿ですね。字と字の空きすぎは要注意ですね。縦書きなのか、横書きなのかわからないくらいに字の間があいていると、見た瞬間にいやになる。縦に読んでいいのか、横に読んでいいのかわからなくなるし、わかってからも、もう読むのが面倒で面倒で(笑)。見づらい印字の原稿は基本的にまだ書き慣れていない人の原稿なので、二次以降にあがってくることはほとんど(いや、まったく)ないので、脱力して読みますね。
> 中にはこんな印字で、君は読み返してみたのかよ! と怒りにかられるようなひどい原稿がありますから。
というのは、たぶん字間の空きすぎの原稿ですね。字と字の空きすぎは要注意ですね。縦書きなのか、横書きなのかわからないくらいに字の間があいていると、見た瞬間にいやになる。縦に読んでいいのか、横に読んでいいのかわからなくなるし、わかってからも、もう読むのが面倒で面倒で(笑)。見づらい印字の原稿は基本的にまだ書き慣れていない人の原稿なので、二次以降にあがってくることはほとんど(いや、まったく)ないので、脱力して読みますね。
イケガミさんの日記に付けたコメントを転載するようご指示があったので――。
======================
私の場合、
> ●落選歴は書くな
入選・落選の経歴は無視することが多いです。結局、その応募原稿を書いたときのポテンシャルの問題なので、以前に最終選考レベルの作品を書いた人でも今回は、ということはありますから。その逆もまた。
●同人誌歴は書くな
同人誌歴は書いてもいいんじゃないでしょうか。同人誌で悪なれしているような原稿が来ることがありますが、同人誌歴が書いてなくてもそれはわかるし。デメリットは無いように思います。
●原稿は必ず綴じる
イケガミさんのおっしゃるとおり右肩一箇所綴じが正しいと思います。二箇所綴じられてしまうと、100ページめあたりから、紙を常に押さえながら読まなければならなくなってしまい、面倒くさいです。一箇所で、できればクリップ留めを希望いたします。私は外して読みます。
●封筒の宛名には必ず「御中」を付ける
「御中」の有無を採点する賞なんて聞いたことがないです!
就職面接の応募書類と間違えているんじゃないでしょうか。人事担当者はたしかにこれ、チェックします。
●名前入りの原稿用紙・コピー・ヘッダー・フッター入り原稿は不可
まったく気にしません。でもできたら原稿用紙応募は勘弁していただきたいです(枚数がかさむから)。
●感熱紙の使用は不可
プリントアウトしてから経年劣化で全体が黒っぽくなっている用紙以外はまったく問題ないです。イケガミさんのおっしゃるとおり、ドットプリンターなどでかすれた印刷よりはいいですね。
●よけいな文章を書くと自滅する
たしかに息抜きになりますね。でも、「この作品は即ドラマ化が可能なマルチメディア要素がある」とか「近年の時流を的確にとらえ、時評としても成立している」とか、自作を評論めいた言葉で誇るのは勘弁してもらいたいです。なんだか切ない気持ちになりますよ(特に小説がつまらない場合)。
●最終選考に残ったということは、編集部の中に、あなたの作品を非常に高く評価してくれた人物がいるということです。
うひゃあ。
これは正直本当に勘弁してもらいたいです。「このミス」大賞などで予選委員をやっていることを明かしているため、選考後にアドバイスがほしいとか、売り込み先を紹介してほしいとか、メールをいただくことが多いのです。私の何倍かの量を編集者はもらっているはず。それらにいちいち対応できるほど余裕のある編集者はいないでしょう。
======================
私の場合、
> ●落選歴は書くな
入選・落選の経歴は無視することが多いです。結局、その応募原稿を書いたときのポテンシャルの問題なので、以前に最終選考レベルの作品を書いた人でも今回は、ということはありますから。その逆もまた。
●同人誌歴は書くな
同人誌歴は書いてもいいんじゃないでしょうか。同人誌で悪なれしているような原稿が来ることがありますが、同人誌歴が書いてなくてもそれはわかるし。デメリットは無いように思います。
●原稿は必ず綴じる
イケガミさんのおっしゃるとおり右肩一箇所綴じが正しいと思います。二箇所綴じられてしまうと、100ページめあたりから、紙を常に押さえながら読まなければならなくなってしまい、面倒くさいです。一箇所で、できればクリップ留めを希望いたします。私は外して読みます。
●封筒の宛名には必ず「御中」を付ける
「御中」の有無を採点する賞なんて聞いたことがないです!
就職面接の応募書類と間違えているんじゃないでしょうか。人事担当者はたしかにこれ、チェックします。
●名前入りの原稿用紙・コピー・ヘッダー・フッター入り原稿は不可
まったく気にしません。でもできたら原稿用紙応募は勘弁していただきたいです(枚数がかさむから)。
●感熱紙の使用は不可
プリントアウトしてから経年劣化で全体が黒っぽくなっている用紙以外はまったく問題ないです。イケガミさんのおっしゃるとおり、ドットプリンターなどでかすれた印刷よりはいいですね。
●よけいな文章を書くと自滅する
たしかに息抜きになりますね。でも、「この作品は即ドラマ化が可能なマルチメディア要素がある」とか「近年の時流を的確にとらえ、時評としても成立している」とか、自作を評論めいた言葉で誇るのは勘弁してもらいたいです。なんだか切ない気持ちになりますよ(特に小説がつまらない場合)。
●最終選考に残ったということは、編集部の中に、あなたの作品を非常に高く評価してくれた人物がいるということです。
うひゃあ。
これは正直本当に勘弁してもらいたいです。「このミス」大賞などで予選委員をやっていることを明かしているため、選考後にアドバイスがほしいとか、売り込み先を紹介してほしいとか、メールをいただくことが多いのです。私の何倍かの量を編集者はもらっているはず。それらにいちいち対応できるほど余裕のある編集者はいないでしょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
小説家・ライターになろう講座 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
小説家・ライターになろう講座のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170659人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89523人