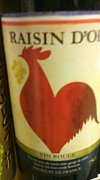1.病気発覚
「飯田さん、診察に来られるとき、いつもお酒の匂いさせているんですが、どれくらい飲まれているんですか?」
午前中の仕事を半休して、何度か通った横浜の大学病院の精神科を受診した時、主治医は憐みのこもった眼をしてそうつぶやいた。精神科の受診はいつも午前中だったので、当然昨夜のアルコールも残っている。その上、その頃には朝から飲む習慣も出来ていた。当然、酒臭い息を撒き散らしての受診である。酒臭い息をしていることは気にならないと言えば嘘になるが、全身が脱力感でいっぱいで、もうどうにでもしてくれと半ば投げやりになっていた。
「はい、毎晩焼酎1Lと、最近は朝から飲むようになってます。」
ごまかしても医者は騙されないだろうと観念して正直に打ち明けた。その女性主治医は何やら気の毒そうに次の言葉を発した。
「それはですね、アルコール依存症です。立派な病気ですよ。昔はアル中って言ってました。治療が必要です。」
初めてアルコール依存症と宣告されても、なぜかピンとこなかった。むしろある種の勲章をもらった気分だった。文学の世界ではポー、フィッツジェラルド、ヘミングウェイ、スタインベックは立派なアルコール依存症者である。日本人としては石原裕次郎、美空ひばり、そして私の大好きな作家、中島らも氏も立派なアル中だ。私はその時、彼らの仲間入りができたと思って内心嬉しかった。しかし、次の言葉は衝撃だった。
「アルコール依存症の治療はアルコールを断たないといけません。」
いわゆる断酒というやつである。もう酒が飲めないのか・・・そう言うと、その主治医は奥の部屋から何枚かのプリントを持ってきて、私に手渡した。断酒会やAAの案内である。当時はそれが何なのかさっぱりわからなかった。
「いちど参加されてみたらどうですか?」
その時は参加してどうなるものでもでもないだろうと思って聞き流した。もちろん参加の意思はない。参加しても断酒するつもりはなかった。酒の飲みすぎて死んでも後悔なない。かつてジークムント・フロイトはタナトスを攻撃や自己破壊に傾向する死の欲動を意味する用語として採用したが、私はタナトスの傾向が強かったようだ。
事の発端は、数週間前、出勤前に歯磨きをしていたときに急に吐き気がして、少量ながらも吐血したことである。その時は上司に事情を話して早退させてもらったが、それ以前にも吐き気や、異常な発汗、手の震え、下痢の症状はあったものの、アルコールさえ飲めば解決していた。いわば、私にとってアルコールはガソリンみたいなものだったのである。しかし今や並大抵の酒量では解決できなくなっていた。会社に酒を持っていってトイレで飲んだこともある。
ところが、ある朝、起床してみると、全身が震えて体が思うように動かなかった。何度も嘔吐を繰り返し、必死の思いで床をはいずるようにして実家に電話をかけたのだが、通じない。仕方がなく結婚している姉に電話をかけて事情を説明し、会社に連絡を入れてもらった。しばらくして社長と奥さんが到着し、救急車を呼んでくれて、病院に運ばれた。救急車に乗ったのはこれが初めてである。
ところが病院について様々な検査をした結果は何の異状もないと言う。結局栄養剤の点滴一本で帰されてしまった。しかし、社長の奥さんだけは私の不調に気付いており、総合病院で精密検査を受けるように勧めてくれた。それが冒頭の大学病院である。
後日、会社を早退させてもらって病院へ向かう。今まで大病の経験のない私は多少緊張していた。病院はさすが大学病院だけあってさまざまな科が分かれており、ひとまず内科の受診を申し込んだ。初診の医者は私の仕事ぶりと、胃が痛いという言葉から、
「ストレスと過労からくる胃の痛みは胃潰瘍かもしれないな。」
そう言うと次々に一通りの精密検査の日程を決めていった。
検査は採尿採血、レントゲンに始まって、心電図、超音波、CT、内視鏡と続いた。しかしながら、特に異常は見られず、唯一、内視鏡で食道と胃を見たときに多少の傷があっただけだった。そうしてまず内科の受診が始まった。消化器内科にしばらく通って胃薬を処方されて飲んでいたのだが、しばらくすると自宅で飲酒していると体の震えと嘔吐が止まらす、駅前からタクシーでその大学病院に行って救急で診察してもらい、点滴を2本打った。その時、体が小刻みに震えていたので、当直の医者から心療内科の受診を勧められた。しかしながら心療内科で血液検査をしても異状は見られず、デパスを服用していたのだが体の不調が治らなかったので最終的に精神科に回されることになったのである。
「飯田さん、診察に来られるとき、いつもお酒の匂いさせているんですが、どれくらい飲まれているんですか?」
午前中の仕事を半休して、何度か通った横浜の大学病院の精神科を受診した時、主治医は憐みのこもった眼をしてそうつぶやいた。精神科の受診はいつも午前中だったので、当然昨夜のアルコールも残っている。その上、その頃には朝から飲む習慣も出来ていた。当然、酒臭い息を撒き散らしての受診である。酒臭い息をしていることは気にならないと言えば嘘になるが、全身が脱力感でいっぱいで、もうどうにでもしてくれと半ば投げやりになっていた。
「はい、毎晩焼酎1Lと、最近は朝から飲むようになってます。」
ごまかしても医者は騙されないだろうと観念して正直に打ち明けた。その女性主治医は何やら気の毒そうに次の言葉を発した。
「それはですね、アルコール依存症です。立派な病気ですよ。昔はアル中って言ってました。治療が必要です。」
初めてアルコール依存症と宣告されても、なぜかピンとこなかった。むしろある種の勲章をもらった気分だった。文学の世界ではポー、フィッツジェラルド、ヘミングウェイ、スタインベックは立派なアルコール依存症者である。日本人としては石原裕次郎、美空ひばり、そして私の大好きな作家、中島らも氏も立派なアル中だ。私はその時、彼らの仲間入りができたと思って内心嬉しかった。しかし、次の言葉は衝撃だった。
「アルコール依存症の治療はアルコールを断たないといけません。」
いわゆる断酒というやつである。もう酒が飲めないのか・・・そう言うと、その主治医は奥の部屋から何枚かのプリントを持ってきて、私に手渡した。断酒会やAAの案内である。当時はそれが何なのかさっぱりわからなかった。
「いちど参加されてみたらどうですか?」
その時は参加してどうなるものでもでもないだろうと思って聞き流した。もちろん参加の意思はない。参加しても断酒するつもりはなかった。酒の飲みすぎて死んでも後悔なない。かつてジークムント・フロイトはタナトスを攻撃や自己破壊に傾向する死の欲動を意味する用語として採用したが、私はタナトスの傾向が強かったようだ。
事の発端は、数週間前、出勤前に歯磨きをしていたときに急に吐き気がして、少量ながらも吐血したことである。その時は上司に事情を話して早退させてもらったが、それ以前にも吐き気や、異常な発汗、手の震え、下痢の症状はあったものの、アルコールさえ飲めば解決していた。いわば、私にとってアルコールはガソリンみたいなものだったのである。しかし今や並大抵の酒量では解決できなくなっていた。会社に酒を持っていってトイレで飲んだこともある。
ところが、ある朝、起床してみると、全身が震えて体が思うように動かなかった。何度も嘔吐を繰り返し、必死の思いで床をはいずるようにして実家に電話をかけたのだが、通じない。仕方がなく結婚している姉に電話をかけて事情を説明し、会社に連絡を入れてもらった。しばらくして社長と奥さんが到着し、救急車を呼んでくれて、病院に運ばれた。救急車に乗ったのはこれが初めてである。
ところが病院について様々な検査をした結果は何の異状もないと言う。結局栄養剤の点滴一本で帰されてしまった。しかし、社長の奥さんだけは私の不調に気付いており、総合病院で精密検査を受けるように勧めてくれた。それが冒頭の大学病院である。
後日、会社を早退させてもらって病院へ向かう。今まで大病の経験のない私は多少緊張していた。病院はさすが大学病院だけあってさまざまな科が分かれており、ひとまず内科の受診を申し込んだ。初診の医者は私の仕事ぶりと、胃が痛いという言葉から、
「ストレスと過労からくる胃の痛みは胃潰瘍かもしれないな。」
そう言うと次々に一通りの精密検査の日程を決めていった。
検査は採尿採血、レントゲンに始まって、心電図、超音波、CT、内視鏡と続いた。しかしながら、特に異常は見られず、唯一、内視鏡で食道と胃を見たときに多少の傷があっただけだった。そうしてまず内科の受診が始まった。消化器内科にしばらく通って胃薬を処方されて飲んでいたのだが、しばらくすると自宅で飲酒していると体の震えと嘔吐が止まらす、駅前からタクシーでその大学病院に行って救急で診察してもらい、点滴を2本打った。その時、体が小刻みに震えていたので、当直の医者から心療内科の受診を勧められた。しかしながら心療内科で血液検査をしても異状は見られず、デパスを服用していたのだが体の不調が治らなかったので最終的に精神科に回されることになったのである。
|
|
|
|
コメント(40)
2.幼少時代
私は昭和43年。大阪の下町である東大阪の長瀬で生まれた。しかしながら生まれてすぐに大阪郊外の大東市の野崎に移り住んだので、長瀬時代の思い出は全くない。いまは唯一先祖代々の墓地があるだけである。
野崎という町は、大阪府内の外郭部を通り、大阪郊外の主要都市を結ぶ骨格的な環状道路軸である大阪外環状線が走り、典型的な郊外の殺伐とした景観が広がっている。寂れた工場や中古車販売所、ガソリンスタンドやトラックターミナルが連なっていた。しかし、背後には生駒山系の山が連なっており、野崎観音(のざきかんのん)として知られる福聚山慈眼寺があって緑も多く、小学生時代にはそこで良く遊んだものである。そうした殺伐さと山に築かれた寺院が後々まで私の原風景になっている。
当時の私は、近所の友達と遊ぶよりは一人で遊ぶことが多かったように思う。そのころ住んでいた家には適当な庭があり、そこに土で城郭を作って一人だけのファンタジーに浸っていた。また、世界の偉人伝を読むのが好きで学校が終わると自宅に閉じこもっていた。どこか人との付き合いを避けていたところがあったのだろう。振り返ってみると、幼少時代から私は現実世界から逃避して、自分ひとりの世界に引き籠りがちで、人づきあいが苦手だった。それは今も変わらない。
初めてアルコールを口にしたのは、はっきりと覚えていないが、4歳か5歳の時だったように思う。父の会社の同僚や友人たちが実家に遊びに来たおりなどに彼らが飲んでいたビールを悪戯心で飲んでは酔っ払い、庭を走りまわっていたと後日両親から聞かされた。
その時、どんな感じがしたのかは覚えてないが、酒の味よりもむしろアルコールがもたらす「酔い」や「酩酊」に気持ちよさを感じていたと思われる。つまり私にとってのアルコールは、飲んだ時から味や香りを楽しむ嗜好品としての「酒」ではなく、現実から逃避させてくれるドラッグとしての「アルコール」だった。
私は昭和43年。大阪の下町である東大阪の長瀬で生まれた。しかしながら生まれてすぐに大阪郊外の大東市の野崎に移り住んだので、長瀬時代の思い出は全くない。いまは唯一先祖代々の墓地があるだけである。
野崎という町は、大阪府内の外郭部を通り、大阪郊外の主要都市を結ぶ骨格的な環状道路軸である大阪外環状線が走り、典型的な郊外の殺伐とした景観が広がっている。寂れた工場や中古車販売所、ガソリンスタンドやトラックターミナルが連なっていた。しかし、背後には生駒山系の山が連なっており、野崎観音(のざきかんのん)として知られる福聚山慈眼寺があって緑も多く、小学生時代にはそこで良く遊んだものである。そうした殺伐さと山に築かれた寺院が後々まで私の原風景になっている。
当時の私は、近所の友達と遊ぶよりは一人で遊ぶことが多かったように思う。そのころ住んでいた家には適当な庭があり、そこに土で城郭を作って一人だけのファンタジーに浸っていた。また、世界の偉人伝を読むのが好きで学校が終わると自宅に閉じこもっていた。どこか人との付き合いを避けていたところがあったのだろう。振り返ってみると、幼少時代から私は現実世界から逃避して、自分ひとりの世界に引き籠りがちで、人づきあいが苦手だった。それは今も変わらない。
初めてアルコールを口にしたのは、はっきりと覚えていないが、4歳か5歳の時だったように思う。父の会社の同僚や友人たちが実家に遊びに来たおりなどに彼らが飲んでいたビールを悪戯心で飲んでは酔っ払い、庭を走りまわっていたと後日両親から聞かされた。
その時、どんな感じがしたのかは覚えてないが、酒の味よりもむしろアルコールがもたらす「酔い」や「酩酊」に気持ちよさを感じていたと思われる。つまり私にとってのアルコールは、飲んだ時から味や香りを楽しむ嗜好品としての「酒」ではなく、現実から逃避させてくれるドラッグとしての「アルコール」だった。
こんなにある 依存性薬物の種類
アルコール
ビール、ワイン、ウイスキー、日本酒、焼酎、リキュールなどは、いずれも「エチル・アルコール」が主成分。合法的に市販されているが、れっきとした依存性薬物だ。なお、未成年の飲酒は成長期の心身に大きなダメージを与えるため「未成年者飲酒禁止法」で禁じられている。作用はヘロインなどのモルヒネ型薬物に似て、身体依存性が高く、離脱症状は激しい。
臓器への急性・慢性毒性があり、急性アルコール中毒で死に至ることも。慢性毒性としては、肝臓病や脳の萎縮をはじめ、すい炎や糖尿病、骨粗しょう症、さらに上部消化器ガン(食道ガンなど)のリスクも高まる。多量 の飲酒によって、からだは病気の見本市のようになる。
未成年者にとっては、違法薬物へと移行するきっかけになる入り口のドラッグでもある。また、違法薬物を転々と使用した後に再びアルコールへ戻るという最終のドラッグにもなっており、深刻な複合依存を招いている。
http://www.ask.or.jp/yakubutsusort2.html#1
アルコール
ビール、ワイン、ウイスキー、日本酒、焼酎、リキュールなどは、いずれも「エチル・アルコール」が主成分。合法的に市販されているが、れっきとした依存性薬物だ。なお、未成年の飲酒は成長期の心身に大きなダメージを与えるため「未成年者飲酒禁止法」で禁じられている。作用はヘロインなどのモルヒネ型薬物に似て、身体依存性が高く、離脱症状は激しい。
臓器への急性・慢性毒性があり、急性アルコール中毒で死に至ることも。慢性毒性としては、肝臓病や脳の萎縮をはじめ、すい炎や糖尿病、骨粗しょう症、さらに上部消化器ガン(食道ガンなど)のリスクも高まる。多量 の飲酒によって、からだは病気の見本市のようになる。
未成年者にとっては、違法薬物へと移行するきっかけになる入り口のドラッグでもある。また、違法薬物を転々と使用した後に再びアルコールへ戻るという最終のドラッグにもなっており、深刻な複合依存を招いている。
http://www.ask.or.jp/yakubutsusort2.html#1
3.少年時代
小学校5年生の12月、奈良の生駒に移り住み、中学卒業まで両親とともにそこで過ごした。当時の実家周辺は、急速に大阪のベッドタウンとして開発された住宅地である。しかも市民の70%が大阪に通勤通学に行くので地域のコミュニティーは希薄であった。大阪外環状線沿線とは趣が違うが、やはりここも郊外だ。大都市の郊外で生まれ育ったのがその後のアルコール依存症になる萌芽とは必ずしも言えないが、私の人格形成には大きく影響している確かなようだ。
奈良に移住し、中学生になった頃から私は両親から干渉されることに事あるごとに反発し、次第に両親との間に不協和音が響き始めるようになった。それが直接的な原因かどうかは分からないが、親の目を盗んでタバコを吸い、アルコールを飲むようになっていた。それについての罪悪感は全くない。
例えば夏に学校に凍らせたお茶を持っていくのが生徒たちの間に流行った。普通なら麦茶や緑茶を凍らせて持っていくのだが、私はウイスキーの麦茶割を持って行って、それを飲みながら酔っ払って授業を受けていた。しかしながら、当時の私はアルコールが美味いとはとても言えなかった。それゆえ喫煙や飲酒は真面目な生徒であることを期待していた両親や教師たちへの反抗以外の何物でもなかったのである。
中学3年生の頃になると、両親と一緒に暮らすことが苦痛になり、同級生たちが地元の奈良や大阪、京都の高校に進学するのを横目に、人と同じ事をするのに納得のいかなかった私は、ふと、書店で見かけた全国版の高校案内を購入し、どれどれとパラパラ学校選びをはじめた。私立校ばかりだったが、北は北海道から、南は九州までの学校がずらりと並んでいた。以前にも、中学2年の時の面談でアメリカのハイスクールに行きたいと言い放ったこともあるのだが、さすがにこれは直ちに却下された。それではと、国内でもいいから遠くの学校に進みたい。当時、頭にあったのは、どうしても家から出たい、家族から離れたい。それが動機だった。反抗期の真最中。このまま両親と同居し続けるといつの日か、彼らを殺してしまうかもしれない。かなり危機的な状況にはあった。
しかし、両親を説得させるにはそれなりのネームバリューのある学校で、生活するために寮が完備されていて、なおかつ自分の偏差値で確実に合格できる学校を選んでそこに入学しなければならない。全国くまなく探して、これならと見つけたのが、函館のカトリック系の男子校、函館○○○○。 同系列の学校は鹿児島にもあるが、ここは到底無理。でも、函館ならなんとかなる。そう思うと、その学校に行きたくて仕方がなくなった。「北国」という言葉の響きにも惹かれた。親には内密で学校案内を取り寄せ、願書を出した。そして悲願は実ることができた。
小学校5年生の12月、奈良の生駒に移り住み、中学卒業まで両親とともにそこで過ごした。当時の実家周辺は、急速に大阪のベッドタウンとして開発された住宅地である。しかも市民の70%が大阪に通勤通学に行くので地域のコミュニティーは希薄であった。大阪外環状線沿線とは趣が違うが、やはりここも郊外だ。大都市の郊外で生まれ育ったのがその後のアルコール依存症になる萌芽とは必ずしも言えないが、私の人格形成には大きく影響している確かなようだ。
奈良に移住し、中学生になった頃から私は両親から干渉されることに事あるごとに反発し、次第に両親との間に不協和音が響き始めるようになった。それが直接的な原因かどうかは分からないが、親の目を盗んでタバコを吸い、アルコールを飲むようになっていた。それについての罪悪感は全くない。
例えば夏に学校に凍らせたお茶を持っていくのが生徒たちの間に流行った。普通なら麦茶や緑茶を凍らせて持っていくのだが、私はウイスキーの麦茶割を持って行って、それを飲みながら酔っ払って授業を受けていた。しかしながら、当時の私はアルコールが美味いとはとても言えなかった。それゆえ喫煙や飲酒は真面目な生徒であることを期待していた両親や教師たちへの反抗以外の何物でもなかったのである。
中学3年生の頃になると、両親と一緒に暮らすことが苦痛になり、同級生たちが地元の奈良や大阪、京都の高校に進学するのを横目に、人と同じ事をするのに納得のいかなかった私は、ふと、書店で見かけた全国版の高校案内を購入し、どれどれとパラパラ学校選びをはじめた。私立校ばかりだったが、北は北海道から、南は九州までの学校がずらりと並んでいた。以前にも、中学2年の時の面談でアメリカのハイスクールに行きたいと言い放ったこともあるのだが、さすがにこれは直ちに却下された。それではと、国内でもいいから遠くの学校に進みたい。当時、頭にあったのは、どうしても家から出たい、家族から離れたい。それが動機だった。反抗期の真最中。このまま両親と同居し続けるといつの日か、彼らを殺してしまうかもしれない。かなり危機的な状況にはあった。
しかし、両親を説得させるにはそれなりのネームバリューのある学校で、生活するために寮が完備されていて、なおかつ自分の偏差値で確実に合格できる学校を選んでそこに入学しなければならない。全国くまなく探して、これならと見つけたのが、函館のカトリック系の男子校、函館○○○○。 同系列の学校は鹿児島にもあるが、ここは到底無理。でも、函館ならなんとかなる。そう思うと、その学校に行きたくて仕方がなくなった。「北国」という言葉の響きにも惹かれた。親には内密で学校案内を取り寄せ、願書を出した。そして悲願は実ることができた。
4.高校時代
高校時代は監視の目が厳しい寮生活を送っていたためにアルコールを頻繁に飲む機会はなかった。それでも同級生たちは焼酎を飲んでは瓶を寮のロッカーに隠し、後に見つかって大量処分となったりしていたので飲んでいたのだろう。しかし、私はその輪には参加しなかった。群れるのが嫌いだったからである。飲むなら一人で飲みたい。
寮には食堂があって基本的にはそこで食事をするのだが、時々それに飽きた時などは級友と街へ出かけて外食することがあり、その時はいつもワインを飲んでいた。酒と言えば当時はワインである。それは当時読んでいた小説の影響かもしれない。高校時代は学校の勉強はしなかったが、本だけは大量に読んだ。しかし、相手はワインである。しかも、当時の酒量はわずかなもので、グラスに2,3杯程度で、酔っ払って寮に帰ってくることはなかった。単純に大人の真似がしたかったのだ。
生まれて初めて自分の意志で酔っ払ったのは、高校2年生の時のクラス旅行の時である。当時はまだ青函連絡船が走っており、クラスメート全員と担任が函館から青森の八甲田へ行った。そこで宿泊した旅館で引率の教師の目を盗んで悪友たちと酒盛りをしたのだが、飲みすぎで気分が悪くなり、浴室で嘔吐した。それにもかかわらず、まだ飲み足りない気がして自動販売機で日本酒を購入し、取りつかれるように飲んだ。初めはちょっとだけなら大丈夫と思っていたのだが、いつの間にか限界量を超えていた。飲み方が異常で、徹底的に酔い潰れるまで飲まなければ気が済まなかったような気がする。一緒に飲んだ同級生たちは良い気分に酔っ払って早々に寝ていた。
この時点で、今にして思えば、私はアルコールに対してコントロールが効かなかったのである。しかし、それは即連続飲酒にはつながらなかった。まだ耐性が出来ていなかったこともある。これ以上飲めないという限界もあった。それ以上にアルコールにのめり込まなかったのは、アルコール以上に私を酔わせてくれるものがあったからである。それが音楽だった。
小さいときからピアノを習っていた姉がいたおかげで音楽に関しては早熟だったように思う。小学生時代も周りの生徒は、当時のアイドルに夢中だったが、私は姉が聴いていた洋楽のロックを同じように聴いていた。ベイシティーローラーズから始まり、KISS、クイーン、チープ・トリック等など。
そして中学校生時代には自分でセレクトしたディープパープルやレッド・ツェッペリン等のブリティッシュ・ハードロックが好きになった。母親の財布から1万円抜き出してレッド・ツェッペリンの海賊版ライブレコードを買ったこともある。当時はシンコーミュージックが出版していた「ミュージック・ライフ」という雑誌がバイブルだった。そしてそこで紹介されていたアーティストの中から自分なりのお気に入りの音楽を探していた。マーク・ボラン、T−REX・・・
しかし、後世に一番影響を与えたのは80年代のパンク&ニュー・ウェーヴとの出会いと、メジャーな音楽産業には属さない、独立性が高くアート志向なインディーズ・レーベルを知ったことである。特にスターリンとZELDAには大きな影響を受けた。そして高校時代になると1980年代のポップカルチャーで誌面が埋め尽くされた『月刊 宝島』やプログレッシブ・ロックやニュー・ウェーヴといった当時の先端的な音楽を中心とし、ウィリアム・バロウズなどのサブカルチャーまでを取り扱った『FOOL'S MATE』がバイブルとなり、ありったけのマイナーではあるが芸術性の高い音楽を追求していった。
もうひとつパンク&ニュー・ウェーヴがもたらしたものは、アーティストが等身大だったことである。セックス・ピストルズとシド・ヴィシャスの関係のように、バンドの追っかけがバンドのメインメンバーになれたのだ。お約束のように私は学校の落ちこぼれ仲間を集めて「造反有理」というパンクのコピーバンドを結成した。当時コピーしていたのは関西出身のハードコアパンクバンドの「ラフインノーズ」である。学校の授業が終わると我々は貸しスタジオに集まり、練習に明け暮れた。公開の場での演奏は3年生の時の学園祭での一曲だけだったが、私はそれに酔っていたのである。
高校時代は監視の目が厳しい寮生活を送っていたためにアルコールを頻繁に飲む機会はなかった。それでも同級生たちは焼酎を飲んでは瓶を寮のロッカーに隠し、後に見つかって大量処分となったりしていたので飲んでいたのだろう。しかし、私はその輪には参加しなかった。群れるのが嫌いだったからである。飲むなら一人で飲みたい。
寮には食堂があって基本的にはそこで食事をするのだが、時々それに飽きた時などは級友と街へ出かけて外食することがあり、その時はいつもワインを飲んでいた。酒と言えば当時はワインである。それは当時読んでいた小説の影響かもしれない。高校時代は学校の勉強はしなかったが、本だけは大量に読んだ。しかし、相手はワインである。しかも、当時の酒量はわずかなもので、グラスに2,3杯程度で、酔っ払って寮に帰ってくることはなかった。単純に大人の真似がしたかったのだ。
生まれて初めて自分の意志で酔っ払ったのは、高校2年生の時のクラス旅行の時である。当時はまだ青函連絡船が走っており、クラスメート全員と担任が函館から青森の八甲田へ行った。そこで宿泊した旅館で引率の教師の目を盗んで悪友たちと酒盛りをしたのだが、飲みすぎで気分が悪くなり、浴室で嘔吐した。それにもかかわらず、まだ飲み足りない気がして自動販売機で日本酒を購入し、取りつかれるように飲んだ。初めはちょっとだけなら大丈夫と思っていたのだが、いつの間にか限界量を超えていた。飲み方が異常で、徹底的に酔い潰れるまで飲まなければ気が済まなかったような気がする。一緒に飲んだ同級生たちは良い気分に酔っ払って早々に寝ていた。
この時点で、今にして思えば、私はアルコールに対してコントロールが効かなかったのである。しかし、それは即連続飲酒にはつながらなかった。まだ耐性が出来ていなかったこともある。これ以上飲めないという限界もあった。それ以上にアルコールにのめり込まなかったのは、アルコール以上に私を酔わせてくれるものがあったからである。それが音楽だった。
小さいときからピアノを習っていた姉がいたおかげで音楽に関しては早熟だったように思う。小学生時代も周りの生徒は、当時のアイドルに夢中だったが、私は姉が聴いていた洋楽のロックを同じように聴いていた。ベイシティーローラーズから始まり、KISS、クイーン、チープ・トリック等など。
そして中学校生時代には自分でセレクトしたディープパープルやレッド・ツェッペリン等のブリティッシュ・ハードロックが好きになった。母親の財布から1万円抜き出してレッド・ツェッペリンの海賊版ライブレコードを買ったこともある。当時はシンコーミュージックが出版していた「ミュージック・ライフ」という雑誌がバイブルだった。そしてそこで紹介されていたアーティストの中から自分なりのお気に入りの音楽を探していた。マーク・ボラン、T−REX・・・
しかし、後世に一番影響を与えたのは80年代のパンク&ニュー・ウェーヴとの出会いと、メジャーな音楽産業には属さない、独立性が高くアート志向なインディーズ・レーベルを知ったことである。特にスターリンとZELDAには大きな影響を受けた。そして高校時代になると1980年代のポップカルチャーで誌面が埋め尽くされた『月刊 宝島』やプログレッシブ・ロックやニュー・ウェーヴといった当時の先端的な音楽を中心とし、ウィリアム・バロウズなどのサブカルチャーまでを取り扱った『FOOL'S MATE』がバイブルとなり、ありったけのマイナーではあるが芸術性の高い音楽を追求していった。
もうひとつパンク&ニュー・ウェーヴがもたらしたものは、アーティストが等身大だったことである。セックス・ピストルズとシド・ヴィシャスの関係のように、バンドの追っかけがバンドのメインメンバーになれたのだ。お約束のように私は学校の落ちこぼれ仲間を集めて「造反有理」というパンクのコピーバンドを結成した。当時コピーしていたのは関西出身のハードコアパンクバンドの「ラフインノーズ」である。学校の授業が終わると我々は貸しスタジオに集まり、練習に明け暮れた。公開の場での演奏は3年生の時の学園祭での一曲だけだったが、私はそれに酔っていたのである。
5.浪人時代
高校卒業後、大学受験に失敗した春、中学時代の同窓会があった。高校は卒業したものの、まだ皆そろって未成年である。しかし、誰もそんな事は気にしていない。私も当然のように飲酒した。ほかの連中は会話を楽しみ、料理を食べながら飲んでいるが、私はというと料理にはほとんど手をつけず、ひたすら黙々とビールを胃の中に流し込んだ。その様子は高校時代のクラス旅行の時と変わらない。酔いが回ってくると飲酒のスピードも速まり、当然のように吐き気がしてくる。よく大学生が新歓コンパなどで急性アルコール中毒で病院へ運ばれるが、私はその一歩手前であった。何度もトイレに行って吐いてはまた飲む。同窓会後半はもうそれの繰り返しである。同級生たちの思い出話などもはや聞こえない。すでに強迫的飲酒状態で、飲酒という行動の中に完全に閉じこもっていた。
高校時代にはまだ校則や寮の規則がストッパーになっていたが、卒業と同時にそのタガが外れ、毎日飲むようになった。習慣飲酒が始まったのはこの頃からである。2年間の浪人時代、奈良の実家から大阪の予備校に通っていたが、授業にはたまにしか出席せず、毎日のように大阪や京都、神戸の街をアルコール片手に徘徊し、夜には決まって大阪の戎橋筋にある酒のディスカウントストアに寄っては酒を買って帰り、親の目が届かない自室にこもっては形だけ受験勉強の振りをしながら飲みながら小説を読み漁った。そしていつしか酔いつぶれては眠りこんでしまう毎日だった。
飲んでいたのは、初めの頃はワインが多かった。特に淡いマスカットに似た香りを持つ、フレッシュでフルーティーな辛口の白ワインの「ミュスカデ」がお気に入りだった。ワインを飲みながら文学に耽るというのは、どこかデカダンスでボードレール気取りである。当時好きだったのは、倉橋由美子の「シュンポシオン」だ。シュンポシオンとはギリシァ語である。古代ギリシァたちは床に寝そべり、酒を酌み交わしながら談笑を楽しんだ。その小説の中の登場人物たちもまた21世紀に入って10年がすぎた夏の日の避暑地=半島の海辺にある別荘に集う数組の男女の優雅な〈饗宴(シュンポシオン)〉を繰り広げる。いつかそんな生活ができたら・・・私の理想である。
しかし、そうやってワインを飲み続けるうちにワイン一本では酔えなくなってきた。酔えなくなるとアルコールではない。そうかと言ってワインを2本も3本も買って帰ると親にばれてしまう。それに空き瓶の処理も面倒だ。そして当然の帰着としてアルコール度数の高い酒を飲むようになった。
初めに好きになったのは1980年代末にリバイバルヒットになっていた明治時代に誕生した、ブランデーベースのカクテルの「電気ブラン」だった。明治の頃は、その度数は当時45度と高く、口の中がしびれる状態と、電気でしびれるイメージとが一致していたため、ハイカラな飲み物として人気を博したらしい。私は電気ブランの味そのものよりも、その「しびれる」という感覚が好きだった。
そうやってどんどんアルコール度数の強い酒を求めて、いつのまにかジンやウォッカを一晩で飲み明かすようになっていった。そして昼間もまたビールを飲む。10代にして連続飲酒の一歩手前まで来ていたような気がする。飲酒には特別な理由付けは必要ないかもしれない。尊敬する作家の中島らも氏はいみじくも飲酒の理由を「ただ気持ちがいいから」と断言した。それはその通りだろう。
しかし、言い訳になってしまうが、この当時、どうしてこんなにアルコールに取りつかれてしまったか考えてみると、高校3年生の頃から受験勉強というものに嫌悪感を抱きながらもそれをしなければならなかった自分の中での矛盾、そして浪人生という中途半端な立場から何とか逃げようとしていた現実逃避の道具としてアルコールを使っていたのだと思う。その証拠に、大学合格後はあれほどアルコールに呪縛されていた生活から解き放たれたように、強迫的に飲酒することはなくなった。だた、毎日飲む習慣は残ったが・・・。
高校卒業後、大学受験に失敗した春、中学時代の同窓会があった。高校は卒業したものの、まだ皆そろって未成年である。しかし、誰もそんな事は気にしていない。私も当然のように飲酒した。ほかの連中は会話を楽しみ、料理を食べながら飲んでいるが、私はというと料理にはほとんど手をつけず、ひたすら黙々とビールを胃の中に流し込んだ。その様子は高校時代のクラス旅行の時と変わらない。酔いが回ってくると飲酒のスピードも速まり、当然のように吐き気がしてくる。よく大学生が新歓コンパなどで急性アルコール中毒で病院へ運ばれるが、私はその一歩手前であった。何度もトイレに行って吐いてはまた飲む。同窓会後半はもうそれの繰り返しである。同級生たちの思い出話などもはや聞こえない。すでに強迫的飲酒状態で、飲酒という行動の中に完全に閉じこもっていた。
高校時代にはまだ校則や寮の規則がストッパーになっていたが、卒業と同時にそのタガが外れ、毎日飲むようになった。習慣飲酒が始まったのはこの頃からである。2年間の浪人時代、奈良の実家から大阪の予備校に通っていたが、授業にはたまにしか出席せず、毎日のように大阪や京都、神戸の街をアルコール片手に徘徊し、夜には決まって大阪の戎橋筋にある酒のディスカウントストアに寄っては酒を買って帰り、親の目が届かない自室にこもっては形だけ受験勉強の振りをしながら飲みながら小説を読み漁った。そしていつしか酔いつぶれては眠りこんでしまう毎日だった。
飲んでいたのは、初めの頃はワインが多かった。特に淡いマスカットに似た香りを持つ、フレッシュでフルーティーな辛口の白ワインの「ミュスカデ」がお気に入りだった。ワインを飲みながら文学に耽るというのは、どこかデカダンスでボードレール気取りである。当時好きだったのは、倉橋由美子の「シュンポシオン」だ。シュンポシオンとはギリシァ語である。古代ギリシァたちは床に寝そべり、酒を酌み交わしながら談笑を楽しんだ。その小説の中の登場人物たちもまた21世紀に入って10年がすぎた夏の日の避暑地=半島の海辺にある別荘に集う数組の男女の優雅な〈饗宴(シュンポシオン)〉を繰り広げる。いつかそんな生活ができたら・・・私の理想である。
しかし、そうやってワインを飲み続けるうちにワイン一本では酔えなくなってきた。酔えなくなるとアルコールではない。そうかと言ってワインを2本も3本も買って帰ると親にばれてしまう。それに空き瓶の処理も面倒だ。そして当然の帰着としてアルコール度数の高い酒を飲むようになった。
初めに好きになったのは1980年代末にリバイバルヒットになっていた明治時代に誕生した、ブランデーベースのカクテルの「電気ブラン」だった。明治の頃は、その度数は当時45度と高く、口の中がしびれる状態と、電気でしびれるイメージとが一致していたため、ハイカラな飲み物として人気を博したらしい。私は電気ブランの味そのものよりも、その「しびれる」という感覚が好きだった。
そうやってどんどんアルコール度数の強い酒を求めて、いつのまにかジンやウォッカを一晩で飲み明かすようになっていった。そして昼間もまたビールを飲む。10代にして連続飲酒の一歩手前まで来ていたような気がする。飲酒には特別な理由付けは必要ないかもしれない。尊敬する作家の中島らも氏はいみじくも飲酒の理由を「ただ気持ちがいいから」と断言した。それはその通りだろう。
しかし、言い訳になってしまうが、この当時、どうしてこんなにアルコールに取りつかれてしまったか考えてみると、高校3年生の頃から受験勉強というものに嫌悪感を抱きながらもそれをしなければならなかった自分の中での矛盾、そして浪人生という中途半端な立場から何とか逃げようとしていた現実逃避の道具としてアルコールを使っていたのだと思う。その証拠に、大学合格後はあれほどアルコールに呪縛されていた生活から解き放たれたように、強迫的に飲酒することはなくなった。だた、毎日飲む習慣は残ったが・・・。
6.大学時代(パート1)
大学に入学すると、私は何のクラブやサークルにも入らず、一人孤独に勉強とアルバイトの生活を送った。なぜなら、多摩美術大学の建築科は厳しく、同期入学の1/3しか4年間のストレートで卒業できないという現実があり、2年間も浪人してしまった私は留年することが自分自身の中で許されなかったからである。
そのため、結果的に飲酒するときはいつも一人だった。また、外で飲むという習慣もなかった。たまに、友人や、時には教授たちと一緒に飲み会に誘われることも無くはなかったが、その時はいつも自分を殺して飲んでいて、酔いつぶれるということは一度もなく、下宿に戻ってから一人飲み直すことが多かった。その習慣は、大学を卒業して社会人になってからも変わることはなかった。一度だけ酔いつぶれて失敗してしまったことは、フランス語原書講読の試験前日に深酒してしまって、試験に間に合わなかったことくらいである。おかげでその講義の単位は落としてしまったが・・・
大学時代を通じて習慣飲酒は続いていたが、当時飲んでいたのはビールやワインなどのアルコール度数の低い酒で、むしろ大学時代を通じては飲酒よりもナイトクラビングに明け暮れていて、週に2度3度と最終電車で六本木や西麻布に行っては朝まで踊り明かしていた。まだ20歳そこそこの学生なので体力はあったと思う。当時よく通っていたのは六本木の「ラゼルダゼル」だった。夜は通常営業するのだが、週末の深夜2時を過ぎるとアフターアワーズパーティーとなって入場料が1000円になる。それで入ってノンドリンクで朝の8時過ぎまで踊り狂う。金のない学生にはもってこいだ。
元々音楽が好きで、暗闇の中、ストロボライトを浴びながら好きな音楽で踊り狂うことはドラッグと同じで、何時間も休みなく踊り続けることで日常のストレスを忘れさせてくれ、ランナーズハイに似たトランス状態に導いてくれた。当時は、アルコールよりもダンスに酔っていたのである。それを教えてくれたのが、当時通っていた英会話学校の講師であるデヴィッドだった。自分もコンビでVJをやっていたのでよくクラブに誘われた。彼らが師として仰いでいたティモシー・リアリーにもクラブで会ったことがある。「チベットの死者の書―サイケデリック・バージョン」を記した元ハーバード大学教授の心理学者である。彼は、ハーバード時代はシロシビンやLSD(リゼルグ酸ジエチルアミド)といった幻覚剤による人格変容の研究を行った。幻覚剤によって刷り込みを誘発できると主張し、意識の自由を訴え、私が会った晩年は、宇宙移住をサイバースペースへの移住へと置き換え、コンピュータ技術に携わった。コンピュータを1990年代のLSDに見立て、コンピュータを使って自分の脳を再プログラミングすることを提唱していた。
大学に入学すると、私は何のクラブやサークルにも入らず、一人孤独に勉強とアルバイトの生活を送った。なぜなら、多摩美術大学の建築科は厳しく、同期入学の1/3しか4年間のストレートで卒業できないという現実があり、2年間も浪人してしまった私は留年することが自分自身の中で許されなかったからである。
そのため、結果的に飲酒するときはいつも一人だった。また、外で飲むという習慣もなかった。たまに、友人や、時には教授たちと一緒に飲み会に誘われることも無くはなかったが、その時はいつも自分を殺して飲んでいて、酔いつぶれるということは一度もなく、下宿に戻ってから一人飲み直すことが多かった。その習慣は、大学を卒業して社会人になってからも変わることはなかった。一度だけ酔いつぶれて失敗してしまったことは、フランス語原書講読の試験前日に深酒してしまって、試験に間に合わなかったことくらいである。おかげでその講義の単位は落としてしまったが・・・
大学時代を通じて習慣飲酒は続いていたが、当時飲んでいたのはビールやワインなどのアルコール度数の低い酒で、むしろ大学時代を通じては飲酒よりもナイトクラビングに明け暮れていて、週に2度3度と最終電車で六本木や西麻布に行っては朝まで踊り明かしていた。まだ20歳そこそこの学生なので体力はあったと思う。当時よく通っていたのは六本木の「ラゼルダゼル」だった。夜は通常営業するのだが、週末の深夜2時を過ぎるとアフターアワーズパーティーとなって入場料が1000円になる。それで入ってノンドリンクで朝の8時過ぎまで踊り狂う。金のない学生にはもってこいだ。
元々音楽が好きで、暗闇の中、ストロボライトを浴びながら好きな音楽で踊り狂うことはドラッグと同じで、何時間も休みなく踊り続けることで日常のストレスを忘れさせてくれ、ランナーズハイに似たトランス状態に導いてくれた。当時は、アルコールよりもダンスに酔っていたのである。それを教えてくれたのが、当時通っていた英会話学校の講師であるデヴィッドだった。自分もコンビでVJをやっていたのでよくクラブに誘われた。彼らが師として仰いでいたティモシー・リアリーにもクラブで会ったことがある。「チベットの死者の書―サイケデリック・バージョン」を記した元ハーバード大学教授の心理学者である。彼は、ハーバード時代はシロシビンやLSD(リゼルグ酸ジエチルアミド)といった幻覚剤による人格変容の研究を行った。幻覚剤によって刷り込みを誘発できると主張し、意識の自由を訴え、私が会った晩年は、宇宙移住をサイバースペースへの移住へと置き換え、コンピュータ技術に携わった。コンピュータを1990年代のLSDに見立て、コンピュータを使って自分の脳を再プログラミングすることを提唱していた。
6.大学時代(パート2)
私が大学に入学したのは1989年である。時代はまだ80年代の香りを残しており、バブルとサイバーに浮かれていた。バブルの方では特に恩恵は与らなかったが、サイバーにはどっぷりとハマってしまった。サイバーパンクである。
サイバーパンクの語源となるサイバネティクスとは、アメリカの数学者、ノーバート・ウィーナーが提唱し、本来はフィードバックの概念を核にして生理学と機械工学、システム工学、情報工学を統一的に扱う学問領域であるが、これが転じて脳神経機能の電子的・機械的補完拡張やコンピュータへの接続技術を指すようになった。サイバーパンクではこれらの人体と機械が融合し、脳内とコンピュータの情報処理の融合が「過剰に推し進められた社会」を描写する。さらに、社会機構や経済構造等のより上位の状況を考察し、それらを俯瞰するメタ的な視点・視野を提供するという点で従来のSFと一線を画する。ウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』などがサイバーパンクの代表作で、それに続く『カウント・ゼロ』や『モナリザ・オーヴァドライヴ』を貪るように読んだ。それが私とコンピュータとの出会いである。コンピュータとの付き合いは23年後の今に至るまで蜜月関係だ。また、『ニューロマンサー』の主人公のケイスが依頼主との契約違反の制裁として、脳神経を焼かれてジャック・イン能力を失い、ドラッグ浸りのチンピラ暮らしを送っていた電脳都市千葉市(チバ・シティ)の風景は私が幼少時代に過ごした大阪の郊外、大東市の殺伐とした風景を思い起こさせる。
ナイトクラビングの理論的な背景がサイバーパンクなら、音楽ではブリープ・ハウスがそれに当たる。NYの王道HOUSEやGARAGEの虜になるのは後のことである。
1989年から1991年にかけてイギリスの北部、シェフィールドのレコードレーベルWARP Recordsを震源地に、小さいながらもブリープ・テクノ、ブリープ・ハウス、ノーザン・テクノ、ヨークシャー・ブリープなどと呼ばれるダンスミュージックのムーブメントがあった。その特徴は、アメリカのシカゴ・ハウスやデトロイト・テクノからの影響をストレートに表したそれまでに無かったようなフィルター全開の重低音のシンセベースと剥き出しの電子音だ。そしてデヴィッド達が作り上げるビデオMIXと相まってクラブの中はまさにコンピュータやネットワークの中に広がるデータ領域を、多数の利用者が自由に情報を流したり得たりすることが出来る仮想的な空間であるサイバースペースだった。当時のキーワードはバーチャルリアリティである。私はサイバーに酔っていた。
大学の設計課題の作成は大変だったが、週末などは夜の11時までそれをやり、最終電車で遊びに行って何時間もサイバースペースに浸りきり、朝帰ってきてからまた昼前まで続きをやるということが当たり前になっていた。しかも酒を飲みながらである。
私は人を驚かせる癖がある。入学から卒業まで真面目な学生を演じていて、教授たちには私が六本木や西麻布で遊びまくっていたことなど想像もつかなかっただろう。卒業式の後の謝恩会の時に学友たちが私を指さして、
「六本木の帝王はここにいますよ。」
と言うと、教授たちは一斉に、
「もう学生たちを信用できないよ〜。」
と言ったことが懐かしい。
私が大学に入学したのは1989年である。時代はまだ80年代の香りを残しており、バブルとサイバーに浮かれていた。バブルの方では特に恩恵は与らなかったが、サイバーにはどっぷりとハマってしまった。サイバーパンクである。
サイバーパンクの語源となるサイバネティクスとは、アメリカの数学者、ノーバート・ウィーナーが提唱し、本来はフィードバックの概念を核にして生理学と機械工学、システム工学、情報工学を統一的に扱う学問領域であるが、これが転じて脳神経機能の電子的・機械的補完拡張やコンピュータへの接続技術を指すようになった。サイバーパンクではこれらの人体と機械が融合し、脳内とコンピュータの情報処理の融合が「過剰に推し進められた社会」を描写する。さらに、社会機構や経済構造等のより上位の状況を考察し、それらを俯瞰するメタ的な視点・視野を提供するという点で従来のSFと一線を画する。ウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』などがサイバーパンクの代表作で、それに続く『カウント・ゼロ』や『モナリザ・オーヴァドライヴ』を貪るように読んだ。それが私とコンピュータとの出会いである。コンピュータとの付き合いは23年後の今に至るまで蜜月関係だ。また、『ニューロマンサー』の主人公のケイスが依頼主との契約違反の制裁として、脳神経を焼かれてジャック・イン能力を失い、ドラッグ浸りのチンピラ暮らしを送っていた電脳都市千葉市(チバ・シティ)の風景は私が幼少時代に過ごした大阪の郊外、大東市の殺伐とした風景を思い起こさせる。
ナイトクラビングの理論的な背景がサイバーパンクなら、音楽ではブリープ・ハウスがそれに当たる。NYの王道HOUSEやGARAGEの虜になるのは後のことである。
1989年から1991年にかけてイギリスの北部、シェフィールドのレコードレーベルWARP Recordsを震源地に、小さいながらもブリープ・テクノ、ブリープ・ハウス、ノーザン・テクノ、ヨークシャー・ブリープなどと呼ばれるダンスミュージックのムーブメントがあった。その特徴は、アメリカのシカゴ・ハウスやデトロイト・テクノからの影響をストレートに表したそれまでに無かったようなフィルター全開の重低音のシンセベースと剥き出しの電子音だ。そしてデヴィッド達が作り上げるビデオMIXと相まってクラブの中はまさにコンピュータやネットワークの中に広がるデータ領域を、多数の利用者が自由に情報を流したり得たりすることが出来る仮想的な空間であるサイバースペースだった。当時のキーワードはバーチャルリアリティである。私はサイバーに酔っていた。
大学の設計課題の作成は大変だったが、週末などは夜の11時までそれをやり、最終電車で遊びに行って何時間もサイバースペースに浸りきり、朝帰ってきてからまた昼前まで続きをやるということが当たり前になっていた。しかも酒を飲みながらである。
私は人を驚かせる癖がある。入学から卒業まで真面目な学生を演じていて、教授たちには私が六本木や西麻布で遊びまくっていたことなど想像もつかなかっただろう。卒業式の後の謝恩会の時に学友たちが私を指さして、
「六本木の帝王はここにいますよ。」
と言うと、教授たちは一斉に、
「もう学生たちを信用できないよ〜。」
と言ったことが懐かしい。
7.20代
社会人になってからの数年間も大学時代と同じく、どんなに仕事が忙しくてもナイトクラビングだけは欠かさず、土曜日などは朝の4時過ぎまで仕事をした後、5時の始発電車に飛び乗って朝の10時までアフターアワーズパーティーをしているクラブに行ったこともあった。当時の私には飲酒に代わる「酔い」があったとも言える。それがダンスだった。
いわゆるダンシングハイである。ランニングハイは、ジョッキングやランニング界では、有名な言葉だが、ダンス界では、ランニングハイのような脳内麻薬のような言葉がない。しかし、ランニングハイのときのようなβーエンドルフィン様の分泌は否定できない。ランニングハイは、ランニング開始15分程度、ダンス(踊り)の場合は、踊り開始1分でスグ現われ気持ち良くなってくる。
飲酒にしてもダンスにしても「現実逃避」という意味では同じものであり、私の生き方そのものは何ら変わっていなかったと思われる。これが後に依存症に陥る原因となる。
入社当初、一度だけ飲酒で失敗しかけたことがある。会社に入社して初めての仕事は、マンション建設のための駐車場の立ち退き交渉で、ある保険会社の社員が数人、立ち退きに抵抗したことがあった。そのため土曜日に出勤し、専務と顧問弁護士を連れて交渉に出かけ、何とか説得して自宅に帰ってゆっくり焼酎のウーロン茶割を飲んでいると、専務から呼び出され、翌日の日曜日に土地売却契約書に実印を押してもらうために徳島に飛んでくれと言われた。羽田発の始発の飛行機で徳島に向わなければならなかったのだが、前日の疲れと深酒で予定の起床時間を大幅に遅れて起床してしまい、顔も洗わずに急いでスーツを着込み、電車の中でネクタイを締めてやっとのことで離陸間近の飛行機に間に合った。
会社の仕事がだんだん忙しくなってきたのは入社2年目の頃からである。それまで、設計の仕事は外注をしていたのだが、社内でやることになり、CADが使える私に図面作製の仕事が集中することになった。上司の課長は設計の指示だけ出して図面は描かない。また、後輩もCADが使えないのでサポート的な仕事しかできなかった。連日2時3時までの残業が続き、また8時に出勤である。仕事の時はずっとCADに張り付いている状態で、常にコンピュータのモニターがちらついて、仕事が終わってからも頭はハイだった。そのためだんだん眠れないようになり、睡眠薬代わりの飲酒が常態と化し、次第に酒量も増えていった。
社会人になってからの数年間も大学時代と同じく、どんなに仕事が忙しくてもナイトクラビングだけは欠かさず、土曜日などは朝の4時過ぎまで仕事をした後、5時の始発電車に飛び乗って朝の10時までアフターアワーズパーティーをしているクラブに行ったこともあった。当時の私には飲酒に代わる「酔い」があったとも言える。それがダンスだった。
いわゆるダンシングハイである。ランニングハイは、ジョッキングやランニング界では、有名な言葉だが、ダンス界では、ランニングハイのような脳内麻薬のような言葉がない。しかし、ランニングハイのときのようなβーエンドルフィン様の分泌は否定できない。ランニングハイは、ランニング開始15分程度、ダンス(踊り)の場合は、踊り開始1分でスグ現われ気持ち良くなってくる。
飲酒にしてもダンスにしても「現実逃避」という意味では同じものであり、私の生き方そのものは何ら変わっていなかったと思われる。これが後に依存症に陥る原因となる。
入社当初、一度だけ飲酒で失敗しかけたことがある。会社に入社して初めての仕事は、マンション建設のための駐車場の立ち退き交渉で、ある保険会社の社員が数人、立ち退きに抵抗したことがあった。そのため土曜日に出勤し、専務と顧問弁護士を連れて交渉に出かけ、何とか説得して自宅に帰ってゆっくり焼酎のウーロン茶割を飲んでいると、専務から呼び出され、翌日の日曜日に土地売却契約書に実印を押してもらうために徳島に飛んでくれと言われた。羽田発の始発の飛行機で徳島に向わなければならなかったのだが、前日の疲れと深酒で予定の起床時間を大幅に遅れて起床してしまい、顔も洗わずに急いでスーツを着込み、電車の中でネクタイを締めてやっとのことで離陸間近の飛行機に間に合った。
会社の仕事がだんだん忙しくなってきたのは入社2年目の頃からである。それまで、設計の仕事は外注をしていたのだが、社内でやることになり、CADが使える私に図面作製の仕事が集中することになった。上司の課長は設計の指示だけ出して図面は描かない。また、後輩もCADが使えないのでサポート的な仕事しかできなかった。連日2時3時までの残業が続き、また8時に出勤である。仕事の時はずっとCADに張り付いている状態で、常にコンピュータのモニターがちらついて、仕事が終わってからも頭はハイだった。そのためだんだん眠れないようになり、睡眠薬代わりの飲酒が常態と化し、次第に酒量も増えていった。
8.病気発症
飲酒行動が異常をきたしてきたのは30歳の夏頃からだった。それまではいくら仕事が忙しいと言っても自分が好きで選んだ設計の仕事だったので、仕事の疲れや不眠はあったものの、常識的な社会生活を送ることはできていた。しかしながら、この頃から設計の仕事は激減し、全くの素人にも関わらず補償コンサルタントの仕事を一人で任されるようになった。これが原因でまずは鬱病になった。
補償コンサルタントとは不動産に関するコンサルタントのひとつであり、日本国憲法第29条第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」という条項を根拠とする。これを法制化したものが土地収用法であるが、ほとんどの場合任委買収に依る。しかしながら当然税金を投入するため、厳密な公共事業にあたり土地取得と建物移転などの損失補償額を算定する「公共用地の取得に伴う損失補償基準」があり、それに基づく単価表もあって、民間の事業の損失補償と違って答えは一つである。多くても少なくてもいけない。土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業補償・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償の8つの登録部門に分かれており、私が任されたのはそのうち物件、営業補償、事業損失であった。
公共事業に関する仕事なので発注は役所であり、業務に着手するときにはメンバー表を提出して複数で仕事を行うことになっていたのだが、私以外のメンバーは全員ダミーであった。そのため基本的に4人くらいで行う仕事を私一人に押しつけられる形になり、慣れない仕事ということもあってミスを連発し、その結果、役人から厳しく叱責されることが毎日のようになった。そうした背景もあり、私は次第にその仕事のストレスと責任感の重圧から逃れるたびに毎日浴びるように酒を飲み、アルコールというドラッグに溺れるようになっていった。また、30歳を越えるとナイトクラブで踊ることもなくなり、アルコールだけがつかの間現実を忘れさせてくれる道具になった。
アルコールに対する耐性も次第に形成されてくると、それに伴って酒量も一気に増えていった。毎日、仕事帰りに焼酎の一升パックを買って帰っては、一日に半分から、多いときには一本を開けるペースで飲み続けた。休日になると朝から飲むようになり、飲んでは眠り、目が覚めたらまた飲むという習慣ができた。アルコールが切れてくると落ち着かなくなり、まだストックが半分以上残っているにもかかわらず、いくら飲んでもまだ酒が残っているという安心感がほしかったためにさらに買い足した。しかもいつもお酒を買う酒屋に買いに行くと不審がられる。それからは自宅の向えにある東急ストアーに買いに行くようになった。レジのオバちゃんは顔まで覚えてはいまい。
そうした日々が続くと、そのうち平日に仕事に行かなければならないにもかかわらず朝から飲まないとつらい仕事をこなす気力が出なくなり、仕事中でも隙を見ては酒を飲む機会を探すようになっていった。自分なりにアルコールの問題が大きくなっていることは分かっていたのだが、既に手遅れの状態で、いつの間にか道具(手段)出会ったに過ぎないアルコールが目的に代わっていった。
そのうちアルコールの離脱状態が顕われるようになり、不眠・発汗・下痢・手の震えが次第に酷くなり、夕方になると必ず毎日のように吐き気がして、会社のトイレで嘔吐することも頻繁になった。特に手の震えはコンピュータのタイピングをおぼつかなくさせ、下痢は外出した際などに必ずトイレの場所を確認しないと昼食も取れなくさせていた。そして常に落ち着きをなくし、仕事の能率も日を追って落ちていき、体が鉛のように重くなって、会社を休まざるをえない日が度重なるようになった。
また、おそらく幻覚だったのだろうがゴキブリの大群がシンクを走り回っている光景を見たり、行った覚えのない焼肉屋や寿司屋のレシートが財布から頻繁に出てきたり、トイレの鏡を粉々に叩き割っていたり、タバコを吸いながら酔いつぶれて寝てしまい、ボヤ騒ぎを起こすこともあった。しかしそれらは全く記憶にない。いわゆるブラックアウトだ。
会社では毎日のように朝から酒臭いと注意を受けていたのだが、問題飲酒行動は辞められなかった。クライアント(役所)との打ち合わせの際も酒臭い息をさせていたので上司から注意されただけでなく先方からも指摘され、仕事から外されることになった。そして31歳の時、通院していた内科から精神科に転院するようになり、初めてアルコール依存症と診断され、断酒を勧められた。
飲酒行動が異常をきたしてきたのは30歳の夏頃からだった。それまではいくら仕事が忙しいと言っても自分が好きで選んだ設計の仕事だったので、仕事の疲れや不眠はあったものの、常識的な社会生活を送ることはできていた。しかしながら、この頃から設計の仕事は激減し、全くの素人にも関わらず補償コンサルタントの仕事を一人で任されるようになった。これが原因でまずは鬱病になった。
補償コンサルタントとは不動産に関するコンサルタントのひとつであり、日本国憲法第29条第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」という条項を根拠とする。これを法制化したものが土地収用法であるが、ほとんどの場合任委買収に依る。しかしながら当然税金を投入するため、厳密な公共事業にあたり土地取得と建物移転などの損失補償額を算定する「公共用地の取得に伴う損失補償基準」があり、それに基づく単価表もあって、民間の事業の損失補償と違って答えは一つである。多くても少なくてもいけない。土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業補償・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償の8つの登録部門に分かれており、私が任されたのはそのうち物件、営業補償、事業損失であった。
公共事業に関する仕事なので発注は役所であり、業務に着手するときにはメンバー表を提出して複数で仕事を行うことになっていたのだが、私以外のメンバーは全員ダミーであった。そのため基本的に4人くらいで行う仕事を私一人に押しつけられる形になり、慣れない仕事ということもあってミスを連発し、その結果、役人から厳しく叱責されることが毎日のようになった。そうした背景もあり、私は次第にその仕事のストレスと責任感の重圧から逃れるたびに毎日浴びるように酒を飲み、アルコールというドラッグに溺れるようになっていった。また、30歳を越えるとナイトクラブで踊ることもなくなり、アルコールだけがつかの間現実を忘れさせてくれる道具になった。
アルコールに対する耐性も次第に形成されてくると、それに伴って酒量も一気に増えていった。毎日、仕事帰りに焼酎の一升パックを買って帰っては、一日に半分から、多いときには一本を開けるペースで飲み続けた。休日になると朝から飲むようになり、飲んでは眠り、目が覚めたらまた飲むという習慣ができた。アルコールが切れてくると落ち着かなくなり、まだストックが半分以上残っているにもかかわらず、いくら飲んでもまだ酒が残っているという安心感がほしかったためにさらに買い足した。しかもいつもお酒を買う酒屋に買いに行くと不審がられる。それからは自宅の向えにある東急ストアーに買いに行くようになった。レジのオバちゃんは顔まで覚えてはいまい。
そうした日々が続くと、そのうち平日に仕事に行かなければならないにもかかわらず朝から飲まないとつらい仕事をこなす気力が出なくなり、仕事中でも隙を見ては酒を飲む機会を探すようになっていった。自分なりにアルコールの問題が大きくなっていることは分かっていたのだが、既に手遅れの状態で、いつの間にか道具(手段)出会ったに過ぎないアルコールが目的に代わっていった。
そのうちアルコールの離脱状態が顕われるようになり、不眠・発汗・下痢・手の震えが次第に酷くなり、夕方になると必ず毎日のように吐き気がして、会社のトイレで嘔吐することも頻繁になった。特に手の震えはコンピュータのタイピングをおぼつかなくさせ、下痢は外出した際などに必ずトイレの場所を確認しないと昼食も取れなくさせていた。そして常に落ち着きをなくし、仕事の能率も日を追って落ちていき、体が鉛のように重くなって、会社を休まざるをえない日が度重なるようになった。
また、おそらく幻覚だったのだろうがゴキブリの大群がシンクを走り回っている光景を見たり、行った覚えのない焼肉屋や寿司屋のレシートが財布から頻繁に出てきたり、トイレの鏡を粉々に叩き割っていたり、タバコを吸いながら酔いつぶれて寝てしまい、ボヤ騒ぎを起こすこともあった。しかしそれらは全く記憶にない。いわゆるブラックアウトだ。
会社では毎日のように朝から酒臭いと注意を受けていたのだが、問題飲酒行動は辞められなかった。クライアント(役所)との打ち合わせの際も酒臭い息をさせていたので上司から注意されただけでなく先方からも指摘され、仕事から外されることになった。そして31歳の時、通院していた内科から精神科に転院するようになり、初めてアルコール依存症と診断され、断酒を勧められた。
9−1.初めての入院
横浜の大学病院の精神科で初めてアルコール依存症と診断され、断酒を勧められた時には私は全く飲酒をやめる気になれず、病気だから飲酒を繰り帰すのが当然と考えていた。それは当時かかっていた病院がアルコール依存症の専門治療を行っていなかったことと、主治医もアルコール依存症の専門家医ではなかったからである。だからアルコール依存症の病気の説明もほとんどなく、私が自主的に断酒することが唯一の治療と考えていたきらいがある。ましてや、私自身、自暴自棄になっており、とことんまで落ちてやろうという思いもあった。
私の病状が悪化の糸をたどるに従って母が心配し、様子を見に来た。その時、私の1Kの部屋はアルコール臭で充満していた。母はそれに気付くと半狂乱のようになって大学病院の最後の診察に社長とともに付き添った。そして私一人では置いておけないと判断したのだろう。社長と相談して実家の奈良に連れてかえることをとんとん拍子に進めていった。休職は3カ月となっていた。
その時の私はこれまでにない脱力感に苛まれていた。帰りの新幹線の中で最期の一杯と諦めかけていたビールを一口飲み、実家に帰ったのだが、固形物が一切受け付けなくなっていた。食事を出されても全て嘔吐し、栄養失調状態であった。
とりあえず奈良には近畿大学付属奈良病院というホテルのような病院がある。まずはそこの神経科で診察を受けるつもりで行ったのだが、そこの医者もアルコール依存症には門外漢で、あちこちのアルコール専門治療を行っている精神病院に片端から入院治療ができるかどうか確信してくれた。どこも満員で、やっと見つかったのが堺にある○○中央病院である。
入院は生れて初めてである。しかもアルコール依存症治療には3か月もの入院が必要と宣告された時には失望した。せっかくの休みを入院だけで済ますなんて・・・。一通りの入院手続きをしているとき、自分の手が震えて自分の名前さえ碌に書くことができない。その時には絶望感を味わったものである。医師はその様子をじっと眺めていた。
最初にベッドを与えられ入室した病室はナースステーションの隣にあり、24時間モニターで監視されていた。隣のベッドにはかなり重症の患者が点滴を受けていた。もちろん大小便は垂れ流しである。顔色も土色で、死を感じさせた。
「これはもしかしたらとんでもない所に来てしまったのではないだろうか?」
それが入院初日の感想だ。しかし、次の日は隣の比較的静かな病室に移された。心底ほっとしたものである。
入院から数日たったある日の午後、主治医から診察室に呼び出されて数枚の書類を手渡された。まず一枚目にはアルコール、睡眠薬・抗不安薬、咳止め薬、シンナーなど、アンフェタミン、マリファナ、LSD、ヘロイン、コカイン、類似薬物、ニコチンが箇条書きにされていて、それぞれの毒性や精神依存性や身体依存性が詳細に書かれてあった。アンフェタミンだけが初耳だったので主治医に聞いてみると。
「覚醒剤ですよ。いわゆるシャブってやつです。」
それぞれの項目で強さを表す丸印を見てみると、アルコールは身体依存で覚醒剤を勝っていたのである。そして医師の次の言葉が強烈に印象に残った。
「いちどアルコール依存症になれば一生治ることはありません。しかもアルコール依存症者が飲酒すると、脳内からモルヒネ同様の物質が分泌され、死に至ります。」
心の中で私は何度もつぶやいた、
「モルヒネか〜〜〜モルヒネか〜〜〜モルヒネか〜〜〜」
ドラッグに関する知識はウィリアム・バロウズやティモシー・リアリーなどの著作を読んでいただけにある程度持っていた。実際、クラブでLSDをやったこともある。しかし、麻薬=アヘン、モルヒネ、ヘロインだけには手は出すまいという自負だけはあった。あれに手を出すと人間をやめなければならない。当時の私はどこか厭世的でいつ死んでもいいくらいに思っていたのだが、人間という尊厳だけは失いたくなかった。そしていざ死を前にすると心とは裏腹に足がすくんでしまう。その時、急に生への希求が出てきた。
「いちどアルコール依存の悪循環の回路ができてしまったら死ぬまで治りませんよ。」
そう説明されると、初めて事の重大さに気がついて仕方なくではあるものの断酒を決意する以外には生きるすべがなくなり愕然となった。
横浜の大学病院の精神科で初めてアルコール依存症と診断され、断酒を勧められた時には私は全く飲酒をやめる気になれず、病気だから飲酒を繰り帰すのが当然と考えていた。それは当時かかっていた病院がアルコール依存症の専門治療を行っていなかったことと、主治医もアルコール依存症の専門家医ではなかったからである。だからアルコール依存症の病気の説明もほとんどなく、私が自主的に断酒することが唯一の治療と考えていたきらいがある。ましてや、私自身、自暴自棄になっており、とことんまで落ちてやろうという思いもあった。
私の病状が悪化の糸をたどるに従って母が心配し、様子を見に来た。その時、私の1Kの部屋はアルコール臭で充満していた。母はそれに気付くと半狂乱のようになって大学病院の最後の診察に社長とともに付き添った。そして私一人では置いておけないと判断したのだろう。社長と相談して実家の奈良に連れてかえることをとんとん拍子に進めていった。休職は3カ月となっていた。
その時の私はこれまでにない脱力感に苛まれていた。帰りの新幹線の中で最期の一杯と諦めかけていたビールを一口飲み、実家に帰ったのだが、固形物が一切受け付けなくなっていた。食事を出されても全て嘔吐し、栄養失調状態であった。
とりあえず奈良には近畿大学付属奈良病院というホテルのような病院がある。まずはそこの神経科で診察を受けるつもりで行ったのだが、そこの医者もアルコール依存症には門外漢で、あちこちのアルコール専門治療を行っている精神病院に片端から入院治療ができるかどうか確信してくれた。どこも満員で、やっと見つかったのが堺にある○○中央病院である。
入院は生れて初めてである。しかもアルコール依存症治療には3か月もの入院が必要と宣告された時には失望した。せっかくの休みを入院だけで済ますなんて・・・。一通りの入院手続きをしているとき、自分の手が震えて自分の名前さえ碌に書くことができない。その時には絶望感を味わったものである。医師はその様子をじっと眺めていた。
最初にベッドを与えられ入室した病室はナースステーションの隣にあり、24時間モニターで監視されていた。隣のベッドにはかなり重症の患者が点滴を受けていた。もちろん大小便は垂れ流しである。顔色も土色で、死を感じさせた。
「これはもしかしたらとんでもない所に来てしまったのではないだろうか?」
それが入院初日の感想だ。しかし、次の日は隣の比較的静かな病室に移された。心底ほっとしたものである。
入院から数日たったある日の午後、主治医から診察室に呼び出されて数枚の書類を手渡された。まず一枚目にはアルコール、睡眠薬・抗不安薬、咳止め薬、シンナーなど、アンフェタミン、マリファナ、LSD、ヘロイン、コカイン、類似薬物、ニコチンが箇条書きにされていて、それぞれの毒性や精神依存性や身体依存性が詳細に書かれてあった。アンフェタミンだけが初耳だったので主治医に聞いてみると。
「覚醒剤ですよ。いわゆるシャブってやつです。」
それぞれの項目で強さを表す丸印を見てみると、アルコールは身体依存で覚醒剤を勝っていたのである。そして医師の次の言葉が強烈に印象に残った。
「いちどアルコール依存症になれば一生治ることはありません。しかもアルコール依存症者が飲酒すると、脳内からモルヒネ同様の物質が分泌され、死に至ります。」
心の中で私は何度もつぶやいた、
「モルヒネか〜〜〜モルヒネか〜〜〜モルヒネか〜〜〜」
ドラッグに関する知識はウィリアム・バロウズやティモシー・リアリーなどの著作を読んでいただけにある程度持っていた。実際、クラブでLSDをやったこともある。しかし、麻薬=アヘン、モルヒネ、ヘロインだけには手は出すまいという自負だけはあった。あれに手を出すと人間をやめなければならない。当時の私はどこか厭世的でいつ死んでもいいくらいに思っていたのだが、人間という尊厳だけは失いたくなかった。そしていざ死を前にすると心とは裏腹に足がすくんでしまう。その時、急に生への希求が出てきた。
「いちどアルコール依存の悪循環の回路ができてしまったら死ぬまで治りませんよ。」
そう説明されると、初めて事の重大さに気がついて仕方なくではあるものの断酒を決意する以外には生きるすべがなくなり愕然となった。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
アルコール依存治療への疑問 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-