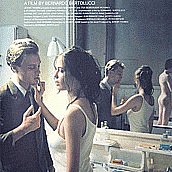邦題; 君を想って海をゆく (2009)
原題; WELCOME
上映時間 110分
製作国 フランス
監督: フィリップ・リオレ
製作: クリストフ・ロシニョン
脚本: フィリップ・リオレ、 エマニュエル・クールコル、 オリヴィエ・アダム
撮影: ローラン・ダイヤン
出演:
ヴァンサン・ランドン シモン
フィラ・エヴェルディ ビラル
オドレイ・ダナ マリオン
デリヤ・エヴェルディ ミナ
ティエリ・ゴダール ブリュノ
セリム・アクグル ゾラン
オリヴィエ・ラブルダン 警察代理官
「パリ空港の人々」「灯台守の恋」のフィリップ・リオレ監督が、次第に不寛容へと傾きつつある移民政策を真正面から取り上げ、本国フランスで大ヒットしたヒューマン・ドラマ。イギリスに移住した恋人に会うため、最後の手段としてドーバー海峡を泳いで渡る決意をしたクルド難民の少年と、ひょんなことから彼の泳ぎを指導することになったフランス人中年男性が、次第に心を通わせ、絆を深めていく姿を真摯な眼差しで綴る。主演は「すべて彼女のために」のヴァンサン・ランドンと新人フィラ・エヴェルディ。
2008年12月、フランス北端の街カレ。イラクの国籍を持つ17歳のクルド難民ビラルは、家族と共にロンドンに移住した恋人を追って、イラクから4000キロの距離を歩いてやって来た。しかし、ドーバー海峡を越えるべく密航を試みるも失敗に終わり、カレに足止めとなってしまう。もはやビラルに残された手段は、海峡を泳いで渡る以外にはなかった。そして、市民プールで子どもや老人相手に指導をしているフランス人シモンにコーチを懇願する。最愛の妻と離婚調停中のシモンは、難民支援のボランティアをする妻に認めてもらえるのではとの思いから、コーチを引き受けることにするのだが…。
上記が映画データベースの記述である。
今から5年前に同じ問題を扱った、マイケル・ウィンターボトム監督の In This World (2002)を観て次のように記している。
http://
当時の舞台が2000年、本作が2008年と設定され、その間の事情はヨーロッパのいよいよ慢性する不況とそれにともなう移民政策の強化に伴って南から北を目指す違法経済難民たちにとっては悪化していると認められる中での物語りである。 丁度2,3日か前にクルド人独立を目指す党PKKの犯行と認められるトルコ軍に対するテロで10名を越す兵士が命を落としそれに抗議してオランダ・ハーグ市でクルド撲滅を叫ぶ在蘭トルコ人極右グループからトルコナショナリストたちの集会の模様が報道されたその夜の本作でもあったのだが国を持たないクルド人がどのような運命を辿っているかはここでは問題ではない。 アフリカ、中東、アジアの各地からよりよい生活を目指して命を賭しての移動である。 ウインターボトムの作では今と比べるとまだ単純な冒険の果てに成功の可能性を残していたものが本作では開始早々それがいかに甘い過去のものかを少年や我々に思い知らせることとなり、雪崩を打って輸送トラックにもぐりこみ英仏間のトンネルを渡ろうとする密航者を捕らえるべくより科学的効率的なCO2探知で当局が対抗するその裏をかく自殺行為すれすれのビニールバッグかぶりにこれまで8年の差を垣間見るようであり、当時はこのような行動そのものがその日の食事を提供するボランティアと密入国者だけのものだったのが今ではそれらに対して同情的な市民までもこれに関わると幇助罪というおどしで難民達と市民を隔離しようとする政策の実際が示され当時からより深刻化した移民政策の程度をも示している。
そして嘗ての移民の息子を今大統領に掲げ人権保護を世界に誇ってきたフランスの二枚舌の象徴ともみられるのが本作中、水泳コーチのアパートの向かいの住人の玄関にしかれたシートの文字 Welcome であり、その部屋の住人の態度に経済不況の中で失業、年金の減額、警察国家に向かうような国で怯える市民の姿をみるようであり、これが本作の眼目であって、ここでの少年の愛の物語はいわば刺身のつまでさえある。 だから大陸が地続きであり歩いて何カ国も渡って来てここからは泳いで恋人に会いに行くという少年の愛の物語をロマンチックな題に翻訳する国には祖国を棄て、逃れ、離れていく者やそれを扱いかねるそれぞれの受け入れ国の人々の屈託は大陸や半島からの移民が多いことが歴史の事実であるとしてもそれを見てみぬふりともみられかねぬメディアのそぶりとシンクロしていると見られてもそれには異存はないだろう。 いずれにしても他所の国の問題なのだ。 それを如実に示すのが本作中テレビの画面に一瞬写るサルコジ大統領のスピーチであるといえるだろう。
それにしてもこういう世界でも、というかこういうぎりぎりの世界だからこそかコミュニケーションとしての言語に英語が使われるのが特徴的だ。 これから50年経つと英語が中国語に取って代わられるという人があるがこういう問題で中国語が共通語になるには中国はこれから幾つものハードルを越さねばならないだろうと思われる。 今のところ経済弱者が雪崩をうって中国におしよせるという話は逆はあってもそういうことは聞いていない。 英語に話をもどすと当然、舞台ではドーバーを越えイギリスを目指す人々の集団であるから英語が話せなければ未来はない、ということもあるだろうが作中でも妻が英語教師という設定になっているものの実際には仕事を離れては殆んど聞くことはなく、逆に水泳コーチが危なっかしい訥々の英語で少年と意思の疎通を図るというところにも工夫がなされているようだ。 私事、30年以上前、パリ北駅の案内所でまともに英語が話せる者がいないことを経験して驚いたものが、その後10年づつ経つにしたがってパリの夜中に路頭で警官と英語でよもやま話が出来るようになったこと、その後田舎の大きなスーパーには必ずちゃんとした英語が話せるものがいるようになった近年、世界言語としての英語がフランス語防御というか自国語を守る世界的な牙城にもなっているといわれていたフランスに徐々に浸透したことに、いささか自国語保護に耐性疲労が見え、まだ少しはパックスアメリカーナが続くことが感じられる現在、新天地を目指すものは英語圏の国を目指すということもわかるような気がするのだが、住んでみればイギリスが必ずしも夢見たような住みやすい国とはいえないことも分かるのだろうが命を懸けた二者択一の場ではそれを知る由もないということだろう。
何週間か前に80の半ばでイギリスからフランスまで泳ぎきった女性の話をテレビで観たのだが、この女性は30半ばぐらいで海峡横断を試み失敗していて今回再チャレンジでの成功だったのだがここでは年齢はほぼ関係がないだろう。 それについては様々に研究や経験のデータがあるのだから予め周到な準備もし、泳ぐこと自体がある意味では生涯の夢であり泳ぎきることに様々な保険をかけ伴走するコーチや食料の補給もあるのだから同じ泳ぐといってもここでの話とは次元が違う。 本作を見たものにはこの水泳コーチの同情心もわからないでもないとしてもそれを薦めるにあたっては無謀のそしりを受けても仕方がないだろう。 ま、しかしそれもストーリーのことである。 イギリスからフランスに泳ぐ話では大分前に観たイギリス映画もあったような気がする。 そこでは中年男が横断を試み泳ぎきることの意味が問われる話となっていたのではないか。 渋い俳優、Pete Postlethwaite が泳いだのではないかと思ったのだが他の俳優のものだったのかもしれずいずれにしてもそこでも複数のサポーターとともに周到の準備、助けのもとに行われていたのだった。
原題; WELCOME
上映時間 110分
製作国 フランス
監督: フィリップ・リオレ
製作: クリストフ・ロシニョン
脚本: フィリップ・リオレ、 エマニュエル・クールコル、 オリヴィエ・アダム
撮影: ローラン・ダイヤン
出演:
ヴァンサン・ランドン シモン
フィラ・エヴェルディ ビラル
オドレイ・ダナ マリオン
デリヤ・エヴェルディ ミナ
ティエリ・ゴダール ブリュノ
セリム・アクグル ゾラン
オリヴィエ・ラブルダン 警察代理官
「パリ空港の人々」「灯台守の恋」のフィリップ・リオレ監督が、次第に不寛容へと傾きつつある移民政策を真正面から取り上げ、本国フランスで大ヒットしたヒューマン・ドラマ。イギリスに移住した恋人に会うため、最後の手段としてドーバー海峡を泳いで渡る決意をしたクルド難民の少年と、ひょんなことから彼の泳ぎを指導することになったフランス人中年男性が、次第に心を通わせ、絆を深めていく姿を真摯な眼差しで綴る。主演は「すべて彼女のために」のヴァンサン・ランドンと新人フィラ・エヴェルディ。
2008年12月、フランス北端の街カレ。イラクの国籍を持つ17歳のクルド難民ビラルは、家族と共にロンドンに移住した恋人を追って、イラクから4000キロの距離を歩いてやって来た。しかし、ドーバー海峡を越えるべく密航を試みるも失敗に終わり、カレに足止めとなってしまう。もはやビラルに残された手段は、海峡を泳いで渡る以外にはなかった。そして、市民プールで子どもや老人相手に指導をしているフランス人シモンにコーチを懇願する。最愛の妻と離婚調停中のシモンは、難民支援のボランティアをする妻に認めてもらえるのではとの思いから、コーチを引き受けることにするのだが…。
上記が映画データベースの記述である。
今から5年前に同じ問題を扱った、マイケル・ウィンターボトム監督の In This World (2002)を観て次のように記している。
http://
当時の舞台が2000年、本作が2008年と設定され、その間の事情はヨーロッパのいよいよ慢性する不況とそれにともなう移民政策の強化に伴って南から北を目指す違法経済難民たちにとっては悪化していると認められる中での物語りである。 丁度2,3日か前にクルド人独立を目指す党PKKの犯行と認められるトルコ軍に対するテロで10名を越す兵士が命を落としそれに抗議してオランダ・ハーグ市でクルド撲滅を叫ぶ在蘭トルコ人極右グループからトルコナショナリストたちの集会の模様が報道されたその夜の本作でもあったのだが国を持たないクルド人がどのような運命を辿っているかはここでは問題ではない。 アフリカ、中東、アジアの各地からよりよい生活を目指して命を賭しての移動である。 ウインターボトムの作では今と比べるとまだ単純な冒険の果てに成功の可能性を残していたものが本作では開始早々それがいかに甘い過去のものかを少年や我々に思い知らせることとなり、雪崩を打って輸送トラックにもぐりこみ英仏間のトンネルを渡ろうとする密航者を捕らえるべくより科学的効率的なCO2探知で当局が対抗するその裏をかく自殺行為すれすれのビニールバッグかぶりにこれまで8年の差を垣間見るようであり、当時はこのような行動そのものがその日の食事を提供するボランティアと密入国者だけのものだったのが今ではそれらに対して同情的な市民までもこれに関わると幇助罪というおどしで難民達と市民を隔離しようとする政策の実際が示され当時からより深刻化した移民政策の程度をも示している。
そして嘗ての移民の息子を今大統領に掲げ人権保護を世界に誇ってきたフランスの二枚舌の象徴ともみられるのが本作中、水泳コーチのアパートの向かいの住人の玄関にしかれたシートの文字 Welcome であり、その部屋の住人の態度に経済不況の中で失業、年金の減額、警察国家に向かうような国で怯える市民の姿をみるようであり、これが本作の眼目であって、ここでの少年の愛の物語はいわば刺身のつまでさえある。 だから大陸が地続きであり歩いて何カ国も渡って来てここからは泳いで恋人に会いに行くという少年の愛の物語をロマンチックな題に翻訳する国には祖国を棄て、逃れ、離れていく者やそれを扱いかねるそれぞれの受け入れ国の人々の屈託は大陸や半島からの移民が多いことが歴史の事実であるとしてもそれを見てみぬふりともみられかねぬメディアのそぶりとシンクロしていると見られてもそれには異存はないだろう。 いずれにしても他所の国の問題なのだ。 それを如実に示すのが本作中テレビの画面に一瞬写るサルコジ大統領のスピーチであるといえるだろう。
それにしてもこういう世界でも、というかこういうぎりぎりの世界だからこそかコミュニケーションとしての言語に英語が使われるのが特徴的だ。 これから50年経つと英語が中国語に取って代わられるという人があるがこういう問題で中国語が共通語になるには中国はこれから幾つものハードルを越さねばならないだろうと思われる。 今のところ経済弱者が雪崩をうって中国におしよせるという話は逆はあってもそういうことは聞いていない。 英語に話をもどすと当然、舞台ではドーバーを越えイギリスを目指す人々の集団であるから英語が話せなければ未来はない、ということもあるだろうが作中でも妻が英語教師という設定になっているものの実際には仕事を離れては殆んど聞くことはなく、逆に水泳コーチが危なっかしい訥々の英語で少年と意思の疎通を図るというところにも工夫がなされているようだ。 私事、30年以上前、パリ北駅の案内所でまともに英語が話せる者がいないことを経験して驚いたものが、その後10年づつ経つにしたがってパリの夜中に路頭で警官と英語でよもやま話が出来るようになったこと、その後田舎の大きなスーパーには必ずちゃんとした英語が話せるものがいるようになった近年、世界言語としての英語がフランス語防御というか自国語を守る世界的な牙城にもなっているといわれていたフランスに徐々に浸透したことに、いささか自国語保護に耐性疲労が見え、まだ少しはパックスアメリカーナが続くことが感じられる現在、新天地を目指すものは英語圏の国を目指すということもわかるような気がするのだが、住んでみればイギリスが必ずしも夢見たような住みやすい国とはいえないことも分かるのだろうが命を懸けた二者択一の場ではそれを知る由もないということだろう。
何週間か前に80の半ばでイギリスからフランスまで泳ぎきった女性の話をテレビで観たのだが、この女性は30半ばぐらいで海峡横断を試み失敗していて今回再チャレンジでの成功だったのだがここでは年齢はほぼ関係がないだろう。 それについては様々に研究や経験のデータがあるのだから予め周到な準備もし、泳ぐこと自体がある意味では生涯の夢であり泳ぎきることに様々な保険をかけ伴走するコーチや食料の補給もあるのだから同じ泳ぐといってもここでの話とは次元が違う。 本作を見たものにはこの水泳コーチの同情心もわからないでもないとしてもそれを薦めるにあたっては無謀のそしりを受けても仕方がないだろう。 ま、しかしそれもストーリーのことである。 イギリスからフランスに泳ぐ話では大分前に観たイギリス映画もあったような気がする。 そこでは中年男が横断を試み泳ぎきることの意味が問われる話となっていたのではないか。 渋い俳優、Pete Postlethwaite が泳いだのではないかと思ったのだが他の俳優のものだったのかもしれずいずれにしてもそこでも複数のサポーターとともに周到の準備、助けのもとに行われていたのだった。
|
|
|
|
|
|
|
|
ヨーロッパ☆外国映画を観よう 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ヨーロッパ☆外国映画を観ようのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170662人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89526人