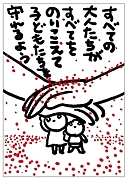日本の事故評価や安全基準は、IAEAやICRPなどの国際原子力機関の評価や基準がベースとなっているが、その国際原子力機関の評価や基準の実態もこんなもんだ。
日本国政府(省庁)及び行政は、日本国憲法の概念に則って「全ての国民=全ての納税者(消費税含む)とその家族」に健康被害が及ばぬよう対応する義務と責任がある。
いわゆる「統計的な少数切り捨ての理屈」は、日本国政府(省庁)及び行政には適用されないのであって、原発事故の事後対応はひとりの被曝被害を出してはならない。
従って事故原発に対する日本国政府(省庁)及び行政の対応は、安全基準は本より、避難指定地域、瓦礫処理問題も含めてその義務と責任を果たしていないと断言出来る。
-------------------------------------------------------------------------------------
■IAEAチェルノブイリ事故安全宣言の実態
【重松逸造】
汚染がひどいところには入らずに、しかも遠くから食料を持参して現地のものを口にしないで、それでいてチェルノブイリ事故への安全宣言を出した当時のIAEA事故調査委員長。
1991年、チェルノブイリ事故への安全宣言を出したのはIAEA。当時のIAEA事故調査委員長を務めたのは重松逸造。重松氏の調査は被害が大きい地域に入らずにおこなわれた。当時のドキュメンタリー番組の一部を文字におこした。(動画6:40から)
【原発事故】安全宣言のカラクリ そして子供になにが起きたか追跡
http://
櫻井「広河さん、こうして見ますとね、国際原子力機関が住民の影響に問題ないと発表したのは、一体なんだったんでしょうかね」
広河「VTRの中でも名前が出てましたけどね、調査団長は重松さんっていって広島の学者なんですね。国連の機関、しかも広島の医学者がリーダーになったから公正な調査があると信じてたのに安全だと発表したので現地の人々は唖然としています。」
櫻井「ただ調査団の人たちは、現地の情報を見たんですか?」
広河「現地のお医者さんの話では、汚染がひどいところには入ってないそうなんですね。しかも遠くから、食料を持参して現地のものを口にしないで、それでいて安全宣言をしたことで、すごい怒ってたんですね。怖くって、それで食べられないんだったら、危険だというべきなんです」
櫻井「もう、この国際原子力機関の信用性そのものが、深刻に問われてるわけなんですねえ」
広河「ええ。あのちょうど旧ソ連の原子力産業と、アメリカを中心とする原子力産業が、ビジネスとしての取引を始めたころから、チェルノブイリの被害を小さく見せることで、利害が一致したんじゃないかってい言う声があります」
櫻井「うんうん、なるほど、次回は汚染地域の生活を追います」
【IAEA(国際原子力機関)】
団体種類 国際機関
設立 1957年
所在地 オーストリア ウィーン
Wagramer Strasse 5, A-1400 Vienna, Austria
主要人物 天野之弥(事務局長)
活動内容 原子力技術の平和利用の促進、軍事転用の監視・防止
ウェブサイト http://
国際原子力機関(こくさいげんしりょくきかん、英: International Atomic Energy Agency、略称:IAEA)は、国際連合傘下の自治機関であり、原子力の平和利用を促進し、軍事転用されないための保障措置の実施をする国際機関である。2005年度のノーベル平和賞を、当時の事務局長モハメド・エルバラダイとともに受賞した。本部はオーストリアのウィーンにある。またトロントと東京の2ヶ所に地域事務所と、ニューヨークとジュネーヴに連絡室がある。
【広島の御用医師「重松逸造」】
1941年に東京帝大医学部卒業。金沢大医学部教授(公衆衛生学)、国立公衆衛生院疫学部長などを経て、81〜97年に放影研理事長。WHO(世 界保健機関)上級諮問委員会委員、ICRP(国際放射線防護委員会)第1委員会・主委員会委員、IAEA(国際原子力機関)チェルノブイリ計画国際諮問委 員長、厚生省原爆障害症調査研究班長などを歴任、イタイイタイ病など多くの公害の研究にも関わった。「疫学とはなにか」(講談社)など多数の著書がある。原爆投下後に降った「黒い雨」を巡っては、広島県・市設置の専門家会議の座長を務め、放射線による人体影響を「認められない」とする報告書(91年)を出した。
※御用医師「重松逸造」の軌跡
・ 「環境庁の水俣病調査中間報告「頭髪水銀値は正常」、論議必至。(一九九一年六月二三日付読売新聞)重松氏は水俣病の調査責任者で「水俣病被害者とチッソの因果関係はない」と発表。
・「黒い雨「人体影響認められず」広島県、広島市共同設置の「黒い雨に関する専門家会議」(座長・重松逸造・放射線影響研究所長、十二人)は、十三日、「人体影響を明確に示唆するデータは得られなかった」との調査結果をまとめた。(一九九一年五月一四日付毎日新聞)ここでも重松氏は調査責任者。
・「イタイイタイ病について環境庁の委託で原因を調査していた「イタイイタイ病およびカドミウム中毒に関する総合研究班(会長・重松逸造放射線影響研究所理事長)とし、イ病の発症過程を解明するに至らなかった。イ病では、認定患者百五十人のうち、既に百三十四人が激痛の中で死亡している」(一九八九年四月九日付読売新聞。)
・岡山スモンの記録「スモン研究の思い出。前厚生省スモン調査研究班々長重松逸造。結局は後で原因と判明したキノホルムに到達することができませんでした」重松氏はスモン調査の責任者でありましたが、キノホルムの因果関係はないと発表。
・九三年一月一三日、岡山県の動燃人形峠事業所が計画している大規模な回収ウラン転換試験の安全性を審査していた「環境放射線専門家会議」(重松逸造委員長)はゴーサインを出しました。
あらゆる公害問題においての政府・企業の利益になる決定に重松氏が責任者となっている。
【広島の御用医師「重松逸造」と対極の広島の医師「肥田舜太郎」】
肥田舜太郎(ひだしゅんたろう)
1917年広島生まれ。1944年陸軍医学校卒。軍医少尉として広島陸軍病院に赴任。1945年広島にて被ばく。被ばく者救援にあたる。全日本民医連理事、埼玉民医連会長などを歴任。全日本民医連会長などを歴任。全日本民医連顧問、日本被団協原爆被害者中央相談所理事長。鎌仲ひとみ氏との共著『内部被ばくの脅威』(ちくま新書)は内部被ばくのメカニズムを解き明かし、その脅威の実相に迫る
http://
【6/16 フジテレビ特ダネ 土壌汚染マップ,首都圏でも管理区域並み】
http://
-------------------------------------------------------------------------------------
■ICRP被曝安全基準の実態
【ICRPは放射能防護に関する国際的基準】
昭和31年(1956年)以降は世界保健機構(WHO)の諮問機関として放射線防護に関する国際的な基準を勧告してきた。ICRPの勧告は国際的に権威あるものとされ、我が国をはじめ、各国の放射線防護基準の基本として採用されている。ICRP「国際放射線防護委員会」のスポンサーは全て各国の原子力推進機関。
【ICRP名誉委員A】
「低線量のリスクなどどうせわからないのだから、(危険度を)半分に減らしたところで大した問題ではない」
【ICRP名誉委員B】
「(ICRPの被曝基準に)科学的な根拠などない。我々の判断で決めたのだ」
【ICRP「国際放射線防護委員会」のスポンサー】
1:米国原子力規制委員会 25万ドル
2:欧州共同体委員会 13万500ドル
3:ドイツ原子力安全省 11万5千ドル
4:日本原子力研究開発機構 4万5千ドル
5:カナダ原子力安全委員会 4万ドル
------------------------------------
年間予算合計 約62万ドル
【ICRP(国際放射線防護委員会)】
国際放射線防護委員会(こくさいほうしゃせんぼうごいいんかい、英: International Commission on Radiological Protection、ICRP)は、専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う民間の国際学術組織である。ICRPはイギリスの非営利団体(NPO)として公認の慈善団体であり、科学事務局の所在地はカナダのオタワに設けられている。 助成金の拠出機関は、国際原子力機関や経済協力開発機構原子力機関などの原子力機関をはじめ、世界保健機構、ISRや国際放射線防護学会(International Radiation Protection Association; IRPA)などの放射線防護に関する学会、イギリス、アメリカ、欧州共同体、スウェーデン、日本、アルゼンチン、カナダなどの各国内にある機関からなされている。
-------------------------------------------------------------------------------------
小出裕章さん『隠される原子力』
http://
日本国政府(省庁)及び行政は、日本国憲法の概念に則って「全ての国民=全ての納税者(消費税含む)とその家族」に健康被害が及ばぬよう対応する義務と責任がある。
いわゆる「統計的な少数切り捨ての理屈」は、日本国政府(省庁)及び行政には適用されないのであって、原発事故の事後対応はひとりの被曝被害を出してはならない。
従って事故原発に対する日本国政府(省庁)及び行政の対応は、安全基準は本より、避難指定地域、瓦礫処理問題も含めてその義務と責任を果たしていないと断言出来る。
-------------------------------------------------------------------------------------
■IAEAチェルノブイリ事故安全宣言の実態
【重松逸造】
汚染がひどいところには入らずに、しかも遠くから食料を持参して現地のものを口にしないで、それでいてチェルノブイリ事故への安全宣言を出した当時のIAEA事故調査委員長。
1991年、チェルノブイリ事故への安全宣言を出したのはIAEA。当時のIAEA事故調査委員長を務めたのは重松逸造。重松氏の調査は被害が大きい地域に入らずにおこなわれた。当時のドキュメンタリー番組の一部を文字におこした。(動画6:40から)
【原発事故】安全宣言のカラクリ そして子供になにが起きたか追跡
http://
櫻井「広河さん、こうして見ますとね、国際原子力機関が住民の影響に問題ないと発表したのは、一体なんだったんでしょうかね」
広河「VTRの中でも名前が出てましたけどね、調査団長は重松さんっていって広島の学者なんですね。国連の機関、しかも広島の医学者がリーダーになったから公正な調査があると信じてたのに安全だと発表したので現地の人々は唖然としています。」
櫻井「ただ調査団の人たちは、現地の情報を見たんですか?」
広河「現地のお医者さんの話では、汚染がひどいところには入ってないそうなんですね。しかも遠くから、食料を持参して現地のものを口にしないで、それでいて安全宣言をしたことで、すごい怒ってたんですね。怖くって、それで食べられないんだったら、危険だというべきなんです」
櫻井「もう、この国際原子力機関の信用性そのものが、深刻に問われてるわけなんですねえ」
広河「ええ。あのちょうど旧ソ連の原子力産業と、アメリカを中心とする原子力産業が、ビジネスとしての取引を始めたころから、チェルノブイリの被害を小さく見せることで、利害が一致したんじゃないかってい言う声があります」
櫻井「うんうん、なるほど、次回は汚染地域の生活を追います」
【IAEA(国際原子力機関)】
団体種類 国際機関
設立 1957年
所在地 オーストリア ウィーン
Wagramer Strasse 5, A-1400 Vienna, Austria
主要人物 天野之弥(事務局長)
活動内容 原子力技術の平和利用の促進、軍事転用の監視・防止
ウェブサイト http://
国際原子力機関(こくさいげんしりょくきかん、英: International Atomic Energy Agency、略称:IAEA)は、国際連合傘下の自治機関であり、原子力の平和利用を促進し、軍事転用されないための保障措置の実施をする国際機関である。2005年度のノーベル平和賞を、当時の事務局長モハメド・エルバラダイとともに受賞した。本部はオーストリアのウィーンにある。またトロントと東京の2ヶ所に地域事務所と、ニューヨークとジュネーヴに連絡室がある。
【広島の御用医師「重松逸造」】
1941年に東京帝大医学部卒業。金沢大医学部教授(公衆衛生学)、国立公衆衛生院疫学部長などを経て、81〜97年に放影研理事長。WHO(世 界保健機関)上級諮問委員会委員、ICRP(国際放射線防護委員会)第1委員会・主委員会委員、IAEA(国際原子力機関)チェルノブイリ計画国際諮問委 員長、厚生省原爆障害症調査研究班長などを歴任、イタイイタイ病など多くの公害の研究にも関わった。「疫学とはなにか」(講談社)など多数の著書がある。原爆投下後に降った「黒い雨」を巡っては、広島県・市設置の専門家会議の座長を務め、放射線による人体影響を「認められない」とする報告書(91年)を出した。
※御用医師「重松逸造」の軌跡
・ 「環境庁の水俣病調査中間報告「頭髪水銀値は正常」、論議必至。(一九九一年六月二三日付読売新聞)重松氏は水俣病の調査責任者で「水俣病被害者とチッソの因果関係はない」と発表。
・「黒い雨「人体影響認められず」広島県、広島市共同設置の「黒い雨に関する専門家会議」(座長・重松逸造・放射線影響研究所長、十二人)は、十三日、「人体影響を明確に示唆するデータは得られなかった」との調査結果をまとめた。(一九九一年五月一四日付毎日新聞)ここでも重松氏は調査責任者。
・「イタイイタイ病について環境庁の委託で原因を調査していた「イタイイタイ病およびカドミウム中毒に関する総合研究班(会長・重松逸造放射線影響研究所理事長)とし、イ病の発症過程を解明するに至らなかった。イ病では、認定患者百五十人のうち、既に百三十四人が激痛の中で死亡している」(一九八九年四月九日付読売新聞。)
・岡山スモンの記録「スモン研究の思い出。前厚生省スモン調査研究班々長重松逸造。結局は後で原因と判明したキノホルムに到達することができませんでした」重松氏はスモン調査の責任者でありましたが、キノホルムの因果関係はないと発表。
・九三年一月一三日、岡山県の動燃人形峠事業所が計画している大規模な回収ウラン転換試験の安全性を審査していた「環境放射線専門家会議」(重松逸造委員長)はゴーサインを出しました。
あらゆる公害問題においての政府・企業の利益になる決定に重松氏が責任者となっている。
【広島の御用医師「重松逸造」と対極の広島の医師「肥田舜太郎」】
肥田舜太郎(ひだしゅんたろう)
1917年広島生まれ。1944年陸軍医学校卒。軍医少尉として広島陸軍病院に赴任。1945年広島にて被ばく。被ばく者救援にあたる。全日本民医連理事、埼玉民医連会長などを歴任。全日本民医連会長などを歴任。全日本民医連顧問、日本被団協原爆被害者中央相談所理事長。鎌仲ひとみ氏との共著『内部被ばくの脅威』(ちくま新書)は内部被ばくのメカニズムを解き明かし、その脅威の実相に迫る
http://
【6/16 フジテレビ特ダネ 土壌汚染マップ,首都圏でも管理区域並み】
http://
-------------------------------------------------------------------------------------
■ICRP被曝安全基準の実態
【ICRPは放射能防護に関する国際的基準】
昭和31年(1956年)以降は世界保健機構(WHO)の諮問機関として放射線防護に関する国際的な基準を勧告してきた。ICRPの勧告は国際的に権威あるものとされ、我が国をはじめ、各国の放射線防護基準の基本として採用されている。ICRP「国際放射線防護委員会」のスポンサーは全て各国の原子力推進機関。
【ICRP名誉委員A】
「低線量のリスクなどどうせわからないのだから、(危険度を)半分に減らしたところで大した問題ではない」
【ICRP名誉委員B】
「(ICRPの被曝基準に)科学的な根拠などない。我々の判断で決めたのだ」
【ICRP「国際放射線防護委員会」のスポンサー】
1:米国原子力規制委員会 25万ドル
2:欧州共同体委員会 13万500ドル
3:ドイツ原子力安全省 11万5千ドル
4:日本原子力研究開発機構 4万5千ドル
5:カナダ原子力安全委員会 4万ドル
------------------------------------
年間予算合計 約62万ドル
【ICRP(国際放射線防護委員会)】
国際放射線防護委員会(こくさいほうしゃせんぼうごいいんかい、英: International Commission on Radiological Protection、ICRP)は、専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う民間の国際学術組織である。ICRPはイギリスの非営利団体(NPO)として公認の慈善団体であり、科学事務局の所在地はカナダのオタワに設けられている。 助成金の拠出機関は、国際原子力機関や経済協力開発機構原子力機関などの原子力機関をはじめ、世界保健機構、ISRや国際放射線防護学会(International Radiation Protection Association; IRPA)などの放射線防護に関する学会、イギリス、アメリカ、欧州共同体、スウェーデン、日本、アルゼンチン、カナダなどの各国内にある機関からなされている。
-------------------------------------------------------------------------------------
小出裕章さん『隠される原子力』
http://
|
|
|
|
コメント(7)
「被曝リスク基準」は信用できるか?(上)ICRPに欠ける「科学性」と「合理性」
2012/03/29
塩谷喜雄 Shioya Yoshio
科学ジャーナリスト
福島第一原発敷地内での作業後、放射線量の測定を受ける男性(c)時事
東京電力・福島第一原子力発電所が、周辺地域に大量放出した放射性物質による被曝が「ただちに健康に影響はない」根拠として、東電と政府は、国際放射線防護委員会(ICRP)の示す国際基準を繰り返し挙げている。これは明らかな誤用、誤解である。
ICRP勧告が示す被曝線量限度は、それ以下なら安全・安心という個人を守る「健康基準」ではない。為政者、事業者、管理者が、作業員や一般公衆にどれだけのリスクを強いても許されるかという、「受忍の限度」を示す基準である。しかも、その数値については、最新の科学的検討が反映されておらず、事業者寄りのバイアスがかかっているとして、科学性と合理性の両面に強い批判があることも、日本国内ではあまり知らされていない。こと原子力に関する限り、国際機関への無条件の信頼は、かえって危機を増幅させる。
ツギハギの国際基準
3.11以来、放射線の人体への影響について、一方的で断片的な言葉がメディアを飛び交っている。一番有名なのは先に挙げた「ただちに健康に影響はない」で、「放射線の発がん性はタバコの1万分の1」などというのもあった。
原子力を取材していて、いつも感じるのは、放射線安全、放射線防護の基準や規則が、国際基準も含めて、いかにもツギハギだということだ。もっともらしいのだが、よく考えると、科学性と合理性に欠けている。
典型的なのは、一般公衆と、原発作業員や放射線技師など放射線作業従事者との「年間被曝線量限度」の差である。一般公衆の場合は「環境被曝」と呼ばれ、関連従事者の場合は「職業被曝」という。
3.11前は日本では環境被曝の年間許容線量は1ミリシーベルトで、職業被曝は年間最大50ミリシーベルトで50倍だった。3.11後、政府は職業被曝の年間許容線量を250ミリシーベルトに上げ、環境被曝は20ミリシーベルトとした。
どちらもICRPの基準に沿っているので、これを守っていれば安全・安心だと、政府、電力会社、学者、メディアが言ってきた。人間の健康と命に直結する基準なのだから、豆腐の上に建つおから原発の安全神話とは違って、虚構の積み重ねではないことを願いたいが、残念ながらこちらも相当に怪しい。
2012/03/29
塩谷喜雄 Shioya Yoshio
科学ジャーナリスト
福島第一原発敷地内での作業後、放射線量の測定を受ける男性(c)時事
東京電力・福島第一原子力発電所が、周辺地域に大量放出した放射性物質による被曝が「ただちに健康に影響はない」根拠として、東電と政府は、国際放射線防護委員会(ICRP)の示す国際基準を繰り返し挙げている。これは明らかな誤用、誤解である。
ICRP勧告が示す被曝線量限度は、それ以下なら安全・安心という個人を守る「健康基準」ではない。為政者、事業者、管理者が、作業員や一般公衆にどれだけのリスクを強いても許されるかという、「受忍の限度」を示す基準である。しかも、その数値については、最新の科学的検討が反映されておらず、事業者寄りのバイアスがかかっているとして、科学性と合理性の両面に強い批判があることも、日本国内ではあまり知らされていない。こと原子力に関する限り、国際機関への無条件の信頼は、かえって危機を増幅させる。
ツギハギの国際基準
3.11以来、放射線の人体への影響について、一方的で断片的な言葉がメディアを飛び交っている。一番有名なのは先に挙げた「ただちに健康に影響はない」で、「放射線の発がん性はタバコの1万分の1」などというのもあった。
原子力を取材していて、いつも感じるのは、放射線安全、放射線防護の基準や規則が、国際基準も含めて、いかにもツギハギだということだ。もっともらしいのだが、よく考えると、科学性と合理性に欠けている。
典型的なのは、一般公衆と、原発作業員や放射線技師など放射線作業従事者との「年間被曝線量限度」の差である。一般公衆の場合は「環境被曝」と呼ばれ、関連従事者の場合は「職業被曝」という。
3.11前は日本では環境被曝の年間許容線量は1ミリシーベルトで、職業被曝は年間最大50ミリシーベルトで50倍だった。3.11後、政府は職業被曝の年間許容線量を250ミリシーベルトに上げ、環境被曝は20ミリシーベルトとした。
どちらもICRPの基準に沿っているので、これを守っていれば安全・安心だと、政府、電力会社、学者、メディアが言ってきた。人間の健康と命に直結する基準なのだから、豆腐の上に建つおから原発の安全神話とは違って、虚構の積み重ねではないことを願いたいが、残念ながらこちらも相当に怪しい。
被曝許容量50倍の根拠
許容線量が人の健康を保つための基準だとすれば、その値が人によって50倍も違うのはなぜだろう、という素朴な疑問からまず考えてみよう。
年齢、性別、妊娠の有無などによって、生物学的・医学的な「放射線に対する感受性」と「被曝の影響」が違うことは知られている。事実、職業被曝については性別や妊娠の有無で線量限度を変えている。感受性と影響によってグループ分けして、きめ細かく許容線量を設定する、というのなら、健康を守る基準としては至極まともだ。
職業で基準を分ける意味は何だろう。放射線技師や原発の作業者は、放射線に対し一般公衆の50倍もの耐性を持っている、とでもいうのだろうか。防護服などの装備や各種の安全システムも、被曝を避けるためのもので、被曝した後でその健康への影響を緩和する機能を備えているわけではない。
一般公衆と放射線作業従事者の許容線量が50倍も違う最大の理由は、原子力や放射線の「利用技術」が著しく未熟なことである。放射性物質の持つリスクを、ほぼ完璧にコントロールできるなら、システムの運転者も一般公衆も、健康基準としての許容線量は同じでなくてはならない。
残念ながら、実際には、放射性物質を利用する時、様々な「リーク=漏れ」が存在する。漏れるのは、放射線であったり、その線源である放射性物質であったりする。事故がなくても、原発や核燃料の再処理工場などからは、周辺環境に、わずかだが放射性物質が放出され続けている。
技術の未熟さを覆うダブルスタンダード
原発の敷地内や放射線源の近くで働く運転者、作業者は当然、一般公衆より高い線量を実際に浴びる。やむなく、職業被曝と環境被曝という別の基準、典型的なダブルスタンダードを設け、技術的未熟を科学的な意匠を凝らした「制度」で上手にくるんでしまった。二重基準は、原子力技術が抱える決定的な弱点を覆い隠す苦肉の策、高踏的「ぼろ隠し」といえるかもしれない。
繰り返すが、ICRPの線量限度という基準は、それを守ってさえいれば安全、安心という値ではない。もともと「受忍すべきリスク」として設定されている。統治する側、管理する側が、住民や作業者にどれくらいの我慢を強いても許されるか、という数値だと胆に銘じておく必要がある。
これはICRP自身が認めている。一人ひとりの健康を放射線の影響から守るための基準というより、「政策判断」の目安を提供する数値だと……。
社会はその数値を受け入れることで、作業者らの高い被曝リスクと引き換えに、技術が未熟なままの原子力エネルギーや医療放射線を利用している、という構図である。
本来なら、原子力は高いリスクと引き換えのエネルギー源であるという認識を、社会は共有しなければならない。しかし、学校で教えているのは、「基準を守っているから安全」という、「雨が降ったら天気が悪い」というのと同じくらい、無意味な安全神話だ。
許容線量が人の健康を保つための基準だとすれば、その値が人によって50倍も違うのはなぜだろう、という素朴な疑問からまず考えてみよう。
年齢、性別、妊娠の有無などによって、生物学的・医学的な「放射線に対する感受性」と「被曝の影響」が違うことは知られている。事実、職業被曝については性別や妊娠の有無で線量限度を変えている。感受性と影響によってグループ分けして、きめ細かく許容線量を設定する、というのなら、健康を守る基準としては至極まともだ。
職業で基準を分ける意味は何だろう。放射線技師や原発の作業者は、放射線に対し一般公衆の50倍もの耐性を持っている、とでもいうのだろうか。防護服などの装備や各種の安全システムも、被曝を避けるためのもので、被曝した後でその健康への影響を緩和する機能を備えているわけではない。
一般公衆と放射線作業従事者の許容線量が50倍も違う最大の理由は、原子力や放射線の「利用技術」が著しく未熟なことである。放射性物質の持つリスクを、ほぼ完璧にコントロールできるなら、システムの運転者も一般公衆も、健康基準としての許容線量は同じでなくてはならない。
残念ながら、実際には、放射性物質を利用する時、様々な「リーク=漏れ」が存在する。漏れるのは、放射線であったり、その線源である放射性物質であったりする。事故がなくても、原発や核燃料の再処理工場などからは、周辺環境に、わずかだが放射性物質が放出され続けている。
技術の未熟さを覆うダブルスタンダード
原発の敷地内や放射線源の近くで働く運転者、作業者は当然、一般公衆より高い線量を実際に浴びる。やむなく、職業被曝と環境被曝という別の基準、典型的なダブルスタンダードを設け、技術的未熟を科学的な意匠を凝らした「制度」で上手にくるんでしまった。二重基準は、原子力技術が抱える決定的な弱点を覆い隠す苦肉の策、高踏的「ぼろ隠し」といえるかもしれない。
繰り返すが、ICRPの線量限度という基準は、それを守ってさえいれば安全、安心という値ではない。もともと「受忍すべきリスク」として設定されている。統治する側、管理する側が、住民や作業者にどれくらいの我慢を強いても許されるか、という数値だと胆に銘じておく必要がある。
これはICRP自身が認めている。一人ひとりの健康を放射線の影響から守るための基準というより、「政策判断」の目安を提供する数値だと……。
社会はその数値を受け入れることで、作業者らの高い被曝リスクと引き換えに、技術が未熟なままの原子力エネルギーや医療放射線を利用している、という構図である。
本来なら、原子力は高いリスクと引き換えのエネルギー源であるという認識を、社会は共有しなければならない。しかし、学校で教えているのは、「基準を守っているから安全」という、「雨が降ったら天気が悪い」というのと同じくらい、無意味な安全神話だ。
ICRPは一種の「国際NPO」
ご都合主義のダブルスタンダードを「国際基準」として提唱している本家本元がICRPである。ここが発する「勧告」に準拠して、各国はそれぞれ自国の安全基準を設けている。ICRPは、国際学術団体だが、各国政府の政策を法的に拘束するような権限を持つ国際機関ではない。一種の国際NPOである。
出自は1928年にさかのぼる。X線やラジウムなど、放射線や放射性物質を扱う研究者、医学者が集まって、それらを扱う際の安全基準を検討する組織を設けることを決めた。原爆が登場する前で、一般公衆の被曝など全くの想定外で、目的はもっぱら職業被曝のリスク軽減、放射線の生体影響の科学的研究だった。
それが第2次大戦後、一変した。広島、長崎の後、米国は突然原子力の平和利用を提唱し、一方で、核保有国による核実験が相次いだ。当然、一般公衆の被曝リスクは高くなり、反核運動も広がる。
特に、広島、長崎の被爆者が受けた放射線による障害については、世界的に関心が高く、その評価は国際的な原子力政策の焦点だった。
1950年、X線とラジウムだけでなく、電離作用を持つ放射線全てについて、利用と被曝のリスクの関係を科学的に評価する学術団体に衣替えして、ICRPは再スタートした。
ひたすら「緩める」方向に進んできた基本原則
繰り返すが、ICRPが示している線量限度という考え方の根底には、社会的、経済的に、放射線利用によって誰もが何がしかの利益、便益を受けているのだから、被曝による影響もそれなりに我慢・受容すべきだという論理が貫かれている。便益と費用・リスク負担の関係を、放射線被曝と健康影響にも持ち込んだ、といえるかもしれない。
それは、ICRPの基準作りの基本原則の変遷からも、明瞭に読み取れる。1954年には許容線量は「TO THE LOWEST REVEL AS POSSIBLE=可能な限り低く」設定するとしていたが、56年には「AS LOW AS PRACTICABLE=実現可能な限り低く」に一歩後退した。
65年には「AS LOW AS READILY ACHIEVABLE=現実的に達成できる範囲で低く」と、さらにハードルを下げ、「経済的、社会的考慮」を計算に入れるという文言まで付記した。そして、直近の変更は73年。「AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE=合理的に達成できる範囲で低く」と、一段と穏やかに、丸くなった。
この先、行きつくところは「AS REASONABLE AS POSSIBLE=可能な限り安上がりに」ではなかろうか。否、実際の規制基準はとっくにその域に到達していて、核施設や原発は経済性を最優先して運営されているのかもしれない。
ささいなリスクを言い立てて、事業者が撤退するしかないほどの厳しい基準を作っても、実質的な意味はない。基準の提示にあたっては、当然、誠実な管理者ならば合理的に達成できる範囲であることも、十分配慮すべきだと思う。
とはいえ、ICRPの哲学の変遷は一方向に一直線、ひたすら「緩める」方向に動いてきたのが、かなり引っかかる。科学的知見が積み重なれば、原理・原則も移ろうのは当然だが、それに伴う「揺れ」や「揺れ戻し」が全くなく、ひたすら一方向というのは、科学とは違うある種の意志が働いているようにも映る。
ご都合主義のダブルスタンダードを「国際基準」として提唱している本家本元がICRPである。ここが発する「勧告」に準拠して、各国はそれぞれ自国の安全基準を設けている。ICRPは、国際学術団体だが、各国政府の政策を法的に拘束するような権限を持つ国際機関ではない。一種の国際NPOである。
出自は1928年にさかのぼる。X線やラジウムなど、放射線や放射性物質を扱う研究者、医学者が集まって、それらを扱う際の安全基準を検討する組織を設けることを決めた。原爆が登場する前で、一般公衆の被曝など全くの想定外で、目的はもっぱら職業被曝のリスク軽減、放射線の生体影響の科学的研究だった。
それが第2次大戦後、一変した。広島、長崎の後、米国は突然原子力の平和利用を提唱し、一方で、核保有国による核実験が相次いだ。当然、一般公衆の被曝リスクは高くなり、反核運動も広がる。
特に、広島、長崎の被爆者が受けた放射線による障害については、世界的に関心が高く、その評価は国際的な原子力政策の焦点だった。
1950年、X線とラジウムだけでなく、電離作用を持つ放射線全てについて、利用と被曝のリスクの関係を科学的に評価する学術団体に衣替えして、ICRPは再スタートした。
ひたすら「緩める」方向に進んできた基本原則
繰り返すが、ICRPが示している線量限度という考え方の根底には、社会的、経済的に、放射線利用によって誰もが何がしかの利益、便益を受けているのだから、被曝による影響もそれなりに我慢・受容すべきだという論理が貫かれている。便益と費用・リスク負担の関係を、放射線被曝と健康影響にも持ち込んだ、といえるかもしれない。
それは、ICRPの基準作りの基本原則の変遷からも、明瞭に読み取れる。1954年には許容線量は「TO THE LOWEST REVEL AS POSSIBLE=可能な限り低く」設定するとしていたが、56年には「AS LOW AS PRACTICABLE=実現可能な限り低く」に一歩後退した。
65年には「AS LOW AS READILY ACHIEVABLE=現実的に達成できる範囲で低く」と、さらにハードルを下げ、「経済的、社会的考慮」を計算に入れるという文言まで付記した。そして、直近の変更は73年。「AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE=合理的に達成できる範囲で低く」と、一段と穏やかに、丸くなった。
この先、行きつくところは「AS REASONABLE AS POSSIBLE=可能な限り安上がりに」ではなかろうか。否、実際の規制基準はとっくにその域に到達していて、核施設や原発は経済性を最優先して運営されているのかもしれない。
ささいなリスクを言い立てて、事業者が撤退するしかないほどの厳しい基準を作っても、実質的な意味はない。基準の提示にあたっては、当然、誠実な管理者ならば合理的に達成できる範囲であることも、十分配慮すべきだと思う。
とはいえ、ICRPの哲学の変遷は一方向に一直線、ひたすら「緩める」方向に動いてきたのが、かなり引っかかる。科学的知見が積み重なれば、原理・原則も移ろうのは当然だが、それに伴う「揺れ」や「揺れ戻し」が全くなく、ひたすら一方向というのは、科学とは違うある種の意志が働いているようにも映る。
科学的根拠に疑問符
1960年代から原子力産業の勃興と核開発競争を背景に、ICRPにも核開発と原子力産業に関係する科学者が増え、産業の視点や核開発政策と統治の原理などが科学の上に覆いかぶさり、基準作りに反映するようになる。多角的な視点からの検討という意味では、ある種の前進ともいえるかもしれないが、科学的な厳密性、実証性が大きく損なわれたことも事実だ。
問題は、基準に経済性や社会的合理性を取り入れるという流れが、事業者や行政にとって望ましい合理性だけに偏っていないか、という懸念である。「可能な限り低く」という、当初の簡にして明、凛とした姿勢を、なぜ変えねばならなかったのか。
「合理的に達成できる範囲で低く」というのは、守れないような厳格な基準は設けませんよ、と初めから宣言して、為政者や管理者の論理にただ寄り添うものでしかないのではないか。
妙に物わかりのいい好々爺風の口ぶりの裏に、核をめぐる政治・経済の思惑、実際に発生した作業者の健康被害や周辺環境の汚染を封印する胡乱なものを感じてしまうのは、筆者の思い過ごしだろうか。基準を超えたらシステムを「止める」という選択肢をはなから放棄した「国際基準」が、有効に働くとは思えない。
ただ、ICRPの示す基準が、放射線被曝のリスク評価、リスク管理に、一定の役割を果たしてきたことは否定しない。実験による検証が難しい分野で、リスクの推定、健康影響の科学的評価を進めてきた、という「歴史的」意味は大きい。
しかし、現在只今の活動に対しての、科学的信頼性はかなり低い。基準値や許容量の数字と、その算定方法について、多くの研究者、科学者から反論・異論が出ている。国際的に問われているのは、ICRPの抽象的な「姿勢」などではなく、具体的な基準の「科学的根拠」である。
最新の分子生物学が解明しつつある遺伝子レベルでの発がんメカニズムの知見や、チェルノブイリ事故による広範囲にわたる被曝影響の評価も、ICRPは基準数値にほとんど反映させていない。
科学が決めた客観的な安全基準だと、政府や電力会社が言い続けてきたICRPの基準は、実はずっと、その科学的根拠に疑問符が付いていたことは、学界では周知の事実である。
1960年代から原子力産業の勃興と核開発競争を背景に、ICRPにも核開発と原子力産業に関係する科学者が増え、産業の視点や核開発政策と統治の原理などが科学の上に覆いかぶさり、基準作りに反映するようになる。多角的な視点からの検討という意味では、ある種の前進ともいえるかもしれないが、科学的な厳密性、実証性が大きく損なわれたことも事実だ。
問題は、基準に経済性や社会的合理性を取り入れるという流れが、事業者や行政にとって望ましい合理性だけに偏っていないか、という懸念である。「可能な限り低く」という、当初の簡にして明、凛とした姿勢を、なぜ変えねばならなかったのか。
「合理的に達成できる範囲で低く」というのは、守れないような厳格な基準は設けませんよ、と初めから宣言して、為政者や管理者の論理にただ寄り添うものでしかないのではないか。
妙に物わかりのいい好々爺風の口ぶりの裏に、核をめぐる政治・経済の思惑、実際に発生した作業者の健康被害や周辺環境の汚染を封印する胡乱なものを感じてしまうのは、筆者の思い過ごしだろうか。基準を超えたらシステムを「止める」という選択肢をはなから放棄した「国際基準」が、有効に働くとは思えない。
ただ、ICRPの示す基準が、放射線被曝のリスク評価、リスク管理に、一定の役割を果たしてきたことは否定しない。実験による検証が難しい分野で、リスクの推定、健康影響の科学的評価を進めてきた、という「歴史的」意味は大きい。
しかし、現在只今の活動に対しての、科学的信頼性はかなり低い。基準値や許容量の数字と、その算定方法について、多くの研究者、科学者から反論・異論が出ている。国際的に問われているのは、ICRPの抽象的な「姿勢」などではなく、具体的な基準の「科学的根拠」である。
最新の分子生物学が解明しつつある遺伝子レベルでの発がんメカニズムの知見や、チェルノブイリ事故による広範囲にわたる被曝影響の評価も、ICRPは基準数値にほとんど反映させていない。
科学が決めた客観的な安全基準だと、政府や電力会社が言い続けてきたICRPの基準は、実はずっと、その科学的根拠に疑問符が付いていたことは、学界では周知の事実である。
「ヨウ素10兆ベクレル」未公表=世界版SPEEDI試算−文科省、安全委連携不足
東京電力福島第1原発事故で、昨年3月15日、放射性物質の拡散予測データ「世界版SPEEDI」の試算結果で、千葉市内で計測されたヨウ素を基に推計した同原発からの放出量が毎時10兆ベクレルという高い値が出ていたにもかかわらず、文部科学省と原子力安全委員会の間で十分な連携が取られず、現在も公表されていないことが3日、分かった。
文科省や安全委によると、世界版SPEEDIは放出される放射性物質の拡散状況を半地球規模で予測するシステム。日本原子力研究開発機構が同システムを運用しており、昨年3月も文科省の依頼を受け、試算を行っていた。
それによると、昨年3月14日午後9時ごろに福島第1原発から放出されたヨウ素の量は毎時10兆ベクレル、セシウム134、137もそれぞれ同1兆ベクレルと推計された。
この試算データの評価について、文科省は安全委の担当と判断し、同16日に安全委へデータを送るよう同機構に指示した。同機構はメールに添付して送信したが、安全委は重要情報と認識せず、放置したという。同様にデータを受け取っていた文科省も、安全委に公表するよう連絡しなかった。(2012/04/03-12:49)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012040300430
東京電力福島第1原発事故で、昨年3月15日、放射性物質の拡散予測データ「世界版SPEEDI」の試算結果で、千葉市内で計測されたヨウ素を基に推計した同原発からの放出量が毎時10兆ベクレルという高い値が出ていたにもかかわらず、文部科学省と原子力安全委員会の間で十分な連携が取られず、現在も公表されていないことが3日、分かった。
文科省や安全委によると、世界版SPEEDIは放出される放射性物質の拡散状況を半地球規模で予測するシステム。日本原子力研究開発機構が同システムを運用しており、昨年3月も文科省の依頼を受け、試算を行っていた。
それによると、昨年3月14日午後9時ごろに福島第1原発から放出されたヨウ素の量は毎時10兆ベクレル、セシウム134、137もそれぞれ同1兆ベクレルと推計された。
この試算データの評価について、文科省は安全委の担当と判断し、同16日に安全委へデータを送るよう同機構に指示した。同機構はメールに添付して送信したが、安全委は重要情報と認識せず、放置したという。同様にデータを受け取っていた文科省も、安全委に公表するよう連絡しなかった。(2012/04/03-12:49)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012040300430
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
■危機管理@放射能情報倉庫 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
■危機管理@放射能情報倉庫のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170669人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人