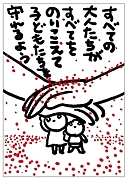■原子力ムラ
原子力発電を巡る利権によって結ばれた、産・官・学の特定の関係者によって構成された特殊な社会的集団及びその関係性を揶揄(やゆ)または批判を込めて呼ぶ用語。
2011年の福島第一原子力発電所事故により原子力を巡る産・官・学の癒着や閉鎖性がマスコミなどによってクローズアップされた。国際原子力委員会(IAEA)からも日本の原発規制当局には十分な独立性がないと指摘された。年間数兆円とも言われる原発の利権に特定の企業・機関・個人などが群がって、独善的でレトリカルな言論で懐疑的な意見や批判的な意見を封殺するという、狷介(けんかい)で偏狭なムラ(村)社会のごとき様相を端的に表現する言葉として「原子力ムラ」の用語が急速に巷間(こうかん)に広まった。
環境エネルギー政策研究所を主宰する飯田哲也氏は、「原子力村」は自らの造語であるとし、全体が利益共同体であり、かつその内部が「意志決定中心」のない「ムラ社会」であることにより名づけたとしている。日本政府がエネルギー政策の中心に据えてきた原子力発電は、その開発や運用に巨額の資金を必要とする。これらが電力会社、原子力プラントメーカー、監督官庁、大学や研究機関とその研究者、政治家、マスコミ・業界紙などのうち原発に関わる特定の部門に集中して環流することにより利益共同体を形成している。
内田樹神戸女学院大名誉教授は、原子力工学を学んだ学生の進路の幅の狭さが癒着の構造を招くとしている。原発関連企業や機関のポストは少なくないが、専門技術者や研究者の就職先は限定される。ここで職を求めるには、担当教授などの口利きなしには難しい。更に、就職後の人事的交流も専門性などを理由に、企業・機関内でも限定的な部門の中で転属が繰り返され外部との交流が絶たれる。こうした人脈の狭さから公的機関の中立性に不安が生じるということは、自由民主党の河野太郎衆議院議員も指摘している。
核融合など学術的には大きな進展が見込めない状況、諸外国ですでに始まっている原子力依存からの脱却、いつか確実に訪れる破綻(はたん)に対する焦燥感や絶望感などがムラをむしばんでいたと飯田氏は述べている。また、原子力行政についての展望もあいまいなままに原発建設だけが先行しており、万一の方向転換に際しての責任の所在やあり方が明確に定められていないため、ムラには屈折した狭量な仲間意識が生じていたとも言われる。マスコミ各社からも、原発批判勢力とは無関係に安全性や経済性にわずかでも疑義を示しただけでも、論難を浴びせてムラからの放逐を図るなどのムラの傾向が指摘され、原発の安全性確保を脅かす結果につながったのではないかとの批判がある。
( 金谷俊秀 ライター )
■なぜ「原子力ムラ(げんしりょくムラ)」は形成されたのか
《原子力の規制組織は独立性が保たれ、その役割を明確にすべきだ》
福島第1原発の事故を受けて国際原子力機関(IAEA)は6月、報告書の中で責任の所在や役割分担が曖昧な、日本の原子力行政の問題点を指摘した。
国と産業、学者がなれ合いの中で原発を推進してきた「原子力ムラ」の仕組み。異様さと危うさを、国際機関は見抜いていた。
「今回の事故の遠因は、まさにこの『原子力ムラ』にある」。NPO法人「環境エネルギー政策研究所」を主宰する飯田哲也(52)はそう断言する。
飯田は「原子力ムラ」という言葉を平成9年に論文で初めて使用し、日本の原子力行政の問題点を指摘したことで知られる。
飯田は神戸製鋼所で放射性廃棄物の仕事に従事。財団法人「電力中央研究所」で原子力安全基準づくりにも関わるなど、自らもムラの中を渡り歩いた経歴を持つ。「新たに判明した安全上の問題点も、既存の基準さえ満たしていれば目を向けず、外部からの貴重な指摘があっても無視をする」
「原子力ムラ」と呼ばれる独特のコミュニティーは、なぜ、どのように形成されるのか。
日本原子力学会副会長の沢田隆(64)は「専門家や技術者の経歴をたどると、限られた大学に集約される。数が少ないため、原子力を知る人材を産学官で使い回すしかなく、どこかで顔見知りになる」と解説する。
原子力を学ぶことができる大学は一部の国立大と私学に限られ、1学年も20人足らずと少ない。そこから研究者や役人、電力会社、メーカーへと進路は分かれるが、「原子力」が絆となり人脈はつながり続ける。
強固なネットワークは、異なる組織間の人事交流を通じて、産学官を貫く「利益共同体」として力を持つようになる。
12年以降に電力会社から内閣府や文部科学省に出向した社員は約100人。逆に経済産業省から電力会社への天下りは過去50年で68人に上る。原子力の研究者に対しては国から年間約1500億円(22年度)もの研究費が計上されている。
警鐘を鳴らす人がいなかったわけではない。立命館大名誉教授の安斎育郎(71)は、そんな数少ない専門家の1人だ。
安斎は昭和35年にできた東京大原子力工学科の1期生。原子力という夢の技術に希望を持って入学したが、周囲からは冷たくあしらわれた。本人いわく「原子力発電の安全性に疑問を持つようになったから」だという。担当教授が「安斎は干す」と言ったと知人から聞いた。研究費もほとんど割り振られない時期が続いた。安斎は、それが「原子力ムラの掟(おきて)」だと受け取った。
安斎は今後の日本の原子力行政について、「批判に耳を傾ける仕組みを作らなければ、何も変わらない」と話す。
IAEAの指摘などもあり、国も原子力ムラのあり方を見直し始めた。福島第1原発の事故後、政府は、経産省原子力安全・保安院と、内閣府原子力安全委員会を統合し、環境省の外局として原子力安全庁(仮称)を新設する方針を決めた。
その存在が、日本の原子力政策そのものだった原子力ムラ。原発事故から半年がたち、ムラの内部からも反省の声が公然と出始めた。
9月19日、北九州市で開かれた日本原子力学会。シンポジウムで東京工業大教授の二ノ方寿(65)は「こんな事故は起こらないと思っていた。大きな反省点だ。自己批判しながら提言や提案をしたい」と“自己批判”にまで言及した。
東京大教授で学会会長の田中知(61)からは、将来を見据えたこんな発言も出た。「学会は、一刻も早い環境の修復と避難住民の帰還に貢献する。国民に信頼される専門家集団に発展させたい」。「掟」を破壊できるのか。その動きは緒についたばかりだ。(敬称略)
■福島の前知事が、原子力“先進国”の内情を語る
「『ムラ』の人々はいつも『安全だ』と言い続けてきたが、福島が裏切られたのは初めてではない」
そう語り始めたのは、昭和63年から平成18年まで福島県知事を5期18年務めた佐藤栄佐久(72)。汚職事件の責任をとって知事を辞職し、政治から距離を置く立場になってすでに5年がたつ。原子力の恩恵にあずかった地元の首長が言うな――という声も出るかもしれないが、かつて自らがその一角を担っていた原子力“先進国”の内情を振り返った。
佐藤は在任中、原子力発電をめぐって幾度も「煮え湯」を飲まされた経験から、東京電力福島第1原発の事故を「起こるべくして起きた人災」と言い切る。「ムラ」とは、原子力に携わる人たちの閉鎖的社会のことを指す。
MOX(ウランとプルトニウムの混合酸化物)燃料を一般の原発で燃やすプルサーマル計画など、原子力政策で国や東電と対立を演じてきた佐藤。「闘う知事」と評されたこともある。
しかし、佐藤は「知事選にあたって反原発を掲げたことはなかった」と話す。むしろ、第1原発(双葉町、大熊町)と第2原発(富岡町、楢葉町)が並ぶ双葉郡の地域振興を訴えるなかで、「過疎地域の人口が1万人くらい増え、経済面で良い面がある」と考えていた。
その佐藤も知事就任後は、東電と対立する場面を繰り返した。背景には、昭和63年の就任後、間もなく抱いたある種の「違和感」の存在があるのだという。
昭和64年1月6日。時代が平成へと変わる2日前のこと。福島第2原発3号機で警報が鳴り、原子炉が手動停止された。
一報は現地から東電本店を通じ、通商産業省(現経済産業省)、県へと伝わった。だが、東京電力の思考には、地元の富岡、楢葉両町への伝達優先という発想はなかった。
地元の不信感を煽る事態は続く。部品が外れて原子炉内に三十数キログラムもの金属片が流入、4回の警報が鳴っていたにもかかわらず、運転を継続していたことが後に判明した。
県庁に陳謝に訪れた東電幹部が放った言葉がこれだ。「安全性が確認されれば、(部品が)発見されなくても運転再開はあり得る」
「『安全は二の次なのか』と思った」。佐藤は、当時の東電とのやり取りを今でも忘れない。
佐藤が原子力発電に感じた違和感は他にもあった。それは原発立地のメリットである「カネ」をめぐる違和感だった。
福島第1原発の事故は、日本の原子力の「安全神話」を終わらせた。しかし、日本の将来を見据えると「神話の終焉」を「原発の終焉」にすることは許されない。その神話を支えてきた産学官一体の「原子力ムラ」。ここにメスを入れない限り強固な安全構築はあり得ない。原子力ムラの独特の構造とその掟に迫る。
福島第1原発がある双葉町、大熊町。双葉町の商店街の入り口には「原子力 明るい未来の エネルギー」と書かれた看板が掲げられている。原発誘致に積極的だった事故前の地域の雰囲気を象徴する光景だ。
双葉町議会が平成3年9月、7、8号機の増設要望を議決した。《当初の誘致から10数年で、経済のみならず教育、文化、医療、交通、産業、全ての面で大きく飛躍発展を遂げた》。決議文は原発の恩恵に言及し、こう続く。《しかし、厳しい財政となって……。よって増設を望むところであります》
地元自治体にとって、莫大(ばくだい)な税収をもたらす原発施設の固定資産税。だが、施設の減価償却が計算されることで年々減額され、先細りする。
窮した自治体が、さらに増設を求める――。大熊町町長の渡辺利綱(64)は「原発の安全神話を過信してしまった。『安全だ』と言われれば信じるしかないようにされてきた」と悔いる。
当時、福島県知事だった佐藤栄佐久(72)にも自らも含め地元が、原子力ムラの掟にからめ取られていくのが分かった。
だが、「地元には2、3家族に1人は原発関係者がいる」と佐藤。知事としてのポストを支えている一角が、原発関係者という現実がある。
「ムラを飛び出し、『脱原発』に踏み切って解決できる問題ではなかった」
《電力産業との共生を図りつつ、発電所立地の優位性を生かして、新たな産業の誘致や育成を進める必要がある》
震災の1年前、福島県が平成22年4月にスタートさせた「県総合計画」の一節だ。
福島県には、明治以降、会津の只見川流域や猪苗代湖で開発された水力発電によって、「首都圏の電気を賄ってきた」という強烈な自負がある。東電は福島県に対してことあるごとに、「明治以来、長きにわたってお世話になっている」(平成6年7月、佐藤にあいさつに来た際の東電社長の言葉)と低姿勢だった。
だが安全に関しては、「お世話になっている」はずの地元が、いつも後回しにされた。
14年、東電が福島第1などのトラブル記録を意図的に改竄、隠蔽していた「トラブル隠し」が露見した。関連会社の元社員が実名で内部告発したにもかかわらず、監督官庁の原子力安全・保安院は告発者を容易に特定できる資料を、当事者の東電側に渡していた。
電力会社と、それを監視すべき立場にある保安院が「グル」だと思われても仕方ない構図。当然、地元は反発した。
低姿勢を装いながら、電力会社も国も、「原発は安全で、原発なしでは地域は成り立たない」と思わせ、地元自治体をも取り込んでいく巧妙なレトリック。そして安全面では地元は軽視される。それが原子力ムラの掟だった。
渡辺は指摘する。
「原発に依存する地元は、安全に関しては常に蚊帳の外に置かれてきた。国と電力会社が癒着(ゆちゃく)していると疑っても仕方のないことだった……」
佐藤も自責の念を込めるように、こう語る。「ムラの掟を崩壊しなければ日本の原子力行政は再生できない。それが社会を大切にするということだ」(敬称略)
■「フクシマのうそ」より
【福島県前知事佐藤栄佐久氏の辞任の真相】
フクシマの第1号原子炉は70年代初めに
アメリカのジェネラルエレクトリック社が建設し
それ以来アメリカのエンジニアが点検を行ってきた。
そしてフクシマでは何度も問題があった。
(ハーノ記者)
東電は、点検後、なにをあなたに求めたのですか?
(スガオカ氏)
亀裂を発見した後、彼らが私に言いたかったことは簡単です。
つまり、黙れ、ですよ。
何も話すな、黙ってろ、というわけです。
問題があるなど許されない
日本の原発に問題など想定されていない
アメリカのエンジニア、ケイ・スガオカ氏も
それを変えようとすることは許されなかった。
(スガオカ氏)
1989年のことです、蒸気乾燥機でビデオ点検をしていて
そこで今まで見たこともないほど大きい亀裂を発見しました。
スガオカ氏と同僚が発見したのは、それだけではない。
(スガオカ氏)
原子炉を点検している同僚の目がみるみる大きくなったと思うと
彼がこう言いました
蒸気乾燥機の向きが反対に取り付けられているぞ、と。
もともとこの原発の中心部材には重大な欠陥があったのだ。
スガオカ氏は点検の主任だったので
正しく点検を行い処理をする責任があったのだが
彼の報告は、東電の気に入らなかった。
私たちは点検で亀裂を発見しましたが、東電は
私たちにビデオでその部分を消すよう注文しました。
報告書も書くな、と言うのです。
私はサインしかさせてもらえませんでした。
私が報告書を書けば、180度反対に付けられている蒸気乾燥機のことも
報告するに決まっていると知っていたからです。
(ハーノ記者)
では、嘘の文書を書くよう求めたわけですか?
(スガオカ氏)
そうです、彼らは我々に文書の改ざんを要求しました。
スガオカ氏は仕事を失うのを怖れて、10年間黙秘した。
GE社に解雇されて初めて彼は沈黙を破り
日本の担当官庁に告発した。
ところが不思議なことに、告発後何年間もなにも起こらなかった。
日本の原発監督官庁はそれをもみ消そうとしたのだ。
2001年になってやっと、スガオカ氏は「同士」を見つけた。
それも日本のフクシマで、である。
18年間福島県知事を務めた佐藤栄佐久氏は
当時の日本の与党、保守的な自民党所属だ。
佐藤氏は古典的政治家で
皇太子夫妻の旅に随行したこともある。
始めは彼も、原発は住民になんの危険ももたらさないと確信していた。
それから、その信頼をどんどん失っていった。
(佐藤前知事)
福島県の原発で働く情報提供者から約20通ファックスが届き
その中にはスガオカ氏の告発も入っていました。
経産省は、その内部告発の内容を確かめずに
これら密告者の名を東電に明かしました。
それからわかったことは、私も初めは信じられませんでした。
東電は、報告書を改ざんしていたというのです。
それで私は新聞に記事を書きました。
そんなことをしていると、この先必ず大事故が起きる、と。
それでやっと官僚たちもなにもしないわけにはいかなくなり
17基の原発が一時停止に追い込まれた。
調査委員会は、東電が何十年も前から重大な事故を隠蔽し
安全点検報告でデータを改ざんしてきたことを明らかにした。
それどころか、フクシマでは30年も臨界事故を隠してきたという。
社長・幹部は辞任に追い込まれ、社員は懲戒を受けたが
皆新しいポストをもらい、誰も起訴されなかった。
一番の責任者であった勝俣恒久氏は代表取締役に任命された。
彼らは佐藤氏に報告書の改ざんに対し謝罪したが
佐藤氏は安心できず、原発がどんどん建設されることを懸念した。
そこで佐藤氏は日本の原発政策という
「暗黙のルール」に違反してしまった。
2004年に復讐が始まった。
(佐藤前知事)
12月に不正な土地取引の疑いがあるという記事が新聞に載りました。
この記事を書いたのは本来は原発政策担当の記者でした。
この疑惑は、完全にでっち上げでした。
弟が逮捕され
首相官邸担当の検察官が一時的に福島に送られて検事を務めていた。
彼の名はノリモトという名で
遅かれ早かれ、お前の兄の知事を抹殺してやる、と弟に言ったそうです。
事態は更に進み、県庁で働く200人の職員に
圧力がかかり始めました。
少し私の悪口を言うだけでいいから、と。
中には2、3人、圧力に耐え切れずに
自殺をする者さえ出ました。
私の下で働いていたある部長は、いまだ意識不明のままです。
それで、同僚や友人を守るため、佐藤氏は辞任した。
裁判で彼の無罪は確定されるが
しかし沈黙を破ろうとした「邪魔者」はこうして消された。
これが、日本の社会を牛耳る大きなグループの復讐だった。
そしてこれこそ、日本で原子力ムラと呼ばれるグループである。
原子力発電を巡る利権によって結ばれた、産・官・学の特定の関係者によって構成された特殊な社会的集団及びその関係性を揶揄(やゆ)または批判を込めて呼ぶ用語。
2011年の福島第一原子力発電所事故により原子力を巡る産・官・学の癒着や閉鎖性がマスコミなどによってクローズアップされた。国際原子力委員会(IAEA)からも日本の原発規制当局には十分な独立性がないと指摘された。年間数兆円とも言われる原発の利権に特定の企業・機関・個人などが群がって、独善的でレトリカルな言論で懐疑的な意見や批判的な意見を封殺するという、狷介(けんかい)で偏狭なムラ(村)社会のごとき様相を端的に表現する言葉として「原子力ムラ」の用語が急速に巷間(こうかん)に広まった。
環境エネルギー政策研究所を主宰する飯田哲也氏は、「原子力村」は自らの造語であるとし、全体が利益共同体であり、かつその内部が「意志決定中心」のない「ムラ社会」であることにより名づけたとしている。日本政府がエネルギー政策の中心に据えてきた原子力発電は、その開発や運用に巨額の資金を必要とする。これらが電力会社、原子力プラントメーカー、監督官庁、大学や研究機関とその研究者、政治家、マスコミ・業界紙などのうち原発に関わる特定の部門に集中して環流することにより利益共同体を形成している。
内田樹神戸女学院大名誉教授は、原子力工学を学んだ学生の進路の幅の狭さが癒着の構造を招くとしている。原発関連企業や機関のポストは少なくないが、専門技術者や研究者の就職先は限定される。ここで職を求めるには、担当教授などの口利きなしには難しい。更に、就職後の人事的交流も専門性などを理由に、企業・機関内でも限定的な部門の中で転属が繰り返され外部との交流が絶たれる。こうした人脈の狭さから公的機関の中立性に不安が生じるということは、自由民主党の河野太郎衆議院議員も指摘している。
核融合など学術的には大きな進展が見込めない状況、諸外国ですでに始まっている原子力依存からの脱却、いつか確実に訪れる破綻(はたん)に対する焦燥感や絶望感などがムラをむしばんでいたと飯田氏は述べている。また、原子力行政についての展望もあいまいなままに原発建設だけが先行しており、万一の方向転換に際しての責任の所在やあり方が明確に定められていないため、ムラには屈折した狭量な仲間意識が生じていたとも言われる。マスコミ各社からも、原発批判勢力とは無関係に安全性や経済性にわずかでも疑義を示しただけでも、論難を浴びせてムラからの放逐を図るなどのムラの傾向が指摘され、原発の安全性確保を脅かす結果につながったのではないかとの批判がある。
( 金谷俊秀 ライター )
■なぜ「原子力ムラ(げんしりょくムラ)」は形成されたのか
《原子力の規制組織は独立性が保たれ、その役割を明確にすべきだ》
福島第1原発の事故を受けて国際原子力機関(IAEA)は6月、報告書の中で責任の所在や役割分担が曖昧な、日本の原子力行政の問題点を指摘した。
国と産業、学者がなれ合いの中で原発を推進してきた「原子力ムラ」の仕組み。異様さと危うさを、国際機関は見抜いていた。
「今回の事故の遠因は、まさにこの『原子力ムラ』にある」。NPO法人「環境エネルギー政策研究所」を主宰する飯田哲也(52)はそう断言する。
飯田は「原子力ムラ」という言葉を平成9年に論文で初めて使用し、日本の原子力行政の問題点を指摘したことで知られる。
飯田は神戸製鋼所で放射性廃棄物の仕事に従事。財団法人「電力中央研究所」で原子力安全基準づくりにも関わるなど、自らもムラの中を渡り歩いた経歴を持つ。「新たに判明した安全上の問題点も、既存の基準さえ満たしていれば目を向けず、外部からの貴重な指摘があっても無視をする」
「原子力ムラ」と呼ばれる独特のコミュニティーは、なぜ、どのように形成されるのか。
日本原子力学会副会長の沢田隆(64)は「専門家や技術者の経歴をたどると、限られた大学に集約される。数が少ないため、原子力を知る人材を産学官で使い回すしかなく、どこかで顔見知りになる」と解説する。
原子力を学ぶことができる大学は一部の国立大と私学に限られ、1学年も20人足らずと少ない。そこから研究者や役人、電力会社、メーカーへと進路は分かれるが、「原子力」が絆となり人脈はつながり続ける。
強固なネットワークは、異なる組織間の人事交流を通じて、産学官を貫く「利益共同体」として力を持つようになる。
12年以降に電力会社から内閣府や文部科学省に出向した社員は約100人。逆に経済産業省から電力会社への天下りは過去50年で68人に上る。原子力の研究者に対しては国から年間約1500億円(22年度)もの研究費が計上されている。
警鐘を鳴らす人がいなかったわけではない。立命館大名誉教授の安斎育郎(71)は、そんな数少ない専門家の1人だ。
安斎は昭和35年にできた東京大原子力工学科の1期生。原子力という夢の技術に希望を持って入学したが、周囲からは冷たくあしらわれた。本人いわく「原子力発電の安全性に疑問を持つようになったから」だという。担当教授が「安斎は干す」と言ったと知人から聞いた。研究費もほとんど割り振られない時期が続いた。安斎は、それが「原子力ムラの掟(おきて)」だと受け取った。
安斎は今後の日本の原子力行政について、「批判に耳を傾ける仕組みを作らなければ、何も変わらない」と話す。
IAEAの指摘などもあり、国も原子力ムラのあり方を見直し始めた。福島第1原発の事故後、政府は、経産省原子力安全・保安院と、内閣府原子力安全委員会を統合し、環境省の外局として原子力安全庁(仮称)を新設する方針を決めた。
その存在が、日本の原子力政策そのものだった原子力ムラ。原発事故から半年がたち、ムラの内部からも反省の声が公然と出始めた。
9月19日、北九州市で開かれた日本原子力学会。シンポジウムで東京工業大教授の二ノ方寿(65)は「こんな事故は起こらないと思っていた。大きな反省点だ。自己批判しながら提言や提案をしたい」と“自己批判”にまで言及した。
東京大教授で学会会長の田中知(61)からは、将来を見据えたこんな発言も出た。「学会は、一刻も早い環境の修復と避難住民の帰還に貢献する。国民に信頼される専門家集団に発展させたい」。「掟」を破壊できるのか。その動きは緒についたばかりだ。(敬称略)
■福島の前知事が、原子力“先進国”の内情を語る
「『ムラ』の人々はいつも『安全だ』と言い続けてきたが、福島が裏切られたのは初めてではない」
そう語り始めたのは、昭和63年から平成18年まで福島県知事を5期18年務めた佐藤栄佐久(72)。汚職事件の責任をとって知事を辞職し、政治から距離を置く立場になってすでに5年がたつ。原子力の恩恵にあずかった地元の首長が言うな――という声も出るかもしれないが、かつて自らがその一角を担っていた原子力“先進国”の内情を振り返った。
佐藤は在任中、原子力発電をめぐって幾度も「煮え湯」を飲まされた経験から、東京電力福島第1原発の事故を「起こるべくして起きた人災」と言い切る。「ムラ」とは、原子力に携わる人たちの閉鎖的社会のことを指す。
MOX(ウランとプルトニウムの混合酸化物)燃料を一般の原発で燃やすプルサーマル計画など、原子力政策で国や東電と対立を演じてきた佐藤。「闘う知事」と評されたこともある。
しかし、佐藤は「知事選にあたって反原発を掲げたことはなかった」と話す。むしろ、第1原発(双葉町、大熊町)と第2原発(富岡町、楢葉町)が並ぶ双葉郡の地域振興を訴えるなかで、「過疎地域の人口が1万人くらい増え、経済面で良い面がある」と考えていた。
その佐藤も知事就任後は、東電と対立する場面を繰り返した。背景には、昭和63年の就任後、間もなく抱いたある種の「違和感」の存在があるのだという。
昭和64年1月6日。時代が平成へと変わる2日前のこと。福島第2原発3号機で警報が鳴り、原子炉が手動停止された。
一報は現地から東電本店を通じ、通商産業省(現経済産業省)、県へと伝わった。だが、東京電力の思考には、地元の富岡、楢葉両町への伝達優先という発想はなかった。
地元の不信感を煽る事態は続く。部品が外れて原子炉内に三十数キログラムもの金属片が流入、4回の警報が鳴っていたにもかかわらず、運転を継続していたことが後に判明した。
県庁に陳謝に訪れた東電幹部が放った言葉がこれだ。「安全性が確認されれば、(部品が)発見されなくても運転再開はあり得る」
「『安全は二の次なのか』と思った」。佐藤は、当時の東電とのやり取りを今でも忘れない。
佐藤が原子力発電に感じた違和感は他にもあった。それは原発立地のメリットである「カネ」をめぐる違和感だった。
福島第1原発の事故は、日本の原子力の「安全神話」を終わらせた。しかし、日本の将来を見据えると「神話の終焉」を「原発の終焉」にすることは許されない。その神話を支えてきた産学官一体の「原子力ムラ」。ここにメスを入れない限り強固な安全構築はあり得ない。原子力ムラの独特の構造とその掟に迫る。
福島第1原発がある双葉町、大熊町。双葉町の商店街の入り口には「原子力 明るい未来の エネルギー」と書かれた看板が掲げられている。原発誘致に積極的だった事故前の地域の雰囲気を象徴する光景だ。
双葉町議会が平成3年9月、7、8号機の増設要望を議決した。《当初の誘致から10数年で、経済のみならず教育、文化、医療、交通、産業、全ての面で大きく飛躍発展を遂げた》。決議文は原発の恩恵に言及し、こう続く。《しかし、厳しい財政となって……。よって増設を望むところであります》
地元自治体にとって、莫大(ばくだい)な税収をもたらす原発施設の固定資産税。だが、施設の減価償却が計算されることで年々減額され、先細りする。
窮した自治体が、さらに増設を求める――。大熊町町長の渡辺利綱(64)は「原発の安全神話を過信してしまった。『安全だ』と言われれば信じるしかないようにされてきた」と悔いる。
当時、福島県知事だった佐藤栄佐久(72)にも自らも含め地元が、原子力ムラの掟にからめ取られていくのが分かった。
だが、「地元には2、3家族に1人は原発関係者がいる」と佐藤。知事としてのポストを支えている一角が、原発関係者という現実がある。
「ムラを飛び出し、『脱原発』に踏み切って解決できる問題ではなかった」
《電力産業との共生を図りつつ、発電所立地の優位性を生かして、新たな産業の誘致や育成を進める必要がある》
震災の1年前、福島県が平成22年4月にスタートさせた「県総合計画」の一節だ。
福島県には、明治以降、会津の只見川流域や猪苗代湖で開発された水力発電によって、「首都圏の電気を賄ってきた」という強烈な自負がある。東電は福島県に対してことあるごとに、「明治以来、長きにわたってお世話になっている」(平成6年7月、佐藤にあいさつに来た際の東電社長の言葉)と低姿勢だった。
だが安全に関しては、「お世話になっている」はずの地元が、いつも後回しにされた。
14年、東電が福島第1などのトラブル記録を意図的に改竄、隠蔽していた「トラブル隠し」が露見した。関連会社の元社員が実名で内部告発したにもかかわらず、監督官庁の原子力安全・保安院は告発者を容易に特定できる資料を、当事者の東電側に渡していた。
電力会社と、それを監視すべき立場にある保安院が「グル」だと思われても仕方ない構図。当然、地元は反発した。
低姿勢を装いながら、電力会社も国も、「原発は安全で、原発なしでは地域は成り立たない」と思わせ、地元自治体をも取り込んでいく巧妙なレトリック。そして安全面では地元は軽視される。それが原子力ムラの掟だった。
渡辺は指摘する。
「原発に依存する地元は、安全に関しては常に蚊帳の外に置かれてきた。国と電力会社が癒着(ゆちゃく)していると疑っても仕方のないことだった……」
佐藤も自責の念を込めるように、こう語る。「ムラの掟を崩壊しなければ日本の原子力行政は再生できない。それが社会を大切にするということだ」(敬称略)
■「フクシマのうそ」より
【福島県前知事佐藤栄佐久氏の辞任の真相】
フクシマの第1号原子炉は70年代初めに
アメリカのジェネラルエレクトリック社が建設し
それ以来アメリカのエンジニアが点検を行ってきた。
そしてフクシマでは何度も問題があった。
(ハーノ記者)
東電は、点検後、なにをあなたに求めたのですか?
(スガオカ氏)
亀裂を発見した後、彼らが私に言いたかったことは簡単です。
つまり、黙れ、ですよ。
何も話すな、黙ってろ、というわけです。
問題があるなど許されない
日本の原発に問題など想定されていない
アメリカのエンジニア、ケイ・スガオカ氏も
それを変えようとすることは許されなかった。
(スガオカ氏)
1989年のことです、蒸気乾燥機でビデオ点検をしていて
そこで今まで見たこともないほど大きい亀裂を発見しました。
スガオカ氏と同僚が発見したのは、それだけではない。
(スガオカ氏)
原子炉を点検している同僚の目がみるみる大きくなったと思うと
彼がこう言いました
蒸気乾燥機の向きが反対に取り付けられているぞ、と。
もともとこの原発の中心部材には重大な欠陥があったのだ。
スガオカ氏は点検の主任だったので
正しく点検を行い処理をする責任があったのだが
彼の報告は、東電の気に入らなかった。
私たちは点検で亀裂を発見しましたが、東電は
私たちにビデオでその部分を消すよう注文しました。
報告書も書くな、と言うのです。
私はサインしかさせてもらえませんでした。
私が報告書を書けば、180度反対に付けられている蒸気乾燥機のことも
報告するに決まっていると知っていたからです。
(ハーノ記者)
では、嘘の文書を書くよう求めたわけですか?
(スガオカ氏)
そうです、彼らは我々に文書の改ざんを要求しました。
スガオカ氏は仕事を失うのを怖れて、10年間黙秘した。
GE社に解雇されて初めて彼は沈黙を破り
日本の担当官庁に告発した。
ところが不思議なことに、告発後何年間もなにも起こらなかった。
日本の原発監督官庁はそれをもみ消そうとしたのだ。
2001年になってやっと、スガオカ氏は「同士」を見つけた。
それも日本のフクシマで、である。
18年間福島県知事を務めた佐藤栄佐久氏は
当時の日本の与党、保守的な自民党所属だ。
佐藤氏は古典的政治家で
皇太子夫妻の旅に随行したこともある。
始めは彼も、原発は住民になんの危険ももたらさないと確信していた。
それから、その信頼をどんどん失っていった。
(佐藤前知事)
福島県の原発で働く情報提供者から約20通ファックスが届き
その中にはスガオカ氏の告発も入っていました。
経産省は、その内部告発の内容を確かめずに
これら密告者の名を東電に明かしました。
それからわかったことは、私も初めは信じられませんでした。
東電は、報告書を改ざんしていたというのです。
それで私は新聞に記事を書きました。
そんなことをしていると、この先必ず大事故が起きる、と。
それでやっと官僚たちもなにもしないわけにはいかなくなり
17基の原発が一時停止に追い込まれた。
調査委員会は、東電が何十年も前から重大な事故を隠蔽し
安全点検報告でデータを改ざんしてきたことを明らかにした。
それどころか、フクシマでは30年も臨界事故を隠してきたという。
社長・幹部は辞任に追い込まれ、社員は懲戒を受けたが
皆新しいポストをもらい、誰も起訴されなかった。
一番の責任者であった勝俣恒久氏は代表取締役に任命された。
彼らは佐藤氏に報告書の改ざんに対し謝罪したが
佐藤氏は安心できず、原発がどんどん建設されることを懸念した。
そこで佐藤氏は日本の原発政策という
「暗黙のルール」に違反してしまった。
2004年に復讐が始まった。
(佐藤前知事)
12月に不正な土地取引の疑いがあるという記事が新聞に載りました。
この記事を書いたのは本来は原発政策担当の記者でした。
この疑惑は、完全にでっち上げでした。
弟が逮捕され
首相官邸担当の検察官が一時的に福島に送られて検事を務めていた。
彼の名はノリモトという名で
遅かれ早かれ、お前の兄の知事を抹殺してやる、と弟に言ったそうです。
事態は更に進み、県庁で働く200人の職員に
圧力がかかり始めました。
少し私の悪口を言うだけでいいから、と。
中には2、3人、圧力に耐え切れずに
自殺をする者さえ出ました。
私の下で働いていたある部長は、いまだ意識不明のままです。
それで、同僚や友人を守るため、佐藤氏は辞任した。
裁判で彼の無罪は確定されるが
しかし沈黙を破ろうとした「邪魔者」はこうして消された。
これが、日本の社会を牛耳る大きなグループの復讐だった。
そしてこれこそ、日本で原子力ムラと呼ばれるグループである。
|
|
|
|
コメント(3)
「国の行く末」も「国民の権利」も考えない『利権と金だけの原子力ムラの連中』は、昨年の原発事故よりあらゆる手段を講じての「原発反対論の火消し」に躍起になっている。ネットでの安全論者、原発推進者は、ほぼ原子力ムラの手先だと考えて差し支えない。
また色々調べた結果だが、
「日本の国防のために日本に核兵器を」と考える軍国主義者は、原子力ムラの連中と同じ穴のムジナではなく別ものだと考えた方が良い。「日本の国防のために日本に核兵器を」と考える軍国主義者にとっては原発が稼動してようが停止してようが関係ないからだ。
日本の全ての子供たちの敵、東北の被災者の敵は、『己らの利権と金だけしか眼中にない原子力ムラの連中だけ』と考えておくべきであり、以下に代表される「風評被害を訴える火消し」は全て『利権と金だけの原子力ムラの連中』だと認識しておいたほうがよいだろう。
また色々調べた結果だが、
「日本の国防のために日本に核兵器を」と考える軍国主義者は、原子力ムラの連中と同じ穴のムジナではなく別ものだと考えた方が良い。「日本の国防のために日本に核兵器を」と考える軍国主義者にとっては原発が稼動してようが停止してようが関係ないからだ。
日本の全ての子供たちの敵、東北の被災者の敵は、『己らの利権と金だけしか眼中にない原子力ムラの連中だけ』と考えておくべきであり、以下に代表される「風評被害を訴える火消し」は全て『利権と金だけの原子力ムラの連中』だと認識しておいたほうがよいだろう。
■被ばく基準緩和 NHK番組 原発推進団体が抗議(東京新聞)/原子力ムラの逆襲?(東京新聞「こちら特報部」)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012020102000039.html
【社会】
被ばく基準緩和 NHK番組 原発推進団体が抗議(東京新聞)
2012年2月1日 朝刊 1面
NHKが昨年末、国際的な低線量被ばくのリスク基準が政治的な判断で低く設定されたという内容の番組を放映したことに対し、原子力発電推進を訴える複数団体のメンバーらが「(番組内容には)誤りや論拠が不明な点、不都合な事実の隠蔽(いんぺい)がある」として、NHKに抗議文を送っていたことが分かった。
団体側はNHKに先月末までの回答を求めていた。NHKの広報担当は「番組内容に問題はないと考えているが、(抗議には)誠実に対応させていただく」としている。
抗議文は外務省の初代原子力課長、金子熊夫氏が会長を務める「エネルギー戦略研究会」、東京電力出身の宅間正夫氏が会長の「日本原子力学会シニア・ネットワーク連絡会」、元日立製作所社員の林勉氏が代表幹事の「エネルギー問題に発言する会」の三団体が作成、提出した。
番組は昨年十二月二十八日に放送された「追跡!真相ファイル 低線量被ばく 揺れる国際基準」。国際放射線防護委員会(ICRP)が被ばくによる発がんリスクの基準設定を政治的な判断で低くしたという趣旨を同委員会メンバーへの取材を交えて報じた。
これに対し、団体側は「インタビューの日本語訳が意図的にすり替えられている」「政治的圧力で(被ばく)規制値を緩和したかのような論旨だが、論拠が不明確」などと指摘し、調査を求めた。
三団体は過去にも報道機関に「原子力は危ないという前提で、編集している」といった抗議活動をしてきたが、東京電力福島第一原発事故後では今回が初めての行動だという。
原爆の影響調査に携わってきた沢田昭二名古屋大名誉教授は「番組の内容は正確。日本語訳もおおむね問題はなかった。重要な情報を伝える良い番組だった」と話している。
■NHK 追跡!真相ファイル: 低線量被ばく 揺れる国際基準(12月28日 22:55〜23:23)
「ICRP、低線量被ばくのリスクを半分に過小評価していた」
http://www.asyura2.com/11/genpatu19/msg/695.html
■ICRPの被曝基準は各国原子力推進派の都合
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1818247356&owner_id=4090144
■人間と環境への低レベル放射能の脅威
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=67811121&comm_id=5524954
■元凶は原子力ムラ
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1832865814&owner_id=4090144
■ドイツZDFテレビ 「フクシマのうそ」
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1832864926&owner_id=4090144
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012020102000039.html
【社会】
被ばく基準緩和 NHK番組 原発推進団体が抗議(東京新聞)
2012年2月1日 朝刊 1面
NHKが昨年末、国際的な低線量被ばくのリスク基準が政治的な判断で低く設定されたという内容の番組を放映したことに対し、原子力発電推進を訴える複数団体のメンバーらが「(番組内容には)誤りや論拠が不明な点、不都合な事実の隠蔽(いんぺい)がある」として、NHKに抗議文を送っていたことが分かった。
団体側はNHKに先月末までの回答を求めていた。NHKの広報担当は「番組内容に問題はないと考えているが、(抗議には)誠実に対応させていただく」としている。
抗議文は外務省の初代原子力課長、金子熊夫氏が会長を務める「エネルギー戦略研究会」、東京電力出身の宅間正夫氏が会長の「日本原子力学会シニア・ネットワーク連絡会」、元日立製作所社員の林勉氏が代表幹事の「エネルギー問題に発言する会」の三団体が作成、提出した。
番組は昨年十二月二十八日に放送された「追跡!真相ファイル 低線量被ばく 揺れる国際基準」。国際放射線防護委員会(ICRP)が被ばくによる発がんリスクの基準設定を政治的な判断で低くしたという趣旨を同委員会メンバーへの取材を交えて報じた。
これに対し、団体側は「インタビューの日本語訳が意図的にすり替えられている」「政治的圧力で(被ばく)規制値を緩和したかのような論旨だが、論拠が不明確」などと指摘し、調査を求めた。
三団体は過去にも報道機関に「原子力は危ないという前提で、編集している」といった抗議活動をしてきたが、東京電力福島第一原発事故後では今回が初めての行動だという。
原爆の影響調査に携わってきた沢田昭二名古屋大名誉教授は「番組の内容は正確。日本語訳もおおむね問題はなかった。重要な情報を伝える良い番組だった」と話している。
■NHK 追跡!真相ファイル: 低線量被ばく 揺れる国際基準(12月28日 22:55〜23:23)
「ICRP、低線量被ばくのリスクを半分に過小評価していた」
http://www.asyura2.com/11/genpatu19/msg/695.html
■ICRPの被曝基準は各国原子力推進派の都合
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1818247356&owner_id=4090144
■人間と環境への低レベル放射能の脅威
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=67811121&comm_id=5524954
■元凶は原子力ムラ
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1832865814&owner_id=4090144
■ドイツZDFテレビ 「フクシマのうそ」
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1832864926&owner_id=4090144
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
■危機管理@放射能情報倉庫 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
■危機管理@放射能情報倉庫のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8447人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82528人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208286人