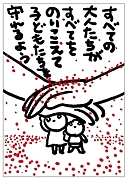■都心部、想定外の震度7も…東京湾北部地震で「マグニチュード(M)7・3」
(読売新聞 - 02月21日 03:14)
http://
発生は30年後、10年後かも知れないし、1分後かも知れない。
震度7と言えば、日本では阪神大震災、中越地震、東北大震災の3つの大災害と同等。大都市圏における直下型地震は同じマグニチュード(M)7・3の阪神大震災が一番近く、震源の深さによっては阪神大震災以上の被害に及ぶ可能性もある。
尚、震度5、6については「弱」「強」の区分表示があるが震度7については強弱表示が存在しない。
・震度6烈震…家が倒れる割合が30%以下で、崖崩れ、地割れが起こる。
・震度7激震…家屋の30%以上が倒れ、山崩れや地割れができる。
【画像】阪神・淡路大震災
http://
【資料】
■阪神・淡路大震災(都市直下型)
気象庁発表による正式名「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」によって引き起こされた激甚災害であり、戦後最大の都市型大災害である。
平成7年(1995年)兵庫県南部地震は1995年(平成7年)1月17日午前5時46分発生、明石海峡を震源地とするマグニチュード7.3の直下型地震。最大震度は7、周辺地域に甚大な被害が発生した。大都市直下を震源とする日本で初めての大地震で、震度7の激震を記録した初めての地震である。
発生時刻
1995年(平成7年)1月17日午前5時46分52秒(日本時間)
震源
淡路島北部(あるいは神戸市垂水区)沖の明石海峡
北緯34度35.9分、東経135度2.1分
震源の深さ
16km
マグニチュード
Mj7.3
最大震度
震度7
概要
1995年(平成7年)1月17日午前5時46分、明石海峡を震源地とするマグニチュード7.3の直下型地震「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」によって明石市、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市など阪神間の各都市(兵庫県の沿海部とその周辺地域)、および淡路島北部が最大震度7の激しい揺れに襲われ、各地で甚大な被害が発生した。死者6,433名、行方不明者3名、負傷者4万人以上、家屋の全半壊24万軒(世帯としては約44万世帯)。地震による火災での全半焼約6,200軒超。災害救助法適用は兵庫県内10市10町にのぼる。
交通関係については、港湾関係で埠頭の沈下等、鉄道関係で山陽新幹線の高架橋等の倒壊・落橋による不通を含むJR西日本等合計13社において不通、道路関係で地震発生直後、高速自動車国道、阪神高速道路等の27路線36区間について通行止めになるなどの被害が発生した。また地震発生直後から長期間にわたるライフライン(上下水道・電気・ガス・電話)の不通、消防・救急体制の混乱、各種産業・企業への被害、文化財への被害など、被害総額はおよそ10兆円に達した。
■新潟県中越地震(直下型)
新潟県中越地方を震央として平成16年10月23日17時56分ころ発生した地震のこと。顕著な被害があったことから命名された。震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは6.8(速報値)、最大震度は7(新潟県川口町)。揺れの強さを示す目安の一つである加速度は、小千谷市で研究所観測史上最大の1500ガル*1を記録したと発表があった(防災科学技術研究所による)。さらに、震度6強もともなう、大きな余震が続いた。
17時56分ごろの強震動
発生時刻
2004年10月23日(土)17時56分ごろ
最大震度
震度7(川口町役場にある震度計で観測)
震源地
北緯37.3度・東経138.8度
震源の深さ
20km
地震の規模
マグニチュード6.8
■東北地方太平洋沖地震(海溝型)
2011年3月11日14時46分頃、三陸沖で発生した地震。英名「The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake」(気象庁)。太平洋プレートと北米プレートのプレート境界域における海溝型地震である。西北西-東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型。岩石が破壊された震源域は岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmの広範囲に及ぶ。このような規模の地震は869年の貞観三陸地震(M8.3~8.6)に続いて、約1000年ぶりに発生した可能性も指摘されている。
名称については気象庁が「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」と命名した。なお、この地震に伴う災害の呼称について、3月中はNHKが東北関東大震災、民放などが東日本大震災としていた。4月1日の閣議で正式名称が「東日本大震災」と決まった。
発生時刻(JST) 2011年3月11日14時46分18.1秒
震央地名・震源経緯度 三陸沖、北緯38°6.2′ 東経142°51.6′
深さ 24km
マグニチュード(Mw) 9.0
第1波
14時46分、震源の深さ24km、マグニチュード9.0(暫定値。モーメントマグニチュードMwによる発表)の地震が発生。宮城県栗原市築館で最大震度7を記録。
震度7を記録したのは新潟県中越地震以来、7年ぶりで、日本の地震の中で3回目である。(前二回は兵庫県南部地震(Mj7.3/Mw6.9)、新潟県中越地震(Mj6.8/Mw6.6)。)気象庁は日本観測史上では最大規模の地震であると発表、1900年以降世界で起きた地震の中で4番目に強い地震となった。
高度利用者向け緊急地震速報第1報では、「3/11 14:46:19発生 三陸沖でマグニチュード4.3、深さ10kmの地震が発生、最大予想震度2」との情報が配信されたが、最終報で「3/11 14:46:17発生 三陸沖でマグニチュード8.1、深さ10kmの地震が発生、最大予想震度7」と急激に上方修正された。
数分後、気象庁が最大震度6強を発表、それと同時に大津波警報、津波警報、津波注意報を発表。さらに数分後最大震度が7に修正された。
第2波以降この地震に続いて、15時8分に最大震度5弱、同時9分に最大震度5強の余震と思われる地震が発生。
宮城沖M8.4の地震発生から29分後、茨城県沖で最大震度6弱、深さ80km、M7.4の地震が発生、東北地方から関東地方にかけての広い範囲に甚大な被害をもたらした。北米プレートの端に沿って、このベルト上で多くの余震が発生している。
第2波以降
この地震に続いて、15時8分に最大震度5弱、同時9分に最大震度5強の余震と思われる地震が発生。宮城沖M8.4の地震発生から29分後、茨城県沖で最大震度6弱、深さ80km、M7.4の地震が発生、東北地方から関東地方にかけての広い範囲に甚大な被害をもたらした。北米プレートの端に沿って、このベルト上で多くの余震が発生している。
【マグニチュードと震度】
マグニチュード
マグニチュードとは、地震の規模(エネルギーの対数の大きさ)を数字に表したもので、1937年に、アメリカの地震学者チャールズ・F・リヒターによって定義された。マグニチュードが1増えると、エネルギーは約32倍になる。要するに地震が起こるときの力(エネルギー)そのものの大きさ。この「magnitude」というのはラテン語で「大きさ」という意味なんですが、英語では「大きさ」のほかに「光度」という意味もあって、星の明るさを表すときにも使われている。一等星が「ファーストマグニチュード」みたいな感じ。
震度
震度とは、ある場所での地震の揺れの強さを気象庁震度階級に則って表したもの。 同じ地震の揺れでも、測定する場所によって揺れの大きさは変わる。震源地に近いところや地盤が弱いところなんかが揺れが大きい。マグニチュードで表されるエネルギーが地面を伝わって、地表まで達したときの揺れの大きさのことで、日本では気象庁震度階級として設定されている。
震度階級
1948年の福井地震のあとに震度7が設けられた。
震度0無感…地震計(震度計)が検知し、人は揺れを感じない。
震度1微震…静止している人や特に注意している人だけに感じられる。
震度2軽震…人に感じられ、障子などがわずかに動く。
震度3弱震…家が揺れ、戸・障子などが音を立てる。
震度4中震…家が激しく揺れ、八分目ぐらい入れた水が入れ物からあふれ出る。
震度5強震…壁が割れ、煙突が壊れたりする。
震度6烈震…家が倒れる割合が30%以下で、崖崩れ、地割れが起こる。
震度7激震…家屋の30%以上が倒れ、山崩れや地割れができる。
(読売新聞 - 02月21日 03:14)
http://
発生は30年後、10年後かも知れないし、1分後かも知れない。
震度7と言えば、日本では阪神大震災、中越地震、東北大震災の3つの大災害と同等。大都市圏における直下型地震は同じマグニチュード(M)7・3の阪神大震災が一番近く、震源の深さによっては阪神大震災以上の被害に及ぶ可能性もある。
尚、震度5、6については「弱」「強」の区分表示があるが震度7については強弱表示が存在しない。
・震度6烈震…家が倒れる割合が30%以下で、崖崩れ、地割れが起こる。
・震度7激震…家屋の30%以上が倒れ、山崩れや地割れができる。
【画像】阪神・淡路大震災
http://
【資料】
■阪神・淡路大震災(都市直下型)
気象庁発表による正式名「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」によって引き起こされた激甚災害であり、戦後最大の都市型大災害である。
平成7年(1995年)兵庫県南部地震は1995年(平成7年)1月17日午前5時46分発生、明石海峡を震源地とするマグニチュード7.3の直下型地震。最大震度は7、周辺地域に甚大な被害が発生した。大都市直下を震源とする日本で初めての大地震で、震度7の激震を記録した初めての地震である。
発生時刻
1995年(平成7年)1月17日午前5時46分52秒(日本時間)
震源
淡路島北部(あるいは神戸市垂水区)沖の明石海峡
北緯34度35.9分、東経135度2.1分
震源の深さ
16km
マグニチュード
Mj7.3
最大震度
震度7
概要
1995年(平成7年)1月17日午前5時46分、明石海峡を震源地とするマグニチュード7.3の直下型地震「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」によって明石市、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市など阪神間の各都市(兵庫県の沿海部とその周辺地域)、および淡路島北部が最大震度7の激しい揺れに襲われ、各地で甚大な被害が発生した。死者6,433名、行方不明者3名、負傷者4万人以上、家屋の全半壊24万軒(世帯としては約44万世帯)。地震による火災での全半焼約6,200軒超。災害救助法適用は兵庫県内10市10町にのぼる。
交通関係については、港湾関係で埠頭の沈下等、鉄道関係で山陽新幹線の高架橋等の倒壊・落橋による不通を含むJR西日本等合計13社において不通、道路関係で地震発生直後、高速自動車国道、阪神高速道路等の27路線36区間について通行止めになるなどの被害が発生した。また地震発生直後から長期間にわたるライフライン(上下水道・電気・ガス・電話)の不通、消防・救急体制の混乱、各種産業・企業への被害、文化財への被害など、被害総額はおよそ10兆円に達した。
■新潟県中越地震(直下型)
新潟県中越地方を震央として平成16年10月23日17時56分ころ発生した地震のこと。顕著な被害があったことから命名された。震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは6.8(速報値)、最大震度は7(新潟県川口町)。揺れの強さを示す目安の一つである加速度は、小千谷市で研究所観測史上最大の1500ガル*1を記録したと発表があった(防災科学技術研究所による)。さらに、震度6強もともなう、大きな余震が続いた。
17時56分ごろの強震動
発生時刻
2004年10月23日(土)17時56分ごろ
最大震度
震度7(川口町役場にある震度計で観測)
震源地
北緯37.3度・東経138.8度
震源の深さ
20km
地震の規模
マグニチュード6.8
■東北地方太平洋沖地震(海溝型)
2011年3月11日14時46分頃、三陸沖で発生した地震。英名「The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake」(気象庁)。太平洋プレートと北米プレートのプレート境界域における海溝型地震である。西北西-東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型。岩石が破壊された震源域は岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmの広範囲に及ぶ。このような規模の地震は869年の貞観三陸地震(M8.3~8.6)に続いて、約1000年ぶりに発生した可能性も指摘されている。
名称については気象庁が「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」と命名した。なお、この地震に伴う災害の呼称について、3月中はNHKが東北関東大震災、民放などが東日本大震災としていた。4月1日の閣議で正式名称が「東日本大震災」と決まった。
発生時刻(JST) 2011年3月11日14時46分18.1秒
震央地名・震源経緯度 三陸沖、北緯38°6.2′ 東経142°51.6′
深さ 24km
マグニチュード(Mw) 9.0
第1波
14時46分、震源の深さ24km、マグニチュード9.0(暫定値。モーメントマグニチュードMwによる発表)の地震が発生。宮城県栗原市築館で最大震度7を記録。
震度7を記録したのは新潟県中越地震以来、7年ぶりで、日本の地震の中で3回目である。(前二回は兵庫県南部地震(Mj7.3/Mw6.9)、新潟県中越地震(Mj6.8/Mw6.6)。)気象庁は日本観測史上では最大規模の地震であると発表、1900年以降世界で起きた地震の中で4番目に強い地震となった。
高度利用者向け緊急地震速報第1報では、「3/11 14:46:19発生 三陸沖でマグニチュード4.3、深さ10kmの地震が発生、最大予想震度2」との情報が配信されたが、最終報で「3/11 14:46:17発生 三陸沖でマグニチュード8.1、深さ10kmの地震が発生、最大予想震度7」と急激に上方修正された。
数分後、気象庁が最大震度6強を発表、それと同時に大津波警報、津波警報、津波注意報を発表。さらに数分後最大震度が7に修正された。
第2波以降この地震に続いて、15時8分に最大震度5弱、同時9分に最大震度5強の余震と思われる地震が発生。
宮城沖M8.4の地震発生から29分後、茨城県沖で最大震度6弱、深さ80km、M7.4の地震が発生、東北地方から関東地方にかけての広い範囲に甚大な被害をもたらした。北米プレートの端に沿って、このベルト上で多くの余震が発生している。
第2波以降
この地震に続いて、15時8分に最大震度5弱、同時9分に最大震度5強の余震と思われる地震が発生。宮城沖M8.4の地震発生から29分後、茨城県沖で最大震度6弱、深さ80km、M7.4の地震が発生、東北地方から関東地方にかけての広い範囲に甚大な被害をもたらした。北米プレートの端に沿って、このベルト上で多くの余震が発生している。
【マグニチュードと震度】
マグニチュード
マグニチュードとは、地震の規模(エネルギーの対数の大きさ)を数字に表したもので、1937年に、アメリカの地震学者チャールズ・F・リヒターによって定義された。マグニチュードが1増えると、エネルギーは約32倍になる。要するに地震が起こるときの力(エネルギー)そのものの大きさ。この「magnitude」というのはラテン語で「大きさ」という意味なんですが、英語では「大きさ」のほかに「光度」という意味もあって、星の明るさを表すときにも使われている。一等星が「ファーストマグニチュード」みたいな感じ。
震度
震度とは、ある場所での地震の揺れの強さを気象庁震度階級に則って表したもの。 同じ地震の揺れでも、測定する場所によって揺れの大きさは変わる。震源地に近いところや地盤が弱いところなんかが揺れが大きい。マグニチュードで表されるエネルギーが地面を伝わって、地表まで達したときの揺れの大きさのことで、日本では気象庁震度階級として設定されている。
震度階級
1948年の福井地震のあとに震度7が設けられた。
震度0無感…地震計(震度計)が検知し、人は揺れを感じない。
震度1微震…静止している人や特に注意している人だけに感じられる。
震度2軽震…人に感じられ、障子などがわずかに動く。
震度3弱震…家が揺れ、戸・障子などが音を立てる。
震度4中震…家が激しく揺れ、八分目ぐらい入れた水が入れ物からあふれ出る。
震度5強震…壁が割れ、煙突が壊れたりする。
震度6烈震…家が倒れる割合が30%以下で、崖崩れ、地割れが起こる。
震度7激震…家屋の30%以上が倒れ、山崩れや地割れができる。
|
|
|
|
|
|
|
|
■危機管理@放射能情報倉庫 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
■危機管理@放射能情報倉庫のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90004人
- 3位
- 酒好き
- 170654人