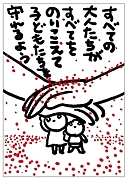---------------------
【政府、官僚の基本姿勢】
----------------------------------------------------------------------------
日本の政府、官僚、企業は「原発は”安全”なんだから事故対応なんか想定する必要はない」「事故なんか想定してそのための対策を講じたら、まるで”原発は危険だ”と言ってるようなものだから、そんな事故想定なんか許さん!!!」が基本姿勢です。
あと避難区域と被曝基準の設定は「国、企業の責任」と「被害補償、損害賠償の金額」と比例、直結しますので「国民の健康被害」が前提ではなく「出来うる限り責任は小さく」「被害補償額と損害賠償額は抑える」が大前提であると認識して間違いありません。
-----------------------------------------------------------------------------
国際評価は40km〜80km圏内
50km圏避難なら1200万人 試算
http://
■米国は50マイル80km・米国エネルギー省でさえ25マイル40km圏内
アメリカが当初指示を出していた50マイル80km圏内避難勧告。原発推進の米国エネルギー省でさえ25マイル40km圏内を避難勧告エリアとしている。日本の避難勧告は20km圏内で30km圏内は屋内退避だった。その発表をした枝野官房長官の家族は事故直後にシンガポールに避難で、枝野官房長官が福島現地視察で車から降りたのは5分。レベル7を国民には隠蔽し、安全だと呼びかけていた枝野官房長官=政府=官僚には、もはや信用性は全くない。
■資料
【米軍、福島原発80キロ圏内からの避難命令】2011年 3月 17日 8:07 JST
米国防総省は16日、福島第1原子力発電所からの放射能被ばくを避けるため、少なくとも50マイル(80キロメートル)圏から避難するよう軍関係者に命じた。国防総省が設定した範囲は、日本政府が先に設定したものよりも大きい。日本では原発から20キロ圏の避難と20〜30キロ圏内の屋内退避が指示されている。米政府はこれまで、日本にいる米国人は日本政府の勧告に従うよう求めていた。在東京米大使館は15日、米国人は20キロ圏から離れるよう勧告。また同日出された米原子力規制委員会(NRC)の声明は「日本政府が勧告した措置は、米国が同様の状況下で取る措置と同じだ」としていた。
これとは別に、ホワイトハウスは16日、原発から80キロ圏内にいる米国人は避難するよう勧告した。カーニー米大統領報道官によると、ジャッコNRC委員長は原発状況の「悪化」に鑑みてオバマ大統領に勧告した。同報道官は、避難の支援が必要な米国人は在日大使館に連絡を取るよう求めている。ラパン米国防総省副報道官は16日、記者会見し、在日米軍は原発から80キロ以上離れるよう命令を受けたと述べるとともに、これは予防措置として「米軍だけに対して」出されたと指摘した。同副報道官は、米軍がいつこの80キロ圏を設定したのかすぐには分からないとしている。さらに、震災救援に当たっている米軍も事態の変化に対応できるようにしていると語った。
同副報道官は「われわれはあらゆる事態に対応できるように訓練され、装備を持っている」とし、「われわれは測定、検査、対応、予防措置の方法を知っている」と強調した。一方で米軍による震災救援活動は活発化しており、これまでに船舶14隻が東北沖合に到着。第7艦隊旗艦のブルー・リッジは17日に到着する予定だ。また、米軍は2台の消防車を原発に派遣。日本政府は追加のポンプやホースの提供を求めている。これらの消火設備は日本人が操作している。
【40キロ圏外は避難不要 米国エネルギー省が見解】
米エネルギー省(DOE)は7日、福島第一原子力発電所から25マイル(約40キロ)圏外の放射線量は減り続けており、避難や移住などの必要がない放射線量になっている、とする見解を発表した。航空機観測などに基づく推定データで、米国民の避難範囲を「50マイル(約80キロ)圏内」としている。米原子力規制委員会(NRC)の勧告見直しにつながる可能性がある。DOEはまた、放射線を出している物質の多くが半減期が8日と短いヨウ素131とみられることや、3月19日以降は測定にかかるほどの量の放射性物質の降下がないことも明らかにした。
【50マイル圏内避難が妥当】2011年4月16日 (土)
【パリ】フランスの放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)は、福島第1原発事故で大気中に放出された放射性物質が今後1年間に、同原発から北西に向かう帯状の50〜60キロの範囲で土壌に強い影響を与える可能性があるとする報告書をまとめた。特に雨に含まれた放射性物質が遠方に拡散し、地上に堆積(たいせき)する危険性を指摘している。報告書は、米国が計測したこれまでの放出量などをもとに、土壌汚染が原発から北西50〜60キロの範囲で帯状に続き、最高でフランス人の年間平均被ばく量の4〜8倍になる可能性があるとした。一方で、放射性物質の中には半減期が短いものがあるため、土壌の汚染度は数週間で低下するとも指摘した。
【<福島第1原発>内閣官房参与、抗議の辞任】
(毎日新聞 - 04月29日 21:23)
東日本大震災発生後の3月16日に内閣官房参与に任命された小佐古敏荘・東京大大学院教授(放射線安全学)が29日、菅直人首相あての辞表を首相官邸に出した。小佐古氏は国会内で記者会見し、東京電力福島第1原発事故の政府対応を「場当たり的」と批判。特に小中学校などの屋外活動を制限する限界放射線量を年間20ミリシーベルトに決めたことに「容認すれば学者生命は終わり。自分の子どもをそういう目に遭わせたくない」と異論を唱えた。
小佐古氏は、政府の原子力防災指針で「緊急事態の発生直後から速やかに開始されるべきもの」とされた「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」による影響予測がすぐに実施・公表されなかったことなどを指摘。「法律を軽視してその場限りの対応を行い、事態収束を遅らせている」と批判した。
小佐古氏はまた、学校の放射線基準を、年間1ミリシーベルトとするよう主張したのに採用されなかったことを明かし、「年間20ミリシーベルト近い被ばくをする人は放射線業務従事者でも極めて少ない。この数値を小学生らに求めることは、私のヒューマニズムからしても受け入れがたい」と述べた。【吉永康朗】
内閣官房参与が「抗議」の辞任
http://
小佐古参与「官邸の対応場当たり的」と辞職届
東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応に当たるため、先月、内閣官房参与に任命された小佐古敏荘・東大教授(放射線安全学)は29日、国会内で記者会見し、「政府の対応は法にのっとっておらず、誰が決定したのかも明らかでなく、納得できない」として30日付で参与を辞任することを明らかにした。
小佐古氏は29日夕、首相官邸を訪れ、菅首相との面会を求めたが、実現せず、秘書官を通じて辞職願を提出、受理された。
その後、記者会見した小佐古氏は、辞任理由について、「今回の原子力災害で、官邸の対応はその場限りで場当たり的だ。提言の多くが受け入れられなかった」と語った。具体的には、年間被曝放射線量20ミリ・シーベルトを上限に小学校などの校庭利用を認めた政府の安全基準について、「この数値を小学生などに求めることは許し難い」と指摘した。
(2011年4月29日20時33分 読売新聞)
小佐古 敏荘(こさこ としそう)
国籍 日本
教育 東京大学大学院
工学系研究科博士課程修了
業績
専門分野 原子力工学
勤務先 東京大学
小佐古 敏荘(こさこ としそう)は、日本の工学者(放射線安全学)。東京大学大学院工学系研究科教授。
東京大学原子力研究総合センター助教授、内閣官房参与などを歴任した。
来歴
生い立ち
東京大学に入学し、工学部の原子力工学科にて学んだ。1972年、同大学を卒業、大学院に進学。工学系研究科の原子力工学専門課程にて学び、1974年に修士課程を修了。1977年に博士課程を修了。
工学者として
東京大学大学院を修了した1977年、同大学に採用され、原子核研究所の助手として着任した。その後、1982年には、東京大学の原子力研究総合センターにて、助教授に昇任した[1]。2005年、東京大学大学院において、工学系研究科の原子力専攻にて教授に昇任した。また、2011年には、福島第一原子力発電所事故の発生にともない内閣官房の参与に就任したが、同年、「いろいろと官邸に申し入れてきたが、受け入れられなかった」と述べ、退任を示唆した。特に、原子力発電所の作業員の緊急時被曝線量限度を年100ミリシーベルトから年250ミリシーベルトに引き上げたことについて「もぐらたたき的、場当たり的な政策決定を官邸と行政機関が取り、手続きを無視している」と主張するとともに、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムの測定結果の公表が遅いと指摘した。2011年4月29日に小沢系の民主党空本誠喜衆院議員の同席の元に内閣官房参与の辞任記者会見を行った。
現在は、東京大学大学院にて、工学系研究科の原子力専攻の教授を務めている。
人物
趣味として、水泳や工作を挙げている[5]。『日本経済新聞』を愛読する。幼いころの将来の夢は旋盤工だったという[5]。
略歴
1972年 - 東京大学工学部卒業。
1974年 - 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。
1977年 - 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。
1977年 - 東京大学原子核研究所助手。
1982年 - 東京大学原子力研究総合センター助教授。
2005年 - 東京大学大学院工学系研究科教授。
2011年 - 内閣官房参与。
【政府、官僚の基本姿勢】
----------------------------------------------------------------------------
日本の政府、官僚、企業は「原発は”安全”なんだから事故対応なんか想定する必要はない」「事故なんか想定してそのための対策を講じたら、まるで”原発は危険だ”と言ってるようなものだから、そんな事故想定なんか許さん!!!」が基本姿勢です。
あと避難区域と被曝基準の設定は「国、企業の責任」と「被害補償、損害賠償の金額」と比例、直結しますので「国民の健康被害」が前提ではなく「出来うる限り責任は小さく」「被害補償額と損害賠償額は抑える」が大前提であると認識して間違いありません。
-----------------------------------------------------------------------------
国際評価は40km〜80km圏内
50km圏避難なら1200万人 試算
http://
■米国は50マイル80km・米国エネルギー省でさえ25マイル40km圏内
アメリカが当初指示を出していた50マイル80km圏内避難勧告。原発推進の米国エネルギー省でさえ25マイル40km圏内を避難勧告エリアとしている。日本の避難勧告は20km圏内で30km圏内は屋内退避だった。その発表をした枝野官房長官の家族は事故直後にシンガポールに避難で、枝野官房長官が福島現地視察で車から降りたのは5分。レベル7を国民には隠蔽し、安全だと呼びかけていた枝野官房長官=政府=官僚には、もはや信用性は全くない。
■資料
【米軍、福島原発80キロ圏内からの避難命令】2011年 3月 17日 8:07 JST
米国防総省は16日、福島第1原子力発電所からの放射能被ばくを避けるため、少なくとも50マイル(80キロメートル)圏から避難するよう軍関係者に命じた。国防総省が設定した範囲は、日本政府が先に設定したものよりも大きい。日本では原発から20キロ圏の避難と20〜30キロ圏内の屋内退避が指示されている。米政府はこれまで、日本にいる米国人は日本政府の勧告に従うよう求めていた。在東京米大使館は15日、米国人は20キロ圏から離れるよう勧告。また同日出された米原子力規制委員会(NRC)の声明は「日本政府が勧告した措置は、米国が同様の状況下で取る措置と同じだ」としていた。
これとは別に、ホワイトハウスは16日、原発から80キロ圏内にいる米国人は避難するよう勧告した。カーニー米大統領報道官によると、ジャッコNRC委員長は原発状況の「悪化」に鑑みてオバマ大統領に勧告した。同報道官は、避難の支援が必要な米国人は在日大使館に連絡を取るよう求めている。ラパン米国防総省副報道官は16日、記者会見し、在日米軍は原発から80キロ以上離れるよう命令を受けたと述べるとともに、これは予防措置として「米軍だけに対して」出されたと指摘した。同副報道官は、米軍がいつこの80キロ圏を設定したのかすぐには分からないとしている。さらに、震災救援に当たっている米軍も事態の変化に対応できるようにしていると語った。
同副報道官は「われわれはあらゆる事態に対応できるように訓練され、装備を持っている」とし、「われわれは測定、検査、対応、予防措置の方法を知っている」と強調した。一方で米軍による震災救援活動は活発化しており、これまでに船舶14隻が東北沖合に到着。第7艦隊旗艦のブルー・リッジは17日に到着する予定だ。また、米軍は2台の消防車を原発に派遣。日本政府は追加のポンプやホースの提供を求めている。これらの消火設備は日本人が操作している。
【40キロ圏外は避難不要 米国エネルギー省が見解】
米エネルギー省(DOE)は7日、福島第一原子力発電所から25マイル(約40キロ)圏外の放射線量は減り続けており、避難や移住などの必要がない放射線量になっている、とする見解を発表した。航空機観測などに基づく推定データで、米国民の避難範囲を「50マイル(約80キロ)圏内」としている。米原子力規制委員会(NRC)の勧告見直しにつながる可能性がある。DOEはまた、放射線を出している物質の多くが半減期が8日と短いヨウ素131とみられることや、3月19日以降は測定にかかるほどの量の放射性物質の降下がないことも明らかにした。
【50マイル圏内避難が妥当】2011年4月16日 (土)
【パリ】フランスの放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)は、福島第1原発事故で大気中に放出された放射性物質が今後1年間に、同原発から北西に向かう帯状の50〜60キロの範囲で土壌に強い影響を与える可能性があるとする報告書をまとめた。特に雨に含まれた放射性物質が遠方に拡散し、地上に堆積(たいせき)する危険性を指摘している。報告書は、米国が計測したこれまでの放出量などをもとに、土壌汚染が原発から北西50〜60キロの範囲で帯状に続き、最高でフランス人の年間平均被ばく量の4〜8倍になる可能性があるとした。一方で、放射性物質の中には半減期が短いものがあるため、土壌の汚染度は数週間で低下するとも指摘した。
【<福島第1原発>内閣官房参与、抗議の辞任】
(毎日新聞 - 04月29日 21:23)
東日本大震災発生後の3月16日に内閣官房参与に任命された小佐古敏荘・東京大大学院教授(放射線安全学)が29日、菅直人首相あての辞表を首相官邸に出した。小佐古氏は国会内で記者会見し、東京電力福島第1原発事故の政府対応を「場当たり的」と批判。特に小中学校などの屋外活動を制限する限界放射線量を年間20ミリシーベルトに決めたことに「容認すれば学者生命は終わり。自分の子どもをそういう目に遭わせたくない」と異論を唱えた。
小佐古氏は、政府の原子力防災指針で「緊急事態の発生直後から速やかに開始されるべきもの」とされた「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」による影響予測がすぐに実施・公表されなかったことなどを指摘。「法律を軽視してその場限りの対応を行い、事態収束を遅らせている」と批判した。
小佐古氏はまた、学校の放射線基準を、年間1ミリシーベルトとするよう主張したのに採用されなかったことを明かし、「年間20ミリシーベルト近い被ばくをする人は放射線業務従事者でも極めて少ない。この数値を小学生らに求めることは、私のヒューマニズムからしても受け入れがたい」と述べた。【吉永康朗】
内閣官房参与が「抗議」の辞任
http://
小佐古参与「官邸の対応場当たり的」と辞職届
東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応に当たるため、先月、内閣官房参与に任命された小佐古敏荘・東大教授(放射線安全学)は29日、国会内で記者会見し、「政府の対応は法にのっとっておらず、誰が決定したのかも明らかでなく、納得できない」として30日付で参与を辞任することを明らかにした。
小佐古氏は29日夕、首相官邸を訪れ、菅首相との面会を求めたが、実現せず、秘書官を通じて辞職願を提出、受理された。
その後、記者会見した小佐古氏は、辞任理由について、「今回の原子力災害で、官邸の対応はその場限りで場当たり的だ。提言の多くが受け入れられなかった」と語った。具体的には、年間被曝放射線量20ミリ・シーベルトを上限に小学校などの校庭利用を認めた政府の安全基準について、「この数値を小学生などに求めることは許し難い」と指摘した。
(2011年4月29日20時33分 読売新聞)
小佐古 敏荘(こさこ としそう)
国籍 日本
教育 東京大学大学院
工学系研究科博士課程修了
業績
専門分野 原子力工学
勤務先 東京大学
小佐古 敏荘(こさこ としそう)は、日本の工学者(放射線安全学)。東京大学大学院工学系研究科教授。
東京大学原子力研究総合センター助教授、内閣官房参与などを歴任した。
来歴
生い立ち
東京大学に入学し、工学部の原子力工学科にて学んだ。1972年、同大学を卒業、大学院に進学。工学系研究科の原子力工学専門課程にて学び、1974年に修士課程を修了。1977年に博士課程を修了。
工学者として
東京大学大学院を修了した1977年、同大学に採用され、原子核研究所の助手として着任した。その後、1982年には、東京大学の原子力研究総合センターにて、助教授に昇任した[1]。2005年、東京大学大学院において、工学系研究科の原子力専攻にて教授に昇任した。また、2011年には、福島第一原子力発電所事故の発生にともない内閣官房の参与に就任したが、同年、「いろいろと官邸に申し入れてきたが、受け入れられなかった」と述べ、退任を示唆した。特に、原子力発電所の作業員の緊急時被曝線量限度を年100ミリシーベルトから年250ミリシーベルトに引き上げたことについて「もぐらたたき的、場当たり的な政策決定を官邸と行政機関が取り、手続きを無視している」と主張するとともに、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムの測定結果の公表が遅いと指摘した。2011年4月29日に小沢系の民主党空本誠喜衆院議員の同席の元に内閣官房参与の辞任記者会見を行った。
現在は、東京大学大学院にて、工学系研究科の原子力専攻の教授を務めている。
人物
趣味として、水泳や工作を挙げている[5]。『日本経済新聞』を愛読する。幼いころの将来の夢は旋盤工だったという[5]。
略歴
1972年 - 東京大学工学部卒業。
1974年 - 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。
1977年 - 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。
1977年 - 東京大学原子核研究所助手。
1982年 - 東京大学原子力研究総合センター助教授。
2005年 - 東京大学大学院工学系研究科教授。
2011年 - 内閣官房参与。
|
|
|
|
コメント(15)
子供を産む夢がつぶされたら
東電副社長が謝罪も怒号飛ぶ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1588319&media_id=2
東電側の説明に納得できない住民から「ふざけるな」と怒号が飛び、女子高生が「将来結婚し、子供を産む夢がつぶされたら補償してくれるのか」と問いかける場面もあった。
【資料】
福島市内から峠を越え、盆地に広がる福島県飯舘村(人口約6千人)8日午前、役場前で7〜8マイクロシーベルト。隣接する川俣町中心部の約10倍。土壌からは高濃度のセシウムとヨウ素が検出。
■母乳の放射性物質濃度等に関する調査結果(厚生労働省)
放射性ヨウ素(131I)
放射性セシウム(134Cs)
放射性セシウム(137Cs)
測定値(ベクレル/キログラム)
1福島市
2011/4/25
ND(検出下限値:1.7)
ND(検出下限値:1.9)
ND(検出下限値:2.3)
2郡山市
2011/4/25
ND(検出下限値:1.8)
ND(検出下限値:2.4)
ND(検出下限値:2.4)
3相馬郡
2011/4/25
ND(検出下限値:2.0)
ND(検出下限値:3.2)
ND(検出下限値:2.8)
4いわき市
2011/4/25
3.5
ND(検出下限値:2.2)
2.4
3/11-14は30km圏内に住んでいた
5ひたちなか市
2011/4/25
ND(検出下限値:2.1)
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.9)
6常陸大宮市
2011/4/25
3.0
ND(検出下限値:4.2)
ND(検出下限値:3.1)
7水戸市
2011/4/25
8.0
ND(検出下限値:3.0)
ND(検出下限値:3.0)
8結城市
2011/4/24
ND(検出下限値:2.0)
ND(検出下限値:2.6)
ND(検出下限値:2.3)
9下妻市
2011/4/25
2.2
ND(検出下限値:2.7)
ND(検出下限値:2.8)
10笠間市
2011/4/24
2.3
ND(検出下限値:2.4)
ND(検出下限値:2.7)
11笠間市
2011/4/25
2.3
ND(検出下限値:3.4)
ND(検出下限値:2.6)
12
笠間市
2011/4/25
ND(検出下限値:2.1)
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.7)
13那珂市
2011/4/25
ND(検出下限値:2.7)
ND(検出下限値:3.1)
ND(検出下限値:3.0)
14千葉市
2011/4/25
ND(検出下限値:3.6)
ND(検出下限値:4.6)
ND(検出下限値:3.4)
15千葉市
2011/4/25
2.3
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.6)
16埼玉県
越谷市
2011/4/24
ND(検出下限値:1.9)
ND(検出下限値:2.1)
ND(検出下限値:2.1)
17杉並区
2011/4/24
ND(検出下限値:1.8)
ND(検出下限値:2.2)
ND(検出下限値:1.9)
18世田谷区
2011/4/25
ND(検出下限値:2.3)
ND(検出下限値:3.9)
ND(検出下限値:2.9)
19中野区
2011/4/25
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.7)
ND(検出下限値:2.8)
20武蔵野市
2011/4/25
ND(検出下限値:2.4)
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.7)
21中野区
2011/4/25
ND(検出下限値:6.5)
ND(検出下限値:7.2)
ND(検出下限値:7.0)
22江戸川区
2011/4/24
ND(検出下限値:1.6)
ND(検出下限値:1.8)
ND(検出下限値:1.9)
23文京区
2011/4/25
ND(検出下限値:2.6)
ND(検出下限値:3.7)
ND(検出下限値:3.0)
※ND=不検出(検出下限以下)
・放射性ヨウ素 100ベクレル/キログラム
・放射性セシウム 200ベクレル/キログラム
厚生労働省の検査でも母乳から微量の放射性物質
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110430/t10015647491000.html
検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001azxj-img/2r9852000001b01o.pdf
東電副社長が謝罪も怒号飛ぶ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1588319&media_id=2
東電側の説明に納得できない住民から「ふざけるな」と怒号が飛び、女子高生が「将来結婚し、子供を産む夢がつぶされたら補償してくれるのか」と問いかける場面もあった。
【資料】
福島市内から峠を越え、盆地に広がる福島県飯舘村(人口約6千人)8日午前、役場前で7〜8マイクロシーベルト。隣接する川俣町中心部の約10倍。土壌からは高濃度のセシウムとヨウ素が検出。
■母乳の放射性物質濃度等に関する調査結果(厚生労働省)
放射性ヨウ素(131I)
放射性セシウム(134Cs)
放射性セシウム(137Cs)
測定値(ベクレル/キログラム)
1福島市
2011/4/25
ND(検出下限値:1.7)
ND(検出下限値:1.9)
ND(検出下限値:2.3)
2郡山市
2011/4/25
ND(検出下限値:1.8)
ND(検出下限値:2.4)
ND(検出下限値:2.4)
3相馬郡
2011/4/25
ND(検出下限値:2.0)
ND(検出下限値:3.2)
ND(検出下限値:2.8)
4いわき市
2011/4/25
3.5
ND(検出下限値:2.2)
2.4
3/11-14は30km圏内に住んでいた
5ひたちなか市
2011/4/25
ND(検出下限値:2.1)
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.9)
6常陸大宮市
2011/4/25
3.0
ND(検出下限値:4.2)
ND(検出下限値:3.1)
7水戸市
2011/4/25
8.0
ND(検出下限値:3.0)
ND(検出下限値:3.0)
8結城市
2011/4/24
ND(検出下限値:2.0)
ND(検出下限値:2.6)
ND(検出下限値:2.3)
9下妻市
2011/4/25
2.2
ND(検出下限値:2.7)
ND(検出下限値:2.8)
10笠間市
2011/4/24
2.3
ND(検出下限値:2.4)
ND(検出下限値:2.7)
11笠間市
2011/4/25
2.3
ND(検出下限値:3.4)
ND(検出下限値:2.6)
12
笠間市
2011/4/25
ND(検出下限値:2.1)
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.7)
13那珂市
2011/4/25
ND(検出下限値:2.7)
ND(検出下限値:3.1)
ND(検出下限値:3.0)
14千葉市
2011/4/25
ND(検出下限値:3.6)
ND(検出下限値:4.6)
ND(検出下限値:3.4)
15千葉市
2011/4/25
2.3
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.6)
16埼玉県
越谷市
2011/4/24
ND(検出下限値:1.9)
ND(検出下限値:2.1)
ND(検出下限値:2.1)
17杉並区
2011/4/24
ND(検出下限値:1.8)
ND(検出下限値:2.2)
ND(検出下限値:1.9)
18世田谷区
2011/4/25
ND(検出下限値:2.3)
ND(検出下限値:3.9)
ND(検出下限値:2.9)
19中野区
2011/4/25
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.7)
ND(検出下限値:2.8)
20武蔵野市
2011/4/25
ND(検出下限値:2.4)
ND(検出下限値:2.8)
ND(検出下限値:2.7)
21中野区
2011/4/25
ND(検出下限値:6.5)
ND(検出下限値:7.2)
ND(検出下限値:7.0)
22江戸川区
2011/4/24
ND(検出下限値:1.6)
ND(検出下限値:1.8)
ND(検出下限値:1.9)
23文京区
2011/4/25
ND(検出下限値:2.6)
ND(検出下限値:3.7)
ND(検出下限値:3.0)
※ND=不検出(検出下限以下)
・放射性ヨウ素 100ベクレル/キログラム
・放射性セシウム 200ベクレル/キログラム
厚生労働省の検査でも母乳から微量の放射性物質
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110430/t10015647491000.html
検査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001azxj-img/2r9852000001b01o.pdf
「直ちに影響はない」の意味
【直ちに影響は無い】
政府、官僚、東電がいつも発表する「直ちに影響は無い」というコメント、基準値、指導方針は、下記潜伏期間を無視した「直ちに影響は出ないが何年か先の影響は知らない」という意味です。
■放射線誘発ガンの潜伏期間「晩発影響」
晩発影響とは被曝後 長時間を経て現れる症状のことです。がん、白血病、放射線白内障などが挙げられます。
「国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告」によると、1Sv の放射線被曝をしたときに生涯のあいだに生じる致死的なガンの発生確率は0.04%と報じられています。
【放射線誘発ガンの潜伏期間】
白血病
2年(最小潜伏期間)
8年(中央値)
40年(生涯)
その他のガン
10年(最小潜伏期間)
16〜24年(中央値)
生涯(生涯)
(ICRP Publ.60) 出典]辻本忠・草間朋子:放射線防護の基礎-第2版-、日刊工業新聞社(1992.4)、p79
【直ちに影響は無い】
政府、官僚、東電がいつも発表する「直ちに影響は無い」というコメント、基準値、指導方針は、下記潜伏期間を無視した「直ちに影響は出ないが何年か先の影響は知らない」という意味です。
■放射線誘発ガンの潜伏期間「晩発影響」
晩発影響とは被曝後 長時間を経て現れる症状のことです。がん、白血病、放射線白内障などが挙げられます。
「国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告」によると、1Sv の放射線被曝をしたときに生涯のあいだに生じる致死的なガンの発生確率は0.04%と報じられています。
【放射線誘発ガンの潜伏期間】
白血病
2年(最小潜伏期間)
8年(中央値)
40年(生涯)
その他のガン
10年(最小潜伏期間)
16〜24年(中央値)
生涯(生涯)
(ICRP Publ.60) 出典]辻本忠・草間朋子:放射線防護の基礎-第2版-、日刊工業新聞社(1992.4)、p79
「老婆心ながら守秘義務」と官邸、小佐古教授に
福島原発
東京電力福島第一原子力発電所の事故対策を巡り、4月30日に内閣官房参与を辞任した小佐古敏荘(こさことしそう)・東京大学教授が2日夕に予定していた報道関係者向け説明会が中止された。
民主党の空本誠喜・衆院議員によると、小佐古教授が官邸から守秘義務の指摘を受けたことが、中止の理由だという。
小佐古教授は、政府の事故対応に納得できないとして、29日に辞任の意向を表明した。空本氏によると、小佐古教授は2日夕、小学校の校庭利用などについて文部科学省が説明した放射線被曝(ひばく)限度の問題点について詳細な説明を行う予定だった。
ところが1日、小佐古教授から空本氏に、「(官邸関係者から)老婆心ながら、守秘義務があると言われた」として、説明会には出席できないと電話で伝えてきたという。
文科省は校庭利用の放射線被曝限度を年間20ミリ・シーベルトとしている。空本氏は「小佐古教授は、子供の被曝量はせいぜい年間5ミリ・シーベルトにとどめるべきだという考え。きちんと説明する場がなくなったのは残念だ」と話している。
(2011年5月2日23時14分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110502-OYT1T01026.htm
福島原発
東京電力福島第一原子力発電所の事故対策を巡り、4月30日に内閣官房参与を辞任した小佐古敏荘(こさことしそう)・東京大学教授が2日夕に予定していた報道関係者向け説明会が中止された。
民主党の空本誠喜・衆院議員によると、小佐古教授が官邸から守秘義務の指摘を受けたことが、中止の理由だという。
小佐古教授は、政府の事故対応に納得できないとして、29日に辞任の意向を表明した。空本氏によると、小佐古教授は2日夕、小学校の校庭利用などについて文部科学省が説明した放射線被曝(ひばく)限度の問題点について詳細な説明を行う予定だった。
ところが1日、小佐古教授から空本氏に、「(官邸関係者から)老婆心ながら、守秘義務があると言われた」として、説明会には出席できないと電話で伝えてきたという。
文科省は校庭利用の放射線被曝限度を年間20ミリ・シーベルトとしている。空本氏は「小佐古教授は、子供の被曝量はせいぜい年間5ミリ・シーベルトにとどめるべきだという考え。きちんと説明する場がなくなったのは残念だ」と話している。
(2011年5月2日23時14分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110502-OYT1T01026.htm
【復興のために日本中の企業に脱原発を唱えるように訴えよう】
この方向がピンチをチャンスに変える方向だ。今後、ほとんどの経済が国際社会から締め出されるこれからの日本が「現在の最悪の事態をチャンスに変えて経済を回復させる方法」はコレしかない。この金融機関のように「脱原発」に向いた全てのビジネスが「日本が全ての国際社会、世界中の国民に受け入れられる唯一のビッグビジネス」「復興に向けたビジネス」となる。また国民の声では成し遂げられない「脱原発」も、日本中の企業が「脱原発」を唱えれば成し遂げられるかもしれない。
城南信用金庫が脱原発宣言〜理事長メッセージ
【内容】
とかく、お固い印象の金融機関が「脱原発」を宣言した。東京都品川区に本店を構える信金業界大手の城南信用金庫がホームページに、「原発に頼らない安心できる社会へ」と題したメッセージを掲載し、話題となっている。メッセージは2011年4月8日に掲載され、異例ともいえる「宣言」にネット上では「勇気ある行動だ」「応援する。預金する」「本気かよ。業界から爪弾きにされるんじゃない?」などの声があがっている。
■LED照明やソーラーパネルを導入
「東京電力福島第一原子力発電所の事故は、我が国の未来に重大な影響を与えています。」ではじまるメッセージは、言葉は抑えているが「反原発」への思いが明確に伝わってくる内容だ。まず事有るごとに「安全だ安全だ」と謳われてきた原子力発電は「全く安全ではないもの」「安全は嘘だった」ということに言及、その上で「信用金庫という地域を預かる金融機関にとって、その地域を失いかねない事態の福島県を思うと、いま企業の姿勢として反原発の立場を明確にし、そのうえで省エネや節電に協力していくことが必要だと考えた。自らが言うべきことを言い、やるべきことをやれば、地域金融機関として地元企業の協力を引き出していくこともできると考えている」と、城南信用金庫の吉原毅理事長はそう説明する。
同信金はメッセージで、今後は省電力や省エネルギー、代替エネルギーの開発利用に「少しでも貢献する」とし、その具体的な取り組みとして、徹底した節電運動の実施や冷暖房の設定温度の見直し、省電力型設備の導入や断熱工事の施工、緑化工事の推進、ソーラーパネルの設置にLED照明への切り替え、燃料電池や自家発電装置の導入など――をあげている。すでに本店のロビーやウインドウディスプレイの照明や、エレベーターの節電などで通常の電力量の約3割をカットできた。LED照明の切り替えや、大型店でのソーラーパネルの導入も、「できるところから順次実施していく」(吉原理事長)という。城南信金によると、営業区域内の経営者にも被災地の出身者は少なくなく、「反原発」宣言に賛同した福島県出身の工場経営者が、同信金が呼びかけている義援金に100万円を寄付したり、震災直後から取り扱っている「震災ボランティア預金」が発売後1か月の残高で2億円超を集めたりと、共感する人は少なくないようだ。
■「草の根金融」でユニークな取り組み
城南信用金庫といえば、「小原鐵学」といわれ、担保主義の銀行経営を嫌って「草の根金融」を説いた故・小原鐵五郎氏の経営を旨としてきた。本店に入ると事務室までの廊下は節電で薄暗く、ふだんから経費節減は徹底している。その一方で、宝くじ付定期預金の火付け役として「懸賞金付き定期預金スーパードリーム」をいち早く発売するなど、ユニークな取り組みで地域に根ざしてきた。震災支援も、被災地の金融機関への「支援金」や「見舞金」の振り込み手数料の無料化や、被災者への物資の支援にも積極的に取り組んでいる。吉原理事長は「ストップ原発も、信用金庫と同じ草の根運動で広がっていくものと考えている。メッセージに共感してもらえて、地元企業に省エネや節電運動が広がっていけばいい。もちろん、そのための融資には積極的に応じるし、こちらからも提案していきたい」と話している。
この方向がピンチをチャンスに変える方向だ。今後、ほとんどの経済が国際社会から締め出されるこれからの日本が「現在の最悪の事態をチャンスに変えて経済を回復させる方法」はコレしかない。この金融機関のように「脱原発」に向いた全てのビジネスが「日本が全ての国際社会、世界中の国民に受け入れられる唯一のビッグビジネス」「復興に向けたビジネス」となる。また国民の声では成し遂げられない「脱原発」も、日本中の企業が「脱原発」を唱えれば成し遂げられるかもしれない。
城南信用金庫が脱原発宣言〜理事長メッセージ
【内容】
とかく、お固い印象の金融機関が「脱原発」を宣言した。東京都品川区に本店を構える信金業界大手の城南信用金庫がホームページに、「原発に頼らない安心できる社会へ」と題したメッセージを掲載し、話題となっている。メッセージは2011年4月8日に掲載され、異例ともいえる「宣言」にネット上では「勇気ある行動だ」「応援する。預金する」「本気かよ。業界から爪弾きにされるんじゃない?」などの声があがっている。
■LED照明やソーラーパネルを導入
「東京電力福島第一原子力発電所の事故は、我が国の未来に重大な影響を与えています。」ではじまるメッセージは、言葉は抑えているが「反原発」への思いが明確に伝わってくる内容だ。まず事有るごとに「安全だ安全だ」と謳われてきた原子力発電は「全く安全ではないもの」「安全は嘘だった」ということに言及、その上で「信用金庫という地域を預かる金融機関にとって、その地域を失いかねない事態の福島県を思うと、いま企業の姿勢として反原発の立場を明確にし、そのうえで省エネや節電に協力していくことが必要だと考えた。自らが言うべきことを言い、やるべきことをやれば、地域金融機関として地元企業の協力を引き出していくこともできると考えている」と、城南信用金庫の吉原毅理事長はそう説明する。
同信金はメッセージで、今後は省電力や省エネルギー、代替エネルギーの開発利用に「少しでも貢献する」とし、その具体的な取り組みとして、徹底した節電運動の実施や冷暖房の設定温度の見直し、省電力型設備の導入や断熱工事の施工、緑化工事の推進、ソーラーパネルの設置にLED照明への切り替え、燃料電池や自家発電装置の導入など――をあげている。すでに本店のロビーやウインドウディスプレイの照明や、エレベーターの節電などで通常の電力量の約3割をカットできた。LED照明の切り替えや、大型店でのソーラーパネルの導入も、「できるところから順次実施していく」(吉原理事長)という。城南信金によると、営業区域内の経営者にも被災地の出身者は少なくなく、「反原発」宣言に賛同した福島県出身の工場経営者が、同信金が呼びかけている義援金に100万円を寄付したり、震災直後から取り扱っている「震災ボランティア預金」が発売後1か月の残高で2億円超を集めたりと、共感する人は少なくないようだ。
■「草の根金融」でユニークな取り組み
城南信用金庫といえば、「小原鐵学」といわれ、担保主義の銀行経営を嫌って「草の根金融」を説いた故・小原鐵五郎氏の経営を旨としてきた。本店に入ると事務室までの廊下は節電で薄暗く、ふだんから経費節減は徹底している。その一方で、宝くじ付定期預金の火付け役として「懸賞金付き定期預金スーパードリーム」をいち早く発売するなど、ユニークな取り組みで地域に根ざしてきた。震災支援も、被災地の金融機関への「支援金」や「見舞金」の振り込み手数料の無料化や、被災者への物資の支援にも積極的に取り組んでいる。吉原理事長は「ストップ原発も、信用金庫と同じ草の根運動で広がっていくものと考えている。メッセージに共感してもらえて、地元企業に省エネや節電運動が広がっていけばいい。もちろん、そのための融資には積極的に応じるし、こちらからも提案していきたい」と話している。
ベラルーシの少女の言葉
「私たちは国に見放されたのです。 汚染された食品を食べ続けてベラルーシが消えても、地球全体には何の影響も無いでしょう。 一つの民族が消えたという程度ですよ」
少女の体に放射能は
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1715161644&owner_id=4090144
終わりなき人体汚染
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1715158934&owner_id=4090144
■チェルノブイリの子供たち〜残酷な現実〜
チェルノブイリ原発事故の放射能内部被曝によって生まれてきた子供たちの写真、いわゆる「原発事故の遺産」です。今、日本人にも迫りつつある「原発事故の現実の残酷さ」「目に見えない放射能の危険性」から目を背けることなく、未来への正しい選択をするために「旧ソ連において放射能の被害を受けた子供たちからの悲しいメッセージ、怒りのメッセージ」としてここに遺しておきます。
※NETで誰でも拾える写真ですが見る見ないはご自身の判断で。
http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000019131715&owner_id=4090144
■【被曝による生殖腺の損傷】
人間は一年間に宇宙から0.4ミリシーベルト、大地から0.5ミリシーベルト、ラドンから1.2シーベルト、食物から0.3ミリシーベルトの合計約2.4ミリシーベルトの自然放射線を被爆しています。
この被爆によって生体は損傷を受けますが、最も重要な損傷は生殖腺の損傷、つまり妊娠能力の低下や奇形児が生まれることです。5シーベルトも被爆すれば人間は永久不妊となり、2.5シーベルトでも1〜2年は妊娠できません。
妊娠している女性が0.1シーベルト以上被爆すると奇形児が生まれる可能性が高くなります。このため、妊娠から出産までの期間は1ミリシーベルト以下になるように就労を制限している国が多いのです。
京都大學名誉教授 鍵谷 勤
http://www.gakkai.net/KRI/p-n.html
■「直ちに影響はない」の意味
【直ちに影響は無い】
政府、官僚、東電がいつも発表する「直ちに影響は無い」というコメント、基準値、指導方針は、下記潜伏期間を無視した「直ちに影響は出ないが何年か先の影響は知らない」という意味です。
■放射線誘発ガンの潜伏期間「晩発影響」
晩発影響とは被曝後 長時間を経て現れる症状のことです。がん、白血病、放射線白内障などが挙げられます。
「国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告」によると、1Sv の放射線被曝をしたときに生涯のあいだに生じる致死的なガンの発生確率は0.04%と報じられています。
【放射線誘発ガンの潜伏期間】
白血病
2年(最小潜伏期間)
8年(中央値)
40年(生涯)
その他のガン
10年(最小潜伏期間)
16〜24年(中央値)
生涯(生涯)
(ICRP Publ.60) 出典]辻本忠・草間朋子:放射線防護の基礎-第2版-、日刊工業新聞社(1992.4)、p79
「私たちは国に見放されたのです。 汚染された食品を食べ続けてベラルーシが消えても、地球全体には何の影響も無いでしょう。 一つの民族が消えたという程度ですよ」
少女の体に放射能は
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1715161644&owner_id=4090144
終わりなき人体汚染
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1715158934&owner_id=4090144
■チェルノブイリの子供たち〜残酷な現実〜
チェルノブイリ原発事故の放射能内部被曝によって生まれてきた子供たちの写真、いわゆる「原発事故の遺産」です。今、日本人にも迫りつつある「原発事故の現実の残酷さ」「目に見えない放射能の危険性」から目を背けることなく、未来への正しい選択をするために「旧ソ連において放射能の被害を受けた子供たちからの悲しいメッセージ、怒りのメッセージ」としてここに遺しておきます。
※NETで誰でも拾える写真ですが見る見ないはご自身の判断で。
http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000019131715&owner_id=4090144
■【被曝による生殖腺の損傷】
人間は一年間に宇宙から0.4ミリシーベルト、大地から0.5ミリシーベルト、ラドンから1.2シーベルト、食物から0.3ミリシーベルトの合計約2.4ミリシーベルトの自然放射線を被爆しています。
この被爆によって生体は損傷を受けますが、最も重要な損傷は生殖腺の損傷、つまり妊娠能力の低下や奇形児が生まれることです。5シーベルトも被爆すれば人間は永久不妊となり、2.5シーベルトでも1〜2年は妊娠できません。
妊娠している女性が0.1シーベルト以上被爆すると奇形児が生まれる可能性が高くなります。このため、妊娠から出産までの期間は1ミリシーベルト以下になるように就労を制限している国が多いのです。
京都大學名誉教授 鍵谷 勤
http://www.gakkai.net/KRI/p-n.html
■「直ちに影響はない」の意味
【直ちに影響は無い】
政府、官僚、東電がいつも発表する「直ちに影響は無い」というコメント、基準値、指導方針は、下記潜伏期間を無視した「直ちに影響は出ないが何年か先の影響は知らない」という意味です。
■放射線誘発ガンの潜伏期間「晩発影響」
晩発影響とは被曝後 長時間を経て現れる症状のことです。がん、白血病、放射線白内障などが挙げられます。
「国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告」によると、1Sv の放射線被曝をしたときに生涯のあいだに生じる致死的なガンの発生確率は0.04%と報じられています。
【放射線誘発ガンの潜伏期間】
白血病
2年(最小潜伏期間)
8年(中央値)
40年(生涯)
その他のガン
10年(最小潜伏期間)
16〜24年(中央値)
生涯(生涯)
(ICRP Publ.60) 出典]辻本忠・草間朋子:放射線防護の基礎-第2版-、日刊工業新聞社(1992.4)、p79
■1号機は「メルトダウン」…底部の穴から漏水
(読売新聞 - 05月12日 22:55)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1599577&media_id=20
結果、今回はたまたまメルトダウンが最悪の状況、いわゆる「水蒸気爆発に繋がらなかっただけ」「チャイナシンドロームに至らなかっただけ」「ただ単に運が良かっただけ」ということであり、漏水が給水を上回ったり、給水が一時的にでも出来無くなったら終わりだ。
現状が【人類史上最悪の綱渡り状態】であることは間違いない。
だいたい炉心の状態もマトモにモニタリングも出来ない状況下で、これまでの「安全」とか「影響は無い」とかを国民に公式発表してる時点で、結局「国や東電のご都合発表」「何の根拠も無い安全」「嘘吐き政府と嘘吐き企業」であることが明らかになっただけのことだ。
国も東電も危機管理意識が低すぎる。
危機的状況において「状況が掴めていない状態での希望的観測」「多分こうだろう」という安易な憶測は事実でも現実でも何でもないし、危険を増幅させるてるだけだ。現場の人間の勇気に報いるためにも国や東電は「本当の現実」「事実だけ」を国民に公表すべきだ。
コメント
レイコ2011年05月13日 11:57
ほんとに、、、。真っ暗闇で、なにも見えていないなか、
刀をふりまわしていただけ、、、みたいな感じですね。
二ヶ月、何をやっていたのでしょうか、、、。
前線で働いている人には申し訳ないけれど、
最先端技術で、対応は素人なみ、、なのが解せません。
はやく原発なくすべき。
酋長2011年05月14日 02:09
>レイコさん
ありがとうございます。
日本の政府官僚、東電は「原発は安全なんだから事故対応なんか想定する必要はない」「事故なんか想定してそのための対策を講じたら、まるで”原発は危険だ”と言ってるようなものだから、そんな事故想定なんか許さん」が基本姿勢です。
したがって日本では「根拠のない安全」を前提に事故対応スタッフは養成していないでしょうから、現在の前線作業員は「原発事故専門スタッフ」ではなく「原発建設専門スタッフ」だと考えられますので政府対応、東電トップ対応の問題だと思います。
最初から「原発事故対応の専門家」を世界から呼び寄せて対応しておけば、もっと状況も早く把握、的確な対策が取れて、ここまで被害は拡がらなかったかもしれないのに政府は事故現場隠蔽策でそういう対応に動きませんでしたからねー。
結局、原子炉建屋内の高濃度放射能汚染によって日本の原発事故専門ではない「原発建設作業員レベル」では手の付けようが無くて、この2ヶ月で水の注入以外は炉心から離れた場所のモニター復旧くらいしか出来てないのだと思います。
(読売新聞 - 05月12日 22:55)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1599577&media_id=20
結果、今回はたまたまメルトダウンが最悪の状況、いわゆる「水蒸気爆発に繋がらなかっただけ」「チャイナシンドロームに至らなかっただけ」「ただ単に運が良かっただけ」ということであり、漏水が給水を上回ったり、給水が一時的にでも出来無くなったら終わりだ。
現状が【人類史上最悪の綱渡り状態】であることは間違いない。
だいたい炉心の状態もマトモにモニタリングも出来ない状況下で、これまでの「安全」とか「影響は無い」とかを国民に公式発表してる時点で、結局「国や東電のご都合発表」「何の根拠も無い安全」「嘘吐き政府と嘘吐き企業」であることが明らかになっただけのことだ。
国も東電も危機管理意識が低すぎる。
危機的状況において「状況が掴めていない状態での希望的観測」「多分こうだろう」という安易な憶測は事実でも現実でも何でもないし、危険を増幅させるてるだけだ。現場の人間の勇気に報いるためにも国や東電は「本当の現実」「事実だけ」を国民に公表すべきだ。
コメント
レイコ2011年05月13日 11:57
ほんとに、、、。真っ暗闇で、なにも見えていないなか、
刀をふりまわしていただけ、、、みたいな感じですね。
二ヶ月、何をやっていたのでしょうか、、、。
前線で働いている人には申し訳ないけれど、
最先端技術で、対応は素人なみ、、なのが解せません。
はやく原発なくすべき。
酋長2011年05月14日 02:09
>レイコさん
ありがとうございます。
日本の政府官僚、東電は「原発は安全なんだから事故対応なんか想定する必要はない」「事故なんか想定してそのための対策を講じたら、まるで”原発は危険だ”と言ってるようなものだから、そんな事故想定なんか許さん」が基本姿勢です。
したがって日本では「根拠のない安全」を前提に事故対応スタッフは養成していないでしょうから、現在の前線作業員は「原発事故専門スタッフ」ではなく「原発建設専門スタッフ」だと考えられますので政府対応、東電トップ対応の問題だと思います。
最初から「原発事故対応の専門家」を世界から呼び寄せて対応しておけば、もっと状況も早く把握、的確な対策が取れて、ここまで被害は拡がらなかったかもしれないのに政府は事故現場隠蔽策でそういう対応に動きませんでしたからねー。
結局、原子炉建屋内の高濃度放射能汚染によって日本の原発事故専門ではない「原発建設作業員レベル」では手の付けようが無くて、この2ヶ月で水の注入以外は炉心から離れた場所のモニター復旧くらいしか出来てないのだと思います。
■児童・生徒への放射線量、文部科学省が試算(読売新聞 - 05月12日 20:40)
福島県内の学校校庭などで通常より高い放射線量が検出されている問題で、文部科学省は12日、4月に国が決めた、屋外活動を制限する基準値以上の学校に通い続けたと仮定した場合、福島第一原発事故後の1年間で子供が浴びる積算放射線量は約10ミリ・シーベルトになるとの試算を公表した。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1599463&media_id=20
省庁⇒原発が一番コストが安い、安全
事実⇒原発が一番コストが高い、危険
省庁⇒福島原発事故はレベル5以下
事実⇒福島原発事故はレベル7以上
人間には大人にも子供にも「個体差」があり、同じ子供でも体力や免疫力、発達差、持病やストレスの在る無しで「同じ10ミリ」でも影響は全く異なる。
■文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における暫定的な考え方」に対する日本医師会の見解
社団法人 日本医師会
文部科学省は、4 月19 日付けで、福島県内の学校の校庭利用等に係る限界放射線量を示す通知を福島県知事、福島県教育委員会等に対して発出した。この通知では、幼児、児童、生徒が受ける放射線量の限界を年間20 ミリシーベルトと暫定的に規定している。そこから16 時間が屋
内(木造)、8 時間が屋外という生活パターンを想定して、1 時間当たりの限界空間線量率を屋外3.8 マイクロシーベルト、屋内1.52 マイクロシーベルトとし、これを下回る学校では年間20 ミリシーベルトを超えることはないとしている。
しかし、そもそもこの数値の根拠としている国際放射線防護委員会(ICRP)が3 月21 日に発表した声明では「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして、1〜20 ミリシーベルト/年の範囲で考えることも可能」としているにすぎない。この1〜20 ミリシーベルトを最大値の20 ミリシーベルトとして扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にある子どもたちの放射線感受性の高さを考慮すると、国の対応はより慎重であるべきと考える。
成人についてももちろんであるが、とくに小児については、可能な限り放射線被曝量を減らすことに最大限の努力をすることが国の責務であり、これにより子どもたちの生命と健康を守ることこそが求められている。国は幼稚園・保育園の園庭、学校の校庭、公園等の表面の土を入れ替えるなど環境の改善方法について、福島県下の学校等の設置者に対して検討を進めるよう通知を出したが、国として責任をもって対応することが必要である。国ができうる最速・最大の方法で、子どもたちの放射線被曝量の減少に努めることを強く求めるものである。
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20110512_31.pdf
福島県内の学校校庭などで通常より高い放射線量が検出されている問題で、文部科学省は12日、4月に国が決めた、屋外活動を制限する基準値以上の学校に通い続けたと仮定した場合、福島第一原発事故後の1年間で子供が浴びる積算放射線量は約10ミリ・シーベルトになるとの試算を公表した。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1599463&media_id=20
省庁⇒原発が一番コストが安い、安全
事実⇒原発が一番コストが高い、危険
省庁⇒福島原発事故はレベル5以下
事実⇒福島原発事故はレベル7以上
人間には大人にも子供にも「個体差」があり、同じ子供でも体力や免疫力、発達差、持病やストレスの在る無しで「同じ10ミリ」でも影響は全く異なる。
■文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における暫定的な考え方」に対する日本医師会の見解
社団法人 日本医師会
文部科学省は、4 月19 日付けで、福島県内の学校の校庭利用等に係る限界放射線量を示す通知を福島県知事、福島県教育委員会等に対して発出した。この通知では、幼児、児童、生徒が受ける放射線量の限界を年間20 ミリシーベルトと暫定的に規定している。そこから16 時間が屋
内(木造)、8 時間が屋外という生活パターンを想定して、1 時間当たりの限界空間線量率を屋外3.8 マイクロシーベルト、屋内1.52 マイクロシーベルトとし、これを下回る学校では年間20 ミリシーベルトを超えることはないとしている。
しかし、そもそもこの数値の根拠としている国際放射線防護委員会(ICRP)が3 月21 日に発表した声明では「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして、1〜20 ミリシーベルト/年の範囲で考えることも可能」としているにすぎない。この1〜20 ミリシーベルトを最大値の20 ミリシーベルトとして扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にある子どもたちの放射線感受性の高さを考慮すると、国の対応はより慎重であるべきと考える。
成人についてももちろんであるが、とくに小児については、可能な限り放射線被曝量を減らすことに最大限の努力をすることが国の責務であり、これにより子どもたちの生命と健康を守ることこそが求められている。国は幼稚園・保育園の園庭、学校の校庭、公園等の表面の土を入れ替えるなど環境の改善方法について、福島県下の学校等の設置者に対して検討を進めるよう通知を出したが、国として責任をもって対応することが必要である。国ができうる最速・最大の方法で、子どもたちの放射線被曝量の減少に努めることを強く求めるものである。
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20110512_31.pdf
■子どもの「年20ミリシーベルト」基準に対する日弁連会長声明 2011/04/25 18:51
みなさま
文部科学省が、福島県の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安を「年20ミリシーベルト」とした件について、日本弁護士連合会の宇都宮健児会長の声明が4月22日付で出されています。以下、高木基金理事の中下裕子弁護士からのメール情報を転載します。
「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明
4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1〜20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とする」とされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。
しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。
第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可能性があることから、放射線被ばくはできるだけ避けるべきであることは当然のことである。とりわけ、政府が根拠とする国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)は成人から子どもまでを含んだ被ばく線量を前提としているが、多くの研究者により成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けやすいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受けるのが子どもであることにかんがみると、子どもが被ばくすることはできる限り避けるべきである。
第2に、文部科学省は、電離放射線障害防止規則3条1項1号において、「外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3 ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」を管理区域とし、同条3項で必要のある者以外の者の管理区域への立ち入りを禁じている。3月あたり1.3mSvは1年当たり5.2mSv であり、今回の基準は、これをはるかに超える被ばくを許容することを意味する。しかも、同規則が前提にしているのは事業において放射線を利用する場合であって、ある程度の被ばく管理が可能な場面を想定しているところ、
現在のような災害時においては天候条件等によって予期しない被ばくの可能性があることを十分に考慮しなければならない。
第3に、そもそも、従前の基準(公衆については年間1mSv)は、様々な社会的・経済的要因を勘案して、まさに「安全」と「社会的便益の両立を考えて判断」されていたものである。他の場所で教育を受けることが可能であるのに「汚染された学校で教育を受ける便益」と被ばくの危険を衡量することは適切ではない。この基準が、事故時にあたって、このように緩められることは、基準の策定の趣旨に照らして国民の安全を軽視するものであると言わざるを得ない。
第4に、この基準によれば、学校の校庭で体育など屋外活動をしたり、砂場で遊んだりすることも禁止されたり大きく制限されたりすることになる。しかしながら、そのような制限を受ける学校における教育は、そもそも、子どもたちの教育環境として適切なものといえるか根本的な疑問がある。
以上にかんがみ、当連合会は、文部科学省に対し、以下の対策を求める。
1 かかる通知を速やかに撤回し、福島県内の教育現場において速やかに複数の専門的機関による適切なモニタリング及び速やかな結果の開示を行うこと。
2 子どもについてはより低い基準値を定め、基準値を超える放射線量が検知された学校について、汚染された土壌の除去、除染、客土などを早期に行うこと、あるいは速やかに基準値以下の地域の学校における教育を受けられるようにすること。
3 基準値を超える放射線量が検知された学校の子どもたちが他地域において教育を受けざるを得なくなった際には、可能な限り親やコミュニティと切り離されないように配慮し、近隣の学校への受け入れ、スクールバス等による通学手段の確保、仮設校舎の建設などの対策を講じること。
4 やむを得ず親やコミュニティと離れて暮らさざるを得ない子どもについては、受け入れ場所の確保はもちろんのこと、被災によるショックと親元を離れて暮らす不安等を受けとめるだけの体制や人材の確保を行うこと。
5 他の地域で子どもたちがいわれなき差別を受けず、適切な教育を受けることができる体制を整備すること。
2011年(平成23年)4月22日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
みなさま
文部科学省が、福島県の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安を「年20ミリシーベルト」とした件について、日本弁護士連合会の宇都宮健児会長の声明が4月22日付で出されています。以下、高木基金理事の中下裕子弁護士からのメール情報を転載します。
「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明
4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1〜20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とする」とされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。
しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。
第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可能性があることから、放射線被ばくはできるだけ避けるべきであることは当然のことである。とりわけ、政府が根拠とする国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)は成人から子どもまでを含んだ被ばく線量を前提としているが、多くの研究者により成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けやすいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受けるのが子どもであることにかんがみると、子どもが被ばくすることはできる限り避けるべきである。
第2に、文部科学省は、電離放射線障害防止規則3条1項1号において、「外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3 ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」を管理区域とし、同条3項で必要のある者以外の者の管理区域への立ち入りを禁じている。3月あたり1.3mSvは1年当たり5.2mSv であり、今回の基準は、これをはるかに超える被ばくを許容することを意味する。しかも、同規則が前提にしているのは事業において放射線を利用する場合であって、ある程度の被ばく管理が可能な場面を想定しているところ、
現在のような災害時においては天候条件等によって予期しない被ばくの可能性があることを十分に考慮しなければならない。
第3に、そもそも、従前の基準(公衆については年間1mSv)は、様々な社会的・経済的要因を勘案して、まさに「安全」と「社会的便益の両立を考えて判断」されていたものである。他の場所で教育を受けることが可能であるのに「汚染された学校で教育を受ける便益」と被ばくの危険を衡量することは適切ではない。この基準が、事故時にあたって、このように緩められることは、基準の策定の趣旨に照らして国民の安全を軽視するものであると言わざるを得ない。
第4に、この基準によれば、学校の校庭で体育など屋外活動をしたり、砂場で遊んだりすることも禁止されたり大きく制限されたりすることになる。しかしながら、そのような制限を受ける学校における教育は、そもそも、子どもたちの教育環境として適切なものといえるか根本的な疑問がある。
以上にかんがみ、当連合会は、文部科学省に対し、以下の対策を求める。
1 かかる通知を速やかに撤回し、福島県内の教育現場において速やかに複数の専門的機関による適切なモニタリング及び速やかな結果の開示を行うこと。
2 子どもについてはより低い基準値を定め、基準値を超える放射線量が検知された学校について、汚染された土壌の除去、除染、客土などを早期に行うこと、あるいは速やかに基準値以下の地域の学校における教育を受けられるようにすること。
3 基準値を超える放射線量が検知された学校の子どもたちが他地域において教育を受けざるを得なくなった際には、可能な限り親やコミュニティと切り離されないように配慮し、近隣の学校への受け入れ、スクールバス等による通学手段の確保、仮設校舎の建設などの対策を講じること。
4 やむを得ず親やコミュニティと離れて暮らさざるを得ない子どもについては、受け入れ場所の確保はもちろんのこと、被災によるショックと親元を離れて暮らす不安等を受けとめるだけの体制や人材の確保を行うこと。
5 他の地域で子どもたちがいわれなき差別を受けず、適切な教育を受けることができる体制を整備すること。
2011年(平成23年)4月22日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
■1シーベルト上がるごとにがんによる相対過剰死亡数が率にして0.97(97 %)増
【被ばく量が1シーベルト上がるごとに、がんによる相対過剰死亡数が率にして0.97(97 %)増える計算。死亡統計により国民死亡の30 %ががんによる日本では10ミリシーベルトを被ばくすればがんの死亡率は30.3 %、100ミリシーベルトの被ばくでは33 %】
テレビや新聞で報道されている被ばくに関する専門家のコメントに100ミリシーベルトを基準として「これ以下の被ばくは問題ない」とするものが多々見受けられますが、この表現には問題があるので、指摘します。「広島、長崎のデータなどから100ミリシーベルト以下では人体への悪影響がないことは分かっています」という記事がありました。確かに100ミリシーベルト以下の被ばくでは火傷のような急性症状は出ません。急性症状について言っているなら妥当な表現です。しかし、広島、長崎で被爆した人の追跡調査では50ミリシーベルト以下の低線量被ばくでも発がんによる死亡増加を示唆する研究結果があります。
放射線はわずかな線量でも、確率的に健康に影響を与える可能性があります。低線量被ばくについては、日本を含む世界15カ国で40万人の原子力施設作業員の調査をしたレポートがありますが、これによると、被ばく量が50ミリシーベルト以下でも発がん率は上昇しています。また被ばく量が1シーベルト上がるごとに、がんによる相対過剰死亡数が率にして0.97(97 %)増える計算です。相対過剰死亡率の計算は若干難しいので、結果だけ示しますと、死亡統計により国民死亡の30 %ががんによる日本では、10ミリシーベルトを被ばくすれば、がんの死亡率は30.3 %、100ミリシーベルトの被ばくでは33 %になります。
100ミリシーベルト以下は安全だとする説は、ここ数年でほぼ間違いだとされるようになっています。人間は放射線被ばくだけで発がんするわけではありません。私は、「発がんバケツ」という考え方をします。それぞれの人が容量に個人差のある発がんバケツを持っています。放射線だけでなく、タバコや農薬など、いろんな発がんの原因があり、それがバケツにだんだんとたまっていき、いっぱいになってあふれると発がんすると考えます。ある人のバケツが今どのくらい発がんの原因で満たされていたかで、今回被ばくした量が同じでも、発がんする、しないに違いがでます。ですから、放射線量による発がんの基準値を決めるのは難しいのです。
たばこを吸う本数による発がんリスクも、吸う本数や年齢、吸ってきた年月により変わり、計算が難しい。ですから、放射線被ばくのリスクと喫煙による発がんのリスクを比較してより安全だということに疑問を感じます。同じ記事中に「100ミリシーベルトを被ばくしても、がんの危険性は0.5 %高くなるだけです。そもそも、日本は世界一のがん大国です。2人に1人が、がんになります。つまり、もともとある50 %の危険性が、100ミリシーベルトの被ばくによって、50.5 %になるということです。たばこを吸う方が、よほど危険と言えます」とあります。
0.5 %という数字は、国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年の勧告中にある、1シーベルトあたりの危険率(5 %)に由来していると思います。つまり1シーベルトで5 %ならば、その10分の1の100ミリシーベルトならば、危険率は0.5%になるというわけです。しかし、この数字は発がんリスク(がんになるリスク)ではなく、がんで死ぬリスクです。ここでは、2人に1人ががんになるというのは発がんの確率ですから、ここに、危険率(がんで死ぬリスク)の0.5 %をプラスしているのは、発がんリスクとがん死亡のリスクを混同していると考えられます。
リスクを混同している上に、喫煙量も明示せずにたばこの方が危険と言っている。メディアの方は、こういう乱暴な議論に気をつけ、科学的な根拠の誤用に気をつけていただきたいと思います。
近藤誠(こんどう・まこと)慶応義塾大学医学部放射線科講師
1948年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学医学部卒。患者の権利法を作る会、医療事故調査会の世話人をつとめる。
【被ばく量が1シーベルト上がるごとに、がんによる相対過剰死亡数が率にして0.97(97 %)増える計算。死亡統計により国民死亡の30 %ががんによる日本では10ミリシーベルトを被ばくすればがんの死亡率は30.3 %、100ミリシーベルトの被ばくでは33 %】
テレビや新聞で報道されている被ばくに関する専門家のコメントに100ミリシーベルトを基準として「これ以下の被ばくは問題ない」とするものが多々見受けられますが、この表現には問題があるので、指摘します。「広島、長崎のデータなどから100ミリシーベルト以下では人体への悪影響がないことは分かっています」という記事がありました。確かに100ミリシーベルト以下の被ばくでは火傷のような急性症状は出ません。急性症状について言っているなら妥当な表現です。しかし、広島、長崎で被爆した人の追跡調査では50ミリシーベルト以下の低線量被ばくでも発がんによる死亡増加を示唆する研究結果があります。
放射線はわずかな線量でも、確率的に健康に影響を与える可能性があります。低線量被ばくについては、日本を含む世界15カ国で40万人の原子力施設作業員の調査をしたレポートがありますが、これによると、被ばく量が50ミリシーベルト以下でも発がん率は上昇しています。また被ばく量が1シーベルト上がるごとに、がんによる相対過剰死亡数が率にして0.97(97 %)増える計算です。相対過剰死亡率の計算は若干難しいので、結果だけ示しますと、死亡統計により国民死亡の30 %ががんによる日本では、10ミリシーベルトを被ばくすれば、がんの死亡率は30.3 %、100ミリシーベルトの被ばくでは33 %になります。
100ミリシーベルト以下は安全だとする説は、ここ数年でほぼ間違いだとされるようになっています。人間は放射線被ばくだけで発がんするわけではありません。私は、「発がんバケツ」という考え方をします。それぞれの人が容量に個人差のある発がんバケツを持っています。放射線だけでなく、タバコや農薬など、いろんな発がんの原因があり、それがバケツにだんだんとたまっていき、いっぱいになってあふれると発がんすると考えます。ある人のバケツが今どのくらい発がんの原因で満たされていたかで、今回被ばくした量が同じでも、発がんする、しないに違いがでます。ですから、放射線量による発がんの基準値を決めるのは難しいのです。
たばこを吸う本数による発がんリスクも、吸う本数や年齢、吸ってきた年月により変わり、計算が難しい。ですから、放射線被ばくのリスクと喫煙による発がんのリスクを比較してより安全だということに疑問を感じます。同じ記事中に「100ミリシーベルトを被ばくしても、がんの危険性は0.5 %高くなるだけです。そもそも、日本は世界一のがん大国です。2人に1人が、がんになります。つまり、もともとある50 %の危険性が、100ミリシーベルトの被ばくによって、50.5 %になるということです。たばこを吸う方が、よほど危険と言えます」とあります。
0.5 %という数字は、国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年の勧告中にある、1シーベルトあたりの危険率(5 %)に由来していると思います。つまり1シーベルトで5 %ならば、その10分の1の100ミリシーベルトならば、危険率は0.5%になるというわけです。しかし、この数字は発がんリスク(がんになるリスク)ではなく、がんで死ぬリスクです。ここでは、2人に1人ががんになるというのは発がんの確率ですから、ここに、危険率(がんで死ぬリスク)の0.5 %をプラスしているのは、発がんリスクとがん死亡のリスクを混同していると考えられます。
リスクを混同している上に、喫煙量も明示せずにたばこの方が危険と言っている。メディアの方は、こういう乱暴な議論に気をつけ、科学的な根拠の誤用に気をつけていただきたいと思います。
近藤誠(こんどう・まこと)慶応義塾大学医学部放射線科講師
1948年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学医学部卒。患者の権利法を作る会、医療事故調査会の世話人をつとめる。
【与謝野 VS 枝野】は枝野の勝ち
■東電賠償巡り、与謝野氏と枝野氏がバトル
(読売新聞 - 05月14日 07:44)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1601161&media_id=20
「原子力損害賠償法3条ただし書きの適用」については、
1:原発事故発生の直接の起因は自然災害
2:原発事故と放射能被害の直接原因は「原発の根本的な安全管理の手抜きと甘さ」
3:事故発生における被害拡大の根本的原因は「政府、官僚、東電の事故後対応の間違いと甘さ」
という見解が正しい。
したがって「原子力損害賠償法3条ただし書きの適用」は在り得ない。
但し、
原子力政策を立案、主導し、安全管理においても実質的に電力会社を意のままにコントロールしてきた省庁、いわゆる国家と原子力政策立案当時からの政府の責任は、電力会社の責任を遥かに上回る責任の重さであり、よって電力会社の責任が追及されるのは当然であるが、同時に国家=省庁、政府には「原子力損害賠償法3条ただし書きの適用レベル」の賠償責任が追求され、また科せられるべきである。
■東電賠償巡り、与謝野氏と枝野氏がバトル
(読売新聞 - 05月14日 07:44)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1601161&media_id=20
「原子力損害賠償法3条ただし書きの適用」については、
1:原発事故発生の直接の起因は自然災害
2:原発事故と放射能被害の直接原因は「原発の根本的な安全管理の手抜きと甘さ」
3:事故発生における被害拡大の根本的原因は「政府、官僚、東電の事故後対応の間違いと甘さ」
という見解が正しい。
したがって「原子力損害賠償法3条ただし書きの適用」は在り得ない。
但し、
原子力政策を立案、主導し、安全管理においても実質的に電力会社を意のままにコントロールしてきた省庁、いわゆる国家と原子力政策立案当時からの政府の責任は、電力会社の責任を遥かに上回る責任の重さであり、よって電力会社の責任が追及されるのは当然であるが、同時に国家=省庁、政府には「原子力損害賠償法3条ただし書きの適用レベル」の賠償責任が追求され、また科せられるべきである。
■「計画停電」はヤラセだったことが判明 東電と経産省が情報操作 民主議員と東京新聞が暴露
(画像↑の東京新聞記事を参照)
■そもそも、リスクを冒してでも原発を必要とする理由はない。原発をすべて停めても、現在の火力発電所の稼働率を7割に上げれば、カバーできる。
京都大学原子炉実験所 小出裕章氏に聞く(全編1時間22分)より抜粋
http://www.ustream.tv/recorded/13897618
政府と電気事業者の公開データの原発がないと電力が不足するというのは真っ赤な嘘。政府、マスコミは本当の事実を伝えない。また原発が安く電力を供給しているというのも嘘。(ustの1:00以降で詳解)原発のコストは最も割高。そのために、日本人は世界一高い電気代を払わされ、家計だけでなく、産業界にもダメージを与えている。アルミ精錬は、高い電気代に耐えられず、海外に出ていった。今、日本に残っているのは日本軽金属の一工場のみ。そこは水力の自家発電機をもっているからこそ、操業が可能に。原発は生産性を下げ、経済にもマイナスの影響を与えている。ことほど左様に、原発存続の理由は、何もない。
(画像↑の東京新聞記事を参照)
■そもそも、リスクを冒してでも原発を必要とする理由はない。原発をすべて停めても、現在の火力発電所の稼働率を7割に上げれば、カバーできる。
京都大学原子炉実験所 小出裕章氏に聞く(全編1時間22分)より抜粋
http://www.ustream.tv/recorded/13897618
政府と電気事業者の公開データの原発がないと電力が不足するというのは真っ赤な嘘。政府、マスコミは本当の事実を伝えない。また原発が安く電力を供給しているというのも嘘。(ustの1:00以降で詳解)原発のコストは最も割高。そのために、日本人は世界一高い電気代を払わされ、家計だけでなく、産業界にもダメージを与えている。アルミ精錬は、高い電気代に耐えられず、海外に出ていった。今、日本に残っているのは日本軽金属の一工場のみ。そこは水力の自家発電機をもっているからこそ、操業が可能に。原発は生産性を下げ、経済にもマイナスの影響を与えている。ことほど左様に、原発存続の理由は、何もない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
■危機管理@放射能情報倉庫 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
■危機管理@放射能情報倉庫のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人