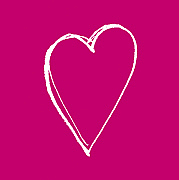このテキストはたいへん長いので、ご興味がある方だけ、お読みください。
(すみません、あきらかにウェブにアップする分量ではないのですが
・・・読みやすいように段落替えを多用しました。)
まずは、編集せずにそのまま掲載してしまうことが重要、
だと思いましたので、ここにアップさせていただきました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
「SHIBUYA GIRLS POP 〜 本当の日本のかわいい(REAL JAPANESE KAWAII)」
「渋谷を行き来する女の子&女性にポジティブなメッセージを!ポストカードは、全てテイク・フリー。渋谷センター街入り口、大盛堂書店、店頭で手に入ります。」という内容で、2年前から続けて来た「SHIBUYA GIRLS POP」ですが、この企画は、現在も大盛堂書店さんにて好評継続中です!
同様に周囲の方々からも評価をいただくようになり、海外からのアプローチもいくつかいただいております。
そんな状況にありますので、これまでずっと言葉にこそしてきませんでしたが、頑に守って来たこの企画の「ある空気感」を、もう一度「コンセプト」としてまとめ、改めてみなさんに明快に示してみたいと思います。
この「SHIBUYA GIRLS POP」という企画は、毎月1名のイラストレーターさんに、渋谷を行き来する女の子向けにポジティブなメッセージをというテーマでイラストを描いていただき、ポストカードを制作し、渋谷を行き来する女の子&女性に無料で配布するというものです。ごく簡単に言えば、そうなります。
この企画で最も重要なポイントになっているのはそのタイトルに含まれているように、配布場所が「渋谷」ということ、対象が「女の子」という2点です。まずは、ここからお話を始めたいと思います。
ボクが思うに、「渋谷」という街はとても「ミックス度」が高い街で、いろんなモノがあり、いろんなタイプの人たちがいる街です。「共存」している街です。そのため、勝手に想像(創造)をする自由が、余地が、かなり許されていて、かつその範囲も広いのではないでしょうか。これはもちろん、「渋谷」に限ったことではなく、「街」というものは多かれ少なかれそういった性格を持っているものです。ですが、「渋谷」は特にその傾向が強い、むしろ、他に類をみないぐらい「ミックス度」が高いのではないでしょうか。それは、他の街と対比してみることで、よりその姿を浮き彫りにすることができるのではないかと思います。
現在も変貌し続けている街に、特定の言葉を当てはめてみようとするのはリスクが高いことですが、あえてざっくりと一般的なイメージでやってみます。
例えば「原宿」は中・高校生的、「恵比寿」は大人の街的(団塊Jr.)、「代官山」はセレブ的、「新宿」は昭和的、「池袋」はアジア的、「秋葉原」はオタク的、「銀座」は大人の街的(団塊世代)、「吉祥寺」は庶民的で、「自由が丘」はセレブ(ママ)的・・・。
そして「渋谷」ですが、かつて「渋谷系」という言葉があったように、この街が系統だてて呼ばれる余地というものは確かにあります。とても話題になりやすい街ですから。とはいえ今の渋谷を、2010年の渋谷を、何々的というのはもはや当てはまらないのではないかと思うのです。個人的な印象ですけれども。「ミックス度」が高まり、何々的ということができなくなってしまった。そんな印象があります。
今の「渋谷」は、何々的と言いがたい街。他のどの街よりも雑多性を持った街。確かに街はどこであれ雑多ですが、サブカルチャーからハイカルチャーまでバランス良い混ざり方をしているのは「渋谷」をおいて他にないのではないのでしょうか。
このような想像力(または現状認識)は実はとても大切で、この街でできるだけ多くの人にポストカードを配りたいと思っているような人間にしてみれば、「その街がどんな性格を持っているのか」、分析的に考えてみたりするのはむしろ必然なのでした。
この「街に対する想像の自由度が高い」という部分は、むしろ、ボクたちの結果を見て欲しいと思います。「SHIBUYA GIRLS POP」の過去のイラストレーターさんの作品を見てみてください。実は、実際に「渋谷」そのものを描いてくれたイラストレーターさんは誰もいないのですね。イメージしてもらうのは「渋谷」ではなく「渋谷を行き来する女の子&女性たち」でお願いしている、ということもありますけれども。さらにそうお願いしたとしても、そこからさらに外れようとするイラストレーターさんもいらっしゃいました。ですが、それはそれで良いのです。なぜなら、渋谷という街の雑多性やミックス度が、その作家さんに「気持ちの自由度や、流動性」を与えている、ということなのでしょうから。
渋谷という場所で配布するポストカードは「想像の中の渋谷」が描かれている。
そんなふうに、コンセプトは「街」に導かれ、勝手に出来上がった、と言っても過言ではないのです。
また、若干話が逸れてしまいますが、根本的に、そのイラストレーターさんの作品が(どんなものであれ)「渋谷」で配布されるということそのものが、この企画に合っている(もしくはおもしろいと感じさせる)ものであれば、すでにその事実だけで充分刺激的、という(メタ的な)判断があります。つまり真っ先に、イラストレーターさんをチョイスする時点で刺激的でなければならないというローカル・ルールを敷いているのです。これは、このルールを守ることにより、二重の意味での成功を狙っているつもりなのです。
ですので・・・実はイラストをお願いするイラストレーターさんのチョイスは、かなり慎重に行っています。
いずれにせよ、「渋谷」という街そのものがむしろ、自動的にコンセプトをもたらしてくれた、というところは多分にあります。
次は「女の子」という観点で考えてみたいと思います。
先ほどもお話したように、渋谷は様々な人が行き交う街です。そこに居る女の子の種類(いわゆる「層」で分けてみても)も様々です。その子たちが属するカルチャーや年齢も多種多様です。その中でボクたちは、ポストカードをできるだけたくさんの層に、できるだけたくさんの年齢の女の子、女性に届けたい、そう考えたわけです。
そのためにどうすべきか、どうあるべきかを考えなければなりませんでした。
そして、その答えは、自分のすぐ側にありました。
それは、「かわいい」という言葉です。
この言葉は、その場で急に捻出したものかというとそんなことはなく、「SHIBUYA GIRLS POP」を始める以前から、明確にボクの中で意識されていた言葉でした。ではなぜ、ボクが「SHIBUYA GIRLS POP」のために選んだ言葉が「美しい」や「きれい」ではなく、「かわいい」だったのでしょうか。
・・・それはまず、言ってみれば、肌感覚レベルの直感です。と、あまりにも答えにもなってない答えで申し訳ないのですが。
ボクが、その言葉を見つけるのは全く難しい事ではありませんでした。むしろ、とても簡単なことでした。
10年以上渋谷で働き、終いには住んでしまっているボクにとって、「かわいい」は日常的に目にし、耳にしている言葉だったのです。さまざまな女の子(時に男性も)が、この「かわいい」という言葉に取り憑かれ、そして「ハッピー」になっている場面を、ボクは渋谷という現場で見て来ていたのです。店頭、街角などで。ですから、そんな人たちのために、「かわいい」をテーマにポストカードを作ってあげれば良いのだなと考えたのは、とても自然ななりゆきだったのです。
この感覚はみなさんにも共有していただけるのではないでしょうか。日常で「かわいい」を目にし、耳にする機会のなんと多い事か。
そんないきさつがあって、「SHIBUYA GIRLS POP」は「かわいい」という言葉を掲げて展開していけばいい、そう考えたのです。
「女の子」の視点で考えていたら、話はすぐに、直感的に、「かわいい」に行き着きました。
そして、それはそれでいいと思っています。極論を言えば、イコールで結んでしまっても良いもの同士なのでしょうから。
では、「かわいい」についてもう少しお話させてください(実はいよいよ、ここからが本題です)。
「SHIBUYA GIRLS POP」の活動の本質は「かわいい」にある、としているボクにとっては、これを避けるわけにはいかないのです。
ですが実際のところ、この「かわいい」という言葉は日本において、あまりにもたくさんの意味・用法を持っていて、分析しようとするとたいへん骨が折れます。素人ながらそれをやってみようと思うわけですが、ここでは日本と海外との「かわいい」の使われ方を比較することで、よりそれがやりやすくなる気がしておりますので、勝手ながらそのアプローチで進めさせてもらいます。
(それと、まず真っ先に言っておきたいのは、ボクが言おうとしていることは決して新しいことではない、ということです。先人による活動や、示唆が大きくボクに影響を与えているという点、了解ください。)
まずは前提からお話します。
すでにみなさんもご存知だとは思いますが、主に1990年代から始まった日本発のアニメ、マンガ、ゲームを中心としたOTAKUカルチャーの波は、2000年代に入り、ますますその勢いを増し、アンダーグランウンドでもオーバーグラウンドでも、ほぼ全世界を席巻しました。
現在では、日本発のファッション、キャラクターのいくつかも、そういった事例として挙げる事ができるでしょう。
その中で「かわいい」もの、「かわいい」という概念は、アニメやマンガというパッケージの中に組み込まれ、世界中に行き渡たりました。組み込まれたと言ってもそれは当然、物理的に「かわいい」というものが輸出された、ということではなく、アニメやマンガやゲームのストーリーの中に、キャラクター造形の中に組み込まれた、という意味です。これはポップ・カルチャーだからこそなし得たことだと思います。その姿は(本来「かわいい」という概念のほうが日本古来からあったものなのに)、その精神性を失うことなく変態(メタモルフォーゼ)を果たし、まるで別の次元に移行したかのような印象すら、ボクたちに与えています。
そう言った意味で、「かわいい」はアニメやマンガなどのOTAKUカルチャーと、共犯関係にあると言ってまったく差し支えないと思います。
もちろんそこには、WEBを介した個人のHPやコミュニティ、ショップのネットワークの存在が、日本のポップ・カルチャーの普及に大いに貢献した、ということは言うまでもありません。それこそ、改めてボクが言うことではないでしょう。
本当に、このポップ・カルチャーからの視点というものはとても大事で、「かわいい」を含むアニメやマンガやゲームは、日本人の一般的認識の上では「一部のひとのもの、オタクのもの」とされてしまいがちです。それが大変なポテンシャルを秘めているものであるのにかかわらず、見過ごされてしまっているケースが本当に多いと思います(「COOL JAPAN」として、捉えられ直されているとはいえ・・・)。
グローバルな視点から見れば、つまり積極的にポップ・カルチャーを理解しようとすれば、それが「特殊な人のものである」という認識がいかに誤ったものであるか、ということに気づくはずです。もはや「かわいい」を含む日本のポップ・カルチャーはすでに全世界で受け入れられており(むしろ熱狂的に)、WEB上ではそのネットワークをさらに強固なものにすべく、日々さまざまな情報が行き交い、更新されています。
個人的には、「かわいい」について調べれば調べるほど、それがもつ本来のポテンシャルの高さを知り、驚かされています。
そんな中で、ボク自身は「SHIBUYA GIRLS POP」という企画を進めながら、ごく自然な流れで、海外における「かわいい」の受け取り方の微妙な違いというか、ズレに似たような空気感を、少しずつ感じ取っていったのでした。
それを説明するために、「かわいい」について踏み込んで考えてみましょう。
たとえば英語では「かわいい」はcuteやprettyと訳されますが、それは表面上、その意味が似通っているということであって、決してイコールで結ぶことはできません。それは他の国の言語でもたいてい同様なようです(※「かわいい」論(四方田 犬彦/筑摩書房)参照)。
この事実から分かることは「かわいい」という概念が、いかに日本独自のものであるのかということです。
日本における「表面上のかわいい」とされる部分を、あえて別の言葉で表現してみると、「ちいさいもの」「まるいもの」「やわらかいもの」「ふわふわしたもの」「どこか懐かしいもの」「保護欲を喚起するもの」「庇護するべきもの」「未成熟なもの」「未完成なもの」「何かが足りていないもの」「無国籍なもの(エキゾチック)」・・・と次々に思い浮かべることが出来ます。この意味のバリエーションを包括しているのが「かわいい」であって、やはり、cuteやprettyではなし得ないことなのです。
また、みなさんもご存知のように、日本において「かわいい」という言葉は日常の中、様々な場面で使われています。現代の日本では、「かわいい」はその時の状況、発語者の感情・目的によって意味合いを変えていきます。
また一方で、ずっと意味を変えることのない「かわいい」もあれば、時代そのものにより意味が変わっていく「かわいい」もあります。
さらに他の視点から言うと、日本では(例外はたくさんあるにせよ)、大人になっても「かわいい」を求める気持ちは変わらないといった傾向があります。変わったとしてもそれは「かわいい」の意味合いにおける変容が起こるのであって(例:「大人かわいい」)、その気持ちが失われるということはない、と言うことができると思います。
なぜならやはり、「かわいい」には古来から続く日本の文化的背景に支えられているという一面があるからです。
先ほどの「大人かわいい」のように、自分も日常的に良くやるのですが、「かわいい」の前に「○○」を付け、「○○かわいい」とすることも多いですよね。勝手にその場で作り出してしまう、新しい「かわいい」。それほど、柔軟に自由に意味を変えていく可能性を持った言葉だと言えるのです。
このような例を重ね、分かることは、「かわいい」に対応する言葉が海外にはありえない、という事実です。文化的成り立ちが違う海外で「かわいい」に対応する言葉がないのは、本来当然なことなのですけれど。
そして現状です。今のところ、海外で受け入れられている「かわいい」は、それに善し悪しがあるにしても、「ある部分」でしかないのだろうな、というのがボクの見解です。そしてまた同時に海外における「かわいい」理解が一面的になってしまうのは、仕方がないことだとも感じています。
なぜなら、海外では派手でエッジーなものが受け入れられやすいという風土があります。それをして「かわいい」と思われる傾向があると思います。
時間的な問題もそうです。実際には日本の「かわいい」が知られるようになってから、たかだか20年〜30年しか時が流れていないのです。一方「かわいい」自体は何度も繰り返すように、日本の伝統や精神を踏まえた多義的な言葉であり、その概念は1000年来の起源を持つものなのですから。
その上で(ボクが言うのもなんですが)、実際どの国でどのように「かわいい」が消費されるかということは、コントロールできることではありません。そしてそれ自体はとても良いことだと思っています。根本的にはその国がもつ文化的背景に支配されて然るべきものだからです。
とはいえ、そこで「かわいいの別の側面」もしくは「本当の日本のかわいい」を伝えようという努力をしない、というコトではないと思います。そういう動きはあってもいい、そう思うのです。むしろ、それを積極的に提示してみようという動きのひとつとして、この「SHIBUYA GIRLS POP」が何かできるのではないか、と考えているのです。
ただここで誤解して欲しくないのは、決してその「誤りを正そう」とか、「こちらが王道」というような、啓蒙的な運動をしたいと思っているわけではないということです。これだけ「かわいい」が世界に伝播した現状、もちろんその先駆者の方々には本当に心の底から感謝とリスペクトを捧げたい気持ちです。
その上で、エッジーなものだけではなく、「日本の一般の女の子たちが普通に、日常的に好き、というようなかわいい」を世界に提示してもいいのではないか、という提案なのです。誤解を許容する幅こそが「かわいい」なのだとは思います。ただ、日本の文化として「かわいい」をいろんな側面から伝えるということもまた、今後はますます重要なことになってくるのではないか、と考えます。
ボクは現在の海外における「KAWAII」も個人的には大好きなのですが、その流れにそのまま取り込まれてしまってはせっかくのこの「SHIBUYA GIRLS POP」の魅力もまた半減してしまうだろう、と考えています。
ようやく伝えたい本筋に入って来た感じなのですが、この「SHIBUYA GIRLS POP」はその最初期からずっと、「日本のごく普通の女の子たち」が「かわいい」と言ってくれることを想定して活動を続けてきました。その普通の女の子たちの「空気感」をなるべく掬い取れるように、慎重にイラストレーターさんの選択をして来ました。
また、本当に小さな努力ではあるのですが、意識して表記を「KAWAII」でもなく「カワイイ」でもなく、また「可愛い」でもない、「かわいい」としてきたのです。これは、日本本来の「かわいい」感を演出するために意図的に行ってきたことです。
「SHIBUYA GIRLS POP」においてボクは、そろそろその活動の意図を明らかにして、日本の本来の「かわいい」、「日本の普通の女の子が想うかわいい」をきちんと提案し直す必要があるのではないか、と感じたわけですが、「SHIBUYA GIRLS POP」の活動の核を明言すれば、イラストレーターさんの表現を通して、あらためて「日本の大多数のごく普通の女の子または女性が、日常的にかわいいと思っているもの、普遍的にかわいいと思えるもの、という視点を提案してあげること」と言っていいと思います。
それは、決して奇抜であればいい、ということだけではない、「かわいい」なのです。
またその立ち位置を明確にするために示してみようと思いますが、知っての通り、「かわいい」は時に、カウンター・カルチャーの側面を担うこともあり「ロック」的なダイナミズムを纏う事もあります。
その例として6%DOKIDOKI好きの女の子のように、極彩色の「KAWAII」を身に纏ったり、ロリータの女の子がフリル満載のロココ調・パステルカラーの服を着たり、ゴシック系の女の子が黒尽くめの服を好んだりするように・・・自分のアイデンティティを主張するのと同義に「かわいい」の変奏を行ったりします。これには実に「ロック」的な感性の動機付けが垣間見られます。良い意味での「緊張」が支配する世界です。
そこで改めて「SHIBUYA GIRLS POP」の立ち位置を見てみると、その名の通り、とても「POP」的です。もう少しゆったりとしていて、自然な雰囲気です。それは、先ほども述べた通り、「日常の中のかわいい」を見つめる視線に注目した企画であるのですから。
これは、どれがどれだけ優れている、というような問いなのではありません。いずれにせよその全てが、「かわいい」の中から産まれて来たことに違いなく、その幅をもって「日本のかわいい」なのですから。共存して然るべきなのだと思います。
また逆に、「SHIBUYA GIRLS POP」がこのような企画になることは、極めて自然であったとも言うことができます。
それはこの企画がポストカードを実際に「大多数を占める普通の、一般的な女の子」に持って帰ってもらえないと、現実に配布している意味がない、という条件付けがあったからです。
それはまさに、ボクたちが一般的な「かわいい」とは何なのだろう?と思考を開始し、試行錯誤をする契機にもなったのです。
そしてまた、別の角度から「SHIBUYA GIRLS POP」を捉え直すこともできます。
海外においてアニメ、マンガ、ゲーム、ファッション、キャラクターの紹介が進む中、イラストレーション、アートの側面での「かわいい」の紹介が遅れているのではないか、という部分です。これは恐らく、確かなことでしょう。
むしろここは、このタイミングで「本当の日本のかわいい(REAL JAPANESE KAWAII)」イラストレーターさんたちを、ボクたちが再提示・紹介できる機会がある、そう前向きに受け止め、チャンスと捉えたいです。
さらに(これは蛇足的な内容かも知れませんが)、日本では長年に渡り、女性をターゲットにさまざまなマーケット研究が行われ、メディア主導のカテゴリー・ブーム作りが行われて来ました。レッテルを貼り、売りやすくするという手法、もしくは存在しないブームを生み出して行こうという行為です。ですが、自分はその流れには属したくない、レッテルを貼られたくない、と強く望んでいました。もちろん、それはロマンティックでナイーブな幻想でしかありません。
ですがそれでも、時の流れにも風化しない、メディアの操作やレッテル貼りにも屈しない、普遍的な「かわいい」を示せたら、どれだけ素晴らしいだろうとも考えています。それは、今の世界的な「かわいいバブル」の後にも残る事ができる「かわいい」の提案です。
消費されて、跡形も無くなってしまうのは誰にとっても恐ろしい事です。
とはいえ、イラストそのものを見れば、個々のイラストレーターさんのお仕事を見れば、そんな心配はないと気づき、とても安心できるのです。「SHIBUYA GIRLS POP」に参加していただいたイラストレーターさんたちは、本当に普遍的な「かわいい」を表現するのに長けた、素晴らしい方たちばかりなのですから。
その流れで話しますが、長年に渡って「KAWAII」を世界に発信続けている6%DOKIDOKIの増田さんが、今まさに懸念している、状況を見てにわかに「KAWAII」を持ち出すといったマナー、そういった表面的な動きとSHIBUYA GIRLS POPとは根本的に立っている位置が違う、ということはご理解いただけたかと思います。
このように「SHIBUYA GIRLS POP」の活動の本質を説明するために、長々と書いてきました。
最初に言ったように、この活動はすでに2年間続いてます。
その中で自分たちは常に、関わっていただいたみんながハッピーになれるよう心がけています。
そして当然のことですが、渋谷の街を行き来する、普通の女の子、女性に対しては特に。
そこから得られる反応を常に大切にして、時に分析して、次の活動に繋げようとしています。
今後も、核になる良い部分は変えることなく、と同時にどんどんと柔軟にその姿を変えて行きたいと思っています。
まるで、日本語における「かわいい」という言葉のように。
これからも、「SHIBUYA GIRLS POP」の応援を、よろしくお願いいたします。
SHIBUYA GIRLS POP 主宰 加藤和裕
(すみません、あきらかにウェブにアップする分量ではないのですが
・・・読みやすいように段落替えを多用しました。)
まずは、編集せずにそのまま掲載してしまうことが重要、
だと思いましたので、ここにアップさせていただきました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
「SHIBUYA GIRLS POP 〜 本当の日本のかわいい(REAL JAPANESE KAWAII)」
「渋谷を行き来する女の子&女性にポジティブなメッセージを!ポストカードは、全てテイク・フリー。渋谷センター街入り口、大盛堂書店、店頭で手に入ります。」という内容で、2年前から続けて来た「SHIBUYA GIRLS POP」ですが、この企画は、現在も大盛堂書店さんにて好評継続中です!
同様に周囲の方々からも評価をいただくようになり、海外からのアプローチもいくつかいただいております。
そんな状況にありますので、これまでずっと言葉にこそしてきませんでしたが、頑に守って来たこの企画の「ある空気感」を、もう一度「コンセプト」としてまとめ、改めてみなさんに明快に示してみたいと思います。
この「SHIBUYA GIRLS POP」という企画は、毎月1名のイラストレーターさんに、渋谷を行き来する女の子向けにポジティブなメッセージをというテーマでイラストを描いていただき、ポストカードを制作し、渋谷を行き来する女の子&女性に無料で配布するというものです。ごく簡単に言えば、そうなります。
この企画で最も重要なポイントになっているのはそのタイトルに含まれているように、配布場所が「渋谷」ということ、対象が「女の子」という2点です。まずは、ここからお話を始めたいと思います。
ボクが思うに、「渋谷」という街はとても「ミックス度」が高い街で、いろんなモノがあり、いろんなタイプの人たちがいる街です。「共存」している街です。そのため、勝手に想像(創造)をする自由が、余地が、かなり許されていて、かつその範囲も広いのではないでしょうか。これはもちろん、「渋谷」に限ったことではなく、「街」というものは多かれ少なかれそういった性格を持っているものです。ですが、「渋谷」は特にその傾向が強い、むしろ、他に類をみないぐらい「ミックス度」が高いのではないでしょうか。それは、他の街と対比してみることで、よりその姿を浮き彫りにすることができるのではないかと思います。
現在も変貌し続けている街に、特定の言葉を当てはめてみようとするのはリスクが高いことですが、あえてざっくりと一般的なイメージでやってみます。
例えば「原宿」は中・高校生的、「恵比寿」は大人の街的(団塊Jr.)、「代官山」はセレブ的、「新宿」は昭和的、「池袋」はアジア的、「秋葉原」はオタク的、「銀座」は大人の街的(団塊世代)、「吉祥寺」は庶民的で、「自由が丘」はセレブ(ママ)的・・・。
そして「渋谷」ですが、かつて「渋谷系」という言葉があったように、この街が系統だてて呼ばれる余地というものは確かにあります。とても話題になりやすい街ですから。とはいえ今の渋谷を、2010年の渋谷を、何々的というのはもはや当てはまらないのではないかと思うのです。個人的な印象ですけれども。「ミックス度」が高まり、何々的ということができなくなってしまった。そんな印象があります。
今の「渋谷」は、何々的と言いがたい街。他のどの街よりも雑多性を持った街。確かに街はどこであれ雑多ですが、サブカルチャーからハイカルチャーまでバランス良い混ざり方をしているのは「渋谷」をおいて他にないのではないのでしょうか。
このような想像力(または現状認識)は実はとても大切で、この街でできるだけ多くの人にポストカードを配りたいと思っているような人間にしてみれば、「その街がどんな性格を持っているのか」、分析的に考えてみたりするのはむしろ必然なのでした。
この「街に対する想像の自由度が高い」という部分は、むしろ、ボクたちの結果を見て欲しいと思います。「SHIBUYA GIRLS POP」の過去のイラストレーターさんの作品を見てみてください。実は、実際に「渋谷」そのものを描いてくれたイラストレーターさんは誰もいないのですね。イメージしてもらうのは「渋谷」ではなく「渋谷を行き来する女の子&女性たち」でお願いしている、ということもありますけれども。さらにそうお願いしたとしても、そこからさらに外れようとするイラストレーターさんもいらっしゃいました。ですが、それはそれで良いのです。なぜなら、渋谷という街の雑多性やミックス度が、その作家さんに「気持ちの自由度や、流動性」を与えている、ということなのでしょうから。
渋谷という場所で配布するポストカードは「想像の中の渋谷」が描かれている。
そんなふうに、コンセプトは「街」に導かれ、勝手に出来上がった、と言っても過言ではないのです。
また、若干話が逸れてしまいますが、根本的に、そのイラストレーターさんの作品が(どんなものであれ)「渋谷」で配布されるということそのものが、この企画に合っている(もしくはおもしろいと感じさせる)ものであれば、すでにその事実だけで充分刺激的、という(メタ的な)判断があります。つまり真っ先に、イラストレーターさんをチョイスする時点で刺激的でなければならないというローカル・ルールを敷いているのです。これは、このルールを守ることにより、二重の意味での成功を狙っているつもりなのです。
ですので・・・実はイラストをお願いするイラストレーターさんのチョイスは、かなり慎重に行っています。
いずれにせよ、「渋谷」という街そのものがむしろ、自動的にコンセプトをもたらしてくれた、というところは多分にあります。
次は「女の子」という観点で考えてみたいと思います。
先ほどもお話したように、渋谷は様々な人が行き交う街です。そこに居る女の子の種類(いわゆる「層」で分けてみても)も様々です。その子たちが属するカルチャーや年齢も多種多様です。その中でボクたちは、ポストカードをできるだけたくさんの層に、できるだけたくさんの年齢の女の子、女性に届けたい、そう考えたわけです。
そのためにどうすべきか、どうあるべきかを考えなければなりませんでした。
そして、その答えは、自分のすぐ側にありました。
それは、「かわいい」という言葉です。
この言葉は、その場で急に捻出したものかというとそんなことはなく、「SHIBUYA GIRLS POP」を始める以前から、明確にボクの中で意識されていた言葉でした。ではなぜ、ボクが「SHIBUYA GIRLS POP」のために選んだ言葉が「美しい」や「きれい」ではなく、「かわいい」だったのでしょうか。
・・・それはまず、言ってみれば、肌感覚レベルの直感です。と、あまりにも答えにもなってない答えで申し訳ないのですが。
ボクが、その言葉を見つけるのは全く難しい事ではありませんでした。むしろ、とても簡単なことでした。
10年以上渋谷で働き、終いには住んでしまっているボクにとって、「かわいい」は日常的に目にし、耳にしている言葉だったのです。さまざまな女の子(時に男性も)が、この「かわいい」という言葉に取り憑かれ、そして「ハッピー」になっている場面を、ボクは渋谷という現場で見て来ていたのです。店頭、街角などで。ですから、そんな人たちのために、「かわいい」をテーマにポストカードを作ってあげれば良いのだなと考えたのは、とても自然ななりゆきだったのです。
この感覚はみなさんにも共有していただけるのではないでしょうか。日常で「かわいい」を目にし、耳にする機会のなんと多い事か。
そんないきさつがあって、「SHIBUYA GIRLS POP」は「かわいい」という言葉を掲げて展開していけばいい、そう考えたのです。
「女の子」の視点で考えていたら、話はすぐに、直感的に、「かわいい」に行き着きました。
そして、それはそれでいいと思っています。極論を言えば、イコールで結んでしまっても良いもの同士なのでしょうから。
では、「かわいい」についてもう少しお話させてください(実はいよいよ、ここからが本題です)。
「SHIBUYA GIRLS POP」の活動の本質は「かわいい」にある、としているボクにとっては、これを避けるわけにはいかないのです。
ですが実際のところ、この「かわいい」という言葉は日本において、あまりにもたくさんの意味・用法を持っていて、分析しようとするとたいへん骨が折れます。素人ながらそれをやってみようと思うわけですが、ここでは日本と海外との「かわいい」の使われ方を比較することで、よりそれがやりやすくなる気がしておりますので、勝手ながらそのアプローチで進めさせてもらいます。
(それと、まず真っ先に言っておきたいのは、ボクが言おうとしていることは決して新しいことではない、ということです。先人による活動や、示唆が大きくボクに影響を与えているという点、了解ください。)
まずは前提からお話します。
すでにみなさんもご存知だとは思いますが、主に1990年代から始まった日本発のアニメ、マンガ、ゲームを中心としたOTAKUカルチャーの波は、2000年代に入り、ますますその勢いを増し、アンダーグランウンドでもオーバーグラウンドでも、ほぼ全世界を席巻しました。
現在では、日本発のファッション、キャラクターのいくつかも、そういった事例として挙げる事ができるでしょう。
その中で「かわいい」もの、「かわいい」という概念は、アニメやマンガというパッケージの中に組み込まれ、世界中に行き渡たりました。組み込まれたと言ってもそれは当然、物理的に「かわいい」というものが輸出された、ということではなく、アニメやマンガやゲームのストーリーの中に、キャラクター造形の中に組み込まれた、という意味です。これはポップ・カルチャーだからこそなし得たことだと思います。その姿は(本来「かわいい」という概念のほうが日本古来からあったものなのに)、その精神性を失うことなく変態(メタモルフォーゼ)を果たし、まるで別の次元に移行したかのような印象すら、ボクたちに与えています。
そう言った意味で、「かわいい」はアニメやマンガなどのOTAKUカルチャーと、共犯関係にあると言ってまったく差し支えないと思います。
もちろんそこには、WEBを介した個人のHPやコミュニティ、ショップのネットワークの存在が、日本のポップ・カルチャーの普及に大いに貢献した、ということは言うまでもありません。それこそ、改めてボクが言うことではないでしょう。
本当に、このポップ・カルチャーからの視点というものはとても大事で、「かわいい」を含むアニメやマンガやゲームは、日本人の一般的認識の上では「一部のひとのもの、オタクのもの」とされてしまいがちです。それが大変なポテンシャルを秘めているものであるのにかかわらず、見過ごされてしまっているケースが本当に多いと思います(「COOL JAPAN」として、捉えられ直されているとはいえ・・・)。
グローバルな視点から見れば、つまり積極的にポップ・カルチャーを理解しようとすれば、それが「特殊な人のものである」という認識がいかに誤ったものであるか、ということに気づくはずです。もはや「かわいい」を含む日本のポップ・カルチャーはすでに全世界で受け入れられており(むしろ熱狂的に)、WEB上ではそのネットワークをさらに強固なものにすべく、日々さまざまな情報が行き交い、更新されています。
個人的には、「かわいい」について調べれば調べるほど、それがもつ本来のポテンシャルの高さを知り、驚かされています。
そんな中で、ボク自身は「SHIBUYA GIRLS POP」という企画を進めながら、ごく自然な流れで、海外における「かわいい」の受け取り方の微妙な違いというか、ズレに似たような空気感を、少しずつ感じ取っていったのでした。
それを説明するために、「かわいい」について踏み込んで考えてみましょう。
たとえば英語では「かわいい」はcuteやprettyと訳されますが、それは表面上、その意味が似通っているということであって、決してイコールで結ぶことはできません。それは他の国の言語でもたいてい同様なようです(※「かわいい」論(四方田 犬彦/筑摩書房)参照)。
この事実から分かることは「かわいい」という概念が、いかに日本独自のものであるのかということです。
日本における「表面上のかわいい」とされる部分を、あえて別の言葉で表現してみると、「ちいさいもの」「まるいもの」「やわらかいもの」「ふわふわしたもの」「どこか懐かしいもの」「保護欲を喚起するもの」「庇護するべきもの」「未成熟なもの」「未完成なもの」「何かが足りていないもの」「無国籍なもの(エキゾチック)」・・・と次々に思い浮かべることが出来ます。この意味のバリエーションを包括しているのが「かわいい」であって、やはり、cuteやprettyではなし得ないことなのです。
また、みなさんもご存知のように、日本において「かわいい」という言葉は日常の中、様々な場面で使われています。現代の日本では、「かわいい」はその時の状況、発語者の感情・目的によって意味合いを変えていきます。
また一方で、ずっと意味を変えることのない「かわいい」もあれば、時代そのものにより意味が変わっていく「かわいい」もあります。
さらに他の視点から言うと、日本では(例外はたくさんあるにせよ)、大人になっても「かわいい」を求める気持ちは変わらないといった傾向があります。変わったとしてもそれは「かわいい」の意味合いにおける変容が起こるのであって(例:「大人かわいい」)、その気持ちが失われるということはない、と言うことができると思います。
なぜならやはり、「かわいい」には古来から続く日本の文化的背景に支えられているという一面があるからです。
先ほどの「大人かわいい」のように、自分も日常的に良くやるのですが、「かわいい」の前に「○○」を付け、「○○かわいい」とすることも多いですよね。勝手にその場で作り出してしまう、新しい「かわいい」。それほど、柔軟に自由に意味を変えていく可能性を持った言葉だと言えるのです。
このような例を重ね、分かることは、「かわいい」に対応する言葉が海外にはありえない、という事実です。文化的成り立ちが違う海外で「かわいい」に対応する言葉がないのは、本来当然なことなのですけれど。
そして現状です。今のところ、海外で受け入れられている「かわいい」は、それに善し悪しがあるにしても、「ある部分」でしかないのだろうな、というのがボクの見解です。そしてまた同時に海外における「かわいい」理解が一面的になってしまうのは、仕方がないことだとも感じています。
なぜなら、海外では派手でエッジーなものが受け入れられやすいという風土があります。それをして「かわいい」と思われる傾向があると思います。
時間的な問題もそうです。実際には日本の「かわいい」が知られるようになってから、たかだか20年〜30年しか時が流れていないのです。一方「かわいい」自体は何度も繰り返すように、日本の伝統や精神を踏まえた多義的な言葉であり、その概念は1000年来の起源を持つものなのですから。
その上で(ボクが言うのもなんですが)、実際どの国でどのように「かわいい」が消費されるかということは、コントロールできることではありません。そしてそれ自体はとても良いことだと思っています。根本的にはその国がもつ文化的背景に支配されて然るべきものだからです。
とはいえ、そこで「かわいいの別の側面」もしくは「本当の日本のかわいい」を伝えようという努力をしない、というコトではないと思います。そういう動きはあってもいい、そう思うのです。むしろ、それを積極的に提示してみようという動きのひとつとして、この「SHIBUYA GIRLS POP」が何かできるのではないか、と考えているのです。
ただここで誤解して欲しくないのは、決してその「誤りを正そう」とか、「こちらが王道」というような、啓蒙的な運動をしたいと思っているわけではないということです。これだけ「かわいい」が世界に伝播した現状、もちろんその先駆者の方々には本当に心の底から感謝とリスペクトを捧げたい気持ちです。
その上で、エッジーなものだけではなく、「日本の一般の女の子たちが普通に、日常的に好き、というようなかわいい」を世界に提示してもいいのではないか、という提案なのです。誤解を許容する幅こそが「かわいい」なのだとは思います。ただ、日本の文化として「かわいい」をいろんな側面から伝えるということもまた、今後はますます重要なことになってくるのではないか、と考えます。
ボクは現在の海外における「KAWAII」も個人的には大好きなのですが、その流れにそのまま取り込まれてしまってはせっかくのこの「SHIBUYA GIRLS POP」の魅力もまた半減してしまうだろう、と考えています。
ようやく伝えたい本筋に入って来た感じなのですが、この「SHIBUYA GIRLS POP」はその最初期からずっと、「日本のごく普通の女の子たち」が「かわいい」と言ってくれることを想定して活動を続けてきました。その普通の女の子たちの「空気感」をなるべく掬い取れるように、慎重にイラストレーターさんの選択をして来ました。
また、本当に小さな努力ではあるのですが、意識して表記を「KAWAII」でもなく「カワイイ」でもなく、また「可愛い」でもない、「かわいい」としてきたのです。これは、日本本来の「かわいい」感を演出するために意図的に行ってきたことです。
「SHIBUYA GIRLS POP」においてボクは、そろそろその活動の意図を明らかにして、日本の本来の「かわいい」、「日本の普通の女の子が想うかわいい」をきちんと提案し直す必要があるのではないか、と感じたわけですが、「SHIBUYA GIRLS POP」の活動の核を明言すれば、イラストレーターさんの表現を通して、あらためて「日本の大多数のごく普通の女の子または女性が、日常的にかわいいと思っているもの、普遍的にかわいいと思えるもの、という視点を提案してあげること」と言っていいと思います。
それは、決して奇抜であればいい、ということだけではない、「かわいい」なのです。
またその立ち位置を明確にするために示してみようと思いますが、知っての通り、「かわいい」は時に、カウンター・カルチャーの側面を担うこともあり「ロック」的なダイナミズムを纏う事もあります。
その例として6%DOKIDOKI好きの女の子のように、極彩色の「KAWAII」を身に纏ったり、ロリータの女の子がフリル満載のロココ調・パステルカラーの服を着たり、ゴシック系の女の子が黒尽くめの服を好んだりするように・・・自分のアイデンティティを主張するのと同義に「かわいい」の変奏を行ったりします。これには実に「ロック」的な感性の動機付けが垣間見られます。良い意味での「緊張」が支配する世界です。
そこで改めて「SHIBUYA GIRLS POP」の立ち位置を見てみると、その名の通り、とても「POP」的です。もう少しゆったりとしていて、自然な雰囲気です。それは、先ほども述べた通り、「日常の中のかわいい」を見つめる視線に注目した企画であるのですから。
これは、どれがどれだけ優れている、というような問いなのではありません。いずれにせよその全てが、「かわいい」の中から産まれて来たことに違いなく、その幅をもって「日本のかわいい」なのですから。共存して然るべきなのだと思います。
また逆に、「SHIBUYA GIRLS POP」がこのような企画になることは、極めて自然であったとも言うことができます。
それはこの企画がポストカードを実際に「大多数を占める普通の、一般的な女の子」に持って帰ってもらえないと、現実に配布している意味がない、という条件付けがあったからです。
それはまさに、ボクたちが一般的な「かわいい」とは何なのだろう?と思考を開始し、試行錯誤をする契機にもなったのです。
そしてまた、別の角度から「SHIBUYA GIRLS POP」を捉え直すこともできます。
海外においてアニメ、マンガ、ゲーム、ファッション、キャラクターの紹介が進む中、イラストレーション、アートの側面での「かわいい」の紹介が遅れているのではないか、という部分です。これは恐らく、確かなことでしょう。
むしろここは、このタイミングで「本当の日本のかわいい(REAL JAPANESE KAWAII)」イラストレーターさんたちを、ボクたちが再提示・紹介できる機会がある、そう前向きに受け止め、チャンスと捉えたいです。
さらに(これは蛇足的な内容かも知れませんが)、日本では長年に渡り、女性をターゲットにさまざまなマーケット研究が行われ、メディア主導のカテゴリー・ブーム作りが行われて来ました。レッテルを貼り、売りやすくするという手法、もしくは存在しないブームを生み出して行こうという行為です。ですが、自分はその流れには属したくない、レッテルを貼られたくない、と強く望んでいました。もちろん、それはロマンティックでナイーブな幻想でしかありません。
ですがそれでも、時の流れにも風化しない、メディアの操作やレッテル貼りにも屈しない、普遍的な「かわいい」を示せたら、どれだけ素晴らしいだろうとも考えています。それは、今の世界的な「かわいいバブル」の後にも残る事ができる「かわいい」の提案です。
消費されて、跡形も無くなってしまうのは誰にとっても恐ろしい事です。
とはいえ、イラストそのものを見れば、個々のイラストレーターさんのお仕事を見れば、そんな心配はないと気づき、とても安心できるのです。「SHIBUYA GIRLS POP」に参加していただいたイラストレーターさんたちは、本当に普遍的な「かわいい」を表現するのに長けた、素晴らしい方たちばかりなのですから。
その流れで話しますが、長年に渡って「KAWAII」を世界に発信続けている6%DOKIDOKIの増田さんが、今まさに懸念している、状況を見てにわかに「KAWAII」を持ち出すといったマナー、そういった表面的な動きとSHIBUYA GIRLS POPとは根本的に立っている位置が違う、ということはご理解いただけたかと思います。
このように「SHIBUYA GIRLS POP」の活動の本質を説明するために、長々と書いてきました。
最初に言ったように、この活動はすでに2年間続いてます。
その中で自分たちは常に、関わっていただいたみんながハッピーになれるよう心がけています。
そして当然のことですが、渋谷の街を行き来する、普通の女の子、女性に対しては特に。
そこから得られる反応を常に大切にして、時に分析して、次の活動に繋げようとしています。
今後も、核になる良い部分は変えることなく、と同時にどんどんと柔軟にその姿を変えて行きたいと思っています。
まるで、日本語における「かわいい」という言葉のように。
これからも、「SHIBUYA GIRLS POP」の応援を、よろしくお願いいたします。
SHIBUYA GIRLS POP 主宰 加藤和裕
|
|
|
|
|
|
|
|
SHIBUYA GIRLS POP 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
SHIBUYA GIRLS POPのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75489人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6451人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208289人